|
|
|
Web�]�_���u�R�[���v |
|
���n���̎� ���{���̕\���i�ڎ��j�� ���{���̃o�b�N�i���o�[ ���ǎ҂̕Ł^���ӌ��E���z �����e�K�� ���W�҂�Web�T�C�g ���v���C�o�V�[�|���V�[ |
|
���{���̊֘A�y�[�W�� |
|
���u�J���`���[�E�������[�v�̃o�b�N�i���o�[ ���]�_���ula Vue�v�̑��ڎ� |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
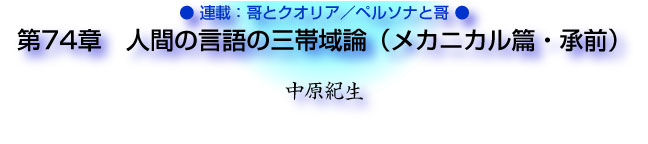
|
|
�i�{�����̉����̓����N�������Ă��܂��B�܂��A�L�[�{�[�h�F[Crt +]�̑���Ńy�[�W���g�債�Ă��ǂ݂��������܂��B��Microsoft Edge�̃u���E�U�[����Ƀ��C�A�E�g���Ă���܂��̂ŁA����ȊO�̃u���E�U�[�ł������������ꍇ�ł́C�啝�ɐ}�`�Ȃǂ������ꍇ������܂��B�j
�@
�����o�̕��z�Ǝl�F���������J�j�J���тQ
�@
�@�l�Ԃ́i���j����̃��J�j�J���ȑш�ɂ�����u���o�̕��z�v���߂���u�����v���A�V���莮�ɔ��l���܂��B
�@
�P�D���̗̕��Ɖ��̗̕�
�@
�Z����i���^�t�B�W�J���ȑш�Ƃ̊E�ʁj���u���v�̗̕��A�����i�}�e���A���ȑш�Ƃ̊E�ʁj���u���v�̗̕��ƂƂ炦��B�i�`���̔}���Ƃ��Ă̌��Ɖ��B���邢�́A�Ӗ��Ɛg�́m��1�n�B�j
�@
�Z�}�[�N�E�`�����M�[�W�[���w�q�]�ƕ����r�̈Í���������Ɖ��y�A���ق̋N���x�i���́j�ɂ��ƁA���E���̌��ꂪ���o�i���j�ł͂Ȃ����o�i���j�����ɂ��Ă��闝�R�͎��̂Ƃ���B�i���́A�`�����M�[�W�[�̌����u���o�v���u�G�o�v�m��2�n�������́u�������o�v�i�O�ؐ��v�j�A�u�̐����o�v�Ƒ��������B���邢�́A�u���o�����u���o�v�ɑ���u���o���ߐڊ��o�v�B�j
�E���o�ɗ���ƁA�w��╨�A��ÈłŖ��ɗ����Ȃ��B���o���������A���Ƃ��w��A���A�A�Èłł��A�ӎv�̑a�ʂ��ł���B
�E���o�������Ă���̂́u����͉����H�v�u�ǂ��ɂ��邩�H�v�Ƃ����^��ɓ����邱�ƁB���ʁA�u�����N���������H�v�ɓ����邱�Ƃ͋��ɂ��Ă���B
�E���̗��R�͂����P���ŁA�悤����Ɍ��̂������B���̏�̂�������̂����˂���B������A�ڂɉf���Ă����i�̒��ňړ���ω����N�����Ă��A�������E�ʼn��������������Ƃ͌���Ȃ��B
�E���o�́u�����N���������H�v�����ނ̂Ɍ����Ă���B���錻�ۂ����ۂɐ������Ƃ������M�������m���邩�炾�B
�E�R�~���j�P�[�V�����͈��̏o����������A��͂蒮�o���������̂����R���낤�B�����������͈Ⴄ�B�ӂ��A�킽�������͎����̍l���������ƒ����I�ɋL�^���Ă��������Ƃ��ɗp����B
�E���R�E�ł͏o�����̔��������ɂ���ē`���d�g�݂�����A������A�����I�ȓ����̂������o�ɗ���悤�ɂȂ����B
�@
�Z���̗̕��́u����v�̎���i�o�����̔z�u�A�{���̔F���ƋL�^�j�ł���A���̗̕��́u�\���v�m��3�n�̋�ԁi�o�����̔����E�ړ��E�ω��̔F�m�j�ɂȂ���B�����̗̕��̗Z���ɂ���Đ��ݏo�����̂��i�����Ƀ��J�j�J���ȁj�u���A�����v�̒m�o�̗̕��A���Ȃ킿�u�V����ԁv�m��4�n�ł���B
�@
�Z���̗̕��̓A�|���I�Ȗ��̐��E�i�`�ې��E�j�ɂ����鑢�`�|�p�́A���̗̕��̓f�B�I�j���\�X�I�ȓ����̐��E�ɂ����鉹�y�E���x�̕���ł���A�����E�̗Z���ɂ���Đ��ݏo�����|�p�`�����i�����Ƀ��J�j�J���ȁj�����ł���B
�@
�@�@�@�s�\�P�t���J�j�J���ȑш�̎O�t�\���iVer.5�j
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ⴡ�^�t�B�W�J���ȑш��
�@�@��������������������������������������������������������
�@�@�����i�Ӗ��j�̗̕�
�@�@ �E�u����v�̎���i�o�����̔z�u�A�{���̔F���ƋL�^�j
�@�@ �E�A�|���I�Ȗ��̐��E�i�`�ې��E�j�ɂ����鑢�`�|�p
�@�@��������������������������������������������������������
�@�@���m�o�̗̕�
�@�@ �E�u���A�����v�̒m�o�̗̕����u�V����ԁv
�@�@ �E�i�����Ƀ��J�j�J���ȁj����
�@�@��������������������������������������������������������
�@�@�����i�g�́E�����j�̗̕�
�@�@ �E�u�\���v�̋�ԁi�o�����̔����E�ړ��E�ω��̔F�m�j
�@�@ �E�f�B�I�j���\�X�I�ȓ����̐��E�ɂ����鉹�y�ƕ��x
�@�@��������������������������������������������������������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��}�e���A���ȑш��
�@
�m��1�n���邢�́A�Ӗ��Ɨ����B�����ȉ��́A�����������w������G�f�B�V���� �ʉe���{�x���́u�������E�͂��Ȃ��E����E�]��v�Ɏ��߂�ꂽ�u�g�c���D�w�k�R���x�v�̈�߁B
�m��2�`4�n�`�ؐL�V���w�f�₩��̗��j�����x�����~���̗��j�N�w�x��́u�ؒf����̑������x�����~���ƃN���[�ɂ�����j��ƍ\���v����B
�@���킭�A�x�����~���͉f���Z�p���u���ӎ��̗̖�v��������A�f���̂����Ɂu���R�ȗV����ԁm�V���s�[�����E���n�v���J�����Ƃ̏d�v�������������B�����Ă��̋�Ԃ��J���A�z�����������f�����\������Z�@�Ƃ��ă����^�[�W�����d�������B
�@�`���x�����~���̋c�_���A�{���̋c�_�Ɂi�����Ɂj�Ή�������Ǝ��̂悤�ɂȂ�B
�@
�@�@��������������������������������������������������������
�@�@�����̗̕��@�F�z���@���ӎ��̉��
�@�@��������������������������������������������������������
�@�@���m�o�̗̕��F�����^�[�W���i�ؒf�E���p�E�\���j
�@�@��������������������������������������������������������
�@�@�����̗̕��@�F�z�N�@�G�o�I�ȃV���b�N
�@�@��������������������������������������������������������
�@
�����o�̕��z�Ǝl�F�����i���O�j�����J�j�J���тQ
�@
�Q�D�l�F����
�@
�Z���J�j�J���ȑш�̎l���Ɏl�̊��o��z�u����B�k���i�\�j�Ɂu���o�v�A����i���j�Ɂu�G�o�v�A�����i�E�j�Ɂu���o�v�A�����i���j�Ɂu�����o�v�B
�@
�Z�`�����M�[�W�[�O�f���i�w�q�]�ƕ����r�̈Í��x��O�́j�ɂ��ƁA�F�ʂƊ���͋������т��Ă���B
�u�킽���́A�ߋ��̌�����O���w�q�g�̖ځA���ق̐i���x�̒��ŁA�킽�������쒷�ނ̐F�o�����Ƃ�킯�A�V����̗쒷�ނł���q�g�̐ԂƗɑ���q��������������قǔ��B�������R�́A�畆�̉��ŋN���錌�t�̐����w�I�ȕω����@�m���邽�߂ł��낤�A�Ƙ_���Ă����B���������F�̐M�������߂�A���l�̐S����Ԃ̂��肩����ς��悤���킩�邩�炾�B�܂�F�ʂ͐l�ԓI�ŁA�����Ɛ[���Ȃ��肪���邩�炱���A�킽�������̊�������B�v
�@
�Z���J�j�J���ȑш�̎l���Ɏl�̐F�ʂ�z�u����i�{�e��68�͑�5�߂̒�4�Q�Ɓj�B�k���i���o�j�Ɂu�����v�A����i�G�o�j�Ɂu����F�v�A�����i���o�j�Ɂu�ԐF�v�A�����i�����o�j�Ɂu�ΐF�v�A�����Ē��ԂɁu�D�F�v�������́u���n�F�v�m��1�E2�n�B
�@
�@�@�@�s�}�P�t���J�j�J���ȑш�ɂ����銴�o�̕��z�Ǝl�F����
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ᎋ�o��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�k�����l
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@��
�@ �ዤ���o�� �@�@�@ �@���@�@�@�@�@ �ᒮ�o��
�@�k�Ό��l���������k�D�F�l���������k�ԐF�l
�@�@�@�@�@�@�@�@ �k���n�F�l
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@��
�@�@�@�@�@�@�@�@ �k����F�l
�@�@�@�@�@�@�@�@�@��G�o��
�@
�m��1�n�p�E���E�N���[���w���`�v�l�x�i�y����ꑼ��A�����܊w�|���Ɂj����A���Ɣ��A�ԂƗ��߂���N���[�̌��t����������B
�@���ƈłƂ��܂��������ȁu�J�I�X�i�������j�v�̊�{�I��Ԃ́u�D�F�v�ł���B���́u���E�̐_�b�I�Ȍ��m�E�A�n��ԁv���珙�X�ɁA���邢�͓ˑR�Ɂu�F���i�����j�v���`�������B�u�����獕�ցv�Ɓu�Ԃ���ցv�Ƃ����^���E������ʂ��āB�u�J�I�X�̂Ȃ��̊D�F�v����u�F���̂Ȃ��̊D�F�v�ցB�i�㊪68-69�Łj
�@���ʉ�u�[�ׁA��ƒ��̕�����ځv�i1922�N�j���߂���B�u�^���Ɣ��Ή^���i�㏸�Ɖ��~�j���N��A�Η�������݂̂͌��ɂ��߂������B�Â��疾�ɂ�����i�K�ł́A�ŏI�I�ɂ͗��҂̗Z���ށB���ꂪ�A�u���Ɣ��Ƃ̒��Ԃɂ���A��F��тт������ł���A���̂Ƃ����L���Î~�͋K�����痣�ꂪ���ł���B�v�v�i�㊪72�Łj�����u�����v�i����j���Ȃ킿�g�����B
�@
�@�������炢�܈�A�N���[�̌��t����������B
�u�ϔO�I��i�m���A���ÁA�F�ʁn�́A�������犮�S�ɗ����킯�ɂ͂����Ȃ��B�����I��i�m���A�����A�K���X�Ȃǁn�ɂ��˂A���������A�ǂ�����āu�����v�̂��B�킽�����Ԃǂ����Ƃ������t���C���N�ŏ����Ƃ��悤�B����ƁA���̂Ƃ��C���N�̉ʂ������͎���Ƃ͂����Ȃ��܂ł��A�Ԃǂ����Ȃ�T�O���P�v�I�ɒ蒅��������̂̓C���N�ł���B���������āA�C���N�͂Ԃǂ����ɉi������^����B�����ƊG�A���Ȃ킿�������Ƃƕ`�����Ƃ́A���{�I�ɂ͂ЂƂȂ̂ł���B�v�i�㊪81�Łj
�@
�@���c���i���̕��ɔʼn���u�u���ԗ̈�v�̎v���Ƒn��v����B
�u�N���[�ɂƂ��āA�`�ԂƂ͂��������^���ɂ��čs�ׂɂ��ăG�l���M�[�Ȃ̂��B�v�i�㊪341�Łj
�u����m���l�T���X�̓����}�@�i�p�[�X�y�N�e�B���j���A�Œ肵�����_�i�ώ@�҂Ƃ��Ă̎�́���Ƃ̎��_�j������肵�����E����`���������̂ł��������Ɓn�ɂ������āA�N���[���v���`���Ă���̂́A������Ƃ̎��������������͐g�̄����ƂƂ��ɕω����Ă����_�C�i�~�b�N�Ȑ��E�̃C���[�W�ł���B�v�i����343�Łj�m��3�n
�u�m�N���[�ɂƂ��ān�D�F�́A�n���ƏI���A�͂��܂�ƏI���A���Ǝ��������ǂ�F�Ȃ̂��B���̐F�́u�����������ʓ_�Ƃ��āA�܂葽�����̊ԂɈʒu����_�Ƃ��āv�A�u�킽���v�Ɠ������S�̈ʒu���߂Ă���B�u�킽���v�Ɓu�D�F�v�́A�����ω��̋N�_�ł���Ƃ����Ӗ��ň�v���Ă���B�v�i����344�Łj
�@
�m��2�n�����������w���n�F�̕��@������������̏C���w�x����A���n�F�i�̕��@�j���߂��鍡�����̃����J���Ń|�G�e�B�b�N�Ń}�e���A���ȕ��͂�������������������B
�@
�u���ׂĂ̐F�ʂ��������킹�Ăł��������A����𐅂Ŕ��������ق����Ă������W�����n�̔��ׂȔZ�W�v�i11�Łj�B�u���n�́A�������E���ʂ鉩�F���A���F���A�D�F���A�����Ĕ��g�F�ł���A���ꎩ�g�̂����ɓ���邱�Ƃ��ł���v�i12�Łj�B
�@
�u����炷�ׂẴ��m�Ɠ���ƌ���̘A�ւ̂Ȃ��ɁA�A���ɑ�\����鎩�R�E�̗����͂ɂ�������l�Ԉӎ��̍����I�ȐZ�������݂͂�B���Ƃ̉���}��ɂ��āA��̓I�ȃ��m�̗͂Ɠ��������܂��܂ȐS�ӂ�ϔO���Ăяo���A����炪���݂Ɍ��э����Ȃ���Ӗ��̗�����̑̌n�������Ă䂭�B���n�F�̕��@�������ƂƂ́A���̂悤�Ȗ����̋�̂̉��Ǝ����̘A�ڂɂ���ĖL���ȍʂ��l������A�������t�Ƃ͈قȂ镽�s���E������Ȃ��Ă���̂��B�v�i110�Łj
�@
�u���Ƃ��A�Ӗ����E�ɒ��n���邱�ƂŘ_���I�ȑ̌n�����肠�����O�ŁA�I�m�}�g�y�̋[���Ɉ˂����F�����Ƃ��Ẵm�C�Y���A���n�F�̕��@�������ǂ�u���ƂΈȑO�v�̉�����ǂ����Ŏx���Ă���B���C�E���C�m�u���W���̃C���f�B�I�N���̊y��n��炵�ėx��_���T�[�̈Èł̐g�̂ɋ����鎄�́A���̂��ƂΈȑO�̉��Ɨ����Ɋ҂낤�Ƃ��鎩�����̓��ɂ������ɑ��݂��邱�Ƃ����m����B�v�i119�Łj
�@
�u���̔��̎ցA���n�F�̖��ʖ͗l�Ɍ��闆���^���̌����́B�ւł���A�W���K�[�ł�����A�����ł�����A����炪�����鎝������X�艹�A�S�[���A�K���K�����̂Ȃ��ɁA�l�Ԃ����̐����̒[���ŐG�ꂽ�͂��̎n���̈ł�z�N���Â��邱�ƁB���ꂪ��������ȑO�́A�ӎ���従��̋�������邱�ƁB����́A������̍^���̂Ȃ��Ńm�C�Y�Ƃ��Ă̚X����̂āA�Èł̊y��̂�������K�ɂ������Ď�������Ă��܂����l�Ԃɂ�������A�V�������ꕶ�@�ւ̗U���ł�����B�v�i122�Łj
�@
�u�����������R���ۂ̂Ȃ��ɁA���o�I�ȉQ�◆���̌`��ƁA�X��Ƃ��������I�Ȏ��̂Ƃ��A�����Ɍ���Ă���B�������̐g�̂́A���̗������C�̗���Ƃ��Ă̕��̂Ȃ��ɁA�����ƚX��Ƃ��A�����Ɋ��m���Ă���ɂ������Ȃ��B���̐����ڂ����C�E���C��g�D�[���D�[�E�[�̂悤�ȚX��ߋ�y�킪���ɂ͂�ރJ���}���̉Q�B���̕s���̋C���Ɣg���̗����`�����̔ޕ��Ɋ����Ȃ���A���͂ӂ����іk���Ɍ������Đg�̂𗧂Ă�B�v�i128�Łj
�@
�u�c�^�̑n���I�Ȕ����́A�[���ւ̒����ݏo���A�[���Ƃ�����Ԃ̂Ȃ��ɒu���ꂽ�����̋�Ǔ_�������邱�Ƃ��ł���B���̋�Ǔ_�������L���ȋ��B�����炱���A�������Ăяo���́A�܂��ɑ̓��̋����炷�������ɂ���Đ�������˂Ȃ�Ȃ��̂ł���B�A���A�m�W�����E�P�[�W�̐��y��i�n�͂��̂��߂̎����̉̂ł���B�����Ȃ錾����A���̎n���̕��������錴����A���ߌ���ȑO�́u���o�v�̓f����������Ă���B���n�F�ɂ�炮�ЂƂ̉��C�̕��@�Ƃ��āB�v�i141�Łj
�@
�m��3�n�N���[�́u������Ƃ̎����v�́A�p�C���b�g���Ȃ킿�u���Ԑl�ԁv�̎��o�ɂȂ���B
�@�O�Y��m���w�X�^�W�I�W�u���̑z���̈́����n�����Ƃ͉����x��l�́u�n�����Ƃ�����l�������M�u�\���Ƌ{��x�v����A�u���Ԋw�I�m�o�_�A������A�t�H�[�_���X�̐S���w�v���N�����W�F�[���Y�E�i�E�M�u�\���Ɋւ���L�q�������B
�@���Ԑl�Ԃ̎��o�Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂��B����́u���l�T���X�̓����}�@�v���Ȃ킿�����ߖ@�Ɋ�Â����̂ł͂��肦�Ȃ��B
�@�������肵���b��ɂȂ邪�A������́u�����̒n���������u�V��̏郉�s���^�v�v�Ɏ��̂悤�ȋL�q������B�u�n����������������z���邱�ƁA���ꂱ�����o�ɐ���ł����\�͂ł���A���̔\�͂�Ώۉ�����Ɍ����邩�����ɂ����̂��l�Ԃ̌���Ȃ̂ł͂Ȃ����v�i196�Łj�B
�@
���ԑt����l�̎��ԂƑ�l�̐�
�@
�@�����œ�{�A�⏕���������܂��B
�i���邢�͋c�_���L���[�߂邽�߂̍H��̏N�W�B�����ق�Ƃ��͕����ƌ��������Ƃ��낾���A����܂ʼn��{������߂��点�Ă͕��u���Ă��Ă���̂ŋC���������B���̉���͎��͈ȍ~�Ɋۓ������邱�ƂɂȂ�B�єV���ۊw�a�w��u��������`�l�Ԃ̌���сv�́A��ꑊ�u�����o���`�R�g�o�сv�Ƃ��ǂ��A���͂܂邲�Ƒ�O���u����`��܂Ƃ��ƂΕсv�̋c�_���߂̒��������ł���B�ƁA����͌�ǂ��̎��ȕى��B�j
�@
�@�⏕�����̈�A��l�̎��ԁB
�@�쑺�������́A�w�i���e�B���E���ԁE�R�~���j�P�[�V�����x�Ɏ��߂�ꂽ�u���^�u���Ԙ_�� �u���������ԁv�Ƃ͂Ȃɂ��v�̂Ȃ��ŁA�}�N�^�K�[�g�̎��Ԙ_�i�`�n��A�a�n��A�b�n��j���g��������l�̎��ԁA���Ȃ킿�u�d�n��̎��ԁv����Ă��܂��B�ȉ��A�쑺���̔������E���܂��B
�@
���`�n��̎��������S���I�Ȏ��ԁA���݉����ꂽ���́i��F���`�j
�E�����Ə����ƕ������������ԁi�ߋ��E���݁E�����ɂ�鎞�Ԕc���j
�E�u���܁A�����v��O��Ƃ����ӎ��̐��E�̎��ԁA��邱�Ƃɂ���ĈӖ�������ϓI����
�@
���a�n��̎������������I�Ȏ��ԁA�O�݉����ꂽ���́i��F����j
�E�������Ȃ������ƕ������������ԁi�u���O�v�u����v�ɂ�鎞�Ԕc���j
�E���v�̎����A�q�ϓI�Ȏ��ԁA�����I�Ȏ���
�@
���b�n��̎��������ԁA��~�������́i��F�Î~��j
�E�����ƕ��������Ȃ������������ԁi��邲�Ƃɉ����������čs���ꍇ�͂c�n��i��F�J�����_�[�j�j
�E���ԂɂȂ�ȑO�̎��ԁA�O�ɐi�܂��J��Ԃ��Ă��鎞��
�@
���d�n��̎��������Θb�I�Ȏ��ԁA�������������́i��F�_���X�j
�E�����Ə����ƕ������������Ȃ����ԁi�����Ă��邱�Ƃ��������Y���ƕω������邾���j
�E�ő�̓����͑��҂���Ƃ̓��������������i�V���N���i�C�[�[�V�����A�G���g���C�����g�j
�E�����邱�ƂŐ��܂��u���������ԁv�A�����̃��Y�������ގ��ԁi�ۓ��A�ċz�A�����A�̓����v�j
�E�J�[�j�o���I�Ȏ��ԁA�Ղ�̎��ԁm��1�n�A�V�тɖ����ɂȂ��Ă��鎞��
�@
�@�d�n��̎��Ԃ̈��A�gWe had a great time!�h�ƕ\�������R���T�[�g�̌o���B����́A�쑺�������Ƌ����~��Y�E���ΐ^�����Ƃ̋����_���u�d�n��̎��ԂƂ͂Ȃɂ������u�����v�Ɓu����v����l���鎞�Ԍn�v�i�w���Ԋw�����x��8���i2015�N3���j�ŋ�����ꂽ���́B
�@�쑺���̎��Ԙ_�̃G�b�Z���X���A���̋����_�����璊�o����ƁA���̎O�_�ɐ����ł��邩�Ǝv���܂��B
�@
�@�}�N�^�K�[�g�̂悤�Ɏ��Ԃ̎��݂��Ԃ��������N�w�I�_�l�ł͂Ȃ��B
�@���ԂƂ������̂������Ă�������v���v��̂ł͂Ȃ��A���v�Ƃ����u�^���́v��������u����v���A�܂�u���v�ipunctuation�j���Ǔ_�����Ԃ������Ă����Ƃ��������ɗ����Ă���B�i�����Ƃ������̂������Ă�������t���\�ۂ���̂ł͂Ȃ��A����E���ʂ������ݍs�ׂ�R�~���j�P�[�V����������������Ă����Ƃ���F���_�A������u����I�]��i�i���e�B���E�^�[���j�v�Ɠ����_�@�B�j
�@���A���Y�������ށA�L���Ƃ������s�ׂ�ʂ��Đ��E�𒁏����ĂĂ������ԁi�u����Ƃ��Ď��ԁv�j���_������B
�A�d�n��̎��Ԃ́u�����v�isynchronicity�j���u�������݁v�ientrainment�j����n������B
�@���ݍ�p��������U������B���Y���ƃ��Y�����o������Ƃ��ɋN���鎖�ۂ������ł���B
�@�����͕������E�i�U�q�̋��U�j�A�������E�i�S���E�������v�E�Q��j�A�l�Ԑ��E�i�_���X�E�����E��b�j�ɋ��ʂ���B
�@�����w�̖@���͎��ԑΏ̂ʼnߋ��Ɩ����̋�ʂ��Ȃ�����A���̎��ԁi���Θ_�I����j�͂`�n��ł��a�n��ł��Ȃ��B�ώ@�҂Ɩ��W�ȋq�ϓI�Ȏ���A���Ȃ킿�b�n������݂��Ȃ��B
�@���̂悤�ȁu�ώ@�҂������Ԃł̏o�����v�ł��邩����A�������E�Ɍ��炸�������E�ł��l�Ԑ��E�ł��A�����őn������̂͑��ݍ�p��ʂ��ċǏ��I�ɓ������鎞�ԁA���Ȃ킿�u�d�n��̎��ԁv�ł���B
�B�w���@�ᑠ�x�Ɂu���͂��L���i�����j�́A�����łɂ���L�Ȃ�A�L�݂͂Ȏ��Ȃ�v�Ƃ���B�u���͎p�A�l���������Ă���B�����Ă��邳�܂��A�������݂��邱�Ƃ��A���̎p�ł���v�B
�@���Ȃ킿�A�`�n��d�n��܂ł́u���ԁv�́u���v�́u�p�A�l���v�ł���B�u���v�͂�������i��́u���^���ԁi�L���j�v�ł���B
�@�u���ԁv�����Y���ɚg����Ȃ�A���ꂼ��̌n�Ԃ��قȂ�^�C�~���O�Ŕ��q���Ƃ邱�Ƃŏd�w�I�ȁu�|�����Y���i�������Y���j�v�̗̈悪�`�������B
�@�u���ԁv�𐺂ɚg����Ȃ�A���ꂼ��̌n�Ԃ́u���v�����݂ɓ�������u�|���t�H�j�[�i�������j�v�̐��E���o������B
�@
�@������}�݂܂��B
�@�����[���̂͘_�_�B�ł����A�����_����O�f���ł́A�K�������S�䂭�܂Ř_�����Ă��܂���B���̏���ȉ��߂ɂ��ƁA�u���i�L���j�v�̓A�N�`���A���Ȏ����ɑ����Ă���A�u����̎��ԁv���\������l�̎��Ԍn�A�����郊�A���Ȏ����Ƃ́A���ꂱ�����݂̎������قȂ�܂��B�i�����Ɍ����ƁA�`�n��ɑ�����q���r�͖{���A�N�`���A���Ȏ����ɑ�����B�j�����āA�d�n��̎��Ԃ́u����̎��ԁv�̍����ɂ����āA���́u���^�v���Ȃ��Ă���B�d�n��̎��Ԃ̏�ɁA����u�{���v�̂悤�Ȃ������ŁA�قȂ鑼�̌n��̎��Ԃ��u�i���́j�p�v�Ɓu�i���́j���Y���v�Ɓu�i���́j���v�̎O�̗̈�ɂ킽���đ��w�I�ɑ͐ς��Ă���A�Ƃ����̂������������Ă���C���[�W�ł��m��2�n�B
�@�t������ƁA�u�������H�C�X�ivoice�j���ԁv�̂Ȃ��肩��i�H�j�A�d�n��̎��Ԃ́A�i���̂�����łƂ肠���郔�@�����[�́u��l�̐��v�Ƃ��ǂ��j�A�u�����ԁv�imiddle voice�j�Ɩ��ڂȊW��茋�т܂��B���̓_�́A���́u��܂Ƃ��Ƃ̗c�̐��n���v�ɐ[����������Ă���̂ł͂Ȃ����ƁA���͒��ς��Ă��܂��B
�@
�@�@�@�s�\�Q�t���J�j�J���ȑш�̎O�t�\���iVer.6�j
�@
�@�@���b�n��i�ԁj
�@�@��������������������������������������������������������
�@�@���`�n��
�@�@�@���������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����C���i�C�j
�@�@��������������������������������������������������������
�@�@���a�n��
�@�@�@����������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����������
�@�@��������������������������������������������������������
�@�@���d�n��
�@�@�@���p�@�@�@�@�@�@�@�@�����Y���i���j�@�@����
�@�@��������������������������������������������������������
�@�@�s�p�����v�Z�X�g�t�@�@�s�|�����Y���t�@�@�s�|���t�H�j�[�t
�@
�m��1�n�u�C���g���E�t�F�X�g�D���i�Ղ̂��Ȃ��j�v�i�ؑ��q�w���ԂƎ��ȁx�j�I���ԂƌĂ�ł�����������Ȃ��B
�@�������Ƃ���ƁA�`�`�b�n��̎��ԂƁu�A���e�E�t�F�X�g�D���i�Ղ�̑O�j�v�I���Ԃ�u�|�X�g�E�t�F�X�g�D���i�Ղ̌�j�v�I���ԂƂ̊W�A����ɂ́u�R���g���E�t�F�X�g�D���i�Ղ̂��Ȃ��j�v�i��ԏr��w�g�̂̎��Ԅ����q���r���邽�߂̐��_�a���w�x�j�I���Ԃ�u�C���^�[�E�t�F�X�g�D���i�ՂƍՂ̊ԁj�v�i�֓��w�����L�[��������{�x�j�I���ԂƂ̊W���C�ɂȂ�B�i���̘_�_�́A���́u�`���̂́i�����j���_�v�ɂ�����܂̐��_�Ƃ��W���Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���B�j
�@
�m��2�n�O�Y��m���̘_�l�u�J�j���O�n���܂ł̐����N�������z�̐g�̂P�v�i�w�l����g�́x�����j����B
�@
�E���z�ƕ��x�͂Ƃ��ɐl�ނ̗��j�Ɠ����قǂɌÂ��\���̗l���ł���B
�E�_�a���l�Ƃ��Ӗ��̔Z����ԁi�F����X�����ۂւ̈،h�̔O�̑̌n�̏ے��j�ł���A�������܂����x���A���⊠�����̎d�����A���̗������U�镑���̗D��Ȕ�����v�������B
�E���t�͐g�U��ƂƂ��ɂ������B���l�͕��x��ł���A���x���t�������B
�E�����̓o��ȑO�A���t�Ɛg�U��ƌ��z���͂قƂ�Ǔ������̂ƌ��Ȃ���Ă����B��������A�X�����ۂɌĉ�����Ӗ��Ƃ��ē����ł��������炾�B
�E�����o���A����̔������ώ���ԂƂ������z����܂��A���̌��z�ɂƂ��Ȃ��ĕ��x���特�y�ƊG�悪�������A���Ǝ{�݁A�R���T�[�g�E�z�[���A���p�ق����݂��ꂽ�B
�i�����Ɂu���x�ƌ��z�̂��̊W�v�Ƃ���ӏ��́A�u���x�ƌ��z�̂��́e�����ԁf�I�ȊW�v�Ə��������Ă悢�Ǝv���B�j
�@
�@�����O�Y���̋c�_���A�{���́s�\�Q�t�̏�ɋ����Ɂi�g�{�����́u�\���_�v�i���E����E���j��g�ݓ���āj���Ƃ����ނƎ��̂悤�ɂȂ�B
�@
�@�@���b�n��i�ԁj
�@�@��������������������������������������������������������
�@�@���`�n��
�@�@�@���������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����C���i�C�j
�@�@�@�y���z(����)�z�@�@�@�y�G��z�@�@�@�@�@�y����z
�@�@��������������������������������������������������������
�@�@���a�n��
�@�@�@����������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �y���z
�@�@��������������������������������������������������������
�@�@���d�n��
�@�@�@�y���z(�_�a)�z�@�y���y�z�y���x�z�@�@�@�y���z
�@�@�@���p�@�@�@�@�@�@�@�����Y���i���j�@�@�@����
�@�@��������������������������������������������������������
�@�@�s�p�����v�Z�X�g�t�@�@�s�|�����Y���t�@�@�s�|���t�H�j�[�t
�@
�@�y���y�z�Ɓy�G��z�́A�y���z�z�̏ꍇ�Ɠ��l�A���ꂼ�ꉺ�w�Ə�w�̑o���ɑ�����Ɖ����ׂ���������Ȃ��B���Ƃ��}�e���A���ȉ��y�i���ہj�ƊG��i���A�lj�j�A���^�t�B�W�J���ȉ��y�i���F�[�x�����j�ƊG��i�N���[�j�Ƃ������������ŁB
�@�y���z�́A�����炭�O�̑w�̂��ׂĂɂ�����镡�w����s��ł���B���Ƃ��Ή��w�ɍ�������p�I���J�A��w�̔ߌ��i�f�E�X�E�G�N�X�E�}�L�i���~�Ղ���H�j�A���ԑw�ɂ����鉼�ʌ���l�`���i�\��̕�����܂߂āj�Ƃ������������ŁB
�@�y�f��z�ɂ��ẮA�O�Y�����O�f�������̃G�b�Z�C�u�����ꂽ�焟���f��̐g�̂P�v�̖����Ɂu���ɔŕt�L�v�Ƃ��ċL�������̈ꕶ���Q�l�ɂȂ�B�i�u�����������v�̐����܂߂āA���͎O�Y���̋c�_�ɐ����͂������Ă���B�j
�@���Ȃ݂Ɂw�X�^�W�I�W�u���̑z���́x�攪�́u�n�����̔�r���w�����t�H�[�h�E���V�E�{��x�v�ŎO�Y���́A�����Y���V�˓I�Ȓ��ϗ͂������āu�f��Ƃ������̂����͒n�����ɐ[����������Ă���A����A�n���������f��𐬗������錈��I�ȗv���Ȃ̂��v�ƌ������Ă����Ǝw�E���i329�Łj�A���̏�����Ŏ��̂悤�ɏ����Ă���B
���ԑt����l�̎��ԂƑ�l�̐��i���O�j
�@
�@�⏕�����̓�A��l�̐��B
�@�˖{�������ɂ��ƁA�u���@�����[�͐��̂����ɁA�������̑w�����邱�Ƃ��w�E���Ă���v�i�u�q��l�̐��r�������@�����[�̐��Ɋւ���l�@�v�A�˖{�������ҁw���ƕ��w�����g������g�̗̂U�f�x�����j�B
�@
�P�D�u���v�������Ŋ����鐺
�Q�D���l�������Ƃ�u���v�̐�
�R�D�^���Ȃǂ̉����e�N�m���W�[�ɂ���Ē蒅����A���͂̑ΏۂƂȂ�A���͂�u���v�̐��Ƃ͎v���Ȃ���
�S�D�ȏ�̂�����Ƃ��قȂ�A�����������Ă��関�m�i���\�j�̐��Ǝ����̘b�������̐��̋��E�ɂ��鐺
�@
�@�ȉ��A�˖{���̌��t�������������������܂��B
�@
�u���ɂ́A�ʂ̑��݂ɐ[���������A���̌ʑ��݂̏��łƂƂ��ɏ����Ă䂭�����ƁA�ʂ̑��݂��A���Ԃ��Č��Â��镔�����������Ă���̂ł͂Ȃ����낤���B�v�i145�Łj
�@
�u����ɂ͊O�������Ă��鐺������A��������ɂ͂��̐��ɑΉ������Ԃ������̂����ɑn�肾�����Ƃ��長���肪����Ƃ������̓�d���́A���@�����[������Ƃ������̂ɕ����Ă���T�O���̂��̂ł���B�v�i147�Łj
�u�c�Ƃ�킯�����[���̂͂��́m���ȂƑ��҂Ƃ̋��E�ō\��������l�̐��́n�\�������Ԃ��Đ�����݂�����m���̑h���n�Ƃ������ۂɐ[���ւ���Ă���Ƃ��鎋�_�ł���B�����������ė��鐺�́A������Ƙb����ɕ����q��d�̈�ҁr�ł���悤�Ȏ����n�肾���B���̎���̌�鐺�́A�����̐l�����Θb�����킷����Ŏ���̎v�l��W�J����B�v�i150�Łj
�@
�u�����ɑ��Ęb�����t���A���l�����̐l�̐S�̂Ȃ��ŌJ��Ԃ��邱�Ƃ��A�����̏W�ς��琺����݂����邱�Ƃ̊�ՂƂȂ�Ɓm���@�����[�́n�����̂ł���B�v�i153�Łj
�u�q��l�̐��r���������ė���ꏊ�́A���ӂ��Â炷���Ƃ��̂��̂����ӂ̑Ώۂ݂����ꏊ�A���Ԃ�����Ă���Ƃ������o�����݂�ɂ����悤�ȏꏊ�ł���B�v�i154�Łj
�u�L���\���́A�f���_�m�w���ƌ��ہx�n�ɂ��L�����e�ւ̗����ɂ���ē`�d����̂ł͂Ȃ��B����l�������ɘb�����t���A���l�������ɘb�����Ƃ��ł��鄟�����̍\������������邱�Ƃɂ���ē`�d����̂��B�q�������b���̂��r�Ƃ����\�����̂��̂��A�ʂ̐l�Ԃɂ��̂܂ܔg�y������Ƃ����̂ł���B���@�����[�̍l�@�́A���̔����𐺂̑h���ƌ��т��Ă���_�ɓ���������B�v�i155�Łj
�@
�u�����������ė������Ɏ��܂��A�������Ƃ���p������A�c���҂̌��t������Ƃ���ЂƂ̐S�I�\������������A�ƃ��@�����[�͎咣����B�v�i156�Łj
�u���݂Ƃ��Ďp����������҂́A�����̂��̂ƂȂ��Ă������ɑΘb�����킷���݂ƂȂ��Ă���B�c�ǎ҂��܂������̂��̂ƂȂ�A�q��l�̐��r�ƂȂ��āA�����̂Ȃ��ɂ��鑼�҂Ƃ̉�b���n�߂�c�B�v�i156�Łj
�u���I���ꂪ�A�q����ҁr�̂Ȃ��Ɂq���ҁr����肾�����Ƃ��̂��̂ɂ́A�a�I�Ȃ��̂͂Ȃ��B���炪���҂ƂȂ�A���҂̘b�����t�������̂��̂ł��邩�̂悤�Ɉ����邱�Ƃɂ���Ă����A�l�͌��t��b����悤�ɂ͂Ȃ�Ȃ����炾�B���́A�����肪�����̂Ȃ��ɋ��������A�����Ƃ͂܂����������̑��҂̐��Ƃ݂Ȃ��悤�ɂȂ�Ƃ��ł���B�v�i157�Łj
�u�q��l�̐��r�́A�����������苕�\�������肷�邳�܂��܂Ȑl���̐�����������ꏊ�Ȃ̂��B�v�i159�Łj
�@�Ō�̈��p���Ɂu��{�̎��ւ̕ϐg�v�Ƃ���̂́A���@�����[�̑Θb�сu�����߂���Θb�v�ŁA���N���e�B�E�X�������ւ̕ϐg���w���Ă��܂������u��{�̐A���Ƃ͂ЂƂ̉́A���Y�����m���Ȍ`�Ԃ��J��Ђ낰�A��Ԃ̂Ȃ��Ŏ��Ԃ̐_����J������ЂƂ̉̂Ȃ̂��v�B
�@�˖{���́A�u���@�����[�����̍Đ����̂��̂��ے�������Ƃ��ĕϐg�̃e�[�}���J��Ԃ���肠���Ă��邱�Ɓv�ɒ��ڂ��A���́u������Ȃ���v�̈�Ƃ��āA�������Θb�сu�G�E�p���m�X�v�ŁA���z�ƃG�E�p���m�X�������̌��Ă��w�����X�̐_�a�����Č�����u���������ϐg�v�ƂƂ��ɋ����Ă�����̂ł������u���̗D���Ȑ_�a�́A�c�ڂ����K���ȗ��������R�����g�X�̖��̐��w�I�`�ۂȂ̂��B���̐_�a�͂��̖��̓Ɠ��̐g�̂̋ϐ����Č����Ă���B���̐_�a�͂ڂ��ɂƂ��Đ����Ă���̂��I�v�B
�@
�@�����u�������H�C�X�ivoice�j���ԁv�̂Ȃ������āA�u��l�̎��ԁv�Ɓu��l�̑ԁv�i�����Ԃ������́u���ԁv�i��62���Q�Ɓj�j��A�����A���̐����ɏ���āu��l�̐l�́v�ւƐڑ�����B����Ȃ��ڂ낰�ȁu�\�z�v�������Ĕ����������n�߂Ă݂����̂́A�ǂ����m���钅�n�_�����o���Ȃ��܂������Ă��܂����悤�ł��B�i�폜���邱�ƂȂ��k�J�̍��Ղ��c���Ă����āA��̋c�_�ɂȂ��邩�ǂ���������Ă݂�B�j
�@���@�����[�ɂ͂܂��u��l�̐g�́v�Ƃ����T�O�������āi�u�g�̂Ɋւ���f�p�ȍl�@�v�j�A���ꂪ�u��l�̐��v��A���̘_�l�Q�ł��Ď�肠�����u�����́v�̊T�O�i���@�����[�E�I���W�i���̂��̂ƁA�s��_�ɂ�邻�̊g���Łu���ݓI�i�����I�j�����{���ݓI�����{�\�I�����{�s�\�ȓ����i���j�v�i��45���Q�Ɓj�j�Ƃ��Ȃ����Ă��܂��m���n�B������@�艺���Ă݂��������[���b��ł͂���̂ł����A��ۂ悭�����ł������ɂ���܂���B
�@
�m���n���c�������w�쐶�̐��������l�͂Ȃ��̂��A�x��̂��x��X�́u�A���g�[�Ɩ����I�j�Չ����v����B
�@�{�_�l�̂��ꂩ��̋c�_�ɂƂ��Č��������Ƃ̂ł��Ȃ��T�O�Q���i������Ɂj�U��߂��Ă���Ǝv���̂ŁA���������������������B
�@���Ȃ݂ɁA��Ⴂ�̒���������ƁA�O�͂́s�\�T�t�ŗp�����u�O�m�[�V�X�I�g�́v�Ƃ�����́A���c���̎��̕��͂�����������́B�u�A���g�[�̓J�o���̋Z�@�ɂ�萸�_�̎����Ɏ���A�����̐g�̂ł���O�m�[�V�X�I�g�̂Ƃ��̂����튯�����g�̂������A���݂ȐS�̉^���I��Ƃ��Ă̔o�D��n�����悤�Ƃ����̂��B�v�i241�Łj
�@
���]�т�U�������J�j�J���сi����E���j
�@
�@���҂̋c�_�̈��p�i�H��̏N�W�j�ɏI�n���āA�̐S�̃��J�j�J���ȑш�̓������߂���l�@�����낻���ɂȂ����B���̂�����Ől�Ԃ́i���j����̎O�ш�_����āA���f���Ă����єV���ۊw�a�w��̋c�_�ɖ߂�Ȃ��Ƃ����Ȃ��B���A���̑O�ɁA���̂Ƃ��낸���ƍA���Ɏh�����������̂悤�ɋC�ɂȂ��Ă������_�I�s�����A�Ƃ������u�]�сv���U���Ă��������B
�@
�@���A�l�Ԃ́i���j����ɂ����鐺�ƕ����A���o�Ǝ��o�̈ʒu�W���߂����āB
�@�O�͂́s�\�R�t�ŁA���́u��l�̂̕�����ԁv�����J�j�J���ȑш�̏���i�\�j�ɁA�u���ق̐��v�������i���j�Ɉʒu�Â����B�܂��{�͂́s�\�P�t�ł́A�u���v���Ȃ킿�����⎋�o�ɂ������̕�������ɁA�u���v���Ȃ킿���⒮�o�ɂ������̕��������ɐݒ肵�Ă���B�Ƃ��낪���͂́s�}�P�t�ł́A���o�̈ʒu�Â��͂��̂܂܂����A���o���E���ɂ����Ă����B��71�͂́s�}�R�t�ɂ������ẮA���J�j�J���ȑш�̉E���Ɂu���v���A�����Ɂu���v�����Ă����Ă���B
�@�����́u�����v�������́u�����v�ɂ��Đ��ڂ��Ă����ƁA�܂��A���o�Ǝ��o�̈ʒu�W�͕K���������ƕ����̂���ɘA������킯�ł͂Ȃ��̂Ŗ��͂Ȃ��B�i���ƌ��͔��������A���Ȃ��Ƃ��u���v�͒��o�����łȂ��G�o�i�U���j�ɂ��W����B�j���ɁA���ƕ����̈ʒu�W�ɂ��Ă����A��������͈�т��Ă���B�����E���ŁA�����͍����B�u�i��l�̂́j������ԁv��������ɁA�u�i���ق́j���v���E�����ɂ��炷���ƂŖ��͉�������B
�@�ȏ�ɏq�ׂ����Ƃ�}������ƁA���̂悤�ɂȂ�B�i���}�́A��71���́s�}�R�t���l�Ԃ́i���j����̎O�ш�Ɋւ��Ď��������������J�j�J���ȑш�̎O�t�\���̂����Ƀt���N�^���Ɂu�k��v���ĕ\���������́B�u���������v�́A�C�X���[����J�b�o�[���[�̕����_���`�̐��E���ꌾ�Ō����\�킻���Ƃ�����B�܂��u�q���r�v�Ɓu�߁v�́A��69�͂̑�P�߂Łu�V��́q���r�^�n�����E������߁v�ƑΔ䂳���ėp�����\�L�B�j
�@
�@�@�@�s�}�Q�t���J�j�J���ȑш�̎O�t�\���iVer.7�j
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �m���^�t�B�W�J���ȑш�n
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@�@�@�@�@�@�@����������������������������������
�@�@�@�@�@�@�@�����J�j�J���ȑш�i�L�`�E�\�j
�@�@�@�@�@�@�@ �m��l�̂́@ �@ ���@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@������ԁn�@��
�@�@�@�@�@�@�@�@�����������@�@���@���_�́q���r
�@�@�@�@�@�@�@����������������������������������
�@�@�@�@�@�@�@�����J�j�J���ȑш�i���`�j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@�m���n�����������������ꄪ���������������ꄪ���������m���n
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@�@�@�@�@�@�@����������������������������������
�@�@�@�@�@�@�@�����J�j�J���ȑш�i�L�`�E���j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�� �m���ق̐��n
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@�@�@�@�@�@�@�@���ی`�����@�@���@���߁A�I�m�}�g�y
�@�@�@�@�@�@�@����������������������������������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �m�}�e���A���ȑш�n
�@
�@���A���I����_�Ƃ́u�n���w�v�I�Ȃ˂�����߂����āB
�@��64���ŁA���̃p�[�X�y�N�e�B�����߂��铮�Ԙ_�����I����_�ɓ������A�q����r�Ɓq�����r�Ɓq���r�Ɓq���r���߂���l�̎��I���ꑊ�݂́u�ʒu�v�W���m�肵���B��66���́s�}�P�t�Ŏ������悤�ɁA�����̂����q�����r���߂��鎄�I����͐}�̉E������A�q���r���߂��鎄�I����͍�������u�����Ă���B
�@���̂ǂ��Ɂu���_�I�]�сv������̂��Ƃ����ƁA��64�͂Ŏ��͎��̂悤�ɋK�肵�Ă��āi�����_�̘_���ɉ����Ĉꕔ������Ă���j�A�u�����E���ŁA�����͍����v�ň�т��Ă���ƒf���������Ƃɖ��炩�ɔ����Ă���B
�@
���q�����r���߂��鎄�I����
�E�E����Ɍ������āu�\���v�̃x�N�g�������o
�E�������I�ȉ\�����܂ށq�����r��錾��i�����������̓J�^���j
���q �� �r���߂��鎄�I����
�E������Ɍ������āu���Ԑ��v�̃x�N�g�������o
�E�Z���Ȏ��Ԑ��i�q���r�j��тт�����̕������錾��i�߂������̓E�^�j
�@
�@���́u���v�́A�ȑO�ɏq�ׂ��悤�Ɂi��69����Q�ߒ��Q�j�A�{�����ʐ}�ł͕`�ʂł��Ȃ����ԁi���̐}�ł��l�����}�ł��`�ʂł��Ȃ����ԁA�����炭�����̐��E�̏o�����j�����ĕ\�����Ă��邱�Ƃ��琶����\�ʓI�Ȃ��̂ł���B
�@���I���ꂪ�ғ�����u�[�w�v�ƁA�����ŋc�_���Ă���l�Ԃ́i���j����̃��J�j�J���ȑш�Ƃł͎������قȂ�B�������66�͂́s�}�t�̂悤�ɁA���������ʂɏ������ނ��Ƃ͖{���ł��Ȃ��B���t�������ԈႦ�Ă��邩������Ȃ����A���E�i�f�B�}�P�[�V�����j�������́u�z���v�����Ȃ�������Ȃ��͂����B
�@
�i�V�T�͂ɑ����j
���v���t�B�[����
�����I���i�Ȃ��͂�E�̂肨�j1950�N�㐶�܂�B���Ɍ��ݏZ�B��N���̂ɏ����ꂽ�a�̂̈Ӗ��������ł���̂͂��������Ƃ��B�ł��A�{���Ɂu�����v�ł��Ă���̂��B�����Ɂu�Ӗ��v�Ȃǂ���̂��B�����������t���g���ĉ�����`�B���邱�Ƃ��̂��̂��s�v�c�Ȍ��ۂ��Ǝv���B
Web�]�_���u�R�[���v50���i2023.08.15�j
���F�ƃN�I���A�^�y���\�i�ƚF����V�S�́@�l�Ԃ̌���̎O�ш�_�i���^�t�B�W�J���сE���O�j�i�����I���j
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU�@2022 Rights Reserved.
|
| �\���i�ڎ��j�� |
