|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「la Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
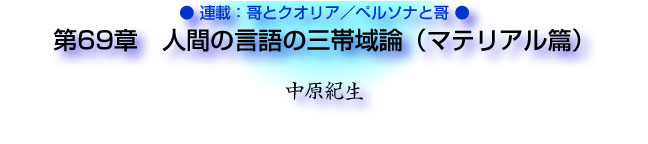
|
|
(本文中の下線はリンクを示しています。また、キーボード:[Crt +]の操作でページを拡大してお読みいただけます。)
■「水波の比喩」をめぐって
人間の(諸)言語の三つの稼働帯域について、以下、前章の《図》を念頭におきながら、マテリアル篇、メタフィジカル篇、メカニカル篇の順に考察していきたいと思います。が、その前に、この図の地勢学的解釈、すなわち「マテリアルな帯域/メカニカルな帯域/メタフィジカルな帯域」∽「海/波/風」の対応関係に関連して、ソシュールとドゥルーズの思考を、いずれも孫引きのかたちで拾っておきます。
その一、石田英敬著『記号論講義──日常生活批判のためのレッスン』[*1]。
いわく、ソシュールは、「シニフィアン」(意味スルモノ=記号表現、音声・音調・音響イメージ)と「シニフィエ」(意味サレルモノ=記号内容、観念・概念)との、表裏一体で互いに切り離し得ない対応関係を「水」と「大気」の関係に喩えた。
原典にあたる(と言っても、これまた丸山圭三郎著『ソシュールの思想』からの孫引き)。いわく、「ソシュールは、第二、三回講義で、あの有名な波動の譬えを用いて、「コトバとは関係を樹立する活動である」という真理を説明した」。
その二、平倉圭著『かたちは思考する──芸術制作の分析』第8章「普遍的生成変化の〈大地〉──ジル・ドゥルーズ『シネマ2*時間イメージ』」。
いわく、『意味の論理学』では「ニーチェ−アントナン・アルトーの「大地−大海」と、ソクラテス−プラトンの「天空」との間に、ストア派−ルイス・キャロルの「表面」を描き出すこと」が賭けられていた。だが『シネマ2』においてドゥルーズの思考は決して「表面」にとどまることができない。なぜなら映画はこの世界を撮影するものだからだ。キャロルが描く言葉の世界とは異なり、この世界は重力で満たされている。私たちの身体は「大地」に落下する。(204-205頁)
「海」もまた『シネマ2』のなかでは私たちを待ち構える崩壊の場所として描き出される。「海」は私たちを深く呑み込み、記憶の彼方へと連れ去ってしまう。「記憶のあらゆる広がりのむこうには、それらをかきまぜる波の音があり、一つの絶対を形づくる内部のあの死があり、それをまぬかれえたものは、そこから復活するということを理解しなくてはならない。」[『シネマ2』訳書289頁](206頁)
『シネマ2』第9章「イメージの構成要素」では「現代映画において視覚的イメージから切り離されていく、音声的言語行為の諸相」が論じられる。なかでもストローブ=ユイレの『モーゼとアロン』は、天空の言葉=音声的イメージ(モーゼ)と大地の視覚的イメージ(アロン)との乖離そのものをテーマとしている点で範例的だ。「出来事とは、つねに抵抗であり、言語行為がもぎとるものと大地が埋め隠すものとの間にある。それは天空と大地の間、外の光と地下の炎の間の循環であり、それにもまして音声的なものと視覚的なものとの間の循環である。」[『シネマ2』訳書352頁](213-214頁)
──これらの議論のあいだには、微妙または明白な違いがあります。たとえば、ソシュールの「音声」は下方に位置づけられ、ドゥルーズの「音声的なもの」は天空に立ち昇る、といった具合に。それらの差異を強引に結びつけ、かつ独自の拡張をおりまぜ「整合」させると、次のような図式が得られます。
◎ソシュールの「記号学」
・観念(精神的な実体)の次元:大気=メタフィジカルな帯域(原型+反復)
・記号(関係性の形式)の次元:波 =メカニカルな帯域
・音声(物理的な実体)の次元:水 =マテリアルな帯域(模倣+母型)
◎ドゥルーズの「シネマ」
・天空からの〈声〉(精神性):メタフィジカルな帯域(反復)
・流体化した視覚像(物質性):マテリアルな帯域(模倣)
◎ドゥルーズの「シネマ」(拡張版)
・刻印としての文字(受肉性、複製性):メタフィジカルな帯域(原型)
・地下世界からの聲(憑依性、復活性):マテリアルな帯域(母型)
◎ドゥルーズ−平倉の「中空」
・語ることのできない者の言語(叫び(命名)[*2]):メカニカルな帯域(母型/反復)
・見ることのできない者の視覚(透視(仮象)[*3]):メカニカルな帯域(模倣/原型)
《図1》人間の言語の二契機と三帯域(Ver.2)
≪純粋言語≫
↓
δ==== <受肉> ====
↓
原 型 │ 反 復
│
γ━━━━━━┿━━━━━━
│
模 倣 │ 母 型
↑
β==== <憑依> ====
↑
≪私的言語≫
※γ〜δ=メタフィジカルな帯域:大気(風)
γ =メカニカルな帯域 :波
β〜γ=マテリアルな帯域 :水(海)
[*1]「私の考えでは、ソシュールの同時代人であるクレーの「造形思考」には、記号とかたちについてのある本質的な問いが含まれている」(『記号論講義』62頁)。石田英敬氏は、ソシュールの記号学を取り上げた同書第2章の冒頭でそのように語り、記号すなわち「二つの異質な次元の間に結ばれる関係性の形式[=かたち]」の意味作用を探究したクレーの「造形思考」の(ソシュール記号学と共通する)エッセンスを、「分節」(差異にもとづく構成単位、音素と形態素)と「反復」(記号結合、範列と連辞)と「布置」(記号実現、文の成立=記号と世界との関係づけとしての意味の出来事)として摘出している。
ライナー・クローンは「意味のかけらの宇宙──パウル・クレーの音節について」で、ソシュールの言語論と重ね合わせながらクレーの「建築的絵画」について論じている。
「上方」すなわちメタフィジカルな帯域に棲息する「形態素(morpheme)」もしくは「記号素(moneme)」、「下方」すなわちマテリアルな帯域に蠢く「形成素(figurae)」もしくは「文字素(grapheme)」+「音素(phoneme)」。
[*2]「叫び(命名)」は「名は言語の究極の叫びであるだけでなく、その本来の呼びかけでもある」というベンヤミンの議論に依ったもの(「言語一般および人間の言語について」第九段落、この文章は前章の註でも引用した)。
[*3]「透視(仮象)」(あるいは「透視される死」と書くべきか)の出典は、森田團『ベンヤミン──媒質の哲学』。森田氏は、イメージ(仮象)と冥界的なもの(死)との結びつきを論じた第六章「イメージにおけるハデス的なもの──前期ベンヤミンにおけるイメージ概念」で次のように書いている。
同じこと(と私には思われる)が、吉田裕氏の「イマージュの経験──バタイユはラスコーに何を見たか?」(『洞窟の経験──ラスコー壁画とイメージの起源をめぐって』所収)では次のように論じられている。「イマージュは実現されることのない対象を捉えようとする運動であり、そのために描線は反復されて錯綜し、その中から仮象としての形象が現れる。」(83頁)
■「マイナス内包=形相なきマテリアル」と「無心の形而下学」─マテリアル篇1
人間の(諸)言語の稼働圏域を下支えするマテリアルな帯域、その色調もしくは音調(音象[ネイロ])を体感させる素材。
その一、入不二基義著『現実性の問題』第7章「無内包・脱内包・マイナス内包」。
入不二氏はそこで、クオリアを第〇次内包として捉えた永井均氏の説を拡張し、「マイナス内包としてのクオリア」という概念を呈示する。いわく、マイナス内包としてのクオリアとは、特定の概念による明確な括りの下で(たとえば赤の赤らしさとして)感じられるようになる(ありありと現前するようになる)より「以前」の、「(概念なき)潜在的なクオリア」あるいは「クオリアの潜在態」を言う。もしくは「クオリアの闇」であって、そこから無数の顕在的な(ありありとした)クオリアが発現してくると想定される存在論的な「無尽蔵」である。(261頁、279頁、292-293頁)
文中の「形相なきマテリアル」は「形相なき質料的現実」[*1]とも言い換えられる。人間の(諸)言語の第一の稼働帯域は、この「形相なきマテリアル=形相なき質料的現実」と「マイナス内包=無尽蔵のクオリアの潜在態」が同じ一つのものになる場、つまり物と心が通底し地続きになる「潜在性の場」[*2・3]に根差している。
その二、井筒俊彦著『意識と本質』Ⅶ、禅の分節論。(本稿第29章ですでにとりあげた議論なので、ここでは文脈に即して簡単に要約する。)
いわく、禅は「無心」の「形而下学」である。ここで「無心」とは、「有心」すなわち「分節意識」に対する「絶対無分節的意識」もしくは「純粋無雑なノエシスそれ自体」を言う。
禅の実在体験(悟り、見性体験)の全過程を分析すると、「分節Ⅰ」(=有「本質」的分節)→「無分節」(=形而上的「無」)→「分節Ⅱ」(=無「本質」的分節)となる。「山は山である」→「山は山ではない」→「山は山である」。
分節Ⅱの次元ではあらゆる存在者が互いに透明である。花は花として現象しながら、しかも花であるのではなく、花のごとし(道元)である。この花は存在的に透明な花であり、他の一切にたいして自らを開いた花である。
井筒俊彦が「無「本質」の花」と呼ぶもののことを、私は前章で「詩的物質(マテリアル)」と名づけた[*4]。自由分節の世界、すなわち「詩的物質」が相互浸透し合うマテリアルな帯域。そのような存在の「かたち」をめぐる「流動・浸透」の原理を、私は「模倣」の名で呼びたいと考えている。
[*1]「形相なき質料的現実」には次の註が付いている。「私がここで念頭においているのは、永井均が「物理学主義(physicalism)」と対比させて述べた「究極の唯物論(materialism)」である。」(337頁)
入不二氏が「念頭においている」永井均の議論(「聖家族──ゾンビ一家の神学的構成」)を引用する。
[*2]入不二氏によると、「現実性(actuality)」と「潜在性(potentiality)」の対照には、認識論的な水準と存在論的な水準がある(76頁)。認識論的な水準における現実性は潜在性の発現(manifestation,realization)・現前(presence,appearance)としてあり、そこでは現実性と潜在性は相互排他的である。これに対して存在論的な水準におけるそれは一番外側で透明に働く現実性であり、発現・現前するしないに関わらない「純粋現実」である。そこでは潜在性は現実性の働きの内にあって「‘現に’潜在している」のである。
入不二氏の「潜在性の受肉化」は、私のターミノロジーでは「憑依」に該当する。
ここで前章の《図》をめぐる場違いな註を加える。私がそこで【空】の語をあてがったのは(ベルクソン−ドゥルーズ的な意味合いでの)「潜在性(virtuality)」の領域を言い表わすためである。そして「空/現」の垂直軸全体が(広義の)「現実性(actuality)」の働きを、【現】が(狭義)の「現実性」の領域を表現している。したがって、オリジナルな発想は入不二氏が言うところの「存在論的な水準」にあったが、一方で、(「無」ではなく「空」の語を採用したように)、「空」の発現・現前としての「現」という「認識論的な水準」の発想を重ね合わせてもいた。
これまで何度か伝導体もしくは伝導体類似の概念図式を作製してきたが、そのたび感じたのは、本来平面に描けない(そもそも三次元であれ四次元であれ静止画像では示せない)事態を表現していることの座りの悪さだった。まだ模索段階ではあるが、入不二氏の議論を援用し、次のような思考の手順に従い修正することで、事柄の実相に少しでも迫り得るのではないかと思う。
・《図》中の「虚−実」の水平軸(横軸)は本来三次元の空間に時間を加えた世界を縮減して表現したもの(それを私は「モンタージュの時空」と呼んだ)。
・そこに「存在論的な水準」における「潜在性/現実性」の動性が、すなわち純粋な現実性としての力の作用(憑依と受肉)が第五の次元として書き加えられる。
・しかしこの五次元世界は存在すると同時に崩壊し、「空/現」の垂直軸(縦軸)として《図》中にその痕跡を残す。
・《図》中の「空/現」の垂直軸(縦軸)は「認識論的な水準」における「潜在性/現実性」の動態を、すなわち「顕現化(「空」の憑依)/退隠化」(と、その鏡像反転形である「脱受肉化/(「現」の)受肉化」)を示している。
・存在論的な水準における「現」は《図》の中心点から手前に(この文章の読み手が位置する側に向かって)立ち上がり、存在論的な水準での「空(無)」は《図》の中心点から彼方=奥底に(この文章の読み手が位置する側とは反対側に向かって)その深度を深めていく。
・しかしこの存在論的な水準における「空(無)/現」の力の作用は存在すると同時に崩壊し、「空/現」の垂直軸(縦軸)として《図》中にその痕跡を残す。(以下、同様のプロセスを繰り返す。)
[*3]「形相なき質料的現実」(潜在性の場)と「無内包の現実」(一番外側で透明に働く現実性)の違いについて、入不二氏は次のように論じている。
私の考えでは、入不二氏が言うところの区別・境界・差異がまだ入っていない「ベタ」が、吉本隆明の「意味多様体のアモルフなかたまり」につながる。
[*4]この論考群の地下水脈の一支流をなす「イマージュの四分類」の議論──「像(イマージュ)/喩(フィギュール)/象(パライメージまたはパンタスマ)/肖(アケイロポイエートスあるいはホモイオーシス)」(第42章、第58章、第59章参照)──に関連づけると、「詩的マテリアル」(もしくは「意味多様体のアモルフなかたまり」)は「象」に該当する(第36章、第37章参照)。
■「アモルフな意味多様体」と「大洋のような母音の波の拡がり」─マテリアル篇2
その三、吉本隆明著『宮沢賢治』第Ⅵ章「擬音論・造語論」。
「物」(形相なきマテリアル)と「心」(クオリアの潜在態)が地続きになる潜在性の場。花が鳥に浸透し、花が鳥であり、他のすべてのものであり、そして、(「水素よりももっとすきとおっ」た)「無」である世界。このような、透明な花(詩的マテリアル)が咲き添い、透明な鳥(詩的マテリアル)が飛び交う形而下の世界をめぐる極限的表現(「文字の記述」)を、吉本隆明は「意味多様体のアモルフなかたまり」と名づけた。
(本稿のこれからの議論に関連づけると、「擬音と造語の世界」はテレパシーに、「同時に多重な表現」はアナグラムにつながっている。)
その四、吉本隆明著『母型論』「大洋論」。
前々章で引用した文章のなかで、安藤礼二氏は、「吉本が宮沢賢治のうちに見出した、意味多様体のアモルフで重層した「詩語」の姿は、この後、『母型論』において、より科学的にそしてよりポエティックに展開されることになる。母音の「大洋」に浮かぶ、自然の風物をすべて音としてとらえることを可能にする「胎児」の喜びに満ちた世界として」(『吉本隆明』101頁)と書いていた。
この、大洋のような「母音(=言語母型の音声)の波の拡がり」は、それ自体で言語といえるだろうか? 吉本はそのように問いを立て、自ら答えていわく、内蔵系(植物系)の情感の跳び出しである心の動きと、筋肉系(動物系)の筋肉の動きの表出である感覚の変化から織りあげられた母音の波は、「「概念」に折りたたまれた生命の糸[*1]と出合えないかぎり、言語と呼ぶことはできないはずだ」(45頁)。
ここで吉本は、角田忠信の研究を踏まえ、本来それだけでは意味をなさない母音の波の響きを、言語優位の脳(左脳)で意味(前意味)をもったものとして感受する、旧日本語族やポリネシア語族の「特異な」事例をもちだし、そこから垣間見える「新しい地平」を論じている(47頁)。[*2]
吉本隆明による言語(へ)の発展段階を、かの私的言語の三段階(本稿第65章、第66章参照)と対比させると、次のようになるだろうか。
【第一段階】「アワワ」音声の水準
・〈感情〉をめぐる私的言語
【第二段階】擬音や前意味的な音声の段階
・〈現実〉をめぐる私的言語
・〈 今 〉をめぐる私的言語
【第三段階】「概念」の同定、言語としての意味形成
・〈 私 〉をめぐる私的言語
[*1]この「生命の糸」が「母型」と「詩語」(同時に重層している意味多様体のアモルフなかたまり)を繋ぐ媒質となる。そして、あたかも細胞の内部に折り畳まれたDNAを思わせる「生命の糸」が紡ぎだすものの名を「時間」という。(あるいは時間の胎内に宿るものこそが生命の糸であり、そして詩語であるのかもしれない。)
──ここで「アモルフなかたまり」から連想した話題を挿む。安藤礼二氏は『熊楠──生命と霊性』に収録された「粘菌・曼陀羅・潜在意識」のなかで、「熊楠の粘菌の起源」(18頁)となったエルンスト・ヘッケルの「モネラ」(無機物と有機物のミッシング・リングとなる生命の原初形態)をとりあげている。
スティーヴン・J・グールド著『個体発生と系統発生』を踏まえていわく、「一つの原初的な生殖細胞のなかには、太古から続く生命の無限の記憶が「波動=原子」として、つまりは粘菌の「原形体」のように絶えざる流動を続けながら、蓄えられていた」(21頁)。
また佐藤恵子著『ヘッケルと進化の夢』に依っていわく、ヘッケルはむき出しの「原形質」(plasma)として存在するモネラをモナドと同様なものとした。「ヘッケルは、そのようなモネラ=モナドは、精神を有する物質の基盤である、とさえ述べている。ヘッケルは、物質と精神の分割を拒み、非生命から生命(モネラ=モナド)の「自己発生」を推定している。」(24頁)
非生命と生命、死と生、物と心、男と女、植物と動物、等々を媒介するヘッケルの「モネラ=モナド」と熊楠の「粘菌=曼陀羅=潜在意識(アラヤ識)」をめぐる安藤氏の議論は、ヘッケルとパース(アブダクション)、パースと熊楠(萃点の思想)の方法論的類似性、そして熊楠と大拙の出会いと交流(未発見の往復書簡)へと進んでいく。
(未解決の論点群──吉本隆明の「母型」と鈴木大拙の「(日本的)霊性」の関係性、あるいは「詩的マテリアル」(詩語)と「霊的マテリアル」(霊性)との関係性、さらには「詩的・霊的マテリアル」としての「プラズマ」(モネラ=原形質、物質の第四状態)と「エーテル」との関係性。)
[*2]本文では割愛した吉本隆明の議論を書き留めておく。
■間奏─ベンヤミン的概念と吉本隆明的概念の融合
吉本隆明著『宮沢賢治』の末尾の文章を抜き書きしているちょうど同じ時期、山口裕之著『映画を見る歴史の天使──あるいはベンヤミンのメディアと神学』第6章「歴史的時間とメシア的時間」の、「想起[Eingedenken]」の概念をめぐって書かれた文章を読みすすめていた。そして、私の脳髄のなかで、吉本隆明が言う「同時に重層している意味多様体のアモルフなかたまり」とベンヤミンの「アレゴリー的形象」の概念がオーバーラップしていった。
山口氏はそこで、「歴史的時間」から「メシア的時間」へという、想起(目覚め)と歴史認識にかかわる「コペルニクス的転換」(『パサージュ論』[K1,2])について論じている。それは「時間によって規定されるわれわれの「歴史」の世界をその外側から見る歴史の天使のまなざし」(239頁)にかかわるものだ。
ここで山口氏は、『パサージュ論』のなかの次のメモを引用する。「過去がその光を現在に投影するのでも、また現在がその光を過去に投げかけるのでもない。そうではなく形象のなかでこそ、〈かつてあったもの〉が〈いま〉と閃光のごとく一瞬に出会い、一つの布置を作り上げるのである。言い換えれば、形象は静止状態にある弁証法である。なぜならば、現在が過去に対してもつ関係は純粋に時間的・連続的なものであるのに対して、〈かつてあったもの〉がこの〈いま〉に対してもつ関係は弁証法的だからである。」([N2a,3])
再び、「歴史の概念について」の議論が挿入される。「時間が胎内に何を宿しているのかを時間から聞き出した預言者たちは、まちがいなく、時間を均質なものとしても空虚なものとしても経験していなかった。このことをありありと思い描く者は、おそらく、過ぎ去った時間が「想起[アインゲデンケン]」においてどのように経験されてきたか、わかるだろう。つまり、まったく同じように経験されてきたのだ。」(補遺B)
以上の議論を念頭に置いて、ベンヤミン的概念・布置と吉本的概念・布置を適宜組み合わせると、下図の(仮設的な)構図を得る。
(ここで私は、ベンヤミンが言う「メシア的時間」をハンナ・アーレントが『過去と未来の間』の序文で述べた「非時間の空間[ノン・タイム・スペース]」に(本稿第49章、第65章参照)、また〈かつてあったもの〉=〈いま〉を永井均氏の独在性の〈私〉や〈今〉に(もしくは入不二基義氏の「純粋な現実性」の概念に)関連づけて考えている。)
《図2》人間の言語の二契機と三帯域(Ver.3)
≪アウラ≫
[δ]
┃
Ⅱ ┃ Ⅰ
┃
[α]━━━━━ 〇 ━━━━━[β]
┃
Ⅲ ┃ Ⅳ
┃
[γ]
≪根源≫
※α−β:歴史的時間
連続的・事実的なものの世界(空間化された無時間)
γ/δ:メシア的時間
γ=無時間,δ=非時間(時間の停止、一瞬、永遠)
〇:アレゴリー的形象
≒同時に重層している意味多様体のアモルフなかたまり
Ⅰ:原型(かつてあったもの)の反復(複製)
Ⅱ:原型(かつてあったもの)の受肉=引用(想起)
Ⅲ:母型(かつてあったもの)の模倣(復活)
Ⅳ:母型(かつてあったもの)の憑依=翻訳(想起)
■「根源的産出」と「原ミメーシス」─マテリアル篇3
その五、森田團著『ベンヤミン──媒質の哲学』。
序論。──ベンヤミン哲学の核心に「媒質 Medium」をめぐる思考がある。ベンヤミンにとって媒質とは関係する二項(自然と人間、等々)をはじめて根源的に産出する母胎であった。「媒質を絶対的に、かつ根源的に思考することによってあらわになるのは、媒介者であるものが、逆に媒介するはずの二項を構造的に含み込んでいることにほかならない」(16頁)。
第九章「イメージとミメーシス」。──ベンヤミンは初期言語論(「言語一般および人間の言語について」)において「言語(名[Name])」としての媒質を論じ、後期言語論(ミメーシスと言語の根源的な関係を述べた短いメモ「模倣の能力について」とその初稿「類似性の理論」)において「イメージ[Bild]」としての媒質から「言語(文字)」への変転過程の解明(読むことがいかにしてイメージを言語へと変転させるか)に取り組んだ。(334頁)
・無意識的なミメーシス、すなわち息子が父に似ていると言われる場合、生物学的類似性を除いてもなお「似ること」の生起のうちで秘かに働いている潜在的なミメーシスを、森田氏は「原ミメーシス」と呼ぶ。
──次章へ、続く。
[*]森田氏はここに註をつけ、これと「ほぼ同じ見解」を小池澄夫氏の「ミーメーシス」(『コピー 現代哲学の冒険6』所収)から引いている。興味深い議論なので、森田氏が引用した箇所の前後の論脈も含めて抜き書きしておく。
小池氏によると、ミメーシスは「似像[エイコーン]系」(視覚と手の動きに対応するミメーシスの系統)と「再帰系」(声・聴覚に代表される身体運動に対応するミメーシスの系統)に二分される。後者は「まねる」=「自分自身(の声、姿かたちなど)を……に似せる」が再帰的動作をあらわす中動態動詞であることに依る。
ここで言われる圏域、すなわち反復によって条件づけられた「反響的動作」(=中動態的身振り?)が波動上にひろがる「全身」のことを、私は人間の言語のマテリアルな帯域と捉えている。
(第70章に続く)
★プロフィール★
中原紀生(なかはら・のりお)1950年代生まれ。兵庫県在住。千年も昔に書かれた和歌の意味が理解できるのはすごいことだ。でも、本当に「理解」できているのか。そこに「意味」などあるのか。そもそも言葉を使って何かを伝達することそのものが不思議な現象だと思う。
Web評論誌「コーラ」48号(2022.12.15)
<哥とクオリア/ペルソナと哥>第69章 人間の言語の三帯域論(マテリアル篇)(中原紀生)
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2022 Rights Reserved.
|
| 表紙(目次)へ |
