|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「la Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
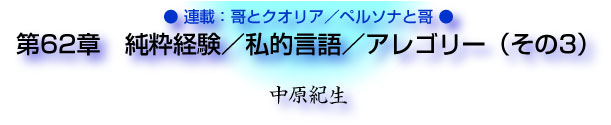
|
|
■私的言語の生成とその受肉
前章で、私は、「梵我一如」の構造をめぐって、永井均氏の議論を踏まえ次のように定式化しました。
【Ⅰ】〈 〉=〈私〉:「そもそもの初めから存在する(=それがそもそもの初めである)ある名づけえぬもの」すなわち〈 〉が、開闢の「あとから」他のもの(たとえば他人)との対比が持ち込まれて〈私〉と名づけられる。あるいは梵(〈 〉)と真我(〈私〉)の合一。
しかし、この、科学的・歴史学的な客観的事実を超えた「超越的な存在」をめぐる等式は、やがて「世界にはたくさんの人間が並列的に存在し、それぞれに自我があるというような、通常の平板な世界解釈」のもとでとらえられるようになります。すなわち、次のようなかたちで。
【Ⅱ】《私》=「私」:「対比が持ち込まれた後では、あたかも対比が成り立つための共通項[私と他人に共通の「人間」]がもともとあったかのような錯覚が生まれる。そして、この錯覚こそが現実になる」(『私・今・そして神』41頁)。
ここで、【Ⅰ】から【Ⅱ】への推移(頽落)のプロセスを、空想的に追跡してみます。
①〈私〉=『私』:超越的世界における【Ⅰ】の等式が、この世界の内部へと類比的に繰りこまれる。
②〈私〉⇒《私》:独在性の〈私〉(この世界の客観的事実を超えた語りえない存在)は、単独性の《私》(この世界に実在する他でもないこの私)として語られる。
③《私》=『私』:①と②によって。
④『私』⇒「私」:愛と経済の主体である特殊・個別の『私』は、公的言語(日常言語)における一般的な「私」として語られる。
⑤《私》=「私」:③と④によって。
ここまでに登場した四つの等式(〈 〉=〈私〉,〈私〉=『私』,《私》=『私』,《私》=「私」)の、それぞれの等号を矢印に変形すると、次の四つの式が得られます。
・〈 〉⇒〈私〉:世界の開闢
・〈私〉⇒『私』:キリストの受肉
・《私》⇒『私』:並列的な世界の描像(モナドロジー、華厳経の世界)
・《私》⇒「私」:平板な世界解釈(公的言語の世界)
最後に、これら四つの式を一般化します。それらは、「名づけえぬもの」(開闢の奇蹟)がこの世界の内部で、「その内部に存在する一つの存在者として位置づけられ[=受肉され]、名づけられる」(『私・今・そして神』43頁)プロセスを示しています。(永井均氏は『世界の独在論的存在構造』で、「私の見るところでは、超越的事実を平板な世界像の内部へ強引に位置づけることは、一般に宗教というもののもつ特性の一つなのだ」(293頁)と書いている。以下の四式は、そのような宗教のはたらきを示すものと理解することができる。)
【A】〈 〉⇒〈E〉
【B】〈E〉⇒『E』
【C】《E》⇒『E』
【D】《E》⇒「E」
これらの式に用いた「E」は、ドイツ語「Etwas」の頭文字で、それは、「言語的な象徴によって心にもたらされる「何か」」(井筒俊彦)とか、「〈私〉は、だれでもないどころか、何でもないのだ。しいていうなら、ただ‘これ’でしかない。それが‘何であるか’は決してわからないどころか、いやむしろ、それは‘何であるか’がない」(永井均)などと言われるときの、その「何か」や「これ」を指しています。あるいは、『新版 哲学の秘かな闘い』の第8章「語りえぬものを示す(2)──時間を隔てた他者の可能性としての私的言語の可能性」で示された、ウィトゲンシュタインの『哲学探究』二六一節の永井訳に出てくる「何ごとか」を。
永井氏は、同書第7章「語りえぬものを示す(1)──野矢茂樹『語りえぬものを語る』一八章における私的言語論の批判」のなかで、このウィトゲンシュタインのテクストをめぐって、次のように論じています。
本稿で考察しようとしている私的言語は、ここで永井氏によって余すところなく定義されたそれ、つまり、固有名で置きかえることができる《私》ではない、独我論的主体たる〈私〉の言語、あるいは、私秘的な感覚──永井氏が『〈私〉の哲学 を哲学する』の序章「問題の基本構造の解説」のなかで、「現実性の累進構造こそが「私秘的な意識」(あるいは「クオリア」)という不可解な概念の根源にあるのではないか、ということが、私が『なぜ意識は実在しないのか』で論じた問題であった」(36頁)と書いていた、その「クオリア」──を語る言語ではなく、独在的な存在を語る言語にほかなりません。
このことを、前章までの論脈にそくしていいかえると、私的言語とは、語り得ない純粋経験を語る言語である、となります。そして、その純粋経験(〈E〉)には、独在性の〈私〉のほか、〈今〉や〈現実〉(や〈感情〉)が含まれる。というか、私がこれから取りくもうとしているのは、そのような「純粋経験を語る(四つの)私的言語」をめぐる考察にほかならないのです。
■私的言語のやっかいな本性
ここで、私的な註をひとつ。
純粋経験について、前々章で私は、「言葉を発し、文章を書きつけるとき、私の意識のうちに立ち現われてくる言語的な思いや感じ」あるいは「言詮不及の意味体験」と規定した。そして、この語りえぬ純粋経験をめぐる言語表現を通じて、それが「言語以前の直接的なもの」もしくは「言語に先立つ空虚な実在」であることが確定する、とも書いた。ここには純粋経験の、そしてまた純粋経験を語る私的言語がもつ、一筋縄ではいかないやっかいな本性(あるシステムの内部で生起する出来事が実はそのシステムの起源をなすといった倒錯[*1]、あるいは開闢と持続の断絶)が露出している。
これらのことを踏まえると、以下の議論では、この世界の内部に居場所をもたない純粋経験について語る私的言語が(この世界の外に?)生成し、やがて公的言語のうちに受肉(頽落)していくプロセス(【A】~【D】)と、この世界の内部において言語が誕生し、やがて言詮不及の言語現象(純粋経験)を語る境位にまで進化していくプロセスとが、あたかも合わせ鏡のような関係を切り結ぶことになるだろう。
しかし、この世界の外(言語の外)で起こった(と、言語使用に習熟した「後から」知ることができる)メタ・フィジカルな出来事について語る言葉を、そもそも私はもちあわせていない。
先走りの議論になるが、ここで露になったやっかいな本性(倒錯、断絶)は、「私的言語」と「言語ゲーム」の関係に置きかえて考えることができるのではないか。たとえば、次のような仮説のもとで。
……私的言語は「夢の言語」(夢のなかの言語、夢としての言語、夢を語らう言語、等々)であり、言語ゲームは「言語が見る夢」(意味)を「映画」(無数の夢の引用)として形象化する。(ポール・クローデルは「物質化された夢」としての能をめぐって、「もはや演者[=言語ゲームのプレイヤー]の内側に感情があるのではなく、演者が感情の内側に身を置くことになる」(『朝日の中の黒い鳥』)と語った。)そして、「夢の言語」と「言語が見る夢の形象化」としての能=映画をつなぐのが、「アレゴリカルな文字像」(ベンヤミン)[*2]である……。
前章の末節に、言語ゲームは本来、定家論理学の世界に属する問題で、貫之現象学のC層にいたってようやく取りあげることができるテーマであると書いた。
以前用いた言葉を使ってこれを詳説すると、次のようになる。すなわち、定家論理学を本籍とするのは、言語によって世界を創造し、その世界のなかに「純粋経験」(の主体=ペルソナ)をつくりだす「強い」言語ゲームであり、他方、「純粋経験」を通じて言語がつくられ、そしてその言語が世界そのものであるところの「強い」私的言語は、貫之現象学を本籍地とする。また、貫之現象学の圏域内で稼働するのは「弱い」言語ゲームであり、定家論理学の内部ではたらくのが「弱い」私的言語である。
ここに俊成系譜学の世界を導入する。かつて(第40章で)「像、イマージュ、形」と定式化した貫之現象学の世界と、「象、パライメージ、体」と定義した定家論理学の世界(あるいは、これに「イマジナル」を掛け合わせて得られる「虚象、パンタスマ、虚体」の狭義の定家論理学の世界=虚なるものの世界)の中間に、「喩、フィギュール、姿」の俊成系譜学の世界を位置づけることができる。
この道具立てを使ってさきの仮説を「解説」すると、貫之現象学における「強い」私的言語(夢の言語)と定家論理学における「強い」言語ゲーム(能=映画)を媒介するのが、俊成系譜学における「アレゴリー」である、となる。あるいは、貫之現象学の「体験」(クオリアの世界)と定家論理学の「言語」(ペルソナの世界)を、俊成系譜学の「文字像」が仲介すると。
[*1]永井均氏が『なぜ意識は実在しないのか』で導入した「逆襲・逆転」という発想をめぐって、入不二基義氏が「無内包の現実」(『〈私〉の哲学 を哲学する』第Ⅰ部「入不二基義セクション」)で次のように書いている。前後の文脈や術語(「関係の第一次性」や「独立の第〇次性」)は気にせず、引用する。
[*2]道籏泰三著『ベンヤミン解読』の二章「髑髏のにたにた笑い──廃墟からの構築としてのアレゴリー」から。
■私・今・現実そして感情?
永井ワールドにもどります。
『私・今・そして神』がその開闢を告げた「現在の」永井哲学の現時点での到達点、というかその最先端の議論は、哲学探究1・2の副題をもつ『存在と時間』、『世界の独在論的存在構造』の二冊の書物に見ることができます。それらの著書で(何度でも最初から)取りくまれているのは、〈私〉と〈今〉そして〈現実〉が存在することへの驚きと、それらに共通する構造の解明という、紛れもない永井哲学(永井神学)の刻印を帯びたテーマにほかなりません。このことについて、たとえば「哲学探究2」の雑誌掲載稿の冒頭では、次のように述べられています。
私と今と現実をめぐるメタ・フィジカルな問題は、『私・今・そして神』の最終局面で述べられた言語による世界創造をめぐる形而下的な言語哲学的問題と響き合っています。「言語は開闢を隠蔽する。逆に言えば、世界を開く。人称、時制、様相は、客観的世界の成立に不可欠な要件だが、それは開闢それ自体を隠蔽することによって可能になるのだ。「私の今の言語」──この言い方が、言語の内部ではその人称概念と時制概念に吸収されて理解されることになる。」(222頁)
ところで、その『私・今・そして神』で、永井氏は、「私の分裂」と並行的に論じて哲学的意味を失わない思考実験として、「世界の分裂」と「今の分裂」、そして「神の分裂」を挙げていました(107頁)。また、第2章最終節の最後の項「神・現実・私・今」では、「この私」や「今」や「現実世界」や「神」の存在証明をめぐる議論を経て、次のように述べていました。
神と現実と私と今の取り合わせは、同書最後の一文にも登場します。
冒頭でふれた「現在の」永井哲学の最先端の議論、すなわち、三つのメタ・フィジカルな存在の共通構造の解明と、ここで語られた四つの思考実験、四つの哲学史上の中心課題とを組み合わせてみます。するとそこに、ひとつの「空白」があらわれてきます。(さらに客観的世界の成立要件の話題をこれに組み合わせると、人称、時制、様相に次ぐ第四の文法的概念の欠落が浮き彫りになってくる。)
・〈 私 〉⇔ 私の分裂 :コギト命題の解釈をめぐる論争
・〈 今 〉⇔ 今の分裂 :A系列とB系列をめぐる時間論上の議論
・〈現実〉⇔ 世界の分裂:現実世界の位置をめぐる可能世界論における対立
・〈 〉⇔ 神の分裂 :神の存在論的証明をめぐる哲学史上の諸説
最後の山括弧の中に入る語彙の第一候補は、間違いなく「神」(=「在りて在るもの」すなわち「存在」?)でしょう。つまり、〈神〉の存在構造(〈存在〉の存在構造?)をめぐる考察は、永井哲学においていまだ手つかずの課題として残されている、ということになるのでしょう。あるいは、〈神〉とは〈私〉と〈今〉と〈現実〉が三位一体的に存在することそれ自体にほかならず、だから〈神〉の存在構造をめぐる課題はそれら三者の共通構造の解明作業のうちに回収されていくのだ、(だから山括弧の中は空白のままでこそ意味があるのだ)、といった議論がありうるかもしれません。(〈神〉をめぐる私的言語は〈神〉について語り合う言語ゲームのうちに回収されるのだ、といったような議論も?)
しかし、私はこれまでから、そこに「感情」という語を嵌めこめないかと考えてきたわけです。
■純粋経験を語る四つの私的言語・序論
永井氏は、先に引用した、「私の分裂」と並行的に論じて哲学的意味を失わない思考実験をめぐる話題に関連して、次のように論じていました。
いわく、それでも「私の分裂」と「世界の分裂」とでは、事情が異なるのではないか。私の場合は、それまでの私の記憶を受け継いでいるほうがなぜか私ではない、ということが(ライプニッツ原理によって)起こりうるが、世界の場合は、現実世界のこれまでの歴史とつながった歴史経過が別の世界で生起しはじめたら、その非現実の世界のほうが(カント原理によって)現実世界になる、と言いたくなるのではないか。
開闢の神による現実世界の創造と私の創造とは、同じ一つの行為である。いや、そもそも「どの世界が現実であるかはそこに私が(しかも今)存在するか否かで決まる」のだとしたら、「世界」と「私」と「今」の「現実」性が、同じ一つの行為によって決まることになる。ここに出てきた四つのキーワード、「世界、現実、今、私」が、これからの議論のテーマ、すなわち、純粋経験を語る四つの私的言語をめぐる考察の起点となります。
ただし、このうち「世界」については、私の個人的な事情(こだわり)によって、「感情」の語に置きかえます。それは、たとえば、記号生成や言語創出、世界における現実性の出現に際して情動・感情が決定的な役割を果たしていること(次章でとりあげる石田英敬氏の議論)、あるいは、大森荘蔵が「世界は感情的なのであり、天地有情なのである」(「自分と出会う──意識こそ人と世界を隔てる元凶」)と述べたこと(第32章参照)、そして、その大森哲学における「相貌」の概念をめぐって、野矢茂樹氏が「知覚風景のパースペクティブはそれが開ける主体の立つ視点位置を刻印しているが、それと同様に、知覚風景の相貌はそれが開ける主体の感情を刻印している。」と書いていたこと(『大森荘蔵──哲学の見本』、本稿第5章、第52章参照)、等々に拠るのですが、いまひとつ論拠を示すとすれば、富士谷御杖の歌論における「神」(迦美)が、個人の内なる神すなわち「私思欲情」を指していたこと(第6章参照)を挙げてもいいでしょう。
いや、それらはなんの「論拠」にもなっていない。それどころか、(次節で検討する「無内包の現実性」の議論を踏まえて言えば)、そこに「感情」などという質料性(内包性、事象内容性)を含んだ概念を投入するのは、端的なミステイクであるとさえ思えてくる[*]。──と、考えは定まりませんが、ここでは、純粋経験を語る四つの私的言語の第一を「〈感情〉をめぐる私的言語」(別名もしくは原名は「〈世界〉をめぐる私的言語」)とし、第二を「〈現実〉をめぐる私的言語」(厳密には「〈(現実世界の)現実性〉をめぐる私的言語」)、第三、第四をそれぞれ「〈 今 〉をめぐる私的言語」、「〈 私 〉をめぐる私的言語」と命名し、先を急ぎます。
[*]私は、純粋経験がもたらす独特の感触、実質的内容からは独立したその(「空っぽの存在=空虚な器」性がもたらす)触感のようなものを表現する語を探していたのだろう。そして、仮に採用した「感情」の語に心底納得できていないのだろう。それを「アウラ」と言いかえても、あるいは東洋思想の文脈を踏まえて(霊性ならぬ)「‘礼’性」などと名づけてもよかった。そんな過激な語彙でなくても、より形式性の意味合いが強い「感性」の方がまだましだったかもしれない。
いや、それはやはり「感情」でなければならなかった。なぜなら、この論考群の(表向きの)関心事は、王朝和歌、たとえば貫之歌を「私的言語」(夢の言語)として読み、たとえば定家詠やその歌論を「言語ゲーム」(言語が見る夢の現実化)の観点から読み解くことにあるのだから。それゆえ、まず「人のこころをたねとして、よろづのことのはとぞなれりける」の「人のこころ」を、とりわけ「心におもふことを見るものきくものにつけていひいだせるなり」の「(世の中にある人が)おもふこと」(「思ひ」や「感じ」)を、詠歌(私的言語の発出)の起点に据えておきたかった。
■承前、無内包の現実性をめぐって
いや、起点となるのは、「感情、現実、今、私」の四つ組ではなく、それらがそこに充填される「空虚な器」(〈 〉)の方でした。「器」などと言うと、何やら空間的な拡がり(質料性、内包性、事象内容性)を想起させるので、ここではこれを「無内包の現実性」と言いかえたいと思います。
無内包の現実性──「それが何であるかは決してわからないどころか、いやむしろ、それは何であるか[=リアリティ(実在性)]がない」純粋なアクチュアリティ(現実性)。この概念は、二次にわたる「永井(均)-入不二(基義)論争」(私の勝手な命名)を通じて精錬されてきたもので、その経緯をざっと一瞥すると、以下のようになります。
《第一次・永井-入不二論争》
○永井が『なぜ意識は実在しないのか』(2007年11月)でクリプキ-チャーマーズの二次元的意味論を踏まえ「第〇次内包」の概念を導入。
○入不二が「〈私〉とクオリア──マイナス内包・無内包・もう一つのゾンビ」(共著『〈私〉の哲学 を哲学する』所収、2010年10月)で、永井の「第〇次内包」の概念には「私秘性」(感覚の認知の自立)と「独在性・現実性」の二つの場面が同居していると批判。これを、①「(当初の意味での)第〇次内包」=クオリア、②「マイナス内包」=潜在的なクオリア(特定の概念[例:痛み]から自立・逸脱した不明瞭な「何らかの感じ」)、③「無内包」=〈私〉や〈今〉、の三つに腑分けした。
○永井が入不二の指摘を一部(無内包に関する部分)受け入れ、『改訂版 なぜ意識は実在しないのか』(2016年6月)を刊行。「[「私」の私秘性を作り出す]基になっているのはもちろん独在性であり、独在する私です。…これはもはや第〇次内包ではなく、無内包の現実性です」(170頁)。
──第一次論争を通じて明らかになった「三次元的」意味論の概要は次のとおり。(私的言語とは「無内包の現実性」を語る言語、いわば「無内包言語」であって、「第一次内包言語」(=パブリック言語)と関連づけられていない「第〇次内包言語」(永井前掲書改訂版131-132頁)のことではない。)
【無内包】
・独在的な〈私〉や〈今〉(=純粋経験)
【第〇次内包】
・私秘的な意識=クオリア/内的体験/「文脈独立的・内面孤立的な内包」(入不二前掲論文)
・「[第一次内包に対する]第一の逆襲[=感覚の認知の自立]をへて、何も酸っぱいものを食べていなくても、なぜだか酸っぱく感じられることが可能になった段階の酸っぱさの感覚そのもの」(永井前掲書改訂版12頁)
・「《つめたいもの》や《しめり》として現象する神(テオス)」(ロレンス『黙示録論』)
【第一次内包】
・公的言語において認知された「感じ」/外的文脈(ふるまい・表情)/「日常文脈的な内包」(入不二前掲論文)
・「酸っぱさの例でいえば、梅干しや夏みかんを食べたときに酸っぱそうな顔をするとき感じている‘とされるもの’」(永井前掲書改訂版12頁)
・「海や湖の透明度が高くて飲める液体、水らしきもの」(チャーマーズ『意識する心』)
【第二次内包】
・物理的な状態・事実/「科学探究的な内包」(入不二前掲論文)
・「[第一次内包に対する]第二の逆襲[=物理的状態の側からの逆襲、脳科学的・神経生理学的な探究]」によって判明する酸っぱさの本体、脳内のミクロな物理的状態(永井前掲書改訂版)
・「水はH2Oである」(チャーマーズ前掲書)
《第二次・永井-入不二論争》
○第4回現代哲学ラボ(2016年9月)で永井が「無内包の現実性とは」の演題で講演。「[カントがデカルトやアンセルムスの神の存在証明を批判して言ったことは、]要するに様相に関すること──可能的か現実的か必然的か──は事象内容的[=リアル]なことではない[=アクチュアリティ(現実性)に関わることである]、と単純に言い切ってもいいですね。それに対して私は、同じことが様相だけじゃなくて、‘人称’の場合にも、それから時制の場合にも言えるということを考えたわけですね。」(『現代哲学ラボ 第4号──永井均の無内包の現実性とは?』(Kindle版))
○同ラボで入不二が「現実の現実性と時間の動性──永井均『存在と時間──哲学探究1』へのコメント」を発表。〈私〉や〈今〉で語られる永井の「無内包の現実性」は「中心指向(収斂)的」で無内包性が不十分であると批判し、無人称・無時制・無様相の「全域指向(発散)的」な現実性を提唱した。「人称・時制・様相というのは対比のシステムですから、最小限の内包性あるいは内包への傾きが残っている」。
○入不二の批判、提唱に対する永井の応答。──中心性が残らないように「無内包の現実性」を考えることができるのは当然だが、あえてそうしないところに妙味がある。内包的にまったく同じものをもっている「他のもの」の可能性との対比において「これが現実だ」という話をしているから、対比性はどうしても残る。[*1]
○永井の応答に対する入不二の発言。──妙味を強調すると、同時にある種の「誤解」も引き寄せることになる。つまり「結局永井の言っている独在性はいつまでも私秘的な話をしている」というふうな。
──永井-入不二論争は、ほんとうはもっと豊かな内容と多岐にわたる論点を含んでいるのですが、(そして、永井均・入不二基義・森岡正博著『現実性を哲学する』(『現代哲学ラボ 第4号』の書籍版、本稿執筆時未刊行)、入不二基義著『現実性の問題』(2020年8月刊行)、永井均著『哲学探究3』(2020年9月から連載中)での議論を通じて論争の内容は深堀されるに違いないし、さらに第三次論争の勃発すら予見(期待)されるのだが)、私の関心事にそくして、以上のことから導かれる、「無内包の現実性と(そこから発し、形而下の世界に向かって分岐し頽落していく)四つの私的言語」の粗削りな目録を作製しておきたいと思います(私的言語の公的言語への受肉=頽落に際して設えられる文法的概念との対応関係を書きこんで)[*2]。
・〈 〉:無内包の現実性[*3] :無態[*4]・無様相・無時制・無人称
・〈感情〉をめぐる私的言語⇒マイナス内包:態 (voice)・法(mood)
・〈現実〉をめぐる私的言語⇒第一次内包:様相(modality)
・〈 今 〉をめぐる私的言語⇒第二次内包:相(aspect)・時制(tense)
・〈 私 〉をめぐる私的言語⇒第〇次内包:人称(person)
[*1]永井氏は『存在と時間──哲学探究1』では次のように述べている。
別の個所では、「無根拠な現実性として、なぜか存在してしまったこの私は、「現象界の中に生き残った物自体のお零れのようなもの」なので、この世界の内部に自らをちゃんと実在させるためには、自ら超越論的統覚となる(そういう自己分裂を起こす)ほかはない」(114頁)とも。
[*2]永井氏は「聖家族──ゾンビ一家の神学的構成」(『〈私〉の哲学 を哲学する』第Ⅳ部「あとから考えたこと」)で、哲学的ゾンビ三兄弟とその父母による家族構成(と、その権力闘争の様相)を描いている。すなわち、父:存在、母:時空(支配)、長男:言語/第一次内包、次男:物質/第二次内包、三男:意識/第〇次内包。この構成を、本文で示した「無内包の現実性と四つの私的言語」の図式と(強引に)重ね合わせると、次のようになる。
・〈 父 〉:〈存在〉⇔〈 〉
・〈 母 〉:〈時空〉⇔〈感情〉をめぐる私的言語
・〈長男〉:〈言語〉⇔〈現実〉をめぐる私的言語
・〈次男〉:〈物質〉⇔〈 今 〉をめぐる私的言語
・〈三男〉:〈意識〉⇔〈 私 〉をめぐる私的言語
この対応関係にどのような意義があるか(ないか)は、今後の検討課題だが、いま直ちにここで言えることがあるとすれば、第一に、「無内包の現実性」(純粋なアクチュアリティ)に「父:存在」が対応することから、はじめに存在ありき、という「驚き、タウマゼイン」(根源的な感情)が最初にあって、それが第一の私的言語につながっているのではないかということであり、第二に、時空が「感性」の形式である(カント)とすれば、その時空を支配する「母」の位置には〈感情〉をめぐる私的言語がふさわしいということである。
[*3]入不二氏は「無内包の現実」(『〈私〉の哲学 を哲学する』第Ⅳ部「あとから考えたこと」)で、次のように書いている。
ここで言われる「現実」は、純粋なアクチュアリティとしての「存在」(現実存在=実存)のことであり、第二の私的言語でいう「現実」とは意味合いが異なる。この点を誤解しないかぎりは、次のように理解することも、無害であろう。すなわち、入不二氏が言う「真空状態」は、かねて本稿で用いてきた「空虚な器」と響きあうと。
[*4]追補。入不二基義氏は『現実性の問題』第3章「事実性と様相の潰れと賭け」で、「無態」という概念を呈示ている。
■アヴィセンナのウジュード
ひきつづき、無内包の現実性をめぐる話題。永井均著『存在と時間──哲学探究1』の第15章から、「小説や映画の世界」と題された節の(ほぼ)全文を引用します。
また、同書第17章の註では、次のように書かれています。
最初の引用文中に「考えることができるだけで想像することはできない」云々とあるのは、おそらく、リアルな(想像可能な内容や中身、ストーリーをもった)実在物と区別される、アクチュアルな(完璧に外在的な出来事としての)現実存在を指し示していて、そして、そのような意味での「存在」、すなわち本質(実在界)の「外から端的に」付与される無内包の現実性が、アヴィセンナの「存在」(ウジュード)に近い、と永井氏は感じているわけです。
ここで、永井氏が無内包の現実性と同一視するアヴィセンナの「ウジュード」について、井筒俊彦著『イスラーム思想史』の記述を参照すると、そこには、アヴィセンナが、「存在」(existentia)と「本質」(essentia)との間に実質的に区別があるか否か、という「大問題」を西欧のスコラ哲学に投げかけた、と書かれていました。
いわく、アヴィセンナによると、我々が経験する事物は存在論的に二つの要素から成り立っている。それらが「現にそこにある」(Xがある)ことと、「何々としてある」(Xはaである)ことの二つである。このうち前者を「存在」(ウジュード)、後者を「本質」(マーヒーヤ、それは何であるかということ=何性)と呼ぶ。
このような「存在」と「本質」がどういう仕方で互いに結び付いているのか。この問いに対してアヴィセンナは、存在は本質の「偶有性」であると主張した。本質(例:馬性)はそれ自体で自分の存在を作り出すことはできず、存在という性質を他から得た時にはじめて「ある」もの(存在する馬)として実現する。
この存在の偶有性の概念に関連して、アヴィセンナが呈示したもう一つの重要な概念が「可能的存在」と「必然的存在」の区分である。前者は「存在することはできるが、必ずしも存在しなければならないというのではない」もの。これに対して後者は「もしそれが存在していないと仮定すればそのまま矛盾に陥らざるをえないような存在者」である。
アヴィセンナの言う「必然的存在」すなわち「存在が本質そのものであるもの」こそ、永井-入不二論争を通じて炙りだされた「無内包の現実性」にほかなりません。
■アヴィセンナの幽霊、三たび
ここで私は、かの、井筒豊子和歌論三部作(のうち「意識フィールドとしての和歌」)で取りあげられた、アヴィセンナの「空中浮遊人間」を想起しています。定家の「詠みつつある心」(尼ヶ崎彬)や世阿弥の「無心」に通じる「アヴィセンナの幽霊」(山内志朗)。この話題については、これまでに二度、(第28章と第39章で)言及しました。(精確に記録しておくと、第40章や第56章でもふれた。とくに第56章の議論は、ここで述べようとしていることと密接な関係をもつ。)
永井氏が言及している「ウジュード」が、この「アヴィセンナの幽霊」とどのような関係を切り結ぶか、同一のものとして扱ってよいかどうか、私には判断できません[*1]。ただ、「無内包の現実性」と(ほぼ)同一視されたアヴィセンナのウジュードを、(さらに)アヴィセンナの空中人間=幽霊と関連づけることによって、私的言語を語る立場、視点、主体といった事柄をめぐる考察をすすめるうえで、ずいぶん見晴らしがきくパースペクティヴを獲得することができるのではないかとは思います。
すなわち、(かつて、第30章で引用した)井筒豊子の「意識フィールドとしての和歌」の最後の文章[*2]中の、意識フィールド=言語フィールド=認識フィールドという「三重の磁場」を小説や映画を含む「本質」(マーヒーヤ)の世界として見るポジションに、「アヴィセンナの幽霊」すなわち「存在」(ウジュード)を据えることによって。そして、無内包の現実性(アクチュアリティ)の側から実在性(リアリティ)の世界を俯瞰する幽霊の視点を、かの夢のパースペクティヴをめぐる議論とからめて論じることによって[*3]。
[*1]アヴィセンナの「ウジュード」が、井筒俊彦が『意識と本質』で「マーヒーヤ」と対比させた「フウィーヤ」と同一のものなのかどうかも、私には判断できない。ちなみに山内志朗氏は「アヴィセンナの存在論と西洋中世」(『東洋学術研究』180号/2018年)で、次のように述べている。
[*2]井筒豊子著『井筒俊彦の学問遍路──同行二人半』から。
[*3]細川亮一氏は「恐れと驚き──死と再への問い」(市川浩他編『死──現代哲学の冒険1』所収)で、次のように論じている。いわく、一人称としての死が「私は死ぬだろう」という未来形でしか語りえないことは、私の死が今だ来ないことであるだけではなく、「私が存在しない」という現在を私が思惟しえないことを意味している。
世界内に実在しない虚焦点として指し示される〈私〉の視点、それは、アヴィセンナの幽霊の眼差しであり、もっとわかりやすく言えば末期の目、あるいは死者のパースペクティヴである。(私的言語は詩的言語ならぬ死的言語=死者の語りに発する。)
なお、細川氏の議論は、古荘真敬「時の過ぎ去り──人称的世界の時間的構造の探究のための準備的考察」(『山口大学哲学研究』13巻/2006年)で引用されていた。[https://researchmap.jp/read0196292/published_papers/4983696]
(63章に続く)
★プロフィール★
中原紀生(なかはら・のりお)1950年代生まれ。兵庫県在住。千年も昔に書かれた和歌の意味が理解できるのはすごいことだ。でも、本当に「理解」できているのか。そこに「意味」などあるのか。そもそも言葉を使って何かを伝達することそのものが不思議な現象だと思う。
Web評論誌「コーラ」44号(2021.08.15)
<哥とクオリア/ペルソナと哥>第62章 純粋経験/私的言語/アレゴリー(その3)
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2021 Rights Reserved.
|
| 表紙(目次)へ |
