|
|
|
Web昡榑帍乽僐乕儔乿 |
|
仭憂姧偺帿 仭杮帍偺昞巻乮栚師乯傊 仭杮帍偺僶僢僋僫儞僶乕 仭撉幰偺暸乛偛堄尒丒姶憐 仭搳峞婯掕 仭娭學幰偺Web僒僀僩 仭僾儔僀僶僔乕億儕僔乕 |
|
亙杮帍偺娭楢儁乕僕亜 |
|
仭乽僇儖僠儍乕丒儗償儏乕乿偺僶僢僋僫儞僶乕 仭昡榑巻乽la Vue乿偺憤栚師 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
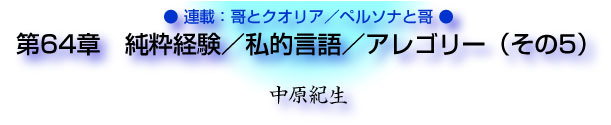
|
|
乮杮暥拞偺壓慄偼儕儞僋傪帵偟偰偄傑偡丅傑偨丄僉乕儃乕僪丗[Crt +]偺憖嶌偱儁乕僕傪奼戝偟偰偍撉傒偄偨偩偗傑偡丅乯
丂
仭傾儗僑儕乕偺乽斶偟傒乿偑悽奅傪尰徾偝偣傞
丂
丂堷偒偮偯偒丄柍撪曪偺尰幚惈乮偺尒偊側偄嵀愓丄偍楇傟丄桯楈偺偛偲偒傕偺乯傪岅傞尵岅偺戞擇椶宆偐傜戞巐椶宆傑偱丄偡側傢偪乹尰幚乺傗乹崱乺傗乹巹乺傪傔偖傞巹揑尵岅偵偮偄偰峫嶡偡傞偼偙傃偲側傝傑偟偨丅偑丄偟偐偟丄乮榑偠傞傋偒傾僀僨傾偑偄傑偩崀椪偟側偄丄偲偄偆偐丄偦傕偦傕巹揑尵岅偵偮偄偰岅傞傋偒撪幚側偳偁傝偊側偄偺偱偼側偄偐丄偲巚偆婥帩偪偑曞傞偺偱乯丄堦婥偵愭偵恑傑偢丄偡偙偟塈夞楬傪偨偳偭偰傒偨偄偲巚偄傑偡丅
丂
丂悽奅偺奐钃乮乹丂乺佀乹俤乺乯傪岅傞巹揑尵岅偵巚偄傪傔偖傜偣偰偄偔偆偪丄巹偺擼撪偱丄傂偲偮偺壖愢偑偦偺椫妔傪偁偒傜偐偵偟偰偒傑偟偨丅偦傟傪堦尵偱妵傞側傜丄巹揑尵岅偲偼傾儗僑儕乕偱偁傞丄偲側傞偱偟傚偆偐丅
丂壗傕昞尰偟側偄乽帊揑尵岅乿偲丄偦傟偲偼傑偨堘偭偨堄枴偱丄壗帠傪傕尵偄昞傢偝側偄乽岞揑尵岅乿丅偙傟傜偺椞堟偺拞娫偵偁偭偰丄乮偁傞偄偼丄儗儞儅幉佮傾僋僠儏傾儕僥傿偺幉偲儘僑僗幉佮儕傾儕僥傿偺幉傪寢崌偡傞傾乕儔儎幆佮僐乕儔乮攇偵梙傟傞奀乯偺扅拞偵偍偄偰乯丄巹揑尵岅偼椉幰傪攠夘偡傞丅偦偺偼偨傜偒丄偡側傢偪帊揑尵岅偐傜岞揑尵岅傪惗惉偟丄傕偟偔偼岞揑尵岅傪帊揑尵岅傊偲慿峴偝偣傞乮偁傞偄偼丄帪娫惈偺夘擖偵傛偭偰擛棃憼丒弮悎儗儞儅揑抦惈傪暘夝偟丄傕偟偔偼帪娫偺嬻娫壔偵傛偭偰壺尩揑丒弮悎儗儞儅揑抦惈傊偲慿峴偝偣傞乯攠夘嶌梡偺偙偲傪丄傾儗僑儕乕偺偼偨傜偒偵弨偊偰峫偊傞偙偲偑偱偒傞偺偱偼側偄偐丄偲偄偆偙偲偱偡丅
丂嶳岥桾擵巵偼丄亀儀儞儎儈儞偺傾儗僑儕乕揑巚峫亁偺戞嘨復偱師偺傛偆偵榑偠偰偄傑偡丅偄傢偔丄儀儞儎儈儞偼乽傾儗僑儕乕偑偦偺傛偆側傕偺偲偟偰怳晳偍偆偲偟偨暥帤乿偺偙偲傪乽傾儗僑儕乕揑暥帤憸乮Schriftbild乯乿偲屇傫偩丅偦傟偼傾儖僼傽儀僢僩側偳偺昞壒暥帤偱偼側偔丄徾宍暥帤偺傛偆偵偦傟偧傟偺暥帤偑抐曅偲偟偰偡偱偵乽堄枴乿傪傕偭偨昞堄暥帤偱偁傞丅
丂儀儞儎儈儞偵偁偭偰壒惡乮Laut乯偲偟偰岅傜傟偨乽偙偲偽乮Wort乯乿偲乽暥帤乮Schrift乯乿偲偼椉嬌揑側埵抲傪愯傔偰偄傞丅乽偙偲偽乿偲乽暥帤乿偺娭學偼丄偦偺弶婜尵岅榑偵偍偗傞乽僷儔僟僀僗偺尵岅乿乮柤徧尵岅丄捈愙惈偺尵岅乯偲丄慞埆傪傔偖傞抦偵傛偭偰偦偙偐傜懧棊偟偨尵岅乮揱払尵岅偡側傢偪壗偐傪堄枴偡傞尵岅丄捈愙惈傪幐偭偨尵岅乯偲偺娭學傪堷偒宲偄偱偄傞偺偱偁傞丅乽傾儗僑儕乕偼乽堄枴乿偲乽帠暔乿偵寢傃偮偄偰偄傞偙偲偵傛偭偰丄偁偔傑偱傕旐憿暔偺嵾偺楢娭偺偆偪偵偲傜偊傜傟偰偄傞丅乿乮176-178暸乯
丂偙偙偱岅傜傟傞傾儗僑儕乕偺帠暔惈丄偁傞偄偼乽乮堄枴傊偺乯懧棊乿偲乽乮懳徾傊岦偐偆乯峔惉揑巙岦惈乿偲偵偁偄傢偨傞偦偺椉媊惈乮傕偟偔偼丄庴摦懺偱傕擻摦懺偱傕側偄拞摦懺揑側偁傝條乯偼丄慜復偱奣娤偟偨丄帊揑尵岅偲岞揑尵岅偲偺拞娫偵偁偭偰椉幰傪椉媊揑偵攠夘偡傞丄乽暔帺懱偺偍楇傟乿偲偟偰偺巹揑尵岅偺摿幙偲摨宆側偺偱偼側偄偐丄偦偟偰乹姶忣乺傪傔偖傞巹揑尵岅偙偦丄偦偆偟偨傾儗僑儕乕揑惈奿傪傕偭偲傕怓擹偔懷傃偰偄偨偺偱偼側偐偭偨偺偐丅巹偼丄偦傫側傆偆偵峫偊偰偄傑偡丅
丂
仭攋夡偲暅妶劅儀儞儎儈儞偺傾儗僑儕乕榑
丂
丂巹揑尵岅偼丄傾儗僑儕乕偱偁傞丅偁傞偄偼丄彮側偔偲傕巹揑尵岅偺峔憿偲婡擻偼丄傾儗僑儕乕偲摨宆偱偁傞丅偙偺偙偲傪妋擣偡傞偨傔丄傑偢丄摴庾懽嶰挊亀儀儞儎儈儞夝撉亁偺婰弎乮戞擇復乽閼閻偺偵偨偵偨徫偄劅劅攑毿偐傜偺峔抸偲偟偰偺傾儗僑儕乕乿乯傪傕偲偵丄儀儞儎儈儞偺傾儗僑儕乕榑傪奣娤偟傑偡丅
丂
侾丄傾儗僑儕乕偺擇偮偺曽岦惈
仜摴庾巵偼丄傾儗僑儕乕偺乽堦偮偺嬌尷宍懺乿乮64暸乯偲偟偰丄亀抦妎偺庺敍亁乮搉曈揘晇乯偑徯夘偡傞弶榁偺彈惈姵幰偺乽尵岅怴嶌乿傪椺偵嫇偘傞丅劅劅悽奅杤棊懱尡偺壥偰偵丄曵夡偟偨悽奅偺尰幚傪杽傔崌傢偦偆偲偱傕偡傞偐偺傛偆偵怴偨側悽奅拋彉傪愗傝奐偔偨傔偺巜昗偲偟偰弌尰偡傞撲偺僔僯僼傿傾儞丄僂僠僇僞丄僸僩僇僞丄僆儌僇僎僪僐儘丄僆僩僠丄僆僞僇儔丄摍乆丅
丂偙偙偵傾儗僑儕乕奣擮偺擇偮偺曽岦惈偑帵偝傟偰偄傞丅戞堦丄婰崋悽奅偺攋夡揑丄潣棎揑側曄梕丅戞擇丄僐乕僪側偒尵岅幚慔偵傛傞怴偟偄悽奅偺尰弌丅
丂
俀丏婰崋偵斀棎偡傞暔幙劅傾儗僑儕乕乮暥帤憸乯偲壒妝乮壒惡尵岅乯
仜儀儞儎儈儞偺亀僪僀僣斶寑偺崻尮亁偺戞堦偺栚揑偼丄尵梩偺暔幙惈乮擏懱惈乯丄偲傝傢偗暥帤偲偟偰偺暔幙惈傪嵺棫偨偣傞偙偲偵偁偭偨丅
仜偟偐偟丄尵梩偺暔幙惈偼暥帤憸偩偗偵恠偒傞傢偗偱偼側偄丅尵岅壒惡傕傑偨丄暥帤憸偵暲傫偱丄暔幙偲偟偰偺尵梩偺傕偆傂偲偮偺廳梫側梫慺偱偁傞丅
仜儀儞儎儈儞偼亀崻尮亁偵丄壒惡尵岅偼乽旐憿暔偺僄僋僗僞僔乕乿乮壒妝乯偱偁傝丄暥帤偼乽旐憿暔偺廂廤乿乮傾儗僑儕乕乯偱偁傞偲彂偄偨丅
俁丏閼閻偐傜偺傾儗僑儕乕揑嵞峔抸劅暋惢媄弍偵傛傞傾僂儔側偒峔抸乮暅妶乯
仜傾儗僑儕乕乮暥帤憸乯偼丄乽堄枴偺敳偗棊偪偨偁偲偺尵岅偺巆梋偱偁傝丄婰崋榑揑丄揱払揑側堄枴偵懳偡傞巙岦偑崥慠偲徚幐偟偨偁偲偺奫崪偲偟偰偺尵梩乿偱偁傞乮76-77暸乯丅
仜儀儞儎儈儞偼乽幨恀偺幨恀偨傞備偊傫乿傪乽堄幆偺楢懕惈偐傜敳偗棊偪偨柍堄幆乿偵尒偰偄傞丅
仜儀儞儎儈儞偼丄懳徾偐傜傾僂儔傪攳扗偡傞幨恀偺婡擻偼乽朶業乿偱偁傝丄幨恀偺傕偭偲傕杮幙揑側峔惉梫慺偼乽愢柧暥乿偱偼側偄偐偲彂偄偰偄傞乮亀幨恀彫巎亁乯丅
仜偟偐偟丄偙偆偟偨傾儗僑儕乕揑嵞峔抸丄閼閻丒攑毿偐傜偺傾僂儔側偒峔抸乮暅妶乯偲偼丄偨傫偵攑毿偺側偐偵怴偨側攑毿傪抸偒忋偘傞偩偗偺乽婥惏傜偟乿偵偡偓側偄偺偱偼側偄偐丅
仜儀儞儎儈儞偼丄傾儗僑儕乕偵偍偗傞乽媡揮乿偺恾幃傪乽恄旈揑嬒峵乵億儞僥儔僔僆儞丒儈僗僥儕僆乕僒乶乿乮婋側偘偵拞嬻傪晜梀偟偰偄傞僶儘僢僋挙崗偺揤巊偨偪偺巔傪宍梕偡傞偨傔僇乕儖丒儃儕儞僗僉乕偑巊梡偟偨梡岅乯傪庁梡偟偰愢柧偟偰偄傞丅
乵仏乶摴庾巵偼偮偯偗偰丄師偺傛偆偵彂偄偰偄傞丅
丂側偍丄摴庾巵偼乽乽傾儗僑儕乕亖暥妛乿榑劅劅儀儞儎儈儞偵偍偗傞傾儗僑儕乕偺幩掱乿乮亀僪僀僣暥泏尋媶亁戞35崋乯偱丄儕僢僞乕偺乽偒傢傔偰摿堎側尵岅榑乿偲儀儞儎儈儞偺傾儗僑儕乕榑偲偺偐偐傢傝偵偮偄偰徻嵶偵榑偠偰偄傞丅
丂
仭憡梕傟側偄擇偮偺椡偺嫟懚劅億乕儖丒僪丒儅儞偺傾儗僑儕乕榑
丂
丂儀儞儎儈儞偺傾儗僑儕乕榑偵娭偟偰擇揰丄曗懌偟偰偍偒傑偡丅偄偢傟傕傾儗僑儕乕偵偍偗傞乽帪娫惈偺嬻娫壔乿偵娭偡傞傕偺偱丄弌揟偼丄嶳岥桾擵挊亀儀儞儎儈儞偺傾儗僑儕乕揑巚峫亁丅
丂
乑儀儞儎儈儞偑亀僷儕劅劅廫嬨悽婭偺庱搒亁乮嘪乽儃乕僪儗乕儖偁傞偄偼僷儕偺奨楬乿乯偱丄乽擇媊惈偲偼曎徹朄偑僀儊乕僕偲偟偰尰傢傟偨傕偺偱偁傝丄惷巭忬懺偵偍偗傞曎徹朄偺掕懃偱偁傞丅偙偺惷巭忬懺偑儐乕僩僺傾偱偁傝丄曎徹朄揑僀儊乕僕偼偟偨偑偭偰柌偺僀儊乕僕偲偄偆偙偲偵側傞丅偦偺傛偆側僀儊乕僕傪側偟偰偄傞偺偑偨偲偊偽彜昳偦偺傕偺丄偮傑傝暔恄偲偟偰偺彜昳偱偁傝丅傑偨偨偲偊偽壠壆偱傕偁傝奨楬偱傕偁傞僷僒乕僕儏丄傑偨偨偲偊偽攧傝巕偲彜昳傪堦恎偵寭偹傞彥晈偱偁傞丅乿乮偪偔傑妛寍暥屔亀儀儞儎儈儞丒僐儗僋僔儑儞侾亁348暸乯偲彂偄偰偄傞偺傪摜傑偊偰丅
乑傑偨亀僪僀僣斶寑偺崻尮亁乮戞擇晹乽傾儗僑儕乕偲僶儘僢僋斶寑乿乯偵丄乽僶儘僢僋斶寑偲偲傕偵楌巎偑晳戜偺側偐偵擖傝偙傫偱偔傞偲偒丄偦傟偼暥帤偲偟偰擖傝偙傓丅帺慠偺婄杄偵丄偼偐側偝傪堄枴偡傞徾宍暥帤偱丄乹楌巎乺偲彂偐傟偰偁傞偺偩丅僶儘僢僋斶寑偵傛偭偰晳戜偺忋偵掓帵偝傟傞帺慠巎偺傾儗僑儕乕揑憡杄偑幚嵺偵栚偺慜偵尰傢傟傞偺偼丄攑毿偲偟偰丄偱偁傞丅乮棯乯帠暔偺悽奅偵偍偄偰攑毿偱偁傞傕偺丄偦傟偑丄巚峫偺悽奅偵偍偗傞傾儗僑儕乕偵傎偐側傜側偄丅乿乮偪偔傑妛寍暥屔亀僪僀僣斶寑偺崻尮壓亁50-51暸乯偲偁傞偺傪庴偗偰丅
丂嶌嬈傪偮偯偗傑偡丅
丂搚揷抦懃巵偼亀億乕儖丒僪丒儅儞劅劅尵岅偺壜擻惈丄椣棟偺壜擻惈亁偺乽偁偲偑偒乿偵丄乽撉傓偙偲偲偼昄桧丄嬯擸偲娊婌偺嫹娫偱塱媣偵拡捿傝偵偝傟傞偙偲丄傾儗僑儕僇儖側嫬堟偱婑傞曈側偔昚偄懕偗傞偙偲側偺偐傕偟傟側偄丅偙傟傕傑偨僪丒儅儞偺巇帠偐傜妛傫偩廳梫側嫵孭偺堦偮偱偁傞丅尵梩偼忢偵傒偢偐傜偲暿偺傕偺傪嵎偟帵偡丅偦傟偼尵梩偺廻柦揑側峔憿偱偁傝丄扤傕偦偙偐傜摝傟傜傟側偄丅乿乮190暸乯偲彂偄偰偄傑偡丅
丂傾儗僑儕僇儖側嫬堟偲偼壗偐丅偦偟偰丄尵梩偺廻柦揑側峔憿偲偼丅劅劅埲壓丄摨彂戞嘨復乽傾儗僑儕乕偺彅憡乿偍傛傃戞嘪晹乽暥帤偺暔幙惈乿偵傕偲偯偒丄億乕儖丒僪丒儅儞偺傾儗僑儕乕榑傪奣娤偟傑偡丅
丂
侾丏椉媊惈丄撪揑暘楐劅尵岅亖僥僋僗僩偺傾儗僑儕僇儖側婡惂
仜乽傾儗僑儕乕乿偼僊儕僔儍岅偺乽allos(other)乿偲乽agoreuein(to speak)乿偐傜偺攈惗岅丅偡側傢偪乽暿偺傕偺乮allos乯偵偮偄偰岅傞乮agoreuein乯乿偲偄偆尵岅偺摥偒傪懱尰偡傞奣擮偱偁傞乮54暸乯丅
仜搚揷巵偼乽傾儗僑儕乕乿傪儂乕僜乕儞偺抁曇彫愢偺彈庡恖岞偺妟偵崗報偝傟偨乽曣斄乮birth-mark乯乿偵歡偊偰偄傞丅
俀丏暔幙惈偲尰徾惈劅暥帤亖尵岅偺廻柦揑側峔憿
仜億乕儖丒僪丒儅儞偼丄暥帤偺乽暔幙惈乮materiality乯乿偺奣擮丄偡側傢偪乽堄枴偵夞廂偝傟側偄暥帤偺柍婡幙側杮幙乿乮135暸乯傪掓帵偟丄偙傟傪暥帤偺乽尰徾惈乿偺奣擮偲懳抲偝偣偨丅
仜億乕儖丒僪丒儅儞偼丄乽暔幙揑側帇慄乿傪乽撉傓乿偲偄偆峴堊偺応偵摫擖偟乽旕尰徾揑側撉傒乿傪丄偡側傢偪乽僷儔乚僼傿僊儏儔儖側乮斾歡揑側傕偺偵斀偡傞乯師尦乿偵拞怱傪抲偔撉傒曽傪懪偪弌偟偨乮133-4暸乯丅
仭柌乮悈乯偺拞偺撉傔側偄暥帤
丂
丂傾儗僑儕乕偺奣擮偼掙偑怺偔丄捠傝偡偑傝偵堦曀偟丄寉乆偵壗帠偐傪岅傞偺偼恎偺掱抦傜偢偺嬈偩偲巚偄傑偡偑丄偙偙偱丄偙傟傑偱廂廤偟偰偒偨媍榑傪丄巹揑尵岅偵偁偰偼傔偰峫偊偨偄偲巚偄傑偡丅
丂
丂乧乧巹揑尵岅偲偼丄嘆婰崋悽奅乮岞揑尵岅偺悽奅乯偺攋夡偲丄嘇僐乕僪側偒尵岅幚慔偵傛傞偦偺嵞峔抸乮傾僂儔側偒暅妶乯偲偄偆丄恀媡偺儀僋僩儖傪傕偮擇偮偺椡偑摨帪揑偵壱摥偡傞憰抲偱偁傞丅
丂偁傞偄偼丄乮拞搰撝偑乽暥帤壭乿偱丄乽堦偮偺暥帤傪挿偔尒媗傔偰偄傞拞偵丄偄偮偟偐偦偺暥帤偑夝懱偟偰丄堄枴偺柍偄堦偮堦偮偺慄偺岎嶖偲偟偐尒偊側偔側偭偰棃傞丅扨側傞慄偺廤傝偑丄側偤丄偦偆偄偆壒偲偦偆偄偆堄枴偲傪桳偮偙偲偑弌棃傞偺偐丄偳偆偟偰傕夝傜側偔側偭偰棃傞丅乿偲彂偄偨丄偦偆偟偨堄枴偱偺丄暥帤偺乯乽暔幙惈乿偲丄偙傟偲偼椉棫晄壜擻側乽尰徾惈乿乮暔幙揑側傕偺偺湏堄揑側夞廂偵傛傞乽暔岅乿偺尰弌傪桿摫偡傞奣擮乯偲偑憡屳埶懚偺娭學傪愗傝寢傇尵岅幚慔偱偁傞丅
丂偦偙偱偼丄嘆偲嘇丄暔幙惈偲尰徾惈偑嫟嵼偡傞曎徹朄揑側惷巭忬懺乮恄旈揑嬒峵乯偑丄偡側傢偪乽帪娫惈乮暔岅壔丄堄枴嶌梡乯偺嬻娫壔乮宍徾壔丄嬅屌亖寢徎壔乯乿偑幚尰偟偰偄傞丅乮偦傟偼丄傎偲傫偳拞戲怴堦挊亀儗儞儅妛亁偑榑偠偨乽壺尩揑嬻娫乿偦偺傕偺偩両乯
丂偟偐偟丄偦傟傜偼偄偢傟傕丄偡偱偵惉棫偟偨婰崋悽奅偺拞偱偺榖丄傕偟偔偼岞揑尵岅偑惉棫偟偨屻偺弌棃帠偱偁偭偰丄杮摉偺偙偲傪尵偊偽丄攋夡偝傟嵞峔抸偝傟傞摉偺婰崋悽奅偦偺傕偺偑丄僐乕僪側偒尵岅幚慔乮僜僔儏乕儖偑尋媶偟偨堎尵傗傾僫僌儔儉丄嫸恖偺尵岅怴嶌丄儅儔儖儊揑側旕恖徧揑尵岅幚慔丄摍乆乯傪捠偠偰惗惉偟偨偺偱偁傞丅乮傾僋僠儏傾儖側傕偺偺奅堟亖帊揑尵岅偵崻嵎偟偨巹揑尵岅偐傜丄儕傾儖側帠徾悽奅傪峔抸偡傞岞揑尵岅偑惗惉偡傞両乯乧乧
丂
丂暥帤憸偲偟偰偺傾儗僑儕乕偲尵岅壒惡乮惡偲偟偰偺傾儗僑儕乕丠乯偲偺娭學偑婥偵側傞偲偙傠偱偡偑丄偙偙偱偼丄乽傾儗僑儕乕亖暥帤憸乿偲偄偆儀儞儎儈儞揑娤揰偵偟傏偭偰媍榑傪恑傔傑偡丅
丂
丂偙偙偱丄堦杮偺曗彆慄傪堷偒傑偡丅
丂愇柎楃摴巕偵乽柌偺拞偺暥帤乿偲偄偆丄抁偄偗傟偳怺偔擹偄報徾傪扻偊偨暥復偑偁傝傑偡丅埲慜丄戞係復偱尵媦偟偨乮惛妋偵偼丄偦偺偲偒尵媦偟偨乽偐側偲惛恄暘愅乿偲偄偆榑峫偑愇柎楃摴巕偺暥復傪堷梡偟偰偄偨乯傕偺偱偡偑丄偙偙偱丄偁傜偨傔偰偦偺堦愡傪敳悎偟傑偡丅
丂昅幰偼偮偯偗偰丄柌偺拞偺暥帤偺僀儊乕僕傪媮傔丄屻廍堚廤愗偺揱尮弐棅昅偐傜杒惸偺杸奟偺戱杮傊丂偦偟偰幝揷搷峠乮亀偄傠偼巐廫敧暥帤亁乯偺壖柤暥帤傊偲丄乽傂偲偝傑偺昅偺愓乿傪偨偢偹偨宱堒傪捲傝丄嵟屻偵丄乽彂壠偱側偄恖娫偼丄尪憐偺暥帤偵偙偆偟偰埀偆偙偲偑偱偒傞丅偳傫側傑傏傠偟偺懕偒傪尒傟傞偙偲偐偲丄傗偭傁傝尰悽偵嫃傝偯傜偄傢偨偟偼丄暥帤偺拞偐傜丄偐偺愳掙傊崀傝偰備偒偮偮偁傞丅乿偲寢傫偱偄傑偡丅
丂偁偺悽乮惗傑傟偸慜乯偐傜偙偺悽傊丄愳掙乮愳彴乯偐傜愳柺傊偲悈拞傪晜忋偟偰偔傞夝撉偱偒側偄暥帤乵仏乶丄堦搙傕宍偵側偭偰偔傟側偄暥帤丄惗傑傟傞偙偲偑弌棃側偄暥帤丄彂偐傟偞傞乮彂偗側偄乯暥帤丄擥傟偨敮偺傛偆偵丄榓巻乮婎掙嵽乯偲嫟偵梟偗偰備偔栄昅偱彂偐傟偨壖柤暥帤丄戣柤偺側偄壒妝乮嫊柍揑側柍尷傪偁傜傢偟偨丄敀偄惷偐側墛傪敽偭偰偄傞嬋乯偲丄偙偲偽埲慜偺僀儊乕僕傪傑偲傢偣偨暥帤丅乮愇柎楃摴巕偼乽偙偲偽埲慜乿偲戣偝傟偨僄僢僙僀偱傕丄傕偺怱偮偔崰偵乽柍岅偺悽奅乿傪奯娫尒偨嵟弶偺婰壇乮墦偄宨怓乯偲偟偰丄乽愒偄銧埦偺壴堦椫傪帩偭偰丄敀偄徾偲嫟偵椃傪偡傞帺暘偺巔乿傪岅偭偰偄傞乮摨彂450-451暸乯丅乯
丂偙偙偵昤偐傟偨乽柌偺拞偺暥帤乿偙偦丄乽偦傟偼壗偱偁傞偐乿乮儕傾儕僥傿乯偺鏱偐傜夝偒曻偨傟丄弮悎偵乽偦傟偑嵼傞偙偲乿乮傾僋僠儏傾儕僥傿乯偵崻偞偟偨巹揑尵岅偺丄杮慠偺巔傪偐偨偳偭偨傕偺偱偼側偄偐丄乮偦傟偼傑偨乽堄枴乿偺鏱偐傜扙偟偮偮偁傞暥帤憸偲偟偰偺丄偦偟偰戣柤偺側偄壒妝乮巜帵偺椡傪幐偄偮偮偁傞惡丠乯偑偦偙偐傜桸偒偩偡偲偙傠偺傾儗僑儕乕偺杮慠偺巔偦偺傕偺偱偼側偄偐乯丄巹偼丄偦偺傛偆偵峫偊偰偄傑偡丅
丂
乵仏乶栴岥峗巕丒怴媨堦惉偺乽偐側偲惛恄暘愅乿偵傛傟偽丄撉傔側偄暥帤偼乽屄暿乿偱偁傞丅柌偺拞偺暥帤偼乽晛曊乿乮亖堄枴乯傪嫅愨偟偰偄傞丅壒偲堄枴偵偮側偑偭偰偄偨暥帤偼丄屄暿幰偵傛偭偰墴偟偮傇偝傟丄偔偢偝傟丄彂慄偲壔偡丅
丂戝抇側偔偢偟偵傛偭偰晛曊偲偺娭學偑抐偪愗傜傟偰傕丄嵟廔揑偵偐側偼彂慄偵偄偒偮偔偙偲偑側偔丄娍帤偵懳偟偰屄暿偺埵抲傪偲偭偰偄偨偐側偑丄擔杮岅偺拞偱崱搙偼晛曊偺埵抲傪偲傞傛偆偵側傞丅偦偺寢壥丄彂偺悽奅偱丄偐側偵傛偭偰傆偨偨傃屄暿懚嵼傪帵偡偨傔偺夝懱偑丄偡側傢偪楢柸傗嶶傜偟彂偒丄乮榓壧偺乯堄枴偲柍娭學偺嬫愗傝偲偄偭偨媄朄偑梡偄傜傟傞傛偆偵側偭偰偄偭偨乮151-154暸乯丅
丂劅劅乽偐側偲惛恄暘愅乿偺偦偺屻偺媍榑偼丄乮彂偼壒妝偲摨條偵乽帺桼側傞惗柦偺儕僘儉乿偺敪尰偱偁傞偲偟偨惣揷婔懡榊偺乽彂偺旤乿偲傕偳傕乯丄屻偺乽傗傑偲偙偲偽乿傪傔偖傞峫嶡偵偮側偑偭偰偄偔丅
丂
仭巹揑尵岅偺惷懺偲摦懺
丂
丂巹揑尵岅乮佮傾儗僑儕乕乯偼柌偺拞偺暥帤偱偁傝丄悈掙偲悈柺偺拞娫椞堟傪墲偒偮傕偳傝偮偟側偑傜丄偦偺椉抂傪攠夘偡傞丅曗彆慄乮愇柎楃摴巕乽柌偺拞偺暥帤乿乯偐傜尒偊偰偒偨偙傟傜偺偙偲偺偆偪丄偙偙偱偼丄偦偺慜抜偺榑揰偵偮偄偰丄偡偙偟徻偟偔尒偰偍偒偨偄偲巚偄傑偡丅偦偺嵺丄巹揑尵岅偺乽偼偨傜偒乿偺奣宍傪偮偐傓偨傔丄娧擵尰徾妛偺俙憌丒戞擇憡偱榑偠偨帠暱傪丄偡側傢偪丄柌悽奅偵偍偗傞僷乕僗儁僋僥傿僽偺懱尡峔憿偲壱摥尨棟傪傔偖傞乽棟榑乮巹壠斉乯乿傪墖梡偟傑偡乵仏乶丅
丂
丂傑偢丄媍榑偺慜採偲偟偰丄乮戞52復偱峫嶡偟偨乯柌偺僷乕僗儁僋僥傿償偺惷懺丄偡側傢偪昞憌偐傜挻怺憌偵帄傞巐偮偺師尦偺僷乕僗儁僋僥傿償乮俹侾乣俹係乯傪傔偖傞媍榑偺乽夵掶斉乿傪宖偘傑偡丅
丂夵掶撪梕偺戞堦偼丄乽怺憌偺俹侾乿偵懳偡傞乽昞憌偺俹侾'乿丄乽昞憌偺俹俀乿偵懳偡傞乽怺憌偺俹俀'乿傪柧妋偵乮俹侾丄俹俀偲摨奿偺傕偺偲偟偰乯埵抲偯偗偨偙偲丄戞擇偼丄乮戞28復偱庢傝偁偘偨乯堜摏朙巕偺堄幆亖怱偺巐奒掤榑乽怱抧乛嫬乛堄幆僼傿乕儖僪乛尵岅僼傿乕儖僪乿傪孞傝崬傫偩偙偲偱偡丅
乮側偍丄夵掶斉拞偺乽乮抦妎揑丄姶妎揑乯挱朷乿偲乽憡杄乿偼丄偄偢傟傕栰栴栁庽挊亀怱偲偄偆擄栤劅劅嬻娫丒恎懱丒堄枴亁偵嫆傞丅栰栴巵偼偙偺彂暔偱丄乽挱朷榑乿傪乽抦妎揑挱朷乿乮嬻娫偲偄偆梫場偐傜懆偊傜傟偨悽奅偺尰傢傟乯偲乽姶妎揑挱朷乿乮恎懱偲偄偆梫場偐傜懆偊傜傟偨悽奅偺尰傢傟乯偺擇偮偺僷乕僩偵暘偗偰榑偠丄師偄偱丄挱朷榑偱偼懆偊偒傟側偄抦妎偺朙偐側懁柺傪乽憡杄乿乮堄枴偲偄偆梫場偐傜懆偊傜傟偨悽奅偺尰傢傟乯偲偟偰榑偠偰偄傞乮杮峞戞53復嶲徠乯丅乯
丂
仛昞憌偺僷乕僗儁僋僥傿償乮俹侾'亄俹俀乯
丒尵岅揑揱摫嬻娫偺僷乕僗儁僋僥傿償
丒嫊偲幚偑暘棧偟丄巒傑傝偲廔傢傝偲嬝傪傕偭偨暔岅偑惉棫偡傞乽抦妎揑挱朷乿偺悽奅
佱尵岅僼傿乕儖僪佲
丒乽梋忣乿亖柍暘愡旕宍徾乮俹侾'乯
丒乽帉乿亖暥帤丒壒惡尵岅丄奜揑尵岅乮俹俀乯
丂
仛怺憌偺僷乕僗儁僋僥傿償乮俹侾亄俹俀'乯
丒慜尵岅揑丄恎懱揑揱摫嬻娫偺僷乕僗儁僋僥傿償
丒乽姶妎揑挱朷乿偺悽奅
佱堄幆僼傿乕儖僪佲
丒乽忣乮偙偙傠乯乿亖堄枴揑柍暘愡乮俹侾乯
丒乽巚傂乿亖堄枴揑暘愡婡擻丄撪揑尵岅丄懳徾揑巚堃乮俹俀'乯
丂
仛嵟怺憌偺僷乕僗儁僋僥傿償乮俹俁乯
丒儕僘儉揑丄攞壒揑揱摫嬻娫偺僷乕僗儁僋僥傿償
丒捠懺揑丄拞摦懺揑丄旕恖徧揑丄嫊憐揑乽挱朷乿偺悽奅
丒暔岅揑丄姶忣揑乽憡杄乿偺悽奅
佱嫬乮偝偐傂乯佲
丒崱丄崯張偲偄偆帺徠揑懚嵼偺堄幆惈乮俹俁乯
丂
仛挻怺憌偺僷乕僗儁僋僥傿償乮俹係乯
丒姰椆宍偺岅傝偵傛偭偰屻偐傜惢嶌乮憐婲乯偝傟傞抧暯揑僷乕僗儁僋僥傿償
丒旕尠嵼揑丄愽嵼揑側悽奅
佱怱抧乮偙偙傠乯佲
丒柍暘愡丄枹敪丄枹惗偺挻墇揑旕尰徾乮俹係乯
丂
丂師偵丄乮戞54復偱峫嶡偟偨乯柌偺僷乕僗儁僋僥傿償偺摦懺傪偐偨偪偯偔傞巐偮偺僾儘僙僗乮俹係佀俹俁丄俹俁佀俹侾丄俹俁佀俹俀丄俹侾佁俹俀乯偺媍榑傪墖梡偟傑偡丅偙偙偱妋擣偟偰偍偒偨偄偺偼丄柌偺僷乕僗儁僋僥傿償偺摦懺榑偵丄傆偨偮偺廳梫側榑揰亖壖愢偑偁偭偨偙偲偱偡丅
丂戞堦偼丄悅捈乮俹係佀俹俁乯偲悈暯乮俹侾佁俹俀乯偺椉塣摦傪婎杮偲偡傞僾儘僙僗偵偁偭偰丄偦偺梫偺埵抲傪愯傔傞偺偑乽俹俁乿乮戞嶰師尦丒嵟怺憌偺僷乕僗儁僋僥傿僽乯偱偁傞偙偲丄偟偨偑偭偰丄柌偺僷乕僗儁僋僥傿僽偺摦懺偼丄乽俹俁偺抋惗偲惉挿偺弌棃帠乿偲乽俹俁傪晳戜偲偟偰揥奐偝傟傞悽奅宍惉偺暔岅乿偺擇抜奒偱峔惉偝傟傞偙偲丅
丂戞擇偼丄乽俹俁乿傪婎幉偲偟偰壱摥偡傞柌偺僷乕僗儁僋僥傿償偺巐偮偺僾儘僙僗偑丄乽姶忣乿乽條憡乿乽帪惂乿乽恖徧乿偺巐偮偺暥朄僇僥僑儕乕偺惉棫偵偮側偑傞柌懱尡偺僼僃乕僘偵懳墳偟偰偄傞偙偲丄偦偟偰偦偙偵丄乮埲壓偵偦偺梫揰傪宖偘傞乯栰栴栁庽巵偺乽憡杄亖暔岅乿榑傪摫擖偡傞偙偲偱丄乽戞堦抜奒丗乹姶忣乺偺抋惗偲惉挿偺弌棃帠乿偲乽戞擇抜奒丗乹姶忣乺傪晳戜偲偟偨悽奅宍惉偺暔岅乿偺昤憸偑摼傜傟傞偙偲丅
丂
佱憡杄亖暔岅榑偺梫揰乮偦偺侾乯佲
丒抦妎偼帪娫偺棳傟偺拞偵埵抲偟丄偝傑偞傑側壜擻惈偵庢傝姫偐傟偰偄傞丅
丒偦偙偱丄抦妎傪庢傝姫偔乽帪娫惈乿偲乽壜擻惈乿偲偄偆梫場傪庢傝弌偡偨傔丄乽暔岅乿偲偄偆尵梩傪梡偄傞丅
丒暔岅偼尰嵼偺抦妎傪夁嫀偲枹棃偺撪偵埵抲偯偗傞丅
丒傑偨丄巹偨偪偼尰幚偺暔岅偩偗偱側偔丄斀帠幚揑側壜擻惈偺暔岅傕岅傝弌偡丅
丒抦妎偼偙偆偟偨暔岅偺傂偲僐儅偲偟偰堄枴偯偗傜傟傞丅
丒暔岅偵墳偠偰堎側偭偨堄枴偯偗傪梌偊傜傟傞抦妎偺偙偺懁柺偑丄乽憡杄乿偱偁傞丅
丂
佱憡杄亖暔岅榑偺梫揰乮偦偺俀乯佲
丒擔杮岅偱姶忣傪昞傢偡岅渂偼嬃偔傎偳彮側偄丅
丒擔杮岅偼丄斶偟傒偑偦偺棟桼偵墳偠偰愮嵎枩暿偱偁傞偙偲傪偦偺傑傑庴偗擖傟偨偺偱偁傞丅
丒姶忣偑棟桼偵傛偭偰昞尰偝傟傞偲偄偆偙偲偼丄姶忣偲棟桼偲偑杮幙揑側娭學偵偁傞偙偲傪帵嵈偟偰偄傞丅
丒姶忣偼偦偺棟桼偲杮幙揑偵寢傃偮偒丄棟桼偼婰弎偵埶懚偡傞丅偦偟偰婰弎偼暔岅傪奐偔丅
丒偮傑傝丄堎側傞棟桼偱斶偟傫偱偄傞恖偼丄偦傟偧傟堎側傞暔岅傪惗偒偰偄傞丅
丒偦傟備偊丄姶忣傪斀塮偟偨抦妎偺偁傝曽偼乽暔岅傪斀塮偟偨抦妎偺偁傝曽乿偡側傢偪乽憡杄乿偱偁傞丅
丂
丂埲忋丄奣棯偺傒弎傋傑偟偨丅偙傟傜傪擮摢偵偍偒丄柌偺僷乕僗儁僋僥傿償偺摦懺榑偵懳墳偝偣側偑傜丄巹揑尵岅偺巐椶宆偺奣宍傪慹昤偟傑偡丅
丂
亂戞堦抜奒亃
嘆乹姶忣乺傪傔偖傞巹揑尵岅乮俹係佀俹俁乯
丒柍乮俹係乯偐傜桳乮俹俁乯傊丄償傽乕僥傿僇儖偱椡摦揑側娭學惈
丒柍撪曪偺尰幚惈乮弮悎側傾僋僠儏傾儕僥傿乯偺嵀愓傪乹姶忣乺偺憡偵偍偄偰帵偡尵岅
丂
亂戞擇抜奒亃
嘇乹尰幚乺傪傔偖傞巹揑尵岅乮俹係佀俹俀'丄俹俁佀俹俀'乯
丒俹係乛俹俁偐傜俹俀'偵岦偐偭偰乽壜擻惈乿偺儀僋僩儖偑敪弌
丒斀帠幚揑側壜擻惈傪娷傓乹尰幚乺傪暔岅傞尵岅乮暥帤傕偟偔偼僇僞儕乯
丂
嘊乹 崱 乺傪傔偖傞巹揑尵岅乮俹係佀俹侾丄俹俁佀俹侾乯
丒俹係乛俹俁偐傜俹侾偵岦偐偭偰乽帪娫惈乿偺儀僋僩儖偑敪弌
丒擹岤側帪娫惈乮乹崱乺乯傪懷傃偨姶忣偺暔岅傪岅傞尵岅乮氵傕偟偔偼僂僞乯
丂
嘋乹 巹 乺傪傔偖傞巹揑尵岅乮俹侾佁俹俀'乯
丒恎怱乮俹侾乯偲怺憌偺尵岅乮俹俀'乯丄儂儕僝儞僞儖偱憡屳斀揮揑側娭學惈
丒乽偄傑丒偙偙乿偵岦偐偭偰夞婣偡傞帪娫偺側偐偱乹巹乺偺柤傪崘偘傞尵岅
丂
乵仏乶偙偺偁偨傝偺媍榑偼丄偱偒傟偽乽寳榑乮俠ategory 俿heory乯乿傪巊偭偰昞尰偟揥奐偟偰傒偨偄丅寳榑傊偺娭怱偼丄亀儗儞儅妛亁偺乽晅榐堦丂暔偲怱偺摑堦乿偱拞戲怴堦巵偑乽帺慠妛偲恖暥妛傪偮側偖娐乿偺摥偒傪偡傞弮悎悢妛棟榑偲偟偰尵媦偟偰偄偨偺偑抂弿偲側傝丄偦偺屻丄惣嫿峛栴恖丒揷岥栁挊亀乹尰幚乺偲偼壗偐劅劅悢妛丒揘妛偐傜巒傑傞悽奅憸偺揮姺亁偑乽尰徾妛偲寳榑揑巚峫偺捠掙乿傪岅偭偰偄傞偺傪撉傫偱寛掕揑偵側偭偨丅
丂偵傢偐曌嫮偑偳偙傑偱懕偔偐丄偦偟偰巊偄偙側偣側偄傑偱傕丄偣傔偰寳榑揑巚峫偲壧榑揑巚峫偺憡屳偺曄姺傪姶偠偲傟傞堟偵払偟偆傞偐偳偆偐帺怣偼側偄偑丄惣嫿峛栴恖懠亀寳榑偺摴埬撪劅劅栴報偱偊偑偔悢妛偺悽奅亁傪婎杮彂偲偟偰丄傑偨晍嶳旤曠丒惣嫿峛栴恖乽晄掕帺慠曄姺棟榑偺峔抸丗寳榑傪梡偄偨摦揑側斾歡棟夝偺婰弎乿傗怷揷恀惗乽揘妛幰偺偨傔偺寳榑擖栧乿側偳傪嶲峫彂偲偟側偑傜尋鑢傪怺傔偰偄偗傟偽偲巚偭偰偄傞丅
丂
丂梋択偲偟偰丅暯弌棽巵偑乽栰奜傪備偔帊妛乿乮亀寍弍恖椶妛島媊亁強廂乯偺側偐偱丄僲償傽乕儕僗偺乽悢妛傪婎掙偵偟帊妛傪婎幉偵偟偨億僄僕乕傪傔偖傞巚峫偺帺嵼偝偼丄傾僫儘僕乕娭學憡屳偺偁偄偩偺傾僫儘僕乕偵傑偱払偟偰偄傞乿乮198暸乯偲彂偄偰偄傞偺偼丄柧傜偐偵寳榑乮僇僥僑儕乕榑乯傪擮摢偵偍偄偰偄傞丅
丂偵傢偐巇崬傒偺乽抦幆乿偵傛傞偲丄愭偺堷梡暥拞偺乽傾僫儘僕乕娭學憡屳偺偁偄偩偺傾僫儘僕乕乿偑丄寳榑偵偍偗傞乽帺慠曄姺乮 natural transformation乯乿偵奩摉偡傞乮亀寳榑偺摴埬撪亁戞侾復乯丅偦偟偰師復偱尒傞傛偆偵丄乽巹乿偲偼乮乽帺慠楌巎乿側傜偸乯乽帺慠曄姺乿乮傾僫儘僕乕偺娫偺傾僫儘僕乕乯側偺偱偁傞乮亀乹尰幚乺偲偼壗偐亁146暸乯丅
丂
乮俇俆復偵懕偔乯
仛僾儘僼傿乕儖仛
拞尨婭惗乮側偐偼傜丒偺傝偍乯1950擭戙惗傑傟丅暫屔導嵼廧丅愮擭傕愄偵彂偐傟偨榓壧偺堄枴偑棟夝偱偒傞偺偼偡偛偄偙偲偩丅偱傕丄杮摉偵乽棟夝乿偱偒偰偄傞偺偐丅偦偙偵乽堄枴乿側偳偁傞偺偐丅偦傕偦傕尵梩傪巊偭偰壗偐傪揱払偡傞偙偲偦偺傕偺偑晄巚媍側尰徾偩偲巚偆丅
Web昡榑帍乽僐乕儔乿45崋乮2021.12.15乯
亙欶偲僋僆儕傾乛儁儖僜僫偲欶亜戞64復丂弮悎宱尡乛巹揑尵岅乛傾儗僑儕乕乮偦偺俆乯
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU丂2021 Rights Reserved.
|
| 昞巻乮栚師乯傊 |
