|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「la Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
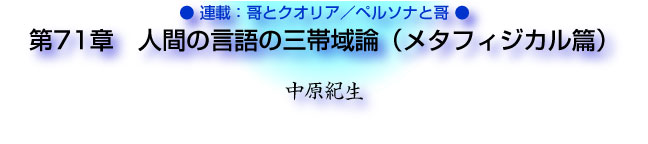
|
|
(本文中の下線はリンクを示しています。また、キーボード:[Crt +]の操作でページを拡大してお読みいただけます。★Microsoft Edgeのブラウザーを基準にレイアウトしておりますので、それ以外のブラウザーでご覧いただく場合では,大幅に図形などが崩れる場合があります。)
■プラズマとエーテル、あるいは「曼陀羅」から「天使」へ─メタフィジカル篇1
読むことが「すぐれてテレパシー的な過程」であると書いたとき、ベンヤミンの念頭にあったのは、天空の星の配置や運行に人の運命を「読む」といった、非感性的類似性にもとづく特別な経験ではなくて、「読むという行為の世俗的啓示」、つまり文字を通じて言葉の意味を読みとるというありふれた経験だったと思います。それは、音声のかたちをとった言葉を介してその意味を聴きとることと同様、ごく普通の日常的な経験にすぎません。
しかし、このありふれた「世俗的」な現象をめぐって、文字という形象そのもの、あるいは発出された音声の響きを通じて言葉の意味が「啓示」されるとき、それでは、その意味の受容はどのような仕組みによってもたらされるのか、音声が空気を、文字(光)が空間を媒質として伝播していくように、言葉の意味の伝達を媒介する場や物質のようなものを想定することができるのだろうか、などと愚にもつかぬことに思いをめぐらせているうち、私の脳髄に、おぼろげにあるアイデアが浮かびあがってきました。
それは、人間の(諸)言語の三つの稼働帯域をめぐる「地勢学」的解釈を拡張して、物質の相転移にかかわる「物性論」や、世界を構成する「元素(エレメント)説」と組み合わせ、そうすることで、「意味の場」もしくは「意味伝達物質」のごときものを炙りだすことができるのではないか、というものでした。以下、途中の推論(逡巡)過程[*1]をとばして、その結果だけを書いておきます。
【天】 ⇔ 【プラズマ】 ⇔ 【エーテル(光素)】
【火】
【風】メタフィジカルな帯域 ⇔ 【気体】 ⇔ 【風(空気)】
【波】メカニカルな帯域
【海】マテリアルな帯域 ⇔ 【液体】 ⇔ 【水】
【地】 ⇔ 【固体】 ⇔ 【土(地)】
テレパシー的な意味伝達の場、すなわちメタフィジカルな帯域は、プラズマやエーテルの光の成分を濃厚に含んだ風や気息(プネウマ)や神の息(ネシャマー)[*2]によって組成されている。そしてそれは、(マテリアルな帯域が如来蔵=曼陀羅的な存在様態のもとにあったことと対比させるならば)、プラズマやエーテルがそこから発出する「アウラ」や「一者」の受肉・啓示(神通的直接伝達)を媒介する「天使」の世界である。私は、そう考えています。
補助線を一本引きます。
西平直氏が『東洋哲学序説 井筒俊彦と二重の見』の序章で取りあげた話題。今道友信との対談「東西の哲学」のなかで、井筒俊彦は、ペルシアの神秘哲学者スフラワルディーの天使論をめぐって、次のように語っています。少し余分なところ(井筒俊彦の「創造的思惟」の起点を探るうえで、とても貴重な発言)を含めて、関係個所を抜き書きします。
最後の話題に関連する井筒の別の発言を二つ。──「歌論、俳論、能理論のようなものまで含めて、それの哲学化ということを考えれば、日本思想は哲学的な別な[西洋的でも東洋的でもない]第三の態度だと思う」(41頁)。「『古事記』なら『古事記』、そこから『古事記』的な哲学的思惟が自然に出来るようにしなくては話にならない」(42頁)[*3]。
[*1]「物性論」をめぐる推論(逡巡)過程。──固体・液体・気体の三態に次ぐ物質の第四の状態「プラズマ」はオーロラの光をもたらす太陽風の成分であり、(オーロラは「アウラ」につながり、惑星ソラリスの「プラズマの海」[*4]につながり)、生物学の分野における「原形質(プロトプラズマ)」(=モネラ)に、ひいては南方熊楠の「粘菌=曼陀羅=潜在意識(アラヤ識)」につながる。
「元素説」をめぐる推論(逡巡)過程。──ガストン・バシュラールの『蝋燭の焔』(澁澤孝輔訳)に「存在の夢想家には、?は、彼岸の方、エーテル的な非存在の方に身を伸ばしていると見えるほど、本質的に垂直である。」云々とある。また、土(地)・水・風(空気)・火の四元素を拡張した第五の元素「エーテル」を、宮沢賢治は「春と修羅」で「光素」と訳した。
[*2]神は土の塵から「人間の言語」を形づくり、そこに意味の息(ネシャマー)を吹き込み、これを生きるものとした。
[*3]西平氏は序章の最後に、井筒俊彦が「『古事記』的な哲学的思惟が自然に出てくるように」西洋とは異なる論理を見出そうとしたのと同様、西田幾多郎も東洋思想を基礎づける「新しい論理」を願い、「自己表現に於て自己を有つ」という実在の自己表現の形式(ベンヤミンの「根源的媒質」をめぐる森田團氏の議論を想起させる)を「論理」と呼んだ、と書いている。以下に、「論理と数理」冒頭の該当箇所を引く。
[*4]ラテン語の「ペルソナ」(仮面)と等値されるギリシャ語の「ヒュポスタシス」(ラテン語 substantia の語源)は、「液体の中の沈澱物、固体と液体の中間のようなどろどろしたもの」という古い意味をもつ(坂口ふみ著『〈個〉の誕生──キリスト教教理をつくった人びと』)。私がイメージする「プラズマの海」は、そのような「ヒュポスタシス」的沈澱物である。
付記すると、かつて(第36章、第42章で)、「固体と液体の中間のようなどろどろした」ゼリー状の「プラズマの海」から連想して、「ペルソナの海」という語を用いたことがある。それは「クオリアの空(宇宙)」の対となる概念だったのだが、本稿のここでの論脈に即して言うと、(あるいは、本文で考察した「物性論」的感覚から言えば)、詩的マテリアルに深く根差すクオリアについて「クオリアの海」と、またエーテル的・天使的な意味世界[*5]にかかわるペルソナについて「ペルソナの空=宙」あるいは「ペルソナの風=光」と呼ぶのがふさわしい。
[*5]「エーテル的・天使的な意味世界」と書いたとき、私の念頭にあったのは、「純音楽的な意味」を表現したバッハの楽曲だった。──ゲオルギアーデス著『音楽と言語』(木村敏訳)に、「バッハ以降、言語は音楽の目標ではなくて手段にすぎなくなり、自己自身以外のなにものかを指示する単なる指標にすぎなくなる。」(142頁)と書いてある。
言語の「天使的」な側面に関連して。──『意識と本質』Ⅹの「元型」イマージュを論じたところで、井筒俊彦はユング派心理学者ヒルマンが使った「コトバの新しい天使学」(a new angelology of words)という表現をめぐって次のように書いている。
■間奏─「三段階モデル」と「意識の構造モデル」の重ね描き
形象的・イマージュ的な世界(アンリ・コルバンの“mundus imaginalis”)における形象体験。すなわち自分自身の意識内部、実存の渦巻きのなかにイデア(もしくは原型)を投げ込み、思想伝統の力とのインターペネトレーションを経て形象化(変形加工)され、受肉された根源的ヴィジョンをなまなましく体験すること。そしてそれを原動力・原点として創造的思惟の自由な展開をはかっていく(自己表現に於て自己を有つ)こと。
井筒俊彦は、このような(イスラーム神秘主義的な光の天使の世界、あるいは密教的な曼陀羅世界をもたらす)体験領域のことを、かの「意識の構造モデル」において、「想像的(イマジナル)」イマージュが棲息する空間、言語アラヤ識に発する「元型」イマージュが生起し働く場所、すなわち表層意識と深層意識の中間地帯をなす「M領域」と名づけました。
ここで少し、寄り道をします。『意識と本質』(岩波文庫)には、全部で四箇所、図解をほどこしたところがあります。
1,宋儒が実践する「静座」の行程(84-85頁)
・表層から深層へ、意識の最後の一点すなわち無極(意識のゼロ・ポイント)への垂直的深化
・無極=太極(存在のゼロ・ポイント)からの喜怒哀楽・全存在の発出
◎表層
↘ ↗
◎深層 ○ = ○
【無極】【太極】
2.実在体験(悟り、見性体験)=無分節を頂点とする禅修行(禅体験)の行程(144頁・170頁)
【無分節】
↗ ↘
【分節Ⅰ】 【分節Ⅱ】
有「本質」的 無「本質」的
3,意識の構造モデル(214頁)
◎表層意識(A領域)
◎深層意識
・中間的意識空間(M領域)
・言語アラヤ識の領域(B領域)
・無意識の領域(C領域)
◎意識のゼロ・ポイント(〇)
4,カッバーラーにおける「セフィーロート」(神の内的世界)の構造モデル(281頁・283-285頁・287頁)
<同心円>
①収縮(ツィムツーム)モデル
②放散モデル
<セフィーロート・マンダラ>
③円形構造体
④セフィーロートの木
これらのうち、「静座」の行程は「意識の構造モデル」に取りこむことができますし、また、「セフィーロート」はM領域の「想像的」イマージュ空間に具体的形象として現われるものなので、これもまた「意識の構造モデル」のうちに収まります。これらに対して、「禅体験」の三段階(三角形)はややニュアンスが異なります。というのも、「この三角形の底辺は経験的世界、頂点に向う一方の線はいわゆる向上道、頂点から経験的世界に向う下降線はいわゆる向下道」(142頁)であって、「意識の構造モデル」における表層意識と深層意識、ゼロ・ポイントとの位置関係が真逆だからです。
西平直氏は『東洋哲学序説 井筒俊彦と二重の見』の第五章で、このふたつのモデルが「どう関係するのか」という問いをたて、その解として、禅体験をめぐる三段階モデルを「谷型」(無分節が下方に位置する)の構図に変形加工したうえで、両モデルを重ね合わせています。
(井筒俊彦は『意識と本質』で「あらゆる事物の無「本質」性、存在の絶対無分節、のこの深層的了解が成立した時、さきに掲げた「分節(Ⅰ)→無分節→分節(Ⅱ)」という三角形構造の頂点をなす無分節が深層意識的事態として現成する。それを禅は簡単に「無」という言葉で表現する。」(156頁)と書いていて、西平氏によると、「井筒は、この場面で、上下のズレを自覚せぬまま、「三段階モデル」と「構造モデル」とを重ねていたことになる」(西平前掲書129頁)。)
私は、西平氏の解釈(禅的三段階モデルを山形でなく谷型ととらえる、つまり「無分節」を深層意識的事態ととらえる)には説得力があると思います[*]。しかしここでは、あえて別の方向を探ります。そうすることで、人間の(諸)言語をめぐる三帯域の説を、井筒俊彦の「共時的構造化」の哲学に接続させたいと思うからです。
[*]西平氏の議論で説得力を感じたのは他に三点あり、それらはむしろ本文記載の項目より興味深いものだった。
その第一は、禅的修行主体における三段階モデルが、井筒の言う「マンダラのイマージュ空間」=「密教的修行主体の脱自的意識そのもの」(『意識と本質』199頁)すなわちM領域の体験を語ることはなく、このように文脈も舞台も違う禅的モデルと密教的モデルを重ね合わせることは、地平の異なる東洋の多様な伝統思想の「共時的構造化」を構想した井筒哲学の核心に触れる機会であるという指摘(西平前掲書132頁)。
第二は、逆に、密教的(かつ唯識的)モデルすなわち「意識の構造モデル」は分節・無分節の区切り方をせず、むしろ両者の連続的相違(グラデーション)を示すこと、その典型がC領域であって、この領域は「究極の「無分節(意識と存在のゼロポイント)」」すなわち「それ自身が自己分節へと向かう力動性」であるところの無分節が「自己分節へと胎動を見せる、微妙な場面」であるという指摘(西平前掲書134頁)。──C領域を「無分節→分節(Ⅱ)」の力動性の空間ととらえるこのアイデアは、入不二基義氏が『現実性の問題』で呈示した「命題の外側で働く透明な力」すなわち「純粋な現実性」の概念への接続をはかる重要な手掛かりとなる。
第三に、禅的三段階モデルの分節(Ⅱ)、すなわち分節Ⅰ(経験的分節)と絶対無分節との「同時現成」(『意識と本質』136頁)、西平前掲書で「二重の見」と呼ばれる事態を、分節・無分節の区切りを語らぬ「意識の構造モデル」がどう説明するのか、という設問に対する西平氏の見解。いわく、その答えは『意識と本質』冒頭の「東洋の哲人」をめぐる定義のうちに示されている(西平前掲書138-139頁)。「表層意識の次元に現われる事物、そこに生起する様々の事態を、深層意識の地平に置いて、その見地から眺めることのできる人。表層、深層の両領域にわたる彼の意識の形而上的・形而下的地平には、絶対無分節の次元の「存在」と、千々に分節された「存在」とが同時にありのままに現われている」(『意識と本質』16頁)。
■間奏─「三段階モデル」と「意識の構造モデル」の重ね描き(承前)
禅体験にかかわる三段階モデル(三角形構造)と密教的・唯識的な意識の構造モデルとの「上下のズレ」を解消する、西平氏とは異なる解釈の方向として、まず考えられるのは、禅の三角形モデルを意識の構造モデルと同一の平面に重ね合わせるのではなく、両者をいわば直交させて、「意識の構造モデル」が書き込まれた紙面の向こう側に「無分節」を位置づける、といった立体的構造化の方向です。が、ここではこのアプローチはとりません。あくまで「上下」の位置関係にこだわり、たとえばイスラーム神秘主義の天使と密教の曼陀羅を同じ平面上に構造化しておきたいからです。
私が試みるのは、第68章(と第69章)で採用した「鏡像反転」による重ね合わせです。そのヒントは、前節の註で引いた井筒の文章中の「表層、深層の両領域にわたる…意識の形而上的・形而下的地平」という表現にあります。これを読んで私は、絶対無分節に「形而上的無分節」と「形而下的無分節」の区分があることに思い至ったのです。井筒俊彦は講演「対話と非対話──禅問答についての一考察」(『意識と本質』所収)のなかで、「一者」の自己分節をめぐって次のように発言しています。
いわく、「一者」が自己分節するとは、別々の部分に分れることではない。それぞれが「一者」の違った現れ方なのである。「その意味で、一々の事物事象がいずれも絶対無分節者の言語的自己分節なのであります。」(400頁)たとえば今私が見ているこの山は、同様にそれを見ているこの私も、今ここでの「一者」の直接無媒介的な自己提示である。「私が山を見るという一見極めて単純な経験的事実が、実は「一者」が自らを自らの鏡に映して見るという形而上的事件なのです。」(401頁)
「一者」すなわち形而上的無分節と、禅的な「無」すなわち形而下的無分節。──以下、新しい(山形・谷型の三角形構造を意識の構造モデルに組み込んだ)三帯域図作図法の概略を粗描します。
1.「無分節」を形而下的「無分節1」(絶対無)と形而上的「無分節2」(一者)に分割する。
2.「無分節1」を「意識(と存在)のゼロ・ポイント」(もしくはそれ以前、あるいは父母未生以前?)に位置づけ、「無分節1→分節(Ⅱ)」の力動的プロセスを「C1」のうちに落とし込む。その結果、深層意識「V1」が塑型され、「V1=B1+M1」の分節(身分け)を経て、人間の(諸)言語の三帯域のうち「マテリアルな帯域」(M1)が設営される、「分節(Ⅰ)」の領域すなわち「メカニカルな帯域」(A)が区画(言分け)される。
(これと同時に「A」から「〇」へ、すなわち「分節(Ⅰ)→無分節1」の遡行プロセスが並行的に進行し、その結果、「分節(Ⅱ)」=「A×V」の「二重の見」が成立する、塑型と遡行の二重のプロセスの同時進行が成就する。)
3.上記の作業を鏡像反転的に反復し、(その起点となる「鏡」は、おそらく「B1」(言語アラヤ識の領域)と「M1」(模倣する身体の領域)との界面に設えられる[*])、天空のもう一つの「ゼロ・ポイント」(神の座)から発する「無分節2→分節(Ⅱ)」の力動的プロセスを「C2」に落とし込む。その結果、(深層意識ならぬ)高層意識「V2」が塑型され、「V2=B2+M2」の分節(気分け=リズム的分節?)を経て、人間の(諸)言語の三帯域のうち「メタフィジカルな帯域」(M2)が生成する、「メカニカルな帯域」(A)が確定する。
(同時並行的に上方の「〇」に向かう遡行プロセスが進行し、もう一つの「二重の見」が成立する、逆方向の塑型と遡行の二重プロセスが成就する。)
4.これら二つの作業を合成して、人間の(諸)言語の稼働圏域における「C1//B1//M1/A/M2//B2//C2」∽「…//マテリアルな帯域/メカニカルな帯域/メタフィジカルな帯域//…」の解釈図式を
(C・B・Mの各領域を同心円のかたちで構造化することもできる。すなわち、外部(絶対無分節)から「ゼロ・ポイント〇」を「境(さかひ)」として到来する透明な力のフィールド「C1~C2」を一番外側の見えない円とし、大円「B1~B2」と中円「M1~M2」と小円「A~A」を同心円の関係のもとに並べることによって。)
《図1》人間の言語の二契機と三帯域(Ver.4)
≪無分節2≫
~~~~~~~〇~~~~~~
C2
ε…………………………………
B2
δ=============
M2
γ━━━━━━A━━━━━━
M1
β=============
B1
α…………………………………
C1
~~~~~~~〇~~~~~~
≪無分節1≫
※ε:天
γ~ε=高層意識:V2
δ~ε=純粋言語の圏域
β~δ=人間の(諸)言語の稼働圏域
γ~δ=メタフィジカルな帯域
γ =メカニカルな帯域
β~γ=マテリアルな帯域
α~β=私的言語の圏域
α~γ=深層意識:V1
α:地
[*]この鏡は、かの「ちはやぶる神の心を荒るる海に鏡を入れてかつ見つるかな」(土左日記二月五日)の「鏡」であり(第15章・第65章参照)、かつ「鏡1」である。三帯域図作図の端緒を「無分節2」に置いて本文を書き換えると、その際「鏡像反転」の起点となる「鏡2」は、「M2」(名前はまだ無いが、「反復する歴史」とでも?)と「B2」(同様に「現勢態[アクチュアリティ]、つまり過去と未来の間の時間の裂け目」(ハンナ・アーレント『過去と未来の間』14頁)とでも?)との界面に設えられる。
(本文では取りあげなかった「三角形構造」をこの二つの「鏡」を使って書き込むと、「山形」の三角形は「鏡1」を底辺とし上方の「ゼロ・ポイント」(=境(さかひ)2)を頂点とし、「谷型」は「鏡2」を底辺とし下方の「ゼロ・ポイント」(境1)を頂点とするものとなる。)
ちなみに、この「鏡」は実在するもの(物象心象、可触不可触、可視不可視を問わぬ森羅万象)を映しだす(表象する)のではなく、そこに映しだされる(表現される)ものの実在性を逆に産みだす。ちょうどベンヤミン的媒質が根源的産出(根源的分節=地(時)分け?)の働きをするように。「鏡1」は生命世界における「模倣の鏡」、「鏡2」は精神世界(歴史世界)における「反復の鏡」と呼んでもいい。
補遺。人間の(諸)言語の三帯域図を作図するとき、私はいつも下方から、一者からではなく絶対無から、無分節2からではなく無分節1から、純粋言語からではなく私的言語の方から始める。それは海外で宗教は何かと問われたら、よくある助言にしたがって「buddhism」と答えることにしているのとは無関係だ。
上方から始めることに(無意識の)抵抗や躊躇があるとしたら、それは私には一神教のことがよくわからない(わからないのではなく信じられない、というかそもそも「信じる」とはどういう事態なのか、態度なのかがよくわかっていない)からかもしれないが、それも関係ないと思う。
そもそも言語の起源・発生や進化は「身体」なしにあり得ない現象だと私は素朴に思っていて、だから生命世界に専属する言語現象について、当の生命世界によって「基づけ」られた精神世界(歴史世界)の側からその起源・発生や進化を語ることは倒錯した試みではないかと考えているからだ。
もちろん言語の進化には不可逆的な転換点があって、それ以後の言語現象は生命世界の軛を離れ、精神世界(歴史世界)に固有な法則性のもとで自律的に進化すると考えることはできる。そうであれば、精神世界(歴史世界)の側から言語の起源・発生や進化を語ることに何の問題もない。(言語の起源については疑問なしとしないが、しかし「語る」こと自体、精神世界(歴史世界)に専属するのだから、そもそも言語について語ることは精神世界(歴史世界)の側からでしかできないことだ。)
それ以外にも、上方からのアプローチを「正当化」する方法はある。その一つは(仏教(無神論)か一神教かという対立を無効にしてしまう)仏基一元論、いま一つは(先に述べた精神世界(歴史世界)の生命世界からの自立に通じる)深層意識(無意識)のうちに超越的な神の座の起源を設定すること。
第一の方向には、鈴木大拙や折口信夫の系譜に連なるもの(安藤礼二氏の著書に描かれていた系譜)があるが、私が注目したいのは「永井均的仏基一元論」。近年(求められて)仏教思想とのつながりを深めている永井哲学を、私はかねてから「信仰なき神学」として読んできた。そのことは、中田考氏がツイッターで「一神教の真の意味を理解している数少ない日本人」と永井を評したことに始まる一連の応酬を見て確信が深まった。以下は『存在と時間──哲学探究1』第6章からの抜萃。
中田「今の〈私〉と過去の〈私〉、そして有り得ざるべき「〈私〉たち」の間に有り得ざるべきコミュニケーションが成立しているとすれば、唯一の〈私〉の神は「〈私〉たち」とそれらの「世界」の唯一の神でもなければならないのではないでしょうか。」
永井「なるほど。「有り得ざるべき」ことが(なのに)現に有るということが発条になって「世界」の唯一の神になるわけですね。それは(私には)よく理解できる道筋ではあります。」
中田「はい。〈私〉の唯一性という奇跡が神の唯一性の証明であり、〈私〉の唯一性とは神の唯一性の顕現に他ならず、〈私〉は神と世界の接点であり、それゆえ世界の開闢の場となるのだと思っております。」
永井「むしろ、こちらが先ですね? 次に「有り得ざるべきコミュニケーション」が成立しているので〈私〉たちとそれらの「世界」の唯一の神にもなるという順番。よく理解できますが(私などが心配しても仕方がないけど)この二つに神概念が分裂してしまわないかが心配です。」
中田「この二つの神を一つと見做す(信じる)のが、アブラハム的(啓示的)一神教の信仰の精髄かと思います。」
永井「ああ、そこで信仰が成立するのですか! ひじょうによく分かりました。」
永井氏はこのやりとりを紹介した後で次のように書いている。
──だから私は上方のゼロ・ポイントと下方のゼロ・ポイントを同じ記号「〇」を使って表記したのだ。
第二の方向には、ユングの集合的無意識(『意識と本質』では「集団的無意識」)による神の産出という議論がありうるが、ここではフロイトの場合で考えたい。新宮一成氏が『夢分析』の最終局面で次のように書いている。
──だから私は…。(本当はこの後に続く「夢の語らい」をめぐる議論が大事なのだが、それはこの補遺の関心事を超過する。)
余録。歪なまでに長くなりすぎた註に、いまひとつ蛇足を加える。
最近、中野剛志著『小林秀雄の政治学』を読んでいて、とても刺激的な「発見」があった(24-25頁)。中野氏によると、小林秀雄はマルクスの唯物論における「物」を「あるがままの現実」(子供には「中天にかかった満月は五寸に見える」(「様々なる意匠」))と解釈した。そのことは「マルクスの悟達」という随筆を読めばわかる。「…この世はあるがままにあり、他にあり様はない、この世があるがままであるという事に驚かぬ精神は貧困した精神であるという事である。弁証法的唯物論なるものの最も率直な表現である。」(『新訂 小林秀雄全集第一巻』105頁)
そして、(満月を五寸だと)あるがままに現実を見ることを「直接経験」(「文芸批評の科学性に関する論争」)と呼んでもよい、と中野氏は言う。「世に芸術家程、直接経験の世界に忠実な人種はありません。(略)彼等は、形を、色を、音をまともに常に感じていないでは、どんな夢も見る事は出来ないのです。(略)これは、何も特殊な事情ではありません。子供はみなそうです。」(同131頁)
私は、中野氏が指摘した事柄「マルクスの唯物論における「物」とは「直接経験」である(と小林秀雄は解釈した)」を拡張理解すれば、かのマテリアルな帯域の下方に「私的言語」の領域がひかえていて、それは究極的に「純粋経験(直接経験)」に発する、という本稿の立論にとって有力な「エビデンス」が得られると思った。
付言すると、本稿の図解ではこれまで「純粋言語の圏域」と「私的言語の圏域」とを対にしてきたが、正しくは「純粋言語」には(「私的言語」ではなく、その前段階の)「純粋経験」が対応する。精確には、「純粋経験⇒私的言語⇒公的言語」のプロセスと「純粋言語⇒言語ゲーム⇒公共言語」とが対になる。これが私の本来の構想だったが、残念ながら本稿のこの段階では(私的言語と同様に)言語ゲームのことがまだよく判らない。
■元型と原型、あるいは「原初の刻印」─メタフィジカル篇2
マテリアルな帯域とメタフィジカルな帯域は、実は同じM領域の異なる位相であった。というか、そのように私は考えたわけです。
ここで、M領域をめぐる井筒俊彦の議論を参照します。そしてその次に、マテリアルな帯域とメタフィジカルな帯域に共通する特性を踏まえたうえで、両者の違い、とりわけメタフィジカルな帯域がもつ固有の形而上的特性(あからさまな同語反復を避けて、メタフォリカルな特性と言い換えてもいい[*1])を抽出することにしたいと思います。
まず、『意識と本質』の抜き書き(引用者の独自の見解による加筆あり)から。
◎「想像的」イマージュ【A領域→M領域】
・「想像的(imaginal)」イマージュとは、たとえば神憑りしトランス状態にあるシャマンの意識の深層から屡々湧出してくる異次元のイマージュである。
・日常的意識から離れつつ「自己神化」の過程にあるシャマンの目に眺められた事物は、経験的世界(A領域)の事実性を離れて、異次元のイマージュ空間(M領域)に移される。そして純然たるシャマンの意識において、すべてのものが始めから「想像的」イマージュとなる。空海の金胎両部マンダラはそうした「想像的」イマージュ空間(M領域)の構造的呈示である。
◎「元型」【C領域→B領域】
・「元型または範型」(archetype)は事物事態の存在根源的「本質」である。(それはゲーテの「根源現象」(Urphaenomen)に結び付く。)
・ユングによれば「元型」は具体的形をもたず、未決定・未限定・不可視・不可触。集団的無意識または文化的無意識の深みにひそむ、一定の方向性をもった深層意識的潜在エネルギーである。
◎「元型」イマージュ【B領域→M領域】
・「元型」は言語アラヤ識(B領域)から生起し、人間の深層意識(「想像的」イマージュの空間:M領域)において「元型」イマージュ(例:易経の「象」)として事物事態の「本質」を開示=形象化=呈示する。
・「元型」イマージュは経験的現実の世界に直結する表層意識(A領域)まで上がっていかず、M領域で止まってしまう。このM領域こそ「元型」イマージュの本当の住処である。
以上の議論は、「深層/表層」の区分を基本とする「意識の構造モデル」に基づいているので、前節の構図で使った「M1」(中間地帯=マテリアルな帯域)や「B1」(言語アラヤ識)、「C1」(無意識の領域:コトバ以前)の符号を割りあてて理解すべきものです。このことを念頭において、井筒俊彦の議論を上方に、鏡像反転的に分節・拡張し、本稿のここでの関心事であるメタフィジカルな帯域を、「表層/高層」の区分に基づくもうひとつの「意識の構造モデル」のうちに位置づけると、次のようなかたちになります。
《図2》人間の言語の二契機と三帯域(Ver.5)
≪無分節2≫
~~~~~~〇~~~~~~
↓
ε ……………↓……………
原 型
↓
δ == ↓ =========
(反 復)
原 型 想像的
イマージュ イマージュ2
↑↓
γ ━━━━━━━━━━━━━
↑↓
想像的 元 型
イマージュ1 イマージュ
(模 倣)
β ========= ↑ ==
↑
元 型
(母 型)
α ……………↑………………
↑
~~~~~~〇~~~~~~
≪無分節1≫
※ε~〇:C2(アクチュアルな力(としての純粋言語)の場)
γ~ε=高層意識:V2
δ~ε=純粋言語の圏域:B2(過去と未来の間の時間の裂け目)
β~δ=人間の(諸)言語の稼働圏域
γ~δ=メタフィジカルな帯域:M2(反復する歴史)
γ =メカニカルな帯域 :A
β~γ=マテリアルな帯域 :M1(模倣する身体)
α~β=私的言語の圏域:B1(言語アラヤ識)
α~γ=深層意識:V1
〇~α:C1(ヴァーチュアルな力(としての純粋経験)の場)
たくさんの言葉を、定義・説明抜きで導入しました[*2]。ここでは、元型ならぬ「原型」をめぐって一言、補います。
安田登著『あわいの時代の『論語』──ヒューマン2.0』に、「元型」は「天命」である、という議論が展開されています(203-205頁)。簡単に紹介すると、まず、「天命」の「天」は人の頭部を意味する。また「令(命)」の字の上部は「神威の象徴としての蓋」、下部は「神意を尋ねるために跪く人」をあらわす。蓋の代わりに「手」を加えると「印」になり、これは大きな手(神の手)で祈る人を抑える形、すなわち「刻印」。手でなく蓋で覆うのが「令(命)」、したがって「天命」は神からの命令であるとともに、人間に刻印された神の大命ということになる。
天(頭)はギリシャ語で「アルケー」、また「令(命)=刻印」は「テュポス」。「天命(最初に刻印されたもの)」をギリシャ語でいうと「アルケー・テュポス」となり、これはユングのいう「元型」にほかならない。
最近の著書『野の古典』にいわく、「天命とは、その人に生まれつき刻まれた刻印です。この「原初の刻印」をギリシャ語でいえば…[アルケー・テュポス]…になり、これがユングの「元型[アーキタイプ]」になります。/その原初の刻印、元型に気づくのが「天命を知る」ことなのです。」(91頁)
私は、この「天」を文字通りに受け止め、上方(高層)からの「原初の刻印」を「原型(アーキタイプ)」と呼称し、「下方」(深層)からの「元型(アーキタイプ)」=母型と区別したわけです。
[*1]松岡正剛氏が『江戸問答』のなかで、宮沢賢治が「イギリス海岸」や「イーハトーブ」と呼ぶあの感覚はまったく欧米にはないというロジャー・パルバースの指摘について、「宮沢賢治のああいうメタフォリカルな「ずらし」の幻想感覚は日本にしかない不思議なものだということを、パルバースは書いている」(332頁)と紹介し、「それは「ずらし」なんですか」という対談者(田中優子)の質問に、「日本文化的にいえば「見立て」ですね。江戸ふうにいえば「やつし」でしょうか」と応じている。
──日本的「反復」の方法としての「ずらし」「見立て」「やつし」?
[*2]かつて(第42章や第58章、第59章で、異なる分類基準のもとで)試みた「イマージュの四分類」の説をここに組み入れることもできる。下記の分類にしたがうと、本文の図に記載した四つのイマージュはいずれも「喩」の範疇に属する。
【像】
・A領域(メカニカルな帯域)
・オリジナル(実物)に対するコピー(写し)
・インデックス(指標記号)
【喩】
・M1領域(マテリアルな帯域)+M2領域(メタフィジカルな帯域)
・オリジナルが受肉もしくは憑依したコピー
・イコン(類似記号)もしくは形象化された反復もしくは模倣
【象】
・B1領域+B2領域
・コピーなきオリジナル
・シンボル(象徴記号)としての原型もしくは母型(元型)
【肖】
・C1領域+C2領域
・オリジナルなきコピー(もしくはオリジナルの自動転写=アケイロポイエートス)
・マスク(仮面記号)
■原型と反復、あるいは「想起と想像とのアマルガム」─メタフィジカル篇3
中島義道氏は『観念的生活』6章「過去と他者の超越」で、「過去こそ時間の本来的あり方であり、想起する私こそ本来的な私なのである」と書き、プルーストの無意志的想起をめぐるドゥルーズ(『プルーストとシーニュ』)の議論を「誤魔化しである」としたうえで、「ドゥルーズの主張したいことは実はわかっている」、と議論を進めています。
この話題はいつか取りあげようと大事にとっておいたもので、貫之現象学C層の、たとえば歴史の概念をめぐる議論のなかで参照することになるのではないかと思うので、ここでは前後の文脈はとばして、私の記憶に残っている中島氏の文章を抜き書きしておきます。
想起と想像とのアマルガム。──私の今ここでの関心事に引き寄せ、(ターミノロジーも本稿の「語脈」にあわせて)、これを言い換えると、次のように「分節」することができるでしょう。
★マテリアルな帯域(模倣原理)
・M領域の「マンダラ」的側面(深層意識と純粋過去にかかわる?)
・「母型(元型)イマージュ」と「模倣イマージュ」(想像的イマージュ1)とのアマルガム
★メタフィジカルな帯域(反復原理)
・M領域の「天使」的側面(高層意識と純粋未来にかかわる?)
・「原型イマージュ」と「反復イマージュ」(想像的イマージュ2)とのアマルガム
(純粋過去、純粋未来とくれば、純粋現在という概念を繰りだしたくなる。が、これはメカニカルな帯域について論じる際、必要があればあらためて取りあげることとして)、ここに出てきた四つのイマージュの実例をいくつか、『意識と本質』の叙述も参照しながら、挙げておきたいと思います。後の議論につなげるため、下図では四つの象限に区画して整理していますが、本来、ⅠとⅡ、ⅢとⅣは「アマルガム」もしくは「アモルフなかたまり」として、あるいは複素数の実部と虚部のように結合したものとしてとらえなければなりません。(Ⅰ+Ⅱ=物語性、Ⅲ+Ⅳ=構成性(構造性)のようなかたちで[*]。)
《図3》人間の言語の二契機と三帯域(Ver.6)
[原型]
=============
│
Ⅱ │ Ⅰ
│
[字]━━━━━━┿━━━━━━[声]
│
Ⅲ │ Ⅳ
│
=============
[母型]
※Ⅰ:反復イマージュ
・始原(太始[はじめ])のコトバ(「そのコトバは神であった」)
・根源音「アーレフ」に始まるヘブライ語の二十二の子音システム
Ⅱ:原型イマージュ
・イスラームの文字神秘主義
・カッバーラー文字神秘主義(セフィーロート)
Ⅲ:模倣イマージュ
・象形文字
・八卦、六十四卦
Ⅳ:母型イマージュ
・オノマトペ
・空海の阿字真言(マンダラ)
説明不足の図解に終始しました。最後に、これだけは書いておかねばならない事柄にふれて、この章を閉じます。
本論考ではこれまでから、反復とは「一回性をもった出来事を何度でも初めて「今、ここ」で経験すること」であると定義し、折に触れて思考をめぐらせてきました(第11章、第48章、第58章他参照)。最終的には、おそらく仮面や伝導体、主体や世界、物語や歴史、等々を主題的関心事とする貫之現象学C層にいたって、いちおうの見極めがつく(か、その解明を最終的に断念する)ことになるだろうと思います。
そういうしだいなので、ここでは、先の定義に直結する三つの参考文献から、関連する文章を抜き書きするにとどめます。
その一、新宮一成著『夢分析』(本稿第4章参照)。
その二、塩川徹也著『虹と秘蹟──パスカル〈見えないもの〉の認識』(本稿第38章参照)。
その三、桧垣立哉著『瞬間と永遠』(本稿第59章参照)。
[*]井筒俊彦によると、「元型」イマージュは、「文化的枠組」によって根本的に条件付けられるという特徴と、事実性からの遊離(非即物性、脱即物性)という特徴のほか、それよりもっと大切な二つの顕著な特徴もつ。すなわち、①説話的自己展開性、あるいは「神話形成的」発展性、②一定の法則性をもって結合し、整然たる秩序体をなすという、構造化の傾向。
以下、井筒による解説を引用する。(「元型」イマージュと「想像的」イマージュとのアマルガムが意味するものを理解するため、また貫之現象学C層における「物語論」につなげる意味で。)
私の理解では、(井筒俊彦が挙げた例とは食い違うが)、「元型」イマージュがもつ顕著な特徴のうち「物語性」はメタフィジカルな帯域(《図3》のⅠとⅡ)に、「構成性(構造性)」の方はマテリアルな帯域(ⅢとⅣ)に、それぞれより強く妥当する。
(第72章に続く)
★プロフィール★
中原紀生(なかはら・のりお)1950年代生まれ。兵庫県在住。千年も昔に書かれた和歌の意味が理解できるのはすごいことだ。でも、本当に「理解」できているのか。そこに「意味」などあるのか。そもそも言葉を使って何かを伝達することそのものが不思議な現象だと思う。
Web評論誌「コーラ」49号(2023.04.15)
<哥とクオリア/ペルソナと哥>第71章 人間の言語の三帯域論(メタフィジカル篇)(中原紀生)
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2022 Rights Reserved.
|
| 表紙(目次)へ |
