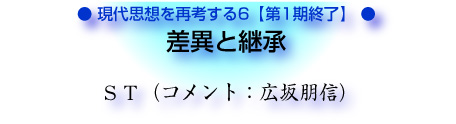|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「La Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
|
【凡例】:岡田さんが二つと広坂さんが二つ書いた計四つの文章と、その小見出しに番号を振り、私がそれらから引用する時には、例えば広坂さんの一つ目の文章(「神話劇を見る視点」)の三つ目の小見出し(「見世物としてのニュース」)については、「広坂1−3」と書く。
***
岡田さんと広坂さんの文章で常に問題とされ続けていたのは、ヘーゲルであった。私もまた今回の文章ではヘーゲルを重要視しつつも、しかしもう一人の思想家の目印を幾つか標記しながら、この文章を進めて行きたいと思う。それはニーチェである。
1:差異
この文章で問題となるのは差異とその継承である。そこでまず、批判・検討を加えるべき叩き台として問いを立てる:差異を如何にして継承するか?
この問いの批判・検討をされるべき点は、この問いが、差異を継承に先立って現前するものであると聞き手に誤解させる恐れのある点である。つまりこの問いは、現前的で同一な差異というものがまずあって、その後にそれを継承する方法を問う問いであると、聞き手に誤解させる恐れがある。
しかし勿論、「現前的で同一な差異」という文は矛盾している。差異は差異である限り、いかなる現前性と同一性からも差異化する。だから差異は、差異として現前性と同一性において規定されること自体からも差異化するものである。つまり差異は、差異(という規定)から差異化し、したがって差異自身から、自己自身から差異化する。自己からの差異化が差異である。
私は差異を、差異化と言い直した。名詞と動詞の区別に頼るとすれば、これは、名詞としての差異から動詞的差異への言い直しである。デリダが差延を語る時、差異(difference)の間にaを入れたこと(differance)を思い起こしていただきたい。デリダによれば、それはフランス語の現在分詞の働き、英語で言えばingの働きを、名詞としての差異に与えることである(Jacques Derrida, Marges de la philosophie, Paris, Editions de Minuit , 1972, pp.8-9 Eにアクサンテギュ)。それによって名詞は動詞となり、差異は差異化となる。差異の働きは、差異として自己自身の内で規定されず、自己の終点に至らず、常に自己から差異化し続ける働きである。
ところで規定とは、determination(デターミネイション)の訳語である。この単語はその内にterm(ターム)という語を持つ。termは学期、期間、期日などの意味の他に、限界点(面、線)の意味も持つ。規定determinationとは、点や面や線によって限界を設け、時間的空間的な連続や運動に始まりと終わりを持つ一定の幅を与えることである。したがって差異が差異としての規定から差異化するというのは、つまり差異が始まりと終わりを設けられることから差異化すること、あるいは、或るものと他のものとの間に位置づけられた差異として規定されることから差異化すること、であり、始まりと終わりという限界が無い、無限の運動を行うことである。(termという語から、終点や終着を意味するターミナルという語が生まれた。この語はバスや飛行機や船などの運行を終える地点を指す語である。)
差異が、差異として規定される自己自身からの差異化であり、始まりと終わりとの限界なき無限の運動であるならば、差異を如何にして継承するか、という問いは、次の誤解を読み手に促す可能性のある点において訂正されなければならない、即ち、差異と継承とは区別され限界づけられるものであり、それぞれが現前的同一的規定を持つものであると考える誤解を。差異を、継承とは別の次元において始まりと終わりとの限界の間で規定される運動と考え、次にこの限界内での差異の運動を限界外の別の継承という運動が継承すると考えるのでは、差異を継承することはできない。差異が無限の運動であれば、その運動と継承の運動とを区別する限界を設けることはできない。そうでなく、無限の差異それ自体が継承である。差異は、その自己からの差異化の運動の内においてすでに、自らを他者に送付する継承の運動を持っている。差異「を」継承するのではなく、差異化それ自体が継承なのである。
私は以前書いた文章の初めに、継承を不可能にしてしまう考え方を示した。それは現在の同一性に閉塞する継承の考え方である。「現在が現在自身に同一であって初めて、過去から未来への継承が、両者間〔過去と未来との間〕の隔たりの解消が可能となる。〔…〕しかし、ここが問題だが、こうした考え、すなわち過去と未来との時間的隔たりが、同一的現在の継承によって解消されるという考えは、継承そのものを不可能にしてしまわないだろうか。〔…〕同一性はその外へ〔…〕出ることができず閉塞する。〔…〕そうであれば、現在的同一性の閉塞に陥らないような継承を考え直さなければならないのではないか。〔…〕現在の内にさえ何らかの隔たりを導入しなければならないのではないか。」
そこから私は、反復と痕跡を論じ始めた。まず反復は、現在の内の隔たりとしてあるだけでなく、過去と未来にも先立つものである。反復が過去現在未来のそれぞれを構成する。「(〔…〕反復可能性は過去が過去としてその都度主題化されるための反復なのだから、こうした過去現在未来の通常考えられる区別に先立つのであり、反復によって過去(把持)と現在を(さらには未来(予持)を)構成するのだ。)」次に痕跡は、過去の内にさえ未来を入りこませ、過去と未来とをそれぞれの規定から差異化させるものである。「過去を過去として構成するための反復可能性自体が、常に未だ反復されつづけ未だ想起され続けるという構造を持っている以上、過去の構造そのものの中に未だ来るべく留まる未来が入りこんでいる」。このようにして、私は以前の文章において、現在的同一性に閉塞しない継承のために、過去と現在と未来のそれぞれの規定に先立つ隔たりとしての反復と痕跡を論じたのである。
そうすると、継承は、すでに規定された過去・現在・未来の時間の規定の間での運動ではなくなるだろう。継承が持つ隔たりは、現在自身の(また過去自身と未来自身の)内の隔たりと同じものとなるだろう。(だからその隔たりはもはや、或るものと他のものとの間、例えば現在と過去や現在と未来との間の隔たりとして規定することはできない)。
私が今回の文章で述べる、差異の自己自身からの差異化とは、以前の文章における現在の内の隔たりと同じものである。すると、以前の文章で述べた<継承が持つ隔たり>とは、以前の文章での<現在自身の内の隔たり>(これによって現在の同一性への閉塞が破られる)と同じであり、今回の文章での<差異の自己自身からの差異化>と同じものとなる。
したがって、先程の問いの訂正は次のことを念頭においてなされなければならないだろう、即ち、<継承の隔たり>と<差異の自己自身からの差異化>とが同じものである以上、継承の内に差異(隔たり)を導入しなければ、つまり継承を現前的同一性の内で行うならば、継承される差異もまた同一性の内に消去されてしまう、ということを。では、継承の内に差異を導入するとはどのようなことか?
2:超越論的差異
継承の内に差異を導入することは、原則としては単純である。否定辞を用い続けることである。つまり、差異とはあれでも
「既に、差延は存在しない、現実存在しない、現前的―存在者ではない〔…〕
「確信が持てるのは、この否定的形式についてのみである」。(『他の岬』高橋哲哉、鵜飼哲訳、みすず書房、一九九三年、六三頁)
差異については、否定辞によって無限に差異を標記し続けることでしか語ることができない。継承の内に差異を導入することでしか、差異を継承することはできない。だから、継承を差異化すれば差異が継承される、ということになるが、これは同語反復だと言いたくなる。しかし継承と差異がいずれも自己自身の同一性からの差異化であるならば、差異と継承とを同一化する同語反復というこの診断は、それ自体がすでに差異の消去なのである(つまり継承を不可能にするものなのである)。したがって我々は、この先、差異と継承とを同じものであると考えることに対しては警戒しなければならない。一層適切に言えば、否定辞の反復によって、差異と継承とは異なるものではない、と標記することしか我々にはできない。しかし、異なるものではない、と言いながらまた同時に、かと言って同じものではない、とも標記しなければならないのである(同じものであると言えば、これは両者を同一化させ差異を消去する同語反復であるのだから)。
これに対して当然予想される批判、即ちその差異の無限の標記とはニヒリズムであるという批判については、ごく手短に応えておく。ニヒリズムであるとする診断、それこそは、無限の差異の標記を全て等し並みにして考える思考、即ち差異の消去である。そうであれば我々は、無限の差異の標記をニヒリズムと結論付けることで満足しては(つまり無限の差異化の運動に終点のターミナルを設けては)ならない。まずデリダはこうした批判に対して、ニヒリズムでは
差異それ自体というものが仮にあるとして、今我々は、差異それ自体についてではなく、その継承や、それを語るための無限の差異の標記や、それをニヒリズムと診断することについて論じた。差異それ自体について論じるのではなく、差異を論じる幾つかの議論について論じた。差異については、論じることについて論じる、という事態が起こる。これを、差異の自己言及的構造と呼ぶことは、つまり差異が差異自身へと回帰する運動として理解することは、結局差異の消去となる。なぜなら、まさに差異とは自己自身からの差異化であったからである(自己への回帰や自己言及ではなく)。
したがって、この事態は自己自身からの差異化として理解されなければならない。つまり、差異は、それ自体では何ものでもなく(したがって、前段落の始めで仮に想定した「差異それ自体」なるものはないと言われなければならない)、自己自身からの差異化として、他者へ送付されており、他者とは無数にありうるだろうが少なくとも差異をめぐる議論へ送付されているからこそ、差異については、論じることについて論じる、という事態が起こるのである。したがってこの送付は、差異の他者への運動であるにも拘わらず、あるいはそれゆえにこそ、差異それ自体や差異の自己同一性と異なり、差異と等しい(差異と異なるものでは
これを超越論的という語によって考えてみる。
カントによる超越論的という語の定義は、次のものである、即ち、「私は、対象に関する認識ではなく、むしろ我々が一般に対象を認識する仕方〔…〕に関する一切の認識を超越論的〔transzendental〕と名付ける」、というものである(カント『純粋理性批判 上』篠田英雄訳、岩波書店、一九六一年、七九頁)。ここで言われているのは、超越論的と言われる認識は、対象の認識ではなく、認識の仕方の認識、つまり認識の認識である、ということである。認識が認識自身を認識するこの自己認識、自己との関係が、超越論的と言われることになる。
差異はしかし、自己自身の規定から差異化する。この運動を自己自身の内に回帰させること、つまり始まりと終わりの限界の規定を自己自身へと一致させ、円環的運動における自己の現前の同一性へと方向づけることは(方向については後で立ち戻る)、差異の消去である。その限りでは、差異と超越論とは折り合いがつかない。差異は、もしそれが超越論的自己と関係を持つとしても、自己からの差異化としてのみ関係を持ち、つまり自己との差異的関係をのみ持つ。差異の超越論的関係は、自己との差異的関係である。一方で超越論的関係が自己との関係であり、他方で差異的関係が自己との差異的関係であるならば、差異は超越論的自己関係を差異化する。
超越論的自己関係の差異化によって、もともと<対象の認識>から<認識の認識>へと移行していくものであった超越(トランス)の運動は、さらに、認識の自己関係(認識の認識)をも無限に差異化させ、つまり自己を他者へと開き、<差異についての差異>を常に問題化することになる。そうなると、例えば認識であれ、経験であれ、感性であれ、知性であれ、こうした差異化の運動を止めることはない(差異化はそれらのいずれによっても規定されえず、ターミナルを与えられず、対象化されえない)。むしろそれらは差異によって差異化される。デリダはこのような運動の場を少なくとも一度は、テクストやエクリチュールとして考えた。(先程の『余白』からの引用、差延がそれでないところのものつまり全てを標記しなければならない、という引用を思い起こしていただきたい。標記とはテクストやエクリチュールのことである。)我々が認識し、経験し、感性に与えられ、知性で把握する全てのものが、つまり何ものでもない差異が、むしろそれらを差異化しつつ、書かれたエクリチュールやテクストとして標記され、遺産となる。差異は、自己自身からの差異化の運動として、差異について書かれたエクリチュールやテクストの内に、つまり否定辞の反復と差異の無限の標記がなされたエクリチュールやテクストの内に標記される。そして我々はそれらの遺産を、差異についての差異として(差異について書かれた、差異の無限の標記の資料体として)継承する。しかしまた、差異がそれ自身ですでに、自己からの差異化として、他者への送付(テクストへ標記されること)であるのだから、差異についての差異(の無限の標記)であるテクストとは差異と異なるものではない。<差異についての差異>とは差異化であり、「についての」という形で差異が二重化(差異化)されることは、差異そのもの、差異が自己自身から差異化する働きそのものである。「についての」は差異であり継承である。差異は始めから、差異についての差異である。
だから差異「について」書いているこの私の文章は、差異の継承であり、また差異としての継承である。この文章は、すでに規定された差異を継承しているのではなく、この文章によって差異を継承すること自体が差異化の働きなのである。
だから差異の問題は、際限のない射程を持つ。というのは、差異を「問題」とすること自体が、差異「について」書くこと自体が、差異化の運動なのだから。(重複するが、「差異については、論じることについて論じる、という事態が起こる」。)私は差異「について」書くと述べたが、この書く行為即ちエクリチュール自身が差異化なのであれば、私が差異について書いているのか、或いは差異が私に書かせているのか、どちらか分からない。
この章をまとめれば次のようになる。差異は、自己自身からの差異化であり、自己との差異的関係を持つ(超越論的差異)。自己から差異化する差異は、差異についての差異へと送付され、差異について書くテクスト、差異について語るために無限の差異の標記をするエクリチュールへと送付される。それが継承である。反対に、無限の差異の標記をせず、差異を自己同一的な現前性へと回帰させることは、差異の消去であり、差異を継承しないことである。
3:2の補足
私が前章で「超越論的自己関係の差異化」という語を書いた箇所は、カントによる超越論的という語の定義の後であり、テクストへの差異の標記としての継承の議論の前である。したがって、両者の間に書かれたその語は、<超越論的議論を、継承の議論へと、別の語で言えば伝統の議論へと、移行させる>ものである。今の<>の一文をフランス語を交えて言い直すと問題が明確になる。<トランスセンデンタル(超越論的)議論を、トラディスィオン(伝統)の議論へと、トランスファー(移行)させる>。つまり、transという接頭辞が、差異化として、超越論から伝統つまり継承へと、我々の議論の焦点を移行させていたのである。移行としての差異化を、超越論的議論すなわち認識の自己関係に閉じ込めず伝統と継承の問題へと開くこと。これが、デリダの仕事の一側面であった。
そのことを示すテクストが二つある。いずれのテクストでも差異は戯れという語で言い換えられている。また、二つ目のテクストにはニーチェの名も登場する。ニーチェの目印2。
一つ目のテクストは『グラマトロジー』。(上巻、足立和浩訳、現代思潮社、一九八九年、一〇四頁)
簡単にまとめよう。<戯れが、領域内に、限界の内に、世界の中に、囚われているが、あることによって、この戯れを囚われから解放し、世界そのものの戯れへと、解放しなければならない。そのあることとは、超越論的問題の徹底化だが、これを換言すれば、超越論的問題(ここではフッサールとハイデガーの名が挙げられている)に、抹消記号を与えること、抹消線を引くことである。>
超越論的問題に抹消線を引くこととは、超越論的問題を線の問題へ、エクリチュールの問題へ書きかえることだと考えてよい。超越論的問題の徹底化とは、その問題をエクリチュールの問題へと書きかえることである。それによって、戯れ即ち差異は、世界の中の差異から世界そのものの差異となる。したがって、超越論的問題の徹底化=エクリチュール化とは、超越論的問題系の領域内に閉じ込められていた差異を解放させることである。
これは、「トランスセンデンタル(超越論的)議論を、〔…〕トランスファー(移行)させる」ことを意味する。ここではまだはっきりとは「トラディスィオン(伝統)の議論」について言われていない。そこで二つ目のテクストを引用しよう。『他者の耳』。(Jacques Derrida, L'oreille de l'autre, Montreal , VLB , 1982, p.95)
ここでははっきりと、かつては「世界の中の戯れ」と対比された「世界の戯れ」の言及に留められていた事柄が、伝統(トラディスィオン)の問題として語られている。(ただしもはや超越論的問題は積極的には言われていない。『他者の耳』の中の他の箇所に超越論的という語がないわけではないが。)
こうして我々は、デリダが、超越論的(トランスセンデンタル)議論の中で語られていた差異を、伝統(トラディスィオン)の問題へと、移行(トランスファー)させたことが分かる。
4:方向=意味
差異が自己自身からの差異化の働きによってテクストへと送付される際のその差異化の運動に関して、我々は先程(第二章のカントの箇所で)、「方向づけ」という言葉を用いた。「この運動を自己自身の内に回帰させること、つまり始まりと終わりの限界の規定を自己自身へと一致させ、円環的運動における自己の現前の同一性へと方向づけることは(方向については後で立ち戻る)、差異の消去である」。方向づけることは常に、運動を、運動の始まりにおいて目的として目指された終末の地点から、規制することである。このような、すでに与えられた目的と終末への運動は、円環的回帰の運動である。目的と終末へ方向づけることは、したがって、運動を自己への円環的回帰とし、自己自身から差異化する差異を消去する。
ところで、「方向」はフランス語sensと英語senseとドイツ語Sinnの訳語であるが、これらの語は「意味」という意味も持つ。したがって差異の運動を方向づけるとは、差異の運動を意味づけること、その運動に意味を与えることである。
例えばこうした方向づけ=意味付与においては、或る者の死は、その死によって他の者が生き残ったのならば、<他の者の生
こうした差異の消去へ至らない差異があるとすれば、その差異は常に自己からの無限の差異化として、生と死との差異(二項対立)を差異化し続け、つまり規定された始まりと終わり(生と死)の限界と区別を差異化し、常に生を死とし死を生とする差異である。
デリダはそれをla vie la mort、あるいはハイフンでつなぎla-vie-la-mortと呼んだ。フランス語でvieは生、mortは死である。laは冠詞であり英語のtheである。通常はtheのついた名詞が二つ並べられる(the life the death)ことはない。これを並べるのは、二つを同格としているからであり、だからこそハイフンで一つの単語であるかのようにしてつないでいるのである。日本語では「生死」あるいは「生即死」などと訳される。この語は例えばデリダのニーチェ論『他者の耳』などで現われる。ニーチェの目印3。
5:弁証法
差異化の運動に二つの意味(方向づけ・意味づけ)でのsensを与えること、つまり差異化の運動を自己への円環的回帰として方向づけ、自己の現前性への運動として意味づけたのが、ヘーゲルの弁証法であった。(この説明の仕方にはすでに問題があるのだが、それは後で述べる。)
さらにここでsensの三つ目の意味、つまり感覚、感性という意味が重要になる。感性的なものと叡知的なものを、死と生を区別しつつも、劣位の項である感性的なものと死に対して方向と意味とを与え(つまり三つ目のsensに対して一つ目と二つ目のsensを与え)、感性的なものと死を常に叡知的なものと生へと回帰させることによって、感性的なものと死とがそれらの対立項に対して持つ差異性を規定し、無限の差異化の運動に円環的終末の規定(ターミナル)を与えることで打ち建てられるのが、ヘーゲルの体系的弁証法、全体性である。弁証法にあっては、差異は全体性を超え出てはならない。差異は全体性の内で、自己の現前的同一性へと回収されなければならない。
したがって、継承の問題についてはこのように言うことができる、即ち、自己自身から差異化するという運動を持つ点で、一方の弁証法(即自が対自へ移行する)と、他方の差異化と継承とは、同じである。しかし、弁証法は差異化(叡知に対する感性の差異)を方向と意味によって規定する(ターミナルを与える)点で、無限の差異の標記である差異と継承とは異なる。弁証法は差異を全体性によって自己への回帰として規制するが、全体性それ自身を、つまり自己自身を差異化はさせない。しかし差異と継承とは、常に自己自身からの差異化である。
デリダは、弁証法によるこの差異の規定、つまり方向づけと意味づけを、終末「を目指して」の運動という形で表現した(「竪坑とピラミッド」『余白』)。「を目指して」とは、デリダの用いたフランス語の慣用句「en vue de 〜」の日本語訳である(英語訳では「in view of 〜」となっている)。デリダはこの「目指して」(en vue)に、三つの意味を与えている(同論文「記号学と心理学」の章の最後から二つ目の段落を参照)。目的(destination)と、距離(distance)と、視点(regard)である。
今述べた弁証法をこの三つの語によって換言すれば次の次第である:差異化の運動に「目的」を与えて全体性を超え出ぬようにし、また差異化の運動に「距離」を持たせることで、始まり(即時)と終わり(即時かつ対自)を区別し、また目的の地点から差異化の運動が辿る距離全体を見渡すための「視点」を、差異化の運動に与える、というものである。
こうして差異は、自己自身の現前的同一性の規定へ円環的に回帰する全体性の道程の内に回収される。こうしたことにおいては、差異は自己自身からの差異化としては継承されえない。また、継承それ自身も差異の自己からの差異化であったのだから、この弁証法の内では(何ものの)継承もされえない。差異化も継承も自己からの差異化としての他者への送付を規定され、自己へ回収される。
6:ヘーゲルの継承
しかし実はこのようなヘーゲルの全体性の説明には問題があることを前章の初めに述べておいた。「(この説明の仕方にはすでに問題があるのだが、それは後で述べる。)」この説明は、ヘーゲルの差異を全体性の内に回収する説明であり、その説明自身において差異の標記がなされていない。他方で私は、第二章で「差異については、論じることについて論じる、という事態が起こる」と述べた。差異を論じる(説明する)仕方が論じられなければならない。差異を論じる仕方は、すでに述べたように否定辞の反復と差異の無限の標記としてのみ可能である。差異について論じるその論述に差異を導入しなければならない。
このことをまず超越論的問題に沿って言えば、上述のヘーゲルの全体性の説明においては、デリダが述べた超越論的問題の徹底化が不十分であった。つまり認識の認識、差異についての差異という形で、説明は自己との差異的関係を、説明の自己自身からの差異化を徹底しなかった。次にこのことを「en vue」の三つの意味に沿って言えば、その説明は説明自身に対して、ヘーゲル弁証法の道程(「距離」)の全体を見渡す「視点」と「目的」地点(ヘーゲルの思想が全体的に見えるターミナル)とを、与えてしまったのである。
我々は、冒頭で「差異を如何にして継承するか?」という問いを叩き台として提示した直後に、この問いが、継承に先立ってまず差異は規定されているという誤解を聞き手に与える可能性のあるゆえに批判・検討されなければならないことを述べた。差異は継承に先立って規定されている継承の対象ではない。差異は対象化されない(これはカントの箇所でも述べた)。ところが、先程のヘーゲルの全体性の説明においては、差異を弁証法的全体性の内に回収し、説明の対象にしている。これはヘーゲルの差異を継承しないことである。したがって、或る思想家(例えばヘーゲル)を継承することは、その思想家の思想を対象化することではなくて、その思想家の差異を差異化させることである。
そしてデリダの仕事こそ、これであった。つまり、デリダは方法と対象とを恐らく一度も区別したことがないが(この区別がすでに形而上学的であるから)、強いてその区別にしたがえば、まず方法に関してデリダは、否定辞の反復による無限の差異の標記としてのテクストを書き続けた(これについては先に二つの引用をした)。差異についての論じ方・説明の仕方において、方法において、差異を導入した。次に対象に関してデリダは、彼が論じる思想家について、その思想家の思想が全体性の下に規定され対象化されるものとは考えなかった。彼は、思想家たちが自分たちの思想的体系や全体性の内で差異を二項対立によって規定したのと異なり、差異を差異化させ続けたのである。例えば初期デリダのヘーゲル論「限定経済学から一般経済学へ ――留保なきヘーゲル主義――」(『エクリチュールと差異』)とは、差異をヘーゲルによる限定と留保から一般的なものへと解放する試み、差異を差異化させ続ける試みである。
すると、本章のタイトル、「ヘーゲルの継承」とは、冒頭の叩き台の問いと同様、次のように批判・検討されなければならない。このタイトルは、ヘーゲルが、継承に先立って規定されているという誤解を与える可能性がある。そうでなく、ヘーゲルを差異として思考し直さなければならない。ヘーゲルは弁証法的全体性ではなく、差異の自己からの差異化であり、ヘーゲルを継承することは、その差異化の働きそのものである。
超越論的議論の徹底化により世界の中の差異が世界そのものの差異とされることで伝統(継承)の問題へと移行するように、ヘーゲル弁証法の徹底化によりヘーゲルの中の差異がヘーゲルそのものの差異となり、ヘーゲルの継承としての差異とならなければならないのである。
(デリダの『弔鐘』はそうした仕事であった。このテクストが始まりも終わりもなく、文の途中から始まり文の途中で終わるのは、弁証法的差異の道程に対し起源と終末との円環的一致の規定を与えず、ヘーゲルの弁証法の中の差異を弁証法そのものの差異へと移行させるためである。そして今の我々の叙述もまた、デリダの『弔鐘』を論じ継承するためには、そのテクストには始まりも終わりもないという形で否定辞の反復によって差異の無限の標記を行わねばならない。)
7:両氏の文章の継承1:三つの視点
以上のことを踏まえて、岡田さんと広坂さんの四つの文章を読む。この読解は四つの文章の継承である。
ところで継承は、対象として規定されたものの継承ではなく、差異の自己自身からの差異化としてのみ可能であり、四つの文章の継承は、無限の差異の標記によって、四つの文章の内で働いている差異化の運動を徹底させることで、差異を自己自身から差異化させなければならない。では四つの文章で論じられていた差異とはどのような差異か? それを追跡することが、読解の要となる。
***
広坂さんの一つ目の文章「神話劇を見る視点」から始める。(この順序については後に述べる。)
タイトルによれば、この文章は「視点」について書かれたものである。では何の視点が問題となっているのか? 幾つかある。
一つ目。広坂さんは、今村の著書の二つの注から、山口のスケープゴート論が今村社会哲学を先取りしているという「見通し」を得る。
二つ目。この文章の第三章のタイトルは「見世物としてのニュース」であり、見世物を見る「視点」が問題となる。そして次章では、山口においてその見世物が何であるかが書かれている。「それでは、山口の言う見世物=政治とは何か。一言で言えば、人身御供の儀式である。儀式であるから、数の多少にかかわらず観衆がいる」(広坂1−4)。したがって、二つ目の「視点」は<人身御供を見る観衆の視点>である。
三つ目。第七章のタイトルは「スケープゴート論の視座」である。したがって今度はスケープゴート論を唱えた者つまり山口の「視点」である。広坂さんはそこで、「スケープゴート現象による直接的被害者の立場はつねに深い同情に値する」という山口の言葉を引きつつも、しかし山口が「文化の根源的な活力を保証する仕掛けの一つ」としてスケープゴート現象を位置づけ、文化を根源的に説明するものとしてのスケープゴート論を手放さないことに留意している。そのような山口のスケープゴート論の「視点」は広坂さんにとって「非道徳的」なものである。しかし非道徳的というのは、反道徳的なのではなく、非道なのでもない。それは「視点」が単に道徳的次元にはないということ、つまりその「視点」には道徳との差異があるということだ。この差異を広坂さんは「棚上げ」と呼ぶ。そして広坂さんは、この非道徳的視線にしたがって進むことを選ぶ。
こうして三つの「視線」すなわち、広坂さんの「見通し」、人身御供を見る観衆の視点、山口のスケープゴート論の「視座」が、一つの視線に同一化されるとまでは言わなくとも、協働していくのが分かる。
次章のタイトルは「「スケープゴート論の系譜」について」であり、三つの「視点」は山口の「系譜」を辿り、フレイザーへ至る。最終的に、広坂さんはフレイザー『金枝篇』の序文と附録から、フレイザー自身が認めた或る思想家との「一致」によって、この「系譜」の追跡を止める。その思想家の名は最終章に書かれている。「フレイザーとヘーゲル」、つまりヘーゲルである。
ここに至って、初めに「見通し」を立てた広坂さんの「視線」は、二つの「視点」と協働しつつ、「系譜」を「発見」(この語は「視点」を連想させる広坂さんの語だ)し、その系譜を見渡せる「視点」に立った。ヘーゲル弁証法がそれである。今村、山口、フレイザー、ヘーゲル、という道程を広坂さんはまとめる。
したがってこのヘーゲル弁証法の位置から後ろを振り返れば、その視野の内に今村、山口、フレイザーの「系譜」が収められることになる。
8:両氏の文章の継承2:四つの視点
ヘーゲルに至り我々は次の問いを立てる:広坂さんが明確には数え上げていないもう一つの視点があり、広坂さんの道程においては三つの「視点」がその四つ目の視点へと重ねられていくのではないか? 我々が論じて来た次のことを考慮に入れるならば、三つの「視点」の辿りついたヘーゲル弁証法の地点においてそれらが第四の視点へ重ねられていくと考えるのは不可能ではない、即ち、ヘーゲル弁証法そのものが、その内に全体性を眺める視点を、「en vue de 〜」(を目指して)を、持っていたということ(私の文章の第五章)を考慮に入れるならば。この第四の視点は、「絶対知」「我々」「理性」などと様々に言うことができるだろうが、少なくともヘーゲルの視点である。
この視点から振り返ろう。先程述べたように「このヘーゲル弁証法の位置から、後ろを振り返れば、その視野の内に、今村、山口、フレイザーの「系譜」が収められることになる」。したがって、感性的(sensの第三の意味)死を他の者の生のための死として、方向づけ意味づけ(sensの第一・二の意味)るヘーゲル弁証法の視点からは、次の三つの「視点」が見るものを見渡すことができる、即ち、スケープゴートの人身御供の犠牲から文化を根源的に説明する山口の非道徳的視点や、その観衆の視点や、その「山口の非道徳的な視線が見るものを追おう」とする広坂さんの視点が見るものを。広坂さんは第四のヘーゲルの視点に至り、三つの「視点」を振り返ることになった。
すると、広坂さんが「見通し」から初めて「非道徳視線」を追い「系譜」の根を「発見」した時、ヘーゲルは逆に広坂さんを見ていたのである。だが両者が見つめ合ったというだけでは十分ではなく、広坂さんは初めから(ヘーゲルを名指しする前から)ヘーゲルの視点からこそ今村や山口を読んでいたのだ。広坂さん自身が述べるように、「今村社会哲学の第三項排除効果論、山口人類学のスケープゴート論〔…〕は、ヘーゲル弁証法のパラダイムに乗っていたのである」(広坂1−9)。「発見」に至り両者が見つめ合うよりも先に、広坂さんの追跡の道程は初めからヘーゲルのパラダイムに乗っていた。広坂さんの視点は初めからヘーゲルのそれであった。すると、両者の「見つめ合い」とは、他者との視線の交差ではなく、むしろ広坂さんがもともと自分が乗っていたパラダイムを自覚するということ、自分自身の視点を自分で見る(自分の目を自分の目で見る)ということを意味する。
ここで、二つのことを想起しておきたい。第一点目。こうした見ることを見ることは、先のカントによる超越論的という語の定義の際に確認した、超越論的認識、即ち認識の認識と、形式的に一致している。つまりここで広坂さんは、ヘーゲルの超越論的弁証法の視点に、いわば絡め取られている(この言い方には問題があるが、後ですぐに述べる)。(こうした、カントからヘーゲルへ続き、またその先(フッサール)へと続く超越論的議論を整理した仕事として、熊野純彦『ヘーゲル <他なるもの>をめぐる思考』(筑摩書房、二〇〇二年)に収められた「補論一 ヘーゲル反省論の位置 ――超越論的哲学の流れのなかで」を参照することができる。)第二点目。ヘーゲルについて、乗り越え不可能であると述べたデリダ(『ポジシオン』)は、初期に比べると次第にヘーゲルへ言及する機会を減らしていくのであるが、しかしその後も、例えば反省あるいは反射(reflexion、eにアクサンテギュ)という語によって(他の例も多数あるが)、ヘーゲルの名を出さずともその問題系に議論を関わらせ続けた。その一例として、増田一夫訳「ネルソン・マンデラの感嘆あるいは反省=反射の法則」『この男、この国――ネルソン・マンデラに捧げられた14のオマージュ』ユニテ、一九八九年を参照することができる。
最後に三つのことを考慮しつつ、広坂さんの一つ目の文章を離れることにする。
一つ目。これらの視線は、もし四つとも重なっているのだとすれば、いずれも、「道徳感情」を「棚上げ」した「非道徳的な視点」であることになる。しかしこれは、山口、観衆、またそれを追う広坂さんの「視点」については当てはまっても、ヘーゲルの視点に当てはまるかどうかは留保しなければならない。ヘーゲルの述べる「我々」の視点は、まさに人倫(Sittlichkeit)の視点なのであり、倫理的な問題を棚上げしてしまっては得られない視点なのである。ただしこれには次の留保が続く、即ち、人倫が道徳的な体系であったとしても、その体系外に排除された他者(そうしたものが仮にあるとして)に対する倫理は、ヘーゲルの体系では問題とされえない、という留保が。これについては岡田さんの文章ともつなげて後ほど少し言及しよう。
二つ目。広坂さんは、この視点の追跡を、どこまで、いわば真摯に、本気で、あるいは自覚的に、やっていたのだろうか、という疑問は残る。広坂さんは文章の最後で述べている、「私がこう言ったからといって、そんなことで今村や山口を批判したつもりか、ましてやヘーゲルを...、などとはどうかお考えにならないでいただきたい。私としては、実に素直にヘーゲルの影響力の大きさ、洞察力の深さに感嘆しているだけなのだから」(広坂1−9)。(洞察力という、また視点を連想させる語があることに注意。)自身の文章は弁証法と等しいなどとは述べておらず、ただ感嘆しているだけだというのである。すると広坂さんの追跡は、私が書いたことに反して、つまり<ヘーゲル的弁証法をそれと知らずにヘーゲルと共に辿り、ついに自身のパラダイムと自身の視点を掴み、自身について知の知あるいは超越論的認識を手に入れたもの>ということに反して、むしろ、喩えてみるならばヘーゲルの肩に乗り、困難な道のりを歩かず視点だけを借りて、ヘーゲルの「洞察力」の深さを知るためのものであったかもしれない。広坂さんはその文章の冒頭で「浅薄かつ散漫におしゃべりしてみたい」とも「一知半解の駄弁」とも書いた。これをヘーゲル弁証法と見つめ合うもの、視点を共有するもの、さらには絶対知と重なるものと考えるのは、それこそ、ヘーゲル弁証法の持つ差異の掴みがたさを度外視し、広坂さんをヘーゲル弁証法の内に、はみ出すことなく位置づけられると思考する者の陥穽である。私は広坂さんが弁証法的視点に「絡め取られている」と書いたが、まさにそのように広坂さんを読むこと自体が、弁証法と広坂さんとの差異、また両者それぞれが持つ差異を思考しえない現前的同一性に絡め取られた読解なのである。それは差異の消去であり、広坂さんを継承しないことである。
(広坂さんが意図的に私を罠にはめた(その追跡をヘーゲルの足取りに似せ読者に弁証法的道程を歩ませつつ、最後にはただ感嘆しているだけだとして弁証法を突き放し、それまでの道程を弁証法と同一視させて差異を消去させた)わけではないが、広坂さんのテクストに罠にはめさせるものがないわけではない。恐らくここではもはや、罠と欺き、換言すれば嘘を、何ものかの主体的意図と意図的行為に還元することは不可能である。差異が差異自身から差異化するのと同様、差異であるテクストはテクスト自身に嘘をつき自身を取り逃がすのである。この、言語あるいはテクストの、自己自身に対する差異あるいは嘘については、例えば、言語が語る(あるいは言語が言語する、Die Sprache spricht)というハイデガーの定式を、言語は(自己に/を)語り損なう=約束する(Die Sprache verspricht (sich))と書き変えたポール・ド・マンの議論の射程を検討すべきであるし(例えばデリダは『メモワール ポール・ド・マンのために』や『精神について』でそれに触れている)、また、自分自身に嘘をつくということについて若干の考察をしたデリダの『嘘の歴史』を参照すべきであろう。そこでは形而上学の歴史を「ある錯誤の歴史」として読むニーチェのテクスト「いかにして「真なる世界」がついに作り話となったか」が取り上げられている。ニーチェの目印4。)
三つ目。したがって、今までの議論からは離れ、改めて弁証法の内に、また広坂さんの文章の内に、現前的自己の同一性によって規定されえない無限の差異の標記を導入しなければならない。そしてそのことを実践しているのが、岡田さんの文章である。我々は、岡田さんの文章へと移る。
(私がなぜ岡田さんと広坂さんの四つの文章の内三つ目から始めたか、その順序の理由は、私の方法が否定辞の反復と差異の無限の標記としてのみ可能であるという点にある。即ち、私は広坂さんとヘーゲル的全体性が同じであるとは言えず(それは差異の消去だ)、両者は異なる、あるいは同じではない、という形でのみ、広坂さんを継承しうる。しかし広坂さんは全体性ではないと否定するために、否定に先立って全体性が与えられていなければならない。私は全体性の内に回収された広坂さんをまずは提示するために広坂さんの文章から初め、次にこの私の読解が誤りであることを示す形でこの全体性に否定辞を標記したのである。これら一連の議論の流れは大きな差異の標記である。またなぜ岡田さんの文章を全体化せず広坂さんのそれをそうしたかだが、それは四つの文章の内で広坂さんのこの文章が非常に綺麗にヘーゲル的系譜の内に各視点を秩序立て全体化させうるものだったからである。)
9:8の補足
ここで、一つの語と文脈を、補助線として敷く。その語は二義性であり、補助線とは形而上学の克服である。
私は、広坂さんの議論の足取りが、ヘーゲルの弁証法に絡め取られる可能性のあることを指摘したが、そしてその限りでは広坂さんの文章を批判したと言えなくもないが、しかしそれは、ヘーゲル弁証法を全体化し広坂さんをその内で全体化することで、私の論述もまた弁証法に絡め取られることによってであった。ある言説について批判するためには、批判する当の言説自体もまた、批判されるものの次元の内に絡め取られなければならない。もし批判する言説が批判される言説の全く外部に立ち、批判される言説の論理と異なる論理をその外部で展開するだけであれば、二つの論理の独自性が認められるだけで、一方が他方に対して批判することはできない。したがって、批判する言説は批判される言説に対して内在的にその批判を展開しなければならず、そのことによって、批判をする言説は批判される言説の次元に絡め取られなければならないのである。その時批判する言説は批判される言説の内外に分割され二義性を帯びることになる。
ハイデガーは形而上学の克服(形而上学つまり主導的問いから、形而上学とは異なるものつまり根本的問いへの移行)について、次のように言っていた。「移行的思考においては、<形而上学>についてのすべての語りは二義性〔Zweideutigkeit〕を帯びる」(大橋良介、秋富克哉、ハルトムート・ブフナー訳『哲学への寄与論稿』ハイデッガー全集第六五巻、創文社、二〇〇五年、一八一頁)。
するとヘーゲルについて語る言説が、形而上学に陥らずにそれと異なるものへと移行し、ヘーゲルの弁証法の中に閉じ込められずにその体系の外へ出て行くのならば、その言説そのものが、二義性を帯びなければならない。
ある思想の継承では、継承自体が、差異の自己からの差異化として、無限の差異の標記とならなければならないのだが、二義性とはこの自己自身からの差異化である。するとヘーゲルの弁証法自体も二義性を帯びることになる。形而上学的弁証法は、形而上学的でありかつその他者でもある二義的言説によって語られることで、形而上学として語られ(批判され)ながらも、同時にそれと異なるものの次元へと移行させられることにもなるのである。
岡田さんの文章の一部分にはこうした事態が見られる。
10:両氏の文章の継承3:可変性
先程の私の読解は広坂さんもヘーゲルも継承せず、ヘーゲルの差異を弁証法の中で全体化し、広坂さんの文章中の差異をその弁証法の中にまた全体化する読解である。これは岡田さんがその一つ目の文章(「ヘーゲルの「不在」が意味するもの ――記号と埋葬1」)で批判を向ける、柄谷行人によるヘーゲルの扱いと等しい。
岡田さんはここで、ヘーゲルを他の思想家の「なかにすっぽり包み込んで」しまうことで、他の思想家「から隔てるもの」を認めない柄谷のヘーゲルの継承に対して、批判している。これは差異の消去であり、ヘーゲルの継承としては不適切である。
またその後には、柄谷は構造主義と共に批判される。「柄谷の言説は、〔…〕構造主義的なものの域内に留まったと思われるのだ」(岡田1−5)。
こうしたヘーゲルの継承に対する批判は、二つ目の文章「グラフスの微笑 ――宿命と偶然(記号と埋葬2)」にも続くが、今度は今村が、しかし再び構造主義と共に、批判される。
ここで紙幅のため私なりの言葉で、岡田さんの批判の要点を説明させていただく。岡田さんがいう「構築」は、構造主義の構造と、ポスト構造主義の力や流れとの、いわば<間>にある。構築は、一方で、それが歴史的実践である限りで、構造主義的構造(それは非歴史的である)と異なり、他方で、それが構築的である限りで、今村などのポスト構造主義の力や流れ(それは構築しない)と異なる。たしかに今村はポスト構造主義的観点から構造主義を批判し、その限りで両者は対立するが、両者は、両者のいわば<間>を見れていない。つまり、後者の構造に前者の力と流れを与えたもの、構造に運動を持たせたもの、すなわち構築(構造化とも言えよう)を見れていないのである(言うなれば構築とは、名詞的構造の動詞化だということになろう。構造を構築するとは言い得ても、構築を構造するとは言えない)。
このような整理の仕方には岡田さんが納得しない部分があるかもしれない。あるとすれば、私が今村の力や流れを、「運動」や「〜化」(構造化、動詞化)と言い換えることで、「可変性」(「改変の可能性」とも言う)を与えているという部分だろう。岡田さんからすれば可変性はヘーゲルの「偶然」にあるのであって、今村にはない。今村はむしろ力や流れを結局のところは「自然史的必然性」つまり改変の不可能性に結びつけるのである。
しかしこうした、私のやや乱暴な説明に対する岡田さんの可能な批判によって、岡田さんの議論の要点が明確になったと思われる。思い切って言えば、岡田さんの要点は可変性であり、この観点から、一方で自然も文化も、他方で宿命も運命も、論じられる。またこの可変性によって岡田さんは、ヘーゲルの体系、全体性に対して、差異を導入しようと試みるのである。
まず前者の自然と文化に関して言えば、岡田さんの批判の要点は、次のことにあるのではない、即ち、文化的な制度としてある力や暴力(たとえば資本主義経済)を今村が自然史的必然性として
まず自然(物質)の可変性の主張:「生の在り様の根本的な改変の可能性、ただしその物質的な条件そのものを変えていく可能性」(岡田2−5)、「ヘーゲル及び弁証法的思想の決定的な意義は、〔…〕生を規定する物質的な条件〔…〕をテーマに据えたということだ。それは、この基礎的な条件が、人々にとって変更可能なものであるという考えを可能にする」(岡田2−7)。次に文化(公共空間とそこからの排除)について:「「概念化されるもの」と「されざるもの」、排除によって形成される同一的な空間(公共空間)の内部に属する者と、その外部に排除される者といった二項対立的な図式だけを強調することは、この二項対立(排除のシステム)そのものを抗えない現実(宿命)のように考えさせて、人々の行為をその宿命の甘受へと向かわせる」(岡田2−5)。
次に後者の宿命と運命であるが、これはすでに、今の引用(公共空間とそこからの排除を宿命と考えさせることに対する批判)で語られていた。宿命もまた可変性を消去するものである。宿命には回収され得ない運命が、偶然が、確保されなければならない。
11:両氏の文章の継承4:両義性
ヘーゲルの継承において岡田さんが重視するのは、自然でもなく文化でもなく(否定辞の反復)両者の可変性であり、また可変性を消去する宿命とは異なる運命と偶然に関しても、その偶然が「先取りされた」「記号にすぎない」(岡田2−7)偶然であってはならない、ということになる。(先取りという語は広坂さんの文章でも今村と山口を関係づけるものとして使われていた。先取りは円環の運動を働かせるものであり、方向づけあるいはen vue de 〜である。)
「真の偶然」(岡田2−5)と「先取りされた」「記号にすぎない」偶然との間で、偶然の概念が「すり替え」(岡田2−7)られることになるのだが、最終的に岡田さんはそうした「すり替え」の原因を、ヘーゲルの思想そのものの内に認める一文を書くことになる。そこで登場するものが「両義的」という語である。
まとめれば次のようなことである:自然でもなく文化でもなく、両者に可変性を与えることで、どちらにおいても停止せずに両者の間を可変性によって常に移行し――つまり一方で文化(公共空間や排除のシステム)を必然化するものに対しては自然(物質)の可変性を唱え、他方で自然史的必然性に対してはそれが実のところは文化的な制度であり構築されたものであることを唱え(「実際にはその「暴力」には政治的・時代的な刻印が押されているはずである。つまりそれは、他ならぬ現代資本制社会の「暴力」のはずであり」(岡田2−2))、そしてその限りでは自然と文化との間で否定辞を反復することにほぼ等しいと私は思うのだが(岡田さんはどうお考えか分からないが)――、次にその可変性は、可変性を消去する宿命には回収されない運命と偶然の内に探されるが、しかしさらにまたその偶然概念がすり替えられる原因をヘーゲル思想の両義的性格に帰せることによって、可変性と偶然性が宿命に捕らえられるか否か、ヘーゲルの体系と「予定調和」(岡田さんの語)の先取りに捕らえられるか否かという問いが、依然としてヘーゲル自身の思想の両義的性格に懸けられることになる。
ヘーゲルの体系的宿命を変え得る(可変)か否か、体系的宿命に取り込まれ得ないその外部の問いは、依然ヘーゲルの内部において立てられている。外部と内部の狭間で最後に辿りついたこの両義性こそは、第九章で述べたハイデガーの「二義性」と近いものだろう。そこでは、形而上学をめぐる言説が、形而上学とその他なるものとの間で二義性をおびると言われたように、岡田さんの偶然の概念は、それがヘーゲルの予定調和の宿命に可変性と偶然性を導入するためには、ヘーゲルの体系の外部に留まることはできなかったからこそ、最終的に岡田さんはヘーゲル思想の両義的性格に自らの企図の可能性を見たのである。ヘーゲルの予定調和と宿命にとりこまれないためには、しかしその可能性をヘーゲルの思想の内に持たなければならない。
したがって、岡田さんの試みは、ヘーゲルの思想自体の中に、その思想の体系内の予定調和によっては規定されえない両義性を導入し、それによって、ヘーゲルの思想を思想自身から差異化させる試みであったことになるだろう(ここで私は岡田さんの論じた可変性を私の論じた差異化として捉えている)。ヘーゲルをヘーゲル自身から差異化させるこの継承こそは、我々が論じて来た、差異の差異自身からの差異化としての継承であるだろう。
しかしそうであるためには、この両義性はまた無限の差異の標記でなければならないと私は考える(岡田さんはどうお考えか分からない)。この無限の標記を、両義性という語によって終えるのであれば、恐らくこの両義性は(他の語でもそうだが)、いずれは弁証法(それは必ずしもヘーゲル弁証法ではなく岡田弁証法と言われるものになるかもしれないが)の内部での、最終的には現前的同一性へと回収される差異として、規定されて(ターミナルを与えられて)しまうように思われる。岡田さんが正当にも文章の最後に予告した承認論の問題について言えば、常識的には承認こそ否定(辞)と対立するものと思われるが、私の以上の考えを踏まえると、いかにして承認論は、否定辞の反復としての差異の無限の標記によって論じられる承認論となりうるだろうか? ヘーゲルの承認論の内でいかにして現前的同一性へと回収されない差異を思考しうるか? 岡田さんが時に使う「人々」という語をヘーゲルの「我々」(これはヘーゲルにおいて単に記述のための一人称なのではなく、絶対的実体としての「我々である我、我である我々」であり、承認によってこそ可能となる)の宿命と先取りからいかに差異づけるか? 私自身も考えなければならない課題である。
12:両氏の文章の継承5:宿命と棚上げと差異(化)
一見すると今までの論述は、広坂さんのヘーゲル読解を弁証法の内に捕らえられたもの、反対に岡田さんのヘーゲル読解を弁証法に差異を導入するものと見なしているように思われるかもしれないが、しかし私の意図はそうではない。両者とも、ヘーゲル弁証法の全体性に対しては、ある観点から批判的距離を保っている。そしてその観点が私には重要と思われる。しかし両氏とも、それについて言及をしているのは僅かにであり、詳細な議論を展開してはいない。それ故私の議論も控えめなものとならざるをえない。したがって、この文章の最後に、この観点から、両氏の文章を継承する方途を僅かに探ってみたい。
私含め三者の言葉で端的に言えば、「ある観点から」見られたその問題とは、差異化の運動を規定するもの(ST)、二項対立を宿命とするもの(岡田)、道徳感情の棚上げ(広坂)であり、これらの問題を見るその観点は、あえて私の言葉で言えば、再び、超越論的差異、ということになる。
二項対立を宿命とする、或いは道徳感情を棚上げする――これらの語は両氏のいずれにおいても、政治的、倫理的、道徳的な差異を、その全体性(これは私の語である)において記述することを両氏が問題とする箇所で登場する。それらの箇所を確認しよう。(ここで断っておかねばならないことは、そもそも差異が「倫理」的あるいは「道徳」的あるいは「政治」的な差異であると性格づけられていたのは何故かという問いには、私は関われないということである。私は議論をその先に進めたい。)
まず岡田さんから。「その「暴力」には政治的・時代的な刻印が押されているはずである」(岡田2−2)。これは、「近現代の社会における「第三項排除」の主要な形態」としての「資本制経済」を、今村が「自然史的必然性」とし、「一個の実体として、現実の社会関係の外部にある原理のように語」っていることに対し、岡田さんが暴力に刻印されているはずの政治的性格を想起させる一節である。この一節は次の一節とともに読まれなければならない。
つまり、二つの一節を合わせてまとめれば、こういうことだ:今村は、二項対立的差異を、宿命・必然性・実体・原理として語り、記述している。その語りと記述は、等し並みにすべての個体を、つまり二項対立の両項を、つまり弁証法の全体を、含む。その語りと記述が、改変の可能性を隠す。
岡田さんがここでしていることは、弁証法を全体化する宿命を、今村にしたがって実体とは考えずに、その語りと記述の次元に引き戻すことである。全体性についての語りと記述こそが、全体性をもたらすということである。語りと記述に先立って全体性があるのではない。
次に広坂さん。広坂さんの二つの文章のいずれにも棚上げという語が登場する。「山口はそうした心理レベルでの道徳感情はとりあえず棚上げして事態を見すえようとする。道徳(倫理)が感情のレベルに尽きるものかどうかは議論の余地があるが、今はそのことはさておいて、山口の非道徳的な視線が見るものを追おう」(広坂1−7、ただしここでの「道徳」という語は広坂さんの語でなく山口からの引用である)、「当事者性や倫理的な問いを棚上げにして、死の意味すら語ることができるのも世界劇場論的思考の利点である」(広坂2−5)。
一つ目の引用は、一つ目の文章の七章に登場する。その二章手前に山口の理論(ヴァルネラビリティ論)の「陥穽」「弱点」が書かれている。「ある事件について、被害と加害を相関的なものととらえて事態の全体像を描写するのは結構だが、そのことに当事者が「共同の責任」を負わされてはかなわない。事態を描写する論理と事件の評価とが入り混じっているのである。この弱点は〔…〕」(広坂1−5)。先程の岡田さんの一節から我々が導いたこと、即ち、「全体性についての語りと記述こそが、全体性をもたらすということ」と同様に、ここでも、「全体像を描写する」ことが、「「共同の責任」を負わ」せると言われている。語り・記述・描写が問題とされている。
さて、広坂さんはここで、「事態を描写する論理と事件の評価とが入り混じっている」ことを山口の「弱点」としている。これについては次の問いが立てられるだろう:一方の、広坂さんが推奨しているように思われる分割、すなわち事態の描写と事件の評価を分けることは、他方の、別の箇所(広坂1−7)で広坂さんが差し当たって追従する山口の視線の性格が持つ分割、即ち「事態を見すえる」「視線」とその視線から「棚上げ」される「心理レベルでの道徳感情」との分割と、同じものであるか否か? 事態の描写あるいは事態を見すえる視線は、事件の評価あるいは道徳感情を、棚上げするべきか否か? 広坂さんは、或る箇所(広坂1−5)では「入り混じ」りを「弱点」としながらも、つまり分割を推奨しながらも、別の箇所では「棚上げ」する「非道徳的な視線」を「恐ろしい認識」(広坂1−7)と呼ぶ。広坂さんは、この問題についての結論を保留する。「はたして、山口人類学から、その長所である共同体の力学を描写する論理だけを抽出しえるか。またそうすることに意義があるか、簡単には結論の出ないことのように思う」(広坂1−5)。しかし我々は、この問題に貢献すると思われる僅かの意見を述べたいと考える。その意見の観点は、私が先程あえて述べた「超越論的差異」というものである。そしてそれは、両氏に反し私だけが持つ観点ではなく、この私の文章が両氏の継承である限り、両氏の文章から取り出される観点なのである。
広坂さんの二つ目の引用に移る。「当事者性や倫理的な問いを棚上げにして、死の意味すら語ることができるのも世界劇場論的思考の利点である」(広坂2−5)。ここで、だいぶ前に、感性(sensの三つ目の意味)と死とに意味と方向と(sensの一つ目と二つ目の意味)を与えるのが弁証法だと書いたことを思い起こしていただきたい(第五章)。そしてその意味づけと方向づけは、弁証法の全体性を見る視点(en vue de 〜)においてなされるのであった(同章)。つまり死の意味づけは全体性を見る視点によってなされる。また、広坂さんの一つ目の文章では、ヘーゲルを含めて四つの視点が重ねられていくのだが、その内には人身御供を見る観衆の視点があった(第七章)。また広坂さんは、世界劇場論的思考において作品が成り立つためには、作品が意味を持った全体性であることの必要を述べている:「作品世界は、それを構成する要素の一つ一つが互いに有機的に関係し合って、各要素が全体のなかで意味のあるはたらきをしているような秩序ある全体である」(広坂2−5)。まとめれば次のようになる:死に意味が与えられることで全体性がもたらされるが、それは倫理的な問いを棚上げにした観衆の視点においてなされる。
宿命と棚上げという語を含む両氏の一節を読むことで明らかになったのは、次のことである。<政治・道徳・倫理的問題を隠蔽あるいは棚上げするのは、宿命づけられた全体性であるが、しかしその全体性は、語り・記述・描写・視点によって与えられるのであり、それらに先立ってあるのではない。そして両氏がなしたことは、宿命づけられた全体性を、それらの次元に引き戻すことである。>
そして私は、この< >の内の「しかし」以下を、私の語によって置き換える。<差異化の運動を規定し差異を消去する全体性は、差異の継承において与えられるのであり、継承に先立ってあるのではない。全体性を、継承における差異の消去の次元に引き戻さなければならない。>このことを理解せずして、継承に先立って全体性が与えられていると思考することは、それ自体が差異の消去であり、継承をしないことなのである。上述したように継承は、それに先立って規定された(と考えられた)もの(つまり全体性)の継承ではなく、それ自体が無限の差異の標記となることによって、その規定を(つまり全体性を)差異化させる差異の運動でなければならないのである。
そして、継承それ自体を差異化するということは、超越論的差異が持つ、自己との差異的関係によるものであった。論じ方について論じ、差異の継承の仕方自体に差異を導入し、継承それ自体を差異化するこの自己関係は、両氏の語でいえば、政治・道徳・倫理的問題を隠蔽し棚上げする語り・記述・描写・視点それら自体の政治・道徳・倫理性を問うということである。両氏が、超越論的差異に着想を得ることで、この隠蔽と棚上げの問題に何かしらの貢献ができるとすれば、政治・道徳・倫理の問題を不問に付す全体性それ自体の政治・道徳・倫理性を問いに付す、という形によってではあるまいか?
そのように問われた時、政治・道徳・倫理は、無限に自己自身と差異的関係を持つことになる。差異が、差異として規定された自己自身から常に差異化することであったように、政治・道徳・倫理は、或る全体性の内に取り込まれ或るいは全体性から排除されること自体の、政治・道徳・倫理性を問うものとなる。超越論的差異にならって、やや奇妙であるが、超越論的政治、超越論的道徳、超越論的倫理と言うことができる。
ここに、第八章の最後に書いた三つの考慮の第一点目が関わって来る。ヘーゲルの体系は、それ自体が人倫の倫理的共同体だが、しかし体系の外に排除されたものへの倫理は、その体系の内部においては問えなかった。したがって、倫理は、倫理を体系内に取り込むこと自体の倫理、あるいは倫理を体系の外に排除すること自体の倫理を、問うものでなければならない。(ヘーゲル的全体性を批判しその外部の無限的他者の倫理を思考したレヴィナスはこうした文脈で読まれ得る。)
また、先程の問題、広坂さんが結論を留保した問題(広坂1−5)に対する貢献を、広坂さん自身の文章から、取り出すことができる。事件の評価と道徳感情の問題は、それらが倫理・道徳的問題であるならば、事件の評価から分割される事態の描写それ自体の、また道徳感情を棚上げする非道徳的視線それ自体の、つまり倫理・道徳の分割と棚上げそれ自体の倫理・道徳性を問うものとなる。(なお、広坂さんは文章の終盤で次のように述べている、「もし、私たちが、カーニヴァル的世界感覚の対極にある日常性の意識(木村)、平凡な複雑さ(丸谷)、言いかえれば、正気を維持することにつとめなければ、私たちはカーニバルの法則の支配に従って生きることになるわけだが〔…〕」(広坂2−7)。木村については触れることができないが、丸谷の言う平凡な複雑さとは、世界劇場論的思考の解釈の多面性のことであった。広坂さんによれば、この思考は作品つまり劇場と「距離を取る」(広坂2−5)ものであるのだから、カーニバル的世界感覚のいわば歯止めとなるのである。しかし広坂さん自身が認めていたように、この思考は解釈者の視点から見た作品の全体性を条件あるいは限界としている。そうであれば、平凡な複雑さと多面性は全体性によって規定されており、カーニバルの歯止めとしては弱いのではないか? そして平凡な複雑さと多面性がカーニバルへと至らないためには、全体性を差異化することつまり解釈の視点を差異化することが必要なのではないか? そしてその差異化は生と死との無限の差異化であったのだから、「生の肯定」「生の蕩尽」としてのカーニバルはファシズムつまり全体性へとはもたらされないはずである。)
13:両氏の文章の継承6
以上のことをまとめる形で、問いを立てる。私による両氏の継承とはどのようなものであったか?
私は、継承が、継承に先立って規定されたものの継承である限りは、継承をしないことであるという観点からこの文章を始めた。
継承されるものは、規定されること自身から差異化しなければならないもの、すなわち差異である。
したがって、差異と継承とは、差異の自己自身からの差異化としてのみ可能であることになる。
継承は、継承されるもの(未だ規定されていない)が持つ差異を、規定せずに、自己自身から差異化させることで、継承それ自身が差異とならなければならない。
したがって、私は、両氏の文章を継承するためには、両氏の文章の内に、自己自身から差異化する差異を導入しなければならなかった。またそのことによって、私の継承そのものが無限の差異の標記とならなければならなかった。
私は、まず、広坂さんの一つ目の文章を、その文章の持つ差異を消去することで、ヘーゲル弁証法の内に全体化した。
そして全体化は継承をしないことであるとして、次に岡田さんの一つ目の文章に、全体化に対する批判を見出した。そして岡田さんの二つ目の文章を、ヘーゲル弁証法の内で全体化されえない無限の差異化(可変性)をヘーゲル自身の内に見出す試みとして読んだ。
さらに、私は、両氏の文章それ自身の内に、自己自身から差異化するものの観点を探った。それは、全体性を、その記述や視点の次元に引き戻すという両氏の観点であり、これを私は超越論的自己との差異的関係として読み替えた。
以上がまとめである。
これが私による両氏の継承である。
この継承によって、両氏の文章の内に標記された政治・倫理・道徳は、文章を読解する読者が全体化をすることができないものとなる。読者は、全体化する自らの読解そのものの政治・倫理・道徳性を問われることになる。
読者による継承は、無限の差異の標記としてしか可能ではなくなり、読解と継承に際しては両氏の文章に全体性の視点から意味づけをすることが不可能になる。全体性の視点からの意味づけこそ継承をしないものであるという観点が、両氏の文章の内に認められたからである。両氏の文章は、その読解者に否定辞の反復を促し、読解者たちの間で無限の差異の標記としての注釈書を生みだすものとなる。
14:ニーチェ
最後に、今まで記してきたニーチェの目印への僅かな目配せをしたい。一つ目の目印はニヒリズムに、二つ目は世界の戯れに、三つ目は生即死に、四つ目は錯誤の歴史としての形而上学に関わる。
これらの目印によって明らかとなることは、ニーチェこそは、解釈(視点)の差異化の思想家であったということである。
一つ目のニヒリズムは、ニヒリズムと診断を下すことであり、依然ニヒリズムに対する視点の問題である。否定辞の反復と差異の標記としてのテクストを、ニヒリズムとして一括すること、そのことによって無限の差異の標記としての継承をやめることは、たとえニヒリズムという診断の形であれ、差異の標記としてのテクストに全体性をもたらすことである。
二つ目の世界の戯れは、戯れつまり差異を、解釈者の視点によって全体化(世界の中の戯れ)せずに、解釈者の視点そのものを差異化することを言う。
三つ目の生即死は、死を或る視点によって意味づけ生へと全体化することからの差異を標記している。
四つ目は錯誤の歴史としの形而上学である。力への意志こそが真理をでっち上げるのだが(そして真理の問題を、それをでっちあげるものへ、つまり力への意志へと引き戻すニーチェの身振りは、私が論じた、全体性をその語りの次元へと引き戻すことと同じである)、しかし真理の視点としての力への意志が、不断に自己を差異化することで、視点が差異化され、真理は錯誤へと変わり、真理の歴史としての形而上学は錯誤の歴史となる。
以上のようにニーチェを解釈(視点)の差異化の思想家として読むことが、デリダによるヘーゲルの継承の要であったことになる。
ニーチェについて論じ始めれば、際限のない議論が続くだろうゆえに、今は立ち入ることができない。(ニーチェとヘーゲルの犠牲をめぐって、ごく僅かな議論を展開している貴重な論文を参照することができる。須藤訓任「ヘーゲルとニーチェ」『ニーチェの歴史思想』大阪大学出版会、二〇一一年)
【コメント】
前口上再広坂朋信「本来なら言い出しっぺの私がこの三十年間の「現代思想」の見取り図を提出し、岡田氏の批評を仰ぐのが筋というものだが、あいにく個人的なアクシデントに見舞われて精神的な余裕がない」。黒猫編集長のユーモアあふれる思し召しからはじまったこの変則的なリレーエッセイの前口上で、企画担当者である私はこう言い訳して、まだ修行中だからと固辞するST氏を丸め込み、彼のデリダ論をもって強引にスタートさせたのでした。
ふつうこうした企画では、言い出しっぺがうそっぱちでもいいから大風呂敷をひろげて見せるべきなのに、情けないことに私にはそれができずにST氏と岡田有生氏にお鉢をまわしてトンズラをこいたのでした。まことにお恥ずかしい次第ですが、これまでの議論を掲載順に見てみると面白いことに気づきます。
まずST氏がデリダに依拠しながら継承について述べました。これは一見すると現代日本の思想を再考するというこの企画の枠からはみ出るように見えるかもしれませんが、日本の近代化というものがヨーロッパ近代の継承から始まったことを考えると、すべての議論の前提になる射程の大きな議論でした。
その後、岡田氏が、主に柄谷行人と今村仁司を取り上げて、奥深い議論を展開されました。柄谷や今村は、図式的にいえば大きな物語の失効後、あえて大きな物語の代表格であったマルクス主義の「可能性の中心」を探りながら、ST氏の言う差異化の運動の先駆形態となったと言えるでしょう。
私が試みたことは、「非歴史的な「文化」の理論家たち」(柄谷)を再読することでした。実際には山口昌男と忠臣蔵論争にしか触れられませんでしたが、時間があれば中村雄二郎と丸山圭三郎も再読したいところでした。
そして、今回のST氏の新論考は、またもやデリダに依拠しつつ、岡田さんの批判的思考を引き継ぎ、「文化の理論」を並べ立てる広坂の似非ヘーゲル主義に全体化への欲望を読みとって引導を渡す、という趣向のものです。
もちろん、まだまだ取り上げたい話題はたくさんあったわけですが、しかし、こうして眺めてみると、つまりミネルヴァの梟よろしく事後的な視点から全体を見渡してみると、なんということでしょう、見事に70年代末から90年代初めまでの日本の現代思想の流れの骨格が浮き上がってくるではありませんか。企画当初の目的は図らずも達せられたように思うのです。これを理性の狡知と言わずしてなんというべきか(ST氏は「懲りないオヤジめ」と舌打ちされるでしょうか)。結果オーライということでご容赦願いたいと思います。
ともあれ、この企画はここまでを第一期として、岡田氏の新たな論考をもって第二期のスタートといたします。
Web評論誌「コーラ」19号(2013.04.15)
<現代思想を再考する>第6回:差異と継承(ST)
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2013 All Rights Reserved.
|
| 表紙(目次)へ |