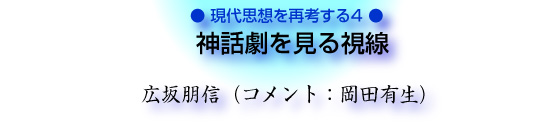|
|
|
Web�]�_���u�R�[���v |
|
���n���̎� ���{���̕\���i�ڎ��j�� ���{���̃o�b�N�i���o�[ ���ǎ҂̕Ł^���ӌ��E���z �����e�K�� ���W�҂�Web�T�C�g ���v���C�o�V�[�|���V�[ |
|
���{���̊֘A�y�[�W�� |
|
���u�J���`���[�E�������[�v�̃o�b�N�i���o�[ ���]�_���u�k�� Vue�v�̑��ڎ� |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
|
�@���c�L�����̑O��̘_�l�́A�����m�i�̑�O���r�����ʘ_�����グ�āA�[���s���₢�������̂��������A���͎R�����j�̃X�P�[�v�S�[�g�_�ɂ��Đ��U���ɂ�����ׂ肵�Ă݂����B��m�����̑ʕق�ǂމɂ̂Ȃ����́A�{�e�Ɋ��鉪�c���̃R�����g�ɂ������ʂ��Ă���������Ό��\���Ǝv���B�ȉ��A��p�Ƃ��}���̂Ȃ����������t�����������������B
�@
�����m�i�̓�̒�
�@���āA�����m�i�͂��̒����w�\�͂̃I���g���M�[�x�̍ŏI�͂Łu���]�i�T�N���t�@�C�X�j�̘_���́A�G�f�B�v�X�E�R���v���b�N�X�A�ے��I���e�E���A�ے��I���E�A�ے��I�ߐe�����Ȃ����i���V�V�Y���A����ɂ̓q�g���[�̐����_�b�I�헪�ɂ�����܂ŁA��X�̌`�Ԃ��Ƃ肤��v�Ƃ��������ŁA����Ɏ��̂悤�Ȓ���t���Ă����B
�@�����āA���́w�\�͂̃I���g���M�[�x�̑��҂ł���A�����̑�O���r�����ʘ_�̌���łƂ�������w�r���̍\���x�ł́A�u���̖����ɂ�����u��O���r���v�̎Љ�I�_���́A�l�ފw�̗p�����Č����A�u�N�E�G�~�b�Z�[�����ʁi�܂��̓X�P�[�v�S�[�g���ʁj�Ƃ�������������v�Ƃ��������ŁA����Ɏ��̂悤�Ȓ���t���Ă���B
�@���̓�̒����牽���ǂ݂Ƃ�邩�B
�@����������̗��_�́A�P�ɐl�ފw�łƂ��������łȂ��A�ߑ�Љ�̐����ɂ����錻���͂������̂Ƃ��āA�R�����j�̃X�P�[�v�S�[�g�_�𖼎w�����Ă���Ƃ������Ƃł���B�����āA�����̗��_�́A�w�[�Q���A�}���N�X����o�����Ă���Ƃ����o�����炵�āA���̐^���͋ߑ�Љ�̐����I���ۂ�ᔻ���Ă������������ׂ����̂��낤�B�����ł���Ȃ�A�����Љ�N�w�́A���̌������͂̑��ʂɂ����Ă͎R���l�ފw�ɐ��肳��Ă����Ƃ������ƂɂȂ�Ȃ����B���̌��ʂ��ɗ��Ȃ�A�R�����j�̃X�P�[�v�S�[�g�_���ēǂ���Ӗ��͂���Ƃ������̂��낤�B
�@
�_�b�E�|�\�E����
�@�R�����j�́A70�N�ォ�琸�͓I�Ȍ��_�������s���āi�����j�L���_�u�[�����܂��������A80�N��ɓo�ꂵ�ăj���[�A�J�ƌĂꂽ�Ⴂ�m���l�����i����V��A����ߎq�A�I�{�T��Y��j�̌㌩�l�̂悤�Ȗ������������l���ł���B���̎R����70�N��̑�\��̈���w���j�E�j�ՁE�_�b�x���Ƃ����Ă������낤�B�����́u��@�v���̃A���P�I���W�[�v�́A���V�A�v���̌��J�҂ł���Ȃ��琭�G�X�^�[�����ɂ���Ĉْ[�҂������������ĒǕ����ꂽ�g���c�L�[�Ɍ������Ă����̂ł���B
�@�R���͂��̘_���̂͂��߂ŁA�u���I�̊v���I�����Ƃ̒��ł������Ƃ�����₩�Ȑ�����Ԃ������t�E�_���B�h���B�`�E�g���c�L�[�̖{���̋P�������߂����Ƃ́A�����𐭎��ɑ��銴�o�̖�ჁA�A�p�V�[���������邽�߂ɕK�v�Ȃ��Ƃł���v�Ƃ��āA�u�g���c�L�[�Ƃ����P�������m���ɍ~�肩�������^����ʂ��āA�����I���E�̘_����_�b�I�Ȏ����łƂ炦�Ă݂����v�ƕ\������B�܂�A�R���̎��_����́A�����́u�����ɑ��銴�o�̖�ჁA�A�p�V�[�v�́A�_�b�I�Ȏ��������@���Ă��邩�炾�Ƃ������ƂɂȂ�B
�@�����̐����I���E�̘_���ł͂Ȃ��A�_�b�_�I�������K�v�Ȃ̂��Ƃ����̂��R���̎咣�ł���B�����Y���ƁA�R���̃g���c�L�[�ւ̎^����ǂ݈Ⴆ�邱�ƂɂȂ�B�Ƃ����̂��A�R���̓g���c�L�[�\�̓V�˂ł��邩�̂悤�ɕ`���Ă��邩�炾�B�u�����w���҂ɂ��āA�o�ϊw�ҁA�Љ�w�ҁA�R���w���ҁA��O�̕����I�N�̑�z�������ƁA���j�ƁA�`�L��ƁA���w��]�ƁA���V�A��U���̑�ƁA�j��H�ɂ݂��Y�ىƂƁA�s���Ƃ���A�K����ꋉ�̐��ƂƂ��Ă̗͗ʂ��������l�ԁv�B�܂�ŃX�[�p�[�}�����B�����Ƃ��u�Q�킴�������܂������s���肾�����l�ԁv�Ƃ��t�������Ă��邪�A�Q�Ƃ��Ȃ킿���H�삪�s���ӂƂ����͕̂K�������}�C�i�X�C���[�W�ł͂Ȃ��B���̂悤�ɎR���̓g���c�L�[��_�߂������Ă���B
�@�������A�R���̎^���̓g���c�L�[�̐����I��`�咣�ւ̎^���ɂ����̂ł͂Ȃ��B���j�̑啑��ɓo�ꂵ���l���̖��҂Ԃ���̎^���Ă���̂ł���B
�@�����ł͎��������u�����ɑ��銴�o�̖�ჁA�A�p�V�[�v����������邽�߂ɕK�v���Ƃ��ꂽ�u�_�b�I�Ȏ����v�Ƃ́A�|�\�̉F���ƌ����������Ă���B����͉����_�I���_���琭�����Ƃ炦��Ƃ������Ƃł�����B���̂悤�Ɍ����ƁA������o�����A���܂��^�����g�����Ƃ����Ă͂₷���C�h�V���[�����ɂ��肵�Ă��鎄�����Ƃ��ẮA�����牽���A�ƌ����������Ȃ邾�낤�B�������A�R���̌����u�����I�F���ƌ|�\�̉F���̎���ꂽ�Ȃ���v�Ƃ́A�����̃��C�h�V���[�����Ƃ͎��I�ɈقȂ���̂ł���B�������̈���ŁA���C�h�V���[������ᔻ���Ė����`��L���ɋ@�\�����悤�Ƃ����^�C�v�̋c�_�Ƃ��Ⴄ���Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B
�@
�������Ƃ��Ẵj���[�X
�@�R�������̕��͂������������ɂ́A�܂����C�h�V���[�����Ƃ������t�͎g���Ă��Ȃ��������A�}�X���f�B�A�������悤�ȓ��������邱�Ƃɂ��ĎR���͂��łɎw�E���Ă����B�w���j�E�j�ՁE�_�b�x�Ɏ��߂�ꂽ�u�]���̘_���v�Ƒ肷�镶�͂ŎR���́A�j���[�X�͒P�Ȃ���̓`�B�ł͂Ȃ��������I���i�������Ă���Ƃ��āu�j���[�X�ɂ̓��[�}�̓��Z��Ɏ������i������v�ƌ����B�u�����͑z�������łȂ������́u�]���v����������B�L�^�f���ʐ^�ɂ��Ă��A���l�̕s�K�̂��n�t���̏㉉�ɓǎ҂�ϋq��U���Ƃ��낪����v�B�Ȃ����Ƃ����ƁA�j���[�X���l�����߂�u�V�����v�́A�u���̖��łȂ��A�Ƃ��̏�̖��v������ł���B
�@�����猾���Ȃ��Ă��A����̎��������d�X���m���Ă���悤�Ȃ��Ƃ����A�R���́i�j���[�X�́j�u���肪������N�����͎̂�҂̎��̌�����A���҂̑����ɖ�������A���҂̍Ō�̈��������̏�v�ł���A�u�͂����́v�i�]���ҁj���u�����̐S��邩�ɖ�点�����͑h��̑̌������v�Ǝw�E����B����͖��͂ȋq�ώ�`�A���ӔC�ȑ��Ύ�`���낤���B���͂����͎v��Ȃ��B�R���́u���͂ɗ��p����₷���ϋq�̓`���v�����炩���ߑz�肵�Ă�������B���C�h�V���[�����������I�ȗ��ꂩ��ᔻ���郁�f�B�A�E���e���V�[�I�Ȍ��_�����A��قǘV���ł��ԂƂ��c�_���Ɗ�����B
�@�j���[�X���u���[�}�̓��Z��Ɏ������i�v�������Ƃ́A���ꂪ�������I�ł��邾���łȂ��A�������I�ł��邱�Ƃɂ���Đ����I�Ȑ��i�������Ƃ������Ă���B�j���[�X�̐������Ƃ����ƁA�ŋ߂ł͂���j���[�X�ɓ���̐����}�h�ɂ��o�C�A�X���������Ă��邱�Ƃ��肪���ڂ���₷�����A�R���͂��������j���[�X�Ƃ������́A�}�X���f�B�A�Ƃ������̑S�̂��������I�E�����I�ł���ƌ����Ă���B�e���r�Ȃǂ͂��̍ł�����̂��낤�B�ԑg�݂̂Ȃ炸�A�����h���}����o���G�e�B�V���[�Ɏ���܂ŁA�������I�E�����I�łȂ����͉̂���Ȃ��B
�@
�������������Ƃ͉���
�@����ł́A�R���̌����������������Ƃ͉����B�ꌾ�Ō����A�l�g�䋟�̋V���ł���B�V���ł��邩��A���̑����ɂ�����炸�ϏO������i���̓_�ŃL���P�S�[���̂�����C�T�N�͂���قȂ�j�B�u���т�_�ɕ����邽�߂ɂ�����E���A�����Ő�������鍬�ׂƂ�����Ԃ̒��ŁA�]������Đ_�Ɛl�A�l�Ɛl�Ƃ̋�ʂ���蕥����v�A���ꂪ�u�������͂̋��ɓI�Ȃ��ǂ���v���ƎR���͌����i�u�j�ՓI���E�v�w���j�E�j�ՁE�_�b�x�j�B�����āu�����̐g�̂܂��ł��A���̂悤�ȏ́A������ł��J��Ԃ���Ă���B�����Ƃ������t���A�ٕ��q���͂����o���A�͂����o�����߂ɁA�ٕ��q������o����Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�Ƃ����̂͂ǂ�ȎЉ�ł��ʗp���Ă��錴���ł���v�i�u�]���̘_���v�j�Ƃ��w�E���Ă���B������܂��A�����猾���Ȃ��Ă����m���Ă���悤�Ȏ����ł͂��邪�A�R���̋c�_�̓����́A���̈��|�I�����ɂ��̂����킹�āA���̓K�p�͈͂��g�債�Ă����Ƃ���ł���B�܂����p�������Ȃ邪�A�R���̋c�_�̓����������ӏ��Ȃ̂ň����B
�@���������ϓ_���猩��A�ٔ����܂��d�v�ȋV���i�������j�ł���B�u�s���]�\�\���̌����\�\���ے��I�Ɍ������A�l�������A����i�������j�ɍڂ��A���]�ɓ��݂��錴���i���S�̋����j�̈З͂Ɍ��P���Y�����邽�߂ɌY���͕K�v�v�Ȃ̂ł���B���̂悤�Ȑ������Ƃ��Ă̍ٔ��Ƃ��āA�X�^�[�����ɂ�锽�Δh�̏l���ٔ��Ƃ��Ēm����u�u�n�[�����ٔ��v�i���X�N���ٔ��j���R���͗�ɂ�����B�����āA���́u���Ӑ[���������ꂽ�����Ǝ����𒆐S�Ƃ��������������A����ގU���v�ɂ��āA�������L�V�R�ɖS�����Ă����g���c�L�[���u�����ɐl�דI�ɓG��o���U���ٔ��v���ƌ������Ă��Ȃ���A����̐g�̏�ɋN���������Ƃɂ��Ă͐��������f�ł��Ȃ������ƕt�������Ă���B
�@�������牽�����P�����ݎ��Ȃ�A���N���Ă��鎖���A���ɁA���炪��������Ă��鎖�����A���������ŋ��A������M���V�A�ߌ���V�F�C�N�X�s�A���̂悤�Ȑ_�b�I���s������������������悤�ȖڂłȂ��߂邱�Ƃ����Ă����Ȃ��ƁA�Ƃߊ쌀���������˂Ȃ��A�Ƃ������Ƃ��낤�B
�@
���@���l���r���e�B�_�̊��v
�@�Ƃ���ŁA��Ɉ��p�������͂Łu����̈ӎu�Ɩ��W�ȁA���錈��I�����������邽�߂̏����v�ƌ����Ă���̂́A��Ƀ��@���l���r���e�B�i�U���U�����j�ƌ�����������A�ٖM���A�ٖe���A���邢�͍��Ȃ瑼�Ґ��Ƃ����悤�ȁA��������̂��Ƃł���i�u���@���l���r���e�B�ɂ��āv�w�����̎��w�T�x�����j�B���鋤���̂̕W���I�ȃA�C�f���e�B�e�B�����E�������������ҁA�O���o�g�ҁA��Q�ҁA�@���I�����ҁA���I�����ҁA����Ȓm����Z�p�����ҁA���i�I�ȕς��ҁA���̑�������}�C�m���e�B�̓����������Ԃ������҂̂��ׂĂ��A���@���l���r���e�B�����҂Ƃ����B�g���c�L�[�ɂ��Č����A�G�L�Z���g���b�N�ȕ��e�A�����I�Ȓm���A�����ʂɂ킽��D�ꂽ�˔\�A�����Ă��Ԃ_���n�̏o���Ȃǂ����@���l���u���ȓ����Ƃ��ꂽ�̂��낤�B
�@�������A���̘_�����R�����ɑ��̕���Ɋg�債�Ă����ƁA���܂��܂ȏ�ʁA�Ⴆ���ʂ₢���߂̏�ʂɂ����Ĕ�Q�҂����Q�҂Ɓu�����̐ӔC���v���ƂɂȂ��Ă��܂��B�����Ă��̏ꍇ�A�����߂⍷�ʂ̔�Q�҂́A�g���c�L�[�̂悤�ȉp�Y�ł͂Ȃ��B�����ɕ��ׂ��Ă͂��Ȃ�Ȃ��Ǝv���̂����A�R���́w�����߂̋L���_�x�i��g���㕶�Ɂj�ɂ����Ă������Ă��܂��̂ł���B����́A���ꂱ���R�����g�͂��܂莩�o���Ă��Ȃ��悤�Ȃ̂����A�R���l�ފw�̎�_�ł���B
�@����܂łɂ��R���l�ފw�ɑ���ᔻ�͂������B���̑�\�I�Ȃ��̂Ƃ��āA�R���̗��_�͖{���I�ȕϊv���Ȃ��A���ǁA���Ƃ̒��������������ߒ���`�ʂ��邾�����Ƃ����ᔻ���������B�Ⴆ�A�ԍ⌛�Y�͎R���̎咘�̈�A�w�����Ɨ��`���x�ɂ�����u���S�^�����v�}�����������Ď��̂悤�ɔ�]���Ă����B
�@�������A���̔ᔻ�͓I���˂Ă��Ȃ��Ǝ��ɂ͊�������B�R���ɂ��Ă݂�A�����̒����̋����Ɛ[�����܂��F������A�Ƃ������ƂȂ̂��낤�B�R���͂����������Ă����B�u�����F�߂邱�Ƃ́A���̂܂܂���F���邱�Ƃł͂Ȃ��B�����F�߂Ȃ��ق����A�ނ���A�����������\���̂����Ƃ���l�ԓI�ȗ��p�����ʓI�ɐ��������邱�ƂɂȂ�v�i�u�]���̘_���v�j�B�I�[�\�h�b�N�X�Ȓ����ɃX�p�C�X���x�ْ̈[�I�v�f����������ŕϊv�҂��C���l��A�u�����͍��ЂƂ��i��Q�Ƃ��A���ʂƂ�etc�j�Ȃ�ċC�ɂ��Ȃ�����v�ƌ����Ȃ��疳���o�ɍ��ʂ���������l�����邱�Ƃ��l����ƁA�킫�܂��Ă����ׂ������̂悤�Ɏv���B
�@����ɑ��āA���@���l���r���e�B��ттĂ��邱�Ƃ������Ĕ�Q�҂Ɖ��Q�҂Ƃ����ƓI���Ƃ����̂́A��Q�҂������Ȃ���Δƍ߂͋N��Ȃ������ƌ����Ă���̂Ɠ����ŁA�ӔC�̏��݂������܂��ɂ���B��Q�Ɖ��Q�͂��ꂼ��Ɨ����Ă���̂ł͂Ȃ��A���֓I�ȊT�O���Ƃ����̂ł���A����͂��̂Ƃ���ł���B�������A���T�O�̑����ɂ��ẮA��Q�҂͂������A���Q�҂ɂ���ӔC�͂Ȃ��B���鎖���ɂ��āA��Q�Ɖ��Q�𑊊֓I�Ȃ��̂ƂƂ炦�Ď��Ԃ̑S�̑���`�ʂ���̂͌��\�����A���̂��Ƃɓ����҂��u�����̐ӔC�v�킳��Ă͂��Ȃ�Ȃ��B���Ԃ�`�ʂ���_���Ǝ����̕]���Ƃ����荬�����Ă���̂ł���B���̎�_�́A�R������҂̃��@���l���r���e�B�ɂ͉��Q�҂ւ̒�����������i�u�X�P�[�v�S�[�g�̎��w�ցv�w�����̎��w�U�x��g���X�����j�Ƃ܂Ō����Ƃ��ɁA����I�Ȍ��_�ƂȂ�B
�@�͂����āA�R���l�ފw����A���̒����ł��鋤���̗̂͊w��`�ʂ���_�������𒊏o�����邩�B�܂��������邱�ƂɈӋ`�����邩�A�ȒP�ɂ͌��_�̏o�Ȃ����Ƃ̂悤�Ɏv���B
�@
�g���c�L�[�͉��҂ɔs�ꋎ�����̂�
�@���ǁA�g���c�L�[�̎��s�́u���̗��z��`�̂䂦�ɁA�l�Ԃ̎��U���{�\�̃G�l���M�[���J�[�j���@���I�V�Y��Ԃɋz�����邱�Ƃɐ������Ȃ������v�i�u�X�^�[�����̕a���I�F���v�w���j�E�j�ՁE�_�b�x�j�Ƃ������Ƃɐs����̂��낤�B
�@�R���́A�g���c�L�[�͉��҂ɔs�ꋎ�����̂��A�Ɩ₤�B�����āu�g���c�L�[���s�ꋎ�����̂́A�܂��ɁA�������������䂳�ꂴ��_�b�I�����ɂ������Ăł���v�Ɠ�����B����ł́A�u�܂��ɁA�����������v�Ƃ́A�ǂ����������̂Ȃ̂��B
�@�_�b�I�����Ƃ͌��ǃe���r�̉��b���̂̂��Ƃ��Ɩ���āu���̒ʂ�ł���v�ƎR���͒f�����Ă���B���́w���j�E�j�ՁE�_�b�x�̌��ɂȂ����_�����G���f�ڂ��ꂽ�̂́A1973�N�̂��Ƃ������������B�����̃e���r�́A�E���g���}���V���[�Y�i�u�E���g���}��A�v�u�E���g���}���^���E�v�j�≼�ʃ��C�_�[�V���[�Y�i�u���ʃ��C�_�[�v�u���ʃ��C�_�[�u�R�v�j��M���ɓ��B���̂�ϐg���̂��Ԑ���ŁA�R���̌����u���b���́v�������w���Ă���̂��͓���ł��Ȃ��B�u���b���́v������E���g���}���̂悤�ȋC�����邪�A�u������тт��p�Y�v�ɂ͉��ʃ��C�_�[�̕����ӂ��킵���悤�ȋC������B�������A����͂��Ԃ�ǂ���ł��������ƂȂ̂��낤�B
�@�Ƃ������A�u�����A�[���ɂȂ�Ɛ_�b�I���E�Ɉ����߂���āv�����q�ǂ��̈�l���������Ƃ��ẮA�R�������̉e���Ƃ��āu���x�����̎���ɂ͂Ƃ������A�Љ�����ł����萫�������͂��߂�ƈ�����グ�Ȃ���ΐ��E�����������ė����ł��Ȃ��^�C�v���o�����邩���v�Ɛ��_���Ă���̂͋C�ɂȂ�Ƃ���ł���B���݁A���{�Љ�͈��萫���������A���h�Ɗ�@�̎���ɂ���ƌ�����B�����āu������グ�Ȃ���ΐ��E�����������ė����ł��Ȃ��^�C�v�v�͎��ۂɏo�������B�u���b���́v�Ƃ̈��ʊW�͕ʂƂ��āA�R���̐��_�͓��������B���₱�̎荇���͐��E���͂��߂Ƃ��ă}�X�R�~�ɂ��l�b�g�ɂ�������ł����o����B
�@�����܂ŁA��Ɂw���j�E�j�ՁE�_�b�x���甲���o�����R���̎咣�ɂ́A�����猩�ĂƂ��ɖڐV�������̂͂Ȃ��Ɗ������邱�Ƃ��낤�B�R�������V�A�v�����ɁA���������傰���Ȍ��Ԃ�Ō���Ă��邱�Ƃ́A����̓��{�ł͒P�Ɋ�O�̎����ł����Ȃ��B�����A�l�\�N�߂��O�ɂ�����������ĂĂ����R���̋c�_�̎˒��̒����ɂ��āA���͋����Ă���ł���B
�@
�X�P�[�v�S�[�g�_�̎���
�@�R�����j���X�P�[�v�S�[�g��_�������͂͏�L�́w���j�E�j�ՁE�_�b�x�̑��ɂ����������A�R���X�P�[�v�S�[�g�_�̎����̂��肩������߂邽�߂ɁA�����ł́w�����̎��w�U�x�i��g���X�A1983�j�����́u�X�P�[�v�S�[�g�̎��w�ցv�ɒ��ڂ������B���s�����A��g����I������{�Ŋ��s���ꂽ�w�����̎��w�x�́A���\�N�㖖���甪�\�N�㏉�߂ɂ����Ă̑S�����̎R���̘_�����W�߂���_���W�ƌ����ׂ����̂ł���A�Ȃ��ł��u�X�P�[�v�S�[�g�̎��w�ցv�́w�����̎��w�x�Ɏ��߂�ꂽ���_���̂����������낵�̏��_�����������Ƃ��V�����i1983�N2�����\�j�B���̏�u�X�P�[�v�S�[�g�̎��w�ցv�̍ŏI�߂��u�����̎��w�ցv�Ƒ肳��Ă��邱�Ƃ���A���̓{�̘_���W�̒��S�I�ʒu���߂�_���ł���Ƃ݂Ȃ����邾�낤�B
�@�R���͂��̘_���́u1�@�X�P�[�v�S�[�g�_�̌n���v�Ńt���C�U�[����W���[���ɂ������s���_�����Ă��邪�A����ɐ悾���āu�͂��߂Ɂv�ɂ����Ď���̃X�P�[�v�S�[�g�_�̓W�J����ڂ��Ă�����B���̓_���瓯�_�����R���X�P�[�v�S�[�g�_�̒B�����������̂ł���ƎƂ߂Ă���߂Ȃ����낤�B�����ŎR���́w���j�E�j�ՁE�_�b�x��u���@���l���r���e�B�ɂ��āv�i�w�����̎��w�T�x�����j�ƕ���ŁA�u��㎵��N�A�w�G�X�v���x���ɔ��\�����u���{�ɂ�����V�c���̐_�b=�����_�I�\���v�ɂ͓������܂��܂Ȕ����������ꂽ�v�Ɠ��M���Ă���B��ɑ啝�ɉ��e����āw�V�c���̕����l�ފw�x�Ɏ��߂��邱�ƂɂȂ邱�̘_���Ɂu�����w�\�͂Ɛ��Ȃ���́x���㈲��������̃��l�E�W���[���������ɒ����𑗂��Ď^�ӂ�\���Ă���A��Ɂw���̏��߂���B����Ă��邱�Ɓx�̂Ȃ��ł����́w�G�X�v���x�_���ɂ��ĐG��邱�Ƃɂ���āA�ނ̎^�ӂ��ꎞ�I�Ȃ��̂łȂ��������Ƃ������Ă��ꂽ�v�ƁA����̃X�P�[�v�S�[�g�_�ƃW���[���̗��_�Ƃ̓����㐫���������Ă���Ƃ���ɁA�R���̎������\��Ă���B
�@���āA�u�X�P�[�v�S�[�g�̎��w�ցv�́u�͂��߂Ɂv�͍Ō�̒i���ŁA�R���X�P�[�v�S�[�g�_�̕��@�I�����\�����Ă���̂Ŏ��Ɉ��p����B
�u�X�P�[�v�S�[�g���ۂ��������̍����I�Ȋ��͂�ۏ���d�|���̈�ł���v�Ƃ͋��낵���F���ł���B�������R���͂����Ɂu�X�P�[�v�S�[�g���ۂɂ�钼�ړI��Q�҂̗���͂˂ɐ[������ɒl���邵�A�����͂����������ۂ̂����炷���ړI��Q���Ƃ߂�w�͂�₦���s��Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��v�ƒf������Ă���B��Ɂw�u�s�ҁv�̐��_�j�x��w�u���܁v�̏��a�j�x�i���������g���X�j���R���́A��т��Ď�������@���l���u���ȃA�E�g�T�C�_�[�Ƃ��Ď��F���Ă����B��ɂ݂��g���c�L�[�_�ł������I�s�҂ւ̓���͉B���悤���Ȃ��B�����A�R���͂��������S�����x���ł̓�������͂Ƃ肠�����I�グ���Ď��Ԃ��������悤�Ƃ���B�����i�ϗ��j������̃��x���ɐs������̂��ǂ����͋c�_�̗]�n�����邪�A���͂��̂��Ƃ͂��Ă����āA�R���̔��I�Ȏ�����������̂�ǂ����B
�@
�u�X�P�[�v�S�[�g�_�̌n���v�ɂ���
�@�u�X�P�[�v�S�[�g�̎��w�ցv�̑�P�߂́u�X�P�[�v�S�[�g�_�̌n���v�Ƒ肳��Ă��邪�A���̕��͂͂ӂ��̈Ӗ��ł̊w���j�ł͂Ȃ��B�u�I�|���֎q�̐l�ފw�̑�Ɓv�u���������̎����̖��ᔻ�I����ɂ���r�@���w�̑n�n�ғ��X�Ƃ������A���܂肠�肪�����Ȃ������𒅂����đ��苎��ꂽ�v�i�E�f�E�t���C�U�[�́w���}�сx���A�u�����̏ے��l�ފw�̐��I�Ƃ������ׂ��̌n�v�Ƃ��ĕ��������鎎�݂Ȃ̂ł���B�w���j�E�j�ՁE�_�b�x�ňˋ����Ă����P�l�X�E�o�[�N���͂��߁A���[�n�C���A�o�t�`���A�G���A�[�f�A�����B=�X�g���[�X�A�~�b�`���[���b�q��̖��O���o�Ă��邪�A�u�X�P�[�v�S�[�g�̎��w�ցv�ł́A�ނ�͂��ׂăt���C�U�[�̐挩�̖����������邽�߂ɓ�������Ă���ɂ����Ȃ��B
�@�t���C�U�[�i���p�����̕\�L�́u�t���[�U�[�v�A�ȉ������j�̒����u���́u���E���v���_���A�l�ފw�ҒB�͈�v���Ĕے肵���v�ƎR���͌����B�������A�R�����g���A�t���J���t�B�[���h�Ƃ���l�ފw�҂ł������B�R���̍ŏ��̒P���w�A�t���J�̐_�b�I���E�x�i��g�V���A1971�j�ɂ͎��̂悤�Ȏw�E������B
�@�܂�A�u���E���v�́u�����`���v�u�Œ�ϔO�v�u�\�v�ł����āA�����ɂ͍s���Ă��Ȃ������B�t���C�U�[�́u�I�����ւ̐l�v�ŁA�u��Ȃ��ƂɁA�ނقǂ̖��J�Љ�Ɋւ��錠�Ђ��A�����͖��J�Љ��K�ꂽ���Ƃ��Ȃ��v�i�R���u�w���}�сx�v�w�l�ފw�I�v�l�x���肩���[�����j�B�A���n�J��̂��߂ɐ��E�e�n�ɔ�яo���Ă�������p�鍑�̏��l��鋳�t�����̕��ޗ��ɏ����������̂��w���}�сx�������B������t���C�U�[�����u�l�ފw�ҒB�͈�v���Ĕے肵���v�Ƃ����̂����R�ł���B�����A�R���̒����ɂ��A���E�������Ă͍s���Ă����Ƃ��������`����A���̌��Ƃ͋N���ɂ����Ă͂����������̂������Ƃ����Œ�ϔO���A���n�̐l�X�̊Ԃɂ͂������B���n�������炻�̂悤�ɎR���͂Ƃ炦�A������o�t�`���̒���ɂӂ�Ȃ���ے��_�I���x���ő����Ȃ����B
�@���̂悤�ɎR�������f�����������E���́A���R�ЊQ��V���ƂƂ炦��l�����ł�����ȏ�A�������ɂƂ��Ă������Ƃ͌����Ȃ��B�����ăG���A�[�f�̉~�I���ԍ\���_���Q�Ƃ��Ȃ���u�N���Ƃ̎��n�Ղɂ����ăJ�[�j���@���I�s�����s���A�O�N�̍Ђ����q������̑ΏۂɒS�킹�Ă���𒁏��̌��O�ɒǕ�����̂́A�Љ����̊��͂����I�ɉ��邽�߂ɕs���̎�i�v�ł����āu����͍����̎Љ�ɂ��[���ɂ��Ă͂܂�v�ƎR���͎w�E����B
�@�R���́A�t���C�U�[�̃X�P�[�v�S�[�g�_���u�����\���̖{���I�������𖾂��郂�f�����蓾�邱�Ƃ��������v�l���Ƃ��āu�A�����J�̕��|���_�Ƃɂ��ēN�w�҂ł�����P�l�X�E�o�[�N�v��������B�ȉ��A���p�������Ȃ邪�A�{�e�O���ŏȗ������w���j�E�j�ՁE�_�b�x�ɂ�����o�[�N�_�i�u�]���̘_���v�j�̃G�b�Z���X���R�����g���v�����͂Ƃ�������̂ŏЉ�����B
�@���̂悤�ɎR���̓o�[�N�ƂƂ��ɁA�u�����̏ے��l�ފw�̐��I�Ƃ������ׂ��̌n�v�Ƃ��ăt���C�U�[�w���}�сx��ǂݑւ����̂ł���B
�@�R���l�ފw�̒��z���A���ۂɃt���C�U�[�w���}�сx���瓾��ꂽ���̂ł��邩�ǂ����͓`�L�I�����̗̈�ɑ����邱�ƂŁA�����ł͖��ł͂Ȃ��B�R��������̊w��ɉe����^���������_���n���I�Ɍ��ɂ������āA�t���C�U�[�����_�Ƃ��Č�肦���B���̂��Ƃ���A�R���l�ފw�ɂ����ăt���C�U�[���d�v�Ȉʒu���߂邱�Ƃ��m�F��������ł悢�̂ł���B
�@
�t���C�U�[�ƃw�[�Q��
�@�Ƃ���Ńt���C�U�[�w���}�сx��O�ŏ����ɂ͎��̂悤�ȕ��͂�����B
�@�����g�́u�u����ҁv�Ƃ͌����Ȃ����D��S�����͂���̂ŁA���̔������������Ǝv�����B�Ƃ��낪�A�c�O�Ȃ����g���ɔłł͖�o����Ă��Ȃ��̂ł���B���ׂ��Ƃ���A�_�����j��E�Βː��p�ďC�̊���Łw���}�с@��p�Ə@���̌���1�x�i�������s��A2004�j�Ɏ��߂��Ă��邱�Ƃ��킩�����B�ǂ�ł݂ċ������B�u�w�[�Q���ɂ������p�Ə@���v�Ƒ肳�ꂽ�t�^�́A�`���Ƀt���C�U�[���g�ɂ��Z���v�|�ƁA�w�[�Q���u�@���N�w�u�`�v����̃t���C�U�[�ɂ�锲������Ȃ��Ă���B�t���C�U�[�͎��g�̐��ƃw�[�Q�����Ƃ̈�v�ɂ��Ď��̂悤�Ɍ����Ă���B
�@��p�Ə@���̍��ق́A��p���l�ԂƎ��R�Ƃ̓W�ł���̂ɑ��āA�@���͐l�ԂƎ��R�Ƃ�}��钴���R�I���݂��O���Ƃ��Ă��O���W���Ƃ������Ƃł���B���̂悤�ɁA�t���C�U�[���g���A�����ƃw�[�Q���@���N�w�̈�v�_���Ƃ��Ă���_�_�́A�����Љ�N�w�̗p��Ō����A��O���r�����ʂ̂��ƂȂ̂ł���B�����āA�����܂ʼnI�Ȃ���C�Â��Ȃ������g�̓݊����ɕ���Ȃ�����A����̓w�[�Q���̌��t�Ō����A�ُؖ@�̂��Ƃ��ƌ����Ă悢�͂����Ƃ������Ƃ��w�E�ł���B�܂�A�����Љ�N�w�̑�O���r�����ʘ_�A�R���l�ފw�̃X�P�[�v�S�[�g�_�A���\�N�ォ�甪�\�N��ɂ����Ă̓��{�ŗ��s�����Љ�_�́A�w�[�Q���ُؖ@�̃p���_�C���ɏ���Ă����̂ł���B
�@�����m�i�ƎR�����j�A�����̒���ژ^������A���\�N�㓖���ɔނ�̉e���͂������ɑ傫���������͗e�ՂɌ��Ď��邾�낤���A���̗����̔��z�̘g�g�݂��w�[�Q���ُؖ@�ɋߎ����Ă��邱�Ƃ́A���\�N��Ɋw��������߂��������ɂƂ��āA�������ւ����Ȃ������ł������B
�@���̗c�t�Ȉ�ۂł́A���\�N�ォ�甪�\�N��A���ɔ��\�N��̂�����u����v�z�v�ɂ����ẮA�����I�E���j�I�ȃe�[�}����������Ă����悤�ȋL�������邵�A�w�[�Q���͂��ꂱ�������̂悤�Ɉ����Ă����B�����m�i�́A�A���`���Z�[���̌����F���_�I�ؒf�������o���āA�}���N�X�ɂ��w�[�Q���̏��z������������_�w���Ă����B����̎R�����j�́A�Q�Ƃ��闝�_���\���l�ފw�⌻�ۊw�I�Љ�w�ł����āA�w�[�Q�����}���N�X���Ƃ₩�܂��������鍶���_�d�̊O����o�ė����l�������B�����̒���R�Ɠǂ�ł������̔]���ɂ́A�w�[�Q���ُؖ@�Ƃ͎���x��ǂ��납���Z���ׂ��������`����w���Ƃ����ϔO�������������̂ł���B����́A�����Ȏ���l�̖ϑz�ł͂Ȃ��͂����B
�@�������A�����̓���̎咘�ɋL���ꂽ����|�̒��Ɏ�������āA�R���̒�����ǂݒ����Ă݂��Ƃ���A�v��ʔ����������B�����̌����ʂ�Ȃ�A�ނ̑�O���r�����ʂ̗��_�́A�R���̃X�P�[�v�S�[�g�_�ƒʒꂷ����肩�A���������̕��͂Ƃ����ʂŐ�悳��Ă���B�����āA�R���̌����ʂ�Ȃ�A�ނ̃X�P�[�v�S�[�g�_�̓t���C�U�[�̉��E���̗��_�Ɍ���������A�t���C�U�[�̌����ʂ�Ȃ�A���̘g�g�݂͊�{�I�ȍ\�}�Ƃ��Ă̓w�[�Q���̏@���N�w�Ɉ�v����̂ł���B
�@������������������Ƃ����āA����Ȃ��Ƃō�����R����ᔻ�������肩�A�܂��Ă�w�[�Q�����c�A�ȂǂƂ͂ǂ������l���ɂȂ�Ȃ��ł������������B���Ƃ��ẮA���ɑf���Ƀw�[�Q���̉e���͂̑傫���A���@�͂̐[���Ɋ��Q���Ă��邾���Ȃ̂�����B
�@
�@
�y�R�����g�z
���\�̗����c�L��
�@
�@�L�₳�_���Ă�����R�����j�ɂ��Ă����A���͒�����������ǂ��Ƃ��Ȃ��B
���̕��͂�ǂ܂��Ă�����Ă��̈�[��m��A����Ȃɂ������w�ҁE������ł������̂��ƁA�����̐�w�ƕs���ɂ��炽�߂ĕ�R�Ƃ������ł���B
�@���̂��Ǝ��̂��������������Ă����������A������l���邽�߂ɂ��A�L�₳��̕��͂�ǂ�ł̎G���Ȋ��z���A�ȉ��ɋL���Ă������B
������
�@�����m�i���������������A�R�����j���\�͂Ƃ����e�[�}�ɂ��đ傫�ȊS���Ă����悤�ł���B�\�͂Ƃ͌����Ă��Ȃ����A�u�́v�Ƃ�����́A��c���ɑ�\�����悤�ɂ��̌�́u����v�z�v�ł��A���ɏd�v�ȈӖ��Â�������Ďg��ꂽ���t�ł���B�����ł͂����ނˁA�\�͂�͂́A�l�Ԃ��Љ���`�����Đ����Ă������߂ɂ͌�������(����邱��)�̂ł��Ȃ������I�ȏ����A�Ƃ����j���A���X�Ō���Ă����B
�@�������ɁA����ꎩ�g�̖\�͐��ɂ��Ă̂��̂悤�ȔF���́A�l�ɂ������ւ�d�v�Ȃ��̂��Ǝv����B�����A�L�₳��̘_�Ō��y����Ă���A�_�b�_�I�Ȏ����ɂ���Č����������A�Љ���`�����邽�߂́u�]���̖\�́v�ƌĂׂ�悤�Ȃ��̂��A�l�Ԃ̎Љ�I���݂�����ŋK�肵�Ă���\�͂̑S�ĂȂ̂��Ƃ������Ƃɂ́A�^�₪����B
�@�x�����~�����u�_�b�I�\�́v����u�_�I�\�́v�����Ƃ��敪���悤�Ƃ����Ӑ}�ɁA�d�Ȃ�̂��ǂ���������Ȃ����A���̓_�ɗ��ӂ��Ȃ���A�����l���Ă݂�B
������
�@���āA�L�₳��̕��͂́A�g���c�L�[���r�̉ߒ��͂���R���̘_�ւ̒��ڂ���n�܂��Ă��邪�A���ꂪ�����ꂽ�V�O�N��㔼����W�O�N��ɂ����Ă̓��{�̐����̐��E�ɂ����āA�X�P�[�v�S�[�g��ٔ��Ƃ������t����v�������ԏo�����́A�Ȃ�Ƃ����Ă��c���p�h���߂�����̂��낤�B
�@�w���|�t�H�x����œW�J���ꂽ���ԗ��ɂ��u�����Njy�v�[�Ƃ��邱�̑傪����Ȑ������́A������v���ƎR���̗��_�ɂ������ۂ蓖�Ă͂܂肻���ȁu���C�h�V���[�̐����v�̚�������悤�ɂ��v����B��������́A�Љ�`�ɂ��u�����v�Njy�̃h���}�Ƃ���(�����ɌӎU�L����S�������Ȃ��͂Ȃ������Ƃ͂���)�A���邢�͂܂��e�ēI�ȕ��c�h(�����{�h�E���a��)�Ɣ�E�e�ēI�ƌ����悢���c���h(��̌o����)�Ƃ̌��͓����Ƃ��āA�l�X�̎��ڂ��W�߂Ă����B
�@����c�h�ɂ��p�h�Ǖ��̐������Ƃ��Č���Ȃ�A�u�c�����g���c�L�[�v�ɑ��āu���c(�h)���X�^�[�����v�Ƃ����A�i���W�[�����藧���Ă��܂����������A����ȋY���͂��Ă����A�R���̘_�̎������Ē��ӂ��Ă����ׂ����Ǝv���̂́A���̐_�b�I�ȃh���}�̍\�����A�]���ɂ���Ǖ�����鑤�̎҂ɂ���Ă����m�ɋ��L����S���Ă������Ƃ��낤�B����́A���̌�������ΏT������C�h�V���[�̐����ɂ����Ă�(���ۂ̌��͓����̏�ɂ����ĂƂ͂��قȂ�)�A�Ǖ������u�����v�������邱�Ƃ���Ƃ����o����n�̐����Ƃ����A�܂�c���A���ہA����A�쒆(��؏@�j)�Ƃ������ʁX�ɐS��I�Ȏx������l����(�����̓I�b�T������)���A�������邱�Ƃɂ���Ď����}�̎x�z�̐����x���Ă����Ƃ����u���ʁv�ɂ悭������Ă���B���傤�ǁA�����ېV��̓��{�̍��Ƒ̐����A��v�ۂ���ɓ��Ƃ������C���X�g���[���ɕ������ꂽ���̂Ƃ��Ắu�����`���v�ɂ���ĕ⊮�I�Ɏx����ꂽ�̂Ɠ����������A�����o����̐����Ƃ����́A������x���o�I�ɉ����Ă����킯�ł���(���݂��H)�B
������
�@�Ƃ���ł��������\���́A�����ł��ؗ��Ă���҂������������Ōp�����Ă���悤�ɂ��v����B
�@�������ۂɂ́A�c�������Njy�̎���ƌ��݂Ƃł́A�傫���ڂ�ς�������̂�����ł��낤�B����́A���̎��܂��[���ł���A���m�ł͂Ȃ��������̂��A����Љ�̑S�̂��ɂ��������Ƃ����Ӗ��ł���B�L�₳��̘_�̍ő�̊�ڂ́A���̓_�Ɋւ���Ă���Ǝv����B
�@�܂荡���ł́A�Љ�I���݂ł���l�ԂɂƂ��Ă̕s��I�ȏ����ł���u�]���̖\�́v�ւ̊��]�Ƃ������̂��A�����{�̍��������ɂ����Ă͕ۂ���Ă������\�Ƃ��Ă̑���(����͐�㖯���`�╟�����ƂƂ������x�Ɋւ��)��E���̂ĂāA���̗��̎p�����炵�Ă���Ǝv����B
�@���ẮA���]�Ƃ����_�b�I�Ȗ\�͂̃h���}�́A���Ƃ��ΐ����Ƃ����̌��͓����Ƃ��ĉ������A�����͂�����ϋq�Ƃ��Ċ���ړ��I�Ɍ��߂邱�ƂŁA����������(�Α��I��)�\�͐��̎��o�ƋL�����ӎ����ɉ��������݂A���̌��͂̎x�z�\�����x���Ă����̂��낤�B
�@����ꎩ�g���A�Љ���\������ɂ������ĕs���Ȗ\�͂̎�̂ł���Ƃ��������́A�������鋟�]�̃h���}�߂�ϋq�Ƃ����A���͋��ƓI�ȃ|�W�V�����ɂ���Ė��ӎ�������Ă����Ƃ�����B
�@�����A�u����^�����v�̎���̓������Ӗ����Ă���̂́A���̕\�ʓI�Ȍ�`�Ƃ͈قȂ�A���Ă͊ϋq�ł����������������g���A���]�̃h���}�̉��Q�I�Ȏ���Ƃ��ĕ����ɓo�ꂵ�A�u�͂����́v�����Ղ�ɂ�����Ƃ����A�V���ȃV�X�e���̏o��(����ʂł͍ė�)�ł���B���̃V�X�e�������p���邱�ƂŁA�����̓������͂͋@�\���Ă���Ǝv����̂��B
������
�@���������ƁA��㐭�����̌����Ă����A�������ϋq�Ƃ���h���}���`�����邱�ƂŁA�l�X�̖\�͐��ւ̎��o�ƋL���������ɂ�������悤�ȃV�X�e���ƁA�����x�z�I�ȁA����������̖\�͂ƍU�����ɊJ�������Č��h��ꂽ�Љ�`���́u����v��i��ʼn�����悤�ȃV�X�e���A���̂ǂ��炪���悢���̂��́A��T�Ɍ����������Ǝv���邩������Ȃ��B
�@�����A���ꂪ�V�X�e���ł���ȏ�A��҂ɂ����Ă����������̖\�͐��ւ̎��o��L���́A���x�I�ɉ��H����A�^�̈Ӗ��ł͉��������܂�Ă���Ƃ������Ƃ��v�_�ł���B�u�]���̖\�́v�Ƃ́A���̉��H���ꂽ��������������t���Ǝv���B
�@���̎Љ�ł́A���̖\�͂̈ӎ��𐧓x�I�ɉ��H����d�g�݂���i�Ɛ��k�ɂȂ��Ă���Ƃ������Ƃł���A�l�X�͂����ł͖\�͂𒁏��̈ێ��ɂƂ��ėL���ȕ����֓������Ƃ��錠�͂̈ӎu�ɉ����āA���܂ňȏ�ɘI���ȑ��҂ւ̖\�͂̍s�g�ɍ����������Ă��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��̂ł���B
�@�������㖯���`�̐��x�́A�������g�̖\�͂̎��o��L���̉B���Ƃ����_�ł́A�����̈ێ��Ɋ�^����r���I�Ȑ��x�������킯�����A�����ɁA�푈�̎���ɂ����ł������悤�ȁA�����S�����e���̓��Ȃ�\�͐��ɊJ������(�^�̖\�͂̑̌��ւ̔��ȓI���o�͌��@�����܂�)�A�������ƂȂ��ċ��]�̐��s�҂ƂȂ�Ƃ����ň��̎��Ԃ��A���낤���ĉ������߂���̂ł��������̂��Ǝv���B
�@�Ȃ��Ȃ炻���ł͐l�X�ɂ́A���]�̃h���}���ϋq�̎����Œ��߂邱�Ƃɂ��A�킸�������A���́u�]���̖\�́v�ւ̗~�]�������ɂ����݂��Ă�����̂ł��邱�Ƃ����o���A�\�͂Ƃ���������(����͐��x�I�ȁu�]���̖\�́v�Ƃَ͈��Ȃ��̂ł���)��ʂ��đ��҂Ƃ̗ϗ��I�ȊW�ɊJ�����]�n���c����Ă������炾�B�����{�̐������x�́A�\�Ԃɖ��������\�ł��������A���������ɂ͐l�X������̖\�͐���^�Ɏ��o���A�����ʂ��đ��҂Ɍ����ĊJ����Ă�����H���A�킸���ɑ����Ă����B���̋��\�́A�ߑ���{�Љ�̂قƂ�Ǐ�Ԃƌ����Ă��悢����}�ȁu�]���̖\�́v�̔×������낤���ĐH���~�߂邽�߂̑��u�������̂ł���B
�@���ꂪ�����ł́A�Љ�`���̌����͂ł��邱�́u�]���̖\�́v�̗~���ւ̉Q����X�����ݍ���ŁA�j��I�ł���Ɠ����Ɍ��͓I�ȁA�\�͂̂���Ȃ�×��ւƂ����炻���Ƃ��Ă���̂��B
������
�@���̏�Ԃ́A�L�₳�_����ց[�Q���̎v�z�ɂЂ����Č����Ȃ�A�u�@���v��u�ُؖ@�I�v�l�v�̋@�\�̑r���ƌĂׂ���̂��낤�B
�@�w�[�Q���̋c�_�����������d�v�Ȃ��ƁA����͂܂��Q�O���I�ɂ����Ă͐��_���͂ƍ\����`�ɂ���Ă悭�p�����ꂽ���̂������Ǝv�����A����͐l�ԂɂƂ��ĎЉ���̌`���ɂȂ���_�b�I�Ȗ\�͂̍s�g���A�s��I�Ȃ��̂��Ƃ����F���ł���B
�@���̎�����F��(���o)���邱�Ƃ��A�ُؖ@�Ƃ������̂̈Ӗ��ł���A�u�@���v�̈Ӌ`�������Ɍ��o����Ă���̂��Ǝv���B�܂�A���̎��������o���Ă��Ȃ���A�����͌��݂����ł���悤�ȁu���]�v�̖\�͂́u��̓I�ȁv�S����ƂȂ��Ă��܂��̂ł���A���̖���}�ȏ�ԁA�_�b�I�\�͂̔×�������邽�߂ɂ́A���̎���̎Љ�I�ō����I�Ȗ\�͐��̎��o�̂��ƂɁA�r��������O��(�����I������_��ݕ��Ȃ�)�����\�I�Ɍ`������u�@���v�̂悤�ȃV�X�e�����`�����鑼�͂Ȃ��Ƃ����̂��A�w�[�Q���I�Ȏv�z�̓��e�ł͂Ȃ���(�t���C�g�̒���A���Ɂu�����ւ̕s���v���A���̖��Ɏ��g��\�I�ȌÓT���낤�B)�B�����ɂ��R���ɂ��A���̐����ɑ���S�ɔZ�W�͂����Ă��A�����������_���p������Ă����ƍl������B�������������̂��A�ڂ��ɂ͂����ƌ����Ă��Ȃ��������A����Ȍ�̓��{�̎Љ�S�ʁA�v�z�E�ɂ��������Ă������̌����ƌ�����̂�������Ȃ��B
�@���炪�s�g����Љ�I�Ȗ\�͂��A�s���̂��̂ł���Ƃ������o���������Ƃ��A���ƂɗU�����ꂽ�\�͂̔×��́A���ɏ����������߂邾�낤�B�������u�ϋq�v�̐Ȃɍ����ċ��ƓI�ɕ�����ӏ܂����㐭���I�ȋ��\�̑��u�ɂ́A������������j�~����Ƃ����A���̈Ӌ`���������B���▾�炩�ɂȂ��Ă���̂́A���̋@�\�̑r���ł���B
�@�ł͂���ɑ���A�u�]���̖\�́v�̔×��ւ̐V���Ȏ��~�߂��A�ǂ̂悤�ɂ�����\�z�ł��邩�B���_���̓������ڂ��ɏo����킯�ł͂Ȃ����A�������̑���ɂ����ł́A�ڂ����g���V�A�W�O�N��ȗ������ƌ����Ƃ��Ă����A���́u���\�v�Ƃ������̂̈Ӗ��ɂ��āA���v���Ƃ���������������������L���Ă��������B
�@����́A�L�₳��̘_����N���Ă���A������̏d�v�ȃe�[�}�A����Ώے��I�����̔F��(���Ԃ̕`��)�Ɨϗ��I����(�����̕]��)�Ƃ̐ڑ��Ƃ������Ɋւ��B
�@
�@�u���\�v�̌��p�́A�������܂߂����j�S�̖̂\�͓I�ȓW�J���A�܂�Ŋϋq�̂悤�Ɍ��o�����_�̊l���ɂ���Ǝv���B�ӔN�̃t���C�g���͂��߁A�����������[���A�I�Ȏ��_�̏d�v���͑����̐l�Ɏw�E����Ă����B
�@�������Ɉ�ې[���̂́A�������������I�Ȗ\�͐��̎��o�ƁA����Əd�Ȃ��Đ�����A���Ȃɑ��ĉ��Q�I�ȑ��҂����܂ސ��E�S�̂ւ́A�����̂悤�Ȋ���A(�܂��Ƀt���C�g���g����ɂȂ��Ă���悤��)�قƂ�ǂ̏ꍇ�j��I�ȁu�]���̖\�́v�̔�Q�������̐l�ɓ����I�Ɍ�������̂��Ƃ������Ƃł���B�����ɂ́A���Q�҂Ƃ̋��Ɛ���f�`�������̂���u���҂̘_��(�m)�v���z����A����������Ǝv����B
�@�����đz������Ȃ�A����́A�u���\�v�̗͂�p���邱�ƂŎ��Ȃ̔�\�͂̑̌����q�ώ����邱�Ƃɂ���āA�u�]���̖\�́v�Ƃ������x�ɂ�镪�f����A���҂Ƃ̋����I�Ȑ��̉\������낤�Ƃ���A���肬��̐헪�̂悤�Ȃ��̂��B����͎����̔�Q�̌��̉ߍ������y�����邽�߂̋��\���Ȃ̂ł��Ȃ��A���x�����߂́A��\�͂����т悤�Ƃ���҂����̌���I�ɌŗL�̕���Ȃ̂ł���B
�@���炭�A�^�́u���\�̗́v�Ƃ́A�����������̂�����ɂ����ւ����̂Ȃ̂��낤�B����́A���x�̎x�z�ɍR����͂Ƃ����Ӗ��ŁA�l�Ԃ́u�\�́v�̂����Ƃ������Ȍ`�Ԃł���Ƃ����v����B
�@���������ɁA�u�]���̖\�́v�̖���}�Ȕ×��ɑ��ẮA����͋t���I�����A�×��������~�߂邽�߂̐��x(���\)�Ƃ��Ďp������킷�B�u�]���̖\�́v���s�g���鑤�A�܂萧�x�⑽�����ɂ���Ď��ꂽ�҂����̑��́A���ł����̂悤�ȁu���\�v�����Ȃ���̂ĂāA����}�ȍU��(���x�I�\��)�̏Փ��̑�g�ɐg���ς˂邱�Ƃ�_���Ă���B
�@����͕ʂ̑��ʂ������A���Ȃ��U������\�͂̑̌����A���҂ɂȂ���悤�Ȏ��o��L������ؒf���āA�W�c�I�ȁu�]���̖\�́v�̔×��̂Ȃ��ɕ����߂悤�Ƃ���ԓx���B�u�]���̖\�́v�̍s�g�҂����́A�\�͂̋L�����B�����邱�ƂŁA���Ȃ̖\�͂̎��o���Ƃ����đ��҂ɊJ������H������������Ƃ���B
�@����́A���Ȏ��g�̕s���Ȗ\�͐��ɋC�Â����Ƃ�ʂ��đ��҂Ƃ̊W���̑厖��(�ϗ���)�̈ӎ�����ނƂ����A�l�ԂɂƂ��ėB��\�ȁu�ϗ��ւ̓��v�����Ă��܂��ԓx�Ȃ̂ł͂Ȃ����B
������
�@���̂悤�ɁA�u�]���̖\�́v�ɑR����A�l�Ԃ̐��̂����Ƃ������Ȍ`�Ԃ́A�u���\�̗́v�Ƃ��Č����Ǝv����B
�@�l���������g�̖\�͐������(�q�ώ�)���邱�Ƃŗϗ��I�Ȑ����ւƓW�J���Ă������߂̂��̌_�@���A�[�I�ɌĂԂƂ���A����́u����v�̋@�\�ł���Ƃ����Ă悢���낤�B
�@���Ƃ���ƁA���̂悤�ȈӖ��ł́u����v�̌��\�̎��Ă��A���݂̏ɂȂ����Ă���Ƃ������ƂɂȂ낤���B
�@���ꂱ��l�������ɂ́A����������ӂꂽ�Ƃ���ɒH������悤�����A���̖₢�����Ƃ���łЂƂ܂��I���Ă����B
Web�]�_���u�R�[���v17���i2012.08.15�j
������v�z���čl���遄��S��F�_�b�������鎋���i�L����M�j
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU�@2012 All Rights Reserved.
|
| �\���i�ڎ��j�� |