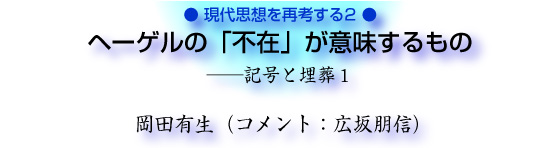|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「La Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
|
1
前回のおさらいから始めたいのだが、掲載されたST氏の論文では、デリダの諸論文における「継承」のテーマの内容が整理され、そこでは「現在の同一性への閉塞」ということが「継承」を困難にするのだという認識が提示されていることが語られていた。
また、この「現在の閉塞」は、デリダが取り組んだ西洋の形而上学の文脈においては、「意味」の支配と呼べるものに結びついていること、それは存在者のみならず「存在」という概念を「現前」として扱う態度(ハイデガーを指す)にも深く関わっているのだという、デリダの考えが示されたのである。
このように整理されるデリダの考えは、たとえば「記憶」という事柄については、次のように表現できるものとされる。
デリダが目指しているもの、あるいは待ち望んでいるものが、「閉塞」からの「開け」であり、何ものかの到来の条件が切り開かれることであることが、ここからも分るであろう。
***
さて、このようなST氏によるデリダの思想の要点(「継承」をめぐる)の提示を受けて、ぼくは前回、次のように書いたのだった。
そして、この「問い」を、自分が体験した80年代以後の日本社会を特徴づける、(おもに消費社会的な)「記号」の氾濫と呼べる現象に結びつけたのが、前回のぼくの文章の最終部だった。
2
この「記号」の問題を考えるにあたって、まず当時のぼくにとって特権的といってもよい書き手であった、柄谷行人の論考「ライプニッツ症候群」(1988〜89年発表 『ヒューモアとしての唯物論』所収)を糸口にしたい。
「吉本隆明と西田幾多郎」というサブタイトルが付けられたこの有名な文章では、初めに、柄谷が「閉じられたシステム」(それは直接には日本の言論空間を示唆している)を越える契機として見出した「関係の外部性(偶然性)」という概念が、「多数性が実際は単一性にほかならない」(p128)というライプニッツ的な論理への批判に行き着くことが示される。
スピノザがライプニッツとはっきり区別されているのは、大事な点なのであろうが、あえて触れないでおく。
柄谷は、ライプニッツの論理から帰結する、こうした「単一性(の支配)」による閉塞を乗り越えるものとして、ラッセルが提示した「外面的関係の理論」に着目する竹内康二の研究を紹介して、次のように述べる。
そしてこの後、柄谷は、こうしたライプニッツ的な思考が、当時の日本の思想や言論の空間を覆っている状況を、吉本隆明の思想の変容と、西田哲学のリバイバルという、二つの事例をあげて語り、批判していく。
このうち西田批判については、後で若干触れることになると思うが、「記号」の問題に関連して、ここでとくに取り上げたいのは、柄谷の吉本批判の方である。
そこで柄谷は、1950年代には「関係の絶対性」という名高い概念によって(非ライプニッツ的な)「関係の外面性(外部性)」の認識をつかんでいたはずの吉本が、60年代以降、しだいにそれを「内面化」してしまい、日本のライプニッツ的な閉じられた思想空間に、いわば取り込まれていったという見方を示している。これは、より後年の吉本の高度消費社会を全肯定する姿も、その延長上に見出されるものだろう。
その過程で大きな転機となったものとして注目されているのが、吉本の文学表現論における「表出」の概念であり、「記号」というテーマは、ここに顔を出す。
柄谷によれば、吉本における「表出概念」とは、一般に考えられているようにマルクス主義のリアリズム論に対抗して主観的な自己表現を主張するためのものではなく、ライプニッツにおける「表出」と同様に、「あるものが何かを表出する」という形で、あるもの(作品)と何か(現実)との対応関係(つながり)を意味するものであるという。
そして、この表出するものが記号(シンボル)だと、柄谷は述べている。
ここで言われている「世界」とは、(公式的な)マルクス主義理論が考えるようなそれではないが、やはり抽象的なものであるといえよう。
柄谷は、吉本が「表出概念」によって主張したのは、たんに文学作品の「自立性」(吉本においてこの言葉が、「政治からの自立」という意味合いをまず持つことは明らかだろう)ということだけではなく、吉本の考える現実に、すなわち「情況」に文学が根ざすことを示すものであったと言う。
柄谷は、こうした吉本の思想のあり方を、一概に批判しているわけではないのだが、ぼくがここで注目したいのは、ここでは吉本の「表出概念」が、文学作品の政治的な領域からの「自立」を確保するものでありつつ、同時にある種の現実(「情況」)への文学表現の従属、少なくとも深い相互的な関係を意味するものとして捉えられていること、そしてそれを可能にするものとして記号という存在が呼びだされているということ、このことである。
これは、吉本において記号は、「情況」と呼ばれる特殊的(ローカル)な場への文学作品の従属を保証するものだったということである。
その後の吉本の思想や発言を考えても、また広くこの時代から現在に及ぶ日本社会全体の動向を考えるにおいても、この柄谷の分析は、いまなお重要なものと言えると思う。
3
ここで、「記号」のテーマからはいったん離れる形になるが、「ライプニッツ症候群」の内容を、もう少し詳しく見ておきたい。
この論考の初めのところでは、「多数性が実際は単一性にほかならない」というライプニッツ的な論理、言い換えれば、各モナドが示す多様性を同一の宇宙の「表出」として捉えるようなタイプの考え方が、マルクスが批判したヘーゲルの論理学と同型のものと見なされ批判の対象とされている。
そこで言われている「ヘーゲルの論理学」とは、実際には、交換の場において全ての商品がおのおの共通の本質(労働時間)を表出しているとする、古典経済学の価値についての考え方と重なるものとして述べられている。それは、各商品に一種の「力」が内在すると考えることと同じであるが、その考え方は「ヘーゲルの論理学」と重なるものだと、柄谷は言うのである(このことの当否は、ぼくには分らない。)。
商品(個物)を共約可能な意味を内在し表示するものと考えることは、「突きつめていくと」、各商品(モナド)を、共通の本質(労働時間)を表出するものであり、それゆえに交換(モナド間の交通)が可能になるとする、ライプニッツの論理に行き着くと、柄谷は言っているのだと思う。この論理(「予定調和」)はもちろん、経済学的には「見えざる神の手」と呼ばれるものにあたるだろう。
マルクスは、そのような古典経済学(及びヘーゲル?)の考え方に対して、各商品に内在する共通の本質(労働時間)などは本当は存在せず、売買という非対称な場における「命懸けの飛躍」こそが、いわば真にリアルなものであると考えた。
もともと商品と商品との交換が成立するのは、「共通の本質」によるのではなく、偶然的・外面的な出来事にすぎない。貨幣による交換はその事実を見えなくするようだが、商品と貨幣との交換(売り)がもつ無根拠さ、非対称性は、この根本にある「関係の外面性」を露呈させざるをえない、というのが、柄谷によるマルクスの議論の解釈である。
こうして、論考「ライプニッツ症候群」においては、「ヘーゲルの論理学」は、個物を共通の本質を「表出」するものとして捉えることでこの世の現実を「予定調和」の色彩によって塗りこめようとするライプニッツや古典経済学の論理のバージョン(変形)として解釈され、マルクスによる古典経済学への批判によって、ヘーゲルの学に対する批判も同時に遂行されて余すところがないかのように見なされている感がある。
要するに、ここではヘーゲルには、ライプニッツ的なものの一バージョンという意味合いしか与えられていない、もしくは、あえてそういう限定的な役割を割り振られているように思われるのである。このことは、実はこの論考の全体を通して受ける印象である。
このことが、とてもくっきりと示されていると思うのは、この論考の後半、当時再ブームが始まっていた西田幾多郎の哲学を、柄谷が批判するくだりだ。
そこで柄谷は、西田のいう「一般者の自己限定」という重要概念を、無としての一般者の自己差異化の運動であり、「フィヒテ・ヘーゲルと同じ論法である」と断じている。
西田はヘーゲルの論理を「過程的弁証法」(類の自己実現の論理)と呼んで批判し、キルケゴール(個の思想)を持ち出して、それを乗り越えようとしたが、結局は、「絶対矛盾的自己同一」という形で、ヘーゲル同様の論理の自己完結的な運動を語ることで終ってしまった。ゆえに西田は、ヘーゲルと同様に全体主義者として現われるほかはなかったのだと、柄谷は言う。
だが柄谷のこの議論は、見方を変えれば、ヘーゲル(あるいは「フィヒテ・ヘーゲル」)の論理を、西田と重なるものとしてしか捉えていないということである。それは、実体(類)の自己運動という考え方、柄谷によって「全体主義」と名指されるような考え方に帰着するとされる。
いわば全体(類)こそが現実であり、個はそれを表出する限りでの多様なものというにすぎず、それ以上の価値はない。そのようにも要約できるであろうこの考え方は、柄谷がこの論考で批判するライプニッツ的な論理の核心であるとも言えよう。
このように、当時台頭していたライプニッツ的な論理に対する批判において、今日読んでも十分に刺激的な柄谷の「ライプニッツ症候群」は、しかし、「ヘーゲル」という項を、ライプニッツ的なもののなかにすっかり包み込んでしまっている。
そこに、ぼくは疑問を感じる。
これには、この論考があくまで当時の日本社会の「ライプニッツ症候群」的な状況を批判する目的で書かれたものだということと、また執筆当時のマルクス主義が置かれていた状況(ソ連崩壊に向う前夜であり、従来から言われていたマルクスとヘーゲルとの切り離しということが、一層切実なテーマになっていたと思われる)とが、密接に関係しているのだろう。
だがそればかりでなく、柄谷は、ヘーゲルをライプニッツ(や古典経済学)から隔てるものの重要性、それは同時に、マルクスにとってヘーゲルが占めていた位置の大きさでもあろうが、それを認めていなかったのではないかと思う。
***
ここで再び「記号」というテーマを呼び戻して整理するなら、ライプニッツ的・古典経済学的な体系における記号と、ヘーゲル的な記号とは、柄谷において、基本的に同じ意味合いを持つものと考えられている。
それらは、「関係の外面性(偶然性)」を見えなくし、商品や作品が流通する単一的・全体主義的な空間を自明のもののように人々に思い込ませて、たとえば「自立」や「表現」や「多様性」といった事柄についても、その自明性のなかでしか考えることが出来ないようにさせる機能を持つものとして、同一とされるのである。
4
それでは、こうした柄谷におけるあるヘーゲルのある種の「不在」が意味するものとは、果たして何だろうか。
ここで、冒頭に触れたST氏の論文の題材ともなった『哲学の余白』に収められたデリダの論考「竪坑とピラミッド」を、導きの糸にしたい。
というのも、この論考は、「ヘーゲル記号学への序論」というサブタイトルをもち、最終部ではまさしくライプニッツの記号学との対比において、ヘーゲルのそれが批判されているからである。
つまりここでは、ヘーゲルが否認し抹消した記号の可能性を重視し追求した人としてライプニッツが称揚されているわけだから、「ライプニッツ的な論理」を批判しつつ、そこに回収されない意義をヘーゲルのなかに見出そうとするわれわれの意図からすると、反対の方向を向いているようにも見える。
ここで、前回ぼく自身が書いたことに触れておきたいのだが、そこでは植草甚一の文体や、その後継者というべき糸井重里、村上春樹らに代表されるような形式的な表現のあり方が、80年代以後の日本社会では、その本来持っていた、同一的な意味の支配を揺るがす力を失い、体制を容認し支えるようなものに変容してしまったのではないか、という意味のことを書いた。
デリダが、この論考でライプニッツの記号学に託して語っているのは、この、同一的な意味の支配を揺るがすものとしての「形式」、つまりライプニッツ的な記号の力だったであろう。それが日本の文脈においては、この「記号」は、そのような力を発揮することなく、逆に消費社会の同一性を強化するものとして働いたと思われる。そのローカルな状況(記号が全体主義的に機能してしまう社会)を批判したのが、柄谷の仕事だったわけだ。
だからほんとうならここでは、日本の文脈においては実現しなかった、形式的な記号の惑乱的な威力の可能性と、その発現の条件について、ヘーゲルの記号学を批判し、ライプニッツのそれを称揚するデリダの議論に沿って考えるのが筋かもしれない。
***
しかしここで試みたいのは、デリダが、批判の対象としての「ヘーゲルの記号学」のなかに何を見出していたか、批判され乗り越えられようとするものの詳細な記述に、視線を注ぐことである。
その理由はひとつには、そうした眼差しが、デリダの思想の、またヘーゲル自身の思想の、大きな特徴をなすものだと思えるからだ。
***
さて、この論考でデリダが行っているヘーゲル記号学への批判の核心は、ヘーゲルが形式としての記号の独立的な重要性をいったんは見出しながら、ただちにそれを、弁証法的な論理を展開するための透明な項のようなものとしてしまった、ということである。
形而上学(その集大成者がヘーゲルだ)は、『記号というものをなんらかの移行=通路としてしか扱えなかった。』(p140)と、デリダは言う。
だがそれまでの過程でヘーゲルが、記号の一面である能記(「能記の不活性な身体」)の重要な性格を発見していたことに、デリダは注意を促すのだ。
ヘーゲルは、能記の「墳墓」としての性格に気づいていた。このことは、記号を意味の体系のなかに回収して捉えることを不可能にするものであり、意味に回収されない、形式としての記号の可能性を、ヘーゲルが察知していたことを示すだろう。
それは、詳述すれば以下のような認識である。
記号は、「魂・生命」すなわち所記を宿すことによって初めて「生きた身体」となるのであり、それなくしては能記は「不活性な身体」(形式)である以外ない。
だが、「墳墓」と呼ばれるこの能記の固有の身体は、そのなかに生を閉じ込め、保護し、永続させて行くものでもある。
それは形式の力によって、生を自然的(偶然的)な死から隔離し、別のものに変えるのだ。
「墳墓」が「生の消滅を聖別する」と言われているのは、記号というものは、死(形式)を通して、人間の生を「死すべきもの」から「永続的なもの」へと意味づけ変容させてしまうものだからである。
記号の働きは、生をいわば文化的なものに、永続的なものに変容させる。
だがわれわれは、この働きの外側で、記号化されざるものとしての生を見出すことはできないだろう。
「魂・生命」とは、この働きの結果として事後的に見出されるものにすぎないからだ。
***
ヘーゲルは、意味の体系(人間の世界)を根底で規定している、この「死の働き」、形式としての記号の作用に気づいていたと、デリダは言っているのである。
それは、われわれにとっての世界が、どこまでも形式によって媒介されたものであるしかない、という認識であり、さらに言えば、世界を変えるということも、何らかの形式の媒介によってしか可能でない、という認識だろう。
あえて書き添えれば、それはわれわれにとって、記号(言語)や制度を通した他者への暴力の行使が、不可避であることをも露呈させると思う。
こうした考え、つまり形式としての記号への注目は、たしかに意味の体系を動揺させるだろう。
これが、デリダのヘーゲル理解の眼目だったと考えられる。
***
たしかにデリダの批判は、ヘーゲルがこのような直観的な洞察にも関わらず、結局は形式としての記号がもつ力を否認し、それを論理のなかに「封入」してしまったことに向けられている。
だがデリダの基本的な態度は、ヘーゲルの思想が含んでいた、この根本的な部分にこそ注目するものだったと思う。
それは、われわれがなしうることは「死の労働」だけであり、記号の体系の外部を夢想するのではなく、現実の記号の体系(制度)を別種のものへと更改することで、生の可能性を切り開いていくしかない、といった考え方である。そのあくなき試みだけが、夢想ではない何事かを可能にする。
デリダは、記号に媒介された生という、われわれの逃れられない現実を引き受けながら、歴史のなかで世界を変えていこうとする、ヘーゲルの意志を受け継いだのだ。
それは、近代的な国家や文化の発展を論じたヘーゲルの思想の運動を、その核心において受けとめ、別の方向へと乗り越えようとすることである。
記号(死)に媒介されていない生というものが、われわれにとってありえないように、制度の暴力に汚染されていないような理念というものもありえず、また歴史の外で無垢・無実でありうるような思考というものもない。
この事実を直視するときに、はじめて開けてくる道筋というものがある。
それは、近代という運動の内部で、歴史の暴力に身を汚しながら、「もうひとつの世界」への実践を重ねること、いわば別種の記号によって境界線を引き直していくという道である。
5
ぼくは、論考「ライプニッツ症候群」の柄谷が見ていなかったヘーゲルとは、こうした存在であると思う。
つまり、そこでは、ヘーゲルが体現した近代というものが、乗り越えていくべき真に内在的で現実的な対象とはされていなかったのだ。デリダが、ヘーゲルの思想との対決を通して、近代的制度の外部を夢想するのではなく、別種の記号の体系(制度)を歴史のなかに作り出すことの重要さを示唆したようには、柄谷は、近代の体現者であるヘーゲルの思想と取り組まなかった。
その思想は結局、歴史的現実のなかに自分を置くことを回避したのだと思うのである。そのことは、ヘーゲルの思想が持つ、近代化を形成していく動力の裏面のようなもの、つまり、弁証法的な発展や、共同体の形成といった、根源的なところから何らかの秩序・制度を現実に作り上げていこうとする力を、柄谷のみならず、日本の「現代思想」が持ちえなかったことにつながっているのではないだろうか。
いや、それが必ずしも日本だけの問題ではないことを、柄谷自身が知っていた。
***
じつは柄谷は、彼の言う「ライプニッツ症候群」が、構造主義に深く関わるものだということを明言していた。つまりそれは、日本特有のものという面を持つと同時に、構造主義的な思考の支配のなかで生じた世界的な現象という面を持っていたということである。構造主義的な思考の特徴は、歴史的な現実から切断されたところで形式的・原理的に物事が捉えられるとすることだろう。それは、いわゆる「全体主義」とは一見違っているけれども、単一性に収斂していくような多様性の思想である。
柄谷は、その現象を批判したのであり、しかもそれが世界的な現象でもあるということを直観していた。
それは、形式としての記号を重視するという思想的な戦略(たとえば構造主義、ポスト構造主義)が、何らかのローカルな、ないしはグローバルな条件のもとでは、歴史を否認する単一的な社会の形成を強化する権力装置として働くことがありうる、という直観だったといえる。
しかし、そうした認識にも関わらず、柄谷の言説は、実際には構造主義的なものの域内に留まったと思われるのだ。
そこに、この時代のローカルないしはグローバルな状況が有した、ヘーゲルの思想の重要な側面を見えなくするような作用の、強力さを見る思いがする。
***
たしかに、人間が制度に媒介された生しか生きられないというヘーゲルの認識の一面は、構造主義の世界観に根拠を与えるものだとも考えられる。
だがその認識は、制度という歴史的な現実を変えていくということが、われわれの生を構成する最も根本的な行為であることの発見でもある。われわれのどんな思考や認識も、この現実的な制度の次元を媒介していないことはありえない。この生の基本的な条件としての制度に関わり、それを変えていくことは、回避することの出来ない思考の基盤なのである。
制度による媒介の不可避性の認識は、制度という歴史的現実を変革する行為の根源性を同時に意味するのでなければ、「意味の支配」を揺るがす力にはなりえない。
ヘーゲルの近代主義の核心(またデリダの反近代主義の核心)は、おそらくそういうものだ。
つまりその精神は、あくまで行為の、また変革の思想なのである。
構造主義や記号論が、何らかの条件のもとでは、それを見えなくさせるように機能してしまう、ヘーゲルの思想の重要な意義とは、そうしたところにあるのだろう。
付け加えれば、これらの形式的思考が、そうした権力的な機能(ぼくには、そうとしか思えないのだが)を持ちうるということは、記号が持つ政治的暴力としての性質を、如実に示すものだと思う。
***
もちろん、このこと、つまり端的に言えば、ライプニッツに抗してヘーゲルを見出すという課題は、今日のわれわれ自身にも要請されているものである。
それは、ライプニッツだけでなく、ヘーゲルを真に克服するためにも、引き受けねばならない要請なのだ。
★プロフィール★
岡田有生(おかだ・ありお)
1962年生まれ。男性、独身、親と同居。プロフィールに書くようなこともなく現在に至る。ブログ:Arisanのノート
【コメント】
妄想二題広坂朋信
■当たるも八卦、当たらぬも八卦
今回、岡田さんが取り上げたのは柄谷行人「ライプニッツ症候群」だ。ライプニッツといえば「易」だろうという安易な連想から、柄谷「ライプニッツ症候群」が発表されたのと同じ1988年に刊行された高田淳『易のはなし』(岩波新書)を再読した。この本は、題名からすると、東洋の占いの伝統についての易しいお話を読ませてくれるエッセイのような印象を受けるが、実際は、『易経』についての明清代の思想家・王船山の解釈を再解釈しながら『易経』の思想構造に迫るという小著ながら本格的な内容で、初めて読んだ時はもちろん、今回も歯が立たなかった。とはいえ、難解なのは本論部分であり、易と西洋文化の交渉を描いた序論部分は簡潔明瞭で、ライプニッツと易についての私の思い違いを正してくれた。
私の思い違いとは、ライプニッツは万象を陰と陽で記述する易にヒントを得て、0と1ですべての数字を表す2進法を思いついたというものである。てっきりそう思い込んでいたのだが、これはまったくの勘違いで、ライプニッツは易を知る前に独自に2進法の着想を得ていて、自分の考案した記数法の原理と同じものが古代中国にもあったと知って驚いたというのが真相だったようだ。私のつまらない思い違いはともかく、高田氏によれば、ライプニッツは易について誤解をしている。易と2進法は発想の違うもので「ライプニッツの二進法がたまたま見かけの一致を示したにすぎない」のだそうだ。
ライプニッツ・2進法・コンピュータ理論の基礎、という連想から、私は易というものに何か完結したシステムのようなイメージを抱いていたが、高田氏によればとんだ誤解で、易とはそういうものではないのだそうだ。高田氏は「易は未済であり、完結することはない」という。「未済」とは六十四卦の最後の卦だが、「未済は、生の終りの消滅ではなく、生生の衰退に他ならない。天地に永遠の終りがないこと、世界に終末のないことを示すために、易は未済を終わりに置いたのである」。そうしてみると、易の示す世界観は、完結しない生々流転の、その折々の相を陰と陽の組み合わせで映し出すことにあり、そうだとすれば、易は「予定調和」とは縁がないことになる。だから、「天の自然に吉凶を委ねてしまうところには、聖人の易を学ぶ易学は存在しない」のだ。
だから、「当たるも八卦、当たらぬも八卦」なのだろうと得心した。当たるか当たらないかはどうでもいいのだ。易は予測や予知ではないのだから。
■オフィーリアの墓
岡田さんはデリダのヘーゲル論のひとつ「竪坑とピラミッド」(『哲学の余白』所収)から引いた言葉に「『精神現象学』は死の労働の叙述である」というものがあった。なんのことかわからないがなかなか味わい深い。『精神現象学』、「死の労働」と言われて私がすぐに連想したのは『ハムレット』の一場面だ。
墓地で墓穴を掘っている道化に行き合ったハムレットは、それが婚約者オフィーリアを埋めるためだとは知らずに「誰の墓だ、これは?」と声をかける(以下、『ハムレット』からの引用は福田恒存訳、新潮文庫による)。
このやりとりから、道化とハムレットのブラックジョークの応酬が続く。やがて道化は土の底から頭蓋骨を掘り出す。ハムレットはそれを見て、生きていたときは政治家か廷臣かと想像する。道化がまた頭蓋骨を掘り出すと、今度は法律家だろうと言う。三つ目の頭蓋骨は、掘り出した道化に心当たりがあって、これは先王(ハムレットの父)の道化師だったヨーリックのしゃれこうべだと言う。
ヘーゲルは『精神現象学』において骨相学を批判している。「骨相学」とは頭蓋骨の形状から人の性格や能力などを知ることができるとする説で、ヘーゲルの時代には大いに流行ったトンデモ科学である(骨相学については本誌掲載の別稿で触れているのでそちらに譲る)。この骨相学批判の途中でヘーゲルは、この場面を思い起こして「もちろん、ハムレットがヨーリックの頭蓋骨を見たときのように、ある頭蓋骨を見て、多くのことを思いつくことはできる」と言っている。この言葉は次のような文脈に置かれている。
頭蓋骨それ自体はあくまでただの骨でしかないのだから、「ハムレットがヨーリックの頭蓋骨を見たときのように、ある頭蓋骨を見て、多くのことを思いつくことはできる」が、頭蓋骨自体が何か頭蓋骨以外のものを語り告げることはないのだ、というのが、ヘーゲルの言い分である。
しかしながら、私としてはこの大哲学者に反論を試みたい。骨相学に対する批判についてはヘーゲルの言うとおりだろう。しかし、頭蓋骨は、それがヘーゲルの時代には存在していなかったレントゲン写真の映像でもないかぎり、確実に自らが骨であること以外の何かを告げている。つまり、頭蓋骨が転がっていれば、その持ち主である誰かの死を雄弁に物語っているではないか。実際に、頭蓋骨、しゃれこうべ、ドクロの形象は、多くの場合、死を意味する記号として用いられている。頭蓋骨は剥きだしの死の記号である。
さて、『ハムレット』の道化は墓穴を掘っている。それは死体を埋めるためである。しかし、死体を埋めるために穴を掘りながら、別の死体、頭蓋骨を掘り出してしまう。さて、いったい、道化が穴を掘っているのは、死を埋めるためなのか、それとも掘り出すためなのか。死を埋めようとして掘り出してしまう、まことに奇妙な「死の労働」である。
奇妙なことはまだある。ヨーリックとは、ハムレットの父王に仕えた道化だ。墓場の道化はそのヨーリックから葡萄酒を頭に注がれた、これを洗礼と解するならば、墓場の道化はヨーリックの後継者ということになる。そして、もう一方のハムレットは、同じ名前をもつ先代ハムレット王の息子であり、父の遺恨を晴らそうとする点で死者の代理人である。つまり、両者は、死者の分身という立場にある。
墓場の道化は、ハムレットに誰の墓を掘っているかと問われて、自分の墓だと答えていた。けれども、墓に埋められるのはオフィーリアのはずだ、するとこの道化はオフィーリアということになるのか。そして穴からはヨーリックの死の記号が掘り出される。墓掘りをする道化は、いったい誰の墓を掘っているのか。やはり道化自身の墓ではないのか。そもそも墓場の道化は生者か死者か。
それだけではない。シェイクスピアの劇世界において、道化は王の影法師である(『リア王』)ことはよく知られている。そして、叔父に王位と母を奪われたハムレットは、父ハムレット王の遺恨を晴らすべく狂気をよそおい、生か死か(存在あるいは非存在)などとうそぶいて道化のようにふるまっている。ヘーゲルは「人間の真の存在はむしろその行為の結果にある」と言っていた。現在の王は簒奪者であり、本来王位につくべき王子は道化のふるまい、さてそうすると、墓場の道化は、いったい誰の影法師なのか。ハムレットが道化なのか、道化がハムレットなのか、あるいはオフィーリアか。生きているのは誰で、死んでいるのは誰なのか。このように、なにやら怪しい妄想をかきたてる場面をヘーゲルは引いているのであった。
前回、ST氏のデリダ論から「内に留まりながら、その内において自己自身との隔たりを見つけるべき」という提言を教訓として記憶したが、さては「内」とは墓穴の内のことだったかと苦笑いしている。
Web評論誌「コーラ」15号(2011.08.15)
<現代思想を再考する>第2回:ヘーゲルの「不在」が意味するもの――記号と埋葬1(岡田有生)
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2011 All Rights Reserved.
|
| 表紙(目次)へ |