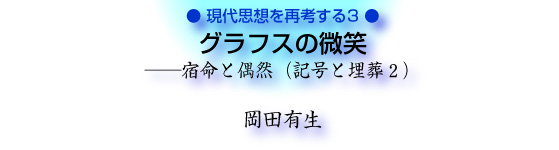|
|
|
Web�]�_���u�R�[���v |
|
���n���̎� ���{���̕\���i�ڎ��j�� ���{���̃o�b�N�i���o�[ ���ǎ҂̕Ł^���ӌ��E���z �����e�K�� ���W�҂�Web�T�C�g ���v���C�o�V�[�|���V�[ |
|
���{���̊֘A�y�[�W�� |
|
���u�J���`���[�E�������[�v�̃o�b�N�i���o�[ ���]�_���u�k�� Vue�v�̑��ڎ� |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
|
�P�@�╔�b�ɂ��u�I�v�e�B�~�Y���v�ւ̒���
�@�O��̕��͂ł́A���J�s�l�̘_�l�u���C�v�j�b�c�nj�Q�v���Q�Ƃ��Ȃ���A�W�O�N��ȍ~�̓��{�ɂ����邢����u����v�z�v�̏d�v�ȓ������A���C�v�j�b�c�I�ȋL���̘_���̎x�z�Ƃ������ƂɌ��o�����Ƃ��A�܂����̏�������̐��E�I�Ȏv�z�̕����ɂ����Ă͍\����`�I�Ȏv�l�̔e���Ƃ������ۂ̈ꕔ�Ƃ��Ĉʒu�Â�����̂ł͂Ȃ����A�ƍl�����̂������B
�u���C�v�j�b�c�I�ȋL���̘_���̎x�z�v�Ƃ������Ƃ��ڂ��������ƁA���j�����������ꂽ�����ȍ��Ƃ��Ă̌����A�P��̑S�̂̕\�o�ƍl�����鏔�L��(���i�h)�̑̌n�̂Ȃ��ŊW�������\�蒲�a�I�ȋ�ԂƂ��āA�Љ�⎖�ۂ𑨂���Ƃ������Ƃł���B
�@�����ł͋L���́A���Ƃ��f���_��������悤�ȁu�Ӗ��v�̎x�z��f������`���I�ȗ͂Ƃ��ē������Ƃ͂Ȃ��A�t�ɑS�̂�\�o���鍀�ł��邩�̂悤�ɋ@�\���邱�ƂŁA���̋@�\�̏�(�s��A�v�l��ԁA�������)�̓��ꐫ�ɂ��Ă̐M�߂��A����������A�u�S�́v�Ȃ���̂��m�łƂ��đ��݂��Ă���Ƃ����C�f�I���M�[���A�����Ɏx������������̂Ƃ��ē����B
�@����A�u���C�v�j�b�c�I�Ș_���v�Ƃ́A�u���l���v�̖��̉��ɁA���ۂɂ͎v�l��l�X�Ȏ��H�̏ꂩ��u�S�́v�ɓ�������Ȃ��^�ɑ��l�Ȃ��̂̑��݂��������A�Љ�I�����̉\���ꐫ�̂Ȃ��ɏk�����Ĉ͂�����ł��܂��悤�Ȃ��̂��ƁA�ڂ��ɂ͎v����B
�@�ڂ��͕��J�ɂȂ���āA�����̓��{�ɂ�����(�����Č��݂ɂ��y�Ԃł��낤)�A���̃��C�v�j�b�c�I�ȋL���̘_���̎x�z���A�\����`�I�Ȏv�l�̎x�z�Ƃ������E�I�Ȏv�z�̕����̂Ȃ��Ɉʒu�Â�����ƍl�����킯�����A����Ɋւ��Ę_����O�ɁA�����菭���O�̎���Ƀ��C�v�j�b�c�̎v�z�̏d�v���ɒ��ڂ��Ă����_�҂̗D�ꂽ�������Q�Ƃ��Ă��������B
�@�Ƃ����̂��A�̂����Ȃ��Ƃ������Ă������A�ڂ����g�͂܂����C�v�j�b�c�̖���ǂ��Ƃ��Ȃ��̂ŁA��ɂ���Ė��������l�̕��̗͂͂���邱�ƂŁA���C�v�j�b�c�̎v�z�����Ӗ���������薾�m�ɂ��A�������킸���ł������Ɛ����͂̂�����̂ɂ������Ɩژ_�ނ���ł���B
�@���Ă��̘_�Ƃ́A�P�X�V�U�N�ɏo�ł��ꂽ�╔�b�ɂ��L���ȃJ���g�_�w�����̕s���x�̂Ȃ��́u�W�@���ԍl�@�v�Ƒ肳�ꂽ�Z���͂ł���B
�@���̂Ȃ��ō╔�́A�J���g���傫�Ȏv�z�I�]����̌����钼�O�̎����A�P�V�T�O�N��ɂ����郉�C�v�j�b�c�N�w�̉e���̑傫���ɒ��ڂ��Ă���̂��B
�@�╔�́A���́u�I�v�e�B�~�Y���v(�F���̖ړI�_�I�����ւ̐�ΓI�M��)�ւ̌X�|�������A�P�V�T�O�N��ɂ�����J���g�̎��R�����𒆊j�Ƃ���v�z�I�c�ׂ̍���ɂ���A������\�ɂ������̂��Ƙ_����B
�@�����ō╔�́A�����������C�v�j�b�c�́u�I�v�e�B�~�Y���v�̂��̎����̃J���g�ւ̉e���̑傫�����A�m��I�ɘ_���Ă���̂����A����́w�����̕s���x���o�ł��ꂽ�P�X�V�O�N���A���́u���ԍl�@�v�Ƒ肳�ꂽ�͂̕��͂����o���ꂽ�P�X�U�O�N��I��荠(���a�S�R�N�ƂȂ��Ă���)�Ƃ������㐫���A������x���f���Ă���p���Ȃ̂�������Ȃ��B
�@�u���H�v��u�����v��u�l�ԁv�̎�������u��U�v������u��(����Ί��ʂɂ����)�A�u�e�I���A�I�v�Ȏv�l�̑ԓx�̏d�v���ɉ��炩�̃��A���e�B�[��K�v�����������Ă���A���������ԓx�������Â�����̂Ƃ��Ắu�ړI�_�I�����v(�u�S�́v�ƌ��������Ă��������낤)�ւ̍m��I�ȊS�����܂��Ă����̂ł͂Ȃ����A�Ƃ������Ƃ��B
�@�����ɂ́u���H�v��u�l�ԁv�̎����Ƃ̌��т�����ΓI�Ȃ��̂Ƃ���邱�Ƃɂ���Č����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��悤�Ȏv�l�̎�����̈���A�Ăь��o�����A�V���Ɍ��ĂĂ������A�Ƃ����悤�Ȑ؎��Ȋ�]�����������Ƃ��z�������B�����ՂɁu�ُؖ@�I�v�ƌĂ��v�z�̂�����ɑ���뜜�����܂��Ă��������Ȃ̂�������Ȃ��B
�@���̘A�ڂ̑O�X��AST���̘_���Ɋ��R�����g�̂Ȃ��ŁA�ڂ��͐A���r����͂��߂Ƃ���V�O�N��ȍ~�̃N�[���ȁu�L���v�̎g���肽��(����d���A����t���Ȃ�)�̍���ɂ������̂́A�u�Ӗ��̎x�z�v�ɑ���킢�̈ӎu�̂悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ə������̂����A���̍╔�̗��_�ɂ�����Ɏ�������I�ȃp�g�X��C����ǂݎ��ׂ��Ȃ̂�������Ȃ��B
�@���������ɂ���͂��������A���H�I�Ȏ����ɂ��S�����v�l�̋�Ԃ��������悤�Ƃ��邩�̂悤�Ȏp���ɂ��v���A���̂��Ǝ��̂̐���͂Ƃ������Ƃ��āA����͗���ׂ��W�O�N��Ȍ�́u����v�z�v�̎���ɂȂ�����̂������ƍl������̂��B
�@���C�v�j�b�c�̎v�z���A�V�O�N�ォ��W�O�N��ȍ~�ɂ킽����(�����Ă����炭���݂ɂ��y���)���{�̎v�z�̏�ɑ��Ď������Ӗ������̑傫���́A�O��Љ�����J�̘_�l��A��L�̍╔�̕��͂��炤���������Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����Ǝv���B
�@���J���ᔻ�����̂́A���ꂪ�u���l���v��P��ȑS�̐��̂Ȃ��ɉ�����Ă��܂��悤�Ș_���ł���Ƃ����_�ł���A�܂�����ɐ旧���č╔�́A���́u�I�v�e�B�~�Y���v�Ƃ����v�f���A�m�����H�I�����Ƃ̍S���I�Ȍ��т����������Ă��̖��m�̉\�����J�����̂Ƃ��Ē��ڂ����̂��Ǝv����B
�@�Ƃ���ŕ��J�́A�����������C�v�j�b�c�I�Ȏv�z�̌X�����\����`�ɒʂ�����̂ƍl���Ă����̂ł���A���̑������͐��������̂��ƁA�ڂ��ɂ͎v�����B
�@�����ŁA���̍\����`�Ɋւ��ĂȂ̂����A�ڂ��̋L���ł̓t�����X�ɂ�����\����`�̗��s�����{�ő傫�ȊS���W�߂��̂͂V�O�N��̘b�ł����āA�W�O�N��Ȍ�́u����v�z�v�̎���ɂ����ẮA�ނ���\����`�ɔᔻ�I�ȁA��������z���悤�Ƃ���_�����嗬���߂Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv���B
�@���̑�\�i�̂ЂƂ肪�A�����m�i�ł���B
�@
�Q�@�����m�i�́u���R�j�ρv(�h���_)
�@���Ƃ������́A�W�Q�N�ɏo�ł��ꂽ�w�\�͂̃I���g���M�[�x�̂Ȃ��ŁA���̂悤�ɏ����Ă���B
�@�Љ�W���u�����v�ɊҌ����đ����悤�Ƃ��郌���B���X�g���[�X�̍\����`�I�ȍl��������̂悤�ɗv�Ĕᔻ���鍡�����A�������肱����Љ�`���y�шێ��̍����I�ȓ��͂Ƃ��Ē������̂́A�u�\�́v�Ȃ����u�����v�Ƃ��������ł������B
�@�܂�A�Љ�W�́u�\���v���̂��̂��`�����A�^�������A�܂��ێ��������鍪��I�ȓ��͂́u�\�́v�Ƃ����u�́v(�����I�Ȃ���)�Ȃ̂ł���A�݂̂Ȃ炸�A���́u�́v�Ƃ����Љ�I�Ȍ����������t�Ɂu�\���v�Ƃ����m�I�E�F���_�I�Șg�g�݂ݏo���\�ɂ��Ă�����̂��A�Ƃ����l�����������ɂ͂������悤���B���ׂĂ̍���́A�����I�ȁu�́v�̋�̓I�����Ƃ��Ắu�\�́v�Ƃ����Љ�I�����ł���A�u�\���v���������琶������̂ł���Ƃ������ƁB
�@���́A�u�\�́v��u�����v���l�Ԃ̎Љ�I���݂ɂƂ��Đ�ɒE���邱�Ƃ̂ł��Ȃ���b�I�ȏ����ł��茴���ł���Ƃ����l���́A�����ɂƂ��ĒP�Ȃ�F���Ƃ����ȏ�̋���(����퐭���I�ȁH)�p�g�X��тт��咣�������悤�ŁA���̖{�̌㔼�ł́A�\�͐����l�ԑ��݂́u�ߌ��I�����v�ł��邱�Ƃ����F���Ȃ��悤�Ȏv�z�́A�u�قƂ�ǎv�z�ɒl���Ȃ��v�悤�Ȏv�z�ł���A�Ƃ܂Œf������Ă���(���Q�Q�U)�B
�@���̊ϓ_����A�ߐ��̍����ȎЉ�v�z�Ƃ������A���Ƃ��Ύ��̂悤�ɍĕ]������邱�ƂɂȂ�B
�@���̂悤�Ȏv�z�I����̂��ƂɁA�u�����v(�Ɓu�J���v)�ɏd�_��u���R�W�F�[�u�̃w�[�Q���lj��ɂ��e�����A�܂������}���N�X�ɂ�鎑�{�����͂̐��k�ȓǂݍ��݂�ʂ��āA���㎑�{���Љ�ɑ���ᔻ�I���͂ƁA�l�ފw��@���w�Ȃǂ̐��ʂł��邢����u�X�P�[�v�S�[�g���_�v�Ƃ̑�_�ō���I�Ȑڍ��̎��݂Ƃ������ׂ��u��O���r���v�̗��_�����グ�Ē����̂��A�����̎��̒���w�r���̍\���x(�W�T�N)���������Ƃ͂悭�m���Ă���B
�@���������ł́A���̍������Ӗڂ��ׂ��Ɛтɐ[����͂����A�w�\�͂̃I���g���M�[�x�ɘb��߂����B
�@�ȉ��̕��͂ɂ́A�l�Ԃ̎Љ�I���݂̖{���Ƃ����u�\�́v�ƁA������߂���Љ�I�\�z�ɂ��ẮA�����̊�{�I�ȃX�^���X���悭������Ă���Ǝv���B
�@�����ɂƂ��āA�u�\�́v�́u���R�j�I�K�R���v�ł����āA�u�������邱�Ƃ͉i�v�ɕs�\�v�Ȃ��̂Ȃ̂ł���B�����āA���̓�����Ȃ��l�Ԃ̑��݂̏����ɑ��āA�Љ�Ȃ�����ł����z�I�ȑΉ�(�u���a�쐬�̃I���K�m���v)�́A���J�Љ�s���Ă����悤�ȁu�V��I�E�ے��I�\�́v�ւ̓]���̃��J�j�Y���A�v����ɑ�O����r�����]���ɂ��邱�Ƃɂ���Ė\�͂̕�����]��������悤�Ȏd�g�݂��A�Ƃ����̂��B
�@�Ƃ���ō����̗��_�ɂ��A�ߌ���̎Љ�ɂ�����u��O���r���v�̎�v�Ȍ`�ԂƂ́A�[�I�ɂ͉ݕ��̑��݂ł���A���̎Љ�I�S�ʉ��Ƃ��Ă̎��{���o�ς̓W�J���̂��̂ł���B���������āA�\�͂Ƃ�����ɓ�����Ȃ������̏�������A����ꂪ�����ł����R�ɂȂ铹�́A���ǁA���{���o�ς��̂��̂̔��W�ɂ����Ă������o���Ȃ��A�Ƃ������_�ɂȂ�B
�@�o�u���o�ς��S���ƂȂ�A����{��`���S�ʓI�ɍm�肳��镵�͋C�ł������W�O�N��̓��{�ŁA�����̎v�z���傫�ȊS���W�߂��̂��A���R���Ƃ����邾�낤(��6)�B
�@��̍����̕��͂��犴��������̂́A�u�\�́v�Ƃ����u���R�j�I�K�R���v�ɑ�����̒��O�ł���A���̍���I�ȏ����������������͉��ς��悤�Ƃ���Ƃ���ɎЉ�`���̌��������o�����Ƃ���\�z�I�Ȏp���A���Ȃ킿�����B���X�g���[�X�̗p��ł����A(�őP�̈Ӗ��ɂ�����)�u�M���Љ�v���s���Ă����悤�ȎЉ�I�\�z�ւ̓w�͂ɑ���ے�I�ȋC���ł���B����Ă��Ɍ����A����Ȃ��Ƃ��\���Ƃ����v���オ�肪�A�X�^�[������`���͂��߂Ƃ���ߑ�̂��܂��܂Ȏ��s�ݏo���A���傫�ȔߎS�ݏo���Ă����̂��ƁA�����͌��������̂����m��Ȃ��B
�@�����A�u���R�j�I�K�R���v�̓������u�\�́v��u�����v�Ƃ��Ė��w������ԓx�́A���łɂЂƂ̃C�f�I���M�[����тт��咣�ł͂Ȃ����B����������A�����ł́u�\�́v�Ȃ���̂��A��̎��̂Ƃ��āA�����̎Љ�W�̊O���ɂ��錴���̂悤�Ɍ���Ă��邪�A���ۂɂ͂��́u�\�́v�ɂ͐����I�E����I�ȍ�������Ă���͂��ł���B�܂肻��́A���Ȃ�ʌ��㎑�{���Љ�́u�\�́v�̂͂��ł���A���ꂪ�l�Ԃ̓�����Ȃ��u���R�j�I�K�R���v�ł���Ƃ����咣�́A���Ȃ킿�A��O�̎��{���o�ρE�Љ�̌����ᔻ�ɗe�F(��E)����C�f�I���M�[�ɑ��Ȃ�Ȃ��̂ł͂Ȃ����B
�u�\�́v��u�����v���u���R�j�I�K�R���v�ł��邱�Ƃɗ͓_��u�������̎v�z�́A���j�̂Ȃ��ł̎Љ�I�\�z�̓w�͂�ے肷��X�������B�����Łu�\�z�v�ƌ����Ă���̂́A�u�\�́v���l�Ԃ̊�b�I�Ȑ��̏����ł���Ɖ��肵�Ă��A��������̊��S�ȉ���𗝑z�Ƃ��Čf��������悤�Ȏv�z�I�E���H�I�ԓx�A�Ƃ������Ƃł���B����́A���̗��z�̎������\�ł��邩�̂悤�ɐU�������Ƃł͂Ȃ��A��ɂ���ׂ��p�Ƃ��Ă��̗��z���f�������ēw�͂���p���̂��Ƃ��B
�@�����������j�̂Ȃ��ł̍\�z�ɑ��Ĕے�I�ł���Ƃ����_�ŁA�\�͂Ƃ����u�́v�́A�u�\���v�ɑ���D�ʂ��咣���鍡���̎v�z�́A��Ɉ��������͂ɂ���������Ă���悤�Ɏ��͍\����`�Ɠ����ł���A�\����`�I�Ȃ��̂̌����ɂ���ƌ�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���B
�@�����u�\�́v�_�́A�����炭�����B���X�g���[�X�̗��_�Ɠ��l�ɁA���j�̂Ȃ��ł̍\�z�I���H�ɑ��Ĕے�I�Ȕ��f���܂�ł���̂ł���(��7)�B
�@��ʓI�Ɍ����Ă��A�u�́v��u����v�ɏd����u���|�X�g�\����`�I�ȋc�_�́A���j�̂Ȃ��ł̍\�z�Ƃ����v�f(�u�M���Љ�v)��ے�I�ɑ�����Ƃ����_�ŁA�\����`���̂��̂ɗގ����Ă���A�ނ��낻�̌����ɂ���ƌ�����ꍇ�������̂ł͂Ȃ����B���҂̍���ɂ����I�ȗv�f���ꌾ�Ō����\���Ȃ�A����͑����u�j�q���Y���v���낤�B
�@�j�q���Y��������Ɋ܂����̎v�z�I�l�Ԃ��A�}���N�X��`�́u�I���v�Ƃ������\�N�����������j�I���Ԃ̂Ȃ��ŁA�܂�����ɑ��ւ������{���o�ς́u�O���[�o�����v�ƌĂ��g���Ɋւ��āA���ꂼ��̍���n��ɂ����Ăǂ̂悤�Ȗ������ʂ������ƂɂȂ������ɂ��ẮA�����ł͋�̓I�Ɍ������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B
�@�Ƃ����������̘_���犴������̂́A�u���R�j�v�Ƃ����T�O�ƁA�u�K�R���v�Ƃ����T�O�Ƃ̔r���I�Ȍ��т��̋����ł���A���̘A���́A�u�\�́v�Ƃ����A�����j�I�Ƃ����Ăׂ�悤�Ȑl�ԑ��݂́u������Ȃ������v�ɂ��Ă̔F���A�ނ�����O�ƌĂׂ�悤�Ȉӎ�������Ƃ��Ă���B
�@�����́A�\�͂��l�ԂɂƂ��ē���邱�Ƃ̂ł��Ȃ������ł���Ƃ����v�z�I�ȗ�����A�F������̂ł͂Ȃ��A�I�тƂ�A���s�I�Ɍ������Ă���̂��ƁA�ڂ��ɂ͎v����B�܂�A�u�\�͂��E�p�s�\�Ȑ��̏����ł���Ƃ�����������������v�ƁA�ǎ҂����ɌĂт�����悤�ȃC�f�I���M�[�I�����ł���Ƃ����v���Ȃ��̂ł���B
�@�Ƃ���ł��́A�\�͂ƁA�\�͂ɂ���Ă����炳�����Q���A������Ȃ�����(�h���I�ȏ���)�Ƃ��Č��A�������e����Ɛl�X�ɔ��邱�Ƃ́A�܂��A�ߑ���{�̐����I�����̏�ɂ�����x�z�I�Ș_���ł�����Ƃ�����̂ł͂Ȃ����낤���B
�@���Ƃ��A��̑��ɔs��ĊC�O��������グ�Ă����l�����̔s��ɂ����Y�̑r����A���邢�͑�s�s�ւ̕ČR�̋�P�ɂ���ЂɊւ��āA���{�̎i�@�́A�u�푈�Ƃ������Ƒ��S�̊�@�ɍۂ��ẮA�����͔�Q����E���ׂ��������v�Ƃ����_��������āA���Ƃɂ��Ӎ߂�⏞�����߂�l�X�̐���ނ��Ă����B�܂��A����ւ̌����̓����͐푈�̑����I���̂��߂ɂ́u�d���Ȃ������v�Əq�ׂ��A�����Ƃ̔������L���ɐV�����B
�@�����������Ƃ���ł͂Ȃ��A�o�ϓI�ȖL�����̈ێ��Ƃ��A���쎀�҂̏��Ȃ��Љ���ێ����邱�ƂƂ��̂��߂ɂ́A�V���R��`�I�Ȑ���̗̍p�⌴���̉ғ����ɂ���炩�́u�]���ҁv���o�邱�Ƃ́u�d�����Ȃ��v�̂��Ƃ��������W�b�N�́A������{�̌�����Ԃ��h�~�i���g�Ș_�����ƌ����Ă悢�قǂł���B
�u�d�����Ȃ��v�Ƃ������t�̒�ɂ́A�\�͓I���Ԃ𐳓��������}�ƂƂ��ɁA�\�z�ւ̋���̈ӎu�����߂��Ă��邪�A���̈ӎu�̎�̂͂����ł͑��Ȃ�ʂ��̌ŗL�̍��Ƃł���A���O�̐l�X�ɖ\�͂��s�g�������Ă��邱�̍��Ƃ��A���̎���̖\�͂ւ̎��o�I�Ȓ�R���������ƁA�\�͂́u�]���ҁv�����ɗ@���A���������Ă���ƁA�ڂ��ɂ͎v����B
�@�����A�������}���N�X����A�k��J���g����w�̂ł��낤�u���R�j�v�Ƃ������t�A���邢�́u���R�j�I�K�R���v�Ȃ�T�O�́A���������A���������u�d�����Ȃ��v�Ƃ����\��(�h��)�ւ̒��O�Ǝ�e�̑ԓx���Ӗ����Ă�����̂Ȃ̂��낤��(��8)�B
�@�J���g��}���N�X�����̂悤�Ȍ��p�����Ƃ��A�����ɂ͋t�ɁA�m���Ȃ��u�h���v�Ȃ���̂ւ̒�R��E�C�Â�����A�\�͂ɑ���\�z�̓W�]���L����悤�ȑ_�������߂��Ă����̂ł͂Ȃ����낤���H
�@�Ƃ͂����Ă��A�����ō����̌������āA�J���g��}���N�X�lj��̂܂˂��Ƃ�W�J����悤�ȗ͗ʂ́A�������ڂ��ɂ͂Ȃ��B�@
�@�ȉ��ł́u�L���Ɩ����v�Ƃ����٘_�̕\��ɑ����āA�܂��O��̕��͂Ńw�[�Q�����߂����ď��������Ƃɗ����߂�Ȃ���A�u���R�v�Ƃ̊W�܂�\�z���߂������A���{��(�Ƃ�킯�ŗL��)���ƂɋN������\�͂���̉���̉\���ɂ��āA��̍l���������L���Ă������Ƃɂ������B
�@
�R�@�w�[�Q���ɂ�����u���R�v�Ɓu���R�v
�@�O��̕��͂̂Ȃ��łڂ��́A�f���_�̘_�l�u�G�B�ƃs���~�b�h�v(�w�N�w�̗]���x����)�̈�߂����p�������A�������Ńf���_�̔O���ɂ������̂́A�w�[�Q���́w���_���ۊw�x�̂Ȃ��́A��͂薄���Ɋւ��ď����ꂽ���̂悤�Ȃ����肾�����낤�Ǝv����B
�@�����ł́A�����Ƃ����s�ׂ��߂����āA�Ƒ��ƍ��ƂƂ̊W�Ƃ����d��ȃe�[�}���o�Ă��Ă���̂����A����ɂ͐G��Ȃ����Ƃɂ���B
�@����ƁA�����ŏq�ׂ��Ă��邱�Ƃ̂����ЂƂ̑�Ƃ��ĕ����яオ��̂́A�w�[�Q�����u���v�Ƃ������̂��A�ӎ��ɂ���Ċm�������l�Ԑ��_�̓��������u���R�v�ɂ���ċ��������o�����Ƃ��đ����A���́u���R�v�Ƃ���ɑ�������I�ȗ͂ɂ��l�ԎЉ�(�l�ϋ�����)�ւ̐N�Ƃ���A�u�����v�ɂ���Ď��҂�����Ύ��߂��A�ӎ��̊��S�Ȏx�z(����)�����邱�Ƃ̏d�v��������Ă��邱�Ƃł���B
�@�܂�A���̋����̂̌`���̘_���ɂ����ẮA���R�̗͂̔۔F�E�}���Ƃ����Ӗ����A�����Ƃ����s�ׂ͎����Ă���Ƃ����B���̈Ӗ��ɂ����āA�����́A�l�Ԃ̋����̂��`������d�v�Ȍ_�@�ł���A�����Ɏ��R�ƕ����Ƃ̋��E���Ȃ��悤�ȍs�ׂł�����B
�@�������甭�����Ă���̂��A�L�����܂ޑ̌n�A�܂�l�Ԃ̕����̒����E���x���낤�B
�@���ꂪ�A�w�[�Q���������ČÑ�M���V���̐l�ϋ����̂ɑ����Ȃ��痧���グ���A�ߑ�I�ȋL���̗͂̋K�肾�����ƍl������B����́A���i�����j��ʂ��āA�ŗL�̋����̘̂_���̂Ȃ��ɐl�X�̐��̉\����������A�����߂悤�Ƃ���~�]�����Ă���B
�@�w�[�Q���I�ȋL���̖��Ƃ́A���̔r���I�ȋ����̖̂��Ȃ̂ł���A�ߑ�I�ȋL���̈З͂́A�ߑ�̎Y���ł���(�Ƃ�킯�ŗL�́A����)�������Ƃ̘_���̈З͂Ɩ����ł���͂��͂Ȃ��̂ł���B���{�́u����v�z�v�Ɍ������Ă����傫�Ȃ��̂̂ЂƂ��A���������ϓ_�ł��邱�Ƃ����������낤�B
�@�f���_�̕��͂Ɏ�������Ȃ���O��ɏ��������Ƃ����A�ڂ������͍��Ƃ̐��x�ɂ��}��̕s�𐫂������Ȃ���A�܂�݂�����̌����U�镑���ɓ��݂���\�͂���Ɏ��o���Ȃ���A�����ɂ��鍑�ƓI�Ȗ\�͂̉����Ƃ����ڕW���A���x�̍\�z�E���ςƂ�����i�ɂ���ĉi���I�ɖڎw���Ă����ȊO�ɓ��͂Ȃ��͂����A�Ƃ������Ƃł���B
�u���R�j�ρv�Ƃ��ĂԂׂ��A�����̂悤�Ȏv�z�̂����(��11)�ɂ́A�܂��ɂ��́u�\�z�v�Ƃ������ƁA�\�͂Ƃ����h���I�Ȃ��̂Ƃ̑Ό��̎p���������Ă����B����́A�\�͂������(�h���I�Ƃ����Ӗ��ł�)���R�I�Ȃ��̂ƌ��Ȃ����Ƃɂ���āA����ꂪ�L����\�͐��̍��ƓI�Ȑ��i�A���邢�͖\�͂̎Љ�I�ȌŗL��(���j��)�Ƃ������̂��v�l���g�ɑ��ĉB�������̂ł���B���̂Ƃ��v�l�ƋL���́A�l�Ԃ���ɑ��Đ����r��鍑�ƂƎ��{�Ƃ̑���I�Ȗ\�͂ɉ��S����A�}���I�ȑ��u�ɕς��Ă��܂��Ă��邾�낤�B
***
�@���������ł́A�u�����v�Ƃ����s�ׂɂ����ĂȂ����A���R�ƕ����Ƃ̕����A�L���Ƌ����̂̌`���̌�������w�[�Q���̋L�q�ɁA�����ƒ��ڂ��Ă݂����Ǝv���B
�@�f���_�̏�L�̘_����ǂ�ł��A�܂��w���_���ۊw�x��ǂ�ł��Ă�������������w�[�Q���̎p�̂ЂƂ́A���_���������u���R�v�̉e�A�_���̉~��j�]�������˂Ȃ��悤�ȁu���v�̈З͂ɂ��炳��Ȃ���A�����ɂ�����ӂ蕥���A�L���ɂ�钁�����\�z���悤�Ƌꓬ����v�z�ƂƂ������̂ł���B
�@�ł́A�w�[�Q���ɂƂ���ނ�������������u���R�v�Ƃ́A�����Ȃ���̂��H
�@����́A�ӎ��◝���ɂ���Đ��䂷�邱�Ƃ̏o���Ȃ����R�I�ȗ͂��Ӗ����Ă���Ǝv����B�ނɂƂ��āu���v���܂��A�����������R(��)�̋��R����I�悳������̂ł��邪�䂦�ɁA�����Ƃ����s�ׂ��Ƃ����Ē�����(�u���ʁv)����˂Ȃ�Ȃ����̂��ƍl�����Ă���̂��B
�@���Ƃ���ƁA�w�[�Q���̎v�z�̂��^�̉\���𑨂���q���g�́A���R�Ƃ����A�ӎ��ɂ���ē���ł��Ȃ�����(���Ґ�)���l���Â����v�z�ƂƂ��Ẵw�[�Q�����̂Ȃ��ɂ���A�Ƃ������ƂɂȂ邩�Ɏv����B�Ƃ�킯�w���_���ۊw�x�̑O���A�u�ώ@���闝���v�Ƃ����p�[�g�̂Ȃ��ŕ\�ʏ�͔ے�I�ɕ`����Ă���A�T�O����ڎw�������̂͂��炫�ɂ���Ă͖��������̂Ă��Ă��܂��悤�ȋ��R�I�Ȏ����̌����A�����(�T�O�����悤�Ƃ���)�����L�q���悤�Ƃ��邾���̒m���̓����A����Δ�T�O�I�Ȓm�ɂ����A�����͖����I�Ȏv�l�̉\�������o������̂ł͂Ȃ����B�����l���Ă悳�����ɂ��v����̂��B
(�O��)���̂Ƃ������̂́A�ނ���L�q���邱�Ƃ̂Ȃ��ł̂��Ƃɂ����Ȃ��B������A�L�q����Ă��܂��A�Ώۂɑ���S�͏����Ă��܂��Ă���B��̑Ώۂ��L�����ƁA�ʂ̑ΏۂɂƂ肩����˂Ȃ�Ȃ��A�����ċL�q���Ƃ����Ȃ��悤�ɁA���������Ώۂ����߂��˂Ȃ�Ȃ��B(����)�܂��ʎ҂��s��ł���Ƃ������̗̈�ł́A�ώ@�ƋL�q�̂��߂ɁA���邱�Ƃ̂Ȃ��������J����Ă���B�Ƃ͂����A�����ł́A�ώ@�ƋL�q�ɂ́A���������Ƃ��ł��Ȃ��悤�ȕ��삪�J����Ă���̂�����A��ʎ҂̌��E�k�w�G���`���N���f�B�[�x��܁Z�߁l�ɂ́A�v�肪�����x�ł͂Ȃ��A�ނ��뎩�R�̌��E���A�ώ@��L�q�̂͂��炫�̌��E��������ꂦ���ɂ����Ȃ��B�ώ@�ƋL�q�́A���̓I�ɑ��݂���悤�Ɍ�������̂��A���R�ł͂Ȃ����ǂ������A���͂�m�肦�Ȃ��̂ł���B���������A���n�ȁA�ア�`�ہA���n�I�ȕs��Ȏp����قƂ�ǐi��ł��Ȃ��`�ۂ��̂��́A�Ƃ�������������Ă�����̂́A�L�q�����Ƃ��������̂��Ƃ������v�������Ȃ��B�k�w�G���`���N���y�f�B�[�x��܁Z�߁l�@(��12)
�@���̍s�Ԃ���(�w�[�Q���̈Ӑ}�ɔ����āH)�����яオ���Ă���u�����̋��R�I�Ȍ����ɑ������m�v�Ƃ��ĂԂׂ��A�C�f�A�́A�������ɖ��͓I�ł���B���́u�ώ@���闝���v�Ƃ����p�[�g��ǂނƁA�w�[�Q���ɂƂ��Ắu�L���v(���\)���A���ۂ̊T�O���Ƃ������ƁA����������u���R���̐؎̂āv�Ƃ������Ƃ��@�\�Ƃ��Ă���̂�����Ǝv��(��13)�̂����A����ɔ����āu�L�q�v�Ƃ����s�ׂ��Ƃ����Ď�������Ă���悤�ɂ��݂��邱�̒m�̂�����́A�����̋��R�I�Ȍ������A�@�ׂɋ~���o���Ă����̌��ɓ͂��Ă������̂Ɏv���邩�炾�B
�@
�S�@�u���R�v���߂�����
�@�w�[�Q���̎v�z���u���R�v�ɒ��ڂ��ǂ݂Ƃ낤�Ƃ��鎎�݂́A�m���Ɋ|���l�Ȃ��ɖ��͂�����̂��Ǝv���̂����A�������A���͂��̋��R�Ƃ������̂̒������A�����������Ȃ̂ł���B
�@����Ƃ����̂��A���ǂ̂Ƃ���w�[�Q���͊T�O�����u�����闝���̂͂��炫�ƁA���̎����̋��R�I�Ȍ����Ƃ����Βu���ꂽ��҂��A�ُؖ@�I(�����I)�Ȓm�̉^���̂Ȃ��ւƓ��������Ă��܂��Ă���悤�����炾�B
�@���ہA�����ň��p���Ă��镽�}�Ѓ��C�u�����[�Łw���_���ۊw�x�̖|��҂ł�����~�R�Ԏl�Y�́A���łɂP�X�T�O�N��㔼�ɁA�w�[�Q���������Ō���Ă���u���R�v�ɂ͋^�킵���Ƃ��낪���邱�Ƃ��������Ă����B
�@�T�O���������̂Ƌ��R�I�Ȃ��́A�ӎ��Ɩ��ӎ��Ƃ������A�Βu�������A���F���Ƃ����đ��������Ƃ����̂́A���ꂪ�܂��ɕُؖ@�Ƃ������̂Ȃ̂����瓖����O�ł͂Ȃ����Ǝv���l�����邩������Ȃ��B�����A�����甼���I�ȏ���O�ɂ��̐�w����N���Ă������̋^��́A���̂ڂ��ɂ͂ƂĂ��d��Ȃ��̂Ɏv����B
�@����Ƃ����̂��A���ꂪ�܂��������̕��͂̑O�����Ř_���Ă����A����ɂ�����u�h���v��u���R�j�I�K�R���v�ɂ܂��v�z�I�ԓx�̖��Ɗւ���Ă���Ǝv���邩�炾�B
�@�܂�́A���R�I�Ȃ��̂ւ̒m���u�\�蒲�a�v�ւ́A����_�ւ̒��O�ɋA�����Ȃ��悤�ȓ��͂���̂��Ƃ����₢�ɁA����͊ւ��B����������A�u�h�������ꂽ���R�v�A�u�h�������ꂽ���R�v�ł͂Ȃ��悤�ȁA���R����R�⑼�Ґ��Ƃ������̂��A�����͌��o����̂��Ƃ����₢�ɁB
�@�����Ă��̖��́A�u���R�v���d�v�Ȍ_�@�Ƃ��ēW�J�����A�w�[�Q���N�w��ُؖ@�I�Ȏv�z�S�̂̍s�����Ɋւ����̂ł�����B�Ƃ����̂��A���R�Ƃ������̂�����ώ����{����邱�Ƃɂ���āA�ُؖ@�I�ȃ��W�b�N�̑S�̂�����Ί����D�ق���A�����̎��{���o�ς̑̐��⍑�ƁE���ے����̂�����F���ێ����邽�߂̑��u�Ƃ��ē����悤�ɂȂ�Ƃ������Ƃ��A�Ƃ��ɂP�X�X�O�N�゠���肩��ڗ����ċN����͂��߂��Ǝv���邩�炾(��15)�B
�@�Ƃ���ŁA���R���߂���w�[�Q���̍l�������u�^���v�Ƃ����T�O�Ɍ��т��Ă��邱�Ƃ́A�悭�m���Ă��邾�낤�B����́A�X�l�̈ӎ��ɂ���Ă͗\�������萧��ł��Ȃ��u�������q�v�ɂ���ė��j�͔��W���Ă����Ƃ����l�����ł���B
�@����͈ꌩ�A����_�I�ȍl���̂悤�ɂ��݂���B
�@�����A�����ő厖�ȓ_�́A�u�^���v�Ƃ����l�����ɂ����ẮA�ӎ��ɂ�鎩�R�̎x�z�i�������j�ւ̗~�]�̖\�����Z�[�u������̂Ƃ��āA���R�Ƃ����v�f����������Ă���悤�Ɏv����Ƃ������Ƃł���B�܂�A���R�Ƃ����A�ӎ����������Ȃ������̗͂̑��݂́A�u�^���v�T�O�ɂ����ẮA�������̗~�]�Ƃ��Ă������悤�Ȑl�Ԃ̖\�͐��ɑ���A��R��\�z�̂悷���̈Ӗ���S���Ă���͂��Ȃ̂��B�����ɂ����A�ُؖ@�I�v�z�̐ϋɓI�Ӌ`�����o���ׂ��ł͂Ȃ���(��q�����╔�b�I�ȑԓx�̐ϋɓI�Ӌ`���A���͂����Ɋւ���Ă���Ǝv����)�B
�@����A�u�h���v�T�O�́A����Ƃ͎��͋t�̋@�\����������́A����͂����茾���A�u�^���v�T�O���甽�\�͓I�E�\�z�I�ȗv�f���������邱�Ƃŕώ������A�l�X�̎��H�I�w�͂ւ̈ӎu�����������邽�߂ɍ��グ��ꂽ�C�f�I���M�[���Ǝv����B�����ł́u���R�v�́A�l�X�ɗ͂�^���������̉\����m�点���肷����̂ł͂Ȃ��A���ʓI�ɐl�X�̎��H�ւ̈ӗ~��j�r������悤�Ȃ��̂Ƃ��Č���Ă���B
�@���́u�^���v�Ɓu�h���v�Ƃ̔����ȍ��ق��A�w�[�Q���ɂ�����u���R�v�̓����̉\�����A�܂���ʂɕُؖ@�I�ƌĂ��v�z��j�ς̉e���Ɖ��߂̂�������A�傫���������̂ɂȂ邾�낤�Ǝv����̂ł���B
***
�@�����ł�Ⓜ�˂����A�⏕�����ЂƂ����Ă��������B
�@���T��́A���̒����w�n�q�x�̂Ȃ��ŁA�Ñ㒆���́u���v�ɂ��Ă̎v�z���O��̊�{�^�ɂ킯�Đ������邱�Ƃ����݂Ă���(��16)�B
�@���ɂ��A���l�ŕ��G�ȁu���v�ɂ��Ă̍l�������A�����ċ����ɕ��ނ���Ȃ�A�@�@�^�@�A�@�h���^�@�B�@�^���^�@�̎O�ɕ������Ƃ����B�����ő傫�ȕ�����ڂ̂ЂƂƂȂ�̂́A�V�ɂ��u���v��K�R�I�h���Ƒ����邩�A���邢�͂����ɐl�דI�w�̗͂]�n���c�����A�Ƃ������Ƃł���B�@
�@�l�דI�w�̗͂]�n���ł��c���͇̂@�ł���悤�����A���ܒ��ڂ������͇̂A�ƇB�Ƃ̊W�ł���B�B�̉^���^�ɂ����ẮA�B����Ă����K�R�I�h��������Ƃ����R�I���ʂ��Č�������A�Ɛ��͏����B���̌����̏u�Ԃ��A�u���v��m�炳�ꂽ�҂̗���łƂ炦��A�����̏h�������o����̂ł��邩��A�A�̏h���^�Əd������Ƃ�����B�@
�@���������ɁA���̉^���^�ł́A�u���v�̓��e����ԂȂǂ�����I�ł��邱�Ƃ�A���̌��肪�ԐړI�Ȍ`���Ƃ邱�Ƃ���`���āA�l�דI�ȓw�͂ɂ���ĉЂ��������]�n���c�����Ƃ����B�܂�A�l�דI�w�̗͂]�n���c����邱�Ƃ��A�h���^�Ƃ̈Ⴂ�ł���B
�@���̐��ɂ������ǂނƁA�l�דI�w�́A�܂�\�z��(�h���ւ́j��R�̉\���Ƃ������ƂƁA�����̌����ɑ��������R�I�Ȓm�̓����Ƃ������ƂƂ��d�Ȃ�Ƃ���ɁA�u�h���v�Ƃ͔����ɈقȂ�u�^���v�Ƃ����m�̂�����̉\�����J���Ă���A�ƍl������B
�@�����ɁA�h�������悤�ȋ��R���ւ̒m�̉\�����A�u�^���v�Ƃ����肩�Ȃ�ʌ`�Œ���Ă���悤�ɂ��v����̂ł���B
�@���ǁA�u���R�v�T�O���߂���u�^���v�Ɓu�h���v�Ƃ̍��ق́A�O�҂ɂ����ẮA�l�Ԃ̐��̊�b�I�ȏ������Ȃ��Ǝv���鐧�x�I�ȕ����̉ϐ����M������]�n������A�����ł́u���R�v�T�O�͂��̐M��ۏ�����̂Ƃ��ē����Ă���ƍl�����邪�A��҂ɂ͂��̐M�ւ̓��͕�����Ă���A�Ƃ������A���x�̉ϐ����B�����l�X�̐����牓�����Ă������߂̑��u�Ƃ��āu�h���v�Ɓu���R�v�̊T�O���p�����Ă���Ƃ���ɂ���ƌ��������ł���B
�@��������ƁA�u���R�v�̐ϋɓI�Ӌ`(�����A�ُؖ@�I�v�l���͂��ł���͂��̂���)�́A�l�X�ɐl�X���g�̐��̊�b�I�ȏ����ł���u���x�v�Ƃ������������ϓI�ł��邱�Ƃ���������A�Ƃ����_�ɂ��邱�Ƃ�����B�܂�A�u���Ȃ��̐��́A���Ȃ�(����)���g�̎�ŁA���{�I�ɂ͕ς�����̂��v�Ƃ������Ƃ������I�Ɏ���������̂Ƃ��Ă̋��R���A�ُؖ@�I�v�l�����錳���́A�܂��őP�̋��R�̎p�ł���B
�@�����A������t�Ɍ����A���R�́A���ꂪ���H(���x�������I�����̉���)�ƌ��т����Ƃ��ɂ����A���̐^�̗͂�l�X�ɊJ��������̂Ȃ̂ł���B
�@�����I�Ȏ��H�̉\������藣����čl�����Ă���悤�ȋ��R�́A���͂�{���̋��R�ł͂Ȃ��A�~�R�̌����������A�u���F�v�ɂ���Đ��肳�ꂽ�u���R�v(�������ʕt����)�ɂ����Ȃ��̂��B
�@����́A�����ĖY��Ă͂Ȃ�Ȃ����Ƃ��Ǝv���B
�@���݂���̐����ێ����邽�߂ɂ́A�l�X������̐��̏����̌����I�ȉϐ��ւ̓W�]���牓�����Ă������߂ɁA���R���炻�̖{���̗͂�D���ĕʂ̂��̂ɂ���ւ��A�����͋��R���\�z�ւƐڑ������邱�Ƃ�{�|�Ƃ���ُؖ@�I�v�l�Ƃ������̂��A�Љ�I�\�z�̓w�͂�l�X�ɒf�O�����邽�߂̃C�f�I���M�[(����_)�ɕς��Ă��܂����Ƃ��A�L���ȕ��@�ƂȂ�B
�@�����������삪�\�ɂȂ�̂́A���R�ƍ\�z(���H)�Ƃ̕������Ƃ����Ăł�����̂ł���B
�@
�T�@���R�̐^�̈Ӌ`�Ƃ�
�@�ł́A���R�Ƃ������̂��A�ُؖ@�I�Ȏv�z�̂Ȃ��ɂ����Ė{�������Ă���͂��̗́A�ϋɓI�Ӌ`�A������ǂ̂悤�Ȃ��̂Ƒ������炢�����낤���B
�@��������邱�Ƃ͂ڂ��̗͂ɂ͂��܂邪�A���������w���_���ۊw�x�̋L�q���̎��ɂ��Ȃ���A�������l���Ă݂�B
�@��͂�A�u�ώ@���闝���v�Ƃ����p�[�g�̂����A�L�@�̂ɑ���F���ɂ��ďq�ׂ�ꂽ�ӏ��̂Ȃ��ɁA���̂悤�Ȃ����肪����B
�@�����ɂ́A�w�[�Q���̍l������݂̈ʊK�����̂悤�Ȃ��̂��A�Ƃ��ɗL�@�̂Ƃ����ΏۂɊւ��āA�悭������Ă���Ǝv���B�L�@�̂̎��ݐ��̊j�S(��ʐ�)���Ȃ����̂́A�u��U�w�I�ȑg�D�v�Ƃ�������Ȃ鎖���̌����ɂ���̂ł͂Ȃ��u�ߒ��v�ɂ���̂ł���A����́u���Ƃ��Ƃ͗����_�@�Ƃ��Č����v�悤�Ȃ��̂ł���B
�@�T�O��(�ُؖ@�I�Ȏv�l)��}��邱�ƂŌ��o����邱�ƂɂȂ�A�u�ߒ��v�Ƃ��Ắu�����_�@�v�A���ꂱ�����u��U�w�I�ȑg�D�v�Ƃ��������Ɂu�Ӗ��v��^����B�w�[�Q���̌����Ă��邱�Ƃ��A���̂悤�ɉ��߂��Ă������낤�B
�@�����ł́A�ُؖ@�I�ȉߒ����o�Č��o�����u�����v�Ƃ������_�I���l���A����(�g��)�̕����I�Ȍ������x�z���A����Ɂu�Ӗ��v��t�^������̂Ƃ��ČN�Ղ��Ă���B
�@�����ɂ�����u�Ӗ��v�̊j�S�������Ă���̂́u�����v�Ƃ��Ă̐��_���Ȃ̂ł���A����Ȃ��ɂ͗L�@�̂��^�̎��ݐ����l�����邱�Ƃ͂Ȃ��ł��낤�B
�@����́A�w�[�Q���ɂ����鐶���̌`����w�I�ȈʊK�������Ƃ�������B�����ł́A�u�Ӗ��v������������Ȃ鎖���̕����I�Ȍ����(�u�r�́v)�́A�����ւƔr������Ă��邱�ƂɂȂ�B
�@�f���_�́u�G�B�ƃs���~�b�h�v�ŁA���̈ʊK�����̓]�|���w�[�Q�����g�̕��͂ɉ����Ď��݂��Ƃ������Ƃ��낤�B�����ĕ��ʂ��ꂪ�A�|�X�g���_���Ƃ��E�\�z�Ƃ������ŌĂ��Q�O���I�㔼�̂ЂƂ̎v�z�̕������������Ǝv���̂����A���̒��������������l���Ă݂悤�B
***
�w���_���ۊw�x�ł͏�̈��p������������̉ӏ��A�l���w�E�����w�Ɋւ���p�[�g�ɂ����Ă��A�l�̐g�̂̑��݂��L�����d���Ƃ������ƁA�܂�l�̈ӎ��̉^���̕\���Ƃ��Ă̐g�̂ƁA����Ɂu���ۂ��錻���v(���R�T�O)�Ƃ��Ă̐g�̂Ƃ̓�d��������A���̓�����Ƃ���ɑΗ����Ę_�����邱�ƂɂȂ�B
�@�����ł́A���(����Ȃ鎖���Ƃ��Ă̐g��)�́A���_�u�Ӗ��v�������u�T�O���v����Ƃ肱�ڂ����u���R�v�I�Ȍ����Ƃ��āA�u�ӎ��̉^���v�̉��ʂɒu�����B�������́A�u�Ӗ��v����������A����͊T�O���Ƃ������_�I�ȏꂩ��͔r������Ă���A�Ƃ�������B
�����āA�l���w�⍜���w�̒m�́A�w�[�Q���ɂ���āA���̋��R�I�Ȍ�����m�̑̌n�ւƍ\�����悤�Ƃ��閳���Ȏ��݂Ƃ��āA���������͔ے肳��Ă���̂��Ǝv���B
�@�����A�������̐S�ȂƂ��낾���A�w�[�Q���͂��̋��R�I�Ȏ��ۂ������A����ɕُؖ@�I�Ȏv�l�̏�(�ߒ�)����r�����Ă���̂ł͂Ȃ��B����͌��ǂ́A���铝�����ꂽ��Ԃ̂Ȃ��ɁA�K�R�I�ł���ƌ��Ȃ��ꂽ���̂����Ƌ��ɒu����邱�ƂɂȂ�A����A�~�R���������Ă����悤�ɁA�ނ���n�߂��炻�̂悤�Ȃ��̂Ƃ��ēo�ꂳ�����Ă���Ǝv����̂ł���B
�@�܂�A�u�T�O���������́v�Ɓu���ꂴ����́v�Ƃ́A���̖��m�ȋ敪�Ɣr���Ƃ́A�d�g�܂ꂽ���́A������\�肳�ꂽ���̂ł���B���҂́A���͎n�߂��瓯�ꐫ�̏�̂Ȃ��ɒu����Ă���̂��B
�@���ꂪ�w�[�Q���̓N�w�́A�܂��ُؖ@�I�Ȏv�l�́A�u�\�蒲�a�v�I�ȑ��ʂƂ������ƂɂȂ邾�낤�B���̑��ʂ��x�z�I�ł������A���̎v�z�̂�����͏h���_�I�ȍl����l�X�ɐA���t���悤�Ƃ��錻���Љ�̌��͂̈ꑕ�u�Ƃ��ē��������Ȃ����낤�Ƃ������Ƃ́A���łɏq�ׂ��B
�u�T�O���������́v�Ɓu���ꂴ����́v�Ƃ́A���̎d�g�܂ꂽ�敪�̓����ɂ��āA����ɍl���Ă݂悤�B�@
�@����͈���ł́A�T�O���������̂���(�Љ�̒��ł́A����͔r�����鑤�̎҂ł�����)�ɂƂ��ẮA�ӎ��ɂ�铝��̂��Ƃœ������ꂽ��ɂ������(�Ӗ��̌���)��ۏ��邾�낤�B�����A���R�I�ƌ��Ȃ���Ă�������r�����ꂽ���̂����́A�r������Ɠ����ɁA���L�Ăȓ����E�Ǘ��̏�̂Ȃ��Ɏ�荞�܂�Ă�����B
�@���҂̋��ʐ�(���ꐫ)���Ȃ��̂́A���͂��̍L�ĂȌ��͂ɂ��A�\�z�̎��H����́u���v�̐ؒf(�r������鑤�ɂƂ��ẮA��d�̔��D)�Ƃ������ƂȂ̂ł���B�w�[�Q�����\�������悤�ȁu�T�O���������́v�Ɓu���ꂴ����́v�Ƃ̖��m�ȓΗ����\�ɂ��A�܂��B���Ă���̂́A���̔�Ώ̓I�ȓ��^���̍\���Ȃ̂��B
�@���́A�����Ō����ɓ����Ă���\�͂̎����ł���B
�u�T�O���������́v�Ɓu���ꂴ����́v�Ƃ̑Η��̐}���́A�ڂ��̂��̘_�l�̑O���Ŕᔻ�����A�����́u��O���r���v�̐}���Ɠ��^���Ƃ�����B�����̗��_�́A�Љ�I�Ȕr���̌��ۂ����ĂȂ��قǂɉs���\���������̂����A���̏h���_�I�ȋL�q�̎d�����̂ɂ���āA���̖\�͂̐^�̎������ނ���B�����Ă��܂����Ǝv����B
�@�܂�A�u���ꂴ����́v(�u���R�v)���O���ւƔr�����邱�Ƃɂ���āA��(������)���`������A���̈��肪�ۏ����Ƃ������ʓI�ȍ\���́A�m���ɂ܂�����Ȃ������Ȃ̂ł��邪�A���̂��Ƃ������ƍ����I�ȃ��x���ő�����ƁA�u�T�O���������́v�Ɓu���ꂴ����́v�Ƃ����Η��̉e�ɉB���悤�ɂ��āA���ׂĂ̌̂ɂЂƂ��Ȃ݂ɑ傫�Ȗ\�͂������Ă���ƌ�����Ǝv���B
�@���̍����I�ȃ��x���Ŗ\�͂����Ă�����̂����A�����炭���R�̐^�̗͂Ɋւ���Ă�����̂��낤�B
�@����͂����Č��t�ɂ���Ȃ�A���݂̍�l�̍��{�I�ȉ��ς̉\���A���������̕����I�ȏ������̂��̂�ς��Ă����\���̂��Ƃ��Ǝv���B
�@�ڂ��ɂ́A�w�[�Q���ɑ�\�����`���I�Ȏv�l�̏d���ɍR���āA���m�̌���v�z�̑�\�I�Ȏv�z�Ƃ����A���Ƃ��f���_���u�S��v�Ƃ����T�O�ɂ���āA�܂��h�D���[�Y���K�^�����u�����ω��v�Ƃ����T�O�ɂ���āA����ɂ͂܂������B�i�X���u��v�Ƃ������t�ɂ���āA���ꂼ��\�͂����蔲�����Ƃ����̂́A����ł��낤�Ǝv����B
�@�����l����ƁA�����́u�r���v���߂���v�z�ɂ́A��͂�ア�ʂ�����B
�u�T�O���������́v�Ɓu���ꂴ����́v�A�r���ɂ���Č`������铯��I�ȋ��(�������)�̓����ɑ�����҂ƁA���̊O���ɔr�������҂Ƃ������Η��I�Ȑ}���������������邱�Ƃ́A���̓Η�(�r���̃V�X�e��)���̂��̂��R���Ȃ�����(�h��)�̂悤�ɍl�������āA�l�X�̍s�ׂ����̏h���̊Î�ւƌ����킹��ƂƂ��ɁA�ق�Ƃ��͂���ꂩ�牽���D���Ă���̂��Ƃ������Ƃ̎��o���ɂ�����댯��������Ǝv���̂ł���B
�@���ہA�����̎咣�������̎Љ�ɂ����炵�����ʂ̈�ʂ́A�����������̂ł������Ƃ�����B�ꌾ�ł����A����͐^�̋��R���m�肵�\�z�ւ̎��H�ւƌ��������Ƃ���A�l���������Ă��܂��ʂ̂���v�z�Ȃ̂��B
�@�^�̋��R�̗͂Ƃ́A���ׂĂ̐l�ԂɁA�����Ƃ�킯������Ԃɐ���������Љ�̃����o�[�ɁA���ȂƂ��̓�����ۏ��Ă��鐧�x�Ƃ̖��������������A���������߂��ƍs�ׂ̉Q�̂Ȃ��ւƓ������ނ悤�Ȃ��̂̂͂��ł���B�ق�Ƃ��ɍm�肳���ׂ����R�Ƃ́A�����������̂�(��18)�B
�@
�U�@�T�ւ̒��L
�@�������A�����Ŕ��ɏd�v�Ȃ��Ƃ́A��ɂ��q�ׂ��悤�ɁA���R�Ƃ������̂͌����̎��H�Ɛڑ�����čl����ꂽ�Ƃ��ɂ����A���̐^�̗͂��J�����Ȃ��Ƃ������Ƃ��B
�@���H�Ƃ́A���������̐����K�肵�Ă��镨���I�ȏ������A���\�͐��̏��Ȃ����̂ւƕs�f�ɕς��Ă������Ƃ���ӎu�ƍs�ׂ̂��Ƃł���B
�@����ꂪ�m�����A����܂ł̐l�Ԃ̎Љ�͂����Ă��͂̕s�ύt�A�܂茠�͂ɂ��}���ƍ��A���ʂƂ������\�͂̂��ƂŐ������Ă����B����䂦�ɂ����A��ɂ���ɒ�R����\�z���v������Ă���̂ł���B�܂���ʘ_�łȂ��A�Ƃ�킯�����̂��̎Љ�ɂ����āA���̕s������\�͐��������ł��邱�Ƃ����̗v���B
�@���Ƃ���A���R�̐^�̗͂̔��D�͍����I�ɂ͑���(���ׂĂ̐l)�Ɋւ��Ƃ͂����Ă��A���̎��ۂ̌����́A�r������鑤�̎҂Ɣr�����鑤�̎҂ƂŁA�����ł͂��肦�Ȃ��B�����āA���D�����̂Ɋւ����̂ł��邩�炱���A�����Ŕj��������悤�Ƃ���͂̃x�N�g���́A��Ɂu��苭�����́v�ւƁA���ݓI�ɂ�������������ׂ��ł���B
�@��ŋL�q�����u�r���v�̎��������ۂ̎Љ�ɂ��Ă͂߂�ƁA�܂�������Ԃ̃����o�[�́A�����ɕ�ۂ���邱�Ƃɂ���Ď��Ȃ̐��̕ϐg�⍬���̉\���D�����B����A������Ԃ���(���̃����o�[�B�ɂ���āA�ł�����)�r�������҂����́A�r���Ƃ����\�͂������ɔ��A�����̗͂�����̂��̂܂ł����D���悤�Ƃ��邱�Ƃœ�d�̔��D�����Ă��邱�ƂɂȂ�B
�@�����Ō�҂Ɋւ��Ă��A�����̗͂��D���悤�Ƃ���Ə������̂́A�����������̌����ɂ���Č`�����ꂽ����̎Љ�ɂ����ẮA������Ԃ̊O���ɔr�����ꂽ�҂����̐����܂��A���܂��܂Ȏd���ŊǗ����A���Ƃ����́u�O�����v���ߏ�ɉ����t������Ƃ����d���ɂ���āA���ۂɂ͂��傫�ȓ����̕��ʂ̂Ȃ��ɂƂ肱�܂�Đ��⎀���}���邱�ƂɂȂ�ƍl�����邩��ł���B
�@���I�Ƃ݂Ȃ���鑼�҂�r������悤�Ȍ�����Ԃ̘_���ƁA��������r�����ꂽ����Ȃ鎖���Ƃ݂Ȃ����g��(�u�r�́v)�̊O��������������悤�Ș_���Ƃ́A���̈Ӗ��ň��̋��ƊW������ł���Ƃ��l������B���҂́A�l�X���A���R�ւƊJ���ꂽ���H�̒f�O�A���̊�b�I�ȏ�����������ς��Ĕ�\�͓I�E�����ʓI�ȎЉ������Ă������Ƃ̕s�\���ւ̒��O�̂Ȃ��ɕ����߂悤�Ƃ���X���ɂ����āA���ƓI�Ȃ̂ł���(��19)�B
�@������A���̍����I�Ȗ\�͂ɍR����ɂ������Ă��A������ׂ����Ƃ́A�Ȃɂ��܂��A�u�r�������(���ʂ����)�v�Ƃ������߂ł���A�����Ӗ��ɂȂ邪�A�r���������l�X��������Ӗ��ɂ����āu����������v�Ɩ������˂Ȃ�Ȃ��B
�@�l�X�̐������m�肵�A�r�����s�킹�Ȃ����Ƃ́A���ׂĂ̐l�ɂƂ��Ă̐��ƍ����̉\�������A�^�̋��R�̗͂�D��Ƃ����A���ՓI�ȈӋ`�������Ƃł�����B�r����������(����͓����Ɋe�l�ɓ��݂���v�f�ł�����)��\�͂����邱�Ƃ́A���ׂĂ̐l�̐��̉����ۏ����ΓI�ȏ����Ȃ̂��B
�@���R�̍m��́A���̂��Ƃ�y��Ƃ��Ă������肦�Ȃ��B��\�͓I�E�����ʓI�Ȍ����̍\�z�Ƃ����s�ׂ���藣���ꂽ�u���R�v(���̉��)�́A���ׂċ��ςɂ����Ȃ��̂ł���B
�@
�V�@���R�Ƙa��
�@���āA�w���_���ۊw�x�ɂ����Č����L���̐����A���R�Ƃ̊u����Ƃ��Ă̕����̍\�z�̉ߒ����A�����̂̌`���Ƃ��������I�ȃe�[�}�Ɛ[�����т��Ă��邱�Ƃ��A��ɏq�ׂ��B���̂��ƂƂ̊ւ��ŁA����܂Ř_���Ă������Ƃ̗v�_���ȒP�ɂ܂Ƃ߂Ă݂����B
�@�����̂̌`���A�܂�l�Ԃ̐��̊�b�I�ȏ����ł���Љ�I�\�z�̎�������ɂ������Ƃ́A�v�z�j�ɂ�����w�[�Q���̈Ӌ`�̑傫��(���_�A�}���N�X�ɂ���Čp�����ꂽ)�������ő�̂��Ƃ��낤�B���̂��Ƃ̓J���g�Ƃ̑Δ�ɂ����āA�Ƃ��ɈӖ������B
�@�J���g�̓N�w�́A�ߑ�I�Ȍl�ɂ�����ϗ�����H�̏d�v�����������Ƃ����_�ŁA�Љ�v�z�̖ʂł��傫�ȈӋ`���������Ǝv���B���������ɂ́A����̐��̕����I�ȏ����������ɍ\�z���ς��Ă����Ƃ����x�N�g���͌����Ă����B����́A�ނ̎v�z�Ɂu���R�j�v�I�Ȃ��̖̂G�肪�݂��邱�ƂƊ֘A���Ă��邾�낤�B
�@����ɔ䂵�āA�w�[�Q���y�ѕُؖ@�I�v�z�̌���I�ȈӋ`�́A�����̂̌`���ߒ��̘_�����Ƃ����`�ŁA�����K�肷�镨���I�ȏ���(�����ŁA�����Ƃ�����̈Ӗ����ő���ɂƂ�Ƃ���)���e�[�}�ɐ������Ƃ������Ƃ��B����́A���̊�b�I�ȏ������A�l�X�ɂƂ��ĕύX�\�Ȃ��̂ł���Ƃ����l�����\�ɂ���B
�@�ڂ��������Ř_���Ă������Ƃ́A���������w�[�Q���I�Ȏv�z�������Ӌ`���A�u���R�v�T�O�Ƃ��̂���ւ��Ƃ����p�x�ɂ����đ����悤�Ƃ��鎎�݂������B�܂�A���̎v�z���l�X�̎��H��͂Â�����̂Ƃ��ē����Ă���̂ł���A�����ł͋��R�Ƃ������̗̂͂��۔F����邱�ƂȂ������Ă���ƍl������B�����A�w�[�Q���̎v�z���}���Ǝx�z�̑��u�Ƃ��ċ@�\���Ă���Ȃ�A�����ɓo�ꂵ�Ă���̂͐��肳�ꂽ�u���R�v�Ƃ����L���ɂ����Ȃ��̂ł���B�����ɁA�w�[�Q���̎v�z�̂����`�I�Ȑ��i���݂邱�Ƃ��o���邾�낤�B
�@�Ȃ����̂悤�Ȃ��Ƃ������Ř_����K�v�����������Ƃ����ƁA���H��ϊv��͂Â�����̂Ƃ��Ẵw�[�Q���E�ُؖ@�I�v�z�̈Ӌ`�̖Y�p�ƁA�t�ɗ}�����u�Ƃ��Ẵw�[�Q���E�ُؖ@�I�v�z�̗��s�Ƃ����A��������������A���{�݂̂Ȃ炸�W�O�N��Ȍ�̐��E�I�Ȏv�z�̗��������Â�����̂��Ǝv��ꂽ����ł���(���̂��Ƃ̑傫�Ȍ����́A���_�w�[�Q���̎v�z���̂ɂ���킯����)�B
�@������ɂ��悻��́A�����I�ȏ����̕ϊv�ƍ\�z�Ƃ����Ӗ��ł�(�w�[�Q������J���A�}���N�X�Ɍp�����ꂽ)�Љ�I���H�Ƃ����ۑ肪�A�v�z�̃t�����g���C������������X���ɂ��������ゾ�ƁA�����ł��������B
***
�@�����ŁA����܂ŋ��R���߂����Ę_���Ă����������A���̃w�[�Q���̎v�z�ƕُؖ@�ɓ��L�Ȑ����I���n�ɐڑ������铹�����������T���Ă݂悤�B����́A�w�[�Q�����W�J����L���X�g���I�ȁu�a���v�̊T�O�Ɋւ����̂ł���B
�w���_���ۊw�x�S�҂̂Ȃ��ł������Ƃ��������L���ȕ��͂̂ЂƂł͂Ȃ����Ǝv���̂����A�uD�@���_�v�̂Ȃ��́u���@�@���v�Ƒ肳�ꂽ�́A���̂Ȃ��̃M���V���ߌ���_���������̂Ȃ��Ńw�[�Q���͎��̂悤�ɏ����Ă���B
�@���̕��͂̑O���ł́A����́u�B�����v�E�s�[���������o���ĕs���������Ă��Ȃ���(�u�x���v���Ă��Ȃ���)�A�m�ɐM�����悹���������ʁA���̏��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��H�ڂɊׂ�u�ӎ��v�̋��������q�ׂ��Ă���B�Ƃ����Ă��w�[�Q���́A���̈ӎ��̒m���s�[���ł���̂́A���ꂪ�u�����Ŏv���Ȃ��A�ʓI�ŋ��R�ł���v���炾�ƌ����Ă���̂�����A�����Ŕᔻ����Ă���̂͂܂��\���ɊT�O������Ă��Ȃ��i�K�̒m�ł���Ƃ͌�����B�܂�A�����ƉȊw�I�E�q�ϓI�Ȕ��B���Ƃ�����̕s�[�����͍�������邩�Ɏv���邩������Ȃ����A���̓w�[�Q���̎v�z�ɂ����ẮA�m�̂��������B�����E�s�[�����A���R���Ɩ��ӎ��ɑ���s���̊���́A�����邱�Ƃ̂Ȃ����{�I�ȗv�f���Ƃ�����ۂ���B�@
�@���̋��R���△�ӎ��ɑ���s���̊�������A�w�[�Q���ُؖ̕@�́A�܂����̓���(�a��)�̗��_�̌����͂��Ƃ��v����̂��B�w�[�Q���̎v�z�ƕُؖ@�I�v�l�������̗v�f�́A���炽�߂Č������A����߂ďd�v�Ȃ��̂��Ǝv���B
�@���R���ւ̒��ς́A���ꂪ�s���ɖ��������̂ł������́A������ӎ��̖\���Ɏ��~�߂�������A���������̂Ȃ��u���v�ł���Â���B�قƂ�ǂ��ꂾ�����A���j���A���`�̐l�Ԃ₠����カ���̂����̗��j�ł��邱�Ƃ�ۏ��邾�낤�B
�@�����āA�㔼�Ɍ���Ă���u�a���v�Ƃ������t�B
�@�J��Ԃ��ɂȂ邪�A�w�[�Q�����u�a���v�Ƃ����T�O��p���ċ����̂̐����I�Ȍ`���ߒ������Ƃ������悤�Ƃ������Ƃ̈Ӌ`�́A�����ɂƂ��Ă������ď����Ȃ��̂ł͂Ȃ��B����́A�����K�肷�镨���I�ȏ������v�l�̃e�[�}�ɐ������Ƃ������Ƃł���A���̊�b�I���������������̗͂ŕύX�\�Ȃ��̂��Ƃ������Ƃ��A�l�X�����o���铹���J�������̂����炾�B
�u�a���v���߂���w�[�Q���̎v�z�́A�\�z�ւ̎��H�Ƌ��R(����)���̔F����ڑ������Ė��O�̉�����u������ُؖ@�I�Ȏv�z�̎n�܂�Ƃ��āA���ꎩ�͍̂��ł��d�v���������Ă��Ȃ��Ƃ�����(��21)�B
�@�����A�����ł���͂�u���R�v�̒���������˂Ȃ�Ȃ��B
�@�܂�A��̃w�[�Q���̕��͂ɓo�ꂵ�Ă���A���R�I�Ȃ��́A�ӎ��̓����邩�ɂ݂�����́A����Ƃ́u�a���v�ɂ���āu�S�̂����Ȏ��g�Ɉ��炤�v�Ƃ���Ă���A���̋��R�̎��̂Ƃ́A�a���ɂ�铝���̂��߂ɐ��肳�ꂽ(�~�R)���̂ł͂Ȃ��̂��Ƃ������Ƃł���B
�@��������ł́A�u���R�v�Ȃ���̂��A���ȂƐ��x�̓��ꐫ��h�邪���悤�ȋ��R�̐^�̈З͂��B�����Ȃ���u�a���v�𐳓������邽�߂̃A���o�C�̂悤�Ɏg���Ă���̂ł͂Ȃ����B
�@�w�[�Q���̌��u�a���v�ɑ���ڂ��̋^�`�́A�����݂������̂悤�Ȃ��̂ł���B
�@�ق�Ƃ��̘a���Ƃ������̂́A�����܂Ő^�̋��R�̍m��̏�ɁA����������A���������̐����\�����Ă����b�I�E�����I�����ւ̍��{�I�Ȗ₢�����̎��H�̂��Ȃ��ł����A�Ȃ����ׂ����낤�B
�@����������̓I�Ɍ����A���҂ɑ��鍷�ʂ���D�̗��j�ƍ\���Ɍ��������A������ق�Ƃ��ɕς��Ă������Ƃ���w�͂̂Ȃ��Ƃ���ɁA���R(����)�Ƃ̏o��Ƃ������̍����I�o���͂��肦���A���������Đ^�̘a��(�\�z�̎���)�Ƃ������Ƃ����肦�Ȃ��̂ł���B
�@�w�[�Q���̌��a���̘_���́A���������^�̏����ɂ��ƂÂ��Ă͂��Ȃ��B�ނ��낻�̔۔F���\�ɂ�����̂Ƃ������ʂ������Ă���Ǝv����B
�@�����ŁA���(�S�̖`����)���p�����~�R�Ԏl�Y�w�N�w�̖��x�̈�߂ɖ߂邪�A�����ł́u���F�ɂ���Đ��肳�ꂽ���R�v�Ƃ����\��������Ă����B���F�̊T�O�́A�w�[�Q���̎v�z�A�Ƃ��ɗ��j�Ɋւ���l���̍������Ȃ��Ƃ���������̂����A�ڂ��̂��̘_�l�ł͂܂������G��邱�Ƃ��o���Ȃ������B�ꌾ�����q�ׂĂ����ƁA��ɏ������u�^�̘a���̏����v�Ƃ́A���́u���F�v�T�O���̂�z����Ƃ������ƂɊW���Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���B
�@�K�������u���F�v��}��Ȃ��A�܂菳�F�ɂ���Đ��肳��Ă͂��Ȃ��^�̋��R(����)�Ɍ������ĊJ����Ă���悤�Șa���̂������T�邱�ƁB���ꂱ�����A���݂̂ڂ������ɉۂ��ꂽ�Љ�I�ۑ�ł͂Ȃ����낤���B
������
�@�J�t�J�̒Z�сu��l�O���t�X�v�ł́A���̍�����Y�p�̉�(�u���[�e�v)��k���Ă���Ă������̂悤�Ȓj�O���t�X�̏o�����A�s���������̐l�Ԃ�s���Ɋׂ��B
�@�O���t�X�́A�����͑�́A�h�C�c�̐[���X�A�V�����@���c���@���g�Ŏ���l�ł���ƌ����B�����܂��ނ́A�����́u�����Ă���ƌ����Ȃ����Ȃ��v�Ƃ������B�u�O�r�̐�v��n�肻���˂āA�ނ̏�����M�́u���̐��̐��ӂ����܂���Ă���v�ƌ����̂��B
�@�����āA��́A�����ĎR�Ŏ������Ă������̋L�������Ɍ��B
�@���ƎR�A�����Ǝ��R�A���Ɛ́A���Ǝ��A�����̋��E��B���ɂ��Ă��܂��A�Y�p���ꂽ(���ꂪ�u�a���v�̏����������͂���)�͂��̑�̂̏o���������O���t�X�̑��݂́A�s���������̏Z�l�ł��������Ԃ̃����o�[�ł���l�X��s���ɂ��A���h������B
�@�����O���t�X�͌��ǁA����ȏ�͒��ɂƂǂ܂�ӎu�̂Ȃ����Ƃ������āA�s�������S������Ƃ���ŁA���̒Z���b�͏I���Ă���B
�@
�@
�@�O���t�X�Ƃ����u�r�������ҁv�������ׂ邱�́u���v�ɂ́A�����ɂ��J�t�J�I��ambiguity(���`���E�B����)����������B
�@�J�t�J�͂����ŁA�ނ̕��ꂪ���������ł���悤�ɈӐ}�������āA�s�������ɂ�鋤���̂́A���Ȃ炸���R�Ƃ������ŕs���������N�������̂����̖{����۔F���邱�Ƃ̏�ɐ��藧�̂��Ƃ����^�����A�X�^�e�B�b�N�ɁA�܂�����䂦�Ɂu����Ȍ����v�Ō��A���̃j���A���X���u���v�ɂ����߂Ă���̂����A����Ɠ����ɂ��́u���v����́A���̋����̂̍����ƕ����Ƃ������ɐƂ����̂ł��邩�Ƃ������Ƃ�������A�F���̗\����тт��s�C���ȃ��b�Z�[�W���Y���Ă���B
�@�܂�A�O���t�X�̔��́A���R���̂��̗̂��`����\�����Ă���Ƃ��ǂ߂�̂��B�h���ւ̒��O���`�����錠�͑��u�̋L���Ƃ��Ắu���R�v�ƁA�����Ɩ�������\�������l�Ɏ��H�ւ̓����J����������R�̕s���ȈЗ͂Ƃ́A���`�����B
�@���̕s���ȈЗ͂������䂦�ɁA���͂́A������������Ƃ�s���e���Ƃ��������̂́A���R���v���ĊǗ��̋�ɕς��悤�Ƃ�����A��������Ђ��������ꂽ�s���ȏ�ƃG�l���M�[�����ʂ�r���̖\�͂ւƓ]�����A���p���悤�Ƃ���B���̂Ƃ��A���R���߂���R�����J�n�����̂ł���B
�@���ہA���̂悤�ȕs���ɖ��������R�ւ̗\�����A�۔F���������͂ŕs�ӂɓ������邱�Ƃ��A���j�̂Ȃ��ɂ͂���B�u�����̔�l�ԓI�Ȏp�A���Ⓓ�▲�Ȃǂ̐��v���A�{���ɐl�X���������͂��߂�̂́A���̎����B�؎��ƂȂ����u���R�I�Ȃ��́v�̓����̗\���̂Ȃ��ŁA���ȂƂ����鋫�E�̖��������ɂ��Ă̐l�X�̕s���͍��܂�A�₪�āA�ߑ㉻�̌ŗL�I�ȉߒ��ɂ����Ďs��(����)�Љ�̒ꕔ�ɉ������߂��Ă��������A������͂��߂邾�낤�B
�@���������e�[�}���N���e�B�J���Ȍ`�ŁA���{�̎Љ�Ɓu����v�z�v�̑O���ɂ͂�����Ɨ�������Ă���̂́A�����ނ˂P�X�X�O�N��ȍ~�A�܂���{�S�̂��o�ρE�����̃O���[�o�����ɗR������|�X�g�E�t�H�[�f�B�Y���ƃ|�X�g�E�������Ƃ̏������͂��߁A�܂�����ɑΉ������V���Ȑ��̖��͉��̌`�Ԃł���u�Ǘ��Љ�v(�h�D���[�Y)�ւƌ��͂̃��f���`�F���W���i�s���Ă����A������������̂��Ȃ��ɂ����Ăł������Ǝv����B
�@
�@
���v���t�B�[����
���c�L���i�������E���肨�j
1962�N���܂�B�j���A�Ɛg�A�e�Ɠ����B�v���t�B�[���ɏ����悤�Ȃ��Ƃ��Ȃ����݂Ɏ���B�u���O�FArisan�̃m�[�g
Web�]�_���u�R�[���v16���i2012.04.15�j
������v�z���čl���遄��R��F�O���t�X�̔��\�\�h���Ƌ��R�i�L���Ɩ����Q�j�i���c�L���j
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU�@2012 All Rights Reserved.
|
| �\���i�ڎ��j�� |