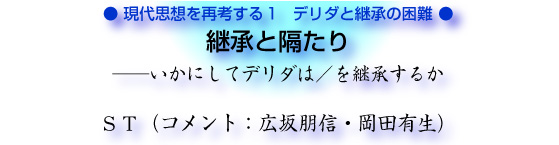|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「La Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
【前口上】
広坂朋信
本誌編集長から、与太話も結構だが少しは文化的・思想的に意義のありそうな企画もやれとの命令を受けて、次のようなことを考えた。
いささか大げさな言い方をすれば、日本社会は風変わりな曲がり角にさしかかっているような気がする。風変わりな、というのは、もはや既定のコースをたどっていればいいというわけではないが、どこへ向かうのか、あらかじめいくつかの選択肢が用意されているわけでもなく、道のない野原の真ん中で立ち止まり、さてどちらに向かったものかとあたりを見回しているような気分がするからである。
人によって違う目印を指すこともあるだろう。だが、2010年前後から何かが変わりつつあるという印象を抱いている人は多いに違いない。直近の出来事としては大震災があった。だがもちろんそれだけではない。その前には政権交代があった。だがもちろんそれだけではない。地震の発生はそれ自体は単なる自然現象であり、政権交代はそれ自体は民主主義国である以上あって当然だったはずの出来事にすぎない。
ふりかえれば、1993年に自民党が下野し細川連立政権が生まれ、羽田、村山と非自民党首班の内閣が続いた。そして1995年に阪神大震災と地下鉄サリン事件が起きた。この時期にも、非常に大きな変動が予感され、事実、その後の日本社会は、現象としてのグローバル化の進展とその反作用としての世論の右傾化が始まった。しかし、その90年代初めの経験も今ほど深い断絶を感じさせるものではなかった。そもそも90年代からゼロ年代にかけての変化については、ある程度まで予想されてすらいた。あの頃も日本社会は岐路に立っていたけれども、変化は方向づけられていたし、選択肢すらあった。今はそれがないように感じる。しかし何かが変わりつつあるという印象だけは揺らぐことがない。
結局、私を当惑させている気分の原因は、変化を言い表す言葉が不足しているからなのだろうと思う。それはもしかすると私の不勉強、視野の狭さ、洞察力のなさに由来するのかもしれない。あるいは私の理解力が乏しいために既に言われている事柄に気づいていないこともありうる。などとつらつら愚考した揚句、80年代以降、「現代思想」というレッテルで流通してきたものを今あらためて読み直したらどうだろう、と思い至った。
とはいえ浅学非才の私一人では、いかにない知恵を絞っても心許ない話であるから、岡田有生氏にご協力を仰ぎ、お付き合いいただくことにした。こういう事情だから、本来なら言い出しっぺの私がこの三十年間の「現代思想」の見取り図を提出し、岡田氏の批評を仰ぐのが筋というものだが、あいにく個人的なアクシデントに見舞われて精神的な余裕がない。そこで思い出したのが、某大学院でジャック・デリダの思想について研鑽中の若い研究者ST氏のことだった(「まだ修業中の身なので」と謙遜されたため仮名にしてある)。このST氏にデリダにおける継承というテーマでリポートしてもらい、それを肴に岡田氏と私とで議論を始めようというのが当初の魂胆であった。
ところが、ST氏から届けられた「継承と隔たり」はご覧のように本格的な論文というべき力作で、これでも半分近く割愛してもらったのだが、たやすく料理できるような代物ではない。サンマの塩焼きでも肴にしてちょいと一杯のつもりだったのに、マグロの解体ショーが始まってあわてふためいているというのが正直なところだ。
余計な前口上はこれくらいにしておこう。ともあれ、デリダが先行世代の思想をいかに継承したのか、その継承の実践とは何かを明らかにしたST論文をお読みいただきたい。そうすれば、現代思想を再考することを看板に掲げながら、なぜデリダにおける継承から始めるのかは自ずとご理解いただけよう。その後に、岡田氏によるST論文へのコメントと私の蛇足を掲載する。岡田氏の応答により私たちの手探りがどの方向に向かいつつあるのかが示されると思う。
【論文】
継承と隔たり――いかにしてデリダは/を継承するかST
■デリダによる継承の実践
継承とは何であるか。一般に継承は、過去のものを現在において想起し証言し、未来へ受け継ぐ営みであると考えられる。そうした考えでは、一方において、現在における同一性が想定されている、すなわち、想起し証言する時の現在は過去と未来とは区別され、厳密には瞬間として、いわば点として幅をもたない。他方において、過去と未来との区別が想定されている。過去が未来であることはない。
哲学を、真理と知の根拠、それらの起源を問うものと考えるならば、哲学はいわば遡及的な営みとなるだろう。その営みが目指す根拠と起源が、――やや奇妙な言い方をするが――過去のもの(時間的に、あるいは論理的に、あるいは価値的に)であるなら、哲学とは想起であることになろう。また哲学が言語を媒介する限り、その想起は証言となる。したがって、過去の根拠と起源を想起し証言する哲学は、その限りで継承の実践であることになろう。
自身哲学者でありながら、過去の哲学者の読み手でもあったジャック・デリダを、継承の問題から読むならば、デリダの哲学つまり脱構築とは、どのような継承の実践となるだろうか。またその際、以上述べた継承の一般的な考え方は当てはまるだろうか。
1990年に発表されたインタビュー「パサージュ」(『中断附点』所収)において、デリダは過去の諸哲学をアナムネーシスすなわち想起として読み替えている。「哲学はそれぞれ、歴史上、アナムネーシスというものの解釈=変奏であった。プラトンのディスクールは、本質的に遠征記あるいはアナムネーシス、つまりは諸々のイデアからなる叡知的な場への遡行です。プラトンの洞穴学における方向転換はアナムネーシスです。ヘーゲルのディスクールはアナムネーシスです。ニーチェの系譜学もアナムネーシスです。ハイデガー流の反復もアナムネーシスです」(註1)。したがって、これらの過去の哲学を想起し解釈すること(それはまさにデリダの仕事の一つである)は、想起を想起し解釈することとなり、「諸々のアナムネーシスのアナムネーシス」となる。例えばデリダは次のように言う、「今日、哲学を想起しようとすることはすでに、記憶に生起したすべてのことに関する、アナムネーシスに生起したすべてのことに関する〔…〕解釈的記憶の中に巻き込まれることであるわけです」。
しかしデリダの仕事すなわち脱構築は、単に想起を想起しているのではなく、過去の哲学と同じように想起をしているのではなく、忘却された起源を想起しているのではない。デリダはここで、「脱構築のモティーフ」について言及するが、それはまず、忘却と記憶との間に一般的に想定される区別と距離を取ることによってであり、さらに、「パラドクシカル」な記憶を提示することによって、すなわち過去を向いた記憶でなく未来を向いた記憶を、提示することによってである。デリダは次のように言う:
私が強調した三つの論点(脱構築のモティーフ、記憶と忘却の関係において一方は他方の反対物ではないこと、現前したことのない過去の記憶すなわち未来の記憶)は後に見ていくことにする。一つだけ指摘しておきたいのは、先程述べた継承の一般的考え方が想定しているもの、すなわち過去は未来であることはないという想定、その想定とは違った事態(「現前したことのない過去の記憶、未来の記憶」)がここで言われているということである。先回りして言えば、ここから導かれることはすなわち、デリダの脱構築がアナムネーシスし想起する記憶とは、来たるべき記憶であるということだ。この事情を後に見ていくことにする。
以上が前置きだが、ここで、本論の初めに、継承の問題について、そしてなぜ継承が問題であるのかについて、ごく簡単に述べ問題提起をしたい。先程、継承は「過去のものを現在において想起し証言し、未来へ受け継ぐ営み」であり、その際には瞬間的で点的な現在における同一性が想定されていると述べた。継承とは、過去から未来への継承である以上、まずは過去と未来との間に或る時間的隔たりを前提としている。しかし継承が成り立つために、次にこの隔たりは解消されなければならない。両者間の隔たりが解消される中間地点に現在がある。だからこそこの現在は、隔たりを持たず瞬間的点的同一性を持つものでなければならなかった。現在の同一性は過去と未来とがバラバラにならないための、つまり継承を成り立たせ時間に連続を持たせるための保証となる。現在が現在自身に同一であって初めて、過去から未来への継承が、両者間の隔たりの解消が可能となる。したがって現在の同一性が、良い継承と悪い継承を区別するだろう。現在が過去や未来に分割されていたり、過去を現在の同一性において十分に想起しえない継承は悪い継承だろう。
しかし、ここが問題だが、こうした考え、すなわち過去と未来との時間的隔たりが、同一的現在の継承によって解消されるという考えは、継承そのものを不可能にしてしまわないだろうか。過去を現在において想起し、その同一性が損なわれると継承が失敗するのならば、例えば何らかの記憶を未来へ継承したとしても絶えずその起源へと、すなわち過去を想起する現在的同一性へと引き戻すべきとなるのであり、保存ならまだしも未来への継承そのものが不可能となる。つまり同一性はその外へ(未来へ)出ることができず閉塞する。しかし未来においても想起されえないものは、結局保存すらできなくなるのであり、つまりは忘却されてしまうのだ。そうであれば、現在的同一性の閉塞に陥らないような継承を考え直さなければならないのではないか。現在の瞬間的点的同一性とそれを起点とした過去と未来の時間の思考を改めなければならないのではないか。例えば現在の内にさえ何らかの隔たりを導入しなければならないのではないか。それはどんな隔たりか。結論から言えばそれは、「反復」であり、「痕跡」である。順に見て行こう。
まず、フッサールを読むデリダによって時間を思考し直すことができる。先程の引用でデリダはアナムネーシスとしての諸哲学の中にフッサールを加えていなかったが、そこにその名を加えることは十分可能である。『内的時間意識の現象学』の時間の構成の議論では、想起が要点となるからだ。点的な瞬間の今において志向性に与えられた原印象(Urimpression)は、次の瞬間に過去把持(Retention)として保持される。この過去把持が第一次想起であるが、第二次想起の再生(Reproduktion)によってそれを主題化することができ、こうして過去の時間が構成される(尚、未来への予測は未来予持(Protention)という)。つまりここでは、(先程までの一般的な時間の考え方はいわば「自然的態度」であり、フッサールが論じる時間の構成は自然的態度を「還元」した上での議論であることをとりあえずは度外視すれば)過去把持は
しかしデリダはフッサールの議論の中に、反復を持ちこむことで、こうした時間の考え方を変容させるのである。フッサールは点的瞬間の今と同時に、今と非−今との連続とを確保しようともして、第一次想起(過去把持)や第二次想起(再生)の間に区別を立て前者を優位においたり、あるいは前者を非−知覚として根源性の領域とは距離をおかせたりするのであるが、いずれにしろデリダは、より一般的な可能性として「反復」を提出する。「われわれはアプリオリに次のように言うことができるはずである。すなわち、この両者〔過去把持と再生(正確には、この箇所では再生は再現前と言われている)〕の共通の根である、最も一般的な形における反−復の可能性は〔…〕今の純粋な顕在性を構成するはずの可能性である、と」。原印象が過去把持によって保持され再生によって想起されることで時間が、すなわち現在が構成されるのであれば、「現在の現前性は、再帰の襞から、反復の運動から出発して考えられているのであって、その反対ではない」。したがって、「根源的と称せられる現前が、このような<自己との非−同一性>をそなえて」いることになるだろう(註3)。反復され得ない時間はないのであり、こうした反復可能性が現在をも構成するのであれば、継承の際に隔たりが解消されることもなく、現在の同一性の閉塞に陥ることもない。(先程私は「
痕跡についてより詳しく説明するため、そして時間について少し違った視点から思考し直すため、論文「ウーシアとグランメー」と「差延」を取り上げよう。そして継承の問題へ接続するため、或る意見を想定してみよう。
例えば次のような意見があるかもしれない:或る文化を継承する場合、その文化をすでに自明のものとして、あるいはすでに規定され定義づけられたものとして考えてはいけない。過去に完成されたものを単に時間的に移動させる機械的技術的反復は継承ではない。継承されるものはその都度常に新しく作りあげられる・現われるのだ。そして時間もそれにしたがって作りあげられる・現われるのだ。継承がなされる現在は、過去現在未来の区別によってすでに構成された現在なのではない、と。
こうした意見は、すでに構成されたものではない対象ないし意味の発生あるいは現出を、また時間の構成を問うフッサールに見合ったものであるし、さらに、存在者とは区別された存在者の存在を問うハイデガーにも見合ったものである。(例えばすでに見たようにフッサール(とそれを読むデリダ)では現在そのものの構成の内に不断の反復の運動が見出されていたのであり、現在はすでに構成されたものではなかったのと同様、ハイデガーにおいても(これから見るように)時間は規定された存在者ではあり得ず、とりわけ点的瞬間の現在が継起したものではない。)その限りでこうした意見は、すでに規定された過去現在未来の区別から逃れ、現在の閉塞から逃れているように見えるが、しかし以前として、継承されるものと時間の現われを、とりわけ
ハイデッガーは『存在と時間』において、時間の本質を今、限界、点、天球として(また時間をその継起として)考えてきたアリストテレスからヘーゲルに至る伝統的な時間の概念を時間の通俗的概念と呼ぶ。そしてこの時間概念は、時間は存在しないというアポリアにぶつかる。「今〔=点〕を基点にして考えると、時間は存在しないという結論にならざるをえない。今が与えられるのはもはや存在しないもの〔過去〕としてであると同時に、未だ存在しないもの〔未来〕としてである。〔…〕時間は非−存在者〔もはや・未だ存在しない者〕たちから合成されている。ところでなんらかの無を含むもの、すなわち非−存在者と妥協するもの〔=時間〕は、現在性=現前性に、実体性に、存在者性そのもの〔…〕に与ることができない」(註4)。だから時間は存在しないことになってしまう。このアポリアは、まさに先程私たちが見た現在の同一性の閉塞であり、隔たりを解消しようとする継承の考え方である。つまりこのアポリアを私たちは継承の問題として読むことができる。すでに構成された点的瞬間の幅を持たない現在(そしてその継起としての時間)を想定すると、未来は未だ存在しない非−存在者として、あるいは絶えず点的現在に引き戻される(隔たりの解消)べきものとして考えられ、現在の閉塞に陥り、結局未来への継承が不可能になる、あるいは時間は存在しないものとなる。(未来だけでなく、過去もまた、現在を基準にして考えられた場合、「かつての現在」「過ぎ去った現在」となり現在の閉塞に陥ることはフッサールの前半部分で見た。ここでのアポリアでも、過去は未来同様非−存在者とされてしまう。)
『自然学』においてアリストテレスは、この時間の問いをアポリアとして提示したまま、解決することなく棚上げし、問いを回避する。デリダはアリストテレス研究者の一文すなわち「アリストテレスが〔…〕回避した形而上学的問題〔=問い〕」という一文を引用しつつ、「形而上学的であるのは、回避された
しかしハイデガーからすれば、存在は点的今の現在的存在者ではなく、さらに存在は存在者でもなく(=存在と存在者との差異=存在論的差異)、時間は現在的存在者ではなく、存在の問いの地平である。点的に規定された「客体的存在者」(註7)としての現在、その存在者
すでに規定された存在者と区別された存在、存在論的差異、存在者
ここで批判されているのは、存在を(すでに規定された)存在者と同一視し、時間を現在から発して考える、現在的−存在者の現前の形而上学である。現在・現前の思考が揺さぶりをかけられている。しかしそれを破壊するハイデッガーさえ、存在の
私たちは、ここで痕跡の問題に戻って来ることができる。なおも現前の形而上学に囚われていたハイデッガーは、『存在と時間』以後、現前についての思考を構成しなおし、『アナクシマンドロスの箴言』では存在論的差異を痕跡として、またその差異の忘却を痕跡が消え失せてしまうこととして提示する(デリダによれば「差異はそれ自体、不在および現前とは異なった他のもの(であり)、(それ自体)痕跡(である)」註10)、すなわち、「現前が現前的存在者のごとく〔言い換えれば存在が存在者のごとく〕現われて〔…〕現前的存在者のうちに自らの由来を見出すようになり、そのことによってただちに〔存在論的〕差異の黎明的痕跡がすっかり消え失せてしまうのである」(註11)。
しかし、例えばアリストテレスのテクストの中に、彼が一度は存在の問いを立て(且つ回避し忘却し)たことの痕跡が残っているように、「痕跡のこの消去〔存在論的差異の忘却〕は形而上学のテクストのなかに痕跡化されたはずである」(註12)。痕跡の消去が痕跡化された。しかし、そもそも「痕跡はなんらかの現前性ではない。〔…〕消去は痕跡の構造に属する。消去は痕跡をつねに襲いうるのでなければならない。さもなくば痕跡は痕跡ではなくて、破壊不可能な、記念建造物のように不朽の実体であることになってしまう。〔…〕この消去はそもそものはじめから痕跡を痕跡として構成する〔…〕。してみれば〔存在論的〕差異の黎明的痕跡の消去とは、その痕跡が形而上学のテクストのなかに痕跡化されることと「同じこと」であるわけだ。形而上学のテクストはそれが失ったもの〔…〕を引きとめて保存したのでなければならない」(註13)。存在論的差異がもはや不在でも現前でもなく痕跡である以上、しかも消去を自身の構造として持つ痕跡である以上、例えばアリストテレスのテクストが存在を忘却したことと、その忘却したことがアリストテレスのテクストに痕跡として残りそのテクストから忘却が読みとられる(ハイデッガーが読みとったように)こととは同じことになる。これは「形而上学的概念の逆転」であり、以後、「現前者〔例えばアリストテレスのテクストに書かれた「現在」「存在」「時間」などの語〕は〔…〕痕跡の痕跡〔例えば存在論的差異の痕跡〕となる。現前者は一切の回付〔通常痕跡が想定させる起源、痕跡化される以前の元のものへの指示〕がそこへと送り返す当のものではもはやない。〔…〕現前者は痕跡であり、痕跡の消去の痕跡である。形而上学のテクストはこのようにして理解される。
フッサールについての論述の最後に私は、現在が「自己とのズレにおいて不断に自己を構成する」反復、「自己と隔たることで自己を構成する」反復について述べたが、自己の消去が自己を構成する痕跡は、この限りで反復可能性と符合するのであり、「したがって厳密には自己を構成しきれない」(同箇所にて前述)ことも同じである。「形而上学のテクストは〔…〕まだ読まれうる」、つまり反復されうる。デリダによって読み直される。忘却し消去したものを、またそのことを、なおも痕跡化したテキストはそれ自身、忘却し消去されたもの・ことを
冒頭のデリダの引用で私が強調した三つの論点をここで整理する。痕跡は消去によって構成される以上、痕跡化とその消去は、つまり記憶と忘却は「反対物」ではない。痕跡は、自己と隔たり未だ反復され想起され続ける記憶を痕跡化する限りで、「未来の記憶」の痕跡でもあり、現前化されたことのない記憶を、現前化しえない未来の記憶としてアナムネーシスするのがデリダの継承すなわち「脱構築」であり、それは過去や未来の現前化ではなく(ハイデッガーによる継承は忘却された存在の
ここから私たちは証言と瞬間と範例性の問題へ進もう。
したがって、継承の際の過去の現前的想起と証言は、反復されることになる。そもそも反復によって過去が過去として度々同定されることができないのなら、それを想起することも証言することも不可能である。だから反復可能性は想起と証言との現前を可能にするが、しかし同時に反復が自己と隔たることで自己を構成する以上(自己を消去することで自己を痕跡化する以上)、厳密な現前は不可能にするのである。自己との隔たりは、点的現在の瞬間さえ、分割するだろう。そのことをデリダは『滞留』において論じている。
フランス語で「瞬間」を意味する語はinstantであり、この語は「切望」や「審級」や「訴訟」を意味する語instanceと語源を同じくする。英語でもinstantは「瞬間」や「差し迫った、緊急の」を意味し、instanceは「例」や「審級」や「訴訟」を意味する。つまり、継承において過去を想起し証言する点的現在は、過去現在未来の中でも特権的で範例的な瞬間であり、範例的な審級であり、まさにやって来ようとしている(sur le point d'avenir=やって来ることの点の上にある)その時点(point=点)にあって、切迫している待機中の瞬間なのである。その切迫は猶予期間、結審前の訴訟中の時間となる。また証言だけでなく証人も同様であり、他の人物でなく証言する範例的人物のみが、分割不可能で代替不可能な瞬間に、唯一の、見・聞き・居合わせ現前した者でなければならない(註15)。
しかしこの点的瞬間と範例性は、そのようなものとして度々同定されるためには反復可能なものでなければならないのだから、反復可能性によって分割されることになる。「証言を行う瞬間には、〔証言の〕文章がそれ自身の反復を〔…〕約束しているのでなければなりません」(註16)。「私が証言するところで、私は唯一代替不可能な者なのです。〔…〕範例は代替可能なものではなりません。しかし同時に、つねに同じアポリアが留まっているのですが、この代替可能性は範例的でなければなりません。つまり代替可能でなければなりません。代替不可能なものはその場で代替可能でなければなりません。すなわち、私が見聞きする唯一の人であったところで〔…〕誰でもよい不特定の人が、私の代わりに〔…〕同じものを見、聞き、触れていたかもしれないという限りでのことなのです。またその不特定の人が範例的に、普遍的に、私の証言〔…〕を反復しうるだろうという限りでのことなのです」。
そうであれば、私が想定したあの継承の意見、すなわち、「過去に完成されたものを単に時間的に移動させる機械的技術的反復は継承ではない」という意見は、覆されざるを得ない。範例的証言は、まさに範例的である限りで、他の誰でもが、他のどの瞬間にも、反復しうるものであり、機械的技術的反復、例えば録音した証言の再生と、文章すなわち言語による証言との間に、厳密な区別を立てることは不可能なのである。「証言〔…〕からは、技術、技術的複製可能性は排除されています。しかし証言は反復されることができなければならない以上、テクネーは、それが排除されているところで、承認され導入されています。そのためにはなにも、テレビカメラやヴィデオ、タイプライター、コンピュータを待つ必要などありません。文章というものが反復可能である、つまりその起源から反復可能である以上、文章が発せられ理解可能に〔…〕なる瞬間〔つまり証言として度々同定される〕には、文章はすでに道具化可能であり、テクノロジーに冒されているのです」(註17)。
(通常の考えでは)過去の記憶の範例的証言による継承は、したがって、範例的証人の現前だけでなく、反復によって他の証人たち、他者たちへと開かれている。他者たちへと開くこの反復の働きは、どんなもの・者であれ、あるもの・者があるもの・者として(過去が過去として、証人が証人として、等々)規定されるための条件である以上、それ自体は規定されえない。現前を条件づける(しかし厳密な現前は不可能にする)その働きは、それ自体条件づけられない無条件なものである。規定されず無条件的な開けは、全く他なる者たちへと開かれている。過去の記憶が常に来たるべき未来の記憶であるとしても、この過去も未来も共に、唯一の範例的証人によって現前化しきることはできず、全くの他者たちへと開かれている。
『アーカイヴの病』でデリダが論じるのはそのことである。デリダはそこで、フロイトの「死の欲動」が「攻撃欲動」や「破壊欲動」であり、「反復脅迫」つまり「反復の論理」がそれらと不可分のものであることに注意を喚起し、無意識(アーカイヴ)は現前しえず、それが記憶したものを同時に破壊し忘却するという逆説を論じる。痕跡の議論で見たように、現われることによって消え去り、自身の消去を同時に痕跡化し保存する痕跡は、記憶と忘却が反対物であるという考えを不可能にするものであった。同様に、『アーカイヴの病』でデリダは、記憶化つまり「アーカイヴ化を許可し条件づける当のものの中に、〔…〕ア・プリオリに忘却〔…〕を導入しつつ破壊へと〔…〕曝すもの以外のものを決して見出さない」と述べている(註18)。フロイトが論じる反復脅迫は、記憶したものを同時に忘却する逆説的なものだった。反復可能性が過去の記憶を未来の記憶にするという初期の「差延」(1968)から後期の『アーカイヴの病』(1994)までの議論は、したがってデリダにおいて一貫していると言えよう。
以上の議論を、デリダ自身が継承について言及している箇所に接続しよう。反復も痕跡も、現前を可能にすると同時に厳密な現前は不可能にするものだが、それ自体は現前的に規定されえないものとして、無規定的なもの、無条件的なものであった。
こうした全ての、時間や過去や継承についての思考が、問おうとするものを何らかの現前性のもとで規定し条件づけるたびに、それ自体は規定されず無条件的なものである継承され想起されるべきものは、忘却され想起されず継承されることができなかったのだ。デリダもまた、デリダ自身言っていたように、差延や反復可能性や痕跡などの語を名称として、すなわち規定し条件づけ意味するところのものを現前化させようとする限りでは、形而上学に陥る可能性を残してしまう。無条件的なものは、そのように条件づけられることによってしか継承しえなかったのであり、忘却されることによってしか記憶されえなかったのだ(記憶と忘却は反対物ではない)。したがって、無条件的なものの遺産の継承は、たえず規定づけを解釈しなおすことによってしか、可能でない。すでに構築されたものをそのまま受け取る継承は、規定づけられた規則的な継承であり忘却であるが、その規定と条件を再度作り変えることによってのみ、半ば忘却しながら継承することによってしか、無規定的で無条件的なものを継承することができないのである。無条件的なものを継承しなければならない、かつそれを条件づけられ規定されたものの再解釈において継承しなければならない、こうした二重の命令があることになる。「私が関心を寄せている問いは、〔…〕遺産というものの本質に関わります。遺産が同時に二重にして矛盾した命令を含んでいるとき、相続〔継承 heriter(最初のeにアクサンテギュ)〕するとはどういうことか? 二重にして矛盾している以上、その命令は夜の中で〔つまり予め規定し指示する知の明るみではなく〕、方向を設定し直し、解釈されなくてはなりません、まるでわれわれは、その時、既成の規範も基準もなしに、記憶を再発明しなくてはならないかのように」(註19)。
こうしてデリダの(による)継承は、過去と未来、記憶と忘却、規則と規則なし、条件と無条件との間で、徹底して二重の挙措となる。記憶を再発明することで、すなわち過去の記憶を未来の記憶とすることで、過去と未来とを交差させ、他方で、これと密接に関連することだが、過去の形而上学のテキストを新たに読み直し、それは例えば痕跡や反復可能性などの新たな名称(なき名称)を提示することによってだが、同時にそれら新たな語を古典的な過去のテキストの読み直しから練り上げ(新たなものと過去のものとの交錯)、さらに他方で、そうした新たな読みの可能性(痕跡や反復可能性などの語による読解の可能性)を、すなわち既成の規範にも基準にも従わない読みの可能性を、しかし過去の様々なテキスト読解の中でこそ配置しなおし規則付ける(たびたび痕跡や反復可能性を読み込み標記づける)。デリダの(による)継承の少なくとも概略が、以上の論述で明らかになったことだろう。
■いかにしてデリダを継承するか
ここから論述は、過去と未来の位置を逆にする。アナムネーシスとしての諸哲学をアナムネーシスするデリダの論じる記憶は、しかし未来の記憶であると述べて来たが、今度は未来を論じる諸哲学とデリダが、しかし過去を論じるものであるということを強調する。そしてまた、デリダによる継承ではなく、今度はデリダを如何に継承するかを、私なりに考えたい。
過去の記憶が来たるべき未来の記憶となるのは、反復可能性によってであった。同様に、来たるべき未来が過去であるのも、反復可能性による。来たるべきもの、つまり過去のものでなく、未だ現在であったことのないもの、日常的な言語で言えば全く新しいもの、そうしたものも、反復としてしかあり得ないのだ。
こうした逆説は、フッサールについての修士論文からすでに一貫していた。後に『フッサール哲学における発生の問題』として出版されることになるこの論文で問題にされていたフッサールの現象学は、すでに構成された対象ではなく対象の発生を、新たな始原を求めて発展しつづける現象学である(その発展を説明する訳者解説の手短なまとめを参照すれば、「経験主義的な発生論からその否定へ、そして意識の内在領域の静態的な描写から超越論的な発生論へ、そして更には超越論的発生の問題を克服するための歴史的目的論へ」。「訳者解説」、三三五頁)。発生という主題ついて問う哲学は、発生という所与の概念に頼ってその主題を問う限り本来的な発生に立ち会えない以上、発生という主題自体が発生しなければならないのであり、発生の主題は主題の発生でなければならない。
これは現前について思考するあらゆる思考が避けられない困難である。すでに規定されたものの反復が現前ではないとすれば、現前についての思考そのものが新しく現前しなければならないのであり、思考は現前という語を使って思考する限りで、すでにして現前を取り逃してしまうのである。
私の知る限りでデリダが一度も取り上げたことのないパラドックスだが、プラトンの「探究のパラドックス」(『メノン』)の伝統が、ここで再度新しく取り上げなおされているとも言えるだろう。すなわち、「人間は自分の知っているものを探究する必要はなく、自分の知らないものは何であるか知らないのだから、探究は不可能である」というパラドックスである。このパラドックスを解決するために導入されたのが想起の概念であり、これが『パイドン』におけるイデアの想起説へとつながる。イデアは経験に先だって生得的に与えられておりそれを想起することが哲学となる。
(フッサールも同様に、とりわけ後期に至っては、沈殿した意味を再活性化するものが現象学となり、受動的総合などの概念にも表れているように、発生が、既に与えられているものの再活性化とされ、発生の受動的側面が強調されるようになる。)
来たるべきものが常に過去のものであること、能動的に構成されるものがすでに受動的に与えられたものであること、だから現前についての思考そのものが現前しなければならないこと、このパラドックスに、デリダが論じた二項対立の全てが連なっていると言ってよい。そして形而上学はこの二項対立をある一者へ還元しようと努めてきた。形而上学の完成者として度々デリダが名指すヘーゲルの円環的弁証法が分かりやすい。経験的なものとアプリオリなもの、感性的なものと叡知的なものを区別するカント的悟性を批判するヘーゲルは、両者の間の弁証法によって、例えば『精神現象学』では絶対知へと至ろうとするのであるが、ヘーゲルが弁証法によって目指す目的は、常に自己への回帰であり、それは時間的に言えば起源への回帰であって、既に与えられ先取りされた目的へと回帰するのである。
こうした形而上学、想起としての哲学においては、過去が未来となり、未来が過去になる。繰り返すが、それは反復可能性による。まず過去に関して言えば、過去は反復によって構成される限りで、未だ未来のものである。他方の未来に関して言えば、来たるべき未来がそれとして構成されるためには(発生やイデアや絶対知の目的などのいずれの議論にしても)、既にその目的が与えられていたのでなければならず、過去に現前していたのでなければならず、そうであれば来たるべき未来は過去の想起によってのみ現前するのであり、すなわち過去の反復によるのである。そして形而上学はその反復を現前的存在者ないし一者に還元しようとするのに対し、デリダは反復可能性が還元不可能であることを示す。なぜなら、繰り返すが反復可能性は過去や未来や現在がそれとして構成されるためのものでありそれらよりも根源的であるからだ、また反復可能性はそれ自身との差異においてのみ可能でありそれ自体では何者でもないのだから還元することが不可能つまり存在と不在との移行や区別によって扱うことが不可能だからだ(反復可能性を解消すなわち不在にして過去現在未来のいずれかを現前的に存在させるのであれ、あるいは反復可能性をそれ自体実体化して現前的に存在させるのであれ)。
来たるべきものを常に過去の反復たらしめる反復可能性をデリダが最後まで還元せず放棄しなかったということ、これはすなわち、デリダは新しいものを現前的に語らなかったということである。デリダは形而上学の脱構築の果てに、何か未来の新しいものを、今までどの哲学者も語ったことがないものを、語っていない。或る意味では、デリダは過去のものをしか語っていない。これはデリダ自身の理論から厳密に導き出される。しかしこれは、過去の反復は常に未来の記憶であると述べてきた今までの論述に、外見上反している。しかしその今までの論述も、厳密に以下のように言い換えられる、すなわち、未来の記憶を論じることができるのは、過去の反復によってでしかない、と。かつての諸哲学が常に過去のアナムネーシスであったというデリダの言葉は、このような文脈で理解されうる。来たるべきものは、それとして常に認識されるためには反復されなければならないのであり、未来とは過去の反復なのである。
私はここから、如何にしてデリダを継承するかという問題を引き出す。つまり、デリダを未来において継承するとは、デリダを反復するということである。しかし改めて問いを立てたい、デリダとは誰か、何をした人なのか。とりわけ、今見て来たように、デリダが何も新しいことを現前的には語らず、過去の反復をしかしなかったのだとしたら、一体そのデリダから(デリダが反復をした他の哲学者ではなく、反復をしかしなかったデリダから)何を継承するというのか、デリダから新しく継承するものはあるのか、「デリダ」という「名」で、何を考えたらよいのか。もう一点付け加えるのならば、私は日本人なので、またこの文章の読者もおそらく日本人なので、日本のわれわれが、デリダから何を継承するのか(しかしこの日本という枠組みを参照したのは恣意的な操作によるものであり、十分な根拠はない。方法上の操作概念でしかない)。
今一度、痕跡と反復可能性に、そしてその「名」に戻りたい。繰り返してきたように、痕跡や反復可能性は、自己自身との差異によって、消えることで現われ、現われることで消えるものであった。こうした逆説的な論理は、「贈与」や「正義」や「歓待」や「赦し」などの様々な語によって変奏的に語られつつも、しかしデリダの生涯に渡って一貫している。デリダを読む際のおそらく最も大きな誘惑は、これら逆説的論理を持つ語を連結させて<デリダの思想>という一つの体系を作り上げることだろう、つまり他の思想家、デリダ的に言えば他の形而上学者との間に区別を立てることだろう。その時<デリダの思想>とは形而上学とは区別された思想、いわば形而上学の<外>を語る思想となるだろう。このように形而上学の外を語る思考として、デリダが用いた逆説的論理を持つ様々な語を連結させる時、その論述は断片的で全く逆説的なものとなる。例えば、消えることで現われ、現われることで消える痕跡、自己自身との隔たりを持ちそれ自身では何者でもない反復可能性、精神分析的無意識への抑圧にも還元されない絶対的忘却としての贈与、贈与として現われない贈与、法を超えかつ法を要求する正義、無条件的な歓待、赦しえないものをしか赦さない赦し、等々。しかもそれらの語は「概念」でも「名」でもない等々。こうした逆説的論理を語る論述は、通常の論理的展開によって段階的に論述することができず、断片的になる。そしていわゆる後期のデリダが、こうした断片的テキストを発表してきたのも確かである。
しかし、逆説的論理を連結させ一貫した<デリダの思想>を構築するこうした読み方に対して、反論が出る。こうした逆説を並べることによって、本当に形而上学の<外>を思考したことになるのだろうか。未だに贈与や正義や歓待や赦しなどの伝統的かつ神学的な語を用いることによって、形而上学の内に留められているのではないか。こうした反論は以下のように言い換えられる。デリダは、西洋哲学の正典を扱い自ら用いる語彙をそこから借りてこざるをえない限りで、西洋哲学を脱構築しながら逆説的にもそれを確固たるものにしているのではないか。こうした批判はフレデリック・ジェイムソンやエドワード・サイードなどによって提起された。また、後期の断片的テキストに対して、評価すべきでないとの批判もある。例えば東浩紀は上述の逆説的論理の形式性に注目して、それを形式的脱構築、論理的脱構築、否定神学的脱構築と読んだ。それらの脱構築は、自己言及的な循環構造を持ち、形而上学から脱出した途端にまた形而上学に陥ってしまうものであり、その脱出口は一つ、単数のものである。これに対して東浩紀が対置させようとしたのは、複数性の郵便的脱構築であった。これらの批判は大筋で言えばいずれも、形而上学や西洋哲学の<外>を思考しようとするデリダの試みは逆説的にもその内へ戻り循環しているというものである。
以上の反論を詳細に見て行く余裕はないが、これらに実に簡略化された形で応えることで、デリダを如何に継承するかについての私なりの考えを述べたい。
まず端的に結論から述べる:一方で、デリダはこうした逆説や循環の<外>へ、生涯逃れなかったのであり、逃れられるとも(さらに逃れようとも)思っていなかったのであり、むしろこの内に留まり続けた。私はそれを批判するつもりはない。他方で、逆に、こうした批判こそが、また逆説と循環に陥るのであり、そして私はそれも批判するつもりはない、と。
後者から述べよう。これらのデリダに対する批判が、デリダが未だ形而上学や西洋哲学の内に留まっていると言いうるためには、形而上学の内や外が何を意味するのかの理解を前提とするが、しかし内と外が未だ形而上学的で西洋哲学的な概念であるとすれば、それらの批判は未だ形而上学及び西洋哲学に留まっており両者を前提していることになる。そしてその前提から抜けるためには、内外の概念についての再考を必要とするが、まさにこれがデリダの仕事の一部であるのだから、これらの批判はデリダと同じスタートラインに立つあるいはデリダの思考を出発点とせざるをえないという逆説および循環に陥るのだ。繰り返すが、私はこのことを批判するつもりはない。これは或る奇妙な必然性なのであり、(またここで形而上学的西洋的語彙を使うことを許してほしいが)いわば有限性なのである。
「暴力と形而上学」においてデリダは、ギリシャ的フッサール・ハイデッガーとユダヤ的レヴィナスを対置させつつも、レヴィナスがギリシャ的自己の外に他者を想定する時、他者が他者として現われ存在するためにはフッサールの現象学とハイデッガーの存在論を前提とすると述べた。また他者の現象や存在を思考するためには言語が必要であるが、しかし言語の反復可能性によって他者の固有性を失わせるという暴力が働かざるをえず――それが言語の有限性だ――、レヴィナスもまた言語を用いる限りこの暴力を前提せざるをえない以上、言語は言語に対して暴力を振いながら――つまり暴力に対する暴力だが、単純化すればフッサール・ハイデッガーとレヴィナスとの論戦である――平和をめざすしかないと言われていた。ギリシャつまり西洋の外(ユダヤ)を思考するためにまさにギリシャを前提せざるをえないこと、ギリシャの中で自己に暴力を振いながら、つまり自己の有限性を批判しながらその<外>を思考せざるをえないこと、まさにデリダはこの逆説と循環に留まり続けたのである。
他者の現前を思考するためには反復可能性が、そして言語の言語自身に対する暴力が必要であった。反復可能性は自己に対する暴力(現前の喪失)であり、自己との隔たりによって消えることで現われ、現われることで消えるのである。つまり痕跡と同じく、自己の消去を自己の構成要素として持つのだ。形而上学の<外>を思考するためには、まさに形而上学が形而上学自身に対して批判をしなければならず、上述のデリダへの批判が述べたように、デリダは形而上学を批判するために形而上学の言語を用いなければならないのである。だから私はこのデリダへの批判を批判しない、それは正当なものである、がしかしその批判もまたデリダを前提するという上述の逆説と循環を指摘することで、私は徹底してその逆説と循環に拘りたいのである。
デリダはこの逆説と循環から生涯出なかった。(もっとも循環(や回帰など)の語に関しては、デリダが後期になってあまり用いなくなることを付言しておく。)いわゆる後期の語として挙げた贈与も同じである。贈与は、贈与の義務があるところでなされてはならない。例えば交換の過程の中で、返済の義務に応えるようにしてなされてはならない。交換や返済の義務になってはならないということは、贈与が交換や返済の循環に中に巻き込まれてはならないということだ。循環の<外>に出なければならないということだ。かくして贈与は義務から出なければならない。しかしここに、義務から出<なければならない>という義務がまた回帰してくるのである。贈与は義務であっては<ならない>という義務、義務でないという義務を負う(『時間を贈与する』)。つまりこれは逆説と循環である。そしてその逆説と循環が、後期になっても未だデリダに取り憑いている、つまり後期にも回帰し、循環しているのである。循環が循環している。
ではデリダは形而上学の内に留まり循環し続け、何もしなかったことになるのか。そうではない。「暴力と形而上学」では、言語の有限性によって他者の現前が、つまりギリシャの<外>の現前が不可能だとしても、言語が言語に対して暴力を振うという道が残されていた。痕跡は自己の消去を構成要素として持っていた、反復可能性も自己との隔たりを持っていた、そして贈与も、義務で<ない>義務という形で、義務自身に対する否定辞を持っていた。つまり、自己への暴力、自己の消去、自己との隔たり、自己への否定のみが、残されている。だからデリダが逆説と循環に留まっていたとしても、それは形而上学と西洋哲学の中に居直って肯定的に自己を語っていたのではなく、形而上学と西洋哲学をそれら自身へとぶつける、それら自身への暴力・消去・隔たり・否定の実践であった。
(「比喩的」な「イメージ」という、本来それ自体哲学的考察を加えなければならないものに訴えることで分かりやすく説明してみれば、デリダは西洋の中からひたすら西洋を囲い込む壁を壊し続けたのだった。デリダは西洋哲学の外に出ることはしなかったし、外が現前的にある(内外の現前的区別がある)とも言わなかったが、とりあえず西洋的なものとして想定されている或る種の哲学(デリダもとりあえずはその想定に従う)を取り上げ、その西洋哲学的建築(それは内外などの二項対立によって建立されている)の内部に一旦留まり、内部から脱構築を行う(内外の二項対立も含めて)ことで、内に既に外が取り憑いていたこと、もはや内外の区別は自明なものではないことを示すのだが、外が外に在るだとか、外が内に在るだとかは言わない。在ることや存在することとは、内にしろ外にしろ、常にある現前性のもとで考えられてきたからであり、今脱構築したのはまさにその現前性だからである。)
したがって、脱構築はつねに形而上学の内で否定されるものを必要とする、あるいは形而上学が否定されることを必要とする。だがこの否定は、形而上学の中のあるものを否定した後に、あるいは形而上学を否定した後に形而上学の外を肯定的かつ現前的に語るのではなく、つまり内の否定を外の現前的肯定への条件とするのでなく、内の否定に留まり続けることで、その内に或る解消不可能なズレ(痕跡や反復可能性などで見た自己との隔たり)を見出だし、その間隙の内に、(つまり過去の記憶が来たるべきものに留まる未来の記憶となる間隙、そして未来の目的が現前されえずいつまでも想起され続けるものに留まる間隙の内に、)外の到来を約束するのであり、その歓待の待機をするのである。それは外を肯定的かつ現前的に語ることとは違う。あたかも外と内との区別が自明であるかのように、形而上学や西洋哲学の外へ出ることが可能であるかのようにデリダを批判する態度とは違う。だから私たち「日本人」が、デリダを継承するならば、デリダに対して未だ西洋の内に留まっているという批判を向けて満足することはできず(外を安易に想定することでデリダ批判者たちが尚も西洋的思考に陥る逆説と循環を先に見たから)、自分たちが日本の内にいると確信したり(例えば自己同一性)その外に出られる(例えば普遍性、範例性)と確信することはできない。そうでなく、日本の内に留まりながら、その内において自己自身との隔たりを見つけるべきなのである。
【コメント1】
継承されざる始まりの回想 岡田有生
この連載企画のことでご相談を受けたのは、まだ2月の中頃のことである。企画の内容は、80年代以後の日本のいわゆる「現代思想」が何を語ってきたのかを再考する、というようなことだった。
自分の能力の及ばない事柄であると思ったが、深く考えずに協力すると答えてしまった。
引き受けてから、古本屋で当時の雑誌や書籍を買いあさったり、多少はリサーチした。それほど本をたくさん読んできたわけでもなく、またぼくは基本的に記憶力がとてもわるい。なので、半分は異国の文化史を研究するみたいにリサーチしていく。
2月の頃には、世間の耳目は、もっぱら中東の民主化の動きに集まっていて、買ったばかりの雑誌『批評空間』(94年第2期第1号)をひろげると、デリダのフロイト論や柄谷行人の文章などに混じってスーザン・ソンタグの手記「サラエヴォでゴドーを待ちながら」が掲載されているのを、リビアからの切迫した報道と重ね合わせるようにして読んだのを憶えている。
その後起きた未曾有の震災と津波の被害、今も収拾の目途がたたない、いや実情さえ分からないままの原発事故、またそれが及ぼす社会全体への影響を考えるのにも、乏しい記憶のなかから95年の阪神大震災や地下鉄サリン事件のことを思い、87年のチェルノブイリの事故を思い出したりした。
***
だがこう書いていても、これらの時間、それはちょうど今回の企画のテーマにおおむね重なる80年代から現在にかけてであるが、それらを自分のこととして十分に体験してこなかった、取り逃がしてきたという思いが、ぼくにはある。そして、その充たされない思いが、「現代思想」という日本語(業界用語?)のニュアンスにも含まれていると感じるのだ。
今回掲載された論文のテーマは、デリダをめぐる「継承について」といったことであるが、この何かを取り逃がしてきたという思いが、ぼくのなかにあるのであれば、それはデリダの言う「継承の困難」ということに、どこか重なるのかもしれない。
デリダが継承の実現を不可能にすると考えた「現在(現前)の同一性」なるものが、西洋形而上学に関わっていたのだとすれば、ぼくにとっての「現在の同一性の閉塞」はどんなものに関わっているのか。80年代も、今も。
この問いは、私的なものに留まるとは限らず、われわれの生の社会的な断面を照らし出すものになるかもしれない。
***
ここでまず、自分の80年代の話をすればいいのかもしれないが、そこに行くまでのことに拘ってしまう。つまり、70年代のことである。
学生であった70年代には、ぼくも人並みに、精神的な危機を幾度か体験した。その頃の個人的な危機の感覚、精神の不安定さは、自分のなかで克服されないままに今もたゆたって、何かの実現を拒んでいると感じている。
考えるのは、その危機は、たんに個人的なものだったのかということである。
70年代は、ぼくにとっては、日々漠然と感じられる世の中全体の暗さ、つまらなさに気が塞ぐような印象の時代だった。
今回のST論文のなかで「現在への閉塞」といった表現を目にした時も、すぐ思い浮かんだのは、あの70年代の重苦しさ、閉塞感だ。
浅間山荘やハイジャック事件、成田闘争、公害報道、「荒れる学校」、ドルショックと不況、ともかく明るい話題がテレビ画面からも消えた時代であった。
しかし、と思う。70年代のあの雰囲気を、ただ「暗さ」や「閉塞」としか捉えられない感じ方の枠組こそ、ぼくが閉じ込められていたものの実体ではなかったろうか?
70年代は、確かに「危機の時代」だったと思う。だが、その危機の実相は、ぼくらの目から遠ざけられ、「暗さ」というレッテルを貼られることによって、その力を奪われた。
ぼくが感じていた閉塞感の真の理由は、その仕組まれた(危機からの)隔離の感触にこそあったのではないか。
***
さて80年代の初め頃、ぼくが好んで読んでいたものの一つは、晶文社から出ていた植草甚一のジャズに関するエッセイだ。
各時代の若者に支持された書き手を名指しする象徴的なコピーとして「50年代の丸山真男、60年代の吉本隆明、70年代の植草甚一」というのがあるそうだが、この植草の本を、たぶん本屋で買いあさって、80年代に読みふけっていたわけである。
今は手元に植草の本が一冊もないのが残念だが、松岡正剛氏が植草の文章の特徴を的確に書いている一文を見つけたので、引かせてもらいたい。
ほんとうにこういう印象だった。
こうした植草の文体は、60年代という政治的変革と反抗の時代に疲れ、それに反発して自分たちの文化を編み出そうとしていた70年代の若者たちの支持を集めた、というふうに語られてきたし、ぼくも当時そういうものとして受けとめていた気がする(事後的に考えれば、ということだが)。
だが、そういう植草の70年代の文章を、今は別様に読み換えてみたい気持ちにかられている。
「音楽を聴き、終わった後、それは空中に消えてしまい、二度と捕まえることはできない」という言葉は、64年になくなったジャズミュージシャン、エリック・ドルフィーの最後のアルバム『ラスト・デイト』に、ドルフィー自身の肉声によって収められたものである(訳はウィキペディアに拠った)。
この言葉には、形而上学の「意味」の支配に抗して戦ったデリダの思想に通じるものがあると思う。デリダはたしかに、声(フォネー)の支配に対して戦ったとされているのだから、こう述べることは逆説的に思えるだろう。だが、ドルフィーのような人が目指していたのも、自分に内在している西洋音楽の「音の現前」の支配からの解放だったのではないか(註1)。
そしてぼくが言いたいのは、植草の、一見クールで軽妙な文章の底に流れていたのも、同一的な意味や現前の支配に対する、こうした戦いの水脈だったのではないか、ということである。
意味の固定、そのことによって生を捕獲すると共に、自らは打倒を逃れ、生き延びてしまう支配的な力との戦いを、デリダもドルフィーも、そして植草も戦っていた。
植草の文章の、あの「入りやすく、読みやすく、そして捨てやすい」という感じは、この「意味との戦い」の、植草なりの形態だったのではないか。
***
いま思うに、こうした試みの背後には、固定的な「意味」の動揺という深刻な危機があったのであり、戦いは、まさにこの危機(深淵)をめぐってなされていたのだ。この深淵を引き受け、その真実の上に新たな世界を作ろうとする人たちと、そこに再び蓋をしようとする人たちとの戦い。
植草のクールで軽妙な文体も、その戦いのなかで生み出された、一つの成果でありスタイルだったと思う。
だとすると、植草の文章のスタイルがはらんでいた可能性は、深淵の絶えざる露呈に向かって、この意味の動揺を持続させることだったはずである。そのことによって、眼前のあらゆる同一性の支配(それによって権力は生き延びる)に風穴を開けていくこと。実際、デリダが目指したのは、そういうことであったと思う。
だが実際には、植草に代表される70年代日本の文化は、80年代以後において、人々の生を動揺させ続けることをやめてしまった。言い換えれば、継承はなされなかったのである。
***
少なくとも80年代以後のぼくは、この「継承の失敗」を条件として生きてきたように感じている。それは、人々が戦いを通して切りひらいてきた生の時間を、自分のものとして引き継ぐことができずに生きてきた、ということである。ここには社会的な共通性(註2
)からの断絶という事態があると思う。
またそれは、危機の肯定の表現でもありえたはずの、70年代文化的な形態を、その可能性を手放して、危機の否認の方向へ、いわば生の領域から切り離されたものとしての消費社会的な記号の流通(意味の充填)に与する方向へと、収束させてしまったということでもある。
ありていに言えば、村上春樹や糸井重里など、「植草以後」の消費社会のスター的な表現者たちのスタイル、意味の呪縛を払いのけて精神の解放感を得ようとする姿勢は、(80年代以後における)権力との戦いの場にこそ相応しいものだったはずだ。だが実際には、それら表現者たちが実践した「意味の否定」は、「権力に反抗することの意味の否定」という特殊な役割だけを担うことになってしまった。
それは、戦いが到達していたもの(地点)の権力による略奪であり、戦いの歴史と意味の、完璧に近い無力化であったとさえ思う(註3)。
いわばこの略奪の裏面として、ぼくが生きてきた時間はある。だが同時にそれは、自分が直面した危機の経験から目を反らしてしまった、自分の過誤(選択)でもあるだろう。
さらにそれは、集団的な出来事としては、かつて一度は日本の社会が危機を通して直面しかけた、社会的な共通性(世界との、という意味でもある)からの、再度の断絶(撤退)を意味したのではないかと思う。この多分に倫理的な問いをかすかに意識しながら、消費社会と「現代思想」におけるある種の「記号」の(その実は「意味」の)支配の時代が、また集団的な「同一性への閉塞」の時代が、そしてまた原発の時代が、幕を開けていったのである。
【コメント2】
蛇足広坂朋信 ST論文を読んで思い知ったのは、私が私を継承することはできない、ということだった。継承という行為が自己と他者の隔たりを自ずから生み出す。過去を継承する自己というものも、継承することによって継承される過去の他者とともに生まれると考えた方がいいかもしれない。ただし、この隔たりを隠蔽し、継承者が継承されたものと同一化したように振る舞うことは可能だ。岡田氏が意味の支配、意味の固定というのも、この隠蔽と自己欺瞞に関わってくるのだろう。これは、過去の知的営為に学びなおそうという私たちの企画が、どんなに謙譲さを装おうとも必ずついてまわる落とし穴だ。「内に留まりながら、その内において自己自身との隔たりを見つけるべき」というST氏の提言を覚えておきたい。
Web評論誌「コーラ」14号(2011.08.15)
<現代思想を再考する>第1回:デリダと継承の困難 継承と隔たり(ST)
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2011 All Rights Reserved.
|
| 表紙(目次)へ |