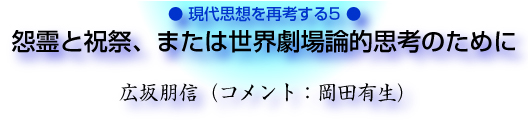|
|
|
Web�]�_���u�R�[���v |
|
���n���̎� ���{���̕\���i�ڎ��j�� ���{���̃o�b�N�i���o�[ ���ǎ҂̕Ł^���ӌ��E���z �����e�K�� ���W�҂�Web�T�C�g ���v���C�o�V�[�|���V�[ |
|
���{���̊֘A�y�[�W�� |
|
���u�J���`���[�E�������[�v�̃o�b�N�i���o�[ ���]�_���u�k�� Vue�v�̑��ڎ� |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
|
���b���_���ւ̈��A
�@���b���_���Ƃ������̂��������B�w������{���b���x�i�ȉ��A���b���Ɨ��L�j�͉̕���̐l�C���ڂ�����A������߂���_���͂������������낤���A�����Ŏ����O���ɒu���Ă���̂́A���N�i2012�N�j��10���ɖS���Ȃ�����ƁE�ےJ�ˈ�ƍ����w�ҁE�z�K�t�Y�Ƃ̂������ŁA1985�N�Ɍ��킳�ꂽ�_���ł���B�_���̃g�s�b�N�X�ƂȂ������b���Ƃ��̃��f���ł���ԕ䎖���ɂ��ẮA����ł����т��ѕ���A�f��A�e���r�h���}������A�֘A���Ђ��������s����Ă���̂Œ[�܂点�Ă��炤�B
�@���āA���̒��b���_���̔��[�́A1984�N�ɔ��\���ꂽ�ےJ�ɂ��]�_�w���b���Ƃ͉����x�i�u�k�Ёj�������B�����w��l�ފw���Q�Ƃ��Ȃ���A���b���Ƃ͌��M�@�ɂ����J�[�j���@���I�������Ƙ_�����ےJ�́A�����̌��_�����Łu����Ƒ�Â��݂Ɍ��ւA�t�Ɠ~�̑Η��ƌ�ւƂ��ӎ��R�E�̏z�̔�g�̏�ɁA���R����j�g���邢�͓���̐��ւ̎�Ђ�����̂��w������{���b���x�̊�{�̍\���v���Ǝ�����v�Ă���B
�@���́w���b���Ƃ͉����x�͊��s�������������]���ɂȂ������A��85�N�ɐz�K�ɂ���đS�ʓI�ȊےJ�ᔻ�u���M�Ɣ����т����v�i�z�K�t�Y�w���Ƒ��̃h���}�c���M�[�x�w�Y���сA�����j�������ꂽ�B����ɑ��ĊےJ�̔��_�u���y�Ɗ����̂��߂Ɂv�i�w�ےJ�ˈ��]�W��O���@�ŋ��͒��b���x���Y�t�H�A�����j���o����A�z�K�̍Ĕᔻ�u���b���̂��߂Ɂv�i�z�K�A�O�f���j�A����ɊےJ�̍Ĕ��_�u���w�̌����Ƃ͉����v�i�ےJ�A�O�f���j�Ƒ������B
�@�Ƃ���ŁA�z�K�̊ےJ�ᔻ�u���M�Ɣ����т����v�͍ŏI�߂Łu�{�e�̈Ӑ}�͊ےJ���̘_�̑S�ے�ɂ���̂ł͂Ȃ��B���b������{���w�j�̐����ȏꏊ�Ɉʒu�Â������Ƃ������̂��l���ɂ͐[��������v�Ƃ��Ƃ���āA�]�_�ƁE�R�萳�a�́u���̖{�́A���E�I�ȉ������J�_�̗͋����T�ł���A�����͎��ɂ��̂܂܉����ł��肤��Ƃ����A�V�����Ӗ��ł́u���E����v�_�̎��݂ɂȂ��Ă���B����͂܂��A�D�ꂽ���{�����_�ł���ƂƂ��ɁA�s�s�_�ł�����̂͂����܂ł��Ȃ��v�Ƃ����w���b���Ƃ͉����x�]�����p���A�u�����ł���v�Ƃ��Ă���B
�@�ےJ�̔��_�u���y�Ɗ����̂��߂Ɂv�͂����Ɋ��݂��Ƃ��납�珑���o���ꂽ�B
�@����ɑ��Đz�K�͍Ĕᔻ�u���b���̂��߂Ɂv�Łu�����g��������悤�ɓ��Y���͂܂������́u���A�v�ł���v�Ɖ��V�����B�����̔ᔻ�͊ےJ���́u�S�ے�v�ł���ƕ\�������̂ł���B
�@���̌�A�ےJ���Ĕ��_�u���w�̌����Ƃ͉����v�ō����w�����̕��@����ɂ��A�z�K�̑ԓx���u�f�p�ȃ��A���Y���v�ƌ��߂������߁A���̘_���́A�����d�錤���҂Ƒz���͂��d���ƁE��]�ƂƂ̂������ŁA�����̋����������_�I���@���𑈂������̂ł��������̂悤�Ȉ�ۂ��������B�Ђ炽�������A�������̂͐z�K�����A�ʔ����̂͊ےJ���A�Ƃ����悤�ȂƂ���ɐ��Ԃ̕]���͗����������B�����Ƃ�����͂����܂ł������̕��w�N���������̐Ȉ�ۂɂ����Ȃ��̂ŁA���ꂱ�����ؓI�Ȕᔻ�ɑς�����̂ł͂Ȃ�����ǂ��B
�@�������A�ےJ�Ɛz�K�̑Η����͕��@�_�ł͂Ȃ��B�u���A�v�̉��V�Ɍ���Ƃ���A���b���͌��M�ɍ��������ŋ��ł���A�J�[�j���@���A���Ȃ킿�j�ՓI�����ł���A���ꂪ�ےJ���̊j�S�ł���A�z�K�͂�����u�S�ے�v�����B���ꂪ�_���̏œ_�ł���B�����āA�u���M�v�Ɓu�J�[�j���@���i�j�Ձj�v�ɂ��Ă̗��҂̒�`���Ⴄ���߁A���̘_���͍ŏ�����Ō�܂ŕ��s�������ǂ����̂ł������B
�@�ꌩ�A���҂Ƃ����邱�Ƃ̂ł��Ȃ��Η��̂悤�Ɍ����邪�A���͂����ł��Ȃ��̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����̂��A�_������O�\�N�߂��o���ė��҂̌�������ǂݕԂ��Ď������������z�ł���B
�@
���M�_�̃A���`�m�~�[
�@�ԕ�Q�m�ɂ��g�Ǔ@��������ɍ]�˂̏��������т����w�i�ɂ́A�������E�j�g�̈����ւ̎��f���������ƊےJ�͉��肵�Ă���B�����₯�ɖ����ᔻ�����邱�Ƃ��ւ����Ă����]�ˎ���A�����͋g�Ǐ���Ƃ̊m���̐^�����𖾂���Ȃ��܂ܑ����ؕ��ƂȂ����ԕ�ˎ�E������������ɓ���A�ނ̗�𐛌����^�╽����̂悤�Ȍ��i����j�Ɍ����ĂāA���̉���̗�Ђɂ�鐢�����A�j�g�����̑œ|��������B�u���O�͎���ɋ����Ȃ�����A�ٕς������炷���Ƃ̂ł���s�g�ȉp�Y�ɓ��ꂽ�炤�v�ƊےJ�͑z�������B�]�ˏ����̊��Ғʂ�ٕς͋N�����B���ԕ�ˉƘV�E��Γ������̗�����ԕ�Q�m���A�]�ˁE�{���̋g�Ǔ@�ɓ�������A�g�Ǐ�����Ƃ����̂ł���B
�@�ԕ�Q�m�͌��M�Ƃ����t���[����ʂ��Ď���̍s���𗝉����Ă����A�����āA�]�ˏ��������M�Ƃ����t���[����ʂ��Đԕ�Q�m�̍s���𗝉������B������x�[�X�ɐ��������̂����b���Ƃ����ŋ����Ƃ����̂��A�ےJ�̑��̎咣�ł������B
�@�z�K�̊ےJ�ᔻ�u���M�Ɣ����т����v�́A�ߐ������j�ɏƂ炵�ĊےJ�̎�����F���w�E���Ȃ���A���M�̒�`�ɂ��ĊےJ�̊g����߂��āA���b���̊j�S�͌��M�ł͂Ȃ������т������Ƙ_�����B�m���ɁA�������������쉻�����ƊےJ�͌������A���𗎂Ƃ����킯�ł��A�]�˂���ԕ�܂Ŕ��ŋA�����킯�ł��Ȃ��B����Ȕh��ȑ�Z�łȂ��Ă��A���߂ĒN���Ɏ��߂��āu��͐�쒷�邪����Ȃ�B��������A�g�ǂ̎�����v�ƌ���邭�炢�͂��Ăق����Ƃ��낾���A���������b���`�����Ă��Ȃ��B�܂��A�ےJ�����M���̖T�Ƃ��ċ����������́A���炩���z�K�ɂ���Ď�����F���w�E����Ă��܂��A����ŊےJ���̐����͂͑傫���������B
�@�����Ƃ��A�z�K�͉̕���́u�r���n�̐l���łȂ���Ό��_�Ƃ͂Ȃ�Ȃ��v�ƌ��肵�Ă��邪�A����ł͍��q�y�ܘY�i�@�ܘY�j���M��Ȃ��B�@�ܘY�̖��́A�z�K���g�����̗�Ƃ��ċ����Ă���̂ŁA����͏d��Ȏ��Ȗ����ł���B�ےJ�́u�z�K�̗��V�őŏ����Ă䂯�A���{�j�Ɍ��_����Ȃ��ȂĂ��܂ӂ��炤�v�i�u���w�̌����Ƃ͉����v�j�Ɣ�����Ă���B
�@���̂悤�ɐz�K�����Ȗ�����Ƃ��Ă܂Œf�łƂ��ĊےJ����r������̂ɂ͕ʂ̗��R������B�ےJ�����݂����z�K�́u���A�v�ɂ́A���͑����������āA�����Őz�K�͊ےJ���b���_���������ᔻ�������@�����̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�@�]�ˎ���ςɂ��Ă͂Ȃ�قǂƎv���B�����Őz�K�͎��グ�Ă��Ȃ����A�j�g�̈����̑㖼���̂悤�Ɍ����鐶�ޗ��݂̗߂͓����Ƃ��Ă͕K�������˔�Ȑ���ł͂Ȃ������Ƃ������i�˖{�w�w���ނ��߂��鐭���x���}�ЁA1983�j�����łɔ��\����Ă����B�������̈����ɋꂵ�ލ]�ˏ����Ƃ����}�́A�㐢�̐V�䔒��ɂ���Č֒����ꂽ�C���[�W�Ȃ̂ł���B�������A�C�ɂȂ�̂́u�]�ˎ���Ɍ�����{�̌̋������鎄�ɂ͂Ƃ��Ă��e�ꂪ�����v�Ƃ��������ł���B�z�K�̌����u���{�v�Ƃ͉����B����͘_���̂�����̃e�[�}�ł���J�[�j���@���Ƃ�������Ă���B
�@
���y�����J�[�j���@��
�@�z�K�̔ᔻ�ɑ���ےJ�̍ŏ��̔��_���u���y�Ɗ����̂��߂Ɂv�Ƒ肳��Ă���̂́A���y�����̕�����ےJ���d�����Ă��邩��ł���B���y�Ɗ����̔ߗ��͒��b���̐l�C�̂���G�s�\�[�h�����A�ŋ߂̉f���e���r�h���}�͎j���̐ԕ䎖�����ӎ����č쌀�����X�������邽�߂��A���܂�傫�������Ȃ��B
�@�ŋ��̑��슨���̃��f���́A���݂����ԕ�ˎm�E����O���ł���B����́A���������ؕ��̑�����A�]�˂��瑁���Ă����Đԕ�ɒm�点���l���ŁA�ԕ�˂����Ԃ��̌�ɓ�������̃����o�[�ɉ���邪�A���e����d�����������߂��Ĕ��݂ƂȂ�A��������O�ɐؕ����Ď��B�ǂ�����������������m��Ȃ����A�ǂ��炩��f���������Ȃ����A�Ǝv��Ȃ��ł��Ȃ����A�ŋ��̍�҂́A�w�����Ƃ����{���𐋂���ꂸ�Ɏ����̊���O�������f���ɑ��슨���^���A�����E���y�i��Γ������̏������f���Ƃ���Ă���j�Ƃ̔ߗ����Ƃ荬���āA�^���ɖ|�M���ꂽ�N�̔ߌ���`���o�����B
�@�ےJ���J�[�j���@���ɂ��Ę_����̂́A�w���b���Ƃ͉����x�̍ŏI�́u�ՂƂ��Ă̔����v�ɂ����Ăł���B�����ŊےJ�̓G���A�[�f�w���Ƒ��x�A�o�t�`���w�h�X�g�G�t�X�L�[�_�x�A�}���[�w���������̉��x�ȂǁA���Ă̏@���w�E�����w�E�l�ފw�̉������Q�Ƃ��Ȃ���A�J�[�j���@���Ƃ́u���Ƃ��Ƃ͎��R�E�̎��ƍĐ��ɊW�̂���A���Â̔_�k�V���v���Ƃ��āA�Ղ̂������������ɋ[����ꂽ�ҁi�U���j���ے��I�ɎE����邱�Ƃɒ��ڂ���B
�@�����Ē��b���́u���̃J�[�j���@���^�̍ՂƂ�����̍\���ŏo���Ă��₤�Ɍ�����v�ƌ����B���t�����~�̉��ŁA���蔻�����t�̉��ł���B�����獂�t���͍Ղ̃N���C�}�b�N�X�ɂ����ċU���Ƃ��ĎE����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����āA�����ؕ��̌�A�����ŏt�̉��̐g����Ƃ��Ċ���i�ߌ��I�Ȏ����Č�����j�̂����슨���i���������Ă��y�͔����̍ȁE�琢��O�̐g���j�ł���A���b���Ƃ́u�t�̉��Ƃ��Ẳ��蔻���Ƃ��̐g���Ƃ��Ă̊������~�̉��ŋ��v���Ƃ����̂��ےJ�̌����Ăł���B���Ȃ킿�J�[�j���@���ɂ�����U���E���̑傪����Ȃ��̂Ƃ����킯���B
�@�ےJ�͂���ɑ�_�ȉ����Ɍ������B���_���J�����ƃJ�[�j���@���Ƃ͋N����������̂ł͂Ȃ����Ƒz������̂ł���B
�@�����āA�ےJ���z�肷��u���Â̐_�b�ƍՂ������̈ӎ��ɍ��荞�܂�Ă�āv�A���ꂪ�u�����̂͂Â݂łƂ���v�u�l�X���������������B����Ȋ�֓I�ȏo���������b�����������̂��炤�v�Ƃ���Ƃ��A����͂������_�Ƃ������A��]�▲�z�̈�ɂ���B
�@
���{�I�ߌ��̌����̌��z
�@�ےJ���ɑ��Đz�K�́u���t�����U���ł���~�̉��ɂ��Ă�͔̂F�߂��鐄��ł���v�Ƃ��Ȃ���i���̓_�Œ��b���ɃJ�[�j���@���I���ʂ̂��邱�Ƃ��ÂɔF�߂Ȃ���j�A�������t�̉��̑㗝���Ƃ����̂́A�ŋ��̓W�J�ɑ����Ė���������A�ƒf����B����Ȃ�u�����͂Ȃ�����Ȃɂ��l�C������̂��v�ƊےJ�ɖ��ꂽ�z�K�͍Ĕᔻ�u���b���̂��߂Ɂv�Łu�����̖��͂̍��{�́A�ނ̎����A�I�v�̌Ñォ��̓��{�l�̎����ςɍ��v���邱�Ƃɂ���v�A�����́u�]���͉����Ƃ͂��Ȃ��̊������v���炾�Ƃ������߂������A���̍����Ƃ��Ď��g�̘_���u���{�I�ߌ��̐����ƓW�J�v�̎Q�Ƃ����߂Ă���B�Y���ӏ��Ǝv����Ƃ���_����������B
�@�z�K�́u�ߌ����M���V�A�^�ߌ����������āA�e�����Ɋe�����ŗL�̔ߌ��̌`��������Ƃ���v�̂�����̗��ꂾ�Ƃ����B���̘_���̖`���Őz�K�́A�X�^�C�i�[�w�ߌ��̎��x�i�}�����[�j���M���V�A�ߌ��ɔ͂��Ƃ����ߌ���������u���{�̉����́A�c�E�ȏ�ʂ�V���I�Ȏ��ł݂��Ă���v������͔ߌ��Ƃ͌ĂׂȂ��Ƃ������ƂɈًc�������A�w�����ꍇ��x�Ɓw�I�C�f�B�v�X���x���r���ċ��ʐ������o���A���X�p�[�X�w�ߌ��_�x�����p���āu�_�ł����ł��Ȃ��Ƃ���̐l�Ԃ��A�l�ԂƂ��Ẳ\�������肬��̂Ƃ���܂ł��߂Ēǂ����߁A�����Ď����̐ӔC�ɂ����Ėv�����Ă����s�ׂ̕`����Ă��邱�Ƃ��A�ߌ��̖{���v���ƒ�`���Ă���B����́u�ߌ����M���V�A�^�ߌ��������v�����Ƃ������A�����܂ŃM���V�A�ߌ����N���Ƃ��鐼���̉����_�̓`������ɂ��āA���{�̉����𐼉����E�ɏ��F�����悤�Ƃ���c�_�Ɏv����̂����A���͂��̂��Ƃ͂����Ƃ��悤�B
�@����ł́A���{�����ɌŗL�̔ߌ��̓����͉����Ƃ������Ƃ����A�u���{�l�̊�{�I�Ȏ����ς́A�i�����j�Đ��E�I�Ȏ����ς̘g���ɂ���v�Ƃ��Ă���ȏ�A�����܂ł͓��{�����ɌŗL�Ƃ͌����Ȃ��B���Ȃ݂ɂ��́u�Đ��E�I�Ȏ����ρv�͂����ς烂�[�X�ƃ��x�[���́w���]�x�i�@����w�o�ŋǁj��_���ɒ��o����Ă���B�����āA���O�����w�����p�Y�x�i���z�Ёj�A�n���\���w�Ñ�|�p�ƍՎ��x�i�}�����[�j���Q�Ƃ��āA�u�ߌ��I���_�́A���̐M�V��̒��ł����ɋ��]�ɂ�����_�̋��]�ɋN�������v�Ƃ����B
�@�z�K�͑另�ՂȂǂ�O���Ɂu���{�I�����ς͔_�Ƌ��]�������Ƃ��邽�߁A�]���͓������]�Ƃ͈قȂ�����Ƃ͂��Ȃ��̊������v�_�ɓ��{�̌ŗL��������Ƃ��Ă��邪�A����ɂ͂�������O������B�z�K���g�������Ă����݂̂Ɍ����Ă��A�����ł́w���{���I�x�A�w�����{�I�x�A�w���{��ًL�x�A�w���̕���W�x�A�w�F���E�╨��x�A�w�_���W�x�A�n���I�ɂ͉���̃E���W���~�A�k�C���A�C�k�̃C���}���e�̍ՂȂǂɓ������]���F�߂���B�z�K�͂���ȊO�ɂ��u���{�œ������]���Ƃ����͂������ď��Ȃ��͂Ȃ��v�Ƃ��Ƃ���Ă���i�Ⴆ�ΐz�K�͋����Ă��Ȃ����M�B�E�z�K��Ђɂ͓������]�̋L�^������j�B
�@���ꂾ���̗�O����Ă݂���z�K�̐������̂������ŁA�_�Ƌ��]�������Ƃ�����{�I�����ς̓K�p�͈͂��A�傫�����ς����Ă�����I�ɂ͒����Ȍ�A�n���I�ɂ͖{�B�̈��_�Ƃ�����Ȓn��A���Ȃ킿���c�����w�̂����햯�̐�����ԂɌ��肳��邱�Ƃ��킩��B������z�K���u�]�ˎ���Ɍ�����{�̌̋�������v�̂��u�ߏ��̔ߌ��I��i�������ē��{�I�ߌ��̓T�^�ƍl����v�̂����R�Ȃ̂ł���B�z�K�����{�l�̖������̔w�i�Ƃ��Ďv���`���u�_�k�𒆐S�Ƃ������a�Ȑ������J��Ԃ��Ă����v�Љ�Ƃ́A���j�I�ɂ͋ߐ����}���Ă��猻�����������̂����炾�B
�@���ǁA�z�K�̂���Ă��邱�ƂƂ́A�����̌ÓT�w�A�l�ފw�A�@���w�Ȃǂ̕��@�ƊT�O�ɂ���Ĕߌ��̖{�������]������������ʓI���f����ݒ肵�A�����ɖ��c�����w�ɂ���čč\�����ꂽ���{�l������Ƃ��ĉ������āA���{�I�ߌ��̓������Ƃ炦��Ƃ������Ƃł���B
�@����ł͊ےJ�͂ǂ����ƌ����A�w���b���Ƃ͉����x�̂��Ƃ�������A���̈ꕶ�������Ă��������ł悢���낤�B
�@���͂⌾�t���₷�K�v�͂Ȃ����낤�B�v����ɁA���̓�l�͓������Ƃ�����Ă���̂ł���B���E���w�j�̒��ɒ��b�����ʒu�t�������B���̏ꍇ�A�u���b���v�Ƃ͓��{�����̉B�g�ł���A���������̓��{�����Ƃ́A��l�����ꂼ��Ɏv���`�����̂łȂ���Ȃ�Ȃ��̂�����A�Ƃǂ̂܂�A�����̓��{���������̐��E�����j�ɂ�����ʒu�Â���T�鎎�݂Ƃ������ƂɂȂ�B�g���W���Ȃ�������������A�O���[�o������ɂ�����i�V���i���E�A�C�f���e�B�e�B�T���̐��ł���A��������x�o�ϐ����𐬂������Ď��M�Ɨ]�T�������Ă������{�Љ��w�i�ɂ��ĂȂ��ꂽ�f�B�X�J�o�[�E�W���p���Ȃ̂ł���B�������A���̌�́A�����Ƃ��`���E�����Ƃ��̌��t�������x���a�Ȍ����ɂ���ׂ�A���҂Ƃ����e�Ƃ����A����̍L���Ƃ����A�͂邩�ɗD�ꂽ�c�_�ł��������Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B
�@�z�K�͊ےJ�̒��b���J�[�j���@������ے肵�Ă��邪�A�u�]���݂͂������j�邱�ƂȂ��ɂ͗��j�I���`�̎����ɍv�����邱�Ƃ͂ł��v���A���́u�]���̔j��͍Վ��̒��S�ɐ������Ȃ���Ȃ�v�Ȃ��̂ł���A�z�K�̍l����ߌ����܂��u�Վ��v�Ƃ����`�������Ձ��J��ł���B�������Ă݂�Ɨ��҂̔ߌ��ς͍��J�̖ړI�ɂ��Ă����Ⴂ�����邪�A���]�����J��͂Ƃ���_�ł͓����ł���B���̓_�ł����҂Ƃ��A�R��̌����Ă����u���E�I�ȉ������J�_�v�̒����̂Ȃ��ŋc�_���Ă���̂ł���A�����Ē��b���͏�Ɏj���̐ԕ䎖���ƑΔ䂳��Ȃ�������킯������A�u�����͎��ɂ��̂܂܉����ł��肤��Ƃ����A�V�����Ӗ��ł́u���E����v�_�v�i�R��j�ł�����킯���B�ȉ��ł͂��̐��E����_�̏����Ɖ\���ɂ��čl���Ă݂����B
�@
�����̎��̈Ӗ�
�@�Ⴆ�A�h���}�̓o��l���������Ŏ��ʁB����̏�ł͉��蔻�������������ʁB�������A����������Ă�����҂����ʂ킯�ł͂Ȃ����A����̏�Ŏ��o��l�����A�j���̐��������⊞��O�������悤�Ɏ��킯�ł͂Ȃ��B�ے��I�Ȏ����ł͐����Ԃ�����A���܂ꂩ�������A�����������肷�邱�Ƃ�����B����͋r�{�≉�o�ɂ���Ă�������ꍇ�����邵�A�ϋq�̐S�̂Ȃ��Ő���������ꍇ������B���̓_�����������̂��ےJ�w���b���Ƃ͉����x�������B�ےJ��ᔻ�����z�K���u�]���͂܂��݂�����j��邱�Ƃɂ���ċ]�����g���i���̐������l���ł���v�Ƃ������炢������ے�͂��Ȃ����낤�B�h���}�̂Ȃ��ł͒N�����ȂȂ��B���ꂪ���̘_���̑O�B
�@���������O�����Ă��邽�߂ɂ́A��̏���������B�u�i���̐����v���l�����鎀�҂́A��i���E�̍\���v�f�łȂ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃł���B��i���E�́A������\������v�f�̈����݂��ɗL�@�I�ɊW�������āA�e�v�f���S�̂̂Ȃ��ňӖ��̂���͂��炫�����Ă���悤�Ȓ�������S�̂ł���B���̋�̗Ⴊ�A������i�ł���A���w��i�ł���A���邢�͍�i�����ꂽ�_�b�E�`���A����Ƃ��Ă̗��j���X�ł���B�ڂ̑O�Ō����ɋN�����o�����ł��A�������̌��i���f����Ƃ���̏�ʂƂ��ĂƂ炦�ăJ�����ɂ����߂���A����͂�����i���B
�@���̑O��́A�w�V�������w�̂��߂Ɂx�i��g�V���A1988�j�ő�]���O�Y�����L���Ă���B��]�̓o�t�`�����Q�Ƃ��āA�u�J�[�j�o���I�Ȑ��E���o�v�Ɓu�O���e�X�N�E���A���Y���v�Ƃ������_����䕚����w�������x��ǂ�ł݂���B
�@������A�h���}�̂Ȃ��ł͒N���{���̈Ӗ��ł͎��ȂȂ��B���������̖`���œo��l���̈�l���E�����B�Ɛl�͒N���H �Ƃ����Ƃ��납�畨�ꂪ�n�܂�B��Q�҂͎E���ꂽ�̂����玀��ł���B����ǂ��A��i�̂Ȃ��ł͌����ĖY����Ȃ��B���̈Ӗ��ł͎E���ꂽ���Ƃɂ���Đ��������Ă���̂ł���B
�@����̏�ł͎�����̉��Z�ł����āA�l�̎��͂��ׂĈӖ��̂��鎀�ł���B�����炱���A�ߎS�Ȏ��𐋂����w�������x�̖����A�O���e�X�N�E���A���Y���̌������Ă�A�u����Ȗ����̑��ɌĂі߂��A���E�̕����I�E���̓I�����ƌ��N�Ɍ��тȂ����Ă��v���Ƃ��ł���Ƒ�]�͑z������B
�@�������A�����͂����ł͂Ȃ��B�w�������x�ŕ`���ꂽ���̎��������̌��i�������ꍇ�A��O�҂����̎����A���܂��܋G�߂͂���ɍ炢�Ă����Ԃƌ��т��āA�����Ȃ銴���ɂЂ��낤�����z�ɂӂ��낤���A���҂��u�����̑��ɌĂі߂��A���E�̕����I�E���̓I�����ƌ��N�Ɍ��тȂ����Ă��v���ƂȂnj����Ăł��Ȃ��B���ꂪ�\�ł���̂́A���̎������w��i�Ƃ������ꂽ���E�ɂ����鎀������ł���B�u�]���݂͂������j�邱�ƂȂ��ɂ͗��j�I���`�̎����ɍv�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v�Ƃ����z�K�̎咣���A���ꂪ�����_�ł��邩��m���l������̂ł����āA���ꂪ�����̐��E�ɂ��Č���ꂽ���t�ł���A���ȋ]����K�{�v���Ƃ���u���j�I���`�v�Ƃ͉����ƁA�������ɖ���邱�ƂɂȂ邾�낤�B�������A�摖���Č����A�����Ґ���ϗ��I�Ȗ₢��I�グ�ɂ��āA���̈Ӗ������邱�Ƃ��ł���̂����E����_�I�v�l�̗��_�ł���B�����ł͎���s�݂⌇�@��Y�p����u�����ł��ʑ��̂Ƃ��Ă̈Ӗ���S���āv����A��]�̌����悤�ɉ��炩�̕��@�I�ӎ��������č�i�ɗՂ߂ΈӖ���ǂ݂����邱�Ƃ���ł���B
�@�Ӗ��̂��鎀�A�i���̐��������藧�̂́A���ꂪ���ꂽ���E�A�L�@�I�Ȓ���������̍�i�́u�����ł��ʑ��́v�Ɋ܂܂�Ă��邱�Ƃ������ƂȂ�B�u���̐��͕���A�l�݂͂Ȗ��ҁB�o�����������v�i�V�F�C�N�X�s�A�j�ł���B����𒆑��Y��Y���w���������_�l�x�i��g���X�j�Œ����u�����I�m�v�̏����Ƃ����Ă������B����͏d��Ȑ���ł���B���ɂƂ��Ă̎��̐��́A�������ʂ܂Ŋ������Ȃ��B������A�ǂ�قǕM�̑�����Ƃł��A���S�Ȏ��`��{���̈Ӗ��Ŋ��������邱�Ƃ͌�����ł��Ȃ��B���͎��̎��������Ӗ��Â��邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B���̐��́A���̎������͂����N�����҂ɂ���Ă����Ӗ��Â����Ȃ��B�������Ȃ����j�́A�X�I�ȋ������Ȃ������i���ł��Ȃ��B���E�������ƌ����Ă邱�Ƃɂ́A���̂悤�Ȍ��E�������B
�@�v���A�����I�m�Ɛl�ފw�I�v�l�̑������悢�̂́A70�N�ォ��80�N��ɂ����Ă̂��̒҂ł��钆���Y��Y�ƎR�����j�ɐe��������������ł͂Ȃ��A�Ώۂ��狗�����Ƃ��đS�̂����n�������A�����҂̎��ȗ����𗣂�ĉ��߂�Ӗ��Â����s���ԓx�Ȃǂ����ʂ��Ă��邩�炾�낤�B�O�҂ɂ͕���Ƌq�Ȃ̋���������A��҂ɂ͐A���n�ƒ鍑�̋����ɉ����ĕ����I���ق�����i�����́w���������_�l�x�̓o�����i�ٕ����j�̉����i��i�j�����f���Ƃ��邱�Ƃœ�d�̑Ώۉ����d�g��ł���j�B�������h���}�ƌ����Ă鐢�E����_�ɂƂ��āA�ΏۂƋ������Ƃ邱�Ƃ͏d�v�ȏ����ł���B
�@
���E����_�I�v�l�̉\��
�@�����܂ł����̌��E�����m���������ŁA�Ȃ̂����A���E����_�I�v�l�̉\���ɂ��čl���Ă݂�B�Ⴆ����́A���p�ϗ��w�̗��s�ƂƂ��ɍL���m��ꂽ�~���{�[�g���ȂǂƂ͎��Ă���悤�ňႤ�B�~���{�[�g���͒P���v�Z�ł���B���10�l�̋~���{�[�g�����Ȃ��̂ɏ�q��11�l����I ���Ăǂ����邩�H �ł���B���̃N�C�Y�́A�S�̂��������т邽�߂Ɍ��]���ɂȂ�͎̂d���̂Ȃ����Ƃ��Ƃ������b�Z�[�W��`���邽�߂̂��̂Ȃ̂ŁA�ً}���Ԃ̑Ώ��@�ɂ��Đ^�̉��������߂Ă���킯�ł͂Ȃ��B�����́A11-10=1�A�N����l����ł��炢�܂��傤�Ƃ������ƂɌ��܂��Ă���̂��B������A�l�߂����Ă�����l���̃X�y�[�X�����Ƃ��A�]�v�ȉו����̂ĂĂ�����l����悤�ɂ��悤�Ƃ��A�������������펯�I�Ŏ��ۓI�ȉ����͋p�������̂ł���B
�@�X�P�[�v�S�[�g�̖��́A�h�X�g�G�t�X�L�[�w����x�̃X�^�u���[�M���̃Z���t�������āA�S����v�ň�l���E�����ƁA�ƒ莮������邱�Ƃ�����i�W���[���j�B����͈ꌩ����Ƌ~���{�[�g���Ɏ��Ă���悤�Ɍ����邪�A�w����x�ɂ�����V���[�g�t�E���́A�~���{�[�g���Ƃ͐l�Ԋςɂ����Č���I�ɈقȂ�B
�@���b�����炢���Ȃ�h�X�g�G�t�X�L�[�Ƃ͂����Ԃ�Ȕ�Ɨ�₩����邩������Ȃ����A�]���́A�V���[�g�t�E���̎�ƃs���[�g���̉A�d�����V�A�̃t�H�[�N���A��w�i�Ɋ�Ă��Ă��邱�Ƃ��w�E���Ă���B
�@���m�̂悤�ɁA�s���[�g����h�ɂ��V���[�g�t�E���́A���ۂɋN�����Z�N�g���̓��u�E�Q�����A�l�`���[�G�t���������f���ɂȂ��Ă���B�����̎�d�҃l�`���[�G�t�ɂ��Ă͏ڂ������Ƃ͂킩��Ȃ����A���V�A�̃A�i�[�L�Y���v�z�ƃo�N�[�j���ƒʂ��Ă����炵���i�q���O���[�w�j�q���X�g�@���V�A�����N�̓^���x�݂������[�j�B�o�N�[�j���͐��E�e�n�𗷂��A�t�����X�ł̓v���[�h���̒m���A�Љ��`�C���^�[�i�V���i���Ń}���N�X�Ƙ_������ȂǑ�ꋉ�̍��۔h�m���l�ł������B�����̐�[�I�v�z�ƌ݊p�ɓn�肠�����o�N�[�j���̃A�i�[�L�Y���ƁA�s���[�g���̖����I�ȁu�����v���O�����v�Ƃ̗����͑傫���B���ԐM�ɒ��ڂ����O�̐�������]���Ȃ���_�ŁA�s���[�g���́u�����v���O�����v�͐����̃A�i�[�L�Y�������ےJ�����b���ɓǂ݂Ƃ����A���M�ɗR������]�ˏ����́u�ٕς������炷���Ƃ̂ł���s�g�ȉp�Y�v�ւ̊��҂ɂ�قNj߂��B
�@�s���[�g���́A�����O���[�v�̌��������߂邽�߂ɒ��Ԃ̈�l�V���[�g�t�𗠐؎҂Ɏd���ďグ�A���̒��Ԃ������̂����ĎE������B�����āA�B���H��̂��߁A���̍߂��L���[���t�ɕ��킹�Ď��E������B���̉A�S�ȃh���}�̂Ȃ��ŁA�V���[�g�t���L���[���t��11-10=1�Ƃ��������̂Ȃ���1�ɂ͂ƂĂ����܂�Ȃ����݊��������ĕ`����Ă���B����͉A�d�ƃs���[�g���𗽉킵�Ă���A�V���[�g�t�̎��̓s���[�g���̏��҂Ԃ���яオ�点�Ă��܂��B�L���[���t�̎��E�Ɏ����ẮA�s���[�g�����L���[���t�̃j�q���Y���𗘗p���Ă���̂��A�L���[���t���s���[�g���̏��H�𗘗p���Ă���̂��A�肩�ł͂Ȃ��B
�@���b���̏ꍇ�͂ǂ����낤���B�Ⴆ�ΊےJ�̌����Ēʂ�A���̎ŋ���������������̌����������A����j�g�̈����ɂ��߂Ă��̟T�����炵�����悤�Ƃ������̂ł���Ƃ���A�j�g�̐g����ł��鍂�t���i�g�Ǐ���j�����܂ł̕��ꒆ�̎��҂͂��ׂāA���蔻���i��쒷��j�̗�Ђ𑝂����߂ɕ�����ꂽ�����Ƃ������ƂɂȂ�B�Ȃ��ł������́A���蔻���̕��g�Ƃ������i�������Ă��āA�����Ŕ����̐ؕ��i���O�̎��j���ĉ����A���̗�́i���ۂɂ͕`����Ă��Ȃ����j�����̖���Ƃ��ėR�ǔV����}�̓�������ɂ��ے��I�ɎQ�����Ă���͂����Ƃ����̂��ےJ�̌����Ăł���B
�@����ł͂��̊����͑̐��ᔻ�̃V���{�����Ƃ����ƁA�����P���Șb�ł��Ȃ��B
�@���������̎ŋ��S�̂̉B�ꂽ��l���Ƃ���ےJ�ɂƂ��āA����́u���{�l�S�́v�̐����ɂ��Ă̑ԓx�u�Ӗ��ƔE�]�v�𐳓������Ă���鑶�݂ł�����B
�@����A�z�K�ɂƂ��Ă̊����́A�d�v�ł͂����Ă������܂Ře���̈�l�ł���B�z�K�͎��̂悤�ɉ��߂���B
�@���̏ꍇ�A�����̎��͗R�ǔV����}�ɂƂ��ĈӖ�������̂ł����āA�ےJ���Ƃ͑傫���قȂ�B�Ȃ��A�z�K�̌������j�I���`�Ƃ́u���j����ʂ���`�̑��݂�F�߂闝�O�v�̂��Ƃł���A���̎����Ƃ́u���I�ȏ��̍�����������邽�߂Ɋ�Ă��Ȃ���A���I�ȑ�̖������������邤���Ɍ���I�Ȗ������ʂ������v�Ƃ������Ƃł���炵���B�����̏ꍇ�́A�n�E���̋^�����������āA�Ƃ�������u�����������A�i�ނ���܂�������A�킪�g�̌������������߂Ɂi���I�ȏ��̍�����������邽�߂Ɂj�ؕ������B���̒���ɋ^��������A�����ςꒉ�`�̎m��Ƃ������ƂɂȂ��ĘQ�m�����̎m�C�����܂�i���I�ȑ�̖������������邤���Ɍ���I�Ȗ������ʂ������j�̂����A�ǂ���炱�ꂪ���j�I���`�̎����Ƃ������Ƃ̂悤�ł���B
�@���̂ق��ɁA�z�K�̊������͂��������B�����́u�������E�̐������������邽�߂̋]���v�����A�z�K�ɂ��u���{�I�����ς͔_�Ƌ��]�������Ƃ��邽�߁A�]���͉����Ƃ͂��Ȃ��̊������v�Ƃ���Ă���̂ŁA�u�����Ƃ͂��Ȃ��̊����v���ĂыN�����l���A���ꂪ�����̂�����̑��ʂƂȂ�B
�@������l���Ƃ��Ă��A���ꂾ���Ⴂ������B�ǂݎ�ɂ���ĈႤ�͓̂��R�Ƃ��āA��l�̓ǂݎ�ɂƂ��Ă������̑��ʂ̂���l���Ƃ��ĂƂ炦����B�ےJ�́u�����̂��낢��ȋǖʁv�Ƃ��ĐN�A���m�A���l�A�엎�ҁA�Q�l�A�s���ҁA���b�A���V�Ȓj�A�t���瓢������ɎQ������S��Ɏ���܂ŁA���ɓ�\�̖ʂ𐔂������Ă���B�Ō�̖S��Ƃ����̂́A�z�K�ɂ��ΊےJ�̎v�����݂Ȃ̂ł���͏����Ƃ��Ă��A�����͏\��̖ʂ��������l���ł���B����ɐz�K�̋�������𑫂��Γ�\��̊�������ƂɂȂ�B�����āA�u�������ł͂����͒N�ł��݂ȁA����Ɠ����₤�ȁA���邢�͂���ȏ�ɕ��G�ȏ����Łi���������ƕ��}�ȕ��G���Łj�����Ă��v�i�ےJ�j�B
�@���E����_�I�v�l�́A�������̎������́u���G�ȏ����v���l���ɓ���Ď��Ԃ��Ƃ炦�邱�Ƃ��ł��Ă����Ӗ�������B�l�Ԉ�l���Ƃ��Ă݂Ă��A���̑��݂�11-10=1�Ƃ����v�Z���ɊҌ�����Ȃ����ʓI�Ȃ��̂ŁA�������������Γ�\��ʑ��ł���B�����Ď������̎Љ�́A�����̓�\��ʑ������̐D��Ȃ��d�w�I�ȋ�Ԃł���B������Ƃ炦�悤�Ƃ���A�ǂ����Ă��c�_�͓���g���̂ɂȂ邾�낤���A�ȒP�ɕ\�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�_�҂ɂ���ĕ����̉��߂����藧�B�ǂ��܂ł������܂������c��A�����ς肵���e�[�[��ł����ɈÎ�����ق��Ȃ��ꍇ�����낤�B�����ɂ��i�D�̈������Ƃł��邪�A����Ő��E����_��͍�����Ȃ�A����Ɗϋq�Ƃ��������I�m�̏�����D�荞�݂A�E�_�b�����ꂽ�Љ�łȂ����o����镨�ꂪ�Đ_�b�������_�@���]�I�ɂ��ނ��ƁA�����������Ƃ����̒[���ɂȂ�̂ł͂Ȃ����낤���B
�@���b���_���ɘb��߂��ƁA�����炭�z�K�������Ƃ����������ےJ�̒��b�������̈ꑤ�ʁu�̐��ɑ��锽�R�Ǝ��f���Y�\�Ƃ��Ắw������{���b���x�v�ɐ��E����_�I��]�̈�̎p���\��Ă���B�u���̋����͖I�N��\���ړI�Ɏ�����������������肷���`���ł͌����ĂȂ��A�������͂������́A�����̊Ⴉ�猩������Ԃ���S�Ȑ��i�̂��̂����v�i�ےJ�j�B
�@�ےJ�̌����u����v�Ƃ͂܂������w������{���b���x�̂��ƂȂ̂��A�u�����v�Ƃ����͍̂]�ˎ���̂��ƂȂ̂��A�u���{�l�v�Ƃ͒N�̂��ƂȂ̂��A�u�ނ�̐��E�v�Ƃ͒N�̐��E�̂��ƂȂ̂��B�Ƃ�����A�j���ƈ�v���邩�ǂ����͕ʂɂ���A�ϋq�̑��݂ɒ��ڂ����Ƃ���ɁA�ےJ�̔�]�ƂƂ��ẴZ���X�������Ă���B
�@
���E����̋S��
�@���͐��E����_�ɂƂ��ăJ�[�j���@���I���ۂ͋S��ł���B
�@���_�a���w�҂̖ؑ��q�́A�j�Ղ��L�[���[�h�Ƃ��đ�\�I�Ȑ��_�����i�Ƃ��̃A�i���W�[�Ō���鐫�i�ތ^�j�ނ����i���p�����́u�����a�v�͌��݂ł͓��������ǂƌĂ�Ă���j�B
�@�����āu���܂܂łƂ��܂���Ƃ����L���Ȍʐ��̋K�肩�������ꂽ�i���̂��܂ɂ����āA�F����Ɋg�債�����Ȃ��A�����I��҂Ƃ��Ă̎��R�Ƃ̘a���̏j�Ղɐ��������v�A���ꂪ�u�j�ՓI�Ȍ��݂̗D�ʁv�A�u�i���̌��݂̌��O�v�Ȃ̂��Ƃ����B�ؑ��͂��̃C���g�D���E�t�F�X�g�D���I�ӎ��̋�̗�Ƃ����ᒂ��N�a�̏Ǘ�̂ق��ɁA�h�X�G�t�X�L�[��i�̓o��l���A�w���s�x�̃��C�V���L���A�w����x�̃L���[���t�A���U���F�[�^�A�w�J���}�[�]�t�̌Z��x�̃A�����[�V���������Ă���B�ށE�ޏ���ɋ��ʂ���̂́A���݂̏u�Ԃɉi����S���E�������Ƃ�A�E���̌��A���邢���N�a�I�G�N�X�^�V�[�ł���B�u���悢��c��ܕ�����ŁA����ȏ㖽�͂Ȃ��Ƃ����Ƃ��ɂȂ�܂����B���l�̂����Ƃ���ɂ��܂��ƁA���̌ܕ��Ԃ��ʂĂ����Ȃ����������ŁA����ȍ��Y�̂悤�Ȏv�������������ł��v�i���C�V���L���j�A�u����͈�x�Ɍܕb���A�Z�b���������Ȃ����A���̂Ƃ����R�Ƃ��āA���S�Ɋl�����ꂽ��i�v���a�̑��݂�����̂��v�i�L���[���t�j�A�u�ޏ��́w�������ق�̈�u�Ԃ��������ł��Ȃ������Ƃ킩���Ă���̂Łx�A�v�������Č��S���āw�S�l�������̈ꎞ�Ԃ�������k�̏�l�ɓq���Ă��܂����x�v�i���U���F�[�^�j�B���Ȃ݂ɁA���C�V���L���̃Z���t�ɂ���u���l�v�Ƃ͍�Ɩ{�l�̂��ƂŁA�h�X�g�G�t�X�L�[�����Y�������A���Y���O�Ɍ��Y���ꂽ�̌����������Ƃ͂悭�m���Ă���B
�@���������C���g�D���E�t�F�X�g�D���I�ӎ��́u�j�ՓI�C���v�Ƃ������������邪�A�����`�ʂ���ؑ������Ղ�C���ŕ�����Ă���킯�ł͂Ȃ��B�ǂ��ɂ��������ɂ��j�ՓI�ȋC���̎x�z���܂˂����I���Ԃ̗�Ƃ��āA�l���x���ł́u���̖@�x�A���R�Ƃ̍��̊��A����_��ւ̒�������A���▃��ւ̒^�M�A�M�����u���ւ̔M���A����ޓ��ɔ��������A���R�̂Ȃ����\�ȎE�l�v�A�W�c���x���ł́u���y�̍��t�⍇���ɂ����鎩��ӎ��̉����A�����̏@���̏W�c�Ö��I�Ȍ��ʁA�f����ЊQ���̌Q�W�S���A�����ĂȂɂ����Ղ̐S���Ɗv����푈�̐S���v�i�ؑ��͋����Ă��Ȃ������R�u�����߁v�̏W�c�S���������Ɋ܂܂�邾�낤�j�������āA�j�Ղɂ͋P�������ʂ����łȂ����̑��ʂ����邱�Ƃɒ��ӂ𑣂��Ă���B
�@�Ƃ���ŁA�j�Ձ��J�[�j���@���̐��i�ɂ��āA�ےJ����]���Q�Ƃ��Ă����o�t�`���̃h�X�g�G�t�X�L�[�_�Ɏ��̂悤�Ȏw�E�����邱�Ƃ͗��ӂ��ׂ����낤�B
�@���͐��E����_�I�v�l���L���ɂ͂��炭�����Ƃ��āA���ꂪ���ꂽ���E��ΏۂƂ��A�ώ@�҂��ΏۂƂ̂������ɋ������Ƃ邱�Ƃ��ł��邱�Ƃ��������B�Ƃ��낪�j�ՂƂ́u���҂Ɗϋq�̋�ʂ��Ȃ��������v���Ƃ����B�u�ӏ܂�����̂ł��Ȃ����A�����Ɍ����ĉ�������̂ł����Ȃ��A����������̂ł���v�̂��Ƃ���A����͎ŋ��̖��̒ʂ��Ȃ������ɂق��Ȃ�Ȃ��B����͐��E����_�I�v�l�ɂƂ��Ă͋���ׂ����Ƃł͂Ȃ����B�����I�m�͂����ł܂����B
�@���ۂɁA���̍Ղ̗ւ̂Ȃ��Ɏ������Q�����Ă��Ȃ��Ă��A�������Ă��邾���ł��Ղ�C���Ɋ������A�ǂ��������ꂽ�C�����ɂȂ�Ƃ������Ƃ͂���B����͏㉉���ꂽ�ŋ����ςĂ��Ă��N���邱�Ƃł���B
�@�����A���������A�J�[�j���@���I���E���o�̑ɂɂ�����퐫�̈ӎ��i�ؑ��j�A���}�ȕ��G���i�ےJ�j�A����������A���C���ێ����邱�ƂɂƂ߂Ȃ���A�������̓J�[�j�o���̖@���̎x�z�ɏ]���Đ����邱�ƂɂȂ�킯�����A�u�j�Ղ͂˂Ɏ��̌����ɂ���Ďx�z����Ă�����v�̂ł���u�j�Ղɋ]���͕s���v�ł���i�ؑ��j�B�����������̑��ʂ������ɂ͂ǂ�������悢���B
�@���J�s�l�͕]�_�u��]���O�Y�̃A���S���[�v�̂Ȃ��Ŏ��̂悤�Ɍ����Ă����B�u����j�I�ȁu�����v�̗��_�Ƃ����́A������\�͂̕ݐ����w�E����B�������A�ߑ�̐����ɍ݂���̂��Վ���J�[�j�o���ɍ݂���̂Ɠ���ł���Ƃ��������Ƃ��w�E���邱�Ƃ͎��Y�ɗނ���B���́A���̐�ɂ���v�B
�@���̕��J�̖���N�A�u���Ƃ��u���̍m��v�A�u���̓��s�v�Ƃ��ăJ�[�j�o���I�ɂ����ꂽ���̂��K���t�@�V�Y���ɓ]������̂͂Ȃ����v�Ƃ����₢�ɑ��āA�c�O�Ȃ��獡�̎��ɂ́A���������Ȃ�̑e���Ȋ��z���q�ׂ�قǂ̏�������Ȃ��B�����A�A�h���m�́u�Љ�S�̂������Ă���Ƃ��ɐ����������Ƃ������̂͂��蓾�Ȃ��v�i�w�~�j�}�E�������A�x�j�Ƃ������t���v���o���������ł���B
�@
�y�R�����g�z
���b�̘_��
�@���c�L��
�@
�͂��߂�
�@�ےJ�ˈ�ɂ��Ă����A�P�O���ɐ��������Ƃ��A�����V���ɍ�Ƃ̒Ҍ��o�ɂ��Z���Ǔ��̃R�����g���ڂ��Ă����B
�@����ɂ��ƁA�ےJ�̍�i�́A�����Ƃ����E�Ƃ��������l������l���ɂ����Ƃ����_�ŁA���{�̏����Ƃ��Ă͉���I�Ȃ��̂������Ƃ����B�l�́A�ےJ�̍�i��S���ǂ��Ƃ��Ȃ��̂����A���̒Ҍ��̕]���͈�ۂɎc�����B�����Ƃ͊u�₵���l���ρE���l�ς̂悤�Ȃ��̂��A�����ɂ���Ǝv��������ł���B
�@�l����ƁA�l�͂���܂ł̂T�O�N�̐l���ŁA��E�ƌĂׂ�悤�Ȃ��̂ɂ������Ƃ��قƂ�ǂȂ��B���܂ŊےJ�̍�i�ɑS���S���������A���]�Ȃǂ̒Z�����͂�ǂ�ł��D�ӓI�Ȉ�ۂ������Ƃ��Ȃ��������Ƃ̈���́A�����ɂ���Ƃ��l������̂��B
�@����ł���Ɏv���o�����̂́A�Ҍ��Ɠ����̑啨��Ƃł��钆�㌒�����S���Ȃ�����(�������Ǝv����)�A����G���ɍڂ������k��ō�Ƃ̉�������A����̈��钷��(�������w�n�̉ʂā@����̎��x�������Ǝv��)�ɂ��Ď��̂悤�Ȃ��Ƃ������Ă������Ƃł���B
�@���̏����ɂ́A��l���̓y���d���̓����Łu��������v�ƌĂ��l�����o�ꂷ�邪�A����̍�i�ɁA���̂悤�ɐE�Ƃ����������ʂ̎s��̐l�����o�ꂷ��̂́A�����ւ�Ӌ`�[�����Ƃ��B
�@����������́A�����������Ƃ������Ă����B
�@�Ҍ��o�Ɖ�����́A�Ƃ��ɂX�O�N��ȍ~�ɋr���𗁂т���Ƃ����A���̓�l����y�̑��Ƃ̎d���ɂ��āA��������A�u�����Ƃ����E�Ɓv���������A�u���ʂ̐l�v����l���ɂ�����o�ꂳ�����肵�����Ƃɒ��ڂ��A������̎^���Ă���B
�@�܂�A�s���Љ�I�ȁu���ʁv�Ƃ������ƁA��E�����������ʂ̐l�̕�炵�⊴�o�Ƃ������̂ɁA���ꂾ�����l�����o�����悤�ɂȂ����Ƃ������Ƃ��낤���A����͗���Ԃ��A���������u���ʁv�̐����Ƃ������̂��A�����̎Љ�ɂ����Ă͂��͂�����ɂ����Ȃ��Ă��邱�Ƃ��������̂Ȃ̂�������Ȃ��B�{���ɂ���ӂꂽ���̂Ȃ�A�l�͂Ƃ肽�ĂĂ���ɊS������̎^������͂��Ȃ��ł��낤�B
�@���ۖl�́A�قƂ�Lj�x���u�����Ƃ����E�Ɓv���������ɗ������A�l��艺�̐���̐l�����̑����́A���������Ƃ���E�����ĂȂ��l���}���ɑ������B���������Ӗ��ł́u���ʁv�̓���Ƃ������̂��A�����ꐬ�����ɂ����Љ�ɂȂ����B���ꂪ�X�O�N��ȍ~�̑傫�ȕω����낤�B���������̂��Ƃ��l����ƁA���������ω��̗\���́A�����肩�Ȃ�O�̎����A���ԓI�ɂ͍D�i�C�ƌ����Ă��������炠�����悤�ȋC������B
�@�����Ƃ����̘b�́A���Ƃ��ΐ��ʂł����Βj���ɂ̂ݓ��Ă͂܂邱�Ƃł����āA�����̏ꍇ�ɂ́A���X����������E�̂悤�Ȃ��̂ɏA���@��͌����Ă����킯�����B
�@�Ƃ�����A�ےJ���߂���L�₳��̘_�́A���������u����v�̈Ӌ`�Ɗ�@�ƂɁA�[���ւ����̂��Ǝv����̂ł���B
�@
���E����_�̌��E�ɂ���
�@���āA�L��_���ł́A���b�����߂���ےJ�E�z�K�̘_�����A�����̐��E�I�Ȓ����������w�u�����͎��ɂ��̂܂܉����ł��肤��Ƃ����A�V�����Ӗ��ł́u���E����v�_�v(�R�萳�a)�x�̕����ɂ�����̂Ƒ������A��������A���̐��E����_�̌��E�Ɖ\���Ƃ��l������Ă���B
�@�܂����̌��E�ɂ��ẮA���������Ȃ����́A�����g�ɂ͈Ӗ��Â����Ȃ����̂ł���͂��̐��̑̌����A���������L�@�I�Ȓ����������������I���E�ɂȂ��炦�đ����邱�Ƃ��痈�镾�Q���q�ׂ���B�w�����Ґ���ϗ��I�Ȗ₢��I�グ�ɂ��āA���̈Ӗ������邱�Ƃ��ł���x�̂��A���E����_�̗��_�ł��茇�_�ł�����A�Ƃ������Ƃ��B
�@�����ɂ͎��ɂ͂��̈Ӗ��𗹉����邱�Ƃ��o���Ȃ��悤�ȏo�����A�s���̑��l�̎��Ƃ��������Ƃ��A���E����_�ł͉��炩�̏ے��I�ȈӖ���t�^����ė����\�Ȏ��ہA�ނ��낻�̂悤�ɗ�������ׂ������̂悤�ɍl������B
�@���ӂ��ׂ��Ȃ̂́A���������̂悤�Ɍ���ė������悤�Ƃ���A���̐��E����_�I�Ȕ��z�Ƃ������̂��A����ɏo�����̖\�͐�����ꎞ�I�ɐ����҂�삷��Ƃ��������́A�܂�͖\�͐��������ɂ������Ă������߂̑��u�ł͂Ȃ��A���ꎩ�̂��A���҂��n��o���傫�ȕ���̘g�g�݂���r�������悤�Ȑl�����ɂƂ��Ė\�͓I�ȗ}���Ƃ��ē������̂ɂ��Ȃ肤��A�Ƃ������Ƃ��낤�B
�@���ہA���̘g�g�݂̒��ł́A�S�̗̂��v�⒁���̈ێ��̂��߂ɒN�����]���ɂȂ�Ƃ������Ƃ��A�e�ՂɁu�d���̂Ȃ����Ɓv�Ƃ���Ă��܂����ƂɂȂ肩�˂Ȃ��B
�@���E����_�I�Ȏv�l�̓�_�́A�����ɂ���ƍl������킯�ł���B
�@���ɂƂ��Ď��̐��́A�������ʂ܂Ŋ������Ȃ����̂ł���͂��Ȃ̂ɁA���ꂪ�N���ɂ���ĈӖ��Â����邱�ƂŊ����������̂̂悤�Ɍ��Ȃ���A�����炱�̐��̌ŗL�̏d�����G�肪�D���Ă��܂��B
�@�Ӗ��Â����Ȃ����̗]���������̒��ɉ�����Ă��܂����ƂŁA���̐����ŗL�ł͂Ȃ����̂ɂ���ւ��Ă��܂����Ƃ��邩�̂悤�ȁA���̐��E����_�̕��̋@�\�́A�\����`�I�Ȏv�l�ɂ���ꂪ�����鑧�ꂵ���}���I�Ȋ��o�ɂ��ʂ�����̂��Ǝv���̂����A���������}���ւ̒�R�̈ӎu��\�������D�ꂽ���̎v�z�̂ЂƂ́A�w�S�̐��Ɩ����x�ɂ����郌���B�i�X�̂��ꂾ�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���B
�@���̂悤�ɏ��������B�i�X������������̂́A�u��l�̓I�v�ȁu�����v����c�E�ɐ藎�Ƃ���Ă��܂��悤�ȁA����I�ȑ��҂Ƃ̊ւ��̌o���̏d���ł���A���̌���Ε���ɂƂ��Ă̏�]�E���Ă��܂����Ƃ���傫�Ȗ\�͂ɑ����R�̐��_�������̂��Ǝv���B
�@����́A���҂ɑ���ϗ����̖����A�����܂œ���ɂ�����W������o�����čl���悤�Ƃ���p�����Ƃ����Ă����B
�@�����āA�����B�i�X�ɂƂ��āA���̌ŗL����A����I�ȊW�̏d�v�����A�����܂�(���z�I�Ƃ����)�u���ҁv�Ɋւ����̂������Ƃ������Ƃ́A�Ƃ�킯�厖�ȓ_���낤�B
�@�L��_���ɖ߂�ƁA�����Ŏw�E����Ă��鐢�E����_�̌��E�́A���ꂪ(���炭�͑��҂Ɋւ��)���̌o���̏d���A�Ӗ��Â��ė������邱�Ƃ��s�\�ȕ������A�����������݂��Ȃ����̂悤�Ɉ����Ă��܂����˂Ȃ��_�ɂ���A�ƍl������B�����āA�u���݂��Ȃ����̂悤�Ɂv����ꂽ���̂́A�����B�i�X�ɂ�����悤�ɂ��ꂪ���҂Ƃ̊W�ɒ�ʂ���čl������̂łȂ���A�s����̂Ȃ����ꂵ���Ƃ��ĎЉ�̒�ɓb��ł����͂��ł���B
�@�����B�i�X�͂����ŁA�t�@�V�Y���̔����̖����A�ނ�����ݓI�ɍl�@���Ă����̂�������Ȃ��B
�@
���E����_�̉\���ɂ��ć@
�@���ɁA�L��_������������A���E����_�́u�\���v�Ɋւ��čl���Ă݂悤�B
�@�����ōl�����Ă���̂͂܂��ɁA�����u���j�v�����肱�ڂ��ꂽ��A�藎�Ƃ���Ă��܂��悤�Ȑ��̗]����A���Ȃ�ʂ��̐��E����_���~�o������\�����Ƃ����悤�B
�@�����ł́A���E����_���A����ꂪ�������ɂ����Đ����Ă���u���G�ȏ����v(�ےJ)�A�����́u��������v�̌��������d�w���Ƃ���������l���ɓ���邱�ƂŁA����Љ�ɂ����镨��̍Đ_�b��(�܂蕨��ɂ��A�l�X�̐��̗}���E���)����������\�����l�����Ă���̂ł���B
�@���́u�i�D�̈����v�A�u�����܂����v��������Ȃ����X�ȑԓx�������A����ɂ����镨��ƍĐ_�b���̖\�͂ɑR����A��̗L�͂ȑԓx�ł͂Ȃ����B
�@�����������Ƃ��A���̂�����ł͏q�ׂ��Ă���̂��Ǝv���B
�@����Љ������Ȗ\�͂́A��ʓI�ɐl�Ԃ̐�������@�ɒǂ������̂ł��邪�A���̏d�v�ȓ����̈�́A���́u�����܂����v��u���G�ȏ����v�Ƃ������̂�۔F���A�������Ă��܂����Ƃ���_�ɂ��邾�낤�B��������������������A�x�z��j��ɂ͍D�s��������ł���B
�@�u���G�ȏ����v���d������ԓx�͓����ɁA�����B�i�X�Ɍ�����悤�ȁA���҂z�I�Ȃ��̂Ƃ��Đݒ肷��R�̂�������A����̍Đ_�b���Ɋ�^���Ă��܂����ƁA�������邱�Ƃŋߑ�I�Ȗ\�͂̂����̏o������Ă��܂����Ƃւ̌����ł�����̂�������Ȃ��B
�@�Ƃ������A�l�Ԃ̐����Љ�I�ȁu�����v�̑��̂悤�Ȃ��̂Ƃ��đ����鐢�E����_�́A���ꂪ���������u���G�ȏ����v�ւ̂܂Ȃ����ƁA�u����Ɗϋq�v�Ƃ̋����̊��o(�ϗ���)�Ƃ�����Ȃ�����ŁA����Љ�̎x�z�I�Ȗ\�͂ɑ����R�̋@�\�����B
�@�L��_���̂��̎w�E�́A�����ւ��ɕx�ނ��̂��Ǝv���B
�@��������̎Љ�ł́A���������e�́u�����v�Ƃ������̂ɍU�����������邱�ƂŁA�����̐������̂悤�ȏd�w�I�ȋ�ԂƂ��ĔF�m����g�g�ݎ��̂��������ɂ����Ȃ��Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃ��A�l���`���ɏ��������Ƃł���A�܂��L�₳����A����ɑ���������Ŏ�������Ă���Ƃ���ł���Ǝv���B
�@�L��_���ɂ����Č��o����Ă��鐢�E����_�̉\���́A�����B�i�X�̂���Ƃ͈�������������̂Ƃ��āA�����̖\�͂ɒ�R����̂Ɉ��̗L���������Ǝv����̂����A���͂₻�̘g�g�𑽂݂��̐l�����������苤�L�����肷�邱�Ƃ�����ȂƂ���܂ŁA�����̖\�͂̐N�U�͐i��ł���B
�@������������ł͂Ȃ����Ǝv����̂��B
�@�����A�������ߍ��ޑO�ɁA���̒�R�̉\���̓Ǝ��ȓ����ɂ��āA�����ƍl���Ă݂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B
�@
���E����_�̉\���ɂ��ćA
�u��������v�̕��G�ȏd�w�ɂ��Ă̍L��_���̋L�q��ǂ�ł���(���������A�����B�i�X���܂��u��v����葱�����킯����)�A�l���z�N�����̂͂�͂�A�G�b�Z�C�u�ʂƃy���\�i�v���͂��߂Ƃ���a�ғN�Y�̐�O�̕��͂̂��Ƃł���B
�@�����ł́A�u�ʁv�Ƃ��Ă̊�ʂ̗D�ʂƂ������Ƃ�����Ă��邪�A���̊�ʂƂ́A�Ƃ��Ă̐l�ԑ��݂ł͂Ȃ��A�l�Ԃ̎Љ�I�ȍ݂�l�̂��Ƃ��ƍl���Ă������낤�B�Љ�I�ɋK�肳�ꂽ���܂��܂ȁu�������ʁv�̑��̂悤�Ȃ��̂Ƃ��Đl�Ԃ͐����Ă���̂ł���A���������l�Ԃ̎Љ�I�Ȑ��Ƃ������̂́A���x�⎑�{���K�肷�鑶�݂̎d���ɑ��Đ�s������肩�A�����I�E���̓I�ȑ��݂ɔ䂵�Ă��������I�ł���B
�@�a�҂̋ߑ�(����`)�ᔻ�̎v�z�̈�[���A�����ɂ悭������Ă���Ǝv���B����́A����Ȃ�l�Ԓ��S��`�Ƃ��������̂ł͂Ȃ��A�����x�z��Ǘ��̂��߂ɓs���̂����P�ʂɏk�����ĂƂ炦�悤�Ƃ���͂ւ́A���R��ڎw�������̂��ƍl������B
�@����ł��A���̂悤�Șa�҂̎v�z���A�����ɂ͓��{�̃t�@�V�Y������R����`���ɑ��āA����̒�R�������Ȃ������ł͂Ȃ����A�Ƃ������_�͓��R���邾�낤���A���������ᔻ�┽�Ȃ͏�ɂȂ���Ȃ���Ȃ�Ȃ����̂��낤�B�Ăу����B�i�X�̎v�z�Ɣ�r����Ȃ�A����������̌o���ɒ�ʂ��ċߑ�I�Ș_���ւ̑R��ڎw�����̂ł���Ȃ���A�a�҂̎v�z�͂��̍��Ƃ⍑����`�ւ̔ᔻ�̌��@�ɂ����āA���������āu���ҁv�ɂ��Ă̗ϗ��I�Ȋ��o�̎コ�Ƃ����Ӗ��ŁA����I�Ȍ��_�������̂������Ƃ������Ƃ͊m���ł���(����w�S�̐��Ɩ����x�̈��p�����̑O����ēǂ��āA�����B�i�X�̋ߑ㍑�Ǝ�`�ւ̔ᔻ���A�C�X���G���̂�������˒��Ɏ��߂Ă������ƂɁA���߂ċC�Â���)�B
�@�����l�͓����ɁA�a�҂��t�@�V�Y�������Ă������{�̎Љ�̓����ɁA�ǂ̂悤�Ȑ[���őΛ����Ă����̂��Ƃ������Ƃ��A���݂�������́A�悭�l����ׂ��ł͂Ȃ����Ǝv���B
�@����͂܂������A�L��_���Ō��y���ꂽ�u���G�ȏ����v�ւ̂܂Ȃ����Ƃ������ƂɊւ�邪�A�ߑ㉻�̖\�͂ɔ�����Ă��錻���̎Љ�ɂ����āA�l���ǂ̂悤�ȉ�H��ʂ��āu�t�@�V�Y���v�ƌĂ��̂Ȃ��ɂ݂�����g�𓊂��A�ۂݍ��܂�Ă����̂����A�a�҂͔ނȂ�ɋÎ����A�������������ւ̒�R�����݂��̂ł͂Ȃ����A�Ƃ������Ƃł���B
������
�@���̂��Ƃɂ��āA�����l����i�߂�B
�@�╔�b�́A�a�҂����A���y�̑O�g�ł���u�����ڗ��v�ɐ[���S�������Ƃɒ��ڂ��A���ꂪ�a�҂̐����I�Ȏv�z�̉\���ɒʂ�����̂ł���Ƃ��āA�h���I�ȋc�_��W�J���Ă���B
�@�╔�͂����ɁA�a�҂̎v�z���A�ߑ��`�I�Ȏv�l�̌��E���z���o�āA�u�\�z�͂ɂ�鋤���̉�H��A�u���̉F���I�����v�ɒB����\�����_�Ԍ��Ȃ���A�a�҂͌��ǂ͐l�Ԃ́u�����v���S�Ă����߂�̂��Ƃ����ߑ��`�E�l�Ԓ��S��`�̘g���ɂƂǂ܂���(����͏�L�́A�u��������v�̓��̂ɑ���D�ʂɒʂ��邱�Ƃ���)���̂ɁA���̉�H���݂���������Ă��܂����̂��Ɣᔻ����̂ł���B
�@�����l�͋t�ɁA�a�҂������܂Ől�Ԃ́u�����v�̗D�ʐ��Ƃ����v�f��������Ȃ������Ƃ���ɁA�ނ̎v�z�̏d�v�ȃ|�C���g��������̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂��B
�@�l�Ԃ̐��E���A�����̂��ɑ�����l�`�ŋ��̂悤�Ɍ��鎋���Ƃ����̂́A���̔w��Ɏ�̂́u���v���A���̎�����I�悳������̂��Ǝv���B���炭�╔�������悤�ɁA�a�҂͗c��������A�����������̂ɑ���s�����o�������Ă����̂ł���A���ꂪ�ނ̋ߑ�ᔻ�̍���ɂ�����̂̂ЂƂȂ̂��낤�B
�@�����a�҂̎v�z(�ϗ��w)�̐^�̈Ӌ`�́A������������������������̂ɍR�����Ƃ������ɉۂ������Ƃɂ���̂ł͂Ȃ����B�u���������������݂����������́v�̓����́A�����̐����̕����̒��ɒu�����A�t�@�V�Y���̎x�z���Ӗ����邾�낤���A������܂��ߑ�Ƃ����͂̈�̌����ɑ��Ȃ�Ȃ����Ƃ��A�a�҂͒m���Ă����͂��ł���B
�@�╔�́A�a�҂��u�l�ԁv�́u�����v�ɍŏI�I�ȗD�ʐ���F�߂���A���邢�͎Ⴂ�����ɂ͎G��I�E�R�X���|���^���I�ȓ��{�����_����l���Ă��Ȃ��猋�ǂ͍��Ǝ�`�I�E������`�I�Ȏv�l�̘g����o�邱�Ƃ��Ȃ��������Ƃ�ᔻ����B
�@�����A�a�҂ɂ����āu�l�ԁv�Ƃ��u�����v�Ƃ����T�O�́A�����̊T�O�̑I�����̂͌��ł������Ƃ��Ă��A�u�l�ԁv���y��������A�������R�X���|���^���I�Ȉʒu�ɗ�������ƈ��Ղɍl�����肷��X���ւ̒�R�Ƃ����Ӗ��ł́A�������������̂��Ǝv���B���̒�R�́A���������l�Ԍy����A����ʂ̃R�X���|���^���I�Ȏv�z���A��O�Љ�ɂ�����t�@�V�Y���̎x�z�Ɩ��ڂɊ֘A�������̂ł���Ƃ��������Ɋւ��Ă����́A���m�ɕW�I������߂Ă����Ǝv����̂ł���B
������
�@�a�҂̎v�z���A�����Ă܂�(���Ԃ�)�ےJ�̕��͂������Ă���̂́A����I�ȊW�̕��G���ւ̂܂Ȃ��������킸�A��������o�����Đ��E�̌����ɑ���A�Ƃ����ԓx���낤�B
�@�ߑ�Ƃ����\�͂́A�܂��ɂ��������ԓx��s�\�ɂ��悤�Ƃ���B�t�@�V�Y���́A��������A������ň��̌����̈�ł���Ǝv����B
�@�����B�i�X���܂������\�͂ɁA�����������ł́u���ҁv�̒��z���Ƃ������Ƃɂ��͓_��u���Ȃ���A�Λ����Ă����͂��ł���B
�@�a�҂�ےJ�̂悤�Ȓ�R�̑ԓx�ɁA(�����炭)�����B�i�X�̂���Ƃ͈قȂ����Ӌ`��F�߂Ȃ�����A���������ԓx�̕ێ����̂��̂�������@�ɕm���Ă���̂��Ƃ�����A���̊�@�̍����͉\���낤���H
�@�����������A�����������̊�@(���E)�́A�͂��߂���a�҂�ےJ�̎v�z�̂Ȃ��ɑg�ݍ��܂�Ă������̂��Ƃ��l������B����́A�ނ�̎v�z�ɂ����ẮA����ɂ����Čo������鑼�҂̊T�O���A���ꂪ�����B�i�X�ɂ�����悤�Ȓ��z����ттĂ��Ȃ����Ƃ͗ǂ��Ƃ���Ƃ��Ă��A���܂�ɂ����������⋤���̂̍����������Ă��܂��Ă���悤�Ɏv����A�Ƃ������Ƃł���B
�@�����炭�d�v�Ȃ��Ƃ́A�a�҂�ےJ���Ƃ��������A����ꎩ�g���A���́u�����܂����v��u���G���v�ɂ���Ď��ׂ����̋�ԁA�W�̎��̂悤�Ȃ��̂��A���Ƃ�x�ɂ���Ĉ����ꂽ������\���Ɉ�E���Ē͂ݎ�邱�Ƃ��o���Ȃ������A�Ƃ����Ƃ���ɂ���B
�@�ǂ�Ȓ����⋤���̂��A�K���r������鑶�݂ݏo���̂ł���A�����̓���́A���ۂɂ͂��������r���̍s�ׂƕs���Ɍ`������Ă���B�r�����ꂽ�҂���������ɂ����ĕs���ł���̂́A���̂��Ƃɂ���Ă����̐��̊O������߂��A����Ƃ������̂��\������Ă��邩��ł���B�����A����ꂪ�z�����鐶�̏����́u���G�v���́A���܂����̍��{�I�ȍ\���̗v�f�ɓ͂��Ă͂��Ȃ��B�u���G�ȏ����v�ւ̂܂Ȃ������������邽�߂̊�Ղ́A�ߑ�̖\�͂ɂ���ĉ�̂������̂ł͂Ȃ��A���X���ꎩ�̋ߑ�(����)��`�I�Ȕr���̘_���ɂ��܂�ɂ����v���Ă����̂ł͂Ȃ����A�Ǝv���̂ł���B
�@�����ɁA�u��������v�̏d�w�Ƃ��Đ��𑨂��邱�Ƃɂ���āA�ߑ�I�Ȗ\�͂ɑR���悤�Ƃ���v�z�́A���{�I�ȍ��܂̗��R������B
�@����́A����ꂪ�Љ�ɂ����鎩�O�́u�����v�Ƃ������̂��A�܂��\���ɍ��グ���Ă��Ȃ��A�Ƃ������Ƃł����낤�B���Ƃ⎑�{�Ƃ������ߑ�I�ȑ��u�ɂ��̂łȂ��A���O�́u�����v�̑��Ƃ��āA����ꂪ���݂̊W����a���グ��ꂽ�Ƃ��A����͉��ƕs���Ƃ̋��E�����������̗͂ŕs�f�Ɉ��������悤�ȁA���҂ɑ��ĊJ���ꂽ�Љ�̓������Ӗ����Ă���͂��ł���B
�@����ꂪ�݂�����́u�l�i�v�𑊌ݓI�Ɍ`������ׂ����҂́A���킩��u�₵�����z�I�ȏꏊ�Ɍ��o�����̂ł��A�����̂̕ǂ������(�\��)�̓�(����ъO)�ɒu����Ă���̂ł��Ȃ��A����̂Ȃ��ŕs���Ȃ��̂ɂ���Ă��鋫�E�A�O�����ɂ������݂��Ă���B
�@�ނ���a�҂�ےJ�̎v�z�I�c�݂́A�����������O�̊W����n�o����\�����A���Ƃ⎑�{�ɂ��ߑ㉻�̖\�͂̂��܂��܂Ȍ`�ԂɍR���āA���́u�����܂����v��u���G���v�̂Ȃ��Ŏ�J��悤�Ƃ���x�N�g���������̂Ƃ��āA���������ׂ��Ȃ̂ł͂Ȃ����낤���B
�@�Ȃ�Ζl��ɂ��܋��߂��Ă���̂́A������������̌o�����͂�ށu�����܂����v��u���G���v���d�����鐸�_(�u�ϗ��w�v)���A�����̂⍑����`�̎�����E���A�������ێ����邽�߂̘_���̊O���ւƁA�����L���Ă������Ƃł͂Ȃ����낤���H
�@
���b�̘_��
�@��O�Ɋ��������w�ҁA���J�s�|(�|�F)�̒���w�G����ڗ��j�x(���m��)�ɂ́A�a�҂����D�����]�ˏ����̏�ڗ��̑�{�̍[�T��l���L�x�Ɍf�ڂ���Ă��邪�A���̂ЂƂɁA������𒆐S�ɗ��������u�@�I(���炭��)�l�`�h�v�̑�\�I�Ȑl�C��Ƃ����w�M�c�ȁx������B
�@���Ȃ݂ɁA���́u�@�I�l�`�h�v�́A�����N�ԍ����猻���A��d�|���̃J���N����p���āA�_���̗쌱�k��d���ω��̕����ɍڂ��Ċ��т��������ł���B���ږx�̐��͂𗘗p�����d�|���̎���Ȃǂ��������Ƃ�������A�����Ƃ��Ă͔j�i�̃G���^�[�e�C�����g�������ł��낤�B
�@�w�M�c�ȁx�͂������A���{�����̏o���ɂ܂��A�����銋�̗t�`�����ނɂ������̂ł���B���J�s�|�ɂ��A���̗t�`�������{�����̏o���Ɍ��т������̂Ƃ��čL���m����悤�ɂȂ������������́A���̏�ڗ��̏㉉�̐����ɂ����̂ł��낤�Ƃ������̃q�b�g�삾�����悤�ł���B
�@���̗t�`���ɂ��ẮA�L�₳�ȑO�A�������̃u���O�ɂ����ւ�D�ꂽ�G���g���[�������Ă���ꂽ�̂ŁA�����Ȍ����l�ɂȂ邪�A�ڂ����͂�������Q�Ƃ��Ă��炢�����B
�@���̃G���g���[�̍Ō�ɂ́A�_���̂Ȃ��ɊےJ�ˈ�̘_������Ƃ��ēo�ꂵ���z�K�t�Y�ɂ�銋�̗t�`���ւ̌��y���Љ��Ă��邱�Ƃ��A�l�ɂ͍D�s���ł���B
�@�l���g�͂��̓`���ɂ��āA��͂蕶�y���D�ƂƂ��Ēm��ꂽ�J�菁��Y�́w�g�슋�x��A���㌒���̊���̒Z�҂�G�b�Z�C��ʂ��Đe����ł����̂������B
�@���āA���́w�M�c�ȁx�����A�Ō�ɋ��̈���̋��ŁA�����̕��Ƃ������{�ۖ����A�����̐��G�b�������̎�̎҂ɂ���Ĕ��ɂ���ĎE�Q�����ƁA���b���W�܂��Ă��āA���[�̊e���������������Ă��܂��B�ォ�炻���ɂ���Ă��������́A��������ċ����A���̏�ɍՒd������ċF����s���ƁA�����̒��b�����������Ă�����⑫�Ȃǂ�����ďW�܂�A���̂����̏�Ԃɖ߂��āA���ɂ͑h������Ɏ���̂ł���B
�@�a�҂́u�ʂƃy���\�i�v�̂Ȃ��ŁA�w��l�߂�ꂽ��ʂ͎��R�Ɏ��̂�����͂������Ă���x�Ə����Ă������A�����ł͂������Ď��̂��A��̂̐����̉��\�ɂ��Ă���B�������A�����͒��b�Ƃ����A���ȂłȂ��ǂ��납�l��(�l�i)�ł����Ȃ��A�����I�ȑ��݂ɂ���Ă����炳��Ă���̂ł���B����̂Ȃ��ŁA�����̕ꂪ��ςƂ���Ă������Ƃ��v���o����悤�B
�@�a�҂�������悤�ɁA�l�i���`��������̂��A��̂Ƃ����I�Ȃ��̂ɊҌ�����Ȃ��Ƃ��������͏d�v���Ƃ��Ă��A����͊����̋����̘̂g���ɂ����Ă����`���������̂ł͂Ȃ��B�ނ���l�Ԃ̐����A�t�@�V�Y�����܂߂��ߑ㉻�̖\�͂̂��܂��܂Ȍ`�Ԃɉ������Ȃ��悤�ȁA�^�̗͂�L�������̂Ƃ��đh�����邽�߂ɂ́A�����⋤���̂���r�����ꂽ���̂����A�����ɒǂ�����ĕs���Ƃ���Ă�����̂����Ƃ��琂������A���{�I�Ȍ_�@�ƂȂ�B���̂��Ƃ�ʂ��āA����ꎩ�g���A���̋�����ꂽ�����̊O���ŁA�t�@�V�Y���Ƃ����ň��̊��v������g�����A�ق���̂́u����v���\�z���錠�\��͂ݎ�邱�Ƃ������̗v�Ȃ̂ł���B
�@�w�M�c�ȁx�ɓo�ꂷ�钹�b�����́A�������������̐��̒D����\�ɂ���_�����A��V�̂悤�ɖ������Ă��邩�Ɏv����B
�@
�@
�y�R�����g�Q�z
���c�L�����ւ́u���A�v
�L����M
�@
�@���c����A���̑ʕ��ɃR�����g�ƌ������^�ɘ_�l�ƌ����ׂ��u���b�̘_���v�������������܂��āA�܂��Ƃɂ��肪�Ƃ��������܂����B
�@�����A���c����͂ǂ����������Ԃ��Ă�����悤�ł��B�Ƃ����܂��̂��A�������E����_���ĕ]�����悤�Ƃ��铮�@���A�u����Љ�̎x�z�I�Ȗ\�͂ɑ����R�v�����݂悤�Ƃ��Ă��邩�̂悤�Ɍ����ĂĂ��������Ă��邩��ł��B���������Ȃ����Ƃł��A�\�O���Ƃ����̂ɉ��Òk�Ƃ͂Ƃn���҂戢����Ə��邩�Ǝv���܂����̂ɁA��R�̉\���Ƃ͂��ꂵ�����Ƃ��������Ⴂ�܂��B
�@�����O��̎R�����j�_�ƍ���̒��b���_�Ŏ��݂����Ƃ́A�u�x�z�I�Ȗ\�͂ɑ����R�v�ȂǂƂ����A����ȑ傻�ꂽ���̂ł͂���܂���B��R�Ƃ͂قlj��������l�I�ԓx�ł��B�������̂��ƁA���C�y�Ȍ����l�I�ԓx�����ߍ���ł���ꂽ����̒m�Ɋw�ђ����Ă݂悤���Ǝv�����̂ɂ����܂���B���E����Ƃ����Ƒ傰���ł��A���߂Đ��E������̌����l���炢�ł͂��肽���A�Ƃ������Ƃł��B
�@�Ƃ���ŁA���̌��e�������グ�ĉ��c���ɉ��Ă��Ԏ���҂������A���c�ȎO�w�S�̎�`�̎���o���x�i�݂������[�j�Ƃ����{��ǂ݂܂����B80�N�㒆������90�N�㏉�߂ɂ����Ă̓��c���̕��͂��W�߂��{�ł��B1994�N10���ɏ����ꂽ�u���Ƃ����v�ŏ��u�ߌ��v�Ƃ������t���g���Ă��āA���̌�ɂ��Ắi���j������܂��B������ƒ����ł����A�ۂ��ƈ����܂��B
�@���c�̌����u���ߐ��v�Ƃ��u�����v�Ƃ��u�Љ�l�ފw�v�Ƃ�����̓I�ɉ����w���Ă���̂��͂悭�킩��Ȃ��̂ł����A�S�̂Ƃ��ẮA�������b���_�����ނɂ��Ă��ǂ���ǂ�Ɍ������Ƃ������Ƃ������Ɍ����\����Ă���悤�Ɋ����āA�����̕s���Ɠǂނׂ��{�������ɑ����������炽�߂Ď��o���܂����B
�@�������A�Ђ邪�����āA�u���ߌ����v�́u���ۊw�I�����ƋL�q�v�̏W�ς���n�߂�Ƃ��āA�͂����Ă���Ŏ���̑��x�ɒǂ����̂��A�Ǝv��Ȃ��ł�����܂���B�e���|�̑����ŋ��̓W�J�ɒǂ����Ă����Ȃ��Ƃ���A���E������̌����l�Ƃ��Ă͗R�X�������Ԃł��B�Ȃ��Ȃ�A���㉉���͌����l���ϋq�̒n�ʂɈ��Z�����Ă��ꂸ�A�����l��������͕���Ɋ������܂�Ă��܂�����ł��B�փ����̍���̂Ƃ��ɁA�ߗׂ̏Z���͕ٓ����Q�ō�����������Ă��������ł����A����ł͂����͂����Ȃ��B�]���̌��Ɍ����O���M�������Ƃ��Ɋϋq�Ȃ͕���ɁA����͌���i���j�ɑ��ς�肷��B���̂��Ƃɑ��鎄�̋����ɁA���c����́u��R�v�Ƃ����X�������O��t���Ă����������̂ł��傤�i������_���͓I�ȁu��R�v�ł��傤���H�j�B
�@�����Ƃ����c����̘_�l���悭�ǂ߂A����ł́i���E����_�I�v�l���O��Ƃ���悤�ȁj�u�����̐������̂悤�ȏd�w�I�ȋ�ԂƂ��ĔF�m����g�g���̂��������ɂ����Ȃ��Ă���v�A�u���͂₻�̘g�g�𑽂݂��̐l�����������苤�L�����肷�邱�Ƃ�����ȂƂ���܂ŁA�����̖\�͂̐N�U�͐i��ł���v�A�܂�L��̖ό��͎���x��ł�����I�ł���ƌ����Ă���킯�Łu�܂������u�S�ے�v�̘_�|�v�ł��B�Ƃ������Ƃ́A�L��̂�����ׂ�Ɂu��R�̉\���v�����悤�Ƃ���̂́A���c����̐a�m�I�ȃ��[���A����o���u���A�v�ɂ����Ȃ��̂�������܂���B
�@�������A���̉��c��������_�l�̍Ō�ɂ͂����g�̃r�W��������ڗ��w�M�c�ȁx�̈��ʁA��������S�Ǝ����A���ƍĐ��̕���ɑ����Č���Ă��܂��̂ŁA���Ƃ��Ă͊��}�̈��A��\���グ��ׂ��ł��傤�B
�@�悤�����A���E����ցB
�@�]�k�ł����A�w�M�c�ȁx�ƌ����Β��b���ł����y����Ă��܂��B���i�ځA�_����͒����ŁA�启�R�Ǐ��ƕ��㑾�v�����̒T�荇���������ʂł��B�u�����l���㑾�v���B�̎v�ւΐM�c�̌ρB�����͂��Ĉꌣ�ނ��ӂ��B�T�A�R�Ǔa�B�v���Ԃ肾���u�v�B�i����͂���ɂāj�B
�@
Web�]�_���u�R�[���v18���i2012.12.15�j
������v�z���čl���遄��T��F����Əj�ՁA�܂��͐��E����_�I�v�l�̂��߂Ɂi�L����M�j
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU�@2012 All Rights Reserved.
|
| �\���i�ڎ��j�� |