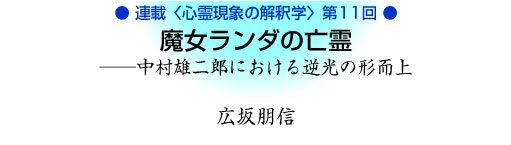|
|
|
Web昡榑帍乽僐乕儔乿 |
|
仭憂姧偺帿 仭杮帍偺昞巻乮栚師乯傊 仭杮帍偺僶僢僋僫儞僶乕 仭撉幰偺暸乛偛堄尒丒姶憐 仭搳峞婯掕 仭娭學幰偺Web僒僀僩 仭僾儔僀僶僔乕億儕僔乕 |
|
亙杮帍偺娭楢儁乕僕亜 |
|
仭乽僇儖僠儍乕丒儗償儏乕乿偺僶僢僋僫儞僶乕 仭昡榑巻乽俴倎 Vue乿偺憤栚師 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
|
丂慜夞丄屄恖偺堄幆傪婎弨偵夦堎傪彇弎偡傞嵺偺擄揰傪巜揈偟偨偑丄偦傟偱偼帇揰傪曄偊偰丄怱楈尰徾傪嫄帇揑偵偲傜偊傞応崌偵偼偳偆偄偆栤戣偑峫偊傜傟傞偺偐丅偙偺僥乕儅偵偮偄偰偼丄偐偮偰偙偺楢嵹乽怱楈尰徾偺夝庍妛乿偱傕丄墌椆梔夦妛偲桍揷柉懎妛傪戣嵽偵偟偨戞俈夞乽梔夦妛偺徴撍乿丄崄愳夒怣亀峕屗偺梔夦妚柦亁傪戣嵽偵偟偨戞俉夞乽乽晄婥枴側傕偺乿偺岦偙偆懁傊乿偱傕庢傝忋偘偨偙偲側偺偱寍偑側偄偲尵傢傟傟偽偦傟傑偱偩偑丄暿偺戣嵽偵傛偭偰嵞搙峫偊偰傒傞偙偲偱怴偨側敪尒偑偁傞偐傕偟傟側偄偲偄偆扺偄婜懸傪書偄偰偄傞丅
丂崱擭偺壞乮2017擭俉寧乯偵朣偔側偭偨揘妛幰丒拞懞梇擇榊巵偼丄恖椶妛幰丒柉懎妛幰偺彫徏榓旻巵偲偺嫟挊亀巰丂21悽婭傊偺僉乕儚乕僪亁乮娾攇彂揦丄1999乯偱朣楈傗墔楈偵尵媦偟偰偄傞丅巹偼朿戝側拞懞巵偺挊嶌傪偮傇偝偵撉傫偩傢偗偱偼側偄偑丄偍偦傜偔亀巰亁偼丄拞懞巵偑儕傾儖側朣楈偵尵媦偟偰偄傞丄偐側傝婓彮側堦嶜偱偁傞丅偙偙偱儕傾儖側朣楈偲偄偆偺偼丄墘寑傗暥妛嶌昳偵搊応偡傞栶暱偲偟偰偺朣楈偱偼側偔丄宱尡択偲偟偰岅傜傟偨朣楈偲偄偆堄枴偱偁傞丅偦傟偼丄嫟挊幰偺彫徏榓旻巵偑亀溸楈怣嬄榑亁丄亀埆楈榑亁側偳偺挊幰偩偐傜偲偄偆僒乕價僗惛恄偵傛傞傕偺傕偁偭偨偐傕偟傟側偄偑梋寁側壇應偼傗傔偰偍偙偆丅
丂摨彂乮p96乯偱拞懞巵偼乽巹偼朣楈偲偄偆偺傪恖娫偺怱偵暲乆側傜偸椡偱嶌梡偡傞償傽乕僠儍儖丒儕傾儕僥傿乕偺堦庬偩偲峫偊偰偄傞乿偲彂偄偰偄偨丅朣楈偲偼償傽乕僠儍儖丒儕傾儕僥傿乕偺堦庬偩偲拞懞巵偼峫偊偰偄偨偺偱偁傞丅偙傟偼丄巹偺乽怱楈妛乿偵偲偭偰傕峫偊偝偣傜傟傞榑揰傪娷傓偲巚傢傟傞偺偱丄偁傜偨傔偰撉傒捈偟偰偍偒偨偄丅側偍丄摨彂偼嫟挊幰彫徏榓旻巵偲偺墲暅彂娙偲偄偆懱嵸偱曇傑傟偰偄傞偨傔丄昁梫嵟掅尷偺斖埻偱彫徏巵偺敪尵偵傕傆傟傞丅
丂
仭悈巕嫙梴
丂偝偰丄拞懞巵偑儕傾儖側朣楈偵尵媦偟偨偺偼丄戞2復乽榁偄偲巰乿偐傜偱偁傞丅偨偩偟丄拞懞巵杮恖偑朣楈偵憳嬾偟偨偲偄偆傢偗偱偼側偄丅榁偄偲庒偝傪懳斾偟丄傗偑偰庒偝傪巀旤偡傞帪戙偼廔傢偭偰巰偺偙偲偽偐傝峫偊傞帪戙偵側傞偩傠偆偲偄偆榖偺廔傢傝偵丄傗傗搨撍偵丄揱暦偲偟偰朣楈偺榖偑帩偪弌偝傟傞丅
丂愴抧偐傜婣崙偟偨尦擔杮暫偑朣楈偵溸偐傟偰偄偨偲偄偆榖偼丄巹偑巕偳傕偺偙傠傑偱偼帪愜傝帹偵偡傞榖戣偩偭偨丅摴嫵偺摴巑傪帩偪弌偡傑偱傕側偔丄巹偺恊偺悽戙偵偲偭偰偼傛偔偁傞悽娫榖偩偭偨傛偆偩丅愴抧偱偆傑偔棫偪夞偭偰摼傪偟偨傜偟偄偲塡偺偁傞恖偑擄偟偄昦婥偵側偭偨傝偡傞偲丄巹偺晝側偳偼偦傟尒偨偙偲偐偲偄傢傫偽偐傝偵丄偁偺恖偼愴抧偱曔椄傪嶦偟偨偐傜偦偺楈偺釳傝偵堘偄側偄偲偄偆榖傪偟偨丅堦曽丄悈巕嫙梴偵偮偄偰偼丄拞懞巵偑側偤偦傟傪愴抧偐傜朣楈傪楢傟婣傞榖偲娭楢晅偗偰帩偪弌偟偨偺偐傛偔傢偐傜側偄丅
丂彫徏巵偼丄悈巕嫙梴偵偮偄偰丄釳傝傊偺嫲傟偲偟偰愢柧偟偨偆偊偱丄釳傝偵偮偄偰師偺傛偆偵晅偗壛偊偰偄傞丅
丂堷梡暥拞乽偙傟傑偱偼乿偲彫徏偑尵偆偺偼丄慜嬤戙偱偼丄偲偄偆堄枴偱偁傞丅戀帣傪堦屄偺恖奿偲偟偰擣幆偟偰偄側偐偭偨慜嬤戙偲丄戀帣傪乽堄巚傪傕偮庡懱揑側懚嵼偲偟偰乿擣幆偡傞嬤戙埲屻偲偱偼悈巕嫙梴偺堄枴偑堎側傞丅戀帣偼丄嬤戙揑側堛妛偺傕偲偱堄巚傪傕偮庡懱揑側懚嵼偲偟偰擣幆偝傟丄傑偨偦偺偙偲偐傜恖尃偺庡懱偲偟偰傕峫偊傜傟傞傛偆偵側偭偨偙偲偐傜乽釳傝乿偺庡懱偵傕側傝偊偨偺偩偲偄偆偙偲偩丅旂擏偵傕嬤戙壔偑悈巕傪墔楈壔偟偨偺偱偁傞丅
丂偙傟偵懳偟偰拞懞巵偼師偺傛偆偵墳摎偟偰偄傞丅
丂偙偆偟偨榖偺棳傟偱丄偄傛偄傛戞3復乽墔楈乿偱丄朣楈偵偮偄偰偺揘妛幰偲柉懎妛幰偺懳榖偑側偝傟傞丅偦偺慜偵丄拞懞巵偑朣楈偲悈巕嫙梴傪儚儞僙僢僩偱帩偪弌偟偨偨傔偵丄偙偺屻偺媍榑偵傕偦傟偑旜傪堷偄偰傢偐傝偯傜偔側偭偰偄傞偺偱丄偙偙偱娙扨偵惍棟偟偰偍偔丅拞懞巵偼悈巕嫙梴偵偮偄偰丄摉弶丄乽傎偲傫偳乽帺慠乿壔偟偨乽姷廗乿乿偲尵偭偰偄偨傛偆偵丄偦傟傪帺慠敪惗揑側惛楈怣嬄丄傾僯儈僘儉偲寢傃晅偗偰峫偊偰偄偨傛偆偩丅偲偙傠偑彫徏巵偼丄尰戙偺悈巕嫙梴偼嬤戙壔偵傛偭偰戀帣偑釳傝偺庡懱偲偟偰偺帒奿傪帩偪偊偨偲偙傠偵娽傪晅偗偨憭嵳價僕僱僗偲偄偆懁柺偑嫮偔丄偦偺揰偱慜嬤戙偺悈巕嫙梴偲偼嬫暿偝傟傞偲愢柧偟偨丅偙傟偑拞懞巵偵偼堄奜偩偭偨傜偟偔丄乽僐儅乕僔儍儕僘儉偙偦偑尰戙偺嵟戝偺廗懎側偺偐傕偟傟側偄丄偲巚偭偰偟傑偄傑偡乿偲偨傔懅傪偮偔傛偆側僐儊儞僩傪巆偟偰偄傞丅偵傕偐偐傢傜偢丄師復偱傕丄崅栰嶳偺悈巕抧憼傪偁偘偰乽悈巕抧憼偲偼擔杮揑傾僯儈僘儉偺慛楏側丄偁傞偄偼側傑側傑偟偄昞尰乿偲丄側偍傕偙偩傢偭偰偄傞偺偩偑丄偙傟偼惗柦椣棟偵偍偗傞拞愨偺栤戣偲偐偐傢偭偰偄傞偐傜偩傠偆丅杮峞偱偼悈巕嫙梴偵偮偄偰偼丄壖偵堷梡暥拞偱怗傟傜傟偰偄偰傕愊嬌揑偵偼庢傝忋偘側偄偙偲傪偍抐傝偟偰偍偔丅栤戣偼朣楈偱偁傞丅
丂拞懞巵偑乽巹偼朣楈偲偄偆偺傪恖娫偺怱偵暲乆側傜偸椡偱嶌梡偡傞償傽乕僠儍儖丒儕傾儕僥傿乕偺堦庬偩偲峫偊偰偄傞乿偲彂偄偨偺偼丄偙偺戞2復偺枛旜偱偁偭偨丅
丂
仭償傽乕僠儍儖丒儕傾儕僥傿乕
丂償傽乕僠儍儖丒儕傾儕僥傿乕偲偼壗偐丅亀弍岅廤嘦亁偵偁傞拞懞巵偺掕媊偼丄扨偵壖憐尰幚偲偄偆偵偲偳傑傜側偄丅偦偙偱拞懞巵偼丄億僷乕偺乽儚乕儖僪俁乿丄僿乕僎儖偺乽媞娤揑惛恄乿丄惣揷婔懡榊偺乽昞尰揑悽奅乿傪嫇偘偰師偺傛偆偵尵偆丅
丂償傽乕僠儍儖丒儕傾儕僥傿乕偼僿乕僎儖偺尵偆媞娤揑惛恄偺摨椶偩偲拞懞巵偼尵偆偺偱偁傞丅偦傟偱偼丄拞懞巵偼僿乕僎儖偺媞娤揑惛恄傪偳偆偲傜偊偰偄偨偺偐丅亀栤戣孮亁乮娾攇怴彂乯偵偼偙偆偁傞丅
丂朣楈偑償傽乕僠儍儖丒儕傾儕僥傿乕偺堦庬偩偲偟偨傜丄偮傑傝丄朣楈傪媅惂偺椡偲偟偰棟夝偡傞側傜丄偦偺傛偆側朣楈偲偄偆岅偼丄斾歡偲偟偰偺朣楈偵傛偔偁偰偼傑傞偩傠偆丅夁嫀偺姷廗傗惂搙丄偁傞偄偼僀僨僆儘僊乕側偳偑尰嵼偺巹偨偪傪峉懇偟丄撍偒摦偐偟偨傝偡傞応崌丄僫儞僩僇偺朣楈偲偄偆丅偦偆偄偆応崌偱偁傞丅偟偐偟丄朣楈偑媅惂偺椡偩偲偟偰傕丄儕傾儕僥傿乕偑側偄偲偄偆傢偗偱偼側偄丅亀巰亁偱偼乽傕偪傠傫丄墔楈偑偦偺崷傒傪偼傜偡偙偲偺儕傾儕僥傿乕偼丄巹傕偮傛偔姶偠偰偄傑偡乿乮p140乯偲拞懞巵偼尵偭偰偄傞丅媅惂亖僼傿僋僔儑僫儖側傕偺偺椺偲偟偰拞懞巵偑嫇偘偰偄傞朄惂搙偼丄傑偝偟偔尰幚傪摦偐偡椡傪帩偭偰偄傞丅
丂梋択偩偑丄偙偺楢嵹偺慜夞偺幹懌偵丄晝偺巰埲棃丄廡偵堦搙偔傜偄丄柧偗曽偵側傞偲実懷揹榖偺拝怣壒偑暦偙偊偰旘傃婲偒傞偙偲偑懕偄偰偄傞偲婰偟偨丅偙傟偼巹帺恎偺幚懱尡偱丄嵟嬤偼廡偵堦搙偑丄擇廡偵堦搙偔傜偄偵側偭偰偄傞偑崱偱傕懕偄偰偄傞丅実懷揹榖乮垽梡偺偄傢備傞僈儔働乕乯傪奐偄偰拝怣棜楌傪尒偰傕側傫偺婰榐傕側偄丅擖堾拞偺晝偑巰傫偩俈寧傑偱偺敿擭娫傎偳丄枹柧偺揹榖偱媫曄傪崘偘傜傟偰昦堾傑偱媫偖偙偲偑偨傃偨傃偁偭偨丅偙傟偑廗偄惈偲側偭偰僼傽儞僩儉丒僶僀僽儗乕僔儑儞傪婲偙偟偰偄傞偺偱偁傞丅偙傟偑巹偵偲偭偰偺晝偺巰偺償傽乕僠儍儖丒儕傾儕僥傿乕偱偁傞丅偙偆偟偨宱尡偺偁傞曽偼懡偄偩傠偆丅孞傝曉偝傟偨巋寖偑廗姷偵側偭偨偺偱偁傞丅偙傟偼屄恖偺廗姷偩偑丄廗姷偲偼幮夛偺姷廗偲側傫傜偐偺楢懕偑偁傞傕偺偲峫偊傜傟偰偄傞丅偨偩偟丄屄懱儗儀儖偺廗姷偲廤抍儗儀儖偺姷廗乮廗懎乯偲偺偁偄偩偵偳偺傛偆側娭學偑惉傝棫偮偐偵偮偄偰偼彅愢偁傞偑丄掕愢偲尵偊傞傎偳偺傕偺偼傑偩側偄丅偟偐偟丄拞懞巵偺偄偆償傽乕僠儍儖丒儕傾儕僥傿乕偲偟偰偺朣楈偲偼丄傕偭偲戝偑偐傝側傕偺偱偁傞傛偆偩丅
丂
仭媡岝偺懚嵼榑
丂朣楈傪償傽乕僠儍儖丒儕傾儕僥傿乕偺堦庬偲偟偰懆偊傞偙偲偼丄惗傪妶惈壔偡傞傕偺偲偟偰巰傪懆偊傞偲偄偆偙偲偵偮側偑傞丅偙傟偼幚嵺丄拞懞巵偑廆嫵偵尵媦偡傞嵺偵彞偊傞乽媡岝偺懚嵼榑乿偺偙偲偱傕偁傞丅彫徏巵偼偦偺僄僢僙儞僗偲偟偰丄拞懞巵偺亀擔杮暥壔偵偍偗傞埆偲嵾亁乮怴挭幮乯偐傜乽亀廆嫵亁偑恖娫偵壜擻偵偟偨偺偼丄偍偺傟偺嫊柍偺帺妎傪攠夘偲偟偨丄憡懳揑壙抣偐傜愨懳揑壙抣傊偺丄桳尷側惗柦偐傜柍尷側惗柦傊偺揮姺偱偁傝丄恀偺帺屓偺扵媶丒敪尒偱偁偭偨乿偲偄偆暥傪拪弌偟偰偄傞丅
丂拞懞巵帺恎偼丄亀弍岅廤嘦亁乽廆嫵乿偺崁栚偱師偺傛偆偵掕幃壔偟偰偄傞丅
丂偙傟偼偍偦傜偔拞懞巵偑弶婜偵庢傝慻傫偩僷僗僇儖亀僷儞僙亁偺桳柤側尵梩乽偙偺柍尷偺嬻娫偺塱墦偺捑栙偑丄巹傪偍偺偺偐偣傞乿偐傜怗敪偝傟偰峔憐偝傟偨傕偺偩傠偆丅拞懞巵偼偙偆拲庍偟偰偄傞丅
丂嬤戙偺僯僸儕僘儉偲偄傢傟傞忬嫷偺妀怱偼丄僐僗儌儘僕乕乮堄枴丒壙抣偺拋彉乯偲僔儞儃儕僘儉乮堄枴丒壙抣偺徾挜懱宯乯偺憆幐偱偁傝丄僔儞儃儕僘儉偵偼偨傜偒偐偗傞僷僼僅乕儅儞僗乮寑揑峴堊丒庴嬯揑峴堊乯偵傛偭偰僐僗儌儘僕乕傪夞暅偡傞偲偄偆偺偑丄拞懞巵偺擭棃偺庡挘偱偁偭偨乮椺偊偽亀杺彈儔儞僟峫亁娾攇彂揦乯丅媡岝偺懚嵼榑偲柤偯偗傜傟偨廆嫵娤傕偙偺峔憐偺墑挿忋偵偁傞丅偦傟偼塱墦偺捑栙偺慜偱棫偪偡偔傒丄偍偺偺偄偰偄傞偩偗偱偼廔傢傜側偄丅
丂帺傜偺桳尷惈傪帺妎偟偨恖偺拞偵偼丄帺暘偑惗偒偰偄傞偺偱偼側偔丄壗幰偐偵乽惗偐偝傟偰偄傞乿姶妎傪傕偮恖偑偄傞偲偄偆丅偦偙偵尃椡巙岦偺嫮偄幰偺湏堄偑夘嵼偡傞偲偲傫偱傕側偄偙偲偵側傞偙偲傪丄僆僂儉恀棟嫵帠審偺徴寕傪庴偗偰彂偐傟偨亀擔杮暥壔偵偍偗傞埆偲嵾亁偱拞懞巵偼寈崘偟偰偄傞偑丄偦傟偱傕偙偺峔憿偼枺椡揑偱偁傞丅帺傜偺桳尷惈傪媡徠幩偡傞壗傕偺偐偑丄暥帤捠傝愨懳懠幰側偺偐丄挻墇揑偱崻尮揑側懚嵼側偺偐偑丄尩偟偔栤傢傟側偗傟偽側傜側偄偑丄偟偐偟丄塱墦偺巰傪攠夘偵偟偰恀偺帺屓傪帺妎偡傞傛偆側宱尡偼丄廆嫵揑夞怱偲偄傢傟傞傕偺偺戙昞揑側僷僞乕儞偱偁傞丅
丂偨偩丄拞懞巵偼夞怱偺攠夘偲側傞巰偵偮偄偰傕丄乽偦偺乽巰乿偼乽惗乿偺妶惈壔偺尨摦椡偲偟偰傕摥偒偆傞偺偱偡乿乮拞懞丒彫徏慜宖彂丄p75乯偲柧尵偟偰偄傞傛偆偵丄惗偺棫応偵幉懌傪抲偄偰峫偊偰偄傞丅傕偪傠傫丄巹偨偪偼惗偒偰偄傞恖娫偩偐傜丄傑偢偼惗偺棫応偐傜峫偊傞偟偐側偄偺偩偑丄偙偆尵偭偰偟傑偆偲丄尰幚偺巰偼晄壜媡側傕偺側偺偵丄巰偑捠夁媀楃偺帋楙偺傛偆偵庴偗偲傔傜傟傗偟側偄偐偲偄偆寽擮偼偳偆偟偰傕巆傞丅
丂
仭墔楈
丂戞3復乽墔楈乿偱丄拞懞巵偼擻偺乽朣楈乿傗亀懢暯婰亁偺乽墔楈乿傪椺偵嫇偘偰師偺傛偆偵尵偆丅乮偪側傒偵亀懢暯婰亁偺墔楈偵偮偄偰偼杮帍乽僐乕儔乿偱傆傟偨丅壀揷桳惗巵偲偺嫟嶌亀抧崠偼堦掕偡傒偐偧偐偟亁偺峀嶁幏昅晹暘乽揤嬬懢暯婰乿傪偛棗偄偨偩偒偨偄乯丅
丂偙偺拞懞巵偺栤偄偐偗偵懳偟偰丄彫徏巵偼乽墔楈敪惗岞幃乿傪帵偡丅
丂墔楈偲偼偡偖傟偰惌帯揑側朣楈側偺偱偁傞丅偙偺傛偆偵彫徏巵偼丄償傽乕僠儍儖丒儕傾儕僥傿乕偲偟偰偺墔楈丄媅惂偺椡偲偟偰偺墔楈偺敪惗忦審傪柧妋偵昤偒弌偡丅偨偩偟丄拞懞巵偺娭怱偲偺陹陾傕偁傞丅拞懞巵偑墔楈偺惗傑傟傞娐嫬偲偟偰傾僯儈僘儉傪擮摢偵抲偄偰偄傞偺偵懳偟偰丄彫徏巵偼楈嵃晄柵偺娤擮偑偁傟偽墔楈偼惗傑傟傞偲偟偰偄傞丅偩偐傜丄彫徏巵偼拞懞巵偺傾僯儈僘儉傊偺偙偩傢傝偵懳偟偰偄傇偐偟偘偵尵偭偰偄傞丅
丂彫徏巵偺摉榝偼傛偔傢偐傞丅墔楈偲偼墔傒傪書偄偰巰傫偩幰偺楈嵃偺敪尰偱偁偭偰丄傾僯儈僗僥傿僢僋側忣擮偲捈愙偺娭學偼側偄丅偦傟偱傕拞懞巵偼師偺傛偆偵尵偆丅
丂墔楈偲傾僯儈僘儉偲偄偆榖戣偼拞懞巵偑帩偪弌偟偨偼偢側偺偵丄傕偆偙偺媍榑偼懪偪愗傝傑偟傚偆偲尵傢傫偽偐傝偱偁傞丅
丂偙偺傗傝偲傝偵巹偼堄奜側巚偄偑偟偨丅拞懞梇擇榊巵偲偄偊偽丄俈侽擭戙俉侽擭戙偺擔杮巚憐奅偺僗僞乕偩偭偨丅偦偺恖婥偺棟桼偼丄惣墷巚憐偺怴摦岦傪岻傒偵僉儍僢僠偡傞傾儞僥僫傗丄恊偟傒傗偡偄僄僢僙僀偵傕偁偭偨傠偆偑丄巹偺報徾偱偼懳択丒嵗択偺柤庤偲偄偆偲偙傠偵傕偁偭偨丅拞懞巵偼丄墿嬥帪戙偺乽尰戙巚憐乿帍偵偟偽偟偽搊応偟丄偦偺攷幆偲廮擃側岲婏怱傪敪婗偟偰偝傑偞傑側暘栰偺愱栧壠偲択榑晽敪偺懳択傪孞傝峀偘偰偄偨乮亀惛恄偺僩億僗亁惵搚幮乯丅側偐偱傕暥壔恖椶妛幰偺嶳岥徆抝巵偲偺懳択偱偼懅偺崌偭偨僐儞價僱乕僔儑儞傪敪婗偟偰丄拞懞巵偺帩榑偱偁傞墘寑揑抦傪幚墘偟偰傒偣偨乮偦偺岲椺偼旤弍巎壠丒崅奒廏帰巵傪岎偊偨揅択亀彂暔偺悽奅亁惵搚幮乯丅偩偐傜丄彫徏巵偺愱峌偡傞恖椶妛丒柉懎妛偼丄拞懞巵偵偲偭偰傑偭偨偔枹抦偺暘栰偱偼側偄偼偢偩丅偦傟側偺偵丄偳偆偟偰偙偆傕媍榑偑偡傟偪偑偆偺偩傠偆偐丅
丂
仭棤偺傾僯儈僘儉
丂戞係復乽棤偺傾儈僯僘儉乿偱偺傗傝偲傝偺拞偱丄偡傟偪偑偄偺梫場傜偟偒傕偺偑巔傪偁傜傢偡丅
丂拞懞巵偺偄偆乽棤偺傾僯儈僘儉乿偵娭楢偟偰丄彫徏巵偼丄摴嬶偑梔夦壔偡傞乽晅憆恄乿傪椺偵偁偘傞丅
丂恖娫偺楈嵃偙偦朣楈偱偁偭偨偼偢側偺偵丄偙偙偱彫徏巵偼墔楈奣擮傪奼挘偟偰丄晅憆恄偲偄偆婍暔偺夦傑偱傆偔傔偰偄傞丅偙偺儘僕僢僋偺攚宨偲偟偰偼丄偙傟傕媍榑偑嶖憥偡傞偺偱傆傟偰偙側偐偭偨偺偩偑丄朣楈偲墔楈傪暘偗傞彫徏巵堦棳偺墔楈娤偑偁傞丅巹帺恎偼丄墔楈偲偼偁偔傑偱傕朣楈偺僇僥僑儕乕偵娷傑傟傞傕偺偱偁傝丄偁傑偨偄傞朣楈偺偆偪偱墔崷偺昞弌偺摿偵嫮楏側恖偨偪偲偄偆擣幆側偺偱丄堄尒傪堎偵偡傞偑丄偙偙偱偼彫徏巵偺堄恾傪渦搙偟偰傒傛偆丅
丂恾幃揑偵偄偊偽丄屄恖揑側摦婡偐傜尰傟傞恖娫偺楈嵃傪朣楈丄惌帯揑側儊僢僙乕僕傪摦婡偲偟丄尰幚幮夛偵嫮偄丄応崌偵傛偭偰偼暔棟揑側塭嬁傪梌偊傞傕偺傪墔楈丄偲偄偆傛偆偵彫徏巵偼峫偊偰偍傝丄偝傜偵丄墔楈偵偮偄偰偼丄釳傝恄偺宯晥偵楢側傞傕偺偲偟偰偄傞丅墔楈偑幚偼釳傝恄偺枛遽偱偁傟偽丄梔夦偼釰傝偡偰傜傟偨恄偩偲偄偆桍揷柉懎妛偺梔夦棟夝偵娷傑傟傞偙偲偵側傞偐傜丄墔楈偲梔夦偲偺奯崻偼偖偭偲掅偔側傞丅偦偙偐傜幪偰傜傟偨婍暔偺惛偺側偡梔夦偱偁傞晅憆恄傕墔楈偺偆偪偵娷傑傟傞丄偲偄偆偲偙傠傑偱偼偐側傝嬯偟偄婥傕偡傞偑丄摴嬶傕懪偪幪偰傜傟偰墔傫偱偄偨偺偩偲尵偊側偄偙偲偼側偄丅
丂偟偐偟丄偙傟偼傗偼傝彫徏巵偑拞懞巵偵彆偗廙傪弌偟偨偺偩傠偆丅傾僯儈僘儉偵傛偔偁偰偼傑傞偺偼朣楈傗墔楈傛傝傓偟傠梔夦偱偡傛偲彫徏巵偼埫偵帵嵈偟偨偺偱偼側偄偐丅偦偆峫偊偨曽偑帺慠偩偲巚偆丅幚嵺丄偙偺偁偲丄拞懞巵偼梇曎偵乽棤偺傾僯儈僘儉乿傪岅傝偩偡丅
丂梔夦偼昁偢偟傕庺鎓傗墔擮偲娭學偡傞傢偗偱偼側偄偺偩偑丄偙傟埲忋媍榑傪嶖憥偝偣傞偺傕柺搢側偺偱丄傕偆傆傟側偄偱偍偔丅拞懞巵偼偙偺屻偱偼丄暯揷撃堺傪帩偪弌偟偰丄乽乽棤偺傾儈僯僘儉乿偺懱尰幰乿偲昡壙偡傞丅
丂捠忢偼朣楈偺斖醗偵擖傞墔楈傕丄梔夦偲傒側偡偙偲傕偱偒傞偲偄偆彫徏巵偺彆偗廙偵忔偭偰堦婥偵暯揷崙妛傑偱偙偓偮偗偰偟傑偭偨丅偙偺偁偨傝偼丄傕偆朣楈偲偺娭學偑敄偔側傞偺偱杮峞偱偲傗偐偔偁偘偮傜偆偙偲偼偟側偄偑丄梫偡傞偵丄拞懞巵偑朣楈乮巰幰偺嵃偺敪尰偲峫偊傜傟傞尪乯偲梔夦乮夦堎偺庡懱偲憐掕偝傟傞惛楈乯偲偺嬫暿傪偁傑傝堄幆偟側偄偱媍榑偟偰偄偨偨傔丄崿棎偑懕偄偰偄偨偺偱偁傞丅
丂
仭杺彈儔儞僟
丂偝偰丄埲忋丄愖妛偺偁偘偁偟傪庢傞傋偔椳栚偵側偭偰棫偪夞偭偰偄傞偐偺傛偆側暥復偵側偭偰偟傑偭偨偑丄巹偼側偵傕拞懞巵傪旕擄偟偨偄偑偨傔偵摨巵偺挊嶌傪奐偄偨偺偱偼側偄丅亀巰亁偺側偐偐傜巹偺摉柺偺娭怱偱偁傞朣楈偵偮偄偰傆傟偨拞懞巵偺敪尵傪廍偄撉傒偟偰偄偔偲偙偆側偭偰偟傑偭偨偙偲偵丄傓偟傠摉榝偟偰偄傞傎偳偩丅
丂梫傜偸曎夝傪偟偰偍偔偲丄巹偑偼偠傔偰攦偭偨亀揘妛擖栧亁偼拞岞怴彂偐傜弌偰偄偨拞懞巵偺挊嶌偱偁傝丄揘妛偼僪儔儅偱偁傞偲偄偆偦偺僗儘乕僈儞偵偡偭偐傝姶壔偝傟偨巹偼丄堦帪婜丄偦傟傪僶僀僽儖偺傛偆偵帩偪曕偄偰偄偨丅娾攇偐傜弌偰偄偨嶰晹嶌亀姶惈偺妎惲亁亀嫟捠姶妎榑亁亀揘妛偺尰嵼亁偼傕偲傛傝丄摉帪懕乆偲姧峴偝傟偨拞懞巵偺挊嶌傪捛偄偐偗傞傛偆偵偟偰撉傫偩丅傕偪傠傫僼乕僐乕偺挊嶌傕拞懞栿偱撉傫偩悽戙偱偁傞丅偨偩丄拞懞巵杮恖偑庡挊偲埵抲晅偗傞亀杺彈儔儞僟峫亁埲崀偼榖偵偮偄偰偄偗側偄偲姶偠傞偲偙傠偑懡偔側傝丄惣揷婔懡榊榑偐傜亀埆偺揘妛僲乕僩亁傑偱偼壗偲偐捛偄偐偗偨傕偺偺丄偦傟埲崀偼愊傫撉偵側偭偨偺偼帠幚偱偁傞乮愊傫偱偁偭偨偆偪偺堦嶜偑亀巰亁偱偁傞乯丅
丂側偤巹偼亀杺彈儔儞僟峫亁偱偮傑偢偄偨偺偐丅偦偺偲偒偵偼偼偭偒傝帺妎偱偒偰偄側偐偭偨偑丄崱丄亀巰亁偲偦偺廃曈偺挊嶌傪撉傒側偍偟偰傒偰傢偐偭偨偙偲偑偁傞丅僀儞僪僱僔傾丒僶儕搰傪朘傟偰杺彈儔儞僟偺搊応偡傞恄榖寑乮僶儘儞寑乯傪娪徿偟偨拞懞巵偼丄僶儕丒僸儞僪僁乕偺傾僯儈僗僥傿僢僋側悽奅娤偵擖傟崬傓丅偦偙偵帺傜偑扵媶偟偰偒偨僐僗儌儘僕乕丄僔儞儃儕僘儉丄僷僼僅乕儅儞僗偑嬶尰壔偝傟偰偄傞偲姶偠偨偺偩傠偆丅杺彈儔儞僟偵偮偄偰偼拞懞巵帺恎偵傛傞梫栺傪堷偄偰偍偔丅
丂偙偺僀儊乕僕傪棟擮壔偟偰彂偒忋偘偨偺偑亀杺彈儔儞僟峫亁偵廂傔傜傟偨楢嶌偱偁傝丄埲屻偺挊嶌偵傕偦偺塭嬁偑偄偨傞偲偙傠偵尒傜傟傞丅亀巰亁偵偍偄偰丄擔杮揑傾僯儈僘儉側偳偲尵偄偩偟偨偺傕丄擻傗亀懢暯婰亁偺墔楈傪傾僯儈僘儉偺堦椶宆偲偟偰偲傜偊傛偆偲偟偨偺傕丄擔杮偺僶儕搰壔嶌愴偺堦抂偱丄墔楈偨偪偵僶儘儞寑偵偍偗傞巰偺彈恄儔儞僟偺栶妱傪墘偠偝偣偨偐偭偨偺偐傕偟傟側偄丅偦偆偩偲偡傞偲償傽乕僠儍儖丒儕傾儕僥傿乕偲偟偰偺朣楈偲偼丄杺彈儔儞僟傪儌僨儖偲偟偨傾僀僨傾偩偲尵偊偦偆偩丅偩偑偦傟偼丄尰幚偺墔楈偺僀儊乕僕偲堦抳偟側偄偨傔撢嵙偟偨偺偱偁偭偨丅
丂巹偼僶儕搰偺幮夛傗暥壔偑偳傫側傕偺偐抦傜側偄偗傟偳傕丄摿掕偺抧堟偺幮夛傗暥壔傪棟憐壔偡傞偙偲偵掞峈傪姶偠偨丅偦偙偑偳傫側偵偡偽傜偟偄偲偙傠偱偁偭偨偲偟偰傕丄恖娫偑曢傜偡幮夛偱偁傞尷傝昞傕偁傟偽棤傕偁傞偼偢偱丄庤曻偟偱偺棟憐壔偼偱偒側偄偩傠偆丅傑偟偰傗丄拞懞巵偺愨巀偡傞僶儘儞寑偼娤岝媞岦偗偵墘弌偝傟偨傕偺偱丄僶儕搰偺柉懎暥壔偦偺傕偺偱偼側偄乮拞懞巵帺恎偑偦偆彂偄偰偄傞乯丅
丂側偵傛傝傕拞懞巵帺恎偑亀杺彈儔儞僟峫亁偺枛旜嬤偔偱丄僊傾乕僣亀僰僈儔乗-廫嬨悽婭僶儕偵偍偗傞寑応崙壠亁傪嶲徠偟偰巜揈偟偰偄傞師偺揰偼偐側傝栤戣偱偁傞丅
丂偺偪偵僗僺償傽僋亀僒僶儖僞儞偼岅傞偙偲偑偱偒傞偐亁乮朚栿傒偡偢彂朳丄1998乯偵傛偭偰尰戙巚憐偺戝偒側僥乕儅偲側傞壡晈弣巰偱偁傞丅幚懺偼怣嬄傪岥幚偵偟偨從恎帺嶦偺嫮梫偱偁傝丄偟偐傕乽儔儞僟偼傕偲傕偲丄壡晈傪堄枴偡傞乿乮拞懞慜宖彂乯埲忋丄偙偙偵偼廳戝側栤戣偑尒偰偲傟傞丅偲偙傠偑丄拞懞巵偑偙傟偵偮偗偨僐儊儞僩偼乧乧丅
丂拞懞巵偺堄恾偵懄偡傞側傜丄埆傗巰側偳傪媀楃偵傛偭偰娚榓偟側偑傜撪懁偵庢傝偙傓巇妡偗偑昁梫偩偲偄偆偙偲偱偁傞丅堦斒榑偲偟偰丄巰偼傕偪傠傫偺偙偲丄埆乮朶椡乯傕姰慡偵徚偟嫀傞偙偲側偳偱偒側偄偩傠偆丅偩偐傜丄僆乕儖丒僆傾丒僫僢僔儞僌傛傝傕傎偳傎偳偺偲偙傠偱棊偲偟偳偙傠傪尒偮偗傞偺偼尰幚揑側採埬偱偁傞丅
丂偟偐偟偙偺尰幚揑側採埬偼丄巰偲偼晄壜媡側傕偺偩偲偄偆傕偆堦偮偺尰幚傪朰傟偰偄傞丅尰幚偺巰偑晄壜媡偱偁傞埲忋丄巰傪彽偔埆偼嫋梕偟擄偄丅偙偺堦慄傪備偢偭偰偟傑偭偨傜丄惗偒側偑傜壩拞偵搳偠傜傟偨柤傕側偒儔儞僟偨偪偺偙偲偼偳偆側傞偺偩傠偆丅扤偐乮偙偺応崌偼嫟摨懱乯偺惗傪妶惈壔偡傞偨傔偵扤偐乮壡晈亖儔儞僟偨偪乯偺巰偑梫惪偝傟傞偙偲傪偳偆庴偗偲傔傟偽傛偄偺偩傠偆偐丅
丂僶儕搰偱壡晈弣巰偑偡偨傟偨偺偼杺彈儔儞僟偺偍偐偘偱偼側偔丄惣墷恖偺旕擄傪偝偗傞偨傔偱偁偭偨丅傓偟傠杺彈儔儞僟偺妶桇偡傞僶儘儞寑偼丄墹偺憭媀偵惗嫜傪嵎偟弌偡慜嬤戙偺僶儕搰幮夛偺峔憿偲柍娭學偱偼側偄偼偢偩丅偦偆偩偲偡傟偽丄僶儕搰偺僐僗儌儘僕乕傪儌僨儖偲偟偨峔憐偵傕丄幮夛偺偨傔偺巰傪峬掕偡傞梫慺偑傑偓傟偙傓偙偲偵側傞丅偙偆偟偨媇惖偺栤戣傊偺娒偝偼丄拞懞巵偩偗偱側偔丄摨帪婜偵妶桇偟偨嶳岥徆抝巵傗崱懞恗巌巵偵傕嫟捠偟偰偄傞偙偲偼丄偐偮偰杮帍偵婑峞偟偨乽恄榖寑傪尒傞帇慄乿側偳偱彂偄偨丅傕偪傠傫丄偙偺堦揰傪傕偭偰丄拞懞巵傗嶳岥巵丄崱懞巵傜偺朿戝側嬈愌傪慡斲掕偡傞偙偲側偳偱偒側偄偟丄嫋偝傟側偄丅傓偟傠丄偄偪憗偔栤戣偺強嵼偵徠柧傪偁偰偨愭尒偺柧傪昡壙偡傋偒偩傠偆丅
丂偲偼偄偊丄偝偧傗拞懞巵偼僶儕搰偺暥壔偵姶柫傪庴偗偨偺偩傠偆偑丄杺彈儔儞僟偵偲傝溸偐傟偨偺偱偼側偄偐偲巚偆傎偳偺擬嫸傪撉傑偝傟偰丄偐偊偭偰巹偼椻傔偰偄偭偨偺傕帠幚偩偭偨丅
丂
仭媡岝偺宍帶忋妛
丂怱楈尰徾偺夝庍妛偺偨傔偵丄拞懞巵偺敪憐偐傜壗偐媯傓傋偒傕偺偑偁傞偲偟偨傜丄傗偼傝媡岝偺懚嵼榑偩傠偆丅偦偺壜擻惈傪尒傞慜偵擄揰傪偁偘偰偍偔丅塱墦偺巰傪攠夘偵偡傞偲偄偆偑丄偄偭傌傫巰傫偱傒偨傜惗偒曉傜側偄偺偑尰幚偱偁傞丅僔儞儃儕僢僋側師尦偱岅傜傟傞巰偲偼丄墲乆偵偟偰嵞惗傪慜採偵偟偨巰偱偁傝丄偦傟偼尰幚偺巰偱偼偁傝摼側偄丅媡岝偺懚嵼榑偵偼丄偙偆偟偨徾挜揑師尦偺巰丄僼傿僋僔儑僫儖側巰偲丄屆偔偐傜乽巰幰晄壜埲暅惗乿乮亀懛巕亁壩峌曆乯偲偄傢傟偰偒偨傛偆側晄壜媡側傕偺偲偟偰偺尰幚偺巰偲偑崿嵼偟偰偄傞丅塱墦偺巰傪攠夘偵偡傞偲尵偭偨応崌丄巹偼偁偔傑偱傕晄壜媡側巰傪擮摢偵抲偒偨偄丅惗偒曉傞傛偆偱偼巰偲偼偄傢傫偩傠偆偲偄偆偺偑丄巰偵偮偄偰偺尰戙偺忢幆揑側棟夝偱偼側偄偩傠偆偐丅
丂巹偺晝偼擣抦徢偱擖堾偟偰偄偨愭偱攛墛偵偐偐傝丄擇寧偵偼婋撃偵側偭偰丄傕偆悢擔帩偮偐偳偆偐偲尵傢傟偨偑丄偦偺屻傕幍寧傑偱偺敿擭娫丄帪偵偼怱掆巭傪娷傓婋撃忬懺傪壗搙傕孞傝曉偟側偑傜傕惗偒偰偄偨丅晝偼偦偆偟偰彊乆偵悐庛偟偰巰傫偩偺偱偼側偔丄幍寧偵偼庡帯堛偑婏愓揑偲嬃偔傎偳偺夞暅傪尒偣丄擇搙傕晽楥偵擖傟偰傕傜偭偰娕岇巘偝傫偨偪偵垽憐徫偄傪怳傝傑偄偨偁偘偔丄忋婡寵偵偡傗偡傗怮擖偭偨傑傑偁偺悽偵峴偭偨丅敿擭娫丄巹偨偪壠懓偼乽偍晝偝傫傑偨惗偒曉偭偨乿偲婌傫偩傝偟偨偑丄偦傟偼偁偔傑偱傕斾歡偱偁偭偰晝偼巰偸傑偱惗偒偰偄偨丅恖憶偑偣側恊晝偩偑丄晝偺巰傪壗搙傕媈帡懱尡偟偨偍偐偘偱丄偄偞偲偄偆帪偺弨旛偑偱偒偰彆偐偭偨丅偦傟偼偲傕偐偔丄巰偵偐偗傞偙偲偲巰傫偩偙偲傪崿摨偟偰偼偄偗側偄丅
丂尰戙恖偺忢幆揑側棫応偐傜峫偊傞側傜丄巰傪攠夘偵偡傞偲偼丄偄偭傌傫巰傫偱傒傞偙偲偱偼偁傝偊側偄丅巰傫偩傜偦傟傑偱偱偁傞丅偩偐傜丄巰偵捈柺偡傞幰偼偁偔傑偱惗偒偰偄傞丅惗偒偰偄傞巹偼巰傪宱尡偡傞偙偲偼偱偒側偄丅僼傿僋僔儑儞偺悽奅偱丄徾挜揑側巰傪媈帡宱尡偡傞偙偲偵堄媊偑側偄偲偼尵傢側偄丅偦傟偼巹偨偪偺丄摿偵惵擭婜偺恖奿宍惉偵婑梌偟偰偔傟傞偩傠偆丅偦偺偨傔偵僼傿僋僔儑儞偼偁傞丅偟偐偟丄尰幚偼堘偆丅惗偒偰偄傞巹偨偪偑帺傜偺巰偵捈柺偡傞丄偦偺巰傪攠夘偵偡傞偲偼丄偦傟偑側偵偐偺儊僞僼傽乕偱側偗傟偽丄巹偺巰屻偼巹偵偲偭偰揙摢揙旜晄壜抦偱偁傞偲偄偆偙偲偺帺妎偱偁傞丅塅拡偺壥偰偑抦傜傟偸傛偆偵丄巹帺恎偺拞偵愨懳偵晄壜抦側椞堟偑偁傞丄傓偟傠丄巰偲偄偆晄壜抦側柍尷偺塅拡偺堦揰偲偟偰巹偺惗偑偁傞丅偙傟偑乽帺屓偺懌壓偵掙柍偟偺嫊柍偺怺暎傪尒傞乿偲偄偆偙偲偩傠偆丅
丂偙偙傑偱偼丄惗偒偰偄傞巹偑峫偊傞偙偲偺偱偒傞斖埻偱偁傞丅偦偺堄枴偱偼杴懎側巹偵傕乽堦斒偵廆嫵揑堄幆偺弌敪揰偲偝傟傞<嫊柍偺帺妎>乿偼偁傞偺偩丅偟偐偟丄偙偙偐傜愭偼廆嫵揑側夞怱傪宱偨幰偩偗偑懱姶偱偒傞偙偲偱偁偭偰丄怣嬄幰偨偪偺尵梩傪庤偑偐傝偵恾幃揑偵昞柺傪側偧傞偙偲偟偐偱偒側偄丅
丂偳偆傗傜桳尷側巹偑柍尷偺嬻娫偲柍尷偺帪娫偺側偐偺旕椡側堦揰偲偟偰懚嵼偟偰偄傞偲偄偆偙偲偐傜丄乽傢傟傢傟偼丄悽奅傗奜奅傪帺暘偺岝偱徠傜偟弌偡慜偵丄偡偱偵壗傕偺偐偵傛偭偰摥偒偐偗傪庴偗丄偦偺岝偵徠傜偟弌偝傟偰偄傞乿偙偲偵巚偄摉傞傜偟偄丅巹偑峫偊傞偙偲偺偱偒側偄椞堟偵偁偭偰丄巹傪峫偊偰偔傟偰偄傞壗傕偺偐偑偄傞傜偟偄偺偩丅偦偺壗傕偺偐偲偼扤偐丅乽愨懳懠幰乿偲偐乽塅拡偺挻墇揑偱崻尮揑側懚嵼乿偲屇偽傟偰偄傞幰偼扤偐丅楌巎揑偵偼丄僉儕僗僩嫵丒僀僗儔儉嫵偺恄丄忩搚暓嫵偺垻栱懮擛棃丄恀尵枾嫵偺戝擔擛棃側偳偑丄偦傟偵偁偨傞偺偩傠偆丅巹偑僄僑偐傜惗偠傞巹偺偼偐傜偄傪幪偰偨偲偒丄<弮悎側庴摦惈>傪摼偨偲偒偵丄乽愨懳懠幰乿乽塅拡偺挻墇揑偱崻尮揑側懚嵼乿偐傜偺岝偵徠傜偝傟偰偄傞偙偲偵婥偯偒丄乽恀偵帺屓偨傝偆傞偟丄恀偺恖奿偨傝偆傞乿偲偄偆偙偲偑婲偒傞傜偟偄偺偱偁傞丅
丂偙偙傑偱偼廆嫵妛側偳偱掕愢偲傑偱尵偭偰傛偄偺偐偳偆偐偼傢偐傜側偄偑丄偐側傝峀偔擣傔傜傟偰偄傞棟夝偱偼側偄偩傠偆偐丅偙偺恾幃偵懳偟偰拞懞巵偑帵嵈偡傞偺偼丄乽愨懳懠幰乿偁傞偄偼乽塅拡偺挻墇揑偱崻尮揑側懚嵼乿偺埵抲偵偼恖奿恄偩偗偱偼側偔丄惗偒偲偟惗偗傞傕偺偺偡傋偰丄帺慠丄塅拡丄悽奅側偳偱傕抲偐傟偆傞偲偄偆偙偲偩丅
丂拞懞巵偑廆嫵偺尨弶宍懺偲偟偰偺傾僯儈僘儉偵拲栚偟偨偺傕丄偡傋偰偺傕偺偵柦偑偁傞偲姶偠傞傾僯儈僗僥傿僢僋側姶妎偑丄恖椶偺廆嫵暥壔偺婎掙偵偁傞偩傠偆偲偄偆摯嶡偵傛傞傕偺偩傠偆丅巰傪攠夘偲偟偨嫊柍偺帺妎偐傜丄帺慠丄枩暔丄塅拡丄悽奅丄偁傝偲偁傞偡傋偰偺帠暔偺岝偵徠傜偝傟偰偄傞帺屓傊偺婥偯偒傪壜擻偵偡傞偺偑丄傾僯儈僗僥傿僢僋側姶妎偱偁傞丅偙傟偑丄媡岝偺懚嵼榑偺墑挿慄忋偵峫偊偆傞夞怱偱偁傞丅
丂姶惈偲偐姶妎偲偐惂搙偲偄偭偨僥乕儅傪廲墶偵榑偠偨拞懞巵偺妶桇偐傜偡傞偲偄偝偝偐堄奜側婥傕偡傞偑丄媡岝偺懚嵼榑偲偼廆嫵揑堄幆偺宍帶忋妛偱偁傞丅偙偺宍帶忋妛傪怱楈尰徾偺夝庍偵惗偐偡偲偟偨傜偳偆側傞偐丅
丂拞懞巵偺昞尰傪梡偄傞側傜丄巹偨偪偑抦傞偙偲偺偱偒傞椞堟偲偼乽恖娫偺帺慠揑側惗柦椡偑傒偢偐傜敪偡傞岝乿偑撏偔斖埻偱偁傝丄巹偨偪偑抦傞暔帠偲偼乽惗柦椡偺敪偟偨岝乿偺斀幩偱偁傞丅巹偺巰偼丄巹偐傜敪偟偨岝偺撏偐側偄偲偙傠偵偁傞丅備偊偵晄壜抦偱偁傞丅壖偵惗柦椡偐傜敪偡傞岝偑崱埲忋偵嫮偔柧傞偔婸偄偨偲偟偰傕丄偦偺岝傪斀幩偡傞傕偺偼惗偺椞堟偵偁傞傕偺偩偗偱偁偭偰丄寛偟偰巰偱偼側偄丅巹偨偪偼昁偢巰偸偵傕偐偐傢傜偢丄巹偨偪偺懁偐傜敪偡傞岝偼巰偵撏偐側偄丅巰偵捈柺偡傞偲偼丄巰偺晄壜抦偺掙抦傟側偝傪巚偆偙偲偱偁傞丅僷僗僇儖偺尵梩傪傕偆堦搙堷偔丅
乽偙偺柍尷偺嬻娫偺塱墦偺捑栙偑丄巹傪偍偺偺偐偣傞乿丅
偩偑丄傢傟傢傟偑杮摉偵愴溕偡傞偺偼丄塱墦偵捑栙偡傞柍尷偺嬻娫偺斵曽偐傜壗幰偐偑偁傜傢傟偨偲偒偱偁傞丅偲偼偄偊丄偙偺傑傑僷僗僇儖偺昞尰傪巊偄懕偗傞偲丄塅拡偐傜嬻旘傇墌斦偑旘傫偱偔傞傛偆側僀儊乕僕偵側傝偐偹側偄偺偱丄拞懞巵偺挊嶌偐傜暿偺昞尰傪廍偍偆丅椺偊偽亀栤戣孮亁偱偼僆僢僩乕傗僄儕傾乕僨傪嶲徠偟偰師偺傛偆偵彂偄偰偄偨丅
丂偦傕偦傕朣楈偼恄偱傕暓偱傕側偄丅偩偐傜摨楍偵榑偠傜傟側偄柺傕偁傞偑丄乽惞側傞傕偺乿偵偼乽堎側傞傕偺乿偺懁柺傕偁傞丅朣楈偼昁偢偟傕惞側傞傕偺偱偼側偄偐傕偟傟側偄偑丄彮側偔偲傕堎側傞傕偺偱偼偁傞丅惞側傞傕偺偑丄僄儕傾乕僨偑楍嫇偟偨傛偆側偝傑偞傑側帠暔傗応強傪捠偟偰偁傜傢傟傞乮偦偺偨傔帪偵偼偦偆偟偨帠暔偲摨堦帇偝傟傞乗惞堚暔乯傛偆偵丄朣楈傕偝傑偞傑側帠暔傗弌棃帠傪宊婡偲偟偰丄偝傑偞傑側応強偵偁傜傢傟傞丅
丂偲偼偄偊朣楈偼乽愨懳懠幰乿偲偐乽塅拡偺挻墇揑偱崻尮揑側懚嵼乿偱偼側偄丅屻幰偱側偄偺偼丄朣楈傕傑偨惗慜偼塅拡偵撪嵼偡傞屄暔偱偁偭偨偙偲偐傜柧傜偐偩偑丄慜幰偱傕側偄偺偼丄偡傋偰偺朣楈偼偐偮偰惗偒偰偄偨扤偐偺楈偱偁偭偰尨棟揑偵偼惗幰偺懁偐傜傾僀僨儞僥傿僥傿傪摿掕偱偒傞偼偢偩偐傜偱偁傞乮偩偐傜偁傞掱搙偺僐儈儏僯働乕僔儑儞偑壜擻偩傠偆偲偄偆婜懸傪傕偰傞乯丅偙偺傛偆偵丄恄暓偵斾傋傞偲丄朣楈偺尠尰偵偼側偵偑偟偐偺忦審傗惂栺偑憐憸偝傟丄愨懳懠幰偲偄偆傛傝偼丄偐側傝巹偨偪偵嬤偄懠幰偱偼偁傞丅偦偙偐傜朣楈偺妶摦傪僐儞僩儘乕儖偱偒傞偼偢偲偄偆捠擮乮怱楈弍乯傕惗偠傞偑丄偦傟偼惗幰偺橖枬偲偄偆傕偺偩傠偆丅朣楈偲偼丄愨懳幰偱偼側偄偵偟偰傕丄惗幰偵偲偭偰晄壜怤偺椞堟偐傜尠尰偡傞懠幰側偺偱偁傞丅丂
丂晽楥晘傪峀偘夁偓偨傛偆側偺偱丄崱夞傕怟愗傟僩儞儃偩偑偙偺曈偱丅
仛僾儘僼傿乕儖仛
峀嶁朁怣乮傂傠偝偐丒偲傕偺傇乯1963擭丄搶嫗惗傟丅曇廤幰丒儔僀僞乕丅挊彂偵亀幚榐巐扟夦択丂尰戙岅栿亀巐僢扟嶨択廤亁亁丄亀夦択偺夝庍妛亁丄嫟挊偵嵟怴嶌亀擫偺夦 (峕屗夦択傪撉傓)亁側偳丅僽儘僌乽嫲嵢壠偺專棫昞乿 丂
Web昡榑帍乽僐乕儔乿33崋乮2017.12.15乯
亙怱楈尰徾偺夝庍妛亜戞11夞丗杺彈儔儞僟偺朣楈劅劅拞懞梇擇榊偵偍偗傞媡岝偺宍帶忋妛乮峀嶁朁怣乯
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU丂2017 All Rights Reserved.
|
| 昞巻乮栚師乯傊 |