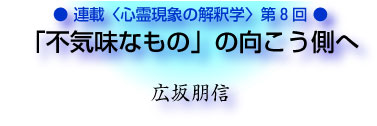|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「La Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
|
不気味なもの
このわがまま勝手な連載で、私は何度かフロイトの有名なエッセイ『不気味なもの』に言及しようとしながら、そのたびにためらってきた。それは私がこの知の巨人の理論に通じていないからということももちろんだが、怪異についての心理学的・精神医学的アプローチに懐疑的だからでもある。
フロイト自身の言葉によれば、『不気味なもの』の「本質的な内容」は次のとおりである。
抑圧されることでウンハイムリッヒなもの(不気味なもの)に転化するハイムリッヒなもの(親密なもの)とは、例えば幼児期の経験や、死(死者)への恐怖などが挙げられている。私はこのフロイトの洞察を否定するつもりはまったくない。人の心とはそういうものなんだろうなあと感心する。だが、こうしたフロイトの洞察を怪異、特にいわゆる「心霊現象」に直接当てはめることについては慎重でありたい。なぜなら、フロイトが論じているのは、何かある対象を不気味だと感じる人の心のはたらきについてであって、当の「不気味なもの」についてではないからである。
いわゆる「心霊現象」や、もう少し広く妖怪も含めた怪異の事例のなかには、自然現象の誤認、生物の珍しい姿態や動作、人為的な技術によって作り出された錯覚、別の文脈で理解された異文化なども含まれる。最初からフロイト『不気味なもの』の図式を前提にしてしまうと、それら怪異についての感じ方に議論を限定することになり、その怪異は何かということは探究されなくなる。それだけならまだしも、怪異一般を心理現象として扱うことになってしまったら大変だ。ツチノコという妖怪は人間が抑圧した自然界の生命力についてのメタファーなんですねなどとまことしやかに説明している論者の指にツチノコが噛みつくということも大いに考えられる。ツチノコと呼ばれるものは、仮にそれが生物だとしたら、妊娠中のマムシの誤認ではないかという仮説も有力なので要注意である。
冗談はともかくとして、「心霊現象」を心理現象に置き換えることによる弊害は大きい。
理性の外部
哲学者の野家啓一氏に『「理性の外部」としての異界』という短い論文がある(雑誌『文学』2001年11,12月号、岩波書店)。そこで野家氏は、このように定義することによって「多くの事柄が考察からこぼれ落ちることだろう」と断りながらも、異界を「理性の外部」とし、それは「想像力で産み出した非日常的な世界」の言い換えだという。そして「単に理性の外部にあるだけでは、それは異界の名には値しない」、異界に欠けてはならないものとは「現実世界と自在に往還できる通路」と「そこから生ずる一種独特の「無気味さ」にほかならない」と野家氏は説く。
この「無気味さ」は「日常的世界の安定を形作る境界が非日常的世界によってゆえなく侵犯されるとき」われわれが感じるものとされているから、怪談の解釈学がめざす異様さと同種のものといえる。また、理性と「理性の外部」が隔たりかつ接する臨界面として境界をとらえる仕方にも賛同する。
続いて野家氏は、フロイトの「無気味なものとは、昔からよく知っている、古なじみのものに由来する類の恐怖だ」という定式に注目し、それを「異界と現実世界との関係」に当てはめ、次のように言う。
さらに「抑圧され疎外されたものの回帰」というモチーフを柳田民俗学による「歴史の古層」の「発見」と結びつける。そして「異界とは日常性に走った一条の亀裂の別名」と結語する。
しかし、異界やそれに接触したときに感じる無気味さ(異様さ)を、私たちの心の中(想像力)から産み出されたものとして理解するべきだろうか。
私たちが心霊体験談の中に「抑圧され疎外されたものの回帰」を見出したとしたら、その体験談を私たちの世界の内側、あるいは体験者の心の中で起こった出来事として解釈したことになる。そのとき心霊体験談は解釈者の理解可能な範囲の物語に書き直されてしまう。その「異界」はもはや私たちのめざす異界ではないし、「理性の外部」でも「日常性に走った一条の亀裂」でもない。
異界は人の心の外にある、怪異はどこかから不意に現れる、それらを「なんだかわけがわからない」ものとして受けとめることから怪談の解釈ははじめられなければならない。出発点を「想像力で産み出した非日常的な世界」とするならば、心霊体験につきまとう驚愕や恐怖などの感情が、想像されたもの対する驚愕や恐怖に置き換えられてしまう。
しかし、日頃より、怪奇文学やホラー映画に慣れ親しみ作家たちの優れた表現力で描き出された恐怖を楽しんでいる者や、自らの出自を霊感のある家系だと称する者でさえも、体験された怪異には想像を絶する質の恐怖を感じている。怪異は心の外からやってくるのであり、それは体験者にとってあくまで現実の出来事である。
野家氏は、山中異界に「歴史の古層が残存している」と考えた柳田が、自らは「異界のとば口まで行ったものの異界を目にすることなく、そのまま里へと引き返した」(野家、前掲論文)と述べているが、「理性の外部」を想像され得るものの範囲に置き換えてしまうならば、野家氏もまた柳田とともに里へ引き返すことになろう。
『江戸の妖怪革命』(香川雅信、角川文庫)
もう一つ、似たようなケースを挙げる。香川雅信『江戸の妖怪革命』(角川文庫)である。同書は江戸時代後期の妖怪文化を豊富な資料によって描き出している画期的な研究成果である。香川氏は、かつては「恐ろしく、忌まわしい存在であった」妖怪が、現代では「かわいいキャラクター」に変貌していることに着目し、その起源を問うた。そして、その試みは成功しているように思われる。本稿が問題とするのはこの研究の中心部分ではなく、その方法の副次的な含意である。
同書の序論で香川氏は従来の妖怪研究には次の二つのレベルがあったと指摘する。
一、民間伝承、「信じられてきた妖怪」、民俗学。
二、文芸、絵画、芸能、「フィクションのなかの妖怪」、国文学、美術史、芸能史。
この二つのレベルの対立または両立は、妖怪研究にとって不毛であったというのが香川氏の主張である。
香川氏の主張はここによく表れている。非科学的な娯楽と蔑視されてきた妖怪文化を、現代の文化に通じるものとして宣揚しようということである。折口信夫の場合はどうかと思わないでもないが、一般論としてはそうなのだろう。
したがって、香川氏の設定する基本的な対立軸は、科学/迷信、芸術/娯楽、高尚/通俗であるはずだ。ところが、実際に『江戸の妖怪革命』を貫いているのはそれらの対立軸とは少しずれたところに線の引かれたもう一つの対立軸である。それが「民間伝承としての妖怪」/「フィクションとしての妖怪」である。
香川氏は「民間伝承としての妖怪」から「フィクションとしての妖怪」への歴史的移行には「妖怪に対する認識が根本的に変容することが必要」(香川、p16-p17)だったと論ずる。その「妖怪に対する認識の変容を記述し分析するうえで」(香川、p17)、M・フーコー『言葉と物』(邦訳・新潮社)のアルケオロジーが持ち出される。香川氏は「このアルケオロジーという方法を踏まえて、日本の妖怪観の変容について記述することにしたい」、「これによって日本の妖怪観の変容を、大きな文化史的変動のなかで考えることができるだろう」(香川、p18)というのだが、西欧近代の知の枠組みの変容を描くフーコーの手法を日本近世に適用することの当否は別としても、本書中で香川氏がフーコーを持ち出して繰り返し説く妖怪観の変容、「類似」から「表象」へという移行は、リアルからフィクションへと言い換えられるものになっている。
実際、序章に続く本論(「第一章安永五年、表象化する妖怪」、「第二章妖怪の作り方」、「第三章妖怪図鑑」)では、江戸時代の出版物、芸能において、いかに妖怪の表象が、民間伝承の「信じられている妖怪」から変容して、娯楽として楽しまれたかが具体的に描かれている。しかし、香川氏の分析から読み取れるのは、近世後期の都市文化における娯楽としての妖怪表象が民俗社会から自立したというところまでであって、「日本の妖怪観の変容」(香川、p18)というのは風呂敷のひろげすぎである。キャラクター化されていない妖怪は現代でも伝承されている。香川氏自身が自らのフィールドワークの経験から、奥能登海岸部の「ミズシ」、徳島県の「犬神」の例を挙げている。少し長くなるが、『江戸の妖怪革命』から引用する。
石川県や徳島県が日本ではないというならともかく、視覚的なイメージでキャラクター化されていない「民間伝承としての妖怪」の伝承者は『江戸の妖怪革命』の視野からくくりだされただけで、現代でも生きていることを香川氏自身の証言によって明らかだろう。
香川氏の議論は実質的には「民間伝承としての妖怪とフィクションとしての妖怪」という対立項を軸に展開され、近世後期に前者から後者へと妖怪観が変容したと説くのだが、この仮説が説得力を持つのは都市の出版文化に限られているように見える。だとすれば、「民間伝承としての妖怪」と「フィクションとしての妖怪」との間の分割線が都市と地方との間に引かれるのであればまだわかるが、香川氏はそれを十八世紀後半という時間軸上に引いている。しかし、それだけであれば、「日本の妖怪観の変容」を「近世都市文化における妖怪観の変容」と書きかえればすむことである。本稿で考えたいのはむしろ「民間伝承としての妖怪とフィクションとしての妖怪」という対立項を設定することがいかなる意味を持つのか、ということである。
「民間伝承としての妖怪」は「フィクションとしての妖怪」と対になって持ち出された表現で、香川氏は当初「民間伝承や噂話などのなかで現実に語り継がれ、あるいは信じられてきた妖怪」と書いていた。その例が奥能登海岸部の「ミズシ」、徳島県の「犬神」である。フィールドワークでその伝承に触れた香川氏は「妖怪たちの原郷である「民俗社会」においては、その視覚的なイメージが伝承されていることのほうが少ない」(香川、p30)ことに驚いた。
それではその歴史的条件とは何かという問いが、香川氏の研究の出発点であったらしいことは「文庫版あとがき」(p308)でも述べられている。香川氏は不可解な事柄を理解する生活の知恵として妖怪を語る人々に出会っていた。彼らに対して、おそらく自身を含む「現代の多くの人びと」が「妖怪と聞けばやはり何らかの図像を思い浮かべる」のはなぜか? そうした妖怪認識を生み出した歴史的条件とは何か? を問うたのである。
しかしながら、「民間伝承における妖怪のあり方を本来的なものとすれば」、それを「民間伝承としての妖怪」として「フィクションとしての妖怪」に対置するとはどういうことか。通常、フィクションの対義語はノンフィクションであり、虚構の対義語は事実ではないだろうか。
現実の民俗社会に生きる人々は妖怪を「民間伝承として」語ったりはしない。「民間伝承としての妖怪」とは、民俗学的知の対象ということである。さらに言えば、妖怪を「民間伝承として」理解するのは、民俗社会を生きる人々自身ではなく、それを対象として調査する民俗学者(人類学者・社会学者・宗教学者etc)である。そして民俗学系妖怪学のなかには柳田国男「妖怪名彙」(柳田『妖怪談義』)にみられるように収集と分類を志向する博物学的視点がすでに含まれているのだから、それは「表象」である。つまり、「民間伝承としての妖怪」と「フィクションとしての妖怪」という対立項は、表象という点では同じレベルで成立している。
このように見てくると、香川氏の図式は、野家氏のものとそう変わらない。「民間伝承としての妖怪」と「フィクションとしての妖怪」という対立項が、表象空間上の、あるいは二つの表象空間の対立だとすると、その外部があったはずである。香川氏はフィールドワークで表象の外部に触れたことがあったはずだ。だが、香川氏はその境界の手前で引き返し、「フィクションとしての妖怪」を内側から描くことに専念したのである。それは「想像力で産み出した非日常的な世界」(野家)であり、「理性の外部」を想像され得るものの範囲に置き換える作業によって成立する領域である。
幻視された自己としての幽霊
香川雅信『江戸の妖怪革命』は「第四章妖怪娯楽の近代」で幽霊を取り上げる。交感魔術と親和的な類似の原理の時代(中世・近世前期)から、表象空間が自己言及的に完結する表象の時代(近世後期)を経て、「人間」が知の特権的な対象としてせり出してくる近代へというフーコー『言葉と物』の図式を借りて、明治以降の妖怪観・妖怪認識を描く。幽霊はそのなかで論じられる。
こうした香川氏の歴史叙述に異議はない。ただし、妖怪観が変わった理由はフーコーの図式によるからではなく、明治政府の国策として文明開化、すなわち学術の西欧化が選ばれ、その具体化として学校教育がおこなわれたからだろう。経緯はともかく、明治の開国によって、西欧で誕生した近代知の支配に日本社会は呑み込まれた。近代的個人は不透明な「内面」を抱え込むことになり、「「私」そのものが「私」にとって「不気味なもの」となる」(香川、p260-p261)。
「エピステーメー」もフーコーの用語だが、自然から人間への関心の移行はフーコーに依拠しなくても社会変動から説明しうるように思われる。それはともかく、幽霊とは、人間自身の不気味さの投影、近代的個人の不安、コンプレックス、トラウマ…etcの投影であるとするなら、やはりフロイト説の変形である。この香川氏の幽霊観にも、妖怪を論じたときと似たような分割線が引かれている。民俗社会と同様に表象の向こう側に追いやられているのは「「私」にとってのリアリティ」(香川、p260)である。「私」は「心霊」の言い換えとして登場する。
厳密には、デカルトのコギトには内面がない。一般に内面を構成すると思われている記憶や感情や想像など(もちろん夢や幻も)を切り捨てたところに成立するのが「われ思う、ゆえにわれ有り」の「われ」である(デカルト『省察』ほか参照)。コギトは構成されない。
しかし、引用した香川氏の叙述で注目したいのは、「内面」を持つ存在としての「私」についての観察である。不可視で、不透明な、自然(物的対象)と違いコントロールのできない、「私以外」と厳然と区切られている「私」。理解不可能、管理(操縦)不可能、同化不可能。これらは自己の特徴でもあろうが、むしろ自己の対概念である他者の特徴として捉えることもできる。
香川氏は「筆者の知人にも、「霊感」が強いと自他ともに認める者が何人もいて、そのような体験談を聞かされることがしばしばある」と言う(香川、p267)。その「「私」にとってのリアリティ」(香川、p260)とは、「他の人間が見えない恐ろしいもの(とりわけ幽霊)を見てしまう、というたぐいの話」をする(筆者=香川氏にとっての)「他者」のリアリティであり、かかる他者の「内面」は、理解不可能、管理(操縦)不可能、同化不可能なのである。
結局、香川氏の議論は、江戸時代の妖怪を語る際も、近代の幽霊を語る際も、同じ操作をしている。妖怪や幽霊を実生活の体験上の事柄として語る人々の括り出しである。香川氏がそうした人々の存在を知らないわけではない。フィールドワークで出会っていたし、交友関係のある知人にもいる。そして、怪異を語る人々の存在が「妖怪の原卿」であることも承知している。にもかかわらず、彼らとの間に生じた違和感を自己の現在の側から解消しようとする傾向があるため、異界を語る他者は困った存在になり、文庫版『江戸の妖怪革命』は、日常への回帰を説く文章で結ばれることになる。
異様さを救い出す
怪談は、それが創作であろうが、信仰の一部であろうが、妖しさを失っては成り立たないだろう。もし私たちが、怪異、忌わしく恐ろしいものや、それを語る人々を遠ざけ、厄介払いしてしまうなら、怪談文化自体がその供給源を離れ、やせ細ってしまうのではないだろうか。
それでは、私たちは怪異を語る他者、またその語りが示す他なるもの、その領域としての異界に、どのように接触すべきか。
怪異との遭遇は、運よく自らが経験したのでない以上は、コミュニケーション可能な他者から、その経験を聞く他ない。「とにかく一遍、何でも彼でも受け容れてしまう」とは折口信夫の平田篤胤評(「平田国学の伝統」『折口信夫全集第二十巻』中央公論社)にある言葉だが、不思議な経験をしたという人に出会えたら、まずは虚心にその話を聞くほかに怪異に迫る出発点はないように思う。内容の吟味や背景の詮索はそのあとの話だ。
心霊体験談の特徴は、私たちが慣れ親しんだ日常の感覚ではとらえきれないものについての物語であることだ。
心霊体験は驚愕や恐怖を伴って体験される。それは物語の構成や表現によるのではなく、体験そのものに深く結びついている。例えば次の体験談はどうだろう。
この体験談を呼んで背筋が凍った、という人は、よほどナイーブな人か、さもなければ似たような状況下で恐怖を味わったことのある人くらいだろう。語り手本人も言っているように、こうした話は「けっこうそこらで聞いたことがあるような」話であり、実際、類話も多い。
だが、語り手は本当に怖がっている。その理由を「あれだけ近くに霊を感じ、さらに重さまで感じたのは初めて」だからと述べている。ここに心霊体験の特徴が表れている。
この語り手は「霊感が強い家系」に生まれ、これまでも幽霊らしいものを目撃したことがあった。よく「視る」人は、いちいち驚いてなんかいられない、という醒めた態度でいることが多く、この語り手もそれまではそうしてきたようなのだが、このときばかりは怖かった。それは従来とはちがう異様な体験だったからである。この体験の異様さを理解することが心霊体験談を聞く(読む)ということである。
しかし、その異様さも通用している物語の類型(この場合は金縛り体験談)で語ることにより、「けっこうそこらで聞いたことがあるような」話になってしまい、幽霊を見慣れた彼ですら震え上がった恐怖が伝わらなくなってしまうのである。
怪談の解釈学の目指すものは、体験を語る物語の類型が語られた体験に与える影響を、民話学などを参考にしながら中和し、「よくある話」「よく似た物語」から体験の異様さを救出することにある。
この異様さとは何かということは、体験者一人一人によって感じ方が異なるので、一つ一つの体験談にていねいにつきあって解きほぐしていくほかない。
★プロフィール★
広坂朋信(ひろさか・とものぶ)1963年、東京生れ。編集者・ライター。著書に『実録四谷怪談 現代語訳『四ッ谷雑談集』』、『東京怪談ディテクション』、『怪談の解釈学』など。ブログ「恐妻家の献立表」 Web評論誌「コーラ」26号(2015.08.15)
<心霊現象の解釈学>第8回:「不気味なもの」の向こう側へ(広坂朋信)
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2015 All Rights Reserved.
|
| 表紙(目次)へ |