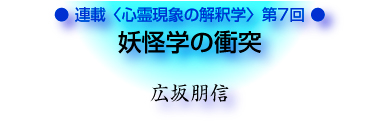|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「La Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
|
これまで、このわがまま勝手な断続的連載でカント、ヘーゲル、エンゲルス、ベルクソンの心霊現象論を見てきたが、私自身が共感するのはカントとベルクソンである。
ヘーゲルの場合は自らの哲学体系と一致しないから骨相学を否定し、逆にメスマーの動物磁気説については自らの哲学体系に親和的であるから肯定したという印象がある。いずれにしてもヘーゲルは伝聞によってしか情報を得ていないし、しかもその理論しか見ていない。
エンゲルスの骨相磁気学批判、交霊術批判は実証精神にあふれている点で好感が持てるが、やはり否定のための検証という印象がある。とはいえ、心霊学的には、具体例を検討しないで動物磁気説に引っかかったヘーゲルより、実例を自ら検討したエンゲルスの方がはるかにましであるし、骨相磁気学が一種の催眠術、交霊術に至ってはトリックであり、むしろ問題はこれにひっかかる科学者の側だという指摘はまことにごもっともである。
私がカントとベルクソンを評価するのは、両者とも、理論上はありうるとしながら、具体例を検討してその難点を指摘している点である。彼らが検証した事例は心霊現象というより、夢物語や風説・噂であったり、心理現象であったりしたが、だからといって一般論として霊魂を否定するものではない。ある意味でごく常識的な結論のように見えるが、問いに開かれた探究的態度といってよいように思う。
明治の妖怪学
シジウィックらが英国心霊研究協会(SPR)を創設(1882年)し、のちに同協会会長に就任したベルクソンが「生きている人の幻と心霊研究」と題した講演(1913年)を行った時期、十九世紀末から二〇世紀初頭とは、日本ではちょうど明治(一五年)から大正の初めにかけての時代にあたる。いわゆる文明開化の勢いに乗って西洋の文物が急激かつ大量に日本に流れ込んだ時代である。明治一七年(1884)には、テーブル・ターニングが伝来し「こっくりさん」として東海・近畿地方で流行するなど、そのなかには心霊主義がらみのものも含まれていた。欧米のスピリチュアリズム流行の波紋が、さほど間をおかずに東洋の島国に到達していたのである。
明治期の日本で、到来した西欧心霊主義への反響のうち、心霊学の観点から興味深いのは、
妖怪学というと現代では民俗学系の妖怪研究のことを指すが、元来、この言葉を使ったのは井上円了が最初である。欧米から流入した近代科学との緊張関係のなかで怪異を位置付けようとした点で、近世の儒学系の鬼神論とも、のちの民俗学とも異なる視覚を切り拓いた。なお憶測だが、「妖怪学」というネーミングはホッブズ『リヴァイアサン』にも出てくる悪魔学(デモノロジー)がヒントになったのではないか。
さて、これまで井上円了の妖怪学といえば、円了自身がモットーに掲げた迷信打破という面だけが強調されてきた傾向がある。特に日本民俗学の祖・柳田国男が円了妖怪学に否定的だったことから、柳田民俗学と対比させるかたちで円了妖怪学は合理主義哲学者の啓蒙活動という枠におしこめられてきた感があるが、はたして円了妖怪学とはそれだけにつきるものだろうか。井上円了は単なる哲学者ではなく、同時代の清沢満之と同様、西洋哲学の洗礼を受けた浄土教の信仰者であり、仏教の近代化を企てた宗教者という顔も持っていた。そうした円了がとおりいっぺんの科学主義者と同じスタンスで怪異を扱ったとは思えない。
円了妖怪学を再評価する方向で柳田民俗学と比較した研究成果としては、
なお、以下の叙述は「宮田妖怪学再考」と題して旧著『怪談の解釈学』(2002、希林館)に寄せた文章の一部をリメイクしたものであるが、同書は版元の廃業とともに絶版となっていることでもあるし(本誌『コーラ』の〆切も迫っていることだし…)無精をお許し願いたい。
宮田妖怪学再考
生前、日本民俗学界の中心人物であった宮田登氏は、日本民俗学の性格上、柳田国男の系譜に連なることは間違いないのだが、他のテーマでの研究はさておき、こと妖怪学に関しては単純な柳田民俗学の信奉者ではなかった。その一つの例が柳田民俗学と真っ向から対立した井上円了の妖怪学を再評価したことである。
円了の妖怪学は妖怪を一律に迷信としたことで柳田からは揶揄気味に否定されているが、一律に迷信としたからこそできたこともある。
柳田の妖怪の定義は零落した信仰の末期状態というものであり、こうした定義を前提とする妖怪学は、現代では失われてしまった古代の信仰の内実を究明するという方向性を持つ。したがって柳田妖怪学は、想定されうる古代の神々に結びつかない怪異を研究対象から除外する。陰陽道や道教など海外から伝えられた宗教文化の影響を受けた異神たちや、仏教説話に登場する幽霊たち、近代になって西洋文化の影響を受けた心霊たちは柳田の考察の対象とはならない。つまり怪異についての資料の取捨選択が、柳田民俗学の日本文化観によって制約を受ける、少なくとも方向付けられている。
対して円了は資料の性格による取捨選択をしない。円了の生きた時代に伝えられていたものをほぼ網羅的に扱っている(『井上円了・妖怪学全集』全六巻、柏書房を参照)。
それが迷信として否定するためではあったとしても、偏りなく、多量に怪異の伝承を収集できたのは、円了妖怪学の成果である。この点を宮田氏は率直に評価した。
円了妖怪学と柳田民俗学
宮田氏が円了を評価したのは、収集した怪談の量だけではない。円了の網羅的な収集を可能にした怪異観、真怪と仮怪の区別についても、民俗学者としては意外なほどていねいに論じ、そして、私の印象では肯定的な評価をしている。
円了は、怪異を分類して全体を仮怪と真怪にわけ、仮怪は錯覚、虚偽、誤認などとして説明できるものとし、説明できないものを真の怪異、真怪とした。この真怪が先に引用した文章で宮田氏が「その結論はともかくとして」と保留した円了の結論である。その内容を宮田氏の整理によってみてみよう。
まず、宮田氏はこのように不可知なものとしての大自然として円了の真怪を理解した。この理解は円了の研究者のなかには異論もあろうが、いまは宮田氏の考えを追うことを第一にする。私自身の理解をいえば、大筋その通りだが、「大自然」という語にアニミズム的なニュアンスを読み込むとしたら円了自身の意図からは逸れることになると思う。合理的な思惟の果てに想定される不可知なものとしての真怪とは、円了が尊敬していたカントの物自体に近いものだろう、というのが私の意見だ。
さて、宮田氏は、円了妖怪学と柳田民俗学を比較して次のようにいう。
このように円了妖怪学と柳田民俗学の不思議への態度を比較し、さらに、円了妖怪学が妖怪(真怪+仮怪)を「人間の心より生ずる」ととらえていることを述べている。
宮田氏は民俗学者なのだから、最終的には柳田民俗学に軍配を上げるはずだという見込で読み込めば、妖怪を人の心の迷い、迷信として切って捨て、愚昧な大衆を哲学によって啓蒙しようという円了妖怪学を見限り、「妖怪は妖怪として不思議なものとして人々が信じているのであり、その信ずる精神構造を問題にしようとした」民衆に優しい柳田民俗学を称揚しているように読めば読める文章である。ところがその見込は当てがはずれるのである。
引用文の後も円了と柳田の比較をしながら、宮田氏はついに次のように結論する。
しょせん井上は近代合理主義の啓蒙家で、というような批判はとうとうなされないまま、先に引用した円了の資料収集を賞賛する言葉で「妖怪のとらえ方」と題された章は締めくくられる。あらためて再掲しよう。
まことに公平な態度といわざるを得ない。しかし、それは単なる公平だろうか。繰り返すが、宮田氏は民俗学者なのである。
日本民俗学は柳田国男という人物の思想によって方向付けられている。迷信撲滅運動を唱導した円了は学祖・柳田の敵なのだ。立場上敵対する考え方に公平であるということは、ホンネの部分では、シンパシーを感じていたと想像してもよいのではないか。
不可知なもの
私は、宮田登氏は、民俗学の祖、柳田国男よりもその敵、井上円了に共感する部分があったのではないかと考えている。宮田氏が円了に共感したのは真怪、「不可知なもの」を妖怪研究の前提として想定する態度であろう。
もちろん円了の真怪は形而上学上の存在であり、妖怪と呼ばれる精霊たちではない。他方、柳田は妖怪を民間信仰の事実として承認し、「その信ずる精神構造を問題にしようとした」。ここから妖怪を迷信として否定する近代主義者円了と、妖怪を認め、妖怪を信ずる民衆に暖かいまなざしを注いだ柳田という通俗的な対立の構図が生まれた。
しかし、柳田民俗学は妖怪の存在を肯定していたのだろうか?
そして、円了妖怪学は妖怪の存在を否定していたのだろうか?
柳田国男や井上円了の個人としての信念はここで忖度しない。そして、柳田民俗学と円了妖怪学そのものの全体像についても考慮しない。宮田妖怪学が二人の先達の学問から何を引き継ごうとしたのかに焦点を絞れば、結論は通説の逆となる。
語り得ないものについては沈黙を守るという近代科学の禁欲主義に準拠して、妖怪のリアリティーを人の心の問題として一括処理し、語り得るものとしての妖怪、すなわち「その信ずる精神構造」のみに問題を限定して扱う近代的な学問としての妖怪学(民俗学)を立ち上げたのは円了ではなくむしろ柳田国男である。柳田民俗学における妖怪研究の目的は「通常人の人生観、わけても信仰の推移を窺い知る」(柳田、『妖怪談義』筑摩書房)ためであり、妖怪のリアリティーは不問に付されている。
妖怪が「ないにもあるにもそんなことは実はもう問題でない」という態度で研究する柳田民俗学は、なるほど「腹の底から不思議のないことを信じて、やっきとなって論弁した妖怪学時代がなつかしいくらいなもの」(柳田、前掲書)と円了を揶揄できるほどに近代的な学問なのだ。柳田民俗学の枠内で妖怪を研究する限り、すべての妖怪を「零落した信仰の末期現象」を示す資料としてあつかうわけだから、そこに「不可知なもの」は影も形もない。古代の信仰の内実のように未知なものはあるが、それは研究の進展によってやがては解決される課題とみなされる。
もちろん柳田自身も「幻覚の実験」(柳田、前掲書所収)にみられるような不思議な体験を書きのこしているが、彼が作りだした学問としての民俗学の内部では、研究者が狐狸妖怪に誑かされる心配も、怨霊に祟られる恐れもない近代的な空間に身を置いて民衆の精神構造から古代信仰を再構成することができる。そういう仕掛けになっているのが柳田民俗学である。
一方で真怪を追究しつづけた井上円了は、結果としていかに多くの怪異を迷信として否定したとしても、あくまでも人知を越えた存在、不可知なものが存在することを前提として、それは何かと問い続けた。そして妖怪を「その信ずる精神構造」に還元することなく、現実の課題として正面から論じた。
結果として円了妖怪学は、従来の妖怪を仮怪として退け、形而上学的存在を真怪とせざるを得なかったが、「不可知なもの」を問う姿勢は常に維持された。だから円了が「腹の底から不思議のないことを信じて」いたはずはないのだ。「不可知なもの」の在処がどこに定まるかは、円了自身の世界観を直接揺さぶる問題として意識されざるを得ない。円了妖怪学は「その結論はともかくとして」、幽霊や妖怪を真剣に怖がりながら探究するものの学問なのである。
産女(ウブメ)の事故
円了妖怪学についての宮田氏の解釈が私の理解の通りであるかどうかについては、ポジティブに論ずる材料をもたない。しかし、宮田氏が一見すると合理主義的・近代的な円了妖怪学に「不可知なもの」への本気の態度を感じ取り共感していただろうことは、的はずれな憶測ではないと信じる。
傍証にすぎないが、『妖怪の民俗学』には宮田氏が「不可知なもの」の顕現に、柳田民俗学の近代性とは異質な感慨を漏らした文章がある。
宮田氏は「一人の中年女性の車が暴走して小学生の列に車を突っ込み、十四人の小学生を車ではねてしまった」という週刊誌の記事に注目して、「不思議な記事だった」と述べる。
宮田氏は週刊誌の記事を引用しながらこの交通事故の不思議を指摘している。それによると現場は三辻で、事故を起こしたいすゞピアッツァは時速約四〇キロ前後で走行、ブレーキも踏まず反対車線を横断して歩道の子供たちに突っ込んだ。「一部新聞には居眠りと書いてあったが、居眠りではない。飲酒運転でもない。薬物でもない。精神病の経歴やその他の病気による発作でもないという」(宮田、前掲書より『週刊新潮』昭和五十九年五月三十一日号の記事)。
それではなにが起きたのか。運転していた女性は次のように話したようだ。
そして宮田氏は次のような驚くべき推測を述べる。
ここで宮田氏は、「憶測をほしいままにすれば」と遠慮がちに言いながら、その「憶測」は次のように肉付けされ、積極的に説かれていく。
さらに宮田氏は、事故現場となった土地が「産女」と名付けられたのは、江戸時代に「牧野藤兵衛という者の妻が妊娠中にこの地で死んだので、その霊が産女明神として祀られ、それ以後この名前がついたといわれている」(宮田、前掲書)という伝承に触れ、産女明神は現在でも安産の守護霊として近隣の女性たちの信仰を集めていると指摘する。そして次のような結論にいたる。
宮田氏が「読者の想像にまかせる」というのはレトリックにすぎない。私はこの文章から、宮田氏が産女の出現を確信していることを感じさせられた。それはアカデミックなキャリアをつんだ民俗学者としては交通事故のようなものだったのかも知れない。宮田氏は産女に衝突したのだ。
フォークロア(民間伝承)という呪文
先に引用した文章の前段に注目してほしい。「このような言い伝えのある土地に産女がよみがえってきてもフォークロアの世界では決しておかしくない」と宮田氏はいう。確かに「フォークロアの世界」でならありえることだろうが、ここで問題となっているのは、現実の交通事故である。話が違う。
現実の事柄をもフォークロアとみなしてよいのか。それとも宮田氏はこの世のすべてをフォークロアと同次元に置いて、すべての知識・情報を民間伝承として解釈し直す汎民話主義を唱えているのだろうか。もちろん宮田氏がそんなことを考えていたわけではない。
さらに「とりわけ辻に妖怪変化があらわれるという前提からいえば、辻が持っている霊的な力が民間伝承として現代に発現してきているということになるのかも知れない」という文章も奇妙だ。
仮に「辻に妖怪変化があらわれるという前提」を受け入れたとしよう。さらにその前提である、辻が「霊的な力」を持っていることも承認することにしよう。この場合、辻に霊的な力があるかどうかは事実のレベルで語られているはずだ。そうであるならばなぜ「民間伝承として現代に発現」したと語るのかについては理解に苦しむ。繰り返すが、ここで問題となっているのは、現実の交通事故である。都市伝説や流行神の発生を論じているわけではないのだ。
穏当に解釈するならば、この文章は「産女」という地名が事故車のドライバーの心を刺激しておばあさんの幻覚を見せた、ということを言いたいのだとしてすますこともできる。これは怪異を個人の心の問題に還元する理解の仕方であり、一種の合理主義的態度である。
しかし、もしそうなら、なぜ宮田氏は「この話は理屈の上ではナンセンスと思いつつ、さりとてすべて偶然の一致ということで決着がつくものなのか」と疑問を投げかけたのだろう。地名が深層心理を刺激して産女のイメージを呼び起こしたと説明するのも、「偶然の一致」とするのと負けず劣らず合理主義的な態度である。「理屈の上ではナンセンス」とはとても思えない。
宮田氏がここで思い至った「理屈の上ではナンセンス」なこととはなにか。それは、現実の交通事故の発生を「フォークロアの世界」のこととしたり、「民間伝承として」の発現としたりする、前後の文脈とは矛盾した言葉を差し引いて読み替えればわかる。すなわち次のようなことだ。
「このような土地に産女がよみがえってきても決しておかしくない。とりわけ辻に妖怪変化があらわれるという前提からいえば、辻が持っている霊的な力が現代に発現してきているということになる」
こう宮田氏は思ったのに違いない。これなら確かに通俗的な合理主義では受け入れられない「理屈の上ではナンセンス」なことである。
このとき宮田氏は、怪異を同時代の現実として受けとめてしまった。そうなるともはや「ないにもあるにもそんなことは実はもう問題でない」という柳田民俗学の近代的な安全装置は作動しない。ないのかあるのか「やっきとなって論弁」しなければすまない円了妖怪学の領域に問題は移行するのである。
それならそうと率直に言えばよいではないか、と思われる人もいるかも知れない。だが、それは民俗学者としてはできない。産女の出現を現実のこととして語ることは、妖怪の実在/非実在を不問にし、零落した信仰の末期現象として扱うことで近代的な学問としての正統性を確保した柳田民俗学の境界の外に出ることになる。「フォークロアの世界では」とか「民間伝承として」という余計な限定は、柳田民俗学の境界の外にはみ出てしまった宮田氏が、襲いかかる悪鬼・悪霊から身を守るためにとっさに唱えた呪文だったのではないだろうか。
「真怪」の役割
宮田妖怪学にも、怪異を結局は心の問題とする傾向は顕著にある。しかし、凡百の心理主義に比べて宮田説が優れているのは、先に示した静岡市産女の事故のケースに見られるように、民俗学という近代的な学問の枠をはみ出してまで、妖怪の出現をできるだけ事柄に即してとらえようとする点である。
少なくとも怪異のなかには人知による説明が不可能なものがあり、それについては「出た!」と言ってしまうよりほかに道はない、と受けとめる感性を宮田妖怪学は持っていた。
一方で、井上円了が検証した大量の怪談のなかに、円了をして「出た!」と言わしめたケースは結果としてなかった(円了先生、内心ではさぞや残念だったろう)。だが、結果はどうであれ、円了は怪異を原理的に否定してはいない。不可知なものの存在は可能性としては担保されていた。それが円了妖怪学の「真怪」である。
円了の「真怪」はカントの「物自体」によく比較されるが、物自体を『純粋理性批判』の文脈でだけとらえると円了の真怪も抽象的な存在に思えてくるだろうが、物自体はカント『実践理性批判』の文脈では叡智界に結び付けられる。そしてカントがスウェーデンボリの「霊界」に関心を持ったのは、それが自らの構想にあった叡智界と似ているように感じたからだった。「真怪」や「物自体」は、単に抽象的な意味での不可知の領域というだけではないのである。
宮田氏が例に挙げた静岡市産女での交通事故が、はたして人知による説明が不可能なケースかどうかは異論もあり得るだろう。私自身、この事故のニュースの何が宮田氏の琴線に触れたのか、正直なところよくわからない。しかし、柳田民俗学のように、あらかじめ題材の選択やその扱い方を制約していないという点で、宮田妖怪学と、それを通してみた円了妖怪学には共通する態度があり、それはカントやベルクソンの、問いに開かれた探究的態度とも通じるように思う。
★プロフィール★
広坂朋信(ひろさか・とものぶ)1963年、東京生れ。編集者・ライター。著書に『実録四谷怪談 現代語訳『四ッ谷雑談集』』、『東京怪談ディテクション』、『怪談の解釈学』など。ブログ「恐妻家の献立表」 Web評論誌「コーラ」24号(2014.12.15)
<心霊現象の解釈学>第7回:妖怪学の衝突(広坂朋信)
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2014 All Rights Reserved.
|
| 表紙(目次)へ |