|
|
|
Web�]�_���u�R�[���v |
|
���n���̎� ���{���̕\���i�ڎ��j�� ���{���̃o�b�N�i���o�[ ���ǎ҂̕Ł^���ӌ��E���z �����e�K�� ���W�҂�Web�T�C�g ���v���C�o�V�[�|���V�[ |
|
���{���̊֘A�y�[�W�� |
|
���u�J���`���[�E�������[�v�̃o�b�N�i���o�[ ���]�_���ula Vue�v�̑��ڎ� |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
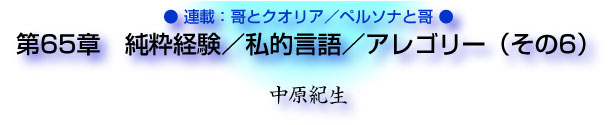
|
|
�i�{�����̉����̓����N�������Ă��܂��B�܂��A�L�[�{�[�h�F[Crt +]�̑���Ńy�[�W���g�債�Ă��ǂ݂��������܂��B�j
�@
���t�B�����Ɖf���̔�g�A�S�̒m�E�ƍݒm�E�}�̒m
�@
�@���ɁA���̒��̕������߂���Ζ��瓹�q�̃G�b�Z�C���猩���Ă����ӂ��̎����̂����A���̌�i�̘_�_����肠���܂��B���Ȃ킿�A���I���ꂪ�A���̐��Ƃ��̐��̒��ԗ̈�ʼnғ����邱�Ƃ��߂����āB
�@
�@�����ŁA�i��ώ��́u�t�B�����Ɖf���̔�g�v�����p���܂��B
�@�E�B�g�Q���V���^�C���́w�N�w�I�l�@�x��l�߂ɁA���̂����肪����܂��B�u�c���݂Ƃ́A�f�ʋ@�̃����Y�̈ʒu�ɂ��傤�ǂ��܂���t�B�����̑т̉f���̂��Ƃł͂Ȃ��B�i���j���ܖ��ɂȂ��Ă���̂̓X�N���[����̉f���ł����āA���ꂪ�s���ɂ����݂ƌĂ�Ă���B�Ƃ����̂��A���̏ꍇ�u���݁v�͉ߋ��Ɩ����ƑΗ�������̂Ƃ��Ďg���Ă͂��Ȃ�����ł���A���������Ă���͖��Ӗ��ȏC����Ȃ̂ł���B�v
�@�i��ώ��́w���E�̓ƍݘ_�I���ݍ\�������N�w�T���Q�x�̑�W�́u���Ȉӎ��Ƃ͉����v�ɂ����āA�u�t�B�������a�n��ƁA�X�N���[����̉f�����`�n��ƁA���ꂼ����߂���킩��₷���B�v�Əq�ׂ������ŁA�E�B�g�Q���V���^�C���́u���v�����̂悤�Ɏw�E���Ă��܂��B�i�`�n��A�a�n��̓}�N�^�K�[�g���w���Ԃ̔���ݐ��x�ɂ����ē��������T�O�B�}�N�^�K�[�g�́A���Ԃ̖{���͏o�����̑O��W�i�a�n��j�ł͂Ȃ��A�ߋ��E���݁E�����̋�ʁi�`�n��j�ɂ���Ƃ����B�j
�@�����ŁA�i�䎁�������u�t�B�����̓��e�i�o�����j�v���Ȃ킿�u���ݐ��E�v���u���ݐ��i���A���e�B�j�v�̗̈�i������ƌ���̐��E�j�ƁA�u�X�N���[����ɂ���f���v���u���ɂ��鐫�v���Ȃ킿�u�������i�A�N�`���A���e�B�j�v�i��������̌������j�̗̈�ƁA���ꂼ����߂���A�b���킩��₷���Ȃ�܂��B
�@�����Ō�����A�V�g�����u�Œ���̎����v���Ƃ́A�ʂ̂Ƃ���Łu�����̂̂����v�ƌĂ�Ă����̂Ɠ������̂ł��B�����i�䎁�͂Â��āA�����ɂ́u�O��̒m�v������Ə����Ă��܂��B
�@���āA�ȏ�̋c�_�����ƂɁA�u�����i����j���t�B�������X�N���[���v�̉f��̃��J�j�Y����}�����A�����ɁA�u����v�i���̐��j���Ȃ킿�A�N�`���A���e�B�̗̈�i�y�`�z�j�Ɓu���ʁv�i���̐��j���Ȃ킿���A���e�B�̗̈�i�y�q�z�j�Ƃ̒��ԗ̈�i�y�l�z�j�A����ΓV�g�I�̈�ɕ��シ��u���̒��̕��������I����v�̓�����`������ł݂܂��B
�@
�@�@�@�s�}�P�t�t�B�����Ɖf���̔�g�i��������j
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ��������
�@�@�@�@�c�c�c�c�c�c�c�E�c�c�c�c�c�c�c
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@�y�q�z������������������������������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ����
�@�y�l�z�@�@�@�@�@ �@�����������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@����
�@�y�`�z������������������������������
�@
�@���q�F�u�S�̒m�v�`�t�B����
�@�@�@�@�����E�̋q�ϓI�����ɂ��Ă̒m
�@�@�l�F�u�}�̒m�v�`�X�N���[����̉f���i���̓��e�̑��ʁj
�@�@�@�@���S�̒m�Ɠƍݒm��}���m�i�m�o�◈���̋L���j
�@�@�`�F�u�ƍݒm�v�`�X�N���[����̉f���i���ꂪ���݂̉f���ł���
�@�@�@�@�@���Ɓj���q���݁r��q���r�̒��ڒm �@
���t�B�����Ɖf���̔�g�A�єV�O�́E�Đ�
�@
�@�����ɁA���˂Ă���{�_�l�Q�i��11�͑��j�Œf���I�Ɍ��y���Ă����єV���ۊw�̒n���w�I�z�u�A���Ȃ킿�u�n�^�C�^��v�̊єV�O�̂̋c�_�A����ɂ́A��Ƙ_���w�̐��E�i���ꂪ���郁�^�t�B�W�J���Ȗ��̊E��j��g�ݓ��ꂽ�u�n�^�C�^��^�V�i���j�v�̎l�̘_�����܂��B
�@�єV�O�̂́A���́u�e����Δg�̒�Ȃ�Ђ������̋��킽���ꂼ��т����v�i�y�����L�ꌎ�\�����j����A�C�̒�̒�Ȃ�u�n�v�Ɓu�C�v�Ɓu��v�Ƃ����E��𒊂������A���̎O�̊E��̋����Ȃ���̊E�ʁA���Ȃ킿�u����i�C��j�v�Ɓu���ʁi�C�ʁj�v���X���b�V���ŕ\���������̂ł����B��Ǝl�̂̏ꍇ�́A����ɁA�u��v�Ɓu�V�v�̋����Ȃ���O�̊E�ʁi�V�U�Ƃł��j�������X���b�V������������Ă��܂��B
�@�Ƃ���ŁA���̊єV�̂ɂ͂����ЂƂ̊E�ʂ��o�ꂵ�܂��B����́A�u���ʂɉf������v�́u�����v�̂��Ƃł��B���̊E�ʁi�g�̒�Ȃ�u��v�j�́A�u���͂�Ԃ�_�̐S���r���C�ɋ������Ă����邩�ȁv�i�y�����L�ܓ��j�́u���v�A���Ȃ킿�i���ʂƂ͈قȂ�����ЂƂʂ́j�u���ʁv�ƂƂ炦�邱�Ƃ��ł���ł��傤�B
�@�������āA�u�n�i���[�w�j�^�C�i�Ő[�w�j�^�C�i�[�w�j�^��i�\�w�j�^�V�i���\�w�j�v�̐}���������܂����B������Ăсu�t�B�����Ɖf���̔�g�v�̐}�ɁA���������x�͌����������ɐ����āA���A���̃p�[�X�y�N�e�B���̓��Ԙ_�i�Ǝ��I����̎l�ތ^�j�����������āA�\�����Ă݂܂��B�i�}���́y�u�z�̓��@�[�`���A���e�B�̈Ӂm���n�B�܂��y�l�z�̓~�f�B�A���ɉ����~���[�A�~���[�W�����܈ӁB�j
�@
�@�@�@�s�}�Q�t�t�B�����Ɖf���̔�g�i���������j
�@
�@�y�`�z������������������������������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@����
�@�@�@�@�@�@ �����������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@����
�@�y�q�z������������������������������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y�z
�@�@�@�@�@�@�@�@�o�P�@�́@�o�Q'
�@�@�@�@�@�@�@ �y���z�����y���z
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ����
�@�y�l�z������������������������������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y���z
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�o�R
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@�y�u�z�c�c�c�c�c�c�c�E�c�c�c�c�c�c�c
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ��������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�o�S
�@
�@���q�F�u�S�̒m�v
�@�@�l�F�u�}�̒m�v
�@�@�`�F�u�ƍݒm�v
�@�@���F�q����r���߂��鎄�I����i�o�S�˂o�R�j
�@�@���F�q�����r���߂��鎄�I����i�o�S�˂o�Q'�A�o�R�˂o�Q'�j
�@�@���F�q �� �r���߂��鎄�I����i�o�S�˂o�P�A�o�R�˂o�P�j
�@�@�F�q �� �r���߂��鎄�I����i�o�P�̂o�Q'�j
�@
�@���������I��H���o�āA�i�܂��A�����̎����ɂ��āA�[���ȋᖡ�E�������قǂ����Ȃ��܂܁j�A�悤�₭�O�̖͂`���Ɍf�����_���A���Ȃ킿�A������̌������������A��O�A��l�ތ^�̎��I����ɂ��Ďv�Ă��ׂ��ꏊ�ɋA�҂��܂����B
�@�����܂ł̋c�_�𗐖\�ɑ�������ƁA�����́A�q����r���߂�����i�K�i���ތ^�j�̎��I����Ɏ������i�K�̎��I����ɂ��A�����̈قȂ�ӂ��̃t�F�C�Y�������āA���̑O�i�i��P�t�F�C�Y�j���Ȃ��q�����r�̎��I����Ɓq���r�̎��I�����ʂ��āA�q���E�r����q��ԁr�Ɓq���ԁr�����ꂼ���o����A�����āA�݉c���ꂽ�q���܁E�����r�̃t�B�[���h�ɂ����āA��i�i��Q�t�F�C�Y�j�́q���r�̎��I����i���`�̎��I����j���N������A�Ƃ������Ƃ���ł��傤���B�i���Ȃ݂ɁA�N�_�ƂȂ�q���E�r�A���Ȃ킿�A�q��ԁr�Ɓq���ԁr������ȑO�́q����r�Ƃł�������̈��̂��A����Α�Z�t�F�C�Y�́q����r���߂��鎄�I����ł���B�r
�@
�m���n�����ł́u�A�N�`���A���e�B�i�L�`�j�����@�[�`���A���e�B�{�A�N�`���A���e�B�i���`�j�v�̊T�O�敪��O���ɂ����āA���́u�`���́v�̗��_�ւ̐ڑ����͂������B���܂ЂƂ̎��Ɋւ��Ă��u���A���e�B�i�L�`�j���C�}�W�i���[�{���A���e�B�i���`�j�v�̓������̗p����A�s�}�Q�t���́y�l�z�́y�h�z�ƕ\�L���邱�Ƃ��ł���B
�@�]�k�Ƃ��āB��������u��́w���҂̏��x�������c�Ĉ��ƃG�h�K�[�E�A�����E�|�[�v�i�w���{�ƉF���x�����j�̂Ȃ��Łu�܌��M�v����c���j�����������̉c�ׂ��A���̐l�����m�������w���V���ɔ����������̂ł���Ɛ錾����قǂ̉e���͂��������j�V�r�̕\���ҁv�ɂ��āu�|�[�Ɠ�����̓��{�ɂ����āu���҂����̍��v�������l���v�i20�Łj�ƋK�肵�����c�Ĉ��i�w��̐^���x�j�̋c�_�����p����Ȃ�A�s�}�P�t����сs�}�Q�t���́y�q�z�́u�����i������j�v�ɁA�y�u�z�́u�H���i�������j�v�ɊY������B
�@
����r�s�\�Ȃ��̂�����̔�r�s�\�����������Ĕ�r�\�Ȃ��̂ɂȂ�Ƃ����\��
�@
�@����ł́A�܂��A��P�t�F�C�Y�̎��I����A���Ȃ킿�q�����r�Ɓq���r���߂��鎄�I����ɂ��ĊT�ς��܂��B
�i�ŏ��ɒf���Ă����ƁA�ȉ��̋c�_�́A���߂��܂߂���߂đe���Ȃ��̂ł����Ȃ��B���Ƃ��q�����r�Ɓq���r���q��ԁr�Ɓq���ԁr�ɒP���ɒu�������Ę_���Ă�����A�܂����˂Ă��瘺�߂����Ă������I����ƕ��@�J�e�S���[�̊W�ɂ��Ă��G��邱�Ƃ��ł��Ă��Ȃ��B���ꂪ�����Ă��Ȃ���Ȃ�����}���̂��Ƃ����ƁA���ق���悤�����A���I����̎����i�Œ���̎������j�ɂ��Ę_����ׂ��ꏊ�͂����ł͂Ȃ��ƁA�i���������āA�u�����v���I�����u�ア�v���I����ɂ��Ė{�i�I�ɘ_����ׂ��ꏊ�������ł͂Ȃ��Ɓj�A�x����Ȃ���C���������炾�B�������ɍs���ċꂵ�ނ��ƂɂȂ�̂͊o��̂����ŁA�����ł͎��I����̒n���w�I�ʒu������߂邱�ƂɓO���邱�Ƃɂ����B�j
�@
�@�����b��l�E�c���Β��w�q�����r�Ƃ͉����������w�E�N�w����n�܂鐢�E���̓]���x�ɁA���ԂƋ�Ԃ��߂��鋻���[���c�_���W�J����Ă���̂ŁA���p���܂��B���킭�A���Ԃɂ��āA�����͒ʏ�u�ꎟ���I�Ȓ����I�����v���v�������ׂ邪�A���̂悤�ȋ^����ԓI�Ȏ��ԃC���[�W�́A���Ƃ͂Ƃ����u�B��́v���݂����݂Ƃ��Č��������邱�Ƃɂ���Ă������肦�Ȃ��B
�@���́u���ꕽ�ʏ�ł������ɂł��Ȃ����́v�ɂ����āA�u��ԁv���͂��߂ė����\�ɂȂ�B�n�}��̎O�_���a���b���`�Ɛi��ł��b���a���`�Ɛi��ł��u�����v�_�ɓ�������B���̂��Ƃ������A�u��Ԑ��v�̖{���Ȃ̂ł���B�u��萳�m�ɂ����A�Ⴄ�s�����Łu�����v�_�ɓ��B������A���ꂪ��ԓI�ƌĂ��̂��v�i83�Łj�B
�@�{���ɓY����ꂽ�R�����������I�Ȃ̂ŁA���łɈ��p���Ă����܂��B
�@���āA�ȏ�̋c�_��f�ނƂ��āA�������q�����r�Ɓq���r���߂��鎄�I����Ɂi�����Ɂj�֘A�Â��Ă݂܂��B
�@���p�����A��r�s�\�Ȃ��́i��F�B��̌��݁j���A����̔�r�s�\�����������āA��r�\�Ȃ��̂ɂȂ�Ƃ����\���A�Ƃ���̂́A�i��ώ����w���E���E�����Đ_�����J蓂̓N�w�x�ŁA�u����ȏ�k�s���悤�̂Ȃ��A���Â��邱�Ƃ����ł��Ȃ��͂��̊J蓂̊�ւ��A���̊J蓂̓����ŁA���̓����ɑ��݂����̑��ݎ҂Ƃ��Ĉʒu�Â����A���Â����邱�Ɓv�i42-43�Łj�Ə����Ă���̂ƁA�u�ɂ��������v�̊W�ɂ���܂��B
�@�Ȃ��u�ɂ��v�̂��Ƃ����ƁA��r�s�\�Ȃ��́A���Ȃ킿�u�����ē��ꕽ�ʂɉ���ł��Ȃ����́v�ɂ����ނ��邩��ł��B�i��L�����g���ĕ\�L����ƁA�A�N�`���A���ȁq�`�r�i�ƍݘ_�I���݁j�ƃ��A���ȁs�`�t�i�u���ꕽ�ʏ�ł������ɂł��Ȃ����́v�Ɣ�r�\�Ȕ�ނȂ����́j�B�����āA�w�q�����r�Ƃ͉����x�̋c�_�́A�����Ř_�����Ă����r�s�\�Ȃ��̂��A���F�s�y�́q�`�r�ł����Ă����ꉻ�\�ȁs�`�t�ł����Ă����������藧����ł��B
�i����A���m�ɂ́A���w�i�����_�j�ƓN�w�i�����ۊw�j�̃R���{���[�V�����ɂ���ē]�������u���E���v�Ƃ́u�����邱�Ɓv�̗��_�ł���̂�����A�����Ŏ��グ����ׂ��́u�����́v�i���q�@�r�v�ł͂Ȃ��u���ہv�i���s�`�t�j�ł���A�ƌ����ׂ���������Ȃ��B�����āA�u�����̂̂����v�i���q�`�r�j����鎄�I����i���Ƃ��Ήi��ς̓N�w�j���A����Ɓu�ɂ��������v�̊W�������̂��ƁB�j
�@���̂��Ƃ܂��A�����E�c�����̋c�_���i���Ȃ�̌�b�ɒu�������āj��������ƁA���̂悤�ɂȂ�܂��B
�@
�E�q�@�r�ˁq�Ӂr
�E�q�Ӂr�ˁq��ԁr�i�s��ԁt�ˁu��ԁv�j
�E�q�Ӂr�ˁq���ԁr�i�s���ԁt�ˁu���ԁv�j
�@
�@�����Łu�Ӂv�́A�u�`�v�i�����ē��ꕽ�ʂɉ���ł��Ȃ����́j��u����v�i���ԁ{��ԁj�ƕ\�L���Ă������̂ł����A���i�K�E��Z�t�F�C�Y�̎��I����ɂ���đ��q���E�r�̎������Ȃ킿�V�g�I��������\�����邽�߁A�J���g�\���̒����W���_���ӎ����č̗p���܂����B�i����́A���Ȃ킿�q�Ӂr�ƕ\�L����鐢�E�́A�w�����}�w�x�ł̒���V�ꎁ�̌�b���ؗp���āA�u����Ɖ��y�̐��܂�錴���̏ꏊ�Ƃ������ׂ������ԓI�ȋ����̋�ԁv�������́u���ԂƋ�Ԃ���ɗn�������āv�����Ă����u�،��I��ԁv�ł���ƌ����Ă������낤�B�j
�@���ɁA���i�K�E��P�t�F�C�Y�̎��I����̂����A�q�����r����鎄�I�����ʂ��ĉ\����тт��q��ԁr����A�q���r����鎄�I���ꂩ��g�̐������ꂽ�q���ԁr�̗̈悪�͏o����Ă���킯�ł��B�q�@�r�Ɓq�Ӂr���߂���u���ى��i�u����v�j�̍\���v����������A�u��Ԑ��v�̍\���Ɓu���Ԑ��v�̍\���i�u�o�����v�̍\���j������ƌ����Ă������ł��傤�B�i�u��Ԑ��v����u�C�}�W�i���i���j�^���A���i���j�v�̐��������A�u���Ԑ��v����u���@�[�`���A���i��j�^�A�N�`���A���i���j�v�̐����������ꂼ�ꗧ��������A���̓`���̂̍\�}��݂���ƌ����Ă�����������Ȃ��B�j
�@�����čŌ�ɁA�����[�w�̃v���Z�X���i�q���r�̎��I����̂͂��炫�Ƃ����܂��āj�\�w�ɂ����Ĕ�������A�s��ԁt�ˁu��ԁv��s���ԁt�ˁu���ԁv�̌����I�E�q�ϓI�v���Z�X�ւƕϖe����B
�@
���u�������s�\�Ȍ�ʂ��Ă̂ݒu�������\�ȕ��Ղ�_���邱�Ƃ��ł���Ƃ�������
�@
�@�Ō�ɁA���i�K�E��Q�t�F�C�Y�̎��I����A���Ȃ킿�A�q���r���߂��鎄�I����ɂ��āB�����ł��A�w�q�����r�Ƃ͉����x�̋c�_�����p���܂��B
�@�u�������s�\����ʂ��Ă̂݁B�u�������\����_���邱�Ƃ��ł���Ƃ����p���h�L�V�J���Ȏ��ԁi142�Łj�B���i���j�̒��̓ǂ߂Ȃ��������Ȃ킿�u�ʑ��݁v��ʂ��Ă̂݁A��lj\�ȈӖ���S�����I�ȕ������Ȃ킿�u���Ձv��_���邱�Ƃ��ł���Ƃ������ԁB�����ł��A�@�ƍݐ��́q���r���߂��鎄�I����i�q�@�r�ˁq���r�j�ƁA�A�P�Ɛ��́s���t���߂�����I����i�s���t�ˁu���v�j�́A�ӂ��̌�����H���d�ˍ��킳��Ă��܂��B
�@��P�t�F�C�Y�̎��I����ɂ���Đ݉c���ꂽ�q���ԁr�{�q��ԁr���q���܁E�����r�̃t�B�[���h�ɂ����āA���̌����́q�Ӂr�̕����������͏k���i�q�Ӂr���q���r�j���ʂ�����A�V�g�I����������葽�ʂɊ܂q���r���߂��鎄�I���ꂪ����������B�����Ă��́q���r�̎��I����̂͂��炫����āA���邢�͂���ɃI�[�o�[���b�v���āA�s���t�ˁu���v�̌����I�E�q�ϓI�v���Z�X���i�s��ԁt�ˁu��ԁv�Ɓs���ԁt�ˁu���ԁv�̃v���Z�X������̌n�Ƃ��ěs�݂j�������A�������āA��ʓI�ȁs�`�t�ˁu�a�v�̕ϊ��������A���A���I���ꂪ�������܂��i��62�͎Q�Ɓj�B
�@�����ŁA�q���r���߂��鎄�I���ꂪ�s���t�ˁu���v�̌��I����Əd�ˍ��킳���_�@�ƂȂ�̂��A�ʑ��݂́u���v�ł���Ǝ��͍l���Ă���̂ł����A���̂��Ƃ͎��͂́A�Ƃ������єV���ۊw�a�w�E��̘_�_�ɂق��Ȃ�܂���B�m���n
�@
�m���n�u���_�v�ɂ�����镶�͂��ЂƂ����������Ă����B
�@���p�����́u�_�v���u�Ώہiobject�j�v�Ɓu���v���u�ˁiarrow�Cmorphisn�j�v�A�����āu�֎�ifunctor�j�v�Ɓu���R�ϊ��inatural transformation�j�v�����_�̗p��B�����̊W���G�c�Ɏ����ƁA�@�Ώہi�Ȃ�炩�̌��ہj�Ǝˁi���ۂ̊Ԃ̕ϊ���ߒ��j����Ȃ�V�X�e�������icategory�j�A�A�����猗�ւ̎˂��֎�i���A�i���W�[�j�A�B�֎肩��֎�ւ̎˂����R�ϊ��i���A�i���W�[�̃A�i���W�[�j�ł���B
�����Ɨ]�^�A�߈ˁE���ʁE�A���S���[�̎l��
�@
�@�{�e�ł́A���I����̓������l����Q�Ƙg�Ƃ��ăA���S���[����肠�����B���̂��߃A���S���[���̂��̂ɂ��Ď��I�ɘ_���邱�Ƃ͂��Ȃ��������A�x�����~���ƃ|�[���E�h�E�}���̃A���S���[�_�A�����_���T�ς��Ă��邤���A���̔]���ɂ������̎����������яオ���Ă����B
�@�A���S���[���鐂ł���A���҂̂��������i�сj�ł���A�u���ʁv�ł���B�A���S���[�͏����o���A������̌������́u�L���v�̍��ՁA�����A�H��ł���A�V�g�I���������u�����v�Ƃ��Ē~����u�Ȋ�v�ł���B�A���S���[�i�����I����j�́A�_������̌���i�����j�ł���A�V���[�}���̌��i���j�ł���A���X�B
�@
�@�@�@�@�@��
�@�A���S���[�͉��ʂł���A���I����͐_�߂�̌���A���Ȃ킿���ʂ������V�e�̌��ł���B
�@������́w�j�_�x��u�u�����N�w�v�̎����Ɍ����āv�i�w�|�p�l�ފw�u�`�x�����j�ɂ����āA�_���́u�_�߂�v�ƃC�X���[���́u�X�[�t�B�[�v�̌��i�u���݁v�Ƃ��Ă̐_�Ƃ̍���̌��j�╧���́u���܂ˁv�i���ǂ��������j�Ƃ́u�������v���w�E���Ă���B
�@�����ɃL���X�g���́u����v�������āu�����o���v�̎l�ތ^���d���Ă�����ƁA�u�C�}�W�i���i���j�^���A���i���j�v�̐������Ɓu���@�[�`���A���i��j�^�A�N�`���A���i���j�v�̐��������ˋ�����A���S���[�i�����I����j�̎l�Ԃ邱�Ƃ��ł���B
�@�a�̂̃��g���b�N�Ɋ֘A�Â��i���A��48���ōl�@�����A�i���W�[�̎l�ԂƂ̊W�����ӎ����j��������ڗ��Ă�ƁA���̂悤�Ȃ��̂ɂȂ�B
�@
�y�A���S���[�Z�z
�@�E�q����r�̎��I����
�@�E�_���̐_������
�@�E�u��v�ivirtual�j�̃��g���b�N�������́u�|���v
�@
�y�A���S���[�T�z
�@�E�q���r�̎��I����
�@�E�C�X���[���́u�X�[�t�B�[�v�̌�
�@�E�u���v�iactual�j�̃��g���b�N�������́u�����āv
�@
�y�A���S���[�U�z
�@�E�q�����r�̎��I����
�@�E�L���X�g���̎��
�@�E�u���v�ireal�j�̃��g���b�N�������́u�{�̎��v
�@
�y�A���S���[�V�z
�@�E�q���r�̎��I����
�@�E�����̕��܂ˁi���ǂ��������j
�@�E�u���v�iimaginal�j�̃��g���b�N�������́u����v
�@
�@�@�@�@�@��
�@������́w�j�_�x�ŁA�u�_���́u�_�߂�v����͂��܂�B�v�Ə����A�w���{���I�x�ɂ����ăA�}�e���X����т��āu�߈ː_�v�Ƃ��ĕ`���ꂽ���Ƃ��w�E����B�u����܁i�u���_�L�v�j�ł́A�{�����J�����A�}�e���X�̂��܂�́u���v�i�u���������v�A�܂�͜߈˂̗́j�ɋ�����Ȃ����V�c���A�A�}�e���X������̖��Ɂu���m�n���v�i�u�߂��v�j�āA�{������O�ւƏo���B�v�i35�Łj
�i���͂����ŁA���́u�S�Ɏv�ӎ������镨�������ɑ����āv�]�X�̌Í��W��������z�N���Ă���B�j
�@
�@�@�@�@�@��
�@���I����i�����ʂƂ��ẴA���S���[�j���ғ�����̂́A�n���i�E�A�[�����g���w�ߋ��Ɩ����̊ԁx�̏��Łu���_�̗̈�v��u�Ԃ̋�ԁv�ƌĂсA�r�����u�×����[���v�Łu���̓��̐[���S�v�]�X�ƒԂ����u�̂̓��v�ɂ����Ăł���B�i�A�[�����g�̕��͂͑�49�͂ň��p���A�r���́u�̂̓��v�ɂ��Ă͑�59�͂œ�j�̒����Ɋ֘A���Č��y�����B�j
�@�ߋ��Ɩ����̊ԁi���Ԃ̗ځj��̂̓��ɂ����Č`�������̂��A�v�l��n��́u�L���v�ł���A���̒S����ƂȂ�u��́v�ł���B���Ȃ킿�u���j�v�i�єV���ۊw�b�w�̃e�[�}�j�ł���B
�@�@�@�@�@��
�@�l�̃x�����~���I�T�O���߂���i�g�����̂Ȃ��j���I���Y�^�B
�@
�@�P�D�A���S���[�i�p�Ёj�F����i�}�X�N�j
�@�Q�D�|��@�i��������j�F�l���i�C���f�b�N�X�j
�@�R�D�A�E���@�@�i�����j�F�l�́i�C�R���j
�@�S�D�z�N�@�@�@�i���j�j�F�����i�V���{���j
�@
�@�u���ʁv�������́u���ʓI�Ȃ��́v�i���Ƃ��C���f�b�N�X�A�C�R���A�V���{���ɕ��ԑ�l�̋L���Ƃ��Ẵ}�X�N�j�́A�u���j�v�ƂƂ��ɊєV���ۊw�b�w�̃e�[�}�Q���\������B�������A���J�s�l���w��{ ���{�ߑ㕶�w�̋N���x�Łu�f�灁�����I�����v�ƑΔ䂵�Ę_�����Ă���u���ʁ��\�ӕ����v�́A�a�w��̃e�[�}�ł���B
�@
�i�S�U���͂ɑ����j
���v���t�B�[����
�����I���i�Ȃ��͂�E�̂肨�j1950�N�㐶�܂�B���Ɍ��ݏZ�B��N���̂ɏ����ꂽ�a�̂̈Ӗ��������ł���̂͂��������Ƃ��B�ł��A�{���Ɂu�����v�ł��Ă���̂��B�����Ɂu�Ӗ��v�Ȃǂ���̂��B�����������t���g���ĉ�����`�B���邱�Ƃ��̂��̂��s�v�c�Ȍ��ۂ��Ǝv���B
Web�]�_���u�R�[���v45���i2021.12.15�j
���F�ƃN�I���A�^�y���\�i�ƚF����65�́@�����o���^���I����^�A���S���[�i���̂U�j�����I��
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU�@2021 Rights Reserved.
|
| �\���i�ڎ��j�� |
