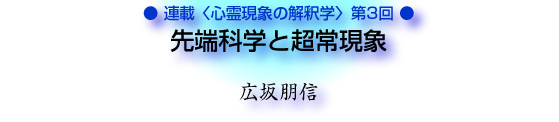|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「La Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
|
もともとは心霊現象をめぐる思想史上のエピソードを面白おかしく紹介しようということで始めたコラムなのだが、初回は東日本大震災にうろたえ、二回目は旧友の死の衝撃から立ち直れずに、それらの言い訳から書きはじめることになってしまった。しかし、さすがに三回目の今回は私の怠慢以外の言い訳の種も尽きたので、いきなり本題に入る。
前回、ヘーゲルが人相学や骨相学に鉄槌をくだす場面を紹介した。
ヘーゲルは『精神現象学』で「人相学者の横っ面を張り倒せ、骨相学者の頭蓋を叩き割れ」と、当時流行したトンデモ科学を威勢よく罵倒していた。そして、ある意味で彼の後継者ともいえるエンゲルスが磁気骨相学のトリックを暴き、交霊術に夢中になる自然科学者たちの無邪気さを冷笑するのも見た。エンゲルスの言葉を繰り返そう。
それゆえに、「視霊家の強弁は経験的な実験を以てではなく、却って理論的な省察を以て始末しなければならない」とエンゲルスは結論付けた。
しかし、このコラムの第一回で取り上げた『視霊者の夢』のカントは、理論的省察の作り出した形而上学が視霊者の夢想と酷似してくることに警鐘を鳴らしていた。そこで今一度、形而上学者の夢の跡をたどってみようと思う。
1 催眠療法の先駆者
若き日のエンゲルスが1843年頃にその実演会を見物したホールの骨相術は、骨相磁気学または磁気的骨相学と呼ばれていた。ヘーゲルが「どたまをかち割ったれ」と言った骨相学には「磁気」がなかった。この「磁気」が、実は大きな問題である。
骨相磁気学の「磁気」とは物理学でいう磁力のことではなく、「動物磁気」と呼ばれたもののことである。これを「発見」したのはドイツ出身の医師フランツ・アントン・メスマー(メスメルとも。1734-1815)である。伝記には、チュイリエ『眠りの魔術師メスマー』(高橋純・高橋百代訳、工作舎)があり、小説仕立てだが精神医学者である著者チュイリエによって催眠療法の先駆者として描かれている。メスマーは、宇宙は目に見えない微細な流体で満たされていると考え、その流体が媒介となって天体が人体に影響を与えているとし、その作用を磁力とのアナロジーから「動物磁気」と名づけて、病気の説明と治療に応用した。
動物磁気を用いた治療とはどういうものだったか。メスマーは動物磁気の欠乏またはバランスの失調によって疾病が起こるとし、正常な状態にある治療者の磁気を患者に送り込むことで、患者の体内の磁気バランスを回復させることができると考えたようだ。彼は「ヴィーンに診療所を開き、自分の原理に従って「磁化」を行なった。これは手で撫でたり触ったりすることによって、メスマー自身の流体を患者の身体に分配することであるが、いく人かの患者はこれで治癒した」(カステラン『超心理学』田中義廣訳、白水社)。
当初ウィーンで開業していたメスマーは、1778年にパリに出るや上流階級に食い込み大きな成功をおさめた。パリでの彼の活動とその社会的反響についてはダーントン『パリのメスマー』(稲生永訳、平凡社)に詳しい。動物磁気説は提唱者の名前をとってメスメリズムとも呼ばれ、その影響は大西洋を渡ってアメリカにも及んだ(庄司宏子「メスメリズムと女性の神経症的身体」、成蹊大学文学部学会編『病と文化』風間書房)。
さらにメスマーは動物磁気を貯めておく蓄電池のような「桶」(バケツ)も発明した。
現代ではこのメスメリズムによる治療は磁気の作用によるものではなく、暗示による一種の催眠療法だったとされており、現代の心理療法や精神分析の遠祖と位置づけられている(エレンベルガー『無意識の発見 上』木村敏・中井久夫監訳、弘文堂)。磁気桶が偽薬効果を発揮したかもしれないし、手かざしに似た動作にも癒しの作用があったかもしれない。催眠状態にして悩みを語らせることで患者のストレスがいくぶんか解消されたかもしれない。ただし、現実に治療効果があったらしいとはいえ、その原因はメスマーが説明していたような「動物磁気」によるものではなかった。
2 動物磁気はいかにして「発見」されたか
そもそも動物磁気はいかにして「発見」されたか。メスマー自身が動物磁気を「発見」した経緯を書きとめている(「動物磁気発見のいきさつ」本間邦雄訳『キリスト教神秘主義著作集16近代の自然神秘思想』教文館所収)。
メスマーの「いきさつ」は短い方法論的省察から始まっており、それは「人間は生まれつき、観察する者である。人間の務めはひたすら観察を重ねて、自分に備わる器官を使いこなすようにすることである」と書き出されていて、いかにも自然科学者らしく観察の重要性を力説しているように見える。
「観察を放棄し、曖昧で空疎な思弁を弄する」ようになった人間精神は「謎めいた抽象を上乗せする理論体系の山を築いてゆくだけ」であり、「真実は見失われ、無知と迷信がはびこるばかりとなった」という意見などは啓蒙思想の決まり文句かもしれないが、なるほどと感心させられる。観察なき思弁によって「人間の知識はこうして歪められ、知識のもととなるはずの現実について、もはや何も教えないのである」と断じるところなど、まるで『視霊者の夢』のカントのようだ。
それではメスマーはいかなる観察によって動物磁気を「発見」したのかと期待が高まるのだが、彼の関心はすぐに学説史の再検討へと移る。
この意見自体には私もまったく同感である。哲学と言っても現代では自然科学や社会科学として独立している分野の多くが含まれていた時代のことだから同列に論じることはできないが、前世代の思想の意義を十分に吟味しないうちから「乗り越えた」と否定して省みない悪癖はもうやめにした方がいい。
しかし、ここから進んで次のように言われると、賛意もいささか微妙になる。
私の考える「心霊学」の方法的態度としては、リスクはあるがこれは有りだ。何をもって「原初に認められた真実の余燼」と見なすことができるかは、かなり慎重に見定めなければならないが、「古今にわたるもろもろの俗説」を抜きにしては「心霊学」は考える手がかりを失う。おそらく妖怪学でも事情は同じだろう。
ただし、この手法は自然科学の方法としてはそぐわないように思われる。俗説を吟味して「原初に認められた真実の余燼」を探し当てるのは理論的なヒントを得る上で役立つこともあるだろうが、その域を出ないだろう。自然科学としてはメスマー自身が最初に言っていたように観察を重ねるのが王道ではないか。この点についてメスマーはどう考えたのだろうか。
しかし、続く文章を読んで愕然とした。
あれほど強調していた観察はどこへ行ったのか。俗説の吟味や、「学問の廃墟」に忘れられた知恵を尋ねるのも結構だが、それは観察とは違う道である。
メスマーは「この問題をめぐって思索を重ねた末に」、1766年に論文『人体疾患に及ぼす惑星の影響について』を発表した。本人があれほど強調していた観察によってではなく、俗説の吟味、おそらくは現代では占星術に分類されるものも含まれていただろう当時の宇宙論の検討、そして思索を重ねることによってである。なかでも彼が目をつけたのはニュートンによる万有引力の理論だった。メスマーは次のように自説の特徴を語っている。
メスマーは、天体間の引力が海の潮の干満を起こすように、人体にも類似の現象を起こすはずだと考えたようだ。
メスマーの「動物磁気発見のいきさつ」はこの後もまだ続きがあるが、それは動物磁気を利用した治療法の確立についてであって、動物磁気の発見に至る経緯は以上のとおりである。
しかし、これははたして「発見」なのだろうか。これをあえて発見というなら、メスマーは先行学説か、自分の思考のなかに動物磁気を発見したのである。
3 宇宙と照応する人体
ここでメスマーに影響を与えたとされるルネサンス期の医師パラケルススのことが連想される。パラケルススはメスマーに先んじて磁気を治療に用いる着想を得ていた(山本義隆『磁力と重力の発見2ルネサンス』みすず書房)。メスマーが「観察」を強調したのと同様にパラケルススも「経験」を重視した。そして、人体を小宇宙と捉え、大宇宙たる天体の運行の影響を受けると想定した点も同じである。天体と人体の関係に磁力で介入するというのがパラケルススの磁気治療のアイデアだった。しかしその磁気治療論を支えているのは「経験」ではなく、占星術と錬金術の知識だった。山本義隆は「経験を重視し「したがうべきは経験なり」とくりかえし主張しているわりにその内容が現実離れしているのが気になるのはやはり避けられない」として次のように評している(山本、前掲書)。
メスマーの動物磁気説もニュートンの万有引力の法則という「新理論」を加味しているとはいえ、その基本的発想においてはパラケルススの自然魔術と大同小異であることが見て取れるだろう。
このメスマーの動物磁気説は当時の学界から異端視され、ついには排斥された。フランスのアカデミズムはラヴォアジェ(実験によってフロギストン説を否定した化学者)を中心とする調査チームを発足させ、動物磁気が物理的に存在する証拠はなく、治療効果は想像力によるものだと結論づけた(エレンベルガー、前掲書)。しかし、メスメリズムが異端視された理由は単に非科学的であるからというだけではなかった。「その治療法が非道徳的とされ、さらには反政府的な過激思想との結びつきが強調されて、メスマーの治療、ひいては、その「学説」、動物磁気説(すなわち、メスメリズム)までもが為政者の不興を買った」(稲垣直樹『フランス<心霊科学>考』人文書院)。
非道徳というのは、患者の身体を撫でさすったり直接手を触れぬまでも患部に手をかざして「動物磁気」を送り込む治療は性的な接触を連想させたし、催眠状態になった患者は治療者の精神的支配下に置かれることになるのが問題視されたのである。実際、女性患者に服を脱げと命令した男性磁気治療者がいたらしい。
一方で、体制と結びついたアカデミズムに挑戦するメスメリズムは、ある種の開放性・進歩性のオーラを帯びていて、それが進歩派を自任する人々に歓迎された。ダーントンは『パリのメスマー』でこの点を強調している。
動物磁気を媒介として宇宙との調和を説くメスメリズムはある種のユートピア思想と接合しやすい性格をもっていた。メスメリズムの信奉者たちは団体を作って動物磁気療法の普及に努めるとともに、それが社会改良の役にも立つと考えた。ある急進的なメスマー主義者は「ルソーの思想傾向を人間相互間の肉体的・心理的関係のメスマー的分析の中に注入することによって、フランスに革命をもたらす道を見出し」さえしたのである。もっとも「政治的危機が民衆の注目を集めるようになった一七八七年から一七八九年にかけての革命派の人びとを満足させることはほとんどなかった」(ダーントン、前掲書)というから、政治思想としては現実を動かすには至らなかったのだろう。
結局、治療法としてのメスメリズムの実態は、ウィーンの医師が自然魔術と新興科学にヒントを得て発案した心理療法にすぎなかったのだが、その理論はフランス革命前夜のパリで流行する過程で思想性を帯び、今でいうニューエイジ・サイエンスのようなものに変貌したのであった。もちろん、ニューエイジ・サイエンスの方こそメスメリズムの子孫にあたるわけだが。
4 ヘーゲルの「心理学」
ヘーゲルはその『精神の哲学』緒論において、メスマーの動物磁気説を「精神の真実でない・有限な・単に悟性的な理解を駆逐することに貢献した」と称賛している(『精神の哲学』船山信一訳、岩波文庫、上巻)。
何を言っているのかよくわからないが、解放、親和性、必然的、「なんら不可解な奇跡ではない」とポジティブな言葉をつらねて動物磁気説への賛意を表明していることだけはよくわかる。緒論においてだけではなく本論部分でもかなり熱を入れて論じている。男性磁気術師が女性の患者に服を脱げと言ったというスキャンダルまで承知したうえでのことだ(実はあのネタの出所はヘーゲルである)。その入れ込みようは尋常ではない。フォイエルバッハは「ヘーゲル心理学はそれ故に「動物磁気の諸現象」を支柱としている」と評している(『唯心論と唯物論』船山信一訳、岩波文庫)。
論理学、自然哲学、精神哲学の三部からなる『エンチクロペディー』の第三部にあたる『精神の哲学』は、主観的精神、客観的精神、絶対的精神に三分割され、そのうち第一篇の主観的精神は、A人間学、B精神の現象学、C心理学、の三章にわかれている。だが、フォイエルバッハが「ヘーゲル心理学」と呼んだのはこのC心理学のことではなく、A人間学の内容を指している。A人間学もさらにa自然的心、b感ずる心、c現実的心の三つの節に分けられている。このうち「b感ずる心」も、感ずる心の直接態、自己感情、習慣の三つの項目に分割されていて、メスマーの動物磁気説が取り上げられるのは「感ずる心の直接態」においてである。
この「b感ずる心」を取り上げた研究としては上村芳郎氏の論文「心の魔術的な関係――動物磁気・狂気・身体」(加藤尚武編『ヘーゲル読本』法政大学出版局所収)がある。ヘーゲル哲学における「b感ずる心」の哲学上の問題点について有意義な知識を求める方はそちらをお読みになることをお薦めする。このコラムで扱うのは、あくまで「心霊学」の無益な考察にとって意味のある点についてだけである。ただ、「感ずる心の直接態」というここでの主題についてだけは植村氏の解説を引いて確認しておきたい。
私と世界との「直接的な一体性」の例としてヘーゲルは「愛されていた近親者・友人等々の死が、後に残った人々に与えるかもしれないような影響を想起してみればよい」と言っている。「すなわち、愛されていた近親者等々が死ねば、後に残った人も死ぬか、または死んだと同然になるのである」。この例ならば、私たちの多くも似たような思いを味わったばかりだ(宮地尚子『震災トラウマと復興ストレス』岩波ブックレットなどを参照)。こうした心のはたらきを、思いこみによる錯覚だとか習慣による愛着にすぎないとだけ言って賢さをひけらかすような態度を「真実でない・有限な・単に悟性的な理解」とヘーゲルは非難したのである。
こうしてみると、ヘーゲルもなかなか人情のわかる人に思えて好感度がアップするが、動物磁気がからむとそれではすまされなくなってくる。
5 超常現象百科全書
ヘーゲル『精神の哲学』の「b感ずる心」は、一読した方なら共感してもらえると期待するが、正直言ってなんと評するべきか扱いに困るという印象が残る。そこで主として論じられているのは、魔術、夢、胎児、守護神(守護霊)、透視(テレパシーと予知)、夢遊病、ダウジング、千里眼、そして動物磁気であり、これらの題材だけながめていると哲学体系の一部門というより、あたかも超常現象百科の様相を呈しているからだ。
そして、それら超常現象ネタについて語るヘーゲルの口調には、カント『視霊者の夢』やエンゲルス『心霊界における自然研究』に見られたような皮肉な調子がほとんど感じられない。著者がコリン・ウィルソンならばなるほどと思うが、ヘーゲルの書いたものだと思って読むと、哲学史の入門書で刷り込まれた現実的な理性主義者という大思想家のイメージと一致しないものだから、はたしてどこまで真に受けていいものやら戸惑うほどだ。
もっとも『精神の哲学』は精神の百科全書でもあるのだから、そこで超心理的話題が出てきても、それは特殊な心理状態の描写の記述として位置付ければよいのかもしれないが、どうもそれではすみそうにない。『精神の哲学』第三〇節の初めには動物磁気を考察する上での条件として次のような文章がある。
これはカントに対する嫌味である。ここでヘーゲルは、カントが『視霊者の夢』でスウェーデンボルグにしたような批判に対して予防線を張っているのだ。事実かどうかの細かい検証はしません。事実かどうかを問題にする人は、どうせ信用するつもりがないのだから、たとえ自分の眼で見ても、科学的でないとか合理的でないとか言って頭から否定してかかるに違いないのです。ヘーゲルはそう言っているのである。まるで開き直った心霊術師の言い訳のようなのだ。
ヘーゲルはこの後、ダウジング(杖や振り子で地中の埋蔵物を探し当てる占い)やサイコメトリー(場所や物からある種のオーラを感じ取り過去の情報を得る霊感)の例を挙げて、「たといこの点に関する現存の物語りのなかには常にどんなに多くのインチキが存在していようとも、しかもその際のべられた若干の場合は信ずるに値するように見える」とも言っている。
ここで一つ断らなければならない。私はヘーゲルの超常現象に対する態度を一概にトンデモと決めつける気にはなれない。ある事柄がその社会で正統とされている知によっては上手く説明できないからと言って、その事柄自体を否定するいわれはない(ただし、例えば科学や良識によって説明が可能であればそれを拒むいわれもさらにない)。
ちなみに、ある事柄ついて人々の関心が高いのに情報量が少ないとデマが発生しやすいと言われている。超常現象を希少だが人々の関心をかきたてる内容をもった現象と解すれば、それについての報告の多くに(ほとんど全部に)誤解や錯覚や虚偽や妄想が含まれていてもなんの不思議もない。逆に一つでも真実の例があれば他のすべてが誤報でも、その特殊な一事例は検討にあたいするはずだ。こうした態度が危険であることは承知しているが、この危ない橋が私の考える「心霊学」への一本道なのである。
この場合、動物磁気説がそうした検討の対象に該当するかどうかが問題である。上村氏は前掲論文で「こうしたいわば無意識のテレパシー現象をヘーゲルが承認しているのは、一つには、当時の動物磁気の実験が提示した「客観的なデータ」に基づいているせいである」と弁護している。しかし、動物磁気説が当時の新興科学だとしても、そもそも科学にも限界はあり、科学者も人間である以上、間違いも犯すし嘘もつくくらいのことはわきまえてしかるべきではなかったか。
例えば、ヘーゲルは、フランス・リヨンのある医師の報告として、別室にいる人のもっている本の内容を読みとった患者のケースが挙げている。医師の報告が正確であれば、そうした現象があったこと自体は疑いえない。ただし、それが動物磁気の作用によるものかどうかはまた別の話である。まったくの偶然の一致かもしれないし、被験者がその本を読んだことがあったのかもしれない。また、被験者たちが観察者である医師の気に入るような結果を出そうと努力したのかもしれないのである。それなのにヘーゲルはそうした別の理由を考慮していない。
ついでにヘーゲルの挙げているおもだった事例を列挙しておこう。
・記憶の回復。磁気的状態ではふだん忘れていることを思い出す。記憶障害の患者も磁気的状態では記憶を回復する。
・千里眼。遠隔地にいる人の姿を幻視する。
・予知。
・テレパシー「他人の心的および身体的状態に関する透視による認識」、「とくに磁気的な夢遊病において起こる」。
・直接の共感。「たいへん遠く離れていながら双方の病気の状態を互いに感じ合っていた」二人の女性の例。遠くにいる母の恐怖を共感した兵士の例。
こうした事例にヘーゲルがほとんど疑いをはさまずに挙げているのは、「感ずる心の直接態」では心と物、心と心が直接ふれあい、一体化するという前提があるからだ。フォイエルバッハはこの点を指摘して「ヘーゲルの心にとっては肉体のあらゆる諸制限およびあらゆる有限な諸連関が消滅してしまっている」、「もし眼なしにもまた見ることができる心が実存するならば、そのときには例えば眼のような身体は何のために存在するのか?」、「脳髄は何のためにあるのか?」と弾劾している(『唯心論と唯物論』)。
ちなみに「磁気的状態」というのは催眠状態のことである。ヘーゲルもメスメリズムが現代で言う催眠術であると認識しており、「磁気的状態はむしろ精神の病気であり精神そのものが通常の意識以下に沈下することであるとみなさなければならない」と言っている。しかし、なにが催眠状態を引き起こす原因かについては動物磁気説を採用しているのだ。
ヘーゲルの言い分の問題点は、当然ありうる疑義を「ア・プリオリな悟性」への執着として一括して切り捨てていること、そればかりか、悟性範疇にとらわれずに概念によって(つまりより高次の立場から)とらえるならば理解しうるのだ、としている点である。カント的悟性の立場ではわからないだろうが、それを越えたヘーゲル的理性の立場からならば理解しうるのだ、というわけだ。こうした上から目線の物言いにはカチンとくるだけでなく、トリックの臭いすらする。
上から目線という点では、現代の科学の成果を踏まえて動物磁気が実在しない前提でヘーゲルを読んでいるお前も同じではないかと言われるかもしれないが、ちょっと違う(そもそも私は科学に詳しくない)。ヘーゲルの場合、すぐ前の世代のカントによる『視霊者の夢』があり、すぐ後の世代のエンゲルス『心霊界における自然研究』もある。しかも『精神現象学』では骨相術については自ら粉砕もしている。当時のアカデミズムも動物磁気は存在せず、治療は想像力によるものだと判定していた。つまり、この時代の知識では動物磁気説の真相を見抜けなかったというわけではないはずなのだ。カントがスウェーデンボルグの霊能力について事情通に問い合わせ、エンゲルスが骨相磁気術の実演を見聞し自ら実験までしたことを思い合わせると、ヘーゲルの態度はあまりに素朴な印象を受ける。
それどころか、ヘーゲルは動物磁気説の信憑性について、同時代の知識人の名前を挙げて権威付けすら行っている。フランスのメスメリスト、ピュゼグーユの他に名前が挙げられたのは、ベルリン大学教授の医学者クルーゲ(「動物の磁気の諸現象に関する一つの有用な外面的分類を与えた」)、オランダの哲学者ファン・ゲールト(「彼によって磁気療法が日記の形式で記述されている」)、医学者カール・シェリング(「自分の磁気的経験の一部を公にした」)の三名であり、彼らが動物磁気説についてのヘーゲルの主な情報源であろうと思われる。問題はこの三名の素性である。
「信頼すべき且つ同時に思想の豊かな人であり、最新の哲学の教養を身につけている人」とされたファン・ゲールトはヘーゲルの弟子であって、彼の「最新の哲学の教養」とはもちろんヘーゲル哲学のことになる。カール・シェリングは、ヘーゲルの旧友シェリングの弟であり古い顔なじみだろう。ちなみにヘーゲルとシェリングの友情は『精神現象学』でのシェリング批判によって決裂したが、腹を立てたのはもっぱらシェリングの方でヘーゲル自身はそのことに気づいていなかったらしい。つまり、三人のうち二人までがヘーゲルにとって身内同然の人だった。そして、クルーゲについては、この動物磁気説についての『精神の哲学』の記事がいつごろ書かれたか私にはわからないので断言はできないが、もし、ヘーゲルのベルリン大学赴任後であれば、同僚ということになり、ここから当時のヘーゲルの周囲で動物磁気説ブームが起こっていたと想像することもできる。「みんなそう言っている」の実情はえてしてこんなものである。
6 否定しきれないものの残留
しかし、ヘーゲルのリテラシー欠如を指摘するだけですませられるか。これはやはりヘーゲルの世界観に由来することではないのか。
ここで疑問が浮かぶ。骨相学については断固粉砕の立場でのぞんだヘーゲルであるのに、動物磁気説についてはやたらと好意的であるのはなぜか。骨相学も動物磁気説も医学・生理学の詳しい知識がなくてもトンデモ科学であることは一目瞭然である。ましてや両者は、エンゲルスが見物したホールの磁気的骨相術のように容易に結合しうる代物だった。
骨相学の前身であるガル頭蓋論は大脳生理学の、メスメリズムから派生した催眠療法は精神分析の、それぞれ先駆だとも言われている。そこで、骨相学を断固粉砕したヘーゲルが動物磁気説には引きつけられたのは、彼の世界観が要素論的・機械論的な大脳生理学よりも、全体論的・力動論的な精神分析に近かったからだとも考えられる。
全体論的・力動論的というのはその世界観の外的特徴にすぎないが、ヘーゲルとメスマーの類似はそれだけではない。ヘーゲルは「心はすべてのものに浸透していくものであって、ただ或る特殊な個体のなかに実存しているだけのものではない」と言っていた。上村氏は、「精神が閉ざされた個人の内部にあるものだとは、ヘーゲルはもとから考えていない」として次のように指摘している(上村芳郎、前掲論文)。
ヘーゲル的心はメスマーの動物磁気のように個体の枠を越えているのだ。つまり、メスマーの動物磁気説は、「浸透する心」を前提とするヘーゲルの体系にとって異物であるどころか、その霊魂観に親和的だったからこそ自分の思想が先端科学によって実証されたと考えて積極的に論じたのだろう。エンゲルスは心霊主義に傾倒した科学者たちが「自分が見ることになっているもの或は見ようと思っているものだけしか見ない」と言っていたが、ヘーゲルにとっての動物磁気説もまた同様である。『精神の哲学』のヘーゲルは動物磁気説を哲学的に解釈しているのではなく、むしろフォイエルバッハが指摘していたように、動物磁気説がヘーゲル心理学の支柱なのである。
個の枠を超えるこうした意識観・精神観は、ヘーゲルだけでなく近代の超克を志向する思想家たちの世界観にしばしば認められる。ニューエイジ運動はなやかなりし頃の本を開くと、精神世界と先端科学が一致するというような話をしばしば見かけるが、それを連想してしまう。それが前近代的世界観への先祖がえりなのか、看板通り近代の超克なのか、判断の分かれるところではある。
以上、大思想家に対してあげ足とりばかりしてきたが、私としてはヘーゲル流の心理解を全否定するつもりはない。それがいかにも怪しげに感じられるのは、動物磁気説という疑似科学と結びついて人間の精神生活の説明原理としてふるまおうとするからである。
ここからは、科学史・哲学史の裏付けのない妄想である。
メスマーの「その原理がどんなに滑稽で、突飛に見えるものであっても、原初に認められた真実の余燼と見なすことのできないようなものは、ほとんどない」という意見に、条件付きながら私は同意した。このアイデアをメスマー自身に適用してみよう。そうすると、こんな情景を想像してみることもできる。最初はパラケルスス流の磁石による磁気療法を試みていたメスマーだが、ある時、治療用に使っていた磁石から磁力が消えていたことに気がついた。しかし磁力のない鉄片でもこれまで同様の治療効果が得られていた。そこでハッと思いあたった。医師と患者の間に物理的な磁力以外の「力」がはたらいている! この「発見」自体は観察による事実であり、私たちはそれを「原初に認められた真実の余燼と見なす」ことができる。ただメスマーはその説明原理を古今の俗説に求めて奇怪な体系を作りあげてしまった。
ヘーゲルの場合も同様に想像できないだろうか。廣松渉は『エンチクロベディー』で描かれたヘーゲルの哲学大系を「総じて絶対的な精神の自己展開、自己疎外と自己獲得の壮大な叙事詩を形成している」(廣松『青年マルクス論』平凡社)と評しているが、ここで取り上げた『精神の哲学』b感ずる心は、第一篇主観的精神のA人間学に含まれており、それはB精神の現象学の手前におかれている。精神の「自己疎外と自己獲得の壮大な叙事詩」とは、周知の通り、もっぱら『精神現象学』で展開されたものであり、それは『エンチクロベディー』ではA人間学の後に位置づけられている。そうすると、このb感ずる心を含む『精神の哲学』A人間学には、『精神現象学』的叙事詩以前の「原初に認められた真実の余燼」が見出されるのではないだろうか。
そこで興味深いのはやはり「心はすべてのものに浸透していくものであって、ただ或る特殊な個体のなかに実存しているだけのものではない」という心理解である。これはその出発点では私たちの心の実情に即したものだったのだろうと私は想像する。すべてのものに浸透していく心という発想は、私たちの生活のなかではそう感じる、という意味でなら、それこそなんの不思議もない。ヘーゲルは近親者への愛の例をあげていたが、私たちはペットや家畜にも心を通わせることができるし、料理も心をこめて作る。手になじんだ道具は自身の一部のようだし、思い出の品には万感の思いがこめられている。文化的な偏差はあれ「心」とはもともとこうした使い方をする言葉なのである。
私たちの心が浸透するのは物体だけではない。生まれ育った土地の風景、住み慣れた町のたたずまいなど環境にも私たちの心は浸透している。それらが何らかの事情で破壊されたり放棄しなければならなくなったりした場合には、それこそ心が引き裂かれるような思いがするものだ。そして、故郷の廃墟をそのただなかで目の当たりにした人が感じただろう気の遠くなるような喪失感は、見わたすかぎり瓦礫で埋め尽くされた光景と切り離して語ることはできないだろう。
こうしてみると、フォイエルバッハが考えたような、身体(脳)に内属した意識としての心理解は、私たちの心の実情を充分に写したものではない。私たちの心は、感覚の対象や、私たちがその中にある環境とも一体化している。そうした心はもはや「私」に限定されない。この限定されない心は、「私」が想像力によってつくりだしたイメージではなく、むしろそれをこの私の身体や思惟に関係づけ、限定することで「私の心」が成立するような、私化される以前の心とでも呼ぶべき何かである。
私の心は、はじめから「私の心」であったわけではない。ヘーゲルの着眼はそこにあったのではないか。だからこそ、母体の中の胎児の意識や催眠状態、テレパシーなどに関心を抱いたのだろう。それらは私化される以前の心、私化されなくなった心、私以外の心との相互侵入であり、心が私(の意識・脳)に限定されないものであることを示す事例として取り上げられている。
しかも、ヘーゲルには、感覚において、感じるものと感じられるものとが一致するという考えがあった。カントなら感覚の対象(現象)の彼方に物自体を残しておくところだが、ヘーゲルはそれを認識論の欠陥とみなした。そうである以上、「感じる心」を語る言葉は、感覚の対象たる自然界と共通の原理をもたなければならない。そこで自らの「心」観を実証的に補強するものとして動物磁気説がうってつけだと考えたのだろうが、そこに落とし穴があった。メスメリズムは科学というより、視霊者の夢に近いものだったのである。
★プロフィール★
広坂朋信(ひろさか・とものぶ)1963年、東京生れ。編集者・ライター。著書に『東京怪談ディテクション』、『怪談の解釈学』など。ブログ「恐妻家の献立表」 Web評論誌「コーラ」16号(2012.04.15)
<心霊現象の解釈学>第3回:先端科学と超常現象(広坂朋信)
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2012 All Rights Reserved.
|
| 表紙(目次)へ |