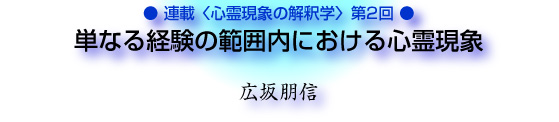|
前回、カント『視霊者の夢』について面白おかしく書くつもりが、東日本大震災の衝撃にうろたえて中途半端なものに終わってしまった。幸い挽回の機会を与えられたので、今度こそ面白おかしく書こうと構想を練り始めた矢先、まことに私的な事柄で恐縮だが、長い付き合いの大切な友人の訃報が届き、それに私はすっかり打ちのめされてしまって、それからしばらくは悲嘆にくれるばかりで何も手をつけられなかった。半年ほどたった頃、ようやく黒猫編集長との約束を思い出してキーボードを叩きはじめたのだが、どうしても喪の気分が抜けず、またもや面白くもおかしくもないメモを提出することをお許し願いたい。
1 時宜を逸した弔辞
彼女が亡くなったのは去年の夏のことだったのだそうだ。死亡通知が遅くなったのは、自らの死期を悟った彼女が、友人たちには自分の死を知らせるな、気まぐれな女のことだから、どこかで勝手に生きているのだろうと思わせておいてほしい、と言い残していたからだという。つまり、どこにもいないのに、どこかにいることにしてほしい、というのが彼女の最後の願いだった。ひねくれ者の彼女の仕掛けた最後の悪戯だ。およそ三十年以上にわたり親交を続けてきた私としては、この嘘を信じるふりだけでもしてやりたいと思う。しかし、そう簡単な話ではない。
彼女は、自覚していなかったふしがあったが、かなりの世間知らずである。私も世知にうとい方だが、それでもアレよりはマシだ。その極端な例が、自分の死を知らせるな、葬式をするな、命日も墓も知らせるな、という遺言である。葬式なんかやってもらっても自分はうれしくないから、というのだ。
君はまったくわかっていない。葬式というものは死者のためにではなく、生き残った者のためにやるのだ。関係者が集まって、その人が死んだことを確認しあい、その人がいない人間関係を再構築するきっかけにするために葬式をやるのだ。いない者はいない、いる者はいる、それを確認しあう。そうしないと、生き残った者の生活にひずみが生じてしまう。ただ単に、死んだはずの人の姿を見かけた、声を聞いた、というだけの、素朴な、場合によってはしみじみとしたお話でもあるような幽霊談をすら怖がる人がいるのは、私たちの生活は死者の不在を前提に営まれているのに、不在であるはずの死者の出現が生活の枠組みを動揺させるからである。
だから、死後も自分を死者として扱うなという願いは、生き残った者にとって困った話なのだ。それは、生きているのか死んだのかもわからず、ただ連絡が途絶えたままの人、すなわち行方不明者として遇せよということでもある。作家・村上春樹の「非現実的な夢想家として」と題されたカタルーニャ国際賞スピーチを、毎日新聞2011年6月10日付から引く。
地震そのものの被害も甚大でしたが、その後襲ってきた津波はすさまじい爪痕を残しました。(中略)海岸近くにいた人々は逃げ切れず、二万四千人近くが犠牲になり、そのうちの九千人近くが行方不明のままです。堤防を乗り越えて襲ってきた大波にさらわれ、未だに遺体も見つかっていません。おそらく多くの方々は冷たい海の底に沈んでいるのでしょう。そのことを思うと、もし自分がその立場になっていたらと想像すると、胸が締めつけられます。
村上春樹は、君が気取り屋だといって嫌っていた作家だ。引いた文章の最後の文は、いかにも君の嫌いそうな感傷だ。死者の立場に立つなどとおこがましい、そもそも行方不明者と死者とは同義ではないと怒ることだろう。そこは、こう読み換えよう。すなわち、もし自分が行方不明者の家族や友人の立場になっていたらと想像すると、胸が締めつけられます、と。そして今まさに私は君の天の邪鬼によってその立場に立たされている。
十月末現在では、震災による行方不明者の数はもっと減っているだろう。それでも何千人という単位であることは変わりないだろう。そして、将来でも残念ながらゼロになるということはありそうにない。行方不明者の家族や友人は、諦めることすらできない。十中八九死んでいるのだろうと覚悟はしながらも、もしかすると帰ってくるかもしれないという期待も抱きながら、探し続け、報せを待つ。これは人によっては喪に服すことよりも辛いことかもしれない。君が要求していることはそういうことだ。
まあ、しかし、腐れ縁の君がぜひにもと願うのであればそうしてあげてもいい。
ただし、君の願いをかなえようとしても、その前には実に厄介な問題が立ちはだかっている。ふつうの人間の精神は、喪の作業を永遠に続けられるほど強くはないのだ。死者はここにいない、呼びかけても返事が返ってくることはないとはわかっていても、どうしてももう一度会いたい、できればともに日々を過ごしたいと願ってしまう、そういう傾向が多くの場合にある。
2 世の中には経験を積んだだけのバカが大勢いる
幽霊の話など、ちらりと聞くだけでも嫌だという人がいる一方で、死んだ人に再会したいと願ってやまない人も古来多くいた。ギリシア神話のオルフェウスの伝説がそうだし、日本の記紀神話にもイザナギが死んだ妻イザナミに会いに黄泉の国におもむく話がある。
古代の神話・伝説はさておくとしても、人々があの世の消息についての関心を示した記録はいくらもある。例えば、江戸時代の『死霊解脱物語聞書』には、その中には、幽霊に取り憑かれた少女に、彼女が見てきたという地獄・極楽の様子を尋ね、さらには、少女に取り憑いた幽霊に対してさえ、あの世での亡き人の消息を尋ねようと大勢の人々が集まってきたことを描いた章がある。同書はその代表的な研究書『江戸の悪霊祓い師』(高田衛著、筑摩書房)の題名が示唆しているように、少女に取り憑いた幽霊を祓おうと奮闘した人々の記録だが、一方で幽霊を厄介祓いしようとあの手この手を尽くしながら、あの世のことは教えてくれというのは、どこか虫のいい話のようにも思われる。けれども、それが人情というものなのだろう。
こうした例は挙げていけばきりがない。1847年、米国ニューヨーク州ハイズヴィルで、有名なフォックス姉妹事件(ハイズヴィル事件とも)が起きる。ハイズヴィル在住のフォックス家の少女たちがラップ音で死者の霊と交信したというニュースは大きな反響を呼んで、米欧に心霊術・交霊会ブームを巻き起こした。この事件の起きた年を心霊学元年と呼ぶ人もいるくらい有名なので、これ以上ふれない。
ともあれ、人はあの世の消息のような、原理上、知りえないものについてまで知りたがる。この傾向について、スウェーデンポリの事例を検討しながら、経験の土台を持たない知の暴走を戒めたのが、前回取り上げたカント『視霊者の夢』だった。
前回(「コーラ」13号)、私はカント『視霊者の夢』の「心霊学」的側面、すなわち非哲学的側面を検討し、カントが「感官一般の錯覚は、理性の欺瞞よりもずっと注目すべき現象だ」と言っているのに着目して、次のような教訓を引っぱり出した。
事実ではないかも知れないがウソではないという基準は感覚や経験にしか当てはまらない。事実ではない理屈はあくまでもウソだ。それに対して、錯覚や幻覚は必ずしも嘘ではない、少なくとも故意の嘘ではない。「心霊学」が嘘に居直った強弁以外のものであろうとするなら、「背理的な穿さくをする理性の思弁」の手前にある経験を手がかりにするほかない。
しかし、経験というものは単純なようでいて厄介なものである。例えば、経験から学ぶなどと言う。私たちは四六時中、何かを経験し続けているのだから、もし、経験=学びであれば、もうずいぶんと頭がよくなってもよさそうなものだが、そうは問屋がおろさない。あくまで、経験「から」学ぶ、のである。経験を吟味することなしに、ぼんやり見聞しているだけでは何も学んだことにならない。経験それ自体は知識にはならない。にもかかわらず、経験は過大評価されがちである。世の中には経験を積んだだけのバカが大勢いるというのに。
そこで、事実ではないかも知れないがウソではないという怪しげな領域に挑む「心霊学」においては、なおさら経験というものの扱い方について注意深く検討しておかなければ、特撮映画を見るたびに人生観が変わらないのはなぜかを、自らに問い質さなければならない羽目に陥る。
3 洗濯物を干そうとするといつも雨が降る
1843年から44年にかけての冬のことだったそうだ。英国マンチェスターで、スペンサー・ホールという人物が磁気的骨相学の実演を行なったという。
骨相学とはガルの頭蓋論を大衆化したものである。ガルという医師によって提唱された頭蓋論は、脳には、感情や意志や思考といった精神のさまざまな働きをつかさどる部分があり、それは頭蓋骨の形状から観察できるとした。いわば当時の「脳科学」である。この説は大脳機能の局在説の先駆として評価されることもあるらしいが、世間に流布されるや「骨相学」と名を変えて、頭のかたちから性格診断や相性判断ができるという触れ込みで広まっていったというから、現代の「脳科学」なみにいかがわしい。それどころか、「白人による人種差別の根拠としても利用された」(吉村正和『心霊の文化史』河出書房新社)というから、かなりトンデモな代物である。
ちなみに、この骨相学は、ヘーゲルが『精神現象学』で人相学と並べて槍玉に挙げている。『精神現象学』と言えば難解で何回読んでもわからないので有名だが、もちろん私にもチンプンカンプンだ。ただ、人相学と骨相学のところだけは、ヘーゲルの論理は難解だが結論は明快である。
すなわち、人相学者の横っ面を張り倒せ、骨相学者の頭蓋を叩き割れ。
いや、表現はもう少し重厚だが、本当にそう言っている。ヘーゲルによれば、結局、人相学の言うところは、いわゆるマーフィーの法則のようなあやふや経験則による思い込みなのであてにならない。
人相学の観察の特徴を前記のリヒテンベルクはこうも表現している。「『お前は正直者のようにふるまってはいるが、おまえの面つきを見れば、むりにそんなふるまいをしていて、本当はごろつきであるのがわかってしまう』などとだれかにいわれたら、平手打ちをお見舞いする正直者がこの世に絶えることはないだろう。」――平手打ちを見舞うのが当然で、そうした思いこみの学問の第一前提が、人間の現実はその顔にある、というのだから、もちろん、それは拒否されねばならない。
ヘーゲルは骨相学についても、死んだ骨からは生きた精神を観察できないとして、人相学同様に退ける。
したがって、ある人間をつかまえて、「お前の頭蓋はこうなっているから、お前は(お前の内面は)こういう人間だ」というとしたら、その意味するところは、頭蓋がお前の現実のありさまだ、というにほかならない。人相学でそんな判断を示されたとき、人相学者に平手打ちをお見舞いする話をしたが、それは人相学の見解と現状にたいする軟らかい部分への反撃にすぎず、平手打ちされる軟らかい顔面が精神の本体でもなければ、現実のありさまでもないことを示すにとどまったが、ここでは、判断にたいする反撃が相手の脳天を打ち割るところまで行くべきで、骨が人間にとってそれ自体ではなんの意味もなく、まして、人間の現実のありさまをあらわしてなどいないことを、相手の知恵にふさわしい明確さをもって示すには、そうするしかないのである。
いま引用したのは、まぎれもなく『精神現象学』(長谷川宏訳、作品社)からであり、樫山欽四郎訳(平凡社ライブラリー)でも、「平手打ち」が「横面をはりとばす」に、「脳天を打ち割る」が「頭蓋骨を打ち砕いて」になっているだけで、大きな違いはない。だがら、ここで述べられているヘーゲルの主張を要約すれば、やはり「人相学者の横っ面を張り倒せ、骨相学者の頭蓋を叩き割れ」としかならないのではないかと思うのだ。
人相学と骨相学についてのヘーゲルの明快な論断は、観察された事実から法則を導き出す際に思いこみが混入することへの洞察から導かれている。ヘーゲルが挙げている例の一つに、洗濯物を干そうとするといつも雨になる、という主婦のぼやきがある。その主婦が洗濯物を干した、その日に雨が降ってきた、いずれも観察された事実だろう。けれども、その主婦が洗濯物を干したことと、その日に雨が降ったこととの間には必然的な関係はない。「実際は、自分の思いこみを語っているにすぎず、したがって、事柄をあきらかにするのではなく、自分にかんする思いをもちだしているにすぎない」。
もっとも、その主婦にとって晴天の日は畑仕事や買い物などで外出することが多いことから、結果的に自宅で洗濯などをする日は雨になるという事情もあったかもしれないが、ヘーゲルがそれに気をまわした形跡はない。忙しくて雨の日くらいしか洗濯するヒマがないのよ、というのがその主婦の言い分だったかもしれないが、それこそ「自分にかんする思いをもちだしているにすぎない」ということなのだろう。「観察する意識は、思いこみのままに、人相、筆跡、声調、等々を手がかりとして、そのむこうにあるものをさぐりだそうとする」。人相学も骨相学も、このようなものだとヘーゲルは断じた。
4 ぶしつけな懐疑
頭蓋論は、当初はガルの医師としての経験則から生まれた仮説として提唱されたものではあったが、オッペンハイム『英国心霊主義の抬頭』(工作舎)によれば、やがてガルの意図した範囲をはるかに越えて、メスメリズムという一種の催眠療法と融合し、「骨相磁気学」(磁気的骨相学も同じ)という、さらに怪しげなものに進化した。
骨相磁気学は学問と言うよりも、一種のショーの演目である。学術講演会という名目で集まった観衆を前にして、催眠状態にされた被験者の頭のどこかを施術者が刺激すると、被験者はガルの頭蓋論で示された通りの反応をする、というものである。このショーの実演者としてもっとも有名だったのが、スペンサー・ホールだったそうだ。ホールによる骨相磁気学の実演会がどのようなものであったか、オッペンハイム『英国心霊主義の抬頭』から、1843年ノッティンガムでの記録を孫引きする。
彼女の頭の前から後ろへ手を泳がせただけだった。三分後、彼女の目は閉じられ、五分後には頭がうなだれて、深い磁気的眠りに入った。「崇拝」と「言葉」を刺戟すると、彼女は小さい声で祈りはじめた。「音楽」の刺激では、大きい声で賛美歌を唄った。「秘密」の器官が触れられると、何を考えているのかと問われても「貴方には言いません」と答える……「真似」の刺戟で、観客が手を叩くと彼女も叩き、それ以外にもいくつかの音を真似して笑いを誘った。
オッペンハイムは「このような『説教』は成人向け教育というよりも純粋な娯楽であり、シェフィールド、マンチェスター、ヨーク、ダービー、ミドルズブラ、ブラックバーン、リバプール、バーミンガムなど各地で繰り返された」と、ホールの活動を記している。イギリス各地を巡回公演していたわけだ。それらのうち、マンチェスターでの公演を、当地に滞在していた若いドイツ人ビジネスマンが見聞していた。
ところで、私もたまたまこのスペンサー・ホール氏を同じ一八四三年―四四年の冬にマンチェスターで見たことがある。この男は全然月並みのいかさま師で、二、三の坊主どもの援護のもとに国内を流して歩き、一人の若い女の子を使って磁気―骨相学的な見世物をやっていて、これによって神の存在、魂の不死性、並びに当時オーウェン主義者によってすべての大都会で説かれていた唯物論の無効を証明しようというのであった。この女は磁気的催眠にかけられ、術者が彼女の頭蓋の任意のガル氏器官に触れるとたちまち、当該器官の活動を示すところの芝居がかった精一杯の身ぶり素振りをやった。例えば小児愛の器官にあっては彼女は仮想の赤ん坊を愛撫し接吻するなど。
そして、ホールはガルの頭蓋論で示されている機能だけではあきたらず、頭のてっぺんに「崇拝」という機能を新たに設定していた。そこを刺激すると「かの催眠少女はひざまずいて両手を合わせ、崇め慕って歓喜にむせんでいる天使を驚いている善男善女の前に演出してみせた。これがこの見世物の大団円であり頂点であった。神の存在は証明せられたというわけであった」(エンゲルス『自然弁証法』岩波文庫、引用にあたり一部の表記を変えた)。
1842年、父親の経営する会社のマンチェスター工場を監督するために、イギリスに単身赴任したフリードリッヒ・エンゲルス(1820-95)は、そこで、後に一大ブームとなる交霊会の原型とも言える骨相磁気学に出くわした。当時まだ22歳の青年だったエンゲルスは友人と実験に取りかかった。ホールの骨相磁気学を再現してみようとしたのである。詳細は略すが、12歳の少年を被験者とした実験はあっけないほど簡単に成功した。ガル頭蓋論の分布図で示された場所と機能を入れ替えることも新たな機能を付け加えることも自在になしえた。結局、骨相磁気学とは医学的・解剖学的所見とは無関係の催眠術にすぎず、ガルの頭蓋論はレトリックとして用いられているだけだったことが暴露されたのである。
ヘーゲルが死んだ骨から生きた精神を観察するようなものだと言ったように、ガルの頭蓋論には唯物論的側面、現代でいえば科学主義的傾向があった。それが催眠療法であるメスメリズムと結びつき「骨相磁気学」と化したことによって、頭蓋論のメカニズムを、人間がコントロールしうるものになった。近代自然科学の背景には機械論的唯物論がある。その決定論的傾向は人間の自由意志や精神の価値を無効にするものと受けとめられた。それに不安を抱いた人々は、精神の優位という構図のもとで科学をコントロールしたいという欲望を抱いたのである。その願いに応えたのが骨相磁気学という超科学である。
すでにフォイエルバッハの影響下に唯物論の立場をとっていた若きエンゲルスが、この骨相磁気学に「ぶしつけな懐疑」をもって挑み、嘲笑したのは当然であった。しかし、『自然弁証法』の執筆をはじめたエンゲルスはすでに円熟の境地にある。若き日の手柄話を得意げに吹聴するだけでは終わらない。エンゲルスが、ホールの骨相磁気学の思い出話を持ち出したのは、ウォーレス批判の文脈であった。
A.R.ウォーレスはダーウィンと相前後して進化論を提唱した生物学者である。ウォーレスの生物学者としての活躍については新妻昭夫『種の起源をもとめて』(朝日新聞社)に詳しい。しかし、「生物学者」といっても、現代の基準をあてはめるとちぐはぐな印象を受ける。よく知られているように、ウォーレスは心霊主義を信奉し、「心霊主義にもとづく、自然選択の人間への適用の否定」(新妻、前掲書)を唱えて、ダーウィニズムから逸脱した。再びオッペンハイム『英国心霊主義の抬頭』によれば、彼は人間の心だけは生物進化の例外であり、「人間の精神的成長は、自然界の他の現象とはまったく違って独自の過程を辿るとした」のだという。
オッペンハイムは、ウォーレスが心霊主義の領域に近づいたのは、一八六五年に交霊会に出席しはじめてからと認定しているようだが、同時代の観察者であるエンゲルスによれば、ウォーレス自身が著書のなかで、一八四四年にメスメリズムについてのホールの講義に出席して興味を持ち、自らも実験してみてガル頭蓋論の正しさを確認したと述べているという。つまり、エンゲルスの標的は、ホールではなく、ウォーレスだったのである。
5 ありえるのではない、あるのだ
エンゲルス『自然弁証法』の冒頭に据えられた「心霊界における自然研究」は、十九世紀の中頃からイギリスを席巻した心霊ブームを、同時代に居合わせた思想家がとらえた記録でもある(ついでだがオッペンハイムの大著にエンゲルスのエの字も出てこないのはどうしたわけか、同時代の証言として貴重だろうにと不審に思う)。
ところでエンゲルスと言えば、カール・マルクスの陰にかくれて、いまひとつパッとしない、いや失礼、縁の下の力持ち的存在だが、かつて廣松渉は、エンゲルスとマルクスとの共著『ドイツ・イデオロギー』の成立過程におけるエンゲルス主導説を唱えて、この地味な、いや、謙虚な男に脚光をあてた。そこで、もしやエンゲルスの心霊主義への挑戦について、かの碩学が卓見を示しているのでは?と思って、名著の誉れ高い『エンゲルス論』(廣松渉著、ちくま学芸文庫)をひもとき、とくにその第4章「マンチェスター時代」は目を皿のようにして読みふけったが、残念ながらエンゲルスと骨相磁気学との邂逅については何も述べられていなかった。エンゲルス自身の思想形成やその思想史上の意義については、廣松『エンゲルス論』にゆずるとして、私としては、「心霊界における自然研究」の非思想的側面にのみ注目したい。
さて、エンゲルスが若き日の武勇伝を持ち出して骨相磁気学のトリックを暴いたのは、ダーウィンと並ぶ進化論の提唱者ウォーレスを批判するためだった。ウォーレスはすでに心霊主義の代表的論者だった。三たび、オッペンハイムを引けば、ウォーレスの心霊現象についての態度は次のようだった。
ウォレスは科学者としての責任感から心霊現象を研究したのではない。一八六五年に交霊会に出席しはじめると、即座に揺るぎない信念を抱いてしまったようなのだ。(中略)ウォレスにかかると自分が目撃した現象を疑うに足る証拠がないとなってしまう。自分の五官で確かめた証拠、数世紀にわたる無数の研究者たちの記録、これらは心霊主義の正当性の十分な基盤になっていると彼は信じていた。
これはエンゲルスの「彼はホーム、ダヴェンポート兄弟、その他の多かれ少なかれ金銭を払えば見ることができ、かつ大部分は度々詐欺師として仮面を剥がれたことのある「霊媒師」のいずれも名ばかりの奇跡だけでなく、昔から見かけだけはもっともらしい心霊談の一切合財をも真に受けることを要求している」という記事に一致している。
エンゲルスは、ウォーレスの強弁ぶりの例として、心霊写真を挙げている。当時の心霊写真は、例えばハーヴェイ『心霊写真』(青土社)で見ることが出来るが、どこから見ても合成写真にしか見えないものばかりで、これをどうして霊が写っていると思い込んだのか、その方がよほど不思議である。しかし、ウォーレスはびくともしない。これが心霊写真でなければ詐欺だ、しかるに自分はこの写真に写っている(生きている方の)人たちをよく知っているが、「この人たちは自然科学の領域における一人の真面目な真理探究者と同様にこの種の詐欺ができないのだ、という絶対的な確信を私は持っている」。詐偽ではない以上、これは真正な心霊写真である、というわけだ。
自らの「絶対的な確信」に居直るウォーレスにあきれながらも、エンゲルスは問題の写真を写した写真師が「心霊写真の常習的偽造で公に罪に問われた」ことを指摘しているが、この事実すらウォーレスの「絶対的な確信」には説得力を持たないだろうと、投げやりな皮肉を言っている。
「心霊界における自然研究」でウォーレスと並んで槍玉に挙げられている科学者にウィリアム・クルックスがいる。タリウムの発見などでノーベル賞も授与された人物だが、フローレンス・クックという若い霊媒にメロメロになってしまった。クックは女性の幽霊を召喚することができた。「この心霊は自分ではケーティーと名乗り、クック嬢に驚くほどよく似ていた」。つまり、エンゲルスはケーティーとクックが同一人物(同一霊?)である可能性を示唆しているのだが、クルックスは、ケーティーとは縄抜けをして衣装とメイクを替えたクックかもしれないとはついぞ思わなかったらしい。
彼女はクルクス氏の宅でまでも出現し――今となってはこのことをわれわれは毛頭不思議には思い得ないが――、彼の子供たちと遊び、(中略)わが身を氏の腕にとらせて、それによって氏が彼女の手応えのある物質性を確信するようにし、彼女の一分間の脈拍と呼吸の数を確かめさせ、そしてしまいにはまたクルクス氏と並んで写真をとらせもした。
その折の記念写真と思われるものが、先に挙げたハーヴェイ『心霊写真』に掲載されている。「ケイティ・キングの肖像」と題されたその写真は、白い紗のような衣装をまとった若い女性と髭を生やした男性が、まるで花嫁とその父のように腕を組んだ姿で写っている。先に、当時の心霊写真は見るからに合成写真ばかりだと書いたが、この写真はそれどころか、どこから見てもただの写真である。おそらくは髭の男性がクルックスで、彼にエスコートされている女性が自称ケーティー・キングなのだろう。
クルックスやウォーレスはあくまでも彼女をクックの呼びだした幽霊だと信じていたようだが、ケーティーが活動しているあいだクックが閉じ込められているはずの部屋には隠し扉があり、自由に外部と往来できるようになっていたことが暴かれていることをエンゲルスは付け加えている。しかし、何を言っても彼らには通用しなかったろう。クルックスは心霊現象について「ありえるのではない、あるのだ」と豪語したと伝えられる。
ちなみに、ケーティーとクックは同一人物だろうという説はエンゲルスの独断ではなく、当時、同様の疑問を抱いた人は多くいたらしい。作家のコナン・ドイル(1859-1930)もまた心霊現象に多大の関心を示した。名探偵シャーロック・ホームズの生みの親なのだから、イカサマ心霊術のトリックをあざやかに見破ってくれてもよさそうなものだが、交霊術に取り憑かれてしまったようである。『コナン・ドイルの心霊学』(新潮社)に収められた「重大なるメッセージ」では、「霊媒のクックが変装しただけだろうという疑問に対しては、二人がいっしょに写っている写真がその疑問を打ち消してしまう」と書いてクルックスを擁護している。1921年発表のホームズもの「マザリンの宝石」(『シャーロック・ホームズの事件簿』所収)でドイルは、ホームズが自分そっくりの人形で容疑者の目を欺く場面を描いているというのに。いやはや、どう思う?ワトソン君、とホームズが肩をすくめそうである。
6 返事はまだ来ない
この他にも「心霊界における自然研究」には面白い話がたくさん載っているのだが、このくらいにしよう。エンゲルスの暴露は、途中までは奇術師ハリー・フーディーニ(1874 - 1926)の仕事と変わらない。フーディーニと並べるのはエンゲルスをおとしめているのではなくて、むしろその反対である。奇術王フーディーニなら、はるかに手際よく交霊術のトリックを暴いただろうから。
ところで、フーディーニが交霊術に関心をもった理由が、亡き母親の霊と再会したかったからだということはよく知られている。ただ、本業が奇術師だっただけに、霊媒の下手なトリックにすぐに気づいてしまった。フーディーニは、本当の霊媒を探そうとしていたのだ。
一方のエンゲルスにしても、霊媒のイカサマ暴露に取り組んだのは、それ自体が目的ではない。ウォーレスもクルックスも、専門の自然科学の領域ではすぐれた業績をあげた科学者である。それが、子供だましに近い交霊術のトリックに気づかなかったのはなぜか。それが彼の問題意識だった。
廣松渉はエンゲルスが『自然弁証法』を書いた企図について、次のように指摘している。
エンゲルスは、経験論的実証主義にも批判を向けるが、さしあたっての問題は「自然科学がイギリス経験論から受け継いだそれ特有の偏狭な思考方法」(中略)、この「形而上学的」な世界観、存在観、思惟様式の排却に懸る。(『物象化論の構図』)
エンゲルス自身の言葉も引いておこう。
どれが自然科学から神秘主義への最も確実な道かということが手にとるように明かに示されている。それは自然哲学の深々と茂った学説ではなくておよそ浅薄な、あらゆる理論をさげすみ、一切の思考を頼みとしない、経験主義である。心霊どもの現存を証明するものは先天主義の必然性ではなくて、却ってウォーレスさん、クルクスさん及びその一派の経験的な観測なのである。
ヘーゲルが「人相学者の横っ面を張り倒せ、骨相学者の頭蓋を叩き割れ」という元気のいい結論に至ったのも、経験はそれ自体では法則や原理とはならず、そこには思い込みがまぎれこんでいるからだった。エンゲルスも「単なる経験主義は心霊術者連を片付けることができない。第一にこの「高級」諸現象はいつも、既に当該「研究者」が自分が見ることになっているもの或は見ようと思っているものだけしか見ないまでにすっかりとらわれてしまっているときにだけはじめて示されるのである」と指摘する。この点に注目する限り、エンゲルスはヘーゲルの良き後継者である。あるいはここから、ドイツ観念論とは経験論、すなわち認識論における大英帝国を仮想敵とするヴァーチャルな戦いであったとする仮説を導き出せるかもしれないが、それはまた別の話。
かくしてエンゲルスは言う。「視霊家の強弁は経験的な実験を以てではなく、却って理論的な省察を以て始末しなければならない」。なるほど、経験とは私たちの関心に制約されるし、経験に与えられるものはすでに演出(加工・編集)されたものかもしれない。だから、経験に与えられた出来事をそのまま真実とみなすのではなく、それは原理的に可能なものであるかどうかを検討する必要がある。しかし、「視霊家の強弁」を「理論的な省察を以て始末しなければならない」とエンゲルスは言うが、はたしてそう簡単に始末できるものだろうか。経験を制約する関心、この場合は、亡き人に再会したいという願いは、結構しぶといものなのだ。
かく言う私自身、旧友の死を知らされてから一ヶ月も経った頃、彼女に宛ててこんなメールを送っていた。
「いまだに君がいなくなったのが信じられないのだが、もし悪い冗談だったなら、機嫌を直して返事をくれないか。」
あれから半年経ったが、返事はまだ来ない。
★プロフィール★
広坂朋信(ひろさか・とものぶ)1963年、東京生れ。編集者・ライター。著書に『東京怪談ディテクション』、『怪談の解釈学』など。 ブログ「恐妻家の献立表」
Web評論誌「コーラ」15号(2011.12.15)
<心霊現象の解釈学>第2回:単なる経験の範囲内における心霊現象(広坂朋信)
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2011 All Rights Reserved.
|