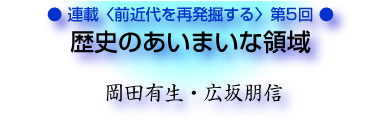|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「La Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
|
田楽ダンスは上手く踊れない(広坂朋信)
■高時天狗舞
『太平記』の「相模入道田楽を好む事」(第五巻4)は、田楽に耽溺する得宗北条高時を印象的に描いている。
当時、京都で田楽が大流行だと聞いた高時は、田楽の一座を鎌倉に呼んで、これに夢中になった。ある晩、酔った高時が自ら田楽舞を踊っていると、どこからか十数名の田楽一座の者があらわれて、高時とともに舞い歌った。これが実に面白かった。しばらくしてから歌の調子が変わって「天王寺の妖霊星を見ばや」と歌いはやした。高時の屋敷に仕えていた女中が障子の穴からのぞいてみると……。
田楽一座の踊り手と思っていたものは一人も人ではなかった。あるものは口ばしが曲がり、あるものは背に翼をはやした山伏姿で「ただ異類異形の怪物どもが、姿を人に変じたるにてぞありける」。
驚いた女中の通報で高時の舅が駆けつけてみると、化け物どもはかき消すようにいなくなり、座敷には高時一人が酔いつぶれて寝ていた。天狗でも集まっていたのか、畳の上には鳥獣の足跡が残っていた。
北条高時が夢中になった田楽とは何か? 中世にブームになった芸能で、能・狂言の源流の一つということはわかるが、それだけではイメージがつかめない。高時が田楽に夢中で政治を省みなかったため足利や新田の離反を招いたという説を私はとらないが、しかし、鎌倉幕府の滅亡も、その後の一連の動乱も、田楽をBGMにして演じられた。
■「面白すぎて死ぬー!」
田楽は『太平記』の書き手たちが動乱の時代を回顧するにあたって想起せざるを得ない、時代とともにあった流行であった。この田楽とはいったいどのような芸能であろうか。京都の人びとは、天皇以外はみな見物したと言われほどの人気を博した田楽の実像はよくわからない。当の『太平記』に「田楽の事」(第二十七巻9)という章がある。京都で大規模な田楽が催された折の事件についての記事である。
鎌倉幕府が滅び、復位した後醍醐天皇による建武の新政の混乱を経て、新田義貞との抗争を制した足利尊氏が室町幕府を開いた後のことである。すでに南朝のカリスマ後醍醐は吉野で憤死し、楠正成の遺児・正行を大将とする南朝勢の反撃も足利家の重臣・高師直の指揮する戦闘によって退けられ、持明院統の天皇を担いだ足利幕府が権力基盤を固めつつあるように見えた。
もっとも、室町幕府内部では、軍事面での功臣・高師直一派と、尊氏の実弟で幕府の行政面での指導者であった足利直義とのあいだに不和が生じ、緊張が高まっていた。こうした時期に京都・四条河原で大規模な田楽興業が行われた。
この四条河原勧進田楽には、人気一座が一堂に会して芸を競うとのことで、大勢の人々が集まった。会場には見物席として三層の桟敷が急造され、将軍、関白、天台座主といった高位高官も訪れて、京の人びとは天皇以外はみな見物に来たとまで言われた。見物人が鈴なりになったこの桟敷が崩れて大事件となるのだが、本稿ではそのことではなく、ここで演じられた田楽についての記述を見ていきたい。
まずはオープニング。
派手な衣装をまとった美少年(容疑美麗の童)・美青年(白く清らかなる法師)たちによるダンス・パフォーマンスでショーは始まった。
最初の演目は本座の阿古のびんざさら、続いて新座の彦夜叉が乱拍子で芸を競った。びんざさらとはリズムをとる打楽器で、乱拍子は小鼓を使う。
次の演者は「日吉山王の示現利生の新たなる事をしけるに」というから、山王権現の霊験譚から題材をとった新作を披露したのだろう。
「おどりいでたり」と読む語句に「跳り出でたり」と漢字をあてるところにも躍動感がある。
新座の閑屋が演じた新作は、観客を熱狂させ、「あら面白や。堪へ難や。われ死ぬるや。これ助けよ」と叫び騒ぐ声が小一時間も続いたというから、たいへんなものである。興奮した観客が騒いだため、三層の桟敷が崩れ、多数の死傷者を出すことになった。将軍・足利尊氏隣席の田楽興業で起きた大惨事は、やがて始まる室町幕府内の内紛、足利直義と高師直による権力闘争の予兆であったというのが『太平記』作者の趣向なのだが、私の関心は演じられた田楽にある。
派手な衣装に猿の面などを身に着けていたこと。びんざさら、小鼓の乱拍子というから、かなりリズミカルなものだったようだ。拍子を踏むのだから、舞いというよりダンス。飛んだり跳ねたりしたらしい。そういえば、「相模の入道田楽を好む事」(第五巻4)でも、高時が躍り疲れ酔いつぶれた座敷には「踏み汚したる畳の上に、鳥獣の足跡多し」とあった。足踏みで拍子をとるダンスがイメージされる。
田楽が現代にも伝えられる能楽の源流の一つであることは、世阿弥の『申楽談儀』にあることからも確かだ。私たちが能楽の舞台を見物するときに、知らず知らずのうちに能楽に継承された田楽のある要素も見聞しているということになる。ただしそれが何かは曖昧模糊としてはっきりとはわからない。
そもそも『太平記』の記述から想像される田楽のイメージは、現代に伝えられる能楽から受ける印象、幽玄とか、内容を知らないと眠くなるとか、典雅で静かな古典劇というものとは大いに異なっている。観客が「面白すぎて死ぬー!」と絶叫するほど興奮を喚起する舞踏劇だったらしい。
■ジャズ的リズム
松岡心平は著書『宴の身体』(岩波現代文庫)の第2章で、田楽の流行が「悪党の流行とある意味では軌を一にしている」ことに着目して、「日常の側への強烈な侵犯力をも含む悪党的な放埓な行動性を、芸能のレベルで、さらに純化した身体の形として示しているのが田楽である」とする。松岡氏は『太平記』、世阿弥『申楽談儀』以外にもさまざまな史料にあたって、田楽がどのような芸能だったかを描き直そうとしている。以下、松岡氏の描く田楽の身体を見ていく。
松岡氏は『東寺御修法記』(一一四一)という文献から田楽について「狂乱婆娑」という形容を取り出して「田楽の群舞の狂乱婆娑的性格は、その音楽の喧騒さや、即興性、リズムの変幻に負うところが大であった」として、『中右記』の記事にも「田楽が、「喧嘩(かまびすしい有様)」で、即興性に富み、自在のリズムをもっていた様子」がうかがえるとする。
リズムに注目する松岡氏は、田楽で用いられる打楽器びんざさらについて「踊り手のステップに従うその乾いた切断的騒音のリズムによって「鼓笛喧嘩」を支え、これに交りあっていたにちがいない」。そして、鼓笛の鼓は小鼓と腰鼓で、「わけても小鼓の方には曲打ち傾向が顕著であった」ことを『鳥獣人物戯画』や『年中行事絵巻』などを例示して見せる。「こうした小鼓や腰鼓の曲打ちは、田楽のリズムに一層の変化と即興性を与えたことだろう」。
このように田楽のリズムの特徴を喧騒さ、即興性、リズムの変幻自在さに見る松岡氏は、それを大胆にも「ジャズ的リズム」と形容し、先に『太平記』から紹介した北条高時と天狗のダンスについて、「ジャズ的リズムに乗って乱舞し曲芸をも行なう田楽の身体」を「鳥の比喩で捉え」たものと解釈する。
あたかも現代舞踏の批評を読まされているようだが、この傾向は『太平記』の四条河原勧進田楽について述べるにあたり、さらにエスカレートしていく。
しかし、こうした解釈はあくまで解釈であって、松岡氏はまるで見てきたように書いているが、それが北条高時が夢中になり足利尊氏も見物した田楽と同じものかどうかを私たちが知ることはできない。伝統の源流を語ることは、作業仮説としてであればともかく、ややもするとそれを語る現代人の期待や不安、あるいは現実の投影になりかねないことは、よく知られている。
竹の子族とか言い出すと、いかにもバブル世代の思い出話のようで恐縮だが、しかし実際、青少年層が路上でダンス・パフォーマンスを始めたのは八〇年代初頭からである。ドゥルーズ/ガタリ『ミル・プラトー』の部分訳(『リゾーム』)が出たのは1977年。上に紹介した文章を松岡氏が書いたのは1984年、掲載誌は『へるめす創刊号』(岩波書店)で、今読み返せば、いかにもあの時代ならではの筆づかいとも感じられる。
田楽は実在した。後世にも大きな影響を与えた。けれども、それがどういうものであったかは、よくわからない。歯がゆいようだが言えることはここまでである。
羽仁五郎の抵抗線(岡田有生)
■壬生狂言と花田清輝
去年から何度か、京都壬生寺の壬生狂言を見る機会があった。
鎌倉時代の正安年間に始まり、700年以上の歴史を持つとされるこの伝承芸能は、プロの芸能者ではなく、地域の人々によって受け継がれてきた、無言の仮面劇だ。狂言とはいっても、能と同様に言葉(台詞)がないのである。
背景に流れる音楽も、かね・太鼓・笛の三つだけによるたいへんシンプルなものであり、それに合わせて仮面をつけた人たちが仕草で演じる筋そのものも、会場で安価で売られている台本を見ない者には、なかなか分かりにくい。5月初めの好天の下、薫風に吹かれながら屋外で演じられるこの夢幻的な舞台を見ていると、私などは文字通り夢幻の中に迷い込みそうになる。
だが、さすがにいくつも演目を見るうち、気づくこともある。毎日決まって最初に演じられることになっている「炮烙割り」という、壬生狂言の代名詞的な演目では、演じ慣れているためか、演者の仕草が伴奏とピタリと合って、ひときわ見事であり、この芸能が、演劇というより舞踊に近いものであることが実感される。
そこには言葉はないが、言葉以外の要素が伝承され、見る人たちにも一つの力として伝えられ共有されていく。そういう目に見えない、民衆の力の伝承のようなものを、ぼんやりとイメージできる思いがするのだ。
今回も花田清輝のことに触れるが、エッセイ集『もう一つの修羅』に入っている「日本人の感情表現」(1960年発表)という文章のなかで、花田は郡司正勝が『かぶきの発想』のなかで論じている新潟県刈羽郡女谷につたわる綾子舞の狂言の方について、次のように書いている。
ここを読んでいると、私などは「なるほど」と感心するのだが、しかし花田はこう切って捨てた後で間もなく前言をひるがえして、こう思いなおすのである。
読んでいる方としては、「どっちやねん!」と突っ込みたくもなるが、このどっちつかなさ自体が「日本的な独自性」ということになるのであろうか。
いや、「日本的な独自性」などというからややこしくなるので、やむをえずそうなる場合も民衆にはある、というぐらいにしておけばいい気がするのだが。
実際、花田自身がよく知っていたであろうように、そんな「基本的な型」や「仕草」を演じる民衆の腹の底など、だれにも見通せるものではないだろう。朝鮮人や中国人を虐殺したのも、ヒトラー政権や安倍政権を生み出したのも、やはり民衆なのである。
しかし、そういえば、壬生狂言で使われる仮面は、どこか朝鮮の農民たちのマダン劇のそれを思わせるところがある。以前に奈良の国立博物館で、奈良・平安の頃に日本に伝わった仮面の展示を見た時、伎楽などで用いられる豊かな表情の仮面が、能などのオーソドックスな芸能にはあまり伝承されなかったらしいのを知って、不思議に思ったものだが。
■現在からみる歴史
田楽というものは、私は見たこともない。壬生狂言の発祥もそうであったとされるような、民衆の信仰にかかわるルーツを持っているのだろうか?
しかし、五味文彦著『殺生と信仰―武士を探る』(角川選書 1997年)を読んでいると、久安年間に平清盛が祇園社に「田楽」を調立した(意味が定かに分からない語だが)時に闘乱が生じ、山僧が清盛の流罪を求めて蜂起したことを理由に、鳥羽院が「源氏平氏之輩」に坂本の守護を命じて比叡山の山僧の入京を阻止する措置をとり、その際に守護する武士たちの閲兵を行うという派手なデモンストレーションを院がやったことが書かれているから、元来この田楽というものには、なにやら武力とか動乱に通じるような、物騒な性格が秘められているのかもしれない。
北条高時が耽溺したというのも、むべなるかなというところである。
ところで、動乱というと、最近私は羽仁五郎の著作にハマっているのだが、筑摩叢書の一冊として1986年に出た『羽仁五郎歴史論抄』という本のなかに、「歴史教育批判」(1936)という戦前の論文が収められていて、他の文章同様、今読んでも、いや今読むからこそ実に面白い内容なのだが、そこにこんなことが書いてある。
ここで羽仁は、わが「国史」の教科書というものは、『政治的活動の常態についてよりもその非常の場合のみを、それも社会的変革としてではなく支配の上の激変として、好んで叙述』するものであるとし、それについて、
と書いている。
ここで、やっと「北条氏尊氏足利氏等」が出てきて、少しほっとしたが、羽仁の「人民史観」は、やはり『太平記』とは折り合いが悪いことは間違いなさそうだ。
だが、とはいえ、『太平記』を好んだ者の多くも、また「人民」ではなかろうか。
羽仁は、ファシズムの時代というものを体験したにしては、人民・民衆というものを、あまりに理想化してしまっているのではあるまいか。
しかし、ここはよく考えてみなければならないところだ。
人民史観と呼ばれる羽仁の歴史に対する考え方は、私淑していたイタリアの哲学者クローチェの影響下で形成されたものだ。クローチェの歴史哲学は、羽仁自身の要約によれば、『すべての歴史は、現在の歴史であり、現代の歴史である』(p284)というテーゼになるのだが、羽仁におけるこの思想をよく表していると思われるのが、やはり戦前に書かれた「新井白石と国語の時代」(1939)のなかの、次のような一節である。
これは、たしかに進歩を礼賛する近代主義的な歴史観にみえる。だが、むしろ、ここで羽仁が批判しているのは、「1939年の日本」という差し迫った「現在」の重要さを、過去から未来に流れる既定の時間のなかに解消してしまうような線形的な歴史の捉え方であり、そのなかに「人民」の抵抗や解放の可能性を閉じ込めてしまおうとするような発想と力なのである。
その力は、個々の社会の事情に応じ、ときに復古的な装いをしてあらわれて、啓蒙や進歩の圧力に反発する民衆の心を籠絡したり、また「改革」の美名のもとに、やはり民衆の願望や欲望を巧みに動員したりする。
いずれにせよ、その本質は人々の生きる力の統制ということであり、秩序の中に人間の歴史を封じ込めるということだろう。そのために、この力は、人々の意識から差し迫った「現在」を遠ざけておこうとするのである。
この力(国家権力とかシステムと呼んでもよいが、民衆自身をもそこに含むもの)との対決の姿勢こそが、一時は成立直後のムッソリーニ政権に接近しながら、やがてイタリアの反ファシズム運動の精神的支柱とみなされるようになったクローチェから、羽仁五郎が学びとったものだったと思う。
羽仁は、1933年に逮捕され、拘留中に「手記」を書いて釈放される。いわゆる「転向」といってよいだろう。
だが、多くの注目すべき羽仁の仕事は、その後に集中的になされ、それは1942年に遂に一切の発表が許されなくなるまで、信じがたいほどのエネルギーを傾注して続けられた。
そのことは、「転向」の事実を消し去るものではないが、後年彼が、この逮捕を契機として『いままでの歴史学ではだめだ、新しい歴史学を発見しなければならない』と確信するに至ったと述べているのは、彼がここでクローチェの継承者としての(つまりファシズムへの抵抗者としての)本分に目覚めたということを意味しているのだと思う。
それは、ファシズムにやすやすと呑みこまれていく目の前の民衆自体を、彼が直視と対決(働きかけ)の対象として選んだということと同義である。
それに関連して、同じく「新井白石と国語の問題」から、もう一カ所引いておく。
■曖昧なものの評価をめぐって
ところで、民衆の生を統制しようとするこの力は、この時期の日本において、ファシズム(民衆の、強権への積極的加担)という形をとって出現したわけだが、そのような姿をとるのは、やはりこの国家と社会が、天皇制という特殊な近代国家の形態をとっていることに深く関わっているといえる。
その特殊性についての理解を、羽仁は講座派の代表者、野呂栄太郎から学び、さらにそれを独自に深めたと思われるのだが、それについて、敗戦直後の1946年に書かれた「日本歴史の特殊性」では、次のように述べられている。
なお、以下で言われている「氏族社会」とは、ほぼ原始共産制と言い換えてよい概念だと思う。
これは、字面においては古代史を語ったものだが、あくまで「人間天皇」としての天皇裕仁の復権が歴然としてきた「現在」において述べられていることが肝心だ。
羽仁にとって、明治天皇を立てた維新以後の国家体制は、内外の帝国主義勢力の要請による封建制の残存という世界史的な意味づけをされるものだったのだが、同じことが、意匠だけを「民主主義的」なものに変えて、敗戦直後の「現在」においても繰り返されつつあると羽仁には見えたのである。
この「残存」が要請されるのは、天皇のユートピア的で温和(人間的?)な「外被」、また神秘的な「悠久のすがた」によって、人民の奴隷化に結びつくような過酷な帝国主義の支配の「現在」が人々の意識から隠され、革命と解放の必要性が忘れられることになるからである。
天皇という特殊的なものが、日本という近代国家における人々の意識のあり方を決定している。それは、神秘的な悠久の存在に調停者のような役割を仮想することで、過酷な支配の現実から目をそらし続けようとする態度だが、もちろんそのことによって、他者の存在を含む、私たちの生存の全体が、現実には犠牲となっていく。「戦後体制」もまた、この構造を破却することはなかったのである。
先に触れた花田清輝のエッセイのなかで述べられていた、民衆の芸能に表れている『抵抗しているのか、心服しているのか、嘲笑しているのか、さっぱりわからないような型』というものが、この天皇の存在に関わっていることは、確かだと思われる。
それは、支配権力との直接的対決を避け、場合によっては、それに迎合することで生き延びよう、あるいは地位や財産を保持しつづけようとする民衆の意思を表現しているかのようである。
花田はそれを、「日本的な独自性」と呼んでいたわけだが、それはむしろ、天皇のような前近代からの「残存」が、支配を容易にする精神的な装置として機能する社会では、どこでも見いだせるような民衆の生の実態なのではないだろうか。
なにより、天皇制という、頂点に立つ者が責任を問われずにすむような構造は、そこに生きる民衆個々の、加害性を含む責任をも曖昧にできるという効果を持つので、民衆自身にとっても実は都合のよいものなのである。
戦前の「ファシズムの時代」に、天皇制下の民衆のこうした実態に直面することを余儀なくされた羽仁五郎は、それを肯定(自然化)するのでもなければ、無視するのでもなく、目の前にある現実として見据え、そこにこそ働きかけて社会を作り変えていこうとする道を、選んだのだと思う。
だが、ここで確認しておきたいのは、民衆のこの曖昧なあり方に対する、羽仁と花田のスタンスの違いである。花田の場合、逡巡しながらも、結局はそこにしたたかな抵抗のポテンシャルを見ようとする態度に傾いていると思われる。それは、特に60年以後の、大衆向けの歴史読み物に接近したような花田の創作の傾向と関係するだろう。
一方、羽仁の場合には、この曖昧な領域は、あくまで働きかけ(啓蒙)によって作り変えられていくべき対象なのであり、その前近代性はやはり否定されるべきものと見なされていたとみるしかなかろう。
そのことは、先に触れた羽仁の歴史観とも関連している。羽仁にとって歴史とは、現在を起点とした進歩の道筋においてこそ真に存在しているものであって、その現在から照射される限りでのみ、過去は意味を持つ。そこでは、この光によって明確な意味を与えられないような、曖昧な姿をした過去というものは、切り捨てられると考えざるをえないのだ。
これはずいぶん、暴力的な態度に思える。コギトの光に照らし出されないものは、存在していない(いなかった)のと同様だと、羽仁は言いたいのであろうか?
だが、ひるがえって考えてみると、花田のように、民衆が示した曖昧な姿勢に抵抗のポテンシャルを読み込もうとすることも、やはり現在の願望にもとづく態度ではなかろうか。羽仁の態度も、花田の態度も、どちらも政治的なのである。
そして、羽仁がもっとも警戒したのは、曖昧な領域に自分たちが期待する意味を仮託し、神秘的な意味づけをすることで現実の過酷さから目をそらしていようとするような人々の心のあり方であり、それを巧みに利用するこの国の支配権力の手口だった。
それは、曖昧な領域の切り捨てという代償を払っても、退いてはならない抵抗の線だと、羽仁には思えたのだ。
そして、もっとも重要なことは、この抵抗線の死守という命題が、戦後においても、羽仁にとって決して「過去のもの」となることは無かったという事実である。
「現代に生きる歴史学徒の任務」(1966)は、鬼気迫ると言ってよいほどの迫力に満ちた講演の記録だが、最後にその中から一か所だけを引いて、終わることにしたい。
■コメント(広坂朋信)
三木清は『社会科学の予備概念』で盟友・羽仁五郎の訳したクローチェ『歴史叙述の理論及び歴史』から、歴史とは現代の歴史である云々という有名なくだりを引用しながら次のように記している。
「現代の意識は過去の歴史が如何に把握されるかといふことに對する根源である」とはわかりづらい表現だが、後年の『歴史哲学』第一章で三木は、現代と現在という用語の区別を厳密にすることでこのアイデアをさらに詳しく述べている。三木によれば、現代とは、古代、中世、近代と同じような時代区分であり、それはすでに過去である。クローチェのいう現代とは、むしろ現在というべきものだとする。
三木は、現在が歴史を手繰り寄せるというが、その手繰り寄せをさせるのは、「我々の現在のうちになほ働いてゐるところ」の過去ではないだろうか。それは能楽にとっての田楽のようなもの、それなしには現在はないが、それが何であったかはよくわからなくなってしまった過去である。それは過去ではあるけれども「我々の現在のうちになほ働いてゐるところのもの」であるがゆえに「またひとつの現在」でもある。無意識としての歴史と言ってもいい。我々がどのような過去を手繰り寄せようとするかは、この無意識としての歴史の働きにかかわってくるのだろう。
★プロフィール★
岡田有生(おかだ・ありお)
1962年生まれ。男性、独身、親と同居。プロフィールに書くようなこともなく現在に至る。ブログ:Arisanのノート
広坂朋信(ひろさか・とものぶ)1963年、東京生れ。編集者・ライター。著書に『実録四谷怪談 現代語訳『四ッ谷雑談集』』、『東京怪談ディテクション』、『怪談の解釈学』など。ブログ「恐妻家の献立表」Web評論誌「コーラ」29号(2016.08.15)
<前近代を再発掘する>第5回:歴史のあいまいな領域(広坂朋信/岡田有生)
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2016 All Rights Reserved.
|
| 表紙(目次)へ |