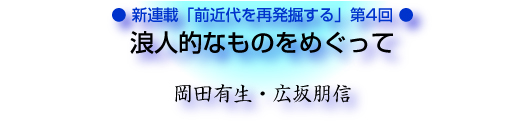|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「La Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
|
『太平記』を読む・続(広坂朋信)
■北条高時の腹切りやぐら
鎌倉幕府を支配する北条一族にとって、おそらく滅びは突然やってきたのであろう。もちろん、執権政治のほころびは顕在化していた。しかし、後醍醐の乱を平定しさえすれば危機は乗り切れるはずだった。彼らには承久の乱というお手本があった。そのマニュアルに従って、笠置山で捕えた後醍醐を退位させ、新天皇を即位させ、先帝後醍醐は隠岐に流罪とし、後醍醐の取り巻きたちも処罰した。すべて手順どおりに事は運ばれていた。それなのになぜ? 得宗・北条高時、執権・赤橋守時といった鎌倉幕府の幹部たちは、どこか得心のいかないまま、幕府滅亡を迎えたのではなかったろうか。
気がつけば鎌倉は新田勢に包囲されていた。幕府はその直前に、近畿で先帝に味方して次々に蜂起する悪党どもを鎮圧するために、足利尊氏(この時点ではまだ高氏だが本稿では一貫して尊氏で通す)らに大軍を率いさせて送り出したばかりだった。その足利尊氏が突如寝返って後醍醐方につき、京都の六波羅探題を攻め落としたという急報に幕府幹部は狼狽したことだろう。その驚きの冷める間もなく、今度は上野(群馬県)の豪族・新田義貞の一族が鎌倉に攻めよせてきた。
義貞が倒幕の軍を立ち上げたとき「その勢、わづかに百五十騎」で討死覚悟の出陣であった(岩波文庫版『太平記』第十巻2)。だから挙兵当初は、蟷螂の斧と笑う人も幕府にいたそうだ(第十巻4)。にもかかわらず、新田勢は鎌倉を目指して南下する道すがら、足利氏の残存兵力や各地の勢力を糾合して雪だるま式にふくれあがり、幕府が小手指と分倍河原に敷いた防衛線を突破。ついに鎌倉を包囲したのであった。
新田義貞が稲村ケ崎の難所を抜けて鎌倉に攻め入る武勇伝はよく知られているから省略しよう。
当時の鎌倉幕府に政権が転覆するような決定的な失政は見当たらない。北条高時が凡愚であったという記事は『太平記』だけではないので史実であったのだろう。そうだとしても高時は暴君というにはほど遠い。病弱で政治にあまり熱心ではなかったという程度であって、鎌倉幕府は北条一門による集団指導体制をとっていたから、それで政務が滞るということはなかったようだ。
『太平記』の「相模入道田楽を好む事」(第五巻4)は、当時流行した田楽に耽溺する高時を印象的に描いている。かつての公共放送で『太平記』がドラマ化された折には片岡鶴太郎が鬼気迫る演技を見せた名場面だからご記憶の方も多かろう。だが、田楽の興業は足利尊氏らも見物しており、高時も流行にのっただけだ。高時の道楽としては、田楽のほかに、闘犬も挙げられている(第五巻5)が、これも武家らしい趣味で、そのために政治を誤ったとか、財政がひっ迫したというわけではない。ただ、犬が噛み合うさまが戦闘を予感させて不吉だというにすぎない。
裏を返せば、田楽に耽溺だとか闘犬が不吉だとか言うのは、『太平記』作者が北条高時を悪役として描こうとしても、特筆すべき悪政が見当たらなかったからではあるまいか。いったいなぜ彼と彼の一族は亡ぼされたのか。
北条一族による幕政の専有とか、幕府と朝廷の二重行政の矛盾とか、客観的な理由を挙げようとすればできなくもないが、それはこの時代に渦巻いていた不満の一般的な理由にすぎない。あえて言えば、改革をしなければならないという強迫観念に取りつかれた時代の生贄になって、北条一族は集団自殺に追い込まれたとしか言いようがない。
■足利尊氏の不機嫌
現実に鎌倉幕府を滅ぼしたのは、後醍醐のまわりに集まっていた不良貴族たちではなく、足利尊氏と新田義貞の軍事力である。おそらくは足利家一門、新田家一門のなかで打倒執権の気運も醸成されていたのだろうが、それぞれの一族のリーダーの名前で各勢力を代表させることにする。
なぜ足利氏と新田氏だったのか。
前回、新田一郎(『太平記の時代』講談社)の言葉を借りて、この二人が、後醍後の反乱鎮圧のための幕府軍に動員されて現地におもむき、そこで幕府の大軍を相手にあの手この手の奇策を繰り出しながらねばりにねばる楠正成の戦いを目の当たりにして、そこに「現状の横滑り的な変化の可能性」を見出したのではないかと述べた。
しかし、現場におもむいたのは足利と新田だけではない。赤坂城を包囲した幕府軍は二十万余騎、足利尊氏は四人の大将軍の一人に数えられているが、その他にも62名の武将の名前が挙がっている(第三巻4)。その後、再起した楠勢の立てこもる金剛山を包囲した幕府軍は三十万余騎、外様の大将として28人の名前が挙がっているが、新田義貞は小勢力だったためか家格が劣っていたからか名前も挙がっていない(第六巻7)。つまり、楠正成のゲリラ的抵抗戦を目の当たりにしたのは、尊氏と義貞だけではなく大勢いた。にもかかわらず、動いたのはあの二人だけだった。しかも、この時点ではまったく無名だった義貞が幕府を倒すことになるのだから面白いものである。
新田義貞の動機については見当がつく。幕府の命を受け、楠正成の立てこもる金剛山包囲に加わっていた新田義貞は、後醍後の皇子、大塔宮護良親王に連絡をとりつけ、護良から倒幕の指令を受けている(第七巻4)。『太平記』はこの記事の直前に楠正成が幕府の大軍を手玉に取る「千剣破城軍の事」(第七巻3)を置く。楠正成を攻めあぐねて兵糧攻めに切り替えた幕府軍は、退屈しのぎに連歌、将棋、双六、茶の会などに興じ、やがて遊女を呼び寄せ、あげくにささいな口論から同士討ち。これではしまりがないと再び攻城戦をしかけるも、またもや正成の罠にはまって大敗。戦線を離脱する将兵も数知れず「前代未聞の恥辱なり」という有様であった。義貞はこの醜態を目の当たりにして幕府を見限ったのではないだろうか。嫌気がさして仮病を使い関東に帰っていたところに、足利尊氏が幕府に叛旗を翻したとの報せが来た。それを知った時点で、天下の趨勢は決したと義貞は思ったに違いない。バスに乗り遅れるな、と。
足利尊氏が倒幕に動いた動機は『太平記』の記事だけからはよくわからない。病気で気分が悪かったのに幕府からたびたび出兵の催促を受けた、しかも亡き父の喪中なのにと怒ったというのだが、尊氏の父が亡くなったのは二年前なので説得力に欠ける。
尊氏という人は複雑な性格であったようだ。勇猛な武将でありながらくよくよと悩んだり、寛大な政治家と言われながら猜疑心に駆られて身内をとことん追いこんだりする。案外、機嫌が悪くてむかついたからというのが真相に近いのかもしれない。
一方、かねてより足利尊氏には天下をとる気持ちがあるという噂もあったらしい(『増鏡』第十七)。北条氏による幕政の専有は、有力御家人同士の度重なる内紛と粛清の結果だが、このサバイバルゲームを生き残った足利氏は、本拠地(栃木県足利市)以外にも東海・近畿各地の要所に領地を持つ大勢力で、天下をうかがうに充分な力量があった。そのために北条氏から警戒されてもいた。しかし、客観的な条件だけでは人は動かない。そこで、何か決定打になるような動機付けがあったはずとの憶測がなされて、足利氏には代々伝わる遺訓があったという伝承も産まれた。
しばしば『太平記』を補うかたちで引き合いに出される今川了俊『難太平記』には、足利家の祖・源義家から七代目の孫が天下をとるべしとの言い伝えがあったとある。了俊はそのことが書いてある源義家の遺言状を見たというのだが、歴史家によると怪しい話だという。さらに足利家第二代の足利義兼は、時折、物狂おしくなることがあり、子孫にも物狂おしくなる者が出るのはその影響だろうという伝承もあったらしい。これは尊氏のことを念頭に置いているのだろう。(黒田俊雄『日本の歴史8蒙古襲来』中公文庫)
今川了俊は足利一門の一人なので、先祖の遺訓だとか悲劇の勇者の血統だとかは、足利氏の天下取りを正統化するために持ち出されたことは間違いない。胡乱な逸話を持ち出したくらいのことで、はたして足利氏の天下を正統化できるのか。了俊はそう思って自らを納得させたのだとしか言いようがない。ただ、そうでもしなければならないほど、足利尊氏の決断がわからないものだったということは確かだ。
天下の趨勢を決めたのは、鎌倉幕府さえ倒せばなんでもうまくいくはずとパラノイアックに言い募った後醍後よりも、得体の知れない足利尊氏というモンスターの方であった。
為朝像の変容『椿説弓張月』(岡田有生)
昭和10年に岩波文庫から出た、和田万吉校訂のものの、戦後に出た何刷めかで、字がずいぶん細かいので難儀したが、読解はまったく問題ないので、現代語訳よりまずはこれを読めばいいのではないかと思う。
後半部では琉球が舞台になるということもあり、かなり熱中して読んだ。僕はとにかく、音読する癖があるのだが、これほど音読が心地よい書物も、そうはないだろう。
主人公の為朝が琉球に流れ着くまでは、保元の乱から小笠原を周遊して教化・平定してしまうくだりまで、ほぼ保元物語を元ネタにしているそうなのだが、僕はそちらを読んだことが無い。
ただ、花田清輝も『もう一つの修羅』のなかのいくつかのエッセイで書いている小笠原のくだりは、さすがに名文で、このあたりから流刑先で為朝が討死したと見せかける(実際は逃げ延びたという設定)場面までが、一番作者の筆が冴えわたっている印象を受けた。
義理や家系や主従関係の桎梏にがんじがらめになったなかで凄惨な命の奪い合いをやっている「内地」の生活から、広々とした未知の外洋に出ることで気持ちが晴れ晴れとし、それがそこで出会った「未開の民」を自らの力と威信の前に平伏させ、教化していく、拡張主義的な行為の正当化につながっていくというようなメカニズムは、この後、明治維新後の日本において本格的に起動するものであろうが、その原型が、見事に示されているともいえる。
よくもこれだけ、奥深い社会と人々の心の底流のようなものを、生き生きと描き出せたものだと、感心するばかりだ。
***
だが、何より印象深かったのは、前半部では、権力闘争に敗れる悲運につきまとわれているとはいえ、どこまでも勇猛で超人的な力をもつ英雄として描かれる為朝が、琉球に漂着して以降は、すっかりその様子を変貌させることだ。
「内地」に居る頃の、若い為朝は、強いには強いが、傲岸で可愛げが無い。
トロツキーは、若いレーニンの性格が傲岸不遜であったことを称揚して、周囲の訳知り顔の大人たちがレーニンに「そんなに弓を強く引くと折れてしまうぞ」と、忠告のようなことを盛んに言ったという事を、嘲るように書いているのだが、当代一の弓の名手、若き為朝もまさにそんな感じなのである。
それが、琉球篇になると、為朝もさまざまな人生の苦労を経てきたせいか、超人的な性格が影を潜めるようになり、しょっちゅう失敗したり(粗忽なのは元々だが)、騙されたり、戦に敗れて這う這うの体で逃げ延びたりのくり返しになる。相変わらず腕っぷしは強いものの、あんまりかっこよくないのだ。
琉球王朝に使える「大里の按司」という一地方領主の地位に甘んじ続けることも、前半の活躍とそこでの為朝の性格を知る者には意外だ。
周囲から、琉球の王になってはと促されても、謙遜なのか自嘲なのか、「われは日本(やまと)の浪人(うかれびと)也」などと呟いて受けようとしない。
そして、敵たちにも、「御曹司などと呼ばれてるが、本土で負けて行き場がなくなったから、沖縄に流れてきただけじゃないか」と露骨に馬鹿にされるのだが、たしかに当っている所もあるし、これもまた、明治以後、最近までも繰り返される日本人(内地の人間)と沖縄とのかかわり方の一つのパターンを先駆けて描いているとさえ思える。
上の「われは日本(やまと)の浪人(うかれびと)也」という台詞に戻って言えば、馬琴は、ここでは「浪人」という存在を描いているとも思える。「大陸浪人」という後世の言葉に代表されるように(フリーターなんて言葉もあるが)、「浪人」は近代日本社会のキーワードであるのかもしれない。
馬琴は、どうもそういう原理を直観しているようである。もっとも、この本の想定される読者層には、浪人を多く含んでいただろうから、商売上の思惑もあったのかもしれないが。
***
いや、それはともかく、考えたいのは、この琉球での為朝像の変容が意味しているのは何かという事だ。
ひとつには、小笠原とは違って、薩摩の支配を受ける以前の琉球が独立した王国であり文化圏であったという著者の認識(異国趣味のようなものももちろんあるのだが)があると考えられなくもない。だが、最終節で展開される、琉球がいかにヤマトの支配下にあるべき国であるかという論理の露骨な強調などを見ると、そうした見方が、どの程度妥当性をもつものか心もとない。
むしろここには、年齢にともなう(為朝と、そしてあるいは馬琴の)成長・変化のようなものを見るべきではないだろうか。
死期を悟った為朝が、終焉の地へ赴こうとし、それを引き留めようとする息子の言葉を聞いて、声高に笑った後で次のような言葉を語るくだりには、どこか心を動かされるものを感じた。
僕自身も、そういう年齢だからであろうか。
■足利直冬の事(広坂)
新幹線のない時代によく移動したものだと思う。岡田氏の取り上げた源為朝は父にうとまれ九州に半ば独立した勢力圏を築いていたという伝説があるからそれにならったのかどうか、建武の新政の後、後醍醐と新田義貞に追放された足利尊氏・直義一派はいったん九州にのがれて再起を図った。尊氏らは北関東の出身である。現在の地名で言うと、栃木から京都経由で福岡にいたり、また京都に向かったのである。この距離を何万人だかの武士団が移動した。JRなら北千住経由で東京駅から新幹線に乗るところだが、徒歩と騎馬である。
尊氏を九州に追いやった後醍醐方の武将は北畠顕家である。かつての公共放送では後藤久美子が凛々しい若武者に扮して話題になったのでご記憶の方も多かろう。この人も京都の公家として生まれながら、陸奥守に任じられて宮城から青森のあたりまで転戦し、足利謀反の知らせを聞くや京都に駆け付けたのだから、たいへんな移動距離だ。もちろん、東北新幹線は開業していない。
父にうとまれ、兄弟と対立し、中央での政争に敗れて漂泊した人物としては『太平記』からは足利直冬が思い浮かべられる。直冬が登場するのは、足利氏が新田氏との抗争を制して後醍後一派を追放し、持明院統の天皇を擁して幕府を開いた後である。
足利直冬は、足利尊氏のご落胤(次男とされる)だが、父・尊氏に認知されず、幼少期は鎌倉・東勝寺で育てられ、京都に出て来て玄恵法師のもとで学問をした後、玄恵の推薦で叔父・直義に引き取られ養子となった。紀州で南朝方が蜂起すると、実父尊氏から父子の名乗りを許され、鎮圧軍の総大将に任ぜられて戦功をあげる。これによって人々から認められるが、実父尊氏はさほどの評価も与えず、あくまで家臣扱い。その後、養父・直義の計らいで西国探題として中国地方の行政を管轄する(第二七巻7)。
尊氏が直冬をなかなか実子として認知しようとせず、認知したあとも家臣扱いにしたのは、直冬の母が正妻ではなく、すでに正妻とのあいだに生まれた足利義詮が後継ぎに決まっていたからだろうとされている。それにしても冷たい扱いだったようだ。
その後、実父・尊氏と養父・直義の抗争が始まると、直義派について尊氏と対立した直冬は九州にのがれ(第二十七巻11)、以後、九州を地盤とし幕府、南朝に次ぐ第三の勢力となる。『太平記』は「呉魏蜀の三国、鼎の如くに立つて、互ひに二つを亡ぼさんとせし戦国の始めに相似たり」と三国志になぞらえて評している(第二十八巻2)。その後、尊氏・直義兄弟の内紛の火種であった高師直一族が粛清されて、壮絶な兄弟喧嘩がいったんおさまると、直冬は九州の軍政を所管する鎮西探題に任ぜられる。しかし、再び幕府内の内紛がはじまり、直義が死ぬと直冬は南朝に降り、南朝方の武将として尊氏と抗争を繰り返す。
一時は京都を制圧したこともある直冬だが、尊氏が死に、実弟・義詮が第二代将軍についてからは消息が知れなくなる。晩年は甥である三代将軍足利義満と和解し、出家して隠棲したらしい。
私が直冬のことを連想したのは、岡田氏の「義理や家系や主従関係の桎梏にがんじがらめになったなかで凄惨な命の奪い合いをやっている「内地」の生活」という言葉にひかれてのことだが、南北朝期の動乱のなかで数奇な人生を送った直冬の晩年を想像してみると、出家したというのも、単に武将として引退し、もはや弓引くことはありませんというポーズだけではないように思われる。
直冬は、もとは鎌倉・東勝寺の稚児だったという。東勝寺とは北条一族が腹を切って果てた寺である。幼い直冬が東勝寺にあずけられたのが、北条氏滅亡の前だったか後だったか。証拠はないが、私には直冬少年が北条一族の滅亡するさまを見ていたのではないかと思われてならない。数百人の武将が腹をかっさばき、死に様を競うように、ある者は自らの傷口に手を突っ込んではらわたをつかみ出し、またある者は十文字に腹を切って見せながら死んでいくありさまを、父に捨てられた少年が見ていた。
修羅の巷に生まれ落ちた直冬にとって、気持ちが晴れ晴れとするような広々とした未知の外洋はあったのだろうか。養父・直義は禅僧・夢窓疎石に教えを乞い、晩年には出家もしたが、その後も兄・尊氏に対抗して挙兵している。直冬の晩年が静かであったことにわずかな救いを感じずにはおれない。
■貴種流離譚(広坂)
源為朝は半ば伝説上の武将であり、その事績にははっきりしないところが多い。はっきりしないからこそ伝説の材料になりやすかったとも言える。その伝説を想像力で思いきりふくらませて一大冒険活劇に仕立てたのが曲亭馬琴の『椿説弓張月』だが、私(広坂)はこの冒険小説を読んだことがなく粗筋(山田野理夫訳『原本現代語訳椿説弓張月』上下、教育社新書)でしか知らない。したがってここからは、岡田氏が馬琴から取り出した源為朝像の変容について私見を記すにとどめる。
琉球での為朝像の変容が意味しているのは何か?
『椿説弓張月』の筋書きは、例えば「百合若大臣」や「御曹子島渡」のような貴種流離譚の枠組みを借りているようだ。違う点は、犠牲による帰還がないというところだろう。「百合若大臣」では手紙を託された鷹の犠牲、「御曹子島渡」では蝦夷の大王の姫の犠牲を機縁として主人公が日本に帰ることになる。ところが、『椿説弓張月』では、忠臣が身代りになって死に、為朝の妻が荒海に身を投げて難破しそうになった為朝の命を救うが、為朝とその息子はそのまま琉球に漂着する。犠牲を契機として故郷に帰り本来の地位を回復するという構成をとっていないのである。
『椿説弓張月』では、琉球の内乱を平定した後、日本に帰った為朝は人知れずに死ぬ。ここには故郷に帰って裏切者に復讐し、元の地位を回復するというモチーフがない。「御曹子島渡」の場合は、主人公が源義経とされているので、帰国したあとの義経の活躍はどなたもご存知ということで省略されたのだろうが、「百合若大臣」では復讐と地位回復も描かれている。もっとも、史実の源為朝は流刑地の伊豆大島で死んだとされているので、馬琴としても、いくら小説のなかとはいえ今さら日本に帰してもうひと暴れさせるわけにもいかなかったのかもしれない。
いずれにせよ、これだけ大きな相違点がある以上、『椿説弓張月』を中世の貴種流離譚を近世的に変奏した小説と片づけてすますわけにはいかない。
忠臣と妻の献身によって為朝が得たものは、内地への帰還と地位回復ではなく、気持ちが晴れ晴れするような広々とした未知の外洋に先にある外地「琉球」という活躍の舞台だった。もしこの琉球で為朝が逆臣・奸臣を倒し、先帝を王位に復帰させていたら、それは内地でできなかったことを外地でなしとげただけということになってしまう。馬琴は作中の為朝をしてそのようにふるまわせなかった。流刑地の伊豆七島では領主然としてふるまったのに、琉球では乞われても自らは王位につかなかった。それどころか行く先々で土地の女性に子を産ませていた為朝なのに、琉球では子づくりをしていない!
琉球以前と以後とでは為朝のキャラクターが変わっているように見えるのは確かだ。為朝が琉球にいる間に、日本では源平の戦が終わり、源頼朝が鎌倉に幕府を開いている。帰国してもうひと暴れし、復讐と地位回復をはたそうにも、もはや為朝の出番はなくなっていた。それならそれでかまわないと吹っ切れた気持ちになったのだろうか。岡田氏はこれを、さまざまな人生の苦労を経てきた為朝の年齢にともなう成長・変化としている。経験の沈澱による成熟と言ってもよいだろう。
しかし岡田氏は、啓蒙の逆説ならぬ成熟の逆説とでも呼びたい二重性を為朝の変化のなかに指摘している。
力づくじゃうまくいかないよと格好よく息子を諭すのは、力ずくで思う存分暴れまわってきた親父である。「われは日本の浪人也」と言って琉球王にはなろうとしなかった為朝は、肩から無駄な力が抜けて好感度はアップしているものの、やっていることは、外地で「出会った「未開の民」を自らの力と威信の前に平伏させ、教化していく、拡張主義的な行為」にほかならない。
★コメント(岡田)
広坂さんには、僕がブログに書いた走り書きのような文章を読みこんで論じていただくことになり、申し訳なかった。
文中にもあるように、今年の一月に辺野古の基地建設反対運動に参加する目的で、初めて沖縄を訪れたのだが、その少し前に古本屋で、岩波文庫の『椿説弓張月』を見つけて買ったときには、それが琉球を舞台にした物語だということは頭になかった。読み始めてから、そういえばもうすぐ沖縄に行くのだと思い、不思議な縁のようなものを感じた。
この物語に興味を持ったのは、これもやはり文中に書いたように、花田清輝の『もう一つの修羅』のなかの、馬琴や「弓張月」を扱った幾つかのエッセーを読んでいたからである。「弓張月」の「海洋」的な魅力への称賛も、花田の受け売りにすぎない。
花田には、侵略戦争や植民地主義を批判するような視点は(少なくとも表面上は)ないのだが。
花田が書いている「弓張月」の世界は、僕には、馬琴と同じ19世紀の北米の小説家、ポーやメルヴィルの作品世界に通じるものを感じさせる。ポーというのは、エッセー「為朝図」のなかに花田も引いている「御覧候え、朝(あした)より暮るるまで、潮曇りして沖の方も見えわかず、常にだに高き浪、二三丈がほど打ちかくるに、かの島のわたりには、潮の満干もよのつねならで、或は東へ引き、また西へ引くときもあり、そがなかに、卯辰のかたよりさす潮あり、また申酉のかたより東へさす潮あり、この二つの潮のはやきこと滝川のごとく、水底の巌にせかれて、鳴りほとばしること、雷霆(いかづち)にもまされり、……」と続くくだりに、あのメエルシュトレエムの大渦の描写を思い出さずにはいられないからでもあるし、またメルヴィルだというのは、琉球や小笠原の「海洋」への進出をテーマにしたこの馬琴の読本から、『白鯨』を書いた同時代の、しかも同じ太平洋の対岸の作家の存在を想起するからでもある。
だが、そればかりではない。この連載の、前回の文章の中で、僕は花田の別の論考、「浪人の季節」に関して書いた。
「われは日本(やまと)の浪人(うかれびと)也」という一節を引いたように、僕からすると、「弓張月」の特に琉球篇は、ヤマトで行き場を失った「浪人」が見知らぬ土地に流れ着いてからの物語として読めるのだが、そうした、異郷に流れ着いた「浪人」を主人公にした作品世界は、太平洋の向こうの同時代の作家たちにも共通しているもののように思えるのだ。
実際、ポー自身も、落ちぶれて最後は酒場の前で酔いつぶれて野宿し凍死したと聞いているし(余談だが、今回の沖縄行きでは、僕もあやうく同じ運命をたどりそうになった)、『白鯨』の乗組員たちも、多くは陸の上で食いつぶしたような男たちだったのではないか。いや、そもそも、アメリカ合衆国という国自体が、ヨーロッパで食いつぶしたり、行き場を持たなかった「浪人」たちの「漂着」なり「侵略」なりによって成立したものではなかったか。
「為朝図」のなかで、花田はこう書いている。
花田もやはり、為朝の「浪人」性に着目していることが、ここからうかがえるのだが、「浪人」たちの鬱屈や慷慨といったもの、言い方を変えれば「男のロマン」のようなものが、侵略や植民地支配に動員されていくというのは、世界的な同時代的な傾向だったとも考えられるのである。
幕末の動乱期の予感のなかで書かれた「弓張月」には、そうした歴史の水底の大きな潮流を直観している部分があるのではないだろうか。そこに、ポーやメルヴィルが捉えた「海洋」の不気味なイメージと相通じるものを、僕は感じるのである。
***
話が肝心の「太平記」にいっこうに近づきそうにないのが申し訳ないが、もう少し続けたい。
琉球に渡ってからの為朝の変容について、それは人生の苦労を重ねたことの表れではないかと僕は書いたわけだが、広坂さんはもっと鋭く、そこに「成熟の逆説」とも呼ぶべき現象の見られることを指摘している。
これは、正直、僕にとっては虚を突かれるものであった。
この指摘を受けて、「弓張月」に記された為朝の「こは武に疎きものの臆説なり」云々という言葉を読み返してみると、「成熟」に達したとみなされ、みずからもそう自負している者の思い上がり、「啓蒙」の姿をまとった愚かな権威主義のようなものが浮き彫りになる気がする。
その権威主義は、またこの為朝の言葉を良しとした、僕自身に内在するものでもあろう。それは、「浪人の権威性」とでも呼べるものだ。
「浪人」は、家父長的な秩序から、一見疎外され、「自由」な「浮かれ者」のごとくに生きる姿によって、「浪人」と呼ばれるのである。
だが、たいていの場合、それは彼が、家父長的な秩序の権威や、権力性といったものから解き放たれていることを意味しない。
公的にも私的にも、大抵の場合、「浪人」が支配や抑圧の装置の尖兵であることを免れないのは、「家」に象徴されるような支配的な秩序への信仰と憧れが、ひそかに彼らの心の底に秘められているからではないか。
若き日の為朝や、足利直冬が経験したであろう「家」をめぐる凄惨な暴力と支配の仕組みは、そこからの「自由」を求めた者たちの内面に深く根を下ろしていて、彼らの行動を他者に対する侵略や収奪の装置の一部分に変えてしまうばかりではなく、ときにはその姿を変えて、(若き日のレーニンのような)「自由」や「解放」を求める人々の行動への抑圧にも転化させるのである。
成熟の立場から啓蒙的な言葉を口にする人間が、自身の権力の土台を成しているこの内面化された暴力の装置を自覚することがなければ、それは「非暴力の教説」という形をとった、特権と支配の正当化の論理にすぎなくなる。
今日でも、DV男の支配・抑圧のロジックというのは、こうしたものであろう。
「浪人」という存在は、たんに暴力的であるというよりも、権威的・抑圧的なのであり、それゆえにまた(支配的権力・秩序に対しては)従属的であるといえる。
いったい、「浪人」が、こうした権威主義と従属性とを脱し、他者に対して抑圧的な存在であることをやめ、その意味で真に「自由」で「対等」な存在に生まれ変わるということは、どうすれば可能なのだろうか?
為朝や楠正成たちの物語が内包していると思われるもの、すなわち、悲惨な歴史の支配的で絶望的な論理のようなものから脱却し、いわば支配と殺戮と抑圧の外側へと、生きる力を解き放っていこうとする人々の意志を、われわれはどうすれば現在に相続することができるのか。
『太平記』や『弓張月』といった日本の古典を読むことは、そこに描かれている封建的な論理や心情が、今でも決して克服されたものであるとは思われないだけに、この問いのリアリティを、あらためて想起させる。
★プロフィール★
岡田有生(おかだ・ありお)
1962年生まれ。男性、独身、親と同居。プロフィールに書くようなこともなく現在に至る。ブログ:Arisanのノート
広坂朋信(ひろさか・とものぶ)1963年、東京生れ。編集者・ライター。著書に『実録四谷怪談 現代語訳『四ッ谷雑談集』』、『東京怪談ディテクション』、『怪談の解釈学』など。ブログ「恐妻家の献立表」Web評論誌「コーラ」28号(2016.04.15)
<前近代を再発掘する>第4回:浪人的なものをめぐって(広坂朋信/岡田有生)
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2016 All Rights Reserved.
|
| 表紙(目次)へ |