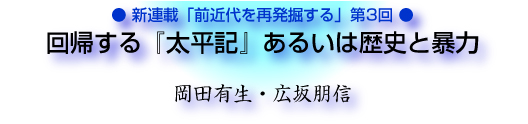|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「La Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
|
なぜ『太平記』か(広坂朋信)
室町時代が生み出した物語として、当の室町時代を生み出した南北朝期の動乱という巨大なカオスを描いた『太平記』がある。日本社会に住む私たちにとって時間軸上での直近の前近代である江戸時代の演劇・文芸には「太平記の世界(時代設定)」が好んでとりあげられた。かの『忠臣蔵』に見られるように「太平記の世界」とは同時代の比喩であった。近世の人びとは「太平記」になぞらえて自分たちの現在を表象したのである。ここから、後世の私たちが『太平記』を読むと、例えば、高師直に吉良上野介のイメージがかぶってしまうというバイアスも生じるほどだ。
『朝鮮太平記』のこと(岡田有生)
私はわりあい最近まで、『太平記』がどういう内容の物語であるか、よく知らなかった。その題名から、漠然と統治による平和の状態を主に描いた話であろうと、考えていたと思う。
ある時、図書館で偶然に、江戸時代に出たらしい十数巻物の『朝鮮太平記』なる本を手にする機会があった。その時代に隣国の平和を賛美するような読み物が書かれ、読まれていたのかと、嬉しいような気がして頁を開いてみると、いわゆる文禄・慶長の役(壬辰倭乱)を描いた軍記物だったので、いくばくかのショックを受けたものだ。
太平記自体もそうだが、この出来事についても、江戸時代全体を通して何度も読み物が書かれ、広く読まれたことが知られており、それについて以下のような研究があるようである。
上によると、江戸時代前期に書かれた物は、ただ日本側の戦闘の様子を賛美するだけの内容で、侵略を行った秀吉についても、その原因となったとされた誇大妄想ぶりを嘲るような書きぶり(それは徳川体制の意に叶っただろう)があるばかりで、戦争の悲惨を引き起こしたことについての反省の兆しはまったく見られないという。それが、江戸時代中期に朝鮮通信使による交流が始まって、被害を受けた朝鮮側の記録に触れる機会が生じてくると、はじめて住む土地を戦場にされ、命を奪われたり、日本へと連れ去られていった人たちの悲惨に、少しは目が向けられるようになったそうだ。『朝鮮太平記』は、この時期の書物である。この変化は、朝鮮の人々についてばかりではなく、戦争によって苦しみを味わう側の存在(つまり「民衆」)というものに、この国の人々が意識を向ける重要な契機になったのではないか、という意味のことが書いてある。
これは、説得力のある見方だと思う。
もちろん、これを逆に、そうした民衆の自己意識の目覚めのようなものが、「太平」の時代の中で育まれてきていて、それがあの侵略や、彼の地の人々の苦しみに対する思慮を生じさせたのだと、考えることも可能だろう。だが、私には、あまりそういう考え方がピンとこない。
と書いて、共同体内部の感情が、普遍的な愛へと連続的に高まっていく可能性を否定したベルグソンのような信念があるわけではないが、どうもそうした可能性を信用しにくいのである。
ところで、朝鮮軍記の話だった。江戸時代中頃には上に書いたような変化があったというが、それが後半から幕末に近づいてくると、再び大きな傾向の変化が生じたようである。上の文章には、秀吉観の変容ということしか書かれていないが、飛躍して私見を述べれば、そこには攻撃的・拡張的な国家主義の予兆のようなものが生じてきたのではないかと思う。
というのも、その時図書館で私が他に見たものに、やはり近世初頭に行われた薩摩藩による琉球侵略を扱った多巻物の書物があり、この二つの史実は、もう一つ、いわゆる石山合戦(織田政権による本願寺包囲戦)と並んで、幕末から明治、戦前にかけての軍記物の人気テーマだったようなのである。その三つに共通する視線は、武力による侵略や制圧という、いわば国家による暴力の賛美の物語であり、民衆が踏みにじられることを是認する態度ということだろう。そのような物語に、読み手である民衆自身が、心躍らせたというわけなのだ。
ただ、これはまあ、心理としては理解できる。私も子どもの頃、第二次大戦の戦記物が大好きだった。といっても、好んで読んだのは太平洋戦争ではなく、主に独ソ戦、それもソ連軍が大の贔屓で、このジャンルは最近では山崎雅弘氏が健筆を振るっておられるようだが、その時分には、バリー・ビットという人が編集長で、著名な戦史家のリデル・ハートが解説を書いたりした第二次世界大戦ブックスというシリーズが、かのサンケイ新聞社出版局から出ていて、それを愛読していたことは、今となってはまさしく黒歴史である。そればかりでなく、他の子どもたち同様に熱狂した、ゴジラやウルトラマンといった特撮物も、その魅力の大きな部分は、やはり疑似戦争物というか、破壊のカタルシスにあったことは否定しようがないだろう。
だから、ただ暴力を題材にしているというだけで、これらの読み物の流行を、反平和的であると断罪したいわけではない。ただ言いたいのは、明治になって具体的な形をとることになる、近代国家の帝国主義的な論理と呼べるものを、前近代の民衆(すでに大衆と呼ぶべきだろうか?)はあらかじめ、ある程度内面化していたと言えるのではないか、ということである。
そうしたものを打破するためには、やはりかつてのように、被害を受けた他者の「声」に接する機会というものが必要だったのではないか。ベルグソンは、
という風にも書いている。
まあ、いずれにせよ、戦乱の物語を「太平」と呼ぶのは、相当にイデオロギー性の強い歴史観であるようには思う。
『太平記』という題名(広坂)
『太平記』は1318年から1367年までの内乱の時代を描いた歴史物語である。後醍醐天皇と鎌倉幕府、足利尊氏と新田義貞、尊氏と弟の足利直義、北朝と南朝などのいくつもの対立と抗争が、東北から九州まで、当時の日本のほぼ全土を舞台に繰り広げられた。その内容は戦いに次ぐ戦いであって、『大乱記』と題するならまだしも『太平記』とは看板に偽りありと苦情がきてもおかしくはない。
もちろん、編まれた物語であるということは、この物語を読む際に、どのような視点から編まれたかについて意識せざるを得ないことを意味する。しかし、これは単純な問題ではない。執筆者として恵鎮(円観)、小島法師、編纂者として玄恵、また校訂を命じた人間として足利直義の名前が挙がることがあるが、それぞれがどの程度関与したのか、また実際の執筆や編纂にかかわった人間はどれくらいいたかなど、成立の具体的な経緯はわからない。そもそも小島法師とは児島高徳のことだとする説もあり、そうだとすると、執筆編纂にかかわった人物の全員が物語中にも登場するということになって、このことは、自然と彼ら以外に最終的な取りまとめをした第三者がいただろうことを想像させる。
しかし、ここで重要な点は、書き手や編纂者が誰であったかよりも複数であったことである。『太平記』成立の歴史学・日本文学の研究者たちの意見は細部については様々だが、大筋では一致している。思いきり大雑把にいえば、この物語には複数の編者・書き手がおり、その人々のそれぞれがさらに多数の人々の証言や主張を集め一書に編んだ。『太平記』の叙述の視点は客観的ではないが、近代的な意味での主観的叙述でもない。編纂の意図、この書の性格については、南朝の正統性の主張、室町幕府の正史、幕府方による南朝の鎮魂など、諸説あるが、そのいずれも決定打となり難いほどこの物語は脱線が多く一貫性がない。しかし題名だけは、かなり早い時期から『太平記』に決まっていたようだ。
複数の編者たちや書き手たち(以後、『太平記』作者と表記する)が、半世紀近くも続いた戦乱の物語を、大いなる平和の物語、『太平記』と名付けたのはなぜか。室町幕府によって平和が到来したのを祝ったというのは成立事情を考えるとありそうもない。前半三分の二ほどは内乱の一方の当事者である足利直義の存命中に出来上がっていた。まだ、あちこちで戦闘中の時期である。平和は訪れていなかった。そこで、平和の到来を期待してそう名付けたという説があるが、これを否定する材料はないものの、なんとなくズレているような気がする。これは私の想像にすぎないが、「太平」という語に込められたニュアンスが、現代とは若干違ったのではないか。
例えば、「平天下」という言葉がある。「修身斉家治国平天下」(『礼記』)の「平天下」は「天下を平らげる」とも読み下す。平和をもたらすという意味でもあるが、「反乱を平定する」というニュアンスもある。平定そのものは平和的にではなく軍事行動による場合が多い。『太平記』とは、意味としては「大乱平定記」であって、乱世の終息を期待して『太平記』と略したのではないかと想像してもよいように感じる。『太平記』成立後、多くの軍記物語が「なんとか太平記」と名付けられたこともこの想像を補強してくれる。そうだとすれば、『太平記』作者の立場とは、その時々の戦いにおける平定者、すなわち勝ち馬に乗る機会便乗主義ということになりそうだ。無節操と言われようと、昨日の友が今日の敵になるような乱世を生きる処世術であり、それが結果としてはこの物語の多様性を受け入れる器になったのではないか。
後醍醐天皇の政治
南北朝の動乱を描いた『太平記』は、史実をそのまま記録したものではなく、誇張やフィクション、事実の誤認をまじえた歴史物語である。しかし、同時代の人が鎌倉幕府の崩壊から朝廷の分裂を経て室町幕府成立にいたるまでの波乱にとんだ時代を後世に語り残そうとして編んだものであることには違いない。その点では同時代史を描くという先例の一つでもある。
現在もなお進行中の社会変動を描こうとして、さて、どこから書きはじめるか。この問いに『太平記』の作者は、後醍醐天皇の即位の記事から書きだした。題して「後醍醐天皇武臣を亡ぼすべき御企ての事」。一人の傑出した個性が特権的な地位に就いたことによって時代が画された、すべてはここから始まったとでも言いたげに見えるが、内容を読んでみるとそうでもない。
そもそも、鎌倉幕府の滅亡から南北朝の動乱にいたる時代が、後醍醐天皇一人の企図によって始まったとするのはどうか?とは出て当然の疑問だろう。
「誠に天に受くる聖主、地に奉じたる明君なり」と称賛されたという後醍醐天皇の政治がどのようなものだったか。とりあえず正中の変に至るまでの後醍醐の行動が『太平記』でどう描かれているかを追ってみる(以下『太平記』のテキストは兵藤裕己校注・岩波文庫版を用いる)。
史実の順序を無視して『太平記』の叙述に沿うなら、即位した後醍醐天皇が初めに手を付けたのは関所の廃止、関税の撤廃による流通の整備である。ついで飢饉対策として自分の朝飯をやめてその分を飢えた民に施した。京都市内に専売所を設けて米価を安定させた。また機能停止していた記録所という役所を復活させ、自ら直接指揮した。
人気取りのパフォーマンスと流通業界への影響力拡大を兼ねた経済政策。自らの手足となる官僚を確保するための行政改革。気のきいた政治家なら誰でも思いつきそうな、場当たり的な政策である。しかし、これで後醍醐天皇は自らの権力の基盤である畿内の安定を確保した。これが畿内限定であることは『太平記』第一巻1の末尾に「ただ恨むらくは、斉桓覇を行ひ、楚人弓を遺れしに、叡慮少しき似たる事を」と作者が釘を刺していることでわかる。
肝心の倒幕計画の方はどうであったか。『太平記』は後醍醐天皇が西園寺実兼の娘禧子を皇后(中宮)に迎えたことを記す。西園寺家は、数代前の西園寺公経が後鳥羽上皇の討幕計画を鎌倉幕府に密告して承久の乱の幕府の勝利に貢献したため、幕府執権北条一族の信頼が厚く、以来代々鎌倉幕府と京都朝廷の連絡役・関東申次となっていた。後醍醐がその西園寺の娘を中宮にしたのは、関東すなわち幕府の「聞こえ宜しかるべしと思し召して」のことで、その証拠に、中宮禧子は当時十六歳のたいへんな美少女だったのに「君恩葉よりも薄かりしかば、一生空しく玉顔に近づかせ給はず」(第一巻2)、形ばかりの妻で夫婦の情愛はなかったと『太平記』は言うのだが、ウソである。
史実では二人の間に娘も生まれているし、他でもない『太平記』(第四巻3)が隠岐に流罪となる後醍醐とそれを見送る中宮との睦まじい姿を描いている。そうすると、後醍醐が幕府の目を欺くために西園寺禧子を中宮に迎えたとする『太平記』の記事は、すべては後醍醐の意志からはじまったとする『太平記』の構成、作者の歴史観と辻褄の合うように作為されたものだろう。この記事に続けて、阿野廉子の美貌に夢中になった後醍醐が政務を怠ったとあるが、これも意図的な挿入だろう。
後醍醐はせっせと子づくりに励んだ。「君恩に誇る宮女、甚だ多かりしかば」中宮以外の宮女にもせっせと子を産ませ、「宮々次第に御誕生ありて、十六人までぞおはしましける」(第一巻3)というが、実際にはもっといたらしい。二十人の女に、三十数人の子を産ませたという。君主制国家にあって王の子づくりはそれ自体が政治である。だが、それにしても多い。それが政治だとすれば過剰な政治である。
当時の皇位は持明院統と大覚寺統と呼ばれる二系列の血統が交互につくことになっており、大覚寺統の後醍醐の子どもらが次の天皇に即位することは想定されていなかった。その上、もともと後醍醐の即位自体、兄である後二条院の子が成人するまでのワンポイントリリーフとして起用されたにすぎない。つまり、どう転んでも後醍醐の子どもらが皇位につくことはありえなかった。だから、子づくりに励む必要などまったくないにもかかわらず、せっせと大勢の女たちに子を産ませたのは、この人事慣行に対する不服を申し立て、かつは自分の繁殖力を誇示するデモンストレーションだったといえるのではないか。
神頼みと無礼講
後醍醐天皇は子づくりにはげみながらも、鎌倉幕府打倒の陰謀も進めていた。しかし、実績をあげつつあった子づくりに比べて、こちらの方は何とも心もとない。中宮禧子の安産祈願という名目で、円観、文観ら密教僧たちを集めて関東調伏のための祈祷をさせたという(第一巻4)。神頼みなのである。ちなみに円観は『太平記』前半の作者の一人とされる恵鎮のことだから、関東調伏の記事は円観自身の体験を基にしたものだろう。
当時、蒙古襲来を防ぐことができたのは神仏のご加護、具体的には異国調伏の祈祷を行った寺社の祈祷のおかげと信じられていたから、神仏への祈祷の信頼度は、現代とは比べものにならないほど高かった(海津一朗『神風と悪党の世紀』講談社現代新書)。とはいえ、呪術戦とは現実レベルでは心理戦・宣伝戦に他ならないのだから、呪殺などの対人呪術が効果を発揮するには、誰かが呪っていることを相手に知らせなければならない。ところが関東調伏の祈祷はその意図が幕府に漏れないように中宮の安産祈願という隠れ蓑で覆ったうえ、祈祷に参加した僧たちも文観ら数名の他は真の目的を知らされていなかったらしい。それほどまでに秘密裏に行われていたとすると、僧らの祈祷が効果をあげたかどうか、はなはだ怪しい。
もちろん、神頼みだけではおぼつかないので、側近の日野俊基が山伏に身をやつして諸国を回り、倒幕に加担してくれそうな勢力を勧誘した(第一巻5)。これには文観らの口ききもあったろう。また、もう一人の側近、日野資朝もリクルートに励み、何人かの武士を陣営に引きいれることに成功した(第一巻6)。だが、武士といっても、後に実質的に幕府を倒した足利尊氏や新田義貞とは比べものにならない小さな勢力であったようだ。
つまり、『太平記』は「後醍醐天皇武臣を亡ぼすべき御企ての事」から始まるが、当の『太平記』の記事を読む限り、その企てには鎌倉幕府打倒という目的にふさわしい具体性も計画性もなかったように見える。
きわめつけが「無礼講」の一件である(第一巻6)。後醍醐天皇と側近の公家たちは、日野資朝の勧誘した武士たちをまじえて倒幕の謀議を行った。その際、幕府の監視の目を欺くためとして無礼講の酒宴を催した。集まったのは後醍醐お気に入りの公家たちと僧侶、呼びかけに応じた武士数名。その宴席に、十七、八歳くらいの美少女二十数名を侍らせたというのである。しかも彼女らは薄い着物一枚、それも「雪の膚透き通つて」とあるからシースルーの肌着を羽織っただけの姿である。下着姿の少女らに酌をさせて「遊び戯れ舞ひ歌」った。芝居の「祇園一力茶屋」を真似たわけでもあるまいし…(おっと順序が逆か)。後醍醐と、その若い側近たちのセンスがよくうかがわれる逸話である。江戸時代の注釈者(『理尽抄』)も言うように、色仕掛けは若い男を手なずけるには効果があるかもしれないが、それ以上のものではない。
乱痴気パーティーもひんぱんになると目をつけられるかもしれないということで、玄恵僧都という学僧を招いて教養講座も開かれた(第一巻7)。玄恵は韓愈の文集を講義したが、乱痴気パーティーに集まった若者たちには不評だったようで、すぐに打ち切りになった。ちなみに、ここで登場する玄恵とは、後に『太平記』前半の改訂作業にかかわった一人と目されているので、この前後の記事には玄恵自身の見聞も反映しているだろう。「かの僧都、謀反の企てとは夢にも知らず」という『太平記』の言葉は、動乱の時代を生き延びた玄恵自身の肉声かもしれない。
討幕計画というのもこんなありさまだから、メンバーから密告者が出て、幕府の京都治安機関たる六波羅探題が出兵し、武士二人はそれぞれの郎党もろとも討死、後醍醐側近の日野俊基と日野資朝は逮捕され、尋問のため鎌倉に護送された(第一巻8、9、10)。これがいわゆる「正中の変」のあらましである。後醍醐自身も釈明の手紙を鎌倉幕府に出したりしている(第一巻11)。
こうしてみると、正中の変にいたる後醍醐天皇の倒幕運動にはその目的にふさわしい計画性が感じられない。仮に陰謀が露見しなかったとして、わずかの手勢で六波羅探題を襲撃して、その後どうするつもりだったのだろう。陰謀が未然に察知されて頓挫したというよりも、そもそも思いつきの域を出ないものではなかったか。鎌倉幕府の寛大な処置もこの憶測を裏付ける。クーデター計画にしてはあまりに未熟だったため、すでに実行部隊をせん滅した以上、もはや実害はないと判断したのだろう。後醍醐の責任は不問に付し、首謀者のうち日野俊基は釈放、日野資朝のみ流罪として幕を引いたのだった。
鎌倉幕府としては、真の首謀者が後醍醐であろうことなど百も承知の上だったろう。『太平記』では、幕府が寛大な処置をしたのは、後醍醐の弁明書を読みあげようとした幕府御家人が急死したことに恐れてということになっている(第一巻11)が、実際はどうだったろうか。「火遊びが過ぎたようですな」と苦笑いする幕府幹部たちの顔が目に浮かぶようではないか。
魔王か? それとも……
伊賀兼光は「鎌倉幕府の有力御家人、北条氏の姻族として評定衆・引付衆等、幕府の首脳部の一翼を担う名門伊賀氏の一族であり、(中略)六波羅探題の枢要な地位にあった」人物だという(網野、前掲書)。その兼光が、正中の変の半年前、後醍醐天皇のブレーン、文観の寺、奈良・般若寺の本尊・文殊菩薩像造立に際して、大施主として資金提供をしていた。それだけでなく、その文殊菩薩像に「金輪聖主御願成就」のためとして文観とともに署名していた。網野は「金輪聖主」とは後醍醐天皇のことであり、「御願成就」とは倒幕の願いだとして、この時点ですでに兼光は後醍醐側に通じていたと推測する。
ここまでの網野の推理は妥当なものだと私も思う。けれども、さらに次のようなことまで言えるかどうかについては、私は懐疑的だ。
なるほどそうだとしても、その伊賀兼光のやったことと言えば、仏像を寄進して倒幕を祈願したということである。これもやはり神頼みの域を出ない。兼光は後醍醐のためにスパイ活動をしていたのだろうと網野の推理は拡がるが、はたしてどうか。もしそうであったなら、正中の変の陰謀が幕府方にもれた際、何らかの善後策が打てたはずなのに、無為無策のまま一網打尽にされているのはどうしたことか。結局、伊賀兼光の件は、機を見るに敏な官僚が二股をかけていただけということもありそうだ。
網野は後醍醐の人物像を「目的のためには手段を選ばず、観念的、独裁的、謀略的で、しかも不撓不屈。まさしくヒットラーの如き人物像」(網野、前掲書)として描く。そして、このイメージを「護摩の煙の朦朧たる中、揺らめく焔を浴びて、不動の如く、悪魔の如く、幕府調伏を懇祈する天皇の姿」という百瀬今朝雄の文章を引いて補強していく。『異形の王権』を読んでいると、魔王のごとき後醍醐が傍にひかえるラスプーチンのごとき文観を使役して倒幕の陰謀をめぐらせているような印象を受ける。ついでに言えば、中沢新一は『悪党的思考』(平凡社)で、網野の考察に基づきながら後醍醐を「魔術王」として描いている。
だが、網野や中沢が後醍醐のカリスマ性を力説すればするほど、二度までもクーデターに失敗してついには皇位を追われ、足利尊氏や新田義貞らの尽力で奇跡の返り咲きを果たした後も、建武の新政に失敗して再度追放された無能な政治家の姿と釣り合いが取れなくなってくる。後醍醐にカリスマ性があったとしても、それは結局、カルト的なものだったのではないか。
楠正成の登場
網野善彦は後醍醐天皇の倒幕の計画性を強調していたが、『太平記』の描く後醍醐の政治は行き当たりばったりで、用意周到とはとても見えない。
後醍醐の二回目のクーデター計画(の失敗)、元弘の変については長々記すまでもないだろう。正中の変で政治的に敗北した後醍醐は巻き返しを図って南都北嶺に行幸し、宗教勢力の糾合に努めた。先に述べた幕府打倒の祈祷はもちろんのこと、僧兵の武力をあてにしてのことである。そのキーパーソンとして護良親王(尊雲法親王)を天台座主の地位にもつけた。だが、この企ても幕府に知られて、側近の公卿は処刑、関東調伏の祈祷を行った僧侶は流刑と、さんざんな結果になった。後醍醐は幕府の追及が自らに及ぶのを察知しても「ただあきれさせ給へるばかりにて、何の御沙汰にも及ばせ給はず」、うろたえるばかりで何の対策も出せなかった(第二巻)。うかつというか、脇が甘いとしか言いようのない無様さである。
八方塞がりとなった後醍後は、側近たちの助けで京都を出て奈良に逃げ出し、ついで笠置山に立てこもる(第三巻)。この籠城も追い詰められての行動で、計画性はみじんも感じられない。たちまち笠置山は幕府軍に取り囲まれて、後醍醐一派は手も足も出なくなる。ところが、後醍醐が行き当たりばったりに倒幕を叫んでじたばたあがいているうちに、思わぬ人物が助っ人に加わる。楠正成である。
楠正成は『太平記』前半の事実上の主人公だが、なぜ彼なのか。後醍醐の展望のなさ、無計画さ、統率力のなさを見てくるとよくわかる。後醍醐は倒幕運動の主力ではない。そもそも彼にそんな力はない。倒幕のために後醍醐がやったことと言えば、『太平記』の派手な誇張を差し引けば、すぐに露見する陰謀と、小競り合い程度の軽微な紛争で、いずれも六波羅探題により簡単に鎮圧されている。楠正成が現れなければ、「主上御謀反」で片づけられていたところだ。ただ一つ、後醍醐の特筆すべき点と言えば、倒幕の旗を掲げ続け、誰かが呼応してくるのを辛抱強く待ったという点である。この執念に応えたのが、河内の悪党、楠多聞兵衛正成という人物だったのである。
現代の歴史学者たちは、楠正成の出自については諸説あってはっきりと決め難いと異口同音に言う。正体不明の人物なのである。『太平記』では、後醍醐天皇は夢のお告げで楠正成と出会ったことにしている(第三巻1)。これは同時代の人にとっても正成と後醍醐の結びつきが意外だったことを示している。夢のお告げで現れた謎の人が大活躍、というのはお伽噺のようだけれども、歴史にはわからないことが起きる。そのわからないことについては無理な理由づけをせずに、それこそ夢のお告げとでもしておく方がある意味で健全とも言える。
突然現れた楠正成は何をしたか。後醍醐天皇一派の立てこもる笠置には合流せず、自分の本拠地、河内国赤坂に城郭を急造して、幕府の大軍を迎え撃った。総大将後醍醐の笠置城が落ちても、なお粘りに粘った挙句、まだ兵糧がつき果てぬうちに兵たちとともに遁走したのである。その逃げっぷりのよさは『太平記』第三巻8にある通り。まんまと逃げおおせた正成は、後醍醐が退位させられ、隠岐に流罪となってからも河内国の各所で暴れまわった(第六巻2.3.4)。楠正成の戦いはゲリラ戦であって、大きな戦果を挙げたわけではない。負けない戦い、いや敗色が濃くなるとさっさと逃げ出してまた挙兵するような、死なない戦いをしつづけたというところだろう。
こうしてみると、『太平記』作者が後醍醐天皇即位の記事から書き始めた理由もわかる。鎌倉幕府打倒は密教の呪詛によってではなく、足利尊氏と新田義貞の軍事行動によってなしとげられた。彼らは二人とも、後醍後の反乱鎮圧のための幕府軍に動員されて、現地におもむいている。そして、そこで楠正成が幕府の正規軍を翻弄するさまを目の当たりにした。彼らはそこに「現状の横滑り的な変化の可能性」を読みとった。それが楠正成の戦いによって拓かれた可能性だった。その正成を歴史の表舞台に呼び出したのが後醍醐だったからこそ、後に続く大きな変化の起点として彼の天皇即位から書き始めたのだろう。だから後醍醐は「魔術王」などではない。いや、あるいは楠正成の召喚こそ、後醍醐の魔術だったとは言えるかもしれない。
二つの論点(岡田)
広坂さんの文章のなかで、特に印象に残ったのは次の二つの論点だ。その一つは、倒幕を志した後醍醐には、展望も計画も統率力もなく、唯一褒められるところといえば、
とされていることである。
鳴くまで待とうホトトギスなどというが、旗かお神輿のような存在であることに徹し、誰か優れた担ぎ手が現われてくれるのをひたすら待ち続けられるというのは、日本的権力者としても、天皇という政治的役割(機関)の体現者としても、なかなかに立派な才能であるという気もする。こうした役割というものを積極的に捉えるならば、自他に対してきわめて冷徹な、ないしはプラグマティックな政治哲学と呼べるものを、むしろそこに見出せるのではないだろうか。
つまり、後醍醐のこうした無能さ、凡庸さは、この国における権力者や権力構造のあり方としては、なかなかに侮れないものを持っているのではないかという風な感想が、一つである。
もう一つの点は、お神輿を担いだ側、すなわち楠正成の奮闘と抵抗のあり様、その「悪党」ぶりのことである。
こうした正成の戦いぶりが、やがて現状の大きな変革をもたらしたのだという見解には、非常に説得力がある。
正成が、戦前もてはやされたような忠臣というよりも、生命力にあふれた「悪党」の性格が強いということは、近年特によく言われてきたところでもあり、これは含蓄に富む論点だと思う。
ただ、物語の先を大幅に急いでしまうことになるが、「死なない戦いをしつづけた」正成は、周知のように最後には自決、それも親子・一族郎党の集団自決というべき壮絶な死を遂げるのである。彼が最後に選んだとされる行為は、生き延びることではなく、自死であった。
それ以外に道がなかったことも確かであろうが、それにしても「死ぬこと」にきわめて重きを置いた態度に思える(もしくは、そのように伝えられてきた)。この事を、どう解するべきであろうか。
これが、考えたい二つ目の点である。
『太平記<よみ>の可能性』
兵藤がこの本で書いている重要なことの一つは、太平記には、天皇の存在をどう捉えるかということをめぐって、二通りの考え方が内在しており、太平記が受容されていく歴史の過程のなかで、その二つのイデオロギーがせめぎ合ってきた、という見方である。そのことを兵藤は、二つの名分論、という言い方で表現する。
その一つは、源平から鎌倉、室町と続いた武家支配の正当性を担保する性格のもので、「不徳の天皇の交替を是認する」名分論である。
これについて、次のように述べられる。
これを兵藤は、「プラグマティックな名分論」と呼ぶ。それは、北畠親房の『神皇正統記』や新井白石のような歴代の武家政権(幕府)のイデオローグにも受け継がれていった思想であり、さらに幕末の吉田松陰のような人にも、その要素が色濃くうかがえると述べている。
たしかに、松蔭の同志である維新の志士たちや、その弟子である明治の元勲と呼ばれた人々、とりわけエタティスト(国家主義者)として狂信的右派の攻撃を受けていた伊藤博文や森有礼のような人たちには、そうしたプラグマティックな天皇観が濃厚にあったと考えられよう。
もう一つの名分論は、社会の周縁に生きる「悪党」たちを天皇に直接結びつける(回収する)ことを可能にするような、「絶対的な名分論」と呼ばれるものである。それは、武家(支配階級)による天皇の首のすげ替えを許さず、天皇を絶対かつ神聖な存在として崇めるところに成立するものであって、兵藤は、イデオロギーとしてのその明確な具現化のはじまりを、後期水戸学の中に見ている。
いわば武家(エスタブリッシュメント)支配によって社会の周縁に置かれてきた者たち(悪党、アウトロー)の情念が、このイデオロギーのもとに、天皇のもとへと呼び集められ、権力交替に「活用」されることになる。
これが、天皇という旗を掲げる(神輿を担ぐ)ことで展開してきた、日本の国家権力の交代劇の、もう一つの捉え方であると言えよう。
さて、ここはやや強引な当て嵌めになるのだが、以上の二つの名分論のうち、「プラグマティックな名分論」は、私が注目した一つ目の論点、つまり政治的役割(機関)としての天皇という考え方に該当し、「絶対的な名分論」の方は、二つ目の論点である、天皇を担ぎ、それに忠義を尽くして戦い死んでいったと見なされる楠正成のような忠臣(悪党)たちについての評価に関わるものだと、ひとまず見なせるのではないか。
ちなみに、この二つの名分論の対立についての見やすい例は、近現代史の出来事のなかに見出せる。というよりも、そうした近現代史についての解釈が、この歴史に対する理解の枠組みを生み出したと言うべきであろうが。
『太平記<よみ>の可能性』に戻ると、兵藤は、このように二つの名分論の存在を指摘したうえで、そのうち「絶対的な名分論」が持つ、社会の周縁部に生きる悪党(アウトロー)的な人々を引きつけて動員する天皇の力に注目し、そこに、やがて国民と呼ばれる存在となる日本の民衆の内面が近代に向って構成されていく重要な契機を見ているのである。
幕末の脱藩浪人たちの討幕運動とは、制度の枠組みをこえて「日本」という普遍的レベルのモラルにむすびつく運動であった。そして君臣上下の枠組みをとび超えて天皇に直結することが、既存の法制度を相対化するもっとも有効な論理であったとすれば、それは戦前の右翼にも、また尊王愛国を標榜する現代の暴力的なアウトロー集団にもつうじる行動の日本的エートスである。(中略)かれらのアジテートする、もうひとつの天皇の物語は、その延長上に日本近代の「国民」概念さえ先取りしていたはずである。(『太平記<よみ>の可能性』講談社学術文庫 p17)
そして、明治以後の展開について、次のように書いている。
つまり、国体論がはらんでいたある種の平等、解放の思想の萌芽が、近代国家の権力によって回収され封じ込められてしまった、という見方なのである。
このような、天皇に対する二つの考え方(二つの名分論)について、まず私見を述べておきたい。
まず「プラグマティックな名分論」について言えば、それは、一面からいえば、人間(ここでは天皇)を道具や「機関」としか見ないような、冷ややかな思考だと言える。なるほど、ファナティズムに対するならば、それを合理的と呼べないこともないが、ここでの本質が、国家的権力の保持と正当化にあったということは、忘れるべきでないだろう。すなわち、このプラグマティズムには、国家中心、民衆抑圧の刻印が押されていることは事実だと思うのだ。
次に、「絶対的な名分論」の方であるが、それはやはり平等や解放といっても、あくまで「臣民」としてのそれであって、近代国家が目指すべき普遍的な思想には、直接にはつながりえないものであることは、再びベルグソンを持ち出すまでもなく明らかだろう。
その歴史上における証左が、国内的には平等を志向しつつ、外に向っては帝国主義的拡大に邁進していった、大正デモクラシー期の社会帝国主義の隆盛だといえる。
要するに、二つの名分論のいずれもが、帝国主義と資本主義を原理とする「国家」の枠外に立つものではありえないことは、たしかだと思われる。
とはいえ、それらを一般的に、権力に対する合理主義的なアプローチと、内在的・情念的なアプローチとの区別という風に見るなら、この二つ以外のアプローチの方法というものも、すぐには思いつかない。言えることはせいぜい、前者の権力観に対しては、後者の観点を忘れず、その逆も真なりで、二つを牽制し合わせることで、国家の論理からの自由を出来るだけ確保しようといったことだろう。
「国家の論理」とは、観念的な言い方になるが、私たちの生と死をおのれのなかに取りこんで、自らだけが生き延びようとする寄生的なシステムの働きのことである。この働きは、もちろん私たち一人一人が内面化してしまっているものでもあるのだが。
慷慨について──「「浪人」の季節」
ここでようやく、広坂さんが楠正成を例にあげて論じていた「悪党」たちの生き延びる力、その生と死について考える段に至ったようだ。
1963年1月の日付があるこの文章で花田が書いている当時の情勢への見方は、上述の兵藤の論旨と重なるもので、桃中軒とアジア主義者宮崎滔天との交流にも言及して、社会の周縁部であえいでいる人々の心情がやがて帝国主義国家の膨張へと吸引され、動員されていくことを予感させるものだといえる。
だが、それに収斂しない要素もそこには読みとれる。それは、花田が、近代化をすすめていく国家の動向と、明治という時代の政治的な雰囲気を脱することが出来ずに取り残されていく桃中軒のような人々との、ズレに着目していることに関わる。このズレを表わす言葉が、「悲憤慷慨」である。その政治的情動は、滔天のような「浪人」たちによって抱かれるなら、やがて天皇を介して国家に動員されていくような要素であると捉えられるだろうが、花田はそれを底辺の「芸人」が抱く憤怒の感情という、国家にとってはつかみにくいものとして描いている。やや長い引用になるが、引いてみよう。
この、世の中に対するやり場のない憤激の感情が、「慷慨(こうがい)」である。
先に一節を引いた、橋川文三の『昭和維新試論』によれば、北一輝、大川周明と共に大正期に台頭した新たな右翼運動の代表格とされた満川亀太郎は、唐詩選の巻頭にある「慷慨の志猶存す」という言葉から、日本の国家主義運動史上に画期をなすとされる団体「猶存社」の名を付けたという。ここで「猶(なお)存す」とは、明治という政治運動の時代が遠くなっても、国を変革してアジアの解放につなげようとする自分たちの理想は死んでいない、という程の意味であろう。これは無論、まごうことなき国家主義の思想、侵略と差別の歴史を生み出したものであり、のみならず、それが「改革」の意匠のもとにあらわれている点では、ファシズム的と言ってよいものではないかと思う。
ただ、ここで注目したいのは、「慷慨」という危険な情動は、国家に飼いならされて生きることを拒絶し、その外に生存の場を模索する態度にもつながりうるものだということである。つまり、慷慨は、その過激さ、攻撃性のなかに、国家を否定し、その論理の外に向かう道を求める可能性を秘めているのだ。
花田が描こうとしている大衆(「芸人」)の姿は、その不幸で鬱屈した心情を、天皇という装置によって国家に回収され、動員されていくだけの受動的な存在ではない。むしろ国家から己を引き離し、したたかな方法で抗いながら、やがて国家を踏み越えていくような力をはらんだ存在として大衆を捉えることの可能性に、花田は賭けていたのだと言えよう(花田が戦時中、ファッショ系の団体に籍を置いたことは、やはり「偽装」で済ませるべきことではない)。
そこで展望されているのは、国家の論理に回収される一歩手前で、「慷慨」という政治的な情動を、己自身の解放につながる力として噴出させようとする民衆の潜在的なエネルギーのようなものだ。
底辺の大衆のなかに渦巻く不穏で攻撃的な情動は、国家へと回収されることを拒んで、逆にその枠組の外側へと己の生を開いていく力にも変容しうるものだという期待を、花田の大衆像には読みとることが出来るのである。
悪党としての正成
桃中軒のようなアウトローの存在の原型とされる、「悪党」としての楠正成像の可能性も、そこに関わっているであろう。
彼は、忠義のゆえに神輿を担いだのではなく、自らの生を貫くために、その道を選んだ。この観点から見れば、湊川における彼とその一族の自決も、たんなる犠牲的な死ではなく、天皇のみならず、己の生命すらも利用して、政治的な野望を後世に実現しようという行為だったと考えられよう。
つまりそれは、何かの為の犠牲として命を捧げたということではなく、彼ら自身が世界を作り変えていくための行為だったのだ。
ここでは、他者に関わろうとする人間の欲望が、国家の論理をきわどく凌駕していると思う。
また同時にそれは、自己の生命を権力獲得の手段に過ぎないものとして軽んじるような、シニカルな精神性とも異なることは、想像できるだろう。それは、プラグマティックな行為かもしれないが、他者にとってのより良き世界の実現という目的を持つ行動として、シニカルな「死の思想」の刻印を拒むものだと考えられる。こちらの面でも、人の生と死を己の道具にすぎないものへと貶めることで存続し続けようとする、国家的な意思は斥けられていると思われる。
おわりに
私たちは、国家の論理に抗って、自らの生と死を貫こうとする態度の、現在におけるあらわれとして、たとえば次のような出来事を見つめることが出来るかもしれない。
それは、2014年11月11日に、安保(戦争)法制の立法推進や、辺野古・高江の基地建設などの安倍政権の政治に抗議して日比谷公園で焼身自殺したという、「新田進」とされる人のことである。
この出来事を紹介したブログ主の方は、『私はこれを、善悪の価値判断したり蓋をしたりするのではなく、それ以上のものでもなくそれ以下のものでもなく、「そのもの」として記憶したいと思っている』と書いている。
また、『「命どぅ宝」(命こそ宝)という価値観を大事にしている沖縄の市民たちにとっては非難すべき行為なのかもしれない』とも述べる。
私も、同じ思いだ。決して、抗議や抵抗のための自死というようなことを賛美したいわけではない。そういう行動を、犠牲的行為から区別することは、実際にはきわめて難しいだろうとも思う。また、今日の社会においては、そうした行為がもたらす効果は、当人の意思のまったく及ばぬ事柄だということも、たしかだろう。
ただ、ここで確認しておきたいことは、私の命は、本来私自身によってこそその大切さを見出され尊重されるべきものであって、国家なり誰なりによって、その価値とか大切さを認定され、その保持を命じられるような筋合いのものではないはずだ、という事である。
生も死も、本来私の権能の内にあるのであって、国家のもとにあるのではない。そして、何よりも肝心なのは、私が国家の枠を越えて生きることを可能にするものは、他者との共存という事実に他ならないということだ。
私の死を見届けることが出来るのは、私ではなく、他者に他ならないのだから、私の死と、死によって完結する私の生とは、私一個に属するものではなく、他者と共に在ることにこそ属するというようなことを言ったのは、ハイデッガーだったかナンシーだったか。
われわれの祖先が、自分たちによって被害を受けた隣国の人々の体験を知ることで、民衆の苦しみという、いわばおのれの身体の感覚を取り戻し、その自覚の薄らいだ時に侵略と憎悪と差別への道が、またそれによる自己抑圧(国家の論理の内面化)への道が準備されたことは、『朝鮮太平記』にふれながら述べたとおりである。
人は他者と共に在ることによって、はじめて真に己自身になれるのだ。その「他者と共に在る」ことに、国家が介入してよい余地など無いはずだ。
その、生の根本的な在り様の享受を、もし国家が阻むのであれば(戦争ほど、それを直截に阻害するものはあるまい)、私は政治的情動と行為によって、それに力の限り立ち向かわねばならぬ場合も、ないとは言い切れない。「慷慨の志猶存す」という政治的心情をあらわす言葉を私が引いたのは、他者と共に生きる自由を、ぎりぎりのところで保持し続けたいがためなのである。
そのための行為が、自死のような形をとることは、本当は無い方が良いに決まっている。
だが、結果としてそのような形をとった場合にも、その死の意味の判断と引き受けは、国家にではなく、共に在る「他者」にだけ託されているのだということは、とくに言っておきたい。
★プロフィール★
岡田有生(おかだ・ありお)
1962年生まれ。男性、独身、親と同居。プロフィールに書くようなこともなく現在に至る。ブログ:Arisanのノート
広坂朋信(ひろさか・とものぶ)1963年、東京生れ。編集者・ライター。著書に『実録四谷怪談 現代語訳『四ッ谷雑談集』』、『東京怪談ディテクション』、『怪談の解釈学』など。ブログ「恐妻家の献立表」Web評論誌「コーラ」27号(2015.12.15)
<前近代を再発掘する>第3回:回帰する『太平記』あるいは歴史と暴力(広坂朋信/岡田有生)
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2015 All Rights Reserved.
|
| 表紙(目次)へ |