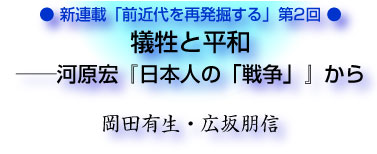|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「La Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
|
古典の誤用(広坂朋信)
河原宏『日本人の「戦争」』(講談社学術文庫)の初めの章「日本人の「戦争」」は、日本の古典と明治以降の日本人の歴史意識との関係、特にアジア太平洋戦争の時代に焦点を当てて、あの戦争の「古典依存的性格」を指摘している。もっとも、その冒頭で、ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)の観察に依拠して日本人一般の意識を規定している点には賛同できないが、古典の誤用を指摘している箇所は興味深い。
例えば、「海行かば」は荘重、悲壮な曲として知られるが、大伴家持によるその原歌は「黄金の産出を喜ぶ祝祭歌の一部だった」。ところがこの古歌を近代日本が利用したところ「大いなる歓びを歌った原歌が予想もしなかった葬送曲、それも日本自体の葬送曲を奏でてしまった」という指摘は面白い。
また、真珠湾攻撃の作戦計画を昭和天皇に説明した上奏文に「本奇襲作戦ハ桶狭間ノ戦ニモ比スベキ大胆ナル作戦」とあるのを挙げて、信長が奇襲戦法をとったのは桶狭間の時だけだったのに「日本軍は陸海軍ともに奇襲作戦を常用し、この例に限らずしばしばそれを桶狭間の戦いに譬えた。逆にいえば軍部は織田信長から桶狭間以外のことは学ばなかったようである」と手厳しい。河原によれば、織田信長の長所は合理主義と「絶え間のない自己変革」であり、「信長は戦うたびに、自らの軍団と作戦のあり方に自己変革をとげながら戦国の世を戦いぬいていった」のに、「軍にかぎらず多くの日本人が信長の疾風のような生涯に魅せられ」ながら、ついぞこの自己変革を学ぶことはできなかった。
こうした河原の指摘は、単に面白いだけでなく、「前近代的なものを否定的媒介にして、近代的なものをこえようとする」(花田清輝)構想を活かそうとするときに大事なポイントを示してくれるように思われる。
河原はこの他にも『古事記』や『平家物語』なども取り上げているが、面白いのは中世の楠木正成だろう。
戦前の教育では楠木正成は「七生報国」という言葉とともに、忠臣の鑑、帝国臣民の手本とされた。しかし、実在の楠木正成がどのような人物だったか、歴史学的にはよくわからないらしい。というのも、「正成の実像は、ほとんどはっきりしていない。なぜなら正成に関する文献史料が『太平記』以外にはごくわずかしかないから」(松尾剛次『太平記』中公新書)であり、
これは逆にいえば、楠木正成の人物像については、史料としては正確さに欠ける『太平記』と、正成が論じられる際にたいていの論者が引くエピソード、新田義貞を切り捨てて足利尊氏と手を結んだらどうかと後醍醐天皇に進言したマキャベリストぶりが記録されている『梅松論』。これらだけが正成の人物像をイメージする手がかりなのであって、こと正成の人物像については論者の立場を問わず同じ条件の下にある。つまり、『太平記』と『梅松論』、とりわけ『太平記』をどう読むかということに尽きる。
それでは、河原は『太平記』の正成をどう読んだか。
「あの言葉」とはもちろん「七生報国」である。河原は『太平記』の名場面を引く。
引用にあたり『太平記(三)』岩波文庫を参照して一部表記をあらためた。この場面で正成の弟・正季のセリフから「七生報国」という言葉が作られたわけだ(原文に即するなら「七生滅敵」というべきだが……)。
「的確に運命を洞察しながら」というのは、新田義貞軍の敗走を知ってあわてふためいた後醍醐天皇から出陣を命じられた正成は、いったん足利軍を京都までおびき寄せて、楠木勢と新田勢とで前後から挟み撃ちにする作戦を提言するのだが、面子にこだわる公家たちに却下されたという経緯が伏線になっている。正成は「そうですか、あなた方は私らに無策のまま敵の大軍に突っ込んで死ねと命じられるのですね。よろしい、それなら死んで見せましょう」(意訳)と見得を切って、死を覚悟して出陣した。これを「節義に殉じた」と評すべきかどうか、私にはいささか疑いが残るが、もう少し河原の議論を追おう。
河原は、死に臨んで弟の「七たび生まれかわっても…」という決意を聞いた正成が「罪業深キ悪念ナレ共」と応じていることに注意を促して、「それは戦いが、永劫の輪廻と苦患の淵に沈む『修羅』の道だという罪の自覚からだった」とする。
つまり、正成は「戦いは修羅の業という人間としての罪の自覚」と「そこから生まれる優しさの感覚」をもった人物であるというのが、河原の見立てである。なるほど、そのように読めば、楠木正成、なかなか魅力的な人物である。
一方で、戦時中のスローガンとしての「七生報国」は、「当時の武士たちをとらえていた修羅の実感も、正成が抱いた的確な予感も」欠けていて、内容空疎で逆効果だったと指摘する。
菊水は楠木正成の紋所にちなんだ名づけだが、ほとんど戦果は上がらなかった。この無謀な作戦を立案し命じた軍上層部は、体面にこだわって正成らをいたずらに死地におもむかせた南朝の公家を気取っていたということだろうか。沖縄戦が湊川の戦いだという連想がはたらいたのなら、当然それは必敗の戦いとなるだろう見通しもあったはずで、それなら早々に終戦工作を進めるべきであった。それが歴史に学ぶということではないのか。河原が楠木正成を持ちだしたのはそのことが言いたいためであったろう。この点については私も同感である。
しかし、河原の見立てどおりなら、楠木正成はなにやら宗教者のようだ。的確な運命の洞察、節義に殉じた生涯、悲愴美、人間としての罪の自覚、輪廻感覚、河原が正成に与える形容はいささか重々しすぎる。
花田清輝は「建武中興と戦後」と題したエッセイ(『冒険と日和見』創樹社所収)で、「建武の中興で、体制がわの一員になってしまったとはいえ、わたしは、楠木正成なども、佐々木道誉とそれほど変りのない、悪党たちの一人だったのではないか」と、バサラ大名・佐々木道誉と正成を同類としているが、正成が中世の新興勢力「悪党」の一人だったというのは、日本史の研究者たちから広く支持されている見解だろう。一例だけ挙げておくなら、
ちなみに海津は正成を足利方の武将・高師直と並置して、このように評しているのである。正成を、佐々木道誉や高師直と同類のバサラ者とするのには無理があるかもしれないが、悪党の一人であったことは中世史の定説といってよいだろう。花田清輝は早い時期からこの点に着目して正成の死を受けとめていた。
なにやら宗教的な罪の自覚をもって大義に殉じた武将ととらえるよりも、動乱の時代を思い切りよく駆け抜けた硬骨漢という方が、悪党・正成にふさわしい評価のような気がする。河原の正成像は、戦前戦中に作られた無二の忠臣イメージを相対化してこそいるが、河原の思い入れから別の鋳型にはめ込んでしまっているように思われる。
犠牲と平和(岡田有生)
河原宏『日本人の「戦争」』第二部以下では、日本の開戦も敗戦も「国体」の護持がその動機であったという考えが語られている。「革命より戦争がまし」「革命より敗戦がまし」という支配層の論理によって、開戦も敗戦もなされた、ということだ。
著者は、戦前の天皇制日本国家が「国体」と呼んだものの実質を土地所有制度にあると考え、二・二六事件や左翼労働運動によって噴出しはじめたその矛盾の根源を、改革によって解消することなく乗り切る方途として、権力者たちは日中戦争に始まる泥沼の道のりを選択したと見る。
また、ポツダム宣言の受諾による敗戦という選択も、天皇制という機構によって支えられてきた特殊な社会構造・権力構造の温存を、その目的としたものだったことが、戦争継続による革命の危険を天皇に忠言した「近衛上奏文」なども引きながら論証される。
こうした指摘は、たいへん鋭いと思う。
天皇制に代表されるような「場」の維持を最も(人命その他よりも)重視して、そのために開戦を選択したり、敗戦を受け入れたりするという権力構造のあり方に着目するのは、柄谷行人の日本社会分析にも通じるものだろう。それは、「家」(日本的家族)や「会社」という「場」の絶対性の論理と同型だ。
だが、ひっかかるのは、著者がこうした「改革」や「革命」を忌避する社会的な特徴を、日本人なり日本文化の本質のように捉えた上で、それを両義的に(ということは、長所としても)評価していることだ。
つまり、物事を主体的とか原理的に突き詰めず、曖昧にすることで、既定の「場」のようなものを守ろうとする精神的な態度のゆえに、「本土決戦」は回避され、敗戦(ポツダム宣言の受諾)が選択されたと著者は言うのだが、しかし、忘れてならないのは、そのことの裏面として、日本は沖縄には「決戦」を強いたということである。
このことは、著者が両義的に捉えている「形而上的な思考を好まない」日本社会の性格(それが日本的寛容さと呼ばれたりする)が、他者に対しては、最悪の暴力性を差し向ける一面を持つものだ、ということを示しているのではないだろうか。
著者は、この「形而上的な思考を好まない」日本社会の性格を、伝統的な美質でもあると捉え、近代主義だの軍国主義だのというものは、その伝統的美質を毀損する外来の悪であると考えているようなのだが、歴史の中で日本が他者に対して何をやったかを考えれば、そんな手前勝手な内と外の区分けは出来るはずがなかろう、と思う。
そもそも、「革命」や「改革」を忌避しようとし、原理的な思考を好まないという精神のあり方なるものを、「日本的なもの」の純粋なモデル、かつ専売特許のように考えようとする著者の思考のあり方に、私は、近代主義的・帝国主義的な胡散臭さを感じる。
日本人は、それほど温和で攻撃的・破壊的なものを好まない民族的・国民的本質を有した集団であろうか?「革命」を言う者ばかりでなく、「改革」や「戦争」を言う者も、その本質から外れた「非国民」として権力の周縁に置かれてきたのだと言いうるほどに、われわれの近代の歴史は「美しい」「本質」を根底に秘めたものであったろうか?
・自国の兵士
こうしたことは、「特攻・玉砕への鎮魂歌」と題された終章の議論に対する違和感につながる。
ここで著者は、吉田満の『戦艦大和ノ最期』(初出作)や吉田嘉七の『ガダルカナル戦詩集』を引きながら、次のように書く。
だが、言うまでもなく、戦争によって「非業の死」を遂げたのは戦死した日本軍の兵士だけではない。アジアや他国の死者たちの膨大な存在があるし、戦災によって亡くなった民間人の数も、もちろん膨大なものである。その中から、著者はあえて特定の死者を選び出し、それに同一化しようとしている。それは、こうして選び出されて想像されている死者の心情なるものが、すでに著者(の欲望)によって特定の政治性を付与されているということを意味する。
つまり、これは政治的な追悼なのだ。それならば、その政治的な欲望の中味がどのようなものかが、問われなければなるまい。
著者は、日露戦争期に作られた唱歌『戦友』と太平洋戦争中に作られた軍歌『同期の桜』とを対比し、その大きな違いは、前者には死んだ兵士にとって「還るべき場」があることだと言う。それは、還るべき「くに」であり、本居宣長の書物に示されているような「民俗の信仰」に根ざした空間だ、というのである。
靖国に対する批判は、その通りであろう。しかし、靖国の思想は、明治の初めから確実にこの国の、とりわけその戦争の思想の中心部に存在してきたものだ。
帝国主義戦争における自国の兵士の死者だけを、特権的な追悼と同一化の対象として選び出すような著者の眼差しによってでは、「民俗の信仰」の奥深さというような、普遍性につながりうる(非近代的な)領域を、まともに想像することは不可能であると思う。
・民衆の戦争責任
『日本人の「戦争」』第三章では、天皇や指導層、及び民衆の戦争責任が論じられる。
著者は、天皇を含む日本の為政者や日本国民は、政治的・法制度的には戦争責任を負わなくてよいが、倫理的・道義的には責任を有する、と論じているのだが、その主張の含意は、日本という近代国家が有している根本的な無垢さのようなものを護持するということ、その無垢さを汚したものとして、近代主義や軍国主義の反倫理性を断罪するということである。
それについての異議は上に書いた。
ところで東京裁判について、著者は、直接の戦争指導者だけを断罪することで、「日本資本主義と官僚機構に無罪の根拠を提供した」と言って批判している。
そのことを端的に示すのは、戦後政界における岸信介の復活である。著者はここで、戦犯である岸の復活と政権の安定が、不況を恐れ経済的繁栄を希求した「民衆の政治的意志の表明」であったことを強調する。
これも非常に鋭い指摘だと思うが、ここでも著者はそうした民衆の心理を批判するわけではないのだ。
こうしたことがどうにも、私には理解しがたいところである。
*戦後の平和と『楢山節考』
先に書いたように、『日本人の「戦争」』の著者の河原宏は、日本人の特性として、「形而上的な思考を好まない」ということをあげ、その昭和史における例として、「国体」という「場」の維持を最大の目的として、そのために戦争を始めたり、逆に「本土決戦」を回避して戦争を終わらせたりしたのだ、という見方を示していた。
ドラスティックな改革や革命によって、「国体」に代表される同質的な「場」が瓦解してしまうことを何よりも忌避し、そのためには戦争を起こしたり(十五年戦争)、それを切り上げたり(ポツダム宣言受諾)さえするような、特異な精神構造のようなものを、河原は「形而上的な思考を好まない」と表現していたのである。
同質的な「場」の維持を絶対的な目的とする、このような精神構造を、しかし河原は、両義的に捉え、近代主義や軍国主義に対立する温和な精神のあり方として、日本人の美質のようなものとして評価してもいた。私は、そのことに疑問をもったのであった。
というのも、たとえばポツダム宣言の受諾によって、本土決戦が回避され、天皇の戦争責任も曖昧なままに、いわゆる戦後の平和がもたらされたことは事実だが(天皇制日本という場は堅持された)、それは沖縄戦と、その沖縄の切り捨てという代償を伴うものでもあった。
他者にこのような過酷を押しつけ、犠牲にすることによって成り立っていくような「場」の維持の構造を、温和さや寛容さといった言葉によって肯定的に評価することなどできるであろうか。
これはもちろん、この国の「戦後の平和」と呼ばれているものの評価にも関わる問いだ。
私は、「場」の維持を絶対的な目的として、他者や、ときには自分たちの(戦争を始めた時はそうだった)生命までも平然と犠牲にしてしまうような精神構造を、自分の奥深くに実感するからこそ、そこに肯定的な価値など見出すべきでないと、考えてしまうのである。
ところで、この連載の前の回では、花田清輝のエッセイ「柳田国男について」をとりあげたが、その最後のところで深沢七郎の『楢山節考』が話題に出てくる。花田は、この小説を、柳田国男が再評価したような前近代的価値観を現代に甦らせるものとして、肯定的に捉えていたようなのだが、私から見るとあの小説は、戦後(広く近代のと言ってもよい)の日本社会が、前近代と変わらず根本的には犠牲の仕組みの上に成り立っているという事実を、不気味に指し示したものであると思える。
中公文庫の『楢山節考/東北の神武たち 深沢七郎初期短編集』には、この小説が第一回中央公論新人賞を受賞した際の、伊藤整、武田泰淳、三島由紀夫による選後評の鼎談が収録されているのだが、そこで印象的なのは、『楢山節考』の物語にある種の伝統的な「美しさ」を見いだす武田泰淳の言葉に、三島が反発して、怖さや不快さ、脅かされたといった表現を、しきりに使っていることである。
三島は、この作品の何に、これほど脅かされながらも引きつけられたのだろうか。
それはおそらく、この小説が、戦後の日本社会が根底では「前近代的な」犠牲の仕組みによって成り立っており、そこでは三島が為そうとしたような「近代(戦後)」への否定の仕方も、やすやすと回収されてしまうのだという事実を突きつけてくるものだということを、彼が直感したからではないかと思う。
『楢山節考』のラストでは、主人公のおりんを「楢山」に送った息子の辰平が家に戻ってみると、孫夫婦がすでにおりんの着物をちゃっかりと着こんで座っているのだが、これは作者が捉えた「戦後」の日本社会の実態そのものではなかろうかと思うのだ。
そこに示されているような、戦後(近代)日本の犠牲の仕組みは、三島が体現したようなラディカルな否定を簡単にのみ込んでしまう。三島は、「戦後」の欺瞞性を告発し、いわば本土決戦をあらためて行えば事足りると考えていただろうが、その戦後とは、実際には前近代と近代を貫く犠牲の仕組みのもとに成り立つものであり、ラディカルな否定は、犠牲の一種として消化され、システムの維持に利用されるだけなのである。
・『水平軸の発想』
ところで、『日本人の「戦争」』に関して、私は沖縄の犠牲ということに言及したが、沖縄戦の悲劇に深い関わりをもつと考えられる他者の暴力的な同化及び抹殺の機構と、河原宏が示唆したような原理性(形而上学)の排除によって行われる同質的な「場」の護持の論理とが、表裏一体をなしていたというのが、日本の近代の悪しき実像だといえるのではないだろうか。
私は最近、沖縄宮古島の出身で、戦後の沖縄を代表する思想家の一人と思われる岡本恵徳の、いくつかの文章を読んだ。そこには、上記のような日本の近代というものの性格を見詰め直し、私たちがその桎梏を真に乗り越えていくための貴重なヒントが含まれていると思うので、以下、それをめぐって論をすすめたい(岡本恵徳の存在と思想については、新城郁夫氏の著作と発言から大きな示唆を受けた)。
「沖縄の「共同体意識」について」という副題をもつ岡本の代表的論考、『水平軸の発想』は、それが収録されている二冊の本(注 『わが沖縄第六巻・沖縄の思想』(谷川健一編 木耳社、1970)、『現代沖縄の文学と思想』(岡本恵徳著 沖縄タイムス社、1981年))が今では入手困難のようなのだが、幸いにして以下のサイトで全文を読むことができる。
ここでは、それを参照させてもらうことにする。
論考『水平軸の発想』は、まず冒頭で、筆者である岡本自身にとって「沖縄」というものが、かつてはそこから「脱出すべき不毛な領域」と思われていたということが語られ、そうしたものとしての「沖縄」が葛藤と長い模索を経て肯定的な対象(注 後述するように、これは沖縄の特殊性ということではない。)として再発見されていく過程が、これ以降述べられることが予告される。
この部分で注目されるのは、そうした発見が、島尾敏雄や谷川健一といった非沖縄(「本土」)出身の人たちによる沖縄・南島(ヤポネシア)の発見とは、意味合いの違うものとして捉えられていることだ。
同じ対象を扱ってはいても、「逆の発想になる」というこの違いは、私なりに深読みするなら、「本土」の論者たちが近代日本の同一性を補強するために「南島」を発見しようとしたのに対して、岡本にとっての「沖縄」とは、同化を強いてくる近代日本の圧迫から、自分のなかのかけがえのないものを守りぬくための手掛かりのようなものだった、ということであると思う。
岡本が見いだす「かけがえのないもの」を守る道は、沖縄の「共同体」(前近代)の再発見に関わるものである。
その「かけがえのないもの」を、私たちはどのように捉えるべきだろうか。
それについては、後ほど論じたい。
さて、『水平軸の発想』は続いて、岡本の私的体験を詳しく検証しながら、「日本」への暴力的な同化の過程に他ならなかった、沖縄における「近代」というものの実像を克明に描き出し、沖縄においては(日本への)「愛国」という感情が、「沖縄の人間」であることへの自己否定・自己卑下から起因するものに他ならなかったという事情が説明される。
その後、山之口獏の詩に対する解釈や、安保闘争時に実感した「本土」の政党や労働組合の「硬直」した(「近代的な」ということになろう)体質への失望などに言及しつつ、岡本がしだいに内なる「沖縄」を、たんに「脱出すべき不毛な領域」としてではなく、身体の奥深くに刻み込まれて存在する情動的な対象、硬直した「近代」からの離脱の手がかりとなるようなものとして見いだしていった経緯が語られる。
こうした内的道程を経て、東京から沖縄に帰郷した岡本が、内なる「沖縄」の内実を見極めるために着目したのが、沖縄戦の民衆的体験であり、なかでもとくに、渡嘉敷島の集団自決事件という出来事であった。
渡嘉敷島や座間味島などで起きた集団自決に関しては、軍の命令の有無や強制性をめぐって、きわめて多くの論議や争いが起こってきた。だが岡本は、まず軍の命令の有無は大きな問題ではなく、軍人たちの住民に対する意識と扱い方からすれば、そこには命令が下されたのと同じ状況(広義の強制)があったと考えるべきだとし、それよりもむしろ、そうした状況があったにもせよ集団自決という行為を住民たちが選ぶに至った内面のあり方に目を向けて、深く考察していく。
別の論考(注 「「沖縄に生きる」思想―「渡嘉敷島集団自決事件」の意味するもの」(『「沖縄」に生きる思想』岡本恵徳著 未来社、2007年 所収))で明瞭に述べられているように、そこには上述してきたような、近代日本の同化の暴力が生み出す沖縄の人々の自己否定・自己卑下の感情が働いており、そこから「近代」と「日本」への同一化の狂おしい希求が生じたことが、集団自決という「崇高な犠牲的精神」による惨劇の原因の一つであると、岡本は見るのである(注 右翼が『楢山節考』の作者である深沢七郎と集団自決事件の二つを共に攻撃対象としたのは、それらがいずれも「犠牲の物語」の「美しさ」を毀損するものだと感じられたからではないかと思う。)。
つまり、近代という暴力が、犠牲的な集団死へと人々を追い込んだメカニズムが、ここで見極められているのだ。
だが、それにとどまらず、『水平軸の発想』で岡本は、この集団自決を「共同体の生理」に関わるものとして否定的に論じた石田郁夫の文章を参照しながら、この「共同体の生理」と集団自決という出来事とに、しかし肯定的なポテンシャルを見いだしていくのである。
これは、肯定的対象としての内なる「沖縄」の再発見ということだが、そこに、岡本が切り開いた、もう一つの「近代の超克」の展望を、私は見る思いがする。
このように、岡本が対峙しているのは、「おのれのみよければ、すべてよし」という近代主義の原理であり、集団自決という出来事のなかには、たんなる犠牲的行為ということを越えて、この近代主義を克服していく萌芽が示されているのではないか、それこそを「内なる」糧として自分(たち)は育んでいくべきではないかというのが、彼の論点なのである。
さらに、『水平軸の発想』の最後のパートでは、岡本は、近代の暴力に抗する生の力の拠り所としての「共同体的生理」の重要性を説いたうえで、国家権力は、その「共同体的生理」に沿うことで、人々を巧妙に支配しようとするものだと指摘する。
そのことにどう抗い、「共同体的生理」という前近代的なもののポテンシャルを、国家の支配から奪い取って私たちの生の実現に資するものにするかが、課題となるわけである。
岡本は、次のように書いている。
・私たちが学ぶべきこと
『水平軸の発想』の概要は以上だが、そこで私たちに示唆されていると思われるものについて、整理して考えてみたい。
まず、岡本にとっての「沖縄」とはいかなる対象であり、それは彼が守ろうとしていた「かけがえのないもの」(これは私の言葉だが)と、どのような関係にあるのか、ということから見ていこう。
岡本にとって「沖縄」は、自己の奥深くに内在する情動的な対象だったが、彼はこの対象が持つ普遍的な意味を、自分自身の葛藤と、沖縄の人々(民衆)が刻んできた歴史の記憶をたどることとを通して、創出したといえると思う。その過程で発見されたのが、近代主義に回収されない「共同体的生理」というものの重要性であり、その民衆的なポテンシャルとよべるものである。
岡本がこの論考の前半部で語っていた同化の暴力についての記述を読むと、いわば自分が元々それであったはずの存在を、自ら否定し差別するところに、「近代」への回収(近代化)が行われ、また愛国心のようなものも形づくられるというこのメカニズムは、沖縄においてもっとも如実であるとはいえ、しかしもっと一般的にもあてはまるもの、少なくとも私たち日本の人間のすべてが程度の差はあれ経験してきたこと(そして、いま切実に経験しつつあること)ではないかという示唆を、岡本から受けているような気がしてくる。
岡本の内なる「沖縄」をめぐる探求が、私たちに指し示すのは、けっしてたんなる特殊性の問題に還元される何かではなく、その土地の歴史のなかで生きられ、そして岡本という一人の人間によって「内なるもの」として発見された、近代(国家)の介入以前に存在するはずの共同的な生のポテンシャルであり、それは近代の暴力に対する抵抗を通してしか見いだされないような、構成的で肯定的な「前近代」の姿だと考えられる。
岡本は、犠牲的な集団死という歴史の惨劇のなかから、国家の暴力によって隠蔽されたこの生のポテンシャルを拾い上げてくるのである。
この「共同体的生理」の重視ということは、岡本の思想を捉えるうえでとくに大事な点だと思うので、回り道をするようだが、ここで岡本の別の文章を少し引いておきたい。
それは、1978年に沖縄タイムスに掲載された「「同化」と「異化」をめぐって」(注 『「沖縄」に生きる思想』(上掲)所収)という文章である。このなかで岡本は、当時に話題にされていた、沖縄から集団就職で「本土」に働きに出た若者たちが、「文化の違い」とされる理由から離職してしまうことが多いという事柄に関して、次のようなことを書いている。
ここには、岡本の民衆(共同体)に対するスタンスが、よく現われていると思う。
それは、「前近代」的とも思えるような、抑圧され剥奪された人々が近代の暴力によって抱え込まされた困難や空虚や葛藤を、自分の「内なる」ものとして捉え、その人々が次第に力と自信を回復していく過程に、自らの生を重ね合わせて進もうとするような態度である。
民衆の困難や葛藤や限界を、自分自身のそれでもあることを認め、共に苦しみ、共に歩んでいこうとする姿勢が、ここにはある。
こうした方法以外に、近代の暴力との闘争は不可能であるという確信が、岡本にはあったのだと思う。
ここから私たちが学ぶべき肝心なことは、自分が置かれている困難や葛藤を、いかに的確に対象化し、それを共有していくかということだろう。そこにしか、真の民衆的思想や運動というものの、出発点はないはずだ。
次に、この(「共同体的生理」がはらむ)ポテンシャルによって守られるべきだと考えられる、「かけがえのないもの」をどう捉えるべきかを、考えてみよう。
ここまで、「犠牲」ということについて何度か言及したが、倫理学者の野崎泰伸は、近著『「共倒れ」社会を超えて』(筑摩書房、2015)のなかで、犠牲を、こう定義している。
岡本が近代的暴力から守ろうとして、私的な葛藤を続け、また歴史のなかにその在り処をさぐった「かけがえのないもの」とは、まさにここで言われている「交換や譲渡ができないもの、しないもの」ではないだろうか。
それは、国家や資本といった近代的な力によって、あるいは共同体それ自身によっても、犠牲として差し出されることを求められることがあるが、それが本来はできない、してはならないような、生の根底的な条件であると考えられる。
岡本は、「沖縄」という形で現れた彼の内面の葛藤や困難のなかから、この根底的で普遍的な生の条件を見つけだしてきたのだといえよう。彼にとって、沖縄という特殊性に特別な価値があるのではなく、それは近代国家の暴力から、人間として生きるための大事な要素を守るための拠り所となるものだからこそ(沖縄の民衆の歴史が、それを可能にしたと言ってよいだろうが)、肯定されるのである。それが共同的な生のポテンシャルに関わるということは、すでに述べた。
岡本が守ろうとしたと思われる「かけがえのないもの」とは、近代の(これはほとんど、人間の歴史の、と言い換えてもよい気がするが)暴力が強いてくる「犠牲」(交換原理の全面化)への誘導に抗して守りぬかれるべき、共同的な生のあり方だということになろう。
ところで、岡本が、「沖縄」という自分のなかの情動的な対象を、近代の暴力によって抑圧された領域として把握し、さらにその領域の持つ意味を普遍的なものへと開くことになった契機は、沖縄戦・集団自決という民衆の体験であった。
彼は、自分が抱えた葛藤を、戦争という極限的な状況のなかで近代の原理・国家の論理に呑みこまれそうになりながらも抗った人々の体験と重ね合わせることによって、犠牲を肯定しない社会のあり方、「ともに生きよう」とする意志を具現化するような社会の像を描くことができたのである。
それは、歴史のなかで抹消されてきた、抑圧された者たちの願いや意志を、自分自身のものとして受け継ぐことである。そこに、前近代そのものというより、歴史を貫いて存在してきたはずの生の力を継承することで、近代の暴力と国家権力との支配を乗り越えていく、真の「近代の超克」の道筋が示されていると思う。
それは、犠牲を当たり前のことと考え、他者の生命や心、あるいは自分自身のなかの「かけがえのない」何かを、大きな社会的な力に差し出してしまうことに無感覚であるような、この「日常」というもののあり方を突破していく態度である。また一方、それは近代や国家権力へのラディカルな否定に走ることによって、別の形で自他の生命と「かけがえのない」ものとを犠牲に供することをも、拒む態度でなければならない。
私たちは、岡本にならって、近代国家の暴力と抗おうとした人たちの、見えにくい姿を歴史のなかから探り出し、また今現在においても注意深くそれを見いだし、そこに自分たち自身の「ともに生きのび」ていく未来への展望を重ねていかなくてはなるまい。
しかし、そのような継承の対象となり得るような、両義的で開かれた民衆的記憶というものを、「本土」の側の私たちは、果たしてもっているだろうか?
私には、そのもっとも大きなものは、憲法9条に集約されるところの「戦後の平和」、それ自体ではないかと思えるのだ。
日本の戦後の平和を考えるとき、私たちは、それが冷酷な同化的犠牲の暴力によって維持されてきたという事実を忘れてはならない。それはまた、日米安保条約と重なり合う欺瞞に満ちたものでもあった。しかも、この「犠牲による平和」のメカニズムは、とりわけ3・11以後の日本社会では、際限もなくその凶悪さをむき出しにして働き続けていると思えるのである。その露骨さは、いまや再び戦争という極限的な形態をとって現象しつつある。
だが同時に、この犠牲と欺瞞のメカニズムから逃れる道は、それによって形成されてきた「平和」のラディカルな否定のなかにもあるわけではないということが、確認されねばならない。
この国の戦後の「平和」は、犠牲のシステムに同一化することで安定と繁栄をむさぼってきた、私たちだけのものではない。この平和は、なによりも、私たちの国によって殺された人々、私たちが虐げてきた人々、国家や社会の犠牲にされることを私たちが容認し、そして忘却と否認によってその生死の体験を無いもののように扱ってきた人々への、いまだ果たされていない約束なのだ。そのことを引き受け、私たちが犠牲とその否認の構造への同一化からほんとうに脱却するとき、はじめて「平和」は、民衆的な理念として私たち自身の身体の内部で生命を与えられ、「ともに生きのび」ていく未来への道を指し示すものになるだろう。
その約束の実現のためにこそ、私たちはこの平和を手放してはならないのだし、そのことは、私たち個々がいかなる形においても、それぞれのなかの(また相手のなかの)真に「かけがえのない」ものを犠牲に捧げはしないという決意によって、保証されるものなのである。
・付記(広坂)
今回、広坂は病気療養のため、ほとんどの執筆を岡田氏に押し付けることになってしまった。冒頭の広坂執筆部分で紹介した河原宏『日本人の「戦争」』への疑問点についても、岡田氏が巧みにすくいとってくださった。記して感謝する。
★プロフィール★
岡田有生(おかだ・ありお)
1962年生まれ。男性、独身、親と同居。プロフィールに書くようなこともなく現在に至る。ブログ:Arisanのノート
広坂朋信(ひろさか・とものぶ)1963年、東京生れ。編集者・ライター。著書に『実録四谷怪談 現代語訳『四ッ谷雑談集』』、『東京怪談ディテクション』、『怪談の解釈学』など。ブログ「恐妻家の献立表」Web評論誌「コーラ」26号(2015.08.15)
<前近代を再発掘する>第2回:犠牲と平和――河原宏『日本人の「戦争」』から(広坂朋信/岡田有生)
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2015 All Rights Reserved.
|
| 表紙(目次)へ |