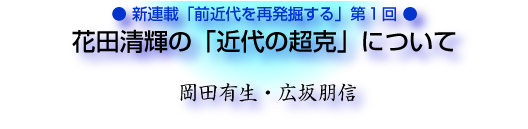|
|
|
Web�]�_���u�R�[���v |
|
���n���̎� ���{���̕\���i�ڎ��j�� ���{���̃o�b�N�i���o�[ ���ǎ҂̕Ł^���ӌ��E���z �����e�K�� ���W�҂�Web�T�C�g ���v���C�o�V�[�|���V�[ |
|
���{���̊֘A�y�[�W�� |
|
���u�J���`���[�E�������[�v�̃o�b�N�i���o�[ ���]�_���u�k�� Vue�v�̑��ڎ� |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
|
���O����i�L����M�j
�@�������i���c�L���ƍL����M�j�́A�u�ߑ�̒����v�ƌĂ��e�[�}���Č������Ă݂����Ǝv���������B�Č����Ƃ����̂́A���a�풆���ɂȂ��ꂽ�u�ߑ�̒����v���k��Ƃ��̎��ӂ̎v�z�ɂ��ẮA��l���������ꂼ��̎��_����ڍׂɌ��������D�ꂽ���ʂ����łɂ��邩�炾�B
���Ƃ��A�|���D�w�ߑ�̒����x�i�}�����[�j�A�A���w�q�ߑ�̒����r�_�x�i�����o�ŎЁ^�u�k�Њw�p���Ɂj�A�q����M�w�u�ߑ�̒����v�Ƃ͉����x�i�y�Ёj������A�ŋ߂ł̓n���[�E�n���g�D�[�j�A���̑咘�w�ߑ�ɂ�钴���x�i��g���X�j���ꂽ�B�������ɂ́A������Ƃ����ɂ��v�z�j�����ɐV�����_�_��t�������悤�Ƃ�����S�͂Ȃ��B
�@�������̊S�́u�ߑ�̒����v�ƌĂ��e�[�}���������ɖ₢�����Ă�����̂ɂǂ��������邩�Ƃ������Ƃɐs����B��̓I�ɂ́A�O�ߑ�̕����┽�ߑ�̎v�z�̂Ȃ��ɁA���ߓI�ɍč\�����ꂽ���̂Ƃ��Ăł͂���A�����̋ߑ�ᔻ�̌_�@���@��N�������ƂŁA�u�ߑ�̒����v�ƙG�̂���鈫�������{�^�ߑ��`�̉^���ɑR���Ă������Ƃ͉\���H�@���̉ۑ�́u��ヌ�W�[������̒E�p�v�ȂǂƂ����C�J�T�}�́u�ߑ�̒����v���̂����Ă��鍡�A���g�ނɂ�����������̂��ƐM����B
�@�������A�������̒��ڂ̊S�͏���Ƃ��_���Ă����u�ߑ�̒����v���k��ɂł͂Ȃ��A�u�ߑ�̒����v�Ƃ����e�[�}���̂��̂ɂ���̂ŁA���k��Ƃ��̎��ӂ̎v�z�ɂ��Ă͊ȒP�ɐG���ɂƂǂ߁A���A���c���j��_���邱�Ƃŋ��s�w�h�̓N�w�҂�������{�Q���h�̕��w�҂����Ƃ͈قȂ�A������́u�ߑ�̒����v�_�̉\����T�낤�Ƃ����ԓc���P�u���c���j�ɂ��āv�i�w�ߑ�̒����x�����j���ŏ��̎肪����ɑI��ŋc�_���n�߂�B
�@
�P�@�ԓc���P�u���c���j�ɂ��āv�i���c�L���j
�@�ԓc���P�̃G�b�Z�C�u���c���j�ɂ��āv�́A1959�N�ɏo�ł��ꂽ�w�ߑ�̒����x(�����Ё^�u�k�Њw�|���Ɂj�Ɏ��^����Ă���B
�@���̘_�W�̂Ȃ��ŁA�ԓc�͂����Ζ��c�ɂ��āA�����ւ�m��I�ɂƂ肠���Ă���̂����A�w�i�ɂ́A�������c���A�ێ甽���̑�\�҂̂悤�ɍl�����Ă����Ƃ������Ƃ�����̂��낤�B�ԓc�́A���c�̊w������̂悤�ɐ��Ď̂Ă邱�Ƃ��A�������ĕϊv���㊊��Ȃ��̂ɂ��Ă��܂��Ƃ����l������A�x����炵���B
�@���c���ێ甽���ƌ��Ȃ����悤�ɂȂ������R�̈�ɁA�s���ɖ��c���s���������A���ɓ����u�i���h�v�Ɩڂ���Ă������l���̐l�����Ƃ̑Βk�ɂ����锭�����������悤�B���j�w�҉Ɖi�O�Y�Ƃ̑Βk�́A���̒��ł��A���ɖڗ����̂ł���B
�@���̃G�b�Z�C�ł̉ԓc�̘_���A���̉Ɖi�̖��c�ς�ᔻ���邱�ƂœW�J���Ă����B����́A����43�N�̒���w����g�_���x�Ŗ��c���������A��i�Ёj�ɂ��_���^���ɑ���A���c�̗��`�I�Ƃ��Ăׂ鑨�����Ɋւ��B�����Ŗ��c�́A�_���̋����̂̓������d�������̉^�����A���̔_�{��`�I�C�f�I���M�[�Ɋւ��Ă͎��{��`�o�ω��̔_���̋ꋫ���ڗ����Ȃ����̂Ƃ��Č������r���Ȃ�����A����ŁA�M�p�g�����x�ɂ��ߑ�I���v��i�߂�ɂ������Đ������Ă����ׂ������������̂Ƃ��ėi�삵�Ă�����̂ł���B
�@�����������c�̑ԓx���A�u�ݑ��n��C�f�I���M�[�v�i�_�������j�̘g���z�����Ȃ��ێ琫�̏؍��Ƃ��Ĕᔻ����Ɖi�O�Y�ɑ��āA�ԓc���P�͂����ɖ��c�́A
�Ə����̂��B
�@���ꂪ�A�ԓc�̍l����A�^�́u�ߑ�̒����v�̕��@�������B
�@�ԓc�ɂ��A�Ɖi�̂悤�Ș_�҂́A�܂����{�̃}���N�X��`�҂�i���h�̐l�X�́A�_���Ȃǂ́u���{�l�̐����v�ɖڂ������邱�Ƃ�Y��Ă���B�܂�A�ϊv���Ă����ׂ��y��i��Ӂj��A�ϊv�ɂ���ċ~���ׂ��Ώۂ̂���l�Ƃ��������̂��A�������������ƌ��Ă��Ȃ��̂ł���B
�@�ϊv�Ƃ����Ƃ��ɁA���ۓI�Ȗ����������ǂ����߂��āA�̐S�ȕϊv�̖{�̂Ƃ������̂����c����邩��A�����㊊��Ȃ��Ƃɂ����Ȃ�Ȃ��B�ϊv��v����i�����ƁA���邢�͂܂��������Ȃǂƌ��ł͌������A���ۂɂ͂��̂���Ă��邱�Ƃ͐^�t�̌��ʂ������݂����Ȃ��̂ł���B
�@���c�́A���̓y��ł���{�̂ł�����̂ɒ��ڂ����ƍl������킯�ŁA�ԓc�������]��������c�̊w��̎p���Ƃ����̂́A�����������̂ł͂Ȃ����Ǝv���B����́A���O�̐����Ƃ����y����l�����邱�Ɓi�����w�j�ƁA���̎��ԓI�ȓy��ł��閯�O�̗��j��T�邱�Ɓi�j�w�j�Ƃ��A�s���ƂȂ����w�̎p�����B
�@�������ĉԓc�͖��c�Ƌ��ɁA���̓y��ɑk�s���A�܂���ӂɒ������悤�Ƃ���킯�����A���ꂪ��ɐ^�̕ϊv�Ƌ~�ς����߂�p���ł��������Ƃ����A�̐S�ȓ_�ł���Ǝv���B
�@�\���҂ł���ԓc�́A�������ɁA�|�p�\���̖��Ƃ��čl�����B�u���c���j�ɂ��āv�̌㔼�́A���̂��Ƃ�_���Ă���B
�@���a13�N�Ɋ��s���ꂽ�w�̘b�ƕ��w�x����A�����ȑO�́u�����ʐl�����v�i���O�j�ɂ��������|�̓`�����̗g������c�̕��͂����p���āA�ԓc���咣����̂́A�O�ߑ�ɂ�������������̉��l�̍Ĕ������A�ߑ�́u���������v�ɂ��x�z������A�����̐V���ȁu�����o�����v�̌`���Ɣ��W�Ɍ��т��ł��낤�Ƃ����A�ϋɓI�Ȍ����Ăł���B
�@����́A�ԓc�������Ō����Ă��錻��̑�O�I�ȁu�����o�����v�Ƃ������t����A����Ƀe���r��W�I�̂��Ƃ������v�������ׁA���邢�͂܂�����ɂ�����IT�ɂ��o�ŕ��̐Ȋ��Ƃ��������Ԃ������l����Ȃ�A�Ȑi����`�҂̃I�v�e�B�~�Y���Ƃ��Ƃ�ꂩ�˂Ȃ����̂��낤�B
�@�����A�ԓc�������������̂́A������e���r�Ƃ��������f�B�A�i�}�́j�ɂ��x�z����̉���Ƃ������Ƃł���A���Č��������ɂ����Ă͊l������Ă����͂��́A�\���҂Ƌ���҂Ƃ̐g�̓I�ȑ��ݐ��̏�����߂��Ƃ������ƂȂ̂��B�ԓc���A��т��ċY�Ȃ̏㉉�ɋ����M�ӂ��X�������R�́A�����ɂ���̂��낤�B
�@���̑Γ��ȁA���ݓI�ȕ\���̏ꂪ�D���Ă������́A�ǂ�ȕ\����i�ł����Ă��A����͗}���I�Ȃ��̂ł���B
�@���̗}���̍\����Ŕj����悤�Ȏ�̐����A������O���g���D�悷�邱�ƈȊO�ɁA�ǂ�Ȋv����u�����v�̕��r�����邩�B���ꂪ�A���̌|�p�_�E�\���_�ɂ����Ă��A�ԓc�̌����Ƃ��Ă��邱�Ƃ��Ǝv���B
�@�ߑ�ɂȂ���x�z�̍\���̂Ȃ��ŗ}���������������Ă��������̂̕����A�����Ė��O�́A���Ƃ�x�z���͂���Ȃ��A�������������Ő����ĎЉ�����グ�Ă������Ƃ���͂Ɠ��i�^�́u�ߑ�̒����v�j���A�u�O�ߑ��ے�I�}��Ƃ����v�V���ȁu�����o�����v�̌`���Ƃ����ϋɓI�r�W������ʂ��ĒT���Ă���̂ł���B
�@���́u���c���j�ɂ��āv�̍Ō�ł́A�ԓc�́A�����炭���c�̍ł��D�ꂽ�ᔻ�҂������Ƃ��l������K�����v�̒�������A���c�̎��̂悤�Ȕ��������p���āA���߂������Ă���B
�@����́A���c�Ƃ̑Βk�ŌK�����A�i���c�̂悤�ȁj�u�����̊w�ҁv�ɂ́u�f�p�����悢�Ƃ��낪����v���A�����������̂͂���Ȍ�̐���ɂ͂��͂�Ȃ��Ǝv���A���̈Ⴂ�͂ǂ����痈�Ă���̂��낤�Ɛq�˂��̂ɑ��āA���c���A���������ɐ��܂ꂽ�w�҂́u���`�͂Ƃ������A�F�s�����͋^��Ȃ������v�ƌ����A���́u�F�s�v�Ƃ������̂��A�P�Ȃ�ϔO�ł͂Ȃ��A�����̊w���P�o���Ă����ׂɕ�e���Ă��鎅�Ԃ̃C���[�W�Ƃ��āA�u�����I�ȁA�������w���́x�v�Ƃ��đ��݂��Ă������炱���A�u�悢�v�̂��A�Ɠ������Ƃ�����|�̘b�ł���B
�@���̂����̌�ŁA�K�����A����ł��u�F�s�v�Ƃ����悤�Ȏ���������ɕ��������邱�Ƃɂ͎����͔����Əq�ׂāA���c������ɓ��ӂ����Ƃ�����������Љ�Ă���A�ԓc�͂������߂������Ă���B
�@���c���j���A�u���`�͂Ƃ������A�F�s�����́v�ƌ��������A�����ɂ͍��Ƃ̘_�����疯�O�̎v�����敪���Ď�肽���Ƃ����A�ނ̈ӎu�̍ŗǂ̕�����������Ă���Ƃ��l������B
�@�����C���[�W���A�l�ɗ͂�^����Ɠ����ɁA�l���v�������Ȃ��Ƃ���Ɉ��������Ă������͂������̂ł��邱�Ƃ��m���ł���B�܂�A�u�����I�ȁA�������w���m�x�v�Ƃ��ẴC���[�W�̗͂��A���c�̈ӂɔ����āA�����I�ȓ����̌���ł̕����Ƃ�����������т������댯�����\���ɂ���̂ł����āA�����ɓB���������K���̈ꌾ�́A�����Ė�邾�ƌ����Đ�̂Ă�ׂ����̂ł͂Ȃ��̂��B
�@�ԓc�͂����炭�A������l�����������ŁA���c�ɂ́A�u�ߑ��`�ҁv�K���Ɍ��������Ƃ����O�ߑ�I�Ȃ��̂����͂̑傫�����C�Â����Ăق��������A�ƌ����Ă���̂��낤�B����͓����ɉ���ł�����̂ł͂Ȃ��A�ނ��듹���ɑ����𐁂����ނ悤�ȉ��[���͂ł��낤�B
�@�v�z�Ɖԓc�̊S�́A�Љ��y�䂩��ϊv�����߂�悤�ȁA���̖��O�̍����I�ȗ͂Ɍ������Ă���B
�@
�Q�@���яG�Y�w����Ƃ��ӎ��x�i�L��j
�@�ԓc���P�u���c���j�ɂ��āv�ɂ́A�펞���́u�u�ߑ�̒����v�̕����v�̗�Ƃ��āA���яG�Y�u����Ƃ������v���������Ă���B���яG�Y�͏��a�\���N�A�w���w�E�x�\�����Ɍf�ڂ��ꂽ�u�ߑ�̒����v���k��ɏo�Ȃ��Ă͂��邪�A�u����Ƃ������v�͂��̂��߂ɏ��������͂ł͂Ȃ��B�������A�ԓc�����т̖����������̂́A�����炭�P�Ȃ�v���Ⴂ�ł͂Ȃ��B���N�Z���ɓ����w���w�E�x���ɔ��\���ꂽ�u����Ƃ������v��A�O�サ�ď\���N���Ɂw���w�E�x���Ɍf�ڂ��ꂽ�u�����v�A�u���ƕ���v�A�u�k�R���v�A�u���s�v�Ƃ��������т̌ÓT���w�_�́A������̋�C���z�����ԓc�ɂ́u�ߑ�̒����v�_�̈�ތ^�Ƃ��ĎƂ߂�ꂽ�̂��낤�B����A����ǂ��납�ԓc�́u�푈���A���яG�Y�́w����Ƃ��ӎ��x�Ȃǂɂ���đ�\�����u�ߑ�̒����v�̕����v�Ƃ܂Ō����Ă���킯������A�ԓc�ɂƂ��ď��т́u����Ƃ������v�́u�ߑ�̒����v�_�̒P�Ȃ��ތ^�ɂƂǂ܂炸�A�ނ����\��ƌ��Ȃ���Ă���B
�@���̂悤�ȉԓc�́u�ߑ�̒����v�ς́A���s�w�h�̓N�w�҂����𒆐S�Ɂu�ߑ�̒����v�_���Ƃ炦��c�_�A�Ⴆ�A�A���w�q�ߑ�̒����r�_�x�i�u�k�Њw�p���Ɂj�Ƃ͈ꌩ����Ƒ傫���قȂ�B�L���́A�w���w�E�x���k��ł̏��т當�w�҂����̔������u���|���k��v�A�u���_�I�J�I�X�v�Ǝ茵�����]���Ă���B���ɏ��тɂ��Ắu�e�I���[�Ƃ��Ă͂����ɂ�����`�v�A�u���_�ȑO�I�v�Ɨe�͂��Ȃ��B�������A����͍L�����g�̕����u�ߑ�̒����v�Ƃ����ۑ�ɏ��т̔������Ȃ���^���Ȃ�����ł����āA���т̔������̂ɂ��Ă̍L���̕��͓I�v��͓I�m���B�ԓc�����тɁu��\�����u�ߑ�̒����v�̕����v���Ă͐�Ɉ��p�����ȏ�̂��Ƃ��q�ׂĂ��Ȃ��̂ŁA�֖@�Ƃ��čL���ɂ�镪�͓I�v������p���邱�ƂŁA���ю��g�́A�I������ǂ����e�̔������͂������ʂ���Ԃ��Ȃ����Ƃɂ��悤�B
�@�L���͏��т̔����A�u�ÓT�ɒʂ���r�͋ߑ㐫�̊U�ƐM���鏈�܂ŕ����đ��l�Ɏv�Ӂv�A�u�ق��ɑn���I����Ƃ��ӂ��̂͐V�������̂͗v���v�A�u���j����ɕω��ƍl�ֈ��͐i���Ƃ��ӂ₤�Ȃ��Ƃ��l�ւĊςĂ��͔̂��ɊԈ�Ђł͂Ȃ����c�B�������������̂Ƃ��ӂ��̂��т����l���܂�i���Ȃ̂ł��v�ȂǂƂ����������������Ď��̂悤�ɕ]����B
�@���������L���̕��͓I�v��́A�u����Ƃ������v�́u���߂����₵�ē����Ȃ����̂������������v�Ƃ������t�ɑ�\����鏬�т̗��j�ρA�`���ρA����ςɈ�v����悤�Ɏv����B�L���͏��т̔��������_�I�łȂ����Ƃ������āA�����ɒl���Ȃ��悤�Ȍ��Ԃ�ŕ]���A���ہA���т當�w�҂̌����̕��͂ɂ͑����̎������������ƂȂ��A�����ς狞�s�w�h�́u���E�j�̓N�w�v�̌����ɐ��͂𒍂��ł���̂����A�������A�����炱���A�L���Ƃ͈قȂ�S�Łu�ߑ�̒����v�Ƃ����e�[�}���Ƃ肠���悤�Ƃ���ꍇ�ɂ́A���т̔�]���w�Ɏv������̂Ȃ��L���́A��O�ғI�ȁA�Ώۂ�˂����������_����̕]�����Q�l�ɂȂ邾�낤�B
�@���j�͓����Ȃ��Ƃ����̂́A�j���Ƃ����Ӗ��ł���A����͓��R�̂��Ƃ��B�j�������т��ѕς��悤�ł́A���݂����藧���Ȃ��B�ς��Ƃ�����A���j�̈Ӗ��̕��ł���B���j�̈Ӗ��́A���݂���l�Ԃ̉��߂ɂ���ĕς�肤��B���т͂�������₵���B���j�����߂����₵���̂ł͂Ȃ��A���т����₵���̂ł���B���̓_�ŁA�u�i���̍��Ƃł������ׂ�������̂ւ̊o���Ɖ�S�����̊j�S���Ȃ��Ă���v�Ƃ����L���̕]�͌������Ė��ł���B���́u�i���̍��Ƃł������ׂ�������́v�Ƃ͉����B�L���́u���[���b�p�l���_�I�Ȑ�Ύ҂��Ĕ�������}���ɉ�����ŗ�������Ă͂Ȃ�Ȃ��ł��낤���A�܂��A�����I�Ȍ���ƌĂԂ��Ƃ��K�ł͂���܂��v�Ƃ����B
�@���т��u����Ƃ������v�������A�u�ߑ�̒����v���k��ɏo�Ȃ������a�\���N�́A�O�N�\�̓��ĊJ��A�^��p��P�U���̐����Ƃ������j�I�u�Ԃ̗]�C�ɂ܂��Z���Ă���ꂽ�����A���������m�푈�̏���̏����ɑ���{�鍑�����������Ă����N���B
�@���a�\���N�ꌎ�Ɂw���|�t�H�x�ɔ��\���ꂽ�u�O�̕����v�Ƒ肷�鏬�т̕��͂́A���ĊJ��̕�ɐڂ����C���������������̂ł���B����܂ŁA���a�\�Z�N�l��������Č��̍s�����₫�������Ȃ��猩����Ă������A�u��̖{���̂Ƃ���ǂ�Ȋ|������������Ă�����̂Ȃ̂��A�l���ɂ͂悭����Ȃ��v���̂�����u�l���}�v�́A��ɗl�X�ȋ�z�ŁA�k�ɔ��Ă���v�A�u���ׂ̈ɖl���̋������Ԃ͔���Ȃ��̂��낤�v�ƁA���N�ȏ���u�֔�NJ��ҁv�̂悤�ȋC�����ł����킯�����A�u���ꂪ�u�퓬��Ԃɓ����v�̂������ꌾ�ŁA�_�U���������v�Ƃ����B
�@���̕��͂́A���т́u�i���̍��Ƃł������ׂ�������̂ւ̊o���Ɖ�S�v�i�L���j�̐��i���悭�����Ă���B���j�ւ̉���̒f�O�ł���B������P�Ȃ���O�ł͂Ȃ��B�J��Ƃ����l�ׂɑ�����O�ł��邩��A�D�ނƍD�܂���Ƃɂ�����炸���������j�Ɋ֗^���Ă��邱�Ƃ̖Y���ł���B
�@���̂悤�ɍl���Ă݂�ƁA�ԓc���P�̌����u���яG�Y�́w����Ƃ��ӎ��x�Ȃǂɂ���đ�\�����u�ߑ�̒����v�̕����v���ǂ��������̂��A�푈���́A�u�ߑ�̒����v�̕������A�ǂ̂悤�ȈӖ��ŏ��яG�Y�́w����Ƃ��ӎ��x�Ȃǂ���\���Ă��邩���킩���Ă���B���т͐l�Ԃ����j�I���݂ł��邱�Ƃ�֔邪���������悤�ɃX�b�L���ƖY�ꂽ�B�������āA����₩�ȋC�����Ō��͂ɕ��]�����̂ł���B
�@���āA�ԓc�̌����u�ߑ�̒����v�A�u�O�ߑ�I�Ȃ��̂�ے�I�}��ɂ��āA�ߑ�I�Ȃ��̂������悤�Ƃ���i���I�ԓx�v�����Ȃ��Ƃ��ǂ̂悤�Ȃ��̂ł͂��肦�Ȃ������m�F�����Ƃ���ŁA���яG�Y�ւ̌��y���ԓc���g�̕����ɒu���������B
�@���i���w������������l�X�x�́A�������疾���ɂ����Ċ����̓����ƕ��y�ɐs�͂����{�؏����Ƃ����l�������ɓ��{�̊��ň���̗��j��`���������ł���B���̍�i�ɂ���ē��i�́u���{����j���t�����Ƃ肠�����A�����ǂ���A�����炵�����������̑n���̂��߂ɕ��������̂��v�B�u���������ƂƂ��ɁA�ߑオ�͂��܂�v�i�ԓc�j�B���i�̏����̑薼�Ɍf����ꂽ�u���v�Ƃ͋ߑ�[�ւ̌��̂��Ƃł��낤�B��������͉ԓc�͐�O�풆�̃v�����^���A��Ƃ́u�ߑ�������悤�Ƃ���悤�ȃ|�[�Y�v�́A�u�|�[�Y�ȊO�̂Ȃɂ��̂ł��Ȃ��A�����̎���́A�啔���A�ߑゾ���ɂ������Ă����v�B�܂�A�ނ�͎�����A�ߑ��`�҂ł���������ǂ��A���тɑ�\�����^�C�v�́u�ߑ�̒����v�ւ̒�R�Ƃ��Ă͈Ӗ����������ƕ]���Ă���B
�@����ɔ�ׂ�Ȃ�A���̋ߑ��`�A�ԓc���g�����l�ł������w�ߑ㕶�w�x�h�̕��w�҂��������ɂ������ƂƂ����u�P���ȕ��������v�ł����āA��O�풆�̃v�����^���A��Ƃ����́u����Ȏd���v�̑��ΓI�i�����ɑ��āA���ΓI�ɕێ�I�ł���Ɖԓc�͒f����B�{�e�ł́A��O�풆�̃v�����^���A���w�ɂ��āA�܂��A���́w�ߑ㕶�w�x�h�̍�Ƃ����̊����ɂ��Ẳԓc�̔�]���������Ă��邩�ǂ�������������]�T�͂Ȃ��B��������A�ԓc�̔�]�̍\���ɒ��ڂ������B
�@�ԓc�́A�v�����^���A��Ƃɂ��Ă��A���́w�ߑ㕶�w�x�h�ɂ��Ă��A���j�I�̂Ȃ��ő��ΓI�ɕ]�����Ă���B�u�ߑ㐫�̊U�ƐM���鏈�܂Łv���B�����Ə��т������ꂽ�����ɁA�u�ߑ���܂��邽�߂Ɂv�[�ւ̕����I��b�ł��銈�ň���̐��҂�`�������i�̋ߑ��`�ɂ͑��ΓI�i������F�߂�B���̉ԓc�̃X�^���X�́A�u��ヌ�W�[������̒E�p�v�ȂǂƂ����C�J�T�}�́u�ߑ�̒����v���̂����Ă��錻��ł��L���Ȏ��_���낤�B
�@�������������Ƃ���ƁA����̎��������A���Ẵv�����^���A��Ƃ�낵���A�ߑ�̗��O�̗̏g�ɐ�O���������悢�̂��낤���B�����ŋߑ�Ƃ������̂̓��e������Ă���B�Ⴆ�ΎY�Ƃ̍������E�������Ƃ����Ӗ��ł̋ߑ㉻�ł���A���ꂱ���u�ߑ㐫�̊U�ƐM���鏈�܂Łv�B�����悤�Ɋ�������B�����\�����Ƃ����l�����邾�낤�B���������ɐ����i�߂悤�Ƃ��Ă���̂��������ߑ��`����l�I���x�����Y���ł���B����ŁA�Љ�̖��剻�Ƃ����Ӗ��ł̋ߑ㉻�͒B���Ƃ����ɂ͒������B�����v�ɂ���Ă߂����ꂽ���̂̂��܂��B������Ă��Ȃ��ߑ㉻���������̂́A�C�J�T�}�́u�ߑ�̒����v�ł���B���̂����͂����͐�O�̓��{�ł����łɈӎ�����Ă����B������ȗ��̘a���m�˘H���ŕЂÂ��悤�Ƃ����̂��풆�́u�ߑ�̒����v�ł��邪�A����́u��ヌ�W�[������̒E�p�v�͂��̗R�s�[�ȉ��Ȃ̂�����n���Ɉ����B���̂����͂��Ȏ���ɂ����āA�ԓc�̒���u�O�ߑ�I�Ȃ��̂�ے�I�}��ɂ��āA�ߑ�I�Ȃ��̂������悤�Ƃ���v�ߑ�̒���������ɂ����ĎƂ߂�Ƃǂ��Ȃ邩���{�e�̉ۑ�ł���B
�@
�@
�R�@�ĂсA�u���c���j�ɂ��āv�i���c�j
�@�����ōĂсA�u���c���j�ɂ��āv�ɗ������ǂ��čl�������̂����A���̑O�ɂЂƂ����Ă����������Ƃ�����B����́A���̂悤�Ȃ��Ƃ��B
�@�ŏ����́w�������̐��_�x�ȗ��A�˂ɉԓc�������I�ł���d�v�ƍl����̂́A�W�Ƃ��W�c�Ƃ��������̂ł����āA���ʂ́A��������h�����ė�����̂ɂ����Ȃ��Ƃ����B�������A���̏ꍇ�̊W��W�c�Ƃ����̂́A���炩�̊��������ɍs���Ƃ��ɂ̂ݑ��݂���Ƃ����Ă��悢���̂ł���A�ނ���d�v�Ȃ̂́A���̋����I�Ȋ����̕��Ȃ̂��B
�@�����͑厖�Ș_�_�Ȃ̂ŁA�u���c���j�ɂ��āv���痣��邱�ƂɂȂ邪�A���Ƃ��ē����w�ߑ�̒����x�Ɏ��߂�ꂽ�u�������̏ؐl�v�Ƃ����G�b�Z�C�̒�����A�Z���f�Ђ����p���ĖT�Ƃ��Ă������B
�@���̈Ӗ��ʼnԓc�̎v�z�́A�l�̓��ʂ���b�I�ȃG�������g�ƌ��Ȃ��ߑ��`�Ƃ��A���K��x�̗͂ɂ���Ď�������W��W�c�����̂ƌ��Ȃ������̎�`�Ƃ��A��������̂ł���B
�@���������ƁA���̂��鎞���܂ł̉ԓc�̋c�_�ɂ́A�����̓��{�̑����̍����v�z�Ƃ����Ɠ������A�T���g���̋����e�����������A�W�c�ƌl�Ƃ̊W�ɂ��Ă͓��ɂ����v���̂����A�Ƃ͂������������l�����́A���Ƃ��Ǝv�z�Ɖԓc���P�̍���ɂ���l�ԊρE�Љ�ς��甭���Ă�����̂ł�����̂��낤�B
�@���āA��ɂ������G�ꂽ�A�_���̋����g���^���ɂ��Ă̖��c�̑ԓx��]������ԓc�̕��͂́A�ŋߕ��J�s�l�����́w�V���_�x�i���t�V���j�̂Ȃ��ŏڂ������グ�����̂����A�����ōĂђ��ڂ��Ă݂����B
�@����_�����̓`���I�Ȍݏ��g�D���A�g���^���ɂ��_���̕ϊv�̒��Ő������Ă������Ƃ������c�̒Ɋւ��āA�ԓc�͎��̂悤�ɏq�ׂĂ���B
�܂��A���c�j�w�Ɩ��c�����w�Ƃ̊֘A�ɂ��āA
�@�������炤�������邱�Ƃ́A�ԓc�́A���c�̊w����A�_���ɐV�����W���A�����炭�͐^�ɑΓ��ȁi�͓I�ȁj�W���̏���������邽�߂̎v�z�Ƃ��Č��Ă���A�Ƃ������Ƃł���B���J�s�l���������Ă����悤�ɁA�ԓc�́u�o���ϖ��v�̎v�z�ƂƂ��Ă̖��c�ɃX�|�b�g�Ă��킯�����A�����A���ꂪ���ɔ_�������̋����I�Ȑ������H�̂�����̖��Ƃ��đ������Ă����_�ɁA�����ł͒��ӂ������̂ł���B
�@���̋����I�Ȏ��H�Ƃ́A���c�̌��t�����A�w���Ō݂��ɏ��������Đh�����Đ����Ă��������x�Ƃ����悤�Ȃ��̂ł���B���́u�����v�����悤�Ƃ��Ȃ��ߑ��`�I�E�[�֎�`�I�ԓx�ɕ�����c�ɁA�ԓc�͋�����������B
�@�����ԓc�ɂƂ��ẮA���̋�������W���̊�ڂ́A�����܂ł��ꂪ�n�����ҁA�������Ă���ғ��m�́A�͓I�E��ˑ��I�Ȏ��H�ł���Ƃ����Ƃ���ɂ������̂ł͂Ȃ����Ǝv���B�܂�A����͊O���̌��͂�A���̓]���Ƃ��Ă̋����̓����̌��͓I�\���Ƃ��������̂��玩�R�ȁA���̈Ӗ��Ŏ��������A���O�̘A�т�W�����w��������̂������B
�@���̂悤�ȊW���̏�́A�_�����͂��߂Ƃ�����{�̏]���̎Љ�̒��ɂ��A�����ɂ͂قƂ�Ǒ��݂��Ȃ������ƍl�����邵�A�܂����m�Љ��ߑ㉻���ꂽ�s�s�̎Љ�ɂ��A���l�Ɍ��o������̂ł���B
�@�ԓc�́A���̍���ȊW���̏��n�o���関�\�L�̉\�����A�u�y��v��ێ����ϗe�����邱�Ƃɓq�����̂��B���ꂪ�܂�A�ԓc�̖ڎw��������Ƃ������̂́A���������ċߑ�̒����Ƃ������̂́A�������Ǝv���B
�@�����āA���́u���ߑ�I�v�Ɖԓc���ĂԁA�Γ��ȊW���̏�������H�����Ƃ����_�ɂ����āA�����炭�ԓc�͖��c�̎v�z�Ƃ́A���{�I�ɑ��e��Ȃ��ʂ��������͂��ł���B
�@���c���������ɁA�u�o���ϖ��v�̎u�����l�ł���A���̊ϓ_����A���{�̑O�ߑ�ƌ��Ȃ������́A���Ƃ��Δ_�������̌ݏ��g�D��A���邢�͌��������Ƃ��������̂�i�삵�āA����炪�y�����ꂽ��Y�ꂳ���悤�Ƃ��邱�Ƃɕ������B
�@�����A���c���O�ߑ��i�삵���̂́A�����ɁA�j��Ɠ����ɉ���������炷�͂ł�����[�ւ̉^�������₷�鍪�������o����Ǝv��ꂽ����ł͂Ȃ����H�@�ނ́A�y������閯�O�i�햯�j�̂��߂ɓ{�����̂ł͂Ȃ��A�햯�̑��݂ɂ���ĕۏ����A�ގ��g�̐��E�ς��ʑ�����邱�Ƃɓ{��̐����グ���̂��B���c�́A�S����햯���������ł��낤���A���̐l�X�̎��R��^�ɔF�߂邱�Ƃ��o�������ǂ����͋^��ł���B
�@�ł́A�ԓc�̗���͂ǂ̂悤�Ȃ��̂��H�@���̂��Ƃ��A�����w�ߑ�̒����x�i �w�ԓc���P����W �W�x�j�̒��Ɏ��߂��Ă���A�u���q����̌|�p�v�Ƃ����G�b�Z�C���肪����ɂ��čl���Ă݂����B
�@
�S�@�ԓc���P�u���q����̌|�p�v�i���c�j
�u���q����̌|�p�v�́A���ܓǂނƁA�u���c���j�ɂ��āv�ȏ�ɖ��܂݂̘_�l�Ȃ̂����A����ł��A�v�z�Ɖԓc�̊�{�I�����m�邤���ŁA�����ւ�d�v�Ȃ��Ƃ�������Ă���Ǝv���̂ŁA�����ďЉ��̂ł���B
�@�����ł́A�ԓc�͊ۖE�ԏ��i�ۖؕv�ȁj�́u�����̐}�v��A����O�V�A��c�m�q��̌����̌���`�����������ɂ����āA���{�̌|�p�Ƃ������`���u���q����v�i�j�̎���j�̃C���[�W���A�O�ߑ�I�ȕ\�ۂ���E���Ă��炸�i�u�����̐}�v�ɂ��ẮA��Ў҂����̎p�������̕`���H��̂悤�ɕ`����Ă���A�Ɣᔻ����j�A�����̓��ʐ��E�����������߂悤�Ƃ���ӎu�Ɍ����Ă��邱�Ƃ�ᔻ����B
�@����ɁA����O�����I�ȗ�Ƃ��āA�ԓc�͉f��w�S�W���x���Ƃ肠���A�����ɂ́w�����␅���̒��ڂ̔�Q�҂̎��f�A�����A���ρA�������炤�܂��}��I�ȋC�����A�͂�����ɂ��݂łĂ���x�i����@��247�j�Ə����A������u�A�j�~�Y���╧���I���ρv�Ɏx�z���ꂽ�u���{�I�j�q���Y���v�ƌĂ�ł���B
�@����́A�����𓊉������A�����J��SF�f�悪�A���Q���̗D�z����A�j�Z�p�ƉȊw�̔��W�ɑ����Ȃ��̃I�v�e�B�~�Y������点�Ă���̂ɔ�ׂ�A�܂����������ł��邵�A���d�����ׂ����̂ł͂��邪�A�����Ă��̂܂܂̌`�ŕ��u���Ă����Ă悢�悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��B���́u���{�I�j�q���Y���v���������邱�Ƃ����A�ԓc�̉ۑ�Ƃ����킯�����A���̕��@�Ƃ��Ĕނ��q�ׂ�̂́A���̃j�q���Y���̒P�Ȃ�ے�ł͂Ȃ��A�ނ���u�A�j�~�Y���╧���I���ςƐ≏�����j�q���Y���v�̊l���Ƃ������ƂȂ̂ł���B
�@�ނ͂����ŁA�u����������ꂸ�ɂ����Ȃ�v�ƑO�u�����āA������������ɔ픚�n�Ŏ��Â��s�킸�ɕ��쐬�̂��߂̒������s�����A�A�����J�̏o��@��A�EB�EC�EC�i���q���e��Q�����ψ���j�̖v���l�I�ȑԓx�̂Ȃ��ɁA�w�Ԃׂ����̂�����Əq�ׂ�B
�@�ԓc�̏ꍇ�A�ł���b�I�ȃG�������g�Ƃ����̂́A�����I�Ȋ����ł����āA�l�̓��ʂƂ������̂̕R�т�S��Ƃ��������̂́A���̊����̕��Y���Ƃ��ď��߂Đ�����ƍl�����Ă��邱�Ƃ́A���ɏ������B
�@�����ł́A�u���a�^���v���A�����������O�̋����I�����̋�̗�ł���A�����ւ́u�ϋɓI�Q���A���̂Ȃ��Ōo�����邳�܂��܂ȍ���A��]�v��ʂ��āA�l�X�̎Љ�I�ȐS�����ώ����Ă������Ƃ����҂���Ă���B���Ȃ킿�A�u�A�j�~�Y���╧���I���ρv�ɗނ���A����Β��߂̃j�q���Y���A�ꑮ�̎v�z�Ƃ��������̂���A�������́u�Њd�v�ɋ����Ȃ��u�؋�����́v��R�̃j�q���Y���ւ́A����Γ��{�̖��O�̐S���I�u�y��v���Ȃ��Ă���l������j�q���Y�����̂��̂̕ϗe�ł���B
�@�����ł͓��ɁA�j����ɂ��S�Ђ��A�{���I�ɂ͐������͂́u�Њd�v�Ƃ��đ������Ă��邱�Ƃɒ��ӂ������B���Ƃ��A���������ɂ���Ўҁi�픚�ҁj�����̎p���u�H��v�̎p�ŕ`���Ă��܂��u�����̐}�v�������Ă���̂́A�u�Њd�v�ɒ��ʂ��Č��͂̎v���܂܂ɁA�O�ߑ�I�ȏ�ɕ�������A��R����߂Ă��܂��l�X�̂���l�ł���B
�@���_�A��Ђ�픘�Ƃ����̌����A�������͂̎��������ő���������̂łȂ����Ƃ͊m���ł��낤���A�ԓc�������Ŗ��ɂ��Ă���̂́A���C���Ƃ��������ʓI�ȉ�H��ʂ��āA�l�X�����͂̎v���ǂ���ɑ����Ă��܂����J�j�Y���Ȃ̂��B����́A�f��w�S�W���x�̉�ʂɂɂ��ݏo�Ă���u�����␅���̒��ڂ̔�Q�҂̎��f�A�����A���ρA�������炤�܂��}��I�ȋC���v�Ɠ��l�̂��̂ł���B
�@���������A���グ��ꂽ���ʂ̉�H���A�������͂́u�Њd�v�ɂ��x�z�E����ɑ��āA�l�X�͂ɂ��Ă���B���̉�H���A�ԓc�́u���{�l�̃j�q���Y���v�ƌĂ�ł���킯�ŁA���������̐S�����A�ʏ�̌[�֎�`�҂̂悤�ɊO����ے肵�Ă��܂���̂ł͂Ȃ��A�ނ��낻����u�y��v�Ƒ����������ŁA���̕ϗe�Ƃ����d���Łi�ߑ�I�I�v�e�B�~�Y���Ɠ��{�I�j�q���Y������̓�d�́j�u����v���������悤�Ƃ���Ƃ���ɉԓc�̐^����������B
�@����́A���̃j�q���Y�����A����Ύ莝���̕���Ƃ��āA�x�z���͂ɍ���������Ƃ������Ƃ����A�����Ȃ邽�߂ɕK�v�Ȃ̂́A��̓I�ȋ����s���́A���Ȃ킿�^���̎��H�ł���A���̒��ł͂��߂āA�l�X�͎x�z���͂́u�Њd�v�ɍ��E����Ȃ��A��R�̐��_�I��ՂƂ��������̂���ɂ��邱�Ƃ��o���邾�낤�B
�@�Ƃ���ŁA�ԓc�������łƂ���A�EB�EC�EC�̗�������o���Ă���̂́A���グ��ꂽ�u�����v��ʂ��Đl�X�𑀍삵�A�x�z���ѓO���悤�Ƃ���u�Њd�v�I�Ȑ������͂ɑ��āA�����܂Łu�m���v��Ƃ��ē������Ƃ��A���O�ɂ́A�����ƒ��B�ɂ����A�u�E�����ҁv�̑��ɂ̗͊v���Ƃ������Ƃ��A�������������߂ł��낤�B
�@���q���[�}�j�Y���Ƃ������A����Ύ�ϓI�Ȃ��́A�����I�Ȃ��̂́A���������ɂ��Ďx�z���͂̊i�D�̓���ƂȂ�B���̌X���́A������l�b�T���X�̎Љ�����A�ނ��냁�f�B�A�ƃl�b�g�������������鍡���̎Љ�ɂ����Đr�������Ƃ�����B�Ƃ�킯�A�e���r��l�b�g��Ԃł́A��ʂɗ��ʂ��鐔����摜������Ȍ��ʂ����A�����ł͊������ς����Ă��܂��Ƃ��������A���{�I�ɕʌ̃��A���e�B�����������A�����̕����ɍ��グ��ꍪ�����낵�Ă��܂��ƌ����Ă悢�قǂ��B���݂̎Љ�ł́A���̂悤�ɂ��č��グ��ꂽ�l�H�I�Ȋ����̗̈��ʂ��āA�������͂��l�X���x�z������d�g�݂���������蒅������̂����A�ԓc�������\�����A�Ό����悤�Ƃ��Ă������̂́A���̃��f�B�A�Љ�̐V���Ȑ����I�l���������̂ł͂Ȃ����Ƃ����C������B
�@������f�B�A�Ƃ������ƂɊւ��Ĉꌾ����ƁA�e���r�̕��y�Ȃǂ̃��f�B�A�ɑ���ԓc�̌����Ƃ����̂́A�����ĒP���Ȏ����o������^�ł͂Ȃ��A��ł����O�̎�̐����d�����A�O�ߑ�̕����ɂ����Ă͎������Ă����Ǝv����u����ʁv���������ꂽ�A�V���ȕ����I�E���O�I�ȕ\����i���\�z���Ă������Ƃ���Ƃ���ɁA���̎�Ⴊ�������Ǝv����B����́A�e���r�Ƃ����u�����ʁv�̃��f�B�A�ɂ��A�����I�E�l�H�I�Ȋ����̐A���t���ɑ����R�Ƃ������i�����������̂ł����āA�o�ϐ������o�č��x����Љ�ւƐi�މߒ��ɂ����ĂЂ������O�̎I�Ȋ������m�肵�������A�_�G�̋g�{�����Ƃ́A���̓_�ł��������Δ���Ȃ��Ă���Ƃ����邾�낤�B
�@���́u�����̘_���v�ɑ��A�����炭�A���̕��͂ł̉ԓc�̎咣�́A���̋��͂��I���Ȏx�z�ɑ��āA�j�����ŎE����A�Њd�����ҁA���邢�͂܂��A�����̘_���̉��Ɍ��̂Ă��Ď���ł������ƂR�Ƃ����悤�Ȏ҂����́A�\�͂ɂ��A���d�Ƃ������́A�G�ɑ����I�ł���Ƃ����Ӗ��ō��{�I�ɔ��͂ȑR�̓���I�Ԃ̂łȂ���A�m���Ƃ��������Ȃ��莝���̓����L���ɗp���邱�Ƃ��l����ׂ����A�Ƃ������Ƃł���B
�@�m���̎g�p�Ƃ́A�����Ƃ������͑��ɗL���ȉ�H�ɑ���A�ő���̐T�d�������̂��B�����́A���������������̂��̂Ƃ��Ď��ʂ������̂ł���Ȃ�����A���͂̎v���̂܂܂Ɋ����I�ɂȂ邱�ƂɁA�o�������p�S�[���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�@�������������A���̕���Ƃ��Ắu�m���v�Ƃ������̂́A�u�O����̌[�ցv�̂悤�Ȃ��̂ł����Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ���Ȃ�A�ǂ̂悤�Ȃ���������Ă���̂��낤���B
�@��̈��p���̂�����ŁA�ԓc�́A���a�^���ɐ�S����q���[�}�j�X�g�����Ɏ��̂悤�ɒ��������Ă���B
�u���̂�̓������E�ɁA�����߂Ȏ������������v�Ƃ́A���Ȃ̓��ʂɂ���A�x�z�ҁA���͎҂̎v�l�ɓ��������������u�j�q���Y���v�́A�܂�ꑮ����҂̐S������Ă�A�Ƃ������Ƃł��낤�B
�@����A���������S����ێ����邽�߂̐����I���u�Ƃ��Ắu���ʁv���̂��̂����ċ���A�E�����ҁA���Ƃ⌠�͂ɐ�̂Ă��A���邢�͎g���̂Ă���҂Ƃ��ẮA�����̂ɂ��ꑮ���Ȃ��S����A��R�̊����̂Ȃ��ŁA���҂����Ƌ��ɏ�������Ă����Ƃ������Ƃ��A���̉ԓc�̌��t�͈Ӗ����Ă���̂ł��낤�B
�@�˂ɓ������鑤�̎����Ɉ�̉����A�ǂ����ɐ����I�j�q���Y�����߂Ă����Ǝv������c�̎v�z�ɑ��āA�ԓc�̊�{�I�ȗ���́A�Њd����A���삳��A�펞�ɂ����Ă������ɂ����Ă��u�E�����v���ɂ��閯�O�́A�͓I�Ŏ����I�ȊW�̏�����o�����Ƃ�������̂����ɂ������Ƃ�����B
�@�����A���̍ہA�ԓc����R�̕���Ƃ��đI�Ԃ̂́A���{�̖��O�́u�y��v�Ƃ��Ắu�j�q���Y���v�A��Ō����Ƃ���́u�q���[�}�j�X�g�����ɁA�h�ӂƓ����ɕ��̂̔O���������Ă��邱�Ƃ����߂��Ă���v�Ǝv����A�s�������́u��Áv�ȑԓx�ł���B���͂��ꂪ�A�ԓc�ɂƂ��Ắu�m���v�̌����Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂��B
�@����́A���j�̒��ŋs����ꑱ���Ă������O�̊፷���ł���A�v�z�ł���B����́u�����̐}�v�ɕ`���ꂽ��Ў҂̎p������Ɏ��Ă���Ƃ��������̕`���u�H��v�Ƃ́A����ΊK���I�ɈقȂ����A������́i���O�I�ȁj�O�ߑ�̎����ł���B���ꂱ�����A�ԓc�����ݓI�ȉ���i�[�ցj�̌_�@�Ƃ��Č��o�����A�m��I�ȁu�O�ߑ�v�̊j�S�������̂ł͂���܂����B���́A������̗H��̗�O�Ȋ፷���́A��̊m���ȕ���Ƃ��āA�}���I�Ȑ������͂̋�Ɖ������q���[�}�j�Y���⊴�������̂ł���B
�@�t������A�u���c���j�ɂ��āv�ł��A�̘b��H�m�i����̃��W�I�ԑg�Ɏ����ꂽ�O�ߑ�I�ȕ����̓������A�q���[�}�j�Y���̘_���Ƃ̉s���Η������������邱�Ƃ͈�ۓI�ł���B��̈��p���Ɍ����u�����I�ȉ��l���f�v�̔r���Ƃ����v���́A���̈Ӗ��ł́i���O�I�ȁj�O�ߑ�̘_���̓������A�������͂ւ̒�R��A�Љ�ϊv�̂��߂ɕK�{���Ƃ����l�����痈�Ă���̂��낤�B
�@�����������A���̎s���i��O�j���g���A���j�̒��Œ�R�̉^���Ƃ������H���痣��Ă��܂��Ȃ�A�u�H��v�͂͂����܂����̈З͂��Ȃ����ď������A�̂���Ƃ��������I�Ȋ����̖����l�X�����������݂���ł��܂��ł��낤�B�����āA���̂悤�ɉ���̌_�@���Ƃ�ꂽ�u�O�ߑ�v�́A�P�Ȃ镕���I�����̂��߂̓����ւƑ����A�l�X�̌��ɉ�A���Ă��Ďx�z����悤�ɂȂ邾�낤�B���̂Ƃ��A���ꂪ�����L���Ă������������́A���̒����̈ێ��̂��߂̓���ɕώ����A���̖\�͐��́A�x�z�w�̘_���ɍ��v����ꍇ�Ɍ����āA�����I���l���f�̌��O�ɒu����邱�ƂɂȂ邾�낤�B
�@����Ȍ�̓��{�Љ�́A�c�O�Ȃ���A���̕����Ɍ��������̂ł���B
�@
�T�@���L�i�L��j
�@�ԓc���P���u�ߑ�̒����v�Ƃ������t���Ӑ}�I�Ɏg���������̂́A������w�J����x�_������̂悤���B�[�Y�w�J����x�̕]�����߂����ĂȂ��ꂽ���̘_���́A���c���E�ԓc���P�E���쌪�̎O�҂ɂ��C�k�u�n�썇�]�w�J����x�v�i�w�Q���x1958�N�Z�����j�����A�M�ҁi�L��j�͍ŋ߂܂ł��̓��e��m��Ȃ������B�{�e�쐬��A�wKWADE���̎蒟�@�[�Y�x�i�͏o���[�V�Ёj�ɓ]�ڂ���Ă���̂��������̂ŁA�����Ɋ��z��NjL���Ă����B
�@���̓C�k�̓^�C�g���ʂ�A�[�Y�̏����w�J����x�̕]�����߂����Ď��c�E�ԓc�E���삪�c�_�����Ă���B�����ς�ԓc���w�J����x��ϋɓI�ɕ]�����A���삪����ɋ^�`��悷�邩�����Ői�s���Ă���̂����A�_���Ƃ����قǐؔ��������͋C�͊����Ƃ�Ȃ��B�u���ɂ��̍�i�ɂ͊��������v�Ƃ����ԓc���A�M���V�A�ߌ���j�[�`�F�̉i����A�܂Ŏ����o���āu���Ƀ��^�t�B�W�J���Ȃ��̂������܂����v�ƁA���������͂��Ⴌ�C���ɐ�^����̂ɑ��āA���삪�u�����Ԃ����ȉԓc����́v�u�ԓc���̐[�ǂ݂����Ă����v�Ƃ��炩���A�u�ԓc����͈�̐̂Ȃ��Ƃ��Ă����ǂ߂Ƃ�����ł���v�Ǝ��c�Ɍ���ꂽ�ԓc���u���b�̂����Ă����\���I�I�Ȑ��i�A������ӎ����ĂƂ炦�Ă���̂���Ȃ����Ƃ������Ƃł��v�ƌ������Ƃ����悤�ȗ���ɂȂ��Ă���B
�@�����āA�C�k�̖����ɂ́A����Ɖԓc�ɂ�鎟�̂悤�ȁu���L�v������������Ă���B
�@�����A�u�ߑ�̒����v�Ƃ́A�|���D���������߂Ă���悤�Ɂu�푈�ƃt�@�V�Y���̃C�f�I���M�C���\������̂Ƃ��āv�u���������v���t�������i�|���w�ߑ�̒����x�j�B������A���R�A����̕]�͉ԓc�̋c�_��ے�I�ɂƂ炦�����̂��B����ɑ��āA�ԓc�͊J�����������̂悤�Ɉ����������Č����Ă���B���茾�t�ɔ������t�Ƃ�������܂ł����A�ԓc�ɂ͑����̊o�傪�������͂����낤�B
�@�������A�w�ߑ�̒����x�����́u��̊G�v�ł́A���̂悤�ɕ���̖�������Q���Ă���B
�@���Ȃ݂ɉԓc�̑��Ɏ��_�Ƃ�1947�N���s�́w�����̘_���x�Ɏ��߂�ꂽ���̂ŁA�ԓc�ɂ��A���Ԃ��Ȃ��A�ق��Ȃ�ʕ��쌪�ɐ�������ď������ꂽ���̂��Ƃ����B����͂Ƃ������Ƃ��āA�ԓc�̋ߑ�̒������A����̘A�z�����悤�ȓ��{�Q���h�⏬�яG�Y�̂���Ƃ͈قȂ���̂ł��邱�Ƃ͂��łɌ����Ƃ��肾�B
�@�������A�ԓc���u�ߑ�̒����v�ɂ́A����̂��������뜜�Ƃ͈قȂ邪�A��͂肠���̊낤�����Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B���̑��͋ߑ������u�����Ɋւ��B
�@�����甼���I�ȏ���O�A�ԓc���P�͒P�s�{�w�ߑ�̒����x�i�����Ёj�́u���Ƃ����v�Łu�ߑ�̊m�����Ă��Ȃ��Ƃ���ŁA�ߑ�̒���������Ƃ͖������Ă���A�Ƃ������悤�ȌÂ��̂ɂ͂����������v�ƌ����������B�������A�u�Â��́v�͂��̌���̂�ꂽ���A���̂��тɁu�����������v�Ƃ��������J��Ԃ��ꂽ�B�����č��܂��u�Â��̂ɂ͂����������v�Ƃ����������܂��Ă��邪�A���̐��̎�͉ԓc���ے肵������u�ߑ�̒����v�̗R�s�[�ł���B�u�ߑ�̒����v�Ƃ́A���ꂾ�������̓���e�[�}���Ƃ�������B�����̃v���W�F�N�g�Ƃ��ĒB�����ׂ��悫�ߑ�ƁA�������ׂ��������ߑ�Ƃ����R�ƌ���������̂��B���̏�A���鎞�������Ƃ������z���̂��̂��A���������ߑ�I�Ȑ��i�����̂ł͂Ȃ����A�Ǝ��₵���������B�������A�����ŗ����~�܂��Ă��܂��ƈ������j�q���Y���A���߂̃j�q���Y���ɂ������邱�ƂɂȂ�B������A�����͂����Ď��݂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̎��݂�����̖����Ȃȍm���������邽�߂̉I��H�ɂȂ肤�邾�낤�Ɗ��҂��B
�@������̌��O�́A�ԓc���A���Ȃ��Ƃ��u���c���j�ɂ��āv�ł́A���c�̏햯�̖����w�Ɋ�肩�����Ă���悤�Ɍ�����Ƃ��낾�B����͉ԓc�̒��ڂ̊S�ł���[�Y�̏����w��R�ߍl�x�Ɓw�J����x�̓o��l���������_���ł��������߁A�_������ɍ\�z���ꂽ���c�̏햯�T�O�ɂ��܂����Ă͂܂������炾�낤�B
�@���c�����w�́u�햯�v�̑����ɂ��āA�{�c�o�͎��̂悤�Ɏw�E���Ă����B
�@�蒅�_�k�����햯�̕W���Ƃ���Ȃ�A�ߑ�ȑO�A���ɋߐ��̓��{�ł̃}�W�����e�B�ł��邱�Ƃ͊m���Ƃ͂����A���Ƃ��Ă������ď��Ȃ��Ȃ����܂��܂ȃ}�C�m���e�B��r�����邱�ƂɂȂ�B�������茾���A�E�l��|�l�A�^�A�E�ʐM�Ǝ҂����Ƃ������l�тƂ������ۂ蔲�������Ă��܂����A���������햯�Љ�ɂƂ��ă}�[�W�i���ȑ��݂Ƃ��Ĉʒu�Â����邩���낤�B�햯�Љ�̂Ȃ��ɂ����Ă��A����_��A���l�ƌĂꂽ�傫�Ȕ_�Ƃ̎g�p�l�����l�ƂȂ�B
�@�������́u�햯�v�����̊T�O�Ƃ��ċ��������ꍇ�̂��Ƃł����āA�������痣��čL����邱�Ƃ��ł���B�Ⴆ�Βߌ��a�q�́A�N���햯���́u���ΓI�ȓx���̂����v���Ƃ��āA���c���g�����グ���Ώۂ������Ă���B
�@���̂悤�ɁA�W���̎����A���}������鑤�A������������鑤�ɂ��炵�����Ă����Ȃ�A�Ȃ���ˉp�u���w�u�`���v�Ƃ͉����x���Ŏw�E�����R�l�r���̖��͎c��ɂ��Ă��A�햯�T�O�͈͍̔͂L���邾�낤�B
�@�������A�Ȃ��^��͎c��B�ԓc�̋c�_�̎O�ڂ̓�_�ł���B�u���c���j�ɂ��āv�͎��̕��Œ��߂������Ă���B
�@�����Ƃ��āA�w��R�ߍl�x�́u�킪���×��̖��Ԑ��b�ł���u�e���R�v�̂��̂܂܂̕����v�ł͂Ȃ��B���c���j�w���Ɗw���x�����́u�e���R�v�ɂ��A���q���V�e�i�����Ă��V��j���R�Ɏ̂Ăɍs�����b�́A���{�����Ɏl�n���`����Ă���A���̂�����͒����`���̎I�Ȃ��́A��ڂ͕��T�ɓT���̂�����̂ŁA���Ƃ̎O�ڂƎl�ڂ��u�킪���×��v�̂��̂��낤�Ƃ���Ă���B�����āA���Y�i�̂����l�ڂ����Â����̂Ɛ��肳��Ă��邪�A����͐[��w��R�ߍl�x�ƌ���I�ɈقȂ�_������B�u�F�s�Ƃ����l���v�̐���Ƃ������Ƃł͂Ȃ��B�P���Ɍ������Ⴄ�B
�@���q�͎R�Ɏ̂Ăɍs�����V���A��ċA��̂ł���B���̃^�C�v�̘b�����ł͂Ȃ��A���c�ɂ��Ύl��ނ̐e���R�́A���͂ǂ���n�b�s�[�G���h�ŏI���B������A���̝|�ɏ]���ĘV����R�ɒu������ɂ��ċA��A�Ⴊ�~�����̂ŕ�͋Q�����Ɂi�����āj���ʂ��낤�A���ꂪ���߂Ă��̍K���ł������Ƃ����ӂ��ɏI���w��R�ߍl�x�́A�ߑ�q���[�}�j�Y���ւ̃A���`�e�[�[�Ƃ��Đ[�ł��o�����A���ꎩ�̂�����ċߑ�I�ȃX�g�[���[���ƂƂ炦������������B������u�킪���×��̖��Ԑ��b�ł���u�e���R�v�̂��̂܂܂̕����v�Ƃ���Ȃ�A���̉��߂́A�܂������u�ԓc���̐[�ǂ݁v�ł����āA���ӓI�Ƃ̂������Ƃ�܂��B�Ƃ͂����A�ԓc�̐^�ӂ�u�x����u�n�썇�]�w�J����x�v�ł̔����ɂ�����悤�ɁA�O�ߑ�̖��b�̌���I�ȂƂ炦�Ԃ��Ƃ������Ƃ��������������̂��낤�B
�@���Ƃ��Ɖԓc�́u�ߑ�̒����v�\�z�́A�Ȃɂ��[�Y�̏����̕]���Ɍ��肳��ď�����ꂽ���̂ł͂Ȃ��B�ԓc�́A�u�J����v�_���ȑO����A�u�ߑ�̒����v���k��̂��Ƃł͂Ȃ��ߑ�̐���̏�肱���Ƃ��Ă̋ߑ�̒������Ӑ}���Ă����B���Ƃ���1957�N�Ɋ��s���ꂽ�w�����������ɐ����邩�x�����́u�D�v�v�ł́A�����̐_�b��`�����ނɂ��āw�̎��V�ҁx���������D�v�ɂ��āA�u�O�ߑ�I�Ȃ��̂�ے�I�}��ɂ��āA�ߑ�I�Ȃ��̂�����@�ɂ��Ă����������炵���̂��v�Ƃ��Ă���B
�@���́u�D�v�v�ɂ�����ԓc�̋c�_�́A�R���̔_���̐������E��ɂ����[�Y�̏������ӎ����ď����ꂽ�u���c���j�ɂ��āv�Ƃ́A������قɂ��Ă���B�`���Ƃ̒f��A�i�V���i���Ȃ��̂��C���^�[�i�V���i���Ȋϓ_���猩�����Ƃ������Ƃ́A�K�����������Ř_���Ă���Ώۂ��D�v�́w�̎��V�ҁx������ł͂Ȃ��A�Ⴆ�A�{�e�S���ӂ�Ă���u���q����̌|�p�v�ł́A�߉���k�́u�l�J���k�v���s�J�\���A�t���J�̌|�p�ɑ����悤�Ɍ���Ȃ�]�X�Ƃ���B�u�O�ߑ�I�Ȃ��̂�ے�I�}��ɂ��āA�ߑ�I�Ȃ��̂������悤�Ƃ���v�\�z�́A�ԓc�̏����₵���e�N�X�g�̗��j��̐���ɂ�����炸�A�ނ���A�������̎���̐���̂Ȃ��ł��̗L���������炽�߂Č������ׂ��ł��낤�B
���v���t�B�[����
���c�L���i�������E���肨�j
1962�N���܂�B�j���A�Ɛg�A�e�Ɠ����B�v���t�B�[���ɏ����悤�Ȃ��Ƃ��Ȃ����݂Ɏ���B�u���O�FArisan�̃m�[�g
�L����M�i�Ђ낳���E�Ƃ��̂ԁj1963�N�A��������B�ҏW�ҁE���C�^�[�B�����Ɂw���^�l�J���k�@������w�l�b�J�G�k�W�x�x�A�w�������k�f�B�e�N�V�����x�A�w���k�̉��ߊw�x�ȂǁB�u���O�u���ȉƂ̌����\�vWeb�]�_���u�R�[���v25���i2015.04.15�j
���O�ߑ���Ĕ��@���遄��P��F�ԓc���P�́u�ߑ�̒����v�ɂ��āi�L����M�^���c�L���j
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU�@2015 All Rights Reserved.
|
| �\���i�ڎ��j�� |