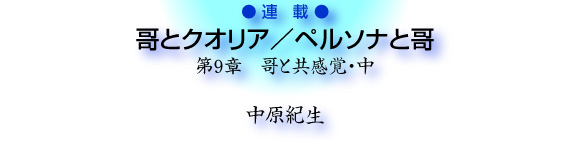|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「La Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
|
■壬生忠岑の和歌体十種
古歌体、神妙体、直体、余情体、写思体、高情体、器量体、比興体、華艶体、両方体。貫之没年の頃、壬生忠岑によって著されたとされる歌論書「和歌体十種」(偽作説あり)において提示されたこれらの歌体について、梅原猛氏は、「かなり精密な美的感情の分類であるばかりか、そこに一種の美的感情の発展運動さえみとめられるように思われる」と指摘しています。以下、同氏の「壬生忠岑「和歌体十種」について」(『美と宗教の発見』)の記述を適宜引きながら、順次、概観していきます。(神妙体は、梅原説にしたがって、器量体のあとにまわしている。また、各歌体の例歌はそれぞれ五首ずつ(欠落あり)挙げられているが、ここでは一首のみ掲げる。)
1.古歌(こか)体
小笠原へゐのみ牧にあるゝ馬(ま)もとればぞなづくこなが袖とれ
古歌体の名で忠岑は、静かな叙情を重んずる彼の美意識に照らして除外されるべき歌を集めた。例歌は多く万葉集からとられている。これらの歌の特徴は、対象の動きをもっていることであろう。あばれる馬、飛ぶ鶴、満ちる湖など。この対象の動きのはげしい感情が拒否される。
2.直(じき)体
秋来ぬと目にはさやかに見えねども風のおとにぞおどろかれぬる
過去から現在、現在から未来へと推移する人生の時。夏から秋、春から夏へとうつりゆく自然の時。こうした時間の推移にたいする率直な感慨を曲折なく歌いあげたもの。この直体において、感情はうつりゆく自然や人生への喜び悲しみとなる。
3.余情(よじょう)体
我が宿の花見がてらに来る人は散りなむ後ぞこひしかるべき
直体において表出された感情が、余情体では、得られない対象を思う感情に深まる。例歌は、満開の桜がやがて散っていく、その有から無への時間の推移を直接歌うのでなく、かつて花見がてらにたずねてきてくれた人、したがって桜が散った後では非在となる人へと愛着している主体の意識が歌われる。
余情の歌の感情の形は、次のようにまとめることができる。S(作者の主体)はG(歌われる対象的他者)を求める。しかしGは得られない。したがってSの意識は不在のGに向けられる。この不在のGへ執着する意識が、Gの不在を暗示するM(主体と対象を媒介する物、例歌では「(散った後の)桜」)によって象徴される。こうして、「詞は一片を標[あら]はし義は万端を籠む」ことが可能になる。「無」となった対象に、延々とまとわりつくような愛着の余韻嫋々たる悲哀感が、余情体の典型的な感情の形であろう。
4.写思(しゃし)体
思ひつゝぬればや人の見えつらむ夢と知りせばさめざらましを
余情体における悲しみの感情が、写思体では絶望の自己意識となる。余情の歌において非在の執着物Gへ向かったSの意識は、写思の歌では自己の中に帰還し、対象の不在から生じる悲しみの感情は、むしろ不在の対象に執着する絶望的自己意識の形をとる。
写思体は余情体と比べて無の意識が希薄なのである。余情体において、意識は対象へ向かうが、そこに無を見出す。写思体は、余情ある悲哀の音の上にもう一度強い執着の音をひびかせる。無に帰する有の音、そして無を背景とした絶望的な有の音、この微妙な感情の相違が余情体と写思体の感情のちがいである。「此の体は、志は胸に在りて顕はすこと難く、事は口に在りて言ふこと難く、自ら想ひ心に見て、歌を以て之を写[おも]ふ。言語道断は、玄の又玄なり。」
5.高情(こうじょう)体
冬ながら空より花の散り来るは雲のあなたは春にやあるらむ
写思体の絶望から一転して、高情体では、感情は遠い実在する光(G)にたいするあこがれとなる。例歌におけるSの周辺は冬、闇につつまれてはいるが、向こう側には春、光が実在している。光は雲の向こう側にあり、雪、花はこの光の世界と闇の世界の媒介者(M)となる。
高情体の歌の感情の形式は、対象に向かう意識である。(この点、自己に向かう意識である写思体とちがう。)同時にそれは、実在する対象に向かい、しかも対象は、既に現在その存在の兆候を表わしている。(この点、対象と自己の間が切れている余情体とちがう。)しかもこの光としての実在者は、現在その姿を全面的にあらわしているのではなく、遮断物を通じてちらほら見えている。(距離の美学、おおわれの美学。)したがって、高情体の感情の質は、悲哀感(余情体)や絶望感(写思体)ではなく、あこがれの感情、遠いものへのかすかな期待の感情であろう。高情は忠岑にとって最上の体である。「此の体、詞凡流と雖も、義幽玄に入り、諸歌の上科と為すなり。」
6.器量(きりょう)体
昨日こそ年はくれしか春霞かすがの山にはや立ちにけり
高情体で見出された光へのあこがれの感情が、器量体では、更に広々と眼前に広がる爽快の感情となる。実在者をおおいかくす遮断物がとりはらわれ、意識の前に現に実在している。例歌では、春霞がまさに今ここに広々と遠々と広がり、私に自己の存在をはっきりとあらわにしている。
7.神妙(しんみょう)体
我が君は千代にましませさゞれ石の巌となりて苔のむすまで
忠岑のいうように、この体は高情体や器量体とまぎらわしい。それらの体が多く自然の美を歌っているのにたいし、神妙体は神または天皇のことを歌っている。この永遠で神聖なる存在物は、深く隠されひそかにその姿をあらわす。その意味で、それは高情体にも器量体にも通じるのである。
8.比興(ひきょう)体
雪のうちに春は来にけり鶯のこほれる涙今やとくらむ
以下の三つの体では、器量体の爽快の感情が理性化され、あるいは推論し(比興体)、あるいは観察し(華艶体)、あるいは比較する(両方体)感情の希薄化された姿で終る。明らかに忠岑は、直体以下の六体よりはるかに軽く低い取り扱いをしている。比興体は、比喩の面白さ(例歌では、鶯の涙が凍るという想像力の面白さ)をねらう知的趣向の勝ったもの。
9.華艶(かえん)体
梅(むめ)が枝に来ゐる鶯春かけて鳴けどもいまだ雪は降りつゝ
艶麗な色彩美の歌。対象は色の世界に照りはえているが、作者の意識は専らこの景色を見るだけの観察者、単なる傍観者に化している。
10.両方(りょうほう)体
山高み雲井に見ゆる桜花心のゆきて折らぬ日ぞなき
意味を両方にかけた洒落の歌。例歌の「心のゆきて」は、行くと満足の二つの意味をかけている。
■クオリアから詞へ
梅原氏は、忠岑の和歌体十種は「見事な意識の動きのとらえ方のように思われるが、写思体から高情体への変化の中に一つの大きな転換があるかに思われる」と書いています。
一言、補足しておきます。ここに記された「高情としての幽玄の美意識」に関連して、梅原氏は、「たしかに高情体は後世「幽玄体」と称せられるものであろう。これはたしかにおぼろでかそけく実在の光が示される美学である。存在の深い光を、ヴェールのこちら側から、かすかにのぞき見る美学である。おそらくこの高情体が平安朝的な「幽玄」の概念といえるであろう。俊成、定家においてこの幽玄の概念は変質する。いかに変質するか、それは他日の問いである。」とも書いていました。
これらのこと、すなわち、平安朝的な幽玄の概念と、中世的な幽玄体の概念との違いについては、第7章で引用した「日本の美意識の感情的構造」で、定家の「み渡せば花ももみぢもなかりけり浦の苫屋の秋の夕ぐれ」をめぐって、「それは、春や秋の盛りの哀歓ではなく、秋の夕べのわびしさそのものであり、悲しみは絶望にまで深まっている。しかし、同時に、自己と対象との間にあった無は、対象そのものにうつされ、却って主観は、純粋観照の主体として嘆きから解放されるのである。非情の美学がここに生れる。このような美意識は「客観化された悲哀」とよばれるべきものかもしれない。」と書かれていたことのうちに暗示されています。
梅原氏がいう「客観化」とは「言語化」のことなのではないか(物=クオリアから詞へ)。そして、そのような客観化のいきつく果てに構築される、言語世界における(純粋に論理的な)事象としての「絶望」や「観照」から、逆説的に世阿弥における「生命の様式」が、すなわち客観化された歌の姿としての「身体」が生み出されていったのではないか(仮面=ペルソナから身体へ)。第7章で、私はそのように書きました。この(先走りすぎた)議論の前段、つまり「客観化=言語化」のプロセスを、それこそ目に見えるかたちで客観化することこそが、古典和歌の世界において歌体論が担ってきた機能なのであり、それこそ、感覚=感情の論理に基づくものなのではなかったか。これが、ここでの私の仮説です。
■身の伝導体と詞の伝導体
忠岑十体のうちには、万葉集から新古今集にいたる古典和歌の感覚の論理とその変遷の上に、いわば一種のパランプセストのかたちで、古今集的な感情の論理が書き込まれています。
まず、古歌体のうちには、対象の動き(自然の律動)と、主体の未分化な身体感覚(広義の共感覚)とが渾然一体となった、万葉集的な感覚世界を原型とする感情が表出されています。それは、「存在するすべてのものは繋がっている」、そして、その「全体には非人格的な力が働いている」(高橋元洋)という二つの特徴でもって構造づけられた「原感情」であり、原初の身体感覚のうちに、異なる複数の身体(身=心としての身(み))を貫通するかたちで蔵された、「身体の記憶」としての「共感情」とでもいうべきものです。(先走った議論を挿入するならば、万葉集的な「原感情=共感情」は、新古今集的な「客観化=言語化された感情」の論理の世界において、「身体の記憶」ならぬ「言葉の記憶」(言葉が見る夢)としての「共思考」とでもいうべきものへと変質します。)
この、目に見える対象の動きと連動した感情が目に見えない時間の推移(不可視の自然の律動)と相即することを通じて、つまり、「見る」から「思ふ」への(あたかも、屏風絵の静止した視覚対象を、詞のはたらきでもって動画化し、はては心象風景めいたものへと転じていくような)価値転倒がもたらされることによって、直体的な感情(たとえば、音として遠方から聞こえてくる秋の気配への「驚き」)が表出され、そこから、個別の感覚(クオリア)に付託して表現される古今集的な感情(たとえば、過去の記憶を一挙によみがえらせる嗅覚のクオリアに伴う「何かせつないような、かなしみに似た情感」)の世界がひらけていくことになります。
その第一は、非在の対象をめぐる根源的な感情としての「悲哀」(ペーソス)であり(余情体)、第二は、その反省的自己意識としての主観的な「絶望」、すなわち言語化への欲望(ひたぶる心)とその不可能性がもたらす屈折した「思ひ」です(写思体)。この二つの感情の様式の上に、第三の感情として、遠方に確かに実在する対象への「憧憬」が(高情体)、第四に、今ここに実在する対象に対する「爽快」の感情が(器量体)、それぞれ表出されるわけです。
これらの典型的な古今集的感情相互の関係について、先の「客観化=言語化」のプロセスに即して再整理すると、次のようになります。
万葉集の感情世界では、個々の感情はいまだ未分化で、しかも森羅万象と直接的につながっていました。(精確には、そのようなものとして「万葉集の感情世界」という概念を規定することができる、ということです。念のために書いておくと、この注記は、ここで論じている他の事柄全般に、たとえば古今集の感覚世界や感情世界、等々をめぐる議論にも妥当することです。)第4章で引用した文章のなかで、大岡氏は、「多くの万葉の歌は、瞬間的な知覚の清新さを、心緒の直接の表白とじかに結びつけており、事物に「寄せて」という間接的反省を通してではなく、事物がそのまま自己のある瞬間の心的状態と融け合っている直接的な一体感において、私たちを魅するのである。」と書いていました。そこでは、心緒(S)と対象的事物(G)とそれらの媒介物=詞(M)の三者がそれぞれ直接的につながり(「S=M」かつ「M=G」かつ「S=G」)、そして、その全体には非人格的な(言霊の)力がはたらいていたのです。
ところが、古今集的な感情の世界では、心緒と事物、そして、詞と心緒、詞と事物の間に「無」の楔が打ち込まれます。まず、直体においてSとGが分離され、その間隙を埋めるはずのMの(言霊的な)はたらきも機能不全におちいります。(秋の訪れ(G)とこれに気づかぬ主体の意識(S)との時間的なズレを風の音(M)が媒介し、そこに驚きの感情が立ちあがるのだが、これを表現する「驚き」という語(M)は、もはや驚きのクオリアそのものには届かず、SとGをつなぎとめる力をもっていない。こうして、「S=M=G」の等式が「S=M」と「M=G」に分離する。)
次いで、余情体では「M=G」の等式が、写思体では「S=M」の等式が破壊され、こうした心緒と詞、事物と詞の乖離のうちに、それぞれ悲哀と絶望の感情が立ちあがっていきます。そこに、「一つの大きな転換」が生じます。すなわち、「絶望にまで否定的に深まった意識が、ひそかに肯定の感情へと転化される」わけなのですが、しかし、そのような「美的感情の発展運動」は、けっして心理的な出来事ではありません。否定から肯定へという美的感情の運動をもたらすのは、実は詞の力です。失われた(言霊的な)詞の力が、貫之的な「いひいだす」ことを介して、言語の世界において恢復されることを通じてなのです。
言い出された歌の詞は、SとGの媒介(M)としてのはたらきによって、高情体(M=Gの恢復)や器量体(S=Mの恢復)の感情を表出し、あるいは創出し、(もしくは、世界の「相貌」として、あらゆる「立ち現われ」にそれらの感情を刻印し)、また、その応用としての神妙体へ、さらには、言葉の編集技術を駆使した理知的な比興体、華艶体、両方体への展開を促していきます。かくして、社交的に洗練された感情表現の型が形成され、大岡氏が「偉大な紋切り型辞典あるいは模範的類型集」(『詩の日本語』)と評した古今集の美意識が確立されます。そして、これへの反駁として出現することになる新しい美意識(非情の美学)を通じて、言語的に構築された「心」の「深み」に向けて内触覚的にしみていく、言語的な「思ひ」としての客観的な感情(たとえば、「身にしむ色の秋風」としての恋の心)が造形され、やがては、正徹や心敬、世阿弥や利休の美学へと引き継がれていくことになるわけです。
自然の律動と相即する感覚の論理の上に、パランプセストのかたちで、身=心としての身(み)の伝導体を垂直方向に貫く感情の論理が立ちあがり、その感情の論理の上に、もう一つのパランプセストとしての(あるいは、アナグラムとしての)詞の世界が書き込まれていく。こうして、貫之現象学における(実在する現象としての)共感覚から、感覚=感情の論理のはたらきを経て「よろづのことのは」の世界における言語的構築物へといたる「自然/身=心/詞」の、あるいは「共感覚(クオリアの宇宙)/身の伝導体(「ひたぶる心の屈折」の理論)/詞の伝導体(「ことばの屈折」の理論)」の三層構造が抽出されました。
■古今集仮名序・再考
この貫之現象学の三層構造は、(夢の詞としての哥のあり様をめぐる三つの徴候、すなわち「ギフト/フィギュール/パランプセスト」という貫之現象学のトリアスと並行するものでもあるのですが)、これを仮名序冒頭の語彙を用いて、「よろづ/人のこころ/ことのは」といいかえることができます。
大岡信氏は、俊成歌論をとりあげた『詩の日本語』の第九章「詩の「広がり」と「深み」」で、「古来風躰抄」の冒頭の一節、「かの古今集の序にいへるがごとく、人の心を種として、よろづの言の葉となりにければ、春の花をたづね、秋の紅葉を見ても、歌といふものなからましかば、色をも香をも知る人もなく、なにをかは本の心ともすべき。」をめぐる窪田空穂の議論を引いています。
この窪田空穂の指摘は、俊成が仮名序の言葉について、「よろづの」の「の」を、ふつう解釈されているような連体修飾の「の」ではなく、主格を示す「の」として読んでいたのではないかということを考えさせる。「つまり、和歌は人の心が種となってさまざまな言葉(歌)になったのだ、という程度のものではなく、人の心を種として、万象が言葉(歌)になったのだ、と彼は解していたように思われるのだ。」大岡氏はそのように述べ、続けて、「よろづ」は主格の抽象名詞ではないかという、寺田透氏の仮説を引きます。「漢詩に対して日本の歌は、ひとの心を一切の発芽の根源として、それから伸び出る幹茎の言語表現衝動から、人事人情思想その他の森羅万象が、さらにその葉に相当するものとして表に出たものである。もともと人事人情思想、森羅万象の刺激が心のはたらきを目ざまし、その中に宿ったのではあるが。」(寺田透「古今所感」、『源氏物語一面』所収)
ここには、平安朝的な「幽玄」と中世的な「幽玄体」との違い(梅原猛)についての一つの解答があります。「広がり」と「深み」の語彙が、その違いを端的に言い表わしています。そして、図式的に単純化すれば、前者が貫之の歌論に、後者が俊成の歌論に、それぞれ割り振られるわけです。しかし、私はあえて、窪田=大岡説に半ば抗って、貫之の「やまとうたは、人のこころをたねとして、よろづのことのはとぞなれりける」には、「人のこころ⇒よろづのことのは」(小松英雄氏によれば、「人の一つ心⇒万の言の葉」)の契機とともに、「よろづ⇒ことのは」の契機が含まれていたのだと解したいと思います。
ここで、半ば抗うとは、仮名序冒頭の一文は、単に「歌の多趣多様であることをいつたに過ぎない」ものではなく、かといって「一切の自然は心の生み出すところのもの(=言語)だ」とまで解釈することもできないが、しかし、そのような俊成歌論が後にそこから立ちあがってくる基本的な構図のごときものは、貫之歌論のうちにあらかじめしつらえられていたのであって、それこそ、「人事人情思想、森羅万象の刺激が心のはたらきを目ざまし、その中に宿」り、そして、その「人の心を種として、万象が言葉(歌)になったのだ」という、およそ「やまとうた」であるかぎりの歌が存在するための条件、すなわち「よろづ(物)/人のこころ(心)/ことのは(詞)」の三層構造(もしくは、小松説を一部加工して繰り入れると、「よろづ/いきとしいけるものの一つ心/世の中にある人の心におもふこと/万のことのは」の四層構造)だったのではないか、という趣旨です。もしそうであるとすれば、言語に先立つ「よろづ」(森羅万象・自然)の側からこれを見るか、あるいは「ことのは」(詠み出だされた歌)の側からこれを見るかは、(いいかえれば、「よろづ⇒人のこころ⇒ことのは」の貫之歌論と、「ことのは⇒人のこころ⇒よろづ」の俊成・定家歌論との差異は)、結局のところ、貫之がしつらえた同じ構図のなかでの運動の方向の違いに帰着します。
■哥が立ち現われる現風景
話は前後しますが、「見る」から「思ふ」へという和歌の本質規定をめぐる第一の価値転倒を担うのは、いうまでもなく貫之です。それは、仮名序冒頭の「人のこころをたねとして」に示されているものでした。この「人のこころ」が、やがて、「広がり」から「深み」へという、俊成による第二の価値転倒を通じて「新しい花」(尼ヶ崎彬)を咲かせ、定家の幽玄体へとつながっていくことになります。
一方、貫之歌論におけるいま一つの転換、すなわち「見るものきくものにつけて」に刻まれた和歌の形式規定(付託法)の方は、縁語・掛詞・本歌取りを含めた、意味とイメージを重層交錯させる高度な修辞技術として後の世に継承され、洗練されていくのですが、私はそこに、貫之歌論における第三の転換を加えることができるのではないかと考えました。それは、仮名序の「いひいだせるなり」のうちに表現されているもの(ヴァーチュアルな次元からアクチュアルな次元へと向かう現働化のはたらきをもたらすランガージュの力、あるいは〈欲望〉)のことです。
第5章で、私は、「いひいだす」ことこそが、貫之現象学の世界(よろづ⇒人のこころ⇒ことのは)を「ひとの世」における歌(心におもふこと⇒詞への付託)につなぐ決定的な役割を果たしているのではないかと書きました。また、第6章では、次のように書きました。
富士谷御杖の「ひたぶる心」とは実は身体のことで、それは言語で表現されてはじめて存在する。そして御杖の「なぐさめむとする心」は、身体と言語の両世界の「境」に存在し、言語表現へと向かう志向性を指しているのであって、それこそ、貫之歌論における「いひいだす心」の本体にほかならないのだと。さらに、貫之歌論にあっては、歌詞(うたことば)への付託法、つまり「見るものきくものにつける」ことよりも、「辞」すなわち(言の葉ならぬ言の端としての)「てにをは」のはたらきを用いて歌を「いひいだす」ことの方が、むしろ大切なことだった。「もののあはれを知る」とは、「詞」(言葉によるクオリアの表現、すなわち「死物」)を「辞」のはたらきを介して生きた「活物」へと転じることだったのではないか。「てにをは」もしくは「辞」とは、フィギュールの異称の一つなのではないかとも。
貫之が「千代経たる松にはあれど古の声の寒さはかはらざりけり」の歌に詠んだものは、実は、このフィギュールとしての哥が生成する原風景、つまり歌が言い出される現場(「身の伝導体」が「詞の伝導体」へと接続される現場)だったのだ。私はそう考えています。
大岡信氏が、「『古今集』の和歌は、いわば極めて微妙な音の響きの重なり合いで成り立っている室内楽、あるいは複雑に交錯して繊細な模様を生み出しているアラベスクの線にも似ていると言えましょう。」と書いていた、その室内楽を構成する「声」とアラベスクになぞらえられる「仮名文字」とが、フィギュールとしての哥が「ひとの世」に立ち現われる際にとるかたちなのであって、「千代経たる」の歌では、そのそれぞれが、松風の音(いにしへの声)、そして松の姿(小松英雄氏の解釈による、寿命が尽きて朽ちかけた松の姿が、仮名文字の形象としてはふさわしい)として現われていました。連綿たる仮名文字によって捕捉された声は、いにしへの声と少しも変わることなく、寒さのごとく身=心にしみてくる。「かはらざりけり」には、差異性に彩られた感覚=感情の世界に対する言語世界の自己同一性が高らかに宣言されている。そんな解釈だって可能なのです。
★プロフィール★
中原紀生(なかはら・のりお)1950年代生まれ。兵庫県在住。千年も昔に書かれた和歌の意味が理解できるのはすごいことだ。でも、本当に「理解」できているのか。そこに「意味」などあるのか。そもそも言葉を使って何かを伝達することそのものが不思議な現象だと思う。
Web評論誌「コーラ」07号(2009.04.15)
<哥とクオリア>第9章 哥と共感覚・中(中原紀生)
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2009 All Rights Reserved.
|
| 表紙(目次)へ |