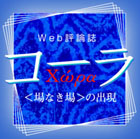|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「la Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
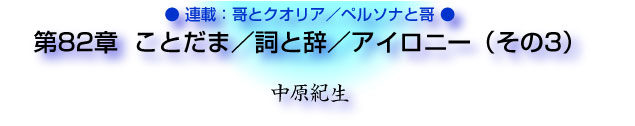
|
|
(本文中の下線はリンクを示しています。また、キーボード:[Crt +]の操作でページを拡大してお読みいただけます。★Microsoft Edgeのブラウザーを基準にレイアウトしておりますので、それ以外のブラウザーでご覧いただく場合では,大幅に図形などが崩れる場合があります。)
■あわわ言葉の言語化・メロスと言霊─ことだまをめぐる諸相(1)
この論考群ではこれまで、言霊について散発的に言及してきました。第5・6章では、「聲と言霊」前後篇として、貫之歌論(古今集仮名序冒頭)をめぐって、たとえば大森荘蔵の「ことだま論」を通りすがりに一瞥し、また尼ヶ崎彬、坂部恵両氏の力を借りて、富士谷御杖の歌論を概観したりもしました。
本来であれば、それらの断片的な考察を繋ぎ合わせ、本格的な言霊論の体系化を目指すべきなのかもしれませんが、ここでは戦線を限定して、ことばが持つ力としての言霊、とりわけ“やまとことば”がその身に纏うクオリア(もしくはクオリアを産み出す力)としての“ことだま”に関連するいくつかの素材を蒐集することに徹したいと思います。そうすることで、“やまとことば”の特質を炙り出せるかもしれないことを期待して。
その1.吉本隆明は『母型論』の「起源論」で、乳幼児の前言語的な「あわわ言葉」(喃語)の段階では、人類の発声器官の構造の同一性ゆえありとあらゆる発音をすることができるのに、その後の言語化の過程を経て、ほとんど相互の了解を拒絶するようにへだたったそれぞれの種族語や民族語の音声の相違、文法の大差がもたらされるのはなぜかを問うている。
◎ヤポネシアのことば─自然音と言語音が同じ位相にある言語
◎模倣言語─喩としての自然音(擬音語)
◎言霊と擬人─人類の言葉が一様に通り過ぎた特性
その2.九鬼周造は「日本詩の押韻」(全集第四巻)において、「韻律の無いところには言霊は宿らないというのが我等の祖先の信仰であった」(443頁)と書いている。
また、『偶然性の問題』では次のように述べている。
■言霊の人称・言葉が心を形成した時代─ことだまをめぐる諸相(2)
その3.藤井貞和氏は『〈うた〉起源考』の第三章で、和歌を「詠む主体」とはだれかという問いを立て、それはあくまで「一首の表現を支える存在」であって、たとえば「〈わ〉がつまも 画にかきとらむ。いづまもが。たびゆく〈あれ〉は みつゝしのはむ」の作中に言及される一人称「わ」「あれ」にそのままなるわけではないと論じている。
藤井氏は「言説内部」での人称、言い換えれば「論理上の文法」における人称(一人称、二人称、三人称──さらに、物語の語り手によって引用される(作中人物が詠む)物語歌における「引用の人称=四人称(物語人称)」)とは別に、それを下支えする「表現主体の文法=表出文法」での人称として、時枝誠記の「零記号」(言説をなす意味語から分離され、表現主体のおもわくを直接に担う助動‘辞’、助‘辞’などの機能語を言う)とも関連させた「ゼロ人称」を──さらに「自然称」や「擬人称」(=地名)、はては「時称」(=現在)を──呈示している。
私は、藤井氏が提唱する「ゼロ人称」を──さらに「自然称」「擬人称」「時称」を──総称して、「言霊の人称」と呼びたい。
その4.下西風澄著『生成と消滅の精神史──終わらない心を生きる』第5章のうち、主として「『万葉集』から『古今和歌集』へ──言葉から心へ」からの抜き書き。
「人間ははじめに心を持ったからそれを言葉で表現したのではない。むしろ人間は先に言葉と振る舞いをインストールし、何度もそれを実行することによって心を生成・形成することができたのだ。」
「…『万葉集』の歌に詠われている意識は「なにものかについての意識(consciousness about something)」であるというより、「なにものかと共にある意識(consciousness with something)」」である。意識は単独で存在することはできず、常に自然と共に在ってはじめて可能になる。」
「彼ら[万葉の歌人]は「雪と共に」悲しんだのであり、「月と共に」愛する人に思いを馳せたのだ。すなわち彼らは自然を通じて心という存在をたしかめた、というよりもむしろ、自然と交わることによってはじめて心を存在させた、とさえ見えるほど、自然と交雑することの意味は大きかったのである。」
「‘自然を通じて心を生成’させていた万葉の歌人らと比べ、古今の歌人らは、自然よりも‘言葉を通じて心を表現’するようになった。すなわち、万葉歌人らが自然と共になければ心さえ存在しない、といった思想を持っていたとすれば、古今の歌人らは、この自然との最初の決別を断行し、自然がなくても成立する心の創造に立ち会っているように思える。」
「…古今時代の人々が見た自然は、桓武天皇によって新造された平安京という都市的文化のなかで‘人工的に構成された自然’であった。」
「…平安京は単なる建築構造物ではなく、一方では宇宙にまで広がる大自然へとアクセスするための巨大な知覚拡張メディウムであり、また同時に大いなる自然を意識のなかへと集約してしまう膨大な圧縮プロトコルの集積回路でもあった。」
「…古今の歌人たちが向き合った自然は、都市的でありかつ場合によっては絵画的な自然、あえて言い換えれば「情報論的な自然」であった。」
「…『イリアス』において「四肢」や「骨」「肉」「皮膚」などの語はあっても、その総体としての「身体」という語が存在しなかったように、万葉の人々にとって「花」や「風」、「霞」「波」「月」は存在したが、その全体としての「自然」はいまだに発見されていない。古今的な心は、そのような生の自然がなくても成立した。すなわちそれは、かつての自然からの決別が、かえって「自然」という対象を存在させた(前景化させた)、という逆説的状況において成立したのである。」
「意識の共存在である万葉の自然から、情報としての古今の自然、という変化のうちに、自然物に対する態度も明確に変わっている。万葉の人々において自然は人の心と不可分であり、彼らは自然のあらゆるもものにメッセージを読み取った。」
「…万葉の歌人たちが、自然を「見る」ことによって自然と「共に」ある意識を持っていたのに対し、古今の歌人たちは自然を「心の対象」として捉えた。これが「見る」から「思う」という表現上の変化、すなわち視覚から思考という意識の変化をもたらしている。」
「私たちは『万葉集』の前史から、『古今集』に至るまでの意識の在り様の変遷を追ってきた。かつて神の言葉の模倣としてはじまった祝詞、その律文形式の洗練から発達した和歌、それは継承された神の言葉であり、神の言葉をシミュレーションすることによって人間ははじめて心のプロトタイプを形成した。そして『万葉集』ではその心を自然と重ねることで日本的な心の在り様を見つけ、『古今集』に至っては言葉そのものが心の支柱を担うほどに役割を強め、和歌はついに「心の表現」となった。別の言い方をすれば、「言葉が心を形成した時代」から、「心が言葉を形成する時代」へと変わったのだと言えるのかもしれない。紀貫之の序文に込められた言葉はその意味で、日本における「心の時代の宣言書」であると考えることもできる。」
強引な括りだが、私は、下西氏が万葉歌に関して述べた「自然」と「言葉」を同義ととらえ、それを「言霊」の語に置き換えて考えている。すなわち、言霊とは、振る舞いと共に人間にインストールされて意識・心を形成し、やがて(情報として)この意識・心のなかへ圧縮・集約されていった「自然=メッセージ=神の言葉=はじまりの言語」であると。
■アルシエクリチュール・言葉の魂─ことだまをめぐる諸相(3)
その5.中島隆博氏は『思想としての言語』の冒頭で「しばしば日本には形而上学がないと言われるが、歌論や文学論こそが日本の形而上学であり、思想としての言語の精髄である。」と書き、空海、紀貫之、本居宣長と夏目漱石を論じている。いずれも興味深く刺激的だが、ここでは第2章「『古今和歌集』と詩の言語」の議論を抜き書きする。
中島氏はそこで、「文(アルシ・エクリチュール)」が和歌の形而上学的対象である“ことだま”の棲息地、発生場所であると論じている。──この「物がそもそも文であり、自然がそもそも文である」ような世界のことを、鶴見俊輔は(自然科学ならぬ)「歌学」と呼んだ。
◎『古今和歌集』の形而上学─自然を可能にする文
◎万物が歌をヨム世界─自然の根源にすでに文があった
◎翻訳による文学空間─物と心情と文が織りなす入れ子状の構造
──備忘録。「文学」の「文」すなわちアルシ・エクリチュールが「憑依体験やシャーマニズムと結びつく」ことについて、出口顯著『声と文字の人類学』が参考になる(第七章)。
その6.野矢茂樹氏は『ウィトゲンシュタイン『哲学探究』という戦い』において、ウィトゲンシュタインが論じているのは「心が言葉に意味を与えるのではなく、言葉が心に志向性を与える」(230頁)こと、すなわち「音声や文字模様等が直接に相手の反応を促すのであり、意味なる何ものかや意味理解なる心の状態がその間を媒介する必要はない」(265頁)ということだったと書いている。
たとえば、誰かに命令するとき、音声や文字模様や身振りを用いて相手にしかるべき反応を引き起こそうとする、まさにその意味において、その「音声や文字模様や身振そのものが「言語」と呼ばれうる道具なのである」(265頁)。
野矢氏はまた、「「シューベルト」という名前はシューベルトの作品と彼の顔にぴったり合っているかのように、私には感じられる。」(『哲学探究』第二部、第二七〇節)というウィトゲンシュタインの所見を引いたうえで、ある言葉が「身につき、なじんだ道具がそうであるように、私の体の一部と化している」とき、それを身から引き剥がし、別の言葉で呼んだときに失われる「言葉にとってきわめて大きなもの」のことを、ウィトゲンシュタインが「言葉の魂」(第五三○節)と呼んだことを指摘する(269頁)。
そして野矢氏は、ウィトゲンシュタインの言う「言葉の魂」と、大森荘蔵が「相手を直接に動かす言葉の力」をそう呼んだ「ことだま」が、「同じかどうかは定かではないが、二人がここで同じような語を用いていることは興味深い」と註をつけている(337頁)。
──私は、心に「意味」そのもの(リアルまたはイマジナルな内容性)をではなく「志向性」(アクチュアルまたはヴァーチュアルな形式性、あるいは茂木健一郎氏が言う「志向的クオリア」)を与える言葉のはたらきが「言霊」であると考えている。「語クオリア」は、語(詞)が喚起する意味やそれが指し示す物的対象の「感覚クオリア」そのものではなく、あくまで「語」が孕む「質」であり「言語感情」なのであって、そのような(マテリアルな次元ではなく、「見えない次元」すなわちメタフィジカルな次元における)クオリア[*]に対する志向性として働くのが「言霊」であり、“ことだま”なのだと。
つまり、“ことだま”は「イマジナル/リアル」の(マテリアルでホリゾンタルな)軸と「ヴァーチュアル/アクチュアル」の(メタフィジカルでヴァーティカルな)軸を繋ぎ、「ヴァーチュアル/アクチュアル」なものが、「イマジナル/リアル」な世界の事物事象が発する音声やその形姿、イメージのうちに顕れるための通路・導管(もしくは依代)である。あるいはその結果として、「イマジナル/リアル」な世界の事物事象が、それを遡行して「ヴァーチュアル/アクチュアル」な世界へ帰還する通路・導管(もしくは痕跡)である。この双方向のプロセスは、音声のみならず文字においても成り立つ。「音霊」に対する「文字霊」として。
[*]メタフィジカルな次元における「クオリア」には、マテリアルな次元における「感覚クオリア」に対応する「語クオリア」とは別の、ウィトゲンシュタイン=野矢の議論に出てきた「シューベルト」に対応するものがある。そのようなものを私は、平井靖史氏の概念を援用して「文章クオリア」もしくは端的に「ペルソナ」と呼びたい(第80章第6節の註1参照)。
それは「自然(万物)としての文」もしくは「体験質(記憶クオリア)としての文」が累積することによって構成される「人生という巨視的な時間を貫いて存続する一人の人格」のクオリアであり、アルシ・エクリチュールの集積物(パランプセスト)としてのテクストが持つクオリアである。
──留意すべきこと。いま述べたメタフィジカルな次元は「ヴァーチュアル/アクチュアル」な世界に属しているわけではない。それはあくまで「イマジナル/リアル」な世界に属する事物事象という「形ある世界に張りついて働く見えない次元」である。
余談ながら、このメタフィジカルな次元とマテリアルな次元と共に人間の言語の三帯域を構成する「メカニカル」な次元に属する言語をめぐって、ウィトゲンシュタインは次のように書いている。
このような、クオリアなき文字列のやりとりのことを、古田徹也氏は「魂なき言語」と呼び、茂木健一郎氏は「言語ゾンビ」と呼んだ(第73章第3節参照)。
■倒語・イロニー・文法─保田與重郎の言霊観
桶谷秀昭は『昭和精神史』第七章「言霊とイロニイ」で、保田與重郎の言霊解釈の「ぜんたいの論理は富士谷御杖の言霊理論からの暗示に負うてゐる」(扶桑社,196頁)と指摘しています[*]。
御杖の言霊論は、たとえば「言語に精霊がひそみ、 その力によって事物や過程がことば通りに実現されるのを期待する」(西郷信綱『詩の発生』)といった類のものではありません。桶谷氏は、次のように解説しています。
桶谷氏は、この富士谷御杖由来の「倒語=言霊」を、保田與重郎が多用した「イロニー」の概念と結びつけます。
かくして、本論考の当面のテーマ群のうち「ことだま」と「アイロニー」が結びつきました。
ところで、河田和子氏は「保田與重郎における「言霊」思想」で、この桶谷の見方は、初期評論(「『好去好来の歌』に於ける言霊についての考察」「戴冠詩人の御一人者」など)ではいいが、その後、保田は御杖の言霊倒語説から離れていったのであり、「言霊私観」やその前後の言霊論になると、保田のイロニーを倒語と同一視する図式は当てはまらないと指摘しています。
河田氏によると、保田が「言霊私観」を発表した昭和17年から19年にかけて、文壇では言霊に対する議論が盛んだった(「大東亜文学者大会」における横光利一の発言や小林秀雄「文学者の提携に就いて」、亀井勝一郎『続人生論』中の「言葉」など)が、当時の言霊論は、音義言霊学的な言霊思想の流行もあり、音声中心に考えられていた。「そこに、同時代の知識人の言霊論と保田の言霊観との相違もある。」
──かくして、「ことだま」と「文法」(詞と辞)が結びつきました。
[*]保田が御杖を「いつ知つたのかつまびらかにしない」と桶谷氏は書いているが、奥山文幸氏は「橋と言霊──保田與重郎「日本の橋」をめぐって」において、「富士谷御杖を象徴主義者として近代文学的に再解釈した土田杏村経由のものである」とし、土田の「御杖の言霊論」から次の一文を引いている。
■ことだまとふろしき─大森荘蔵と時枝誠記
「ことだま」と「文法」を繋ぐ、もう一本の補助線を引きます。
大森荘蔵生誕100年の特集を組んだ『現代思想』(2021年12月号)[*]に掲載された「言葉で世界を造形する──大森荘蔵の芸術哲学素描」において、安藤礼二氏は、大森の言語論・意味論である「立ち現われ」一元論をめぐって──『物と心』に収録された「ことだま論──言葉と「もの‐ごと」(桑子敏雄氏が『感性の哲学』で「大森哲学の白眉」と記した論考)の叙述を踏まえ──次のように書いている。
(安藤氏は、大森の「ことだま」を鈴木大拙の「如来蔵」や折口信夫の「憑依」と関連づけ、そして、大拙と折口を「総合」した井筒俊彦の言語論の呪術的(マジカル)な側面に重ね合わていく。刺激的な議論だが、ここでは割愛する。)
安藤氏の論考とともに『現代思想』(2021年12月号)に掲載され、その後『日本近代思想論』に収録された「大森荘蔵と西田幾多郎──現在と身体をめくって」において、檜垣立哉氏は、大森荘蔵と西田幾多郎の深いつながりを示す例の一つとして、大森が『物と心』所収の「科学の地形、と哲学」で、主体=私なき日本語の構造を説明するため「時枝文法」に言及したことを挙げている(95頁)。
「私はAを見る」の私(主観)・見る(作用)・A(もの)の各項は互いに分離(分節)可能な対象なのではなく、「一体で不可分な事態」の「副詞的な限定の積み重ね」と見るべきだ。この関係は「私が」→「見る」→「A」の形ではなく、{私が《見る(A)》}の形なのである。大森はそのように述べたうえで、「時枝文法のふろしき構造がこの場合に最も適切に思われる」と書いている。
すなわち、「私は机を見る」の場合だと3枚のふろしきが重なっていて、外側のふろしきを広げると「机」の姿が立ち現われ、2枚目で「机が見える」となってこれが普通の日本語。最後のふろしきを広げると「机が見える、(強いて言うとこの)私に(おいて)」といった文になるということだろう。
[*]同誌に掲載された森岡正博・山口尚の対談「未来の大森哲学──日本的なるものを超えて」は、後に刊行された『生きることの意味を問う哲学 森岡正博対談集』の第3章「日本的なるものを超えた未来の哲学」として収録されている。これに付された「解説」の中で、森岡氏は次のように書いている。
──ペルソナを成り立たせる要素として、「顔」と「固有名」あるいは「身体」(姿形、ふるまい、表面性、等々)と「記憶」(歴史、愛着、文脈、等々)を挙げることができるだろう。これらのうち、アニメイテッド・ペルソナは「身体」の成分を濃厚に含んだ概念であると思う。そしてそれは一種の「ゾンビ」性を孕んだ概念でもある。いわば「ことだまゾンビ」。(これは否定的な意味合いでそう述べているのではない。)
(56号に続く)
★プロフィール★
中原紀生(なかはら・のりお)1950年代生まれ。兵庫県在住。千年も昔に書かれた和歌の意味が理解できるのはすごいことだ。でも、本当に「理解」できているのか。そこに「意味」などあるのか。そもそも言葉を使って何かを伝達することそのものが不思議な現象だと思う。
Web評論誌「コーラ」55号(2025.04.15)
<哥とクオリア/ペルソナと哥>第82章 ことだま/詞と辞/アイロニー(その3)(中原紀生)
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2025 Rights Reserved.
|
| 表紙(目次)へ |