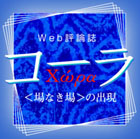|
|
|
Web�]�_���u�R�[���v |
|
���n���̎� ���{���̕\���i�ڎ��j�� ���{���̃o�b�N�i���o�[ ���ǎ҂̕Ł^���ӌ��E���z �����e�K�� ���W�҂�Web�T�C�g ���v���C�o�V�[�|���V�[ |
|
���{���̊֘A�y�[�W�� |
|
���u�J���`���[�E�������[�v�̃o�b�N�i���o�[ ���]�_���ula Vue�v�̑��ڎ� |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
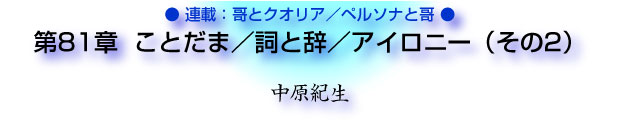
|
|
�i�{�����̉����̓����N�������Ă��܂��B�܂��A�L�[�{�[�h�F[Crt +]�̑���Ńy�[�W���g�債�Ă��ǂ݂��������܂��B��Microsoft Edge�̃u���E�U�[����Ƀ��C�A�E�g���Ă���܂��̂ŁA����ȊO�̃u���E�U�[�ł������������ꍇ�ł́C�啝�ɐ}�`�Ȃǂ������ꍇ������܂��B�j
�@
���f��Ɖ��ʁA�ʎ��Ɠ��ʁi�P�j��������v���߂�����
�@
�@���O�B��܂Ƃ��Ƃ́g�����āh���A���ʂƑf��̗��ʂ��Ӗ����Ă��邱�ƂɊ֘A���āA�����ŁA���u�����܂܂ɂȂ��Ă��镚���̉���A�Ƃ܂ł����Ȃ��Ƃ��A���߂Ė{���ւ̒��n�������͐ڑ����͂����Ă��������Ǝv���܂��B
�@�ȑO�A��65�͑�5�߂̖����ŁA���J�s�l�����w��{ ���{�ߑ㕶�w�̋N���x�ɂ����āA�u�f�灁�����I�����i�A���t�@�x�b�g�j�v�Ɓu���ʁ��\�ӕ����i�����j�v��Δ䂳���Ę_���Ă��邱�ƂɐG��܂����B���̘b��͖{���A�єV���ۊw�a�w�̑�i�l�Ԃ̌���сj�̂ǂ����A���Ƃ��u�����̌���v��_�����ӏ��Ŏ�肠���Ă����ׂ��������̂ł����A�K���Ȓ��n�_�������͐ڑ��_�������邱�Ƃ��ł����A���܂����ɕ������܂܂ɂȂ��Ă��܂����B
�@
�@�w��{ ���{�ߑ㕶�w�̋N���x�̕��͂������܂��B�����ɓ������w���{���d�j�x��ꊪ�ŁA���َ���̉������lj^����S�������ڎs�욣�\�Y�́u�ʎ��I�ł��l�ԓI�Ȕ��͂̂��鉉�Z�v���߂����āA�u�ނ͌Õ��Ȍ֒��I�ȉȔ�����߂āA�����b�̌`�������B�܂��g�̂�k��ɑ傫���������h��ȉ��Z�����A���_�I�Ȉ�ۂ��q�ɓ`�ւ�\�������o���̂ɋ�S�����B�v�Ə��������Ƃɂ��āA���J���͎��̂悤�ɘ_���Ă��܂��i��Q�́u���ʂ̔����v�j�B
�@���X�ƈ��p���܂����B���͂��̕��͂�����܂ʼn��x���A���N�����ɌJ��Ԃ��ǂݕԂ��Ă��܂����B�����Ă��̂��сA�X�������O�Ȓm�I῝���o���A�Ȃɂ����܂Ō������Ƃ��l�������Ƃ��Ȃ������V�������E���A��������J���̂������܂����B�������A����ł��Ȃ���ǂ����Ă��A�Ȃɂ���������ꂫ�Ȃ����̂��������ȂɁA���b���̂悤�ɓb�ނ̂ł��B
�@����͂����炭�A���̂悤�Ȏ���ɂ����̂��낤�Ǝv���܂��B�܂�A���J���ɂ���Ė\���ꂽ�u�L���_�I�ȕz�u�̓]�|�v�̑O�ƌ�Ƃł́A���E�����邱�̎����g�́u�L���_�I�p�[�X�y�N�e�B���v�Ƃł������ׂ����̂��܂邫��قȂ��Ă���B�����ł���ɂ�������炸�A���́A�]�|��́i������v�������炵���j�g�g�݂ł���������������l�����肷�邱�Ƃ��ł��Ȃ��B���̃M���b�v���A���ŗ����������ƂƑ́i�S�j���[�����邱�ƂƂ̘����������炷�̂ł͂Ȃ����ƁB
�@
���f��Ɖ��ʁA�ʎ��Ɠ��ʁi�Q�j���L���_�I�]�|���߂�����
�@
�@���J���̋c�_���A�i���Ȃ�̗����ɉ����āj�u�]�|�v�̑O��r����D�������A�ĕҏW���܂��B
�@
�T�D�]�|�O
�@
�@�@�@�@�@�@�@��
�@
�@�E�����Ƃ͕ʌɑ��݂��镶���i�A���V�G�N���`���[���j����
�@�E���ʂɂ�鉉�Z�i�֒��I�ȉȔ��A�l�`�I�Ȑg�Ԃ�j�@�@����
�@�E��͂��Ƃ��Ɓu�`�ہ��Ӗ��v�i�����̂悤�Ȃ��́j�Ƃ��Ă������B
�@�E�l�X�́u���ʁv�ɂ������A���e�B�i�������Ӗ��j�������Ă����B
�@�E�T�O�Ƃ��Ă̊�ɃZ���V���A���Ȃ��̂������Ă����B
�@
�U�D�]�@�|
�@
-�P�D���l�_�I�E�L���_�I�z�u�̐ݒ�
�@
�@�@�@ �y�ꎟ�I�Ȃ��́z�@�y�I�Ȃ��́z
�@�@�@�@�@�@�@�� �@�@�@���@�@�@ ��
�@
�@�E�����Ƃ��đ��݂��Ă����������Ȃ������m���n������ɂ̂ڂ�B
�@�E�`�́u�Ӗ�������́v���u�Ӗ����̂��́v�ƈʒu�Â�����B
-�Q�D���l�_�I�E�L���_�I�]�|
�@
�@�@�@ �y�ꎟ�I�Ȃ��́z�@�y�I�Ȃ��́z
�@�@�@ �y�Ӗ����̂��́z�@�y�Ӗ�������́z
�@�@�@�@�@�@�@�� �@�@�@���@�@�@ ��
�@
�@�E�����i���j�������i���j������킷���̂Ƃ݂Ȃ��������S��`
�@
-�R�D�L���_�I�]�|�̊���
�@
�@�@�@ �y�Ӗ����̂��́z�@�y�Ӗ�������́z
�@�@�@�@�@�@ (��)�@�@�@���@�@�@ ��
�@
�@�E���i���j���i���j��v�����A���A�����I�����i���j����������B
�@�E�ʎ��I�ȑf��i���j���g����(��)�h���Ӗ�������̂Ƃ��Ă������B
�@�E�f��ɂ��ʎ��I�Ō�����v�I�ȉ��Z
�@�E�ϋq�͂���ӂꂽ�g�Ԃ���̔w��Ɂu�Ӗ����̂��́v��T��B
�@
�V�D�]�|��
�@
�@�@�@ �y�Ӗ����̂��́z�@�y�Ӗ�������́z
�@�@�@�@�@�@�@�� �@�@�@���@�@�@ ��
�@
�@�E���ʁ����I�ȉ����i���j���g�����h�����B
�@�E�f��i���j�����ʁi���j���g�\���h����B
�@
�m���n�w���o�T�C�G���X�x2023�N5�����̋L���u���w�̐��w�u���_�v�̐��E�v�i�G�~���[�E���[���A�r���i�j��j�ɁA���C�t�Q�[���̍l�ĂŗL���ȃW�����E�z�[�g���E�R���E�F�C�̌��t���Љ��Ă����B�u�����͊ԈႢ�Ȃ����݂���̂ɁC�v�l����ȊO�ɒ��ׂ���@���Ȃ��B���̎����͎��ɋ����ׂ����ƂŁC���͂����Ɛ��w�҂�����Ă����̂ɂ��܂��ɗ����ł��Ȃ��B���݂��Ȃ����̂������ɂ��đ��݂�����̂��H�v
�@�������m�F�����킯�ł͂Ȃ����A�����Ō�����u���݁v�Ɓu���݁v�����ꂼ��usomething that exists really�F���A���Ɂi�����Ƃ��ĕ��I�Ɂj���݂�����́v�A�usomething that exists conceptually�F�T�O�I�E�ϔO�I�Ɂi�v�l�ɂ����āj���݂�����́v�ɒu�������čl����ƁA�{�����́u�����Ƃ��đ��݂��Ă����������Ă��Ȃ������v�́u�g���݁h���Ă������g���݁h���Ă��Ȃ������v�Ə�����������B
�@
���f��Ɖ��ʁA�ʎ��Ɠ��ʁi�R�j���ĂсA��܂Ƃ��Ƃ̓������߂�����
�@
�@�����ŁA�O�͍ŏI�߂Ŕ������������╔�b�̋c�_�����������ɏo���Ă݂�ƁA���J�����i�̕���̉��Z���ނƂ��Ȃ���j�`���o�����u�]�|�O�v�̊T�O�E�`�ۂƂ��Ẳ��ʂ́A�╔�b���i�\����ɂ�����d�|�����ɋ����Ȃ���j���o������܂Ƃ��Ƃ́g�����āh�̓����ɒʂ��Ă��܂��B�ꌾ�Ŋ���ƁA�����ɂ́g����h�i���S�j���Ȃ��A�ƂȂ�ł��傤���B
�@�����A���ӂ��Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂́A�]�|�O�̌��ꐢ�E�́A�]�|�ɂ���Ă����炳�ꂽ�u�������S��`�v�ɂ���ĉB������A�{���̂��̂Ƃ܂������قȂ��Č����Ă���\�������邱�Ƃł��B���J���́w�q��O�r�̎v�l�x�����̍u���^�u�����_�v�ɂ����āA�ߑ�̃l�[�V���������܂��ߒ��Ő������u���t�̕ϊv�v���߂����āA���̂悤�Ɍ���Ă��܂��B
�@���킭�A���m�ɂ����Ă��u������v�v�܂�u�V���ȕ��͕\���̑n�o�v���K�v�������B���E�鍑�̌���܂胉�e����⊿����A���r�A�����Ƃ��������ʂ̏������t�ɂ���ĕ\������Ă������ՓI�ȊT�O���A�g�̓I�E����I�Ȋ�Ղɂ��ƂÂ����̂ɂ��邱�ƁA���Ȃ킿�u�������ꂠ�邢�͑���v������o���K�v���������̂ł���B
�@�f���_�́w�O���}�g���W�[�x�̂Ȃ��ŁA�������S��`�̓A���t�@�x�b�g��p���鐼�m�ɌŗL�̍l���ŁA�v���g���ɑk������̂��Ƃ����Ĕᔻ���Ă��邪�A�K����������Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B�������S��`�͂���߂ċߑ�I�Ȃ��̂ŁA�i�V���i���Y���ƌ��т����̂����A�ʂɃv���g������h�����Ă����킯�ł͂Ȃ��B�Ƃ����̂́A�\�����I���{�̍��w�҂̂Ȃ��ɂ��łɉ������S��`�����邩�炾�B�i144-145�Łj
�@�╔�b�������u�����̓��{��v���Ȃ킿�g��܂Ƃ��Ƃh�́A�u��������v�̂��Ƃł͂���܂���B��萸�m�ɂ́A�u�����ȉ����v�Ƃ������i���w�I�H�j�z�������w���Ă���킯�ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł��B
�@�ނ���╔�́A�g�����āh�i���\�ʁj�ɂ����锽�f�i���ꐫ�ƍ��ِ��j�̋Y����߂����āA�u�����ɂ́A�݂�����̂����ɂ��܂��܂Ȑ��w�Ȃ����������ӂ��A���́q�G�N���`���[���r�Ȃ����q�e�N�X�g�r������v�Ƃ��������Ă���̂ł��B����́A���J�����u�]�|�O�v�̊炷�Ȃ킿���ʂ��A�u�����̍��������邢�̓f���_�̂����A���V�G�N���`���[���v�ɂȂ��炦�Ă��邱�Ƃƃp�������ł��B
�@���͑O�͂ŁA���̂悤�ɏ����܂����B�͂��܂�̌���̋L�����u�������v�i�t�B�M���[���j�Ƃ��ē`����̂��g��܂Ƃ��Ƃh�Ȃ̂ł����āA���̂悤�ȋK��̂��ƂŁu��܂Ƃ��Ƃ��l�I�e�j�[�i�c�̐��n�j���v���l���Ă���̂��ƁB�����Ă���ɂ������̂Ȃ��ŁA���A�lj�ɕ`���ꂽ�����ȑO�̌`�ۂɑ��ăA���h���E������=�O�[���������������u�_�b�����i�~���g�O�����j�v�ƁA�u�t�B�M���[���Ƃ��Ă̂��Ƃv���Ȃ킿�g��܂Ƃ��Ƃh�Ƃ̊W���ǂ��Ƃ炦�邩���A���̈�̃e�[�}�ł���Ə����܂����B
�@���̓����́A�i���ꂪ���ړI���ŏI�I�Ȃ��̂ł͂Ȃ��Ƃ��Ă��A���Ȃ��Ƃ������֎��铹�Ƃ��Ắj�A���łɎ�����Ă���̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B���J�������������O�[�����̋c�_����ď����Ă����悤�ɁA�u�G���當�����������̂ł͂Ȃ��A�\�ӕ�������G���������v�̂��Ƃ�����A�����Ō�����i�����≹���I�����Ƃ̑Δ�����j�g�\�ӕ����h���Ȃ킿�u�t�B�M���[���Ƃ��Ă̂��Ƃv���������I�ȁg���C���[�W�h�Ƃł����Â���ׂ��C���[�W�ȑO�̃C���[�W�A�}�������⃔�@�����[���x��q�̓����̂����Ɍ��ĂƂ����g�ی`�����h�A���邢�͖ؑ��d�M���w�͂��߂ɃC���[�W���肫�x�ɕ`���ꂽ�ϔO��V���{���ɐ旧�g�͂��܂�̃C���[�W�h�����������A���̓����Ȃ̂ł͂Ȃ����ƁB
�@�����āA�i�����摖�������Ƃ������Ă����Ȃ�j�A���̂��Ƃ�����̓I������I�ȏ�ʂŊώ@�ł���̂��A�u�������v�i�t�B�M���[���j�Ƃ��Ắg��܂Ƃ��Ƃh�̓������Ȃ��A���Ǝ��̕��@�ł���A�i���J�����_���d������j����������p�̕\�L�@�ł���A�Ȃǂƌ������Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����ƁB
�@
���\�y�Ƒ����ڗ��Ɖ̕��ꄟ��܂Ƃ��Ƃ̃��J�j�J���ȓW�J
�@
�@��i�ޑO�ɁA���������╔�����J���̋c�_�ɂ������܂��B
�@���J�����u���Ƃ��Ɖ̕���͐l�`��ڗ��ɂ��ƂÂ��Ă���A�l�`�̂����ɐl�Ԃ��g�������̂ł���B�v�Ə����Ă���̂�ǂނ��сA���͘a�ғN�Y�́w�̕���Ƒ����ڗ��x��z�N����̂ł��B�a�҂͂��̏����ɁA�̕���⑀���ڗ��̒ʂ��Ղ̊ӏ҂ɂ����Ȃ��������Ȃ����̂悤�ȏ������������̂���ٖ����Ă��܂��B
�@�a�҂͂Â��āA�{����\�l�F�⒉�b���̂悤�Ȑ��^�����̉̕���ŋ��Ǝv���Ă������̂��u���Ə�ڗ��Ō����ɔ����āe�l�`���������f�̂ł����āA�̕�����҂����������̂łȂ������v���ƂɋC�Â��āu���߂Ă̓b�Ǝv�����v�i7�Łj�Ə����A�u���{�̋Y�Ȃ̂Ȃ��̍ł��Y�Ȃ炵����ނ̂��̂́A�F�e�l�`�ŋ��̋r�{�f�ł���v���Ƃ̂����Ɂu���̋^���������������ł��낤�v�i8�Łj�Ɗ����Ă��܂��B
�@�a�҂������u���v�͂����炭�A���ꂼ��Ɨ������N�������\�y�Ƒ����ڗ��Ɖ̕���́u�\���_�I�Ȃ����\���ϊ��_�I�v�i�╔�b�w�a�ғN�Y�x32�Łj�ȊW���̂����ɂ���̂ł��傤�B�ȉ��A�a�Җ{�́u���_�I�ȍ\�����́v�i����37�Łj��S�����т���A�������̕��͂������܂��B
�@
�������ڗ��̎O�̗v�f��
���\�y�̔ے�Ƃ��Ă̑����ڗ���
���G���e�B�b�N�ȉ̕��Ƃ��Ẳ̕���^�\�y�̏�O���͂��ꂽ���́�
�@�╔�b�́w�a�ғN�Y�����ٕ��������̌`�x�̑��́u���o���ꂽ���v�ŁA��ڗ����ɂ�����u���������������݂����������́v���߂���a�҂̖₢���A�u�l�ԂƐ��E�̑��݂̏@���I�����v�ɂ��������̂Ƒ����Ă��܂��i9�Łj�B
�@�����āA�c�N���̘a�҂ɂ�����u���̒E��̌��Ȃ����߈ˑ̌��ɋ߂����́v�i33�Łj�A���邢�́u�_�ɉB����₷���q���v�ł��������c���j�ɒʂ���u�_�b�I�z���́v�i34�Łj��u���̒E��Ɛ_�B���̑̌��v�i35�Łj�ȂǂɌ��y���������ŁA�u�w�̕���Ƒ����ڗ��x�ꊪ�́A��ʂŁA���O�̍\�z�͂̂������ꂽ�Ñw�ւ̒T���Ɣ����̗��ł���Ɠ����ɁA�����������Ă݂�A���Ҏ��g�ɂ��Ȃ��ΉB���ꂽ�݂�����̐S�̂͂邩�ȉ��s�����ẲʂĂ邱�Ƃ̂Ȃ����Ƃ����������A���ʂŐF�Z�������Ă����ƍl������B�v�i38�Łj�Əq�ׂĂ��܂��B
�@
�@�a�ҁ��╔�̋c�_�́A�u�͂��܂�̌���v�̋L�����t�B�M���[���Ƃ��āA�`�ہA�������Ƃ��ĕێ�����g��܂Ƃ��Ƃh�̃��J�j�J���ȓW�J���A���Ȃ킿�߈ˁ��\�Ӂi�Ӗ��̎���j�̃v���Z�X��������珖�q�������̂Ȃ̂ł͂Ȃ����B���͂���Ȃ��Ƃ��l���Ă��܂��B�ȉ��A���˂������Ȋ���ɂȂ�܂����A���ܖ������������̂܂ܓ��̒��ɉQ�������Ă���g�A�C�f�A�h�߂������̂�f�`���Ă����܂��B
�@
�@�c�c�����ő�����l�`�́u���ʁv�ł���A���̃��J�j�J���ȓ����́u�E��I�Ȝ߈ˑ̌��v���������Ƃ��Č��킷�t�B�M���[���ł���B�t�B�M���[�����Ȃ킿�����A���邢�́u�S�̐��v�i��؞L�j�B
�@���ׂẮg�����āh���Ȃ킿�����̊O�ʓI�ȊW���̒��̃��J�j�J���ȏo�����Ȃ̂ł����āA�����ɂ͂������y���\������u�O�̃G�N���`���[���v�i�������E�o���g�j�̂����̈�A���Ȃ킿���v���i��o���b�������ꂽ�����������Ȃ��B����́u���ʁv����k��o�鐺�ł͂Ȃ��B�����Ɂg����h�͂Ȃ��B
�@�u�߂��݂̉̂����ɋ����Ă��鎞�ɂ́A�߂����p����Ɍ�����v�B���Ȃ킿�\���҂Ɛl�`�́u���y�I�\���v�ɑ����āu�`�ۓI�\���v�����B�R���X�|���_���X�i�|���A����j�ƃA�i���W�[�i�����āA�{�̎��j�ɂ��K���̂��ƂŁB
�@����l�`�́u�ʎ��I�ɁA�l�Ԃ̐�����\������v�G�N���`���[������Ĕ\���҂̃��J�j�J���ȁu���v�Ɖ̕�����҂̃G���e�B�b�N�ȁu�������v�������́u�x��v�����Ă����B�c�c
�@
���܌��M�v�w�����_�x����܂Ƃ��Ƃ̗c�̐�
�@
�@���ƂЂƂA������������܂��B���Ȃ��Ƃ��A�Y��Ă���킯�ł͂Ȃ����Ƃ��A�m�F���Ă��������Ǝv���܂��B
�@��72�͂̍ŏI�߂ŁA���͎��̂悤�ȁu�\���v�����܂����B�܌��M�v�́w�����_�x�́A�u�����ȑO�̏�����Ԃ̌���́u�c�́v��ێ������܂Ƃ��Ƃ̃l�I�e�j�[���i���邢�́u����v�Ƃ��Ă̂�܂Ƃ��Ƃj���߂���c�_�ւƗU�����A���̍��������炦��˒��̍L���Ɛ[���������Ă���v�̂ł͂Ȃ����ƁB
�@�����ŔO���ɂ����Ă����̂́A���Ƃ��w�����_�x�ŏI���́u����ƋL���S���Ɓv�̑��߂ɂ�����u�Β��v���߂���c�_�ł����B
�@�܌��������Ă��邢�����̗�̈����肠���܂��B
�@���킭�A�u���E���n���v�ɁA���[�̐g�̔�����������p���ďq�ׂ�u�c�����Ƃ��Ƃ��������˖��c�v�̂����肪����B�u�����Ɓv�Ƃ����ƁA�N�����u�����Ɓe�����f���������v�Ƃ������A�z����B���Ȃ킿�A�u���̎Β����L���S���Ɍ��т��āv�A���˖��Ƃ�����́u���v�Ɓu�����v�Ƃ������e�o����̂ł���B�u�����̒m�I���ʂɂ͂�����������������Ƃ������Ƃ��͂Ȃ����܂łł��邪�A�����Ƃ������̂͑��݂ȁA���̋L���S���̓��e�Β���p�ɂ܂��Ă͂��߂ĈӖ�������̂ƂȂ�̂ł���B�v�i118�Łj�B
�@�����Ȋ��z���q�ׂ�ƁA���ɂ́A���̂≹�̘A����m�o�����p���������̂ɁA�͂����āu�Ύ��v��u�Β��v�Ƃ������T�O�������o���i���o���j�K�v���������̂��ǂ����A�^��Ȃ��Ƃ��܂���B
�@�����A�܌����q�ׂ��u�����v�i�|���j���A�a�̂̃��g���b�N�ɂ����āA�Ñ�I�E�W�c�I�ȋL���i������j�ɍ����������A��������ՂƂ��Ĕ��W�������̂ł��邱�Ƃ܂���Ȃ�A�u�Β��v�Ƃ́A���Ƃ��ΐ_�̐����V���[�}���̒m�o�̂悤�ȁA�g�R�g�o�h�i�䓛�r�F�j���������痧���������ė���i���邢�͂����֓�������j�ϐ��ӎ���Ԃ�\�����悤�Ƃ��Ă�����̂Ɖ����邱�Ƃ͂ł���Ǝv���܂��B
�@������́w�܌��M�v�x�ŁA���̂悤�ɏ����Ă��܂����B�����܌��́u�a�̔ᔻ�̔��e�v�ɂ����Ă��w�����_�x�ɂ����Ă��A���̌��_�����Ō���ɂ����钮�o�Ǝ��o�̋����o���ہA�u�Β��v��_���Ă���B�܌��͂��̌�A�u�ے�����v�̔������A��q�̋�ʂ����ł��Ă��܂��u�߈ˁv�ɒT��A�u�����w�̔����v�Ƃ����_�l�������p���ł䂭�B��������܌��̌Ñ�w���͂��܂����ƁB
�@
�@�w�����_�x�ɂ��ẮA����A�܌��M�v�ɂ��ẮA�����ƒ��J�ɁA�����Ɛ[���@�肳���čl���Ă��������_�_����������܂��B
�@�v�������Ԃ��̂����s���ɏ�������ƁA���Ƃ��A�w�����_�x�̖`���ŁA�u����́A�����`���̔}��ɂ��l�ނ̊ϔO�\�o�^���̈���ʂł���B�v�ƋL���A�u����\�ۂ̊����́A�������t�ˍ�p�ɂ���āA�ϔO�E�ɉ��ۂ������o�����Ƃɂ���Ă�����v�Ə����ꂽ���Ƃ̎����A�Ƃ�킯�u�������t�ˍ�p�v�Ɓu����v�̊W�B
�@���邢�́A�u�E�����ցE�퐢�ք����ً��ӎ��̋N���v�i�w�Ñ㌤���x�����w�тP�j�ŏq�ׂ�ꂽ�u�ԟ[��`�i������ށj�v�ƃl�I�e�j�[�Ƃ̊W�m���n�B�����u�\�N�O�A�F��ɗ����āA����[�^���̊C�ɓ˂��o���剤����̐s�[�ɗ������A�y���Ȕg�H�̉ʂɁA�킪���̂ӂ邳�Ƃ̂���l�ȋC�����ĂȂ�Ȃ����B�����͂��Ȃ����l�C�ǂ�̊����Ɣډ�����C�ɂ́A���ȂĂȂ�Ȃ��B���͐��A�\�Ă͑c�X�̋�����藧�Ă������S�i�̂���������j�́A�ԟ[��`�i������ށj�Ƃ��āA���ꂽ���̂ł͂Ȃ��炤���B�v
�@�܂��A������w�܌��M�v�x�̂����ۓI�Ȓf�Ђɏo�Ă���u����v�Ɓu���C�t���C���f�L�X�v�Ɓg��܂Ƃ��h�̊W�A���X�B�����u�썰�Ƃ��đ��݂���u���v�ɓ�����A�͂��߂ČÑ�Ƃ����u�L���v���S��̂ł���B�u�j���v�͋L�^����A���������ɑ��݂��Ă��邾���ł͉̂Ƃ��Ă̐����������Ȃ��B���l�ɂ���Ď��ۂɌ������܂��Ƃ��A�͂��߂Đ������������̂ƂȂ�A�ߋ����S�点��c�B�^���݂̉��ƌ��݂̋L���ɓ�����ĉߋ��̈Ӗ��Ɖߋ��̋L�����S��B����̐����Ƃ́A���ƈӖ��̊ԂɁA���ƈӖ��́u���فv���̂��̂Ƃ��āA�܂�͌��݂̎���Ɖߋ��̎���́u���فv���̂��̂Ƃ��ěs�܂��B�Ñ�Ƃ́A�썰�Ƃ��đ��݂���u�j���v�A�̂������郉�C�t���C���f�L�X�Ƃ��Ă̎���ɏh��̂��B�v
�@�����̎����ɂ��ẮA�₢��₢�Ƃ��ĕ��������邱�Ƃ������܂͂ł��Ȃ��̂ŁA�����ł��܂��A�������������ȁg�v���t���h����Y�^�Ƃ��ď����c���Ă����܂��B
�@
�@�c�c�܌��M�v�́u�����v�͑O�c�p���������u���ꊴ��v�A���Ȃ킿�u��N�I���A������v�ɂȂ���B
�@����͉ߋ��̋L���A�܂茾��a���̋L���i���N�I���A�j�Ƃ��Ắu�Ñ�v���ԟ[��`�I�Ɍ��݂ɏo�������A�߈˂����A���邢�͎�������A����������u���C�t���C���f�L�X�v�Ƃ��Ă̎���̊j�S���Ȃ��B
�@�����̋L���i�C���f�b�N�X�j�Ƃ��Ă̎���A�N�I���A�ƒn�����̃R�g�o�A���Ȃ킿�g��܂Ƃ��Ƃh�B�c�c
�@
�m���n���c�����w�쐶�̐��������l�͂Ȃ��̂��A�x��̂��x����B
�i�W�Q�͂ɑ����j
���v���t�B�[����
�����I���i�Ȃ��͂�E�̂肨�j1950�N�㐶�܂�B���Ɍ��ݏZ�B��N���̂ɏ����ꂽ�a�̂̈Ӗ��������ł���̂͂��������Ƃ��B�ł��A�{���Ɂu�����v�ł��Ă���̂��B�����Ɂu�Ӗ��v�Ȃǂ���̂��B�����������t���g���ĉ�����`�B���邱�Ƃ��̂��̂��s�v�c�Ȍ��ۂ��Ǝv���B
Web�]�_���u�R�[���v55���i2025.04.15�j
���F�ƃN�I���A�^�y���\�i�ƚF����W�P�́@���Ƃ��܁^���Ǝ��^�A�C���j�[�i���̂Q�j�i�����I���j
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU�@2025 Rights Reserved.
|
| �\���i�ڎ��j�� |