|
|
|
Web�]�_���u�R�[���v |
|
���n���̎� ���{���̕\���i�ڎ��j�� ���{���̃o�b�N�i���o�[ ���ǎ҂̕Ł^���ӌ��E���z �����e�K�� ���W�҂�Web�T�C�g ���v���C�o�V�[�|���V�[ |
|
���{���̊֘A�y�[�W�� |
|
���u�J���`���[�E�������[�v�̃o�b�N�i���o�[ ���]�_���ula Vue�v�̑��ڎ� |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
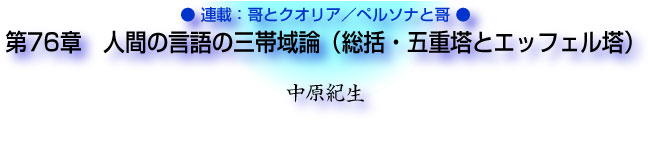
|
|
�i�{�����̉����̓����N�������Ă��܂��B�܂��A�L�[�{�[�h�F[Crt +]�̑���Ńy�[�W���g�債�Ă��ǂ݂��������܂��B��Microsoft Edge�̃u���E�U�[����Ƀ��C�A�E�g���Ă���܂��̂ŁA����ȊO�̃u���E�U�[�ł������������ꍇ�ł́C�啝�ɐ}�`�Ȃǂ������ꍇ������܂��B�j
�@
���d���A���ق̐��̏d�Ȃ�Ƃ��Ă�
�@
�@����܂ł̋c�_�̑��������˂āA���J�j�J���ȑш�ɂ�����l�Ԃ̌���́u�����t���N�^���\���v�i��73�͎Q�Ɓj��O���ɂ����Ȃ���A���T�O�̊K�w�W���A���`�̃��J�j�J���ȑш���Ő�[�i���ցj�Ƃ���d���Ƃ��č�悵�����̂��I���܂��B
�@
�@�@�@�s�}�P�t�d�����l�Ԃ̌�����߂��鏔�T�O�i�K�w�}�j
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���J�j�J���ȑш�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���`�j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ��������������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �y�ܑw�z���J�j�J���ȑш�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���^���`�^�\
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���^���^����j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������������������������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y�l�w�z�l�Ԃ̌���̎O�ш�
�@�@�@�@�@�@ �}�e���A���^���J�j�J���^���^�t�B�W�J��
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@��������������������������������
�@�@�@�@�@�@�@�y�O�w�z�@�@����̎O����
�@�@�@�@�@�@�@�@ ���I����^�l�Ԃ̌���^��������
�@�@�@�@�@�@�@�i�����̌���^�A�_���̌���^�_�̌�j
�@�@�@�@�@�@����������������������������������������
�@�@�@�@�@�y��w�z�@�@�@�@ �S�̎O�K��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����́^�f��^��
�@�@�@�@�@�@�i�M�t�g�^�p�����v�Z�X�g�^�t�B�M���[���j
�@�@�@�@������������������������������������������������
�@�@�@�y���w�z�@�@�@�@�@�@���݂̃��S�X
�@�@�@�@ �i�������j�^�������^�L�����^���_���^�i�ӎ����j
�@
�@�@��������������������������������������������������������
�@
�@��t���̓����i�O�d���j��]���āA�t�F�m���T���u����鉹�y�v�ƌ`�e�����Ƃ��������`���m��1�n������܂����A�����A���̌d���̂����Ɍ��y�d�t�̏d���ȁA���邢�̓N�����l�b�g�d�t�̌y�₩�ȉ��y���A�i�����̌��t�A�d�Ȃ苿���������⋩�т̂���߂����A�ƌ����ׂ����j�A�X�����Ă���̂ł͂Ȃ����Ɗ����Ă��܂��m��2�n�B
�@
�m��1�n�|�������́u�q����鉹�y�r�l�F�ٌ|�p�Ԃɂ����銴�o�̌݊����ɂ��āv�i�w�@����w���{���I�v�E�l���Ȋw�ҁx96���i1996�N2���j�mhttp://doi.org/10.15002/00004605�n�j�ɂ��ƁA����͌�����J���B�V�F�����O�́u���z�͋�Ԃɂ����鉹�y�ł���v�u���z�͂���Ìł������y�ł���v�ɗR������\���ɖ������A�u����������鉹�y�v����n�Ă����͍̂��c�Q�S�ł���B
�@
�@�ȉ��͗]�k�����A�|�����͂��̘_�l�ɂ����ăs�G�[���E�u�[���[�Y�́w�N���[�̊G�Ɖ��y�x����肠���Ă���B
�@���킭�A���̕����͊G��Ɖ��y�ɂ�����u���o�̌݊����v��_���邽�߂̊i�D�̗�ɂȂ�B�u�c�N���[�̍�i�ɂ��ẮA�����Ή��y�Ƃ̊֘A���w�E����Ă������A�ގ��g�A������������ۂɁA���Ƃ��Ή��y�̘a���w�̊T�O��p���āA��i�̏d�w�I�ȕ`�ʂ`�I�|���t�H�j�[�i�������y�j�ƌĂсA��ʂ̒��ł̌`�Ԃ̏d�Ȃ荇���A���������A�J��Ԃ��A�y�����A��������������Ă���B���ہA�u�[���[�Y�Ɍ��킹��A�u����قǃ|���t�H�j�[�ɍ���������i�͋H�v�Ȃ̂ł���B�v
�@�܂��A�u�[���[�Y�́u���[�c�@���g�͂����炭�N���[�̊��ɂ����Ƃ��߂������y�Ƃ������Ƃ����A�u��̐������ƈ�{�̕`���Ƃ͓������v�̎�����A�ނ́u�N�����l�b�g�d�t�ȁv�c�̊ɏ��y�͂ɂ�����N�����l�b�g�̐����ƃN���[�̑�����������ꂽ�Ɠ��Ȑ��`�Ɂc���Ă���v�B
�@
�m��2�n�ʋ{��Y���́w���y�̕s�v�c�x�ŁA���z�Ɖ��y�̋��ʐ���_���Ă���i��ꕔ��\�O�́u�\���i���j�������̐×͊w�Ɠ��͊w�v�������̏͂́u�g���z�͓���鉹�y�ł���h�Ƃ����L���Ȍ��t������B�v�̈ꕶ����n�܂�j�B
�@���킭�A���z�|�p�Ƃ͐l�Ԃ̏d�͂Ƃ̓����̕\���ł���B�u���̔������S�V�b�N���z�A���̊j�S�ł���A�[�`�A����́A�Ƃ����ޗ����������A�d�͂ɂ����ɏ����邩�A�Ƃ������Ƃɑ���݂��Ƃȉ����̕\���ł���B�v�i172�Łj
�@
�s�Α����z����ł͂Ȃ��A�����̓��̔������B����͖؍ނƂ����ޗ����������A�d�͂Ɠ����āA�����ɓV�ɋ߂Â������Ƃ������Ƃ́A��͂�݂��Ƃȕ\���ł��낤�B�ƖƂ̂��������A�S�V�b�N�̉����ƌd���Ƃ̂��������`��ł���̂����A���{�͏d�͂ł���A����������ɂ����Ƃ߂邩�Ƃ����͊w�ł���B�i���j
�@���y���܂������Ȃ̂ł���B
�@���鉹�̎��ɕʂ̉����Ȃ�B���X�Ɖ�������o�āA���鉹�ł��߂�������B���ꂪ���y�ł��邩��ɂ́A���Ƃ̉����O�ɖ������������Ƃ߂�A���z�ʼn��w����w�������Ƃ߂�悤�ɂ����Ƃ߂�B���邢�͂����Ƃ߂��˂ĉ��̐����̂悤�Ȃ��̂�������A������܂Ƃ߂āA��������Ƃ����Ƃ߂�悤�ȉ�������ɂ��ƂɂЂ�����A��������̒����܂Ƃ߂ė����Ђ�������悤�ɂ����Ƃ߂鉹�������B���������悤�ɉ��y�͂ł��Ă���킯�ł���B
�@���y�ɂ����鎞�Ԃ̑O��́A���z�ɂ�����㉺�W�̂悤�Ȃ��̂ɂȂ��Ă���B�d�͂̕����͏ォ�牺�ւƂ��܂��Ă��āA���̂��߂Ɍ��z�͏㉺���t�ɂł��Ȃ��B
�@�ł͌��z�ɂ�����d�͂ɑ���������̂́A���y�ɂ����Ă͉��ł��邩�B�t�i�w���y�̕s�v�c�x173-174�Łj
�@
�@�����Œ��҂́A�g�\�h�̉������āg�h�h�̉�����ƈ�������������̂ɁA�g�h�h�̉����������Ɂg�\�h�̉��������Ƃ܂��������Ă��Ȃ��Ђ炩�ꂽ���������̂͂Ȃ����A�Ɩ₤�B�����āA���́u���y�̍��{�ȕs�v�c�v�́u���R�{�����ہv�ƊW������Ǝw�E����B
�@�g�h�h�̉�����ƁA���F�ɂ���ẮA���̉������łȂ��{���g�\�h�~�V��h�Ȃǂ̉����܂����Ă�������B�g�\�h�Ȃ�g���\�V�t�@�h�Ȃǂ������ɂ�������B�u�������Ă݂�Ɓg�\�h�̂��ƂɁg�h�h������ꍇ�ɂ́g�\�h�̉��̔{���̒��Ɂg�h�h�̉����Ȃ����߂ɁA���Ƃ��猻����g�h�h���{���ɐV�N�Ɋ�������̂ɑ��āg�h�h �̂��ƂɁg�\�h�����鎞�ɂ́g�\�h�́g�h�h�̔{���Ƃ��Ă��炩���߂�����Ă��܂��Ă��邽�߂ɁA�V�N�Ȋ����������Ă���̂����R�ł͂Ȃ����ƍl������B�v
�@���̂悤�ɁA�u���Ƃ��炭�鉹���O�̉��������Ă������ɂƂ��ĐV�N�Ȋ��������Ƃ������Ƃ��A���Ԃ���ւ����ފ����ނ��߂ɕK�v�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��̂��ƍl������v���Ƃ���A���҂́A�u���z�ɂ�����d�̖͂�ڂ��A���y�ɂ����Ă͎��Ԃ������Ă���Ƃ����āA���������������ł͂���܂��v�i175�Łj�ƌ��_�Â��Ă���B
�@
���G�b�t�F�����A�����ȕ����Ƃ��Ă�
�@
�@�d�����Ìł������̏d�Ȃ�ł���Ƃ�����A�G�b�t�F�����͈Ӗ��������悹�鏃���Ȍ`�������ł���B�����ȉ��A�u��Ղƒ���A�܂���n�Ƌ�A���̓�����т��邱�Ƃ������@�\�Ƃ��Ď��v�u�ȕ\���i�L���j�v���߂��郍�����E�o���g�̌��t���A�w�G�b�t�F�����x�i�@���߁E���c�a����A�����܊w�|���Ɂj��������܂��B
�@
�����R���ۂƓ����Ӗ��ł̕���
�@
�s�c���͂˂ɂ����ɂ���B�c����͐�͂Ȃ݂ɁA�Ђ������łɓ��퐶���ɍ��̂��đ��݂��Â��Ă��āA�����ɂ��̈Ӗ��������˂邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A�������ǂ����炪���悤���Ȃ����݂��Ă���Ƃ����_�ŁA���R���ۂƓ����Ӗ��ł́e�����f�ƂȂ��Ă���B�t�i�w�G�b�t�F�����x7�Łj
�@
����n�Ƌ�����т���ȕ\��
���\���ԁi�����j�ł���Ɠ����Ɏԁi�����j
�������̗�������L���銮�S���A�����ɈӖ����Ђ��悹��`
������Ԓ��́i�p�m���}�I�j���E�A��̒��ہi�\���j���Ȃ킿�m�o�`���̓��̉�
�@����ȏ�̐[�x�́i�������Ă��j�ł��Ȃ��̂ŁA�����ł͕\�w�I�Ȍ��t�E�݂ɂƂǂ߁A����}���܂��B�i����ɂ��Ă��A�������E�o���g�̎v�l�͔������B�j
�@��_�����w�E���Ă����ƁA�d���ɂ�����u���v�i����鉹�y�j���A�O�X�͂́s�}�Q�t�́u���ق̐��v���u�߁A�I�m�}�g�y�v�ɑΉ����Ă���Ƃ���A�G�b�t�F�����́u��l�̂̕�����ԁv�ɂ�����u���������v�i�ȕ\���j�ł���B���͂��̂悤�ɍl���Ă��܂��B
�i�������܂������ƈ�A���n�Ȏv�������������߂Ă����B����Ԓ��̃p�m���}�I���E�́A����̒a���Ɛl�Ԃ̓��ʋ�Ԃ̔����ɂȂ���u�n�����v�̑̌�������B���̎��E�������炷���́i�g�{�����������u�p���C���[�W�v�H�j�����A�ŌÂ̌��ꂪ�����炵���̌��i�o���g�������u��̒��ہv���邢�́u���f��̌��v�Ƃł��H�j�������̂ł͂Ȃ����B�j
�@
���d���ƃG�b�t�F����
�@
�@�O�X�߂Łu�l�Ԃ̌�����߂��鏔�T�O�̊K�w�}�v����}���Ă����Ƃ��A���̔]�����悬���Ă����̂́A�u���̐}�͖{���A�㉺�]���|�������������Ȃ��d���ƁA���̑��ւɂ����āi���傤�Ǎ����v�̂悤�Ȍ`�Łj�q�������o�g�}�łȂ���Ȃ�Ȃ��v�Ƃ����g���z�h�ł���A�u�m������Ɠ������Ƃ��A���čl�������Ƃ�����͂����v�Ƃ����g�C�Â��h�ł����B
�@���e���u�����v���Ă݂�ƁA�������ɑ�71�͂́s�}�P�t�ŁA���́A�䓛�r�F�́u�ӎ��̍\�����f���v���x�[�X�ɂ��āA�u��Ζ��v�i�`�����I�u�����߂P�v�j���N�_�Ƃ��镧���I�i�����I�B���I�j�ȏ�����̃��f���ƁA�v���e�B�m�X�́u��ҁv�i�`����I�u�����߂Q�v�j�ɔ����鉺�����̃��f�����A�i�w�����킹�̓�̂̔�����V�ł͂Ȃ��A�������]�ɂ���Ă���g�����킹�h�ɂȂ����㉺�̑o�g�̂̂��Ƃ��j�d�ˍ��킹�Ă��܂����B
�@���́u�l�Ԃ̌���̓�_�@�ƎO�ш�iVer.4�j�v�̐}���A�����ł̋c�_�ɂ������ĕό`���H���Ă݂�ƁA���̂悤�ɂȂ�ł��傤�B�i���}�́u�l�P�E�l�Q�v�͕\�w�ӎ��i�䓛���u�`�v�ƕ\�L�����̈�A���̌�b�ł́u���J�j�J���ȑш�v�j�Ƃa�̈�Ƃ̒��Ԓn�сi�C�}�W�i���ȃC�}�[�W���̏ꏊ�j���A�u�a�P�E�a�Q�v�͐[�w�ӎ��i�b�{�a�{�l�j�̂�������A�������̗̈�A�u�b�P�E�b�Q�v�͖��ӎ��̗̈�����ꂼ��w���B�j
�@
�@�@�@�s�}�Q�t�d���ƃG�b�t�F����
�@�@�@�@�@�@�@�@���l�Ԃ̌���̓�_�@�ƎO�ш�iVer.7�j
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �ӎ����@�@�@�@�@�@�@ �y���w�z
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ᖳ���߂Q��
�@�@�@�@�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�` �Z �`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�Q
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ���@�@�@�@�@�@ �y��w�z
�@�@�@�@�@�@�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�a�Q
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��������@�@�@�y�O�w�z
�@�@�@�@�@�@�@�@��������������������������������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�l�Q
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���^�t�B�W�J���ȑш�y�l�w�z
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������������������������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �i�\�j
�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@���J�j�J���ȑш�y�ܑw�z
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ��������������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@���J�j�J���ȑш�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i���`�j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ ��������������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �y�ܑw�z���J�j�J���ȑш�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �i���j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@������������������������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�y�l�w�z�}�e���A���ȑш�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�l�P
�@�@�@�@�@�@�@�@��������������������������������
�@�@�@�@�@�@�@�y�O�w�z�@�@�@���I����
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�a�P
�@�@�@�@�@�@�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
�@�@�@�@�@�y��w�z�@�@�@�@�@ ������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�b�P
�@�@�@�@�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�` �Z �`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ᖳ���߂P��
�@�@�@�y���w�z�@�@�@�@�@�@�@ ������
�@
�@�}���́A���z���ꂽ�i�{�������ŖڂɌ����Ȃ��j�㔼�g�������ɕ��s�ړ����A�����S���g���X�\���������ĉ��������i�������A�d�͂̊W�ŏ㉺�̌`���t�]�����j���������G�b�t�F�����ɂق��Ȃ�܂���m���n�B
�@�O�߂ŁA���́A�d�����u���ق̐��v���Ȃ킿�u�߁A�I�m�}�g�y�v�i�������́u�^���v�j���Ì����������̂ł���Ƃ�����A�G�b�t�F�����́u��l�̂̕�����ԁv�ɐ͏o�����u���������v�ɊY������Ə����܂����B���̂��Ƃ��A���߂ŁA�䓛�r�F�̋c�_�����p���āA�m�F���Ă��������Ǝv���܂��B
�@
�m���n���̂��Ƃ��71�͂́s�}�R�t���g���ĕ\�킷�ƁA���̂悤�ɂȂ�B
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@ �m���^�n
�@�@�@�@��������������������������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@�@�@�@�@�@ �U �@�@���@�@ �T
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@�m���n���������������������������m���n
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@�@�@�@�@�@ �V �@�@���@�@ �W
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@�@�@�@��������������������������
�@�@�@�@�@�@�@�@ �m��^�n
�@
�@���T�F�����C�}�[�W���F�_�́q���r
�@�@�U�F���^�C�}�[�W���F�����������G�b�t�F������
�@�@�V�F�͕�C�}�[�W���F�ی`����
�@�@�W�F��^�C�}�[�W���F���ق̐��i�߁A�I�m�}�g�y�j���d����
�@
���^�������̌���N�w�ƃC�X���[�������_���`�i�O�i�j
�@
�@�䓛�r�F���u�Ӗ����ߗ��_�Ƌ�C�����^�������̌���N�w�I�\����T��v�i��g���Ɂw�Ӗ��̐[�݂ք������m�N�w�̐��ʁx�j�Ř_�������ƁB
�@
�P�D���݂̓R�g�o�ł��鄟�o���I�����̖��
�@
�@�䓛�͂��̘_�l�ŁA�^�������̌���N�w�I�v�z�̒��j���A�u���݂̓R�g�o�ł���v�Ƃ�����������̌`�Œ���i269�Łj�B�����Ă��̂��Ƃ𗝘_�I�ɁA���Ȃ킿�Ӗ����ߗ��_�����u��X�����ʁA��ꎟ�I�o�����^�Ƃ��ĎƂ߂Ă���u�����v�́A�{���͉�X�̈ӎ����A����I�Ӗ����߂Ƃ�����I�����ʂ��đn��o�������̂ɂ����Ȃ��v�i277�Łj�����̊ϓ_����𖾂��Ă���B
�@���̓��B�_�́A�u��X�̌���ӎ��̐[�w�ɗV������u�Ӗ��v���A�l�X�ɈقȂ�`�A�l�X�ɈقȂ�x���ɂ����āA���݊��N�I�G�l���M�[�Ƃ��ē����Ă���v�i288�Łj�̈�A�܂�u����A�������v�ł���B
�@�䓛�́u�[�w�I�Ӗ��G�l���M�[�v�̖��Ɋ֘A���āA�u�V�j�t�B�A���ƃV�j�t�B�G�Ƃ̊ԂɁA���Ƃ��Ē������`�ŊŎ悳���s�ύt���v�Ɍ��y���A�u�{�_�̂��̌��ŁA���ܖ��ɂȂ�̂́A�c�V�j�t�B�G�̑��ɋN����ُ펖�ԁA���Ȃ킿�A�l���悭�A�R�g�o�̈Ӗ��I���ʂɊ��m�����m��ʐ[���̂��Ƃ����́m��F�k�~�m�[�[�n�̂��Ƃł���v�Əq�ׂĂ���B
�@
�Q�D���݂̓R�g�o�ł��鄟�َ����̃R�g�o�̃��x��
�@
�@�V�j�t�B�G�̑��ɋN���邱�Ƃ̓V�j�t�B�A���̑��ɂ��N����B�������āA�c�_�͓��팾��̃��x���A���Ȃ킿�o���I�������Ă����B
�@�ȉ��A�َ����̃R�g�o�́u�F���I�X�P�[���̑n���́A�S�F���ɂЂ낪�鑶�݃G�l���M�[�̂悤�Ȃ��́v�i289�Łj���߂���c�_���Â��̂����A�����ł́A���́g�d���h�ɂȂ����C�́w���������`�x�ƁA�g�G�b�t�F�����h�Ɍ��т��čl���邱�Ƃ��ł���C�X���[���̕����_���`�ɂ��ďq�ׂ�ꂽ���͂������B
�@
�Q-�P�D�^�������̌���N�w���w���������`�x
�i���ʂ������͉��ʓI�Ȃ��̂��߂��鎄�́u���_�v�ɂ��ƁA�����ɕ`���ꂽ�����̌��������A���i�n�ہH�j������͉̂��ʂ̌����`�Ԃ������͌���I�Ȃ��̂Ȃ̂����j�A�䓛�͂����Łw���������`�x�́u���O�̕��C�A�킸���ɔ�����A�K�������𖼂Â��Đ��Ƃ����Ȃ�v�������A�Â��āu�ܑ�ɂ݂ȋ�����A�\�E�Ɍ������v�������Ă���B
�Q-�Q�D�t�@�Y���E�b�E���[�̕����_���`�I���E��
�@���̕s���A�s�G�́A�l�ԂɂƂ��Ă͖��ɂЂƂ����_�i�F���I���݃G�l���M�[�j�́A���́i�@���L�����̃R�g�o���A�����A���t�@�x�b�g���B���������i�����́u���v�j�ւƒi�K�I�ɐi�ށj�u���Ȍ����̈ʑw�v�ɂ����āA���̖{�̂ł���R�g�o����I�悷��i297�Łj�B
���^�������̌���N�w�ƃC�X���[�������_���`�i��i�j
�@
�@��C�̌���N�w�ƃt�@�Y���E�b�E���[�̕����_���`���߂���䓛�r�F�̋c�_���A��⋭���ɁA�d���ƃG�b�t�F�����̐}�̂Ȃ��ɗ��Ƃ�����ł݂܂��B
�@
�@�@�@�s�}�R�t�d���ƃG�b�t�F����
�@�@�@�@�@�@�@�@���l�Ԃ̌���̓�_�@�ƎO�ш�iVer.8�j
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�_�̃R�g�o�i�_�̐��j
�@�@�@�@�@�@�@�@�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`
�@�@�@�@�@�@�@���L�����̃R�g�o
�@�@�@�@�@�@�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
�@�@�@�@�@�@�����A���t�@�x�b�g
�@�@�@�@������������������������������������������������
�@�@�@�@�@���������i�����̐��j
�@�@��������������������������������������������������������
�@�@�@�@��������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��������
�@�@��������������������������������������������������������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���i���f�j
�@�@�@�@������������������������������������������������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@�@�@�@�@�@�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@�@�@�@�@�@�@�@�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@
�@��_�A�⑫���܂��B
�@�}���Ɂu���i���f�j�v�Ƃ���̂́A�|���q�j���w��C�̌���N�w�����w���������`�x��ǂށx�̉���Ɋ�Â��Ă��܂��B���Ƃ��A�w���������`�x�u�ߖ��v�̈�߁A�u���̏\�E���L�̌���A�F�Ȑ��ɗR���ċN����B���ɒ��Z�������C���ȗL��B����m����n�Ɩ��Â��B���͖����ɗR��B�����͕���҂B�̂ɏ��̌P�ߎҁA�������Ɖ]���́A�W�����̕s�����҂����̂݁B���ꂷ�Ȃ킿�����̕����Ȃ�B�v���߂����āA�|�����͎��̂悤�ɉ�����Ă��܂��B
�@�@�@�@�@��
�@�]�k�A���̈�B�|�����͓����̑�́u�䓛�r�F�̋�C�_�ɂ��āv�ŁA�u�Ӗ����ߗ��_�Ƌ�C�����^�������̌���N�w�I�\����T��v��ᔻ�I�Ɏ�肠���Ă���B
�@���́A�|�����̒������瑽���̂��Ƃ��w�i�{�e�ɔ��f�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��������j�B���̈䓛�ᔻ�ɂ������͂������Ă���B���������̏�ŁA���邢�͂���ȏ�ɁA�䓛���g���_�l�̖`���ɒԂ����헪�I�E�n���I�ȁu��ǁv�Ƃ����A�e�N�X�g�́u�ǂ݁v���߂���錾�ɁA��苭���䂩��Ă�����B
�@
�@�]�k�A���̓�B�w�Ӗ��̐[�݂ցx�̕��ɉ���ŁA�ē��c�T�����u�䓛���m�N�w�̊�{�I���i�v���߂�������w�E���Ă���B
�@���킭�A���m�N�w�ɒʒꂷ��\���̈�Ƃ��āA�䓛�́u���E�̋��ϐ��v�̓��@��������B�Ƃ��낪�A�u�Ӗ����ߗ��_�Ƌ�C�����^�������̌���N�w�I�\����T��v�ň䓛�́A�^�����������̗B��̗�O�Ƃ��Ĉʒu�t���Ă���B�Ȃ��Ȃ�A�������̐����邱�̐��E�̂��ׂẮA���ɂ̑��݂������@���̌��R�g�o�̌����̂ł���A����������@�����̂��̂��R�g�o�i���Ȃ킿�u�^���v�j������ł���B�i378-379�Łj
�@�����A�������Ƃ���ƁA��̓��@�͂ǂ��Ȃ�̂��B�B���E���ρE�T�̕����N�w�A�}�[���[���w�E����C���h�N�w�A�����𐢊E�̐^���ƌ���V���A����炷�ׂĂ�����Ă������ƂɂȂ�̂��B�u�䓛�͂��̖��ɍŏI�I�Ȍ�����^���Ă��Ȃ��B�ނ̓��ɂ́A�T��u���̂̂��͂�v�ɑ��鋤�����܂��ԈႢ�Ȃ����݂���B�����ł���A�Η�����悤�Ɍ����邱����̓��@���ǂ̂悤�ɑ��������悢�̂���_���Ȃ���Ȃ�Ȃ��͂����B�v�i380�Łj
�@�֓����͂����ŁA�����s�\�Ɍ�������̗̂����\�����A�t�b�T�[�����烁�������|���e�B�ւƎp���ꂽ�u��t���v�iFundierung�j�W�����u���E���̑��ݎҊԂɂ͈����̊K�w�W�����藧���Ă���̂����A����͉��̊K�w����̂���̑������u�x���v�A�����̂悤�ɂ��đ��������̊K�w�����̂�����u��ށv�Ƃ����W�v�i383�Łj�����̓��ɊłĎ��B
�@���Ȃ킿�A�ЂƂ��ь���I���߂Ɋ�Â����ݒ��������������Ȃ�A���̑������x���邷�ׂĂ͂��̌���̍쓮�����Ɂu��܂�v�Ďp�����킷�B����ɐ旧���đ��݂��Ă����͂��̂��̂́u�挾��I���߁v�Ƃ��āg����I�ɕ��߉�����āh�̂݁A���݂���̂ł���B
�@�����_�Ƃ�����Ύ҂̉��ł̐��E�n���̏�ʂɒu���ڂ��Ă݂�A�n���ȑO�́u���v�͂��̂܂܂̌`�Ŏp�����킷���Ƃ͂Ȃ��A�u���܂������̂ł��Ȃ��Ƃ���̉����v�Ƃ��āA���Ȃ킿�u�J�I�X�v�u���ׁv�u��v�Ƃ��ċK�肳��Ďp�����킷�B�u�挾��I�v���u����I�v�ł��邱�Ƃ̈�l�Ԃł������悤�ɁB�i387-388�Łj
�@�����Ŏ��̖₢�����シ��B�u�u���v�͂����܂Łu��v�̉�����Ɉʒu���邻�̋Ɍ��Ȃ̂��A����Ƃ��u��v�Ƃ͌���I�ɋ�ʂ��ꂽ�E����Ƃَ͈��̎������w���������̂Ȃ̂��v�i390�Łj�B�䓛�ɂ����āA�u���v�́u��v�̉����ȊO�ł͂Ȃ������̂����A���̂悤�Ȏ��Ԕc���͂͂����Ď����ɑ��������̂Ȃ̂��B�u��v�Ƃ͎����̈قȂ�u���v�Ɍ������Ďv�l��i�߂邽�߁A�u���v�Ƃ������Ԃ��ʘH�ƂȂ肤��̂ł͂Ȃ����B�����ȉ��A�ē��c�T�Ǝ��̎v�����W�J�����B
�@���ɑ��铌�m�N�w�̑Ή��͊T�ˁu��炩�v�ōm��I�Ȃ��̂ł��鄟���u�\�w�ɂ����ē���̈�l���Ƃ��ĕ��߉�����Ďp�����킵�������A�����Ƃ��ĕ��߉�����Đ��E���p�����킷�ȑO�Ɉʒu����[�w�̎����i���́u���݃G�l���M�[�v�̉�A���Ȃ킿�u���ׁv�j�ɖ߂��čs�����ƈȊO�ł͂Ȃ��v�i391�Łj�����̂ɑ��āA���m�̂���͗l�����قɂ��Ă���B
�@�֓����́A�w���݂Ǝ��ԁx�Ŏ��ɏW���I�ȕ��͂��������n�C�f�K�[���A���̂悤�Ȓ[�I�ȁu���v�A�u�ǂ��ɂ��Ȃ��v�u���v�Ɍ������������\�������邱�Ƃ��w�E���A���̂悤�ɏq�ׂĂ���B�u���̌����ȈӖ��ł́u���v�Ɏv�l���G�ꂽ�Ƃ����߂āA���́u���݃G�l���M�[�v�̍��ꐫ�����Ή������B�S���m�N�w�̈���̍��{���@���������ׂĂ������ł���\���́A���̒n�_�Ɏ����ď��߂Ďv�l�̎����ɂȂ�̂ł͂Ȃ����B�v�i394-395�Łj
�@
�@�]�k�A���̎O�B�i��ώ��� Twitter �Łu�䓛�r�F�͒P�ɓN�w�̑f�l�ł���ɂ����Ȃ��v�i2021�N10��15���j�Ə����Ă���B������|�̂��Ƃ����x����������Ă���B�u�����N�w�I�Ӌ`��S���ے肵�����̂͂ނ���w�ӎ��Ɩ{���x���n�߂Ƃ���䓛�r�F�̏����B�C�X�����w�I�ɂ͒m��Ȃ����N�w�I�Ӌ`�͊F���ł���B�v�i2021�N10��14���j
�@�ᏼ�p�㎁�̔����u�g�{�m�����n�̌���ρA�{���_�́A�䓛�Ƌ������U����B�v�ɑ���i�䎁�̃c�C�[�g�B�u�g�{�ƈ䓛�̌���ς̋��U�͌d�Ⴞ�I�@�������A�͂������莄�̈ӌ��������Ȃ�A��l�Ƃ��N�w�I�ȃZ���X���i���Ɏ����悤�Ȏd���Łj�S���Ȃ��B�����Ƒ@�ׂɓ��I�Ȏu���W�i���j��T���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ���ŁA���ׂĂ��Ɏ��̓I�ɐςݏd�˂Ă����Ă��܂��B�v�i2019�N1��29���j
�@���邢�́A���̔����B�u�䓛�Ƃ����l�́A��w�҂Ƃ���Ă��邪���̓V���[�}���̂悤�Ȑl�������̂ł͂Ȃ��낤���B�܂��ɂ���䂦�ɁA���̏@���I���ς͈ȊO�ȂقǕ��ŁA��͂�����ۂ��B�v�i2014�N2��1���j
�@�i�䎁�͂܂��A�u���������ƎႩ������A�A���r�A����w��ŃC�X�����N�w���������邾�낤�B�v�i2017�N4��18���j�A�Ȃ��Ȃ�u�C�u���E�X�B�[�i�[���D��������ł��B�v�i2021�N8��21���j�Ƃ������Ă���B
�@�������́A�g�{�����ƈ䓛�r�F�Ɖi��ς��A�����g���������킹�Ă���u�މ����\�v�ɂ��������āA�悭�����Ε��@�I�u��ǁv�̂��Ɓu�����Ɏ��̓I�ɐςݏd�˂āv�A���̘_�l�Q�������Ă���B������i�Ƃ����ڑ����͂����������j�A�i�䎁�̔����̐^�ӂ�������悤�ȋC������B
�@
�@�䓛�r�F�̒����͕��w��i�ł���B�w�_��N�w�x�͂قƂ�ǒ��ҝR��ł���B���͉����`�B���Ȃ��B��������ɂ���ď��q�������͕ҏW���ꂽ�����`���̂��B���o�̈Ӗ����l���Ȃ��珥���Ă͗L��������B�r�[�ɑދ�����B����Ɠ����ŁA�䓛�r�F�̖{�͑ދ����B�������Ƃ��J��Ԃ�������Ă��邪�����`�B���Ȃ��B�u�����v�ƌ����Ă������B
�@���|�A���A�f��A���y�A���w��i�͉��x�ڂ��Ă��ދ����Ȃ��B���x�ڂ��Ă��ދ����Ȃ����̂��|�p��i�ƌ����B���������Ӗ��ł́A�䓛�r�F�̏����͌|�p��i�ł����ēN�w�I�v�҂̏����ł͂Ȃ��B�N�w�I�v�҂̏����ł͂���̂����A�^���̓N�w���ł͂Ȃ��B
�@�䓛�r�F�́u�V���[�}���̂悤�Ȑl�v�Ȃ̂��B�V���[�}���Ȃ̂�����A������邩�ł͂Ȃ��䓛�r�F���u���v���ƁA���̐��i���U��j�ƕ\��i�ʐU��H�j�Ɛg�U��ɈӖ�������̂��B
�@���́A�ē��c�T���������u�[�I�Ȗ��v�́A�i�䎁����s���`���̌����u�������i�A�N�`���A���e�B�j�v�̊E��ɂ�����̂��ƍl���Ă���B�V���[�}���E�䓛�r�F����鎖���́A�{�l���C�Â��Ă��邩�ǂ����͕ʂƂ��āi�����炭�C�Â��Ă��Ȃ��A�Ȃɂ���V���[�}���Ȃ̂�����j�A���́u���v�̊E��i������̌������j�ɑ����Ă���B���͂����v���B
�@
�i�T�Q���ɑ����j
���v���t�B�[����
�����I���i�Ȃ��͂�E�̂肨�j1950�N�㐶�܂�B���Ɍ��ݏZ�B��N���̂ɏ����ꂽ�a�̂̈Ӗ��������ł���̂͂��������Ƃ��B�ł��A�{���Ɂu�����v�ł��Ă���̂��B�����Ɂu�Ӗ��v�Ȃǂ���̂��B�����������t���g���ĉ�����`�B���邱�Ƃ��̂��̂��s�v�c�Ȍ��ۂ��Ǝv���B
Web�]�_���u�R�[���v51���i2023.12.15�j
���F�ƃN�I���A�A�^�y���\�i�ƚF����V�U�́@�l�Ԃ̌���̎O�ш�_�i�����E�d���ƃG�b�t�F�����j�i�����I���j
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU�@2022 Rights Reserved.
|
| �\���i�ڎ��j�� |
