|
|
|
Web�]�_���u�R�[���v |
|
���n���̎� ���{���̕\���i�ڎ��j�� ���{���̃o�b�N�i���o�[ ���ǎ҂̕Ł^���ӌ��E���z �����e�K�� ���W�҂�Web�T�C�g ���v���C�o�V�[�|���V�[ |
|
���{���̊֘A�y�[�W�� |
|
���u�J���`���[�E�������[�v�̃o�b�N�i���o�[ ���]�_���ula Vue�v�̑��ڎ� |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
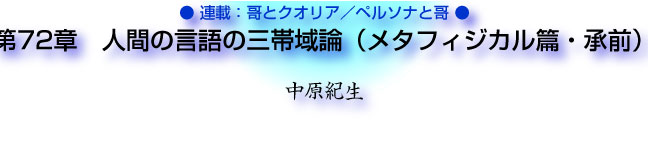
|
|
�i�{�����̉����̓����N�������Ă��܂��B�܂��A�L�[�{�[�h�F[Crt +]�̑���Ńy�[�W���g�債�Ă��ǂ݂��������܂��B��Microsoft Edge�̃u���E�U�[����Ƀ��C�A�E�g���Ă���܂��̂ŁA����ȊO�̃u���E�U�[�ł������������ꍇ�ł́C�啝�ɐ}�`�Ȃǂ������ꍇ������܂��B�j
�@
�������E���`�E����Q�[���i�P�j�����^�t�B�W�J���сi����E���j
�@
�@��69�͂́s�}�Q�t�ŁA�x�����~���́u�����i�trsprung�j�v���u�A�E���v�ƑΔ䂳���Đ}�́u�����v�Ɉʒu�Â����B���̂��Ƃ����܂��ɂ������肱�Ȃ��B�u�㉺�̃Y���v�������Ă��Ȃ����C�ɂȂ��Ă���B���̓_���čl���邽�߁A�܂��x�����~���̕��͂������Ă݂�B����������l�̒�������̑������̂������ŁB
�@
�������i���Y���j�Ƃ��Ă̍����A��Ɣ�����
�@���L�B����e�ō폜���ꂽ�u���_�v���e�ɁA�x�����~���͎��̂悤�ɒԂ��Ă���B�u���ׂĂ̍����I�Ȃ��̂͌[���̖������̕����ł���B�c�c�����I�Ȃ���̂��ꎩ�̂́A����������ł͌[���̕����m�������������p�Ғ��n�Ƃ��āA�����ł͂��̕����ɂ����ĕK�R�I�ɖ������̂��́m��n�Ƃ��ĔF�������d�̓��@�ɂ������炩�ɂȂ�͂��Ȃ��̂��v�B�i�g�c�O��u���@���^�[�E�׃����~���ɂ�����u�����v�ɂ��Ă̈�l�@�����Q�[�e�́u�������ہv�ւ̂��������߂����āv�mhttp://hdl.handle.net/2115/25955�n�ɂ��B�j
�@
���C�i���C���j�Ƃ��Ă̍����A�j��Ə�
�@���L�B�u���Ƃv�Ɋւ��āA�R�����͎��̒���t���Ă���B�u�����̌���_��w�h�C�c�ߌ��̍����x�ɂ����āA�u���Ƃi�vort�j�v�͖��̌���A���Â��錾��̃p���_�C�X�I�ȏ�Ԃ̂����ɂ���A�Ƃ�킯�u���ꐸ�_�̑߁v�ȍ~�́u���ې��v��тсA�u�Ӗ��v�킳�ꂽ����i�Ƃ�킯�u�����i�rchrift�j�v�j�ɑ��āA�u�����i�kaut�j�v�̒��ڐ��Ƃ������������������Ă���B�v�i261�Łj
�@
�@�����u���O�v�Ɓu�����v�Ɓu���j�v�i���j�I���E�A�����I�Ȃ��̂̐��E�j�̑��݊W�A���邢�́i���������N�w�I�Ɍ��������āj�u���v�i�A�E���j�Ɓu���Ƃv�i���Y���E���C���j�Ɓu����v�i�Ӗ��̖q�̓I�ȘA�ցj�A�������́u�A�_���̌���v�Ɓu�V�g�̌���v�Ɓu�l�Ԃ́i���j����v�̑��݊W���߂����āA��̍\�}���l���邱�Ƃ��ł���B
�@���Ȃ킿�A�u�����^���j�^���O�v�̂悤�Ɂu�����v���u�����v�Ɉʒu�Â���\�}�i��69�͂́s�}�Q�t�ō̗p�������́j�ƁA�u���j�^�����^���O�v�̂悤�ɍ������u����v�ɁA�Ƃ������u���w�v�̒��Ԓn�тɈʒu�Â���\�}�B���̍\�}�́A�u���j�������v�̉��~�i�j��j�Ɓu���������O�v�̏㏸�i�j�̓��Ԃ��\������Ă��Ė��͓I�����A�����ł́i�x�����~����������_�̐_�w�I���i�ɑ����āj���̍\�}���̗p�������B
�@
�@�@�@�s�}�P�t���j�E�����E���O
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Z
�@�@�@�@�@�@�@�@ �ᗝ�O��
�@�@�@�Ác�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
�@�@�@�@ �i�[���j ���@��
�@�@�@�@�@ �@���p ���@���u�v
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@��
�@�@�@�@�@�@ �y�C�i���C���j�z
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@��
�@�@�@�@�u�������v���@��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@��
�@�@�@�������� �፪���� ��������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@�@�@�@�u��v�@��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@�@�@�@�@�@ �y���i���Y���j�z
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@�@�@�@�@�@�@���p�@���@�u�j��v
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@�@�@���������� ����j�� ��������
�@
�@���ÁF�A�_���̌���@�@�F���i�mame�j
�@�@�F�V�g�̌���@�@�@�F���Ƃi�vort�j
�@�@���F�l�Ԃ́i���j����F����i�rprache�j
�@
�������E���`�E����Q�[���i�Q�j�����^�t�B�W�J���сi����E���j
�@
�@�x�����~�����u�����̗���̂Ȃ��ɉQ�Ƃ��Ă���A�������Ă���f�ނ�����̃��Y���̂����Ɉ������肱�ށv���̂Ƒ������u�����v�Ɋ֘A����O�ؐ��v�̕��͂������B
�@
���F���́u�����`�ہv�Ƃ��ẲQ
�@���L�P�B�O�ؐ��v�́w�����`�Ԋw�������������`�ۂƃ��^�����t�H�[�[�x�ŁA�`�Ԋw�̍�����Ȃ��u�����̂������v���߂����Ď��̂悤�ɏq�ׂĂ���B�u�Q�[�e�͂�����g�trtypus�h���邢�́g�trbild�h�ƌĂԂ̂ł��邪�A�����ł͂�������炽�߂āu���`�v�ƌĂԂ��Ƃɂ���B�����`�ۂ̗��ł��邱�Ƃ͂����܂ł��Ȃ��B�v�i236�Łj
�@
�@���L�Q�B�O�ؐ��v�́w�َ��̐��E�����l�ނ̐����L���x�u���������������`�ɂ��āv�̍��ŁA���̂悤�ɏ����Ă���B�u�c���Ƃ͂Ȃ��ɔ��g�ɂ��ݍ����̊�m��e�̊�n���A�l�X�́u���������v�Ƃ�ԁB�Â��́u�܂ڂ낵�v�Ƃ��������A�����ł́u�C���[�W�v�̂��Ƃ��g���A�`�Ԋw�̐��E�ł́u�����̌`�ہv�A�����āu���`�v�Ƃ���B�v
�@�܂����킭�A�Q�[�e�́u���A���v�i���^�����`�j���u����͌o���ł͂Ȃ����O�i�hdee�j���v�ƌ������V���[�ɑ��A�u�Q�[�e�͂��̂hdee �̖{���̈Ӗ����M���V���̂didos�����g�ʉe�h�����ɋ��߁A�g����͎��ۂɂ��̊�Ō��邱�Ƃ̂ł���h�ЂƂ̌����ł���Ɠ����Ă���v�i�w�����`�Ԋw�����x239�Łj�B
�@
���F���́u�������ہv�Ƃ��Ẵ��Y��
�@���L�B�w�����`�Ԋw�����x�ł̋c�_�B���킭�A�Q�����̂܂��Q�����̂ЂƂ̋Ɍ��ɂ��́u�F�����v���������Ă���B���̑�F���̂Ȃ肽���̂ЂƂ́u���`�v�Ƃ��āA���]���Ȃ�����]����n���̋O�Ղ��l�@���邱�Ƃ��\�ł��낤�B����A���̋ɑ�̐��E�́u�������v�Ƃ��ċɔ��i���q�j�Ɠd�q�j�̐��E���J����Ă䂭�i6�Łj�B�u�Q�[�e�����āu���̍��{�����v�Ƃ܂ł��킵�߂����̖��̕`���o�����Z���̖͗l�́A���܂�F���̐������ی`�����Ƃ��Ă����̑O�Ɏp�����킷���ƂɂȂ����B�v�i7�Łj
�@
�@�����O�ؐ��v�́u�����`�ہv�Ɓu�������ہv���قړ��`��Ƃ��Ďg�p���Ă���i�u�����`�ہ��g���i���Y���j�v�A�u�������ہ����Y���v�A�̂Ɂu�����`�ہ��������ہv�Ƃ����A�u�_�N�V�����̐��_�ɂ��j���A���́u���ہv�̕����u�`�ہv���O�����L���ƍl���Ă���B���Ȃ킿�A���C��������A�Q���◆���̂悤�ȁu�������v�i�G�C�h�X�j�������ہ��`�ۂƁA���Y����g���A�����̂悤�ȁu�������v�������Ȃ��i�A�����t�Ń}�e���A���ȁj���ۂ�����̂ł͂Ȃ����ƍl���Ă���B���̂��Ƃ��A�O�߂̐}���u�ό`�v�i���C���ƃ��Y���̉ғ���������ړ��j�������ɋ����ɏ������ނƁA���̂悤�Ȃ��̂ɂȂ邾�낤�B
�i�O�ؐ��v�̐��E�ɑ��ݓ����Ƃ����܂��u�O�؊w�v���邢�́u�O�؋��v�̉Q���Ɋ������܂�Ă��܂��B�^�[�~�m���W�[�܂ŗh�炢�ł��܂��B�{�͂�����̓���Ƃ��āA���邢�͎O�ؐ��v�Ɍh�ӂ�\���āA�ߖ��ł́u���^�v�ɑւ��u���`�v�̌���̗p�����B�j
�@
�@�@�@�s�}�Q�t���j�E�����E���O�i�ό`�Łj
�@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Z
�@�@�@�@�@�@�@�@ �ᗝ�O��
�@�@�@�Ác�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c�c
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@��
�@�@�@�������� �፪���� ��������
�@�@�@�@�@ �@�@�������`�ہ�
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@�@�@�@�@�@ �y�C�i���C���j�z
�@�@ �i�������A�Q���E�����A���߉^���j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@�@�@���������� ����j�� ��������
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@�@�@�@�@�@ �y���i���Y���j�z
�@�@�@�@�@�@�i�g���A���������j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��
�@�@�@�@�@�@�@ ���������ہ�
�@�@�@����������������������������
�@
�@�����`�����^�t�B�W�J���ȑш�
�@�@���@�@�����J�j�J���ȑш�
�@�@���`�����}�e���A���ȑш�
�@
�@�}���́u���߉^���v��u���������v�̏o�T�͎R�萳�a���w���Y���̓N�w�m�[�g�x�B�������͂���u�����ƒ�R�v���߂��鏘���I�c�_�������B
�@���́u���_�v�̒n���w�I�z�u���猾���A�����ŋc�_����Ă���u���������v�Ƃ��Ẵ��Y���̉ғ��G���A�́A�}�Ŏ������u���j�^���������^�����v�ł͂Ȃ��u�����^���������^���j�v�̂������A���Ȃ킿�u���m�n�n�^���F�����^���`���m�C�n�F���������^���m�g�n�F���j�^���`�m���n�F���߉^���^�Ám�V�n�F���O�v�̍\�}�ōl����̂��K���Ǝv���B�i�������ċc�_�͐U��o���ɁA�܂�u�����v���u�����v�Ɉʒu�Â���i��69�́s�}�Q�t�́j�\�}�ɉ�A����B�j
�@�Ƃ���ŁA���́A�����Ō�����u�Ɠ��̋����[�����ہv�i����Ό���̑��]�ڌ��ہj���A�i�����^���≝���^���A���߂̗����ȂǂƓ���́A�펯�I�\���ł���j�u�C�i���C���j�v�Ƃ�����łƂ炦�����ƍl���Ă���B���邢�́u�C�v�̊T�O���g�����A�����̌��ۂ̐����Ə��ł́u��v�i���������j��\������u���i���Y���j�v�ɑ��āA�P���I�ȗ��O�����^�̕����i�[���j�Ƃ��Ắu�������v��\��������̂Ƃ��ĂƂ炦�Ă��������ƍl���Ă���B
�@
�������E���`�E����Q�[���i�R�j�����^�t�B�W�J���сi����E���j
�@
�@���܈�u�����v�̊T�O���߂���x�����~���̕��͂������B
�@
�������ƌ����ہA�����I�ȓW�J
�s�Q�[�e�̐^���T�O�ɂ��ċL�����W�������̏��q��������ۂɁA���ɂ͎��̂��Ƃ����ɂ͂�����Ƃ��Ă����B�܂�ߌ��_�ŗp���������k�trsprung�l�Ƃ������̊T�O�́A���̃Q�[�e�̊�{�T�O�́A���R�̗̈悩����j�̗̈�ւ̌������٘_�̗]�n�Ȃ��]�p�ł���Ƃ������Ƃł���B������������͌����ۂƂ����T�O���A�ً��I�Ȋϓ_�ő�����ꂽ���R�̖�������A���_�����I�ɑ�����ꂽ���j�̂��܂��܂Ȗ����Ɉڂ����ꂽ���̂ł���B�Ƃ���ŁA�����p�T�[�W���_�ōs�����Ƃ��Ă���̂������̒T���ł���B�܂莄�́A�p���̃p�T�[�W���̂��܂��܌`���ߒ��ƕϗe�̍������A���̎n�܂肩��I���Ɏ���܂Œǂ��čs���A���̍������o�ϓI�Ȃ��܂��܂Ȏ����k�eakten�l�̂Ȃ��ő�����̂��B�������������́A�������ꂪ���ʊW�Ƃ����ϓ_���瑨�����Ă���ꍇ�ɂ́A�܂茴���Ƃ��Č����Ă���ꍇ�ɂ́A�����ہk�trphaenomen�l�ƌ������Ƃ͂ł��Ȃ��ł��낤�B�o�ϓI�ȏ������������ۂɂȂ�̂́A�����̎��������̓����I�Ȕ��W�����ނ���W�J�k�`uswicklung�l�ƌ������ق���������������Ȃ��������ɏ]���āA�p�T�[�W���̋�̓I�ȁA���j��̈�A�̌`�Ԃ��������g�̂Ȃ�����o��������ꍇ�Ɍ�����B���傤�ǐA���̗t���A�o���I�ȁkempirisch�l�A���E�̖L���ȑS�e������̂�������J��L���Ă݂���悤�ɁB�m�m2a,4�n�t�i�w�p�T�[�W���_ �W�������@�Ƃ��Ẵ��[�g�s�A�x17�Łj
�@���L�P�B�u�Q�[�e�ɂ����Ă͒m�o�̑ΏۂƂȂ銴�o�I���E�ƁA���̓��[��\�킷���O�I���E�̔}��͍������ہm�trphaenomen�n�ɂ��ق��͂Ȃ������B���ԓI�ȁi���̈Ӗ��ŗ��j�I�ȁj���E�Ɏp�����킷���̂ƁA�����ԓI�ȁi���̈Ӗ��ŗ��O�I�ȁj���E�Ɍ�������̂̔}��Ƃ����_�ɂ����āA�x�����~���̓W�������̍������ۂ̉��߂�����A���̊T�O�̐��E�F����̍L����A���Ȃ킿�u�����Ɖ��l�A���o���Ɨ��O�Ƃ��܂��E�ߒ��̑S�́v�m�W�������w�Q�[�e�x�n����c������\���I����������̔F�����_�̊�Ղɐ������̂ł���B�v�i�g�c�O�f�_���j
�@
�@���L�Q�B�u�c�����ۂƂ͈��镁�ՓI�Ȃ��̂ł���B�R������͒��ۓI�A�含�I�Ȃ��̂łȂ��A���̈Ӗ��Ŗ@���Ƃ��ӂ����C�f�[�������̓G�C�h�X�i�`�ԁj�ł���A���������̏ꍇ�C�f�[�͌o�����痣�ꂽ���̂łȂ��A�o���ɑ����Ē��ς��꓾����̂ł���B�v�u�e���v�X�͔J�됶���镁�ՂƂ��Č`���@�� Bildungsgesetz �Ɖ������ׂ��ł��炤�B�v�i�O�ؐ��u�Q�[�e�ɉ����鎩�R�Ɨ��j�v�j
�@
�@�����������ہA�������ہi�������`�ہj�A�����Č����ۂƁA�l�X�Ȍ�i���j�ł����Č����\�킳���Q�[�e���x�����~���I�T�O���A�����i���̏́j�ł́A�O�߂ɋL�ڂ������j�܂��āu�����`�ہv�����āu���`�v�ƌĂԁB�i�O�͂Łu���^�C�}�[�W���v�Ɓu�����C�}�[�W���v�Ɩ��Â������̂���������Ɓu���`�C�}�[�W���v�ɐ���B�j
�@�b����₱��������悤�����A�����`�l���w�`�ԂƏے������Q�[�e�Ɓu�̎��R�Ȋw�v�x�ɂ́u���{���ہv�Ƃ�����i���j���o�Ă���B���Ƃ��u�����̊Ⴊ���R�̂Ȃ��ɔF��������̂́A�@���⌴���Ƃ����������̒E�k�ł͂Ȃ��A�i���ɐ������Â��錻�ۂł���v�i135�Łj�Ƃ����u�Q�[�e�I���@�v�Ƃ��Ă̌��ۊw�i�u���ۊw�Ƃ��ẴQ�[�e���R�Ȋw�v�i417�Łj�Ƃ��j���߂��镶���̒��ŁA�������͎��̂悤�ɘ_���Ă���B
�@���킭�A�X�s�m�U��`�҂Ƃ��ẴQ�[�e�ɂƂ��Đ_�͌��ۂ̔w��ɂ���̂ł͂Ȃ��A���ۂ��̂��̂̂����ɂ���B�w�㐢�E�ȂǂƂ������̂͂Ȃ��A���ۂ��̂��̂��^���Ȃ̂��B
�@�������͕ʂ̂Ƃ���ŁA�Q�[�e�́u���{���ہv�̓J�b�V�[���[�́u���ׂĂ̎�̓���Ԃ���Ɋ܂݁A����K���ɂ̂��Ƃ��ē����W�J����u��̓I���Ձv�v�ɂق��Ȃ�Ȃ��Ə����Ă���i143�Łj�B�����āA�u���������ۂ̔c����ڎw���Q�[�e�I�Ȍ���v�i417�Łj���߂���c�_�̒��ŁA�u�i���Ȃ鐶���̉ߒ��ɂق��Ȃ�Ȃ����R�ɑ����v���Q�[�e�̓��I�ȕ��̂ɂ����đΏۂ����ꎩ�g�����S�ɕ\������u���݂Ƃ��Ă̌��v�ɂ��āA�u����͍��{���ہA���������Ɛ��������̓I���Ղł���v�i418�Łj�Ə����Ă���B
�@���{���ہ���̓I���ՂƂ��Ă̌��A����͂��Ȃ킿���R���g����錾�t�A����Ύ��R�̐��ł���B�������͂�����u�`�ی���v�ƌĂԁB�u�c�T�O���l�Ԃɑ����Ă���Ƃ���A�`�ۂ͎��R�ɑ����Ă���B�Q�[�e�͐l�Ԃ���錾�t�̂Ȃ��ɂ����ΉR���A�t�Ɏ��R����錾�t�̂Ȃ��ɂ͐^���������B�v�i420�Łj
�@���̂悤�ȁu���R���`�ۓI�����p���ċL�q���悤�Ƃ���Q�[�e���R�Ȋw�v�́A���③�`�|�p�Ɩ��ڂȐe���W�ɗ����Ă���i424�Łj�B
�@�������������u�`�ی���v�́A�䓛�r�F�́u�R�g�o�v�ɒʂ��Ă���B�䓛�́A�o���I���E�̊��o�I�����������E���ꂽ��ΓI���̋�ԂɁA�u�`����I�B���p�v�ɂ���Ă���َ����̌��������J�������鎍�l�}���������u�R�g�o�̌|�p�Ɓv�ƌĂ�ł���B�R�g�o�͌o���I�����i���݂̓���I�����̒��Ɋ��o�I���́��֊s�m�R���g�D�[���n�Ƃ��Č����Ă���ԁj���E���A�������邱�Ƃł������ɕ��ՓI���݁i�e�肽��Ԃ̃C�f�[���̂��́j���u���y�I�Ɂv�i�����I�����̎����Ƃ͈���������Łj���N������i�w�ӎ��Ɩ{���x�W�j�B
�@�`�ی���A�Q�[�e�I����A�L�@�I����A���X�̊T�O�́A��̈��p���ɏ�����Ă����A�g���[�V���O�E�y�[�p�[�i�p�����v�Z�X�g�j�ɂ���ē��������u���{���ہv��u��ɂ��đS�Ȃ�d�w���v�̘b��Ƃ��ǂ��A���J�j�J���ȑш�ɂ����錾�ꌻ�ۂ�����Â���u�����^�[�W���v������ɓ������鎄�̌�b�Ō����u�g�����ꂽ�A�i�O�����v�A���Ȃ킿�A�����i���G�ȕ��l�A���Y���j�Ƃ��Ă̐��ƕ������A�`�ۂ�Ӗ��i�u�����Ƃق����v���╗�̂悤�ȓ����ȈӖ��j�Ƃ��Ă̐��ƕ����́u���G�v�ƂȂ��Ă��邱�Ƅ����̋c�_�ɂȂ����Ă����B
�@
�������E���`�E����Q�[���i�S�j�����^�t�B�W�J���сi����E���j
�@
�@�Q�[�e���u���`�i���^�j�ƃ��^�����t�H�[�[�̌`�Ԋw�v���x�����~���́u�����v�̊T�O�ɒʂ��A�����ăE�B�g�Q���V���^�C���́u����Q�[���v�ɂȂ����Ă����B�����ȉ��A�Óc�O�璘�w�͂��߂ẴE�B�g�Q���V���^�C���x����A�u�E�B�g�Q���V���^�C���I�`�Ԋw�v���߂���c�_�������B
�@�Óc���ɂ��ƁA�E�B�g�Q���V���^�C���̃Q�[�e�`�Ԋw�̗����ɂ͎��̓�̃|�C���g������i209�Łj�B�@���E�̕����𗝉�����u�W�]�̂������`�ʁv���l�����邽�߂ɂ́A�ʂ̎��ۂ��֘A�Â���u�A�����v�����邱�Ƃ��̐S�B�A�u�W�]�̂������`�ʁv���Ȃ킿�����ۂ���̑S�̂Ƃ��Ē����Â��錩���͂ЂƂƂ͌���Ȃ��B�|�C���g�@�ŃE�B�g�Q���V���^�C���̓Q�[�e�`�Ԋw�̕��@�_�̈Ӌ`��傢�ɔF�߂Ă������A�|�C���g�A�̓E�B�g�Q���V���^�C�����Q�[�e���痣�����錈��I�ȕ�����ڂƂȂ�B
�i�B���ȃC���[�W��ł����Ă��\��Ȃ��Ǝv�����A�����̓E�B�g�Q���V���^�C���̃Q�[�e�`�Ԋw�������߂�����߂�����Ă����ʂȂ̂ŁA�Ƃ������A�G��ʐ^��f���Ƃ������i���`�́H�j�C���[�W�i�uorstellung�j�Ƌ�ʂ����u���v�i�aild�j�ɂ��āA�O���E�B�g�Q���V���^�C���͂�����u�͌^�v�Ƒ����A����ł́u�����̓���̌����v�i�L�`�̃C���[�W�H�j�Ƃ��Ă��̌��p�����Ƃ���Óc���̉��߂��x�[�X�ƂȂ��Ă���c�_�Ȃ̂ŁA���ӂ͍T���邱�Ƃɂ��āj�A�Óc���ɂ��ƁA�E�B�g�Q���V���^�C������������̂́u���Ƃ͖{���A�����̕����]���ׂ��Ώۂł͂Ȃ��A�e�����̔�r�Ώہf�ł���v�Ƃ������ƂȂ̂ł����āu�e�������ǂ̂悤�ł��邩�f�����邪�܂܂ɕ`�ʂ��邽�߂ɁA���͗p������ׂ��Ȃ̂ł���v�i214-215�Łj�B
�@�E�B�g�Q���V���^�C�����g�������Ă���u�A�����v�̗�Ƃ��āA�Óc���́A���z�E�l���u�ΔI�v�Ƌ��ђ�q���Δ������Ă���Ƃ����A�ɓx�ɃV���v���Ȍ���Q�[���i�w�N�w�T���x���߁j����肠����B
�@�܂�A�E�B�g�Q���V���^�C���I�`�Ԋw�ɂ�����u�A�����v�i���^�����`�j�͂ЂƂł͂Ȃ��A�Ƃ������Ƃ��B����ɁA�u�A�����v�͌����ɑ��݂��鎖�ۂɌ����Ȃ��B�����`�Ԃ̐��藧����Ӗ�����������r�ΏۂƂ��Ď����o���ꂽ�u���R��ԁv�̂悤�Ɂi219�Łj�B
�@�E�B�g�Q���V���^�C���͂����e�̂Ȃ��Łu���ۂ̔w��ɉ����T���Ă͂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ����Q�[�e�̃��b�g�[�����p���Ă���B�u�E�B�g�Q���V���^�C���͂��̃��b�g�[�Ɂe���̃Q�[�e�ȏ�ɒ����������f�v�i226�Łj�B
�@
�m���n�����́u�����̓]���v�i�A�X�y�N�g�̓]���j�������炷�̌��A���Ƃ��Δ����G�i�B���G�A���܂��G�j�̂悤�Ɂu�������Ɍ����Ă������̂��S�̂Ƃ��ċ}�ɒ��������Č����Ă���v�i274�Łj�Ƃ����̌����A�E�B�g�Q���V���^�C���́u�A�X�y�N�g�̑M���v�ƕ\�L�����B�u�Q�[�e�̒T���A���Ȃ킿�A�������ɐ������Ă��邾���Ɍ����鑽�l�ȐA���̊ԂɃQ�[�e���ގ��������Ď�����u�Ԅ����ގ��g�̔F���ł́A�A���́u���^�v�𑨂����u�Ԅ������A�܂��Ɂu�A�X�y�N�g�̑M���v��ނ��̌������u�Ԃ������ƌ����邾�낤�v�i275�Łj�B
�@�ȉ��A�u�A�X�y�N�g�̑M���v�Ɋւ��鋻���[���b��������B
�@���̈�B�E�B�g�Q���V���^�C���́A���t�̑��e���]������u�A�X�y�N�g�̑M���v�̑̌��Ɋ֘A���āA�A�X�y�N�g�̐�ւ���̌����邱�Ɓi�u�E�T�M���A�q���v�}���E�T�M��A�q���Ɍ����邱�ƂɁu�����v���Ɓj���ł��Ȃ��u�A�X�y�N�g�Ӂv�i287�Łj�Ƃ����u��r�̑Ώہv���l�Ă����B�A�X�y�N�g�ӂ̐l�͒m�o�ɏ�Q��ُ킪����킯�ł͂Ȃ��i�u�E�T�M���A�q���v�}���E�T�M��A�q���Ƃ��Č��邱�Ƃ͂ł���j�B�ł́A���̐l�͎��ۂ̂Ƃ��뉽�������Ă��邱�ƂɂȂ�̂��B
�@���̖₢�ɑ���E�B�g�Q���V���^�C�����g�̓����̂ЂƂ́A�A�X�y�N�g�ӂ̐l�͌��t�V�т������ł��Ȃ��Ƃ������́B�A�X�y�N�g�ӂ̐l�͌��t�����L���ȉ��s����܈ӂ�����Ƃ��Ĕc�����邱�Ƃ��ł����A���I�ȕ\���̑����𖡂킦�Ȃ��B
�@���̓�B����E�B�g�Q���V���^�C���́u�A�X�y�N�g�̑M���v�Ƃ����̌��ɑ���ȊS�������A���푽�l�ȋ�̗����ׂĂ�����Ƃ��s���Ă���B�u����́A�l�X�ɈقȂ�u�A�X�y�N�g�̑M���v�̊Ԃ̉Ƒ��I�ގ������Ŏ悷��Ƃ����A�e���ꎩ�̂��ЂƂ́u�A�X�y�N�g�̑M���v�ł���悤�ȑ̌��f�����������ƂȂ̂ł���B�v�i291-292�Łj
�@�����u���t�V�т��y���ނ��Ƃ⎍�I�\���𖡂키���ƁA���`��𑽋`��Ƃ��ė������邱�Ɓv�̈Ӗ��ɂ��ẮA�l�Ԃ́i���j����̃��J�j�J���ȑш�ɂ�����u�g�����ꂽ�A�i�O�����v�̋c�_�̂Ȃ��ŁA�l�@���Ă݂����B�܂��u�Ƒ��I�ގ����v�̊T�O���A�}�e���A���ȑш�ɂ�����u�͕팴���v�ƃ��^�t�B�W�J���ȑш�ɂ�����u���������v�̍����ɂ���Đ����O�̌����i�u�ʉe�����v�Ƃł����������j�̂����Ɏ�荞�݁A���J�j�J���ȑш�̃_�C�i�~�Y�����������������T�O�Ƃ��Đ��B���Ă��������B
�@
�������_���߂����Ą����J�j�J���тցA��܂Ƃ��Ƃ�
�@
�@���J�j�J���тւ̓��������܂��Ă����Ƃ���ł����A�C�ɂȂ��Ă���b��Ɂu�����v�����Ă����Ȃ��ƁA���S���Đ�i�߂܂���B
�@���^�t�B�W�J���т̋c�_�̒��ŁA�܌��M�v�́w�����_�x�ւ̐ڑ����ʂ����Ȃ��������Ƃɂ��āA�u�ߖ��v�����Ă��������Ǝv���܂��B���̓����́u�\�z�v�ł́A�}�e���A���т̒��j�Ƃ����������ɋg�{�����́w��^�_�x�𐘂��A���^�t�B�W�J���тł���Ɠ��l�̏ꏊ�Ɂw�����_�x���ʒu�Â��邱�ƂɂȂ��Ă��܂����B���������̌�A�l�����ς���Ă����̂ł��B
�@��67�͂ŁA������w�܌��M�v�x���玟�̂ӂ��̕��͂������܂����B
�@
�`�u�w�P�̌����x�́u���v�Ɍ����u�����o���v���u��������v�ƒu�������Ă݂�A�w�����_�x����͂��܂�܌��M�v�̌Ñ�w�̎˒����A����܂łƂ͂܂������قȂ������ʂ��瑨���������Ƃ��\�ɂȂ邾�낤�B�u��������v�A�\���ɂ����钼�ڐ��̌����B��̎��݂Ƃ��āA���E�̂��ׂĂ�������Ă݂邱�ƁB�v
�@
�a�u�܌��M�v�́w�����_�x�ł܂��{�[�h���[���̖��O�������i�u�{�D�h���B���̐_��̖���J���ׂ��B��̌��͐F�E���E���ł���v�j�A���g�́u�ے�����v�i���ڌ���j�̗֊s��`�����Ƃ��͂��߂�B�^�܌��́u�a�̔ᔻ�̔��e�v�ɂ����Ă��w�����_�x�ɂ����Ă��A���̌��_�����Ō���ɂ����钮�o�Ǝ��o�̋����o���ہA�u�Β��v��_���Ă���B�i���j�^�܌��͂��̌�A�u�ے�����v�̔������A��q�̋�ʂ����ł��Ă��܂��u�߈ˁv�ɒT��A�u�����w�̔����v�Ƃ����_�l�������p���ł䂭�B��������܌��̌Ñ�w���͂��܂�B�v
�@
�@���̃^�[�~�m���W�[�A�Ƃ������T�O�̒n���}���猩��A���p���`�̂悤�ɁA�܌��M�v�́u�ے�����v�i���ڐ��̌���j���u��������v�ƒu��������̂́u����v����̃A�v���[�`�A�܂�l�Ԃ́i���j����̃��^�t�B�W�J���ȑш�ɂ�����o�����Ƃ��āu�ے�����v�𑨂��闧��ł���A����A���p���a�ŏq�ׂ��Ă��鋤���o��߈˂Ƃ����������́A�l�Ԃ́i���j����̃}�e���A���ȑш�ɑ����鎖�ہA�܂�u�����v����̃p�[�X�y�N�e�B���ɂ�����t��o�������̂ɂق��Ȃ�܂���B
�@�w�����_�x�Ђ��Ă͐܌��M�v�̊w��i�Ñ�w�j�́A���^�t�B�W�J���ȑш�ƃ}�e���A���ȑш�A����Ɖ��������������ɍ������Ă���B���������Ӗ��ł́A���J�j�J���т������{�ЂƂ�����̂������̂ł͂Ȃ����B�Ƃ������A���̂悤�Ɉʒu�Â��Ă����w�����_�x�Ђ��Ă͐܌��w���u�������v���Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����B���̂悤�ɍl���āA���́w�����_�x�����^�t�B�W�J���т̘b��Ƃ��ĂƂ肠���邱�Ƃ�f�O���A���J�j�J���тɈς˂邱�Ƃɂ����̂ł��B
�@�������A�i����͂܂����ϓI�ȕ������ł�������܂��j�A�����炭�܌��M�v�̋c�_�̓��J�j�J���т̋c�_���Ă��܂��B����ǂ��납�A�l�Ԃ́i���j����̎O�ш�\�����̂��̂��āA�����ȑO�̏�����Ԃ̌���́u�c�́v��ێ������܂Ƃ��Ƃ̃l�I�e�j�[���i���邢�́u����v�Ƃ��Ă̂�܂Ƃ��Ƃj���߂���c�_�ւƗU�����A���̍��������炦��˒��̍L���Ɛ[���������Ă���B
�@������́w�܌��M�v�x�̑攪�́A�u�����̎w�W�v�̍��Ɏ��̂悤�ɏ����Ă��܂����B�i�������������u�ߋ��i�Ñ�j�̋L���v�͎O�ؐ��v�́u�����L���v�m���n�Ƌ��������B�j
�@�����C�i���C���j�̔������Ɨ��i���Y���j�̈���u���݂̉��v�i�A�N�`���A���ȉ��j�̂����ɗn�������A��������u�Ñ�v����������B�����A���Ȃ킿����Ɯ߈˂ɂ�鎀�҂����́i�u����`�I�������͗c�̐��n�I�ȁj�S��B�Ñ�A���Ȃ킿���^�ƕ�^�̏d�ˍ��킹�ɂ��i���@�[�`���A���ȁj�L���̔����B
�@
�m���n���Ƃ��w�َ��̐��E�����l�ނ̐����L���x�́u�َ��̖��v�i����v��w�h�O���E�}�O���x�ɓo�ꂷ��_���j����肠�����ӏ��ŁA�O�ؐ��v�͎��̂悤�ɏ����Ă���B
�@���������͎��̖��Ƃ������ϑz�����A�܌��M�v�́u�Ñ�̋L���v�ƎO�ؐ��v�́u�����L���v�̊T�O���i�u�����^�����^���_�^�ӎ��v�̎l���E�_�i��V�͎Q�Ɓj�Ƒg�ݍ��킹�āj���̒n���}�̂����ɗ��Ƃ����ނƁA�u���m�n�n�F�����i�G�������g�j�̋L���^���m�C�n�F�����L���^���m�g�n�F�l�Ԃ̌���E���j�^�m���n�F�Ñ�̋L���i���_�j�^�Ám�V�n�F��������E�_�̋L���i�ӎ��j�v�̍\�}��������B
�@
�i�T�O���ɑ����j
���v���t�B�[����
�����I���i�Ȃ��͂�E�̂肨�j1950�N�㐶�܂�B���Ɍ��ݏZ�B��N���̂ɏ����ꂽ�a�̂̈Ӗ��������ł���̂͂��������Ƃ��B�ł��A�{���Ɂu�����v�ł��Ă���̂��B�����Ɂu�Ӗ��v�Ȃǂ���̂��B�����������t���g���ĉ�����`�B���邱�Ƃ��̂��̂��s�v�c�Ȍ��ۂ��Ǝv���B
Web�]�_���u�R�[���v49���i2023.04.15�j
���F�ƃN�I���A�^�y���\�i�ƚF����V�Q�́@�l�Ԃ̌���̎O�ш�_�i���^�t�B�W�J���сE���O�j�i�����I���j
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU�@2022 Rights Reserved.
|
| �\���i�ڎ��j�� |
