|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「la Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
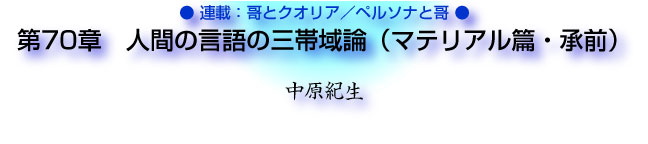
|
|
(本文中の下線はリンクを示しています。また、キーボード:[Crt +]の操作でページを拡大してお読みいただけます。)
■「非感性的類似性」と「未来への想起」─マテリアル篇3
森田團著『ベンヤミン──媒質の哲学』第十章「文字とミメーシス」。
ミメーシスと言語(文字)との関係を規定するため、ベンヤミンは「非感性的類似性」の概念を導入する。この「非」はたんなる否定ではなく、感性に先立ち感性そのものを可能にする「原感性」を指している。そうみなすことで、原ミメーシスを可能にしつつその彼岸に位置する起源の出来事に関係するものとして「非感性的類似性」を解釈することできる。「ベンヤミンのミメーシス概念は、イメージ経験の根柢にある類似性の経験、それも上で解釈したような意味での「非感性的類似性」の経験との連関のうちで究明されねばならない。」(372-373頁)
・ベンヤミンは、オノマトペが感性的な類似性によって理解されていることを批判する。語と意味の関係は非感性的類似性の概念によって説明しうるのであり、しかも音声言語と意味されるものだけでなく、文字のイメージ(文字像[Schriftbild])と意味されるもの、書かれたものと話されたもののあいだにも非感性的な類似性が支配している。(380-381頁)
(『ベンヤミン・アンソロジー』における山口裕之氏の訳註(同書198頁)。──「「文字像 Schriftbild」という語は、一般的には、たとえばローマン体やゴシック体といった、印刷における「書体」を意味する。ここでは、そういった一般的な意味と重ね合わせながら、まさに「文字 Schrift」のもつ「画像 Bild」そのものとしての機能、つまり、本来的には「意味されるもの」そのものとは結びついていない文字の画像性が問題となっている。この語は『ドイツ悲劇の根源』でも、「文字」のもつアレゴリー的特質を語る文脈で使われている。」)
ベンヤミンが、「書かれた言葉が…その文字像[書体]と「意味されるもの」との関係を通じて、非感性的類似性の本質を照らし出す」(「模倣の能力について」)と言うのは、太古(古代・神話に先立つ過去)のイメージ体験を支配する非感性的類似性が、言語能力の行使のたびに何らかのかたちで働いているからにほかならない。(381-382頁)。
・読むことは忘却されたもの(身体)を想起する試みでもある(401-402頁)。ベンヤミンはミメーシス論の第一稿「類似性の理論」で「魔術的な読み」と「世俗的な読み」の区別[*]を呈示し、第二稿では省かれた「読むことの理論」を展開している。(406頁)
・ベンヤミンの後期言語論(ミメーシス論)において、魔術的な読みの可能性の条件として「名」が新たに構想されている。「イメージをそのまま言語へと反転させる可能性としての名」(413頁)。「イメージの翻訳可能性としての名」(414頁)。
・読むことは「未来への想起」であり、そこでのみ名が「贈与」として与えられる。名が生きる時間、それはたんなる瞬間ではなく、「イメージと言語の出会いの可能性そのものを与え続けている最古の瞬間」なのであり、いわば「イメージの‘名’を保持している瞬間」なのである。
[*]今福龍太氏は『身体としての書物』第11章「模倣、交感、墨書──ベンヤミン「模倣の能力について」」で、ベンヤミンのミメーシス論第二稿の「最大の謎」(と今福氏は書いている)である一文、「書く速さ、また読む速さが、言語領域における記号的なものと模倣的なものとの融合を高めるということも、ありえないことではない。」をめぐって、次のように書いている。
「言葉のミメーシス」が、言語領域における「記号的なもの」(伝達的側面、意味の合理性)のうちに「埋没されたり回収されたり」することがないよう、文字を指でなぞるようにゆっくり考えながら徹底的に遅く読むこと、すなわち言語領域におけるもうひとつの側面である「模倣的なもの」(非感性的類似性)にかかわる「魔術的な読み」に徹すること。──そのような「読み」は、言語のマテリアルな帯域(=全身)における反復的な模倣行為、すなわち「反響的動作」にほかならない。
ちなみに、文中の「蜘蛛の糸」は、『一九〇〇年頃のベルリンの幼年時代』に収められた「幼年期の本」の一文、「あちこちのページには、かつて字を覚え本を読み始めた頃私を絡め捕った、あの網になった細い糸が、秋空の木々の枝に漂う蜘蛛の糸のように掛かっていた」(『ベンヤミン・コレクション3』502頁)を踏まえたもの。
今福氏は同書第10章「ページに掛かる蜘蛛の糸──ベンヤミン「幼年期の本」「学級文庫」」で、「秋空の木々の枝に漂う蜘蛛の糸」とは、初歩的な読み書きができるかできないかの頃、読めない文字の線がぼんやりと絡まり合って細い糸の網の目のように見えたこと、つまり「幼い子どもたちが感じる不可解なつづり字への謎の感覚」を指しているのではないかと書いている。
■根源的産出をめぐって─マテリアル篇(落穂拾い)
森田團著『ベンヤミン──媒質の哲学』の議論を抜き書きしている間、脳裏に去来していた事柄をいくつか記録しておく。
媒質による二項の根源的産出をめぐる森田氏の議論を私なりに咀嚼し定式化すると、次のようなものになる。(永井均オリジナルの独在性の符号を使って、aを〈A〉、bを〈B〉に書き換えると、より実相に迫り得ると思う。)
M(a,b)⇒AmB
※M:根源的媒質(絶対的媒介)
m:媒介
A:自然、感覚、直観、対象、個別、…
B:人間・精神・歴史、思考、悟性、概念、普遍、…
⇒:根源的産出(根源的媒質が消去され、A・Bの二項が自立する出来事)
ついでながら、前章では十分に抽出できなかった森田氏のミメーシス論の構図を、「身分け・言分け」[*]によって区画される層構造のうちに粗描すると、次のようなものになる(第四層の設定をはじめ「若干」の改変を施している)。
【第一層】
・「身分け」以前の「太古」の世界
・「原ミメーシス」を可能にしつつその彼岸に位置する起源の出来事
=イメージ経験の根底にある「非感性(=原感性)的類似性」の世界
【第二層】マテリアルな帯域
・「身分け」後かつ「言分け」前の「模倣する身体」(反響的動作)の世界
・「原ミメーシス」のはたらきによるイメージ(やオノマトペ)の産出(根源的産出1)
=イメージを文字と見立て、意味との一回的な出会いを読む「魔術的な読み」の世界
【第三層】メカニカルな帯域
・「言分け」後の記号としての言語(アルファベット)の世界
・「模倣する身体」によるイメージから言語への変転(根源的産出2)
=意味が堅固につなぎとめられた文字を読む「世俗的な読み」の世界
【第四層】メタフィジカルな帯域
・「言分け」後かつ「身分け」前の「意味」の世界
・第一層から第二層への変転(根源的産出1)を鏡像反転的に反復して導出される世界
=「未来への想起」としての読むことのうちに「名」が贈与として与えらえれる瞬間
[*]私はここで、かつて斎藤慶典氏の著書から二度(第3章と第10章で)引用した、フッサール由来の「基づけ関係」を想起している。丸山圭三郎が提唱した「身分け」(身体的分節化)と「言分け」(言語的分節化)の区別をめぐって、斎藤氏は次のように論じていた。
ここで言われる「基づけ関係」を「根源的産出」に倣って定式化すると、たとえば「a⇒b(A→B)」のようなかたちになる。(ここにA=身、B=心を代入すれば、身心問題の構図になる。)
■擬態と死の欲動をめぐって─マテリアル篇(落穂拾い)
森田氏は、前期ベンヤミンのアレゴリーについての洞察を後期のミメーシス論によって基礎づけている。いわく、ベンヤミンは『ドイツ悲劇の根源』で、自然が死の手に堕ち(自らの「意味」を無媒介的に現前させることができなくなり)アレゴリーと化すことを堕罪の言語論的解釈によって説明した。
文中の「擬態」に触れた箇所で、森田氏は次の註をつけている。「ロジェ・カイヨワは、擬態の考察において、その現象の意味を死への欲動とも呼びうる傾向に結びつける方向へと進んでいる。つまり、有機物が無機物へと退行する線上に擬態が位置づけられている。(略)またラング[Tilman Lang]は、ベンヤミンのミメーシス論とカイヨワとの関係について論じる際に、ミミクリーをフロイトの死の欲動に結びつけている。」(503頁)
カイヨワの擬態論(「擬態と伝説的精神衰弱」)は『神話と人間』(久米博訳)の第二部に(かまきりの神話作用を論じた章に続いて)収録されている。「…‘空間への同化による人格喪失’、換言すれば、それはある種の動物がまさに擬態によって形態的に実現していることである。」(117頁)
カイヨワは『遊びと人間』(多田道太郎他訳)では次のように書いている。
これに付されたカイヨワの注。「この研究[『神話と人間』所収の「伝説に現われた擬態と精神衰弱」]の問題のとりあげ方は、現在の私にはあまりにも空想的に思える。いまの私は、擬態を空間的知覚の混乱とか非生物への回帰傾向とは考えない。ここ[『遊びと人間』]で提案しているように、昆虫の世界での人間の擬態の遊びに対応するもの、と考える。」(56頁)
ちなみに、岡本和子氏は「「住む」,「歩く」,「書く」──ベンヤミンにおける模倣の身振り」のなかで、「擬態は生命維持にかかわる一種の模倣であるとする考えや、子どもの遊びと模倣の深い連関といった、自身の模倣理論を構成する重要な観点を、ベンヤミンはカイヨワから得ている。」と書き、森田氏が援用したラングの論文の参照を促している。
養老孟司氏は『虫は人の鏡──擬態の解剖学』の「はじめに」で、「擬態を典型とするマクロ的な情報現象の分析は、基本すらまだ成立していない」と書き、「擬態として一括されている事例は、いわば「症候群」であって、単一の現象ではない」と論じている。以下、同書から、養老氏の(カイヨワ−ベンヤミンの系譜とは別の、いわば「生物−情報論」的観点からの)擬態・模倣をめぐる洞察を二点、抽出する。
その1、写真家・海野和男氏との対談「偶然か必然か」から。
その2、最終章「虫とヒト」から。
いわく、虫は考えない。考えずにきわめて合目的的な行動を行う。ヒトが脳を使ってあれこれ考えてやることを「本能的に」(ゲノムに書かれた行動のプログラムにしたがって)やってしまう。ヒトの脳はそれを見てなるほどと思う。思ってどうするか。その「真似をする」のである。だからヒトの世界はどんどん合目的的な行動で覆われていく。「予測と統御の世界、脳化世界である。」(204頁)
以上、総論。ここからが擬態論。
擬態という「情報現象」をめぐる養老孟司氏の(人間科学的)構図を、森田團氏のミメーシス論の構図と関連づけておく。
◎物質系 ∽ 【第一層】
◎情報系(遺伝子系)∽ 【第二層】マテリアルな帯域
◎工学系(情報学) ∽ 【第三層】メカニカルな帯域
◎情報系(神経系) ∽ 【第四層】メタフィジカルな帯域
■ライムとモワレをめぐって─マテリアル篇(落穂拾い)
平倉圭氏は『かたちは思考する──芸術制作の分析』の序章で、「形象」(figure)を「多数の人間的・非人間的作用が絡まりあう、心的‐物的な記号過程の結び目をなす形」(10頁)と定義し、人間ではなく形象が思考することを「形象の思考」と表現している。そして、そのような形象の思考を内的に統御する「論理」、すなわち詩における「ライム(韻)」のシステムのような基本的な形式の候補として、ベイトソンに倣い「モワレ」(二つの周期的パターンが重ねられるときに現れる第三のパターン)を挙げる。
モワレ的論理をめぐって、ベイトソン(『精神と自然』)は次のように書いている。「カニをエビと結びつけ、ランをサクラソウと結びつけ、これら四つの生き物を私自身と結びつけ、その私をあなたと結びつけるパターンとは?」「ヒナギクに見とれている者は、ヒナギクと自分との‘類似’に見とれているのではないか。」
巻込はなぜ起こるのか。「たとえば母語の獲得がそうだ。人は周囲で交わされる音声や身振りのパターンに巻き込まれ、またそれを巻き込みながら自己を形成する。巻込は、自己形成に侵入する強制力ある「模倣」である。」(18頁)
ここで平倉氏はベンヤミン(「模倣の能力について」)の議論に言及する。かつて宇宙の諸事象と魔術的に「交感(コレスポンデンツ)」していた人類の「古い」力の残滓・痕跡が個体発生上の問題として「子供の遊び」にあらわれている。そして、「まったく書かれなかったものを読む」こと、すなわち内蔵・星座・舞踏から読み取る最古の読み方という、「最深部」の模倣に関するベンヤミンの言葉を踏まえて、次のように括っている。
これ以後の平倉氏の議論(「形象読解の不確定性」に関するポーの長短小説・評論・詩、ロバート・スミッソンの「大地語」の概念、「外化された模倣体」やカイヨワの擬態をめぐる)は刺激的だが、ここでは割愛する。
■テレパシーをめぐって─マテリアル篇(落穂拾い)
いま手元にあるベンヤミンのミメーシス論(初稿)の邦訳。
・道籏泰三訳「類似したものについての試論」(『来たるべき哲学のプログラム』(1992年12月))
・浅井健二郎訳「類似しているものの理論」(『ベンヤミン・コレクション5』(2010年12月))
・山口裕之訳「類似性の理論」(『ベンヤミン・アンソロジー』(2011年1月))
このうち道籏訳には、付録として、ベンヤミンが残した「類似・模倣についてのメモ四篇」が訳出されている。どれも興味深い思考細片だが、ここではフロイトのテレパシー論の引用を取りあげる。
ベンヤミン自身がテレパシーに言及した文章を、「シュルレアリスム---ヨーロッパ知識人の最新のスナップショット」から引く。
テレパシーで私が想起するのは、吉本隆明が『母型論』で書いていた旧日本語の世界、つまり自然物(磐ね、樹立、草の片葉)の発する音が言語になった世界だ。鎌田東二氏はインタビュー「言霊の世界」[https://www.toibito.com/interview/humanities/philosophy/1535/2]のなかで、「草木言語っていうのは、よく使われる言葉でいうとテレパシーみたいなものだと思うんですね。」と語っている。憑依も「テレパシーみないなもの」かもしれない。あるいは、受肉や啓示や直接伝達(キルケゴール)こそ「テレパシーみないなもの」なのかもしれない。
(ちなみに、鎌田氏は『南方熊楠と宮沢賢治』で、テレパシーと「二人のM・K」とのかかわりを取りあげている。潜在意識(アラヤ識)から発現する「静的神通」(テレパシー)などの神秘現象のメカニズムを探求したM・Kと、『銀河鉄道の夜』第三次稿でブルカニロ博士にテレパシー実験をさせたもう一人のM・K。)
[*]栗田勇著『日本文化のキーワード──七つのやまと言葉』に「面授、口伝にみる東洋的伝達方法」の見出しがついた文章があり、禅の不立文字や以心伝心、釈迦と迦葉の拈華微笑の話題がでてくるが(211−212頁)、それらもまた「すぐれてテレパシー的な過程」ではないかと思う。
あるいは「書くという行為」もまたテレパシー的(表意=憑依的?)なのかもしれない。栗田氏は、ときに幼児の遊び書きのようにもみえる良寛の書をめぐって、次のように問うている。彼はなぜ書を書きつづけたのだろうか、書家として書を書くことが目的でないとしたら手段だろうか、何の手段なのであろう、分析すればするほどわからなくなる…。
(第49号に続く)
★プロフィール★
中原紀生(なかはら・のりお)1950年代生まれ。兵庫県在住。千年も昔に書かれた和歌の意味が理解できるのはすごいことだ。でも、本当に「理解」できているのか。そこに「意味」などあるのか。そもそも言葉を使って何かを伝達することそのものが不思議な現象だと思う。
Web評論誌「コーラ」48号(2022.12.15)
<哥とクオリア/ペルソナと哥>第70章 人間の言語の三帯域論(マテリアル篇・承前)(中原紀生)
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2022 Rights Reserved.
|
| 表紙(目次)へ |
