|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「la Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
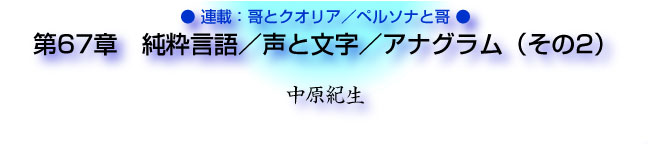
|
|
(本文中の下線はリンクを示しています。また、キーボード:[Crt +]の操作でページを拡大してお読みいただけます。)
■純粋言語の系譜、ベンヤミンとウィトゲンシュタイン(語りえぬものと死後の問題)
前章最終節の「アレゴリー、言語哲学と歴史哲学の結節点」の項で、柿木伸之著『ベンヤミンの言語哲学』から、原文を一部抜き書きした箇所がありました。そのなかの、「アレゴリーという形式は、今やそれ自体として歴史を語るものである、地上の言語そのものの寓意なのかもしれない」のところに、柿木氏は次のような註をつけています。
柿木氏の示唆にしたがって、マッシモ・カッチャーリ著『死後に生きる者たち──〈オーストリアの終焉〉前後のウィーン展望』(上村忠男訳)を繙いてみると、この(田中純氏による解説「哀悼劇の天使的音楽に寄せて」の口真似をするならば、「Liederzyklus(連作歌曲)」のごとく編まれた)書物の開演直後、「哀悼劇の新たな空間」と題されたエッセイに、「‘全’ウィトゲンシュタインの始まりにおいて主張される事実与件空間とはなんだろうか。事実与件空間は、ヴァルター・ベンヤミンがドイツのバロック演劇をもとにして分析した象徴性豊かな哀悼劇の舞台であり空間である。」(38頁)と書かれているのが目にとまりました。
「事実与件空間」とは「Tatsachenraum(the space of facts)」の訳語で、出典は『反哲学的断章──文化と価値』。この概念(You cannot lead people to what is good; you can only lead them to some place or other.The good is outside the space of facts.──Google ブックスの“Culture and Value”で検索した該当箇所)が、前期・中期・後期にわたる「全」ウィトゲンシュタインの起点にあった、そして、それはベンヤミンが分析したバロック悲劇(哀悼劇)の舞台と同質のものであった、というのがカッチャーリの指摘です。
仮面たち、あるいは死後に生きるものたちが、「絶えず語りえないものと接しながら、死後の生を展開させる媒質」すなわち言語による活動を遂行する空間・舞台。死後に生きる者たちの眼差し、あるいは末期の目に映る「氷のように透み渡った」(芥川龍之介)世界。──この、読み通すのに難渋するエッセイ群の行間から、おぼろげにたちあがってくる魅惑的な空間・舞台・世界については、貫之現象学C層をめぐる議論のなかで、あらためてとりくむことができればと思いますが、ここでは、いま述べたこと以外にいくつか、柿木氏がベンヤミンとウィトゲンシュタインを並列させて論じている箇所があることを紹介しておきたいと思います。
<ウィトゲンシュタインとベンヤミン、あるいは像と名>
〇ウィトゲンシュタインによると、ある命題が現実の「像」であるとき、この命題は世界に現に起きていることを表現している。その際、事実と言葉の関係は恣意的・外挿的なものではなく、他ではありえない内的な関係である。「レコード盤、音楽的思考、楽譜、音波、これらはすべて互いに、言語と世界のあいだに成立する内的な写像関係にある。」(『論考』4.014)しかも、楽譜を読む者の脳裏にその楽譜が表現する音楽が響いてくるように、言葉を理解する者はそこに現実が一定の論理的な仕組みをもって描出されていること──不可分のひとまとまりをなす一つの言葉(命題)とその現実とが「論理形式」を共有していること──を直接に理解している。(柿木前掲書96-97頁)
〇ベンヤミンもまた、「名」は名づけられるものと内的な関係を具えると考えた。言語の最初の姿としての「名」は、遭遇した事物や他人に他ではありえない言葉で語りかけながら、世界で起きている出来事を表現する言葉として、おのずと語りだされてくる。このような「媒質」ないし「中動態的なもの」としての言語のあり様を、すなわちベンヤミンが「言葉の魔術」として考察した次元を、ウィトゲンシュタインも見通していた。現実との内的関係を具えた「像」としての言葉はおのずと語られ、それとともに(それ自体は語りえず、おのずと姿を現わすものである)「論理形式」がおのずと示される。「示され‘うる’ものは、語られ‘えない’。」(『論考』4.1212)(柿木前掲書97-98頁)
<語りえないものに対する態度、あるいは翻訳>
〇ウィトゲンシュタイが自然科学的な事実の論理的記述の次元に定位したのに対して、ベンヤミンは詩的言語に軸足を置いた。「語りえないものについては、沈黙しなければならない」(『論考』7)というウィトゲンシュタイの言葉とは反対に、ベンヤミンの「翻訳」──「沈黙した、名を欠いた事物の言語を受け容れ、それを音声ある姿で名へ移す」(「言語一般および人間の言語について」第一八段落)こと──は「語りえないもの」を語ろうとすることでもあり、その経験とともに一つの言語が生成するのである。(柿木前掲書99-101頁)
■純粋言語の系譜、ウィトゲンシュタインとウィリアム・ジェイムズ(言語と経験の問題)
ひとつの年表を掲げます。
これは、純粋言語の系譜(水脈)を、ベンヤミンからウィトゲンシュタインへ、ウィトゲンシュタインからウィリアム・ジェイムズへ、そしてウィリアム・ジェイムズから西田幾多郎、折口信夫へ、さらに折口信夫から井筒俊彦、吉本隆明へとたどったものです。
1890 『心理学原理』(ウィリアム・ジェイムズ)
1902 『宗教的経験の諸相』(ウィリアム・ジェイムズ)
1910 『言語情調論』(折口信夫)
1911 『善の研究』(西田幾多郎)
1916 「言語一般および人間の言語について」(ベンヤミン)
1921 『論理哲学論考』(ウィトゲンシュタイン)
1921 「翻訳者の課題(使命)」(ベンヤミン)
1950 「詩語としての日本語」(折口信夫)
1956 『言語と呪術』(井筒俊彦)
1965 『言語にとって美とはなにか』(吉本隆明)
ラッセル・B.グッドマン著『ウィトゲンシュタインとウィリアム・ジェイムズ──プラグマティズムの水脈』(嘉指信雄他訳)は、『心理学原理』や『宗教的経験の諸相』といったジェイムズの著作とのかかわりを通じて、プラグマティズムに対するウィトゲンシュタインの親和性を際立たせた書物で、たとえば、1912年7月、ウィトゲンシュタインはラッセルに宛てて、「この本[『宗教的経験の諸相』]は、私にとって本当にためになるのです。…私が「憂い」を取り除くのを助けてくれるように思うのです。」と書いています。
(世界のあり様をめぐる第一の意味がカッチャーリの言う「空間・舞台」に、第二の意味がそこで上演される「哀しみの劇」にそれぞれかかわってくる。)
引用文中の「宗教的経験のカタログ」という表現に関して一言。ベルクソンは、「ウィリアム・ジェイムズの実用主義[プラグマティズム] 真理と事象」(『思想と動くもの』)のなかで、『宗教的経験の諸相』を心理学的カタログ本として読むのはジェイムズの思想に対する「重大な誤解」であって、ジェイムズは宗教的経験すなわち「神秘家の心」について思考する前に、それを「同感」をもって経験しようとしたのだ、と書いています。
(ベンヤミンにとって「言語」がそうであったように、ウィリアム・ジェイムズにとっては「心」(アラヤ識・如来蔵に通じる)が「媒質」(中動態的なもの、伝導体)であった。つまり、純粋言語は純粋経験とつながっている。)
鈴木大拙の薦めに応じて『宗教的体験の諸相』に接した西田幾多郎は、ウィリアム・ジェイムズ由来の「純粋経験」を根本に据えた『善の研究』を刊行し、ほぼ同時期に卒業論文『言語情調論』を執筆した折口信夫は、「直接言語(純粋言語)」のアウトラインを示した。これらふたつの概念は「ほとんど同じ事態を示している」。安藤礼二氏が『折口信夫』の「言語情調論」の項の冒頭にそう書きつけたことは、以前(第60章で)紹介しました。「主観と客観、あるいは観念と物質、もしくは内部と外部という対立する二つの概念の消滅。折口信夫が「言語」に見ていたものと西田幾多郎が「経験」に見ていたものは等しい。」(75頁)
■純粋言語の系譜、ベンヤミンと折口信夫(翻訳と詩語の問題)
安藤礼二著『折口信夫』の議論をフォローします。
<純粋言語を唯一の実在として世界を一つにつなぐこと>
〇渡米した鈴木大拙はポール・ケーラスのもとで『モニスト』の編集に携わった。この雑誌はプラグマティズムを主張したアメリカの哲学者たちの一つの中心となっていった。外的な宇宙の発生と内的な意識の発生を一つにむすび合わせる独自の「記号論」を主張したチャールズ・サンダース・パースに、ケーラスは『モニスト』の誌面を提供する。(パースの「記号論」が折口の『言語情調論』に間接的な影響をあたえている可能性も無視することはできない。)そのパースの哲学上の盟友がウィリアム・ジェイムズだった。(『折口信夫』76-78頁,88頁)
〇一元論的哲学の確立を模索したケーラスの理論的支柱の一つはエルンスト・マッハの「感覚要素一元論」だった。ケーラスは『感覚の分析』を英訳し『モニスト』に掲載する。『言語情調論』の起源の一つは、疑いもなくその書物にある。(『折口信夫』79頁)
<コレスポンダンス、斜聴、憑依>
話がいきなり「憑依」や「古代学」に飛びましたが、安藤氏によると、「折口信夫の言語学、すなわち折口信夫の古代学」(安藤前掲書124頁)なのだから、そして「「古代」は「言語」にのみ保存されている」(125頁)というのだから、それは決してここでの本題(純粋言語の系譜)から乖離しているわけではありません。
いまひとつ、『折口信夫』の議論を引用します。
ここで言われる「唯心論的な世界」と「唯物論的な世界」の合一は、ベンヤミンにおける「神学」(言語論)と「唯物論」(歴史論)の融合(徳永恂著『絢爛たる悲惨──ドイツ・ユダヤ思想の光と影』収録の「ベンヤミンの方法と方法としてのベンヤミン──歴史哲学の方法としてのアレゴリー」参照)につながるのではないか、私はそう考えています。
さて、ベンヤミンの「言語一般および人間の言語について」を起点とする純粋言語の系譜(水脈)を、(ウィリアム・ジェイムズ⇒鈴木大拙・西田幾多郎⇒井筒俊彦・吉本隆明とつながる純粋経験の系譜(第60章参照)との照応関係を横目で見ながら)、駆け足でたどってきたわけですが、ここで、これとは別の系譜(水脈)の可能性を確認しておきたいと思います。
起点となるのは折口信夫の「詩語としての日本語」。以下の議論の出典は、これもまた安藤礼二氏の著書『迷宮と宇宙』の冒頭に据えられた「二つの『死者の書』──平田篤胤とエドガー・アラン・ポー」です。(ちなみに、『折口信夫』の最後に置かれた論考のタイトルは「二つの『死者の書』──ポーとマラルメ、平田篤胤と折口信夫」。)
<翻訳が顕現させる純粋言語、マレビトと天使が口にする聖なる言語>
〇晩年の折口は「詩語としての日本語」という自らの詩的言語論を総決算するような論考を書き上げた。民俗学と国文学の二つの学問分野にわたって古代学という独自の手法を確立した折口らしく、「古語」を取り入れることで日本の詩の言葉が活性化されるという主題に論考全体が集約されていくかと思われるが、結論部分では「翻訳」によって詩の未来語を開拓していく行為に焦点が絞られる。(『迷宮と宇宙』3-5頁)
〇折口にとって翻訳とは、古語と未来語(古代と未来)を一つにつなげ、外国語でも日本語でもない言葉の第三の領域(表現の地平)を切り開き、「私」でも「あなた」でもない未知なる言語──「マレビト」(=ベンヤミンの「天使」)すなわち自己と他者の間、共同体の外から出現する中間的な存在だけが口にすることができる、諸言語のあわいに紡がれる聖なる言葉、純粋言語──を躍り出させる営為であった。(『迷宮と宇宙』6頁)
○折口の古代学と詩的言語論は首尾一貫した構造をもっている。折口のそのような主張は、「翻訳」こそ「諸言語の互いに補完しあう志向の総体によってのみ到達可能となる」純粋言語を見出すための重要な手段になるのだとした、折口と同時代を生きたもう一人の異邦の思想家を、折口のすぐ脇に召喚するであろう。(『迷宮と宇宙』6頁)
■純粋言語の系譜、折口信夫と井筒俊彦(憑依と原型の問題)
折口信夫の「詩語としての日本語」を起点とする純粋言語の系譜、それも、本邦におけるその系譜(水脈)をたどるなら、西脇順三郎の「完全言語」を忘れるわけにはいかないでしょう(第22章参照)。萩原朔太郎の「純粋詩」や「音象詩」、九鬼周造の押韻論についても同様だと思います(第17章他参照)。
が、これらの表現者や思索家については、いずれ、貫之現象学から狭義広義の定家論理学の世界を経て、子規以降の近代の詩的言語を考察する運びとなった際の宿題にとっておくことにして、ここでは、折口信夫を直接的な淵源とする、井筒俊彦の言語呪術論と吉本隆明の詩語論(芸術言語論)を、ひきつづき安藤礼二氏の論考にもとづいて、一瞥します。
まず、井筒俊彦。
『折口信夫』の「弑虐された神々」の項で、安藤氏は、折口信夫の古代学の確立を、金沢庄三郎の言語学(神の言葉を聞く=託宣)と柳田國男の民俗学(女性たちの憑依=巫女)の総合のうちに位置づけ(219頁)、そのうえで、折口の理論を受け継ぎ、唯一神教の教義を純粋化したイスラームの起源に「憑依」を見出した井筒俊彦こそ、もっとも深く折口信夫の古代学の可能性を読み解いた人間であったと論じています。「折口信夫の古代学は、井筒俊彦の手によって完成するのだ。」(235頁)
折口信夫と井筒俊彦の共通項。ともに「聖なる書物」(『万葉集』と『コーラン』)の翻訳(口語訳)者であり、同時に表現者かつ研究者(詩人学者)であったこと。ともに「憑依」という言語現象のうちに、哲学・宗教・文学の発生を、(あるいは、「思考される前に感ぜられ生きられた真理」(ベルクソン)を)、自らの身と心をもって見いだしたこと。
井筒俊彦は、『コーラン』上巻の解説で、次のように論じています。いわく、古代アラビアの砂漠には「カーヒン」と呼ばれる特殊な人間がいて、ヘブライの預言者か中国の巫者のように、普通の人間と精霊的世界の仲介者の役割をつとめていた。このシャーマン的性格の人間は突然精霊的な力にとり抑えられ、意識を失い「何者か」の言葉を語り出す。
ここで言われる「一種独特の発想形態」すなわち「サジュウ体」は、「神霊的言語形式」(362頁)とか「神憑りの言葉」(363頁)とか「律動的文体」(367頁)とも言い換えられています。
安藤礼二氏は、「井筒俊彦 ディオニュソス的人間の肖像」(『群像』2020年7月号)で、井筒俊彦のこの文章を引き、つづけて、「イスラーム研究者としての井筒俊彦が生涯をかけて探求した、神と預言者、両者を一つにむすび合わせる神の聖なる言葉の在り方とその条件を明らかに」した書物、『言葉と呪術』を取りあげています。
<原型にして母胎、「超越のことば」の発生条件とその構造>
○『言語と呪術』の結論は神と預言者の関係に集約されるが、その全体は井筒のイスラーム研究を大きくはみ出し拡大するものだった。(「井筒俊彦 ディオニュソス的人間の肖像」)
ここで注目したいのは、「原型」もしくは「原型にして母胎」という語彙です。それは、言うまでもなく「言語アラヤ識」という井筒にとって最重要の鍵概念のあり様を表現していて、安藤氏が、「意味の発生は、存在の発生である。それが井筒による東洋哲学の基本構造になる。「外延」は世界を秩序づける意味の分節性と読み換えられ、「内包」は世界を発生させる意味の無分節性と読み換えられた。」(69頁)と書いている、その「基本構造」こそが、言語アラヤ識という「原型(=母胎)」のあり様にほかならないのです。
<言語の二重性─論理と呪術、外延と内包、有限と無限、指示と喚起、外部と内部>
○『言語と呪術』の要諦──言語は、論理にして「外延」、呪術にして「内包」である。言語には、有限の意味を伝える側面(「指示」)と、無限の意味を生み出す側面(「喚起」)の二つが具えられている。(「井筒俊彦 ディオニュソス的人間の肖像」)
(問題は、「内包」(神秘体験、純粋経験、上演されるドラマ)の由来、成り立ちをどうとらえるか、そして、その「外延」(儀礼・密儀、純粋言語、舞台)の表現形式をいかに継承していくかだろう。)
ここで、安藤礼二著『列島祝祭論』の議論を引用します。安藤氏はこの書物のなかで、『言語と呪術』に先立つ井筒俊彦の重要な著作である『神秘哲学』を取りあげています。
<習合・混交の果てに顕れ出る原型、憑依体験からはじまる共時論的構造>
○ディオニュソスの憑依にギリシャ哲学の起源を見出し、プロティノスによる「一者」の体験(純粋経験)のうちにプラトンのイデア論とアリストテレスの形相質料論の総合を見た『神秘哲学』は、柳田國男と折口信夫による「憑依」の民俗学を最も創造的に引き継ぐ試みであり、また(「神秘体験」を西田幾多郎の「純粋経験」と読み換えるならば)神道的な民俗学と仏教的な哲学の総合、神仏習合思想の新たな次元での再生とその乗り越えである。(『列島祝祭論』21頁)
○井筒俊彦は「神憑かり」に哲学の発生を幻視した。『神秘哲学』は、「神憑かり」が可能にした体験(純粋経験)の哲学的な読み換えである。(『列島祝祭論』192頁)
(来たるべき「原型学」をめぐる私的備忘録。──ドストエフスキーのアウラ体験と躁病を代表例とする「イントラ・フェストゥム的狂気」もしくは「ディオニュソス的陶酔」(木村敏『時間と自己』)。反復する発生、未来へ反復する原型、永遠回帰するアクチュアリティ。何度でも顕れ出る覚者(ブッダ)。語りえぬもの(言語道断の詩的主観)の間歇的伝承(俊成)。未来語(翻訳によって開拓される「詩語」)で語られる来たるべき詩学。)
■純粋言語の系譜、折口信夫と吉本隆明(反復と母型の問題)
次に、吉本隆明。
安藤礼二著『吉本隆明──思想家にとって戦争とは何か』に、「折口信夫とは、生涯をかけてこの「表現する言語」の諸相を探究した言語学者だった」(26頁)と書かれています。文中に「この」とあるのは、折口信夫の『言語情調論』が考察した「言語の仮象性を脱して、表現そのものとなった直接性の言語」、すなわち「詩語」のことにほかなりません。吉本隆明と折口信夫の接点が、ここにあります。
ここで語られたこと(その多くが、折口信夫はもちろんベンヤミンにもあてはまるだろうと思う[*1])、すなわち吉本隆明の生涯にわたる「詩語」探究のプロセスを、安藤氏のこのコンパクトながら濃密な書物を通じて、実地にたどってみること、そして、折口信夫(とベンヤミン)の営為との同型性を腑分けしていくことは、スリリングで魅力的な試みだと思います。が、ここでは(ここでも)先を急ぐことにして、「詩語」と「母型」にかかわる議論を任意に抽出するにとどめます。
<反復(畳み重ね)、和語に固有のリズム、枕詞論>
〇『言語にとって美とはなにか』と『共同幻想論』の成果をもとに、和語で表現された歌謡の最古の「かたち」に理論的に肉薄し、そこから和歌の成立までを迫った『初期歌謡論』は、「詩語」をめぐる吉本の探究がたどり着いた一つの到達点である。(『吉本隆明』90頁)
<意味多様体のアモルフで重層した詩語の姿、柳田の地名論と吉本の枕詞論>
〇柳田国男と宮沢賢治。吉本にとって「詩語」の発生とは、この両者の視点の交差と反発のなかにこそ存在している。──吉本(『悲劇の誕生』所収の「童話的世界」)によると、宮沢賢治の表現の世界は「自然の立体視あるいは離人症的な視点」(吉本隆明全集17、268頁)として特徴づけられるもので、そのため賢治は、現実に幻想を、さらにはその幻想の彼方に「死後の世界」のイメージを容易に重ね合わせることさえ可能になったのである。(『吉本隆明』99-101頁)
○柳田国男はさまざまな幻想に取り憑かれやすい資質と始原的な心性を持つ「憑人」(つきびと)であり、「母型」を幻視する者であった。さまざまなイメージを発散する「物語」の原型を探究し、すべての幻想が発生してくる心的な「母型」をつねに意志する柳田国男は、また旅人であった。(『吉本隆明』102頁)
(憑依(表意)と反復、詩語(死後)、そして原型と母型をめぐる私的備忘録。──「原型」(共時的構造)とは純粋な「アクチュアリティ」あるいは「かたち」そのもの、もしくは純粋な「ヴァーチュアリティ」あるいは空虚な内包の「反復」的生起そのものであって、だからそこでは「起源」(オリジナルなもの)が問題にならないのだとしたら、「母型」とはそこに「リアリティ」の軸が交錯した、いわば表現の生命的・物質的・霊的な基盤である。これを強いて前章の《図1》中に位置づけるとすれば、「憑依」(上方からの「受肉」と下方からの「受肉」)によって「詩語」(上方の〈名〉と下方の「詩的言語」)が「人間の言語(公的言語)」へと逆翻訳される際、「原型」は垂直的な次元に、「母型」は水平的な次元にそれぞれ配置される。)
[*1]『母型論(新版)』の「解説」で瀬尾育生氏が、吉本隆明の言語思想を近代以降の西欧的思想と対比している。
[*2]ここで私は、工藤進著『声──記号にとり残されたもの』を想起している。
(この本を読んでいるとき、私はもう疾うの昔に忘れていた懐かしい幸福感を覚えていた。幼少期、我と時を忘れ夢中になって書物を読み耽っているとき、どこからかこみあげてきた身震いするような感覚。そこから立ち上がってくる「声」(著者・作者のものであれ、作中の人物・事物・事象・概念からのものであれ)がもたらす幸せな気分。何が語られているかという内容ではなく、ただそこに「声」が響いていることが与えてくれる愉悦。)
工藤氏は「おわりに──声の心・心の声」のなかで、「声による言葉は情報のみを伝えているものではない」こと、そして「言葉が意味よりも心を伝えるものであるという、どんな人でも体得している」真理がもたらした幸福な体験について語っている。そして、このような脈絡のもとでバベル以後の世界に思いをはせ、言葉に関わるわれわれの感覚器官(その代表が声)を忘れ、言葉をひたすら思弁の具としてきたわれわれの責任感はけっして小さくないと難じている。
美しい文章だと思う。ひさしぶりに引用の歓びを味わいながら抜き書きしたこの一文は、珠玉の名に恥じないと思う。
(私はこの文章の中に「歌の道も」という語を挿入し、「書物(文字)は要するにレシピであり」や、「秀歌の「こゝろ」と「ことば」と「すがた」と「しらべ」[折口信夫が「和歌批判の範疇」で「およそ歌を見、歌を作る上において、必らず心得て置かねばならぬ、[和歌批判と推敲のための]四つの段階的観察点[範疇]」と呼んだもの]を真似し…」といった文章を、溶け込み方式で書き加えたいと思う。)
肝心なことを書き忘れるところだった。私がこの本のことにふれたのは、「故郷の声──宮澤賢治のことばづかい」と題された文章中の次の一節を是非書き写して(移して)おきたかったからだ。
(68章に続く) ★プロフィール★
中原紀生(なかはら・のりお)1950年代生まれ。兵庫県在住。千年も昔に書かれた和歌の意味が理解できるのはすごいことだ。でも、本当に「理解」できているのか。そこに「意味」などあるのか。そもそも言葉を使って何かを伝達することそのものが不思議な現象だと思う。
Web評論誌「コーラ」47号(2022.08.15)
<哥とクオリア/ペルソナと哥>第67章 純粋言語/声と文字/アナグラム(その2)(中原紀生)
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2022 Rights Reserved.
|
| 表紙(目次)へ |
