|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「la Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
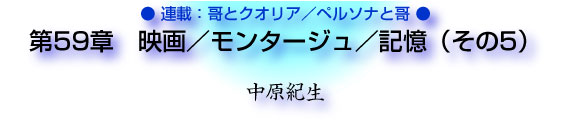
|
|
■不気味なもの─ヒッチコックのモンタージュ(前半)
和歌的モンタージュによって形成される「心的現象=記憶」をめぐる話題へと転じるため、ここで一本、補助線を引きます。
大澤真幸氏が、『今という驚きを考えたことがありますか──マクタガートを超えて』(永井均との共著)に収録された論文「時間の実在性」で、マクタガートの時間の非実在論に対する反論を試み、そのなかで「ヒッチコックのモンタージュ」をとりあげていて、これがとても刺激的なのです。以下、その議論の骨格を摘出します。
1.時間の実在性の証明
〇マクタガートの「時間の非実在論」の骨子は次の通り。
時間の本質は「出来事の先後関係」(B系列)ではなく、「過去/現在/未来」という区別(A系列)にある。
ところで、①「過去である」「現在である」「未来である」は互いに両立不可能な述語である。
しかるに、②どの出来事も「過去であり、現在であり、未来である」。
①と②は矛盾している。ゆえに時間は実在しない。
〇マクタガートに対抗して時間の実在性を証明する戦略は二つある。第一は出来事の実在性を否定すること。第二は「過去であり、かつ、現在である」ような出来事、事象、事態を示すこと。
大澤氏がとったのは第二の戦略で、その際、触媒とされたのが、A系列における〈現在〉と独在性の〈私〉との間に「厳密な並行性」がある、という永井均の「発見」である。
2.永井均の驚きの向こう側
〇〈私〉の本質(何であるかということ)と〈私〉の実存(現に存在しているということ)とは完全に一致する。〈私〉の本質は「ただ現にある」という実存以外にはない。〈現在〉についても同じことが言える。〈現在〉と他の時制(過去・未来)との関係は、〈私〉と他者との関係と類比的である。
〇〈私〉と他者たちとはまったく同じである。誰もが心・意識をもっている。それなのに、ほんものの心・意識は〈私〉の心・意識だけだ。これはまことに驚きではないか!
この永井均の驚きの向こう側に、もうひとつの驚きがある。どうして〈私〉は〈私〉以外の他者にも心・意識が帰属していると確信しているのか? どうして〈私〉は他者もまた(その他者自身が)〈私〉であると知っているのか?
3.ヒッチコックのモンタージュ
〇どうして〈私〉は他者もまた〈私〉であると知っているのか? この問いに答えるため、大澤氏はスラヴォイ・ジジェク(『斜めから見る』)の分析にもとづく「ヒッチコックのモンタージュ」を援用する。
〇たとえば、ヒッチコックは『サイコ』のなかで次の二つのショットを交互に用いている。
① 行方不明になった姉のマリオンを探すライラが、ノーマンの母が住んでいると思しき古い家へと向かう客観ショット
② ライラが目指している古い家の主観ショット=〈私〉としてのライラの視点から見た世界のたち現れ方を表現する映像
〇このような効果(家も〈私〉を見ている)は、このモンタージュを構成するショットとは別の二種類のショットが排除されていることからくる。
③ ぶきみさを発散している家を(ライラの視点以外の)中立的な視点から捉える客観ショット
④ 接近の対象となっている家そのものを主観化したショット=家の内側からライラを見下ろすショット
[*]中井正一は「生きている空間――映画空間論への序曲」(『中井正一全集第三巻 現代芸術の空間』)で、「ローマン的皮肉[イロニー]とは、ヘーゲルの友人のゾルゲルで代表されるところの一つの表現、自分たちのすべてのおこないや言葉のすぐそばに、「黙ってジッと自分を見つめているまなざし」があるという一つの不安と怖れである。」(210頁)と書き、「ハイデッガーの存在論も、この不安の凝視を哲学の中に再現している。」(211頁)と書いた。
また「芸術的空間──演劇の機構について」(『中井正一評論集』)では、「ゾルゲルのイロニーの眼」をめぐって「ハイデッガーのいう何ものかの前に感ずる‘てれたるこころもち’unheimlich」(141頁)をとりあげている。
伊集院敬行氏は「モンタージュが暴露する「無気味なもの」としての現実──中井正一の映画理論にある精神分析的側面について」のなかで、「「模写論の美学的関連」で中井は,カントの実体論に対してハイデ ガーの存在論を評価し,ハイデガーのいう存在の開示を精神分析による無意識の暴露と重ね,モンタージュがこれをもたらすと考えた」と書き、次のように論じている。(以下に引用するのは、前々章の最終節で引いた個所に先立つ文章である。)
文中に「認識の達しない深みにおいて自分自身にめぐりあう」とあるのは、プルーストの言葉。
■不気味なもの─浮遊する視点、アウラ的知覚
いったん中断。
ここまでの議論を参照しながら、(和歌的)モンタージュの空間から(和歌的)記憶の垂直軸が立ちあがるメカニズムの前段、すなわち、和歌的モンタージュの動態を通じて「歌の姿」が立ちあがり、そこに「歌の心」が吹きこまれていくプロセス[*1]をめぐって、若干の「外形的」考察をくわえます。
・フロイトによれば、「不気味なもの」とは「慣れ親しんだもの、馴染みのものであり、それが抑圧された後に回帰してきたもの」のことである(「不気味なもの」、中川元訳)。
・そうだとすると、ヒッチコックのモンタージュにおいて〈私〉を見つめ返すもうひとつの〈私〉、この〈私〉ではない〈私〉=〈他者〉[*2]の「ぶきみな」眼差しとは、「ライラ=観客」としての〈私〉のうちにはりつき同一化した「観客=共視者」の視点が(剥離するのではなく)身体なき意識のように浮遊し、モンタージュ空間の「外部」に通じる事物(物自体?)に定位(憑依?)したものなのかもしれない。
・ベンヤミンは、「…夢の中では[私と私に見えている事物とのあいだに]等式が存在する。私が目にしている事物は、私がそれを見ているのと同じように、私を見ているのだ。」というヴァレリーの文章を引き、このような「夢における知覚」を「アウラ的知覚」と名づけた[*3]。
・夢(映画)のなかでは、事物を見つめる「ライラ=観客」としての〈私〉と、この〈私〉を見つめ返す事物(「観客=共視者」としての〈私〉=〈他者〉もしくは集団的なエス)とのあいだに「等式」が存在し、そこには「アウラ的知覚」が成り立っている。
[*1]そのプロセスの骨子を記しておくと、まず「歌の姿」は、前章の末尾に「使い道のない追い書き」として示したイマージュの四分類を想定している。
【歌の姿Ⅱ】=「インデックス」(オリジナルに対するコピー)としての「像」
【歌の姿Ⅰ】=「イコン」(オリジナルが受肉したコピー)としての「喩」
【歌の姿Ⅲ】=「シンボル」(コピーなきオリジナル)としての「象」
【歌の姿〇】=「マスク」(オリジナルなきコピー)としての「肖」
また「歌の心」については、これまでこの論考群で様々な観点から論じてきたし、その中間総括と言えるものはかつて(第42章で)整理したところだが、ここでの論脈にそくして、あらためてその四類型をめぐる試案を示しておく。
【歌の心Ⅱ】=詠み出された心(狭義の歌の心、実在の作者の心)
・世の中を「ことわざしげく」生きる生身の人の「思ひ」(「和歌」を言い出す心)
【歌の心Ⅰ】=詠みつつある心(虚構の作者の心)
・すべての「生きとし生けるもの」のうちに宿る普遍的な心(「こゑ」を生む心)
【歌の心Ⅲ】=個別の和歌の詠出に先立つ心
・ある特殊な生物種のうちに宿り、やがて「ことのは」へと生長する「たね」としての心(「やまとうた」を詠み出す心)
【歌の心〇】=読みつつある心(実在もしくは虚構の読者の心)
・森羅万象にわたって様々に分岐する心の無限集合、カミの心、タマやスピリット、霊の次元の心(「響き」となって顕われる心)
[*2]このもうひとつの〈私〉を「ドッペルゲンガー」と捉えていいだろうか。
フロイトは、ドッペルゲンガー(分身)とは「自我の消滅を防ぐための防衛機構」であり、「不死」の霊魂こそが肉体の最初のドッペルゲンガーだったと書いている。そして、ドッペルゲンガーの不気味さを「反復強迫」の不気味さに関連づけている。この反復強迫は「欲動のもっとも内的な本性から生まれるものであって、快感原則を超越してしまうほど強いものであり、精神生活の特定の側面にデモーニッシュな性格を帯びさせる」。
道籏泰三氏は「不気味なものを見つめる――ベンヤミン特集によせて」(『思想』2018年7月号の「思想の言葉」)で、次のように書いている。
[*3]ベンヤミン「ボードレールにおけるいくつかのモティーフについて」(山口裕之訳『ベンヤミン・アンソロジー』262頁)による。ただし、以下の引用は『ベンヤミン・コレクション1』収録の久保哲司訳。
この最後の文章にベンヤミンは次の註をつけている。
言葉もまたアウラをもつ。のみならず「真のアウラはあらゆる事物に現われる」(飯吉光夫訳『陶酔論』143頁)。
■純粋過去─ヒッチコックのモンタージュ(後半)
4.他者はどこにいるか
〇ヒッチコックのモンタージュの効果として現れたもうひとつの〈私〉すなわち〈他者〉をめぐって、大澤氏はレヴィナス(『存在するとは別の仕方で』)の議論を援用する。レヴィナスは、〈他者〉の現前(=現在)は「そこにないものであるかのように」求められると書いた。
〇他者の皮膚に触れている最中にそのことを意識してしまうと、それは愛撫ではなく触診に変わってしまう。〈私〉が他者の〈顔〉を見ているとき、〈他者〉(他者の〈私〉)はすでに(〈私〉への)現前から退いてしまっている。(このような〈他者〉の逆説的・否定的な現前の様態を、大澤氏は「遠心化」と呼ぶ[*]。)
それと同じように、〈他者〉を〈私〉が何ものかとして同定し〈私〉へと現前(=現在)させようとしたとき、〈他者〉はもはやそこにないものとして現れるほかない。
5、純粋過去
〇大澤氏はここでドゥルーズの「純粋過去」の概念に接続する。ジェイムズ・ウィリアムズによると、純粋過去とは「すべての出来事が蓄積され、去り行くものとして記憶される、絶対的過去」である。
〇たとえば、今まさに起きつつある出来事について「私は今……している。」と言明するとき、この言明はすでに「過去の出来事の回想」というモードをわずかであれ含んでいる。つまり、「未来を先取りし、その未来の視点から遡及的に捉えたときに過去になるはずの出来事」として、現在は言及されているのである。
〇こうして、われわれはマクタガートの「時間の非実在」についての証明を破り、克服することに成功した、と大澤氏は括る。
6.ふたつの補足─自由と未来
〇すべての出来事は純粋過去の中に含まれている。このような主張は極端な決定論を含意しているように見えるかもしれない。過去・現在・未来のあらゆる出来事が「純粋過去」という非時間的な領域の中で、互いに互いを規定する緊密なネットワークを構成し、そこにはいっさいの「自由」がないといったように。
〇大澤氏は最後に、「未来」という時制の由来、本性について考察している。未来の未来たるゆえんは「絶対に還元できない不確定性」である。そしてそれは〈他者〉を規定する条件でもある。だとすると、こう断言してもよいのではないか。未来とは〈他者〉であり、〈他者〉は、その本来性においては未来なのだ、と。
[*]「遠心化」について、大澤真幸著『身体の比較社会学Ⅰ』から。
大澤氏いわく、「驚くべきは、求心化作用を励起させつつ遠心化作用をも作動させることができる、身体の能力である」(33頁)。
なお、大澤氏は『身体の比較社会学Ⅱ』の「あとがき」で、次のように書いている。
大澤氏がここで示唆しているのは、いや明言しているのは、〈私〉と〈他者〉が絶対的な差異性において同一であるということだ。あたかも「ライラ(〈私〉)=観客・共視者(〈他者〉)」であるように。(この「同一性」の解釈に応じて、かの「一者」と「白光」が分岐するのだろう。)
■純粋過去─時間の実在化、想起のコペルニクス的転回
以上の議論を手掛かりに、(和歌的)モンタージュの空間から(和歌的)記憶の垂直軸が立ちあがるメカニズムの後段、すなわち、「歌の姿」に充填された「歌の心」が、その濃度(深度と高度)を増し、やがて、いにしへよりこのかたへ伝承される「歌の道の深き心」、言い換えれば「詩的共同主観」の系譜がかたちづくられるプロセス[*1]をめぐって、「外形的」考察をかさねます。
・ドゥルーズは『差違と反復』第二章で「生ける現在(現実性)/純粋過去(潜在性)/未来に向かう超越論的時間(永劫回帰)」という三つの時間概念を提示した[*2]。
・これを参照すると、第一の時間(現在)は身体なき意識が自在に移動する(和歌的)モンタージュ空間において生起し、そこから垂直方向に立ちあがる(和歌的)記憶の軸における二方向のうち、第二の時間(過去)はいわば「深度」=(和歌的)伝統の形成に、第三の時間(未来)は「高度」=(和歌的)生成・創造にそれぞれかかわる。
・未来の視点(虚焦点)から自らを過去の一部として知覚する。この「現在の出来事」にかかわる時間的パースペクティヴを「過去の出来事」にあてはめることによって「想起のコペルニクス的転回」[*3]が生じ、(和歌的)過去の歴史(歌の道)が、すなわち〈他者〉(詩的共同主観)の系譜が、(和歌的)現在において制作される。
・さらにこれを「未来の出来事」にあてはめると「アクチュアル」な〈他者〉、つまり「詠みつつある〈私〉」=「読みつつある〈私〉」が、言い換えれば〈言語〉が産出される。
[*1]俊成の「古来風躰抄」に、「この道[歌の道]の深き心、なを言葉の林を分け、筆の海を汲むとも書き述べんことは難かるべければ、ただ、上、万葉集より始めて、中古、古今・後撰・拾遺、下、後拾遺よりこなたざまの歌の、時世の移りゆくに従ひて、姿も詞もあらたまりゆく有様を、代々の選集に見えたるを、はしばし記し申すべきなり。」とある。尼ヶ崎彬氏は、『花鳥の使──歌の道の詩学Ⅰ』に収められた俊成論のなかで、この一文を引き、「改まるのは、むろん「姿」と「詞」だけであって、「深き心」は「時世」を超えて貫道する。」(88頁)と書いている。
この「歌の道の深き心」=「詩的共同主観」の系譜がかたちづくられるプロセスを通じて、歌の道の伝統すなわち(和歌的)記憶が形成される。
しかしそこで根幹をなすのは、記憶内容ではなく記憶主体である。それは、歌の道の伝承にあたって肝心なことは詠歌内容(狭義の歌の心)や歌の姿・詞にではなくて、歌の姿・詞の系譜の通奏低音をなす「深き心」(詩的共同主観)の方にあるのと同断である。
永井均氏が『存在と時間──哲学探究1』で、記憶について考察している。いわく、思い出す記憶は必ず自分の記憶であって、自分の思い出が全体として他人の視点からの思い出に変わっているのに気づくなどといったことはない。もしあったとしても、それはあくまでも推論であり直観ではない。自分が体験したという形をとって現われなければそもそも記憶であるとはいえない。
詠歌をめぐる体験体験の記憶のアルシーヴ、精確に言えば、詠歌内容のリアルな集積ではなく、歌の道の深き心のアクチュアルな系譜の積層(「俯瞰的で遠近感を失った重なりあい」)にアクセスすること、それが、「本当の歌人」にいたる道である。
[*2]本文で参照するほど充分に咀嚼できなかったが、檜垣立哉著『瞬間と永遠──ジル・ドゥルーズの時間論』は刺激的な考察に満ちている。ここでは、ドゥルーズとベンヤミンの関係性について(「アウラ」と「アクチュアルなもの」をめぐって)論じられた箇所をとりあげておきたい。
その1.檜垣氏は、第5章「断片の歴史/歴史の断片」の「ベンヤミン──瓦礫の断片とドゥルーズの歴史」の項で、ベンヤミンが「歴史の概念について」に書きつけた「現在時(Jetztzeit)」や「アクチュアルなもの」という概念を、「複製技術時代における芸術作品」で論じられた「アウラ」(「夏の午後、静かに憩いながら、地平に連なる山なみを、あるいは憩っている者の上に影を投げかけている木の枝を目で追うこと」云々)に関連づけて論じている。
この最後の一文に付した註のなかで、檜垣氏は、「ドゥルーズが描く映像のテクノロジーは、透明な夏の空気のなかでいっさいの距離を近くにとり戻すアウラ的なものを「見せる」装置そのものではないか」(136頁)と書いている。
これと同じことがベンヤミンンも言える。「…ベンヤミンは複製芸術そのものにノスタルジックな「本物性」の消滅を読み込んでいるだけではない。…むしろファシズムが「耽美主義的」に利用してしまった複製芸術を(ベンヤミンが述べるところの)コミュニズム的な利用においてとり戻すことにある。写真や映画というメディア一般に対して、ベンヤミンはあくまでも新しい時代の「知覚」の到来をみている。」(18頁)檜垣氏はここで、自著論文「記憶の実在──ベルクソンとベンヤミン」(『思想』2009年12月)の参照を注記する。
その2.終章「自然の時間と人為の時間」で、檜垣氏は第三の時間に関連して次のように論じている。
ここでも檜垣氏は註をつけている。そのなかで「身体は、オリジナルな体験の装置というよりも、そこにはまさに「振る舞い」において「ふりをする」という事態が織り込まれている」と書き、坂部恵の参照を促している。
場違いな付言。ほんとうは「歌の姿」や「歌の心」と同様、「夢の時間」の四類型(第54章で論じた「インメモリアルな過去、未来完了・前未来、回帰する時間、永遠の今」)をここでの文脈にそくして(また、第56章の想像的叙述のなかで言及した、モンタージュの空間における「永遠の今」と「永劫回帰する今」との整合性に留意しながら)再整理のうえ提示すべきところだが、「理論的」に錯綜をきわめ手に負えない。
ただ一言述べておくとすれば、(和歌的)記憶の垂直軸の形成、すなわち三つの時間の生起を通じて、「夢の時間」の四類型という時間の概念が実在化する(「離接」的な「原初」に「連接」的なつながりが生みだされる?)のではないか、そしてそのことによって(言語や歴史といった)貫之現象学のより高次のステージがひらかれていくのではないか。(だから、この論考群のこの段階で【時間〇】から【時間Ⅲ】までの四類型を提示することが叶わなかったのではないか。)
[*3]ベンヤミンは『パサージュ論──Ⅲ 都市の遊歩者』に収録された「K:夢の街と夢の家、未来の空間、人間学的ニヒリズム、ユング」の項の冒頭に、「私が以下で提供しようとするのは、目覚めの技法についての試論である。つまりは、追悼的想起[Eingedenken]の弁証法的転換あるいはそのコペルニクス的転換を認識しようとする試みである。」と書いている。
道籏泰三著『ベンヤミン解読』によると、ベンヤミンは、無意識的・主客融合的な「想起(Eingedenken)」ないし「経験(Erfahrung)」と、意識に浸透され主観的に構成された「追想(Erinnerung)」ないし「体験(Erlebnis)」とを区別した。「「想起」とは、かつて生じたことをはっきりした意識のなかに呼び起こすことではなくて、むしろ過去の思い出が、プルーストの言うように、無意識の淵よりおのずからふと甦ってくることをいう。」(142頁)
ベンヤミンの「想起」は、おそらくドゥルーズの「第三の時間」に通じている。
檜垣前掲書(27-29頁)によると、第三の時間は、「現在という経験の場面を、そしてそれを形成する記憶という水準を成立させるために、超越論的な審級として要請される」のだが、しかしそれは「たんなる空虚な形式」であるだけでなく、「経験不可能な経験の原型として、ある種のイマージュ化が果たされている」。「直線としての時間が永劫回帰の時間となり、それ自身として一種の迷宮を描きだす。経験から明らかに逸脱した、この超越論的領域のイマージュ化」。そこでは、「時間の蝶番が外れ、「タナトス」として想定される無限に開かれた時間が描かれる」のだが、「無限の時間をダイレクトに表現すること、それは狂うことでもある」。
■イマージュの世界から象徴の世界へ
川端康成の『雪国』の冒頭に、夜汽車の窓ガラスに映った「悲しいほど美しい声」の娘・葉子と夕景色がオーバーラップする情景を描いた美しい文章があります。
私はここで、不遜ながら文豪が用いたのと同じ言葉をつかって、ひとつの決意を語っておきたいと思います。すなわち、これより「この世ならぬ象徴の世界」へ入り、そして、後方にとり残してきた多くの「瓦礫」や「屑」を拾い集め、救出し、(モンタージュして?)、貫之現象学B層の世界を切りひらいていきたいと。
モンタージュの空間から心的現象が立ちあがるプロセスの概観を通じて、私は、ふたつの概念を手に入れることができました。ただしそれは、まだ精錬されない生の素材(瓦礫あるいは屑)にすぎず、これらを極め、自家製の「概念」に鍛えあげていくのは、これからの課題です。
そのひとつ、プロセスの前段から浮上してきたのが「アウラ」です。さまざまな論点に関連づけることができる、とても豊饒な含みと射程をもった概念ですが、B層との関係でいえば、「人称」の秘密に深くかかわってくるだろうと思います。(というか、そのような問題意識をもって、「アウラ」について考察してみたいということです。)プロセスの後段からは、(コペルニクス的転回のもとでの)「想起」の概念が浮上してきました。同様に、B層との関係からは、「時制」の秘密に深く関係していると考えます。
このふたつの概念は、いずれもベンヤミンに由来する(ジル・ドゥルーズにも関係する)ものであると同時に、三浦雅士氏が言語成立の条件として述べた「俯瞰しながらその見ている対象に身を移す能力」のうち、「アウラ」が「相手の身になること」に、(つまり、〈私〉と〈他者〉の反転可能性あるいは憑依可能性に)、そして「想起」が「自他をともに一望する俯瞰する目」に、(これを時間的パースペクティヴにおきかえて、逆向きのデジャ・ヴュあるいは(時間的な)遠心化作用に)、それぞれかかわってきます。
貫之現象学B層の関心から言えば、「様相」や「感情」がどうなっているのか、が気になるところです。「様相」について言えば、たとえば、フレームの外部につながる「現実」[*]といった、(常套化したモンタージュを批判した)アンドレ・バザン的なテーマが、この論点に深くかかわってくることでしょう。
「感情」については、まだここで論じる準備がととのっていませんが、ただ、「不気味なもの」には内容がないこと、すなわち、内容(ヒッチコックのモンタージュにおいて封印されたショット③や④)が与えられると不気味さが消失すること、そして、「体験体験」(永井均)というアイデア、「アプリオリな形式」としての第二の時間や「空虚な形式」としての第三の時間、さらには「死の欲動(タナトス)」が向かう場所、「演示」や「展示」や「振る舞い」が表現するもの、等々の、「事象内容・実在性(リアリティ)」をもたない「現実性(アクチュアリティ)」をめぐる問題群が、私が考想している第四の文法カテゴリーとしての「感情」に深いところでかかわってくる、とだけはこの場で書き記しておきたいと思います。
──多くの論点を(瓦礫や屑のように)放置したまま、貫之現象学A層をめぐる議論を閉じます。
[*]加藤幹朗著『映画とは何か』第Ⅴ章「アメリカ映画のトポグラフィ D・W・グリフィスのアメリカン・インディアン初期映画」から。
(43号に続く)
★プロフィール★
中原紀生(なかはら・のりお)1950年代生まれ。兵庫県在住。千年も昔に書かれた和歌の意味が理解できるのはすごいことだ。でも、本当に「理解」できているのか。そこに「意味」などあるのか。そもそも言葉を使って何かを伝達することそのものが不思議な現象だと思う。
Web評論誌「コーラ」42号(2020.12.15)
<哥とクオリアア/ペルソナと哥>第59章 映画/モンタージュ/記憶(その5)
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2020 Rights Reserved.
|
| 表紙(目次)へ |
