|
|
|
Web�]�_���u�R�[���v |
|
���n���̎� ���{���̕\���i�ڎ��j�� ���{���̃o�b�N�i���o�[ ���ǎ҂̕Ł^���ӌ��E���z �����e�K�� ���W�҂�Web�T�C�g ���v���C�o�V�[�|���V�[ |
|
���{���̊֘A�y�[�W�� |
|
���u�J���`���[�E�������[�v�̃o�b�N�i���o�[ ���]�_���u�k�� Vue�v�̑��ڎ� |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
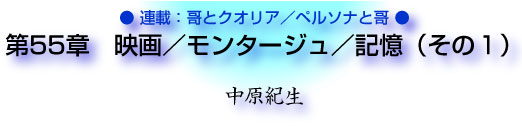
|
|
�������a�͉̂f��ł���
�@
�@�����a�̂Ɖf��Ƃ̖��ڂ��B�ݓI�ȊW���ɂ��āA�������t��₤�ƁA���������W���������قȂ�ӂ��̗̈�ɂ�������I�̌��A�܂�u�r�̑̌��v�Ɓu�f��̌��v�Ƃ̂������ɂ́A�i���ꂪ�{���ɂ��������̂����ۂɂ����Ȃ����A���邢�͓��I�\���������炷�K�R���O�I�Ɉ˂���R���A���X�̑F�c�͂��Ă����j�A�Ȃɂ����猩���Ȃ��W��������ł���̂ł͂Ȃ����A�Ƃ������̒��ς������m�点�鉼�����߂����Ą����A���̘_�l�Q�ł́A����܂ł��炳�܂��܂ȉӏ��Łi���̑����́A����Δ��Y�^�̂悤�Ȃ������Łj���y���Ă��܂����B
�@���������a�̂̐��E���f��Ɗ֘A�Â��čl����悤�ɂȂ����A���̂��������̔��[�́A�w�ፑ�x�`���́A�u�f��I�v�Ƃ����`�e���ӂ��킵�����A���ȐS�ۂ����N���镶�͂��߂����āA����́A�u�����̒����g���l������Ɛፑ�ł������B�v�����A�u��̒ꂪ�����Ȃ����B�M�����ɋD�Ԃ��~�܂����B�v������Ƃ�����̘a�̂Ɍ����Ă邱�Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����A�Ǝv���������Ƃɂ���܂��i��Q�͎Q�Ɓj�B
�@���܁u�f��I�v�Ə������̂́A���Ƃ��w�閾���O�x�̖`���̈ꕶ�A�u�ؑ\�H�͂��ׂĎR�̒��ł���B�v���o��ł���A��i���q�ϓI�E�����ԓI�ɘ��ՁA���k���ĕ`�ʂ���ꕝ�̉�ł���Ƃ���A�w�ፑ�x�̂���́A���Ԃ̐��ڂ������炷��i�Ɛg�̌o���̕ω���D�肱�A�����ɂ���ϓI�ȁA���邢�͉i��ϒ��w���c�����Y��������A�ݕ��A���v�̐����̓�ցx�i�p��\�t�B�A���Ɂj�̋c�_�����p����ƁA�u���������āu���v�Ƃ�������g���Ȃ�A�����̒����g���l������Ɛፑ�ł������Ƃ����A���̂��Ƃ��ꎩ�̂��u���v�Ȃ̂ł���v�i17�Łj�ƌ��������Ȃ��A��q�����ȑO�́u�����o���v��`�ʂ��鄟���i�䎁���g���p�����ʟ����Ō����A�u���v�Ȃ�ʁu�����v�̎��_���������鄟���u�ÂɓƉ�_�I�v�Łu��l�̓I�v�ȁu��������`�v�i��Ώ��j�j���v�킹��A�Ƃ������̌l�I�̌��������\�킷��g�\���ɂق��Ȃ�܂���B
�@�������A����͒P�Ȃ��g���Ă���B���Ȃ킿�A�����a�̂́u�f��I�v�Ȃ̂ł͂Ȃ��āu�f��v���̂��̂Ȃ̂��B������A�w�ፑ�x�`���̕��͂����̘a�̂Ɍ����Ă邱�Ƃ́A�������т̃V���[�g���[�r�[�ƌ��邱�ƂƓ��`�Ȃ̂ł����āA�����A�u�f��^�����^�[�W���^�L���v�̑���̂��ƂŖژ_��ł���̂́A���̂悤�ȁu�����a�͉̂f��ł���v�Ƃ�������̑Ó����Ǝ��������ɂ߁A���ꂪ�a�̓I���I����̐��E�ɂ����炷�A��������߂�A�Ƃ������Ƃɂق��Ȃ�܂���B
�@
�@�����ŁA�F�J���K���w���{��͉f���I�ł��鄟���S���w���猩���Ă�����{��̂����݁x�̋c�_�����p���܂��B
�@���킭�A�r��ÕF�i�w�u���{��_�v�ւ̏��ҁx�A�w���{��Ɠ��{��_�x�i�����܊w�|���Ɂj�j�ɂ��ƁA�u�����̒����g���l������Ɛፑ�ł������B�v�̃T�C�f���X�e�b�J�[�ɂ��p�uThe train came out of the long tunnel into the snow country.�v���\�����p��b�҂����ɕ`�悳����ƁA�u�g���l�����o�āA��̐ς����������Ɏp����������Ԃ���猩�Ă���v�悤�ɕ`���A���{�l�̓ǎ҂́u�g���l���̓��������̕����ցA�Ƃ����A�ԑ���ʂ��Ă݂��f���ω��v���v�������ׂ��B���J���m�i�w�p��ɂ����͂Ȃ������x�j�́A���̉p��Ɠ��{��̎��_�̈Ⴂ���u�_�̎��_�v�Ɓu���̎��_�v�ƌĂ�ŋ�ʂ����B
�@������Ɠǂݎ�Ƃ̂����������łȂ��A�u���ҁv�Ɓu���ҁv�Ƃ̂������ɂ����Ă͂܂�\��������B���������\������{�Ƃ�����́A���ꂱ���A���i�������j�����ꂩ��l���悤�Ƃ��Ă���u�f��v�ɂق��Ȃ�Ȃ��B�����ł́A���҂����҂̕��g�ł���A���҂����҂Ƃ��Ċ������Ă���A���邢�͎��҂����҂̂��ɏ�ɕt���Y���Ă���B���̎��҂̖����u����v�Ƃ����A���҂Ɛ��҂�������Ō��߂Ă���f���ω����u���j�v�Ƃ����B
�@�摖�肪�߂��܂����B�i�u����v�͊єV���ۊw�a�w�́A�u���j�v�͂b�w�̃e�[�}�B�j�b�����ɂ��ǂ��܂��B�����ł́A���ꂩ��̋c�_�̋N�_�i���邢�͏I���_�H�j�𐘂���Ӗ��ŁA�w�ፑ�x�`�����̓lj���ʂ��Ē��o���ꂽ�A�l�̎��_���L�^���Ă��������Ǝv���܂��B
�@
��p��̎��_��
�@���S�̂���Ղ���u�_�v�̎��_�����u��������ł������R���玩�Ȃ����������A���͂⎩�����g�������Ώۉ����āA�o�����̊O���̏��q�ϓI�ɒ��߂�v�p��b�҂̎��_�i���J�O�f��14-15�Łj�B
�@
����{��̎��_��
�A���Ԃ̐��ڂƂƂ��Ɉړ�����u���v�i��l���j�̎��_�����u�D�Ԃ̓����ɐg��C�����Ҏ��g���A���炩�Ɂu�����v�Ƃ����g���̎��_�h�ɂ����āA�g�g���l���̈ł������h�g���A�ፑ���I�h�ƍ��X�ڂ�䂭�ԑ��̕��i�ɋ��Q���A���̐܁X�̌��ݎ��_�ł̔�����A�u�ԏu�Ԃ̐S�̓���[�I�ɓ`����v��ѐ�����������ҁi���̕��g�ł����l���j�̎��_�i�X�c�Ǎs�w���{�l�̔��z�A���{��̔��z�x15�Łj�B
�B���Ԃ̐��ڂƂƂ��Ɉړ�����u���v�i�ǎҁj�̎��_�����z���̒��Łu������̕��g�v�i��l���j�̂��ɏ�ɕt���Y���Ă���u�ǂݎ�̕��g�v�̎��_�B
�C��q�����̏����o����`�ʂ���u�ÂɓƉ�_�I�v�Ȏ��_�����u���E�̒��̌��i���Ƃ������Ƃ��j�v�̎��_�ł͂Ȃ��u�����v�̎��_�i�i��O�f��17�Łj�B
�@
�����{��͉f���I�ł���
�@
�@�Ƃ���ŁA�O�߂ň��p�������͂̂Ȃ��ŌF�J���́A�u�b����ƕ����肪������ŋ��L����f�������߂�v�Ƃ����A���{��̊�{�\���Ɍ��y���Ă��܂����B���̂��Ƃɂ��ďڂ������邽�߁A�w���{��͉f���I�ł���x�̋c�_���������܂��B
�@
�P-1�D����̊�{�\�������O���W�Ƌ�������
�Z�l�Ԃ̃R�~���j�P�[�V�����̊�{�`�́A�u�q�ǂ��v�Ɓu��l�v���ڂ̑O�́u�Ώہv�ɋ����̒��ӂ������邱�ƁA���Ȃ킿�u���������v�ɂ���Đ��藧�O���W�ł���B�i�A�Łj
�Z�R�~���j�P�[�V���������W���Ăł�������́A�N�����ʂ̒N���ɉ�����`���������甭������B���Ȃ킿����́A�u�b����v�u������v�u���L�f���v�̎O���W�̍\�������B�i7�Łj
�@
�P-2�D����̊�{�@�\
�Z�q�ǂ������Ƃ��g���n�߂�Ƃ��A���Ƃɋ��߂��邱�Ƃ��ȉ��ɗ�L����B�ǂ̌���������̓������s�������݂����邪�A����ɂ���Ă��̂����݂ɈႢ������B�i12�Łj
�E�Ώۂ��ʒu���邨���悻�͈̔͂��w�����邱�ƁB
�E���͈̔͂̒�����Ώۂ�I�яo�����ƁB
�E�ΏۂƑΏۂƂ̊W��\�����ƁB
�E�ߋ��▢���ɂ��Č�邱�ƁB
�@
�Q-1�D�u���E���E���v���f���g�Ƌ����Ώ�
�Z�u���L�f���v�͈��͈̔͂��������̂Ȃ̂ŁA������͂ނ��̂��u�f���g�v�ƌĂсA���̉f���g�̒��ŋ�����������Ă�����̂��u�����Ώہv�ƌĂԁB�i8�Łj
�Z�u�f���g�v�i�f���͈̔́j�������w�����̂����A�u�����v�i�ߏ́j�͘b����̋ߕӁA�u�����v�i���́j�͕�����̋ߕӁA�u�������v�i���́j�͘b����E�����肩�痣�ꂽ�̈���w���A���ꂼ��́u�����Ώہv�́u����v�u����v�u����v�Ŏ������B�i16-18�Łj
�Z���{��̎w�����͈ʒu�Ƌ����ɉ����đ̌n�I�ȍ\���𐬂��Ă��邪�A�p��̎w�����́u���������i���������j�v�Ɓu�����������i���������j�v�̓�ŁA��Ԃ̋�肪�����܂��ł���B�i18�Łj
�Q-2�D�u���E���E���v�������w���ɂ�����I��
�Z������O�ɂ��čs����u����w���v�Ɂu���i�ߌi�j�E���i���i�j�E���i���i�j�v�̗̈�敪���������̂ɑ��āA���ꂩ�痣�ꂽ�����i�l�⎞�j�ɑ���u�����w���v�ł́A���̏���b���肪�����Ă��邩�i���̎��j�A�����肪�����Ă��邩�i���̎��j�A���邢�͋��L���Ă��邩�i���̎��j�ɂ���āu���E���E���v�̑I��������̂���{�ł���B�i93�Łj
�@
�Q-3�D���̈����n�����u���v�n�̎w�����̓���
�Z��b�̒��Řb����i�u���v�j���畷����i�u���v�j�Ɉ����n����邱�Ƃ�����B���Ƃ��u���̓����܂������i�ނƁA�����ɗX�ǂ�����v�ł́A�b����͑z���̒��ŕ������������Ă���B�܂�X�ǂ܂ł̏�����Ɉ����n���Ă���B�u���v�n�̎w�����́A�z���̒��ŁA�b���肪������̖ڂ̑O�ɉf������A������n�������������Ă���̂ł���B�i93-96�Łj
�@
�R-1�D���{��Ɖp��̎��_���������猩�邩�O�����猩�邩
�Z���{�ꕶ�Ɖp�ꕶ�̎��_�̈Ⴂ���J�����̈ʒu�̑���ɒu��������ƁA���{��ł́A�b����͎O���W�̓�������A�O���Ɍ����Ă�����̂�\���i�������_�j�B��������{�ꕶ�ł͘b����ƕ�����͏ȗ�����邱�Ƃ������A���L�f�����̑Ώہi��O�ҁj�����ꂪ�����Ώۂł���Ώȗ������i�u���A�i�c���j�����v�j�B�i38�Łj
�Z����A�p��ł͊O������O���W�̑S�̂𑨂���`�����̂ŁA�b�������������Ώۂ�����̒��Ɏ��܂�i�O�����_�j�B�b�ւ̎Q���҂������Ă��A����ɕ\�����Ƃ��e�Ղł���B�i38-39�Łj
�R-2�D���{��Ɖp��̎��_�ړ����n����}���}����n��
�Z���{��ɂ�镶�̍\���́A�܂����������̘g���߁A���ɂ��̒��̑Ώۂ�I��ł����Ƃ����������Ƃ邱�Ƃ������B�u���C�̏����̈�̔����ɂ�ꋃ���ʂ�ĊI�Ƃ���ނ�v�̂悤�ɁA�����O�E�V���b�g����n�܂�~�f�B�A���E�V���b�g�A�N���[�Y�A�b�v�E�V���b�g�ւƐi�ނ̂���{�̗���ł���B�i101-102�Łj
�Z����ɑ��āA�p��̂��Ƃ̍\���͒��S������ӂցA�o��������ꏊ�A���ւƁA���{��Ƌt�̌ꏇ�Ői�ށB�p��́u�}����n�ցv�̏����Ői�݁A���{��́u�n����}�ցv�̏��ō\������邱�Ƃ������B�i103-106�Łj
�@
�S-1�D���{��̉f���\���@���u�́v�Ɓu���v���߂���f���I���_
�Z���{��̏����u�́v�́A���L���ׂ��f���̘g���i��A�ڂ��B�f�����N���[�Y�A�b�v�����艻�����E�Δ�E���ӂ̓��������B����ɑ��āu���v�́A�^����ꂽ�f���͈̔͂̒��ŗv�f��I�����铭�������Ă���B�i49-50�Łj
�Z���{��̎g�p�ɂ͉f���I�Ȍ����������Ă���B�b����ƕ����肪�f�������L���A���̒��g�ɂ��ďq�ׂĂ����ɂ́A�f���g���L���Ƃ����苷���Ƃ����肷�邱�Ƃ��K�v�ł���B���̉f���_���������Ƃ��悭�\���\���`�����f��ł���B�i51�Łj
�Z�u�f��̕��@�v�i�_�j�G���E�A���z���A����e�q�j�Ƃ������Ƃ�����悤�ɁA����̕��@�ɂ��ʂ���f���\���@������B����́A�u�́v�͕��̘g�������A�u���v�͘g�̒��̗v�f���������̂ƌ��Ȃ��l�����ɖ��ڂɂ�������Ă���B�i51�Łj
�@
�S-2�D���{�ꕶ�@�̌���
�Z�f��̉�ʍ\���͎��̎葱���Ƃ��Ă���B����Ɠ����悤�Ȍ����œ��{�ꕶ�@�͑g�ݗ��Ă��Ă���B�i52�Łj
�E����̎n�܂��V�[�����ς�����Ƃ��ɁA����ƂȂ�ꏊ�����i�ő����i�����O�E�V���b�g�j�A���̒��ɓo��l���Ȃǂ�z�u����B�y���[���P�z
�E�����V�[���̎�v�l�����v������߂���ƁA����͋ߌi�������i�N���[�Y�A�b�v�E�V���b�g�j�B�y���[���Q�z
�E��v�l�����v�����ړ�����Ƃ��ɂ͑�ʂ��̂܂܁A�܂��́A�����ɏœ_�����킹�Ȃ���ǐՂ��Ă����i�g���b�L���O�E�V���b�g�j�B�y���[���R�z
�E�N���[�Y�A�b�v����Ă����l�╨���A�W����l�╨�����ꂽ�Ƃ��ɂ́A���i������A���҂͉f���̘g�̒��Ɏ��߂���B�y���[���S�z
�E�l���������ɒ��ڂ���ƁA����̓N���[�Y�A�b�v�E�V���b�g�ŋߌi�Ƃ��ĕ\�����B�y���[���T�z
�@
�S-3�D�ړ��J�����̎��_���u�́v�Ɓu���v���߂���Ӗ��I���_
�Z���ꔭ�B�ɂƂ��Ȃ��āA�f���̘g�Ɨv�f�̊W�͈Ӗ��I�Șg�Ɨv�f�̊W�ɔ��W���Ă����B�u�ۂ͕@�������v�ɂ����āA�u�ۂ́v�͕��̑傫�Șg�����A�u�@���v�͂��̒��őI�ꂽ�v�f�ł���B�i69-70�Łj
�Z��̂��������Ƃ����łȂ��A�ꏊ��s�ׂ̑Ώۂ��u�́v�ƌ������Ęg�ƂȂ邱�Ƃ��ł���B���{��ł́A�����o�����ł������ɂ���ăe�[�}�ƂȂ�g��ύX���Ă������Ƃ��\�ł���A�����ɕ��̌ꏇ�ύX�i�u�́v�����Ƃ��ɂ����Ă��ċ�������j���s���Ă���B
�S-4�D����q�^�\�����܂ށE�܂܂��Ƃ����ʂ̘_��
�Z���{��͘b����ƕ����肪�f�������L���邱�Ƃ���b�Ƃ��č���A���̉f���͂ǂ͈̔͂ɉ����܂܂�邩�Ƃ����_���ŔF������Ă����B�u�́v�Ɓu���v�͂��̂悤�ȁu�܂ށE�܂܂��v�Ƃ����_���Ő��E��F�����邽�߂̓���ƂȂ��Ă���B�i80�Łj
�Z���{�ꕶ�͂��傫�ȕ����i�u�́v�����g�j����菬���ȕ����i�u���v���I�ԗv�f�j���܂ޓ���q�^�̍\�������Ă���B���̂��Ƃ��ŏ��Ɏ������͎̂��}���L�����A���}�̓���q�́u������O�ցv�������ĊK�w������A�M�ҁi���F�J�j�̓���q�́u�O������ցv�i�g����v�f�ցj�������B�i81�Łj
�Z���{��͋�ԓI�ȕ�܊W�Ƃ����u�ʂ̘_���v�ɂ���č��ꂽ����ł���A�p��͗v�f�Ɨv�f���Ō������Ă����u�_�Ɛ��̘_���v�ɂ���č��ꂽ����ł���B�i83�Łj
�@
�S-5�D���{��̎����\�����Տꊴ�̂��錻��I�ȉf��
�Z���{��̕\�����u�ړ��J�����v�ɂ��f���̂悤���Əq�ׂ����Ƃ́A���{��̎����\���ɂ����Ă͂܂�B���Ƃ��u���̂��A�o������O�ɁA�Ⴊ�~���Ă����B�v�ŁA�o�������͉̂ߋ��Ȃ̂Ɂu�o������v�Ɩ����ɑ������铮���`���p�����Ă���B�b����́A�z���̒��ŏo�����悤�Ƃ��Ă�������̉f���̒��ɖ߂�A���̌���ł��łɐႪ�~���Ă������Ƃ��m�F���Ă���̂ł���B�i111-112�Łj
�Z���{��̘b����́A�Տꊴ�̂��錻��I�ȉf���̒��ɕ������A��Ă����B���̂悤�ɑz���s�ׂ����L����Ƃ���ɓ��{��̓���������̂ł���B�i113�Łj
�@
�T-1�D���{���̎��_�����Ƃ��Ȃ��̈�̉�
�Z���{��ł́A���Ƃ��Ȃ��������ŊO���ɂ���ΏۂɎ��_�āA�����\�����Ƃ���{�ł���B�ł́A�����Ώۂ����₠�Ȃ��ɂȂ����Ƃ��ǂ��\�����B���{�ꂪ�Ƃ����̂́A���Ȃ��̖ڂ�ʂ��Ď������A���̖ڂ�ʂ��Ă��Ȃ�������Ƃ������@�ł���B�܂�A���Ƃ��Ȃ��͋����҂ł���Ɠ����ɋ����Ώۂł�����B���{��ł́A���i�b����j�Ƃ��Ȃ��i������j�͈�̓I�ȊW�ɂ���B�i132�Łj
�@
�T-2�D���{�ꕶ�̎��_���l���̎��_
�Z���{��́A�b����ƕ����肪�ڂ̑O�̌i�F�����L����Ƃ����`����{�Ƃ���B���̂��߁A�������b����̂��ɂ���悤�ȋC�����ɂ�����̂��悢���͂ɂȂ�B�w�ፑ�x�`�����̂悤�ɁA���{�ꕶ�̎��_�͓o��l���̂Ƃ���ɂȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�p���̂悤�ɑS�̂]����悤�Ȃ��̂ł����Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł���B�i139�Łj
�@
�T-3�D���Ɏ��邱�Ƅ��ʃ��[���Ƃ��Ă̔o��E�Z��
�Z�ʃ��[�������{�l�ɂ���ĊJ������g���n�߂��Ƃ��������́A���{�l�炵����\���Ă���B����ȂƂ���ɗ����A����Ȃ��̂��������A�Ƃ����u���܁E�����v�̌i�F��e�����l�ɑ��邱�Ƃ��ł���̂́A���{�l�̃j�[�Y�ɓ��ɍ����Ă���B�ł́A�d�q���[����ʐ^���Ȃ��A��ʂ̃I�~���Q���^�������i�����B���Ă��Ȃ�����̓��{�l�́A�ǂ̂悤�ɂ��Ďv���o�������A�����̂��B�����łƂ�ꂽ�̂��u���Ƃɂ��i�F�̎����A��v�ł���B
����܂Ƃ��Ƃ͗c�̐��n��������ł���
�@
�@�F�J���̋c�_����A�a�̂Ɖf��̊W���l���邤���Ŗ𗧂����̃q���g����ɓ���邱�Ƃ��ł��܂��B�Ȃ��ł��A�u�f���g�v�Ɓu�����Ώہv�̃A�C�f�A�͎����ɕx��ł��āA�O�͂̍Ō�ɊT�ς����A�F�m����w�ɂ�����u�t���[���v�Ɓu�œ_�v���߂���c�_�ɂ������ɐڑ������A��C�ɁA���̃p�[�X�y�N�e�B���̈��p�i�����^�[�W���j�Ƃ��Ắu�f�恁�a�́v�̍l�@�ɂ����݂����Ƃ���ł����A���̋c�_�ɓ���O�Ɏ�肠����ׂ����Ƃ��ЂƂ���܂��B����́A�p��̎��_�Ɠ��{��̎��_�̈Ⴂ���߂���A����i�l�I�ȁj�^��ɂ��Ăł��B
�@���̋^��Ƃ����̂́A�����Ղ���u�_�v�̎��_�ł���A�O���W�̑S�̂𑨂���u�O���v����̎��_�ł���A�p��������̓��[���b�p�̌���̓������ۗ�����������Ƃ��Ă͐����͂������Ă�����̂́A���Ă������A�����͉p���[���b�p�̌���ɂ̂ݔF�߂��鎋�_�Ȃ̂��낤���A���{��ɂ����Ă��܂��A�a�̂ɂ�����u�Ȃ��߁v��u�݂킽���v�A�u�̂̒��ňӎ������Ƃ�������v�m��1�n�Ɍ�����悤�ɁA���邢�́u�e����Δg�̒�Ȃ�Ђ������̋��킽���ꂼ��т����v���X����⛌���╂�V���A���Ȃ킿�u�ǐS�v�̂����ɕ\������Ă���悤�ɁA��i��O���W�̑S�̂���]�������͖T�ς��鎋�_�͔F�߂���̂ł͂Ȃ����i�u�_�v��u�O���v�Ƃ������T�O�͔���Ȃ��ɂ��Ă��j�Ƃ����A�����ɂ��ƂÂ��f�p�Ȃ��̂ł��B
�@�F�J���ɂ��ƁA�ߌi���Ɖ��i���ɂ��f�����@�i�y���[���P�z����y���[���T�z�܂ł̉f���\���@�j�ƁA�u�́v�Ɓu���v���Ӗ��̗̈�ł������Â������q�^�_���ɂ����{�ꕶ�@�Ƃ́A�u�g�̐ݒ�E�ړ��v�Ɓu�v�f�̑I���v�Ƃ��������ӂ��̌����ɂ���đg�ݗ��Ă��Ă���̂ł����A�������Ƃ���Ȃ�����̂��ƁA�S�̂���]���鎋�_�i�����O�V���b�g�������炷�J�����ʒu�A���邢�̓n�C�A���O���������͒��ՃA���O���j�́A���{��̂Ȃ��ɑg�ݍ��܂�Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ������ɂȂ�ł��傤�B
�@�t���܂��^�Ȃ�ŁA�n�\�ɂ͂���A������l���⎞�Ԃ̐��ځi����ɂ͉���⋿���⍁�������̋O�Ձj�ƂƂ��Ɉړ�����u���̎��_�v���邢�́u�ړ��J�����̎��_�v�́A�p��ɂ͌����Ȃ����{��ɌŗL�̂��̂Ȃ̂��A�ƌ����A�������͂�Ⴄ�ł��傤�B
�@�F�J���͌����I�ɘ_���Ă���̂ł����āA�ʂ̌���\���̎���������Ĕ�����鎟���̋c�_�ł͂Ȃ��B���̂��Ƃ����m���������ŁA�����Ĉȏ�̑f�p�ȋ^��ɐG�ꂽ�̂́A���̂�����̎���ɂ��ē��S�̂���������������A�u�́v�Ɓu���v�̓����ɂ����{�ꕶ�@�̉f��I���i��ړ��J�����̎��_�A���Ɏ��鎋�_�Ƃ������A�F�J������N���閣�͓I�ȃA�C�f�A���A�S�u���Ȃ��u�a�́��f��v�_�ɓ������邱�Ƃ��ł���Ǝv������ł��B
�@����͂����炭�A���̂悤�Ȏ���ɂ��̂ł͂Ȃ����A�Ǝ��͍l���Ă��܂��B���J���m���w�p��ɂ����͂Ȃ������x�⚠������Y���w�����Ԃ̐��E�x�Ȃǂ��Q�l�ɁA��̑z���������āA�i�����āA���߂łƂ肠���鏑���̌�b��A�C�f�A���ÂɈ��p���Ȃ���j�����Ă݂܂��B
�@
�@�c�c����̒a���Ɛi���̏����̃X�e�[�W�A�܂��p�����{�ꂪ������͂邩�O�̒i�K�ɂ����āA�u�b����^������^���L�f���v�̎O���W�ɂ��ƂÂ����ꌻ�ۂ����ՓI�ɐ��藧���Ă����B����́A���Ƃ��ΕߐH�҂Ɣ�H�ҁA�M���ҁi��j�Ǝ���ҁi�q�j�̂������̐����I�R�~���j�P�[�V�����A�u����E������E���Ɏ���v�Ƃ������o�I�W�̒����͐ς̉ʂĂɊl�����ꂽ���̂������B
�@�����ł́u�l�́v�͂܂��������ŁA���Ƃ��Ȃ��͕�Ǝq�̂悤�ɗZ�����Ă����B���邢�́A���Ƃ��Ȃ��݂̂Ȃ炸�ނ�ޏ��A�A���⓮���A�͂Ă͂��̂��₩�����̂Ȃ����̂Ƃ����݂Ɍ����\�A�߈ˉ\�������B�܂��A�����̔��W�`�Ƃ��ďo����������̔�l�̂̌��n�I�ȓ����́A�o������P�ɏo�����Ƃ��Ė��w�������Ԃ̒i�K�ɂ���A���́u�����v�͂��܂������܂��������B
�@���́i�u�_�b�I�v�ƌ`�e���Ă悢�j�i�K�ł̕��̑g�ݗ��āi�m�o�E�F�����e�̕\���j�ɂ�������ԁE���Ԃ̂ӂ��̎��̂����A��Ԏ��ł́A���i�����Đg�̓I�ߌi����ޕ����Ȃ킿���i�����n����i���X�،���w���{�I�����x�u�킽��̉��ߖ@�v�j�A�����ɂ̓q�A�ƃ[�A�̓_��������z�I�ȍ��݁i�u�_�v�̗̈�j�͋�悳��Ă��炸�A���Ԏ��ł́A����⋿�������u���A�����A���������A�����A�����Ė��v�̂��Ƃ����́i�Ǐ��\�i�w�f��ЂƋY��x�j�A�u�t�̂̑��v�ɑ�������́i���@�����[�j���������ݐZ���I�ɗZ���E�A�����Ă����B
�@�₪�āA���̂悤�ȁi�u�c�N���v�ƌ`�e���Ă悢�j�i���̃X�e�[�W���炳�܂��܂Ȍ��ꂪ���Ă����B���{��A������a�́i��܂Ƃ����j�ɗp����ꂽ��܂Ƃ��Ƃ́A������Ԃ́u���ՓI�v�Ȍ��ꌻ�ۂ��A�����l���Ȍ�ɂ����Ă��u�c�́v�̂܂ܕێ����Â��m��2�n�A����A���[���b�p����͓���ȓW�J�𐋂��A�Ȃ��ł��p��́u��O�I�v�Ȍ���Ƃ��Ĕ��W���Ă������B�c�c
�@
�m��1�n�R�c�N�����́u���{�A���̂�����̄����єV�̏ے��I�I���G���e�C�V�����v�i����i�E��X�h���ҁw���̃|���e�B�N�X�x�����j�̂Ȃ��ŁA�єV�́u�݂�R�����������������t���l�ɂ����ʉԂ₳����ށv�i�Í��W94�j����肠���A�R���ꎩ�̂���_�̂ł���A�����ł����B����Ă���O�֎R�ɂ���ɉ����������Ă���̂ɁA����ł��Ȃ������ɉԂ��炢�Ă���ƕ\������єV�̂́u�l�H���v���߂����āA���̂悤�ɘ_���Ă���B
�@�R�c���͂����Ŏ��~�́u�U��U�炸�l�����Â˂ʌ×��̘I�����Ԃɏt���������v�������āA�u�N���K�˂Ȃ��×��̂��̂悤�ȗL�l���ǂ����Ď��~�͑̌�����ɂ܂Ŏ������̂��H�v�Ɩ₤�B
�@�����ŏq�ׂ�ꂽ�u�g�̂Ȃ��ӎ��v�������炷�f���́A�u�ړ��J�����v�ɂ����̂ƍl���Ă悢�B�������A����͒n���u���v�̎��_�Ƃ������A�u�_�v�Ȃ�ʁu�J�~�i�ޔ��j�v�̎��_����������f�����v�킹��B
�@
�m��2�n���Ƃ��A�܌��M�v���u���i���̔����v�ŁA�Î��L�i�����A�_���j����u�~���́@�ɐ��̊C�̑�m�I�q�V�n�Ɂ@���Љ�m���g�z�n��Ӎח��m�V�^�_�~�n�́@�����m�n�n�Љ�m���g�z�n��A�����Ă���܂ށv�������A�������̌���ɂ�����u���v�̎��_�A���邢�́u�ړ��J�����v�̎��_�̍��Ղ��c���Ñ���{���w�́u�c�́v���Ɍ��y���Ă���B
�@�����p�Y���́A�w�������̍\�������x�Łu�����O���ɐ��������������ł͐�s�����߂Ɍ㑱�����߂��t�������ꂸ�̊W�ł����ƌp��������A�I������Ƃ��낪���b�̖����ɂȂ�s�A�ڍ\���t�ł��������Ɓv���w�E�����i�ƁA�w�݂��Ђƕ����̝R��x�i����A360�Łj�ɏ����Ă���j���A���́u�A�ڍ\���v���܂��A�i�����āA���������a���Ƃ�킯�a�̂Ɋւ��Ē���u�����\���ɂ�鑽�d�\���v���j�A����������p�Ȍ�ɂ�����A���́u�c�́v���̂�����ł���B
�@���܂ЂƂA�u�T�v��������B���쌤��Y���w�F�m����ތ^�_���������u��̉��v�Ɓu�q�̉��v�̔F�m���J�j�Y���x����B
���@���E�f�悻���ĚF
�@
�@�����ŁA�⏕������{�����܂��B
�@�O�Y��m�����u����ɂ���Ċl�����ꂽ���ȂƂ͂��Ȃ킿���Ղ����ł���A����Ώۂɑ����ɐg���ڂ��\�͂ł���v�i130�Łj�Ƃ����\�}�̂��ƂŎ��M�����w�ǓƂ̔��� �܂��͌���̐����w�x�B�{�e�������͂��߂����傤�ǂ��̂Ƃ��A�^�C�~���O�悭���̏��������s����܂����B�u�^�C�~���O�悭�v�Ƃ����̂́A���̑O�N�ɉ��ł��o�ł��ꂽ�A�܌��M�v�́w���{���w�̔��� �����x�i�p��\�t�B�A���Ɂj�̉���ŁA�O�Y�����A���āu�Q���v�ɘA�ڂ����]�_�u�ǓƂ̔����v�Ɍ��y���i�u���̂��̘A�ڂ́A�������̂ɉ������āA�P�s�{�ɂ��Ă��Ȃ��B�v�i371-372�Łj�j�A���ꌻ�ۂ��_���⍰�A���E��يE��ފ݂̊T�O���Ăъ�ق��Ȃ��������ƁA�����Ă��ꂪ�����Ɉُ�ł����Ă��A�������ۂ̕K�R�Ƃ��Đ��������̂͋^�����Ȃ����ƁA���߂��鎩��̌������u��Z�Ɂv����Ă�������ł��B
�@���킭�A�J���u���A�I�ɂ����鎋�o�̔����i���Ղ����̊l���j�ɂ���āA����ւ̓����J���u���̃X�C�b�`�v������A�����ŁA�����ɂ����ĖڂƖڂ��������쒷�ށA����ɑΖʐ������s���l�ԂɎ����āA�u����̐g�ɂȂ邱�ƁA�����Ă��̑���Ǝ��݂ɓ���ւ�邽�߂ɁA�������Ƃ��Ɉ�]������Ղ���ڂ������Ɓv�Ƃ����A���ꌻ�ۂɕs���ȓ�̏������ƂƂ̂����i383-386�Łj�B
�@�O�Y���̏��q�͂����Z�����̂ł����A�ȏ�̂悤�Ɉ��k���A�f�ГI�ɔ����������������ł͋��ݐs���Ȃ��L�`�ȍL����Ɛ[����X���Ă��܂����B���́A����̋N���Ƃ������͎n���A����u�����v�̌���i�u�_�b�̎���v�j���߂���O�Y���̋c�_�́A�u�_�̎��_�v�Ɓu���̎��_�v������ȑO�́A�������̌��ꌻ�ۂ̗l�Ԃ�`�ʂ��Ă��āA���́u�f�p�ȋ^��v�ւ̉��������炵�Ă����͂��B���͂����m�M���A���̏o�ł�S�҂��ɂ��Ă����̂ł����m���n�B
�@���āA���́w�ǓƂ̔��� �܂��͌���̐����w�x����肵�A�ǂݎn�߂�Ƃ��������A���܈��k�E���p�������q�ɕt��������ׂ��L�q���ЂƂڂɗ��܂����̂ŁA�ȉ��ɔ����������Ă����܂��B
�@�O�Y���͂Â��āA�u�@���I����v�Ƃ͉����A�Ɩ₢�܂��B
�@�����ɐl���C�⎇�����A�r���E��Ƃ̖����o�Ă���̂́A�O�Y���̋c�_�̕������A�u�Ⴋ�v�剪�M�̕]�_�u�l���C�ƉƎ��v�ƁA��N�̒����w�������ƌǐS�x�`���̈�сu�̂ƕ���Ɣ�]�v�̎������_�Ƃ́u�����قǂ̑Ή��v���߂�����̂ł��������䂦�̂��ƁB
�@�܂��A�u�v����Ɍ���͂ł���v�Ƃ���̂́A�V�䖀�d�~�ς܂��͑T�Ɋւ���L�q�ŁA������܂��u�̂ƕ���Ɣ�]�v�ɁA�������������҂Ƃ��ė����Ƃ��ł����Ƃ������Ɂu��]�v�Ƃ������̂��[���Ӗ��Ő����������Ƅ����u����́A�u�������v�̐��E�A���y�̐��E�z����u���̐��̂ق��v�̐��E�ւ̊�����Ȃ��邱�Ƃł���A���̂ꎩ�g�̂Ȃ��ɁA�����Ɛ��O�Ƃ̂����Ȃ荇���\���͌^�������A����������Ɍ����ɓK�p���邱�Ƃɂ���āA���ۂ�K�R�I�ɔ�]�̊�Ō��邱�Ƃɂق��Ȃ�Ȃ������B�v�i��g���Ɂw�������ƌǐS�x52�Łj�����ƁA�u�����r���̂悤�ȕ��������̉̐l�E��]�Ƃ̔�]�̗D�G�����A�ނ̕����v�z�̑̌��I�Ȑ[���Ɛ��Ă���Ȃ��W�ɂ���Ǝv���邱�Ɓv�i���j�Ƃ��ʂ������Ă���A�Ə�����Ă���̂܂��Ă��܂��B
�@�v����ɁA�O�Y���́A�u���w�I�����v�Ɓu�@���I����v���A�i�剪�M�̘_�l�̃^�C�g���Ō����A�u�́v�Ɓu����v�Ɓu��]�v���j�A�����ЂƂ̏ꏊ����A�܂茾��a������́A�u���ꌻ�ۂƂ����d�g�݂̊j�S�v���Q�����u�_�b�̎���v���痈�����̂��A�����āu���ꌻ�ۂƂ����d�g�݂̊j�S�v�Ƃ́u����́v�A���Ȃ킿�u���Ղ��Ȃ��炻�̌��Ă���Ώۂɐg���ڂ��\�́v�ɂق��Ȃ�Ȃ��̂��A�Əq�ׂĂ���̂ł��B
�@
�m���n�w�ǓƂ̔��� �܂��͌���̐����w�x�́A�u�Q���v��Z��Z�N�����������Z�ꎵ�N�������܂Łu����̐����w�v�̕\��ŘA�ڂ��ꂽ���e�����Ƃɂ��Ă���B�w���{���w�̔��� �����x�̉���Łu�������̂ɉ������āA�P�s�{�ɂ��Ă��Ȃ��v�ƌ��y���ꂽ�̂͂���Ƃ͕ʂɁA��Z��Z�N�ꌎ�������Z���N�Z�����܂Łu�ǓƂ̔����v�Ƃ��āu�Q���v�ɘA�ڂ��ꂽ�B
�@�w�ǓƂ̔��� �܂��͌���̐����w�x�́u���Ƃ����v�ɂ��ƁA�u�H��̖��v���邢�́u������ю���̐��E���Ȃ����㕶�w�̏d�v�Ȏ��ɂȂ��Ă���̂��v�Ƃ����������������̖����s�̒��ҕ]�_�́A���̎��ɓ���O�ɘ_���Ă����ׂ����ƁA���Ȃ킿�u������ю���̐��E������̏��Y�ł��邱�ƁA�����炱���l�Ԃ̕\���s�ׂ͂قƂ�ǂ˂Ɏ�����ю���̐��E�ɂ�����炴������Ȃ����̎d�g�v��_�����w�ǓƂ̔��� �܂��͌���̐����w�x�̑�A����u�ǓƂ̔��� �܂��͔ފ݂̘_���v�Ƃł������ׂ����̂ł���B
�@
���@���E�f�悻���ĚF�i���O�j
�@
�@�f����܂��A���̓����ꏊ���琶�܂�܂����B
�@����V�ꎁ�́w��ƕ҂��āx�́u�v�����[�O�v�ɁA���Ί펞��̏@���ɂ́u�܂�����Ȃ��f��I�\���v�����݂��Ă��邱�ƁA�f��͎������́u�S�v�̖쐶���J���\�͂������Ă��邱�ƁA�����āA�����������ɂ����͂₭���ڂ����̂��Z���Q�C�E�G�C�[���V���^�C���ŁA�f��̃����^�[�W���Z�p�̖{�����A���Ί�̐l�ނ̎�ƕ҂��Ă̓`���ɂ܂ł����̂ڂ点�����ƁA���X��_���Ă��܂��B���ɂ��ƁA�@�����͂��߂ĉf��̍\���ŗ��������̂́A�t�H�C�G���o�b�n�́w�L���X�g���̖{���x�ł����B
�@���́u�@�����f��v�_�́A���̘_�l�Q�̏����̒i�K�i��S�́j�Ŏ�肠���܂����B����A���p�����c�_����́A�剪�M���єV�̂ɂ��ďq�ׂ��u������̂�����̂ɁA����������Ɍ���̂ł͂Ȃ��A����ΐ���Ƃ����u���v��}��Ƃ��Ă��������Ƃ����t�|�I�Ȏ���\���v�i�������S�͂ň��p�j�̎����ւƂȂ��铱�ǂ�������A�܂��A�f��I�\�����������Â��郁�J�j�J���ȗB���_�I���ʂƐS�I���ۂ̑��ʁA���邢�̓��J�j�J���Ȍ����ƐS�I�Ȍ��i�i�f���j�̓_�Ƃ����A�u�a�́��f��v�I�Ȃ��̂̎������߂���l�@�ւ̎����������Ă��܂����B
�@�f��Ə@���Ɋւ���c�_�ł́A�t�H�C���o�b�n��G�C�[���V���^�C���̂ق��ɂ��A���Ƃ��A�g���m�̐��[�z�ɉf��I���J�j�Y���̖{���������A���h���E�o�U����A�w�V�l�}�x�Łu�f��̃J�g���b�N���v��_�����W���E�h�D���[�Y�����u���̖{�̂Ȃ��Ńh�D���[�Y�́A�f�悪�����َ̈�̘_���i�S�I�v���Z�X�j�������������āA���I�ȑg�D�̂������Ă���l�q���A�݂��Ƃɕ`���o���Ă݂����B�v�i�w��ƕ҂��āx�W�Łj�����ȂǁA�[�����Ƃ̂ł��Ȃ����̂����邵�A�܂��A�u�f��Ƃ͂��������@���I�Ȃ��̂ł���B�v�u�f��̔��W�̓C�G�X�E�L���X�g�ƂƂ��ɂ������B�v���X�̌��t�����w�f��ƃL���X�g�x�i���c���i�j�̋c�_���C�ɂȂ�Ƃ���ł��m��1�n�B
�@���A���̘b��͂����Ő肠���A�c������ЂƂ̘_�_�A�u�@���I������w�I�i�|�p�I�j�����v���邢�́u�@�����f�恁�F�v�Ƃ����A����a���Ɠ����ɐ������������m��2�n�̍����ɂ�����́A���Ȃ킿�u����́v�������́u�ς̖ځv�̖��ɂ��āA�͂����ߎ�肭�݂����Ǝv���܂��B
�@
�m��1�n���܂ЂƂA�F��M�꒘�w�f���g�̘_�x�����X�g�ɉ����A��������A�f����u�q���ԁr������|�p�v�i248�Łj�ƂƂ炦���A���h���E�o�U���Ɋւ���L�q����������B
�m��2�n�u�@�����f��v�̓����ɑ��āu�f�恁�F�v�̓����̐����͔����ł���B
�@�����ł́A��ɒ��́i�������A����j�A�Z�́i����A���j�ւƔ��W���Ă��������̌���\�����u�F�v�ƂƂ炦�Ă����B�i���邢�́A�a�́i����ړ��j�A�o��i�Î��ٍl�j�Ƃ���������\���̌`�����Y�݂�����قƂ��Ắu�F�v�B�j
�@
�i�S�P���ɑ����j
���v���t�B�[����
�����I���i�Ȃ��͂�E�̂肨�j1950�N�㐶�܂�B���Ɍ��ݏZ�B��N���̂ɏ����ꂽ�a�̂̈Ӗ��������ł���̂͂��������Ƃ��B�ł��A�{���Ɂu�����v�ł��Ă���̂��B�����Ɂu�Ӗ��v�Ȃǂ���̂��B�����������t���g���ĉ�����`�B���邱�Ƃ��̂��̂��s�v�c�Ȍ��ۂ��Ǝv���B
Web�]�_���u�R�[���v40���i2020.04.15 �j
���F�ƃN�I���A�A�^�y���\�i�ƚF����55�́@�f��^�����^�[�W���^�L���i���̂P�j
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU�@2020 Rights Reserved.
|
| �\���i�ڎ��j�� |
