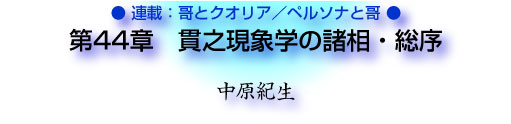|
|
|
Web�]�_���u�R�[���v |
|
���n���̎� ���{���̕\���i�ڎ��j�� ���{���̃o�b�N�i���o�[ ���ǎ҂̕Ł^���ӌ��E���z �����e�K�� ���W�҂�Web�T�C�g ���v���C�o�V�[�|���V�[ |
|
���{���̊֘A�y�[�W�� |
|
���u�J���`���[�E�������[�v�̃o�b�N�i���o�[ ���]�_���u�k�� Vue�v�̑��ڎ� |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
|
���єV���ۊw�̗R��
�@
�@������A�єV�̘_�i�єV���ۊw�j���߂����i�̋c�_�ɓ���܂��B
�@���������u�єV���ۊw�v�Ƃ����ď́A�����Ă����ʂ��Ď����\�z���A���̎��������߂����Ɩژ_��ł����єV�̉̂Ɖ̘_�̐��E�́A�i��ϒ��w���c�����Y�����q��Ζ��r�Ƃ͉����x�ɂ�����u���c���ۊw�v�Ƃ�����ɗR�����A�����Ă����ł̉i�䎁�̋c�_�ɂقڑS�ʓI�ɏ������Ă��܂����B�����ł��̌��_���m�F���A���A���S�ɗ����߁A�i�䎁�̋c�_�̍��g�݂����炽�߂ĊT�ς��Ă��������Ǝv���܂��B
�@
�@���A�єV���ۊw�i�N�I���A�сj�B
�@���c�����Y�������ɂ́u�����o���v�ƌĂсA���̌�́u�ꏊ�v�ƌĂ��́i57�Łj�B���̂悤�ȁA���ׂĂ���������n�܂�u���̏ꏊ�v�Ɍ��������c�̓N�w�I�T�����A�i��ς́u���c���ۊw�v�ƌĂԁi84�Łj�B
�@���c���ۊw�ɂ����āu������̂�m�邱�Ƃ́A���̂�����̂ɂȂ邱�Ɓv�i21�Łj�ł���A�P������܂��u��q�̍���Ƃ��Ă̂��̓����p�ƕʂ̂��̂ł͂Ȃ��v�i23�Łj�B
�u��M�����R��`�������̂ł��悵�A���R����M��ʂ��Ď��Ȃ�`�������̂ł��悢�B�������Ɖ�Ƌ�ʂ̂���̂ł͂Ȃ��B�q�ϐ��E�͎��Ȃ̔��e�Ƃ�������悤�Ɏ��Ȃ͋q�ϐ��E�̔��e�ł���B�䂪���鐢�E�𗣂�ĉ�͂Ȃ��B�v�i�w�P�̌����x�j
�@�����o�������ڌo���́A���Ƃ��u���t�ɉ]�����킷���Ƃ̂łȂ��Ԃ̌o���v�̂悤�ɁA�u�����ɑ̌�����A�ӎ�����鐶�X���������i������A�u�N�I���A�v�Ƃ����j���Ƃ��Ȃ��v�i40�Łj�B
�@�i�䎁�́A���̂悤�ȁu���m�Ȃ܁n�̎����v�i41�Łj�𐼉������N�w�ɂ����u�����i�������݁j�A�G�N�V�X�e���e�B�A�v�ɁA����ƑɂȂ�u�_���I���_�v�����u�{���i�{�����݁j�A�G�b�Z���e�B�A�v�ɂ��Ă͂߂Ă���B
�@�f�J���g�́u���v���A�䂦�ɁA��ꂠ��v�ɂ����ẮA�u�_���I���_�Ɛ��̎����A�܂�{���Ǝ����͘A�����Ă���v�i41�Łj�B�����āA�f�J���g�Ȍ�̐��m�N�w�j���u���̎����ł͂Ȃ�������������������ւƓW�J�����v�m��1�n�̂ɑ��āA���c�́u�������炱�̓W�J�����ۂ����v�i41-42�Łj�B
�@
�@���A���c�_���w�B
�@�u����䂦���c�́A�f�J���g�����ʂ��Ȃ��������ɒ��ʂ��Ă����v�i41�Łj�B����́A�u���t�ɉ]�����킷���Ƃ̂łȂ��v�����o���ɂ��Ĉ�ʓI�Ɍ�錾��i�u���I����v�ƌ����Ă����Ă������낤�j���A���c���ۊw�͂ǂ�����ǂ�����Ď�ɓ����̂��A�Ƃ����₢�ł���i47�Łj�B
�@���̓����͂�����B�u�����o�����ꎩ�̂�������\�Ȃ炵�߂�����\������ɏh���Ă�������v�i47�Łj�ł���B�������āA�u���̌�̐��c�N�w�̓W�J�́A���̌���N�w�Ƃ��ēǂނ��Ƃ��ł���v�i47�Łj�B
�@
�i��l�̓I�ȓ��{��\���̂悤�Ɂu�ÂɓƉ�_�I�v�ȑO�����c�N�w����o�����āA�u�o���̎�̂͏�ɐ��E�̓����ɑ��݂���l�ł���Ƃ����������A����\���̊�b�ɂ��炩���ߐD�荞��ł���v�p��I�\���̐����̓���𖾂��邱�Ɓi17�Łj�B���ꂪ�u���̌�̐��c�N�w�v�̉ۑ�ł������B
�@�������A���̓���𖾂��邽�߂ɂ́A�q�ϓI���E���̂̐����̓���𖾂��Ȃ���Ȃ炸�A���͂���͐��c�_���w�̎���͈͂��Ă����B�j
�@
�@���c�_���w�́u�ł���v�i�{���j�Ɓu������v�i�����j����ʂ��Ȃ��i58�Łj�B�u���z�I���ʁv���u�����Ȃ��ʊT�O�ɂ��K������������A�^�̌��v�i61�Łj�Ɓu���z�I�q��ʁv���u��̓I��ʎҁv�i63�Łj�͈�v����B
�@����͂����u����i��j�́A���̂Ƃ���A�����Ȃ��Ă���v�ƌ����邾���ŁA���������u�ǂ�i��j�v���u�ǂ̂Ƃ���v�Ɂu�ǂ��Ȃ��Ă���v�̂��͌����Ȃ��i63�Łj�B����ł��ꉞ�����͌�����̂́A���z�I���ʂ����z�I�q��ʂɂ���ĕ�ۂ���A�����Ɍ����I�Ȕ��f���������Ă��邩��ł���B
�@����A�����������f�͂�������n�܂�B����́u�ꏊ�̎��ȉ^���v�ł���i64�Łj�B
�@���c�_���w�i�ꏊ�̘_���w�j�ɂ����ẮA���́u���̏ꏊ�v�̎��Ȍ���ɂ���Đ�������i85�Łj�B�����āA�u�ꏊ���ꎩ�̂���������t�����c�N�w�Ȃ̂��v�i67�Łj�B
�@
�@��O�A�Ăѐ��c���ۊw�i�y���\�i�сj�B
�@�Ƃ���ŁA���ł���ꏊ���ǂ����Ď��玩�Ȍ���Ȃǂ����邱�Ƃ��ł���̂��B
�@�i�䎁�̌����Ăł́A���̓c�ӌ��̔ᔻ�ɑ��āA���c�́u���Ɠ��v�Ƃ����_���ŁA�u���Ȃ��Ƃ��l�i���邢�́u�l���v�Ƃ��u�l�i�v�Ƃ����p��ł��� person�j�̐����Ɋւ������v�A���ʂ��瓚�����i85-86�Łj�B
�u���̒�ɓ�������A���̒�Ɏ�������B���͎��̒��ʂ��ē��ցA���͓��̒��ʂ��Ď���������̂ł���B��ɑ��Ȃ邪�̂ɓ��I�Ɍ�������̂ł���B�v�i�u���Ɠ��v�j
�@�܂��A���c���u���Ɠ��Ƃ͒��m�������n�Ɍ������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v�A�����u����Ƃ������Ƃ������@��������\����ʂ��āv�A���邢�́u���Ƃ��`�Ƃ��������̌��ۂ���i�Ƃ��āv���������邱�Ƃ��ł���ƌ��������ƂɊւ��āA�i�䎁�͎��̂悤�ɏ����Ă���B
�@�ǂ����āu���Ƃ��`�v��ʂ��Ē��ڂɌ������Ă��Ȃ����Ƒ��l�����������邱�Ƃ��ł���̂��B���c�͂��̖₢�ɓ����邱�Ƃɐ������Ă͂��Ȃ��i�������A�u�������݂��Ă��邱�Ƃ������A������������Ƃ������̂��\�Ȃ炵�߂Ă���v���ƁA���̈Ӗ��Łu�����\�Ȃ猾�ꂪ�\�����A���ꂪ�\�Ȃ�����\�ł���v���Ƃ𖾂炩�ɂ����i93-94�Łj�Ƃ͂�����j���A���ꂪ�Ȃ��N�w�I�Ȗ₢�ł���̂��A���̂��Ƃ̈Ӗ���N�����[�߂邱�Ƃɐ������Ă���i87�ŁA94�Łj�ƁB
�@
�@���̂�����̉i�䎁�̋c�_�́A���߂ǂ��s���ʐ[�����킢��X���Ă���B�i�u����̎��̈ӎ��������̎��̈ӎ��v�W�Ɓu�����̈ӎ������҂̈ӎ��v�W�Ƃ̗ޔ��A�u�T�O���ɐ旧�������̂��́v���u�[�I�ɔ�T�O�I�Ȃ��́v�Ƃ��Ă̐_�i���̒�ɑ��݂����Ζ��Ƃ��Ă̐_�j�Ɓu�T�O���i�{�����j���ꂽ�����T�O�i�u�����v�Ƃ����{���j�v���u��T�O�I�Ȃ��̂Ƃ����T�O�v�Ƃ��Ă̑��ҁi�����\�Ȃ炵�߂������̖��j�Ƃ̈Ⴂ�A���X�B�j
�@�����ł́A���c�N�w�ɂ����錻�ۊw�̗D�ʐ��ɂ��ďq�ׂ�ꂽ�ӏ�����������ɂƂǂ߂�B
�@���킭�A���҂̐����ƌ���̐����͓����ɂ����w��ł��Ȃ��i95�Łj�B�����Č���͋q�ϓI���E��_���̊�Ղł���B�������Ƃ���ƁA���ꐬ���ȑO�́u���c���ۊw�v�ƌ��ꐬ����́u���c�_���w�v�Ƃ͑����I�ł͂Ȃ��i84�Łj�B
�@���́u�F�ƃN�I���A�^�y���\�i�ƚF�v�Ƃ����_�l�Q�̋N�_�ƂȂ����������قڏ\�N�Ԃ�ɒʓǂ��āA�Ր��ɐG���N�w����ǂނ��тɓ������邠�̊��G�A����u���x�ł����߂Ė��키�v�u�N�o�v�I�����ɂ����P���܂����B
�@����Ɠ����ɁA���͂��܂����̏����ɑ����ꂽ�����̂��̂����ݐs�����Ă͂��Ȃ��A�Ƃ����K�����ɐZ���Ă����܂����B���Ƃ��u���̎����i�N�I���A�j�������v�Ɓu�_���I���_�i�T�O�j���{���v�Ƃ����X�R���N�w�ɕ�������ΊT�O�̓�����A���̂��ƂƂ��傫���֘A����u�������A�A�N�`���A���e�B�v�Ɓu���ݐ��A���A���e�B�v�̊T�O�̈Ⴂ���߂���c�_�i��_�̑��ݏؖ����߂����̋c�_�j���A�u�T�O�ɂ���ċ��ݐs����Ȃ��u�����v�̖{���v�]�X�Ƃ������\���̂����Ɏ�������Ă������ƁB�����́A���ꂩ����g�ށu���c���єV���ۊw�v�́i�ŏI�I�ȁH�j�����ɂƂ��āA���ꂱ�����߂ǂ��s���ʍz���ƂȂ���̂��Ǝv���܂��B
�@
�m��1�`3�n�f�J���g�Ȍ�̐��m�N�w�j���u���̎����v�ł͂Ȃ�������������������֓W�J�����Ƃ����Ƃ��A�u���̕����̒��_�Ɉʒu����̂��E�B�g�Q���V���^�C���ł���v�i44�Łj�B
�@�܂��A�u���߉�����Ă��Ȃ������v�]�X�́A�u���������ɋN���銴�o���w���A�����ɂƂ��Ă����Ӗ�������i�d�j�v������Ƃ��ċ@�\�����邩�ǂ������l�@�����w�N�w�T���x�̋c�_�܂������́B�u�����ŁA�l�͓N�w������ۂɁA���ɂ͕��߉�����Ă��Ȃ����������������Ȃ�n�_�ɒB���邱�ƂɂȂ�B�����������A���̂悤�ȉ�������̕\���ł���̂́A���̌���Q�[���̒��ɂ����ĂȂ̂ł���B���̌���Q�[�����������܋L�q����˂Ȃ�Ȃ��B�v�i�w�N�w�T���x�T�|��Z��j
�@�����āA�u���c�I�m�M�Ɓv�́u�E�B�g�Q���V���^�C���I�m�M�Ɓv�ƑɂȂ��ł���B
�@�Ȃ��A���̂����u��Ƙ_���w�v�́u�E�B�g�Q���V���^�C���_���w�v�ɗR�����A�u�r���n���w�v�́A�i�䎁���E�B�g�Q���V���^�C����c�����Y�ȊO�Ɂu������̂悤�Ȃ��́v�i�W�Łj��������������l�̓N�w�ҁA�j�[�`�F��O���ɂ����Ă���B
�@
���L����`�̊єV���ۊw�ƊєV�O��
�@
�@���āA�ď̂̏o���A�R���ɂ��ĕ��K�����˂čĊm�F�����Ƃ���ŁA���ɁA�єV���ۊw�����ہA�����Ēʂ邱�Ƃ̂ł��Ȃ��b����Ƃ肠���܂��B�Ƃ����Ă��A�����͂���������̏���ȗ����ɂ����Ȃ����̂Ȃ̂ł����B
�@
�@���A�єV���ۊw�̍L����`���ɂ��āB
�@�єV���ۊw�ɂ����āu������̂��r�ނ��Ƃ́A���̂�����̂ɂȂ邱�Ɓv�ł���A�����ɂ́u�єV�����R���r���̂ł��悵�A���R���єV��ʂ��Ď��Ȃ��r���̂ł��悢�B�v�Ƃ������Ԃ��o�����Ă���B���Ȃ킿�u�єV�����R���r�ށv���ƂƁu���R���єV��ʂ��Ď��Ȃ��r�ށv���ƂƂ���ʂł��Ȃ��A���邢�͎v���Ƃ��̎v�����������邱�ƁA�v�������t�ɂ��邱�ƂƂ��̌��t�������ɂ����ė��������鐢�E���̂��̂��o���i�J蓁j���邱�ƁA�����߂������ƂƐ��E���߂������ƁA���X���i�����������̒��̏o�����̂悤�Ɂj��ʂł��Ȃ��u�ÂɓƉ�_�I�v�ȊєV���ۊw�̐��E�B
�@���̂悤�ȁA�u�����o���v�̌��ꉻ���\�Ȃ炵�߂�u�ꏊ�v�̑n���ɂ������A�������́u���ɂ��ցv�̐��E���u���A�����v�ɗ���������u�V�������v�̒T���ɂ������єV���ۊw�ɂ́A�L����`�̈قȂ鑶�ݗl�Ԃ�����B�i���`�̒�Ƙ_���w���ۂ���L�`�̊єV���ۊw�ƁA����Ƃ͋t�ɁA�u��Ƃ��a�̂��r�ށv���ƂƁu���ꂪ��Ƃ�ʂ��Ď��Ȃ��r�ށv���ƂƂ���ʂł��Ȃ��L�`�̒�Ƙ_���w�ɕ�ۂ���鋷�`�̊єV���ۊw�B�j
�@�Í��W�������ɑ����ċK�肷��ƁA�u�l�̂�����i���ˁj�˂��Â̂��Ƃ̂́v�́A���邢�́u�������v���u���ˁv�i�}��E�}���������͔|�{��j�Ƃ���u���Á˂��Ƃ̂́v�́u��܂Ƃ����v�̔����i�����j�v���Z�X���L�`�̊єV���ۊw�ɁA�u���̒��ɂ���l�A���Ƃ킴���������̂Ȃ�A�S�ɂ����ӂ��Ƃ�������̂������̂ɂ��Ă��Ђ�������Ȃ�v�̘a�̉r�o�̃v���Z�X�����`�̊єV���ۊw�ɂ��ꂼ�ꑊ������B
�@���̂��Ƃ��䓛�L�q�̘a�̘_�Ɋ֘A�Â��Č���������ƁA�i��29�͂ŏq�ׂ��悤�Ɂj�A�L�`�̊єV���ۊw�́u�N�I���A�v�i������ȑO�������͕��ꖢ���ȑO�̐��E�Ɓu������v�Ƃ̊E�ʌ��ہj�Ɓu�y���\�i�v�i���u���Ƃ̂́v���Ȃ킿����ɂ���đ��`���ꂩ����z����i���ꂻ�̂��̂Y����j��́j�𗼋ɂƂ���u������i�ہE�����߂̐S�n�j�˂��Ƃ̂́i�ӎ��t�B�[���h�{����t�B�[���h�j�v�̃v���Z�X�ɁA�����ċ��`�̊єV���ۊw�͂���Ɋ܂܂��u�v�Ёˎ��v�̌n��Ɓu��˗]��v�̌n��̂����O�҂́u�v�Ёˎ��v�̃v���Z�X�ɂ��ꂼ��Y������B
�@�����Œ��ӂ��Ă��������̂́A�����������`�̊єV���ۊw�́A�u�l�̐����鐶�g�̐l�Ԃ����ʂ̎v���i�����j�����g���b�N����g���Č��ꉻ�������̂��a�̂ł���v�Ƃ������a�̊ςƂ͂܂������W���Ȃ��Ƃ������Ƃ��B����́A���������u�єV�ɂ͓��ʂ��Ȃ��v�i��T�͑��Q�Ɓj�Ƃ������R�ɂ�邾���ł͂Ȃ��B�����l���Ă��鋷�`�̊єV���ۊw�̊�ڂ́A�L�`�̊єV���ۊw���ΏۂƂ���u��܂Ƃ����v�̐��E�i�[�w�̓`�����ہj���u�l�̐����鐶�g�̐l�ԁv�ɂ��a�̂̐��E�i�\�w�̓`�����ہj�ւƂȂ��͂��炫�A��̓I�ɂ͉������́u���Ђ�������Ȃ�v�̂����ɕ\�����ꂽ�u�����K�[�W���̗́v�ɂ��邩��ł���B
�@
�i���܁u�W���Ȃ��v�Ə������̂͌����߂��ŁA�܂������W���Ȃ��킯�ł͂Ȃ��B���̈Ӗ��ł́A��29�͂Łu���ɂ���l���l�X�ȁu�v�Ёv�i�����j��m�o���ɑ����ĕ\������i���`�́j�єV���ۊw�̐��E�v�Ə��������Ƃ͊ԈႢ�ł������A�Ƃ������͐㑫�炸�ȕ\���ł������B�������́u���ɂ���l���l�X�ȁu�v�Ёv�i�����j��m�o���ɑ����ĕ\���y�������̂��a�̂ł���Ƃ����a�̊ς��������琶�܂����ƂɂȂ����z�i���`�́j�єV���ۊw�̐��E�v�Ə����ׂ��������m��1�n�B
�@�Ȃ��A���q�ׂ��u���Ђ������v�͂��炫��S�����̂̂��Ƃ����́u�t�B�M���[���v�̖��ŌĂсA��̓I�ɂ́u���v�i�u���o���鏼�ɂ͂���njÂ̐��̊����͂��͂炴�肯��v�̉̂ɉr�܂ꂽ�u���ɂ��ւ̐��v�j��u���������v�Ƃ�킯�u�����Ăɂ��́v�i�������u���o���鏼�v�j���A���Ȃ킿�u���Ƃ��`�Ƃ��������̌��ہv�̂��Ƃ�z�肵�Ă���B�j
�@
�@���A�єV�O�̂ɂ��āB
�@�L�`�̊єV���ۊw�̐��E�́A�O�w�\���łł��Ă���B�i����ɑ��āA���`�̊єV���ۊw�͊�{�I�ɓŕ\���ł���B���m�ɂ͓u�W�v�ŕ\���ł���B���̊�ڂ́A���Ƃ��u������˂��Ƃ̂́v�Ƃ����ȗ������ꂽ�͎����́u�ˁv�̂͂��炫�ɐs���Ă���B�j
�@�ȉ��A����܂Ř_���Ă����єV�I�O�w�\���̑�\�I�Ȃ��̂��O���[�v�������ĕ��ׂĂ݂�B
�@
���u�F�Ƃ����M�t�g�^�t�B�M���[���Ƃ��Ă̚F�^�F�̃p�����v�Z�X�g�v
�@
���u���Á^�l�̂�����^���Ƃ̂́v
�@�u���^�S�i�g�j�^���v
�@�u�n���~���^�C���p�g�X�^���S�X�v
�@�u�����^����^�~���v
�@
���u���̓`���́^�g�̓`���́^���̓`���́v
�@�u�����疳�ց^������L�ց^�L����L�ցv
�@�u�����o�E�N�I���A�̉F���^�Ђ��Ԃ�S�̋��܁^���Ƃ̋��܁v
�@
���u�����E�^�z���E�^�ے��E�v�i���J���O�́j�m��2�n
�@�u�~���^�[�w�̃p�g�X�^�\�w�̃��S�X�v
�@�@���u���ӎ��^���ӎ��{���ӎ��^�\�w�ӎ��v�i�ێR�i�\�O�Y�j�O�́j
�@
�@�єV�O�̂ɂ��āA�����ŐV���ɂ�������ׂ����Ƃ͓��i�v��������Ȃ��m��3�n�B�����ꌾ����������Ƃ���A�����͌��ǁA�i�O�X�͂Ŏ��݂��S��C�}�[�W���̎O���ނ������͎l���ނ��܂߂āj�A�䓛�r�F�́u�ӎ��̍\�����f���v�ɁA�܂�u�䓛�O�́v�Ɏ��ʂ��Ă����B
�@
���u�b�̈�^�a�̈�{�l�̈�^�`�̈�v
�@�@���u���ӎ��^����A�������i���^�����̏ꏊ�j�{���Ԓn�сi�z���I�C�}�[�W���̏ꏊ�j�^�\�w�ӎ��v
�@
�m��1�n�u�l�̐����鐶�g�̐l�ԁv�ɂ����ʕ\���i�����A�\���j�Ƃ����a�̊ς́A���`�̊єV���ۊw�ɂ̂ݗR������̂ł͂Ȃ��A���m�ɂ͏r���ƒ�Ƃ̘̉_�A�����肷����`�̒�Ƙ_���w�i���`�̗L�S�𒆊j�ɂ������̘_�j�Ƃ����܂��č����������̂ł���B��G�c�Ɍ����A�u������˂��Ƃ̂́v�̊єV���ۊw�Ɓi�r���I�]�����Ă���Ƒ��Λ�����j�u���Ƃ̂́˂�����v�̒�Ƙ_���w�Ƃ����A���Ɂu��l�i�I�Ȃ��́ːl�i�I�Ȃ��́v�Ƃ�����ʎ��Ŋ����̘_�̓�̋ɓ_���瓙�����̈ʒu�ɂ����āA����炪���o����ْ����ł����������Ăł������d�͂̏�ɔ�������i���������j�a�̊ςł���B
�@
�m��2�n�����Łu�p�[�X�O�́v�Ɍ��y���ׂ��Ƃ���Ȃ̂����A�u���J���O�́v�Ƃ̊W���l����Ƃ������܂��ē�����������B
�@�P���ɍl����A�u��ꎟ�������E���G���^��������}�W�l�[���^��O���������E�T���{���b�N�v�ƑΉ������邱�Ƃ��ł���B����́A��18�͂ň��p�����O�c�p�����̕��͂Ɂu�u��ꎟ���v�́A�u����v�̓����ɑ��Đ��ݓI�Ȃ��̂����A���́u����v�̑S�̂��A�u��O�����v�ɌŗL�̓����ɑ��ẮA�O�ꂵ�Đ��ݓI�Ȃ��́A���邢�͒��ق������̂ł��炴��Ȃ��v�i�w���t�ƍ݂���̂̐��x97-98�Łj�]�X�Ƃ��������ƂȂǂ�����Ó����Ǝv���邪�A���܂ЂƂ��������Ȃ��B
�@��28�͂ł́A�u�S�n�i��j�^���i���j�^�F���E�i���j�v�̏r���O�̂��u��ꎟ���i���A���ݐ��j�v�u����i�̓I�����j�v�u��O�����i�}��A���Ԑ��j�v�̃p�[�X�O�̂Ɋ֘A�Â��Ē莮������ƁA�u��ꎟ���^������O�����^��������v�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ə������B���̍l�����ł����Ɓu�����E����ꎟ���^�z���E����O�����^�ے��E������v�ɂȂ�B
�@���������p�[�X�́u���ۊw�I�J�e�S���[�v�Ȃ���̂��A�܂�u�p�[�X�L���w�v��u�p�[�X�`����w�v�̊�b�ƂȂ�u�p�[�X���ۊw�v�̎��������܂�ɍL�傷���āA���̗������ǂ����Ă��Ȃ��B�i���邢�́A�{�����I�̗ւ̊W��茋�ԃ��J���O�̂̓����������ł��Ă��Ȃ��B�j
�@
�m��3�n�єV�O�̗̂l�X�ȃ��@�[�W��������ׂ��Ē��߂Ă���ƁA�u���ۓI�E�����I�E�`���I�E���z�I�Ȃ��́i�N�I���A�I�Ȃ��́j�^�����I�Ȃ��́i�����I�Ȃ��́j�^�@�B�I�Ȃ��́i���_�I�Ȃ��́j�v�Ƃ������V�����O�̘_�̃A�C�f�A�����サ�Ă���B��O���́u�@�B�I�Ȃ��́i���_�I�Ȃ��́j�v������ɂ�����������Ȃ����A����͕\�w�ӎ����Z�܂�����I�q�ϐ��E�̓�����\���������́B
�@�܂��A�i���́u�����^�����^���_�^�ӎ��v�̎l���E�_�������ɓ������j�A��l���Ƃ��āu�_��I�Ȃ��́i�y���\�i�I�Ȃ��́j�v�������Ă������B�n���w�I�\�L�ł����u�n�^�C�^��^�V�i���j�v�ɂȂ�Ǝv�����A����͂��͂�єV���ۊw���Ē�Ƙ_���w�̗̈�ɒB���Ă���B
�@
���єV���ۊw�̏���
�@
�@�ȏ�̂��Ƃ�O��ɁA�Ƃ�킯�єV�O�̂�O���ɂ����Ȃ���A�єV���ۊw���߂���ŏI�I�ȁi���̂ƂȂ�͂��́j�l�@�Ɍ�����������ƂƂ��āA���炩���߁A���̏������A������O�̎����������͒n�w��蕪���Ă��������Ǝv���܂��B
�@���̎O�̑w�Ƃ́A�Ђ炽�������A�܂��A�̂̓��e�A�̂ɉr�܂ꂽ���E�Ɍ�����i���A�i�ۂɂ������w�i������A�ȉ��A�u�`�w�v�ƌĂԁj�A�����āA�̂��u���Ђ������v��i�ł���A�̂̍\�����������Â���f�ނł����錾�t�ɂ������w�i�������u�a�w�v�j�A�Ō�ɁA�N���A���邢�͉����̂��r�݁A���Ă���̂��A�̂̌��t���u���Ђ����v���A�`�B���Ă���̂��Ƃ������ƁA�܂�A�i���g�̉̐l��_�̂悤�Ȑl�i�I�Ȃ��̂ł���A���u��@�\��g�̂�ꏊ�̂��Ƃ���l�i�I�������͑O�l�i�I�Ȃ��̂ł���A���邢�̓��J�j�X����@�\�Ƃ�������p�A�͂��炫���ꎩ�̂ł���j�A�r�̔����E����̎�̂ɂ������w�i�u�b�w�v�j�̎O�ł��B
�@�����͖{���A��R�ƕ���Ȃ���ʂł���悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��āA�����炭�͑��݂ɟ����������A���R��̂ƂȂ��āA�̂̋������̂悤�Ȃ��̂��������Â����Ă���̂ł��傤���A�����ł́A�����ĕ����������A�����āA�i���͈ȉ��̘_�l�ɂ����āA����Ɂj�A���̂��ꂼ��̑w�̓��������q���ɍĕ������A�������邱�Ƃœ���ꂽ�f�Ђ�g�ݍ��킹�āA�єV���ۊw�𗧑̓I�ɍč\�����Ă����A�Ƃ������I��H�����ǂ��Ă݂����ƍl���Ă��܂��B
�@�ȉ��A���̓����̎��Ƃ��āA������܂��قڏ\�N�Ԃ�ɒʓǂ����́E�剪�M���w�I�єV�x�̋c�_�����p���܂��B
�@
�@���A�єV���ۊw�̂`�w�B
�@�w�I�єV�x���͂ɁA�єV�̂̏d�w����_������������B�u���̉̂��A�\���Ɨ����Ƃɓ�d�̈Ӗ��������A�������\�͗��ɁA���͕\�ɕs���ɗZ�����A����ΑΈʖ@�I�Ȍ��ʂ������ēǂގ҂ɑi���Ă���Ƃ����̂��A���̎�̗̉̂��z�ł���B�єV���������ꂽ�̂��A���̖ʂł̔ނ̎�r�������ނ˓I�m�����ŁA�̂̏d�w�I�ȓ��e���A�����ɂ������Ȃ�������̋��ɕ\����̂ɂȂ��Ă����܂��Ă���̂�����������������ł����������낤�B�v�i�����ܕ��ɁA52�Łj
�i�剪�����Ƃ肠����єV�́u�N���H�ɂ���ʂ��̂��Y�ԂȂǐF�ɂ��łĂ܂����ڂ�Ӂv�ł́A���Y�Ԃ̑���������Q���\�����̈Ӗ��̗����Ɂu����ɖO����ꂽ�Ƃ����ł��Ȃ��Ⴂ�g��Ȃ̂ɁA�͂₭���i���Ɍ�������āH�j�����Ă䂭���̈ڂ낢��Q���S�v�����߂��Ă���B�j
�@�܂���O�͂ł́A�єV���͂��߂Ƃ���u�Í��̐l�����ɂ����鎩�Ȃ̓I����̎��o�Ƃ������v�i84-85�Łj���߂����āA�E�c���̋c�_�����p�����B�u�Í��a�̏W�̉̕��ł��鋝�y�^���̎���̒��ɁA����Ƃ͈ꌩ�Ȃ�̌����Ȃ��v����Ƃ���̗��m�I�ȁA��]�A�����̐��_�̔Z���ɂ܂����Ă���̂́A���I�Z�I�ł��Ȃ��A�V������߂邽�߂̂��̂ł��Ȃ��A���́m�u�g�A�������ɂ��炴�邪���߂ɁA�Љ�I�ɂ��̍˔\��p����H��m�₳��v�A���t�W�̎�������u�u��v���ӎ����鎖�͂͂邩�ɋ����[�������ɂ�������炸�A��������t�Ƃ��鎖��������v�Ȃ��Ƃ����u��d�������������v���Í��̐l�����̄������p�Ғ��n������̎����̂��̂����甽�f���Ă�����̂ƌ���ׂ��ł���B�v�i�E�c���u�Í��a�̏W�T���v�j
�i�єV�́u�H�̌������₯�݂��݂��t�̂���e�������킽�邩�ȁv�Ƃ����u�V�Í��I�ȁA���o�̐�s�ȕ\�����Ȃ����v�i84�Łj���́i�u�������v�I�ȋ��y�^���̎���̂����ɂ܂��肠�������m�I�ȕ����̐��_�A���Ȃ킿�u�ǐS�v���\�����ꂽ�́A�ƌ����Ă�����������Ȃ��j���A�Í��W�ɂ�����{�єV�W�ɂ��^����Ȃ����������̂����ɁA�剪���́u���݂̎������ɂƂ��Ă͐��V�ɂ��ۂ₩�ɂ��v���邱�̂悤�ȉ̂��A�����̈�ʓI�]�����炷��A���̋Z�I�̖����A�i�C�[�����䂦�ɁA�������Ă�������Ȃ��v��ꂽ�v�Ƃ����u�Í��W�Ƃ����W�̂����Ă���Ɠ��Ȑ��i�v���A���Ȃ킿�Í��̐l�ɂ�����u���Ȃ̓I����v�̖������ĂƂ�B�j
�@�ȏ�̂��Ƃ��ӂ܂��ĊєV���ۊw�̂`�w���\������O�̍��������Ƃ���A�u�i���t�Ƃ��鎖��������Ȃ��j��v���u���ӎ��v�������́u�����́v�i���@�����[�j�A�u���v���u���v�������́u�����\�v�A�u�\�v���u�f��v�������́u��������`�v�Ƃ��Ắu�p�v�i��Ώ��j�j�A�Ȃǂƒu�������A��������u�`�w�v���u�����́i���ӎ��j�^���^�f��v��B���̋����Ȗ����̎�|��Ó����ɂ��ẮA���͈ȉ��ŌʂɌ�������B
�i�����Łu�f��v�͉̂̓��e���̂��́i�`�����ہj�A�u���v�͂��̔}�́E�\����i�i�a���\���j�A�����āu�����́v���r�́E�����́i�b�������j�ł���A�Ƃ���������q���̊W��z�肷�邱�Ƃ��ł���B����ɁA���Ƃ��u�����́i���ӎ��j�v���u�����́^�A�i���W�[�^�_���v�ƁA������܂�����q���̍ĕ������قǂ������Ƃ��ł���B�j
�@
�@���A�єV���ۊw�̂a�w�B
�@�w�I�єV�x��l�́B�g��K���Y���G�b�Z�[�u����̒����v�ŁA�єV�́u���Ђ��Ăނ��т����̂��ق����t�����ӂ̕���Ƃ����v���ɂ����A���̉̂��̂��Ă��邱�Ɓi���Ƃ��u���Ђ��Ăނ��т����v�j�����̒ʂ�̍\���Ő��m�̌�ɂ��������邱�Ƃ��ł��邩�A�Ɩ₤�����Ƃ��Љ�������ő剪���͎��̂悤�ɏ����Ă���B
�i�剪���́A���́u������ԎU��ʂ镗�̂Ȃ���ɂ͐��Ȃ���ɔg����������v���߂����āA�u�u�ʂ�v�u�ɂ́v�u�Ɂv�u���v�u����v�̂悤�ȃe�j���n���A���̈��ł͎�����Ƃ߂Ă��āA�����̋��܂ɕx�o�v�Ƌ����������A�̑S�̗̂�����Ԃ������߂Ă���v�i108-109�Łj�Ǝw�E���Ă���B
�@�܂��A��Z�͂ł́u����̊ւ̐����ɉe�����Ă��܂⌡����ޖ]���̋�v�ق��̛����̂��̂Ƃ��Čf���A�����̉̂ɗp����ꂽ�u�u��ށv�Ƃ����U�Ȃ̌����܂킵���A�����̂̏ꍇ�A�撆�̌i�Ɂe���Ԃ̕��f��^����������͂����Ă��邱�ƂɋC�Â������B�G�Ƃ��Ē蒅���ꂽ��Ԃ������ł������I�Ȃ��̂ɂ��邽�߂̍H�v�������Ă����悤�Ɏv����v�i195�Łj�Ə����Ă���B�����Ƃ����X�N���[����Ɂu���Ԃ̕��v�Ɓu�f�恁�����e���v�������炷�e�j���n�i���j�̂͂��炫�B�j
�@�ȏ�̂��Ƃ���A�����ł��܂������ɁA�єV���ۊw�̑��̑w���\������O���o����Ƃ���A�u�a�w�v���u���I����^���ƕ����^���Ǝ��v�ƂȂ�B�����ōŏ��̍��ڂɁu���I����v�̖���^�����̂́A���˂Ď��߂���Ă����u�����o�������l�̎��I����v�i��T�́A��19�͎Q�Ɓj�Ȃ�l�z�Ɉꉞ�̌���������ׂ���ʂ͂��������Ȃ��ƒ��ς�������A�i�֘A����b��A�u�������I����v�Ƃ��Ă̐��c���єV���ۊw�Ɓu��������Q�[���v�Ƃ��ẴE�B�g�Q���V���^�C������Ƙ_���w�Ƃ̑��ݕ�ۂ̊W�́A���̑̌n�ł͂b�w�ɑ�����B�j
�@
�@��O�A�єV���ۊw�̂b�w�B
�@�w�I�єV�x��́B�a�̂����I�Ȃ��̂̈ʒu�Ɂu�̂�������v���߂ɂ́A�������̕x��D���Ƃ�K�v���������B����������A�G�ߊ����J�e�S���[�I�ɕ��ނ��Ώۉ����Ă������ƁB�u����́A���l�����̊�����ɂ��e�����y�ڂ����ɂ͂��Ȃ������B�G�߁A���̋�̓I�Ȍ��ۂƂ��ẲԒ��߂�܂Ȃ����́A�Ώۉ�����ތ^�����ꗝ�O�����ꂽ�G�߁E�Ԓ��̂ނ�������ɁA���������G�߁E�Ԓ��ɂ���ċt�ɈӖ��Â���ꂽ�l���Ƃ������̂��A��d�ʂ��̌`�œ�������̂ł���B�����̉̂��A��l�̂̐��E���̂����ł������ɎO�l�̓I�Ȓ��ې��A���q�I���i��ттĂ��܂��̂́A�a�̂��u�����ɂ����������������ʒu�E�Ƃ��[���ւ���Ă����̂ł���B�v�i170-171�Łj
�@�w�I�єV�x��Z�͂ŁA�剪���͒r�c�T�ӂ́u�G�ߔ����Ƃ��̗ތ^�v���Ƃ肠���A�u�r�c���������Ō����Ă��邱�Ƃ́A�u���{�I�G�ߔ����̑̌n�v�Ƃ������̂��A�����Č����̋G�߂̎������̂��̂ɖ����������̂ł͂Ȃ��A����e�ے��̑̌n��ʂ��Ċ����Ƃ��鋤�ʂ̕����̌��f�Ƃ��������̂��̂��Ƃ������Ƃł��낤�B�i�����j�u���ۂɑ���������̉r�Q�ł͂Ȃ��A����̒Ǒ̌��Ɋ�Â��r�Q�v�i�r�c���j���A�Í��W����V�Í��W�ֈ��������ے��I�R��̓������Ȃ��ɂ�����Ƃ����̂ł���B�v�i180�Łj�Ɗ����Ă���B
�@���Ɉ��p���镶�͂͌Í��̐l�����́u���I�Ȋ����v�ɂ��ď����ꂽ���̂����A�����Ō�����u�t�B���^�[�v�Ƃ́A�єV�𒆐S�Ƃ���Í��W��҃O���[�v���m�������i�Ǒ̌��ɂ���Ċ��������ے��I�ȁj�u���{�I�G�ߔ����̑̌n�v�ɂق��Ȃ�Ȃ��B
�@�w�I�єV�x�掵�́B�܌��M�v�ق����������єV�ɐ������Ґ����߂����āA�剪���́A�u���Ƃ��єV�ł��낤�ƂȂ��낤�ƁA���̉̕���̍�҂��A�ꗬ�Z�э�Ƃ̊�͂Ɗ����������A�a�̂�̎��̖L���ȋ��{�����Ȃ��A�����ꂽ���͂̏�����ł������Ƃ��������́A��邪�����Ƃ��ł��Ȃ��B�܂��Ă��̐l�����єV���g�ł������Ƃ���Ȃ�A�I�єV�_�̕M�҂Ƃ��āA���ʼn��Ƃ��������ɂ����悤���v�i233�Łj�Ə����A�u�єV���g�̉̂��A����I���E�ւ̔Z���e�ߐ���ۂ��A�����Ɏ�̕ω���������A�������̕���I�ɂȂ�悤�ȍ삪�����v�i233�Łj���Ƃ��w�E���A�����ĊєV�́u���R����R��l�v�Ƃ������́u��]�ƂƏ����ƂƂ̕��������A���l�I���l�v�i234�Łj���v�킹��Əq�ׂĂ���B
�@���āA�����̒f�ГI�ȑf�ނ����ł͐S���Ȃ����A�����Ƃ�������߂���Ƃ̔����邱�ƕK�肾�Ǝv�����A���͈ȏ�̂��Ƃ���єV���ۊw�̑�O�̑w���߂���莮�A���Ȃ킿�u�b�w�v���u�`���́^���ʁ^���j�v��B��ɂ���āA���ꂼ��̍��ڂ̖��������A�R���A�Ó����@���X�ɂ��Ă͌�̏͂ł��炽�߂Č�������B
�i�R�S���ɑ����j
���v���t�B�[����
�����I���i�Ȃ��͂�E�̂肨�j1950�N�㐶�܂�B���Ɍ��ݏZ�B��N���̂ɏ����ꂽ�a�̂̈Ӗ��������ł���̂͂��������Ƃ��B�ł��A�{���Ɂu�����v�ł��Ă���̂��B�����Ɂu�Ӗ��v�Ȃǂ���̂��B�����������t���g���ĉ�����`�B���邱�Ƃ��̂��̂��s�v�c�Ȍ��ۂ��Ǝv���B
Web�]�_���u�R�[���v33���i2017.12.15�j
���F�ƃN�I���A����44�́@�єV���ۊw�̏����E�����i�����I���j
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU�@2017 All Rights Reserved.
|
| �\���i�ڎ��j�� |