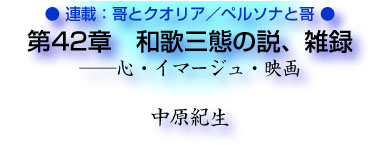|
|
|
Web�]�_���u�R�[���v |
|
���n���̎� ���{���̕\���i�ڎ��j�� ���{���̃o�b�N�i���o�[ ���ǎ҂̕Ł^���ӌ��E���z �����e�K�� ���W�҂�Web�T�C�g ���v���C�o�V�[�|���V�[ |
|
���{���̊֘A�y�[�W�� |
|
���u�J���`���[�E�������[�v�̃o�b�N�i���o�[ ���]�_���u�k�� Vue�v�̑��ڎ� |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
|
���S�̎l������߂�����
�@
�@�G�^�̈�B��40�͂ŁA�S�Ɛ��E�̎l�w�\���Ɏv�����߂��点�Ă����ہA�����Ȃ��������s�I�ɓǂݐi�߂Ă����O���̏����́A���ꂼ�ꂩ��������f�Ђ���ɂȂ����Ă������B���̂��Ƃ������łƂ肠����B
�@
�i���̂P�j
�@�Óc��Y���w�S�͂��ׂĐ��w�ł���x�́A�h���I�Șb��ɏ[���������������B
�i���Ƃ��G�s���[�O�ɂłĂ���`���[�����O�ƉĖڟ����߂���c�_�͏G��B�`���[�����O�E�e�X�g�͖{���u�@�B���l���v�Ă�Q�[���ł͂Ȃ��u�j�������v���e�X�g������̂������B�}���`�F�X�^�[�H�ȑ�w�߂��̓����ɂ́u�̑�Ȃ郍�W�V�����ɂ��ăz���Z�N�V�����Ř_���w�҂̃`���[�����O�ɕ�����v�ƍ��܂�Ă���B�����͒j�Ȃ̂����Ȃ̂��A���������j�Ə��͉����{���I�ɈႤ�̂��Ƃ��������I�ȔY�݂ɒ��ʂ����`���[�����O�������̂悤�Ȑl�Ԃ̕\���`�Ƃ��āA�����Ƃ��ẴZ�b�N�X�̂Ȃ������I�ȋ@�B���l�����B����Ɠ����悤�ɁA�������`���[�����O�Ƃ͋t�ɁA���͐��m�Ɠ��m�̍��قƂ��������ɔ���[����Y�����`�x�[�V�����ɂ��Ēj���̐��i�����j���߂��鏬�����������B�����`�������͐��m�ߑ���ے����Ă��āA���m�I�ŗD�_�s�f�Ȓj��������Ɠ��̃��W�b�N�ł�荞�߁A���������ɂ������̂ł���B�j
�@
�@���̑�Z�́u�L���Ǝ��ԂƐ��_�v�ɁA�u���Ԃ̂Ȃ��_���͖{���̐S�̓�������͉����A�ނ���_���Ɏ��Ԃ���ꂽ���_�������S�̓����ɑ����Ă���v�Ə����Ă���B�ǂ��������Ƃ��Ƃ����ƁA���Ƃ��u���̕��͉R�ł��v�Ɓu�O�̕��͉R�ł��v���g�ݍ��킳���Ɛ^�U������s�\�ɂȂ邪�A�����ɗ��U�I�Ȏ��ԁi���̂��鎞�ԁj�����Đ��_�̌`�ɂ���ƁA�^�ƋU���قȂ鎞�Ԃ̌��_�ɂȂ�i�^�ƋU�������ɏo�Ă���킯�ł͂Ȃ��j�̂Ř_���I����������ł���B���W�b�N�ō\�����ꂽ�@�B�͖���������t���[�Y���邪�A�����͖��������z���Ă����B�u���̂��鎞�ԁv���������̊�{�ł͂Ȃ��̂��A�Ƃ����̂��B
�@���U�I�ȁu���̂��鎞�ԁv���u�S������́v���Ȃ킿�u�����́v�̊�{�ł����āA���ꂪ���邽�߂ɁA�܂�_���Ɏ��Ԃ���ꂽ���_�̓����̂������ŁA�����͘_�����������z���Đ����Ă����B����₷���c�_���Ǝv�����A�������A�_���Ɏ��Ԃ���ꂽ���̂����_���i�_���{���ԁː��_�j�Ƃ����̂͂����炭�t�ŁA�����������c���q���ČJ��L���鐄�_�������玞�Ԃ̗v�f�����������Ăł����������̂��_���Ȃ̂ł͂Ȃ����i���_�|���ԁ˘_���j�B�����̒a���ɐ旧���Ԃ�_���Ƃ������̂����ɂ���Ƃ��Ă��A�����͐����̂ɂ�鐄�_�����̌��ʂ��璊�o����鎞�Ԃ�_���i���_�ˎ��ԁ{�_���j�Ƃ͈قȂ�̂ł͂Ȃ����B
�@
�@�Ƃ���Ŏ��́A�r�̂��܂������́i�S������́j�ɂ�鐄�_�̓����̂ЂƂł���ƍl���Ă��āA��������т邽�߂̐��_�����ƑΔ䂳���ĕ\������ƁA�u���̂��鎞�ԁv����{�Ƃ��錾�ꊈ���̗݁X����W�ς�ʂ��āA�₪�Ă������疳���ԓI�ȁA�ʂ̊��o���⊴��̌����̏ۂ����_���i���o�⊴��̘_���A�u�v�Ёv�̘_���j�����o����Ă����A�Ƃ��������ƂɂȂ�B��������ƁA�����Ő��_�����Ɓi�r�̂��܂ށj���ꊈ���Ƃ̊W�@���Ƃ����_�_�����サ�Ă��邪�A���̍l���͂������ĒP���ŁA����́u���_�����v�Ƃ����g�̂�Ƃ���s���̊�{�\�}�̏�Ɂu���ꊈ���ˎ��ԁ{�_���v�̉��I�ȐS�I�ߒ����d�˕`�����A�Ƃ������̂ł���B
�i�s���̍\�}�̏�ɉ��I�ߒ����d�˕`�����A�Ƃ������������B���ł���A������I�Ɂu���_�����͌��ꊈ�����Ƃ��ĕ�܂���v���邢�́u����͐��_��ʂ��Đ��N����v�ƌ����Ă������B�������ӂ��Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂́A�d�˕`���ꂽ���܂����O�̎��Ԃ�_���Ƃ���Ȍ�̎��Ԃ�_���Ƃ͈قȂ���̂ł���Ƃ������ƂƁA�����������̂悤�ȋK����܂�����ɂ���ĂȂ����Ƃ������Ƃ��B�g�̂�Ƃ����{�\�}�͌���ȑO�̐S�̓����������͌��ꂻ�̂��̂̐��������Ȃ̂�����A���������ŕ\�����邱�Ƃ͖{���ł��Ȃ��i����I�ɕs���ł���j�B���̂��Ƃ������܂��Ă����A�s���̂��̂̏�ɉ������d�˕`�����ƌ��������A�s���̂��̂��������Ƃ��Ċ܂ނƌ��������\��Ȃ��B�j
�@
�@�ȏ�̋c�_����A���̓�̉�������邱�Ƃ��ł���B���̈�A�S�������͐S�̓����i���_�⌾��A�����Ă����炭�͋L�����j�͎��ԂƘ_���łł��Ă���B���̓�A�S�E���ԁE�_���ɂ́A���ꂼ��@���_�ȑO�A�A���_�Ȍ�i�܂��͐��_�������j������ȑO�A�B����Ȍ�i�܂��͌��ꊈ�����j�̎O�̒i�K������B
�@
�i���̂Q�j
�@�����`�����w�s�݂̓N�w�x�́A�q�ϓI���E�͎��݂��Ȃ��i���ۂł���j�Ƃ��������Ɍ���I�\�������������A�����N�w�́i�����_�ł́j�咘�ł���B
�i���̏����Ɖi��ϒ��w���݂Ǝ��Ԅ����N�w�T���P�x�Ƃ��r�l�ʂ��J��Ԃ���䍂��邱�ƂŁA��Ƃ́u�s�݂̔��w�v�ƊєV�́u�������̔��w�v���͂�ޓN�w�I�܈ӂ𒊏o���邱�Ƃ��ł��邾�낤�B���͂���Ȃ��Ƃ�\�����Ă���̂����A���������N�w�ɂ���i��N�w�i�i��_�w�H�j�ɂ���A�N�w���邱�ƂƐ����邱�ƁA������ԓx��p���̂悤�Ȃ��̂��X�V���邱�ƂƂ��ʂ̂��Ƃł͂Ȃ��̂ŁA�{�������Ă��̓���̓N�w����䍂��Ă��������ɁA�����g�̚n�D��u����v�l���̂��̂�����ւ���Ă��܂���������Ȃ��B�j
�@
�@�������ɂ��ƁA�q�ϓI���E�Ƃ́u�ϔO�Ƃ��Ắq���܁r�v�Ƃ����u�ÓI����v�ɊJ�����u���łɈӖ��Â���ꂽ���E�v�̂��Ɓi391�Łj�B����ɑ��āu�����I���݂Ƃ��Ắq���܁r�v�i392�Łj��u���̂ǗN���o������q���܁r�v�i393�Łj�ƌ�������̂������āA����́u�������E�ɈӖ���t�^�����鎞�Ƃ��Ắq���܁r�v�i391�Łj���邢�́u������w�L�@�̂����E���Ӗ��Â�����A�����ɂ�����̔��Α��ɁA�u���v���������铮�I����v�i390-391�Łj�ƒ�`�����B
�@�S�g�����͂��߂�����N�w�I�_�́A���̂ӂ��́u���܁v�̍����I���قɋA������B�����ċq�ϓI���E�����݂��Ȃ��Ƃ́A�u�N���o������q���܁r�v�݂̂����݂Ƃ݂Ȃ����Ƃɂ���āA�q�ϓI���E���u�s�݁v�̂��́A�������́u������������I�ȈӖ��\���́v�i394�Łj�ɂ����Ȃ����̂Ƃ݂Ȃ����ƁA����������邱�Ƃł���B���ꂪ�w�s�݂̓N�w�x�̍ŏI�ǖʂł̋c�_�̔����B�i�J��Ԃ��ɂȂ邪�A�����N�w�ɂ����Ă͓N�w���邱�ƂƐ����邱�ƂƂ�藣�����Ƃ͂ł��Ȃ��B�����炻�̒�����Ǐ����������v�邱�Ƃɂ͖{���Ȃ�̈Ӗ����Ȃ��B�����Ŏ��グ�����̂́A���̂悤�ȁu���_�v�ɂ�����c�_�̏o���_�œ������ꂽ����u����v�ł���B�j
�@�������͖{���ŁA���݂ƕs�݂Ƃ̊W�𖾂炩�ɂ��邽�߂ɁA����u�傪����v�Łu�P���v�ȁu�}���v�����Ă���B���̐}���Ƃ́A�u�����l�Ԃ͗L�@�̂Ƃ��ć@���Ƃ��Ǝ��Ȓ��S�����Ă��邪�A�A���̗L�@�̂�������K�����邱�Ƃɂ���ĒE���Ȓ��S�����A����ɇB�I���Ȓ��S������v�i12�Łj�Ƃ������̂ŁA�����m�o�̏�ʂɑ����Č����\�킷�Ǝ��̂悤�ɂȂ�i58�Łj�B
�@
�P�D������K������ȑO�̗L�@�̂��A���Ȓ��S���Ɋ�āu�h�����ԁv�����i�K�B
�Q�D������K�����E���Ȓ��S���𐋍s�����L�@�̂��A�u�h�����ԁv�����łɈӖ��Â���ꂽ���ՓI�ȁu�ϔO���ԁv�Ƃ��ď��F����i�K�B
�R�D���̌���ɂ���Ĕ}��ꂽ���ՓI�ȁu�ϔO���ԁv���A�ӂ����ю��Ȓ��S�����i�I���Ȓ��S���j�A�q���܁E�����r�ő̌����Ă���i�K�A���Ȃ킿��������炽�߂āu�ԁv�Ƃ��ĈӖ��t��������i�K�B
�@
�@���i�K�́u�h�����ԁv�A���i�K�́u�ϔO���ԁv�ɑ��āA��O�i�K�́u�̌����ԁv�Ɗ�����B������K�������L�@�̂��u�ԁv��m�o����Ƃ́A�P�Ɋ��o�h�������Ƃ������Ƃ����ł͂Ȃ��A�܂����łɈӖ��Â���ꂽ���ՓI�ȊϔO�i�Ӗ��j��������e���邱�Ƃ����ł��Ȃ��āA�u���o�h�������\���I�ɈӖ��t�^����v�i57�Łj�Ƃ������ƁA�܂�u�Ӗ��t�^������v�Ƃ����u�\���I�̌��v�i59�Łj�Ȃ̂ł���B
�@�������ɂ��ƁA���̐}���̊�ڂ́A����K���̗L�l�𐳊m�ɂƂ炦�邱�Ƃɂ���̂ł͂Ȃ��A�N�w�̌ÓT�I���̂���������������I�ϓ_��^���邱�Ƃɂ���B
�@�����Ō�����u�E���Ȓ��S�I���E�v���q�ϓI���E�ɊY�����A�u���Ȓ��S�I���E�v���u�����I���݂Ƃ��Ắq���܁r�v�ɂ����ĊJ����鐢�E�ɑΉ����Ă���B�������̋c�_�́A�O�҂̎��݂�O��Ɍ�ҁi�s�݂̐��E�j���������邢�͓��o���錭�����ے肵�A�u��ҁm���Ȓ��S�I���E�n�ɒ�ʂ��āA�O�ҁm�E���Ȓ��S�I���E�n�̒��ې��𖾂炩�ɂ���v�i14�Łj���ւƐi�݁A��q�́u���_�v�ɓ�����̂������B
�i���Ȃ݂ɁA���p�����́u���ɒm�o���Ă���v��u���ɑz�N���Ă���v�́u���Ɂv�͉i��N�w�ɂ�����u�������A�A�N�`���A���e�B�v�̊T�O�ɂ�������b�ŁA����́u���ݐ��A���A���e�B�v�̊T�O�Ƃ͑f�����قɂ���B�����Ȍ������Ŋ���ƁA�єV���ۊw�́u�������v���u���ݐ��v�ɗD�ʂ���̘_�ŁA��Ƙ_���w�͋t�Ɂu���ݐ��v���u�������v�ɐ旧�̘_�ł���B�����āA���m�ɂ����ăL���X�g���_�w�̒��ێv�l�̉�ō܂Ƃ��Ď��R�Ȋw���Y�ݏo���ꂽ�i�{�V�Ўi�j���Ƃƃp�������Ɍ����A�єV���Ƃ̘̉_�i�̊w�j�A����ɐS�h�␢����◘�x��m�Ԃ̌|�_�́A�嗤�R���̒��ێv�l����ł���{�M�ɂ�������؎v�l�ƌ��邱�Ƃ��ł���B�j
�@
�@�����Ŏ��́A��O�i�K�́u�̌����ԁv����i�K�Ƒ��i�K�̂������ɁA���Ȃ킿����K���������͌���Y�o�̃v���Z�X�̂����ɒu���čl���Ă݂�B����͕��ՓI�ȈӖ��Ƃ��Ắu�ԁv�̑̌���u�ԁv�Ƃ����o�������́u�Ӗ���t�^������̌��v�i59�Łj�ł͂Ȃ��āA���t�ɐ旧�����o���́A���́A���ړI�ȁq�ԁr�̑̌��ł���B���̂悤�ȁA�u���܁E�����v�Ɓi�u���ݐ��v�̃��x���ł́j�w���������Ƃ̂ł��Ȃ��ꏊ�ɂ�����q�ԁr�̏����o�����T�O�Ƃ��Ắs�ԁt�ɂȂ���A�₪�Ă������猾�ꂪ�Y�ݏo����Ă����A���̃v���Z�X�̋N�_�ƂȂ蕑��Ƃ��Ȃ�̌��̂��Ƃ��B
�i�u�̌����ԁv���u���Ȓ��S�I���E�v�Ɉʒu�Â����Ă��邱�Ƃ͌��₷�����A�ʂ����Ă��ꂪ���i�K�́u���Ȓ��S�I���E�v�ɂ���̂�����Ƃ���O�i�K�́u�I���Ȓ��S�I���E�v�Ɉʒu�Â�������̂Ȃ̂��A��̈��p�������ł͔��R�Ƃ��Ȃ��B�������͗��`�����Ӑ}���ĕ��͂������Ă���̂�������Ȃ��B
�@���Ȃ݂ɁA���p���̍Ō�ɏo�Ă����u�s�݂ɂ́A�u���ɂ���s�݁v�Ɓu���ɂȂ��s�݁v�Ƃ����܂������قȂ����������������ނ�����v�Ƃ����w�E�A����͌�ɁA�I���Ȓ��S�����ꂽ�L�@�̂́u�����́u�ɂ݁v�݂̂������I�ɂ݂ł���A���l�̒ɂ݂͂����łȂ��Ƃ����c��d�̐��E�ɐ����Ă���v�i335�Łj�Ƃ������������ŌJ��Ԃ����̂����A�Ƃɂ������̂悤�ȁu��ΓI���ِ��v�i335�Łj�̕����́A���i�K���͂���ł��̑O������ꂼ��̍ݏ��Ƃ���u�̌����ԁv�̓�̑��ݗl���̂����ɂ���̂ł͂Ȃ����B���Ȃ��Ƃ������l���邱�ƂŁA�єV���ۊw�ɂ�����u�������v�ƒ�Ƙ_���w�ɂ�����u�s�݁v�����N���邻�ꂼ��̏ꏊ������ł���̂ł͂Ȃ����B�[���ȋᖡ���o�Ȃ��y���ȕ��������Ƃ͎v�����A���͂����ł���Ȃ��Ƃ��l���Ă���B�j
�@
�@�ȏ�̋c�_�܂��āA��̓�̉����̃��@�[�W�����E�A�b�v��}��B���̈�A�S�������͐S�̓����i���_�E����E�L���j�͎��ԂƘ_���łł��Ă���B���̓�A�S�E���ԁE�_���ɂ́A���ꂼ��@���Ȓ��S�I�E��i�������͑O�j����i�K�i��F�h�������j�A�A���Ȓ��S�I�E����K���i�������͎Y�o�j�i�K�i��F�����o���j�A�B�E���Ȓ��S�I�E����g�p�i�K�i��F���ՓI�Ӗ��̌��j�A�C�I���Ȓ��S�I�E����g�p�i�K�i��F�Ӗ��t�^������\���I�̌��j�̎l�̒i�K������B
�@
�i���̂R�j
�@���đ�T�͂ŁA�Í��W��������f�ނɂ��Ďl�̐S��_�������Ƃ�����B�Đ�����ƁA�@�X�����ۂɂ킽���ėl�X�ɕ���S�̖����W���A�J�~�̐S�A�^�}��X�s���b�g�A��̎����̐S�i�u�����v�ƂȂ��Č�����S�j�A�A���ׂẮu�����Ƃ���������́v�̂����ɏh�镁�ՓI�ȐS�i�u����v�ސS�j�A�B�������Ȑ�����̂����ɏh��A�₪�āu���Ƃ̂́v�ւƐ�������u���ˁv�Ƃ��Ă̐S�i�u��܂Ƃ����v���r�ݏo�����S�j�A�C���̒����u���Ƃ킴�������v�����鐶�g�̐l�́u�v�Ёv�i�u�a�́v�������o���S�j�B�����͂�������ʂ̘a�̂̉r�o�ɐ旧�S�ŁA�r�ݏo���ꂽ�A�������͉r�ݏo�������a�̂ɂ�����S�͂���ɁA�̂̐S�A�r�݂���S�i���\�̍�҂̐S�j�A�����āi���݂������͋��\�́j�ǎ҂̐S�ւƕ��Ă����B
�@�܂���20�͂ł́A�g�{�������w�����̗w�_�x�̘a�̎j�̋c�_�ɑ����āA�ȉ��ɍČf����뎟������O�����܂ł̎l�̐S��_�����B���̎l�̐S�ɂ��Ă͑�28�͂ŁA�䓛�L�q�i�u�ӎ��t�B�[���h�Ƃ��Ă̘a�́v�j���_�����S�̎l�̊K��A���Ȃ킿�@�����߁E�ۂ́u�S�n�i������j�v�A�A�ӎ��̎��ƓI�����Ƃ��Ắu���i�����Ёj�v�A�B�ӎ��t�B�[���h�i�v�Ё{��j�A�C����t�B�[���h�i���{�]��j�Ɋ֘A�Â��Ď��グ���B
�@
�y�O�z�܂��A���R�A���Ȃ킿�u���v�̐��E�Ƃ����傫�ȁu�e��v�i�v���g���́u�R�[���v�A���c�����Y�́u�ꏊ�v�ɁA���邢�́u���A�v�ɒʂ�����́j�������āA���̂Ȃ��ŁA�i�a����L�̏�ݏd�ˁA�������͌��ꊈ���ɕ��ՓI�ȋ��g�I�\������āj�A�u�S�v���C���L���x�[�g�����B���́u�S�v�̂��Ƃ��u�S�O�v�i�뎟���̐S�A�������͗�j�ƕ\�L����Ȃ�A�������āA�u���v�̐��E�Ƃ̌��E�����E������ʂ��āA�A�j�~�Y����V���[�}�j�Y���ɂȂ���i���̌�b�ł����A�u�F�Ƃ����M�t�g�v�ɂȂ����Ă����j�u�S�O�v����܂�B�i�Z�̗w�A���t�W�j
�@
�y�P�z���ŁA��������āi���g�I����\����}��Ƃ��āj�Y�o���ꂽ�u�S�O�v�Q�̏W���̂��ЂƂ̗̖���������Â���A���ꂪ�A�V���ȁu�e��i�R�[���A�ꏊ�A���A�j�Ƃ��Ă̐S�v�i�L�`�̊єV���ۊw�̐��E�A���邢�́u�F�̃p�����v�Z�X�g�v�j�ƂȂ�B����܂ł̊W���t�]���āA����ǂ͂����Ɂu���v���Ƃ肱�܂��悤�ɂȂ�B���́u���v�̐��E�ɒ����i�������j����������̂��A�u�͂��炫�i���^�t�B�W�J���ȓ��o��p�j�Ƃ��Ă̐S�v�i���`�̊єV���ۊw�̐��E���������Â���u���Ђ������v�́A���邢�́u�t�B�M���[���Ƃ��Ă̚F�v�j�ŁA���̂Ƃ��N�������̂��u�S�P�v�i�ꎟ���̐S�j�ł���B�i����́A���́A�e��Ƃ��Ă̐S�̂����ɓ��݉����ꂽ�u�S�O�v���������������̂ł���A�Ƃ����Ă��悢�B���邢�́A�u��܂Ƃ����́A�l�̂���������˂Ƃ��āA���Â̂��Ƃ̂͂Ƃ��Ȃ�肯��B�v�Ƃ����Ƃ��́A���́A�₪�Ď��ւƐ������Ă����u�l�i�ЂƁj�̂�����v�A�������́u���Áv�̂��̂����ւƕϐ��E�Ґ�����Ă����Ƃ��̔}��A�}���ƂȂ�u��i�ЂƁj�̂�����v�̂��Ƃł���A�Ƃ����Ă��悢�B�j
�@
�y�Q�z���́u�S�P�v�̗���������ɂ���āA�܂�u���v�ɂ��C���I�ȕ\��������ʂ��āA�u������̂������́v�i�e��Ƃ��Ă̐S�ɂƂ肱�܂ꂽ�u���v�j�ɕt�����ĕ\�������̂��A�u���̒��ɂ���l�v���u�S�ɂ����ӂ��Ɓv�A���Ȃ킿�u���v�Ɠ��������ɑ����鎖���Ƃ��Ắu�S�Q�v�i���̐S�j�ł���B�i�a�́A�Í��W�j
�@
�y�R�z�₪�āA���́A�e��Ƃ��Ă̐S�̂Ȃ��ŃC���L���x�[�g���ꂽ�u���v�ɂ��\���̒�����}��ɂ��āA�C���I�ȕ\�����Ƃ��Ắu�p�v�i�̂ɉr�܂ꂽ�C���[�W�A�������͉��C�E�����̂������j���A�ے��I�ȁu�S�R�v�i�O�����̐S�j�Ƃ��Č`�ۉ������B���Ȃ킿�A�����Ƃ��Ă̕����S�̐��E��\���̐��E�ւƒ��o��������̃��^�t�B�W�B�N�̓O��ɂ���āA�i���邢�́A�u���̌Í��W�̏��ɂ��ւ邪���Ƃ��A�l�̂��������Ƃ��āA���Â̌��̗t�ƂȂ�ɂ���A�t�̉Ԃ����ÂˁA�H�̍g�t�����Ă��A�̂Ƃ��ӂ��̂Ȃ���܂����A�F�����������m��l���Ȃ��A�������͂��Ƃ̐S�Ƃ����ׂ��v�Ƃ����A�r���I�]�����āj�A����u�e��Ƃ��Ă̎��v�̐��E���������Â����A����ɁA���̂Ȃ��ŃC���L���x�[�g���ꂽ�u�p�v���A���̃��^�t�B�W�B�N�̂͂��炫�ɂ���āA�����������̐��𑼊E���璭�߂邪���Ƃ��u���n�v�Ƃ��Ď��݉������B�i�a�́A�V�Í��W�j
�@
�@���āA�����̐S�̕�������w�S�͂��ׂĐ��w�ł���x��w�s�݂̓N�w�x�̋c�_�Ɠ˂����킹�āA����ɏ�q�̉�����g�ݍ��킹�A��⋭���ɐ��������������āi�Ƃ�������������킹�āj��������Ǝ��̂悤�ɂȂ�B
�i��̒��L�B�e���`���́u�����v�u�����v�u���_�v�u�ӎ��v�́A��V�͂Łu�F�̓`���́v�̊T�O�������ۂɗp�����̂Ɠ����Ӗ������̂��́B�܂��u�����f���v�u�����v�u�Ύ��v�u�Α��v�́A�䓛�L�q�i�u���R��䶗������F���t�B�[���h�Ƃ��Ă̘a�́v�j�����䶗��E�O�����䶗��E�@��䶗��E㹖���䶗��̎l���䶗��̂��ꂼ��ɂ��Ă���i��31�͎Q�Ɓj�B�Ȃ����L�̕��ނ́A�����đ�36���Œ����i�N�I���A�̋�ƃy���\�i�̊C�ɂ͂��܂ꂽ�j�|�p����_�̍\�}�ɃI�[�o�[���b�v���Ă����B�j
�@
�y�S�O�z
�@�����̎����B�����f���B�������ہi���_�j�ȑO�̎��ԂƘ_���B
�@�ۂ́u�S�n�v�����Ƃ��A�u���v����āA�u�ܑ�ɂ݂ȋ�������v�́u�����v�Ƃ��Č�����S�i�N�I���A�Ƃ��Ắu�S�O�v�H�j�B
�@
�y�S�P�|�P�z
�@�����̎����B�����B���Ȓ��S�I�E��i�O�j����I�i�K�̎��ԂƘ_���B
�@�����Ƃ���������̂́u����v�ޕ��ՓI�ȐS�B�@
�y�S�P�|�Q�z
�@�����̎����B�����B���Ȓ��S�I�E����K���i�Y�o�j�i�K�̎��ԂƘ_���B
�@�l�̂����Ɂu���ˁv�Ƃ��ďh��A�₪�Ď��i���Ƃ̂́j�ւƐ������A�u��܂Ƃ����v���r�ݏo�����S�i����j�B
�@
�y�S�Q�z
�@���_�̎����B�Ύ��B�E���Ȓ��S�I�E����g�p�i�K�̎��ԂƘ_���B
�@���̒����u���Ƃ킴�������v�����鐶�g�̐l�̓��ʂɋA�����A�a�̂Ƃ��Č����o�����S�i���v�Ёj�B
�@
�y�S�R�|�P�z
�@�ӎ��̎����B�Α��B�I���Ȓ��S�I�E����g�p�i�K�̎��ԂƘ_���B
�@�r���I�]��A���邢�͌i���ɕ\����^������̃��^�t�B�W�B�N����āA���̂����ɑ��`�����u�r�݂���S�v�B
�y�S�R�|�Q�z
�@�ӎ��̎����B�Α��B
�@�\����}��ɂ��āA����S�̋��n���l��������̃��^�t�B�W�B�N��ʂ��đ��`�����y���\�i�̐S�i�u�S�O�v�ւƒʒꂷ���l�l�̂́u�S�S�v�H�j�B
�@
�@�O���ڂ̏����̂��Ƃ��������炷�Ƃ��낾�����B���_�I�ҁw�Q�������P�x�Ɏ��^���ꂽ�������c�u���a��]�̏����1975-1989�v�ŁA�������厁�����̂悤�ɔ������Ă���B
�@�u�G�R�[�̂悤�ɏd�Ȃ��Ă����v��u�i���t�̏�Ɍ��t���j�Ђ��݂����ɐ܂�d�Ȃ��Ă����v��u���C���[���ǂ�ǂ��Ă����v�Ƃ����\���́A�g�{�������w�E�����a��i����j�ɓ��L�̗������E�C�����̕��@�ł���u��ݏd�ˁv�i�u�����I�Ȃ��́v�̏����j��̗w�̑c�`�ɂ�����u���g�v�I�W�̂���l���߂���씲�Ȕ�g�ƂȂ��Ă���B����ɂܑ͌�F���́u�����v�Ƃ��Ắu�S�O�v���N�_�Ƃ��ďd�w�I�ɕ���a�̂́u�S�v���̂��̂��A�Ђ��Ắu�S���������v�̓�����ʂ��ĐX�����ۂ��u�G�R�[�v��u�Ђ��v��u�p�����v�Z�X�g�v�̂悤�ɐD��d�Ȃ��Ď�����Y�o���Ă����a�̓I���E�i����͂����炭��؋��́u�����I���E�v�ithe �dchosistenz world�j�ɂȂ����Ă���j�̉ғ�������[�I�Ɍ������킵�Ă���B
�@
���C�}�[�W���̎l���ނ��߂�����
�@
�@�G�^�̓�B�䓛�r�F�́u�C�}�[�W���v���߂����āA�w�ӎ��Ɩ{���x�Ŏ��̂悤�ɏ����Ă���B
�@���Ƃ��Ύ��̂悤�ȕ��ނ��l�����邾�낤���B�i�����ł͐[�@�肵�Ȃ����A���l�Ɂu�t�B�M���[���P�`�R�v��u�p���C���[�W�P�`�R�v���߂��镪�ނ��������Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����B�j
�@
�y�C�}�[�W���P�z
�@�`�̈�i�\�w�ӎ��j�Ɍ��ۂ��鋷�`�́u���v
�@�u�����v�i�I���W�i���j�ɑ���u�ʂ��v�i�R�s�[�j�̊W�ɂ��鑜
�@�u�C���f�b�N�X�v�Ƃ��Ă̑�
�@
�y�C�}�[�W���Q�z
�@�l�̈�i�`�̈�Ƃa�̈�̒��Ԓn�сj�ɉғ�����L�`�́u���v
�@�u�g�v�I�W�ɂ���L�`�́u�ہv�i�`�ۉ����ꂽ���^�j
�@�u�C�R���v�i�u�I���W�i���v����������u�R�s�[�v�j�Ƃ��Ă̚g
�@
�y�C�}�[�W���R�z
�@�a�̈�i����A�������j�ɐ��N����ōL�`�́u���v
�@�u�́v�i����������́j�́u�͂��炫�v�Ƃ��ė����オ�鋷�`�́u�ہv
�@�u�V���{���v�Ƃ��Ă̌��^�i�u�R�s�[�v�Ȃ��u�I���W�i���v�j
�@
�@���̎O�̎����́u�C�}�[�W���v�́A�䓛�r�F���_�����w�R�[�����x�̎O�̕\�����x���i��23�͎Q�Ɓj��A����V�꒘�w��ƕ҂��Ą����Ώ̐��l�ފw�U�x�i273-274�łق��j�Ō��ꂽ���Ί펞��̓��A�C���[�W�Q�̎O�w�\���i��S�́A��11�͎Q�Ɓj�A�����Ă�������ɂ�����F��̎O�́u�V���g���v�i��37�͎Q�Ɓj�Ɩ��ڂɊ֘A����B�����̗v�f���̕��ނɑg�ݍ���ł݂�ƁA���̂悤�Ȃ��̂ɂȂ邾�낤���B
�@
�y��T�w�z�u�C�}�[�W���P�v���u���v
�@�@�@�@�@�u�����I�krealistic�l�v�ȑw
�@�@�@�@�@���A�lj�C���[�W�̑�O�Q�i����j
�@�@�@�@�@�g�[�e�~�Y���i�z���E�̃V���g���j
�@
�y��U�w�z�u�C�}�[�W���Q�v���u�g�v
�@�@�@�@�@�u����^�`���I�knarrative/legendary�l�v�ȑw
�@�@�@�@�@���A�lj�C���[�W�̑��Q�i��ۓI�j
�@�@�@�@�@�،������i�ے��E�̃V���g���j
�@
�y��V�w�z�u�C�}�[�W���R�v���u�ہv
�@�@�@�@�@�u�C�}�W�i���^�يE�I�kimaginal�l�v�ȑw
�@�@�@�@�@���A�lj�C���[�W�̑��Q�i���ۓI�j
�@�@�@�@�@�S�ہi�����E�̃V���g���j
�@
�@����͂��Ȃ苭���Ȃ��̂ŁA�Ƃ��ɖ��Ȃ̂́A�\�����x���ɂ�����u����^�`���I�knarrative/legendary�l�v�ȑw�Ɠ��A�lj�̑�O�Q�C���[�W�i����j�Ƃ����܂����ݍ����Ă��Ȃ����Ƃ��B�䓛�r�F�������悤�ɁA�u�����I�C�}�[�W���v�i�C�}�[�W���P�j���l�̈�ɓ����āu�z���I�v�C�}�[�W���ɕώ�������A�u���I�C�}�[�W���v�i�C�}�[�W���Q�j�����̖{���̏Z���𗣂�ĕ\�w�̂`�̈�܂ŏo�Ă�����ƁA���݂Ɉړ�����ꍇ������Ǝw�E���邱�Ƃŗ��_�I�]�т�U�������������Ȃ��B
�@���Ȃ݂ɁA�䓛�r�F�́u���^�v�C�}�[�W���̐��i�Ƃ��āA�����I���A�����A���ꐫ�i���b�I���ȓW�J���A�_�b�`���I���W���j�A�\�����̎l�_�������Ă��āA�Ƃ��ɂ��̂����̑�O�_�ɂ��āA�u���^�v�C�}�[�W�������ł͂Ȃ��l�̈�ɐ��N���邷�ׂẮu�z���I�v�C�}�[�W���́u�{���I�X���v�ł���Ə����Ă���B�i�w�ӎ��Ɩ{���x248�Łj
�@
�@��q�̍\�}�������́u�}���v�ƁA��36�͂Ř_�����u�w�����P�i���o�ʁj�v�u�x�����Q�i��ʁj�v�u�y�����R�i����ʁj�v�̎O�g�݂Ƃ̊W���ǂ��\�z����������B
�@��������A���������G�^�̈�łƂ肠�����S�̎l����Ƃ̊W���������͐������͂ǂ��Ȃ��Ă���̂��B���Ƃ��u�C�}�[�W���O�v���u�сv�i�b�̈�i���ӎ��j�ɐ�������ŋ��`�́u�ہv�j�Ƃ������ތ^�����A�����ɑ�l�̋L���Ƃ��āu���ʁA�}�X�N�v�i�u�I���W�i���v�Ȃ��u�R�s�[�v�j�������́u�l�̎�ɂ��Ȃ������A�A�P�C���|�C�G�[�g�X�v�i�u�I���W�i���v�������]�ʂ��ꂽ�u�R�s�[�v�j�Ȃǂ����Ă͂߂āA�ŌẤy��O�w�z�������́y��W�w�z�Ȃ�n�w�����炦�Ă݂邩�B
�@�����̂Ȃ����⎩���������B
�@
���a�̂̎l�̎p�ԕω����߂�����
�@
�@�G�^�̎O�B�O�Y�N�ƒ��w�f��Ƃ͉��������t�����X�f��v�z�j�x�ɕ`���ꂽ�t�����X�f��ɂ�����u�������̔��w�v�̌n���́A�{�M�����a�̂̎O�ԂƂ���ɐ旧�Ñ�a�̂��܂߂��ÓT�a�̂̎l�Ԃƌ����ɕ������Ă���B
�@
�@�������̂��ƂɋC�Â����̂͘a�̎O�Ԃ̐��E�r���҂ɂ��Ďv�l���߂��点�Ă������̂��ƁB�g�{�����̌|�p����_�ɂ�����g�̗��_���p�X�J���̃t�B�M���[���_�ɂȂ����Ă���ƒm��A����O�璘�w���Ɣ�ց\���p�X�J���q�����Ȃ����́r�̔F���x���Q�l���Ƃ���ㆂ����Ƃ���A���̏����O����ǂݐi�߂Ă����O�Y�{�̘b�肪���傤�Ǒ�O�͂̃��x�[���E�u���b�\���ɂ���������A�����ł̓u���b�\���̏@���I�C���[�W�_�ƃp�X�J���̃t�B�M���[���_�Ƃ̕��s�����w�E����Ă��āA�Q�l�����̃��X�g�ɖ�������������{����u�����̗L�v�Ȏ������v�i144�Łj�ƒ��L����Ă����B���̎���I�ȃV���N���j�V�e�B��Ⴢ�A���u�����Ȃ����́v���u��������́v�ɏh��u����v�̔�V�i124�Łj�ƁA�a���̐��A�ƁA���ԓI�Ɍォ�痈��I���W�i�����\�^�Ƃ��Ẳߋ��̏o�����i�R�s�[�j�̈Ӗ�������������u�\�����t�B�M���[���v�i126�Łj�̊T�O�Ƃ���s�����鉖�쁁�O�Y���̋c�_���A�r���I�]��₻�̌n���w�̎����Ƌ����قNj��������Ă��邱�Ƃɒm�I�����Ɩ��x���o�����B
�@�����łӂƎv�������A�O�Y�{���͂̃A���h���E�o�U���̃��A���Y���_�Ɋւ���_�q�A�O�Y���ɂ��Ƃ���́u�z���I�Ȃ��́v�̌������A���������߂���v�l�i14�ŁA98�Łj�ɂق��Ȃ�Ȃ��̂����A���̃o�U���̃C���[�W�_�ɑk���čēǂ��Ă݂�ƁA���ꂪ�܂��єV���ۊw�Ƃ��̂̌����ɕ������Ă����B���Ȃ��Ƃ����͂����m�M�����B������a�̎O�Ԃ̐��E��ƕ҂̍\�z�ɍۂ��ẮA�t�ɃW���E�h�D���[�Y�́w�V�l�}�x���߂����l�͂̏��q�ɑ�������āu���̂��v�i�f��͂��ꎩ�̐����Ă���j��u���сv�i�f��ւ̖v���Ɗ����j�Ƃ�������Ƙ_���w�̃L�[���[�h���o�����Ƃ��o�������A���͂̃W�����E�p�������F�ɂ�����C���[�W�̎����^���Ɋւ���c�_�A���Ȃ킿�f��Ƃ����V�����Z�p�ɂ��s���̂��̂̉������ԁE���Ԃ̎ړx�̕ύX���X�̘b��́A����i�����j�Ƃ����V�����e�N�m���W�[�̓����������炵���єV�ȑO�̌Ñ㎍�̂̐��E��f�i��������̂ƂȂ����m��1�n�B
�@�ق�Ƃ��͂����ŁA�u���~�j�b�T���X�v�̖��ӎu���i���������j�Ɓu�A�P�C���|�C�G�[�g�X�v�̖���א��i���������j�A�x�����~���́u�A�E���v�A�u�I�[�g�}�g���v�i�����I�ɓ������́j�ƃt���C�g�́u�����v�A���X�A�����������̒��̎��ۂ̂悤�ɕ��яオ���Ă͏����Ă����S���ɏW�����A�܂��r���̘_�ƃp�X�J���̃t�B�M���[���_�A��Ƃ̘̉_�Ɓu��������`�v�i��Ώ��j�j�������́u�����C���[�W�v�i�O�Y�N�Ɓj�Ƃ�������38�͂ŗ\�����Ă����e�[�}��A�u���Ԃ̒������ʁv�i�F��v�j�Ƃ�����41�͂ɏo�Ă������t�ɂ��āA�Ƃ��ɖY�p�̕��ɒ��݂����̑��̘_�_�Q�Ƃ��ǂ����炽�߂Ď��グ�A�O�Y���̋c�_���̎��Ƃ��Ȃ��痧�������Ďv�Ă��ׂ��Ƃ��낾���A�����̘b��ɂ��ẮA����A�єV���ۊw�Ɋւ���l�@�̍ŏI�ǖʂɂ����錜�Ď����Ƃ��Ď��g�ނ��Ƃ��o����Ǝv���B
�@
�@�]�\�Ƃ��āB�g�{�����́w����ɂƂ��Ĕ��Ƃ͂Ȃɂ��x�̑�X�͂ŁA���w��i���u����\�o�̉��l�v�Ƃ��Ăł͂Ȃ��u����|�p�Ƃ��Ẳ��l�v�i11�Łj�Ƃ��Ĉ������߂Ɂu�\���v�̖����Ƃ肠���A���E����E���Ƃ����O�i�K�̌���\���̓W�J�������Ă���B
�@����V�ꎁ�́w�g�{�����̌o�ϊw�x�̑�u�o�ς̎��I�\���v�ŁA�u�g�{�����͌���̉��ɐ��ގ��I�\����T�邾���ł͖��������A�o�ςƂ������̂̉��ɐ��ގ��I�\���܂Ŗ��炩�ɂ��悤�Ƃ����v�i341�Łj�Ə����Ă���B�w�g�{�����̌o�ϊw�x�̑�ꕔ�ɂ͋g�{�̍u���u�ߑ�o�ϊw�́u�����E���̂�����E�h���}�v�v�����^����Ă��āA�����ł̓A�_���E�X�~�X�́u�́v�A���J�[�h�́u����v�A�}���N�X�́u�h���}�v�Ƃ������������Ő�̍\���_�̐��ʂ��p�����Ă���B���ڂ������̂́A���������ɑ�l�̗ތ^�����Ă��邱�Ƃ��B
�@
�@�єV�ȑO���p�������F���Ȃ��Ȃ��m��2�n�B�єV���o�U�����́B�r�����u���b�\��������B��Ɓi������j���h�D���[�Y�����B�i���͂����ɑ�܂̌`�Ԃł���f��i�@�B�d�|���̓`���́j��t�������Ă݂����Ɩ��z���Ă���B�j
�@
�m��1�n�T�䏟��Y���w���{�l�̐��_�j ��ꕔ �Ñ�m���K���̌`���x�̎��̈�߂́A������l�|�[���E���@�����[�ƂƂ��Ɂu�|�p��i�̎�e�o�����u�����v�Ƃ����ϓ_����v�l�����v�i�O�Y�O�f��63�Łj�p�������F�ɂ�����u�����Ȏ����^���̂������v�i��61�Łj�ɒʂ��Ă���B
�m��2�n����V�ꎁ�͍u���u�����w�Ɛl�ފw�v�uhttp://ci.nii.ac.jp/naid/110007172869�n�Ŏ��̂悤�Ɍ���Ă���B
�i�S�R�͂ɑ����j ���v���t�B�[����
�����I���i�Ȃ��͂�E�̂肨�j1950�N�㐶�܂�B���Ɍ��ݏZ�B��N���̂ɏ����ꂽ�a�̂̈Ӗ��������ł���̂͂��������Ƃ��B�ł��A�{���Ɂu�����v�ł��Ă���̂��B�����Ɂu�Ӗ��v�Ȃǂ���̂��B�����������t���g���ĉ�����`�B���邱�Ƃ��̂��̂��s�v�c�Ȍ��ۂ��Ǝv���B
Web�]�_���u�R�[���v32���i2017.08.15�j
���F�ƃN�I���A����42�́@�a�̎O�Ԃ̐��A�G�^�����S�E�C�}�[�W���E�f��i�����I���j
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU�@2017 All Rights Reserved.
|
| �\���i�ڎ��j�� |