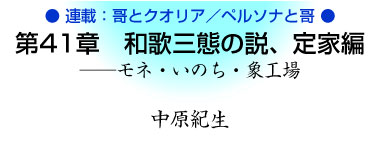|
|
|
Web昡榑帍乽僐乕儔乿 |
|
仭憂姧偺帿 仭杮帍偺昞巻乮栚師乯傊 仭杮帍偺僶僢僋僫儞僶乕 仭撉幰偺暸乛偛堄尒丒姶憐 仭搳峞婯掕 仭娭學幰偺Web僒僀僩 仭僾儔僀僶僔乕億儕僔乕 |
|
亙杮帍偺娭楢儁乕僕亜 |
|
仭乽僇儖僠儍乕丒儗償儏乕乿偺僶僢僋僫儞僶乕 仭昡榑巻乽俴倎 Vue乿偺憤栚師 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
|
仭儌僱傪挻偊傞帋傒丄尵梩偺偐偨偪傪偲傞憐擮丄儗儈僯僢僒儞僗
丂
丂慜復偺枛旜丄昅偑憱偭偰巚傢偢彂偒偮偗偨乽惗偒傞娊傃乿偺岅偵怗敪偝傟偰丄掕壠偺壧偺悽奅偵偍偗傞乽娊傃乿偵娭楢偡傞榖戣傪擇偮偲傝偁偘丄掕壠傪傔偖傞梊旛揑峫嶡傪偟傔偔偔傝偨偄偲巚偄傑偡丅堦偮偼丄僾儖乕僗僩偺柍堄巙揑憐婲偲掕壠偺杮壧庢傝偵嫟捠偡傞丄擣幆偲尵岅偵偐偐傢傞乽摿暿側娊傃乿傗乽椡嫮偄娊傃乿偵偮偄偰丅擇偮栚偺榖戣偼丄悽垻栱傪揟宆偲偡傞擔杮偺拞悽旤榑偵偍偗傞乽姶乿丄偡側傢偪乽偐偨偪乿傪捠偠偰乽傕偺乿偺乽偄偺偪乿偵傆傟偨帪偵摼傜傟傞乽怺墦側娊婌乿傪傔偖偭偰丅
丂
丂戞堦偺榖戣丅朏愳懽媣挊亀撲偲偒亀幐傢傟偨帪傪媮傔偰亁亁偵彂偐傟偰偄偨偙偲丅
丂
侾丏婦幵偺憢偵揥奐偝傟傞岝宨劅塀歡揑側嶖帇丄偵偠傒偲戺傝
丂
丂亀壴嶇偔壋彈偨偪偺偐偘偵嘦亁偵丄僶儖儀僢僋傊岦偐偆楍幵偺憢偵僶儔怓偺挬偺岝宨偲栭偺懞偺岝宨偑嫟懚偟丄柧偗曽偺岝偺曄壔偵墳偠偰崗乆偲偦偺巔傪曄偊偰備偔偝傑傪昤偄偨偔偩傝偑偁傞丅朏愳巵偼丄偙偺応柺傪乽傑傞偱丄帪娫偵傛偭偰曄壔偡傞岝偺巔傪偲傜偊偨報徾攈偺奊偺傛偆偱偼側偄偐乿乮80暸乯偲姶偠丄帪崗偺堘偄偵傛傞岝偺検偲幙偺昤偒暘偗傪暿乆偺奊偲偄偆暯柺偱帋傒偨儌僱偺楢嶌乽儖乕傾儞戝惞摪乿傪楢憐偡傞乮84暸乯丅乵仏乶
丂偦偟偰丄偦傟偑揑奜傟偱側偄偙偲偺崻嫆偲偟偰丄儔僗僉儞挊亀傾儈傾儞偺惞彂亁偺暓栿偵晅偟偨彉暥偱東栿幰丒僾儖乕僗僩帺恎偑丄乽偦偆偟偨帪崗乵岝偺曄壔偵傛偭偰惞摪偺尒偊曽偵偪偑偄偑惗偠傞挬丄屵屻丄梉崗劅劅堷梡幰拹乶傪僋儘乕僪丒儌僱偼寙弌偟偨夋晍偵掕拝偟偰偄傞偑丄偦偺夋晍偵偼丄恖娫偨偪偑嶌偭偨偁偺暔懱丄偦傟偱傕帺慠偑帺傜偺偆偪偵搳偘崬傫偩僇僥僪儔儖偲偄偆暔懱偺惗柦偑尒偄偩偝傟傞乿偲偟偨偨傔偰偄傞偙偲乮85-86暸乯傪帵偟偨偆偊偱丄朏愳巵偼丄乽巹乿偑嵍塃偺幵憢偐傜偺岝宨偵堷偒楐偐傟偨傑傑偱偼偄偢丄乽娫寚揑偱懳棫偡傞抐曅傪偮側偓崌傢偣丄怴偟偄夋晍偵懼偊傛偆偲偟丄偦偆偟偰傂偲偮偺慡懱偺挱傔偲堦枃偺楢懕偟偨奊乵僞僽儘乕乶傪庤偵擖傟傛偆偲偮偲傔偨乿偲彂偐傟偰偄傞偙偲偵拲栚偟乮87暸乯丄偦偺傛偆側乽帪娫偺挍偡暯柺乿乮88暸乯傪傔偞偟偨偲偙傠偵丄儌僱偺帋傒傪挻偊傞帇揰偑夎惗偊偰偄傞偲巜揈偡傞乮92暸乯丅
丂僾儖乕僗僩偵偲偭偰偺塀歡偼丄乽堎側傞傕偺偳偆偟傪摍壙惈偵傛偭偰寢傇偙偲乿偱偁偭偰丄幵憢偐傜尒偨擇偮偺堎側傞岝宨偺偁偄偩傪墲娨偡傞乽巹乿偺摦偒偙偦丄堎側傞傕偺傪偮側偓偲傔傞塀歡偺攠夘揑側摥偒偦偺傕偺偲尵偊傞乮101暸乯丅偦偟偰丄偦偺傛偆側乽塀歡揑側嶖帇乿偲偄偆曽朄偑丄乽偄傑尒偰偄傞傕偺偺偆偪偵丄夁嫀偲偄偆堎側傞帪娫偵尒偨傕偺傪廳偹偰憐婲偡傞偨傔偺曽朄乿偲傕側傝摼傞乮101-102暸乯丅朏愳巵偼偦偺傛偆偵巜揈偟丄乽儅儖僞儞償傿儖偺忇極懱尡乿傊偲昅傪恑傔傞丅
丂
俀丏儅儖僞儞償傿儖偺忇極懱尡劅尵梩偺敪惗丄僄僋僗僞僔僗
丂
丂偦傟偼丄僎儖儅儞僩偺曽傊偺嶶曕偺搑拞丄抦傝崌偄偺堛巘偺攏幵偵廍傢傟帺戭偵憲偭偰傕傜偭偨偲偒偺弌棃帠偱丄摦偔攏幵偺憢偐傜尒傞儅儖僞儞償傿儖偺擇偮偺忇極偲丄偦傟傛傝傕偭偲墦偔偺崅尨偵棫偭偰偄傞償傿儐償傿僢僋偺忇極偲偑傑傞偱偡偖嬤偔偵偁傞傛偆偵暲傫偱尒偊偨偲偒丄乽偲偮偤傫丄巹偼傎偐偺偳傫側娊傃偲傕帡偰傕帡偮偐側偄偁偺摿暿側娊傃傪姶偠偨乿乮120暸乯偲偄偆傕偺丅
乽傗偑偰丄忇極偺昤偔慄偲梉擔傪梺傃偨偦偺昞柺偑丄傑傞偱堦庬偺昞旂偱傕偁傞傒偨偄偵楐偗丄偦偺側偐偵塀傟偰偄偨傕偺偑傎傫偺彮偟偩偗巔傪尰偟丄帺暘偵偲偭偰堦弖慜偵偼懚嵼偟側偐偭偨傂偲偮偺憐擮傪巹偼書偒丄偦傟偼摢偺側偐偱尵梩偺偐偨偪傪偲偭偨丅偦偟偰丄偄傑偟偑偨忇極傪尒偰姶偠偨夣妝偑傂偳偔憹戝偟偨偨傔丄堦庬偺湌崨偵偲傜偊傜傟丄巹偵偼傕偆傎偐偺偙偲偼峫偊傜傟側偔側偭偨丅乿乮亀僗儚儞壠偺曽傊嘥亁乯
丂偙偙偱乽巹乿偑岅偭偰偄傞丄梉擔傪梺傃偨忇極偺昞柺偺壓偵塀傟偰偄偨乽壗偐乿傪傔偖偭偰丄朏愳巵偼師偺傛偆偵弎傋傞丅
丂傕偆堦偮丄朏愳巵偑偙偙偱拲栚偡傞偺偑丄乽巹乿傪偲傜偊傞乽湌崨乿乮乽僄僋僗僞僔僗乿亖乽帺暘偺奜偵棫偮偙偲丄朰変丄扙帺乿乯偲偄偆岅偩丅
丂偙偆偟偰丄塀歡揑側嶖帇偲柍堄巙揑憐婲偲偑偮側偑偭偨丅
丂
俁丏僾僠僢僩丒儅僪儗乕僰偲晄懙偄側晘愇劅儗儈僯僢僒儞僗丄堎側傞帪娫偺嫟嵼
丂
丂偁傞搤偺擔偺挬丄曣偵姪傔傜傟偨峠拑偵傂偲愗傟偺儅僪儗乕僰壻巕傪怹偟偰怘傋偨偲偨傫乽偆偭偲傝偲偡傞傛偆側娊傃乿乮176暸乯偑傂傠偑傝丄偐偮偰擔梛偺挬偛偲儗僆僯廸曣偑峠拑偐曥採庽偺偍拑偵怹偟偰儅僪儗乕僰傪弌偟偰偔傟偨丄僐儞僽儗乕偺擔乆偺婰壇偑偁傝偁傝偲巔傪偁傜傢偡乽僾僠僢僩丒儅僪儗乕僰乿懱尡丅屵屻偺廤偄乮儅僠僱乕乯偵弌偐偗偨僎儖儅儞僩戝岞揁偺拞掚偺擇偮偺晄懙偄側晘愇偵偮傑偢偄偨弖娫偵乽帄暉姶乿乮199暸乯偑廝偄丄偐偮偰懱尡偟偨償僃僱僣傿傾偺僒儞丒儅儖僐帥堾偺愻楃摪偵偁傞擇偮偺晄懙偄側僞僀儖傪姭婲偡傞乽晄懙偄側晘愇乿懱尡丅乮偪偔傑暥屔亀幐傢傟偨帪傪媮傔偰侾侽亁315-316暸嶲徠乯
丂偙偺柍堄巙揑憐婲偺憓榖偺偆偪晘愇偺曽偑儅僪儗乕僰偺僄僺僜乕僪傛傝傕乽屆偄乿偙偲傪丄乽僇儖僱乿偲屇偽傟傞憂嶌庤挓偺婰弎偵傕偲偯偒柧傜偐偵偟偨愭峴尋媶乮204-206暸乯傪摜傑偊偰丄朏愳巵偼丄僾儖乕僗僩偑柍堄巙揑憐婲偺攠夘偲偟偰愇偲偄偆暔幙傪慖傫偩棟桼傪丄偦偺丄帪娫偺宱夁偲偲傕偵戝惃偺恖偺懌棤偵摜傒偟傔傜傟杸柵偟偨乽偡傝尭偭偨愇偺暯柺乿乮260暸乯偺偆偪偵尒偄偩偟偰偄傞丅偦傟偼傑偨丄乽楍幵偺幵憢偐傜尒偨帪娫偺堎側傞傛偆偵尒偊傞擇偮偺岝宨偐傜乽堦枃偺楢懕偟偨奊乿傪偮偔傞偵偼偳偆偟偨傜傛偄偺偐乿偲偄偆栤偄傊偺摎偊偱傕偁偭偨丅
丂朏愳巵偼丄曣偲偲傕偵僒儞丒儅儖僐愻楃摪偵擖偭偨乽巹乿偑丄僉儕僗僩偺庴愻恾傪尒側偑傜戝棟愇偺儌僓僀僋偺彴傪摜傒偟傔偰偄偨偲偒丄擇偮偺姶妎偑摨帪偵摥偄偰偄傞偙偲偵拲栚偡傞丅乽晘愇偺杸柵偵傛傞帪娫偺宱夁偵懌棤偱怗傟側偑傜丄帇慄傪夘偟偰丄帪娫偺宱夁偟偨奊傪尒偰偄傞乧丅偙偺嫟捠姶妎偵傛偭偰丄愇偺杸柵偵帪傪姶偠偨偱偁傠偆怗妎偑奊傪尒傞帇妎偵傑偱揱攄偟偨偐偺傛偆側儁乕僕偑丄亀尒偄偩偝傟偨帪亁偵偼偁傞丅乿乮亀撲偲偒亀幐傢傟偨帪傪媮傔偰亁亁261-262暸乯
丂朏愳巵偑偙偙偱堷梡偡傞偺偼丄師偺傛偆側暥復偩丅乽恄旈傪垽偡傞恖傃偲偼丄帠暔偑丄偦傟傪挱傔偨恖偨偪偺帇慄偺壗偐傪曐懚偟偰偄傞偲巚偄偨偑傝丄婰擮寶憿暔傗奊夋偼丄悢悽婭偵傢偨傞懡偔偺巀旤幰偺垽偲擬帇偑怐傝偁偘偨姶妎偺償僃乕儖偵傑偝偵暍傢傟偰丄偙偪傜偵巔傪尒偣傞偺偩偲怣偠偨偑傞丅乿乮亀尒偄偩偝傟偨帪亁乯
丂杮彂偺嵟屻偱丄朏愳巵偼丄僾儖乕僗僩偺偙偺杸柵偟偨愇偺昞柺乮堦枃偺僞僽儘乕乯傪丄儀儖僋僜儞偑亀暔幙偲婰壇亁偵婰偟偨乽暔幙偺夁嫀偼傑偝偵偦偺尰嵼偺側偐偱梌偊傜傟偰偄傞偺偩乿丄乽夁嫀偼暔幙偵傛偭偰墘偠傜傟丄惛恄偵傛偭偰僀儅乕僕儏壔偝傟偹偽側傜側偄乿偲偄偭偨尵梩偲堷偒崌傢偣傞丅
乵仏乶嶳揷揘暯巵偺乽擔杮丄偦偺傕偆堦偮偺劅劅娧擵偺徾挜揑僆儕僄儞僥僀僔儑儞乿乮亀岅傝偺億儕僥傿僋僗亁強廂乯偵丄儌僱偲娧擵偺娭學偵偮偄偰愢偒媦傫偩暥復偑偁傞偙偲偼丄戞16復偱偲傝偁偘偨丅偙偺嶳揷巵偺媍榑偵怗敪偝傟偰丄偨偲偊偽丄儌僱亖娧擵丄僙僓儞僰亖弐惉丄僺僇僜亖掕壠丄偲偄偭偨懳斾丄偁傞偄偼僼儔儞僗塮夋巚憐偺宯晥偱偄偊偽丄僶僓儞亖娧擵丄僽儗僢僜儞亖弐惉丄僪僁儖乕僘亖掕壠丄偲偄偭偨懳斾偑峫偊傜傟側偄偐丄側偳偲柌憐傪偨偔傑偟偔偟偰偄傞丅
丂偦傟偼偦傟偲偟偰丄尨揷儅僴挊亀僕償僃儖僯乕偺怘戩亁偵偱偰偒偨儌僱偺弎夰偑報徾怺偄傕偺偩偭偨偺偱丄偙偺応傪棙梡偟偰丄彂偒偆偮偟偰偍偔丅乽帪娫偵傛偭偰晽宨偼曄傢傞傫偩丅偄傑尒偰偄傞偙偺宨怓偩偗偑偡傋偰偠傖側偄傫偩丅偁偁丄側傫偱偦傫側扨弮側偙偲偵婥偯偐側偐偭偨傫偩傠偆丅側傫偱偦傫側摉偨傝慜偺偙偲偑乧乧偙傫側偵丄偙傫側偵偆傟偟偄傫偩傠偆乿
丂偄傑傂偲偮丄僈僗僩儞丒僶僔儏儔乕儖亀柌傒傞尃棙亁偵廂傔傜傟偨乽悋楡偁傞偄偼壞偺栭柧偗偺嬃堎乿偐傜丅乽悽奅偼尒傜傟傞偙偲傪朷傫偱偄傞丅尒傞偨傔偺娽偑懚嵼偡傞埲慜偵偼丄悈偺娽丄怷娬偲偟偨悈偺嫄偒側娽偑丄壴乆偺奐偔偺傪傒偮傔偰偄偨丅偦偟偰丄悽奅偑帺暘偺旤傪嵟弶偵堄幆偟偨偺偼劅劅扤偑堎榑傪偼偝傒偊傛偆偐劅劅偙偺悈偵塮偭偨塭偵偍偄偰側偺偩丅摨偠傛偆偵丄僋儘乕僪丒儌僱偑悋楡傪挱傔偰埲棃丄僀乕儖丒僪丒僼儔儞僗偺悋楡偼慜傛傝傕旤偟偔丄戝偒偔側偭偨丅乿乮廰戲岶曘栿丄偪偔傑妛寍暥屔18-19暸乯
丂
仭柍堄巙揑憐婲偲杮壧庢傝乮偦偺堦乯
丂
丂杮峞偱丄巹偼丄柍堄巙揑憐婲偲杮壧庢傝傪摨偠搚昒乮暯柺乯偺偆偊偵暲傋偰榑偠傛偆偲偟偰偄傑偡丅偟偐偟丄杮壧庢傝偲偼榓壧偵偍偗傞偄傢偽乽堄巙揑乿側僥僋僯僢僋偱偁偭偰丄偙偺揰偱丄乽柍堄巙揑乿憐婲偺儊僇僯僗儉偲偼寛掕揑偵堎側傞傕偺偱偡丅堎側傞傕偺傪嫟嵼偝偣傞椡偺応偑乽懱乿偱偁傞丅偁傞偄偼丄堎側傞帠徾傪摨堦偺奣擮偱妵傞偺偑乽嫊懱乿偲偟偰偺尵岅偺偼偨傜偒偱偁傞丅偲丄偦偆尵偭偰偼傒偰傕丄偱偼偦偺乽椡乿傗乽偼偨傜偒乿偺幚懺偼側偵偐傪岅傜側偗傟偽丄偦傟偼偨偩偺欔偒偱偟偐側偄偱偟傚偆丅
丂偙偙偱丄乽嶌幰偺怱乿乮惗恎偺壧恖亖塺壧庡懱偺幚姶傗庯岦乯偲乽壧偺怱乿乮壧偵塺傑傟偨怱亖堄枴乯偲乽塺傒偮偮偁傞怱乿乮塺壧帪偵偍偄偰偺傒惗偠偰偄傞嫊峔偺丄偟偐偟摦揑側惗柦傪傕偭偨怱乯偺嬫暿傪傕偪偩偟偰丄杮壧庢傝偲偄偆乽堄巙揑乿僥僋僯僢僋傪島偠傞偺偼乽嶌幰偺怱乿偩偑丄幚偼丄偦偺塺壧僾儘僙僗偵偍偄偰惗婲偡傞乽塺傒偮偮偁傞怱乿偺偆偪偵偙偦乽柍堄巙揑乿憐婲偑惗偠傞偺偱偁傞丄側偳偲尵偆偙偲偱丄偙偺柕弬傪夝徚偡傞偙偲偑偱偒傞偺偱偼側偄偐丅巹偼偦偆峫偊偰偄傑偡丅
丂塺傑傟偮偮偁傞嶌昳偲偲傕偵棫偪尰傢傟傞乽塺傒偮偮偁傞怱乿偑丄偦偺杮棃偺廧張偲偡傞応強偼丄壧偺摴偺怺偒揱摑偵崻偞偟偨帉偺悽奅丄偡側傢偪椵乆偨傞榓壧乮壧偺怱乯偺廤憼屔乮乽榓壧偦偺傕偺乿偁傞偄偼乽壧偺怱偦偺傕偺乿偺奅堟偲偄偭偰傕偄偄乯偱偼側偄偐偲巚偄傑偡丅偙偺償傽乕僠儏傾儖側師尦偐傜乽偄傑丄偙偙乿偺傾僋僠儏傾儖側師尦偵傓偗偰惗婲偟偨乽塺傒偮偮偁傞怱乿偵偲偭偰丄屆壧乮杮壧乯偼堦庬偺庤懕偒婰壇偺傛偆側傕偺偱丄堄幆偟偰巚偄弌偦偆乮尵岅壔偟傛偆乯偲偡傞偲丄偦偺偐偨偪偑夡傟偰偟傑偆偱偟傚偆丅嬶懱偺壧恖丄偨偲偊偽掕壠偺塺壧峴堊偵傛偭偰暔幙揑尰徾偲偟偰丄偮傑傝惡偲暥帤偵偐偨偳傜傟偨嶌昳乮乽屄乆偺榓壧乿偁傞偄偼乽屄乆偺壧偺怱乿乯偲偟偰尰徾奅偵弌尰偟偨偲偒丄偦偙偵丄榓壧偺儗僩儕僢僋偲偟偰偺杮壧庢傝乮塺壧庡懱亖嶌幰偺怱偵偲偭偰乯偑丄摨帪偵柍堄巙揑憐婲偲偟偰偺岻傑偞傞杮壧庢傝乮塺傒偮偮偁傞怱偵偲偭偰乯偵側偭偰偄傞丄偲偄偭偨乽柍堄巙揑憐婲偺堄巙揑憂弌偲偟偰偺杮壧庢傝乿偲偱傕昞尰偡傋偒帠懺偑惉傝棫偭偰偄傞偺偱偼側偄偐偲偄偆偙偲偱偡丅
丂
乮娧擵尰徾妛偺悽奅偵偍偄偰乽娧擵偑帺慠傪塺傫偩傕偺偱傕傛偟丄帺慠偑娧擵傪捠偟偰帺屓傪塺傫偩傕偺偱傕傛偄乿偲偄偊傞帠懺偑側傝偨偭偰偄傞偲偡傟偽丄掕壠榑棟妛偺悽奅偱偼丄杮壧庢傝偺媄朄傪嬱巊偟偰掕壠偑榓壧傪塺傓偙偲偲丄偦傟偲偼媡偵尵岅偺曽偑丄掕壠偺偆偪偵廻偭偰偄傞傕偆堦偮偺乽嶌幰偺怱乿偱偁傞乽塺傒偮偮偁傞怱乿乮僀儅僕僫儖側乽嶌幰偺怱乿偲尵偭偰偄偄偐傕偟傟側偄乯傪婲摦偝偣丄柍堄巙揑憐婲偺儊僇僯僗儉傪夘偟偰屆壧乮杮壧乯傪尠尰偝偣傞偙偲偲偑摨媊偱偁傞傛偆側帠懺偑側傝偨偭偰偄傞丅偮傑傝乽掕壠偑尵岅乮屄乆偺榓壧嶌昳乯傪塺傫偩傕偺偱傕傛偟丄尵岅乮榓壧嶌昳偺廤憼懱乯偑掕壠傪捠偟偰帺屓傪乮屄暿偺榓壧嶌昳偲偟偰乯塺傫偩傕偺偱傕傛偄乿偲偊傞帠懺丅
丂偪側傒偵丄乽塺傒偮偮偁傞怱乿偺奣擮偺採彞幰偱偁傞擈儢嶈昷巵偑偄偆傛偆偵丄掕壠偺乽桳怱乿偲偼偙偺乽塺傒偮偮偁傞怱乿偵傎偐側傜側偄丅偦偟偰丄巹偼乽桳怱乿亖乽塺傒偮偮偁傞怱乿偺媶嬌偺巔傪擻偺乽僔僥乿偺偆偪偵尒傞偙偲偑偱偒傞偺偱偼側偄偐偲峫偊偰偄傞丅偡側傢偪丄杮壧庢傝偺媷嬌揑尰徾宍懺偲偟偰偺擻丅乯
丂
丂偦傟偱偼丄偦傕偦傕乽杮壧庢傝乿偲偼偳偺傛偆側塩傒側偺偐丅
丂搉晹懽柧巵偼亀榓壧偲偼壗偐亁偺側偐偱丄杮壧庢傝偵懳偟偰丄乽偁傞摿掕偺屆壧偺昞尰傪傆傑偊偨偙偲傪撉幰偵柧帵偟丄側偍偐偮怴偟偝偑姶偠庢傜傟傞傛偆偵壧傪塺傓偙偲乿乮102暸乯偲偄偆掕媊傪梌偊偰偄傑偡丅偙偙偵偼丄屆壧乮杮壧乯偺柧帵偡側傢偪乽屆壧傪偁偊偰尠嵼壔偝偣傞乿乮107乯偙偲偲丄屆壧乮杮壧乯偲怴偟偝偺嫟懚偲偄偆丄杮壧庢傝傪側傝偨偨偣傞擇偮偺廳梫側梫審偑娷傑傟偰偄傑偡丅慜幰偼杮壧庢傝傪偨傫側傞搻嶌偐傜嬫暿偡傞偲摨帪偵丄乽杮壧偲怴嶌壧偺憡屳娭學傪堢偰偰偄偔乿乮107暸乯偲偄偆嶌嬈傊偺撉幰偺嶲壛傪壜擻偵偟傑偡丅屻幰偵偮偄偰搉晹巵偼丄杮壧庢傝偟偨壧偺怴偟偝偼丄乽杮壧偑怴嶌壧偵昁慠惈傗崻嫆傪梌偊偰偄傞丄偲偄偆帠幚乿乮103暸乯備偊偵惉傝棫偭偰偄傞偲巜揈偟偰偄傑偡丅偦偟偰丄杮壧帺懱傕丄桪傟偨怴嶌壧偵傛偭偰怴偟偄枺椡傪尒偣巒傔傞偙偲偑偁傞偲乮125暸乯丅
丂杮壧庢傝傪傔偖傞搉晹巵偺媍榑偱嫽枴怺偄偺偼丄師偺擇揰偱偡丅
丂偦偺堦偼丄杮壧庢傝偼乽旤妛揑乿偱偁傞傛傝乽峴堊揑乿側傕偺偱偁傞偲偄偆巜揈丅杮壧庢傝偼丄壧恖偨偪偺廤傑傞摿掕偺応偵嫽庯傪傕偨傜偡偲偄偆丄媀楃揑嬻娫偵偍偗傞乽尰応揑側姶妎乿傪婎杮偵偟偰偄傞偲偄偆偙偲偱偡丅偦傟偼丄乽杮壧庢傝偺壧偼丄杮壧傪埫彞偟楴鎢偡傞惡傪廳偹偰嬁偐偣傞傛偆丄梫媮偟偰偄傞丅乿乮108暸乯偲巜揈偝傟偰偄傞偙偲偲棤暊側娭學偵偁傝傑偡丅
丂擇揰栚偵偮偄偰偼丄搉晹巵偺暥復傪娵偛偲堷偒傑偡丅
丂巹偼丄愭偺堷梡暥拞偺乽杮壧偑偁傞偐傜偙偦怴嶌壧偑懚嵼偡傞乿偲偄偆搉晹巵偺巜揈傪丄帤媊捠傝偵庴偗偲傞傋偒偩偲峫偊偰偄傑偡丅偦偟偰偦偺偙偲偺堄枴偼丄偦偙偱偄傢傟傞乽屆壧丄杮壧乿傪乽廤抍偺昞尰丄椶宆昞尰乿偲丄乽怴嶌壧丄杮壧庢傝嶌昳乿傪乽屄恖偺丄屄恖偵傛傞昞尰乿偲撉傒姺偊傞偙偲偱柧妋偵側傞偲峫偊偰偄傑偡丅偙傟傜偺偙偲偵偮偄偰偼丄杮壧庢傝偲柍堄巙揑憐婲偲偺娭學偵偮偒丄偄傑彮偟棫偪擖偭偰峫嶡偟偨偁偲偱丄偁傜偨傔偰怗傟傞偙偲偵偟傑偡丅
丂
丂偙偙偱丄掕壠塺偐傜擇偮丄杮壧庢傝偺幚椺傪尒偰偍偒偨偄偲巚偄傑偡丅
丂嵟弶偺壧偼丄偐偺乽嬵偲傔偰懗偆偪偼傜傆偐偘傕側偟嵅栰偺傢偨傝偺愥偺梉偖傟乿偱丄娵扟嵥堦偼丄乽堦懱偙偺婻乵偺乶傝庤偼愥偺梉傋側偺偵壗偺偨傔椃偟偰傤傞偺偐乿乮453暸乯偲栤偄傪偨偰丄偦傟偼乽扤偐偺偲偙傠傊埀傂偵峴偮偨偺偩乿丄乽偦偺憡庤偼偍偦傜偔彈偩偮偨偺偱偼側偄偐乿乮454暸乯偲悇棟偟偰偄傑偡丅偦偟偰丄偦偺鏆嫆偺傂偲偮偲偟偰嵎偟弌偟偰偄傞偺偑丄掕壠偵偲偭偰乽嬵偲傔偰乿偺杮壧偼丄枩梩廤偺壧偲偄偆傛傝傓偟傠尮巵暔岅偺堷壧偱偁偭偨偙偲丄嬶懱揑偵偼丄戞屲廫挓乽搶壆乿偱丄晜廙偲宊傞捈慜偵孫偑乽偝偺偺傢偨傝偵壠傕偁傜側偔偵乿偲岥鎢傫偱偄傞乽帠幚乿偱偡丅乵仏乶
丂孫偑偮傇傗偔屆壧偑乽柉梬乿傔偄偰偄傞偲偄偆巜揈偼丄杮壧庢傝偺媄朄偑曇傒弌偝傟偨楌巎揑攚宨偵丄怴屆崱廤偺帪戙丄廤抍偐傜屄恖傊丄椶宆偐傜屄惈傊偲榓壧昞尰偵偍偗傞屄恖惈偑昞柺壔偟偰偒偨偙偲偑偁傞偲偄偆搉晹巵偺巜揈偲嬁偒偁偭偰偄傑偡丅偦偟偰丄杮壧偑岥鎢傑傟傞偺偑嫊峔悽奅偺側偐偺嫊峔偺儁儖僜僫偵偍偄偰偱偁偭偨偙偲偼丄掕壠偵偍偗傞杮壧庢傝偺堄枴崌偄偵擹偄堿塭傪偁偨偊偰偄傑偡丅
丂
乵仏乶娵扟嵥堦偑嫇偘傞傕偆堦偮偺榑嫆偼丄怴屆崱廤偵偍偗傞乽嬵偲傔偰乿偺壧偺攝楍偱偁傞丅堦庱堦庱傪屒棫偟偨宍偱娪徿偡傞偺偱偼側偔丄乽捄愶廤偲偄傆傾儞僜儘僕乕傪堦偮偯偒偺奊姫暔偲偟偰庴庢傞懺搙乿偱丄慜屻偵攝抲偝傟偨壧偲偺娭學惈傪偮傇偝偵尒偰偄偔偲丄乮偙偺偁偨傝偺庤暲傒偼丄暥妛揑柤恖錣偲偄偆傋偒傕偺偱丄偁傜偡偠傪弎傋傞偩偗偱偼偦偺枴傢偄傕怺傒傕徚偊偰偟傑偆偲巚偆偺偱丄嬶懱揑側榑徹偺夁掱偼徣偔乯丄乽偨偩愥偵偗傇傞偩偗偵偡偓側偄嵅栰偺傢偨傝偑偙傫側偵傕墣楉側偺偼丄幚偼攏忋偵偁偮偰擸傓抝偛偙傠丄偡偔側偔偲傕楒偵嬌傔偰嬤偄巚傂偺偣偄側偺偱偁傞乿偲偄偆寢榑偵払偡傞乮456暸乯丅
丂偙偙偱丄偙偺応傪庁傝偰丄乽杮壧庢傝乿傪傔偖傞戝壀怣挊亀偆偨偘偲屒怱丂戝榓壧曆亁偺媍榑傪堷偔丅壛栁恄幮偵寃偱偨嵺丄崱條乽弔偺弶傔偺攡偺壴丄婌傃奐偗偰幚側傞偲偐丄偍慜偺抮側傞敄昘丄怱夝偗偨傞扅崱偐側乿偺戞嶰嬪傪丄娽慜偺偣偣傜偓偺柤傪屇傃偙傒梬偄曄偊偨偙偲傪屻敀壨堾偑乽愜偵崌傂偰傔偱偨偐傝偒乿偲偨偨偊偨丄偲偁傞乽椑恛旈彺岥揱廤乿姫廫偺婰弎傪徯夘偟偨偆偊偱丄戝壀巵偼師偺傛偆偵榑偠偰偄傞丅
仭柍堄巙揑憐婲偲杮壧庢傝乮偦偺擇乯
丂
丂擈儢嶈昷巵偼丄亀壴捁偺巊亁偱丄乽乮彮側偔偲傕亀嬤戙廏壧亁傗亀塺壧戝奣亁傪挊偟偨帪婜偺乯掕壠偵偲偭偰丄乹偁傞傋偒壧乺偺揟宆偼丄乽杮壧庢傝乿偵尒弌偝傟偰偄偨偲峫偊傜傟傞偩傠偆乿偲彂偒丄偦偺幚椺偲偟偰丄乽偝傓偟傠偵堖偐偨偟偒崱彧傕傗変傪傑偮傜傫塅帯偺嫶昉乿傪杮壧偲偡傞掕壠塺乽偝傓偟傠傗懸偮栭偺廐偺晽傆偗偰寧傪偐偨偟偔塅帯偺嫶昉乿傪偲傝偁偘丄師偺傛偆偵榑偠偰偄傑偡乮134暸乯丅
丂偄傢偔丄堦尒偟偰丄岅偺摑帿娭學偑夝懱偝傟偰偄傞丅乽晽丒傆偗偰乿傗乽寧傪丒偐偨偟偔乿偺岅偺寢崌偼堄枴傪惉偝側偄丅岅偺堦偮堦偮偑棁偱曻傝弌偝傟丄偦偺岅偑娷堄乮埫帵乯偟偆傞僀儊乕僕傗堄枴偑暥柆偵傛傞尷掕傪柶傟偰晜梀偟偰偄傞丅乽偝傓偟傠乿亖姦偄丒嫹猊丄乽晽傆偗偰乿亖栭峏偗偰丒晽悂偒偰偺傛偆偵丄堦偮偺岅偑摨帪偵懡偔偺堄媊傗柺塭傪懷傃偰偄傞丅偟偐傕丄偦偺岅渂偺抐曅偼廫暘偵杮壧傪帵嵈偟丄偦偺晽忣傪憐婲偝偣傞丅暥偺昞柺忋偺旕峔惉偵傕峉傜偢丄杮壧傪抦傞嫕庴幰偺堄幆偺拞偱偼丄堄枴摑崌偼姰慡偵嵞尰偝傟偰偄傞丅偦偟偰姭婲偝傟偨杮壧偺晽忣偑丄暥柆偲偟偰怴壧偺奺岅偺婡擻傪尷掕偟偰備偔丅
丂岅偺摑帿娭學偑夝懱偝傟丄堄枴偲僀儊乕僕偺懡媊惈偺拞傪昚偆嶌昳乮杮壧庢傝壧乯偵丄幚偼乽惛枾側僀儊乕僕乿偑廻偭偰偄傞偙偲傪丄榓壧偺尵岅揑揱摑傗椶宆揑庯岦偵柧傞偄撉傒庤偵姶摼偝偣傞乽暥柆乿乮傕偟偔偼嶌幰偲嫕庴幰偺乽嫟桳嵿嶻乿乯偲偟偰偺杮壧丅偙偙偵偼丄撉幰嶲壛偵傛偭偰乽杮壧偲怴嶌壧偺憡屳娭學傪堢偰偰偄偔乿偙偲偑杮壧庢傝偺梫掹偱偁傝丄偦偺嵺丄怴嶌壧偼杮壧偵傛偭偰偦偺昁慠惈傗崻嫆傪梌偊傜傟傞偺偩偲偄偆搉晹巵偺掕媊偵捠偠傞峫偊曽偑偁傝傑偡丅杮壧偑偁傞偐傜偙偦乮杮壧偑撉幰偺堄幆偺偆偪偵尠嵼壔偟偰偄傞偐傜偙偦乯怴嶌壧偺怴偟偝偑丄偦偟偰偦傕偦傕怴嶌壧偑堦屄偺尵岅揑昞尰暔偲偟偰懚嵼偡傞崻嫆偑偁傞丄偲偄偆傢偗偱偡丅
丂偟偐偟丄擈儢嶈巵偺媍榑偵偼丄搉晹巵偺掕媊偵崌抳偟側偄偲偙傠偑偁傝傑偡丅側偵傛傝傕丄乽偝傓偟傠傗乿偺掕壠塺偼丄杮壧傪柧帵偟尠嵼壔偝偣偼偟偰傕丄杮壧偵宧堄傪暐偄丄偦偺怴偨側枺椡傪敪尒偟丄乽偄傑丄偙偙乿偵嵞惗偝偣偰偄傞丄側偳偲偼摓掙尵偊傑偣傫丅傓偟傠丄杮壧傪攋夡偟丄偦偺怱偲帉傪庤慜彑庤偵嵞惗棙梡偟偰偄傞傛偆偵偝偊姶偠傜傟傑偡丅偩偐傜丄偙偙偵偼丄乽杮壧庢傝偺壧偼丄杮壧傪埫彞偟楴鎢偡傞惡傪廳偹偰嬁偐偣傞傛偆丄梫媮偟偰偄傞丅乿偲偄偭偨娭學惈偼側傝偨偭偰偄傑偣傫丅
丂掕壠偺杮壧庢傝壧偼丄傕偼傗埫彞丒楴鎢偺懳徾偱偼側偄丅偲偄偆傛傝丄乽掕壠偵偲偭偰丄乹偁傞傋偒壧乺偺揟宆偼丄乽杮壧庢傝乿偵尒弌偝傟偰偄偨乿偲偄偆偺偱偡偐傜丄偦傕偦傕掕壠偺壧偼丄峀嫹偄偢傟偺堄枴偵偍偄偰傕丄杮棃乽杮壧庢傝壧乿側偺偱偁傝丄偟偨偑偭偰丄偡傋偰偺掕壠塺偼偍傛偦埫彞丒楴鎢偺懳徾偵偼側傝偊側偄丄偲偄偆偙偲偵側傞偱偟傚偆丅擈儢嶈巵偼丄杮壧庢傝偺幚椺偺専摙傪傆傑偊偰丄掕壠偵偍偗傞榓壧偺偁傝曽傪丄師偺傛偆偵憤妵偟偰偄傑偡丅
丂偦傟偱偼丄弐惉壧榑傪宲偄偩偼偢偺掕壠偵丄堦懱壗偑婲偙偭偨偺偐丅擈儢嶈巵偺媍榑偼丄偙偙偐傜丄乽乹宆乺偲偟偰攃偊傞偙偲偼偱偒側偄偑乹壗偲側偔乺偁傞傛偆側乽怱乿乿乮142暸乯傪塺傓乽桯尯懱乿傊丄偦偟偰丄乽傕偼傗桳尷側乽晽忣乿偺宆偱偼側偔丄偝傑偞傑偺宆偲帉偲偑塓姫偔丄尵岅壔埲慜偺怱揑忬懺乿乮148暸乯傊丄偡側傢偪乽偨偩塺嶌帪偵丄偄傢偽嫊憸偲偟偰惗偠傞乽嶌幰乿乮帊揑庡娤乯乿偺乽怱乿傊丄傕偟偔偼丄乽榓壧偺嶻弌夁掱偵偍偄偰偺傒惗偠偰偄傞丄嫊峔偺丄偟偐偟摦揑側惗柦傪傕偭偰乽怺偔側傗乿傓偙偲偺偱偒傞乽怱乿乿亖乽塺傒偮偮偁傞怱乿丄偮傑傝乽桳怱乿傊偲恑傫偱偄偒傑偡丅乮偙傟傜偺偙偲偵偮偄偰偼丄偙傟傑偱偐傜抐懕揑偵嶶尒偟偰偒偨偟丄傑偨丄師愡偱暿偺帇揰偐傜妋擣偡傞偙偲偵側傞偲巚偆偺偱丄偙傟埲忋偼棫偪擖傜偢乯丄偙偙偱偼丄摉柺偺娭怱帠偵尷掕偟偰丄偙傟偵娭楢偡傞堦愡傪敳偒彂偒偟偰偍偒傑偡丅
丂嵟屻偺僙儞僥儞僗偱尵傢傟傞乽怱乿偼丄榓壧傪偄傢偽乽偁偪傜懁乿偵偍偄偨偲偒偵尒偊偰偔傞乽壧偵塺傑傟偨怱乿偺偙偲偱偡丅偙傟偵懳偟偰丄乽塺傒偮偮偁傞怱乿偼榓壧偺乽偙偪傜懁乿傪杮棃偺廧張偲偡傞傕偺偱偡丅偦偙偼丄擈儢嶈巵偑乽尰幚偺奜偵棫偮帊揑悽奅乿偲屇傫偩応強偱傕偁傝丄乽娷傒乿偡側傢偪旕尠尰揑尰徾偺悽奅偱偁傝丄僀儅僕僫儖側傕偺偺骐缁偡傞乽嫊側傞乿奅堟偱傕偁傞偱偟傚偆丅
丂
丂偝偰丄埲忋偺偙偲傪摜傑偊偰丄慜乆愡偱堷偄偨朏愳巵偺媍榑傪丄杮壧庢傝偵娭楢偯偗側偑傜嵞搙偲傝偁偘偨偄偲巚偄傑偡丅偦偺戝梫偼丄偍傛偦師偺傛偆側傕偺偱偟偨丅
丂戞堦偵丄柍堄巙揑憐婲偼乽堎側傞岝宨丄堎側傞帪娫丄堎側傞姶妎乮僋僆儕傾乯乿傪摨偠堦偮偺暯柺忋偵丄摍壙側傕偺偲偟偰嫟嵼偝偣傞塀歡揑峔憿傪傕偭偰偄偨偙偲丅偦偟偰丄偦偆偟偨歡揑娭學傪攠夘偡傞乽偼偨傜偒乿傪偡傞偺偑丄乽惗偒偨乿恎懱偺摦惷偱偁傞偙偲丅
丂戞擇偵丄柍堄巙揑憐婲偵傛偭偰巔傪偁傜傢偡乽夁嫀丄婰壇乿偺尨弶宍懺偼丄偄偢傟幚懱尡偵傛偭偰偦偺幚幙偑廩揢偝傟傞偙偲偵側傞乽尵梩偺偐偨偪乿傪偲偭偨傕偺偱偁傞偙偲丅乮戝怷憫憼偑偄偆傛偆偵丄偦傕偦傕憐婲偵敽偆偺偼乮傾儕僗僩僥儗僗偺乽嫟捠姶妎乿偵傑偱偵偝偐偺傏傞乯乽尵岅妎乿偱偁偭偰丄憐婲偝傟傞偺偼尵岅揑惂嶌暔乮暔岅傝乯偵傎偐側傜側偄偺偩偲偡傟偽丄偡側傢偪丄乽屆暔偵側偭偨尰嵼宱尡偺嵞宱尡偱偼側偔偟偰夁嫀偦傟帺懱傪捈愙偵宱尡偡傞偺偑憐婲偱偁傞丅壗偐傪尒偨傝暦偄偨傝偡傞偺偱偼側偔丄壗偐傪尒偨丄壗偐偑暦偊偨偲偄偆夁嫀宍偺捈愙揑側弶懱尡側偺偱偁傞乿乮偪偔傑妛寍暥屔亀巚峫偲榑棟亁39暸乯偲偟偨傜丄乽幚懱尡偵傛偭偰偦偺幚幙偑廩揢偝傟傞乿側偳偲偄偭偨尷掕偼晄梫偩傠偆丅乯偦偟偰丄柍堄巙揑憐婲偑傕偨傜偡乽娊傃乿偲偼乽扙帺乿偵傛傞乽湌崨丄僄僋僗僞僔乕乿偵傎偐側傜側偄偙偲丅
丂戞嶰偵丄柍堄巙揑憐婲偑傕偨傜偡乽娊傃乿偼丄乽暔幙揑湌崨乿偲傕屇傇傋偒丄尵岅埲慜偺嫟姶妎揑側恎懱乮亖帪娫偲抦妎傪廻偟偨暔幙乯偺懱尡偱偁傞偙偲丅
丂杮壧庢傝傕偙傟偲摨條偵丄屆壧乮杮壧乯偲怴嶌壧乮杮壧庢傝壧乯丄廤抍揑椶宆壧偲屄恖塺乮媑杮棽柧偑掕壠廫懱傪暘椶偡傞嵺偵巊偭偨尵梩傪庁梡偟偰丄乽懎梬乿偲乽弮悎帊乿偲尵偄姺偊偰傕偄偄乯偲傪丄壧恖偨偪偺恎懱揑峴堊乮彞榓乯偵傛偭偰丄乽偄傑丄偙偙乿偵偁傞摨偠堦偮偺応偵嫟嵼偝偣傞塩傒偱偡丅偦偟偰丄杮壧庢傝偵傛偭偰尠嵼壔偡傞杮壧偼丄幚惗妶偵偍偗傞懱尡偲偼昁偢偟傕楢摦偟側偄帉偺嶻暔偵傎偐側傝傑偣傫丅
丂偙偙偱棷堄偡傋偒偙偲偼丄搉晹巵偑丄杮壧偼怴嶌壧偵昁慠惈傗崻嫆丄懚嵼堄媊丄壙抣傪梌偊傞尮愹偱偁傞偲巜揈偟偰偄偨偙偲偱偡丅乽杮壧庢傝壧傪惉傝棫偨偣傞巒尨偺埵抲偵丄杮壧偑棫偮乿丄偁傞偄偼乽杮壧偑偁傞偐傜偙偦怴嶌壧偑懚嵼偡傞乿偲偄偆傢偗偱偡偑丄巹偼丄偙偺搉晹巵偺巜揈傪丄師偺傛偆偵夝偟偰偄傑偡丅
丂偡側傢偪丄巒尨偺埵抲偵棫偮杮壧偲偼丄屄乆偺榓壧嶌昳偺偙偲偱偼側偔丄偐偮偰乮廤抍揑偱偁傟丄屄恖揑偱偁傟乯塺傑傟丄壧傢傟偨偡傋偰偺榓壧偺廤憼屔乮榓壧偦偺傕偺偑廧張偲偡傞乽榓壧傾儔儎幆乿側偳偲屇傫偱偄偄偐傕偟傟側偄応強乯偺偙偲偱偁傞丅偦偟偰丄偡傋偰偺嬶懱偺榓壧嶌昳偼丄偙偺償傽乕僠儏傾儖側廤憼屔偐傜棫偪尰傢傟偨僀儅僕僫儖側乽塺傒偮偮偁傞怱乿偺乽偼偨傜偒乿偵傛偭偰丄偮傑傝廤憼屔偵懳偡傞傾僋僙僗乮専嶕偲堷梡乯偵傛偭偰丄乽偄傑丄偙偙乿偺傾僋僠儏傾儖側応偵尰徾偝偣傜傟偨杮壧庢傝壧偵傎偐側傜側偄丅偩偐傜丄乽杮壧偑偁傞偐傜偙偦怴嶌壧偑懚嵼偡傞乿丅乮榓壧偺廤憼屔偼丄巹偺尵梩偱偄偊偽乽惗偒偨傞傕偺乿偡側傢偪乽懱乿偱偁傝丄偦偟偰丄偙偺乽懱乿偐傜惗婲偟偦偺乽偼偨傜偒乿偦偺傕偺偱偁傞偲偙傠偺乽塺傒偮偮偁傞怱乿偑乽徾乿乮傕偟偔偼乽徰乿乯偱偁傞丅乯
丂偙傟偼丄慜愡偺朻摢偵偁傜偐偠傔彂偄偰偍偄偨偙偲偺從偒捈偟偵偡偓傑偣傫丅偙偙偱怴偨偵偮偗壛偊傞偙偲偑偁傞偲偡傟偽丄乽榓壧偦偺傕偺乿偲乽屄乆偺榓壧乿偲偺乽偁偄偩乿丄偁傞偄偼椉幰偺乽嵎堎乿偺偆偪偵偙偦丄杮壧庢傝偑傕偨傜偡乽娊傃乿偑偁傞偺偱偼側偄偐偲偄偆榑揰偱偡丅朏愳巵偼丄乽塀歡偲偼丄乽歡偊傜傟傞傕偺乿偑乽歡偊傞傕偺乿偲偄偆堎側傞僀儊乕僕傪夘偟偰乽帺傜偺奜偵棫偮偙偲乿偵傎偐側傜側偄乿偲彂偄偰偄傑偟偨偑丄偙偙偱尵傢傟傞乽塀歡乿傪乽杮壧庢傝乿偵偍偒偐偊偰峫偊傟偽丄杮壧庢傝偺乽娊傃乿偲偼丄乽榓壧偦偺傕偺乿偐傜乽屄乆偺榓壧乿偑乮屄暿壔偝傟偨嬶懱偺杮壧偲杮壧庢傝壧偲偟偰乯愗傝偩偝傟傞偙偲偵偲傕側偆丄懚嵼條懺偲懚嵼師尦偺揮姺偺乽娊傃乿偱偁傞偲尵偆偙偲偑偱偒傞偱偟傚偆乵仏乶丅帺傜偺奜偵棫偮偙偲丄偡側傢偪乽扙帺丄僄僋僗僞僔乕乿丅偦傟偼丄儔儞僈乕僕儏乮尵岅妶摦丄尵梩偺敪惗乯偦偺傕偺偑傕偨傜偡乽娊傃乿偵捠偠偰偄傞丄偲尵偭偰偄偄偐傕偟傟傑偣傫丅
丂偲偙傠偱丄杮壧庢傝偺乽娊傃乿偼扤偵偨偄偟偰丄偁傞偄偼壗偵偨偄偟偰傕偨傜偝傟傞偺偐偲偄偆偲丄偦傟偼丄杮壧偲杮壧庢傝壧偵塺傑傟偨擇偮偺乽怱乿傪丄乮偦偟偰丄嶌幰偲撉幰偺擇偮偺乽怱乿傪乯丄偲傕偵帺傜偺乽怱乿偲偟偰儕傾儖偵懱尡偡傞乽懱乿丄偡側傢偪壧偺塺傒庤偺乽恎懱乿偵傎偐側傝傑偣傫丅偦偟偰丄偙偺応崌偵偍偗傞乽壧偺塺傒庤乿偲偼丄乽塺傒偮偮偁傞怱乿傪帺傜偺乽怱乿偲偡傞僀儅僕僫儖側塺壧庡懱偺偙偲偱偡丅
丂朏愳巵偵傛傞柍堄巙揑憐婲偺戞嶰偺摿挜偼丄偦傟偑傕偨傜偡乽娊傃丄僄僋僗僞僔乕乿偺暔幙惈丄恎懱惈乮嫟姶妎惈乯偵偁傝傑偟偨丅榓壧偺杮壧庢傝偼帉偺悽奅偺榖側偺偱丄偙偺揰偱丄柍堄巙揑憐婲偲偺娭學偑愗傟偦偆偱偡偑丄偟偐偟丄乽塺傒偮偮偁傞怱乿偲偄偆奣擮偺偲傜偊曽偟偩偄偱丄傆偨偨傃椉幰偺枾愙側娭學傪峔抸偡傞偙偲偼偱偒傑偡丅巹偼丄乽塺傒偮偮偁傞怱乿偺暔幙壔偝傟偨嬌尷偺巔傪丄擻晳戜偺偆偊偵尠尰偡傞乽儁儖僜僫乿偺偆偪偵尒傞偙偲偑偱偒傞偲峫偊偰偄傞偺偱偡偑丄偨偲偊偽丄偦偺傛偆側巚峫夞楬傪宱偰丄柍堄巙揑憐婲偲杮壧庢傝偲偑嫟嵼偡傞応傪峔憐偡傞偙偲偼丄偗偭偟偰峳搨柍宮側帋傒偱偼側偄偲巚偄傑偡丅
丂
乵仏乶乽榓壧偦偺傕偺乿偲乽屄乆偺榓壧乿偲偺乽偁偄偩丄嵎堎乿傪丄乽懚嵼偦偺傕偺乿偲乽懚嵼幰乿偲偺偁偄偩偺乽懚嵼榑揑嵎堎乿乮僴僀僨僈乕乯傗丄乽惗柦偦偺傕偺乿偲乽屄乆偺惗偒傕偺乿偲偺偁偄偩偺乽惗柦榑揑嵎堎乿乮栘懞晀乯偵側傜偭偰丄乽壧榑揑嵎堎乿偲屇傫偱傒偰傕偄偄丅
丂栘懞晀挊亀偐傜偩丒偙偙傠丒惗柦亁偵丄乽乽惗柦偦偺傕偺乿偲乽屄乆偺惗偒傕偺乿偲偺偁偄偩偺丄偄偄偐偊傟偽傾僋僠儏傾儕僥傿偲儕傾儕僥傿偺偁偄偩偺丄堦庬偺乽懚嵼榑揑嵎堎乿乿乮75暸乯偲偄偆昞尰偑偱偰偔傞丅偙傟傪嶲徠偡傞側傜偽丄乽壧榑揑嵎堎乿偵偍偗傞乽榓壧偦偺傕偺乿偼乽傾僋僠儏傾儕僥傿乿偺師尦偵丄乽屄乆偺榓壧乿偼乽儕傾儕僥傿乿偺師尦偵強嵼偡傞偙偲偵側傞丅
丂巹偺棟夝偱偼丄乽榓壧偦偺傕偺乿偼杮棃丄償傽乕僠儏傾儖側師尦乮堜摏弐旻偺堄幆偺峔憿儌僨儖偱偄偆俛椞堟乯偵嵼傝丄僀儅僕僫儖側師尦乮摨偠偔俵椞堟乯偱壱摥偡傞乽塺傒偮偮偁傞怱乿偺乽偼偨傜偒乿偵傛偭偰丄傾僋僠儏傾儖側乽偄傑丄偙偙乿偺師尦傊偲乮俙椞堟傪撍偒攋偭偰乯儅僌儅忬偵暚偒忋偘傞丅偦偟偰偦偺椻媝偲偲傕偵丄屄暿壔偝傟偨嬶懱偺杮壧偍傛傃杮壧庢傝壧偲偄偆乽屄乆偺榓壧乿嶌昳偑丄儕傾儖側師尦乮壒惡偲昅嵀偵傛偭偰尰徾偡傞暔幙揑側師尦乯偵徎弌偡傞丅栘懞巵偑尵偭偰偄傞偙偲傪乽壧榑揑嵎堎乿偵偁偰偼傔傞偲丄偦偺傛偆側偙偲偵側傞偺偱偼側偄偐丅
丂偪側傒偵丄掕壠塺乽偝傓偟傠傗懸偮栭偺廐偺晽傆偗偰寧傪偐偨偟偔塅帯偺嫶昉乿偼丄岅偺摑帿娭學偺夝懱偺偆偪偵僀儅僕僫儖側師尦偺嵀愓傪偲偳傔丄偐偮丄屄暿壔偝傟偨嬶懱偺杮壧偲偺暘棧傪壥偨偟偒傟側偄傑傑俙椞堟偱寢徎壔偟偨丄偄傢偽乽杮壧庢傝偟偮偮偁傞杮壧庢傝壧乿偱偁偭偨丄偲尵偆偙偲偑偱偒傞丅
丂
仭桳怱丒柍怱丒嫊怱乵仏乶
丂
丂戞擇偺榖戣丅怴愳揘梇挊亀乽惗偒偨傞傕偺乿偺巚憐劅劅擔杮偺旤榑偲偦偺婎挷亁偼丄弐惉丒掕壠傪婲揰偲偡傞拞悽旤榑偺婎挷傪側偟偰偄偨巚憐傪丄嶌昳傪惗傒偩偡懁偺巚峫傪庤偑偐傝偵峫嶡偟偨挊彂偱丄偄傑丄偦偺奣梫丄媍榑偺崪奿傪拪弌偟偰傒傞偲丄師偺傛偆側傕偺偵側傝傑偡丅
丂
侾丏乽梋忣丒桪丒墣丒偨偗崅偟丒偲傎敀偟丒桯尯丒偝傃丒椻偊丒屚傟乿摍乆丄嶌昳傪娤徿丒嫕庴丒斸敾偡傞懁偑摼偨乽姶乿傪偄偄昞傢偡條乆側尵梩偑偁傞丅偦傟偧傟偺乽姶乿偺旝柇側憡堘偑丄偦傟傜偺尵梩偺堘偄偵戸偝傟偰偄傞丅
丂偟偐偟丄嶌昳傪惗傒偩偡懁偺恖乆偑峫偊偰偄偨傕偺偼丄幚偼丄偦偺憡堘傪偙偊偨偁傞堦偮偺婎挷偱偁偭偨丅偦傟偼丄條乆側乽姶乿偑傕偮忣挷丒枴傢偄偺婎掙偵嫟捠偟偰偄傞乽傕偺偺尒曽乿偺偙偲偱偁傞丅乮4-5暸乯
丂偦偺婎挷偼丄乽桯尯丒椻偊乿偲偄偭偨旤偺尠傢傟偺彅憡偺婎掙傪側偡偩偗偱側偔丄帊壧榑乮壧榑丄楢壧榑丄攐榑乯傗擻妝榑丄拑搾榑丄棫壴榑丄彂榑丄夋榑偲偄偭偨條乆側旤偺椞堟偵偍偗傞巚憐揑婎斦偲傕側偭偰偄偨丅乮272-273暸乯
丂
俀丏偦傟偱偼丄拞悽旤榑偺婎挷傪側偡巚憐偲偼側偵偐丅
丂擻妝榑偐傜偲傝偩偝傟偨偦傟偼丄墘幰偺晳巔偲偄偆乽偐偨偪乿傪捠偠偰乽傕偺乿偺乽偄偺偪乿偵傆傟偨帪偵摼傜傟傞娊婌傪丄嵟傕怺墦側乽姶乿偲偡傞偲偄偆傕偺偩偭偨丅
丂恖偼偦傟偵傛偭偰屓偲悽奅偑妋偐偵乽偁傞乿偙偲傪懱姶偟丄屓偑乽惗偒偰偁傞乿偙偲偺妋偐偝傪庤偵偡傞丅偦偺帪摼傜傟傞尵梩偵偟摼側偄乽姶乿傪丄擻偵偍偄偰嵟傕怺偄婎憌偵悩偊傜傟偨旤偺憡偲偟偰偲傜偊傞偙偲偑偱偒傞丅乮313暸乯
丂
俁丏懡偔偺壧恖傗擻偺墘幰丄拑恖丒壴恖丒彂壠丒夋恖偵偲偭偰偺嵟戝偺壽戣偼丄偄偐偵偡傟偽斵傜偑惗傒弌偡乽偐偨偪乿偺忋偵丄乽惗偒偨傞乿偲偄偆乽姶乿傪恖偵梌偊傞壗偐傪尠傢偟摼傞偐偲偄偆偙偲偱偁偭偨丅
丂乽姶乿傪昞傢偡偺偱偼側偔丄偦偺壗偐丄偮傑傝乽偄偺偪乿傪乽偐偨偪乿偺忋偵尠傢偡偙偲丅
丂偙偺栤偵懳偡傞斵傜偺摎偼丄乽暔乿偺乽偄偺偪乿傪乽壛帩乿偡傞偙偲偱偁傝丄偦傟偑払惉偱偒傟偽帺慠偵乽偐偨偪乿偺忋偵乽偄偺偪乿偑乽弌偱棃傞乿偙偲偵乽側傞乿偲峫偊偨偺偱偁傞丅乮315-316暸乯
丂
係丏偱偼丄偄偐偵偟偰乽偄偺偪乿傪乽壛帩乿偡傞偐丅
丂柍怱丒柍変丒柍巹偲側偭偰乽暔乿傪乽娤乿偢傞偙偲丄乽怱乿傪偡傑偟偰偦偺乽嫬乿偵擖傝傆偡偙偲偵傛偭偰丅乮316-318暸乯
丂偦偺帪丄揤偺娾屗偑奐偒丄嵞傃岝偑偝偡丅恖偼弖帪偵偟偰堦愗偺乽暔乿偺妋偐偝偵怗傟丄屓偑惗偒偰偁傞偙偲偺妋偐偝傪庤偵偡傞丅偦偺妋偐偝偵怗傟偨娊婌丒偄偺偪偺婸偒偑乽壴乿偱偁傞丅
丂娾屗傪奐偗偨偺偼墘幰偱傕側偔丄娤媞偱傕側偄丅墘幰偑乽偡傞乿偺偱偼側偔丄帺慠偵乽側傞乿偙偲偲偟偰乽壴乿傪岅傞偟偐側偄偺偱偁傞丅乮30暸乯
丂
丂怱偺嬚慄偵傆傟偨彂暔傪乽弅栺乿偡傞嵺丄偄偮傕廝傢傟傞嬻偟偝偑偁傝傑偡丅偦傟偼丄偙傟偱偼偙偺杮偵偙傔傜傟偨朙忰側壜擻惈偑媎偊偰偄側偄丄彮側偔偲傕丄偙偺彂暔偵杤摢偟偰偄偨偲偒丄巹偺擼悜偵棫偪尰傢傟偰偄偨巚峫偺桇摦偑掕拝偝傟偰偄側偄丄乮偨偲偊偽丄巹偑傕偭偲傕巋寖傪庴偗偨偺偼丄乽尒強乵偗傫偠傚乶乿偲偄偆岅偵乽堦墳娤媞偲峫偊偰傛偄偑丄杮棃娤媞惾傪堄枴偡傞尵梩偱丄娤媞傪屄乆偺懚嵼偱偼側偔丄堦偮偺暤埻婥傪惗傒弌偡乹応乺偲偟偰曪妵揑偲傜偊傞峫偊曽傪帵偡乿乮18暸乯偲妵屖彂偒偱拹偑偮偗傜傟偨屄強側偺偩偑丄偙偺偙偲偑偆傑偔怐傝偙傔偰偄側偄乯丄偦偟偰側偵傛傝傕丄偦偺彂暔傪撉傒抆偭偰偄偨偲偒偺丄偁偺岾暉側乽偄偺偪乿偺婸偒偺偛偲偒弖娫偑偡偭傐傝偸偗偍偪偰偄傞丄偲偄偭偨晄枮側偺偱偡丅
丂偑丄偟偐偟丄偦傟偼偄偨偭偰屄恖揑側乽姶乿傪傔偖傞偙偲偱偟偐側偄偺偱丄偙傟埲忋偺懯曎偼憗乆偵偒傝偁偘傞偙偲偵偟偰丄偙偙偱偼丄埲忋偺梫栺偺偆偪偵丄亀乽惗偒偨傞傕偺乿偺巚憐亁偺榑弎偺嶰偮偺拰寶偰偑偔偭偒傝偲尠傢傟偰偄傞偙偲傪巜揈偟偰偍偒偨偄偲巚偄傑偡丅偦傟偼丄俙丏旤偺彅憡偲偦偺婎挷丄俛丏嶌昳傪惗傒偩偡懁偺巚峫丄俠丏乽偡傞乿偐傜乽側傞乿傊丄偲妵傞偙偲偑偱偒傑偡丅埲壓丄偙傟傜偺榑揰偵偦偔偟偰丄掕壠壧榑傪傔偖傞怴愳巵偺媍榑傪丄挻栿側傜偸乽挻栺乿偺偐偨偪偱揈弌偟傑偡丅
丂
俙丏旤偺彅憡偲偦偺婎挷劅劅乽傕偲偺怱乿偲偼壗偐
丂
丂拞悽旤榑偼弐惉偵傛偭偰奐巒偝傟傞丅弐惉壧榑偺娽栚偼丄亀屆棃晽懱彺亁偱乽壧偲偄傆傕偺側偐傜傑偟偐偽丄怓傪傕崄傪傕抦傞恖傕側偔丄壗傪偐偼傕偲偺怱偲傕偡傋偒乿偲愢偄偨丄偦偺乽傕偲偺怱乿偵偁傞丅
丂偦傟偱偼丄拞悽旤榑偺婎挷偵捠偠傞乽傕偲偺怱乿偲偼壗偐丅
丂屆崱彉偑偄偆傛偆偵丄偦偟偰弐惉傕擣傔偰偄傞傛偆偵丄恖偺怱傪庬偲偟偰帉偵側偭偨傕偺偑壧偱偁傞丅偙偙偱丄恖偑乽怱偵偍傕傆偙偲乿偑帉偵側偭偨偲峫偊傞偲丄壧偵傛偭偰抦傜傟傞乽傕偲偺怱乿偲偼丄恖偑偁傞暔偵傆傟偰怱偵憐偭偨偙偲偵側傞偩傠偆丅偩偑丄弐惉偼偦偆偼峫偊側偐偭偨丅
丂偨偟偐偵丄恖偺怱偼帉偺庬偱偁傞丅偟偐偟丄偦傟偼丄帉偵側偭偨傕偺偑乽怱偵偍傕傆偙偲乿偱偁傞偙偲傪堄枴偟側偄丅弐惉偑恖偺怱傪庬偲偟偰帉偵側傞偲峫偊偨偺偼丄偨偲偊偽壴丒峠梩偱偁傝丄偁傞偄偼亀屆棃晽懱彺亁壓姫朻摢偵嫇偘傜傟偨巐婫條乆偺宨暔偱偁傞丅偮傑傝丄恖偺怱偵塮偢傞揤抧帺慠偺宨婥偑帺偢偲帉偵乽側偭偨乿傕偺乮偡側傢偪乽暔乮傛傠偯乯佀帉乮偙偲偺偼乯乿乯偑壧偱偁傞偲弐惉偼峫偊偰偄偨丅乮210-211暸乯
丂壧偼乽傕偲偺怱乿傪尠傢偟偨傕偺偩偲偄偆峫偊曽偺攚屻偵丄弐惉偼揤戜巭娤偵偄偆嬻壖拞偺嶰掹墌梈偺棟傪傒偰偲偭偨丅偡側傢偪丄乽傕偲偺怱乿偲偼乽恀擛幚憡丄懄嬻懄壖懄拞側傞乹暔乺偺崻尮揑偁傝曽乿乮220暸乯偱偁傝丄乽恖亖擣幆偡傞傕偺乿偲乽暔亖擣幆偝傟傞傕偺乿偲偑偲傕偵乽傕偲偺怱乿偲偟偰偁傞乽懄旕乿偺娭學偵擖傞偙偲偵側傞丅乮219暸乯
丂怴愳巵偼丄偙偺傛偆側乽傕偲偺怱乿乮偡側傢偪乽旤偺彅憡乿乮壴丒峠梩丒偦偺懠偺宨暔乯偺乽婎挷乿傪側偡傕偺乯偑帵偟偰偄傞撪梕傪擻妝榑偺専摙偺嵺偵梡偄偨尵梩傪巊偭偰乽傕偺乿偺乽偄偺偪乿偲屇傃丄弐惉偐傜掕壠傊偺宲彸丄乽宨婥偺偦傂偨傞乿懱偐傜乽桳怱懱乿傊偺揥奐傪峫偊傞丅乮211暸丄220暸乯
丂
俛丏嶌昳傪惗傒弌偡懁偺巚峫劅劅乽梋忣梔墣懱乿偐傜乽桳怱懱乿傊
丂
丂姏挿柧偼偦偺壧榑彂亀柍柤彺亁偱丄弐惉偑棟憐偲偟偨壧懱傪乽慒偼偨乁帉偵尰傟偸梋忣丄巔偵傒偊偸宨婥側傞傋偟乿偲夝愢偟丄乽桯尯偺懱乿偲徧偟偨丅乮190-192暸乯
丂掕壠偼偦傟傪乽梋忣梔墣懱乿偲偟偰宲彸偟乮乽傓偐偟娧擵丄壧偺怱偨偔傒偵丄偨偗傪傛傃偑偨偔丄偙偲偽偮傛偔偡偑偨偍傕偟傠偒條傪偙偺傒偰丄梋忣梔墣偺懱傪傛傑偢丅乿乮亀嬤戙廏壧亁乯乯丄偝傜偵偙傟傪乽壧偺杮堄偲懚偢傞巔乿偡側傢偪乽桳怱懱乿傊偲揥奐偟偰偄偭偨乮亀枅寧彺亁乯丅乮195暸丄205暸乯
丂挿柧偺乽桯尯懱乿乮亖乽梋忣梔墣懱乿乯偲掕壠偺乽桳怱懱乿偼摨堦撪梕傪巜帵偡傞岅偲偄偭偰傛偄丅堦曽乮桯尯懱乯偼斸昡偺棫応偐傜偡傞壧偺巔偺彅憡傪偄偆尵梩偱丄懠曽乮桳怱懱乯偼塺嬦偺棫応偐傜偡傞壧偺杮幙傪偄偆尵梩偱偁傞丅
丂偙偺乽桯尯懱亖梋忣梔墣懱乿偐傜乽桳怱懱乿傊偺屇徧偺揥奐偼丄悽垻栱偺乽壴乿偐傜乽柍怱偺姶乿傊偺揥奐丄偡側傢偪乽姶乿傪嫕庴偡傞懁偺榑偐傜乽姶乿傪惗傓懁偺榑傊偺怺傑傝偲懳墳偟偰偄傞丅乮206-207暸乯
丂掕壠偼丄壧傪塺嬦偡傞棫応偐傜丄弐惉偐傜宲彸偟偨傕偺傪帺妎揑偵偲傜偊捈偟偰偄偭偨丅偩偐傜偙偦丄弐惉傗挿柧偑棟憐偺壧傪塺傓曽朄傪帺摼偵傑偐偣偰愢偒摼側偐偭偨偺偵懳偟丄乽傛傠偟偒壧乿偡側傢偪乽怱偺傆偐偒乿壧傪塺傓偨傔偺曽朄傪乽傛偔傛偔怱傪偡傑偟偰丄偦偺堦嫬偵擖傝傆偟偰偙偦乿乮亀枅寧彺亁乯偲愢偒摼偨偺偱偁傞丅乮207暸乯
丂
俠丏乽偡傞乿偐傜乽側傞乿傊劅劅弌偱棃傞桳怱丄惉傝擖傞柍怱
丂
丂揤戜嫵妛偵偍偄偰乽嫬乿偲偼乽娤晄巚媍嫬偲偟偰幚憡偺棟傪娤偢傞偙偲乿傪堄枴偡傞乮228暸乯丅偮傑傝丄怱傪悷傑偟偰乽偦偺堦嫬偵擖傝傆偡乿偲偼丄塺壧懳徾乮尰徾丒帠暔乯偵擖傝愗傞偙偲丄悽垻栱偺尵梩偵偡傟偽乽乮偦偺暔偵乯惉傝擖傝偸傞乿乮亀晽巔壴揱亁乯偙偲偱偁傞丅
丂偦偆偟偨乽側傞乿偵帄傞偨傔偵偼丄乽柍怱乿偱偁傞偙偲丄偮傑傝乽偡傞乿搘椡偺壥偰偵帺慠偵壗暔偱傕側偄傕偺偲偟偰乽偁傞乿偙偲偵乽側傞乿偙偲偑梫惪偝傟傞丅偦傟偑丄乽怱傪偡傑偟偰乿偲偄偆偙偲偱偁傞丅乮202-203暸乯
丂怱傪偡傑偡偙偲偡側傢偪乽柍怱乿偲偄偆偁傝曽偼丄懳徾偺崻尮揑側偁傝曽偱偁傞乽偄偺偪乿偲堦擛側傞傕偺偱偁傞丅乮205暸乯
丂掕壠偺乽桳怱懱乿偲偼丄壧偺乽巔乿偲偄偆乽偐偨偪乿傪捠偠偰乽傕偺乿偺乽偄偺偪乿乮亖乽傕偲偺怱乿乯傪尠尰偟摼偨壧丄偦傟偵傛偭偰恖偵怺偄乽姶乿傪梌偊摼傞壧偺偙偲偱偁傝丄偦偺壧傪塺傓偨傔偵乽怱傪偡傑偡乿偙偲偑塺幰偵梫惪偝傟偨丅乮207暸丅227暸乯
丂桳怱懱乮偲偟偰偺廏堩懱乯偺壧傪塺傓偨傔偵偼丄塺幰偼偦偺乽怱乿傪怺偔恠偔偟丄乽傛偔傛偔塺嬦偟偰丄偙偟傜傊偰弌偡傋偒乿偱偁傞偑丄偦偺寢壥乽塺嬦帠偒偼傑乿偭偨壥偰偵乽埬惈偡傒傢偨傟傞乿偲丄帺傜乽偵偼偐偵偐偨偼傜傛傝傗偡傗偡乿偲壧傪乽塺傒偄偩偟偨傞乿偙偲偑乹弌偱棃傞乺偺偱偁偭偰丄偦傟備偊乽傢偞偲乮嶌堊揑偵乯傛傑傫偲偡傋偐傜偢乿丅宮屆偝偊愊傔偽乽帺慠偵塺傒偄偩偝傞傞帠偵偰岓乿丅偙傟偑掕壠偺嫵偊偨塺嶌懺搙偱偁傞丅乮226-227暸乯
丂
丂偩偑丄乽堦嫬偵擖傝傆偡乿偙偲偑偄偐偵偟偰乽巔乿偺忋偵棫偪尠傢傟傞偺偐丅
丂偮傑傝丄娤偠偰偄傞幰偲娤偤傜傟偰偄傞嫬偲偺晄擇堦擛丄懄旕偺偁傝條偲偄偆尵岅摴抐偺帠懺偑偄偐偵偟偰乽帉乿偵乽側傞乿偺偐丅偦偺帪恖偺乽怱乿偼偦偺偙偲偵偳偆娭傢傞偺偐丅偙傟偑掕壠偺榑偵巆偝傟偨栤戣偱偁偭偨丅乮228-229暸乯
丂怴愳巵偼丄嫗嬌堊寭丄壴嶳堾挿恊丄惓揙偺壧榑丄怱宧偺楢壧榑偺偆偪偵弐惉掕壠偺榓壧娤偑宲彸偝傟偰偄傞偙偲傪妋擣偟偨忋偱丄偙偺栤戣偵娭偟偰師偺傛偆偵弎傋傞丅乮259暸乯
丂恖偼壒妝傪挳偔偙偲偵傛偭偰乽帉乿傪梡偄偢乽姶乿傪摼丄壗偐傪屽傝抦傞丅偦傟偲摨條偵丄恖偼乽嫬乿傪娤偠偰乽怱乿偵乽傕偲偺怱乿傪壛帩偡傞乮偦偺帪偦偺応偵棫偪尠傢傟偰偄傞乽傕偺乿偺巔丒偐偨偪傪偦偺傑傑偵娤傞恖偺怱偵塮偡乮221暸乯乯偙偲偵傛偭偰丄偦傟偑壗偱偁傞偐傪乽帉乿偱側偔屽傝抦傞丅
丂偲偡傟偽丄乽帉乿偵偟摼側偄傕偺傪偦傟偱傕側偍乽帉乿偵偟傛偆偲乽偡傞乿搘椡偺壥偰偵乽偵偼偐偵偐偨偼傜傛傝傗偡傗偡乿偲乽帉乿偑晜傃偁偑偭偰偔傞帪丄乽傕偲偺怱乿傪屽傝抦偭偰偄傞乽怱乿偼偦偺乽帉乿偑偦傟偵憡墳偟偄傕偺偱偁傞偙偲傪弖帪偵抦傞丅
丂偙偆偟偰乽傕偲偺怱乿乮乽傕偺乿偺乽偄偺偪乿乯偼乽嫬乿傪娤偢傞偙偲偵傛偭偰乽怱乿偵壛帩偝傟偨寢壥丄帺慠偵乽帉乿偵乽側傞乿丅乮269-270暸丄317-318暸乯
丂偙偺傛偆側拞悽旤榑偺婎挷傪側偡巚憐偼丄嬤悽偵偍偄偰傕宲彸偝傟偰偄傞丅
丂徳栧偺攐榑亀嶰嶜巕亁偵乽徏偺帠偼徏偵廗傊丄抾偺帠偼抾偵廗傊乿丄乽暔偺尒傊偨傞岝乿傪乽帪乿偲偟偰乽尒偲傔暦偒偲傓傞乿塢乆偲偁傞偺偼丄掕壠偺乽堦嫬偵擖傝傆偟偰乿偲摨偠偔乽暔乿傪娤偠偰偦偺乽偄偺偪乿傪壛帩偡傞偙偲傪尵偭偰偄傞丅乮333-334暸乯
丂
乵仏乶掕壠偺桳怱丄悽垻栱偺柍怱丄攎徳偺嫊怱丅掕壠偺桳怱偑悽垻栱偺柍怱偵摓傝丄攎徳偺嫊怱偵嬌傑傞丅偦偟偰乽峀媊偺乿掕壠榑棟妛偑姰惉偡傞丅巹偼偦傫側峔恾傪峫偊偰偄傞丅
丂晽夒丒晽嫸偺怱丄偡側傢偪嫊怱丅乽惣峴偺榓壧偵偍偗傞丄廆媉偺楢壧偵偍偗傞丄愥廙偺奊偵偍偗傞丄棙媥偺拑偵偍偗傞丄懘娧摴偡傞暔偼堦側傝丄偲攎徳偼尵偭偰偄傞偑丄斵偺尵偆晽夒偲偼丄嬻娤偩偲峫偊偰傕傛傠偟偄偱偟傚偆丅惣峴偑丄嫊嬻偺擛偔側傞怱偵偍偄偰丄條乆偺晽忣傪怓偳傞丄偲尵偭偨張傪丄攎徳偼丄嫊偵嫃偰幚傪偍偙側偆丄偲尵偭偨偲峫偊偰傕嵎巟偊偁傞傑偄丅乿乮彫椦廏梇乽巹偺恖惗娤乿丄暥弔暥屔亀峫偊傞僸儞僩俁亁182暸乯
丂
仭徾岺応偺垼偟傒丄抁偄憤妵偲偟偰
丂
丂怴愳巵偺挊嶌偺敳悎嶌嬈傪偟側偑傜丄巹偼丄掕壠偺乽桳怱乿乮僀儅僕僫儖側乽塺傒偮偮偁傞怱乿乯偑悽垻栱偺乽柍怱乿偐傜弌偱棃偰丄擻栶幰乮僔僥乯偺乽儁儖僜僫乿乮壖柺乯偺偆偪偵尠尰偟偨偲偒丄偮傑傝巰幰偑惗幰偺悽奅偵慼偭偨偲偒丄柍堄巙揑憐婲乮亖杮壧庢傝乯偺儊僇僯僗儉傪夘偟偰丄偄傢偽擔杮暥壔偺揱摑偑乽偄傑丄偙偙乿偱峏怴偝傟傞偺偱偼側偄偐丄偲偄偭偨偙偲傪峫偊偰偄傑偟偨丅
丂擔杮暥壔偺揱摑偑峏怴偝傟傞丄偲偼戝嬄側暔尵偄偱偡偑丄偦傟偑峏怴偝傟傞偺偼丄傎偐偱傕側偄偙偺巹偵偍偄偰偱偁偭偰丄偦傟傕丄偡偱偵弌棃偁偑偭偨乽擔杮暥壔偺揱摑乿側傞傕偺偑巹偵棟夝偝傟丄庴梕偝傟傞偲偄偭偨偙偲偱偼側偔偰丄傑偭偨偔怴偟偔丄偁傞偄偼揤抧奐钃埲棃乽偼偠傔偰乿偦偙偵巔傪偁傜傢偟偨偐偺偛偲偔峏怴偝傟傞丅婲尮側偒斀暅丄僆儕僕僫儖側偒僐僺乕偲偟偰偺乽擔杮暥壔偺揱摑乿乮亖乽晽夒乿傑偨偼乽嫊乿偺悽奅乯丅
丂傑偩偆傑偔尵梩偵偱偒傑偣傫偑丄偨偲偊偽丄乽榓壧偺廤憼屔乿偵廂傔傜傟偨帉偺夠傪峫偊偰傒傞偲丄偦偙偐傜屄乆偺榓壧嶌昳傪偦傟偲偟偰愗傝偩偡偙偲偼偱偒側偄偺偱偡偑丄偟偐偟丄偙偺僀儅僕僫儖側乽儁儖僜僫乿亖乽塺傒偮偮偁傞怱乿偵偲偭偰偼丄偦偺堦偮堦偮傪幆暿偡傞偙偲側偳偨傗偡偄偙偲偱丄偺傒側傜偢丄屄乆偺榓壧嶌昳偺偆偪偵帉偱傕偭偰憿宍偝傟偨嫊側傞姶妎乮僋僆儕傾乯傪捈愙抦妎偡傞偙偲偝偊偱偒傞丅偦傟偼偁偨偐傕丄巹偑乹巹乺偱偁傞偙偲傪恄側傜偽幆暿偱偒丄偺傒側傜偢恄偼傎偐側傜偸乹巹乺帺恎偱偁傞丄偲偄偭偨帠懺偲摍壙偱偁傞丅偦傫側偨偲偊榖偵偍偒偐偊傞偙偲偑偱偒傞偐傕偟傟傑偣傫丅
丂嬨婼廃憿乮亀乽偄偒乿偺峔憿亁寢榑乯偺岥暙傪傑偹偰丄乽奣擮揑宊婡偺廤崌偲偟偰偺乹儁儖僜僫乺偲丄乽堄枴懱尡乿偲偟偰偺乹儁儖僜僫乺偲偺娫偵偼丄墇偊傞偙偲偺弌棃側偄娫寗偑偁傞丅姺尵偡傟偽丄乹儁儖僜僫乺偺榑棟揑尵昞偺愽惃惈偲尰惃惈偲偺娫偵偼滲慠偨傞嬫暿偑偁傞乿側偳偲尵偭偰傒偰傕偄偄偱偟傚偆偑丄尵梩傪廳偹傟偽廳偹傞傎偳昞尰偟偨偄帠徾偺椫妔偑偁偄傑偄偵側偭偰偄偔偺偱丄傕偆偙偺偁偨傝偱傗傔偰偍偒傑偡丅
丂傂偲偮偩偗弎傋偰偍偔偲丄乽儁儖僜僫乿偼丄巹偺岅渂偱偼乽徾乿乮傕偟偔偼乽徰乿乯偵側傝傑偡丅乽峀媊偺乿掕壠榑棟妛偺摓払揰偼丄乮乽峀媊偺乿娧擵尰徾妛偺摓払揰偑乽僋僆儕傾乿偺尵岅壔偵偁偭偨偲偡傟偽乯丄偙偺尵岅揑惂嶌暔偱偁傞乽徾乮徰乯亖儁儖僜僫乿偵乽偄偺偪乿傪悂偒崬傒丄乽尰幚偺奜乿乮亖乽帺暘偺奜乿亖乽晽夒乿傑偨偼乽嫊乿偺悽奅乯偵偍偄偰乽徾乿偺悽奅偡側傢偪乽怷梾枩徾乿偺悽奅傪憿宍偡傞偙偲偵偁偭偨丅懞忋弔庽僆儕僕僫儖偺尵梩傪傕偪偄傟偽丄摗尨掕壠偺壧榑悽奅偼乽徾岺応乿偱偁偭偨偲偄偆偙偲偱偟傚偆偐丅乵仏乶
丂嵟屻偵丄亀悽奅偺廔傢傝偲僴乕僪儃僀儖僪丒儚儞僟乕儔儞僪亁偐傜丄徾岺応偲偄偆斾歡傪岅傞乽攷巑乿偺尵梩傪偄偔偮偐敳偒彂偒偟偰丄挿偔側傝偡偓偨掕壠曇傪暵偠傑偡丅
乵仏乶怱宧丄悽垻栱偐傜攎徳傊偄偨傞乽峀媊偺乿掕壠榑棟妛偺宯晥傪丄嬤尰戙暥妛偵媮傔傞偲偡傟偽丄怴挭暥屔亀愥崙亁偺夝愢偱抾撪姲巕偑乽僪儔儅偺寚擛偁傞偄偼晄昁梫乿偲乽儌僲儘乕僌偵嫆傞乿偲偄偆揰偱乽榓壧偵傛傝嫮偔宷偑偭偰偄傞乿偲彂偄偨愳抂峃惉傗丄乽朙閌偺奀乿偺屻偵偼掕壠傪彂偒偨偄偲惗慜塳傜偟偰偄偨嶰搰桼婭晇丄偦偟偰掃尒弐曘偑乽娽傪偙傜偟偰丄擔杮暥妛巎傪戝偒偔偲傜偊傞側傜偽丄拞悽偺悽垻栱偺擻偺昞尰曽朄傪堷偔偩偗偱側偔丄峕屗帪戙偺攎徳偺攐鎫偐傜傕偮傛偄塭嬁傪庴偗偰偄傞乿偲島択幮妛寍暥屔亀巰楈嘦亁偺夝愢偵彂偄偨忹扟梇崅傪偁偘傞偙偲偑偱偒傞偑丄懞忋弔庽乮偨偟偐亀奀曈偺僇僼僇亁偺崰偺僀儞僞價儏乕偱亀怴乆昐恖堦庱亁偵撉傒抆偭偨偲榖偟偰偄偨乯偼偙偺尷傝偱偼側偄丅
丂
乮俁俀崋偵懕偔乯
仛僾儘僼傿乕儖仛
拞尨婭惗乮側偐偼傜丒偺傝偍乯1950擭戙惗傑傟丅暫屔導嵼廧丅愮擭傕愄偵彂偐傟偨榓壧偺堄枴偑棟夝偱偒傞偺偼偡偛偄偙偲偩丅偱傕丄杮摉偵乽棟夝乿偱偒偰偄傞偺偐丅偦偙偵乽堄枴乿側偳偁傞偺偐丅偦傕偦傕尵梩傪巊偭偰壗偐傪揱払偡傞偙偲偦偺傕偺偑晄巚媍側尰徾偩偲巚偆丅
Web昡榑帍乽僐乕儔乿31崋乮2017.04.15乯
亙欶偲僋僆儕傾亜戞41復丂榓壧嶰懺偺愢丄掕壠曇劅劅儌僱丒偄偺偪丒徾岺応乮拞尨婭惗乯
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU丂2017 All Rights Reserved.
|
| 昞巻乮栚師乯傊 |