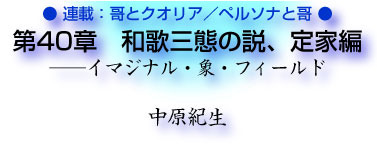|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「La Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
|
■音象、ネイロ、世界の影
前章の最後の節で、パンタスマ(虚象)の音楽的効果について簡単にふれました。今回はその補足、というかやや蛇足めいた話題から始めたいと思います。
大森荘蔵著『物と心』に収められた「無心の言葉」の冒頭に、時枝誠記の著書(『言語本質論』(『時枝誠記博士論文集』1))からの孫引きで、平田篤胤の次の言葉が紹介されています。「物あれば必ず象あり。象あれば必ず目に映る。目に映れば必ず情に思う。情に思えば必ず声に出す。其声や必ず其の見るものの形象[アリカタ]に因りて其の形象なる声あり。此を音象[ネイロ]と云う」(「古史本辞経」、ちくま学芸文庫『物と心』98頁)。
いま手元にある『国語学原論』総論第七節「言語構成観より言語過程観へ」の関連する箇所を拾い読みしてみると、時枝はそこで、「特定の象徴音を除いては、音声は何等思想内容と本質的合同を示さない。これを合同と考えるのは、音義的考[かんがえ]である。」と書き、先の一文を例示したうえ、「音声は聴者に於いて習慣的に意味に聯合するだけであって、それ自身何等意味内容を持たぬ生理的物理的継起過程である。音が意味を喚起するという事実から、音が意味内容を持っていると解するのは、常識的にのみ許せることである。」と書いています(岩波文庫『国語学原論(上)』108頁)。
時枝誠記の批判にかかわらず、五十音図の各行について「各々自然に意あり」とする平田篤胤の音義言霊の説はとても興味深いし、「事わざ繁き物なれば。見る物聞く物につけて。情その中に動きて。其の声種々に発る。然るは物有れば必ず象あり」云々とつづく前段の叙述も気になるところですが、ここで注目したいのは、「音象」の語であり、それに付された「ネイロ」というルビです。
私が「音象」の語にふれたのは、萩原朔太郎の『郷愁の詩人 与謝蕪村』が最初で、それはたとえば、芭蕉の「音楽的詩人」に対し蕪村が「絵画的詩人」と言われることに関して、「蕪村の技巧は、リリカルの音楽を出すことよりも、むしろ印象のイメージを的確にするための音象効果にあった」とし、「鶯のあちこちとするや小家がち」と「春の海ひねもすのたりのたり哉」の句をめぐって、「「あちこちとするや」の語韻から、鶯のチョコチョコとする動作を音象し、「のたりのたり」の音調から春の海の悠々とした印象を現わしている」と論じる際に用いられたものでした。
また、「和歌の韻律について」(『純正詩論』)では、「対比や重韻の構成からして、詩歌の内容する想を音韻に写した者は、即ち所謂「音象詩」である。」(筑摩書房『萩原朔太郎全集 第九巻』34頁)と定義したうえで、その最も成功したものとして「鵲[かささぎ]の渡せる橋におく霜の白きを見れば夜は更けにけり」を挙げ、この作品において重韻されたS音について「それ自ら霜夜の寒そうな感じがするので、内容の想と合って音象的効果を強くあたえる」(36頁)と評していますし、つづけて「きりぎりす鳴くや霜夜のさむしろに衣かたしき一人かも寝む」の重韻されたS音とK音が「固く冷たい感じをあたえる音であるから、この場合の音象として有効である」と書いているのです。
萩原朔太郎の「音象」は、音が与える印象を指しており、聴覚イメージの音楽的効果に力点をおいて用いられたものだといっていいでしょうが、私としてはこの語に、とりわけ「象」の概念のうちにいま少し実質的な意味合いを読みとりたいと思っています。そうすることで、定家の虚なる世界の実質をとらえる手がかりが得られるのではないかと直感するからです。
いまひとつの関心事である「ネイロ」から、私は、井筒俊彦の『意識と本質』を連想しています。それは、精確には、若松英輔著『井筒俊彦 叡知の哲学』に書かれていた事柄なのですが、若松氏はそこで、『意識と本質』以降、井筒俊彦は「コトバ」の一語を中軸にその哲学を構造化していった(221頁)と指摘し、次のように述べていました。「「コトバ」は、言語学の領域を包含しつつ超えてゆく。バッハは音、ゴッホは色という「コトバ」を用いた。曼荼羅を描いたユングには、イマージュ、あるいは元型が「コトバ」だった。」(222頁)「ネイロ」とは、井筒俊彦がいう意味での「コトバ」だった。私はそう考えています。
ところで、大森荘蔵が「無心の言葉」で論じているのは、「心で思うことを口に出し、耳に聞えたことを心で理解する」という「図柄」は、それがいかに自然なものに見えようと実はまやかしの自然さであり、そのような図柄は不可能であるということです。
この図柄は、知覚における「実物」とその「心像」、想起における(かつて存在した)過去の事象とその「影(記憶像)」などと同様、「物」と「心」の二元論的図柄に根ざしたもので、言語に関していえば、「物理現象」としての言葉と「内的個人的思想」としてのその意味(99頁)あるいは「世界の影」としての言葉の意味(121頁)の二項におきかえることができます。「物」の「象(スガタ)」すなわち「形象(アリカタ)」(あるいは、物としての言葉がもつ「音象(ネイロ)」)と「情(ココロ)」との対応を前提とする平田篤胤の音義説も、これを常識論として批判する時枝誠記の「心的過程としての言語本質観」も、ともに等しくこの「図柄」にもとづくものとして一蹴されるわけです。
大森荘蔵によれば、「心」もしくは「心の中」なるものはどこにも存在しません。「心」とは実は「世界」それ自身(107,109頁)にほかならず、「もし「心」なるものがあるとすれば、それは「ここにいる私」を包んで果てのない時と空間に拡がるこの全宇宙なのである」(116頁)。また、たとえば「恐怖の感覚」と呼ばれるものは、「心の内」などではなく五体やみぞおちのあたりにあり(117頁)、「感情、情念、気分、といったものはわれわれを含めた世界の状況の中にあるのであって、その世界から分離された、しかもべったり世界にまといつく「心」にあるのではない。われわれの生活は、無情の物質世界と有情の心的世界が不即不離にからみあったものではない。世界そのものが有情の世界なのである」(120-121頁)。
すなわち、ここには「言葉を解する、という一つのことがありそれを言語器官の動きと「理解」という心的過程とに引き剥がすことはできない」(122頁)のであって、「この緊密一体な状況の中に、「心」の壁をもちこんで何の機能も果たさないへだてを作る必要は毫もない」(123頁)。──以上が、大森無心論のエスキースです。そして、ここにこそ貫之歌論(貫之現象学)と定家歌論(定家論理学)とが重なりあう場所がある[*]、というのが私の見立てです。
[*]私の直感が指し示すところに従うならば、貫之現象学の世界と定家論理学の世界の感触の違いや相互に包摂しあう関係性は、永井均と大森荘蔵のそれぞれの哲学世界がもたらす感触の違いや相互の関係性とパラレルで、ちょうど今さしかかっているのが、永井均(と西田幾多郎)の哲学世界がオーバーラップする貫之現象学と、大森荘蔵(とウィトゲンシュタイン)の哲学世界がオーバーラップする定家論理学とが重なりあう場所なのではないかと思う。(それらはともに独我論的テイストに濃く染めあげられた世界であるが、その触感のようなものは、生と死、あるいは(クオリアに根ざした)アニミズムと(ペルソナにかかわる)シャーマニズムほどに異なっている。)
ちなみに私の構想では、永井(=貫之)現象学と大森(=定家)論理学からなる平行線に直交するもう一対の平行線を引くことができる。それは坂部恵(=木村敏)と井筒俊彦(=小林秀雄)の組み合わせからなるもので、この平行線が、「広義の」定家論理学の世界をかたちづくる連歌(心敬)、能(世阿弥)、佗茶(利休)、俳諧(芭蕉)の美的世界を解明するてがかりとなる。そして、坂部恵と井筒俊彦が共有する折口信夫と、折口信夫から「派生」する吉本隆明とがその補助線となる。さらに、坂部恵から九鬼周造と和辻哲郎が、井筒俊彦から西脇順三郎と萩原朔太郎がそれぞれ「導出」され、子規以後の「やまとうた」の精神史を彩っていく。
■意識と存在と言語の階層構造
貫之現象学と定家論理学が重なりあう場所。それは、「私が悲しいとき(私には)世界が悲しいように映る。」(永井均『西田幾多郎──〈絶対無〉とは何か』16頁)とか、「簡単に云えば、世界は感情的なのであり、天地有情なのである。」(大森荘蔵「自分と出会う──意識こそ人と世界を隔てる元凶」、『大森荘蔵セレクション』454頁)などと表現される世界のことだと言っていいでしょう。しかし、それではあまりに茫漠として掴み所がないので、話を限定します。
貫之現象学の極点にして定家論理学の起点となる場所、つまり「広義の」貫之現象学に包摂される「狭義の」定家論理学の世界。それは「有心(体)」の歌論の世界にほかなりません。「ひとのこころ」を種とする貫之歌論が定家の「有心(体)」に極まる、というわけです。この「有心(体)」については、以前、(第28章で)、井筒豊子の「意識フィールドとしての和歌」で論じられた、四つの次元にわたる「心」の階層構造にそくして考えたことがあるので、その簡略版を以下に再掲します。
【1】和歌における「心」の四層構造
Ⅰ 「心地(こころ)」=無分節・非現象
Ⅱ 「境(さかひ)」=今・此処という自照的存在(アヴィセンナの幽霊)の意識性
Ⅲ 「意識フィールド」=内的現象
(豗) 「思ひ」=意味的分節、内的言語
(豩) 「情(こころ)」=意味的無分節
Ⅳ 「言語フィールド」=外的現象
(豗) 「詞」=文字・音声言語、外的言語
(豩) 「余情」=無分節非形象
【2】有心と有心体
Ⅰ 「有心」(広義)
「意識フィールド」がじつは「境」の媒介作用を通じて現象展開したところの「心地」にほかならないこと。あるいは、「真の意味での」和歌的言語の創造主体は、「境」への遡行的志向性を通じて見出されるものでなければならないこと。
Ⅱ 「有心」(狭義)
「意識フィールド」における意識の展開(「思ひ」+「情」)と、「言語フィールド」における言語の展開(「詞」+「余情」)とを同定し構造的に直結させること。すなわち、「こころ(意識フィールド)」=「ことば(言語フィールド)」。別の言い方をすれば、「言語フィールド」における外的言語の成立に先行して、「意識フィールド」において内的言語が生起していなければならないこと。
Ⅲ 「有心体」(広義)
「意識フィールド」と「言語フィールド」とにまたがって、無分節的な「情⇒余情」の系統が意味分節的な「思ひ⇒詞」の系統よりも美的価値として上位に位置づけられること。
Ⅳ 「有心体」(狭義)
「言語フィールド」において、「詞」がもっぱら「余情」喚起の手段として機能すること。
以上が、「広義の」貫之現象学に包摂された「狭義の」定家論理学の骨格です。(ちなみに、この構図をつかって貫之現象学を定義すると、「広義の」貫之現象学は、「思ひ⇒詞」系列と「情⇒余情」系列をひとまとめにして組みこむ「こころ(心地)⇒ことのは(意識フィールド+言語フィールド)」、「狭義の」貫之現象学は「思ひ(世の中にある人の実感)⇒詞」、とそれぞれ規定することができる。)それでは、この「有心(体)」の構図のもとでの「心」の階層構造が、大森荘蔵の「無心の言葉・有情の世界」の説とどうかかわってくるのか。
ここで、「心=世界」という(大森無心論の)等式を投入します。すると、(和歌的言語創造をめぐる)歌論的主体性の現象展開構造に関する井筒豊子の議論は、これをそっくりそのまま世界の存在構造の議論に変換することができるでしょう。すなわち、世界は、超越的非現象の第Ⅰ領域と、この第Ⅰ領域を現象的時空につなぐ媒体となる第Ⅱ領域、深層的(非顕現的)現象界としての第Ⅲ領域と表層的現象界としての第Ⅳ領域の四つの領域からなる階層構造をなしている、といったぐあいに。
こうして、心の四層構造と世界の四層構造が重なりあい、相互に対応関係を切りむすぶ新しい図柄を得ることができました[*]。そして、これを「外」から、あるいは「パラ位置」(反対側、裏側)から一望するとき、この同じ「心=世界」の構図のもとで、かたや私が悲しいとき世界が悲しいように映り、かたや世界は感情的であり天地有情である、といった感触の違いが生じてくるわけです。
ここに、「存在はコトバである」という井筒言語哲学のテーゼを代入すると、「ココロ」と「モノ」と「コトバ」の三つの「レジスター」の重ね書きの構図が、いわばそれらの三位一体の関係性が見えてきます。この三つの階層構造が相互に対応しあう図柄を、『意識と本質』(岩波文庫、214頁)で井筒俊彦が導入した意識の構造モデルを参照して一般的なかたちで示すとすれば、それはおそらく次のようなものになるでしょう。目下のテーマである「狭義の」定家論理学が稼働する主舞台は、第Ⅲ領域、それも、外界に直接の対応物をもたない様々な「元型」イマージュ(217頁)の住処となるM領域にほかなりません。
【第Ⅰ領域】無の領域
【第Ⅱ領域】意識と存在のゼロ・ポイント
【第Ⅲ領域】深層領域(非顕現的現象界)=無意識《C》+言語アラヤ識《B》+中間地帯《M》
【第Ⅳ領域】表層領域(顕現的現象界)《A》
[*]井筒俊彦は『イスラーム哲学の原像』で、神秘主義の重要な特徴として次の三点を挙げている。第一に、現実(リアリティ)を「明るい白昼の光に照らし出された表層からいちばん下の底知れぬ暗黒の領域まで」を含めた多層的構造のもとでとらえること。第二に、これを認知する人間の意識のほうにも「表層から最深層に及ぶ垂直に重なった領域の拡がり」があり、しかも「客観的現実の多層と、主観的意識の多層とのあいだに一対一の対応関係が成り立っている」と考えること。(25-26頁)
ただし、ここで現実と意識、客体と主体を区別したのはあくまで理論上、そして神秘道における修行上の都合にすぎない。「渾然たる一体をなして、主とも客とも言い難い‘何ものか’こそが真の現実であり、また同時に意識なのであって、それがいろいろの次元で、いろいろの形で、いろいろの釣合いで現われるのである、というふうに考える」のが神秘主義本来の立場である。(27-28頁)
そして第三に、「意識の深い次元が開かれないかぎり、現実の深い次元はぜんぜん見えてこない」ゆえ、坐禅(禅宗)やヨーガ(ヒンズー教)や静坐(宋代儒者)や坐忘(荘子)といった修行によって「経験的次元で働く認識機能、つまり感覚・知覚・理性などとはまったく異質の認識機能」の発動をうながして「意識のあり方を変える」ことが必要になると考えること。(28頁)
■イマジナル、あるいは特別な意味でのイマージュ
貫之の「像、イマージュ、形」、俊成の「喩、フィギュール、姿」に対応させて、定家の世界を表現する概念の組み合わせを示すとすれば、それは「象、パライメージ、体」になるのではないか。そして、これを定家特有の「虚なるもの」の世界(「狭義の」定家論理学の世界)に限定して表現するとすれば、「イマジナル」×「象、パライメージ、体」=「虚象、パンタスマ、虚体」となるのではないか。私はそう考えています。
この後すぐふれるように、「イマジナル」は「創造的想像力」がもたらす「虚なるもの」(経験的事実性の裏打ちはないが架空のものでもない、存在論的根拠をもつ内的実在、たとえば「元型」イマージュ群が織りなす領域)を指し示す言葉です。これまで用いてきた「虚象、パンタスマ」は、イマジナル・フィールド(M領域)を本来の住処とする象、というその出自を強調した語であったと言うことができるでしょう。
それでは、以下、「イマジナル、象、体」のそれぞれの項目についてラフスケッチを描いていきます。(いずれ取り組むつもりの、本格的な定家論理学の考察に向けた素材集として。)
◎「イマジナル」の語の由来について、井筒俊彦は『イスラーム哲学の原像』や『意識と本質』で次のように述べている。
イスラームの神秘家スフラワルディーは、シャーマン的イマージュ空間を指して「アーラム・アル・ミサール」と呼んだ。「ミサール」とは神話的・深層意識的な「元型、アーキタイプ」もしくは元型から生起する「根源的イマージュ」のこと。すなわち「アーラム・アル・ミサール」とは「根源的イマージュの世界」(『イスラーム哲学の原像』119頁)あるいは「形象的相似の世界」(『意識と本質』(201頁)。
これをアンリ・コルバンがラテン語訳して「mundus imaginalis」(ムンドゥス・イマジナリス)とし、この「imaginalis」をそのままフランス語にして「imaginal」という形容詞を造語した(『意識と本質』201頁)。「架空の」という否定的な意味傾向の強い「イマジネール」(imaginaire)ではなく、「特別な意味でのイマージュ」にかかわる「イマジナル」(imaginal)。
◎イマジナルな世界。それはコルバンが「創造的想像力」と呼び、ふつうの想像力(「何もないところに幻想的な形象を生み出していく根拠のない想像力」)と区別した「特別な意味」での想像力、すなわち「存在論的根拠のある想像力」(『イスラーム哲学の原像』120頁)がはたらく領域である。
井筒俊彦は『意識と本質』(244頁ほか)で「イマジナル」を鉤括弧付きの「想像的」の語で言い換えているが、「創造的想像力」をつづめて「創像力」という語を造り、「イマジナル」に「創像的」という訳語をあてていいかもしれない。しかし、それだと「創造」の語から汲みとるべき神学的ニュアンス(「新創造」や「創造不断」といった)が影を潜めてしまう。
井筒俊彦(『コーランを読む』)によれば、『コーラン』の言語テクストは「レアリスティック/イマジナル/ナラティヴ」の三つのレトリックの層からなる。これを「発展史」から見ると、初期=「イマジナル」なレベル(酔った意識)、中期=「ナラティヴ」なレベル(醒めかけた意識)、後期=「レアリスティック」なレベル(完全に醒めきった意識)となる(222頁)。これら三つの層は三重構造としてモデル化することができるが、その際、「イマジナルなレベルが、時間的には一番始めに出てきて、構造的には一番下にある」(245頁)。
若松英輔氏は『イエス伝』第一章(12頁)で、井筒俊彦の「三重構造」のモデルを次のように紹介している。
「一つ目は、「事実的〔realistic〕」な層
二つ目は、「物語/伝説的〔narrative/legendary〕」な層
三つ目は、「イマジナル/異界的〔imaginal〕」な層」
私は、ここにあらわれた「異界的」の語が、イマジナルの訳語としてふさわしい場合があるのではないかと思う。(「異界的」の語は、『叡知の詩学 小林秀雄と井筒俊彦』第七章(118頁)にも見られる。)
◎井筒俊彦は元型と元型イマージュについて、ユングに拠りながら次のように解説している(『意識と本質』Ⅸ章)。
元型とは「一定の方向性をもった深層意識的潜在エネルギー」(206頁)であり、「この無形、無相の内的実在の基本的方向性が、形象化して現われたものが「元型」イマージュである」(206-207頁)。たとえば易の八卦は「その一つ一つが、それぞれ独自の方向に向っての顕現可能性をもったエネルギー体」(同210頁)であり、多様な「イマージュ的自己顕現の可能性」(211頁)を内蔵した元型である。
顕現に向けた基本的な方向性とエネルギーの量・度合・強度によって定義される元型。それは「ベクトル」の概念でとらえることができるかもしれない。そうだとすると、八卦、六十四卦の様々な元型群や「元型」イマージュ群が生起し躍動する領域は「元型ベクトル場」などと表記することができるかもしれない。(この元型ベクトル場は深層における「意味分節体」の生成場であり、井筒豊子が言うところの「意識フィールド」そのものである。「場、フィールド」すなわち「体」。)
◎かの「意識の構造モデル」に関連づけると、元型は深層意識のB領域すなわち言語アラヤ識に成立し(215頁)、「元型」イマージュは深層意識のM領域(A領域=表層意識とB領域=言語アラヤ識との間にひろがる中間地帯)を本来の住処とする(218頁)。
「絶対無分節者の存在エネルギーは、言語アラヤ識(「文化的無意識」)の次元で第一次的に分節されていろいろな意味分節体となり、その中のあるものは「元型」として強力に自己を主張する。そして「元型」は次の段階で形象化して「元型」イマージュとなる。それらの「元型」イマージュは諸多の「想像的」イマージュとともに、一種独特の深層意識的イマージュ空間を現出する。」(『意識と本質』247-248頁)
ここで言われる「一種独特の深層意識的イマージュ空間」こそ、「一種独特の「想像的[イマジナル]」空間」(244頁)すなわち意識のM領域にほかならない。そして、この意識(と存在と言語)のM領域において、「イマジナルの現象学」すなわち「虚象の現象学」(貫之現象学)と「イマジナルの論理学」すなわち「虚体の論理学」(定家論理学)が邂逅する。
◎永井晋氏は「イマジナルの現象学」(『現象学の転回──「顕現しないもの」に向けて』第七章)で、「無限の現象性としてのイマジナルの構造」と井筒俊彦による「分節化」のモデル(『意識と本質』144頁)とを重ねあわせて論じている。そして、「分節Ⅰ(表層の現象性)⇒絶対無分節⇒分節Ⅱ(深層の現象性)」の三段階を経て意識と世界が変容するプロセスの最終段階である「分節Ⅱ」を「イマジナル」な次元に位置づけている。つまり「元型」イマージュ=「分節Ⅱ」。
ここで注意しなければならないのは、井筒俊彦の分節理論は本質否定論の立場に立つ禅思想にそくして導き出されたものであり、したがって「分節Ⅱ」=「無「本質」的分節」であるのに対して、「元型」とは「人の深層意識領域に、根源的イマージュの形で自己を開示する」(213頁)ところの「本質」であり、したがって「元型」イマージュもそのような意味での「有「本質」的分節」(「意味分節体」もしくは「根源的存在分節」(247頁))の形象化であるということだ。
この「矛盾」は、禅が否定する「本質」は表層意識的な抽象的・概念的普遍者であり、これに対して、元型的な「本質」は具体的・象徴的普遍者のことである(245-246頁)、といったかたちで折り合いをつけ、「元型」イマージュ=「分節Ⅱ」という永井説を「救済」することができる。[*]
◎永井氏はまた、「深層のイマジナル次元」にあっては「AはAであってBではない、という同一律と矛盾律というアリストテレス的論理の基本原理」は通用せず、「AはBにもCにもなりうることが可能である」と論じている(『現象学の転回.174-175頁』)。この「イマジナルの論理」は「分節Ⅱ」の論理であり、また「生きたるもの」の論理、すなわち「あいだ」の論理でもある。
木村敏氏は『からだ・こころ・生命』で、「生命そのもの」と個々の生きものとの差異(ハイデガーのいう「存在論的差異」と同一の論理構造をもつ「生命論的差異」)こそが、生きものを「主体」たらしめている主体性なのだと語っている(37頁)。
◎井筒俊彦によれば、スフラワルディーは「イマジナル」な次元のイマージュ(根源的イマージュ、「想像」的イマージュ、「元型」イマージュ)のことを「質料性(あるいは経験的事実性)を離脱した似姿」とも「宙に浮く比喩」とも呼んだ。
ここで「似姿、アシュバーハ」の元来の意味は「砂漠で、遥か遠方に現われるものの姿」(蜃気楼、ミラージュ、つまりパンタスマ)。また「比喩」とは言語表現上のレトリックではなく「存在レトリック的な意味」での比喩のこと。「つまり、「比喩(メタポラー)」の原義通り、存在次元の「移し」によって、物質的、質料的な経験界の存在次元から、非質料的存在次元に「運び移され」て、そこで異次元的に、「宙に浮いて」いる存在者である。」(『意識と本質』203頁)
質料零の似姿、あるいは宙に浮いた比喩存在、すなわち象。言語アラヤ識に発し、イマジナルなフィールド(M領域)を本来の住処とする象。「易の記号体系の基である「象」が、三画の爻からなる八卦も、六画の爻からなる六十四卦も、すべて前述したスフラワルディーの「似姿」「比喩」であり、要するに「元型」イマージュであることを、我々は知る」(『意識と本質』209頁)。
[*]厳密には、そもそも「分節Ⅱ」と「元型」イマージュとではその現象する場面が異なる。前者は表層のA領域を本来の出現場面とし、後者は深層のM領域を本来の住処とする。
井筒俊彦がここで語っていることがらのうち、「仏教の蓮の花」が前者、すなわち「分節Ⅱ」=「無「本質」的分節」の具体例であり(「仏教のイマージュ空間に咲く花は、現実の花に「似ている」だけであって、現実の花の‘じか’のイマージュではない。」(218頁))、非即物的イマージュと言われているのが後者、すなわち「元型」イマージュである。
また、これに関連して、「禅を無彩色文化だとすれば、密教は彩色文化だ」とする説をめぐって、井筒俊彦は次のように語っている。
ここのところを読みながら、私は、かの「ネイロ」という言葉を連想している。音の「象」(スガタ)である「音象」(ネイロ)は、音、声という「元型」イマージュが発散する存在エネルギーの感覚化、すなわち「コトバ」である。
■象と虚象、あるいは存在の裏側
◎「存在には裏側がある」と井筒俊彦は言う。「存在の裏側、存在の深層領域」と。存在の裏側、反対側、つまり「パラ位置」を住処とする像(イマージュ)、すなわち象(パライメージ)[*]。
◎藤田一美「想像」(『講座美学第2巻』)によると、「現象に従ってそのつどの象の刻印としての印象を受けとる表象と、さまざまな印象を素材としつつも自己の個体的偏差をもって新たなる像を創り上げる想像とは明らかに区別されねばならない」(163頁)。
すなわち、「直接的な原体験の相関者としての存在の象」(167頁)と「像」はその「存在論的位相」が決定的に異なる(168頁)。象の地平を歴史的地平と呼ぶとすれば、像の地平は非歴史的地平である。われわれは想像の自由に拠って、前者から後者へ移行する。すなわち想像とは「象の像化」(168頁)であり、「無の地平に存在を喚起し像を現出せしめようとする創造作用」(181頁)なのである。
そして、リルケにとって創造(芸術)とは「必然的な出会いを求めて作品から恣意と偶然を奪い去りそのものの固有の確かな場所」つまり「像が象となる究極の場」を確保することであった(182頁)。「詩人の像は神の象[イマーゴー]」(183頁)なのであり、「詩人はやはり何ものからか存在の象を自らの像として受け取る」(183-184頁)のである。「すなわち想像はなんらかの啓示を介して表象となると言ってよいであろう。」(184頁)
「象の像化」(能動)から「像の象化」(受動)へ。
◎それでは「自己ならざる他者への成り入り」についてはどうか。「想像によって自己としての他者と成ることはできても本来自己ならざる他者と成ることはできないのであろうか。」(185頁)
ここで藤田氏は世阿弥の「先能其物成、去能其態似」(『花鏡』)や禅竹の「像輪」(『六輪一露之記』)に言及し、「像」とは「其物成」(そのものに成り入ること)であり、その極においてこの私は他者へと変貌すると論じる。其物成としての像の可能性について世阿弥は慧能の偈「心地含諸種」を引用しているが、ここで言う「諸種」とは「あらゆる人格[ペルソーナ]とその情[こころ]の可能態」(190頁)なのであって、「もしわれわれの心があらゆる可能性を含む根源的な可能態としての心地の性格をもたないとしたら」、「心の赴くままに他者へと自由に同化してゆくこととして想像を考えることはやはり背理としか言えないであろう」(190頁)。
◎存在の裏側とは他者(その極において死者)が生きる世界である。生と死、作者と役者、オリジナルとコピー、一と多、内と外、主と客、我と汝、自我と自己、等々の相異なるものが連結され並置される「場、フィールド」すなわち「体、フィールド」。そしてこの「生きたるもの」としての「体」から無数の「象」が立ち現われる。「象」とは「生きたるもの」の「はたらき」の別称である。そして、奇妙な言い方になるが、虚象とはおそらく異界における「死せるもの」の「はたらき」の異称である。
(「生きたる者」もしくは「死せる者」の「ペルソナ」から無数の「肖」が立ち現われる、「肖」とは「生きたる者」もしくは「死せる者」の「はたらき」の別称・異称である、などということが言えるかどうか。それが言えるとして、いったいなにを言っていることになるのか。)
◎井筒俊彦は『意識と本質』(224-225頁)で、深層意識領域(言語アラヤ識)における意味「種子」の本源的なイマージュ喚起作用を中心にする言語観をそのまま理論的に展開した大規模な言語哲学の典型的なケースとして、空海の阿字真言、イスラームやカッバーラーの文字神秘主義を挙げている。
コトバという形而上的存在(それを「虚体」と呼んでいいかもしれない)の「はたらき」が「象」として顕現したもの、それが「聲」(空海の場合)や「文字」(ユダヤ神秘主義の場合)、すなわち「虚象」である。
[*]イマージュ(像)とパライメージ(象)との関係を整理しておく必要がある。といっても、フランス語表記と英語表記の不統一といったことが問題なのではない。「像、イマージュ」といい「喩、フィギュール」といい「象、パライメージ」といっても、それらはいずれも「イマージュ」であると言えば言える。そこのところをどう整理するのかということである。(それは「形」といい「姿」といい「型」あるいは「体」といっても、それらはいずれも「かたち」と言えば言えるのをどう整理するかという問題と同根だ。)
■体と虚体、あるいはコトバがもたらす歓び
◎神谷幹夫「アンリ・コルバンの「創造的想像力」について」(『時の現象学Ⅰ』)によると、アンリ・コルバンの「イマジナルな世界」論は「独自な宇宙生成論」である。
◎「生きたるもの」の「ベクトル場」すなわち「体、フィールド」。異なるものが連結的に共在する場(フィールド)。
歌体、伝導体の「体」。言語フィールド、意識フィールド、認識フィールドの統合体。「イマジナルな体」すなわち「虚体」。異なる観念、概念に同一性をもたらす場。「生きたるもの」としてのコトバの領域。そこから立ち現われる「イマジナルな象」すなわち「虚象、パンタスマ」としての聲と文字。
◎若松英輔氏は『叡知の詩学 小林秀雄と井筒俊彦』で、「コトバを考える井筒の態度はまるで、生けるものを扱う職人のような姿をしている。」(3頁)と書いている。
「彼にとってコトバは生ける意味の顕われだった。生けるとは比喩ではない。彼の眼に万物は、うごめく意味の塊りとして認識された。コトバは無数の姿をもって意味を表現する。作家が言葉で語るように画家は色で、音楽家は音で、彫刻家にとってはかたちがコトバである。鳥のさえずりさえ、コトバであると井筒は書いている。」(『叡知の詩学 小林秀雄と井筒俊彦』4頁)
◎「音象、ネイロ」は「生ける意味の顕われ」である。言語フィールドにおける象(すなわち意識=存在(認識)フィールドにおける「元型」イマージュ)としての聲と文字がそうであるように。
そして、コトバの「はたらき」がもたらすのは生きる歓びである。[*]
[*]体のこと、虚体の概念は、まだ見極めがつかない。準備が足りない。それが「生きたるもの」もしくは「死せるもの」であること、そこは異質なもの、異類、異次元が共在する場所であること、そこから立ちあがる象はそのような体や虚体の「はたらき」そのものであること、そして象もしくは虚象がもたらすのは「生きる歓び」もしくは「死せる歓び」のごときものであること、等々は本文に素描したとおりだ。
これらの詳細については、いずれ哥の伝導体の、いや哥にかぎらぬ伝導体一般の理論の精緻化にとりくむなかで、(前節の註に書いた事柄も含めて)立ち入って検討することになると思う。
(31号に続く)
★プロフィール★
中原紀生(なかはら・のりお)1950年代生まれ。兵庫県在住。千年も昔に書かれた和歌の意味が理解できるのはすごいことだ。でも、本当に「理解」できているのか。そこに「意味」などあるのか。そもそも言葉を使って何かを伝達することそのものが不思議な現象だと思う。
Web評論誌「コーラ」30号(2016.12.15)
<哥とクオリア>第40章 和歌三態の説、定家編─イマジナル・象・フィールド(中原紀生)
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2016 All Rights Reserved.
|
| 表紙(目次)へ |