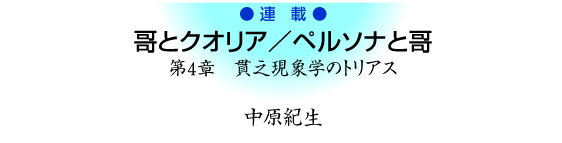|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「La Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
|
■逆倒的な視野構成 土左日記一月一七日のくだりに、明け方、「雲の上[の月と空]も海の底[に映じた月と空]も同じごとくになむありける」なかを、停泊中の室津から五日ぶりに船を漕ぎ出した際、唐代の詩人賈島の詩句「棹は穿つ波の上の月を、船は圧[おそ]ふ海のうちの空を」を下敷きとして、「ある人」つまり紀貫之が詠んだ歌二首が出てきます。そのうちの一つ、後句「船は圧ふ」云々を踏まえた歌は、 影見れば波の底なるひさかたの空漕ぎわたるわれぞわびしき というもので、この歌について、大岡信氏は『紀貫之』で「貫之全作品中の秀逸の一つ」とし、「私はこの歌によって、貫之の歌の面白さに初めてふれた思いがしたのだった。理屈の勝った歌であるにはちがいないが、その理屈っぽさを越えて、ある「わびしさ」の息づく空間の広がりが感じられたのだ。」と記しています。 大岡氏は続けて、この歌がある種の空間的広がりを暗示しえているとしたら、それは水底に空を見るという逆倒的な視野の構成によるところが大きく、そこに、すなわち、そのような逆倒的な感覚のうちに、貫之のポエジーの原型的イメージがあるのではないかと推測しています。そして、古今集巻第一七雑歌上に収録された「二つなきものと思ひしを水底に山の端ならでいづる月影」等々、貫之における「水に映るもの」のモチーフに注目した実例をいくつか抄出し、貫之晩年の屏風歌、たとえば「藤波の影し映ればわが宿の池の底にも花ぞ咲きける」などに見られる陳腐で低調な繰り返しに堕した作品に比べて、同じく晩年に書かれた土左日記中の「影見れば」の作が清新さをたたえているのは、古今集には稀な「われ」の語がここに用いられ、その「われ」の孤独感が広い海原を背景として定着されているからだ、また、「唐の詩人の原作があって、それに乗せて歌ったときに、かえって「われ」の自覚が素直に表出されたというところに、創作心理の興味深い秘密を見出しうるかもしれない。貫之という歌人は、そういう点に、ある問題性を感じさせるところをもっている人なのだ。」と述べています。 そうした議論を経た上で、大岡氏は、「あるものを見るのに、それをじかに見るのではなく、いわば水底という「鏡」を媒介としてそれを見るという逆倒的な視野構成」のうちにこそ、貫之という歌人がもたらした新風が、すなわち、水と空とがたがいにたがいの鏡となる詩的な仕掛け、より一般的にいえば、ある事物と別の事物が相互の暗喩(隠喩)となりうる詩的装置と、この装置に対して自覚的となった新しい詩的態度があるのではないかと指摘しているのです。
大岡氏がいう「逆倒的な視野構成」がもたらす感覚には、どこかしら夢の中の質感や体感を想起させるところがあります。『紀貫之』を読み進めていくうち、私はふと、そんなことを考えるようになっていました。そして、そういう目でもってあらためて「影見れば」の歌を眺めてみると、その(言葉の世界における出来事である)歌そのものが、なにやら夢の世界を描写したもののようにも思えてきたのです。 ■夢の言葉/言葉の夢 貫之の歌を夢の描写として読む。より精確には、夢から醒めた「われ」が夢の中のシーンを後から回想して言葉に託して詠んだ歌を読むという意味ではなくて、夢のあり様そのものを詠んだ歌として、あるいは夢の体験をライブでかたどる言葉として「影見れば」の歌を読んでみる。するとそこに、夢見られる「われ」と夢見る「われ」との分岐を見てとることができます。 ここでいう夢見られる「われ」とは、夢見る「われ」の夢の中に立ち現われる「われ」、具体的には「漕ぎわたるわれ」のことで、この意味での「われ」には、実は二つの様相があります。すなわち、水底に空を映した「海漕ぎわたるわれ」(実証的な「われ」)と水底に映った「空漕ぎわたるわれ」(修辞的な「われ」)。この二つの夢見られる「われ」が、「影見れば」の歌=夢の中で重ね描かれているわけです。 それでは、「影見れば」の歌における夢見る「われ」とはいったい誰のことかというと、それは「空漕ぎわたるわれ」という、夢の中の世界を構成する一事象がもたらす質感や体感(言葉を通してのみ実現する「逆倒的な視野構成」がもたらす感覚)を通じて、その外側にほの見えてくる「われ」、いいかえれば、夢そのものとしての言葉を歌のかたちにおいて詠みいだす主体のことにほかなりません。それが紀貫之という固有名をもつかどうか、あるいは自らを「われ」と名指す主体であるかどうかは、この際関係のないことです。 大岡氏が、「われ」の孤独感が広い海原を背景として定着されているというとき、その「われ」とは夢見られる「われ」のことではなく、したがって、水底に空の影の映発を見ている「漕ぎわたるわれ」その人ではなくて、そのような逆倒的な視野構成がもたらす感覚(純粋経験)そのものを夢見る「われ」、すなわち、夢としての歌を詠みいだす主体のことだと私は解釈しています。 ここで、新宮一成氏の名著『夢分析』の議論を一つ引いておきます。夢見られる「われ」と夢見る「われ」とをつなぐ「空漕ぎわたるわれ」の本性を考察するための有益な手がかりが、そこで得られると思うからです。 新宮氏は、「空は言語の場である」と書いています。それは次のような意味です。言葉を初めて話したときの、それ自体はイメージを伴わない感覚的成分として残された記憶が、「空飛ぶ夢」の運動の中で回復される。言葉を話せるようになるとは、自分を自分の外から見て、自分とはいったい何かを言えるようになることであり、夢の中の「空」は、このような過程に必要とされる純粋な「外側」として与えられている。また、空を飛びつづける夢は、死の象徴的表現になる。
大岡氏がいうように、貫之の逆倒的な視野構成(事物間の映発=暗喩関係)が言葉を通してのみ実現することであるとすれば、そして、新宮氏がいうように、言葉の世界が死の世界(あの世)に通じるものなのだとするならば、「影見れば」の歌に定着されている「われ」の孤独感とは、もとより歌人紀貫之がいだいた個別の特殊な心(内面の思いや感じ)をいうものではなくて、生者であれ死者であれ、およそ言葉を操るもの(言語的主体)のうちに宿る「孤心」、もしくは死の世界を覆う「しじま」のことだったのではないか。 また、無意識や神話とともに、夢もまた一つの言語活動(ランガージュ)として構造化されているのだとしたら、「影見れば」の歌のうちに息づいている「わびしさ」の背景をなす広い海原とは、(質料世界に対する)言語世界のことだったのではないか。さらに、ここでいう言語が私的言語であって、強いてそこに主語を立てるなら、「影見れば」云々という、そのこと自体が「われ」なのだとしたら、そのような夢見る「われ」(独在性の〈われ〉)の夢に包摂された夢見られる「われ」(単独性の《われ》)、すなわち「漕ぎわたるわれ」とは、貫之の場合、水の上に描かれた文字のことだったのではないか。 ……水底に映った広大な空の影(イマージュ)。空の高みが海の深みへと反転し、そうした超越的・垂直的で非人称的な寂寥(しじま)の世界へ向けて、失墜感とも上昇感ともつかない奇妙な浮遊感覚をもって「われ」は飛びつづけている。あたかも生命の営みから切り離された、純粋な言葉の世界を遊弋するかのように。その「われ」は一方で、海と空の中間領域(あわい)をなす水平面に立ち現われ、波に漂う頼りない小船を覚束ない身体感覚をもって操っている。あたかも水面に文字を刻みこむかのように。あるいは、「水に映るもの」すなわち仮名文字そのものとなって……。 夢見る「われ」(「空飛ぶわれ」=「空漕ぎわたるわれ」として、自らの夢の中にその存在の痕跡をとどめている「われ」)が詠む、夢そのものとしての歌。その夢の世界に包摂された夢見られる「われ」(「水に映るわれ」=「海漕ぎわたるわれ」)が刻む、夢の中の言葉の姿としての歌。「影見れば」の夢=歌のうちには、これら二つの歌の世界が重ね描かれています。 そして、後者のうちに前者が包摂されるとき、具体的には、「影見れば」の歌に描かれた世界(ある種の空間的な広がりを暗示している世界)が、夢見られる「われ」の内面における心象風景としてとらえ返されたとき、そこに、夢から醒めた日常的な言語の世界が、そういってよければ近代的な主体の世界がひらけていき、また、そのようにとらえ返された「影見れば」の歌の世界(内面における心象風景)のうちに、再び、夢見る「われ」の世界が、夢そのものとしての歌を詠みいだす主体の世界が見出されるとき、そこに、夢の中の言葉ではなくて言葉が見る夢の世界が、つまり、貫之の逆倒的な視野構成がもたらす詩的世界ではなく、定家の「詠みつつある心」(ペルソナ)が住まいする仮構の世界(物語世界)がひらけていくことになります。 (夢としての歌は、映画としての歌といいかえることができるかもしれない。その場合、大岡氏のいう「水底という鏡」は「スクリーン」と読み替えられることになる。あるいはまた、尼ヶ崎彬氏が『縁の美学』のあとがきで書いているように、芸術経験が、何事かを認識することではなく、自身がどこかに攫われるという意味での身体的経験であり、たとえば、音楽を聞くことが「音楽的時間という非日常的時間を生きること」であり、和歌を味わうことが「言葉の舞踏に引き込まれ、一足ごとに変容するイメージの旅を歩むこと」なのだとすれば、夢としての歌は、音楽としての歌、もしくは舞踏としての歌といいかえることができるかもしれない。) ■貫之現象学のトリアス 少し先を急ぎすぎました。貫之現象学における夢としての歌という主題に即して、以下、『紀貫之』の「古今集的表現とは何か」と題された章から、そのエッセンスと思われる箇所を二つ抜き出し、今後の議論のための若干の素材を蒐集することにします。 まずは、物と言葉との、ひいては物に寄せて(古今和歌集仮名序では、見るもの聞くものに「つけて」)言葉でもって表現された心との関係を、万葉の歌と古今の歌の表現形態の違いを踏まえて論じた文章から。なお、引用文冒頭の「こういう問題」とは、先に抜き書きした、「水という言葉と空という言葉が、ある種の幸福な条件のもとで、はじめて、ちょうど歯車があるときうまく噛み合うように、たがいにたがいの鏡となり、光と影の中で映発し合うのだ」に続けて、しかし、常にそれがそうなるというわけではないのは、貫之の作品において、同じ水底に映るものの影という装置を利用しながらも、それが(「影見れば」の歌のように)成功している場合もあれば、(「藤波の影し映れば」の歌のように)無意味である場合もあったことがその証拠だ、と書かれているのを指しています。
次に、縁語・掛詞の類を駆使した、優美繊細にして理知的な(千年の後、正岡子規によって「駄洒落か理窟ツぽい者のみに有之候」と貶められた)古今調のよってきたるところとその実質を、これも万葉調との関連において、かつまた新古今調への推移にも目配りをきかせながら説き及んだ文章。引用文冒頭の「それ」とは、その直前で取り上げられた、万葉末期の歌人大伴家持の「うらうらに照れる春日に雲雀あがり情[こころ]悲しも独しおもへば」という歌の左註に「凄惆の意、歌に非ずは撥[はら]ひ難きのみ。仍りて此の歌を作り、式[も]ちて締緒を展[の]ぶ。」とあるのを指しています。
これらの文章のうちには、貫之の歌の世界のマトリクス(母型)とでもいうべきもの、すなわち、万葉集的なものを経て歌の発生の現場へと遡行していくベクトルと、(おそらくは源氏物語の成立を経て)俊成・定家の歌の世界、新古今集的なものへと転換されていくベクトル、そしてこの二方向のベクトルの合成の上に現象する貫之固有の言語表現の特質が、それぞれ簡潔に素描されています。 それらはまた、貫之の歌を夢の言葉として読む際に心得ておくべき三つの切り口、もしくは貫之現象学の世界を特徴づける三つの徴候(トリアス)を示しているものと見ることができます。以下、その概略を覚書(というか、生の素材の切抜帳)のかたちで粗描しておきます。 ■哥というギフト 貫之現象学のトリアス、その一。 折口信夫は「国文学の発生(第四稿)」で、「うたの最初の姿は、神の真言(呪)として信仰せられたことである。これがしだいにつづまっていって、神人問答の唱和相聞[カケアヒ]の短詩形を固定させてきた。」と書いた。また、白川静は『詩経──中国の古代歌謡』で、「歌は呵する声」であるとし、「歌謡は神にはたらきかけ、神に祈ることばに起源している。そのころ、人びとはなお自由に神と交通することができた。そして神との間を媒介するものとして、ことばのもつ呪能が信じられていたのである。ことだまの信仰はそういう時代に生まれた。」と書いた。 高橋睦郎は『読みなおし日本文学史──歌の漂泊』に、こう書いている。「おそらくその発生において歌は神から人間への託宣だった。ただ神じしんは人間の聴覚に訴える発声器官を持たないから、人間がこれを代行する。これが神の言葉を語る口寄せとしての巫者(みこ・かんなぎ)で、その後裔が歌びととなる。歌びとはあくまでも神の代行者で、神の存在は歌の中にあると考えられたから、歌びとよりも歌の方が大切にされた。」 これらの証言からうかがえるように、〈哥〉はカミ(迦美)のギフト(純粋贈与)であり、カミとヒトの垂直的な交通=交流の媒体としての〈聲〉であった。しかし、それは「信仰」なのであって、貫之の「影見れば」の歌=夢において、「空漕ぎわたるわれ」のかたちでその存在の痕跡を(残像もしくは残響として)とどめた夢見る「われ」のように、カミは、物と心の直接的な一体化とパラレルな詞の力となってこの世に現象する。 森羅万象の事物が「事問う」アニミズムの時代と地続きの万葉歌人にとって、物すなわち「瞬間的な知覚の清新さ」としてのクオリアがそのまま「心緒」であり、その直接的な融合性・一体性を声としての言葉に詠みいだしたものが歌であった。ここでいう物(クオリア)としての心は、D.H.ロレンスが『黙示録論』で、「古代人の意識にとっては、素材、物質、いわゆる実体あるものは、すべて神であった。」、「水に触れてそのつめたい感触にめざめたとするなら、その時こそまた別の神[テオス]が、《つめたいもの》としてそこに現象するのである。」と書いている、そのテオスに相当する。 レヴィ=ストロースは、『生のものと火を通したもの』の「序曲」に、生のものと火を通したもの、新鮮なものと腐ったもの、湿ったものと焼いたもの、等々の経験的区別が概念の道具となり、さまざまな抽象的観念の抽出に使われ、さらにはその観念をつなぎ合わせて命題にすることができるようになるのはいかにしてかを示すこと、いいかえれば、「さまざまな感覚的なものに論理があること、そして感覚的なものの過程を跡づけ、感覚的なものに法則があるのを証明すること」が著書の目的であると記し、また、おなじ「序曲」のなかに次の一文を刻んでいる。
夢もまた神託であった。西郷信綱著『古代人と夢』に、「私は夢を信じた人々を、ここではかりに古代人と呼んでおく。」と書いてある。その古代人たちは、「夢は人間が神々と交わる回路であり、そこにあらわれるのは他界からの信号だと考えていた。」また、詩人イェイツが、詩は目覚めたトランス(夢幻の境)であるといったように、古代人にとって、夢は一つの独自な「うつつ」であった。 今昔物語に、「太子、斑鳩ノ宮の寝殿ノ傍ニ屋ヲ造リテ夢殿ト名付ケテ、一日二三度沐浴シテ入リ給フ。明クル朝ニ出デ給ヒテ、閻浮提ノ善悪ノ事ヲ語リ給フ。」とある。そのような「夢託」を乞うて聖所にこもることを、古代ギリシャ以来、西欧では「インキュベーション」(孵化、巣ごもること)と呼び習わしてきた。聖所とは洞窟であり、夢殿もまた洞窟である。洋の東西を問わず、おそらくは石器時代以来の古い伝統に根ざしている「洞窟信仰」において、人はカミとの交信を果たし、自らの再生を果たし、死者の魂との交流を果たしたのだ。 西郷氏は「古代人の眼」の章の末尾に、「私は死者の魂の遊行を正目に視たであろう古代人の視覚の独自性を取り出してみようとしたまでである。彼らに、夜寝たときにみる夢が一つの「うつつ」として受けいれられ、強い衝撃をあたえたのも、また彼らが神話という幻想的な文化形式を作り出したのも、視覚のこの独自性と関連しあっているであろう。」と書いている。ここでいわれる「古代人の視覚」は、かの「逆倒的な視野構成」を想起させる。そうした視覚をもたらす「洞窟」での体験を通じて、人は(言語的主体として)もう一度生まれなおすのである。 ■フィギュールとしての哥 貫之現象学のトリアス、その二。 藤原俊成の『古来風躰抄』に、「歌はただよみあげもし、詠じもしたるに、何となく艶にもあはれにも聞ゆる事のあるなるべし。もとより詠歌といひて、声につきて善くも悪しくも聞ゆるものなり。」とある。大岡氏は『紀貫之』で、歌合わせ最盛期における歌界の第一人者俊成が、歌のよしあしの判定にあたって声に出して詠じてみる方法をとったのは、「歌の価値を理智的に弁別し、技巧的に分析してあげつらうことの弊害を正そうとする、はっきりした思想を抱いていたこと」によるのであって、歌の姿もしくは歌の美をめぐる「何となく艶にもあはれにも」を曖昧な物言いととったら誤りなのだとしている。 ここでいわれる「歌の価値を理智的に弁別し、技巧的に分析してあげつらうことの弊害」とは、「歌というものを、言葉の技術の練磨によって、いかようにも磨きあげることのできるものと考える」立場、あるいは、「歌というものに分析的、批評的、構成的態度で接してゆく」立場が、ゆくゆくもたらすことになるもののことにほかならない。しかし、古今集の歌人たちにおいて、歌というものに対するそうした修辞的な態度がどのような意味合いをもつものであったかを考える場合、それも貫之にとっての「言葉の技術の練磨」とは何だっかという問題を考える際に、当時、生成途上にあった仮名文字の存在を抜きにすることはできないだろう。 石川九楊氏は『ひらがなの美学』で、掛詞がなぜ古今和歌集の特徴的なレトリックとしてあるのかといえば、それはまさに(ほぼ女手=平仮名だけを使い、しかも、万葉仮名とは違って濁点を付さずに清音表記された)「書字の姿」に根拠があったと述べている。そして、「秋」に「飽き」を、「松」に「待つ」を掛ける類の掛詞が、書における書きぶりのうちに反映しているものを「掛字[かけじ]」と呼び、また、一般に連綿(つづけ書き)の際の技巧の一種とされてきた、前の字の最終筆と後の字の第一筆が連続する筆画の二重化を「掛筆[かけひつ]」と概念化している。
石川氏がいう「歌の意味の複線化」は、小松英雄氏が古今調の本質とした、和歌の複線構造による多重表現の説を踏まえている。その小松氏との対談(前掲書)で、石川氏が、万葉集から古今集の間に「声の歌」から「文字の歌」への転換が起こったと述べているのも、『みそひと文字の抒情詩』での小松氏の次の議論と呼応している。
聴覚の短歌(万葉集)から視覚の和歌(古今集)へという小松=石川説と、「歌はただよみあげもし」云々という先の俊成の言葉とを組み合わせるならば、そこから、貫之固有の言語表現の特質を示す一つのキーワードを導きだすことができる。すなわち、〈哥〉=ギフトから発するカミの〈聲〉、そして歌合わせという場に唱和相聞する朗詠の声(もしくは「物」としての歌がはらむ幽玄の響き)、その二つの声の間に介在する歌の姿=フィギュール(詞姿)としての仮名文字。それは、かの「影見れば」の歌=夢において、「空漕ぎわたるわれ」との修辞的な重ね描きのうちに夢見られる「海漕ぎわたるわれ」が水面に刻み込んでいる軌跡、つまり夢の文字のことにほかならない。 ■夢の中の文字 夢の中の文字は、読めない。 矢口浩子・新宮一成著「かなと精神分析」(叢書・想像する平安文学第5巻『夢そして欲望』)に、石牟礼道子氏(「夢の中の文字」)が「生まれることができないその文字は、わたし自身であるらしい。」と記した、川底から浮かび上がる「解読できない毛筆の文字」の夢の経験をめぐる考察がある。
佐々木孝次氏の「リチュラテール――ラカンの「日本」」(『文字と見かけの国』)での議論を援用するなら、ここでいう「文字」は、漢字やアルファベットのような体系的な文字のことではない。それらが作られるよりもっとずっと前からすでにあった「印し、痕跡、しみ、きず、などといった文字」のことである。それはまた、無意識の素材であって(「無意識とは文字である」)、シニフィエ/シニフィアンの二項関係のうちにとらえられるものでもない。シニフィアンが「象徴界」の近くにあるのに対して、文字はその有形的な物質性によって「現実界」の近くにある。
この「意味から無意味に向かう」フィギュールの運動は、「洞窟」的なイメージの活動でもある。 中沢新一氏は、「あらゆる宗教現象の土台をなしている人類の心の構造というものが、今日私たちが楽しんでいる映画というものをつくりあげている構造と、そっくりだという事実」の確認から始まる集中講義「映画としての宗教」の特別篇(「洞窟の外へ――TVの考古学」)で、「ディスクールが主に情報の経済的な伝達をめざすコミュニケーションの行為であるのにたいして、フィギュールはむしろ情報の経済的伝達を阻害したり歪曲したりする、非コミュニケーション的な表現行為です。旧石器のホモサピエンスが洞窟内に描き残したイメージ群は、あきらかにこのうちのフィギュールとしての特徴をそなえています。」と語っている。 中沢氏がいう「旧石器のホモサピエンスが洞窟内に描き残したイメージ群」は、次の三つのグループに分類される。 第一群。現実世界に対象物をもたない抽象的イメージ。もしくは非物体的かつ唯物論的な直接的イメージ群。それらは内部光学[entoptic]と呼ばれる現象(「無から無へ」向かうイメージの氾濫、素粒子のようにはかない精霊たちの立ち現われ)がヒトの心の内側に開く超越的領域にかかわる。映画の構造として見ると、このレベルのイメージ群は底なしの暗闇に向かって映写される。そこにはスクリーンにあたるものが欠けている。 第二群。動物やヒトを具体的に描いた具象的イメージ群。ヒトの認知能力を超えた領域に触れている第一イメージ群の「おそるべき力」(ヌーメン)が現実の物質的世界との境界面に触れたときに意味が発生する、その(「無から有へ」向かう)垂直的な運動の過程を保存しようとしているのがこの第二イメージ群である。それは同時に記号的世界の発生をも意味している。これらのイメージは洞窟の壁画をスクリーンとして映写される。 第三群。垂直的な意味発生のプロセスによってあらわれてきた具象的イメージを(「有から有へ」とメタモルフォーシスをくり返す横滑りの運動によって)水平的に結合し、物語(神話やイデオロギー)を通じてこれを統御するイメージ群。こうして第二群のイメージを組織的に組み合わせた「娯楽映画」が発生する。身体(三次元の動くスクリーン)が演じる儀礼が発生する。 洞窟壁画の世界は、これらのイメージ群が層状に積み重ねられてつくられている。表面に近い層では言語的コミュニケーションに適したイメージ群が全体を覆い、その直下には非言語的・非表象的な別のイメージ群が活発な働きを行っている。こうした構成をとらえて、中沢氏は、旧石器の洞窟画の本質を「フィギュール」として理解する。
中沢氏によると、こうした「フィギュール=洞窟」的活動は、誕生以来変わらぬ人類の「心」のトポロジーに基づくものであり、また、旧石器のホモサピエンスによって発明された「結社=組合」(アソシエーション)も、フィギュール化された社会にほかならない。結社=組合の成員は、洞窟でのイニシエーションを通じて、古い個体としては死に、新しい主体としてのよみがえりを果たす。(中沢氏がいう「フィギュールとしての主体」は、尼ヶ崎彬氏が「詩的主観」と呼んだ俊成の「歌の道の深き心」を想起させる。)
■哥のパランプセスト 貫之現象学のトリアス、その三。 貫之の歌が視覚的な表現物であること、そしてそれが、清音と濁音を書き分けない音節文字の体系として、平安初期に成立した仮名文字の特質を巧みに利用し形成された「複線構造による多重表現」によるものであることは、小松氏の指摘する通りであるとしても、それでもやはり、大岡氏がいうように、「古今集の歌が、目で読むよりは、耳で聞いた方が際やかな印象を与える」こと、それも、「万葉集の歌は、大胆に括っていえば、リズムと旋律の鮮やかさによって私たちの耳をうつのに対して、古今集の歌は、和声法的効果によって私たちの耳に染み通ってくる」といわれるときの、その「和声法」的効果(語感としては、声の重ね描きによる「多声法」的効果)において「際やかな印象」を与えるということに、実感として疑いをはさむことはできない。
フィギュールとしての歌は、おそらく、視覚・聴覚といった感覚のモダリティを超えた場所に、つまり、諸感覚が重ね描かれたパランプセストの上に成り立つのだろう。パランプセスト、もしくは共感覚の基体となる「原身体」とでもいうべき場所。 そこはまた、音楽の経験、つまり時間性の経験が成り立つ場所でもあるだろう。「ある音楽的な持続する流れの感覚」のうちに、過去・現在・未来の時間様相が重ね描かれたパランプセスト。あるいは、『かたり──物語の文法』での坂部恵氏の表現を借りれば、「もはや二度と呼び返すすべのない既定性と、一種魂の故郷の味わいをもった神話的なアウラを帯び、通常の記憶ないし思い出を絶してそれらとは別の秩序に属する〈インメモリアル〉な時の後光をなにほどかうけながら、集団や個人の心性のうちに生きたままよみがえる」記憶、いいかえれば、ベルクソンが「純粋想起 souvenir pur」と呼んだ記憶が住まいする場所。レヴィ=ストロースが『野生の思考』で、オーストラリア先住民の聖具(チュリンガ)に託して語った「純粋歴史」に触れる場所。 そして、その場所には、フィギュールとして生まれ変わった新しい主体が、すなわち、虚構世界に住まう複数のペルソナの心が重ね描かれていくことにもなるだろう。(複数の歌が重ね描かれる、といってもいい。大岡氏が、貫之の「影見れば」の歌について、賈島の詩句に乗せて歌ったときにかえって「われ」の自覚が素直に表出される、そういう点に貫之という歌人の問題性があると述べた、その「問題性」とは、もちろん、いずれは本歌取りのかたちで、中世歌人の「言葉の技術の練磨」の極点へといきつくことになるもののことだが、あるいはまた、時代を隔てて、文学が文学を生むモダニズム的なメタフィクションの文法とも呼応するもののことなのだが、ここでは、中沢氏の議論を援用して、「有から有へ」の水平的なメタモルフォーシスの終わりなき反復によって物語を生み出していく、洞窟壁画の第三群のイメージの機能になぞらえておこう。) 再び、坂部氏の言葉を借りる。「一言でいって、[詩的メッセージと科学の理論の]どちらも、特定の視点に拘束されぬ視点の複数性を一定の度合で確保することをそのねらいないし役割とするとはいえ、科学が特定の視点からはまったく自由ないわば〈無人称性〉(ないしより正確には〈無限人称性〉といったほうがよいかもしれない)をすくなくとも理想とするのにたいして、詩は、むしろ、逆に、(とりわけ、それが、演じられ、語られ、朗唱されることによって)、あくまでつまるところ人称的なものの時に神話的アウラを帯びたいわば生きた味わいをその生命ないし魅力のゆえんとしてもち、その意味で無人称でもあるいは一息に無限人称でもあってはならず、どちらかといえば、(〈かたり〉の〈緊張緩和〉の相関効果としての)〈多重人称〉(ないしわたくしがかつて使った表現でいえば〈原人称〉)をその発話の特質としてもつと考えられるのである」。その「多重人称」ないし「原人称」のペルソナ群が層状に積み重ねられ、自らフラクタル化していく場所とは、歌のパランプセストとしての物語世界にほかならない。 それは、見えないものを見させ、死者たちをして語らせる、(あたかも生き物のように自律した)言語の世界である。または、洞窟的なものの本質をなす「フィギュールの精神」のよみがえりとしての映画の世界でもある。鈴木一誌氏は、『画面の誕生』に収められた、ゴダールの『映画史』をめぐる「透過体」という文章の末尾に次のように書いている。
■夢の累層構造 大岡氏がいう、「流動しつづけ、ひたすら「像」を結ぶことを拒もうとしているかにみえる」貫之の歌の運動性は、フィギュールとしての仮名文字のうちにはらまれた「意味から無意味に向かう」運動によって支えられている。それは、「影見れば」の歌=夢において、夢見る「われ」との重ね描きのうちに夢見られる、もしくはその痕跡としての「空漕ぎわたるわれ」が担っているものであった。そして、この垂直方向の運動は、同様に「影見れば」の歌=夢において、「空漕ぎわたるわれ」との修辞的な重ね描きのうちに夢見られる「海漕ぎわたるわれ」が担っていた水平方向の運動と対立しつつ、その対立そのものを自らのうちに繰り込んだ(フラクタルな)運動へと糾われていく。 (ここで、「海漕ぎわたるわれ」が担う水平方向の運動は、具体的には、小松氏がいうところの和歌表現の複線構造による意味の多重性を生み出しながら、『みそひと文字の抒情詩』で、「和歌も和文も、事柄の一義的伝達を目的とする文体ではなかったから、ことばの自然なリズムを基本にして、先行する部分と付かず離れずの関係で、思いつくままに、句節がつぎつぎと継ぎ足される連接構文で叙述され、叙述し終わったところが終わりになる。それは、とりもなおさず、口語表現による伝達に共通する汎時的特徴にほかならない。付け加えておくなら、『源氏物語』が連接構文で書かれているのは、思いついたことをつぎつぎと書き足してできあがったからではなく、そういう構文として推敲された結果である。」と述べられた、その「連接構文」によって駆動される。) こうした垂直方向の運動と水平方向の運動の合成によって、夢見る「われ」と夢見られる「われ」とは、あたかもウロボロスのごとくに相互包摂を繰り返し、もしくは層状に積み重ねられて、「ある音楽的な持続する流れの感覚」とともに、いわば螺旋状に運動を反復し増幅していく。その終わることのない運動継続によって、中間性の領域とでもいうべきもの、もしくは境界領域がきりひらかれ、夢=歌が自らを変幻自在に変換(変身)するパランプセストの空間が多重に編まれていく。 その運動が垂直軸にそって巻きあげられ、極限の動としての静に達したとき、「春の夜の夢の浮橋」がとだえたあと、夢から醒めたあとにもなお続く、メタフィジカルで超越的な夢の世界の深み(高み)がもたらされ、水平軸にそって統合され、運動を停止したとき、こんどこそほんとうに夢から醒めた「われ」が、そして、その「われ」の内面の世界(歌人紀貫之の心象風景としての広い海原)が現象することになるだろう。 いま述べた中間性の境界領域、もしくはパランプセストの空間とは、先に使った語彙を用いるならば、共感覚の基体となる「原身体」であり、また洞窟の空間でもある。 港千尋氏は、『夢見る身体』に収められた「共鳴体──洞窟状意識と建築」で、身体を「流れ」という観点から眺め、これに似たものを自然界のなかに探してみると、いくつかの点で洞窟がイメージされてくると書いている。「洞窟は基本的に流れの産物である。…洞窟には方向がない。…洞窟にあるのはそこを流れる空気と水の方向であり、そしてまた非常にゆっくりと成長する結晶の方向である。」
洞窟とは身体であり、洞窟状の空間は無意識と呼ばれる。(それは、けっして「内面」と呼ばれるもののことではない。)そこでは、実はすべてが見えている。夢の中ではすべてが見えている。読めない文字でさえ、「書かれた跡として、読まれるべきものとして」、つまり文字として見えている。 また、夢は反復する。 新宮一成氏は『夢分析』で、夢の構造を「累層構造」と呼んだ。それは、ニーチェの思想史的継承者であるフロイトが発見し、レヴィ=ストロースによって「神話の構造」として応用されたものだ。「夢は、自分をとらえるために自分の外側の視点に立つという、いわゆる超越の契機を含むものである。…自己を越えでるためにこそ、夢の累層構造は形成されてゆくのである。」 累層構造は自己完結する円環=循環ではなく、基本的に反復の構造である。それは、「終わりの可能性を巧みに回避しながら自己増殖できる構造」であり、「ある意味構造が空間的構造において反復されていたかと思うと、時間的進行の中でも反復されたり、自己相似のモデルにそってフラクタル的に反復されたり、さらに、反復を見ている絶対的視点というものは用意されず、見ている主体が次の層では対象の立場に立ってしまうような視点の変換が起こるなど、さまざまな展開を含みながらなされてゆく反復」である。 夢の反復は、フラクタルな構造をなす。「この累層構造は、夢を語り合うということがなければ、決してつくられはしなかったであろう。」つまり、語る相手が存在しなければ、そして、語ろうという意志と語るための言語がなければ、夢はそもそも存在できなかった。我々の言語活動においても、フラクタルな入れ子構造は重要な位置をしめている。「他者の語らいを自己が取り入れて語り、それが再びどこかで他者の語らいに取り入れられるという形で、言語活動が動いている。夢を見たことを語るという我々の行為は、まさに世界の言語活動の本質を集約しているといって差し支えないだろう。」
新宮氏がいう「夢の語らいの連続体」、つまり、夢と言語活動の二つの累層構造を包みこんだより大きな累層構造のことを、私は「パランプセスト」の名で呼んだ。この、より複雑な累層構造をもった〈哥〉の原身体の終わることなき無限の運動は、カミの〈詞〉(純粋言語)という本来伝達不可能なものの方へ、すなわち、私が「ギフト」の名で呼んだ根源へ向けて、何度でも初めて経験するもの、一回性をもったものの反復(伝導)を通じて、果てしなく遡及していく。
■舞踏するフィギュール 貫之現象学のトリアスをめぐるラフスケッチは、このあたりで一応の区切りをつけます。 歌というギフトの心、というか歌のクオリアとでもいうべきものについては、貫之歌論における言霊論として、また、歌のパランプセスト、いいかえれば歌の身体、もしくは歌の顔(ペルソナ)とでもいうべきものについては、貫之歌論における歌体論として、それぞれ稿をあらためて考察するつもりです。そして、これら二つの項を媒介する中間領域における、フィギュールとしての歌のざわめきの実相については、いわば歌の心身論とでもいうべき問題をめぐる考察を経て、いずれ、前章で予告しておいた、貫之歌論における「(強い)私的言語としての〈哥〉の可能性」をめぐる議論として、これもまた後の考察に委ねます。 貫之の歌を夢として読む。このテーマに関しては、まだまだ書いておきたいことが残っていますが、ここでは、先に引いた大岡氏の文章のなかからいくつか気になる言葉を拾いだして、フィギュールとしての歌をめぐる話題を一つ取りあげておきます。 気になる言葉というのは、古今集的表現の特質を示すものとして用いられた「間接的反省」や「外界の事物に寄せてわが内心の想念をひそかに洩らすという方向に進んでゆく歌心」、「自我の存在様態にある種の二元論的分裂を感じはじめた」などです。これらの表現に、私はかすかな違和感を覚えました。それは、「逆倒的な視野構成」という語がはらんでいるある種の深み、もしくは高みへの志向性のようなものが、平面的で平板なものに、たとえば近代的な自意識といった類のものに矮小化して受けとられてしまう契機が、これらの表現のうちに忍びこんでいるのではないかと疑うからです。 川嵜克哲氏は『夢の分析──生成する〈私〉の根源』で、夢には、垂直軸と水平軸の二つの系列があると指摘しています。第一に、「超越性」のキーワードで括られる古代的・神話的な「神託としての夢」の系列。第二に、「内面性」のキーワードで括られる近代的・科学的な「内面を解釈するものとしての夢」の系列。川嵜氏によると、第一の垂直軸にかかわる系列は、世界を、「隠喩的に重なり合う形象として、つまりすべては多義的になにも隠されていずに「意味されるもの」が現前している」ものとして、超越性との関係でとらえる「言霊論」的な世界観に、第二の水平軸にかかわる系列は、世界を、「換喩的で、「意味するもの」の背後に「意味されるもの」が隠されている」ものとして、因果的な連鎖や内面性との関係でとらえる「記号論」的な世界観に、それぞれ結びついています。 先に引用した文章の中で、レヴィ=ストロースは、「わたしは、ひとびとが神話の中でどのように考えているかを示そうとするものではない。示したいのは、神話が、ひとびとの中で、ひとびとの知らないところで、どのようにみずからを考えているかである。/そしてたぶん、すでに示唆してあるが、さらに踏み込んで、主体というものを取り除いて、ある意味では、神話たちはお互いに考え合っている、と想定すべきであろう。」と書いていました。ここでいわれる「神話」が夢の第一の系列に、また、「主体」が夢の第二の系列に対応していると考えていいでしょう。 川嵜氏によると、平安時代の人は内面をもちません。そうだとすれば、内面をもたない(おそらく、アフォーダンスの理論を実地に生きていた)古今集歌人にとって、とりわけ貫之にとって、「外界の事物に寄せてわが内心の想念をひそかに洩らす」ということがどのような実質をもっていたかを、レヴィ=ストロースがいう意味での「主体」の立場で、すなわち、内面性を装備した近代人の神経症的意識でもって云々することには、充分以上に慎重でなければならないはずです。(これは、自戒の言葉。) もう一つ、注目すべき議論を引きます。川嵜氏が『夢の分析』で取りあげた夢は、「実体的な超越性が生きている世界のなかにいながら、内面をもとうとする」特異な意識をもった、ある女性クライアントでした。この女性(Aさん)が報告する一連の夢(「落ちる夢」と「トイレの夢」に二分類される)は、「シャーマン性と近代的な個人」という本来的には互いに相容れない両者をどのように関係づけていくかという課題をめぐるもので、川嵜氏は、その超越性と内面性とのあいだを幾度も往復運動していく夢の運動を「ダンス」の比喩で表現しています。
かの「解読できない毛筆の文字」の夢をめぐって、「夢の中で文字が、普遍を拒絶しているとしたら、それは、私が私自身のまま存在しようとしているからである。書によって、意味や音を手放そうとする文字は、個別であろうとする私の存在なのである。その存在は意味を得ることはできず、あの世に沈むしかない。だが、読まれてしまうような文字もまた、普遍の中に疎外されて失われてしまうのである。/したがって、読まれないのに文字であり続けるという逆説的な文字の状態は、救いようのない孤在と、疎外された普遍的主体との間の、どちらともつかない位相を表しているといえよう。すなわち、文字が音や意味から剥離し、それによって不気味さを与えつつ、かえって美への可能性をも示すという事実は、文字に託された我々人間の生の、個別と普遍の狭間で行き惑うあり方そのものに由来しているのである。」と書かれていたのは、言霊論的な「あの世」(現実界)と記号論的な「普遍的主体」(象徴界)とのあわいでダンスを踊りつづける、フィギュールとしての〈私〉の位相を指し示したものだったのでしょう。 そして、そのような〈私〉の「対立するものをそれ自体のなかに映し出して、入れ子構造的に反復をつづけていくようなあり方」が秘めている、古代的でも近代的でもない新しい主体のあり方とは、また、一つの身体に複数の心を宿すポスト・モダンな解離症的意識でもない新しい意識のあり方とは、たとえば、歌合わせや夢あわせの場に立ち騒ぎ、アンソロジー(詞華集)や物語世界のうちに重ね描かれていく、フィギュールとして生まれ変わった新しい主体(ペルソナ)、あるいは、歌の語らいや夢の語らいを通じて複数の身体のうちを反復(伝導)していく一つの心(ペルソナ)のことなのではないか。私は、そのように考えています。 (05号に続く) ★プロフィール★ 中原紀生(なかはら・のりお)1950年代生まれ。神戸在住。三ヶ月以上、一つのことに関心が続かない。それができたらきっと凄いことになる(たぶん)。 ブログ「不連続な読書日記」・HP「オリオン」 Web評論誌「コーラ」04号(2008.04.15) <哥とクオリア>第4章:貫之現象学のトリアス(中原紀生) Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2008 All Rights Reserved. |
| 表紙(目次)へ |