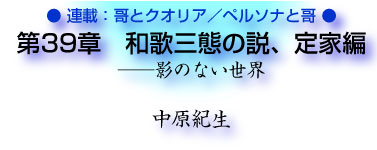|
|
|
Web�]�_���u�R�[���v |
|
���n���̎� ���{���̕\���i�ڎ��j�� ���{���̃o�b�N�i���o�[ ���ǎ҂̕Ł^���ӌ��E���z �����e�K�� ���W�҂�Web�T�C�g ���v���C�o�V�[�|���V�[ |
|
���{���̊֘A�y�[�W�� |
|
���u�J���`���[�E�������[�v�̃o�b�N�i���o�[ ���]�_���u�k�� Vue�v�̑��ڎ� |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
|
����ƂƋ��Ȃ���́A���邢�́u�������Ȃ��v�̗]�C
�@
�@�r�����]�́u�����ĉ́v���A�̖̂{�����u�L����v�ɂł͂Ȃ��u�[�݁v�ɂ����Č��钆�����̂̓��������o�I�E�\���I�ɂ���킵�Ă����A�Ƒ剪�M�����w�E����u�[����Ζ�ׂ̏H���g�ɂ��݂��G�Ȃ��Ȃ�ӂ������̗��v�ł������Ƃ��āA����ł́A��Ƃ̑�\�̂͂Ȃ낤���A����́A����Љ����ǂђ��̓��̐S�����̉̂Ɍ��o�����A�Ɓu����^�E�o���v���`����u���킽���ΉԂ��g�t���Ȃ��肯�肤��̂Ƃ܂�̏H�̂�ӂ���v�Ȃ̂��A����A�S�l���ɐ�����ꂽ�u���ʐl���܂ق̉Y�̗[�Ȃ��ɏĂ�����̐g��������v���������ʂ�̎���̂ł͂Ȃ����A���₢��A����́u�̐D���v�i�ђ����j�������́u�O���t�B�b�N�E�A�i�O�����v�i�ێR�\�O�Y�j��ҏW�����݂䂦�̐�̂�������������Ȃ��A�ȂǂƎ��⎩�����Ă��邤���A�����N�y�э�҂͂Ƃ��ɖ��ڂȂ���A�㒹�H�@���琼�s�@�t�܂ŏ\���l�̐V�Í��̐l���e�X�\�G�̂�������Ƃ����u���]�́v�Ȃ镶�������邱�Ƃ�m��A����������������Ƃ̕����E���ǂ݂����Ƃ���A�f�ڏ������l�̏��������킵�Ă���킯�ł͂Ȃ��ɂ���A���́u�t�̖�̖��̕����Ƃ������ė�ɂ킩��鉡�_�̂���v�Ƒ�O�́u�N���ւʂ��̂邿����́T���R���̂ւ̂��˂̂悻�̂�ӂ���v�̊ԂɌf�����Ă����̂��A
�@
�@�@��Ƃ߂đ������͂�ӂ������Ȃ�����̂킽��̐�̗[����
�@
�ŁA��Ƃ̂��̉̂́A�w�V�X�S�l���x�́u�~�v�̕��\��̍Ōォ���Ԗڂɂ������A�u�t�̖�́v��u���ʐl���v�Ƌ��ɁA�u��Ƃ̍쒆�A�ł��l�����Y�t�������́v�i�V�����ɁE�㊪�A443-444�Łj�ł������ƋL����Ă��܂��B�ےJ�ˈ�̕��͂́A��ɂ���āA���l�Y�Ƃ������A���͂�_��ɒB����ƌ����Ă����o���f���̂��̂ŁA�킯�Ă��A�u���{���w�j�͕S�]�N�O�܂ŁA���̎��l����]�Ƃ̔��ӎ��ƕ��w�ςɂ�Ďx�z����Ă�B�v�i463�Łj�ƁA�j�i�̕��w�j�I�ʒu�Â�������������Ƃ��������ɂ܂킵�āA���̌����͂ЂƂ����₦�₦�Ƃ����Ⴆ���݂��Ă���悤�Ɋ����܂��B
�@���̍�i�́A���t�W�́u�ꂵ�����~�肭��J���O�ւ��荲��̂킽��ɉƂ�����Ȃ��Ɂv�i�����������C�m�Ȃ��̂��݂������܂�n�j��{�̂Ƃ��Ă���A�ےJ�ˈ�ɂ��ƁA�u�×��A�{�̂ǂ�̖͔͂Ƃ��Ă����߂��Ă����v�i445�Łj���ŁA��������̐l�X�ɂƂ��Ắu�h��Ȗ{�̂ǂ�̌���ł����v�i446�Łj�B��Ɖr�Ɩ{�̂ɋ��ʂ���͍̂���Ƃ����̖��Ɓu�킽��v�̌�ŁA�ےJ���͂��́u�킽��v�̌�`���߂����āA�����C�̉̂̏ꍇ�́u�킽��v���Ȃ킿��́u�n���v��ł��邱�Ƃŏ����͂����ނˈ�v���Ă���C�z�ł���̂ɁA��Ɖr�́u�킽��v�ƂȂ�Ɠ���A�܂�u�n���v�Ɓu���߁A��сA������v�̓�̍l�����ɕ�����A���Ă͌�҂̐��������h�������̂��A�ŋ߂ɂȂ��ĐV�Í��W�̓����u����̂킽��v�͓n���Ƃ��Ĉӎ�����Ă������Ƃ�_暂���L�͂Ȍ������o�Ă���A�O�҂̍l�������قڒ���ƂȂ����ƏЉ�������ŁA��������Ƃ̍�i�ɂ́A���Ƃ��u�M�l�v�Ȃǂ̐��C��n��������v�f���܂������Ȃ��A���̂��Ƃ̂ق����ނ���d��Ȃ̂��A�Ƙ_���ݒ肵�܂��i447-449�Łj�B
�@���������̊ےJ�ˈ�̍l�@�͂Ƃ�킯�����ŁA���A�����ɕx���̂Ȃ̂ŁA�ȉ��A�������̉�ɂ킯�Ĕ����������A�ߖ����Ă��������Ǝv���܂��B
�@�����Ɍ�����̂́A���w�I���_�̂����₩�Ȏ���ɂق��Ȃ炸�A����͂܂�A���\���E�̋q�ϐ��Ƃł������ׂ����́A�t�B�N�V���i���ȁu���育�Ɓv�̐��E�ɂ�����u���Ȃ錻�ہv�������́u���|���ہv�m���n�A���Ȃ킿�u���ہA�p���^�X�}�v�̋q�ϐ���A������Ȃ肽�����鏔�@���ւ́u�Ȋw�I�v�ƌ`�e���Ă����A�v���[�`�������炷���̂Ȃ̂��낤�Ǝv���܂��B��Ƃ�A��Ƃ�_����ےJ���̏ꍇ�ł���A����́A���t�̖{���Ƌ@�\�Ƃ��̓`���ɂ������铴�@�ɂ˂������u�̊w�I�v�A�v���[�`�ƌ����ׂ��ł��傤���B
�@
�m���n��S�����́u���{�T�_�v�u�`�ɁA�u�Y�p�͒P�Ɂu�Ȃ��v����������݂̂Ȃ炸�u�L�蓾�Ȃ��v������������o���v�Ƃ���B
�@��S�ɂ��A�u���݁v�Ɂu�����I���݁iens reale�Cens actuale�j�����`�̑��݁iexistentia�j�v�Ɓu�\�I���݁iens possibile�j���{���iessentia�j�v�̓�̗l�Ԃ�����̂ɑ��āA�u���v�i�܂��͔݁j�ɂ́u�ϋɓI���v�i�u�����I���݂łȂ��Ƃ��Ӗ��̗̈�v���u�Ȃ��v�����j�Ɓu���ɓI���v�i�u�\�I���݂ł����蓾�Ȃ��Ƃ��Ӗ��̗̈�v���u�L�蓾�Ȃ��v�����j�Ƃ�����i25�ŁA27�ŁA83�Łj�B
�@���́u�F�̓`���́v�̍\�}�A����́u��^���v�i�u���@�[�`�����Ȃ��́^�A�N�`���A���Ȃ��́v�j�̐������Ɓu���^���v�i�u�C�}�W�i���[�E�t�B�N�V���i���E�|�b�V�u���E�C�f�A���Ȃ��́^���A���Ȃ��́v�j�̐������̒�������ɂ���ē��o����A�u�������v�i��P�ی��j����u�������v�i��Q�ی��j�A�����āu���v�i��R�ی��j����u���v�i��S�ی��j�܂Ŏl�̏ی��ŗ����������̂Ȃ̂����A���̍\�}�ɂ��ƁA�u�����I���݁v�́u�������v�́A�u�\�I���݁v�́u�������v�́A�����āu�ϋɓI�����u�Ȃ��v�����v�́u���v�́A�u���ɓI�����u�L�蓾�Ȃ��v�����v�́u���v�̗̈�ɁA���ꂼ��`���I�ɑΉ������邱�Ƃ��ł���B
�@�{���Łu���Ȃ錻�ہv��u���|���ہv�Ə������̂́u�������v�̗̈�ɂ����鑶�݂̂��Ƃł����āA���̕\���́A�A�N�`���A���Ȃ��̂Ƃ��Ắu���ہv�Ƀ��A���ȁu���ہv�i���Ȃ錻�ہj�ƃC�}�W�i���[�ȁu���ہv�i���Ȃ錻�ہj�̓�̗l�Ԃ�����A���̓�̂��݂̂͌��Ɂu���v�ł���i�������Ȃ��j�A�Ƃ����W���ӂ܂��Ă���B
�@�������A�b����₱�����Ȃ邪�A�����{�͂ōl�@���悤�Ƃ��Ă���u���ہA�p���^�X�}�v�́A��S�̂����u�L�蓾�Ȃ��v�������Ȃ킿�u���ɓI���v���܂�ł���B�܂�A�u���ہv����������̂́u�������v�y�сu���v�̊E��Ȃ̂ł���B�u���v�Ɓu��v�ɂ��ꂼ��u���v�Ɓu���v�̗l�Ԃ�����悤�ɁA�u���v�Ɓu���v�ɂ͂��ꂼ��u���v�Ɓu��v�̓�̗l�Ԃ�����B���������āA�u���ہv���u�L�蓾�Ȃ��v�������Ȃ킿�u���ɓI���v���܂�ł���悤�ɁA�u���ہv�́u�Ȃ��v�������Ȃ킿�u�ϋɓI���v���܂�ł���B
�@���́A���܂����Łu�܂�ł���v�Ə��������Ƃ̎����͂Ȃɂ��ł���B�O�͂ň��������́i�u�������A���I���ꂪ�A���̈Ӗ����A�������E�̉f���ł͂Ȃ��A���I���E�����ł́q���l�̌��̌^�r�Ɉˑ����鎞�i���ݓI�ɂ́q���p�r�A�ݓI�ɂ́q�܂݁r�j�A�q���t�r�͓���̋K����Ď��R�Ɍ������A�����I�Ȑ��E���Y�o�A�W�J���邱�Ƃ��ł����̂ł���B�v�j�̂Ȃ��ŁA��j�����u�܂݁v�Ɩ������Ă���̂́A���̂悤�Ȗ₢�ɂ�������ЂƂ̉ɂȂ蓾�Ă���Ǝv���B
�@
���u�����A�����Ė��v�̂��Ƃ����̂�����������
�@
�@�����ŁA���I�ȑ}�b���͂��݂܂��B
�@���͂���܂ŁA�u��Ƃ߂āv�̉̂��A���悻���̂悤�ȏ�i�i���m�ɂ́A�����Ԃ̂���l�j��`�ʂ�����i�ł���ƎƂ߂Ă��܂����B�ȉ��A���đ�13�͂ŊT�ς����Ǐ��\�i���̋c�_�i�w�f��ЂƋY�ꄟ����Ƃ�ǂށx�j���W�͂łƂ肠�����剪�M���̋c�_�i�w���̓��{��x�j���i�����āA��36�͂ŏq�ׂ��u�p���C���[�W�v�̉��߂��߂���c�_���A�����������ɂ�������ݎv�z�̂悤�ɈÖٗ��Ɂj�Ƃ肢��A�������~�������������ŏq�ׂĂ݂܂��B
�@
�@�c�c����F�ɓh�肱�߂�ꂽ�~�̌���B�����ł́A�u�ԁv��u�g�t�v��u����v��u�Ƃ܂�v�Ƃ������������A�i�����̌i���͎��͌����̎����ł͂Ȃ��A�a�̂̐��E�ɂ����ē`���I�ɂ������Â����Ă����u�̌�̑̌n�v���邢�́u�����I����̑̌n�v��������A�z�ꂽ�ꂪ�������Â���C���[�W�ɂق��Ȃ�Ȃ��̂����i�Ǐ��O�f��195�Łj�A�Ƃɂ����A���̂悤�Ȍi�����C���[�W���j�s�݂ł���B���ꂾ���ł͂Ȃ��B�����ɂ́u�����v���A���Ȃ킿�A�����ǂ����̂�����肪�����炷�^����A�����Ƃ̊W���̂Ȃ��Ő��s�����A�N�V�������܂��s�݂ł���B
�@�~�肵�����ɓ�a����n��̐l�B���A�Ɉړ����Ĕn���Ƃ߁A���ɍ~��ς���������A��̏��~�݂ɂȂ�̂�J����ő҂A���X�B�����������Ԃ̗���ɂ������S�g�̓��Â₵�����̈���A�i�^�����o��g�̊��o�ƌ�������̂��ӂ��߂āj�����ɂ́u�Ȃ��v�B�V���畑��������u��v���܂��u�̌�v�������́u�����I����v�̈��ł����Ă݂�A���������u�~�肵�����v�Ƃ��������̉^�����̂��̂��u�Ȃ��v�B����̂͂����A����F�ɓh�肱�߂�ꂽ�u����̂킽��v�̓~�̏�i�����ł���B����A�̖��́u����v�͌����ɋy���A�u�킽��v��u�~�v��u�[��v���܂��u�Ȃ��v�B�H�̗[������A�����Ɖ����Ȃ��~�̗[��́u�����i�i�j�v�B���́u�����i�C���[�W�j�v�������A�����ɂ́u�Ȃ��v�B�Ȃɂ���u�������Ȃ��v�Ȃ̂�����B
�@�������A�u�����Ȃ��v�Ɓu�������Ȃ��v�Ƃł͂܂������Ⴄ�B�i�u�u�����Ȃ��v�ƌ������ƂƁu�Ԃ��g�t���Ȃ��肯��v�ƌ������ƂƂ́A���炩�Ɍ��ʂ̈Ⴂ������v�i��j�j�悤�ɁB�j�����ɂ́A���̉̂̐��E�ɂ́A���Ȃ��Ƃ��u���킽�����v�Ώہi�q�́j�Ƃْ̋��W�������đΗ�����u���킽���v��́A���Ȃ킿�u���I���E�ł̂ݐ����邱�Ƃ�I�������̐l�i���I�����j�v�i�Ǐ��O�f��195�Łj�̋C�z���A���̑��݂̍��Ղ��A�i������܂��Ǐ����������Ƃ���́A�u����v�Ɓu�Ȃ��v�A�u���O�v�Ɓu�s�݁v�̂͂��܂�T�^�I�ȍݏ��Ƃ���A�s����ňڂ낢�₷���͂��Ȃ��u���A�����A���������A�����A�����Ė��v�̂��Ƃ����̂��i�Ǐ��O�f��44�Łj�j�A���������Ă���m���n�B���̊ȑ��݊����������u�����i�ʉe�j�v�Ƃ��Ă̎�̂́A�u���F�̂��̂̂Ȃ��ɐF��������́i���G�o�I�Łj�����I�ȁi�S�́j��v�i�剪�O�f��56�Łj�������āA���̍�i�̑S�����A�������߂Ă���̂ł���B
�@�����āA���́u�����v�̋C�z������Γ����ȃX�N���[���Ƃ��āA���̌����Ȃ����ʂ̂����ŁA�n��̐l�Ƃ����̒��̓o��l���i�������͈قȂ錾���ԁA�قȂ�a�̂╨�ꂩ��R���[�W�����u���p�v���ꂽ�l���j��A�n���Ƃ߂�A���ɐς�������������͂炤�Ƃ������u�����v���Ƃ��Ȃ����C���[�W�Q���A�����[���̐�Ђ̂悤�Ɋ��w�ɂ��d�˕`����Ă䂭�B���������u�L�蓾�Ȃ��v��z�V�[�����I�[�o�[���b�v����悤�Ɂc�c�B
�@
�@���̂悤�ȁu���߁v�́A���̗v�ƂȂ�u�������Ȃ��v�́u�����v�Ƃ�������A�єV�́u�e����Δg�̒�Ȃ�Ђ������́v�́u�e�v�Ɠ��l�ɁA���邢�͂���������ƍL�����o�f���i�C���[�W�j��ʂƂƂ炦�A��̋���A�u��Ƃ߂đ������͂�Ӂv�l�Ƃ��̓����̉f���͂��Ƃ��A���悻��̃C���[�W�������i����̂킽��j�ɂ́u�Ȃ��v�A�Ɠǂނ��Ƃł͂��߂Đ���������̂ł��B�i�w���{�l�ɂƂ��Ĕ������Ƃ͉����x�����̍u���^�u���t�ƃC���[�W�\���{�l�̔��ӎ��v�ŁA���K�G�����́u�e���l�e�v�ƂƂ炦�Ă���B�u�܂�A���̉̂́u�N�����Ȃ��v�Ƃ������Ƃ������Ă����ł��B�N�����Ȃ���̗[���̎₵���Ƃ���Ƃ����̂��A��Ƃ͂��̉̂ŕ\�킵�܂����B�v�i55�Łj�j
�@�������A���̓ǂݕ��͊Ԉ���Ă��āA�������́A�u�����v�͍~�肵������������u���̂����v�̂��Ƃ������̂ł��B�����A�ےJ�ˈ�̑�z�������w�I���_�̍s������͎��̌�ǂɋ߂Â��Ă���A�Ƃ������A�قƂ�Nj�ʂ����Ȃ��Ƃߕ��ɂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ����ƁA��⋭���ł����A���͂��̂悤�Ɋ����Ă��܂��B
�@
�@�Ƃ���ŁA�����Ɂu���\���E�̋q�ϐ��v�Ƃ��������������܂����B�q�ϐ��́A���҂̑��݂������Ă͂��߂Đ��藧�T�O�ł��B�������Ƃ���ƁA�u������́E���育�Ɓv�̐��E�ɂ����āu���ҁv�Ƃ͂��������N�Ȃ̂��Ƃ�����肪�����������Ă��܂����A����ɓ�����̂͂������ĊȒP�ŁA����́A���������ܒp�����������Ȃ��Ǝ��́u���߁v���J���Č����������g�A���Ȃ킿�u�ǎҁv�̂��Ƃɂق��Ȃ�܂���B
�@
�m���n�����Ɂu�����A�����Ė��v�̂��Ƃ����̂Ƃ��ė��������Ă���̂́A�͂����Ė{���őz�肵���悤�ȉr�̎�́i�̂̐��E�̂Ȃ��ʼn̂��r�ށA���\���ꂽ�r�̎�̂��܂߂āj�Ȃ̂��낤���A����Ƃ������́i�ǎҁA�ϋq�j�Ƃ��ĂƂ炦��ׂ��������̂��낤���B
�@�A���h���E�o�U���́u�����Ɖf��v�i�w�f��Ƃ͉����i��j�x�j�ŁA�u�����I�ȏ�v���Ȃ킿�u����Ƃ������F���v�ƁA�f��ɂ�����u�X�N���[���v�̊ϔO�Ƃ̎��I�ȈႢ�ɂ��Ď��̂悤�ɘ_���Ă���B
�@�f��̊ϋq�A���Ȃ��ӎ�����ϋq�ł���u���v�́A�p�̌����Ȃ��u�����A�����Ė��v�̂��Ƃ����̂ƂȂ��āA�X�N���[���̌�����������ށB
�@�a�̂̍�i��Ԃ������ǂ���̂�����Ƃ��āA����́u�z���v�������́u�t�b�g���C�g�v�i���邢�͔\�ɂ����鉼�ʁA⾉j�̂��Ƃ����̂Ȃ̂��낤���A����Ƃ��u�X�N���[���̊O�g�v���Ȃ킿�u�}�X�N�v�i���邢�͎��߂ɓo�ꂷ��u���g�v�j�ɑ���������̂Ȃ̂��B���Ȃ��Ƃ��u��Ƃ߂āv�̉̂��玄���Ƃ��Ă����ۂ́A��҂ł���B
�@
���u��҂��ǎ҂ɂȂ�A�����Ă܂���҂ɂȂ�v�A�̓I�\��
�@
�@�Â��āA�w�V�X�S�l���x�̕��͂������܂��B
�@�����Ɏ����ꂽ�u��҂��ǎ҂ɂȂ�A�����Ă܂���҂ɂȂ�v�Ƃ����A�i�I�u�W�F�N�g�E���x���ƃ��^�E���x���A�����ƊO���A�����瑤�Ƃ����瑤�����]�������Ēn�����ɂȂ�j�A����ΘA�̓I�ȁu�\���v�̐��ɐG������āA����Ƃ̊֘A�Ŏ����z�N�����̂́A�F��v�����w��Ƃ��w����ꂽ�������߂āx�x�Ř_�����u�v���[�X�g�I�ȁu���v�v�������́u����Ă��錻�݁v���߂���c�_�ł����B����͂ƂĂ����͓I�Ȃ��̂Ȃ̂ŁA�������ڂ������Ă��������Ǝv���܂��B
�@�F�쎁�́A�܂��A�w����ꂽ�������߂āx�̖`���ɂ����ꂽ���́ALongtemps, je me suis couche' de bonne heure. �i�F���u�����������A���͑������珰�ɂ������̂ł���B�v�i32�Łj�j�������ߋ��`�ŁA�܂�u���݂ɂ����āv�i33�Łj�ߋ������̎����s�ׂ̏�Ԃɂ��邱�Ƃ�\�����錻�݊����̌`�������������ŏ�����Ă��邱�Ƃɒ��ڂ��܂��B
�@�u����Ă��錻�݁v�Ƃ́A���̕�����u����Ă��鎄�v�i����j���u���ꂽ���Ԃ̂��Ƃł���A���́u����Ă��鎄�v�ƑΔ䂳���̂��A�i���ߋ��`��P���ߋ��`���ߋ��`�Łj���������e�Ƃ��Ắu����鎄�v�i��l���j�ł��B
�@�F�쎁�ɂ��ƁA���́u���g�v�i�H���i�u�w����ꂽ�������߂āx�̖`���̋�ɂ��āv�������ꂽ��b�j���猩������i�́A���́u�����G�v�ƂȂ��Ă���B�܂��A����Ƃ��Ắu���v�́u���������̑��݁v�A�u�i������j�Ώۂ���͕s�݂ł���ׂ����݁v�ł���A�u���Γ������������݁v�ł���B�i57�Łj
�@����Ƃ��Ă̎��A����Ă��鎄�́A���̂悤�ȊG�����鎋�_�ɗ����Ă���B�����āA�v���[�X�g�͂��̐�ɁA�u�{��ǂޓǎҁv�̎p��z�肵�Ă���B�w���������ꂽ���x�̍Ō�߂��A���悢�掩���̖{���������S�������u���v�́A���̖{�̓ǎ҂ɂȂ�ł��낤�l�тƂɂ��āA�u��������̓ǎ҂ƌ����Ƃ�����A�s���m�ł������邾�낤�B�Ƃ����̂��A���Ɍ��킹��A���������l�X�͎��̓ǎ҂ł͂Ȃ��A�{�l���g�̂��Ƃ�ǂޓǎ҂����炾�v�Ə����Ă���B���̂��Ƃ��߂����āA�F�쎁�͎��̂悤�ɘ_����B
�@������̎��_����ǎ҂̎��_�ւ̈ړ��B����ƃp�������Ȏ��Ԃ��A�����̎O�l�̏����w�W�����E�T���g�D�C���x�ɂ�����A�u�ߋ��̑z�N������Ă��邤���ɁA���̌��i�̎�̂ł���͂��̎O�l�̂̂����Ɉ�l�̐��������v�i61�Łj�Ƃ����A�z�N�̎�́i�O�l�̂ŋL�q����镨��̎�l���j�́u���ije�j�v�ւ̕ϗe�Ɍ��邱�Ƃ��ł���B�v���[�X�g�I�ȁu���v�̓����������o��m�o�̒��ڐ��������i63�Łj�A�u�ށv����u���v�ւ̎�̂̈ڍs�𑣂��i62�Łj�B
�@�Ƃ���ŁA�w����ꂽ�������߂āx�̌���́u���v�ɁA��i���Łu�}���Z���v�Ƃ��������L����Ă�����������B�F�쎁�́A��s�����ɏ������A���̂����̈��́u�������̖{�̍�҂Ɠ������O������ɗ^�����Ƃ�����v�Ƃ����������ł���A������͐��Ȃ̎肪�����Ă��Ȃ����e�䂦�ł��邱�Ƃ��m�F���������ŁA���̂悤�Ɋ���B
�@�F�쎁�̋c�_����A��Ƃ̋��Ȃ鐢�E�ڋ߂��Ă������߂̎肪������A�������肾�����Ƃ��ł���Ǝv���܂��B
�@���ɁA�F�쎁�������u����Ă��錻�݁A����Ă��鎄�v�́A��Ƃ́u�r�݂���S�v�Ɠ����̂��̂Ȃ̂ł͂Ȃ����B�����āA�u����Ă��鎄���r�݂���S�v�Ƃ��Ă̏����聁�r�ݎ�Ƃ����u���g�v�i���_�j���猩��ꂽ���i�����́u�����G�v�ł���Ƃ́A����A���������F�쎁�������u�G�v���̂��̂��A���͉f��̌��i�������́A�f��̌��Ǝ����I�ɓ����ȋ��Ȃ鐢�E�̑̌��j�̂��Ƃ������̂ł͂Ȃ����B�܂�A��Ƃ̉̂̐��E�͉f��̎���Ԃɒʂ��Ă���̂ł͂Ȃ����B�i�u��Ƃ߂āv�̉̂��A����F�̓~�̌���ɗ�������ꂽ�p���^�X�}��`�ʂ���A��т̃V���[�g���[�r�[�ł������悤�ɁB�j
�@���ɁA�u���܂��܂ȕ���̓��e�Ƃ��Ẳߋ��ƁA���������ߋ���z�N���Ă��錻�݁v�Ƃ̊W�́A�ߋ��ɉr�܂ꂽ�{�̂ƁA���݂ɂ����邻�̑z�N�����p�Ƃ��Ă̖{�̎��Ƃ̊W�ƃp�������Ȃ̂ł͂Ȃ����B�����āA�{�̂Ɩ{�̎��Ƃ�A�����镡�G�����ȁu���_�v�̈ړ��́A���i����j�����ɂ��Ȃ��҂ǂ����́A���ԂƋ�Ԃ��u�Ă��A�̓I�ȍ\���i���łɎB��I���A�ҏW���I��������ҁi��ҁj�ƁA���̉f����u���܁A�����v�ɂ����Đ��N����o�����Ƃ��āA�J�����i�u���I�����v�̎��_�j�̈ړ��ƂƂ��ɂ��̒m�o����ω������Ă���ϋq�i�ǎҁj�̊��o�A�ӎ��Ƃ́A��������A���j�������炷�̂ł͂Ȃ����B�i���邢�́A�u���ӎu�I�z�N�v�̈ӎu�I�n�o�Ƃ��Ă̖{�̎��B�j
�@��O�ɁA��҂̎��_���ǎ҂̎��_�Ɉړ����A�O�l�̂̂����Ɉ�l�̂������Ƃ����c�_�́A�i��36�͂Ō��y�����Ó��N�����̋c�_�ɒʂ���ƂƂ��Ɂj�A�\����ɂ����鎀�҂̕����⒴�z�I�Ȃ��̂̌����ɒʂ��Ă���̂ł͂Ȃ����B�����āA�\���҂̎��̂Ƃ��̕���̂́A�a�̂ɉr�܂ꂽ�u���i�v�i�̂̐S�j���A�[�I�ɂ����ΐl�����A���́u���g�v�i���_�j��H���j��A�a�̐��E�̊O���ɒ����o�Ď��������Ă���A���̎p�ł���Ƃ������ƂȂ̂ł͂Ȃ����m���n�B
�@
�m���n�y���b��Y���w�\�A�h���}�����������Ƃ��x�́u�܂������@�\�ւ̉�̂ƍč\�z�v�́A�Z������ǎh���I�ȕ��͂ŁA�ł���ΑS�����p���Ă����������炢�����A�{���̃e�[�}�Ƃ̂������i���Ƃ��A�{�̎��̋��Ɍ`�ԂƂ��Ă̔\�j���Ƃ�킯�[���ӏ����A�����������Ă����B
�@�\�̓R�s�[���I���W�i�����B�����������̂悤�Ȃ��Ƃ��\�ɂ�������ƂȂ肤��̂��B�R�s�[���I���W�i�����́u���v�ɌŗL�̖��ł���B���Ƃ���A���͔\����ɗ���������̂́u���v���u�g�v���u���ہv���A����Ƃ������Ƃ͈قȂ��l�̂��́i���Ƃ��A�����_�w�Ɍ����u�y���\�i�v�̊T�O�ɑ���������́j�Ȃ̂��Ƃ������ƂɂȂ�B�i�����Ă���͎��̂悤�Ȗ₢�ɕό`�����B�\�͉̂����ꂩ�������A����Ƃ����̉f��̐�s�`�Ԃ������̂��B���邢�́A�̂ɐ旧�Ñ�I�Ȃ��̂̍ė����B�j
�@
���A���B�Z���i�̗H��A�Ă�
�@
�@�����ŁA��Ƃ́u�r�݂���S�v���߂���A��j���̃I���W�i���ȋc�_���m�F���Ă��������Ǝv���܂��B�������s���A����̘a�̐����̑����Z�Ƃ��ē�̎��̍����ɐ��_�{�ɕ�[���邱�Ƃ��v�������A���̔���������̂��̒d�̏d���r���i�u��֑��̍��v�j�Ǝ��\�Z�̒�Ɓi�u�{�͉̍��v�j�B�x�d�Ȃ�Ñ����o�āA��Ƃ���O�\�Z�Ԃ́u�{�͉̍��v�̔����͂���ꂽ�͓̂�N�]���̂��ƁB�a���ɂ��������s�͓��������ł����ǂݒʂ��A�������̊������Ƃɏ����������B���s�����ڂ����̂́A�������̂���\���������B
�@�N��Ƃɂ���ė��Ă�ꂽ�V������]��A�V�����a�̎v�z���A�莁�́A�T�d�Ȏ葱�����o�āA��N�́u�L�S�́v�Ɍ��т��Ă����܂��B������Ƃ́A�u�Â����v�̕\���u�S�v���A�܂葀��ΏۂƂ��Ắu�v���̌^�v�⎌�Ƃ����L�����S���Ă���Ӗ��Ƃ��Ắu�S���̎v���v���u�L�S�́v�́u�S�v�Ƃ͔F�߂Ȃ��B�Ƃ���A����͍�Ҏ��g�́u�S���̎v���v�ł���ƍl����ق��Ȃ��B�܂�u�L�S�v�Ƃ́A�u�̂̐S�v�ł͂Ȃ��A�u��҂̐S�v�̖��ł���B
�@���������A�������́i���Ɂu�F�ƃN�I���A�^�y���\�i�ƚF�v�Ɩ��Â����j�_�l�Q�ɂƂ肭�ނ��������ƂȂ����̂��A�莁�́u�r�݂���S�v���߂���c�_�ɂӂꂽ���Ƃł����B�w�Ԓ��̎g�����̂̓��̎��w�T�x�Ɠ������s�I�ɓǂݐi�߂Ă����w���c�����Y�����q��Ζ��r�Ƃ͉����x�i�i��ρj�́u�ƍݐ��́q���r�v�ƁA���́u�r�݂���S�v�Ƃ̊W�������͖��W��T������A����ȃe�[�}�����サ�Ă�������ł����B
�@���܁A���炽�߂ēǂ݂������Ă݂āA�u�̐l�̎��̌����Ă���S��v��u���̌��Ƃ��Ă̐S���̎v���v�̉r�o��a�̖̂{���Ƃ���̂��єV�̘̉_�ł���A�Ƃ���������ɂ͈�a�����o���܂����A�������������ɏ�����Ă���a�̂̎v�z���̂��̂��i�L�`�́j�єV�̘_�̐��E�ɑ����邱�ƂȂ̂ł͂Ȃ����ƁA����Ȏv�������݂����Ă��܂��B�������A���������ł������Ƃ��Ă��A�u�r�݂���S�v�����́A���Ȃ킿�A�r���́u�̂̓��̐[���S�v�܂�u���I��ρv�i��j�j��u���I�����v�i�Ǐ��\�i�j���u���܁A�����v�́u�r�݂��錻�݁v�Ƃ����g�|�X�ɂ����Đ��N�����Ƃ���́u�r�݂���S�v�����́A�єV�̘_�o�����ƃI���W�i���̂��̂Ȃ̂��낤�Ǝv���܂��B���m�ɂ́A���̂悤�ȁu�r�݂���S�v���A���Ƃ��Δ\����ɂ����镑�i�g�j��w�i���j�̂����ɋ�����ꂽ�Ƃ��A���̂Ƃ������A��Ɖ̘_�̃I���W�i���Ȑ��E���\�S�ɕ\�����ꂽ���ƂɂȂ�̂ł͂Ȃ����B
�@�ƁA�����܂ŏ����Ă��āA���̔]���ɂ́A���̃A���B�Z���i�́u�l�ԁv�������́u�A���B�Z���i�̗H��v�i�R���u�N�w�u��ǁv�̓N�w�x177�Łj�����������Ă��܂��B�䓛�L�q���u�ӎ��t�B�[���h�Ƃ��Ă̘a�́v�ŁA�u���܁A�����v�Ƃ������ۓI����ɂЂƂ̃g�|�X�������A����Ƃ̂������ɂ����āi�̂݁j�g�̓I�Ȃ��̂ƌ�������A�Ƃ����A���B�Z���i�i�C�u���E�V�[�i�[�j�̋l�ԁi��28�͎Q�Ɓj�B
�@�䓛�L�q�́u�ӎ��t�B�[���h�Ƃ��Ă̘a�́v���A�u���ՓI�ɏƎ˂��ꂽ�ӎ��́A���́A�����ԓI�E��ԓI�ʑ��A�Ƃ������I�\���́A�\�̉��Z�ɂ������ӎ���Ԃ�A���x�═���̐S�E�g��ԁA�����̔��I��Ԉӎ��ȂǁA�ƂȂ��ēW�J���A�₪�āA������|���I���E��ʂ𐬗�������]���_�ƂȂ����A�ƍl���邱�Ƃ��o����̂ł���B�v�i22�ʼn��j�Ƃ������͂Ō���ł��܂������A�����Ō�����u�\�̉��Z�ɂ������ӎ���Ԃ�A���x�═���̐S�E�g��ԁA�����̔��I��Ԉӎ��v�̊����Ȃ��̂��A�A���B�Z���i�̋l�ԂɌ�����u��̍\���v�ł���A�u�r�݂���S�v�̑��ݗl���ł��낤�Ǝ��͍l���Ă��܂��B�m���n
�@
�@�Ƃ���ŁA�O�߂ň��p�����ےJ�ˈ�̕��͂Ɂu���^���Ƃ��Ӊ��̋����̎w��������̂́A�����Ő�̗[��̍�p�𑶕��ɎāA���g�����߂��̂ł���B�v�Ƃ���܂����B�����ɂ́A���o�Ǝ��o������i�������t�j�̂Ȃ��ŋ����o�I�ɗZ������l���`�ʂ���Ă���̂ł����A����ɂ��Ă��A�u��̗[��v�Ƃ������ہi�p���^�X�}�j�������炷�u��p�v�Ƃ͂������������B���́u���y�I�v�ƌ`�e���Ă��������ʂ̓����Ƃ͉����B����́A����ɂÂ����͂̂Ȃ��ł�������܂��B
�@
�m���n�ߓ��A���j���p�َl�\�N�L�O���ʃA���R�[���u���Ɣ��؈�v�@�i�n�ɑ��Y�v���ςĂ���ƁA�i�n�ɑ��Y���u���؈�v�̓��m�i�I�u�W�F�Ă��j�����̂ł͂Ȃ��A���؈�v�Ƃ����l�ԁi���|��Ɓj�����̂��v�Ƃ�������|�̔��������Ă����̂���ۓI�������B�����Łu���m�v�ł͂Ȃ��u�l�ԁv�ƌ�����Ƃ��́u�l�ԁv���A�u����Ă��鎄�v��u�r�݂��鎄�v��u�l�ԁv�ɒʂ�����̂Ȃ̂��낤�B���ꂪ�u�H��v�̖��ł��Ă�邱�Ƃ́A�ƂĂ������I�ł���B�Ƃ����̂��A���҂������ɂ́u��Ɓv�ł���A����Ƃ̑Δ�ł����A���҂͋��ɂ́u�ǎҁv���Ǝv���邩�炾�B�����āA���̎��҂̐��E�Ɛ��҂̐��E�̂������ɗ���������u�H��v�������A��ƂƓǎ҂̂������ɐ��N����S�A�܂�A�u�a�̂̎Y�o�ߒ��ɂ����Ă̂ݐ����Ă���A���\�́A���������I�Ȑ����������āu�[���Ȃ�v�ނ��Ƃ̂ł���u�S�v�v�����炾�B
�@
�����ہA�u���y�I�Ȍ��ʁv�Ƃ��Ă�
�@
�@����ɁA�w�V�X�S�l���x�̕��͂������܂��B
�@�����ɂ��܂��A���w�I���_�̂���{�����邱�Ƃ��ł��܂��B
�@����I���ӎ��̑w�ɂ������C���[�W�I�A��Ӗ��I�ȉ��̗V���B����ӎ��̐��ݑw�ɂ����鉹�ƃp���^�X�}�̘A���A�C���[�W�I�ȘA�z�ƈӖ��I�Ȋ܂݂̑��^�B����I�ӎ��̌��ݑw�ɂ����鉹�ƃC���[�W�ƈӖ��̑��݈��p�I�E�C���I�ȘA���B�����O�̑w�ɂ܂����鉹�C�̂͂��炫�A���̌��ʂƂ��Ẵp���^�X�}��C���[�W�m���n�B�_�́u���ȂЁv�ɂ���āu���Â�v��A�������A��Ȃ���̂́u�K��v�ł������A���X�̒f�ГI�Ȍ��t�i����Áj���L���̕����畂���т������Ă͏����Ă����c�B
�@�A���h���E�o�U�����u�f�挾��̐i���v�i�w�f��Ƃ͉����i��j�x�j�ɁA�u�����͉f��́u�����v��j�ɂ���Ă����̂ł͂Ȃ��A������������ɂ���Ă����v�Ə����Ă��܂��B�����̂̐��E����r�̂�A�̂��o�āA�\�̎��͂̐��E�ւƂ�����A�i�T�C�����g�f�悩��g�[�L�[�ւ̈ڍs�ɂ��C�G����j�Z�p�I�ω���ʂ��āA�a�̂͂ǂ̂悤�Ɂu�����v����Ă������̂��B���̂��Ƃ́A���Ƃ��Ă̘a�̂̐[�w�̘_���A�Ƃ����_�_�ɂ��Ȃ����Ă������Ƃł��傤�B
�@
�m���n������́A�܌��M�v�̃e�N�X�g�ɖ�������u���v�i�w���҂̏��x�́u�����@�����@�����v�u�����@�����@�����v�Ȃǁj�ɒ��ڂ����g�������A���㌒���A���Y���P������݂ɂȂ炢�A���̒����w�܌��M�v�x�i�攪�́u�F���v�j�ŁA���̂悤�ɏ����Ă���B
�@�����Ř_�����Ă��邱�ƁA���ɂ��X�����ۂ̈�̉��A�ߋ��̋L���̏����A���i�C���[�W�j�̐��N�A���E�ƊO�E�̃��Y���̓����A��ƌi�̍���A���X�́A�����̈ȑO�́u�̂̔����v�Ƃ����A���̘_�l�Q�̎˒��͈͊O�i���邢�́A����ȑO�j�̏o�������߂�����̂��B
�@
�i�R�O���ɑ����j
���v���t�B�[����
�����I���i�Ȃ��͂�E�̂肨�j1950�N�㐶�܂�B���Ɍ��ݏZ�B��N���̂ɏ����ꂽ�a�̂̈Ӗ��������ł���̂͂��������Ƃ��B�ł��A�{���Ɂu�����v�ł��Ă���̂��B�����Ɂu�Ӗ��v�Ȃǂ���̂��B�����������t���g���ĉ�����`�B���邱�Ƃ��̂��̂��s�v�c�Ȍ��ۂ��Ǝv���B
Web�]�_���u�R�[���v29���i2016.08.15�j
���F�ƃN�I���A����39�́@�a�̎O�Ԃ̐��A��ƕ҄��e�̂Ȃ����E�i�����I���j
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU�@2016 All Rights Reserved.
|
| �\���i�ڎ��j�� |