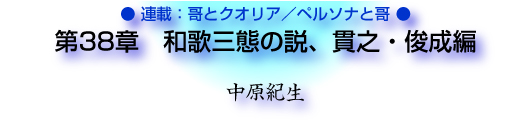|
|
|
Web�]�_���u�R�[���v |
|
���n���̎� ���{���̕\���i�ڎ��j�� ���{���̃o�b�N�i���o�[ ���ǎ҂̕Ł^���ӌ��E���z �����e�K�� ���W�҂�Web�T�C�g ���v���C�o�V�[�|���V�[ |
|
���{���̊֘A�y�[�W�� |
|
���u�J���`���[�E�������[�v�̃o�b�N�i���o�[ ���]�_���u�k�� Vue�v�̑��ڎ� |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
|
�@�єV�̘̉_��єV���r�̂̐��E���A�r�����Ƃ̂����Ɣ�r�ΏƂ��A���̎������ꌾ�Ō����\�킷���t����������Ƃ���A����́u���v�i�C�}�[�W���j�ł͂Ȃ����B�����āA�r���̏ꍇ�ł���u�g�v�i�t�B�M���[���j���A��ƂȂ�u���ہv�i�p���^�X�}�A�t�����X��\�L�ɕ��������킹��Ȃ�A�t�@���g�[���������̓~���[�W���j�Ƃ����ꂪ�A���ꂼ��̘̉_�Ɖ̂̐��E�̓������������āA���Ƃ̊��G�̈Ⴂ���ۗ������錾�t�Ƃ��Ăӂ��킵���̂ł͂Ȃ����B�g�{�����̌���\���_�̊�ڂł��鑜�ƚg�̗��_���߂����Ďv�Ă��߂��点�Ă��邤���A����Ȃ��Ƃ��l����悤�ɂȂ�܂����B
�@������A�i��12�͂̋c�_�Əd������Ƃ��낪���X���邵�A����ɁA�g�{�֘A�{�Ɠ������s�I�ɓǂݐi�߂Ă������g���b�N�_��t�����X�f��v�z�j���߂��鏑���Ƃ̗��O�̑����A�Ƃ��������̔]���̂Ȃ��ł̎v�������Ȃ��R���{���[�V�����������āA���Ȃ�摖�����b��A�_�_���ӂ��ނ��Ƃɂ��Ȃ�ł��傤���j�A���̎v�����A����Ε����O�ԂȂ�ʘa�̎O�Ԃ̐��ɁA���炭��������Ă݂����Ǝv���܂��B�єV�ȑO���邢�͒�ƈȌ��g�ݍ��ނȂ�A�����l�ԂȂ�ʘa�̎l�Ԃ̐��Ƃ����ׂ��Ƃ���ł��傤���B
���єV�Ƒ��A���邢�́u�Ԃ͐�Ƃ��č~��v
�@�܂��A�єV�ɂƂ��Ă̑��B����́A�Í��W�������ɂ����Ƃ���́u������̕������́v�i�Ԓ������j�Ɂu���āv�i�����āA���邢�͜߂��āj�����������ꂽ���̂��́A����������Ɓu�q���r�Ƃ������v�i��j�w�Ԓ��̎g�x�j�ɉf���������A�܂��́u���ɉf����́v�i�剪�M�w�I�єV�x�j�A�܂萅�ʁA����ɉf�����C���[�W�ł���A����ɛ����G�Ƃ����X�N���[���̂����ɕ����ɂ���ďd�˕`���ꂽ�u�p���^�X�}�v�A���Ȃ킿�u�Ȃɂ��̂ɂ��ގ����邱�Ƃ��Ȃ��A���������Ă���ȊO�̂��̂ɍ����������Ȃ��c�C���[�W���̂��́v�i�Ǐ��\�i�w�q�悻�r�̔��w�x�j�ɂق��Ȃ�܂���m���n�B
�@�����ŁA����܂Ō��Ă����єV�̂̂����A�U����i�����ɕ`���ꂽ����ӂ��߂āj�Ɂu���āv�̂�ꂽ���́A�����āA���ʂ������͐���ɉf��C���[�W�i�����ċ�̓I�ȑ������Ȃ��P�[�X���ӂ��߂āj���r���̂��A���ꂼ���g�ݍ��킹�ĂƂ肾���Ă݂܂��B
�@�@������ԎU��ʂ镗�̂Ȃ���ɂ͐��Ȃ���ɔg����������
�@�@���U��̉����͊�����ŋ�ɒm���ʐႼ�~�肯��
�@
�@�@���Ԏ�̎��ɑ���R�̈�̖O���ł��l�ɕʂ�ʂ邩��
�@�@��Ɍ��Ԑ��ɏh��錎�e�̂��邩�Ȃ����̐��ɂ������肯��
�@
�@�@����ʏt�Ǝv�ւlje����ΐ���ɂ��։Ԃ��U�肯��
�@�@�e����Δg�̒�Ȃ�Ђ������̋��킽���ꂼ��т���
�@�ŏ��́u������ԎU��ʂ�v�̉̂ɂ��ẮA�i��S�͂łƂ肠�����j�剪�M���̕]���ɁA�u���S�̂́A���̔���������m�Ȃ���n�̎��͂ɂ��߂��Ă��āA���x�ǂ݂������Ă��A�������肵���u���v�����Ɍ����Ƃ��������͂Ȃ��v�Ƃ���A�܂��A�u�єV�̉̂́c�������Â��A�Ђ�����u���v�����Ԃ��Ƃ��������Ƃ��Ă��邩�ɂ݂���B������������g���A���ׂĂ���̓I�ł�����͒��ۓI�ł���A����Έӎ��̗���̈�u���Ƃ̉��ۂɂ����Ȃ��Ƃ�����ۂł���B���̂��߂ɁA�����\�Ȉ��̓��������A���ꂼ��̂������ɐ����Ă���Ƃ��������������B���̉̂�z���N�����Ƃ��Ă���̐��m�Ȉʒu����߂������Ƃ������̌o�����A�����炭�����������ƂɋN�����Ă���̂��v�A�Ƃ��邱�Ƃ������Y���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��ł��傤�B
�@�剪�����A�u���̉̂�z���N�����Ƃ��Ă���̐��m�Ȉʒu����߂������v�Ə����Ă���̂́A�u������ԎU��ʂ�v�Ƃ܂ŏo�āA���Ƃ́u���v�u���v�u��v�u�g�v�����s���ɕ����т������Ă��A�u���̂Ȃ���v�������̂��A�u��̂Ȃ���v�������̂��A�u�g�Ȃ���v���������A�u���Ȃ���v������������܂�Ȃ��A�Ƃ����o�����w���Ă���̂ł����A���Ȃ��Ƃ��A���̂悤�ȁu���s���v�̞B���ȊW���̂����ɁA�u���v�u���v�u���v�u��v�u�g�v�̌ꂪ���N����֊s�̒�܂�Ȃ��A�i�܂莋�o�I�C���[�W�̂悤�Ȃ�������Ƃ����֊s�������Ȃ��j�A���������ꎩ�̂Ƃ��Ă͑N��ȕ����I���G���Ƃ��Ȃ��C���[�W���A�剪���̈ӎ��̗���̂����ɕ����т������Ă������Ƃ͊m�����낤�Ǝv���܂��B
�@���Ȃ݂ɁA�i������܂��A��S�͂łƂ肠�����b��ł����j�A�Ō�́u�e����v�̉̂ɂ��āA�剪���́A�u����ɋ������Ƃ����c�t�|�I�Ȏ���̊��o�c�ɊєV�Ƃ����̐l�́A���^�I�C���W�̂ЂƂ�����v�Ǝw�E���Ă��܂����B
�m���n�`���łӂꂽ�悤�ɁA�u�p���^�X�}�v�i���ہj�́A��Ƃ̘̉_�Ɖ̂̐��E�̓����������\�킷�T�O�ł���Ǝ��͍l���Ă���B���m�ɂ́A�����C�}�[�W���ƚg���t�B�M���[���Ƌ��ہ��p���^�X�}�̎O�g�̊T�O���A���ꂼ��єV���ۊw�A�r���n���w�A��Ƙ_���w�̎O�̐��E��\������L�[���[�h�̑g�ݍ��킹�Ƃ��ĂƂ肠���������ƍl���Ă���B�����ł���ɂ�������炸�A�єV�Ɋւ���L�q�̂Ȃ��Łu�p���^�X�}�v��p�����̂́A���˂Ă���́u���_�v�ł���u�i�L�`�́j�єV���ۊw�́i���`�́j��Ƙ_���w���ۂ���v�Ƃ��������O���ɂ����Ă̂��Ƃ��B�܂�A�єV���ۊw�̐��E�ɂ́A��Ƙ_���w�̐������i���̔Z�x�͈قȂ�ɂ��Ă��j���łɂ��Ċ܂܂�Ă���B
�@���łɏ����Ă����ƁA�{���ň������u���U��v�̉̂ɂ��āA���X�߂ň��p���镶�͂̂Ȃ��œ�j���́A�u���I���E�ɂ����āA�Ԃ͐�̂悤�ɍ~��i��g�j�̂ł͂Ȃ��A�Ԃ͐�Ƃ��āi�����j�~��̂ł���B�v�Ə����Ă���B�����āA���̂悤�ȁu�C���[�W�̕����v�́A�����̐��E�ł͑��݂��邱�Ƃ��\�ۂ��邱�Ƃ��s�\�Ȃ̂ł����āA�����܂Ŏ��I����́u�p�v�̂Ȃ��ŁA�ԂƐ�͌�������̂ł���Ǝw�E���Ă���B�i����̂Ȃ��łȂ��Ƃ��A�X�N���[����f�B�X�v���C�̏�ŃI�[�o�[���b�v����f���Ƃ��Ăł���A�C���[�W�͎��݂Ɍ������邾�낤�B�u������ԎU��ʂ�v�̉̂��߂���剪���̌o�����v���ɂ��A�a�̂̃��J�j�Y����g���b�N�Ɖf��̃��J�j�Y����Z�@�Ƃ͑��݂ɖ��ڂɒʂ������Ă���B�j�������Ƃ���ƁA�u���U��v�̉̂ɉr�܂ꂽ�u���v�́A�r���I�ȁu�g�v�ɕ��ނ����ׂ��Ȃ̂ł͂Ȃ����Ƃ����^�O�������邪�A�����ł��܂��u�r���n���w�́i�L�`�́j�єV���ۊw�Ɂu��Â��v���Ă���v�Ƃ����A���܂��_����Ă��Ȃ��u�����v��O���ɂ����Ă���B
�@�Ȃ��t������ƁA���͂��āA�i���Ƃ��Α�11�͂Łj�A�t�B�M���[���̂͂��炫�������i���`�́j�єV���ۊw�̎������Ȃ��Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ƃ�������|�̂��Ƃ��������B���̂��ƂƁA�{���Ř_���悤�Ƃ��Ă���u���i�C�}�[�W���j���єV�v�u�g�i�t�B�M���[���j���r���v�]�X�̋c�_�͖������Ă���悤�Ɍ�����B�����A���t�����Ƃ��Ė������Ă���B�������A�ڍׂ͂����ꗧ�������Ċm���߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv�����A�����ł́A�єV���ۊw���r���n���w���ۂ��Ă��邩�ǂ����Ƃ��������Ƃ��������ɁA���������єV���ۊw�ɂ�����t�B�M���[���̂͂��炫�Ər���̘_�ɂ�����t�B�M���[���i�p�j�̂���l�Ƃ́A���̈Ӗ��������܂������Ⴄ�B
�����ƌ`�A�u�����ȕ\�����v�Ƃ��Ă�
�@�єV�ɂ�����u���v�́A���̂��邪�܂܂́u�������v�ɒʂ��Ă��܂��B
�@���яG�Y�́A�{���钷���u�Ώ㎄�i���v�ŁA�u�߂����A���ɕ��m�A���n���Ȃ��v�̂��u�̂̂������v���A�Əq�ׂ����Ƃɂӂ�āA���̂悤�ɏ����Ă��܂��B�u�钷�Ɍ��͂���A�̂Ƃ́A��É���[���Ă��A�u�������v�Ȃ̂��B���́u���m�A���n�v�Ƃ��u�p�v�Ƃ��Ă�Ă��đR����\�����Ȃ̂��B�̂́A�������Ӂu���v�Ƃ��Ēa�������Ƃ��Ӑ钷�̍l�ւ́A�܂��Ƃɂ͂��肵�Ă��̂ł���B�v�i�w�{���钷�x�j
�@�܂��A�]���~�Ƃ̑Βk�ł́A�x���N�\���́u�C�}�[�W���v���߂����āA�w�����ƋL���x�̏����Ɍ��y���Ȃ��玟�̂悤�Ɍ���Ă���̂ł��B�i�ȉ��́A�ȑO�A��13�͂Ō��y�������̂́u���S�Łv�ł��B�j
�@�����Ō�����u��ϓI�ł��Ȃ���A�q�ϓI�ł��Ȃ��������ڂȒm�o�o���v�Ƃ��Ắu���v�A���邢�́A��ϓI�ł�����A�q�ϓI�ł�����u���t�̓����v�A���Ȃ킿�u����������̓����v�Ƃ́A�J�~�i���R�j���єV��ʂ��Ď��Ȃ��r�q�F�r���q�߁r�Ƃ��Ắu�̂�v�R�g�o�ł���A���A���R�i�J�~�j���r�ފєV�̉́����Ƃ��Ắu�܂����v�R�g�o�ł�����܂��B�����āA���̂悤�ȁu�̂�v��̂���u�܂����v��̂ւ̍\���]���̂����ɑ��^����A���A���̓]���̔}�̂ƂȂ���̂��A��܂Ƃ����́u���ˁv�ł���Ƃ���́u������v�ɂق��Ȃ�܂���B���́u������v�́A�y�m�J������u���v�~��v�A���Ȃ킿�l�̓��Ȃ�u�ޔ��v�ɒʂ��Ă���ł��傤�B�u����͖��`��B�r�̂͗L�`�Ȃ�B���ׂČ`�Ȃ����̂ɂ͗�ƁU�܂鎖�Ȃ��B�`������̂ɂ͗삻�̂����ɂƁU�܂�Ď������B�v�i�w�^���فx�j
�@���яG�Y�́w�{���钷�x�ŁA�u���i����j���鐺�̃J�^�`�v�Ƃ����\����p���܂��m���n�B����́A�u�����킯���M�v�Ɂu�J�i�V�~�c���P���o�A���m�d�J���A�߃j���m�A���n�A�����m��B�v�]�X�Ƃ���̂����p�������͂̂Ȃ��ɂłĂ�����̂ł��B
�@��j���́A�w�Ԓ��̎g�x�̊єV�̏͂̌��т̕��ɁA�u���ɂ����̉̐l�����́A��v�킹���̒��Ɉ�Ђ̏ے��I�ȁq���r�𓊂����ގ��A���`�̐����C����Ђ̐o���j�Ƃ��Đ�Ɍ�������悤�ɁA�v�����Ìł��Ĉ�̌`�邱�Ƃ������̂ł���B�q���r�Ƃ������ɉf�����Ƃɂ���āA�q�v���r�͐������܂܂��̎p��蒅������B�v�Ə����Ă��܂������A�����ł�����u�`�v��A���̋[�l�����ꂽ�\���ł���u�p�v���A�u�v�Ёv���f�����u�q���r�̃C���[�W�v�ł���A�u���i����j���鐺�̃J�^�`�v�̂����Ɍ����u�߂��݂̌^�v���Ȃ킿�u�����ȕ\�����v���̂��̂Ȃ̂ł��B
�m���n���������́w���яG�Y�ƃE�B�g�Q���V���^�C���x�ŁA�u�����鐺�̃J�^�`�v���߂��鏬�яG�Y�̕��͂Ɋւ��āA���̂悤�ɏ����Ă���B
�@�����ŁA���t��ӂ�܂��ɂȂ������Ɓi�����I�Ȃ��́A�������A�p�j���u�O�i�v�������́u�ߐڍ��v�A�S�̂Ȃ��ŋN���Ă��邱�Ɓi���I�Ȃ��́A���̂̂��͂�A�Ӂj���u��i�v�������́u���u���v�ƂƂ炦�Ă݂�B���́u�O�i�^��i�v�W�́A�ƂĂ����p�͈͂��L���B
�@���Ƃ��A��j���́w���{�̃��g���b�N�x�́u�p�v���Ƃ肠�����͂̂Ȃ��ŁA�u�O�i��i�̓�d�\���������ς�F���̂��߂̎d�|���ł���Ƃ����l���v�ɂ��Ăӂ�A���m�̉����́u��i�v�ɍ\������鐢�E�i�E���i���j�ɏd�_������A�Y�Ȓ��S�ł������̂ɑ��āA���{�̉����͑O�i�i���o�I���o�I���ʁj�ɏd�_������A���Ғ��S�ł����āA�u���i���v�̊ϋq�́A�c�\�Y�́u��јZ����ٌc�̎����Ƃ��Č���v�̂ł͂Ȃ��A�u�ٌc�̎����Ƃ��Ă̔�јZ��������v�̂��Ə����Ă���B
���r���Ǝp�A���邢�́u�a�̂̓C���[�W�ł͂Ȃ��v
�@���ɁA�r���ɂƂ��Ă̚g�B����Ɋ֘A���āA�������z�N���Ă���̂́A�u�a�̂̓C���[�W�ł͂Ȃ��v�Ƃ����r���̍l���ł��B���m�ɂ́A��j���ɂ���Ă��̂悤�ɋK�肳�ꂽ�A�r���̘a�̊ςł��B�w�Ԓ��̎g�x�Ř_����ꂽ�Ƃ�����A��Ⓑ���Ȃ�܂����A��Ƃɐ����y�ӏ����܂߂āA�܂邲�Ɣ����������܂��B�i�ȉ��̕��͂́A�ȑO�A��12�͂ň��p�������̂́u���S�Łv�ł��B�j
�@�������A�������܂��B���p�����ɕp�o����u���l�̌��v��u���l�̌��̌^�v�A�u����̌^�v�A�����āu�p�v���߂����āB
�@�a�̂ɂ����鉿�l�̌��̌^�A�܂�A�u���͂�v��u���v�A�u�H���l�v��u�P��d䆂��[�v�Ƃ��������I�̌��i�����j�́u���f���v�ƂȂ�̂́A���I�ΏۂƂ���ɑ���S�̍\���Ƃ������������u���t�̌^�v�A���Ȃ킿�u�p�v�ɂق��Ȃ�܂���B�u�q���l�̌��̌^�r�i�H���E�d���Ȃǁj��тт����̂Ƃ��ė������q���t�̌^�r���u�p�v�Ȃ̂ł���v�B
�@�莁�ɂ��ƁA�u���l�̌��̌^�v�Ƃ́u��ς̍\���Ƃ��ꂪ�o��Ӗ��̌^�v�ł����āA�����ł����u�Ӗ��v�́A�F���□�̂悤�ɁA����I�T�O�ɂ���āi�u�H���v�u���v�u���͂�v���X�̗ނɁj���ނ��邱�Ƃ͂ł��Ă��A������L�q���邱�Ƃ͂ł��܂���B�������I���l�Ƃ��đ̌����邵���Ȃ����̂ł��B���l�̌��̌^�͌����ɐ旧���đ��݂��A���݂���́u�Ӗ��̌^�v���Ȃ킿�u�\�߂���ꂽ�q�Ӗ��r�̔͗�v�̂��ƂɂƂ炦���܂��B�u�܂�A���I���E�ɑ�����Ӗ��́A������\�����鎞�ɂ��̌����鎞���A�����Ƃ����_�@��K�v�Ƃ��Ȃ��B����́A��������͎������č݂�̂ł���B�v
�@�܂��A�u���t�̌^�v�ɂ��ẮA�r���́u�̂͂��U��݂��������A�r����������ɁA���ƂȂ����ɂ����͂�ɂ�����邱�Ƃ̂���Ȃ�ׂ��B���Ƃ��r�̂Ƃ��ЂāA���ɂ��Ă悭�����������������̂Ȃ�v�i�×����[���j�Ƃ������t���ӂ܂��āA���̂悤�ɘ_�����܂��B
�@���킭�A�����Ŗ��ɂȂ��Ă���̂́A�[���l���Ă͂��߂Ĕ[�������悤�ȓ��e�̉��s�ł͂Ȃ��A�\�ʓI�Ȍ��t�̑g�ݗ��Ăł���u�����v�ƁA�a�̂��I�ɑ��݂�����u���v�ł���B��ʂɉ����Ƃ��̌����Ƃ͒�R���̂Ȃ������Ȕ}�̂ł����āA��X�́A�����Ɍ��t�̈Ӗ��ɐG��Ă���悤�Ɋ����Ă���B�������a�̂́A�r�݂������邱�Ɓi�r�́j�ɂ���āA��̉����I���̂Ƃ��Đl�X�̑O�ɂ������B�����Ȕ}�̂ł���������ɁA�s�����ȁA���̕�������^���A�a�̂���́u���m�v�ɂ���B���l�ɁA���܂̒�^�������a�̂̌������A�a�̂Ɉ��̕������������炷�B�����āu���́q�����r���A���̊O�`�i�n�߂ƏI��̂͂����肵���S�̐��j�Ɠ����\���i�e�v�f�ٖ̋��ȓ����W�j�������̂Ƃ��đ������鎞�A�������X�́A�q���t�̌^�r�ƌ����v�B
�@�莁�̐����Ƃ���ɂ��������āA�̂̎p�Ƃ͂Ȃɂ�������ƁA����͂܂��A�u���l�̌��̌^���S�v�Ɓu���t�̌^�����v�Ƃ��\����̂ƂȂ����������ł���A���̂����u�S�v�ɂ�����镔���́u��ς̍\���v�Ɓu�Ӗ��i�̌��������I���l�j�̌^�v����Ȃ�A�u���v�ɂ�����镔���́u�����v���Ȃ킿�\�ʓI�Ȍ��t�̑g�ݗ��ĂƁu���v���Ȃ킿�����I�`�ۂ���Ȃ�܂��B���ꂪ�A����u�p�v�̍L�`�̒�`�ł��B
�@����ɑ��āA�u��^�������a�̂́q�����r���A���̊O�`�Ɠ����\���������̂Ƃ��đ������鎞�A�������X�́A�q���t�̌^�r�ƌ����v�Ƃ��A�u���t����́q���m�r�ƂȂ��Ĉ���u�p�v�����悤�Ɂq�����r���ł��Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�ȂǂƂ�����Ƃ��A�����Ř_�����Ă���̂́A������`�̎p�ł���Ƃ����Ă����ł��傤�B
�@��ڂ͌�҂ɁA�܂�u�����v�Ƃ��Ắu�p�v�ɂ���܂��m���n�B���Ƃ���ƁA�u���v�͂ǂ��Ȃ�̂��B���̎����p�̂悵�����ɉe������i�u���ɂ��Ă悭�����������������̂Ȃ�v�j�Ƃ����鉹���I�`�ۂ̕��́A���t�̌^�Ƃ��Ă̌����Ƃǂ̂悤�ȊW���ނ��Ԃ̂��B
�@
�m���n��j���w���{�̃��g���b�N�x�ɂ��ƁA�єV�͉������̌㔼�ŘZ�̐���]���Ă��邪�A���̕��@�̓����́A�̂̕\�w�E�O�`�i���O�i�j�ɑ�����u���ƂA���܁v�̂悵�����ƁA���e�i����i�j�ɑ�����u������A�܂��ƁA�g�v�̂悵�����Ƃ�����̂��̂������g�������A�������������Ɨ��������l�ړx�Ƃ��ē�����d�ň����A���l���f���s���Ă��邱�Ƃɂ���B
�@���̊єV�́u���܁v���A��ɏr���ɂ���ċ[�l������u�p�v�ƌĂꂽ�B�l�ɓ��ʂ̐S�ƊO�ʂ̎p������悤�ɁA�̂ɂ��S�i�[���S����i�j�Ǝp�i���̒��ׂ�C���[�W�̏d�w���O�i�j������B�u�̐l�������̂̊O�`�ɂ��āA�u���܁v�����u�p�v�Ƃ����[�l�I�Ȍ��t��p����悤�ɂȂ����Ƃ������Ƃ́A�̂̊O�`���A���e���^�Ԃ��߂̒P�Ȃ�}�̂ł͂Ȃ��A�l�̐g�̂̂悤�Ɉ�̓���I�S�̂Ƃ��Ď������Ă��邱�Ƃ̎��o�̕\��ł������B�v
���p�ƚg�A�u�`���ݏo�����́v�Ƃ��Ă�
�@�u�p�v�Ɓu���v�̊W�͂ǂ��Ȃ��Ă���̂��m���n�B�n���ז����́u�̍��́q���r�����ǂݏグ�A�r����������v�i�����טY�E�ѐm�ҁw���Ȃ鐺�@�a�̂ɂЂ��ޗ́x�����j�ɁA�肪���肪����܂����B�ȉ��A��◐�\�ȕ���������āA�n�����̋c�_���g���[�X���܂��B
�@�n�����́A���̘_�l�ŁA�r���̂����u���[�v���Ȃ킿�u�p�v�Ƃ́u�̂̕��́v�ł��邱�ƁA�܂蕶���ŏ����ꂽ�a�̂̎��̂Â����i�����j�ł��������Ƃ�O���ɂ����Ă��܂��B�����āA�r�����̂̎p�̗��j�I�ϑJ�ɂ�����������Ƃ��肪����ɂ��Ȃ���A�p�ɂ́A���̎�����L�́u���ݐ��v�ƁA������Đ�����u���j���v�̓�̑��ʂ����邱�Ƃ��w�E���܂��B�̂̓��̐[���S�̓`�����̘_�̒��ɂ������r���ɂƂ��āA�̐S�Ȃ̂́A��҂̗��j���������͓`���i�p���j���ł��������Ƃ͌��₷���ł��傤�B
�@�������Ƃ���ƁA�u�×����[���v�Ɂu�̂͂��U��݂��������A�r����������Ɂv�]�X�Ƃ���A�܂��u�������Ɖ̍��v���땶�ɁA�u��`�m���ق����n�͉͕̂K�����A�G�̏��̂��̂̐F�F�̂Ɂm�O�n�̐��������A�����Â����̂����݂̂��܂��܂��m�n�݂̂��m���n�����m���n�肷���l�ɂ̂݁A��ނɂ͂��炴�鎖�Ȃ�B������݂������A�������Ȃ��߂���ɁA���ɂ���������������邷�����̂���Ȃ�ׂ��B���ƂւA�ݒ����ƕ����b�́A�u���₠��ʁv�Ƃ��ЁA�I���̊єV�A�u���ɑ���R�̈�́v�Ȃǂ��ւ�₤�ɂ�ނׂ��Ȃ�ׂ��B�v�Ƃ���̂́A�������s���̈������ƂɂȂ肻���ł��B
�@�Ƃ����̂��A�r������������u���v�́A��E�g�̐��������u��Ɏc��Ȃ��v�A�܂�u���ݐ��v������Ƃ�����̂ł���A�܂��u���v�́A�����̏�̐l�X�̐S����ɂȂ��Ă����Ԃ��ے��I�Ɏ���������̂ł����A���̂悤�ȁu�����v���܂��u���ݐ��v�ɐ[���������Ă���A������u���������قǁu���j���v�Ƃ̂Ȃ�����������˂Ȃ�����ł��B
�@�����œn���������ڂ���̂͌É̉r�u�A���Ȃ킿�u�É̂�܂ɍ��킹�ĉr�u����s�ׁv�i����ɂ�������̂����̈��Ƃ��Ăӂ��ށj�ł��B�r���̂����̂��u�ǂݏグ��v�s�ׂɁA���̌É̉r�u�̃C���[�W���d�ˍ��킹�邱�ƂŁA��Ɏc��Ȃ��u���v�Ɨ��j�I�Ȍp�����Ƃ̐ړ_���݂��������Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����A�u�̂��Ƃ𐺂ɏo���s�ׁv�ł����āu�����݂��A���j�I�ɒ~�ς���Ă����a�̂̓`���̒��ɐg��u�����Ɓv���\�ɂȂ�̂ł͂Ȃ����A�Ƃ����킯�ł��B
�@���O�ɂ͊m������̂Ƃ��đ��݂��Ȃ����A�ォ��A�V�����̂��Ƃ̍H�v�������ď��߂āA���������n�߂��炻�������`�������������̂��Ƃ��m�M�������́B���́A�n�����ɂ��r���I�u�`���v�̒�`��ǂ�ŁA�i�����Ă܂��A���̂悤�Șa�̓I�u�`���v���͂��ł���p���h�L�V�J���œ|���I�Ȑ��i���A�u���̌Í��W�̏��ɂ��ւ邪���Ƃ��A�l�̂��������Ƃ��āA���Â̌��̗t�ƂȂ�ɂ���A�t�̉Ԃ����ÂˁA�H�̍g�t�����Ă��A�̂Ƃ��ӂ��̂Ȃ���܂����A�F�����������m��l���Ȃ��A�������͂��Ƃ̐S�Ƃ����ׂ��B�v�i�×����[���j�Ƃ������͒��́u���Ƃ̐S�v�ɂ��y��ł��邱�ƂɁA�v�����͂��j�A�����z�N���Ă����̂́A���������̓N�w�v�l�ɂ��ď����ꂽ�����i�R���u�N���w�V�g�̋L���w�x�j�́A�\���ƌ������̊W���߂���c�_�̒��ɏo�Ă���u�Ō�Ɍ������̂��A�ŏ��ɂ������������ł��邩�̂��Ƃ��A���₽�Ԃ���ۂɌ����Ƃ��đ��݂���v�Ƃ������͂ł���A�܂��A�����̊��杂��t�B�N�V�����⋕�U�ł͂Ȃ�����Ƃ��āA�܂�u�g�v�i���g�j�Ƃ��ė�������g�{�����̋c�_�i�u�g�Ƃ��Ẵ}���R�`�v�A�u���^�u�g�Ƃ��Ă̐����v�Ȃǁj�ł����B
�@���c���l���́w�g�{�����ƕ��J�s�l�x�ŁA�u�����ɓ���ʂ��̂͂��ׂăt�B�M���[���m�g�A�\���n�ł����Ȃ��v�Ƃ����p�X�J���̌��t�������A����Ɋ֘A�Â��Ȃ���A�u���������g�{�́A�m����ɂ��V��́n�u�\��v�ipre'figuration�j�����u�g�v�ɂ����Ȃ����V��ɂ����āu�^�Ӂv�Ƃ��Ď�������鄟���́u���\���v���߂����āw�}�`�E�����_�x���������̂������B�v�Ǝw�E���Ă��܂����B���̋L�q���肪����ɁA�ȉ��A�_�w�I�C���[�W�_�Ƃ������ׂ��p�X�J���̃t�B�M���[���_����˂��Ă��������Ǝv���܂��B
�@����O�玁�́u���Ɣ�ք����L������\���ցv�i�w���Ɣ�ց\���p�X�J���q�����Ȃ����́r�̔F���x��U�́A�w�R�s�[�@����N�w�̖`���U�x���o�j�ɁA�u���̗���ɂ����ė���ׂ����̂�\������ƌ��Ȃ��ꂽ�����v�A���Ƃ��A�m�A�̔��D�̓L���X�g����̏ے��ł���A�߉z�Ղ̋]���̎q�r�̓C�G�X�E�L���X�g�̕\���ł���Ƃ������悤�ɁA�u�����ɂ���ē`������l���A�����A���x�Ȃǂ��A�₪�ăL���X�g�̗��Ղɂ����ĊJ��������荂���u���݁v���A���炩���ߏے��Ƃ��Ă��ڂ낰�ɕ\�����Ă���ƍl������ꍇ�v�A�����͓`���I�ȃL���X�g���_�w�ɂ����āu�\���v�ifigura�Cfigure�j�ƌĂꂽ�A�Ƃ���܂��B�ȉ��A���쎁�̋c�_�����܂��B
�@�J�g���b�N�̐��`�� (�~�T) �ɂ����āA���ʂ��ꂽ�p���ƃu�h�E���́A�L���X�g�̑̂ƌ���\��������̂ł���Ƃ����B�������A���̂悤�Ȑ��̂��u�ۂ�ifigure�Ctype�j�A���iimage�j�A�����iantitype�j���v�Ƃ��āA�L���₵�邵�̊ϔO�Ƃ̖��m�ȋ�ʂȂ��ɗp����ƁA�u���ł��鐹�̂͌��^�Ƃ��Ă̐_�L���X�g�ł͂��肦�Ȃ��̂ł͂Ȃ����v�Ƃ����^��ɂ��炳��邱�ƂɂȂ�B�����Ńp�X�J���́A�u�\���v�i�t�B�M���[���j�Ƃ����ϔO������̃L���X�g���i��_�̒��S�ɐ����A�~�T�ɂ����ČJ��Ԃ���u���������o�����v�ƁA���̂̔�ւ̐��������ł���L���X�g�̎���Ǝ��Ƃ����u������̏o�����v�Ƃ̈�v�A���邢�́u�L���������R�s�[�v�Ɓu���́����^���I���W�i���v�Ƃ̈�v���A�i���ł͂Ȃ����Ԃ̂������Ŏ�������u�o�����v�Ƃ��Đ��̂��Ƃ炦���B
�@�������A���߂ɐ_�Ƌ��ɂ��������i�R�g�o�j�A������n��Ȃ������S�X���A�u����ɂ���Ď��R�̂������ɏo�������Ƃ��A���̐_���͘I�ɂȂ�ǂ��납�A�������ăC�G�X�̐l�Ԑ��ɂ���Ĉ�w�[���B����Ă��܂����v�B�u���S�X�v�i���R�Ȃ������j�̒��ɂ���u�ۂ�v�i���R�s�[�j�ɂ���Ďw�����ꂽ�I���W�i���j�̌��O���u�\�ہv�i���R�s�[�j�ƈ�v���邱�Ƃɂ���āA�������ĕ\�ەs�\�ɂȂ�Ƃ����u�����ׂ��v���Ԃ������Ă���̂ł���B�p�X�J���ɂƂ��ĐM�Ƃ́A�����������ɂ����āA���S�X�̌��O���u���邱�ƂȂ��ɁA����邱�Ɓv�ł������B�u���S�X�̌��O�Ƃ����O�����苎���Ă��܂��A�\���͓��B�ڕW�Ƃ��ẴI���W�i���������A����ɕ��V���錶���ɂȂ�v����ł���B
�@�p�X�J���̃t�B�M���[���_�ɂ��ẮA��Ƃ́u���ہ��p���^�X�}�v���T�ς������ƂŁA���炽�߂ĂƂ肠����@�����Ǝv���܂��B�����ł́A�r���́u�p�v���u�`���ݏo�����́v���A�u���Ƃ̐S�v���Ȃ킿������́u�I���W�i���v�ƁA�J��Ԃ��������ĉr�܂��X�̘a�̍�i�Ƃ̈�v���A�̍����̏�ɂ����āA�Ƃ����������ɂ��`�����Ȃ킿�u�`�u�v�ɂ�����u���v�̗͂���Ď�������u�o�����v�Ƃ��Ắu�g�i�t�B�M���[���j�v�ł��������Ƃ��m�F���Ă��������Ǝv���܂��B
�@
�m���n���������u�`�v�Ɓu�p�v�̊W�͂ǂ��Ȃ��Ă���̂��B���邢�́u�`�v�Ɓu�^�v�Ɓu�p�v�͂ǂ������W�ɂ���̂��B���̂��Ƃ��l���邤���ŁA���{�G���Y���w����x�ф����`�̐��Ԏ��x�Ɏ��߂�ꂽ���́i�����̕���Ɠ����̃^�C�g�����t���ꂽ�����ŁA�t�H�V�����w����@�`�̐����x�̖�҂��Ƃ������u�������߂��v���́j���Q�l�ɂȂ�B
�@���҂͂����ŁA�`�͂��̂���������u���݂ȃ��^�����t�H�[�Y������Ԃ��A�₦�ԂȂ��݂�����̕K�R����݂�����̎��R�������Ă���v�Ƃ����t�H�V�����̌��t�������A�X�e�B���ƃt�H�����Ƃ�������߂����āA�u�킽�����������ʃX�e�B���́A�t�H�������`���邢�͌`�ԂƖĂ���Ƃ��ɂ́A�������������Ƃ������́A���̓��������������ڂ�������悤�Ȃ��̂�z�肵�Ă���v�Ə����Ă���B
�@�����āA���ɉf����e����u�G�������v�A�l�`�i�ЂƂ����A���̏ꍇ�́u�����v�͗֊s������`���A�Ȃ����F���Ă��Ȃ��G�̂��Ɓj�܂ł̋��e������u�C�}�[�W���v�̌�`�ɂӂꂽ���ƂŁA�u�t�B�M���[���Ƃ�����ɂȂ�ƁA����Ɏ��Ԃ͕������A�t�H�����A�X�e�B���A�C�}�[�W�������̌�̂Ȃ��ɗ������A�Ӗ��̉Q���䂫�N�����Ă���v�Ə����A�X�^���_�[�h���a���T���ڂ̂R�ތ^�P�U��̖��i�u�`�A�p�A�O�`�A�`�ԁv��u�ё��v�u�}�v�u�g�����v�̊G�D�v�ɂ͂��܂��āu���Ƃ̈��A���p�A���ʁv����u���p�̍\���v�܂Łj���ꗗ����B�u��������Ă���ƁA�t�B�M���[���Ƃ�����ɂ́A��ڗđR�Ƃ����ܒ~�̂��邱�Ƃ����������B���ӂ̒肩�łȂ����́A�s����ȁA��ꓮ���Ă�܂ʂ��̂̌`�Ԃ́A�C�}�[�W���̗̕��ł���B�v�u�c�g�����v�̃L���O�A�N�B�[���A�W���b�N�̊G�D�ɂ́A�l���ƂȂ�^�ƂȂ���������Ȃ��`����A���p�̂��傤���ȍ\���ɂ͕��i������̂�����A�t�B�M���[���̓X�e�B��������A�X�e�B���̓t�B�M���[���̏W���j�ɂȂ�B�v
�@�ȏ�̂܂ݐH���I�Ȕ�����������A�u�`�v�Ƃ́i��ꓮ���Ă�܂ʁu�C�}�[�W���v�̂悤�Ɂj���R�ɕϐg�E�ϑԂ����肩���������I�Ȃ��̂ŁA�u�p���t�B�M���[���v�͂��̂�������Ƃ���������ł��邱�Ƃ��A���ڂ낰�Ȃ��畂���т������Ă���B���яG�Y�̌�b���g���A�u�����ȕ\�����v�Ƃ��Ă̌`�i�^�j�A�u�đR����\�����v�Ƃ��Ă̎p�A�Ƃ������Ƃ��납�B
�@�܂��A��Ώ��j�����u�]��̔��w�����a�̂ɂ�����S�E���E�p�̘A�ցv�Ř_���Ă���悤�ɁA�u�p�v�Ƃ́u��������`�v�Ȃ̂�������Ȃ��B���́u��������`�v�i�������́A�O�Y�N�Ǝ��������Ƃ���́u�����C���[�W�v�i�w�f��Ƃ͉��������t�����X�f��v�z�j�x�j�j�̊T�O�ɂ��ẮA��Ɖ̘_�̐��E��ˌ����A��j���́u�r�݂���S�v�̊T�O�ɂ����������čl�@�������ƂŁA���炽�߂ĂƂ肠���邱�ƂɂȂ�Ǝv���B
���g�ɂ��ރR�g�o�A�Ӗ��̎��
�@�剪�M���w���̓��{��x�ɁA�������́u�������v�ɘ^���ꂽ�A�r�����]�̂��߂���G�s�\�[�h���Љ��Ă��܂��B
�@�����̎t�E�r�b������Ƃ��r����K��A���]�͉̉̂����Ƃ����˂��B���Ԃł́u�ʉe�ɉԂ̎p���������ĂĂ����ւ������ʕ�̂��炭���v�����`����Ă������A�r�����g���������͎̂��̉̂������B
�@
�@�@�[����Ζ�ׂ̏H���g�ɂ��݂��G�Ȃ��Ȃ�ӂ������̗�
�@
�@�r�b�͒����ɁA���̉̂́u�g�ɂ��݂āv�������I�ł��肷���A�������ė]�C�ɂƂڂ����ƌ�����B�剪���́A�r�b�̕]�Ɏ^�ӂ������A��O��͂��炸�����Ȃ̎���Ɏv����Ƃ��A�����A�u�r���͂����炭���������ᔻ�̂��邱�Ƃ͏\�����m�̏�ŁA���̌�������ėp�����ɂ������Ȃ��v�Ə����Ă��܂��B���̍����́A�u���݂�v�Ƃ�����Ɗ��o�̓��{���̂ɂ�����d�v���ɂ���܂��B
�@�剪���ɂ��ƁA�u���̊��o���A�P�ɔ��ɂ��݂���x�̐G�o�̎�������A���_�I�ɂ���Ɛ[�߂��Ă䂭�̂��������̂̑傫�ȓ����v�ł����āA���́u���o�I�Ȃ�����v���u�[����v�̉̂������̂ł͂Ȃ����B���邢�́A�u�g�ɂ��݂āv�Ƃ�������ӂꂽ��ɁA���̂悤�ȁu���㐫���������т��V�����Ӗ��������A�\���I�Ɋ����Ƃ��Ă�������v�����A�r���͂��̉̂��u�����ĉ́v�Ƃ����̂ł͂Ȃ����B�剪���͂��̂悤�Ɏw�E���Ă��܂��B
�@�\�w�̔��ł͂Ȃ��g�̂̓����Ɂu���݂�v���o��A�u�g�ɂ��݂āv�̌�̐V�����Ӗ������ɑ����ꂽ���̂́A�u�L����v�ɂ����Ăł͂Ȃ��A�u�[�݁v�ɂ����ĉ̖̂{��������Ƃ����A�r�����݂�����̌����A��\���Ă����u�傫�Ȓ����I���l�]�|�̈ӎ��v�ł������B����́A�܂�u�[�݁v�ɂ����ĂƂ炦������̂́A�u�r���݂̂Ȃ炸�A�����ȍ~�̘a�́A�����A�\�y�A���ȂȂǁA���|�E�|�\�ɂ����ďd�����ꂽ�u�H���v�Ƃ������O�v�ɂق��Ȃ�Ȃ������B
�@���́A�r���̘_���߂���剪���̋c�_�́A�ȑO�A�i��W�͂Łj�A�r���̎���ɂ͂܂��u���G�o�I�v�������u�g�ɂ��ށv���A��Ƃ̎���Ɏ���Ɓu���G�o�I�v�ȔF���ɂ܂ŒB����A�Ƃ������c�_�Ƃ��킹�ĂƂ肠���܂����B�����ł��炽�߂Č��y�����̂́A�r�������ƂւƘb���]����O�ɁA�єV�Ər���̘̉_�����ɂ���Ă���Ղ��m�F���Ă���������������ł��B����́A��������̐��E�ɍ�������Ɖ̘_�ɂ����Č���I�Ɏ�������́A���Ȃ킿�A���i�C�}�[�W���j�ƚg�i�t�B�M���[���j�Ƃ����܂������ɂƂǂ܂�g�́A���m�ɂ́A�i�O�i�Ƃ��Ắj�g�̂Ɓi��i�Ƃ��Ắj�S�Ƃ̌����̂ł���u�g�v�̂��Ƃɂق��Ȃ�܂���B
�@�����ł�����A���Ă̘b��Ɍ��y���܂��B�ȑO�A�i��13�͂Łj�A���c�Ő����w���y�̒��������������^�Ǝ����錾�t�x����̑������ŁA�u���y�������܂ʼn��y���̂��̂Ƃ��đ����v����]�ƃn���X���b�N�̌��t���Ƃ肠���܂����B
�@�n���X���b�N�́A�u���y�͂����Ȃ銴����A�����Ȃ��i���A��ɕ\�����邱�Ƃ͏o���Ȃ��v�Ƃ�����Ή��y�̍l�����ɗ����Ă��̉��y���_��W�J��������ǁA���Ƃ��u��Ђ̍~�藈�邳�܂Ⓓ�̉H��������̏o�̂��܁v���A�u�����̏����ۂɗ͊w�I�ȈӖ��Ŏ����Ƃ���̂��钮�o��ہv�������炷���Ƃɂ���āu���y�I�ɉ悭�v���Ƃ��ł��邱�Ƃ�F�߂��B�u���̍����⋭���⑁����Y����ʂ��Ď��Ɉ�́u�`�m�t�B�O�[���n�v���^������B��X�قȂ�����ނ̊��o�̊Ԃ��݂ɐڐG���邱�Ƃ̂ł���ސ��ɂ���Ă��́u�`�v�̈�ۂ����̎��o�I�Ȓm�o������̂ł���B�v�i�w���y���_�x�j
�@����������c���̌��t�B�u�n���X���b�N�͂����̋L�q�ɂ����āA�܂��ɔނ���N�ɂȂ��Ĕے肵�悤�Ƃ��Ă������Ɓi�����y�͉�����\������j���A�ɂ߂ėY�قɍm�肵�Ă���悤�Ɏv����B�܂�^�����o��ʂ��ĉ��y�́A����Ƃ�������̂��ɂ߂Đ��X�������N����Ƃ�������̂��B�v�����ł�����u�^�����o�v�����A�u�g�v�Ƃ�������Ŕ�������u���v�Ƃ����ʼn�������u���v�̌`�Ǝp�ƌ^�́A������Ƃ�킯�i���o�I�ȃo�C�A�X�̂��������u�C�}�[�W���v�̌�ɂł͂Ȃ��j�u�t�B�M���[���v�Ƃ�����ɂ�����������u�p�v�̎����Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝ��͍l���Ă��܂��m���n�B
�@��j���́w���ƂƐg�́x�ŁA�������̐g�͓̂�̔F�����v�l�̉�H�������Ă���Ǝw�E���܂��B���S�X�̉�H�ƃ��g���b�N�̉�H������ł��B�����̂����A���g���b�N�̉�H�́A�u�D�ɗ�����v�Ƃ��u���ɓ���v�Ƃ����\��������悤�ɁA�_���i���S�X�j�̉�H�������́u�g�̊��o�v�Ƃ�������u�[���v���߂����Ă���B�u�܂背�g���b�N�Ƃ́A���t�ɂ��g�̂ւ̓��������Ƃ�����ʂ������Ă���v�B�����āA���̉�H�́u���e�v�Ɓu�S�g�Ԑ��v�̓�̍��ō\�������B
�@�����ŘA�z�����̂́A���̏r���̌��t�A�u�̂Ƃ��ӂ��̂Ȃ���܂����A�F�����������m��l���Ȃ��A�������͂��Ƃ̐S�Ƃ����ׂ��v�ł��B�a�̂̓C���[�W�ł͂Ȃ��B�a�̂͑��e�i�p�j�ł���B����ȏr���̘_�̃e�[�[��������ł��܂��B
�@�莁�������u�����̈Ӗ������̌���v�̂��Ƃ��A���́A��Ɖ̘_�̐��E�Ɗ֘A�Â��čl�������ƍ\�z���Ă��܂��B�����̈Ӗ������́u����v�Ƃ́A�����ɂ����āu���ہ��p���^�X�}�v�����������A�����A�Y���u���́v�Ƃł����Â���ׂ��C�}�W�i���[�ȏ�ɂق��Ȃ�Ȃ��A�Ƃ������������ŁB�������A���̘b��͂���ȏ�A�[�ǂ������A�����ł́A�莁�̕��͂ɈӖ��́u����v�Ƃ����ꂪ�o�ꂵ�����ƁA�����āA����͎��́u�g�ɂ��݂�v�Ɠ��`�ł��邱�Ƃɒ��ӂ𑣂��ɂƂǂ߂Ă��������Ǝv���܂��B
�@
�m���n���{�G���Y�́w����x�сx�Ɏ��߂�ꂽ�u�@�B�o���v�ŁA�u�x�������F���v�i�U���@�B�̎�ɂȂ鉺�G�ɖ{������x���V�Í��a�̏W���̎l�G�̂��U�炵���������O�\�Z����g�̐F���A�x�����������A�W�A���p�ُ����j�̑��ԕ��l�}�Ăɗp����ꂽ��@�i�v���`�@�A�d�˓h�葼�j�̌��ʂƁA�Í��a�̏W�̏C���Z�@�i���C�A���C���j�̂���Ƃ̔��I��������_���A�u�قƁR�����@�Ȃ��₳���́@����߂����@����߂�����ʁ@���Ђ����邩�ȁv�ق��̉̂��u���_��t���Ȃ��������������̎p�v�łȂ��߁A�������݁A�u�M�̕䂪�d�Ȃ�ɂ��ގv�������Ȃ��Ɠ�����v�𖡂���������ŁA���̂悤�Ɋ����Ă���B�i���͂����ɁA���̎p�║�̎p�Ȃ�ʁA�u�����̎p�v�Ƃł������ׂ����̂������オ���Ă���̂�������B�j
�i�Q�X���ɑ����j
���v���t�B�[����
�����I���i�Ȃ��͂�E�̂肨�j1950�N�㐶�܂�B���Ɍ��ݏZ�B��N���̂ɏ����ꂽ�a�̂̈Ӗ��������ł���̂͂��������Ƃ��B�ł��A�{���Ɂu�����v�ł��Ă���̂��B�����Ɂu�Ӗ��v�Ȃǂ���̂��B�����������t���g���ĉ�����`�B���邱�Ƃ��̂��̂��s�v�c�Ȍ��ۂ��Ǝv���B
Web�]�_���u�R�[���v28���i2016.04.15�j
���F�ƃN�I���A����38�́@�a�̎O�Ԃ̐��A�єV�E�r���ҁi�����I���j
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU�@2016 All Rights Reserved.
|
| �\���i�ڎ��j�� |