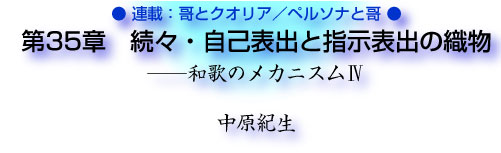|
|
|
Web昡榑帍乽僐乕儔乿 |
|
仭憂姧偺帿 仭杮帍偺昞巻乮栚師乯傊 仭杮帍偺僶僢僋僫儞僶乕 仭撉幰偺暸乛偛堄尒丒姶憐 仭搳峞婯掕 仭娭學幰偺Web僒僀僩 仭僾儔僀僶僔乕億儕僔乕 |
|
亙杮帍偺娭楢儁乕僕亜 |
|
仭乽僇儖僠儍乕丒儗償儏乕乿偺僶僢僋僫儞僶乕 仭昡榑巻乽俴倎 Vue乿偺憤栚師 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
|
仭慶弎偲拹庍傪傔偖傞慜岥忋
丂
丂埲壓丄亀尵岅偵偲偭偰旤偲偼側偵偐亁偺僄僢僙儞僗偲巚傢傟傞傕偺丄偄傢偽媑杮棽柧偺寍弍尵岅尨榑傪帺桼娫愙榖朄偺偐偨偪偱乮偦偺乽摿堎側乿偲宍梕偟偰傕偄偄乽彂偒偞傑乿傪懝側傢側偄偐偨偪偱乯慶弎偟丄庒姳偺拹庍傪傎偳偙偟傑偡丅
丂
丂偦偺慜偵丄杮曆偵愭偩偮拹傪傂偲偮丅
丂嶳忛傓偮傒巵偼乽彫椦廏梇偺僋儕僥傿僇儖丒億僀儞僩乿乮亀暥妛偺僾儘僌儔儉亁乯偱丄彫椦廏梇偺僪僗僩僄僼僗僉僀榑偵尒傜傟傞丄堷梡傗彂偒幨偟偱偼側偔丄尨嶌傪斀暅揑偵嵞峔惉偟偰偄偔婏夦偱堎條側乽彂偒偞傑乿傪傔偖偭偰丄乽彫椦偼亀嵾偲敱亁傪彂偙偆偲偟偰偄傞偺偱偼側偄偩傠偆偐丅偟偐傕丄亀嵾偲敱亁偺彫椦廏梇償傽乕僕儑儞傪偱偼側偔丄柇側尵偄曽偵側傞偑丄彫椦偼偁偺僪僗僩僄僼僗僉僀嶌偺丄偁偺亀嵾偲敱亁傪彂偙偆偲偟偰偄傞偺偱偼側偄偩傠偆偐丅乿偲彂偒丄偦偺栚榑傒傪丄乽尨嶌傪斀暅揑偵憂嶌偡傞乿偙偲傕偟偔偼乽斸昡乿亖乽憂嶌乿偲婯掕偟偰偄傑偡丅
丂偪側傒偵丄偙傟偼媑尨弴擵巵偺乽亀姶憐亁傪偨偳傞丂斣奜曇乿偵彂偄偰偁偭偨偙偲側偺偱偡偑丄孲巌彑媊偺乽堦嬨榋乑擭偺彫椦廏梇乿乮亀暥泏奅亁2002擭俋寧崋乯偵丄暯栰尓偐傜乽亀姶憐亁偼慶弎偩乿偲斸敾傪庴偗偨彫椦廏梇偺斀榑偑徯夘偝傟偰偄傑偡丅乽儀儖僌僜儞傪堦峴偱傕妞傫偱傤偨傜乽慶弎乿偐偳偆偐丄偡偖敾偮偨偩傜偆偵丄悽偺拞偵柍愑擟偺墶峴偙傟偵夁偓偨傞偼側偄丅偩偑丄擭寧偑鉙偮偰摨偠偙偲傪孞曉偡偺傕丄偙偺悽偺偙偲偩偹丄愄丄杔偑乽亀嵾偲敱亁偵偮偄偰乿乮徍榓嬨擭乯傪楢嵹偟偨偲偒丄戝戭氠堦偲偄傆戝抦幆恖偑怴暦偱摨為偺幄尵傪偟偰杔傪殅偮偨傕偺偩丅斵傜偼慶弎偑擩傠惗嶻揑側歾傒偩偲偼丄慡偔抦傜側偄偟丄抦傜偆偲傕偟側偄丅偙傟偼杔偺幄柧偩偲偄偮偰偄偄傕偺偩丄僼儔儞僗偱偼尒偐偗傞偑丄傢偑殸偱偼杔偑弶傔偰偩丄懠偵偁偮偨偲偟偨偲偙傠偱杔偺傗偆偵岺晇傪偙傜偟偰偼傤側偄丅乿
丂傑偨丄撪揷庽巵偺乽僆儕僕僫儕僥傿偵偮偄偰偺岴巕偺嫵偊乿偵丄乽弎傋偰嶌傜偢乿乮亀榑岅亁弎帶戞幍偺堦乯偺堄枴傪傔偖傞敀愳惷偺暥復偑堷偐傟偰偄傑偡丅乽夁嫀偺偁傜備傞惛恄揑堚嶻偼丄偙偙偵偍偄偰婯斖揑側傕偺偵傑偱崅傔傜傟傞丅偟偐傕岴巕偼丄偦偺偡傋偰傪揱摑偺憂巒幰偲偟偰偺廃岞偵婣偟偨丄偦偟偰岴巕帺恎偼丄傒偢偐傜傪乽弎傋偰嶌傜偞傞乿傕偺偲婯掕偡傞丅岴巕偼丄偦偺傛偆側揱摑偺壙抣懱宯偱偁傞乽暥乿偺丄慶弎幰偨傞偙偲偵娒傫偠傛偆偲偡傞丅偟偐偟幚偼丄偙偺傛偆偵柍庡懱揑側庡懱偺帺妎偺偆偪偵偙偦丄憂憿偺旈枾偑偁偭偨偺偱偁傞丅揱摑偼塣摦傪傕偮傕偺偱側偗傟偽側傜側偄丅塣摦偼丄尨揰傊偺夞婣傪捠偠偰丄偦偺楌巎揑壜擻惈傪妋偐傔傞丅偦偺夞婣偲憂憿偺尷傝側偄塣摦偺忋偵丄揱摑偼惗偒偰備偔偺偱偁傞丅乿乮亀岴巕揱亁丆亀敀愳惷挊嶌廤俇 恄榖偲巚憐亁乯
丂側偵偑尵偄偨偄偺偐偲偄偆偲丄巹偑偙傟偐傜帋傒傞乽慶弎乿偼丄彫椦廏梇偑乽敪柧乿偟偨憂憿亖斸昡偲偄偆崅搙側惗嶻揑塩傒傪柾偦偆偲偡傞傕偺偱偼側偄偟丄傑偟偰傗乽柍庡懱揑側庡懱偺帺妎乿傪傕偭偨慶弎幰丒岴巕偺恀帡帠傪婇偰傞傕偺偱傕側偔偰丄偨偩帤媊捠傝偺慶弎偱偁傞偲偄偆偙偲丄偙傟偵恠偒傑偡丅
丂尵傢偢傕偑側偺幹懌傪偔傢偊傞偲丄乽拹庍乿偵偮偄偰傕丄偦傟偼丄乽拲庍妛偼丄乽揘妛乿傪僨傿僐儞僗僩儔僋僩偡傞乪奜晹惈乫偱偁傝乿丄亀榑岅亁傪乽嵟忋帄嬌塅拡戞堦偺彂乿偲撉傫偩埳摗恗嵵埲屻丄乽揘妛偼拲庍妛偲偟偰偟偐偁傝偊側偄乿乮暱扟峴恖乽峕屗偺巚憐乿丆亀尰戙巚憐亁乵椪帪憹姧乶1986擭9寧崋乽摿廤乥峕屗妛偺偡偡傔乿乯偲尵傢傟傞傛偆側堄枴崌偄偺傕偺偱偼側偄偟丄傑偟偰傗丄巕埨愰朚巵偑亀乽帠審乿偲偟偰偺渉渜妛亁偱弎傋偰偄傞傛偆側丄乽岴巕偺摴偼丄愭墹偺摴側傝乿偲偄偆渉渜偺尵梩傪乽尵愢亖帠審丒弌棃帠乿偲偟偰偲傜偊傞傾僾儘乕僠偑愃偗傛偆偲偡傞乽僥僉僗僩偺撪懁傊偺撉傒偺怺壔乿丄偡側傢偪乽強梌偺尵愢偵傛偭偰傕偆堦偮偺傎傫偲偆偺尵愢丄僥僉僗僩偺昅幰偺傎傫偲偆偺堄恾偲偟偰撉傒偲傜傟偨尵愢傪嵞峔惉偡傞偙偲乿傪傔偞偡傾僾儘乕僠偵梌偡傞傕偺偱傕側偔偰丄偨偩旛朰榐偑傢傝偺巹拹傪傎偳偙偡偲偄偆丄儕僥儔儖側堄枴偱偟偐偁傝傑偣傫丅乮偦傟偵偟偰傕乽尵愢亖帠審丒弌棃帠乿偼丄偄偐偵傕乽惗婲丄僄傾傾僀僌僯僗乿傪巚傢偣傞丅乯
丂
仭媑杮棽柧偺寍弍尵岅尨榑乮尵岅偺棟榑乯
丂
嘥丏尵岅偺棟榑劅帺屓昞弌偲巜帵昞弌
丂
嘥亅侾丏尵岅偺杮幙
丂
乮侾乯尵岅敪惗偺婡峔劅尪憐偲尰幚
丂
仢尵岅丄暥妛丄寍弍偼丄儅儖僋僗偑傑偲傕偵偲傝偁偘側偐偭偨僥乕儅偺傂偲偮偩偑丄亀僪僀僣丒僀僨僆儘僊乕亁偺僼僅僀僄儖僶僢僴榑偵師偺尵梩偑巆偝傟偰偄傞丅乽尵岅偼堄幆偲偦偺婲尮偺帪傪摨偆偡傞丅劅劅尵岅偲偼懠恖偵偲偮偰傕巹帺恎偵偲偮偰傕懚嵼偡傞偲偙傠偺幚慔揑側尰幚揑側堄幆偱偁傝丄傑偨丄堄幆偲摨偠偔丄懠恖偲偺岎捠偺梸朷媦傃昁梫偐傜敪惗偟偨傕偺偱偁傞丅乿
丂側偤丄捠懎儅儖僋僗庡媊幰偨偪偼乽懠恖偵偲偮偰傕巹帺恎偵偲偮偰傕懚嵼偡傞偲偙傠偺幚慔揑側尰幚揑側堄幆乿乮懠偺恖乆偵偲偭偰懚嵼偡傞偲偲傕偵丄偦偺偙偲偵傛偭偰偼偠傔偰巹帺恎偵偲偭偰傕傑偨幚嵺偵懚嵼偡傞偲偙傠偺尰幚揑堄幆乯偲偄偆傛偆側丄幪偰傞偵偼惿偟偄旝柇側偄偄傑傢偟傪搳偘偡偰偰偟傑偆偺偩傠偆偐丅儅儖僋僗偑乽堄幆乿偲偙偙偱偄偆偲偒丄偠傇傫偵懳徾揑偵側偭偨乽恖娫揑乿堄幆傪傕傫偩偄偵偟偰偍傝丄乽幚慔揑乿偲偄偆偲偒丄乽奜壔乿偝傟偨堄幆傪堄枴偟偰偄傞丅偙偆偄偆尷掕偺傕偲偱丄奜壔偝傟偨尰幚揑側堄幆偲偟偰偺乽尵岅乿偼丄偠傇傫偵偲偭偰恖娫偲偟偰懳徾揑偵側傝丄偩偐傜偙偦尰幚揑恖娫偲偺娭學偺堄幆丄偄傢偽懳懠揑堄幆偺奜壔偵側傞丅
丂尵岅偑乽懠恖偲偺岎捠偺梸朷媦傃昁梫偐傜敪惗偟偨乿偲偡傞尒夝偼丄乽恖娫偺岎嵺乮岎捠乯偺庤抜偲偟偰曭巇偡傞偨傔偵懚嵼偟乿偲偄偆僗僞乕儕儞偺夵嶌傪備傞偡傕偺偱偼側偄丅亀僪僀僣丒僀僨僆儘僊乕亁偼丄尵岅偵偮偄偰傕僗僞乕儕儞側偳傛傝偢偭偲忋摍偱偁偭偰丄乽帺屓帺恎偲偺岎捠偺梸朷媦傃昁梫偐傜敪惗偟偨乿偲偄偄偐偊偰傕堦岦偝偟偮偐偊側偄乽奜壔乿偺奣擮偲偟偰偙傟傪偮偐偭偰偄傞偙偲偼丄偦偺巚憐宍惉偺夁掱傪偨偳偭偨偙偲偺偁傞傕偺偵偼丄岆夝偺梋抧偼側偄丅
丂
仢楯摥偺敪払偑尵岅偺敪惗傪偆側偑偟偨偙偲偲丄偆側偑偝傟偨尵岅傪恖娫偑帺敪揑偵敪偡傞偙偲偲偺偁偄偩偵偼丄斾歡揑偵偄偊偽愮棦偺宎掚偑偁傞丄偙偺傊偩偨傝偼丄偁偨偐傕僄儞僎儖僗乮乽墡偺恖椶壔傊偺楯摥偺娭梌乿乯偺乽惉棫偟偮偮偁傝偟恖椶偼丄憡屳偵壗帠偐傪尵偼側偔偰偼側傜偸傑偱偵側偮偨乿偲偄偆偄偄傑傢偟傗丄亀僪僀僣丒僀僨僆儘僊乕亁偺乽懠恖偵偲偮偰傕巹帺恎偵偲偮偰傕懚嵼偡傞偲偙傠偺幚慔揑側尰幚揑側堄幆乿乮懠偺恖乆偵偲偭偰懚嵼偡傞偲偲傕偵丄偦偺偙偲偵傛偭偰偼偠傔偰巹帺恎偵偲偭偰傕傑偨幚嵺偵懚嵼偡傞偲偙傠偺尰幚揑堄幆乯偲偄偆偄偄傑傢偟偵懳墳偟偰偄傞丅
丂偙偺愮棦偺嫍偨傝傪丄尵岅偺乽帺屓昞弌乿偲偟偰憐掕偱偒傞丅帺屓昞弌偼尰幚揑側忦審偵偆側偑偝傟偨尰幚揑側堄幆偺懱尡偑偮傒廳側偭偰丄堄幆偺偆偪偵乽尪憐乿偺壜擻惈偲偟偰偐傫偑偊傜傟傞傛偆偵側偭偨傕偺偱丄偙傟偑恖娫偺尵岅偑乽尰幚乿傪棧扙偟偰備偔悈弨傪偒傔偰偄傞丅偦傟偲偲傕偵丄偁傞帪戙偺尵岅偺悈弨傪偟傔偡広搙偵側偭偰偄傞丅尵岅偼偙偺傛偆偵丄懳徾偵偨偄偡傞巜帵偲丄懳徾偵偨偄偡傞堄幆偺帺摦揑悈弨偺昞弌偲偄偆擇廳惈偲偟偰尵岅偺杮幙傪偮偔偭偰偄傞丅
丂
仢尵岅偼丄摦暔揑側抜奒偱偼尰幚揑側斀幩偱偁傝丄偦偺斀幩偑偟偩偄偵堄幆偺乽偝傢傝乿傪傆偔傓傛偆偵側傝丄偦傟偑敪払偟偰帺屓昞弌偲偟偰巜帵婡擻傪傕偮傛偆偵側偭偨偲偒乮尰幚揑側懳徾偵偨偄偡傞斀幩側偟偵丄帺敪揑偵桳愡壒惡傪敪偡傞偙偲偑偱偒傞傛偆偵側傝丄偦傟偵傛偭偰媡偵懳徾偺乽憸乿傪巜帵偡傞傛偆偵側偭偨偲偒乯丄偼偠傔偰尵岅偲傛偽傟傞忦審傪傕偭偨丅偨偲偊偽庪椔恖偑丄帺屓昞弌偺偱偒傞堄幆傪妉摼偟偰偄傞偲偡傟偽乽奀乮偆乯乿偲偄偆桳愡壒偼帺屓昞弌偲偟偰敪偣傜傟偰丄娽慜偺奀傪乽捈愙揑乿偵偱偼側偔乽徾挜揑乿乮婰崋揑乯偵巜帵偡傞偙偲偲側傞丅偙偺偲偒乽奀乮偆乯乿偲偄偆桳愡壒偼尵岅偲偟偰偺忦審傪姰慡偵偦側偊傞偙偲偵側傞丅
丂偙偆偄偆尵岅偲偟偰偺嵟彫偺忦審傪傕偭偨偲偒丄桳愡壒偼偦傟傪敪偟偨傕偺偵偲偭偰丄偠傇傫傪傆偔傒側偑傜偠傇傫偵偨偄偡傞壒惡偵側傞丅傑偨偦偺偙偲偵傛偭偰懠偵偨偄偡傞壒惡偵側傞丅斀懳偵丄懠偺偨傔偵偁傞偙偲偱偠傇傫偵偨偄偡傞壒惡偵側傝丄偦傟偼偠傇傫帺恎傪偼傜傓偲偄偭偰傕傛偄丅
丂
乮俀乯尵岅恑壔偺摿惈劅椶偲屄丄懳帺偲懳懠
丂
仢偁傞帪戙偺傂偲偮偺幮夛偺尵岅偺悈弨偼丄傆偨偮偺柺偐傜偐傫偑偊傜傟傞丅尵岅偼帺屓昞弌偺柺偐傜丄傢偨偟偨偪偺堄幆偵偁傞偮傛偝傪傕偨傜偡偐傜丄偦傟偧傟偺帪戙偑傕偭偰偄傞堄幆偼尵岅偑敪惗偟偨帪戙偐傜偺媫偘偒側傑偨備傞傗偐側偮傒偐偝側傝偦偺傕偺偵傎偐側傜側偄丅偟偐偟巜帵昞弌偲偟偰偺尵岅偼丄偁偒傜偐偵偦偺帪戙偺幮夛丄惗嶻懱宯丄恖娫偺偝傑偞傑側娭學丄偦偙偐傜偆傒偩偝傟傞乽尪憐乿偵傛偭偰婯掕偝傟傞丅偟偄偰偄偊偽丄尵岅傪昞弌偡傞屄乆偺恖娫偺梒帣偐傜巰偸傑偱偺屄乆偺娐嫬偵傛偭偰傕寛掕揑偵塭嬁偝傟傞丅
丂偙傫側傆偆偵尵岅偵傑偮傢傞塱懕惈偲帪戙惈丄傑偨偼椶偲偟偰偺摨堦惈偲屄惈偲偟偰偺嵎暿惈丄偦傟偧傟偺柉懓岅偲偟偰偺摿惈側偳偑丄尵岅偺懳帺偲懳懠偺傆偨偮偺柺偲偟偰偁傜傢傟傞丅尵岅昞尰偱偁傞暥妛嶌昳偺側偐偵傢偨偟偨偪偑傒傞傕偺偼丄偁傞帪戙偵惗偒偨偁傞嶌幰偺惗懚偲偲傕偵偮偐傑傟偰丄巰偲偲傕偵朣傫偱偟傑偆乽壗偐乿偲丄恖椶偺敪惗偐傜偙偺曽丄偮傒偐偝偹傜傟偰偒偨乽壗偐乿偺椉柺偱丄偙傟偼嶌幰偑桪傟偰偄傞偐杴梖偱偁傞偐偵偐偐傢傜側偄傕偺偩丅
丂
乮俁乯旕尵岅揑抜奒劅壒塁乮帺屓昞弌埲慜偺帺屓昞弌乯偲塁棩乮巜帵昞弌埲慜偺巜帵昞弌乯
丂
仢尨巒恖偺嫨傃偛偊偑摿掕偺棩摦傪傕偪丄堄幆偺帺屓昞弌傪傕偮傛偆偵側偭偰丄尵岅偺忦審偑姰惉偡傞傑偱偵丄偳偺傛偆側抜奒傪傊偨偐偼妋徹偝傟側偄偲偟偰傕丄摿掕偺壒偺慻崌偣偑丄摿掕偺懳徾偵傓偡傃偮偒丄偦偺徾挜偲偟偰偁傜傢傟偨偙偲偼丄偨傟傕斲掕偡傞偙偲偑偱偒側偄丅偙偺夁掱偼屄乆偺尨巒恖偺壒惡偺偪偑偄偑偁傞偵傕偐偐傢傜偢丄偦偺側偐偐傜屄暿揑側壒偺嬁偒傪偒偒傢偗偰屄暿揑側偪偑偄傪傒偲傔傞偲偲傕偵丄拪弌偝傟偨壒惡偺嫟捠惈傪傒偲傔傞傛偆偵側偭偨偙偲傪堄枴偟偰偄傞丅
丂偙偆偄偆桳愡壒惡偺拪弌偝傟偨嫟捠惈偑乽壒塁乿偲偟偰擣傔傜傟偨偙偲偼丄婍姱偲偟偰偺壒惡偑丄堄幆偺帺屓昞弌偲偟偰偺壒惡偵崅傔傜傟偨偙偲偲懳墳偟偰偄傞丅嶰塝偮偲傓偑亀擔杮岅偼偳偆偄偆尵岅偐亁偺側偐偱丄壒塁偼丄昞尰忋偺幮夛揑栺懇偵傓偡傃偮偄偰偄傞壒偺堦斒揑側柺偱偁傝堦懓偱偁傞偲偄偆塢偄偐偨偱偝偟偰偄傞傕偺偼丄偙傟偵懳墳偟偰偄傞丅
丂
仢帪巬惤婰偼亀崙岅妛尨榑亁偺側偐偱丄塁棩乮儕僘儉乯偼尵岅偵偍偗傞嵟傕崻尮揑側乽応柺乿偱偁偭偰丄尵岅偼儕僘儉揑応柺偺奜偵幚尰偡傋偒応強傪尒弌偡偙偲偑弌棃側偄乮応柺偼昞尰偵愭棫偭偰懚嵼偟丄偮偹偵昞尰偦偺傕偺傪惂栺偡傞乯偲彂偄偰偄傞丅偙偺塁棩娤偼偲偰傕嫽枴怺偄偑丄傢偨偟偨偪傪枮懌偝偣側偄丅
丂傢偨偟偨偪偼丄尨巒恖偑嵳幃偺偁偄偩偵丄庤攺巕傪偆偪丄懪妝婍傪柭傜偟丄嫨傃惡偺攺巕傪偆偮応柺傪丄壒惡斀幩偑尵岅壔偡傞搑拞偵偐傫偑偊偰傒偨丅偙偆偄偆壒惡斀墳偑桳愡壔偝傟偨偲偙傠偱丄帺屓昞弌偺曽岦偵拪弌偝傟偨嫟捠惈傪偐傫偑偊傟偽乽壒塁乿偲側傞偩傠偆偑丄偙偺偽偁偄桳愡壒惡偑尰幚揑懳徾傊偺巜帵惈偺曽岦偵拪弌偝傟偨嫟捠惈傪偐傫偑偊傟偽尵岅偺乽塁棩乿偺奣擮傪傒偪傃偗傞傛偆側婥偑偡傞丅偩偐傜尵岅偺乽壒塁乿偼偦偺側偐偵帺屓昞弌埲慜偺帺屓昞弌傪偼傜傫偱偄傞傛偆偵丄尵岅偺乽塁棩乿偼丄巜帵昞弌埲慜偺巜帵昞弌傪偼傜傫偱偄傞丅
丂懳徾偲偠偐偵巜帵娭學傪傕偨側偔側偭偰丄偼偠傔偰桳愡壒惡偼尵岅偲側偭偨丅偦偺偨傔傢偨偟偨偪偑尰嵼偐傫偑偊傞偐偓傝偺塁棩偼丄尵岅偺堄枴偲偐偐傢傝傪傕偨側偄丅偦傟側偺偵帊壧偺傛偆偵丄巜帵婡擻偑偦傟偵傛偭偰偮傛傔傜傟傞偺偼偦偺偨傔側偺偩丅儕僘儉偼尵岅偺堄枴偲偠偐偵偐偐傢傝傪傕偨側偄偺偵丄巜帵偑拪弌偝傟偨嫟捠惈偩偲偐傫偑偊傜傟傞偺偼丄尵岅偑婎掙偺傎偆偵旕尵岅帪戙偺姶妎揑曣斄傪傕偭偰偄傞偐傜側偺偩丅偙傟偼摍帪揑側攺壒偱偁傞擔杮岅偱偼壒悢棩偲偟偰偁傜傢傟偰偄傞丅
丂
嘥亅俀丏尵岅偺懏惈
丂
乮係乯堄枴偲壙抣丄偙偪傜偑傢偲偁偪傜偑傢
丂
仢巜帵昞弌偲帺屓昞弌傪峔憿偲偡傞尵岅偺慡懱傪丄帺屓昞弌偵傛偭偰堄幆偐傜偟傏傝弌偝傟偨傕偺偲偟偰傒傞偲偙傠偵丄尵岅偺乽壙抣乿偼傛偙偨傢偭偰偄傞丅偁偨偐傕丄尵岅傪巜帵昞弌偵傛偭偰堄幆偑奜奅偵娭學傪傕偲傔偨傕偺偲偟偰傒傞偲偒尵岅偺乽堄枴乿偵偮偒偁偨傞傛偆偵丅
丂偙偙偱偄偔傜偐拲堄偡傋偒偼丄僜僔儏乕儖偺傛偆偵丄尵岅偺壙抣偑丄摍壙奣擮偲岎姺奣擮側偟偵偼惉傝棫偨側偄偲偄偆偙偲偱偼側偄丅偡偱偵尵岅偺昞弌偑丄恖娫偺堄幆偺帺屓昞弌偲巜帵昞弌偺峔憿偱偁傞偲傒偰偒偨抜奒偱丄偙偲偝傜偦偺昁梫偼側偄丅偨偩丄恖娫偺堄幆偑乽偙偪傜偑傢乿偵偁傞偺偵丄尵岅偺壙抣偼丄乽偁偪傜偑傢乿偵丄偄偄偐偊傟偽昞尰偝傟偨尵岅偵偠偭偝偄偵偔偭偮偄偰惉傝棫偮偲偄偆偙偲偩偗偩丅
丂
仭媑杮棽柧偺寍弍尵岅尨榑乮昞尰偺棟榑乯
丂
嘦丏昞尰偺棟榑劅憸乮僀儅乕僕儏乯偲歡乮僼傿僊儏乕儖乯
丂
嘦亅侾丏憸偺惗婲丄尵岅妛偲偺實傟
丂
乮俆乯憸偺姭傃偍偙偟
丂
仢婘偺忋偺椢怓偺奃嶮傪娽偱傒側偑傜乽僴僀僓儔乿偲偄偆尵梩傪敪偟偨偲偡傞丅偙偺偲偒奃嶮偺乽憸乿傪傂偒偍偙偡偙偲偼側偄丅偟偐偟娽傪偲偠偰乽僴僀僓儔乿偲偄偭偨偲偡傟偽丄奃嶮偺乽憸乿傪姭傃偍偙偡偙偲偑偱偒傞丅偨偩奃嶮傪娽偱傒偨捈屻偵娽傪偲偠偰乽僴僀僓儔乿偲偄偆尵梩傪敪偟偨偲偒偵偼丄捈慜傑偱傒偰偄偨奃嶮偺帇妎憸偵惂栺偝傟傞丅娽傪偲偠偰撍慠偵乽僴僀僓儔乿偲偄偆尵梩傪敪偟偨偲偒偆偐傫偱偔傞奃嶮偺乽憸乿偺帺桼偝偲偼偪偑偭偰偄傞丅偦傟偼帇妎憸偲尵梩偺偁偄偩偵姭傃偍偙偝傟傞憸偲尵梩偲堄幆偺偁偄偩偵姭傃偍偙偝傟傞憸偲偺偪偑偄偩偲偄偭偰偄偄丅
丂憸偲偼側偵偐偑丄杮幙揑偵傢偐傜側偄偲偟偰傕丄偦傟偑懳徾偲側偭偨奣擮偲傕懳徾偲側偭偨抦妎偲傕偪偑偭偰偄傞偲偄偆棟夝偝偊偁傟偽丄尵岅偺巜帵昞弌偲帺屓昞弌偺岎嶖偟偨朌栚偵偆傒偩偝傟傞偙偲偼丄椆夝偱偒傞偼偢偩丅偁偨偐傕丄堄幆偺巜帵昞弌偲偄偆儗儞僘偲帺屓昞弌偲偄偆儗儞僘偑丄偪傚偆偳傛偔偐偝側偭偨偲偙傠偵憸偑偆傑傟傞傛偆偵丅
丂
仢尵岅偺憸偼丄傕偪傠傫尵岅偺巜帵昞弌偑帺屓昞弌椡偵傛偭偰懳徾偺峔憿傑偱傕偝偡嫮偝傪庤偵偄傟丄偦偺偐傢傝偵帺屓昞弌偵傛偭偰抦妎偺師尦偐傜偼偼傞偐偵丄棧扙偟偰偟傑偭偨忬懺偱丄偼偠傔偰偁傜傢傟傞丅偁傞偄偼傑偭偨偔媡偱偁傞偐傕偟傟側偄丅尵岅偺巜帵昞弌偑懳徾偺悽奅傪偊傜傫偱巜掕偱偒傞埲慜偺庛偝偵偁傝丄帺屓昞弌偼懳徾偺悽奅傪抦妎偡傞傛傝埲慜偺庛偝偵偁傝丄斀幩傪傢偢偐偵棧傟偨忬懺偱丄憸偽偐傝偺尵岅埲慜偑偁偭偨偲偄偆傛偆偵丅尵岅偺憸偑偳偆偟偰壜擻偵側傞偐丄傪嫟摨懱揑側梫場傊傑偱愽嵼揑偵偔偖偭偰備偗偽丄堄幆偵帺屓昞弌傪偆側偑偟偨幮夛揑尪憐偺娭學偲丄巜帵昞弌傪偆側偑偟偨嫟摨偺娭學偲偑柕弬傪偒偨偟偨丄妝墍憆幐偺偝偄偟傚傑偱偐偄偔偖傞偙偲偑偱偒傞丅
丂
乮俇乯暥帤偲憸丄昞弌偲昞尰
丂
仢暥帤偺惉棫偵傛偭偰丄昞弌偼堄幆偺昞弌偲昞尰偲偵暘棧偡傞丅尵岅偼堄幆偺昞弌偱偁傞偑丄尵岅昞尰偑堄幆偵娨尦偱偒側偄梫慺偼丄暥帤偵傛偭偰偼偠傔偰偆傑傟偨偺偩丅暥帤偵偐偐傢傞偙偲偱尵岅偺昞弌偼丄懳徾偵側偭偨帺屓憸偑丄偠傇傫偺撪偽偐傝偱偼側偔奜偵偠傇傫偲懳榖傪偼偠傔傞擇廳偺偙偲偑偱偒傞傛偆偵側傞丅
丂
仢尵岅偵偼丄帺屓昞弌偵傾僋僙儞僩傪偍偄偰偁傜傢傟傞帺屓昞弌岅偲丄巜帵昞弌偵傾僋僙儞僩傪偍偄偰偁傜傢傟傞巜帵昞弌岅偑偁傞傛偆偵丄尵岅杮幙偺昞婰偱偁傞暥帤偵傕帺屓昞弌暥帤偲巜帵昞弌暥帤偑偁傞丅
丂傢偨偟偨偪偼巜帵昞弌岅偵丄堄枴傗丄懳徾偺奣擮偺傎偐偵丄偦傟偵傑偮傢傞憸傪偁偨偊偰偄傞偟丄傑偨偁偨偊偆傞丅昞堄暥帤偱偐偔偙偲偑偱偒傞偺偼丄傕偪傠傫巜帵昞弌岅偵偐偓傜傟偰偄傞丅偦偟偰巜帵昞弌岅偩偗偱側偔丄尵岅偺巜帵昞弌傊偺傾僋僙儞僩偼戝側傝彫側傝憸傪偁偨偊傞偲偄偆揰偵丄尵岅昞婰偺惈奿偵偲偭偰嵟屻偺傕傫偩偄偑偁傝丄傑偨尵岅偺旤偵偲偭偰嵟弶偺傕傫偩偄偑偁傜傢傟傞丅
丂
仢尵岅偺昞尰偑丄懳徾偲偟偰偮偔傜傟偨憸堄幆偲崌抳偡傞偨傔偵偼丄偁傞椞堟偑尷傜傟側偗傟偽側傜側偄丅偦偟偰偁傞椞堟撪偱偼昞弌偝傟偨尵岅偼丄偁偨偐傕偦傟帺懱偑乽幚嵼乿偱偁傞偐偺傛偆偵憸堄幆偺懳徾偱偁傝偆傞偺偩丅偦傟偼丄傕偲傕偲尵岅偵偲偭偰摼庤側椞堟偱偼側偄偨傔丄巜帵昞弌偺嫮庛偲帺屓昞弌偺嫮庛偲偑丄朌栚偱檖忔偝傟傞偲偒偵偩偗偁傝偆傞偲偄偭偰偍偔傋偒偩偲偍傕偆丅偦傟偼尵岅偑偨傫偵側偵偐暔徾傪懳徾偵巜帵偟偨偙偲偵傛偭偰傕丄偄傢偹偽側傜偸昁慠偱巚傢偢偄偭偰偟傑偭偨偙偲偩偗偱傕偆傒偩偣側偄丅偠傇傫偵懳徾揑偵側偭偨偠傇傫偺堄幆偑丄乽娤擮乿偺尰幚偵偨偄偟偰丄側偍懳徾揑偵側偭偰偄傞偲偄偭偨摿幙偺側偐偱丄尵岅偲偟偰昞弌偝傟傞偲偒偵丄偼偠傔偰憸揑側椞堟傪傕偮偲偄偊傞丅
丂
仢尵岅偵偲偭偰偺旤丄偡側傢偪暥妛傕傑偨堄幆偺昞弌偱偁傞偑丄偙偺昞弌偼偦偺撪晹偱丄乽彂偔乿偲偄偆暥帤偺昞尰偑惉傝棫偮偲偲傕偵丄昞弌偲昞尰乮produzieren乯偲偵暘楐偡傞丅
丂偙偺偙偲偼丄恖娫偺堄幆傪奜偵偁傜傢偟偨傕偺偲偟偰偺尵岅偺昞弌偑丄偠傇傫偺堄幆偵斀嶌梡傪偍傛傏偡傛偆偵傕偳偭偰偔傞夁掱偲丄奜偵偁傜傢偝傟偨堄幆偑丄懳徾偲偟偰暥帤偵屌掕偝傟偰丄偦傟偑乽幚嵼乿偱偁傞偐偺傛偆偵偠傇傫偺堄幆偺奜偵乽嶌昳乿偲偟偰惗惉偝傟丄惗惉偝傟偨傕偺偑偠傇傫偺堄幆偵斀嶌梡傪偍傛傏偡傛偆偵傕偳偭偰偔傞夁掱偺擇廳惈偑丄柍堄幆偺偆偪偵暥妛揑昞尰乮寍弍偲偟偰偺尵岅昞弌乯偲偟偰慜採偝傟偰偄傞偲偄偆堄枴偵側傞丅
丂尰嵼傑偱棳晍偝傟偰偄傞暥妛棟榑偑丄偄偪傛偆偵乽暥妛乿偲偐乽寍弍乿偲偐埲忋偵丄偦偺峔憿偵擖傠偆偲偼偣偢丄寍弍偲幚惗妶偲偐丄惌帯偲暥妛偲偐丄寍弍偲慳奜偲偐偄偄側傜傢偣偽丄偡傫偩偮傕傝偵側傞偺偼丄昞弌偲偄偆奣擮偑屌桳偺堄幆偵娨尦偝傟傞柺偲丄惗惉乮produzieren乯傪宱偰昞尰偦偺傕偺偵偟偐娨尦偝傟側偄柺偲傪峫嶡偟偊側偐偭偨偑偨傔偩丅
丂
嘦亅俀丏歡偺儊僇僯僘儉
丂
乮俈乯尵岅昞尰偺嫟捠婎斦丄梿慁忬偵偼偣偺傏傞昞尰偺抜奒
丂
仢尵岅昞尰偺偆偪偑傢偵丄偄偔偮偐偺嫟捠偺婎斦傪拪弌偡傞偙偲偑偱偒傞丅偦傟偼丄楌戙偺屄乆偺昞尰幰偑帺桼偵昞尰偟偨傕偺偑嬼慠偵偮傒偐偝偹傜傟偰丄慡懱偲偟偰偼偁偨偐傕昁慠側偁傞偄偼晄壜旔側傕偺偲偟偰偮偔傝偘偨嫟捠惈偩偲偄偊傞丅偙偺嫟捠婎斦偼丄昞尰偲偟偰偺塁棩丒愶戰丒揮姺丒歡偵暘椶偡傟偽尰嵼傑偱偺尵岅偺昞尰偺偡傋偰偺抜奒傪偮偔偡偙偲偑偱偒傞丅
丂傢偨偟偨偪偼偄傑丄寍弍偲偟偰偺尵岅昞尰偺敿曕偔傜偄庤慜偺偲偙傠偵偄傞丅敿曕庤慜偲偄偆偺偼丄尵岅昞尰傪暥妛寍弍偲傒側偡偵偼傑偩乽峔惉乿乮帊丄暔岅丄寑乯偲偄偆偙偲傪丄庢埖偭偰偄側偄偐傜偩丅峔惉傪埖傢側偗傟偽斀暅丄崅梘丄掅壓丄昞尰偺偼偠傔偲偍傢傝偑堄枴偡傞傕偺傪偟傞偙偲偑偱偒側偄丅
丂
仢壒悢棩偼丄擔杮岅偺偆傒偩偟偨偄偪偽傫嫮椡側峔惉偺榞偖傒偱偁傝丄擔杮岅偺巜帵惈偺崻尮偱偁傞丅
丂偍偦傜偔丄抁壧揑側傕偺偺扨弮側拞枴偑丄偳偆偟偰壒悢棩偺側偐偱傂偲偮偺帺棫偟偨旤傪偁偨偊傞偐偲偄偆栤偄偵偼丄偦傟偑擔杮偺暥妛乮帊乯敪惗偄傜偄偺帺屓昞尰偺偄偨偩偒偵楢懕偟偨偮傒偐偝偹傪傕偮偐傜偩偲偄偆偐傫偑偊傪傕偭偰偙側偗傟偽偲偗側偄丅
丂
仢傢偨偟偨偪偼丄歡偲歡偺側偐偱偺塁棩偺偼偨傜偒偲丄尵岅偺塁棩偺偼偨傜偒傪側偑傔傞偙偲偱丄偮偓偺傛偆側偙偲傪傒偰偒偨丅傂偲偮偼丄偁傞嶌昳偺側偐偱応柺偺揮姺偼偦偺傑傑夁掱偲偟偰拪弌偣傜傟偨偲偒歡偺奣擮偵傑偱楢懕偟偰偮側偑偭偰偍傝丄傑偨丄歡偼偦偺歡揑側杮幙偵傑偱拪弌偣傜傟側偄埲慜偱偼丄偨傫側傞応柺偺揮姺偵傑偱偮側偑偭偰偄傞偲偄偆偙偲偩丅歡偺拪弌偑偡偱偵姷梡偝傟偰傆偮偆偵側偭偨傕偺偑丄塀歡丒鎱歡丒堷梡歡丒斀岅朄乧乧側偳偲偄偭偨廋帿揑側嬫暿偵側傞丅偦偟偰丄歡偺奣擮偑弅戅偟偨忬懺傪偐傫偑偊傟偽丄偨傫側傞応柺偺揮姺偲偄偆偲偙傠偵偨偭偡傞丅
丂偦傟側傜偽丄応柺偺揮姺偑弅戅偟偨偲偙傠丄偁傞偄偼傛傝崿撟偲偟偨枹暘壔側偲偙傠傪憐掕偡傟偽丄側偵偑偺偙傞偺偩傠偆偐丅偨偲偊偽丄偨傫偵擟堄偵偲偭偨僼傿儖儉傪偮側偓偁傢偣偨偵偡偓側偄傛偆側婰榐塮夋傕丄応柺傪堄幆揑偵偟傠柍堄幆揑偵偟傠愶戰偟偨偲偙傠偵偡偱偵弶尨揑側旤偺傕傫偩偄偑惉傝棫偭偰偄傞丅側偤丄偦偺応柺傪乽偊傜傫偩乿偐偲偄偆偲偙傠偵偼丄偡偱偵愶戰偺旤偑偁傜傢傟偰偄傞丅尵岅偺昞尰傕丄帺屓昞弌偺堄幆偲偟偰傋偮傕傫偩偄偱偼側偄丅尵岅偺応柺偺揮姺偺弅戅偟偨偲偙傠偵偼丄応柺偦偺傕偺偺愶戰偲偄偆偙偲偑偺偙傞偺偩丅
丂
仢傢偨偟偨偪偼尰嵼丄乽塁棩乿乮尵岅偵偍偗傞嵟傕崻尮揑側乽応柺乿乯傪偄偪偽傫崻偺偲偙傠偵偍偄偰丄乽応柺偺愶戰乿傪偮偓偵傗偭偰偔傞昞尰偺抜奒偲偟丄偝傜偵丄乽応柺偺揮姺乿傪傊偰丄偄偪偽傫崅搙側乽歡乿偺傕傫偩偄偵傑偱梿慁忬偵偼偣偺傏傝丄傑偨丄偼偣偔偩傞昞尰偺抜奒傪傕偭偰偄傞偲偄偭偰偄偄丅偦偟偰丄暥妛偺昞尰偲偟偰丄尵岅偑偮傒偐偝偹偰偒偨偙傟傜偺夁掱偼丄尰嵼偺悈弨偺昞尰偵偡傋偰愽嵼揑偵偼晻偠偙傔傜傟偰偄傞丅偦偟偰偙傟偑丄巜帵昞弌偲偟偰偺尵岅偑乽堄枴乿偲偟偰傂傠偑偭偰岎嶖偡傞偲偙傠偵丄帊揑嬻娫丒嶶暥揑嬻娫偺尰嵼偺悈弨偑偊偑偐傟傞丅
丂傑偨丄彞偆傋偒懳徾傪乽偊傜傃偲傞乿偙偲偑偱偒側偄傑傑偵昞尰偝傟偨婰婭壧梬偺傛偆側屆戙恖偺帊偺悽奅偐傜丄偡偱偵崅搙側歡傪偮偐偭偰尰幚偵愶戰偟偰偄傞乽幮夛乿偲偺娭學傪挻偊傛偆偲偡傞梸媮傪偁傜傢偟偰偄傞尰嵼偺暥妛偺悽奅偵偄偨傞傑偱丄尵岅偑偮傒偐偝偹偰偒偨側偑偄夁掱偼丄尰嵼偺尵岅嬻娫偺悈弨傪峔惉偟偰偄傞丅
丂
乮俉乯歡偺擇廳惈偲埵憡
丂
仢偳傫側偵尵梩傪偮傒廳偹偰傕丄尰偵娽偺傑偊偵偦偺岝宨傪帇側偑傜丄偦傟傪偦偺傑傑尵岅偱嵞尰偱偒側偄偙偲偼愭尡揑偵偒傑偭偰偄傞丅尵岅偼帺屓昞弌傪庤偵擖傟偨偲偒偐傜抦妎偺師尦傪棧扙偟偰偟傑偭偨偐傜偩丅傕偟丄偁傞傂偲偮偺暥復偑栰尨偄偪傔傫偵偝偄偨敀偄僋儘乕僶乕偺憸傪傎偆傆偮偲偝偣傞偙偲偑偱偒偨偲偡傟偽丄偦偺暥復偼帇妎揑側報徾偺偮傒廳偹偵傛傜偢丄尵岅憸傪傛傃偍偙偡椡傪偔傒偁傢偣偨憐憸揑側昞弌偺椡偵傛偭偰偄傞丅
丂偙偆偄偆偲偙傠偵尵岅偺堄枴偲憸偲偺怺暎偑傛偙偨傢偭偰偄傞丅傕偟丄怺暎偺堦抂偵堄枴偩偗傪傂傜偄偰偄傞尵岅傪偐傫偑偊丄懠偺堦抂偵憸偩偗傪傂傜偄偰偄傞尵岅傪偐傫偑偊傟偽丄傢偨偟偨偪偑壙抣偲偟偰傒偰偄傞尵岅偺昞尰偼丄偡傋偰偙偺椉抂傪偮側偖媴柺偺偆偊偵丄偙偺擇抂偺怓偵擇廳偵愼傔偁偘傜傟偰懚嵼偟偰偄傞丅尵岅偼丄尰幚悽奅偲傢偨偟偨偪偲偺偁偄偩偱屘嫿傪傕偨側偄曻楺幰偵偵偰偄傞丅
丂尵岅偼屘嫿傪傕偨側偄曻楺幰偱偁傞偨傔丄傂偲偮偺尵岅偲傋偮偺尵岅偲傪傓偡傃偮偗傞桞堦偮偺杮懱劅劅偮傑傝恖娫偑丄偦偺偁偄偩偵懚嵼偟偝偊偡傟偽丄偦偺幮夛偺側偐偱幮夛偲偨偨偐偄丄柕弬偟偰偄傞崻嫆偐傜丄偳傫側尵岅偲尵岅偺偁偄偩偱傕帺桼偵丄偟偐偟偦偺恖娫偺尰幚幮夛偱偺懚嵼偺巇曽偵偒傔傜傟偰楢崌偝偣傞偙偲偑偱偒傞丅歡偼偦傫側尵岅偺幙偑偁傞偐傜偼偠傔偰壜擻偲側傞偺偩丅
丂
仢塀歡丄鎱歡丄堷梡歡乧乧偲偄偭偨傛偆偵歡傪暻夋揑偵暘椶偡傞傛傝傕丄偨偩乽憸揑側歡乿偲乽堄枴揑側歡乿偺椉抂偑偁傝丅壙抣偲偟偰偺尵岅偺歡偼偙偺椉抂傪傆傑偊偨媴柺偺偆偊偵戝側傝彫側傝偦偺偄偢傟偐偵傾僋僙儞僩傪偍偄偰擇廳惈傪傕偭偰偁傜傢傟偰偔傞偲偄偊偽廩暘偩偲偍傕偆丅偙傟偑歡偺杮幙偱丄偙偺杮幙傪傆傑偊偨偆偊偼丄廋帿妛揑側柪楬偵偝傑傛偆傂偮傛偆偼傑偭偨偔側偄丅
丂歡偼尵岅傪偮偐偭偰偍偙側偆堄幆偺扵嶕偱偁傝丄偨傑偨傑墦曽偵偁傞傛偆偵傒偊傞尵岅偑埮偺側偐偐傜偆偐傫偱偒偨傝丄偨傑偨傑嬤偔偵偁傞偲偍傕傢傟偨尵岅偑墦曽偵朘栤偟偨傝偟側偑傜丄尵岅偲尵岅傪堄幆偺側偐偱楢崌偝偣傞崻嫆偱偁傞尰幚偺悽奅偲丄恖娫偺尪憐偑惗偒偰偄傞巇曽偑丄偄偪偽傫傄偭偨傝偲揔崌偟偨偲偒丄扵嶕偼栚揑偵柦拞偟丄歡偲偟偰惉傝棫偮傛偆偵側傞丅
丂
仢偍偦傜偔丄歡偼尵岅偺昞尰偵偲偭偰尰嵼偺偲偙傠偄偪偽傫崅搙側愶戰偱丄尵岅偑偦偺帺屓昞弌偺偼傫偄傪偳偙傑偱傕偍偟偁偘傛偆偲偡傞偲偙傠偵偁傜傢傟傞丅乽壙抣乿偲偟偰偺尵岅偺備偔偰傪尒偒傢傔偨偄梸媮偑丄梊尒偵傑偱偨偐傔傜傟傞傕偺偲偡傟偽丄傢偨偟偨偪偼帺屓昞弌偲偟偰偺尵岅偑偙偺曽岦偵偳偙傑偱傕偡偡傓偵偪偑偄側偄偲偄偊傞偩偗偩丅偦偟偰丄偨偊偢乽幮夛乿偲偨偨偐偄側偑傜巰傫偩傝丄曄壔偟偨傝丄偟側偗傟偽側傜側偄巜帵昞弌偲岎嶖偡傞偲偙傠偵壙抣偑偁傜傢傟丄偙偙偵歡偲壙抣偲偺傆偟偓側側側傔偵偍偐傟偨埵憡偲娭學偑偁傜傢傟偰偄傞丅
丂
仭擇偮偺婎掙偐傜嶰偮偺婎掙傊
丂
丂偨偔偝傫偺戝愗側榑揰傪廍偄偦偙偹偰偄傞偲巚偄傑偡丅偙傟偐傜愭丄亀尵岅偵偲偭偰旤偲偼側偵偐亁傪撉傒偐偊偡偨傃偵丄偙傟偲偼暿偺偐偨偪偺弅栺偑傕偨傜偝傟傞偙偲偵側傞偱偟傚偆丅枮恎憂醱偱偁傞偙偲傪怺偔帺妎偟偮偮丄愭偵偡偡傒傑偡丅
丂偝偰丄埲忋偵敳偒彂偒偟偨媍榑偺偄偨傞偲偙傠偱丄僞僥幉偲儓僐幉丄傕偟偔偼嫊幉偲幚幉偺岎嵆偵傛傞擇尦榑傪尒傞偙偲偑偱偒傑偟偨丅偄傑丄栚偵偲傑偭偨偐偓傝柍憿嶌偵拪弌偟偰傒傞偲丄師偺傛偆偵側傝傑偡丅
丂
乑尵岅敪惗婡峔偵偐偐傢傞乽懳帺揑堄幆乛懳懠揑堄幆乿丅
乑尵岅敪惗埲慜偺旕尵岅揑抜奒偵偍偗傞乽壒塁乮帺屓昞弌埲慜偺帺屓昞弌乯乛塁棩乮巜帵昞弌埲慜偺巜帵昞弌乯乿丅
乑尵岅偺擇偮偺杮幙乽帺屓昞弌乛巜帵昞弌乿丅乽尪憐乛尰幚乿丅
乑尵岅偺恑壔偵傑偮傢傞乽塱懕惈乛帪戙惈乿丅乽椶乮摨堦惈乯乛屄乮嵎堎惈乯乿丅乽恖椶偺敪惗偐傜偙偺曽偮傒偐偝偹傜傟偰偒偨乽壗偐乿乛偁傞帪戙偵惗偒偨偁傞嶌幰偺惗懚偲偲傕偵偮偐傑傟偰巰偲偲傕偵朣傫偱偟傑偆乽壗偐乿乿丅
乑尵岅偺擇偮偺柺乽懳帺乛懳懠乿丅
乑尵岅偺擇偮偺懏惈乽壙抣乛堄枴乿丅
乑堄幆偺帺屓昞弌偲巜帵昞弌偺乽傆偟偓側朌栚乿偐傜偆傑傟傞戞嶰偺懏惈乽憸乿傪捠偠偨乽昞尰偺棟榑乛尵岅偺棟榑乿偺暘婒丅
乑憸偺擇廳惈乽尵梩偲堄幆偺偁偄偩偵姭傃偍偙偝傟傞憸乛帇妎憸偲尵梩偺偁偄偩偵姭傃偍偙偝傟傞憸乿丅
乑歡偺擇廳惈乽堄枴揑側歡乛憸揑側歡乿丅
乑昞尰偺棟榑偺崪奿傪側偡擇廳惈乽歡乮僼傿僊儏乕儖乯乛憸乮僀儅乕僕儏乯乿丅
丂
丂偙傟傜偺擇尦榑偺償傽儕僄乕僔儑儞偺婎杮偼丄偁傜偨傔偰尵偆傑偱傕側偔丄乽帺屓昞弌乛巜帵昞弌乿偺懳奣擮傪婎掙偲偡傞尵岅偺擇廳惈偺棟榑偵偁傝傑偡丅偲偙傠偑丄榑弎偺懳徾偑尵岅偺棟榑偐傜昞尰偺棟榑偵堏峴偡傞偲丄偦偙偵丄乮柧帵揑偐栙帵揑偐丄栙帵揑偱偁傞偲偟偰堄幆揑偐柍堄幆揑偐丄偼偲傕偐偔乯丄戞嶰偺婎掙乮幉乯偑摫擖偝傟丄媍榑偺婎挷偑丄扨弮柧夣側奜娤傪傕偭偨擇尦榑偐傜丄暋嶨夦婏側條憡傪掓偡傞嶰尦榑側偄偟懡尦榑傊偲揮偠偰偄偔偺偱偡丅乮偙偺偁偨傝偺彇弎偼丄拞懞楃帯巵偺榑峫丄偨偲偊偽乽媑杮棽柧偺嶰尦榑乿側偳偵帵嵈傪摼偰偄傞偑丄撪梕揑偵偼捈愙偺娭學偼側偄丅乯
丂尵岅偺懏惈偵娭偡傞媍榑偺夁掱偱丄巜帵昞弌偺宯晥偵懏偡傞乽堄枴乿偲帺屓昞弌偺宯晥偵懏偡傞乽壙抣乿偵壛偊偰丄戞嶰偺丄尵岅偺巜帵昞弌偲帺屓昞弌偺岎嶖偟偨朌栚偵偆傒偩偝傟傞乽憸乿偺奣擮偑摫擖偝傟丄埲屻丄尵岅偲昞尰偺棟榑偵偍偗傞憸偺埵抲偯偗傪傔偖偭偰丄嶖憥偟偨媍榑乮偨偲偊偽丄壙抣偲偟偰偺尵岅偺昞尰偼丄偡傋偰堄枴偲憸偲偺怺暎偺椉抂傪偮側偖媴柺偺偆偊偵懚嵼偟偰偄傞丄偲偐丄壙抣偲偟偰偺尵岅偺歡偼乽憸揑側歡乿偲乽堄枴揑側歡乿偺椉抂傪傆傑偊偨媴柺偺偆偊偵偁傜傢傟偰偔傞丄偲偐丄歡偲壙抣偲偺傆偟偓側側側傔偵偍偐傟偨埵憡偲娭學塢乆丄偲偄偭偨媍榑乯偑揥奐偝傟傞偙偲偵側傞偺偼丄偦偺尒傗偡偄椺偱偟傚偆丅
丂戞嶰偺婎掙丄戞嶰偺嵗昗幉丅偦傟偼丄僞僥幉乮嫊幉乯偲儓僐幉乮幚幉乯偱寛掕偝傟傞暯柺乮嫊幉傪帪娫丄幚幉傪嬻娫偲婯掕偡傞側傜偽丄巐師尦帪嬻乯傪忋曽乮傕偟偔偼懠奅乯偐傜挱傔偍傠偡悅捈偺帇慄傪傕偨傜偟傑偡丅媑杮棽柧偼亀帊恖丒昡榑壠丒嶌壠偺偨傔偺尵岅榑亁偵廂傔傜傟偨乽尵岅榑偐傜傒偨嶌昳偺悽奅乿偱丄塁棩丒愶戰丒揮姺丒歡偵傕偆傂偲偮壛偊傞偲偟偨傜丄偦傟偼乽僷儔丒僀儊乕僕丄偮傑傝忋曽偐傜偺帇揰偺僀儊乕僕乿偩偲岅偭偰偄傑偡丅僷儔丒僀儊乕僕偵偮偄偰偼丄屻偵亀僴僀丒僀儊乕僕榑嘦亁偱徻嵶偵榑偠傜傟傞偙偲偵側傞偺偱偡偑丄幚偼丄亀尵岅偵偲偭偰旤偲偼側偵偐亁偵傕丄偦偺挍偟偺傛偆側媍榑偑偱偰偒傑偡丅
丂偙偙偵梡偄傜傟偨乽婲廳婡乿傗乽捿傝偁偘乿傗乽婲摦椡乿偲偄偆岅偑丄偦偟偰丄亀尵岅偵偲偭偰旤偲偼側偵偐亁偺楢嵹奐巒偲摨帪婜偵彂偐傟偨乽帊偲偼側偵偐乿偱丄乽掕忢揑側堄幆偐傜偼偠傑偭偰椼婲偝傟偨忬懺偐傜悐戅傪傊偰掕忢揑側忬懺傊偺暅婣傑偱偺昞尰傪帊偲傛傇偙偲偑偱偒傞乿乮亀帊偲偼側偵偐劅劅悽奅傪搥傜偣傞尵梩亁乯傗丄乽帊偵偍偄偰尵岅偼丄堄幆偺帺屓昞弌偲偟偰傕丄巜帵惈偵偍偄偰傕椼婲偝傟偰偄偰丄憐憸揑側傕偺偦傟帺懱偱偁傞乿乮摨乯偲偄偭偨暥復偺偆偪偵尒傜傟傞乽椼婲乿偲偄偆岅渂偑丄塁棩丒愶戰丒揮姺丒歡傊偲乽偼偣偺傏傞乿昞尰偺抜奒偲丄偦偟偰乽歡乿偺偮偓偵偔傞崅搙側昞尰偺曽岦傪巜偟帵偟偰偄偨丄偲尵偭偰偄偄偱偟傚偆丅乮乽帊偲偼側偵偐乿偵偼丄乽帊偺杮幙偼傑偭偨偔偪偑偭偨晹暘偵柆棈傪偮偗傞偙偲偑偱偒傞応強偐傜偟偐帇偊側偄乿偲偄偆昞尰傕偁偭偰丄偙傟偼傑偝偵乽歡偺儊僇僯僘儉乿偑壱摥偡傞応強偺偙偲傪巜偟帵偟偰偄傞丅乯
丂
仭嶰杮偺嵗昗幉傪傔偖傞帋峴揑峫嶡
丂
丂偙偙偱丄媍榑傪愭偵恑傔傞偨傔偺曗彆慄傪堷偒傑偡丅
丂悰栰妎柧巵偼亀媑杮棽柧劅劅帊恖偺塨抭亁偱丄乽嶰杮偺嵗昗幉偑愝抲偝傟偨偙偺嬻娫偼丄傕偪傠傫暔棟嬻娫偦偺傕偺偱偼側偔丄暔棟嬻娫偵斾偣傜傟偨媑杮偺撪晹悽奅偱偁傞丅乿偲彂偒丄偦傟偧傟偺嵗昗幉偵偮偄偰丄師偺傛偆偵掕媊偟偰偄傑偡丅
丂
仢帺慠帪娫乮儅僋儘側師尦偺暔棟尰徾傪婰弎偡傞場壥揑帪娫乯偲屌桳帪乮儈僋儘側暔徾偵屌桳偺旕場壥揑帪娫丄撪晹堄幆偵偍偗傞帪娫惈乯偵擇廳壔偝傟偨帪娫偑偦傟偵増偭偰棳傟傞倃幉丅
仢崱偲偄偆揰偵宍傪梌偊傞尰嵼偺尰幚憤懱偺峀偑傝傪掕媊偡傞倄幉丅
仢杮棃偼堦枃偺乽傢偨偟偨偪乿偺帪嬻丒晽宨偱偁傞偼偢偺倃倄暯柺乮懳尪憐偺椞堟乯傪丄乽傢偨偟乿偺偦傟偲乽傂偲傃偲乿偺偦傟偲偵榗傑偣堷偒楐偔挘椡偺儀僋僩儖傪應傞倅幉丅偦偺忋徃偺曽岦偼撪晹悽奅偵偍偗傞嫟摨惈偺椞堟乮嫟摨尪憐乯傪丄壓崀偺曽岦偼屄揑側椞堟乮帺屓尪憐乯傪巜偟帵偡丅
丂
丂悰栰巵偼偮偯偗偰丄乽屌桳帪偲偺懳榖乿偱媑杮偑傔偞偟偨偺偼丄乽忋徃偝偣傛偆偲偡傞椡偵媡傜偭偰丄懄偪壓崀偡傞椡乵屄揑側傕偺偵揙偡傞偙偲乶偵傛偭偰丄暘楐偡傞屄偲椶丄擇偮偺帪娫丄擇偮偺晽宨傪摑堦偡傞偙偲乿偱偁傝丄乽弮悎偵屄揑側傕偺偺撪偵丄乽傢偨偟乿偲乽傂偲傃偲乿偲偑堦抳偡傞抧揰傪扵偟媮傔傞乿偙偲偱偁偭偨偲偟丄偦偺抧揰乮媑杮偑乽嬻摯偺傛偆側屄強乿乮乽屌桳帪偲偺懳榖乿丆亀媑杮棽柧帊慡廤俆丂掕杮帊廤亁乯偲柤巜偟偨乽庘泴偺掙乿乯偐傜怴偨偵棫偪偁傜傢傟傞乽傢偨偟乿丄偡側傢偪乽儔儞儃僆偲偄傆柤偝傊嬼慠偲巚偼傟傞傎偳偺丄埥傞晛曊揑側弮寜側懚嵼乿乮彫椦廏梇乽儔儞儃僆嘨乿乯偲偟偰偺柍彏偺乽傢偨偟乿偵丄傕偟偁偊偰堦偮偺柤傪梌偊傞側傜乽帊恖乿偙偦偑傕偭偲傕傆偝傢偟偄偩傠偆丄偲彂偄偰偄傞偺偱偡丅
丂悰栰巵偺峫嶡偼丄捠傝偡偑傝偺堦曀傪嫋偝側偄擹偝偲怺傒傪扻偊偰偄傞偺偱偡偑丄偙偙偱偼丄偦偺昞柺揑側堄彔偺傛偆側傕偺傪庁梡偟丄傕偆偡偙偟娙曋側偐偨偪偱墳梡偟偰傒偨偄偲巚偄傑偡丅
丂島墘乽尵梩偺崻尮偵偮偄偰乿乮亀帊偲偼側偵偐劅劅悽奅傪搥傜偣傞尵梩亁乯偱丄媑杮棽柧偼丄師偺傛偆側媍榑傪揥奐偟偰偄傑偡丅
丂偄傢偔丄偡傋偰偺乽懚嵼偡傞傕偺乿偼丄偦傟偵屌桳偺帪娫偲嬻娫偺條幃傪傕偭偰偄傞丅尵岅偺昞尰傕傑偨丄尵岅昞尰偵屌桳側帪娫惈乮僼傿僋僔儑儞偺捛懱尡乯偲嬻娫惈乮堄枴偺峀偑傝丄庴偗擖傟偺巇曽偺峀偑傝乯傪傕偭偰偄傞丅偦傟偼庡娤揑側撪揑堄幆偺帪娫丒嬻娫偲傕丄媞娤揑側帺慠偺傕偭偰偄傞帪娫丒嬻娫偲傕偪偑偆丅
丂傑偨偄傢偔丄尵岅昞尰偺帪娫惈丄嬻娫惈偺崻尮偼丄恎懱偺庴梕惈偲椆夝偺巇曽偵偁傞丅偁傜備傞姶妎婍姱偵傛傞庴偗擖傟乮挳妎揑丄帇妎揑丄歬妎揑丄枴妎揑庴偗擖傟乯偺搙崌丒巇曽偑嬻娫惈偺崻尮偵偁傝丄偙偺庴偗擖傟偨傕偺傪乽奃嶮偱偁傞乿偲椆夝偟偰抦妎嶌梡傪姰椆偝偣傞丄偁傞偄偼乽晄媑側傆偔傠偆偑偲傑偭偰柭偄偨壠偺恖娫偼嶦偟偰傕傛偄乿偲椆夝偡傞丄偦偺椆夝偺巇曽偑帪娫惈偺崻尮偵偁傞丅
丂埲忋偺媍榑偺慜抜傪偮偐偭偰丄偐偺嶰杮偺嵗昗幉傪嵞掕媊偡傞偲丄倃幉亖媞娤揑帺慠偺帪娫惈偲嬻娫惈丄倄幉亖撪揑堄幆偺帪娫惈偲嬻娫惈丄倅幉亖尵岅昞尰偺帪娫惈偲嬻娫惈丄偲側傞偱偟傚偆偐丅悰栰巵偺掕媊偲斾妑偡傞偲丄媍榑偺惁傒偵寚偗傑偡偑丄彮側偔偲傕巹偵偼丄傛傝傢偐傝傗偡偔尒捠偟偺偒偔傕偺偺傛偆偵巚偊傑偡丅
丂偲偙傠偱丄偙偙偵丄屻抜偺媍榑傪慻傒崌傢偣傞偲丄傕偭偲娙曋側掕媊傪摼傞偙偲偑偱偒傑偡丅倅幉傪丄尵岅昞尰偵屌桳側帪娫惈偲嬻娫惈傪偁傜傢偡傕偺偲偡傞偺偼摨偠偱偡偑丄倃幉傪丄嬻娫惈偺崻尮偵偁傞恎懱偺庴梕惈丄偮傑傝姶妎揑抦妎揑嶌梡偵偐偐傢傞幉丄偦偟偰倄幉傪丄帪娫惈偺崻尮偵偁傞椆夝偺巇曽偲偟偰偺忣摦丄堄幆丄堄枴丄奣擮丄摍乆偺椞堟偵偐偐傢傞幉偲掕媊偟偰偼偳偆偐偲偄偆偙偲偱偡丅嶰栘惉晇偺敪惗妛傪墖梡偟偰丄倃幉偼乽姶妎偺摦偒乿丄倄幉偼乽撪憻偺摦偒乿偵乮偟偨偑偭偰丄倃幉偼乽巜帵昞弌乿惈丄倄幉偼乽帺屓昞弌乿惈偵乯偦傟偧傟偐偐傢傞傕偺偲抐掕偟偰傕偄偄偱偟傚偆丅
丂亀媑杮棽柧乽屲偮偺懳榖乿亁偺彉暥偱丄媑杮棽柧偼師偺傛偆偵彂偄偰偄傑偡丅
丂偙偙偵偱偰偔傞乽帴応乿傗乽応柺乿傪倄幉偵偁偰偼傔丄乽挳妎壒乿傗乽帇妎憸乿傪倃幉忋偵埵抲偯偗丄偦偟偰丄偙傟傜傪乽奣擮偺壒乿偵嬅弅偟丄傑偨乽奣擮偺宍徾乿偵傑偱椫妔偯偗傞椡偺曽岦傪倅幉偵側偧傜偊傞側傜偽丄偙偙偵丄僼儗儈儞僌偺嵍庤偺朄懃偵椶帡偟偨娭學乮倄幉亖恖嵎偟巜亖帴奅偺曽岦丄倃幉亖拞巜亖揹棳偺曽岦丄倅幉亖恊巜亖摫懱偵偐偐傞椡偺曽岦乯偑惉傝棫偪傑偡乵仏乶丅乮媑杮棽柧偺媍榑偲僼儗儈儞僌偺朄懃丄偦偟偰僼儗儈儞僌偺朄懃偲嶰偮偺婎幉乮倃倄倅幉乯偲偺娭學偵偮偄偰偼丄塅揷椇堦挊亀媑杮棽柧 乬怱乭偐傜撉傒夝偔巚憐亁偵帵嵈傪摼偰偄傞偑丄撪梕揑偵偼捈愙偺娭學偼側偄丅乯
丂偙偙偱偄偆乽椡乿偼丄掕忢忬懺乮倃倄暯柺乯偐傜偺乽惗婲丄僄傾傾僀僌僯僗乿偵傛偭偰丄尪憐丄廆嫵惈丄摍乆偺椼婲忬懺乮捿傝偁偘傜傟偨怴偟偄倃倄暯柺丄偡側傢偪歡偺儊僇僯僘儉偑偼偨傜偔帊揑帪嬻偱偁偭偰丄偦傟偑悐戅偡傞偲丄庬乆偺斾歡宍徾偑暻夋揑偵暘椶惍彉偝傟傞怴偟偄掕忢忬懺乮廋帿嬻娫乯偵偄偨傞乯傪傕偨傜偡尵岅偺偼偨傜偒傪巜偟偰偄傞丄偲峫偊傞偙偲偑偱偒傑偡丅偙偺偲偒丄倃幉偑捿傝偁偘傜傟偰椼婲偡傞偐丄倄幉偑捿傝偁偘傜傟偰椼婲偡傞偐丄偦傟偲傕倃倄暯柺偦偺傕偺偑乮偄傢偽丄乽媴柺乿忬偵乯偣傝偁偑偭偰椼婲偡傞偐丄尰幚偺椡偺條懺偵傛偭偰丄偄偔偮偐偺償傽儕僄乕僔儑儞偑憐掕偝傟傞偱偟傚偆丅
丂帋傒偵丄媑杮棽柧偺寍弍尵岅尨榑偺偆偪丄尵岅偺棟榑偵偦偔偟偰丄偦偺奣娤傪僗働僢僠偟偰偍偒傑偡丅尵岅偺懏惈乮堄枴偲壙抣偲憸乯偺媍榑偑偆傑偔廍偊偰偄傑偣傫偑丄偄傗丄偦傕偦傕亀尵岅偵偲偭偰旤偲偼側偵偐亁傪捠撉偟偰偄偨嵺偺桇摦偑傑偭偨偔媎偊偰偄傑偣傫偑丄偙傟偑尰帪揰偱偺悈弨偩偲傒偒傢傔傞偟偐偁傝傑偣傫丅憸偲歡傪庡幉偲偡傞昞尰偺棟榑偵偮偄偰偼丄偍偦傜偔偙傟偲偼堘偆偐偨偪偵側傞偱偟傚偆偑丄偱偒傟偽師復埲壓偱偲傝偔傒偨偄偲巚偭偰偄傑偡丅
丂
嘆旕尵岅帪戙
倃(侽)幉亖尰幚悽奅傪捈偐偵巜帵偡傞斀幩揑側壒惡乮摦暔揑丒抦妎揑側師尦丄姶妎偺塣摦乯
倄(侽)幉亖堄幆偺乽偝傢傝乿傪傆偔傓壒惡乮撪憼偺塣摦乯
丂
嘇尵岅偺婲尮偲敪惗
倅(侽)幉亖桳愡壒惡偺嫟捠惈偺乮巜帵惈偲帺屓昞弌偺曽岦傊偺乯拪弌
倃(侾)幉亖巜帵昞弌埲慜偺巜帵昞弌傪偼傜傓塁棩乮尵岅偵偍偗傞嵟傕崻尮揑側乽応柺乿乯
倄(侾)幉亖帺屓昞弌埲慜偺帺屓昞弌傪偼傜傓壒塁
倅(侾)幉亖帺敪揑側桳愡壒惡偺敪弌丄帺屓昞弌偺堄幆偑婲廳婡偺傛偆偵桳愡壒惡傪捿傝偁偘傞乮尰幚偐傜尪憐傊乯
倃(俀)幉亖尰幚偺悽奅偺懳徾傪捈愙揑偵偱偼側偔徾挜揑乮婰崋揑乯偵巜帵偡傞尵岅
倄(俀)幉亖堄幆偺帺屓昞弌偲偟偰敪偣傜傟傞壒惡乮帺暘帺恎傪娷傒側偑傜懳帺揑偵側傝丄傑偨偦偺偙偲偵傛偭偰懳懠揑偲側傞壒惡乯
丂
嘊尵岅偺恑壔
倅(俀)幉亖尵岅敪惗埲棃偺媫寖側傑偨娚傗偐側愊傒廳側傝偲偟偰偺堄幆 偺嫮偝乮倃幉偐傜乯
丂丂丂丂丂幮夛揑彅娭學偐傜偆傒偩偝傟傞尪憐偵傛傞尵岅偺婯掕乮倄幉偐傜乯
倃(俁)幉亖尵岅偺懳懠柺偺偁傜傢傟乮帪戙惈丄屄惈偲偟偰偺嵎暿惈丄柉懓岅偲偟偰偺摿惈乯
倄(俁)幉亖尵岅偺懳帺柺偺偁傜傢傟乮塱懕惈丄椶偲偟偰偺摨堦惈乯
丂
嘋暥妛昞尰傊偺椼婲
倅(俁)幉亖憐憸揑側傕偺偦傟帺懱偲偟偰偺尵岅
倃(係)幉亖偁傞帪戙偵惗偒偨偁傞嶌幰偺惗懚偲偲傕偵偮偐傑傟偰丄巰偲偲傕偵朣傫偱偟傑偆乽壗偐乿
倄(係)幉亖恖椶偺敪惗偐傜偙偺曽丄偮傒偐偝偹傜傟偰偒偨乽壗偐乿
丂
乵仏乶嶰杮偺嵗昗幉傪丄倃幉亖尰幚奅乮暔偺悽奅乯丄倄幉亖憐憸奅乮怱偺悽奅乯丄倅幉亖徾挜奅乮帉偺悽奅乯偵偍偒偐偊傞偲丄偐偺儔僇儞嶰懱乮娧擵嶰懱乯偵嬤愙偡傞丅傑偨丄倃幉亖懚嵼丄倄幉亖杮幙丄倅幉亖奣擮偲峫偊傞偲丄僿乕僎儖榑棟妛偲偺娭學偑晜忋偟偰偔傞丅偦傕偦傕椼婲亖巭梘偲偲傜偊傞偲丄曎徹朄偲偺娭學偼偳偆側偺偐丄偲偄偭偨榑揰偑惗婲偟偰偔傞丅倃幉亖屄乮摿庩乯丄倄幉亖椶乮堦斒乯丄倅幉乮忋徃乯亖晛曊丄倅幉乮壓崀乯亖扨撈丄側偳偲偁偰偼傔偰峫偊傞偙偲傕偱偒傞偩傠偆丅
丂奣擮娫偺椶帡惈傗娭學惈傪傒偄偩偟峔抸偡傞偙偲偵墄傃傪姶偠傞僞僀僾偲丄嵎堎惈傗柍娭學惈傪檻漃偡傞偙偲偵擬拞偡傞僞僀僾偑偁傞偲偡傟偽丄巹偼偁偒傜偐偵慜幰偺僌儖乕僾乮愜岥怣晇偺偄偆乽椶壔惈擻乿偑桪埵偵偨偮懁乯偵懏偟偰偄傞丅偙傟傑偱偐傜峫偊偮偯偗偰偒偨欶偺揱摫懱偺棟榑丄偦傟偼乽僀儅僕僫儕乕乛儕傾儖乿偺悈暯幉偲乽償傽乕僠儏傾儖乛傾僋僠儏傾儖乿偺悅捈幉偲偄偆擇杮偺嵗昗幉偱傕偭偰愝偊傜傟偨帄嬌扨弮側丄偄傢偽惷懺揑側棟榑儌僨儖側偺偩偑丄偄傑媑杮棽柧偺巚峫偺婎掙傪側偡嶰杮偺嵗昗幉偺傾僀僨傾傪抦傝丄偙傟傪儅僌僱僢僩偵偟偨奣擮偺廳偹拝偺壜擻惈傪帋偟偰偄傞偆偪丄償傽乕僠儏傾儖側椡偺壱摥傪慻傒崬傫偩摦懺揑儌僨儖傊偺僽儗僀僋僗儖乕偺偨傔偺廳梫側庤偑偐傝偑摼傜傟傞偺偱偼側偄偐偲偄偆婜懸偑傔偽偊巒傔偰偄傞丅偨偩偟丄偙偺梊姶偑尰幚偺傕偺偵側傞偵偼傑偩悢擭偼梫偡傞偩傠偆偲巚偆丅
丂
乮俀俈崋偵懕偔乯
仛僾儘僼傿乕儖仛
拞尨婭惗乮側偐偼傜丒偺傝偍乯1950擭戙惗傑傟丅暫屔導嵼廧丅愮擭傕愄偵彂偐傟偨榓壧偺堄枴偑棟夝偱偒傞偺偼偡偛偄偙偲偩丅偱傕丄杮摉偵乽棟夝乿偱偒偰偄傞偺偐丅偦偙偵乽堄枴乿側偳偁傞偺偐丅偦傕偦傕尵梩傪巊偭偰壗偐傪揱払偡傞偙偲偦偺傕偺偑晄巚媍側尰徾偩偲巚偆丅
Web昡榑帍乽僐乕儔乿26崋乮2015.08.15乯
亙欶偲僋僆儕傾亜戞35復丂懕乆丒帺屓昞弌偲巜帵昞弌偺怐暔劅榓壧偺儊僇僯僗儉嘩乮拞尨婭惗乯
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU丂2015 All Rights Reserved.
|
| 昞巻乮栚師乯傊 |