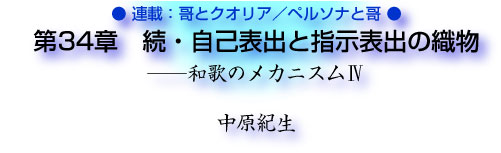|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「La Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
|
■生起と喩のメカニズム、再説
中沢新一氏によって、吉本隆明の「自己表出」と「指示表出」に重ねあわせて論じられた「生起」と「喩のメカニズム」について、いま少し、こだわりたいと思います。
まず、生起について。
中沢氏自身が書いていたように、この語は、ハイデガーの「エアアイグニス[Ereignis]」に由来します。一般には「事件、出来事」と訳され、英語では「イベント[event]」、フランス語では、(たとえば、丸山圭三郎が『言葉と無意識』で、「人間は、言葉をもったために生じたカオスへの恐怖と、それをまた言葉によって意味化する快楽に生きる。この恐ろしさとめくるめく喜びこそ、ルドルフ・オットーのいう〈ヌミノーゼ的体験〉であり、形を絶えず突き崩す動きと、動きを絶えず形とする力の舞台であり、そこで起きる〈出来事〉[エヴェヌマン]とは、同時に形であり動きであると言ってよい。」と書いていた、その)「エヴェヌマン[e've'nement]」にあたる語です。
後期ハイデガーの思索を導く「主導語」であり、翻訳不可能とさえいわれる「エアアイグニス」の概念が主題的に論じられたのは、ハイデガー第二の主著、あるいは真の主著とも評される『哲学への寄与』でした。鈴村智久氏は、論考「Martin Heidegger archives5」において、この高度にエソテリック(秘教的)な著書のなかで、ハイデガーは、「「存在」が我々「存在者」を「呼び求める」という、その存在それ自身の「不可視」の「活動」」を「エアアイグニス」と規定していて、このことを、『哲学への寄与』のもう一つの鍵概念である「深淵[Abgrund]」とあわせ考えると、そこに「霊的な意味」が結びついてくる、と書いています。
鈴村氏はここで、諏訪春雄著『霊魂の文化誌』を参考に、「他界」という民俗学の概念を導入します。「諏訪氏によれば、「他界」から出現するのが「幽霊」であり、「異界」から出現するのが「妖怪」である。「他界」が「世界」と隣り合った同心円として存在しているのに対し、「異界」は「世界」の円と完全に重なり合っている。つまり、「世界」のあらゆる領域が、何らかのシャーマン的祭儀、もしくは心霊現象などを通じて突然、「異界」化する可能性を持つとされている。」
ここで「深淵」を「沈黙」とおきかえて、それに、講演「芸術言語論――沈黙から芸術まで」のなかで吉本隆明が、大要、「言語というものは、沈黙の幹と根を重要な根底とする「自己表出」と、コミュニケーションという枝葉の問題にかかわる「指示表出」とが、縦糸と横糸みたいに織り合わせてできている」、と語っていることに関連づけて考えるならば、「エアアイグニス」とは、脱魂や憑依(憑霊)、祈りや預言といった儀礼、言語現象から発生する詩的言語のはたらきそのものではないかと思えてきますし、あるいは、ここで議論されているのは、文字通り幽霊が登場し、生者にむかって「呼び求める」能の劇的構造のことだったのではないかと思えてきます。
「生起」すなわち「エアアイグニス」は、華厳教学にいう「性起(しょうき)」におきかえて考えることができます。(『哲学の寄与』は「エアアイグニスについて」の副題をもち、邦訳では『哲学への寄与論稿(性起から〔性起について〕)』(創文社「ハイデッガー全集」第65巻)とされている。)
このこと、つまり「エアアイグニス」と「性起」との関係についてては、頼住光子氏が、「西洋哲学と道元禅──「エアアイグニス」と性起の間」(『正法眼蔵入門』)などで論じていますが、ここでは、頼住氏が研究代表者となった「道元の思想構造の総合的研究─比較思想的観点から」の研究成果報告書の該当箇所を抜き書きしておきます。
ハイデガーの「エアアイグニス」が、華厳教学の「性起」の批判的摂取を介して、道元の「現成(げんじょう)」につながりました。そして、『井筒俊彦 言語の根源と哲学の発生』(KAWADE道の手帖)に収めれた文章(「井筒俊彦と道元」)のなかで、頼住氏が、「井筒は、道元を、ある究極的な実在体験について沈黙せずそれを論理化し、言語化した例外的な禅者と捉えていた。井筒にとって道元は、禅の修行と哲学的思惟とを両立し得た点で自分の先駆者であり、同時に、ギリシアの哲人たちやイスラーム神秘主義思想家などと同様に、修行を基盤とした至高体験を論理化した、神秘道と哲学との両者を兼ね備えた神秘主義哲学者であった。」と書いているように、道元は、井筒俊彦が共感し傾倒してやまない先達でした。
『意識と本質』から、関連する文章を引きます。井筒俊彦はそこで、『正法眼蔵』第二十九「山水経」巻の「水現成の公案」を、井筒自身の言語=存在分節論の観点からとりあげています。いわく、「分節(Ⅱ)」すなわち無「本質」的分節の次元においてはじめて、水の真のリアリティが現成する。それは、「無分節者の直接無媒介的顕現としての水」であり、「本質」(として妄想されたもの、たとえば「水は流れるもの」)の繋縛をはなれた、自由無碍にして生々躍動する姿における「本水」である。
■M領域と群論・その他の註記
前章の末尾で、「深層、垂直、発生、…」と「表層、水平、現象、…」の二つの系列に「自己表出、生起」と「指示表出、喩」の対概念を関連づける際、私は、「自己表出、生起」が「深層」に、そして「指示表出、喩」が「表層」にといった単純な重ねあわせをしてすますわけにはいかない、と自戒の弁を註記しました。
その趣旨は二つあります。第一に、潜在的夢思想、顕在的夢内容の概念にでてきた「潜在/顕在」と「深層/表層」を単純に重ねあわせることはできないということ。強いて両者を合成するなら「深層(潜在+顕在)/表層」となるでしょうし、そこに「無意識」の概念を導入すると、井筒俊彦の拡張された「意識の構造モデル」に、すなわち「C領域(無意識)/B領域(言語アラヤ識)+M領域(中間領域、想像的イマージュの場所)/A領域(表層意識)」になるのではないかと思います。
なにが言いたいのかというと、顕在的深層意識すなわちM領域こそが、意味の増殖をつかさどる喩のメカニズムの本拠地なのではないかということです。(これに対して、A領域における喩は、意味の伝達をつかさどる修辞技法として、吉本隆明の表現をつかえば、「壁画」的に分類される対象となります。)そして喩とはフィギュールであり、M領域にうごめくものは、ほかならぬ想像的イマージュすなわち像なのだから、ここに喩と像、フィギュールとイマージュをめぐるあやしい関係が、(たとえば、吉本隆明が『言語にとって美とはなにか』で、「意味的な喩」とともに呈示した「像的な喩」という概念の正体はなにか、といったかたちで)、解明されるべき論点として浮かびあがってきます。
さらに、井筒俊彦によれば「マンダラ」は「M領域に現成する存在構造を形象化した深層意識的絵画」の一例にほかならないのですから、井筒豊子のいう「自然曼荼羅」(和歌的創造主体の視野に現成するところの「景観」で、その「表象的一典型」を国宝・那智瀧図に見ることができるもの)と「フィギュールとしての和歌」をめぐるあやしい関係、もしくは無関係といった論点もあわせて浮かびあがってくるでしょう。
第二の趣旨は、そもそも「自己表出/指示表出」と「生起/喩」を平面的に重ねあわせること自体が乱暴きわまりない議論であるということ。概念の先祖、親戚探しをするなら、吉本自身が言及しているマルクスの「交換価値/使用価値」(「経済の記述と立場──スミス・リカード・マルクス」,『吉本隆明の経済学』)をはじめ、夏目漱石(『文学論』)の「F(焦点的印象または観念)/f(Fに付着する情緒)」(「飛躍と転回」,『柄谷行人インタヴューズ 1977―2001』)や、フッサール(『論理学研究』)の「表現(意味記号)/指標(指示記号)」(詩人・富哲世の指摘、なお竹田青嗣著『世界という背理──小林秀雄と吉本隆明』に同趣旨の記述がある)など、まだまだ蒐集の余地があります。(他にも、ソシュールの「連合/連辞」やヤコブソンの「選択/結合」「置換/結構」、量子力学の「波動性/粒子性」、はては「歴史/世界」や「時間/空間」、等々。)
このことと関連するのではないかと思うので、吉本隆明があるインタビューに答えて語った言葉を引きます。
数学の表現論のことなどとても手におえないし、たとえ多少聞きかじっていたとしても軽率に言及すべきではないと思いますが、付け焼き刃で遠山啓の本を読んでいて次のような記述が目にとまりました。『現代数学入門』に収められた「数学は変貌する」という文章の群論を解説したところにでてくる比喩です。吉本隆明が『言語にとって美とはなにか』の根底に数学の表現論があると語っていることの意味は、おそらくこのあたりにあるのだろうと私は直観しています。
いわく、「群」とは何らかの「操作」(オペレーション、手続き)の集まりをいう。それは二つの操作を結合して第三の操作が出てくる代数的構造をもっている。生物の現象など時間・空間の両面にわたる動的な体系、動的な構造を理解するのに有効な方法である。その方法とは、何かの構造を知るためにそれを動かしてみる、ある操作でそれを変化させてみる、そうしてどう変化するかを見てそのものの構造を知るというやり方である。たとえばスイカを割らずに外から叩いて熟度を調べる、医者が患者のおなかを触診する、地下の地質の構造を地震波の伝わり方で調べるといった「打診」的方法であって、解剖学的な方法ではない。幾何学でも原子の世界でも建築でも模様でも絵でも、およそ構造をもつものであれば群論の打診的方法が使える。
吉本隆明が『言語にとって美とはなにか』で多重多様に展開している言語の二重性の概念を、「深層=垂直=発生=自己表出=生起=…/表層=水平=現象=指示表出=喩=…」といった類の平板な二項図式でもって静的・平面的にとらえるのはミスリーディングです。言語表現物という「生きた」動的体系、多重多様な動的構造に拮抗しうる、それ自身「生きた」ダイナミックな操作群として、吉本表現論はとらえられなければなりません。
寄り道が長くなりすぎたあげくに、すこし先走りました。
合田正人氏は『吉本隆明と柄谷行人』の第三章「意味とは何か」で、吉本による言語論の核心は「像(Bild,image)」と「喩(figure)」に関する考察であると書いています。この指摘は正鵠を射ている。私はそう考えるのですが、このことを確認するためには、『言語にとって美とはなにか』の理論的考察を(自由間接話法のかたちで)濃縮し、私自身の関心や理解力にそくして復元するという難儀な課題をクリアしておかねばならないでしょう。
■余録と補遺、他界について・その他
先走りついでに、いくつか気になったことを、脈絡なく書き残しておく。
まず、吉本隆明の表現論が「生きた」ダイナミックな操作群あると書いたことに関して。それではそこでいう「操作」とはどういうものか。
たとえば韻律・撰択・転換・喩のそれぞれが、そして喩のうちの「像的な喩」と「意味的な喩」のそれぞれがまた(詩人・評論家・作家に共通する)「操作」である。「ある作品のなかで、場面の転換はそのまま過程として抽出せられたとき喩の概念にまで連続してつながっており、また、喩はその喩的な本質にまで抽出せられない以前では、たんなる場面の転換にまでつながっている」(『定本 言語にとって美とはなにかⅠ』)といわれるときの「抽出」が(主として評論家にとっての)「操作」をいいあらわす語である。
操作は「方法」に、抽出は「抽象」に通じる。菅野覚明氏は『吉本隆明──詩人の叡智』で、吉本隆明の思想的方法の核心をめぐって次のように書いている。
いま一つ、柴田弘美著『開かれた「構造」──遠山啓と吉本隆明の間』の議論を引く。
いわく、自同律や排中律を絶対的なものとしてしまうと世界は二分され、果てしない叩き合い、罵り合いが繰り返される。「不快」「ぷふふい」というだけで済ましているわけにはいかない。吉本はこうした不毛な党派的抗争の根っこに潜む「論理の病」を一挙に止揚する方途を見出した。これら対立し反発しあう概念は実は直交する座標軸(基底ベクトル)のように「互いに独立」なのではないか。
ここでいわれる「史的必然性を担うもの」がタテ軸(自己表出)に、「個体的な偶然性、一回きりの現在性を担うもの」がヨコ軸(指示表出)につながっている。私自身は、吉本隆明の方法=抽象すなわち「座標変換操作」のもっともシンプルなかたちはタテ・ヨコの二軸ではなく、「固有時との対話」にでてくるX・Y・Zの三つの座標軸でとらえるべきだと考えている。
次に、他界をめぐって。
諏訪春雄著『霊魂の文化誌──神・妖怪・幽霊・鬼の日中比較研究』によると、他界は「ほかの場所、死者の世界」という二つの意味をもつ。後者の意味は中国に出典がなく、鎌倉時代になってはじめて用例がみられる。これに対して、異界は異人とむすびついて新しくつくられたことばである。
記紀神話や万葉集などに表現されている他界観を検討した柳田國男、折口信夫らの成果をまとめると、古代の日本人の他界観は、「地下他界」(黄泉国・根の国)、「海上(中)他界」(妣の国・常世の国・海宮[わたつみのみや])、「天上他界」(高天原)、「山上(中)他界」、「東方他界」、「西方他界」の六つになる。
しかし、自由であった現世と他界との往来が、一方で、閉じられてしまった話のあることも見のがすことはできない。著者はそのように書き、のぞき見したことが原因となって他界との往来が絶たれる神話を二つとりあげる。
この他界をめぐる議論を、たとえば吉本隆明が「詩魂の起源」(『詩とはなにか──世界を凍らせる言葉』)で論じた「詩の精神=魂」の三つの行動様式(山の頂・海の彼方・洞窟)に接続し、定家の「よそ」と関連づけ、また異界と他界を、(第16章でとりあげた)「二者交換」的なパラレル・ワールドと「二者並立」的な並行世界や、(第32章、第33章で論じた)「内と外」のホリゾンタルな二項対立図式と「一と多」(根源的一者と現象的多)をむすぶヴァーティカルな力動的視点にそれぞれ関係づけて論じることで、和歌のメカニスム(喩と生起)が稼働するフィールド、つまり「同時に形であり動きである」(丸山圭三郎)ものを生起させる力の舞台の成り立ち・構造・稼働原理を解明するための有力な手がかりが得られるのではないか。
(35章に続く)
★プロフィール★
中原紀生(なかはら・のりお)1950年代生まれ。兵庫県在住。千年も昔に書かれた和歌の意味が理解できるのはすごいことだ。でも、本当に「理解」できているのか。そこに「意味」などあるのか。そもそも言葉を使って何かを伝達することそのものが不思議な現象だと思う。
Web評論誌「コーラ」26号(2015.08.15)
<哥とクオリア>第34章 続・自己表出と指示表出の織物─和歌のメカニスムⅣ(中原紀生)
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2015 All Rights Reserved.
|
| 表紙(目次)へ |