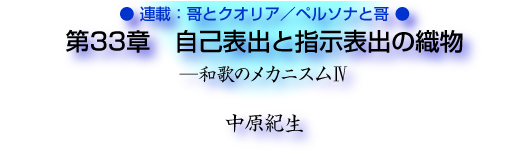|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「La Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
|
■土をこねて一生を使いはたす生き方
はじめに、前章の最後で、和歌の表現における「自然の事物事象の多出」をめぐって書いたことに、若干の補足をします。
……自然曼荼羅における事物事象群は、自然記号としての「コトバ」であり、かつ、いま・ここに現象する思ひとしての「ココロ」であり、それらは同時に、クオリア的実在としての「モノ」そのものである。つまり、自然曼荼羅こそ、和歌をなりたたせる「物・心・詞」の三つの要素を束ねる窮極のアソシエイションである。
そうしたアソシエイションの優位のもとで遂行される「やまとうたの思想」にあって、「よろづ」と「ひとのこころ」と「ことのは」は、自然曼荼羅のうちに水平的交換と垂直的映現の関係をきりむすぶ。和歌を詠むとは、そのような、「モノ=ココロ=コトバ」となって自然曼荼羅を現出させる高次の位相における事物事象を詠むこと、あるいは自然の事物事象が自らを詠みいだすことにほかならない。……
私はおよそ、そのように書きました。はたしてどこまで判って書いたのか、そこにくっきりとした実感は伴っていたか、頼りないことですが、今となっては朦朧としています。その後、筑摩書房の『吉本隆明〈未収録〉講演集1』に収録された「日本的なものとはなにか」を読んで、ひとつ腑に落ちたことがあったので、それについて記しておきます。
吉本隆明は、講演の冒頭で、比較言語学や民族学や人類学の方法ではない、折口信夫独自の「言語思想的」な方法について述べています。それは、日本語の古典を読んでいるうちにでてくる一種の自己イメージからさかのぼって、日本語以前の日本語の言い方を見つけだすというもので、日本語以前の古い言い方とは、たとえば「日琉語族論」(原文では「日琉同族論」)という論文で折口が論じた「逆語序」(例:小さい地域から大きい地域へと、通常とは逆の順序で広げていく地名の言い方)がそれにあたります。
吉本隆明はつづいて、モーリス・レーナルトの『ド・カモ』から、日本語以前の日本語においても大きな特徴の一つとなる「内臓語」と「自然語」という表現のしかたをとりあげます。
内蔵語とは、「あなたの考えはどういうことですか」を「あなたの腹は何ですか」と言うように、内臓の動きが心の動きになり、その心の動きが言葉に表現されるもの。「言葉には自己表出といいまして、内蔵的な表現が心の表現になって、それが言葉の表現になるという、そういう側面があるわけです。」
自然語とは、自然物はすべて人と同じであるという思想、土地の名や生き物、自然現象の全部が人の名前にいつでも交換できるし、それらと会話もできるという考え方にもとづくもの。
吉本は、イスケヨリヒメが「狭井川よ 雲たちわたり 畝傍山 木の葉さやぎぬ 風吹かむとす」と詠み、子どもたちに警告を発したことをとりあげて、「古事記」の成立時代でも「自然物を詠むことによって、別の言いたいことがいえるのだということ、逆にいえば、別の言いたいことをいうためには、自然物を描写すればいいのだという考え方」が存在したことを指摘します。このような「狭井川に雲が立ちおこっている」という視覚的イメージを使った言葉は、先の「内蔵の表現」に対して「感覚の表現」と呼ばれ、「この場合には、ぼくらは「指示表出」という言い方をしています」。
内蔵語や自然語は古い日本語の大きな特徴なのですが、現代の日本語の感覚でいうと、それらはみな比喩の言葉と受け取れます。「でも本当にその古い日本語の、つまり原始未開の時代の日本語のあり方からいいますと、それは比喩ではないので、何かをいうためには、内臓語や自然語を使う以外になかったのだということです。」
それでは、なぜ日本語(オーストロネシア語族)では「自然を描写する言葉」や「内臓の動きを使う言葉」でしかものがいえなかったのか。インド=ヨーロッパ語のように抽象的な表現が可能な言葉として発達せず、自然語や内蔵語を使わないと何かがいえない、あるいは何かをいおうとすると翻訳語の抽象語しか使えないということになっているのか。それは、原始未開の時代のところで停滞の時代があったからではないか。インド=ヨーロッパ語もそういう時代をとったのだが、そこを速やかに通っていったのではないか。
自然曼荼羅の景観のうちに見えてくる事物事象とは、一生涯にわたって土をこねて生きた人の手になる陶器のようなものなのかもしれません。あるいは、あたかも土をこねるようにして古い日本語を使って(使われて)表現した人の手になる、自己表出と指示表出の「織物」のごときものなのかもしれない。
■無相真如、あるいは呪術的な祈りのことば
観世寿夫に「無相真如」と題する短い文章があります。日本古典文学大系『謡曲集上』の月報のために書かれ、『観世寿夫 世阿弥を読む』に収められたこの一文のなかで、観世寿夫は、能には二つの謡い方があると書いています。
ひとつは、「隅田川」のシテが、ワキの船頭から「さても去年三月十五日、しかも今日に相当たりて候」と、わが子の悲惨な最期を語り聞かされるときのように、ことばの意味がはっきりと伝達される「カタリ」。いまひとつは、「芭蕉」の「それ非情草木といつぱ、真[まこと]は無相真如[むそうしんにょ]の体[たい]、一塵法界[いちじんほうかい]の心地[しんち]の上に、雨露霜雪[うろそうせつ]の象[かたち]を見[み]す」が、ことばとしては正確に「ムソオシンニョ」と聞こえたとしても、それが直ちに「無相真如」、すなわち「形相を超えて存在する絶対真理」の意味だとわかってもらえるとは到底考えられない「うなる」謡い方。
後者について、観世寿夫は、「断片的に出て来る単語や慣用句によって、その一段の、全体的なイマージュさえ感じられれば良いので、ひとつひとつのことばの意味は必要でなくなってしまうのではないか」と述べ、さらに、謡にとって詞章の意味が必要でなくなるだけではなく、能にとって筋書きやシテの人物までもが「たいした問題ではない」ことになる場合がある、と説き及びます。
観世寿夫はつづけて、単にドラマ、演劇として考えれば、歌舞伎や新派、新劇のほうがはるかに面白く、いまさら古くさい能などを持ち出す必要はないのであって、能の美しさは、「いわばドラマを超越したところから生まれて来るところの生命感といったもの」にあるのだ、と論じます。
表面的なドラマの筋書きやことばの意味を伝える「カタリ」。意味のない音と意味のない動きの流れに添って謡われる「ウタ」、というよりむしろ呪術的な祈りのことばに近い「ウナリ」。能におけるこれら二つの言語現象は、一方が「ことばという具体的なもの」の次元で進展する「意識的なドラマの世界」に属しているのにたいして、他方は、「人間の声そのものの持つ実在感とか、声にはならない息の持つ緊迫感」に、ひいては意味のない「音と動きといった、より抽象的なもの」に身をゆだねるなかから生まれてくるところの「生命感」、さらには東洋的な「無」の境域(さかい)につながっていきます。
このことを、坂部恵著『かたり──物語の文法』の議論を援用していいかえると、かたや表層的な「日常効用の水平の時空」に属し、かたや非日常的な神話空間や記憶を絶したその「インメモリアル」な時間にふれる「記憶や想像力の垂直の時空」の深層的次元に属している、となるでしょうか。そして、そのうちの後者、すなわち、坂部氏が提唱する言語行為とふるまい一般に関する二つの図式中の「はなし──かたり──うた」における「うた」と、同じく「ふるまい──ふり──まい」における「まい」の流れに添って謡われる高次の言語現象にあっては、ことばの意味やその語り手の個別の心理・感情などはもはや「たいした問題ではない」ことになっていくのでしょう。あたかも、アナグラムのように。
■アナグラム、あるいは深層のポリフォニー
表層と深層、あるいは表層言語=意識と深層言語=意識。水平と垂直、あるいは意味や観念を伝達する具体的な「ことば」(水平的なディスクールのはたらき)と意味のない抽象的な「音・動き」(フィギュール群の垂直的な生起と流動)。丸山圭三郎著『言葉と無意識』(第Ⅲ章「アナグラムの謎」)によれば、これら言語の相異なる二つの位相を、ソシュールは、「ラング」(表層言語)と「ランガージュ」(深層言語)として峻別しました。
いわく、ソシュールは、制度化された構造である「ラング」の体系内の「透明な記号の世界や、これによってディジタルなA/非A的思考と認識に陥っている表層意識」に対して、人間のシンボル化能力とその活動である「ランガージュ」の概念を導入することにより、「不透明な非記号の世界と、マグマ状の意味可能体の差異化が行われる意識の深層における意味生成の働き」を対置したのであり、その具体的な例こそが、ラカンの「言葉としての無意識」やクリステヴァの「間テクスト性」の理論を生み出す源となった「アナグラム研究」にほかならない。
文字や詩句の配置がえの「言葉遊び」ではなく、詩の成立の原因そのものとみなされる「音の法則」としてのアナグラム。ソシュールは、この「神話的思考がそのイメージを構成するのと同じ」隠された詩法に関心をよせ、広義のアナグラムを、①アナグラム(テーマ語がいくつかの単音に分けられて散在するもの)、②アナフォニー(その不完全な形)、③イポグラム(テーマ語がいくつかの複音に分けられて散在するもの)、④パラグラム(テーマ語が、アナグラムよりも広い範囲、すなわちテクスト中に散種されているもの)の四種類に分類し、このうちパラグラムを最も重要な形とみなした。
しかし、ソシュール自身は、アナグラムの技法が詩人にとって「意識的か、偶然か」という点に最後までこだわり、これを「意識的である」とする仮説を裏付けてくれる詩人からの証言を得たいと願った。
丸山圭三郎は、さきの文章にでてきた「深層言語のポリフォニー性」をめぐって、ソシュールのアナグラム研究は、「詩的言語が、本質的かつ普遍的に多声音楽的[ポリフォニーク]・多義的[ポリセミーク]性格をもつことを明らかにした」とするヤーコブソンの言葉を引用し、また、パラグラムの論理は、科学のような「独語(モノローグ)=単一論理(モノロゴス)」ではなく、「対話(ダイアローグ)=二重論理(ディアロゴス)」であるとするクリステヴァの解釈に言及したうえで、次のように述べています。
ここで、丸山圭三郎は、あらためて「アナグラムのポリフォニー性」について考察をくわえます。いわく、アナグラムには、ポリフォニーとは本質的に異なる独自の多声性がある。アナグラムに聴きとられるものが深層意識における多声性・多義性であるのに対し、ポリフォニーの技法が生み出す重層性は、複数の音が表層意識に直接訴えるものにすぎない。「アナグラムの多声性は、あくまでもモノフォニーのなかから‘内なる’耳目に感じとられる複数の声なのである。」
かくして、アナグラムの話題が能楽につながり、そして、言語=意識の構造的な二重性・重層性をあらわす対概念、「表層・深層」「水平・垂直」に、「現象・発生」という第三の類型がくわわりました。
丸山圭三郎の議論は、このあと、ソシュールのアナグラム研究が提起した「真に現代的な問題」へと、すなわち「語るものは誰か」、そして同時に「意味とは何か」という問いへ向かって進んでいきます。
そこでは、マラルメにおける「主体の非人称化」やヴァレリーにおける「私の複数化」、ランボーの「私はもう一人の他者である」という内的体験などの「主体の壊乱」(ラカン)が、「深層言語における意味の不在」と切っても切れない関係にあること、また、表層意識において「意味に連結される言葉の連鎖」が優勢であるのに対し、深層意識にあっては「音のイメージに媒介される言葉の連鎖」が圧倒的で、これが、表層言語の意味の崩壊や主体の壊乱をもたらす原因となり、かつ、「擬論理的(パラロジカル)」や「古論理的(パレオロジカル)」といった精神分裂病者の心的構造の典型に、ひいては「私たちの誰もが身の奥にもっている〈深層のロゴス=パトス〉の言葉の姿」につながっていくこと、そして、そこでは事物の分割線は消滅し、「いわば〈事事無碍〉的な、境界線の取り払いによる生命の流動性の回復」がはたされるのであって、この点において、「アナグラムのソシュール」とラカンの思想とが一つに重なりあうこと、等々が論じられます。
これらの論点については、いずれ、「グラフィック・アナグラム」とでも呼べる「歌織物としての百人一首」や、「意識的な」アナグラム、あるいは「意識的でもありかつ無意識的でもある〈間テクスト性〉の一種」とみなされるべき「本歌取り」といった興味深い話題ともども、しかるべき論脈(たとえば、詩的言語・深層言語・狂言綺語としてのコトバ=フィギュールのあり様をめぐる)のもとであらためてとりあげることにして、ここでは先を急ぎ、当面の作業にもどります。
■唯言論について・その他の備忘録
いま、「当面の作業」と書いたことについて、着地目標点を見誤らないための手控えとして書いておく。
第22章でふれたように、西脇順三郎は「超現実主義詩論」のなかで、「純粋芸術のメカニスムの構成要素」として、次の二項を掲げている(『ボードレールと私』)。「エステティクの世界に於て二つの相異なりたる経験意識を聯結すること。」「強烈なる生きんとする力。換言すれば美を求めんとする‘強烈すぎる力’が必要である。この力がなければ第一にあげたメカニスムは単にコミックな効果にのみ終るのである。」
私は、この第一のメカニスムを「表層・水平・現象」の位相における「イマジナリー・フィクショナル・ポッシブル・イデアル(虚)/リアル(実)」の軸に、第二のメカニスムを「深層・垂直・発生」の位相における「ヴァーチュアル(空)/アクチュアル(現)」の軸にそれぞれ関連づけ、かつ、これを『意識と本質』で井筒俊彦が導入した「意識の構造モデル」にあてはめて考えようとしてきた。
井筒俊彦の「意識の構造モデル」とは、人の深層意識領域において「想像的イマージュ」体験というかたちで自己を開示する「本質」(=「元型」イマージュ)の実相を分析するために、深層・表層の二分法によって「極度に単純化した」意識の「二重構造モデル」を、「深層意識」という語が指示する意識機能の構造的多層性をふまえて複雑化したもののことで、それは、「意識のゼロ・ポイント/無意識/言語アラヤ識/M領域(中間地帯)/表層意識」と表記することができる。
井筒豊子が和歌論三部作で論じた、言語・意識・認識の三つのフィールドに関する構造論と、そこでの稼働原理である「遡行と塑型」をめぐる議論は、基本的にこのモデルに立脚している。(ちなみに、井筒豊子が、言語のもつ二つの側面をあらわすものとして導入した概念のうち、「シンタックス」は「表層・水平・現象」の位相に、また「アソシエイション」は「深層・垂直・発生」の位相にそれぞれ関連づけることができる。)
そして、本稿で再三とりあげてきた、「欲動(無意識)/深層のパトス(潜意識・下意識)/表層のロゴス(表層意識)」もしくは「カオス/ノモス化されないコスモス/ノモス化されたコスモス」という丸山圭三郎の構図もまた、井筒俊彦の拡張された「意識の構造モデル」と相同である。(「物(よろづ)/心(ひとのこころ)/詞(ことのは)」もしくは「地=欲動/海=パトス/空=ロゴス」の貫之三体もまた同様。ただし、前章でとりあげた井筒豊子の議論をふまえると、「地/海/空」の「空」のうちには、「山の端」を介して「天」(海中の心と相互映現しあう月の領域)が区画される。)
井筒俊彦と丸山圭三郎の関係をめぐって、若松英輔氏は『井筒俊彦──叡知の哲学』で、「おそらく、丸山は、「コトバ」が、井筒俊彦におけるもっとも重要な術語であることを最初に看破した人物だった。」と書き、丸山自身が主著『生命と過剰』で、「井筒俊彦氏と晩年のアナグラムのソシュール、そして私自身に共通する言語=存在論」と表現したことを指摘している。(この三者に共通する言語=存在論とは、丸山自身の要約によれば、「意識の表層と深層とに同時に関わるコトバの意味分節作用が、知覚の末端的事物認知機能のなかにまで本質的に組みこまれていて、我々の内面外面に拡がる全存在世界そのものは、コトバの存在喚起力の産物にほかならぬ」(『生命と過剰』)という考え方である。)
なお、『生命と過剰』には、井筒俊彦の「アンティ・コスモス」(コスモス以前の単なる渾沌としてのカオスに対して、コスモスの成立後、コスモスに敵対する否定的エネルギーとしてとらえられた第二のカオス)の概念をめぐって、コスモス対アンティ・コスモスは「ホリゾンタルな内と外なる二項対立図式」を構成するのではなく、アンティ・コスモスはコスモス空間そのものの中に構造的に組み込まれている破壊力である、といった議論がでてくる。
この「ホリゾンタルな」図式という表現は、同書の他の個所にもみることができる。それは、チョムスキーの「表層構造/深層構造」は「ホリゾンタルな言語/精神あるいは言語/普遍的理念構造の図式」であって、チョムスキーの「精神」とはデカルト的コギト以外の何もでもない、云々といった文脈のなかで使われている。そして、一方、「意識の深層におけるコトバの働きをヴァーティカルな視点から捉えていたのは、東洋の哲学者たちであった。」として、東洋の「唯言論」(唯ランガージュ論)をめぐる議論がこれにつづく。
「ホリゾンタル」な二項対立図式(内と外)と、深層領域へと向かう「ヴァーティカル」な力動的視点(根源的一者と現象的多をむすぶ)。井筒俊彦と丸山圭三郎の思考の同型性をあらわすキーワードがここにある。そして「存在はコトバである」とは、若松英輔氏がいうように、井筒俊彦の思想を一言で収斂させる言葉であった。(さらにいえば、以前、第10章でとりあげた、意識の表層と深層のあいだの円環的往復運動をめぐる丸山圭三郎の議論は、井筒豊子のいう遡行と塑型をめぐるそれと同型のものと見ることができる。)
しかし、「当面の作業」とは、井筒俊彦の意識の構造モデルとこれに立脚した井筒豊子の和歌論を、丸山圭三郎の議論に接続することではない。吉本隆明の思想(芸術言語論)、とりわけ『言語にとって美とはなにか』へと接続していくことである。
■自己表出と指示表出、あるいは生起と喩のメカニズム
『吉本隆明の経済学』の第二部「経済の詩的構造」で、中沢新一氏は、吉本隆明が『言語にとって美とはなにか』で論じた言語の本質的構造、すなわち、人間の心の仕組みの奥で活動し、いっさいの心的現象がそこから立ち現れるところの根源的な「詩的構造」をめぐって、次のように書いています。(文中の「図」とは、『定本 言語にとって美とはなにかⅠ』に示された、感動詞から名詞までの「品詞のもつ位相」を、自己表出性(縦軸)と指示表出性(横軸)との直交座標上に示したもの。)
中沢氏は、「潜在空間から現実世界へと向かおうとする言語の現象性の本質」にかかわる「垂直的な過程」を、ハイデッガーにならって意味の「生起」と呼び、この生起を通じて潜在空間から立ちあがってきた「意味の胚」(AとBの双葉で表現される)を組織する働き、すなわち、たがいに似ている事物を「同じもの」としてまとめる能力のことを「喩」と呼びます。そして、生起と喩からなる「潜在空間(X)⇒現実界(AとB)」に関して、次のように語っています。
以上の議論を、私なりの語彙を使っていいかえると、次のようなものになるでしょうか。
……人間の言語は、指示表出と自己表出という二つの軸の結合としてつくられている。そのうち指示表出は「イマジナリー(虚)/リアル(実)」のホリゾンタルな軸にかかわり、実在するもの(実)と実在しないもの(虚)が自在に反転(交換)しつつ自己増殖する「喩」の空間をかたちづくる。また自己表出は「ヴァーチュアル(空)/アクチュアル(現)」のヴァーティカルな軸にかかわり、無の領域にふれる潜在空間(空)あるいは身(み)の深層次元から「アクチュアルな世界(実と虚を包摂する現の領域)」を「生起」させる。人間のおこなうすべての言語表現は「実・虚・現・空」の四元数としてこれをとらえることができる。
ヴァーチュアルな空間における「意味の種子」Xが生起して、アクチュアルな世界における「モノ」A・Bとなる。たとえばA=花、B=鳥とすれば、そこには「花が咲き鳥が啼く。鳥と花とは互いに透明であり、互いに浸透し合い、融け合い、ついに帰して一となり、無に消える。だが、消えた瞬間、間髪を容れず、また花は咲き鳥は啼く。」(『意識と本質』)と表現される「分節Ⅱ」(無「本質」的分節)の関係がむすばれる。……
このいいかえ、もしくは転換・翻訳では、吉本=中沢の議論から読みとれる、哥というギフト・フィギュールとしての哥・哥のパランプセストという「広義の」貫之現象学への含意をくみとることができていません。また、現実界・想像界・象徴界というラカン由来の三つ組の概念をすくいあげ、さらには、言語フィールド・意識フィールド・認識フィールドという井筒豊子の三つのフィールドの「三位一体性」をめぐる議論への接続線を引くこともできていません。
が、これらの論点は、後の課題として、ここでは、言語=意識の構造的二重性をあらわす「深層=垂直=発生/表層=水平=現象」に、「自己表出/指示表出」もしくは「生起/喩」という新たな対概念がくわわったこと(『言語にとって美とはなにか』を実地にひもとくと、そこに、時枝誠記(『国語学原論』)の「辞(観念語、自己表出語)/詞(指示表出語)」、三浦つとむ(『日本語はどういう言語か』)の「主体的表現(自己表出)/客体的表現(指示表出)」を重ね描きできること、そして、宇田亮一著『吉本隆明 “心”から読み解く思想』が、三木成夫由来の「内臓表出(植物の心)=自己表出/体壁表出(動物の心・感覚)=指示表出」の関係を強調し、また、柴田弘美著『開かれた「構造」──遠山啓と吉本隆明の間』が、「波動的現象(シュレジンガーの波動力学)=自己表出の連続的な転化/粒子的現象(ハイゼンベルグらの行列力学)=指示表出の時代的・個的現存性」の関係を強調していること、さらには、折口信夫と西脇順三郎、井筒俊彦と吉本隆明の言語理論の核心をなす言語の二重性、すなわち「感性的機能/知性的機能」をつけくわえることができること[*]、ただし、「自己表出/指示表出」もしくは「生起/喩」が単純に「深層/表層」に重ねあわさるわけではないこと)を確認しておきます。
[*]安藤礼二氏は『折口信夫』の「詩語論」の章に収められた「言語と呪術──折口信夫と井筒俊彦」で、次のように述べている。
いわく、井筒俊彦は、西脇順三郎がその言語学講義で、ソシュールとともに強いこだわりと愛着をもって取り上げたフレデリック・ポーランの『言語の二重機能』について、「言語の二重機能、つまり事物、事象を、コトバが概念化して、それによって存在世界を一つの普遍妥当的な思考の場[フィールド]に転成させる知性的機能と、もうひとつ、語の意味が心中に様々なイマージュを喚び起こす、心象喚起の感性的機能との鋭角的対立を説く」と概説している(「西脇先生と言語学と私」)。
この一節に、言語の「感性的機能」を意識的に働かせることによる現実の乗り越え、つまり「超現実が現実を破壊する瞬間にポエジイが生まれるという理論」にもとづく西脇順三郎の詩学の核心が示されている。それはまた、大学卒業論文『言語情調論』のなかで、「言語の直接性(言語のもつ超現実的かつ表現的な「感性的機能」)によって言語の間接性(現実的かつ交換的な「知性的機能」)が打ち破られた瞬間にポエジイが生まれ出ることを確信していた」折口信夫の詩的言語論につながる。さらに、西脇順三郎の弟子であり、折口信夫の講座に出てその『古代研究』のエッセンスを西脇に伝えた井筒俊彦自身の詩的言語論に。「西脇順三郎と折口信夫の学と表現が最も創造的に交差した地点に、井筒俊彦の学と表現の起源を位置づけることが可能なのである。」
安藤氏はさらに、吉本隆明の言語芸術論をこの系譜につらなるものとしてとりあげる。
(26号に続く) ★プロフィール★
中原紀生(なかはら・のりお)1950年代生まれ。兵庫県在住。千年も昔に書かれた和歌の意味が理解できるのはすごいことだ。でも、本当に「理解」できているのか。そこに「意味」などあるのか。そもそも言葉を使って何かを伝達することそのものが不思議な現象だと思う。
Web評論誌「コーラ」25号(2015.04.15)
<哥とクオリア>第33章 自己表出と指示表出の織物─和歌のメカニスムⅣ(中原紀生)
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2015 All Rights Reserved.
|
| 表紙(目次)へ |