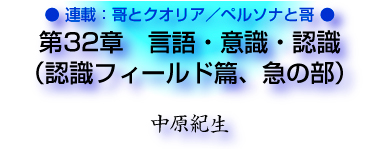|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「La Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
|
■「あはれ」の二つの視座
土左日記十二月二十七日の項に、「さをさせどそこひも知らぬわたつみの深き心を君に見るかな。という間に、楫取りもののあはれも知らで、おのれし酒をくらひつれば、早く去なんとて「潮みちぬ。風も吹きぬべし」と騒げば、船に乗りなむとす」とあります。
京へ向けて出港した一行に追いつき、惜別の歌をうたう「心ある」(情の厚い)人たちに応えて、前の国司つまり貫之が、李白の漢詩「贈汪淪」(汪淪に贈る)の一節、「桃花潭の水深きこと千尺、汪淪が我を送るの情に及ばず」を踏まえた歌を詠む。ところが、もののあはれの分からぬ船頭が、自分は存分に酒を飲み、出発を急いて騒ぐので、一行はしかたなく船に乗ろうとする。
この一文を引用して、井筒豊子は、「形而上的・美的・文人倫理的な価値的意味単位、としての〝もののあはれ〟の成立を示唆する一例である。」と書いています。こうした「正」の評価のもとでの「あはれ」の用例として、そのほかにも、「あはれてふことにしるしはなけれども いはではえこそあらぬものなれ」(後撰集)に見られる、前言語的で「表徴性(しるし)」をもなたい情動的充溢を美的価値ととらえたもの、「色よりも香こそあはれと思ほゆれ たが袖ふれしやどの梅ぞも」(古今集)や「春はただ花のひとへに咲くばかり もののあはれは秋ぞまされる」(拾遺集)のように、非形象性・隠在性や深層性・重層性の美的価値をみとめたものが挙げられています。
あるいは、「あはれてふことだになくは何をかは 恋の乱れのつかね緒にせむ」(古今集)に詠われた、現象現出的多(恋の乱れ)に対する根源的全一性への憧憬や、「紫のひともと故にむさしのの 草はみながらあはれとぞ見る」(古今集)の、可感的森羅万象・仮現的万象のうちに「形相的一者」=「たま」の潜在・憑依を見る視座にも、「あはれ」の美的価値に対する「正」の評価をみとめています。
(「紫の」の歌について、井筒豊子の解説を参酌しながら、生硬でくだくだしい意訳をつけてみる。真空妙有的・形相的一者の「阿の声」に通じる「紫の色」を根(潜在層)にもつ一本(ひともと)の紫草、その「たま」の被憑依体・依坐としての存在性格(あはれ)が、紫草と同一の位相、つまり「むさしの」という金剛界曼荼羅第八会において可感的に現象現成する仮現的万象としてのすべて(皆ながら)の草のうちにもみとめられることだ。)
このように肯定的に措定される「あはれ」の一声(阿の声)は、しかし、「たま」⇒「のる」主体⇒「まうす」主体、「真空妙有的・形相的一者」(第一会)⇒「覚」的一者(第六会)⇒「吽字」的主体(第七会)という、「位相的生成展開の俯瞰展望的基軸」を逆転させることによって、(つまり、空(非現象)⇒仮(現象)の「創造的生成展開」を展望する視座から、仮⇒空の、派生的仮現的現象位相からその根源となる十全な形相的位相を対置させて展望する視座へと置換するとき)、一転して、「嗟嘆と悔恨に満ちた‘負’の陰影をおびた美的価値単位」として把握されることになります。
以上のような分析を経て、井筒豊子は、「認識フィールド」論文・急の部の議論へとつないでいきます。いわく、美的価値単位・意味単位としての「あはれ」は、一種、「象徴記号(メタ記号)」的に成立している[*]。これに対して、和歌の創造主体の「自照的意識宇宙・自照的自然空間」(すなわち、自然曼荼羅)との構造的関連上に位置づけられる「鍵的意味単位」である「ながめ」と「みわたし」は、より記述的で感覚・知覚的具体性をもつ「意味直示的記号」として成立している。
[*]大西克礼は「あはれについて」(『幽玄とあはれ』)で、「あはれ」の概念に包括される意味内容の発展段階を次の五つに区分している。井筒豊子がいう「象徴記号(メタ記号)」としての「あはれ」は、大西克礼がいう第四の、「形而上学」的な意味合いをもった「あはれ」に相当するのではないかと思う。
1)特殊的心理的意味
「哀」「憐」等の特殊の性質をもった感情を直接に表示する。
2)一般的心理的意味
特殊の限定された感情的内容を超越して、汎く一般の感動的体験そのものを指す(土左日記の楫取りが知らない「もののあはれ」)。
3)一般的美的意味
感動一般の形式(一般的心理的意味の「あはれ」)の中に、物の心を知る、事の心を知ると云うような直観や静観の知的契機が加わり、そこから発生する美意識ないし美的体験一般の意味。
4)特殊的美的意味
再び元の「哀愁」「憐愍」といった特定の感情体験のモティーフと結合し、同時に、特定現象の範囲を超えて、人生や世界の「存在」一般の意味にまで拡大された、「世界苦」にも似た美的体験を指す。人生や世界に対する、一種の形而上学的「心構え」が根拠。
「例えば吾々は秋の夕暮の空を眺めて、そこに端的直接に「あはれ」と云う言葉によって表された、一つの「本質」を諦観する。私はこの特殊な一つの「本質」を明瞭ならしめんがために、広い意味内容をもつところの「あはれ」の概念について、その第四の意味を特に区別したのである。」(『幽玄・あはれ・さび 大西克礼美学コレクション1』)
5)美的範疇としての意味の完成
優美、艶美、婉美等の種々の美的契機を摂取し、綜合し、統一することによって、もはや概念をもって記述すべからざる特殊の渾然たる美的内包が成立する。
■急の部:「ながめ」の視野と「みだれ」の視野
自然曼荼羅の現成にかかわる第一の意味単位は、「ながめ」です。
「ながめ」は、①憧憬的志向性を伴う遠望(長目・長雨)ないし遠隔対象の凝視・望見であり、②「たま」的被憑依体相互間に成立する力動的親和関係・憧憬的相互関係(例:「たまあひ」や「あくがれいづる(遊離)魂」などの語が示唆する不可視・非現象の深層空間)の内視である。井筒豊子はそのように述べ、「おきもせず寝もせで夜を明かしては 春のものとてながめくらしつ」ほかの古典和歌の用例をいくつか挙げたうえで、「ながめ」を「〝たま〟的な憧憬的志向性を伴う遠望凝視」と定義します。
このような、「たま」的な根源的全一性や、その被憑依体である「のる」主体の前言語的情動的飽和充溢性を、つまり「正」の評価のもとでの「あはれ」を痕跡としてとどめる視覚動詞「ながめ」の視野は、内観的・非可感的な意識フィールドと外観的・可感的な認識フィールドの双方に、「自照的空間」として成立します。「〝ながめ〟の視野に生起する現象現出的多、意味単位・存在単位、の遠心的拡散・散乱[みだれ]は流動変転してとどまることがない。」
(ここに出てくる「収斂」と「拡散」の対語は、ベルクソンが『物質と記憶』で駆使した「収縮」と「弛緩」の対概念と、ちょうど真逆の方向で対応しているような気がするのですが、それは、ここでは措くとして)、このように、「ながめ」(と「みだれ」)の視野は、「たま」系統の構造と密接な連関性をもって成立します。そして、「のる」主体(第一フェイズの「こころ」)の、意識フィールド・認識フィールドにまたがってひろがる「ながめ」の視野は、万象のうちに「たま」の潜在を見る「あはれ」の視座に通じ、また、「まうす」主体(第二フェイズの「こころ」)の「みだれ」の視野は、(「ながめ」の視野と同じフィールドにおいて)、それ自体としての万象を「はかなし」と見る視座に通じています。「あはれ」と「はかなし」、そして「ながめ」の視野と「みだれ」の視野は、いわば同一の位相において、(あたかも、春の長雨のなかで移りゆく「花の色」のように、あるいは、いたづらに世にふる「わが身」のように)、リアルなものとイマジナリーなものとが反転する、そのような関係性のもとにあるといっていいでしょう。
いま私の脳裏をかすめているのは、(「かきやりしその黒髪のすぢごとにうち臥すほどは面影ぞたつ」(藤原定家)と、その本歌である「黒髪のみだれもしらずうちふせばまづかきやりし人ぞ恋しき 」(和泉式部)、そして「くろ髪の千すぢの髪のみだれ髪かつおもひみだれおもひみだるる」(与謝野晶子)の三つの歌の響きあいとともに)、「おきもせで」の歌に見られる「眺め」について、「春の長雨期の男女間のもの忌につながる淡い性欲的気分でのもの思い」であるとした折口信夫の議論[*]と、その引用をもってはじまる『意識と本質』の考察です。
井筒俊彦はそこで、「春は春、花は花、恋は恋」というふうに、あらゆる事物事象・人事百般がくまなく「普遍本質」的に明確に規定された古今和歌の世界を「マンダラ的存在風景」と呼び、これに飽きたらぬ詩人たちが、本質消去の手段として「ながめ暮す心」を特殊な詩的意識のあり方にまで昇華させた、と書いていました。このことについては、(井筒俊彦がいう「マンダラ的存在風景」と井筒豊子の「自然曼荼羅」との関係いかん、といった論点とあわせて)、「みわたし」をめぐる井筒豊子の議論を一瞥した後で、あらためてたち帰ることにします。
[*]「伊勢物語」の講義ノートに残された折口信夫の発言を引いておく。
《「ながめ」とは、男女が性的にぼんやりとしているときの気持だ。たいていは男女が逢って後に、また久しく逢わずにいて、憂欝な気持にいること。その前は、隔離された性生活にいる人の気持だ。性欲が満たされずに、ぼんやりしている気持だ。それがはっきり出てくる用例は古事記にある。
景行天皇が、大根ノ王の娘、兄比売、弟比売を、御子の大碓ノ命に命じてお呼び寄せになった。命はその娘と自分が結婚して、天皇には別の女を、偽って差し出した。天皇はそれを違う女だということをお悟りになって、いつまでもあわなかった。それを「長眼を経しめたまふ」、「ながめ」を経験おさせになった、といっている。「め」は、万葉集の用例でも、男女が逢うことだ。それを、「長」がついているから長眼を、長く逢わずにいることと感じてきた。そうして憂欝に暮していることをそういうことになった。それが更に転じて、逢うて後のぼんやりしたことをいうようになってきた。更にこの一段前がある。
日本の農村には、霖雨期(五月、十月)には、厳重な物忌みがあった。長雨の物忌み、「ながめいみ」である。この時期には、田の神が出て来ているので、農村の男女はかたらいをしない。五月の田植えの時期に男女があわない生活は近代まであった。この「長雨忌み」にはいっていることを、「ながむ」「ながめ」といった。更にもう一段前があるが省略する。》(『折口信夫全集ノート編第十三巻』)
■急の部:「みわたし」の視野の諸相
自然曼荼羅の現成にかかわる第二の意味単位は、「みわたし」でした。
万葉集に多出する「みわたし」は、本来的には「外観・景観の展望」を意味する視覚動詞ですが、古今・新古今の時代になると、内と外との「相即的同融」を示唆する語、「自照的視座と視野にかかわる鍵的意味単位」として登場し、その視野は、「万有の形相的位相磁場と万有の現象現成的位相磁場とが、同時俯瞰的に、いわば〝横竪[おうしゅ]・経緯[たてぬき]〟に遠望・展望されるとき」に生起する、と井筒豊子は指摘します。そして、形相界と現象界にあいわたる「みわたし」の視野の拡がり(深まり)の諸相を、実例を挙げながら、次のように叙述しています。(ただし、以下の「第一相」「第二相」「第三相」のラベルは、井筒豊子のオリジナルな議論に出てくるものではない。)
【第一相】見わたせば柳桜をこきまぜて 都ぞ春の錦なりける(古今集)
《現象現出の‘多’の(肯定的把握としての)可感的全開顕、の絢爛たる展望である。純然たる感覚・知覚対象として(‘有’的に)把握されるところの自然界の事物・事象の外観・景観は、そのまま、和歌的創造主体みずからの内観的・自照的な視野ともなる。つまり、可感的自然界の万有の合集はそのまま曼荼羅の一位相として、‘見渡される’。》
この、和歌的創造主体の主観面においてとらえらえた「みわたし」の視野の第一相(内と外の相即的同融)は、「無分節全一の非現象」⇒「現象的多」という存在論的構造のアレゴリーとしてこれを把握するなら、客観的なものとしても成立し得る。「この自然曼荼羅の客観的〝みわたし〟はさらに[第二相、第三相へと]展開して、見るものと見られるものとを、主と客とをともに包摂するところの、より自照的・内観的な、自然空間の〝みわたし〟へと転換する」。
【第二相】見わたせば山本かすむ水無瀬川 夕べは秋となに思ひけん(新古今集)
《可感的現象位相の現成に先行するところの不可視・不可触の諸位相はその根源位相である万有の形相的全現前・全開顕の位相とともに、この〝みわたし〟の視野に、幽玄深秘の奥ゆきを附加し、可感的現象界の千紫万紅の地平もまた、霞の半透明性を透過して見渡される。》
【第三相】見わたせば花も紅葉もなかりけり 浦の苫屋の秋の夕暮(新古今集)
《可感的現象有に対する不可視・不可触の形相有、顕在的有に対する隠在的有、という、いわば知覚・感覚的な有[ポジ]と無[ネガ]との照応・対置によるその認識論的構造基軸を──自性有に対する仮有、自体性に対する影現性、という──存在論的構造基軸に置換することによって、万有〝みわたし〟のこの自照的視野は、仮有的・影現的な、無的事態の自照的視野へと転換する。》
第一の相から第三の相への「みわたし」の視野の転換にともない、その主体は、和歌的創造主体(世の中にある歌人としての)から主客合一、梵我一如の、より深層(「浦の苫屋」の「うら」=「たま」が住まいする)の世界の主体へと推移していきます。「存在論と意識論とを表裏一体とする」金剛界曼荼羅の構造モデルに即していえば、第八会の可感的・対他的・身心的主体から第七会の言語意味分節的・再帰的意識主体へ、そして「真空妙有的・形相的一者」を志向しつつ第六会の全一・無分節的充溢の「覚」的主体へ、と言うことができるでしょうか。
先に「ながめ」の視野について述べたこととの対比でいえば、「みわたし」の視野は、そしてその主体は、いわばアクチュアルな次元とヴァーチュアルな次元という、異なる存在領域を俯瞰しつつ転換していく、そんなふうに規定することもできます。
(ここで注意しておきたいのは、金剛界曼荼羅には、第一会から第九会に向かう道と、その逆に第九会から第一会に向かう道があったということ。
第九会の解説のなかで、井筒豊子は、第八会に成就した心身的存在単位群は、第九会において「吾なし」の純粋経験的志向機能を発現し、それらはそのまま第二会へと連接する、そして「この連接によって、一→多(往相)・多→一(還相)、という現象的生成展開は、円環的連接構造、となる」のだが、「この現象現成的生成展開構造における往相・還相は、当然、行者の実践道においては逆方向の遡行構造となる」と書いていた。
そうだとすると、いま述べた、第一相から第三相への「みわたし」の視野の移行は、「行者の実践道」における「遡行構造」に該当し、これと逆方向の第三相から第一相への視野の移行、そしてそれに伴う深層(潜在層)から表層(可感的自然界)への主体の推移を想定することができる。)
■急の部:「ながめ」と「みわたし」の交点、自然曼荼羅の現成
「ながめ」の視野と「みわたし」の視野との交点、その「相互照応の重層的視野」のうちに、自然曼荼羅の景観が生起します。いよいよ議論は、最終局面をむかえました。
「ながめ」と「みわたし」の交点に成立する「力動的機能空間」たる可感的自然界、すなわち自然曼荼羅の景観の特質は、第一に、そこでは、自然の事物事象が純然たる感覚・知覚の対象でありながら、もはや単なる認識客体ではありえず、見るものと見られるもの、認識の主体と客体が「同一位相に現象する同位要素相互間の、交感・呼応の関係」にあるということ、そして第二に、そのただなかに、意識フィールドと認識フィールドとの「内外照応・呼応的な相互同定」による「〝いま・ここ〟の、実存的・覚的な時空磁場」が成立するということです。
(かなり強引な議論になるが、そして井筒豊子の語彙の使い方に反するところがあるが、私は、自然曼荼羅の第一の特質は「内と外」の交感・呼応の関係に、第二の特質は「一と多」の照応・呼応の関係にそれぞれ関連づけられるのではないかと考えている。
見るものと見られるもの、認識主体と認識対象の関係を「内と外」の関係と見るのは、たとえば見る主体の「心の中」を「内」ととらえ、見られる客体を「外」に在るものと考えるならば、主体と客体とが、それらを共に包摂する同じ次元、同一の位相において同位要素相互間の交感・呼応の関係にあることと、「内」と「外」とが地続きになることは同義であると言えるのではないかと思うからだ。
また、そのような「内」(=意識フィールド)と「外」(=認識フィールド)とが内外照応・呼応的な相互同定の関係にあるとき、たとえばほかならぬ「この今」と無数の「今」との関係において、(あるいは実存的経験たる一回限りの「この今」と概念としての「今」の複数の外延との関係、もしくは個々の経験を超越する「永遠の今」と実存的経験としての一つ一つの「この今」との関係、さらには(『哲おじさんと学くん』での永井均氏の新しい用語を借用して)「特在」する「今」と「併在」する「今」との関係において)、多の中の一、その一が多を含むといったかたちで、可感的自然界のただなかに「いま・ここ」の時空が成立する、などといった理路を通じて「一と多」に関連づけることができるのではないか。
蛇足を加えると、私は、この「内と外」の関係をつきつめれば「全体と部分」の関係に行きつき、また「一と多」の関係の究極のかたちは「有限と無限」の関係になるのではないかと考えているが、これにはさしあたって使い道がない。)
「いま・ここ」の時空は、私の語感でいえば、世界の「アクチュアル」かつ「リアル」な領域に相当します。「イマジナリー」なものと「リアル」なものとの同一位相内での反転という、いわば水平的な関係性のもとにある「ながめ」の視線、そして、「ヴァーチュアル」なものと「アクチュアル」なものとの、次元の異なる位相間にあいわたる転換という、いわば垂直的な関係性のもとにある「みわたし」の視線、この二つの視線が交差することによって、その交点のうちに立ちあがる「いま・ここ」の実存的・覚的な時空磁場。
井筒俊彦は、「春は春、花は花、恋は恋」の古今的な「マンダラ的存在風景」における普遍的本質の存在規定性を消去する手段として、歌人たちが、王朝文化の雅びの生活感情の基底であった「ながめ暮す心」を一つの特殊な詩的意識のあり方にまで昇華させ、新古今集の時代になると、その「ながめ」の意識は、事物の本質的規定性を朦朧化し、そこに現成する茫漠たる情趣空間のなかに存在の深みを感得しようとする意識主体的態度となっていった、と論じていました。
私は、ここで言われる二つの「ながめ」を、(「形相的還元」あるいは「本質直観」、「超越論的還元」あるいは「エポケー(判断停止)」という二つの現象学的還元になぞらえながら)、古今的な「眺め1」と新古今的な「眺め2」に区分し、「眺め1」を「リアル(実)⇒イマジナリー(虚)」もしくは「事物のありありとした描写⇒渾沌未形の状態にある可能性の領野」と、また新古今的な「眺め2」を「アクチュアル(現)⇒ヴァーチュアル(空)」もしくは「生き生きとした実在⇒世界を成立させる実質(存在深層)」と、それぞれ規定しました(第25章)。
「ながめ」と「みわたし」の交点から「自然曼荼羅」が生起し、その景観のただなかに、「いま・ここ」の実存的・覚的な時空磁場が成立するという井筒豊子の議論は、「眺め1」と「眺め2」の意識主体的態度が「マンダラ的存在風景」の規定性を消去・朦朧化するという井筒俊彦の議論と、ちょうど真逆の方向で対応していると見ることもできます。いま、このことを簡略に定式化すると次のようになるでしょうか。
◎「遡行」のメカニスム(井筒俊彦)
「マンダラ的存在風景」の消去・曖昧化=「実⇒虚」(眺め1)+「現⇒空」(眺め2)
◎「塑型」のメカニスム(井筒豊子)
「虚⇒実」(ながめ)+「空⇒現」(みわたし)=「自然曼荼羅」の生起
(「ながめ」の視野の定式は、本来は「虚⇔実」の相互反転を基本とするが、「眺め1」との違いを際立たせるために、ここでは「虚⇒実」の側面を強調した。また「みわたし」の視野の転換は、これも「眺め2」との違いを強調するため、第一相から第三相への「遡行構造」ではなく第三相から第一相への「現象現成的生成展開構造」にもとづくものとした。)
先に留保しておいた論点、井筒俊彦の「マンダラ的存在風景」と井筒豊子の「自然曼荼羅」との関係については、それらは同じものだとも言えるし、似て非なるものだとも言える、といったはなはだ中途半端な回答しか用意できません。「マンダラ的存在風景」であれ「自然曼荼羅」であれ、それが「力動的機能空間」と呼びうる性格のものであるかどうかで、まったくそのあり様が異なったものになるからです。「遡行」のメカニスムは、生き生きと実在ずる普遍的本質が抽象的概念に堕したときに起動するものであるはずだし、「塑型」のメカニスムが起動するのは、まさに「遡行」のメカニスムが行きつく果てに、再び見出された無分節・非現象の「存在の深み」が感得されときにほかなりません。
遡行と塑型のプロセスは、実はつねに同時に進行している。むしろ、そのように言うべきかもしれません。それこそが「和歌のメカニスム」である、と。そしてそのとき、つまり和歌のメカニスムが本然の姿で稼働しているとき、見るものと見られるものとが交感し、意識フィールドと認識フィールドが照応するとき、和歌的創造主体の「こころ」のうちにありありと、かつ生き生きと自然曼荼羅が立ちあがる。
その景観の実相を詠んだものとして、井筒豊子は、次の三つの歌を挙げています。(同じ位相にあって反転する「花と雪」。異なる存在次元にあって相互に映現しあう「空と海」。これらの景物群が醸しだす絢爛たる和歌的世界の究竟を表象する「月と心」、すなわち空を超越する天涯の「月」と言葉の海の底なる「心」。現実空間における存在分節単位から言語空間における言語分節単位へ、そして心的空間における意味分節単位へと変容していく「山の端」。ながめるこころ=「われ」がながめられるこころ=「月」とともに入っていく「月=心」の究竟。その「さかひ」をなす「山の端」。)
秋の夜の月は心に入りにけり 山の端とのみなに思ひけん(右衛門督家歌合せより)
山の端は名のみなりけり見る人の 心にぞ入る冬の夜の月(後拾遺集)
山の端にかくるる月をながむれば 我も心の西に入るかな(山家集)
(ここで私が想起しているのは、「象徴的感情移入」という美学用語であり、「紫文要領」中の「物のあはれをしるといふは…その時の心にしたがふて、同じ物も感じやうのかはる也。かなしき時は見るもの聞くものがみなかなしき也」云々であり、『善の研究』の、たとえば「我々が物を知るということは、自己が物と一致するというにすぎない。花を見た時は即ち自己が花となっているのである。」や「物が我を動かしたのでもよし、我が物を動かしたのでもよい。雪舟が自然を描いたものでもよし、自然が雪舟を通して自己を描いたものでもよい。元来物と我と区別のあるのではない、客観世界は自己の反影といい得るように自己は客観世界の反影である。我が見る世界を離れて我はない…。」といった一節である。
あるいは、「私が悲しいとき(私には)世界が悲しいように映る。」(永井均『西田幾多郎──〈絶対無〉とは何か』)や「簡単に云えば、世界は感情的なのであり、天地有情なのである。其の天地に地続きの我々人間も又、其の微小な前景として、其の有情に参加する。それが我々が「心の中」にしまい込まれていると思いこんでいる感情に他ならない。此のことを鋭敏に理解したのが、山水画、文人画を含む日本画家達であり、又西洋ではフランスの印象派の人々であったと思う。彼等は其の風景の描写にあたって何よりも其の風景の感情を表現するのに努力したからである。又音楽も、三次元空間に鳴り響く世界そのものが、音楽的感動なのであって、我々は其の感動のお相伴を受けているだけなのではあるまいか。」(大森荘蔵「自分と出会う──意識こそ人と世界を隔てる元凶」、『大森荘蔵セレクション』)といった文章。
それらはみな、次のように叙述されるリルケの「世界内面空間」に通じているのではあるまいか。「それは〈見る〉を超えることによって〈対象[もの]〉としての世界でない世界(〈開かれた世界・世界内面空間〉)の現前を可能にする。自己はここでは全存在と一体化し、全存在という形で(もはや自己意識はなく)純粋な活動体となる。つまり自己の内面は純粋に透明化することによって、外面世界と完全に一体化する。」(辻邦生『薔薇の沈黙──リルケ論の試み』)
以上にとりあげた言説は、いずれも、(次節での語彙を先走って用いるならば)、「モノ」と「ココロ」の関係をめぐるものだった。それでは、自然曼荼羅における「モノ」と「コトバ」の関係、「ココロ」と「コトバ」の関係はどうなっているのか。前段の問いに対しては、パースの壮大な記号論と、前田英樹氏がこれと関連づけた空海の言語哲学が圧倒的なスケールで答えているのだろう。後段の問いについては、それこそがまさに古今集仮名序を起点とするやまとうたの歌論の最大イッシューなのであって、これに全力をあげて答えたのが井筒豊子の和歌論三部作だったと言うことができる。)
■那智滝図─自然曼荼羅の景観
さて、ここまでくると、以前、「認識フィールド」論文にとりくむに先だって述べておいた論点が、もはや解き明かされるべき問題でもなんでもない境位に達したのではないかと思います。その論点とは、次のようなものでした(第30章)。
「言語フィールド」論文では、和歌的言語表現の特色として、極端な短詩型、装飾語の多用、自然の事物事象の多出」(和歌における主題選択が、外的自然界の事物事象の美観に偏していること)の三点が挙げられていた。そして、それらは、シンタックスに対するアソシエイションの機能的優位という、和歌固有の言語フィールド展開の特性に関連づけて分析されているが、他の二つの特色と比較して、「自然の事物事象の多出」に関する説明にはいまひとつ得心がいかないところが残った。
「認識フィールド」論文を最後まで読み進めてきて、私が、ほぼ確信をもって言えるのは、自然曼荼羅こそ、「物・心・詞」という和歌の三つの要素を束ねた窮極の「アソシエイション」なのであって、その自然曼荼羅の景観のうちに現象する自然の事物事象とは、端的に「コトバ」(自然記号)であり、かつ「ココロ」(いま・ここに成立する実存的・覚的な「思ひ」)でもあるところの「モノ」(クオリア的存在)なのだということです。
少なくとも、貫之の仮名序に発し、俊成的転回[*]を経て定家の「有心」の歌論にきわまった「やまとうたの思想」においては、「ひとのこころ」と「ことのは」と「よろづ」は、「自然曼荼羅」というアソシエイションのうちに交感・照応・呼応の関係をきりむすび、したがって、和歌を詠むとは自然の事物事象を詠むことにほかならない、といった事態がなりたっている。そして、それは同時に、「他者的・外来的な思考・思想の同化融合[アシミレイション]と同時並行的に、日本的自己同一性の成立を創造的に志向する」ところの「日本的固有性の思想的構造化」の方法論であり、かつ思想的営為そのものにほかならなかった。
これが、井筒豊子の和歌論三部作の最終到達点だと、私は考えています。
最後に、「認識フィールド」論文の掉尾を飾る文章を引いておきます。
堂々たる完結の辞をしめくくる「那智滝図」は、やまとうたの歌論、やまとことばの思想をめぐって、いつか解き明かされるべき「幽玄深秘の奥ゆき」を指し示す記号として、深く濃い印象を残します。
というのも、(世界が天地有情であることを鋭敏に理解したのが、山水画、文人画を含む日本画家達であった、と大森荘蔵書いていたことにも触発されて)、井筒豊子の和歌論は、言葉が見る夢としての映画論のごときものに接続されていくのではないか、というかねてからの関心が昂じたからであり、このことを主題的に論じようとするならば、三部作の最後に示唆された「自然曼荼羅の表象的一典型」の探究をさけてとおることは許されないからです。
ただ、現時点ではそのための準備ができていないので、(アンドレ・マルローが、「那智滝図」を見た感動を「滝はここではまさしく神だ」「自然の精神化としての神なのだ」「この被瀑図は、至高の記号であり、カリグラフィーである」等々の言葉で表現したこと(竹本忠雄著『マルローとの対話──日本美の発見』)や、山本健吉著『いのちとかたち──日本美の源流を探る』がこのことに触れ、「マルロオは「内的実相」あるいは「気」「気韻」を現すものを、シーニュの名で呼んでいる。徴証・指標であるが、言うまでもなく、「いのち」の徴証であろう。」(序章「那智滝私考察」)、「それはセザンヌ流の、対象化された滝ではない、凝視することは、同時に讃歎し、信じ、跪拝することなのである。」(終章「造化と自然と」)、等々の言葉を残していることなど、魅力的な素材はいくつか手元にありますが)、これ以上の考察は別の機会に委ねることにします。
[*]「俊成的転回」とは、古来風躰抄に、「かの古今集の序にいへるがごとく、人のこころを種として、よろづの言の葉となりにければ、春の花をたづね、秋の紅葉を見ても、歌といふものなからましかば、色をも香をも知る人もなく、何をかはもとの心ともすべき。」とあるのをふまえて、「思ひ⇒詞」の貫之歌論を、俊成が「詞⇒思ひ」の遡行的な視座に転回したことを指している。
この解釈は、『花鳥の使──歌の道の詩学Ⅰ』での尼ヶ崎彬氏の説に依っている。「花紅葉のもつ色香に心が感動して歌が生まれる、というのが貫之の説であるとすれば、俊成のこの言い方は、逆に、あらかじめ歌というものがなければ、人は花紅葉を見ても、その色香がわからない、というものである。貫之にとって、花の色香は、あらかじめ花に備っているものだが、俊成に言わせれば、詩人が花の歌を詠んではじめて、その色香は人々の前に立ち現れるのである。つまり、色香とは、詩人の心を種として生じた言の葉に輝き匂うものであって、自然の花紅葉にあるのではない。」
あるいは、大岡信氏の『詩の日本語』に紹介されていた窪田空穂(「藤原俊成の歌論──主として艶と幽玄と本歌取につきて」)の説の方が、より端的な言い方かもしれない。「彼は、自然の美は、歌を離れては解せられないものだといふのである。或は歌を離れては存在しないものだともいふのである。(略)古今集の、「人の心を種として、よろづの言の葉とぞなれりける」といふのは、歌の多趣多様であることをいつたに過ぎない。彼は、その「種」を本とし、そして一切の自然は心の生み出すところのものだとしたのである。」(中公文庫『詩の日本語』からの孫引き)
ところが、山本一著『藤原俊成──思索する歌びと』によると、「何をかはもとの心ともすべき」という個所は、「色をも香をも知る人もなく」と並列的な関係で捉えられるのであって、「どちらも、「人の心」を通いあわせる歌の働きの重要さを、ことばを変えて説いているのであり、「もとの心」という語が特別に重い意味を担っていると考える必要はなくなる」。
山本氏はそのように述べ、かの俊成の一文を、「歌は心情に形を与えるものである。そのような歌がもしなかったならば、春秋の景物にことよせて、花の色香にも比すべき微妙繊細な心情を理解し合うこともできないし、さまざまな場合に、お互いの変わらぬ心を確かめあうこともできはしない。」と現代語訳したうえで、そこにこめられた思想について、「「人の心」の表れとしての歌という「仮名序」に含まれていた考え方の、自然な発展として理解されるのである」と書いている。
和歌論三部作での井筒豊子の見方は、「もとの心」を古今集真名序にいう「心地」ととらえ、そこに仏教系・漢語系の思考を導入するものだった。その意味では、仮名序・真名序をこきまぜた古今序歌論の「自然な発展」として俊成歌論を理解しようとするものといえるかもしれない。
★プロフィール★
中原紀生(なかはら・のりお)1950年代生まれ。兵庫県在住。千年も昔に書かれた和歌の意味が理解できるのはすごいことだ。でも、本当に「理解」できているのか。そこに「意味」などあるのか。そもそも言葉を使って何かを伝達することそのものが不思議な現象だと思う。
Web評論誌「コーラ」24号(2014.12.15)
<哥とクオリア>第31章:言語・意識・認識(認識フィールド篇、急の部)(中原紀生)
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2014 All Rights Reserved.
|
| 表紙(目次)へ |