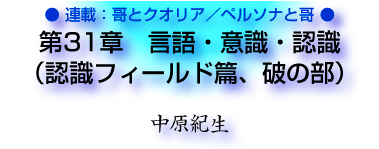|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「La Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
|
■二つのこころ─古今序を原起点とするやまとうたの思想
前章の末尾で、古今集仮名序および真名序をとりあげた際、「こころ⇒ことのは」と「心地⇒詞林」の重層構造に関連して、「こころ」の二相化、という表現をもちいました。これは、もちろん私の創作ではなく、井筒豊子のオリジナルな議論にもとづくものです。
仮名序において、ひとの「こころ」(意味単位群もしくは意識フィールド)を「たね」(根源・根基)として「ことのは」(言語単位群もしくは言語フィールド)となったものがやまとうたであり、そして「こころ」と「ことのは」の相関者として現象するのが森羅万象(としての「よろづ」、すなわち存在単位群もしくは認識フィールド)であるとされ、また真名序において、和歌とはその根を「心地」(空すなわち非現象)に託け、その華を「詞林」(仮すなわち現象)に発くものであるとされたこと。この、古今序の二つのテクストに登場する二つの「こころ」、真名序由来の「心地」と仮名序由来の「こころ」の関係をめぐって、井筒豊子は、それらは、すなわち「心地[こころ]的全一主体」と「言語分節的意識主体」とは、「同一の心的主体性の、先行・後行的二位相[フェイズ]」として現象的に展開するものであり、同時にまた、「二種の独立固有の主体的事態」でもある、と規定しています。
この(シンタックスに対するアソシエイションの圧倒的優位のもとで綴られた)叙述を透かして、おぼろげに浮かびあがってくるのは、仮名序・真名序をこきまぜた古今序歌論が含意する(と、井筒豊子によって解釈された)和漢混合の重層的構造、いわば、やまとうたの思想がそこにおいて立ち現われる舞台(和歌のメカニスムである「遡行(的志向性)」と「(実体化的)塑型」のはたらきがそこにおいて稼働する場所)の構図にほかなりません。以下に、その概略を示します。
【零次層】
潜在層(非現象・無分節層)=隠在・潜在・非現象・無限定・無分節の収斂的全一主体としての「心地[こころ]」の領域
【一次層】
現象・無分節層=非現象・無分節の「心地」の直接無媒介的・即自的な発現、つまり無分節の非言語的・力動的志向性、非再帰的・不可逆的志向性としての「情動[こころ]」=第一位相の「こころ」の領域
【二次層】
現象・分節層=拡散的・意味分節的な心的事態としての言語意識的主体性、そして対自的・再帰的な自照主体でもある「意(識)[こころ]」=第二位相の「こころ」の領域
【二次層(内界)】
非可感的分節層=「内的言語」としての「思ひ」と表象単位としての「内的森羅万象」が現象する領域
【三次層(外界)】
可感的分節層=可感的な声・字としての「外的言語」(詞)と可感的存在単位としての「外的森羅万象」が現象する領域(=可感的存在時空)
念のために註記しておくと、この構図のうちには、三対の異なる領域の組み合わせが多層的に重なりあっています。まず、零次層と一次層とのあいだにしつらえられた分断線で、真名序由来の「非現象/現象」(空=心地/仮=詞林)の対領域が、次いで、一次層と二次層とのあいだの分断線を介して仮名序由来の「無分節/分節」(一つの心/萬の詞)の対領域が、最後に、二次層と三次層とのあいだの分断線によって「非可感的内界/可感的外界」の対領域がそれぞれ区画されます。
井筒豊子の和歌論にいう三つの「フィールド」との関係についてふれておくと、「意識フィールド」は、(零次層に根ざしつつ)一次層と二次層、つまり第一位相の「こころ」と第二位相の「こころ」の領域にまたがり、かつ二次層(内界)において他の二つのフィールドと重なり合いながら拡がっていき、(強いていえば、一次層=無意識、二次層=深層意識、二次層(内界)=表層意識、となるでしょうか)、「言語フィールド」と「認識フィールド」は、二次層(内界)と三次層にまたがって、それぞれ「内的言語+外的言語」、「内的森羅万象+外的森羅万象」のかたちで拡がっている、と規定することができるでしょう。
付言すると、このような、仮名序歌論に根ざした「有心」的発想を離れて、虚心にこの構図を俯瞰するならば、「言語フィールド」も「認識フィールド」も、実は、ともに二次層(深層意識)、そして一次層(無意識)にまでおよんでいるのであって、窮極的には零次層に達する(発する)、ということもできるでしょう。(存在はコトバであり、ココロでもある。)
なお付言すると、第一位相の「こころ」と第二位相の「こころ」とが、「同一の心的主体性の、先行・後行的二位相」として現象的に展開するというのは、まさにそうした「有心」的発想を言い表したものにほかならず、また、それらが「二種の独立固有の主体的事態」でもあるというのは、内的言語としての「思ひ」には非言語的・無分節的な「情[こころ]」が平行し、外的言語としての「詞」には無分節・不可視の「余情」が纏綿する、そして、定家の歌論にあって、後者の系列(情⇒余情)が前者の系列(思ひ⇒詞)よりも上位に置かれる、という「意識フィールド」論文での「有心体」をめぐる議論をふまえたものにほかなりません。
さて、以上で、古今序歌論を原起点とする和歌の思想を考察するための基本的な構図[*]が描かれました。「こころ→ことば、無分節・収斂的一→分節・拡散的多、無分節・飽和充実(の感嘆詞的)主体→再帰的言語意識主体、という現象展開の二位相は、和歌・歌論的コンテクストにおいて、いわば二系列の形而上的思想体系をその構造的背景として、重層構造的に展開する。」
ここでいわれる、和語系と漢語系の二系列の「形而上的思想体系」とは、ひとつは「たま」的主体性の位相展開構造であり、他のひとつは金剛界曼荼羅体系の存在論的・意識論的な位相展開構造のことです。やや強引に先の「構図」にあてはめると、両者はいずれも零次層から三次層にまたがって展開するのですが、零次層から二次層へと進み、そのうちの「内界」と表記したフィールドに達したところで分岐し、和語系の「たま」構造は「言語フィールド」の方へ、漢語系の曼荼羅構造は「認識フィールド」の方へそれぞれ展開していく、と大雑把にとらえておいていいのではないかと思います。
ここから、「認識フィールド」論文・破の部の議論が始まります。
[*]この構図を、井筒俊彦が『意識と本質』で示した「意識の構造モデル」のうちに(やや強引に)落とし込んで図示すると、次のようなものになる。
(詞・余情) (外的万象)
┌───────────────────┐
│ │
│ A │
│ │
├─(思ひ・情)─────(内的万象)─┤
│ │
│ │
│ │
│ M │
│ │
│ │
│ │
│ (意識=第二位相のこころ) │
│ │
├───────────────────┤
│ │
│ B │
│ │
└───(情動=第一位相のこころ)───┘
\ /
\ /
\ /
\ C /
\ /
\ /
\ /
\ /
\ /
〇
図中の記号は井筒俊彦のモデルにもとづくもので、Aは表層意識を、Mは中間的意識空間、想像的(元型的)イマージュの場所を、Bは「言語アラヤ識」、集団的無意識、元型成立の場所を、Cは無意識の領域を、そして〇は「意識のゼロ・ポイント」(『意識の形而上学』では「意識と存在のゼロ・ポイント」)を表わす。
(「意識のゼロ・ポイント」は、おそらく「意識フィールド」論文で井筒豊子が「超越的非現象(心地・心原)の自己顕現として現象する心機能を、ひとつの実存的意識事態として成立させる媒体となる」ものと規定した「境(さかひ)」に相当する。なお、井筒豊子の構図における「心地[こころ]」は、ここでは図示できない。なぜなら、それは潜在層に住まいするもの、すなわち非現象のものだから、現象界に位置づけることはできない。)
かの「哥の伝導体」の理論にひきよせて考えることもできる。たとえば、非現象の潜在層から可感的存在時空に向かって(非現象⇒現象、無分節⇒分節、内界⇒外界の三つの屈折、存在次元の転換を経て)垂直方向に「ヴァーチュアル/アクチュアル」の軸を、またA領域・M領域を区画する水平線と外界・内界(A領域)を区画する水平線にまたがって横断する「イマジナリー/リアル」の軸を引き、これらの(本来交わるはずのない)二軸の交差を通じて四つの世界を導出することによって。
(ここでとりあげることはできなかったが、井筒俊彦の「意識の構造モデル」と、ベルクソンが『物質と記憶』の第三章で示した「記憶の逆円錐」の図との逆倒的な関係が気になる。)
■破の部:和語系、ことだま的言語構造
第一の形而上的思想体系は、「たま」的主体性・「たま」的存在の位相転換にかかわるものです。以下、井筒豊子の議論を、三つの項目にわけて概観します。
1.憑依による「たま」的主体の位相転換
「たま」は、関連語の「ち すたま かみ もの かげ うら こころ」等々と同様に、「それ自体としては、空間的延長を持つ存在単位ではない。いわば、存在固定の場を持たない無分節的飽和充溢の機能的単体」であり、「不可抗的自発自展の力動性、と不可逆的志向性とを、それ自体の唯一固有の即自的機能とするところの、浮遊・浮動の機能的単体」である、と定義されます。
空間的延長をもたない純粋機能体である「たま」は、したがって、「様々な可感的存在単位をその〝憑坐[よりまし]〟とすることによって、始めてみずからを、この可感的現象時空の存在位相に、現象的機能主体として現象させる」。すなわち「〝たま〟は〝から・からだ(可感的存在単位)〟において、みずからをトポス的に同定することによって、〝み(可感的現象時空における心身的機能主体)〟としての現象現成を実現する。」かくして、「たま→から・からだ→み」という「たま」的主体性の位相転換構造の図式が得られました。
(佐竹昭広は『萬葉集抜書』に収められた論考「意味変化について」のなかで、「「からだ」という「宅舎」に「たましい」という生命が入居して「身」をかたちづくる。」と書き、「「こころ」とは、「たましい」の宿った「身」の中で営まれる精神活動であり、思考作用である以上、「からだ」と「たましい」の不一致は、そのまま、「からだ」と「こころ」の齟齬という結果に通じている。」と書いている。「認識フィールド」論文に明記されているように、井筒豊子はこの佐竹昭広の議論を参照している。
ところで、佐竹昭広は、この「身」における「からだ」と「こころ」の対立を、「語」(音声記号)における「音声形式」と「意味」の関係にアナロジカルに適用している。「音声記号は、一定の音声形式と意味とから成り立っている。人間の「からだ」が「こころ」の器であるなら、音声形式も、また、意味の器にほかならない。「からだ」に「こころ」の宿っているものが生きた「身」であるなら、音声形式に意味の宿っているものが、すなわち「語」にほかならない。」
そして、「語」の意味に対応する概念として、「身」の方に「こころ」という言葉が見出されることに注目する。「一般に、意味論は、意味を客観的認識の対象として、当の言語主体から切り離しすぎたうらみがある。いま、語の意味を、「こころ」という和語によって認識しなおしてみるとき、語の意味と言語主体の心的活動は、確実に一本のキイ・ワードで架橋されることになるであろう。意味論にとって、これは、すこぶる重要な示唆だとはいえないであろうか。」
この指摘は、目下の課題、すなわち井筒俊彦がこころざした「古今、新古今の思想的構造の意味論的研究」の実質を考えるうえで重要な示唆となる。歌の「こころ」と「からだ」、ひいては能役者の「身」のあり様をめぐる議論にとっても。)
2.「のる」から「まうす」へ─和歌の「ことだま」的言語意識現象
「たま」とは第一位相の「こころ」(無分節の情動的志向性)に相当するもの(より精確には、第一位相の「こころ」として現象している「心地」的主体性)であり、心身的機能主体である「み」のうちの心的機能の方が第二位相の「こころ」(意味分節的な言語意識的主体)に相当する。おおよそ、そう考えておいていいだろうと思います。井筒豊子はそのそれぞれに、祝詞の預言的・託宣的文脈における「のる(宣・告)」主体、奏上的・祈願的文脈に関連する「まうす(申・奏・曰・白)」主体の名を与えています。
和歌・歌論の「言語的事態構造」をめぐる議論への橋渡しとして、井筒豊子は、「のる」と「まうす」に対応するそれぞれの言語意識事態に関して、前者の「即自的・非再帰的自己発露」が、後者の「再帰的自己陳述・記述」に先行することを指摘します。
ここに述べられている事柄、すなわち、「のる」主体とは実は「たま」が憑依した「身」、つまり「まうす」主体(純然たる人間主体)にほかならず、その「まうす」意識(純然たる人間の言語意識)そのものが、「のる」主体による「たま」的言語現象=「ことだま」的言語意識現象を通じて成立しているのであり、そして、和歌を詠むとはそうした「ことだま」的言語意識現象を、いわば「初めての夢」(もしくは、始まりの哥としてのやまとうた)を何度でもわが「身」において自覚的に反覆再現することそのものである、という議論は、序の部にでてきた「意味記号的構造転換」の言い換えであり、そしてそれこそが古今序を「原起点」とするやまとうたの思想の実質にほかなりません。
3.感嘆詞からメタ記号へ─「あはれ」の位相展開
「のる」主体は「たま」の直接・無媒介的・即自的な自己発露であって、その機能は「非言語的、というよりは、前・言語的な情動の事態」として発現する。したがって、その機能は「前・言語的な純粋志向的力動性、であり、もしも強いて言語的事態との類比性において把握するとすれば、最も意味志向性の薄いあるいは低い、〝‘声’に最も近いことば〟つまり〝感嘆詞〟に対応する」。すなわち、感嘆詞としての「あはれ」こそ、「たま」的主体の唯一の自己発現である。
井筒豊子はそのように論じ、つづいて、「あはれ」の語を用いた万葉集歌の分析を通じて、そこに通底する、非在性もしくは非形象的不可視性・隠在性、遠望的焦点ないし空間的非限定性を示唆する浮動性、といった意味的表徴を指摘したうえで、たとえば「かき霧らし 雨の降る夜を ほととぎす 鳴きて行くなり あはれその鳥」の例歌において、闇夜に鳴くほととぎすが、あたかも感嘆詞的「あはれ」の真の発現主体である「たま」の被憑依体ででもあるかのように登場していることを指摘します。
このような、感嘆詞的事態からメタ記号(象徴記号)へ、という「あはれ」の位相展開は、非現象・無分節の「たま」的主体(「のる」主体)が、「あはれ」の一声の発出を契機として、再帰的・反照的な意識・認識的言語主体へと、つまり心身的な知覚・感覚的自己同一性である「身」=「まうす」主体へと位相展開的に連接していくこととパラレルな関係をきりむすびます。
井筒豊子は、こうした「非現象⇒現象」の形而上的・存在論的な構造軸は、ある種の範型を抜きにしては考えられないとし、とりわけ俊成、定家の「有心」的歌論の背景には、「意味分節単位=存在分節単位、の構造に焦点を置く真言密教の金剛界曼荼羅における識大内含的万有の位相的生成展開構造内に成立するところの…自照的意識主体の介入が考えられる」と指摘します。
■破の部:漢語系、曼荼羅的言語構造
感嘆詞的主体(第一フェイズ)から再帰的言語意識主体(第二フェイズ)へという、やまとうたの現象展開の構造的背景をなす和漢二系列の形而上的思想体系のうち、その第二のものは、金剛界九会曼荼羅という位相展開構造のモデルです。
以下、「第一会」から「第九会」まで九つの位相から成る、「存在論と意識論とを表裏一体とする」曼荼羅の構造をめぐって、井筒豊子が試みた「ポストモダン的」な読解、もしくは「意味論的・ポストモダン的な誤読」の芳醇・豊穣なる成果を丸写しし、若干のキーワード、解説を抜き書きした上で、多くの謎を残しつつも、私が理解(もしくは誤解)しえたかぎりのことを記しておくことにします。
Ⅰ.形相位相に全開顕する「第一次的」な四位相
【第一会】成身会─根本会
「過去・現在・未来、有情・非情、の全存在単位が、[真空妙有の]形相的一者の内部分節として、形相的全顕現を円成しつつ、[不生常瑜伽]無始・無時間、の形相的位相磁場、に各自その全現前を成就している。(この[成身会]磁場の自自映現、として大曼荼羅が成立する。)」([ ]は原文。以下同じ。)
この位相は一言で、「形相[イデア]的多者の形相的全現前磁場」と定義される。「形相的多者」すなわち「形相的万有」を「同位的内部分節」とするところの「真空妙有的・形相的一者」とは、第一会の中尊、大日如来のこと。
【第二会】三昧耶会─三昧耶曼荼羅
「形相的全存在単位が、不生常瑜伽の形相的位相を脱して[六大・地水火風空識、の]構成元素を共有するところの、現象機能的生成展開の発現基体、として、各自その[本質的]純粋志向性を発動し、即自的純粋機能展開に入る。」
第一会の「形相的多者」が第二会において「即自的純粋志向機能」として発現する。「現象機能的時間展開開始の磁場」。その総体は「三昧耶」(samaya)形、すなわち「象徴物」(持ち物、象徴記号)の集合で示唆される。
【第三会】微細会─法曼荼羅
「即自的・純粋志向的な生成展開機能単位群の網羅的総体、が各自その[識大内含的]純粋機能それ自体による、対自的・再帰的な自己同定・自己分節によって、意味単位素[声・種子・真言]としての、対自的自己同一性、を獲得する。」
第二会の「即自的純粋志向機能」と第一会の「形相的多者」との相即的相互同定によって、対自的に対象化・客体化された自己同一性の単位群が現象する。
【第四会】供養会─羯磨曼荼羅
「意味単位群相互間の対他的相互相関作用の発現が、関係的差異性による対他的自己同定を可能にし、その結果、相互相関的網目組織磁場の全同位項が、対他的自己同一性を獲得して、意味単位群=存在単位母型群、の網羅的総体の現象現成が成立する。」
第三会の「対自的自己同一性」の各単位が、対他的な差異性による「対他的自己同一性」を獲得し、第一会の「(非現象的)形相的常寂位相磁場」の全体が、そのまま「現象機能の網羅的組織磁場」と成る。
その現象的生起とともに、「生成展開の全位相を包摂するとされる大・三・法・羯、の四種曼荼羅(四曼相大)の第一次的全過程が実現・完成」する。「その内の第二会・三昧耶会位相は(無相の)‘意密’の、第三会・微細会位相は(無相の)‘口密’の、そして第四会・供養会位相は(無相の)‘身密’の、機能磁場に当る。」
Ⅱ.現象的位相展開を継続する「第二次的」な四位相
【第五会】四印会
「生成展開の四位相[自自映現・即自・対自・対他、大・三・法・羯、の四曼荼羅]磁場の継起的現象現成、の完了を契機として、それら四位相磁場を自らの内部分節としかつ自照的対境とするところの、四曼それぞれの識的摂持主体、の共時的現象現成磁場、が成立する。」
四曼、三密の第一次的過程の完了を契機として、四波羅蜜、五大菩薩を共時的に全包摂する「識的」(=心的)大曼荼羅が現象現成する。継起的現象展開の第二次的過程の開始。
【第六会】一印会
「継起的現象現成を成就した識的摂持主体の全四位相、が共時的に全開顕するところの、識的大曼荼羅[四印会]磁場、を媒介として、[真空妙有の智拳印]一者の形相的絶対覚が現象的に活性化され、一者の、全一・無分節的充溢、の覚(空)的宇宙磁場が生起する。」
第五会の成立を契機として、第一会の「形相的一者」(=「阿字」)が現象機能的に現成する。この第六会の位相磁場には、「全一・無分節の〝覚〟の現象機能的全現前、(いわば阿の〝声〟、阿の一声、)以外には、現前するなにものもない」。
【第七会】理趣会
「(一印会一者の全一無分節的志向性の分節的自己顕現として)欲動・感覚・情動・我覚[欲触愛慢]的諸機能、とそれによって操作された識的万有・全意味単位群の二項対立的網羅組織、とを自らの内部分節・自照的対境とするところの[能く迷い能く悟る]可塑的意識主体、が現成する。」
第六会に(一者の自己顕現として)現成する無分節全一の「覚的一声(阿の声)」は、第七会において「無数無量の意味単位=存在単位を集積的内部分節として全包摂するところの、意識・認識的現象の機能磁場」=「多一的「吽字」の意味磁場」へと連接する。「心・身的ないし身語的な現象機能主体」による「人間的な心的[サイキ]機能の全時空磁場」が現成する。
【第八会】降三世羯磨会
「[理趣会の]意味単位群を分節母型群とする可感的存在分節作用、によって塑型されたところの(六大の可感的所成としての)全存在単位群・森羅万象、が現成する。自照的意識主体も可感的自己同一性を獲得し、対他的・身心的行為主体、としてこの可感的時空の存在位相に現象する。」
金剛界曼荼羅の九つの位相の中で唯一、「可感的実在界、つまり人間の知覚感覚的対象界」として措定されている。第一会から第七会に到る各位相に現成する万有は、すべて「意味元型的または意味分節的な自己同一性」であり、第七会に現成する万有も意識対象としての言語意味分節単位であって、知覚・感覚対象としての可感的・具体的な存在単位ではない。「この可感的万有界・森羅万象界、はその現象的生成展開の根源位相であるところの不生常瑜伽の形相的位相の、映現的・影現的な事態としての、一種の実体化的塑型[レイフィケイション]を受け、意識・認識機能の機能対象、ないし持続的対境、として幻視する」。
ここにおいて、第五会から第八会へと継起的に生起する「意識宇宙・識的時空」としての現象的位相展開が完了し、四種曼荼羅の第二次的な全過程が実現する。
第六会の「一者の(現象現成的実存の)〝覚〟の無分節全一的志向的機能」を(有相の)「意密」とし、第七会の「言語意味分節的・再帰的な識機能」を(有相の)「語密」とし、第八会の「対他的相互相関の行為的機能」を(有相の)「身密」とする「三密的自己同一性」がこの「可感的現象位相」に成就する。
Ⅲ.永劫回帰へ
【第九会】降三世三昧耶会
「存在の生成展開過程の継起的全位相を完了し各自その現象的可感的全顕現を成就した全存在単位が──成身会に開顕する不生常瑜伽の十全なる形相的各存在単位を自らのテロスとして志向しつつ──各自その必然不可避[除垢障]の即自的生成展開の純粋機能[無相の三密]に回帰する。」
第八会に成就した「三密的自己同一性」の心身的存在単位群は、第九会において、それぞれの「個別的な内的所証[リアリティ]」によって規定され方向づけられた「全一無分節の即自的志向機能(いわば〝吾なし〟の純粋経験的志向機能)を発現」する。それらは「そのまま、存在論的生成展開の初発位相である第二会・三昧耶会の三昧耶機能へと、永劫に反覆するその回帰的連接、を成就する」。
■曼荼羅的言語構造をめぐる若干の註釈
空海、真言密教、曼荼羅に関する急場しのぎの断片的知識を元手に、なんども繰り返し読みこんでいくうち、おぼろげな輪郭のようなものが浮かび上がってはくるものの、しかし、それをしっかりとつかまえて、自分自身の言葉で定着するだけの熟成にはとうてい到りません。ここでは、形相的一者、不生常瑜伽、三密、声字実相、四種曼荼羅、といった語彙をめぐる若干の、それも先賢、先達の業績を借りての註釈をほどこします。
その一。「真空妙有的・形相的一者」が、かのプロティノスの「一者」に通じていることをめぐって。
井筒俊彦は、司馬遼太郎との対談「二十世紀末の闇と光」で、真言密教、とくに空海の精神的な世界においては、大日如来は単なる理念ではなく、人格的な荒々しさを持ったアッラーの神のような活き活きした「実在者」だと思う、と語っている。
神の三つのペルソナ(父と子と聖霊)と、後でとりあげる大日如来の三つの潜在的なはたらき、すなわち三密(身密・口密(語密)・意密)との関係が気になるが、ここでは、大日如来の本質が「不生無礙常瑜伽」であることをめぐる井筒俊彦の発言を、重ねて引いておきたいと思う。
いま、東洋哲学全般を見渡すような哲学をつくりたいと思ってやっている、そのためには哲学的、東洋的なメタ・ランゲージの世界をつくりたい。そのように語る井筒俊彦に、司馬遼太郎が「その東洋は、インドから東でしょうか。」と問う。
その二。「身」「語」「意」の三密と「声字実相」との驚くべき関係をめぐって。
前田英樹著『言葉と在るものの声』に、三密と「声字実相」をめぐる「驚くべき」(パースの記号の考え方についての前田氏の評言)議論が展開されている。
いわく、大日如来は「三密」の働きそのものとして在る。「「三密」のなかには一切の根底が、潜在性を極めるものがあり、その働きが如来という実体にほかならない。「三密」は、「身」「語」「意」の三つの等しい「密」、すなわち潜在性で成り、これら三つはこの世の「六塵」となって顕われてくる。」「如来の「身」は「語」を発し、「語」は「意」を帯びて「文字」を顕わす。これらは三つにして、ただひとつの潜在的働きである。」
「三密」は「文字(もんじ)」となって顕われ、「六塵」(色塵、声塵、香塵、味塵、触塵、法塵)に現働化する。「ここで彼[空海]の言う「文字」は通常のそれをはるかにはみ出している。(略)生きている者にとって、六塵、すなわち五種の知覚対象と思考されるその諸関係は、さまざまな「文字」となって顕われざるを得ない。それらは、生きて行動する者に対して意味を持ち、何らかの解釈をいやでも迫らずにはいないからだ。したがって、こうした「文字」は、パースの言う「記号」の概念に極めてよく通じるものだと言える。」
「如来の「三密」は、「身」「語」「意」の三つから成るが、「身」は「実相」に、「語」は「声」に、「意」は「字」に対応する。すなわち、如来の三つの潜在性は、「声字実相」の切り離し得ない働きをもって現勢化する、あるいは〈表現〉されるのだと言うことができる。」
「如来の「三密」は、身、語、意が一体となった潜在性の働きのことだった。「声字実相」とは、この一体の働きがそのまま現働化して在る態[さま]を言う。「声」はすなわち「語」の働き、「字」は「意」の働き、「実相」は「身」の働きを言い、「声字実相」三つの働きが、同時に互いを支え合っていなければ、「三密」は顕われず、衆生は救われない。」
「最も潜在的な宇宙の身体が、人の言葉(「文字」)を通して自己を明かす。如来の「声」は、人が用いる「文字」となってみずからの「身密」を、「実相」を表現する。「声字実相」とは実にこのことを言う。
空海のこうした考えは、宗教的であると同時に、極めて詩人風なものだ。詩人とは、宇宙の身体が、彼をして語らしめる機会を持つ人間のことでなくて何であろうか。」
前田氏の議論は途方もなく深い。通りすがりの要約を許さない。ここに示された「身⇒語⇒意」と「実相⇒声⇒字」の構造的対応は、井筒豊子の議論に直結している。
◎「語密」(如来が持つ潜在的な言語能力(ランガージュ))=「声」(記号活動の力(ランガージュ))
◎「意密」(記号が持つ潜在的次元の働き、六塵を通して「文字(もんじ)」へと現勢化するもの)=「字」(パースの言う「記号」の概念)
◎「身密」(この宇宙で最も潜在的なもの、潜在的質料の全体)=「実相」
その三。「目まいのするほど複雑壮大な」パースの記号分類をめぐって。
パースは、記号を三つの在り方によって分類する。記号は、それ自体で捉えられ(第一次性=潜在的な流動)、対象を持ち(第二次性=第一次性から現働化する二項関係)、解釈される(第三次性=三項関係)。このうち、第一次性において、つまりそれ自体で捉えられた記号の在り方に「性質記号」「個物記号」「法則記号」の三種類がある。
この、第一次性において捉えられた三種類の記号の在り方が、「身・語・意」の「三密」、それも「無相」の三密と、そしてまた四種曼荼羅にいう「自自(映現)・即自・対自・対他」の四相と、ある精妙な論理の道筋を介してつながっていくのではないかと思う。それはたとえば(かの「哥の伝導体」の理論にひきよせて)次のような等式で表現できるかもしれない。
【第零次性】零記号=無相の三密=自自映現
【第一次性】性質記号=身密=即自
【第二次性】個物記号=語密=対自(再帰・自照)
【第三次性】法則記号=意密=対他
零記号は急場しのぎの造語で、むしろ「霊記号」か「(表意ならぬ)憑依記号」と命名すべきかもしれない。
ところで、「実に驚くべきもの」と前田氏が言う「パースの巨大な記号分類」は、第二次性において、つまり対象との関わり(表意作用)で捉えられた記号の在り方(類似記号・指標記号・象徴記号)、第三次性において、推論や解釈との関わりから捉えられた記号の在り方(名辞・命題・論証)へとつづく。このことと、金剛界曼荼羅の位相展開における四種曼荼羅の第一次的過程(無相の三密)、第二次的過程(有相の三密)、そして「永劫に反覆する回帰的連接」との関係は、もうひとつの「目まいのするほど複雑壮大な」体系へと連接している。
■破の部:曼荼羅構造と「たま」構造との構造的照応
最後に、曼荼羅的言語構造と「ことだま」的言語構造との関係、同様に、曼荼羅的自然構造と「たま」の被憑依体的な森羅万象の構造との関係、について。
井筒豊子によれば、曼荼羅構造にあっては、すべての「有」は、それが可感的なもの(感覚知覚対象)であれ非可感的なもの(意味分節単位)であれ、例外なく、「形相的一者」の「声」をその根基的要素として内包しています。だから、一切の言語意味単位は、いわば真正主体によって憑依された「有」として現成し、また、(言語意味単位の現象現成であるところの)可感的万有もまた、被憑依体的多者として可感的現象界に現成することになります。つまり、曼荼羅構造と「たま」構造との間には、次のような連接、照応、相互補完性の関係が成立しているわけです。
(1)形相的一者=「たま」的主体
第一に、万有をみずからの内部分節として包摂しつつ、その内部分節・万有の位相展開とともに、万有と同一の位相磁場(第六会)に、みずからの現象現成を成就する「形相的一者」(第一会)は、万有をみずからの憑り代として現象する無分節全一の憑依的・隠在的な真正主体、「たま」と照応する。
(2)「覚」的主体=「のる」主体、可塑的意識主体=「まうす」主体
第二に、曼荼羅構造における第六会の「覚」的主体は、「たま」構造における「のる」主体(第一位相の「こころ」=無分節の情動的志向性)と交感し、「心地」的な無分節的充溢の磁場は、第六会の「覚」磁場と映発し合う。
また、曼荼羅構造における第七会の言語意味分節的・再帰的な意識・認識的機能主体、つまり「吽字」的・可塑的意識主体は、「たま」構造の「まうす」主体(第二位相の「こころ」=意味分節的な言語意識的主体)に呼応し、「詞林」の万華万葉の機能磁場は、第七会の意識・認識的機能地平の万華鏡と映発し合う。
(3)阿の声=「あはれ」の一声
第三に、「形相的一者」の機能的現象現成である、第六会の一者の「阿の声」、つまり無分節全一の力動的充溢としての「覚」機能の現象現成は、「たま」の内発的・即自的な純粋志向性の発現としての、無分節全一の感嘆詞的事態である「あはれ」の一声と構造的に照応する。
(4)曼荼羅構造的多=「たま」構造的多
第四に、「たま」(=「形相的一者」)の即自的現象機能発現としての「あはれ」の一声(=阿の声)を契機として、「のる」主体の無分節・情動志向磁場(第六会)から「まうす」主体の意味分節・言語意識磁場(第七会)への位相的展開が開始され、意識・認識的「多」の位相磁場が開顕し、それとともに可感的現象界(第八会)の分別的「多」が現象する。すなわち、「ひとのこころをたねとして」現象現成するところの「よろづ」の被憑依的事物事象と、曼荼羅における森羅万象・可感的万有・被憑依体的多者とが、「同根の差別相・万有」として現成する。
(本稿冒頭の「構図」に即していえば、一次層における阿声、「あはれ」の一声を契機として相互照応的に展開してきた曼荼羅構造と「たま」構造が、二次層(内界)において分岐し、三次層において、可感的森羅万象と「よろづのことのは」をそれぞれ現象現成する。ところがそれらの現象的多は、実は零次層における潜在的無分節全一主体を等しく「胚胎・憑依」するものであり、したがって「同根の差別相・万有」として現象現成している。)
《隠在的真正主体を等しく胚胎・憑依するところの曼荼羅構造的多(意味単位=存在単位)と〝たま〟構造的多(被憑依体的事物事象)とによって構成されたところの、和歌の詩的創造主体の(非可感的・可感的)対境、つまり、みずからの意識磁場の全体と認識磁場の全体とが、ともに、そのような意味では、和歌の詩的創造にとっての一種の聖別された意味的意識宇宙ないし聖別された可感的自然空間、として措定され把握される。自照的意識宇宙・自照的自然空間、の成立である。
この和歌的創造主体の自照的意識宇宙・自照的自然空間を、(いわば気韻生動的に)満たしているのが、(隠在的真正主体の現象機能的自己発露としての)〝たま〟の一声・〝あはれ〟の全一的情動であり、一印会一者の〝覚〟の全一的純粋志向性の飽和充実である。
和歌の創造主体の、この自照的意識宇宙・自照的自然空間、との構造的関連上に位置づけられる鍵的意味単位に〝ながめ〟と〝見渡し〟がある。》
ここで、「和歌の詩的創造にとっての一種の聖別された意味的意識宇宙ないし聖別された可感的自然空間、として措定され把握される。自照的意識宇宙・自照的自然空間の成立である。」と語られているのが「自然曼荼羅」であり、その「自然曼荼羅」の現成機序が、ほかならぬ「認識フィールド」論文・急の部のテーマとなります。
(24号の32章に続く) ★プロフィール★
中原紀生(なかはら・のりお)1950年代生まれ。兵庫県在住。千年も昔に書かれた和歌の意味が理解できるのはすごいことだ。でも、本当に「理解」できているのか。そこに「意味」などあるのか。そもそも言葉を使って何かを伝達することそのものが不思議な現象だと思う。
Web評論誌「コーラ」24号(2014.12.15)
<哥とクオリア>第31章:言語・意識・認識(認識フィールド篇、破の部)(中原紀生)
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2014 All Rights Reserved.
|
| 表紙(目次)へ |