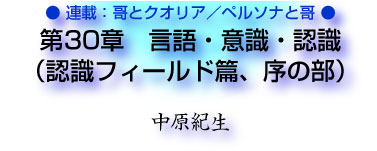|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「La Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
|
■森羅万象の織りなす千紫万紅の綴れ織り
井筒豊子は、和歌論三部作の第二論文「意識フィールドとしての和歌」の末尾に、「蛇足」として、次の一文を書き加えています。
最後に予告された、和歌・歌論における認識界のフィールド構造について、自然観照の側面からのアプローチを通じて考察した論考とは、和歌論三部作の掉尾を飾る「自然曼荼羅──認識フィールドとしての和歌」にほかなりません。
この章ではいよいよ、三部作中もっとも精妙で濃密な議論が展開された、この「認識フィールド」論文に挑むわけですが、その際、あたかも「森羅万象の織りなす千紫万紅の綴れ織り」を思わせる華麗な細部の叙述に溺れ、全体の理路と筋道を見失うことにならないよう、いま抜き書きした文章に繰り返しなんども立ち返っては熟読玩味し、礎石を固める必要がある。と、これは自戒の弁として記しておきます。
(引用文の前段を読んでいると、後段の、たとえば「観照的空間」などという語彙がもたらす連想ともあいまって、どこかしら映画的なもの、それも、一挙に最後まで見終えてしまった夢のなかでの映画体験のようなものが思い浮かび、もしかしたら、井筒豊子の和歌論は映画論としても読めるものだったのではないか、それも、言葉が見る夢としての映画論のごときものを目論んでいたのではないか、とあらためて思いをめぐらせました。が、このことは、いずれ稿を改めて考えたいと思っているので、ここではこの程度でとどめておきます。)
■二つのマンダラ、二つのアソシエイション
「言語フィールド」論文で、和歌的言語表現の特性とされた三つの項目のうち、「自然の事物事象の多出」(和歌における主題選択が、外的自然界の事物事象の美観に偏していること)をめぐる考察は、他の二つの項目、「極端な短詩型」と「装飾語の多用」に関する分析と比較して、いまひとつ得心のいかないところが残りました。
簡単にふりかえっておきます。井筒豊子によると、和歌に独自、固有の言語フィールド構造は、語の統辞的連結組織(シンタックス)の側面に対して、意味単位の遊動的連鎖連合組織(アソシエイション)の側面の方が、不均衡なほどの機能的優位を占めることの上になりたっていて、そのような言語構造のもとでは、「各意味要素は、統辞的意味限定の拘束力と限界枠をはるかに超えて、広大な、言語的網目組織の意味地平全域を、遊動の機能的磁場としながら、本来的に重層的な、その意味連鎖の波紋を展開し、拡大してゆく」ことになります。
そのようなわけだから、かけことば、枕言葉、縁語、みたて、等々の、過剰とも見える修辞修飾的語句の多用は、統辞的意味限定の拘束力を緩和し、意味の遊動的連鎖展開(意味のフィールド展開)を助長する機能を果たしているのであり、また、三十一音節という和歌の狭小さは、けっして最小の規模なのではなく、圧倒的なアソシエイションの機能的優位のもとでは、むしろ最大(マクシマム)に近い規模であるとさえ言っていい。そのように明快に規定したうえで、最後に、井筒豊子は、和歌における自然の事物事象の多出について、おおよそ次のように述べています。
○自然の事物事象を示す語の意味単位は容易に物象化され、存在分節単位にそのまま直結する傾向を持っている。
○そして同時に、それら(存在分節単位)の状況的背景(「外界の存在空間、認識空間としての、場的な、空間的延長展開」)そのものをも随伴的に喚起する。
○その結果、それらの語を組み込んだ和歌(「意味連鎖の網目組織の全領域を、意味連動の磁場とする、三十一音節の、言語意味フィールドの一単位」)は、自然界と呼ばれる外的空間を背後に持つ認識空間の一単位と相互喚起的、相関的に関与することとなる。
○自然の事物事象を指示する語は、それらが全面的に概念化されステレオタイプ化されたものであればあるほど、「対象化された外界としての、現象空間的背景の拡がり」を和歌の言語フィールドに喚起的、示唆的に附与する。
○言語意味連鎖のフィールド展開という無時間的地平に現象界の時間秩序、時間推移という時間流動の遠望的背景を附与するのも、概念化され典型化された形で把握され指示される自然の事物事象(という原初的な所記(シニフィエ)的普遍者)の和歌における独自の機能である。
さきに、得心がいかない、と書いたのは、いま箇条書きのかたちで抽出した議論だけでは、和歌における自然の事物事象の多出という特色と、シンタックスに対するアソシエイションの機能的優位という和歌に固有の言語フィールド展開の特性との結びつきが、(極端な短詩型、装飾語の多用という他の特色との関係のようには)直接的、必然的なかたちで説明しきれていないからです。端的にいえば、和歌における主題(というより、素材もしくは語彙)の選択が、ほぼ全面的に自然の事物事象に偏り、たとえば闘いや政治的陰謀などの歴史、哲学的真理や見えないものに対する信仰といった事柄を詠む歌が欠落しているのはいったいなぜか、そのことが腑に落ちるようには説明されていないのです。
ただ、ひとつ言えるのは、そこでは、「意味連鎖の網目組織の全領域を、意味連動の磁場とする、三十一音節の、言語意味フィールド」と形容されているものと、「存在分節単位」の背景をなす「外界の存在空間、認識空間としての、場的な、空間的延長展開」もしくは「対象化された外界としての、現象空間的背景の拡がりを」と表現されるものとのあいだに、なんらかの照応関係がなりたっていることが暗に示されていることです。精確には、和歌に特有の言語フィールド展開と相即的に生起するところの意識フィールドと認識フィールドとのあいだに、そのような、もしそう言ってよければ「華厳的な縁起」に裏うちされた、アナロジカルな関係性がなりたつことが示唆されているということです。
実は、これと同様の議論が、前節で抜き書きした文章のなかでも展開されていました。
煩を厭わず再掲するならば、引用文の前段で、「意味的分別・分節機能によって分出されたところの、意味単位群の可能的総体(森羅万象)の連鎖連合による意味的網目の組織的地平展開の現成空間そのもの」とあるのが、意識フィールドの無時間的空間を言い表わす一文で、これに対応する認識フィールドのあり様については、後段で、「存在分節単位の成立する認識対象界は、歌論の世界では、自然の事物界、自然界、と同定され、その自然界はまた、他の二つのフィールド、特に意識フィールドと交感的に相照応することによって、(観照的空間としての)観照的自然領界を構成する」と書かれています。
そして、この両者のあいだになりたつアナロジカルな関係性を暗示するのが「マンダラ」の語でした。
まず、意識フィールドの無時間性をめぐって、それは、意味単位群の可能的総体(森羅万象)の「地平的一的挙展開、現象現出の一挙展開、意味的網目組織の(意識フィールドの現成と揆を一にする)一挙展開」を意味するような無時間性であり、「いわばマンダラ的無・時間の空間性であり、華厳的な縁起の、宇宙大に広大無辺の、意味的網目組織の、無・時間的展開地平」である、と書かれているなかに登場する「マンダラ」。次に、認識フィールドが、意識フィールドとの交感的照応を通じて歌論の世界で構成するとされる観照的空間に関する定義、「自然の事物形象が意味記号として機能するような、自然記号の成立空間、いわば、自然マンダラ、の成立する領界」のうちに使用された「マンダラ」。
このふたつの「マンダラ」は、かたや意識フィールドに成立する意味分節単位群としての事物事象の連鎖連合組織(アソシエイション)であり、かたや認識フィールド(ただしそれは外的な、主客二分の経験的認識対象界ではなく、あくまで歌論の世界において構成される観照的空間)に成立する存在分節単位群としての事物事象の連鎖連合組織(アソシエイション)であって、それぞれを組成する成分の違いと、かたやフィギュラティブ(マンダラ的)、かたやリテラル(マンダラそのもの)という言語表現上の違いはあるものの、それらを構成する原理(華厳的縁起)においてアナロジカルに相同であり、ひいては「意味分節単位=言語分節単位=存在分節単位」という、三重に相呼応し相照応し合う和歌的世界の最終形へといたる契機となるものでもあります。
そうだとすると、「言語フィールド」論文で提示された、シンタックスに対するアソシエイションの機能的優位(S<A)という、和歌的言語フィールドの構造構成原理は、「意識フィールド」論文で、広狭二義の「有心体」の関係(狭義:「詞」<「余情」,広義:「思ひ⇒詞」<「情⇒余情」)に転換され、また、広狭二義の「有心」の概念(狭義:「こころ=意識フィールド(思ひ+情)」⇒「ことば=言語フィールド(詞+余情)」,広義:「空=非現象(心地)」⇒「仮=現象(こころ+ことば)」)へと変奏されていったように、「認識フィールド」論文において、さらに、言語・意識・認識の三つのフィールドが相互に照応し合う複合的なシステムもしくはメカニスムの編制・稼働原理を解明する「世界観」、あるいはより一層高次かつ深遠な「思想」として、その究極的な表現を与えられることになるのでしょう。
以上の議論をふまえて、ここで、あらかじめ結論めいたことを述べておきます。それは、つまり、和歌・歌論において表現される究極的な「思想」とは、ひと言で、「存在はコトバであり、ココロでもある。」(存在分節単位=言語分節単位=意味分節単位、あるいは唯物論=唯言論=唯心論)とくくることができるものであって、そのような「やまとことば」の思想の実質を叙述し、かつ、そうした思想が、和歌的言語フィールドにおけるアソシエイションの優位、そしてその意識フィールドでのバージョンアップ版である「有心」のメカニスム(とりわけ、遡行的志向性のはたらきによる「詠みつつある心」の起動)を介して、和歌的認識フィールド(観照的自然空間)のうちに結実していくプロセスを解析したのが、ほかならぬ「認識フィールド」論文であると。
前文がその職分を大きくふみはずし、長々しくなってしまいました。
■序の部:二つの森羅万象
「認識フィールド」論文は、序の部・破の部・急の部と名づけていい、三つの論述の塊に分けることができると思います。その概略を述べておくと、まず、序の部の冒頭で述べられているのは、次のような事柄です。
1.隠在する構造構成力
やまとうたの歌論は非体系的かつ非思想的で、そこに用いられる語彙も概念も精錬(リファイン)されすぎ定義不可能であるかのように見えるが、そうした外見にかかわらず(歌論をその典型とする)やまとことばによる思考展開には強力な内的構造構成力が潜んでいること。
2.和語系と漢語系の重層
その隠された内的構造とは第一に、和語系の思考のうちに漢語系の思考を「構造的類比対応」(アナロジー)の形で保持しながら進められる複合的・重層的な思考展開が要請するもの、つまり統辞的意味展開(シンタックス)よりはむしろ意味単位群相互間の連鎖連合(アソシエイション)に依拠するところの、意味の「類比対応的」(アナロジカル)な整合構造であること。
3.空の哲学・言語理論
隠された内的構造の第二は、空の哲学すなわち存在の無「自性」性の哲学、特にその真言密教の言語観・言語理論を契機とするものであり、そこから言語現象・意識現象・認識現象を巻き込んだ(単なる歌論の枠内にとどまらない)ひとつの世界観にもつながる和歌の言語記号的・事物事象的な「類比対応」(アナログ)構造が導き出されること。
以上は、論考全体の骨格をなすプロット、というか趣向のようなもので、序の部では、このうち「空の哲学・言語理論」にかかわる基礎理論的な構図(言語・意識・認識の三項関係の構造構成的図式)が与えられ、それをふまえて和歌論三部作を総括する最終命題(それは、やまとことばによる思考展開の内的構造構成力にかかわる)の輪郭が示されます。
次いで、破の部では、この構図を「実証」もしくは「論証」するために、「空の哲学・言語理論」の和語系ヴァージョンとしての和歌・歌論における「ことだま的言語構造」(「のる」主体と「まうす」主体)がとりあげられ、その漢語系ヴァージョンである「曼荼羅的言語構造」とのあいだの、和漢複合の重層的な相互補完性が叙述されます。
そして最後に、急の部で、歌論における自然観照(「ながめ」と「みわたし」)の重層的視野のうちに「自然曼荼羅」が生起するプロセス(それは、やまとことばの思考をめぐる最終命題そのものでもある)が解析されるわけです。
※
それでは、序の部の内容を、立ち入って見てみることにしましょう。まず、第一の論件、言語フィールドと意識フィールドと認識フィールドの関係をめぐる議論の導入部の抜き書きから。
ここには、先に述べた二つの「マンダラ」に関連づけて考えることができそうな「自然の事物事象」の二類型、つまり二つの「森羅万象」が出てきます。
かたや意味的一般者・識的万有としての資格において現象現出するところの森羅万象、かたや可感的存在時空に分出された存在単位群としての可感的森羅万象。前者は、意識の函数的・縁起的相互相関項であり、意味単位群を母型として可感的に「塑型」されたもののことですが、著者の言葉遣いでは、「意味単位群を母型として可感的に塑型され」ることと「可感的存在時空に分出され」ることとは同義(塑型=分出)ですから、それは結局、後者と一致します。すなわち、「意味的一般者・識的万有としての森羅万象」=「可感的森羅万象」。
ただ、このことと、「意味単位群=存在単位群」の等式が意味することとは、微妙にその意味合いが異なります。というのも、ここで言われる「森羅万象」は、純粋な意味分節単位でも純粋な存在分節単位でもなく、意識フィールドと認識フィールドが重なり合う領域(「和歌の意識・認識フィールド」=「和歌的自然観照の意味地平」)に住まいするものだからです。
もうひとつ、気になることがあります。それは、文中で、「外在的自己同一性の単位群として現前している」ところの可感的存在単位群、と言われているものと「可感的森羅万象」との関係をどう考えればよいか、ということです。
議論がこみいってきたついでに書いておくと、序の部の別の箇所では、鴨長明(『無名抄』)の「郭公などは、山野を尋ね歩きて聞く心をよむ。鶯ごときは待つ心をばよめども、尋ねて聞く由をばいとよまず。」云々の文章に出てくる、郭公・鶯・鹿の音・桜・楊・初雪・時雨・霰・花・紅葉などの語に関して、次のように書かれています。
ここで言われる「外在する自然の対象把握・描出所産という資格で考察された」事物事象が、「外在的自己同一性の単位群として現前している」可感的存在単位に相当し、「意味の充溢体=意味的自己同一性の一単位=存在単位の母型」が「意味的一般者・識的万有としての森羅万象(=可感的森羅万象)」に相当することは一目瞭然です。が、それでは、「具体的経験のコンテクストにおける活たる現前性・現実性」を捨象されない自然の事物事象とはいったい何なのか。それは、いま引いた一文のすぐ後に出てくる、「可感的自然の事物事象が、その活たる実存的力動性の事態コンテクストを背景として、メタ記号的に機能する場合、それの発揮する意味指示可能性は無限に多様であり、それの意味分出機能は、無限の流動的可塑性を持ち」云々、という文章中の「可感的自然の事物事象」と同じ事項なのかどうか。
そもそも、意識フィールドにおける意味分節単位群の「マンダラ的」一挙展開と、和歌的認識フィールドにおける「自然マンダラ」の成立という、二つの「マンダラ」と、いま述べた二つの「森羅万象」、そして二つ(ないしは四つ)の「自然の事物事象」との関係はどのようなものなのか。
そして、より根本的な問いとして、自然の事物事象が、その活たる現前性・現実性を捨象され、概念化されステレオタイプ化されたとき、そうであるにもかかわらず、あるいはそのようなものであればあるほど、(つまり、それらが「識的万有・意味的一般者」として措定されたものであるならば)、この形骸化・定型化とも見られる事態に伴う不毛性が一転して、無限の記号創造的力動性へと転成する、というのはいったいいかなるメカニスムに基づくものなのか。このことは、先にふれた序の部の二つの論件のうちの第二のものにかかわってきます。
■序の部:万象生起の力動的意味空間の現成
以上の論点群を念頭におきながら、「認識フィールド」論文・序の部の議論を、私なりに編集してみます。
まず、第一の論件、言語・意識・認識の三つのフィールドの関係にかかわる理論的な布置結構を確認しておきたいと思います。その議論の起点となるのが、「自然の事物事象」という概念です。井筒豊子の和歌論では、大きく分けて次の四つの類型が想定されていました。
【第一類型】
可感的認識対象として外界に措定される具体的存在者。
精確には、「主体が外的客体を認識するという構造モデルに随伴するような、認識的・経験的時間空間」において成立する具体的存在者としての事物事象。より精確には、そうした構造モデルのもとでの外在的な指示対象の「自己同一性の単位群として現前している」事物事象。実在の次元すなわち「外在する自然の対象把握・描出所産という資格で考察された」事物事象。
このような意味での自然の事物事象は、和歌・歌論のコンテクストの埒外、すなわちやまとことばの思考の圏外にある。
【第二類型】
可感的自然の事物事象。
第一類型の事物事象と同様、個別具体的な存在者だが、第一のものとは違って主客二分の認識モデルには羈束されず、したがって「具体的経験のコンテクストにおける活たる現前性・現実性」を捨象されることもない。また「活たる実存的力動性の事態コンテクスト」を背景として「メタ記号」的に機能する場合には、無限に多様な「意味指示可能性」と無限の流動的可塑性を持った「意味分出機能」を発揮する。
井筒豊子の言葉遣いでは「メタ記号」とは「象徴記号」のことで、それは「より記述的であり、感覚・知覚的具体性を持つ意味直示的記号」と対比される。その意味するところを汲むならば、第二類型の自然の事物事象は、「クオリア」類似の力動的な現前性・現実性を帯びてそれ自体として在る具体的存在者だが、それが「象徴(メタ)記号」として機能する際には、意味の指示や分出において無限の多様性と流動的可塑性を発揮する「自然記号」の性質を帯びることになる。
【第三類型】
可感的存在時空に分出された存在単位群としての可感的森羅万象。
意識フィールドにおいて成立する意味単位群を母型として可感的に「塑型」された事物事象群で、「直接的には、意識の対象・意識の函数的(縁起的)相互相関項」として認識フィールドおいて「分出」される事物事象群。
ここで「森羅万象」と言われるは、第二類型の可感的事物事象のような個別具体の存在者としてではなく群として、その「可能的総体」においてこれを表現するためである。その意味では「可感的事物事象」は「可感的森羅万象」という集合の要素をなすものであり、したがって「自然の事物形象が意味記号として機能するような、自然記号の成立空間、いわば、自然マンダラ、の成立する領界」に登場する「自然マンダラ」こそ、「活たる実存的力動性の事態コンテクスト」のもとでの可感的森羅万象のあり様そのものを言い表わしている。
【第四類型】
意味的一般者・識的万有としての資格において現象現出する森羅万象。
空の自己分節、無の「真空妙有」的自己限定によって現成する意味単位群、すなわち無限の「記号創造的力動性」を持つ「意味の充溢体=意味的自己同一性の一単位=存在単位の母型」群が、それらが成り立つ場所そのものである意識フィールドの出現と同時に一挙展開すること、それらの可能的総体が一挙に現象現出すること、すなわち「華厳的な縁起の、宇宙大に広大無辺の、意味的網目組織の、無・時間的展開」を、井筒豊子は「マンダラ的」と形容する。ここで「マンダラ」とは「アソシエイション」(意味単位の遊動的連鎖連合組織)と同義の言葉、精確には「アソシエイション」の創造的・力動的な側面を言い表わす言葉ととらえておいていいだろう。
そうしたメカニスムと力動性のもとにある意味単位群が(あたかも公理的集合論における「分出公理」に基づくように)縁起的(=函数的)に自らを認識フィールドへと塑型(=分出)した存在単位群が、意味的一般者・識的万有としての自然の事物事象である。
したがって「意味的一般者・識的万有」(第四類型)=「可感的森羅万象」(第三類型)。そしてこの等式が成り立つ場所、すなわち意識フィールドと認識フィールドが重なり合う領域が、そこにおいて「自然マンダラ」が成立する「観照的自然空間」である。というより、意味単位群の一挙展開と同時に「意識フィールド」が出現したように、意味的一般者・識的万有=可感的森羅万象(=存在単位群)の塑型・分出と揆を一にして認識フィールドが、精確には「意識フィールド=認識フィールド」(=観照的自然空間)が出現する。(あたかも「〈無〉⇒〈有〉」のビッグバンによって一挙開闢した宇宙の内部において、「A⇒B」(例:「(真空妙有的)《無》⇒《有》」あるいは「アダムの言語⇒バベル崩壊後の諸言語」)が「A⇒A+B」もしくは「A=B」のごとく無時間的に現象するように。)
(第四類型の自然の事物事象には、井筒俊彦が言うところの「分節Ⅱ」(無「本質」的分節)の事態が成り立つ。ただしそれはあくまで「空の哲学・言語理論」のもとでとらえられた場合の話であって、裏を返せば、つまり「空の哲学・言語理論」の構造構成ベクトルを逆転させて、「主体が外的客体を認識するという構造モデル」に随伴する「外在する自然」のごときものを想定する立場からこれをとらえるならば、そこに現われるのはいわば死んだ概念としての「分節Ⅰ」(有「本質」的分節)の事態、「個別的具体的経験の完全なる形骸化・定型化」すなわち創造的力動性を欠除した不毛な「ステレオタイプ」でしかないだろう。)
以上の構図のもと、おおよそ次のようなプロセスを経て、「意味分節単位=言語分節単位=存在分節単位」(すなわち「意識フィールド=言語フィールド=認識フィールド」)という「三重の磁場が相互に呼応し、照応し合う世界」が成立することになります。
Ⅰ.意味単位群と存在単位群とがアナロジカルに同定される。
いいかえれば、第二類型、第三類型、第四類型の自然の事物事象が「活たる実存的力動性の事態コンテクスト」のもとで交感的に呼応し合い、それぞれがそれぞれのままで(三位一体的に)同じ一つのものになる。(あたかもパースのセミオシスにおいて、第二類型=「対象O」を第三類型=「記号S」が示すとき、その記号Sを第四類型=「解釈項I」によって解釈するプロセスが無限に連鎖連動していくように。)
Ⅱ.それと同時に、意識フィールドと認識フィールドとがアナロジカルに同定される。
この「和歌の意識・認識フィールド」すなわち「意味単位群=存在単位群の重層的な網羅組織磁場」は「和歌的自然観照の意味地平」であり「(観照的空間としての)観照的自然領界」を構成する。観照的自然空間、すなわち「自然の事物形象が意味記号として機能するような、自然記号の成立空間、いわば、自然マンダラ、の成立する領界」。
Ⅲ.意識・認識フィールドで展開される個々の意識・認識経験の「網羅的間主観性」において「(意味単位群の函数的連鎖連合の巨大な網羅組織、つまり)言語記号組織の全体」が通時的・共時的に現成する。
そして、意識・認識フィールドと言語フィールドとのあいだに「完全な相互映現的照応関係」が成立する。すなわち「意識フィールド=言語フィールド=認識フィールド」。
ここでは、和歌のメカニスム、あるいは「やまとことば」による思考のプロセスが、「可塑性と流動性にみちた豊穣なこの意味地平磁場、を和歌的創造主体みずからの意識・認識(の機能)フィールドと」することを起点とし、「万象生起・現象現出的多、の力動的意味空間」の言語的現成を終点とする、ダイナミックなものであることを、しっかり記憶にとどめておきたいと思います。
■序の部:遡行と塑型、あるいは意味記号的構造転換
序の部の第二の論件、やまとことばによる思考展開に隠在する内的構造構成力にかかわる最終命題について。ここでも、井筒豊子の文章を二つ、直に見ておきます。
ここで言われる「意味記号的構造転換」とは、「可塑性と流動性にみちた豊穣なこの意味地平磁場、を和歌的創造主体みずからの意識・認識(の機能)フィールドと」することをその決定的な起点とし、その上で、「意味単位群の生成展開の通時的堆積とその共時的相互相関関係とを自覚的背景として」、「和歌の、言語記号的・事物事象的な、類比対応構造」を「方法論的に操作」することにほかならないでしょう。
簡略化していいかえると、「仮」の世界のただなかにあって「遡行的志向性」のはたらきを介して「空」(=心地)を発動させ(広義の有心)、創造的・力動的な志向性を通じて「他者的・外来的な思考・思想」を「同化融合」(assimilation)すること、すなわち、(あたかも、「外在する自然」から到来した事物事象というステレオタイプを、非可感的意識フィールドにおいて「意味的一般者・識的万有」としてとらえなおし、力のベクトルの向きを逆転させ、これを認識フィールドにおいて可感的森羅万象として「塑型」するように)、「和歌的創造主体」固有の意識・認識フィールドにおいて独自に創造的に展開することにほかなりません。(急の部での言葉遣いを先取りして、ここに「実体化的塑型」(reification)の語をあてはめていいかもしれません。)
古今和歌集仮名序に「ひとのこころをたねとして、よろづのことのはとぞなれりける」とありました。この「こころ」を意識フィールドに成立する意味単位に、「よろづ」を認識フィールドに成立する存在単位(萬=森羅万象)に、「ことのは」を言語フィールドに成立する言語単位にそれぞれおきかえ、かつ、真名序「託其根於心地、発其華於詞林」の「心地」を「空」(=非現象)、「詞林」を「仮」(=現象)ととらえるならば、この和漢複合の重層的な解釈(「こころ」の二相化)を通じて見えてくるのは、「認識フィールド」論文・序の部が述べようとしていること、つまり「存在はコトバであり、ココロでもある。」という、やまとうたの思想ともいうべきものそのものだろうと思います。
★プロフィール★
中原紀生(なかはら・のりお)1950年代生まれ。兵庫県在住。千年も昔に書かれた和歌の意味が理解できるのはすごいことだ。でも、本当に「理解」できているのか。そこに「意味」などあるのか。そもそも言葉を使って何かを伝達することそのものが不思議な現象だと思う。
Web評論誌「コーラ」23号(2014.08.15)
<哥とクオリア>第30章:言語・意識・認識(認識フィールド篇、序の部)(中原紀生)
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2014 All Rights Reserved.
|
| 表紙(目次)へ |