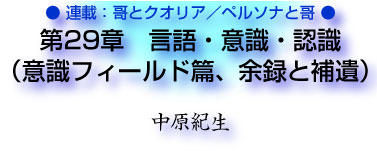|
|
|
Web�]�_���u�R�[���v |
|
���n���̎� ���{���̕\���i�ڎ��j�� ���{���̃o�b�N�i���o�[ ���ǎ҂̕Ł^���ӌ��E���z �����e�K�� ���W�҂�Web�T�C�g ���v���C�o�V�[�|���V�[ |
|
���{���̊֘A�y�[�W�� |
|
���u�J���`���[�E�������[�v�̃o�b�N�i���o�[ ���]�_���u�k�� Vue�v�̑��ڎ� |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
|
�����݂̓R�g�o�ł���A�R�R���ł�����
�@
�����c�o���w���킢�̗́@�u�S�̎���v�̎�����x�ɁA�u������^�����Ё^�S�i����j�v�Ƃ������{�I�ȁu�S�i������j�v�̎O�w�\���̐�������Ă���B
�@���킭�A�u������v�̓����́u�ω�����v���Ƃɂ���A������ς�肷��A�ڂ낢�₷������u������v�ł���B���́u������v�̉��Ɂu�����Ёv������B�\�w�́u������v�ݏo�����ƂɂȂ�A���I�ȐS�I��p���u�����Ёv�ł���B�u�\�Ƃ����̂́A���́u�����Ёv�����k�����|�\�ŁA�����Ĕ\��������Ƃ������Ƃ́A���́u�����Ёv���𓀂��Ă�����ƂȂ̂�������܂���B�v
�@���́u�����Ёv�̉��A�����Ƃ��[���w�Ɂu�S�i����j�v�����݂���B�u�S�i����j�v�́u�c�v�ɒʂ��A�u�_�v�ɒʂ���B�u�����Ёv��u������v�Ƃَ͈��̐_��I�ȐS�I��p�ł���B���t�╶����}��Ƃ����A��u�ɂ��đ���ɓ`��鉽���B�ȐS�`�S�Ƃ����Ƃ��́A�����Đ����킪�u�S�m����n���S�m����n�ɓ`�ӂ�ԁv�Ƃ����Ƃ��́u�S�i����j�v�B
�@
�@
���a�̂ɂ�����u�S�v�̎l�̑��ݎ����E�K��̘_���A�i��ς̓N�w�ɐڑ�����Ƃǂ��Ȃ邩�B
�@�i�䎁�́w�q���r�̃��^�t�B�W�b�N�X�x�́u�q���r�̌`����w�v�u�w���x�̗ϗ��w�v�u�g���h�̐l�Ԋw�v�̎O���\������Ȃ邪�A���̂��Ƃ����ɁA�����̍\�z�ł͌`����w�Ɨϗ��w�̂������Ɂu�u���v�̘_���w�v���݂�����l���\���ƂȂ�͂��ł������Ə�����Ă���B���́u���v�͂����炭�s���t�ɑ���������̂̂��Ƃ��낤�B��������Ƃ����Ɂu�ƍݐ��́q���r�v�u�P�Ɛ��́s���t�v�u���ȓI�ȁw���x�v�u�l�ԁi�����j�Ƃ��Ắg���h�v�̎l�́u���v���o�ꂷ�邱�ƂɂȂ�B
�i����ɂ����ɁA���J�s�l���́u�����l���̎l�̌`�ԁv�A���Ȃ킿�u�����l���`�i�ݏV�j�v�u�����l���a�i���D�ƍĕ��z�j�v�u�����l���b�i���i�����j�v�u�����l���c�i�����l���`�̍������ł̉j�v���W�Â��邱�Ƃ͂ł��Ȃ����B�j
�@
���ᏼ�p�㎁�́w�䓛�r�F�����b�m�̓N�w�x�̑��́i�w�ӎ��Ɩ{���x���Ƃ肠�����́j�ŁA�u�ӎ��i�I�K��j�v�Ɓu���݁v�̊W���߂����Ď��̂悤�ɘ_���Ă���B
�@
�@
�����̈ꕶ�ɂÂ��āA�ᏼ���́w�ӎ��Ɩ{���x�́u�قƂ�ǍŌ�̕��́v�������A�u����͌���ł����邪�A���_�����Ă�����B�����ł́u���݁v�͑��ݎ҂ł͂Ȃ��B�C�u���E�A���r�[�̂����u���݁v�A����͐�ΓI���z�҂ٖ̈��ł���B�v�Ə����Ă���B�i���̈Ӗ��ł́u���݁v�͂܂��A��敧���̌`����w�ɂ����u�^�@�v���Ȃ킿�u��Ζ����ߎҁv�̂��Ƃł�����B�j
�@�w�ӎ��Ɩ{���x�̌���ɂ��Ă��̌��_�����������镶�͂Ƃ́A�u���m�N�w�ɂ����ẮA�F���Ƃ͈ӎ��Ƒ��݂Ƃ̕��G�ő��w�I�Ȃ���ݍ����ł���B�����āA�ӎ��Ƒ��݂̂��̂���ݍ����̍\����Nj����Ă����ߒ��ŁA�l�͂ǂ����Ă��u�{���v�̎��ݐ��̖��Ɉ�������������Ȃ��B�v�Ƃ������̂ŁA���́u�ӎ��Ƒ��݂Ƃ̕��G�ő��w�I�Ȃ���ݍ����v�Ƃ��Ắu�F���v���߂�������Ƃ肠�����̂��A�䓛�L�q�́u�F���t�B�[���h�v�_���ł���B
�@
���w�ӎ��Ɩ{���x�ł́u�R�R���v�̂������̎g�p��A�u���̃R���e�N�X�g�Ŏg���u���S�v�u�L�S�v�͓��`��ł͂Ȃ��B�u���S�v�Ɓu�L�S�v�Ƃ͂��ꂼ��Ⴄ�����Ő�������R�R���ł���v�ɂ����u���̃R���e�N�X�g�v�Ƃ́A�u���m�N�w�̗l�X�ȓ`���̒��ŁA�u�{���v�ے�_�ɑΗ����ē��Ɂu�{���v�̎��ݐ����咣���闧����O�̊�{�^�ɕ��ނ��A�v��́u�i�������v�ɑ�\�������̌^�����������łɁA���̐����̗���Ƃ��đT�́u�{���v�ے�_�����グ�v�A������������A�u�����I�g�g�@�\�̒��Ɍ`�����ꂽ�u�{���v�̌n�A���Ȃ킿���ݕ��ߑ̌n�ƁA����Ƃ̐[���ւ��v�̂��ƂŘ_����Ƃ��������������Ă���B
�@���������āA�����ł�����u�L�S�v�́A��Ɖ̘_�́u�L�S�v�Ƃ͂��̑��ݗl�����܂������قɂ��āA�o�����E�ɂ�����l�Ԃ̈ӎ��̒ʏ�̂�����A���Ȃ킿�������X�ʁX�Ȃ��̂Ƃ��ĔF������u���߈ӎ��v�̂��Ƃł���B�u������ϑz���ʁA���ݕ��߂̋��ʁB���̋��ʂɓ������߈ӎ�����X�͕��ʁA���Ɂu�ӎ��v�Ƃ������ŌĂяK�킵�Ă���B�v�����āu���S�v�Ƃ́A���̂悤�ȁu�l�Ԃ̐���ȐS�̓������v�i�L�S�j�ɑ�����́u���^�ӎ��v�Ƃ��Ắu��Ζ����ߓI�ӎ��v�������B
�@
�@
���䓛�r�F�́A���ܔ��������������͂̂������ƂŁA�u���������ϋɓI�ȈӖ��ɉ����ꂽ�u���S�v���A�ƁX�u�S�v�ƌĂ��̂͂ނ��듖�R�łȂ���Ȃ�Ȃ��B�i���j�����A�����ĕٕʂ���Ƃ���A�u�S�v�Ƃ����m��I�\���ɂ́A�܂��ɂ��̍m�萫�̂䂦�ɁA��Ζ����ߎ҂��{���I�ɓ������鑶�݃G�l���M�[�ւ̎���������A�ƌ����邩���m��Ȃ��B�v�Ə����Ă���B
�@�����ł�����u�S�v�����A�w�ӎ��̌`����w�����w���N�M�_�x�̓N�w�x�ɂ����Ę_�����ꂽ�u�S�i����j�v�ł���A�䓛�N�w�����ʂ��������̃e�[�[�u���݂̓R�R���Łi���j����v�ɂ����u�R�R���v�ɂق��Ȃ�Ȃ��B
�@
����̕��߁A��̉Ԓ�
�@
���䓛�r�F�ɂ��ƁA�T�́u�u���S�v�́e�`�����f�w�v�ł���A�u��Ζ����ߎ҂��ꎩ�̖̂��u�{���v�I���߂𒆐S�Ƃ��ēW�J���A�܂�����ɋ��ɂ���v�B
�@����ł́A�T�ɂ����邱�́u�u�{���v��}��Ƃ��Ȃ������̕��߁v�͂����Ȃ�����\�������̂��B�䓛�r�F�͂�����A���Ȃ킿�u�T�̎��ݑ̌��v�i���A�����̌��j�̑S�ߒ����A�u�����߁v�_�Ƃ��u���߇T�v�Ɓu���߇U�v���ӂ̗��[�Ƃ���O�p�`�̌`�Ŏ����B
�@
�@
���䓛�r�F�ɂ��T�I�W�J�̍\�����f���́A�u���߇T�˖����߁˕��߇U�v�i��F�u�R�͎R�ł���v���u�R�͎R�ł͂Ȃ��v���u�R�͎R�ł���v�j�Ƃ��Ď������B
�@��Ƃ̘̉_�ł́A�u���߇T�˖����߁v�̏㏸�ߒ��́A�u�F���E�i���ۊE�A�o���E�j�v����u���v�i�u�ӎ��E���݂̃[���|�C���g�v�Ƃ̐ړ_�j�ւ̑k�y�I�u�����̂͂��炫�ɑ�������B�T�҂Ȃ�ʉ̐l���u�S�n�v���u�����߁v�ւ̒��ړI�ȎQ�����ʂ������Ƃ͂��Ƃ�肩�Ȃ�Ȃ��B�}��K�v�ł���B
�@�܂��u�����߁˕��߇U�v�̉��~�ߒ��́A�^�̘a�̓I�n����̂ł���u�r�݂���S�v���u�������G�ȃm�G�V�X���ꎩ�́v�̓����i����͕��������\�ɂ������W�e�̓o��ɒʂ��Ă���j�ɑ�������B
�@
���T�I���ݑ̌��̏o���_���Ȃ��u���߇T�v�̎��ԁA���Ȃ킿�u�L�u�{���v�I���ݎ҂̐��E�v�ɂ��ď����ꂽ�䓛�r�F�̕��͂��L���Ă����B�����ɁA��̎ᏼ���̕��͂ň��p����Ă��������܂܂�Ă���B
�@
�@
������ł́u�T�N�w�̒��S���Ȃ��v�Ƃ���́u���u�{���v�I���߁v���Ȃ킿�u���߇U�v�̓��I�l���Ƃ͂ǂ̂悤�Ȃ��̂��B
�@
�@
������ɂ��Ă��A���u�{���v�̐��E�����䓛�r�F�̕��͔͂������B
�@
�@
���V�����ԁA���邢�̓t�B�[���h�S�̂̎��Ȍ���
�@
���u�Ԃ̂��Ƃ��v�Ƃ�������̂́A��j�����w�Ԓ��̎g�x�Łu�a�̂̓��e���A�������Ƃ����l�I��������ؗ�����Ď�������q������́r�ƂȂ�A���̌��t���A�����ɂ��肤�鐢�E���L�q���邱�Ƃ���߂āA��̏Փ˂ƌ�������Ǝ��̌����Ԃ��\�z����悤�ɂȂ鎞�A�����Ƃ����y�납���d�ɍ���f����ꂽ�a�̂́A�܂��Ɂu�l�̐S�v��������Ƃ��āA�V�����Ԃ��炩���邱�ƂɂȂ�B���̎��A����͒������}����B�v�Ə����Ă����A���̏r���E��Ƃ́u�V�����ԁv�ɒʂ��Ă���B
�@���́i�ǂ�������m���@�[���X�̐��Ԃ�A�v���I�V���C�݂̓������I�␅�f���������Ƃ����Ƃ����Ă�����͂̐���A�z������j�u�V�����ԁv�̓������́A�u�сi���₩��j�v�������́u�g�v�i���t�B�M���[���j�ɒʂ��Ă���̂��A����Ƃ��u�ہi�����ǂ�j�v�������́u���v�i���C�}�[�W���j�ɂȂ����Ă����f���̂��̂Ȃ̂��B���邢�́u���g�v�u���ہv�u���́v�Ƃ�����������Ă͂߂�̂��ӂ��킵���̂��B
�@
���䓛�L�q�́u�ӎ��t�B�[���h�v�_������A�u��i������j�v�̊T�O���������������܂邲�Ɣ����������Ă����B�����ŁA�ߓI�E�����ԓI�ȋ�ԓI�O�a�[���̎��ԂƂ����Ă���̂��A���u�{���v�I���߂̈ӎ��I���ʂ������\���Ă���B�܂�u�v�Ёˎ��v�n�����u���߇T�v�ɁA�u��˗]��v�n�����u���߇U�v�ɂ��ꂼ��Ή����Ă���B
�@
�@
�����������́w���S�̃_�C�i�~�Y�������u���Ȃ₩���v�̌n���x�̑�́u�䓛�r�F�̑T�N�w�����T�̖��S�̓N�w�I�����v�ŁA�G���m�X�w��ł̈䓛�r�F�̍u���_���g�she �rtructure of �relfhood of �yen �auddhism�h���Ƃ肠���Ă���B
�@��s����u���ŗ�ؑ�ق��u���S�v���gno-mind�h�Ƃ������t�ɑ��������Ƃ��āA�䓛�r�F�́A����́u���ӎ��i�S�������A�����Ȃ��j�v�̏�Ԃ��Ӗ�����̂ł͂Ȃ��A�u�S���ō��̋��x�Ɩ������������ċ@�\���Ă���v��Ԃł���Əq�ׁA�n�[�v�i�Ձj���t�̖��l���u�����ɉ��y���ꎩ�g�ƈ�ɂȂ��āv�����Ԃ��ɋ�����B���̖��l�̋��n�̓p�t�H�[�}���X�̋ɂ݂ɂ����Ă��������b�݂̂悤�ɂ���Ă�����ʂ̑̌��ł����āA����ɑ��đT�͓��X�̕�炵�̒��ł��ꂪ�ʏ�̈ӎ��ƂȂ邱�Ƃ�ڎw���Ă���B
�@�Ƃ���Łu���S�v�́u���y�ƈ�̂ƂȂ��������v�ɂƂǂ܂�̂ł͂Ȃ��B�u���S�v�̋��n�́A�@�u�y��̂݁v�A�A�u��̂݁v�A�B�u����Ȃ��y����Ȃ��v�A�C�u�������A�y�������v�Ƃ����l�̋ǖʂ����B���̍Ō�̂��̂��u���y�ƈ�̂ƂȂ��������v�̋��n�ł���A�u�킽�����E�y����E�e���Ă���v�Ƃ������B�����Ă��ꂪ�A��́u��v���Ώہu�y��v�ɑ����������Ƃ�������I�ȏƂ͈Ⴄ�ǖʂł��邱�Ƃ��A�䓛�r�F�́u�t�B�[���h�S�̂̎��Ȍ����v�Ƃ����������ŕ\������B
�@�������͂��́u�t�B�[���h�v�̊T�O���A��q�����ɕ�ݍ���ł���A�ӎ��̃t�B�[���h�ł���Ɠ����ɑ��݂̃t�B�[���h�ł�����A�����G�l���M�[�̗��̓I�ȓ����ł���Ɛ������A���̂悤�Ɋ���B
�@
�@
���p���e�N�X�g�����Ƃɂ����u�T�I�ӎ��̃t�B�[���h�\���v�i�w�R�X���X�ƃA���`�R�X���X�x�����j�ŁA�䓛�r�F���g�̋c�_���m�F���Ă����B
�@���킭�A�u���͍��������v�Ƃ����P���Ȗ���́A���ʂ̈Ӗ��ŁA�܂��E�q�Η��I�F���@�\�̂��Ƃł̔F���o���̖��肾�Ƃ���A�� ������ ���������Ə������ŕ\�L����邪�A�u���S�v�I��̂̎����ł́A�啶���̂h �r�d�d �s�g�h�r�ɕς��B
�@
�@
�@�ӎ��E���݃t�B�[���h�ɂƂ��Ă̎l�̎�v�Ȍ����`�ԂƂ́A�u�l����D�v�i�l����������q���Ƃ��Ɉӎ��E���݃t�B�[���h�̕\�ʂɎp�������Ȃ����ƁF����Ȃ��y����Ȃ��j�A�u�D���s�D�l�v�i��̂݁j�A�u�D�l�s�D���v�i�y��̂݁j�A�u�l����s�D�v�i�������A�y�������j�́u�l���ȁv�ł���B
�@
�@
�����ݘ_�ƈӎ��_���d�Ȃ�Ƃ���
�@
�����u�{���v�̐��E�����w�ӎ��Ɩ{���x�̕��͂��A���܂����Lj����B
�@
�@
������ł́u�^�@�v�Ƃ͂Ȃɂ��B�䓛�r�F�́w�ӎ��̌`����w�����w���N�M�_�x�̓N�w�x�Ŏ��̂悤�Ɍ��B
�@���킭�A�w�N�M�_�x�̍l�z����u�^�@�v�́A��Ζ����߂ł���R�g�o�ȑO�ł���ۑԁi�`�̈�F�u�����^�@�v�j�ƁA�����̕��ߒP�ʂ̕��G�ɍ�������Ӗ��A�ւƂ��Č��݂��錻�ۑԁi�a�̈�F�u�ˌ��^�@�v�j�̓�K�w�\�������B����͂��������u�S�F���̐�Ζ��I�ɓ_�v�Ɓu���L�̕��v�̑o�ʐ����͂�v���e�B�m�X�́u��ҁv�̌`�p�����킹��B
�@
�@
���܂����킭�A�u�^�@�v�́w�N�M�_�x�̎v�z�S�̂�ʂ��Ē��S�I�ʒu���߂�B���������̋ɓx�ɒ��ۓI�ȁu�����i������j�v�́A���̂܂܂ł͋�̓I�Ȃ��Ƃ���،��Ȃ��B�N�w�I�������͐M�I�Ɏv�z��i�߂Ă������߂ɂ́A�����Ɛ��X�Ƃ����Ӗ�������یꂪ�K�v�ł���B�����Łw�N�M�_�x�͈�̐V�����L�[�^�[���A�u�S�i����j�v������B
�@
�@
���L�[�^�[�����u�^�@�v����u�S�i����j�v�Ɉڂ�A���ݘ_���ӎ��_�ɂȂ��Ă��A�w�N�M�_�x�̌`����w�I��{�\���i�`�̈�{�a�̈�j�͕ς��Ȃ��B�����A���̖��̂��ς��B���Ȃ킿�A�`�̈恁�u�S�^�@�v�i��Ζ����ߓI�E�����ۓI�ӎ��A�ӎ��̃[���E�|�C���g�j�A�a�̈恁�u�S���Łv�i�u�����~�܂��N�ł���L���ߓI�E���ۓI�ӎ��j�B
�@�`�̈�Ƃa�̈�̑��݊W�͗����I�A�s���I�ł���A�_��ł���B���҂͕s�f�ɑ��ݓ]�����Ă���B���Ƃ��Ƃa�͂`�́u���ȕ��߁v�ɂق��Ȃ�Ȃ�����ł���B�u�`�̈�Ƃa�̈�Ƃ̂��̓��قȌ����A���҂̂��̖{�R�I���ݓ]���A�́e�ꏊ�f���w�N�M�_�x�͎v�z�\���I�ɑ[�肵�āA������u�A�������v�ƌĂԁB�v
�@���̂`�̈�Ƃa�̈�Ƃ̂������ɉ�݂��ė��҂�A�����钆�ԗ̈���A�䓛�r�F�͂l�̈�ƌĂԁB�����āA�l�̈悪�Ȃ����̂悤�ȏd��ȋ@�\���ʂ������Ƃ��ł���̂��Ƃ����A�w�N�M�_�x�����ڂɓ����邱�Ƃ����Ă��Ȃ��₢�����āA���������������B
�@
�@
�����̂l�̈悪�䓛�L�q�i�r���A��Ɓj�̂����u���i�����Ёj�v���Ȃ킿���Ƃ̎����̈�ɑ�������̂��낤���B����Ƃ��u�l�̈恁���i�����Ёj�{��i������j�v�ƒ莮�����ׂ��Ȃ̂��낤���B
�@����|�́u�i�ӎ��́j�\�����f���v��掦�����w�ӎ��Ɩ{���x�ł́A�ӎ��̂l�̈�́u�z���I�v�C�}�[�W���̏ꏊ�ƒ�`����Ă���B����A�������Ő��������u���^�v���l�X�ȃC�}�[�W���Ƃ��Đ��N����Z���B�u�V�g�A�V���A��S�A����A�����A���b�ǂ������̃C�}�[�W����Ԃ��[�����B�i���j���̃C�}�[�W����Ԃ��A����ɐl�Ԉӎ��̈�l�ԂƂ��邱�Ƃɖ������Ȃ��ŁA����Ɏ��ݐ��A���ݘ_�I���i��^����l�X�ɂƂ��ẮA����͑O�ɏq�ׂ� mundus imaginalis �ƌĂ����Ɠ��̑��ݐ��E�ł���B�v
�@���́u�z���I�v�C�}�[�W���̐��E�����o���������̂��}���_���ł���B�u�l�̈�Ɍ������鑶�ݍ\�����`�ۉ������[�w�ӎ��I�G��A�Ⴆ�}���_���v�B
�@
���w�N�M�_�x�������u�ӎ��̌`����w�v�̑��ݘ_�I�E�ӎ��_�I�\�����͂��I�����䓛�r�F�́A�Â��āu�^�@�v�i���u�S�v�j�`����w�ɂ��ƂÂ��I�����̓��I���J�j�Y���̉𖾂ɂƂ肭�ށB
�@�܂��A�u�l�˂`�v�̗��O�̓������߁A��Ζ����ߓI�u��������S�����S�v�ɂ�����u�o�v�ƁA�u�l�˂a�v�̐��ŁE���]�̓����s���A�������ۓI�����̒������C���Đ�����u�s�o�v�Ƃ��A�u�݂��ɓ]�����A���ݏz���Ȃ��牝���߂��������I���̓��I�t�B�[���h�̔��W�����v�͂����A�����čŌ�Ɂu����v�Ƃ��Ď��̂悤�ɏq�ׂ�B�i�����Ɂu�S�n�v���o�ꂷ��B�j
�@
�@
�i���ł��u����v�i�s�g�h�r�j�ɓ]�����]��������u���v�i�h�j�B���邢�́A ���҂��琶�҂ւ̗։��]���B���ҁA���Ȃ킿�u���v����������ҁB�j
�@
�����t�����閲�A�������閲
�@
���䓛�L�q�̋c�_�́i�L�`�́j�єV���ۊw�̍\�}���ӂ܂��Ă���B��Ƃ́u�L�S�v��u�L�S�́v�̂Ƃ炦�����A���邢�͂��̍���ɂ���u����t�B�[���h�v�ɑ���u�ӎ��t�B�[���h�v�̋@�\�I�D�ʐ��⌻�ۊE�ɑ���ۊE�i����ȑO�̐��E�j�̍��������A�u������˂��Ƃ̂́v�̉������̘_�̐��E�ɕ�ۂ��ꂽ�i���`�́j��Ƙ_���w�̂���l�������Ă���B
�@
�@�i�L�`�́j�єV���ۊw�́u�N�I���A�v�Ɓu�y���\�i�v�𗼋ɂƂ���t�B�[���h�A���Ȃ킿���݂ƈӎ��ƌ��ꂪ���G�ɗ��݂������u�a�̃t�B�[���h�v��݂���B
�@�N�I���A�Ƃ͌���ȑO�������͕��ꖢ���ȑO�̐��E�Ɓu�l�̂�����v�Ƃ̊E�ʌ��ۂł���B�i�N�I���A���u���R�L���v�ƌĂ�ł������B�����ă}���_���Ƃ̓N�I���A�̉F���ł���ȂǂƂ������Ƃ��ł��邩�B�j�y���\�i�Ƃ́u���Ƃ̂́v���Ȃ킿����ɂ���đ��`���ꂩ����z����i���ꂻ�̂��̂Y����j��̂ł���B
�@
�@�u�a�̃t�B�[���h�v�ɂ�����u������˂��Ƃ̂́v�̃v���Z�X��ʂ��āu���Ƃ��Ẳ́v���a���������B���ɂ���l���l�X�ȁu�v�Ёv�i�����j��m�o���ɑ����ĕ\������i���`�́j�єV���ۊw�̐��E���Ђ炩���B
�@����\���ɐ悾���āA����ł͕\���ł��Ȃ��u�v�Ёv����������Ă���B���́u�v�Ёv���u���Ђ����v���J�^�`��^�������Ƃ�����ނɂ�܂�ʁu�Ђ��Ԃ�S�v�i�x�m�J���j�ɓ˂���������A�u�v�Ёv�ɂ܂Ƃ����N�I���A�ގ��́u���肠��v�������Ɍ����E�蒅�����邱�Ƃɐ��������Ƃ��A�̂��r�ނ��Ƃ���̐S�i�v�Ёj�`����i����������ƌ��������Ă������j���ƂƓ������Ȃ�B
�@���������u���Ƃ��Ẳ́v�̏W�ς�ʂ��āA�₪�āu�v�Ёv�����ꉻ���邱�ƂƁu�v�Ёv������I�ɐ��Y����邱�ƁA����ɂ͌��ꂻ�̂��̂������ɂ����ė���������ꏊ�i�y���\�i�j���o�����邱�ƂƂ���ʂł��Ȃ��i�L�`�́j�єV���ۊw�̐��E���A�u������������ꂸ���āA���߂������������A�߂Ɍ����ʂ��ɐ_�������͂�Ƃ����͂��v�鉼�����̘_�̐��E���Ђ炩���B
�@
�i���̋L�q�Ƃ��Ă̘a�́B���̖��͎��҂�����A���҂̕���ł���B���҂��Z�ނƂ���A����͌���̐��E�B���҂̓R�g�o�ł��菃�����_�ł���B�܂�a�̂̓R�g�o�����閲�B
�@���҂̃R�g�o�ɂ���Đ��҂͐�������Ă���B���҂͖������Ă���B���҂ɂ���Ďv���Ă���B�����āA���҂̃R�g�o�ɂ���ĕ������u���v���a�̂��r�ށB�R�g�o����B�j
�@
�@�i���`�́j�єV�̘_�ɂ��āA����ɐ旧�u�{�̂�����v�Ƃ����ǂ�����i�a�̓I����\���̓`���j�������Ă����̂��̂��Ƌt�]�������̂��r���ł���A�i�L�`�́j�єV�̘_���t�B�N�V�����ł���Ƃ��A�u���߂������͂�m��Ƃ͂��ɂ��ւ̒N�����͂肼�~���̓��v�Ɖr�̂���Ƃł������B
�@���������̌��邩����A�r���̘̉_����Ƃ̘̉_���i�L�`�́j�єV���ۊw�̍\���̂Ȃ��ł̃G�s�\�[�h�ł����Ȃ��B�����͂�������A���w�ɂ��܂�d�Ȃ��ĕ��G���k����܂�Ȃ����ݗl�Ԃ������u������v��㱑��̂����ɂ���B
�@�єV�́u������˂��Ƃ̂́v�ƒ�Ƃ́u���Ƃ̂́˂�����v�����݂ɕ�ۂ������B�єV�́u���Ƃ̂́v�̂����ɒ�Ƃ́u������v���h��A��Ƃ́u���Ƃ̂́v�̂����ɊєV�́u������v���h��B���̑��ݕ�ۊW�A����q�W�́A�������i�L�`�́j�єV�̘_�̍\�}�̂Ȃ��ł̑��ݔ��]�ł����Ȃ��B
�@
�@���̊W��f���邽�߂ɂ́A�u�r���I�]��v�̈Ӌ`���l�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�r�����i���`�́j�єV�̘_���t�]�����邱�Ƃɂ���ĉ����u���������B������S�A�S���畨�ւ̑k�s�I�u�����ɂ���Ėڎw���ꂽ���̂͂Ȃ������B���ꂪ�u�S�n�i������j�v���u�S�i����j�v�Ƃ������z�I�ۂł������Ƃ���A����͉�����āi�L�`�́j�єV�̘_�̐��E�ɉ�������B
�@���ꂪ����ł���Ƃ������Ƃ͔����Ă���B�r���A��Ƃ́u�V�����ԁv�Ƃ͌���I�\�z���ł���A��Ƃ́u�L�S�v���u�r�݂���S�v���܂����ꐢ�E���Z���Ƃ���B
�@�i��ϒ��w���c�����Y�x�̕\������āA�єV���ۊw�̊�{�e�[�[���u�̌��͌��t�ƓƗ��ɂ��ꂾ���ňӖ�����������B���t�̈Ӗ����܂����������̌��ɂ����Ȃ��̂��v�ƌ����\���Ȃ�A��Ƙ_���w�́u���t�͑̌��ƓƗ��ɂ��ꂾ���ňӖ�����������B�u�̌��v���܂������������t�ɂ����Ȃ��̂��v�ƋK�肷�邱�Ƃ��ł���B
�@
�i�������t���g���čl���A���t�ɂ���ĕ\�����鎖���A�����͂��ׂāA���t�������g���čl���A����ʂ��ĕ\�����Ă���̂ł���B�������̂悤�Ȕ��]���������Ƃ��A�܂莄����̂ł͂Ȃ��}�̂̒n�ʂɈڍs�����Ƃ��A����ł����͍l���A�\�����Ă���Ƃ��������͐��藧���낤���B
�@������藧�̂����A����ł́A���̎����̎������Ȃ����͉̂����낤���B�u��������l���A�����\�����Ă���Ƃ��������͐��藧�B���̎������܂����t�Ȃ̂��B�v����������͈̂�̒N�Ȃ̂��B�j
�@
�@�䓛�L�q�̋c�_���i�i���`�́j�єV���ۊw�����̓����ɕ�ۂ���Ƃ���́j�i�L�`�́j��Ƙ_���w�̍\�}�̂��Ƃœǂ݊����邽�߂ɂ́A�܂�i�L�`�́j�єV���ۊw�̍\�}�������ɔ��]���邽�߂ɂ́A�i������̂悤�ȓǂ݊����┽�]�ɈӖ�������Ƃ��Ă̘b�����j�A�V�����L���_�̊m�����K�v�Ȃ̂ł͂Ȃ����B
�@����̓p�[�X�̎O�L���A���Ȃ킿�u�w�W�L���iINDEX�j�v�u�ގ��L���iICON�j�v�u�ے��L���iSYMBOL�j�v�ɉ�����l�́u���ʋL���iMASK�j�v���߂���A����Ή��ʂ̋L���_�Ƃł������ׂ����̂ɂȂ邾�낤�B�i�u���҂̃R�g�o�̋L���_�v�Ƃ����ď̂��̂Ă������B�j
�@�������w�����A�ے����A�͕킷��̂ł͂Ȃ��A�w�����ے����͕킷��Ώۂ��̂��̂Y����L���̂͂��炫�B�u��v�Ɓu���v�i�u�����v�\�Ɓu���݁v�\�̌��g�ݍ��킹��Ȃ�A�u���i���j�v�Ɓu���v�A�u�������v�Ɓu�����݁v�j�̊W���𗘗p���āA�u���v����u�L�v�i���g�A���ہA���́j�����肾���u�ʂ`�˂`�v�Ƃł��\�L�ł��鉼�ʋL���̍�p�B
�@
���ᏼ�p�㎁�́w�r�c���q �s�ł̓N�w�x�ŁA�r�c���q�́w���}�[�N1997-2007�x���玟�̈�߂����p���Ă���B
�@
�u����
�@���̂̈��ł͂Ȃ�
�@�����ł͂Ȃ����`���ɂ����đ��݂����
�@�܂�يE�̎�
�@�̎v���ׂ����ƁA���ꂪ����ł���
�@
�@���҂̎v���ׂ��҂͐����Ă���
�@���҂Ɂe�v���āf���҂͐����Ă���
�@���������āA�����Ƃ͂��̂悤�ȕ���Ȃ̂ł���v�i�e�f�����T���j
�@
�@
���w�J���g�u����҂̖��v�x�i���X�����j�̕��ɉ���u��]�Ƃ̖��v�ŁA�O�Y��m���́A�w���������ᔻ�x�͌���_�Ƃ��ēǂ݊�������ׂ����Ə����Ă���B
�@
�@
�@��]�Ƃ̖��͂����ŏI���Ȃ��B
�@
�@
�i�Q�R���ɑ����j
���v���t�B�[����
�����I���i�Ȃ��͂�E�̂肨�j1950�N�㐶�܂�B���Ɍ��ݏZ�B��N���̂ɏ����ꂽ�a�̂̈Ӗ��������ł���̂͂��������Ƃ��B�ł��A�{���Ɂu�����v�ł��Ă���̂��B�����Ɂu�Ӗ��v�Ȃǂ���̂��B�����������t���g���ĉ�����`�B���邱�Ƃ��̂��̂��s�v�c�Ȍ��ۂ��Ǝv���B
Web�]�_���u�R�[���v22���i2014.04.15�j
���F�ƃN�I���A����29�́F����E�ӎ��E�F���i�ӎ��t�B�[���h�сA�]�^�ƕ��j�i�����I���j
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU�@2014 All Rights Reserved.
|
| �\���i�ڎ��j�� |