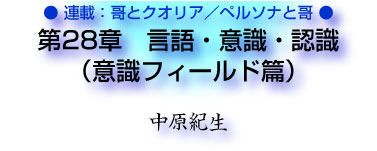|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「La Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
|
■漢語系と和語系、二つの言語意識
井筒豊子・和歌論三部作のうちの「意識フィールド」論文を、かれこれもう一年近く読みあぐねています。
この間、矯めつ眇めつ繰りかえし眺めているのにいまだ見極めがつかず、しっくり腑に落ち得心できたという実感がこみあげてきません。なにがどう論じられているかは読めば判るし、判ればとても刺激を受けるのに、読みかえすたびまた初めての読中読後感が立ちあがってきて、どうにも読み尽くせない。「言語フィールド」論文もけっして御しやすくはなかったものの、それでも論じられている事柄や主張それ自体はとてもシンプルで、かつ、議論の輪郭や筋道もくっきりと見通しがきくものだったのですが、「意識フィールド」論文は、文章、構文、叙述の全般にわたって複雑、錯綜の程度が高まり、読みくだし理解するのに難渋をきわめるのです。(これが「認識フィールド」論文ともなると、文章量の飛躍的な増量とともに論述の中身の複雑、錯綜、晦渋の質がより高次の域に達して、もはやその精緻きわまりない顕微鏡的な解像度についていけない。)
それは、読み手の力量の問題だけではなくて、じつは書き手の側の事情によるところが大きいのかもしれない。私は、そのように感じています。どういうことかというと、井筒豊子の論考が「難解」なのは、あるいは「難渋」するのは、その文体が和歌的な言語世界のあり様をなぞっているからではないかと思えるのです。ある事象や物事を客観的・批判的に分析しようとする者が、その当の考察の対象と同期し、あるいは魅入られ取り憑かれてしまう、それとちょうど同じように、井筒豊子の文体は、そのみずからのかたちでもってほかならぬ井筒豊子自身の和歌論の実質を、というより古典和歌の世界そのものの手触り、色や香に通じる質感のようなものを模倣的に体現しているのではないだろうかということです。
和歌に独自、固有の言語フィールドを成立させる機能構造の特徴として、井筒豊子は、「シンタックス(意味の統辞組織)」に対する「アソシエイション(意味単位の遊動的連鎖連合組織)」の機能的優位性を指摘していました。この、「言語フィールド」論文で導入された「シンタックス」と「アソシエイション」という言語の二側面は、(質料世界における言語の二つの存在様態のうち、「声」にかかわるのが「シンタックス」で「文字」にかかわるのが「アソシエイション」、いいかえると前者を(受動的・内在的な)「聴覚系」、後者を(能動的・離在的な)「視覚系」などと括ってみることもできるのではないか、と私は考えているのですが、それはさておき)、「意識フィールド論文」にでてくる「漢語系」と「和語系」という二つの言語意識もしくは意味世界に、後者の前者に対する機能的優位という関係性を含めてまるごと、対応させて考えることができるのではないかと思います。
藤原俊成が、天台止観の形而上的構造(空・仮・中の三諦)を読み換えることにより、「日本歌論を…美的価値創造の肯定的位置づけに関するアポロギアを構造的に内蔵するような形而上的背景を持った一つの美的・芸術的整合構造、へと、晶化させることを構想し、企図した」ことをめぐって、井筒豊子は次のように書いています。
文中の「心地」や「空」については、後でふれます。
ここでは、(「各意味単位内部の、分析組織的細分化、概念的分節の過剰性を特徴とする」とされた「漢語系」の意味展開が、はたしてそのまま言語の「シンタックス」的側面に通じているかどうかは措き、少なくとも)、「分節・分別を内にふくみつつ、本来、渾沌として幽玄、そして、飽和的豊穣と全包摂的な実存性を特徴とする」と規定された「和語系」の意味世界が、和歌的言語のフィールド展開において(筆者の口吻を借りるなら、「不均衡なほどに」)重点をおかれる言語の「アソシエイション」的側面に通じていて、そしてそれは同時に井筒豊子の、濃厚芳醇なネクターのような後味(余情)を醸しだす特異な文体に、したがってまたその思考の生理のようなものに通じているのではないか、とだけ述べておきます。
なお、和語系意味世界の特徴を俊成が「海」と「空」の景観でもって表象したとして、先の一文につづけて著者が抜き書きしている古来風躰抄の一文は、「なかなか深く境に入りぬるにこそ、虚しき空の限りもなく、わたの原波の果も究めも知らずは覚ゆべき事には侍るべかめれ。」(日本古典文学全集版の現代語訳では、「かえって深い和歌の境地にはいってしまうと、大空が無限であるように、限りなく、大海の果ても際限もわからないように、果ても極みもわからないものと思わなければならないことのようである。」)というもので、ここに出てきた「境(さかひ)」(和歌の境地)という語彙が、「心地」と並ぶ「意識フィールド」論文のもう一つのキーワードになります。
(かの「声字実相義」の空海を想起させ、そして、「空」は形相世界における言語の、「海」は質量世界における言語のあり様にそれぞれ対応しているのではないかといった連想を誘う井筒豊子の書きぶりが気になります。が、これは深読みが過ぎるというものでしょう。)
■有心体と有心、あるいは遡行的志向性
さて、これより「意識フィールド」論文の内部に立ち入って考察していくわけですが、その際、井筒豊子の論述の流れとは真逆の方向で、つまり、仮名序から俊成、そして定家にいたる話題の展開に沿うのではなく、最終到達点(定家歌論における「有心」と「有心体」)から初発へと向きを変えて、いわば順行ではなく遡行のかたちで、その議論を思い切って縮約することにしたいと思います。
というのも、この論文は、順を追って継起的、論理的に腑分けされていく、いわば通時型(もしくは統辞=シンタックス型)のそれではなく、最初から一挙に顕わになった全貌が、しだいに肉づけされ細部が充填されていく、共時型(もしくは遊動=アソシエイション型)の論述スタイルをとっていて、これをそのまま忠実になぞっていくと、(「春の花を惜しみ、秋の紅葉をたずね、人を恋い、といった和歌的な、てんめんたる色と香にむせぶ濃密な…ひときわ鮮冽な色相界」を思わせる)その文章に耽溺し、すっかり絡めとられ、径を見失いそうになるからにほかなりません。
(安田登氏が『異界を旅する能 ワキという存在』や『あわいの力 「心の時代」の次を生きる』で、能では、(あの世からやって来る)シテは「遡行する時間=死者の時」を生き、(あの世とこの世の「あわい」を生きる)ワキはこの世の「順行する時間=人の時」に縛られていて、このシテとワキが出会うと、遡行する時間と順行する時間が交わり、渾然一体となり、やがて「いまここ」が昔になる、つまり「いまは昔」の現象(神話的時間)が生じると論じていますが、それとちょうど同じような仕方で、井筒豊子の和歌論三部作の要石になると思われる「意識フィールド」論文を「いまここ」でアクチュアルに立ちあげてみたいという、己の非力を顧みない不遜な思いが頭をよぎっています。)
※
言語のシンタックス的側面に対するアソシエイション的側面の機能的優位という、和歌的言語フィールドにおけるその特徴的な機能構造は、「意識フィールド」論文では、というよりそこで論定される定家歌論にあっては、次のように変奏されていきます。(「有心」と「有心体」の概念をそれぞれ広狭二様に区分したのは私=中原の独断で、少なくとも井筒豊子が明示的に論じているわけではありません。)
1.和歌の詩的言語としての「詞」と(詞が「その音声言語や文字言語の現象的形姿の周辺に、艶や匂のように、纏綿させている」ところの)無分節・不可視の美的価値である「余情」を構成要素とする言語のフィールド展開において、「詞」がもっぱら「余情」そのものの喚起的醸成の有効な手段として機能すること。(=狭義の「有心体」)
2.「詞」と「余情」からなる和歌的「言語フィールド」と、そのような和歌的言語現象の機能的創造主体としての(つまり、これを「構成する」ところの)意識空間──すなわち「思ひ」(「時間的・継起的(全体としては統辞的な)展開を持つ言語的意味分節機能、いわば〝内的言語〟」)と「情」(「無時間的・無分節的飽和充実の事態として現成する〝情[こころ]〟」)からなる「意識フィールド」──とにまたがって、「情⇒余情」(無分節的現象展開)の系統が「思ひ(内的言語)⇒詞(外的言語)」(意味分節的現象展開)の系統よりも美的価値としては上位に置かれること。(=広義の「有心体」)
3.和歌的「意識フィールド」の創造性と和歌的「言語フィールド」の創造性との同定(「こころ=ことば」)、すなわち(文字化や音声化による)外的言語(詞)が成立するのに先行して意識フィールドにおける内的言語(思ひ)が生起している筈であること。(=狭義の「有心」)
4.和歌的創造主体の真の探究は(「意味的現象界」それ自体であるところの)意識フィールドを超出して「言語的現象現出の本元」へと、つまり意識フィールドそのものを生起させる発出源泉たる「超越的非現象」(後述の「心地」)への「遡行的志向性」によって可能となる筈であること。(=広義の「有心」)
■思ひから詞へ、情から余情へ
ここは肝心なところなので、下手な縮約で済ますのではなく、実地に井筒豊子の文章を引いておくことにします。
まず、毎月抄に見られる定家歌論のエッセンスと思われる事柄(広義の「有心」)が述べられた箇所から。文中の「一境に入り伏し」は毎月抄の「[有心体の歌は]よくよく心をすまして、その一境に入りふしてこそ稀にもよまるゝ事は侍れ。」からの、また、「その根を心地に託け」は古今集真名序の「夫和歌者、託其根於心地、発其華於詞林者也。」(「それ和歌は、其の根を心地に託け、其の華を詞林に発くものなり。」)からの引用です。
引用文中の「心地」や「自照」について、その詳細は次節に譲り、ここでは、「心地」(別のところで「こころ」とルビがふられている)とは、和歌的言語フィールドや和歌的意識フィールドといった「有形無形の、現象する限りでの全現象」の「発出基盤」となり「言語的創造機能の超越的本源」となる非現象・無分節・未生の「空」の異名であり、その「心地」を発動させ現象的に顕現させる媒体もしくは媒介となるのが「自照」(即自的自己照射)性もしくは「自照」の次元領域であると、とりあえず記しておきます。
そのあたりのことが、つまり「心地」⇒「自照」⇒「意識フィールド(思ひ+情)」⇒「言語フィールド(詞+余情)」と(「こころ=ことば」の四つの次元もしくは階梯と二つの系統にわたって)展開する定家歌論のダイナミクスが、次の文章ではより詳細に叙述されます。
(ここで、註釈を一つ挿入します。(文中の「一瞬一瞬に新しい不可逆性に於いて現象するところの、意識磁場の位相展開」云々は、いかにもベルクソンの「持続」を想起させます。が、このことはここでは措き)、第26章で引いた『フッサール 起源への哲学』のなかで、斎藤慶典氏が、「私」は世界が現象することの媒体なのであって、世界が現象するとき、それは「いま・ここで・現に」この「私」自身のもとででしかない、と論じていたときの、その「私」に相当するのが、井筒豊子がいう「自照」的存在の意識性にほかならない。私は、そう考えていいと思っています。じつは、この、超越的非現象の「空(ヴァーチュアリティ)」=「心地」と現象世界を媒介する「あわい」もしくは「ミーティング・プレイス」、すなわち「自照」の次元領域と俊成の「境」や定家の「一境」との同定こそが、「意識フィールド」論文の眼目となるアイデアにほかなりません。)
最後に、和歌の意識フィールドと言語フィールドとの関係に説き及んだ文章を引いておきます。
■心地と空、境と自照
話題が前後してギクシャクしますが、ここであらためて、「心地(こころ)」や「空」、「境(さかひ)」や「自照」性といった、「意識フィールド」論文の鍵となる概念群をとりあげます。
古今集仮名序をふまえて、俊成は、「人の心を種としてよろづの言の葉となりにければ、春の花をたづね、秋の紅葉を見ても、歌というものなからましかば、色をも香をも知る人もなく、なにをかは本の心ともすべき」(古来風躰抄)と書きました。この「本の心」が何を意味するのかをめぐって、それは、「心的現象」(意識フィールドにおける現象)や「言の葉」(言語フィールドにおける現象)が生起してくる大本となる「かくされた本元」、すなわち古今集真名序にいうところの「心地」にほかならないと井筒豊子は解釈します。しかもそれは、単に仮名序の和語「こころ」に相応するものとして縁語的、装飾的に用いられた漢語ではなく、仏教用語としての「心地」であると。
俊成は、ここに述べられた意味での森羅万象の本源たる「本の心=心地」(未発の非現象)を、天台止観の「空・仮・中」の三諦のうちの「空」ととらえ、「現象顕現(仮)の次元に(それも、その万朶なる分節・分別の十全なる展開に於て)非現象的本元(空)を観る」という「〝中〟的視座」そのものを和歌的創造主体の視座ととらえます。
つまり、同じく「中」的視座といっても、俊成は、「仮」的存在次元に大きく比重を傾け、「和歌的創造主体が、現象界(仮界)の豊穣きわまりない分別・分節的展開に深く積極的に参与し、かかわり合い、巻きこまれることによって」、美的創造と享楽の世界そのもの、すなわち「浮言綺語の戯れ」(古来風躰抄)に似た和歌的言説を、「空」の価値的直接提示を志向する「法文金句の深き義」(同)の世界、すなわち仏説の世界に対置させた。
ところで、「心地=空」というヴァーチュアルな非現象の世界が、いかなるメカニスムのもとでアクチュアルな心的現象の世界と結びついていくのか。
ここでいわれる「今・此処という自照的存在の意識性」、すなわち、「心地─→心機能─→ことば、という、歌論的主体性の現象展開構造に於て、超越的非現象(心地・心原)の自己顕現として現象する心機能を、ひとつの実存的意識事態として成立させる媒体となる」ものこそが、古来風躰抄や毎月抄といった「新古今時代の歌論」において、「最も重要な役割を荷って登場」したところの「境(さかひ)」である、というのが(先にも述べたように)「意識フィールド」論文の背骨ともなる着想です。
井筒豊子は、この「境」の次元領域を「心・身状況的[サイコ・ソマティック]コンテクストで叙述した、と思われる一例」として、アヴィセンナ(イブン・シーナー)の「空中人間」の比喩をとりあげます。
山内志朗氏が『「誤読」の哲学──ドゥルーズ、フーコーから中世哲学へ』で、「アヴィセンナの幽霊はやっと日本にも出るようになった」と書いているように、“nafs”(ラテン語の“anima”)をめぐるイブン・シーナーの書の邦訳『魂について──治癒の書 自然学第六篇』(木下雄介訳)が最近刊行されました。その訳書の巻頭におかれた文章で、山内氏は次のように書いています。
しかし、この山内氏の解説には少々危ういところがあるように感じます。井筒豊子が「空中人間」の比喩を、あくまで「心・身状況的」コンテクストにおいて見ていることに注目すべきだと思います。「意識フィールド」論文の叙述にもどります。
「空中人間」という自照的存在の意識性が、「今・此処」というその自照的トポスとのかかわりにおいて、「心と身」の同定を実現していること(すなわち、自照的存在の意識性=心・身的主体性)。それが、実践的・動的な型にぞくする東洋的思考における基本的主体構造の原点でもあり、さらには、「能の演技にかかわる意識空間や、舞踊や武道の心・身空間、茶道の美的空間意識」となって展開していったこと。
このあたりの議論は、私がかねてから考えてきた、歌論における「ペルソナ」の出自(永井均の「独在性の〈私〉」と尼ヶ崎彬のいう「詠みつつある心」)とその系譜(俊成の「歌の道の深き心」)、そしてまたその領域の拡がり(和歌における「物・心・詞・姿」が能役者の身体に具現化される、等々)とほぼ完全に一致する。というか、そのような問題意識をもって私は井筒豊子の論考を読みすすめているわけなのですが、しかしこのことは、ここで通りすがりのようにふれてすますわけにはいかず、またその準備も整っていません。
■境へ、遡行するペルソナ
井筒豊子が論述する俊成歌論の骨格を図式的に整理すると、「心地(=空、法文金句の世界)/境(=中)/色相界(=仮、浮言綺語の世界)」となるでしょうか。ここで、第三項(仮、和歌的言説)の第一項(空、仏説)に対する優位のうちに、あるいは少なくともその対置に、俊成的転回の意義がみとめられる。そのように括ることもできるのではないかと思います。
(ただし、第二項(中)のすわりが悪いのが気になる。たとえばこの定式を、「第一次性(質、潜在性)」「第二次性(個体的事実)」「第三次性(媒介、中間性)」という「パース三体(パースの三つの現象学的カテゴリー)」に関連づけて考えてみると、俊成の「境(中)」はパースの「第三次性(媒介)」に相当する。しかも、俊成歌論における「中」は、あくまでも「中的視座」という機能、作用、はたらきにおいて、「空」「仮」という、ヴァーチュアルな実在とアクチュアルな(もしくはフィクショナルな)存在とを関係づけていくのだから、空、仮、中をおなじ土俵(次元)に並置するのはおかしい。いや、空仮中の三諦は空観・仮観・中観の三観に通じているのだから三項鼎立は可能で、そもそも「中」を「空」と「仮」の媒介作用(中的視座)ととらえるのがおかしい。
あるいはまた「物(よろづ)/心(ひとのこころ)/詞(ことのは)」の「貫之三体」や「ル・レエル/リマジネール/ル・サンボリック」の「ラカン三体」、はては「欲動(無意識)/深層のパトス(潜意識・下意識)/表層のロゴス(表層意識)」の丸山圭三郎の構図や「地=欲動/海=パトス/空=ロゴス」の貫之=丸山三体と「俊成三体」との関係如何、等々の自問自答がとめどなくつづき、収拾がつかなくなっていく…。)
以上の「総括」をふまえて、ふたたび定家歌論の話題にもどります。
井筒豊子によると、俊成が、天台止観の「空・仮・中」の構造に依拠して、歌論を「外がわから」客観的に規定したのに対して、定家は、その構造内に位置づけられた和歌的創造主体の「内側に」視座を据え、特に「自照性」に重点を傾けることによって、「和語〝こころ〟を結晶核として成立するところの、あの、〝こころ〟の多重多層的‘意味領域’の全体を、いわばそのまま、‘意識領域’そのものへと転化させるのである」。
ここで「あの、〝こころ〟の多重多層的‘意味領域’」とあるのは、古今集仮名序の冒頭に登場する「こころ」が、「たま」「うら」「もの」といった和語の意味単位を類縁的関連語としてもち、また「心地」や、その現象顕現形態として真名序に登場する「思」「情」「懐」などの漢語の意味単位をも包摂しながら、和漢混交的な重層的な意味領域を実現していることをさしています。このような多重多層的な「こころ」の意味領域をそのまま、「思ひ、情、詞、余情」という「こころ=ことば」の意識領域そのものへと転化させたのが定家歌論の特質である。これが井筒豊子の所論です。
また、定家の歌論が特に「自照性」に強調点を置き、重点をそこに傾けたとあるのは、次のような事柄をさしています。
ここに書かれているのは「意識フィールド」論文の最終的な到達点であり、定家歌論の肝となる「(広義の)有心」のあり様にほかなりません。それは、つまり定家歌論のエッセンスとは、現象界(仮)から超越的非現象(空)へと遡行することによって、(ただし、現象界に属する人が、人であるままに現象界を超出することはかなわないので、超越的非現象に最も近接する「境」もしくは「一境」へと遡行することによって)、はじめて真の意味で主体的な和歌的「言語操作」が「可能となる筈」だというものです。定家にとって有心は和歌的言語創造の「当為」である、と井筒豊子が書いていたのも、そのような意味合いにおいてのことでした。
話が一回りしてもとの論件にもどってきました。
■だれが歌を詠んでいるのか
ここで、私は二つのことが気になっています。
ひとつは、そのような有心的機能構造のもとでの和歌創造における「遡行的志向性」の担い手はいったいだれなのか、いいかえると、だれが歌を詠んでいるのかということです。いまひとつは、「真の意味での、主体的な言語的創造操作」と「擬似的言語操作」とを区別するのはいったい何なのか、それが「(広義の)有心」すなわち和歌的言語が「その根を心地に託け」ているかどうかであるとすれば、そうした定家の歌論は、結局のところ「やまとうたは、人のこころをたねとして、よろづのことのはとぞなれりける」の貫之歌論のうちに回収されてしまうのではないかということで、私の感触では、この二つの問題は密接に関連してきます。
そもそもの発端は、(言語論的転回ならぬ)俊成的転回の意義をどうとらえるかにあります。
この論稿では、これまでからなんどとなくこの論点にふれてきました。尼ヶ崎彬、窪田空穂、寺田透、大岡信の諸氏の所説を孫引きも含めて引用し、そのうえで(いまだ形成途上の)私見を披瀝もしました。このことはいずれ、歌に詠まれた内容としての「歌の心」ではなくて、いにしへよりこのかたの「歌の道の深き心」(古来風躰抄)、すなわち尼ヶ崎彬氏がいうところの「詩的(共同)主観」をめぐる系譜学を主題的に考察する際に、あらためて整理整頓をし、決着をつけなければなりません。したがって、ここでは、あくまで井筒豊子の和歌論の文脈にそった暫定的な解釈でのぞむことにします。
仮名序の第二文は「世の中にある人、ことわざしげきものなれば、心におもふことを見るものきくものにつけていひいだせるなり」とつづきます。これに着目して、貫之はここで、現実の世にある人が心に思うこと、つまり実感としての「思ひ」を知覚物に付託して言語で表現したものが和歌であると主張しているのだと解釈すると、かの「思ひ⇒詞」系列こそが貫之歌論のエッセンスであるということになります。
これに対して、仮名序の第一文「やまとうたは、人のこころをたねとして」云々に着目し、しかもそこでいわれる「人のこころ」を世にある人の個別の心(実感)に限定せず、そのような「思ひ」や「感じ」がそこにおいて立ち現れる器のごときもの(場所としての心)と考えるならば、それは結局のところ、井筒豊子がいうところの「心地」に、つまり俊成が天台止観の形而上的構造に準拠してみいだした「本の心」にかぎりなく近づいていき、そしてこの場合の貫之歌論のエッセンスは、「思ひ⇒詞」系列と「情⇒余情」系列をともに包摂する「こころ(心地)⇒ことのは(意識現象+言語現象)」となります。
(一言ことわっておくと、「思ひ⇒詞」にせよ「こころ⇒ことのは」にせよ、それはあくまで「歌の思想」(吉本隆明)、和歌の本質論としての規定なのであって、現実の貫之が数多くの屏風歌を残した歌の職人であったこと、世にある人の実感や深遠な心をのみ詠んだわけではなかったことなどは、この際、直接の関係はありません。
付言すれば、仮名序に記された貫之歌論の世界では、「やまとうた」とはカミ(迦美)からのギフト(純粋贈与)なのであって、その〈哥〉の力をもってすれば、(「あめつちもあはれ知るとはいにしへの誰がいつはりぞ敷島の道」(拾遺愚草巻下・述懐)という、定家の揶揄にもかかわらず)、「ちからをもいれずして、あめつちをうごかし、めに見えぬおに神をもあはれとおもはせ」ることなど容易いわざなのです。)
私自身は、後者(器=場所としての心)を「広義の」貫之現象学の世界、前者(実感としての心)を「狭義の」貫之現象学の世界と名づけ、俊成歌論(俊成系譜学)や定家歌論(広狭両義の定家論理学)の世界との相互包摂関係を考えようとしているのですが、ここでは、つまり井筒豊子の和歌論の文脈においては、「思ひ⇒詞」と定式化される(狭義の)貫之歌論に対して、俊成が「詞⇒思ひ」という逆方向の遡行的な視座を提示し、ひいては「ことのは(仮)⇒こころ(空)」という(広義の貫之歌論を裏返しにした)和歌的構造を客観化したこと、そしてこの「俊成的転回」を引き継いだ定家がその構造の内側に視座を据え、和歌的言語創造の現場で臨場的に把握されるところの「和歌の創造主体」(「真の意味での、主体的な言語的創造操作」の担い手、もしくは言語が見る夢としてのペルソナ)をみいだしたことの二点を、はなはだ概略的にすぎますが指摘しておくにとどめます。
俊成がしつらえた歌論の構造(おそらくそれは自然記号としての森羅万象(=よろづ)がかたちづくるもう一つの「言語フィールド」に通じている)の内側において、遡行的志向性のはてにみいだされる「主体」(おそらくそれは狂女や鬼といったシテの仮面の裏側の世界に通じている)とは、それこそが定家歌論における「(広義の)有心」の実質をなすものであり、それはまた尼ヶ崎彬氏がいうところの「詠みつつある心」のことにほかなりません。そして、それはまた結局のところ(広義の)貫之現象学の世界のうちに回収されてしまう(あるいは、回収し得る)のではないか。現時点で、私はそう考えています。
■心の四つの存在次元・階梯
最後に。「意識フィールド」論文には、四つの存在次元ないし階梯における「心」、もしくは和歌における「心」の六つのあり様が示されていました。いまいちど整理すると、次のようになります。
Ⅰ 「心地(こころ)」=無分節・未発・未生の超越的非現象
Ⅱ 「境(さかひ)」=今・此処という自照的存在の意識性、「心地」と「意識フィールド」の媒介
Ⅲ 「意識フィールド」=内的現象、和歌的言語創造の機能現場
(ⅰ) 「思ひ」=意味的分節機能、内的言語、対象的思惟
(ⅱ) 「情(こころ)」=意味的無分節
Ⅳ 「言語フィールド」=外的現象
(ⅰ) 「詞」=文字・音声言語、外的言語
(ⅱ) 「余情」=無分節非形象
井筒豊子の「心」の階梯は、以前、第20章で述べた、零次性から三次性までの「心」の四つの存在様式と対応させることができます。
Ⅰ 「心0」(零次性の心)=「よろづ」すなわち物の世界との霊交によってインキュベートされる心、もしくはその集蔵体がかたちづくる「容器としての心」
Ⅱ 「心1」(一次性の心)=「よろづのことのは」へと生長していく心、もしくは「よろづ」(森羅万象)と「詞」を媒介する「人のこころ」
Ⅲ 「心2」(二次性の心)=「見るものきくもの」に付託して表現される、「世の中にある人」が「心におもふこと」
Ⅳ 「心3」(三次性の心)=「俊成的転回」を介してかたちづくられる「容器としての詞」のなかで、修辞的に表現され象徴的に形象化された「姿」
この区分でいうと、定家の「有心体」は、狭義では、三次性の「心3」の領域において「詞」がもっぱら「余情」喚起の手段として機能すること、広義では、二次性の「心2」と三次性の「心3」とにまたがって、無分節的な「情⇒余情」系統が意味分節的な「思ひ⇒詞」系統よりも美的価値として上位に位置づけられることと定義できます。
また狭義の「有心」は、二次性の「心2」における意識のフィールド展開(「思ひ」+「情」)と、三次性の「心3」における言語のフィールド展開(「詞」+「余情」)とを同定し構造的に直結させること(こころ=ことば)、別の言い方をすれば、三次性の「心3」の領域における外的言語の成立に先行して、二次性の「心2」の領域において内的言語が生起していなければならないことと規定できます。
そして広義の「有心」は、二次性の「心2」がじつは一次性の「心1」の媒介作用を通じて(「心2」として)現象顕現したところの零次性の「心0」にほかならないこと、同様に、「真の意味での」和歌的言語の創造主体は、一次性の「心1」への遡行的志向性を通じて見出されるものでなければならないことと規定することができます。
ただし、これらの定義や規定は、私の理解では、というより私の(勝手な)語彙体系のなかでは、あくまで「思ひ⇒詞」(狭義の貫之現象学の系統)と「情⇒余情」を包摂する「こころ⇒ことのは」という広義の貫之現象学の世界での物言いにほかなりません。
俊成や定家、とりわけ広義の定家論理学の立場からは、これと異なる論理体系のもとでの定義や規定がなされるはずで、それはおそらく「心」とパラレルな「詞」の四つの存在様式、たとえば「詞0」から「詞3」へいたる(死人のコトバから狂人のコトバへいたる、といってもいい)四つの次元・階梯にまたがるものになるでしょう。そしてそれはまた、井筒俊彦の言語哲学の基本テーゼを言い表わす表現を借りて、「存在はコトバである」と総括できる思想的立場にたつものになる。これが、現時点での私の予想です。
★プロフィール★
中原紀生(なかはら・のりお)1950年代生まれ。兵庫県在住。千年も昔に書かれた和歌の意味が理解できるのはすごいことだ。でも、本当に「理解」できているのか。そこに「意味」などあるのか。そもそも言葉を使って何かを伝達することそのものが不思議な現象だと思う。
Web評論誌「コーラ」22号(2014.04.15)
<哥とクオリア>第28章:言語・意識・認識(意識フィールド篇)(中原紀生)
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2014 All Rights Reserved.
|
| 表紙(目次)へ |