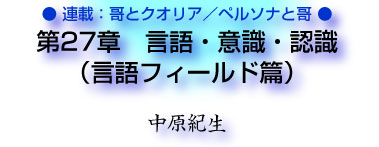|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「La Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
|
■井筒豊子の和歌論三部作
日本古典文学、とりわけ古今、新古今をめぐる言語哲学的意味論。この、実現されなかった井筒俊彦の和歌論を「類推」させる仕事として、若松英輔氏は『井筒俊彦──叡知の哲学』で、次の五つの事例をあげていました。
その第一は、千載集における幽玄の復活を論じ、和歌の蘇生を、そして同時に和歌における自覚的な伝統の樹立を考察した風巻景次郎の『中世の文学伝統』、(風巻景次郞いわく、「だから私は『千載集』の抒情調をもって幽玄であるということにしよう。そこで『千載集』が『古今』の正調に復したというのは、つまり幽玄の調を打ち立てたことにほかならぬのである。ただ『古今集』と『千載集』とではどこがちがっているのであるかといえば、それは『千載集』は、幽玄という如きことを「詩」の必要条件として要求する心の生んだものであったということである。『古今集』にはそうした意識はまだ成立していないのである。(中略)和歌がこのようにして、蘇生したのであるが、同時にそれは自覚的な伝統の樹立であったわけである。伝統は、失わんとするが故に、改めて愛することを強いられた心に樹[た]てられる。『千載集』はあらゆる意味において、中世和歌伝統の淵源となった。ということは中世の「詩」の源流となったということである。」(『中世の文学伝統』第三節))、第二、第三が、佐竹昭広の論考「『見ゆ』の世界」と白川静の万葉論、第四に、井筒俊彦自身による「存在体験」としての新古今の「眺め」論、そして最後が、井筒豊子の和歌論三部作で、若松氏によると、その論考群は「実現されなかった夫俊彦の仕事の展開を類推させる論拠」となっており、「一読するだけで、二人の間に「哲学的意味論」をめぐる深い意見交換があったことが分かる」。ここに、三つの論文のタイトルとその初出を掲げておきます。
○「言語フィールドとしての和歌」(岩波書店『文学』52巻1号、1984年1月)
○「意識フィールドとしての和歌」(岩波書店『文学』52巻12号、1984年12月)
○「自然曼荼羅──認識フィールドとしての和歌」(『岩波講座東洋思想16 日本思想2』1989年3月)
以下、「言語フィールド」論文、「意識フィールド」論文、「認識フィールド」論文と、順次、発表順にその中身を見ていくとして、井筒豊子の特異な(叙述の方法、流れが、それが叙述している当の思想の内容と動きをそのかたちにおいて模倣している、とでも言えるような輻輳した)文体が、いや、文体というよりは多重多層に織り重なっていく思考の生理、その独特の息遣いのようなものが、文面を透かして最深部から、尋常でない緊張感、臨場感をもって切迫し、読みかえすたび、以前は見えなかった異なる相貌が立ち顕われて収拾がつかず、全体を俯瞰し要約整序することなどかなわぬこととなるので、ファイルを圧縮して容量を小さくする、といった意味での(祖述ならぬ)「粗述」に徹するしかないと思ってはいるものの、それでも、その作業に先だちあらかじめ述べておきたいことがあります。
それは、「言語フィールド」「意識フィールド」「認識フィールド」と名づけられている、井筒豊子の和歌論の機軸をなす三つのフィールドの関係をどうとらえればよいのかということで、それこそまさに、三部作の読みこみを通じて、私自身がその解をつかみとっていかなければならない課題にほかなりません。
(私はこのことを、「ル・レエル/リマジネール/ル・サンボリック」のラカン三体や「物/心/詞」の貫之三体に関連づけ、さらに、井筒俊彦の『意識と本質』や吉本隆明の『言語にとって美とはなにか』、また、吉本隆明が同書で「現象学の方法をほとんど完璧に国語研究に土着させた」と書いた時枝誠記の『国語学原論』、さらにその「時枝のかんがえを修正」したとされる三浦つとむの『日本語はどういう言語か』などの議論にも接続させながら、あれこれ考えをめぐらせたいと目論んでいるのですが、それはそれとして)、ここでは、そもそも「フィールド」という概念はいかなる出自をもち、はたしてどのように規定されるべきものなのかについて、あらかじめ一瞥しておきたいと思います。
■フィールドという概念をめぐって
フィールドという言葉そのものは、以前(第23章で)、井筒俊彦の意味論のエッセンスを、「意味論序説──『民話の思想』の解説をかねて」からの抜き書きというかたちで整理した際、たとえば、「意味構成要素の有機的集合体としての意味フィールド」のような用例とともに出現していました。
いわく、意味論があつかう「意味」とは、一つのシニフィアンに一つのシニフィエが対応する、といったような概念的・抽象的かつ一義的なものではなく、あたかも「鈴生りの果実のギッシリ詰まった一房」のごとく、様々に異なる意味構成要素が互いに交錯し、多重多層に結び合う濃密な有機的全体であり、「言い換えれば、ここでは「意味」はひとつの有機的フィールド構造としての内部分節的拡がりなのであって、それを構成する個々の要素、がシニフィアンに対応する「意味」、すなわちシニフィエ、なのではない」(『読むと書く』)。
意味論的意味のフィールド構造の説は、井筒俊彦自身が「有機体」の語で形容し、また「鈴生りの果実のギッシリ詰まった一房」の比喩をもちだしているように、生物学的な対象や概念、たとえば多細胞生物のようなものをイメージすると分かりやすいかもしれないのですが、私は、(好みの問題ですが)、これを数学や物理学の対象、概念になぞらえて考えています。
数学に、「群」(group)・「環」(ring)・「体」(field)の理論があります。このうち「体」とは、大雑把にいうと、有理数、実数、複素数のように加減乗除の四則演算が可能な集合のことですが、これを「援用」して、読む・書く・話す・聞くといった言語運用に関する四則演算が自由におこなえるか、意味や表現、等々の言語機能が過不足なく定義された対象領域のことを、井筒俊彦、井筒豊子は「(言語)フィールド」と呼んでいるのだ、と考えてみる。
そこまでいくと「悪乗り」がすぎるので、物理学にいう「場」(field)の理論、そのうちとくに、電場、磁場や重力場のような、電磁気力、重力といった力の強さと向きの空間的な分布状況を示す「ベクトル場」の概念を「参照」して、意味論的意味フィールドの実質を考えてみる。これなら、あとあとの「応用」の可能性も広がるように思うし、なによりも井筒豊子自身が、「磁場」という語に「フィールド」とルビをふっている例があることからも妥当ではないかと思います。(田邊元の種の論理につながる「テンソル場」という概念に準拠しても面白いと思うのだが、これは私にはよくわからない。)
その実例は、たとえば「意識フィールド」論文のほとんど肝にあたる次の文章に見ることができます。「意識空間に、意識磁場[フィールド]そのものの力動的展開として生起するところの、内的意味の分出機能、いわば〝内的言語〟現象をひとつの対象的事態として臨場的に把握し、それを和歌的言語創造のコンテクスト内で提示し、それを歌論の中心機軸として提起している、という点で、『毎月抄』は特異である。」
いまひとつ、こんどは『意識と本質』での用例を挙げるならば、第25章で抜き書きした、芭蕉の「瞬間のポエジー」をめぐる文章に、「実存的邂逅の場[フィールド]」と「場」を「フィールド」と読ませる箇所がありました。ここでは、それに先立つ同様の用例(ただし、そこでいわれる「場」は「磁場」のこと)を引用しておきます。
(余談になるが、井筒俊彦晩年の『東洋哲学覚書 意識の形而上学──『大乗起信論』の哲学』に「言語磁場」という語が見られる。それは、「同一の言語磁場に、二つの異なる意味領域が隣接すれば、両者相互の間に働きかけが起るのが通例」で、もし一方が強勢ならば、他方の劣勢のものは限りなく強勢のものに近づき、内的変化を起こし、時には同化されてしまうのであり、「このような意味領域の内的変化または同化現象が、すなわち、意味分節理論の観点から見た「熏習」現象である」、といった議論のなかにでてくる。
そもそも、井筒俊彦が同書でくわだてた「東洋哲学全体に通底する共時的構造の把握」の「共時的構造」、あるいは『起信論』のテクストの特徴のひとつとされる「思想の空間的構造化」の「空間的構造」、これらの語彙がさししめしていたのが、実は、強度と志向性をもった力のベクトル場すなわち「フィールド」のことだった。)
以上で、井筒豊子の和歌論三部作の実地検分に先立つ序説的な考察を終えることとし、その最後に、先に述べたあとあとの「応用」に関連する(すこし先走った)話題をとりあげます。
吉本隆明著『心的現象論序説』に、原生的疎外と純粋疎外という二つの心的領域をあらわす概念がでてきます。「原生的疎外」とは、無機的自然にたいする有機体(生命体、生物)の異和をいい、これはフロイトの「生の欲動」にあたります。原生的疎外の心的領域は、同じくフロイトの「エス」に相当するものとされています。そして、原生的疎外の「ベクトル変容」として想定されているのが「純粋疎外」の心的領域、すなわち「心的現象がそれ自体として存在する‘かのような’領域」です。(角川文庫改版解説で三浦雅士氏は、これら二つの心的領域の関係をめぐって、「物質から生命へ(原生的疎外)、生命から言語へ(純粋疎外)」と表現している。)
以下、(現象学的還元との関係にもふれた)吉本隆明の文章を抜き書きしておきます。
■言語フィールドとしての和歌
さてこれより、井筒豊子の和歌論三部作を実地に見ていくことにします。
まず、「言語フィールド」論文では、ウィリアム・ジョージ・アストンという、アーネスト・サトウと同時代の学者外交官が著した『日本文学史』がとりあげられ、そこで披瀝された和歌批判の論を、(徹底して西洋詩のパラダイムに準拠し、和歌をその変異態と見る立場からなされた)「誤読」として、ただし、それが提示する和歌の(あくまで、西洋詩を不変・普遍の「イデア」と見た場合の)「欠落」が、否定的、逆説的なかたちで、和歌に特有の整合的構造を示唆し暗示しえている、そのような意味での「創造的誤読」として論じています。
和歌に関するアストンの立言(井筒豊子によるその要約)は、以下の三点です。
1.極端な短詩型
形式、内容、ともに、和歌の機構はまことに単純至極であり、その展望[スコープ]が、極端に狭隘であること。要するに、和歌は、情動表出をもっぱらとする一種のエピグラム、としで規定し得ること。
2.装飾語の多用
三十一音節の無押韻詩[ブランク・ヴァース]という、その矮小さにもかかわらず、‘もじり’言葉風の修辞的技巧を弄し、それを多用すること。
3.自然の事物事象の多出
主題選択は、ほとんど全面的に、外的自然界の事物・事象の美観に偏していること。
一言で言えば、不可思議で奇妙な「貧困」と「過剰」、すなわち、三十一音節という狭隘な限界や自然の事物事象、情動表出というとぼしい素材・手段、そして装飾語句の多用。物語り和歌もなければ教訓詩的和歌もなく、哲学和歌も風刺和歌も欠落している。象徴表現や「抽象概念の人格化」とも無縁で、西洋詩と比較して想像的能力に欠けている。アストン自身の要約によれば、「和歌は、主として、それの持つ(否定的)限界性に於て、その特質を提示する。云い換えれば、それが何を有っているか、ではなく、それが何を欠いているか、という点で、和歌は、その、いちじるしい特性、を示すのである」。
これに対して、著者は、「和歌には和歌の、独自固有の、美的整合構造が存在する」という仮定にたって、その議論を展開していきます。一方で脱落遺漏が存在し、他方で過剰が見られるという和歌の言語的特殊形式を、否定的限界や障害と見るのではなく、そうしたアストンの立論をいわば逆手にとることによって見出される、和歌に固有の構造的整合軸の観点から、それらの特徴を、機能的有効性と必然性をもった肯定的要素に転換させようというわけです。
議論の本筋から少しずれることになるかもしれないのですが、ここで、「構造的整合軸」とは何かをめぐる文章を抜き書きして、著者の思考の息遣いのようなものを体感しておきたいと思います。引用文中、「文化的準拠枠」とあるのを「構造的整合軸」と読みかえれば、当面の議論につながります。
それでは、和歌に固有の中空的機能軸「X」とはなにか。著者はここで、和歌の二側面、というよりは広く、言語一般に妥当する「シンタックス」と「アソシエイション」の二つの側面に言及します。(こまかい註記をひとつ。シンタックスを水平の線的時間軸上に位置づけるのは、より精確に言えば、以下の要約で「水平」という語彙を用いているのは、アソシエイションを「垂直」の次元に位置づける著者の議論に触発された、私=中原の勝手な用語法であって、著者のオリジナルな言葉遣いではない。)
◎シンタックス:線的、時間的に水平展開する語の統辞的側面
言語の本来的、第一次的性質である、語の「統辞組織」(シンタックス)の側面。いわば「水平」方向の時間軸にそった線的、継起的な機能展開。「先行する各語が、その痕跡を留保しながら、しかも、次々と自己を消去し、その痕跡と残像を重ね繰り延べてゆくことによって、線的に、契機的継続として、展開してゆく」。
◎アソシエイション:場的、無時間的に垂直展開する意味単位の連鎖連合的側面
同一の統辞組織上に収束的に成立している、意味単位相互間の同時的「連鎖連合組織」(アソシエイション)の側面。いわば「垂直」方向の空間軸にそった面的、共時的な地平展開。「各自固有の意味領域の射程を超出して、可能的な、存在する限りの意味単位の──部分的重複によって累畳的に展開するところの──その意味領域づたいに、次々と網目状に、そして波紋を画くように、意味の余韻と余影を伴いながら、拡散的に展開し、その連鎖連合は、可能的には、言語的に分節された意味次元の全地平を遍行し、その果てにまで到達する」。
以上の道具立てをつかって、著者は、和歌特有の整合的構造とは「シンタックス」に対する「アソシエイション」の機能的優位性である、と規定します。「つまり、意味単位の分節・連鎖、という、無時間的・空間的機能展開の側面に、不均衡なほどに重点を傾けたような、特殊な機能構造の上に成立しているのが、和歌的言語構造であり、そして、それが、和歌的言語のフィールド展開、であり、和歌に独自、固有の、和歌的言語フィールド、である」。
事実、和歌的詩語による「統辞的側面」は、ほとんど第二次的な役割しかになっておらず、極論すると、その統辞組織は、どこまでも拡散してゆく意味単位の連鎖連合をかろうじて拘束し凝固させるための、いわば凝固剤の役割を果たしているにすぎない、とすら見受けられる場合がある。
この「和歌的言語のフィールド的機能構造」の視点から、アストンが「不可解な制限、欠落、あるいは過剰」として注目した、和歌の三つの特徴について再考してみると、それらこそが、まさに、和歌に固有の構造を整合的に支え実現している三つの主要軸となっていることがわかります。以下、著者の議論をかいつまんで紹介します。
1.極端な短詩型
「和歌の統辞組織の、継起的、時間的展開の途上に出現する個々の語、各個の意味要素の全てが、共時的同一次元に、しかも、──比喩的表現をすれば──いわば、創造主体・鑑賞主体の視座から見て垂直の等間隔に散開し、各語、各意味要素が、全て俯瞰的展望下の複数焦点として一望されるような、構成を取ることが、言語フィールドの一単位の成立、実現を可能とする重要な条件であるとすれば、三十一音節の短詩型は、むしろ、多分、最大[マクシマム]に近い規模であるかも知れない。少なくとも、決して最小の規模とは云い難いだろう。」
2.装飾語の多用
和歌における装飾語群の機能は、(水平線上の)意味の統辞的展開をぼかし緩和し押え、それと同時に、(垂直方向における)意味の無時間的・遊動的なフィールド展開を助長することにある。かけことば、枕言葉、縁語、みたて、等々の修辞修飾的語句は、意味の流動的多様性・重層性を醸成するのはもちろんのこと、一文の統辞的意味構成にたいして遠心的、拡散的に働くという機能的役割を果たすことによって、和歌の「言語フィールド性」を成立させ、広大な意味連鎖の拡散的伝導を実現している。
3.自然の事物事象の多出
自然の事物、事象、事態を示す語の意味単位は、容易に物象化され、存在分節単位に直結する傾向をもつ。しかも、事物事象の存在空間そのものをも随伴的に喚起することで、和歌の背景となる外界の場的、空間的な延長展開を容易に喚起する。その結果、和歌の言語フィールドは、自然界と呼ばれる外的空間を背景にもつ「認識空間」と、相互喚起的、相関的に関与することとなる。
以上の、「和歌的詩的言語の構造構成的特殊性」をめぐる分析は、「和歌歌人の創造的主体から、一応、切りはなされた形で成立しているところの、いわば、客観的、対象的な、言語構造的側面からのアプローチ」である。「和歌的言語フィールドの特殊構成は、実のところ、其処に、和歌的創造主体が関与することによって、はじめて、より精緻な、独自の、その構造的全貌の真面目を、私共に垣間見せるのである。」
著者は、最後にそのように記し、藤原定家の「毎月抄」に展開される「こころ」と「ことば」、「詩的主体性」と「意味分節」の関わりの世界、すなわち「詩的創造主体の意識に生起する言語の現象的発出、発生と、その展開の経路」が、一人の天才詩人によって独創的に把握されていることに言及し、「未完」の稿を閉じます。定家歌論の話題は、三部作の第二、「意識フィールド」論文に引き継がれます。
(詩的創造主体の話題に関連して、「極端な短詩型」をめぐる先の引用文にでてきた比喩表現、すなわち「創造主体・鑑賞主体の視座から見て垂直の等間隔に散開し、各語、各意味要素が、全て俯瞰的展望下の複数焦点として一望される」云々は、とりわけそこで用いられる「俯瞰」や「一望」という語彙は、(すぐ後で言及する「遠望」の語とともに)、古今、新古今における「眺め」の意識主体的態度を論じた井筒俊彦の和歌論を想起させる。
また、自然の事物、事象、事態を指示する語が、概念化され典型化されたものであればあるほど、和歌の言語フィールドに「現象空間的背景の拡がり」や「時間流動の遠望的背景」を附与するという議論は、井筒俊彦が「あまりに明確な輪郭線で区切られた「本質」的事物の、ぎっしり隙間なく充満する…マンダラ的存在風景」と形容した古今的和歌の世界を想起させる。が、これらのことはいずれ三部作の第三、「認識フィールド」論文をとりあげる際、あるいはその後、あらためて考えてみたいと思う。)
■二つの実例、超絶技巧と認識の転換
井筒豊子の「和歌的言語フィールド」の説は、おそらく、(和歌を「むこう側」にあるものとして外から眺め、解釈鑑賞するのではなく)、和歌を「こちら側」にあるものとして読み、玩味賞翫し、また自ら詠む立場からは、共感をもって受け入れられるのではないか。私はそのように感じました。あるいは、古典和歌、とりわけ古今集の和歌が観念的、技巧的で知的遊戯の類に属するものと見られてきたことに対する、説得力のある反論になりえているのではないかとも。
たとえば、「「空に知られぬ雪」とは駄洒落にて候。「人はいさ心もしらず」とは浅はかなる言ひざまと存候。」(正岡子規「再び歌よみに与ふる書」)とか、「昔の和歌に巧妙な古歌の引用をもって賞讃を博したものがあるが、この種の絵[美術院展覧会に出展された作品]もそういう技巧上の洒落と択ぶ所がない。自己の内部生命の表現ではなく、頭で考えた工夫と手先でコナした技巧との、いわばトリックを弄した芸当である。」(和辻哲郎「院展日本画所感」)などと評されることに対して、そのような、いわば水平的表層にあらわれた和歌の「統辞的側面、シンタックス」にのみとらわれていては、和歌の心髄に迫ることはできない。いわば垂直的深層における「意味単位の連鎖、アソシエイション」にまで達するのでなければ、古典和歌の髄脳はつかめない、といったようなかたちで。
(ここで、「水平」を目に見える、もしくは「頭で考えた工夫と手先でコナした技巧」が弄される「表層」と組み合わせ、「垂直」を不可視の、もしくは「内部生命」の現象が遊動的に連鎖連合する「深層」と組み合わせたのは、私=中原の独自の用語法であって、井筒豊子のそれではない。)
ただ、井筒豊子の筆致は、(自己が自己を触発し、自己を高みにつりあげていく)自己牽引的な特性をもっていて、つまり、焦点化される語の指示対象の個別性、現実的具体性をぼかし、しかも、その対象化された世界としての、意味空間的背景の拡がりを喚起的、示唆的にもたらすといった特殊な機能を発揮するので、頭では直観的に正しいと思えるものの、感覚的にはいまひとつ腑に落ちきらないところが残ります。要すれば、実例がほしい、ということです。
「言語フィールド」論文を読みすすめながら、私が想起していたのは、たとえば、(第19章でとりあげた)藤原俊成の「七夕のとわたる舟の梶の葉にいく秋かきつ露のたまづさ」をめぐる『新々百人一首』の読解でした。丸谷才一はそこで、この歌にしつらえられた二層の縁語関係と、二種の音声的反覆の技巧を指摘しています。縁語関係の第一の層は、「七夕」「と(門)」「渡る」「舟」「梶(櫓・櫂)」とつながる「天の川」の系列で、第二の層は、「梶の葉」(紙の原料)「書く」「露」「たまづさ(手紙)」とつづく「恋文」の系列。また二種の音声的反覆とは、「梶」「秋」「書き」のk音と、「七夕」「と渡る」「つ」「露」「たまづさ」のt音。「この哀れ深いt音の連続は水のしたたる音であつた。宇宙の水である銀河の星屑[天の川の系列]は、神話と伝承と祭祀によつて、人間の水としての泪[恋文の系列]に結びついてゐる。」
このような、音節にとどまらず単子音レベルにまでおよぶ精妙きわまりない響きの聞き分けをふまえた超絶技巧が可能となるのは、たしかに三十一音節をマクシマムとする和歌ならではのことなのではないかと思えてきます。(余談ながら、幸田露伴の「音幻論」(『露伴随筆集(下)』)に、五十音図のカ行とタ行の「親しかるべき」関係をめぐり、「kの声」が「tの声」に遷りゆく例を示した個所がある。「幸」は「サキ」でもあり「サチ」でもある。「ヤキモチ」と「ヤキモキ」は同じ語であろう。易の「乾」はすなわち「天」だ。「ch」は「極軟かな時にはシと発音し、少しく硬くなるとチとなり、もつと硬ければキ・クとなる」等々。)
いまひとつ「実例」をあげます。以前(第21章で)引用した、三浦つとむ著『日本語はどういう言語か』の文庫解説で、吉本隆明は次のように書いていました。
ここで言われる「認識の転換」の具体例は、『言語にとって美とはなにか』の第Ⅲ章「韻律・選択・転換・喩」で、現代短歌の作品群を素材とする表現解析のかたちで示されています。(そこにはまた、「伝統的な短歌の美の特質である変り身のはやい転換や連合」とか「短歌的な原型の複雑な転換」、「〈省略〉や転換の変り身のはやさを身上とする短歌」や「発生的には純粋叙景歌にあらわれた短歌の原型がもっている場面転換のすばやい複雑な変わり身」、等々の指摘がちりばめられている。)
それはとても美事なもので、いま、その一例をとりあげると、中城ふみ子の「肉うすき軟骨の耳冷ゆる日よいづこにわれの血縁あらむ」をめぐって、「「肉うすき」が視覚的な形容だから、作者からは誰かわからぬものの耳を見ている位置になり、つぎの「軟骨の」は触覚的だから作中の〈誰か〉がじぶんの耳を触った形容とうけとれる。このふたつの感覚としてちがった「耳」の形容によって、即物的なようにみえるこの句がじつは、即物性をはなれた構成的なものであることを暗示しえている。」、「「冷ゆる」という自動詞で作中の〈誰か〉は作者とおなじものとしてせばめられる。」と分析し、これが自由な現代詩だったら、その意味は「耳が冷たくひえてくるようにおもわれて触れてみたある日、じぶんの血縁はどこにいるのだろうか、どこにもいないのだ、ということを‘ふと’かんがえた」というほかはなく、これ以外の理解はできないはずだと指摘する。
この、「作品の言葉を、極端にいえば、一字、一字たどり、それごとに、背後にある作者の認識の動きを、推量してみる」という吉本隆明の方法は、和歌における「アソシエイション」(「個々の語、各個の意味要素の全てが、共時的同一次元に、しかも、…創造主体・鑑賞主体の視座から見て垂直の等間隔に散開し、各語、各意味要素が、全て俯瞰的展望下の複数焦点として一望されるような、構成を取ること」)の優位性を説く井筒豊子の主張につながるものだと思います。(同時に、和歌や現代短歌にかぎらず詩的作品を読む際の、いや韻文であれ散文であれ戯曲であれ、およそ言語芸術に接する際の基本的態度と普遍的方法に通じ、また、細部を大事にせよ、「文学を成り立たせているのは、一般的な観念ではなく、個別的な啓示なのである」(野島秀勝訳『ナボコフの文学講義上』)という教えにも通じている。)
■修辞から修字への転換、言語による茫漠たるホログラム
最後に、小松英雄著『古典和歌解読』の議論を引きます。
小松氏がそこで論じているのは、万葉集=素朴、古今集=観念的(理知的)、新古今集=幽玄という歌風の違いを、和歌表現の変容=叙情表現の深化の歴史と見る立場から叙述された、音節の連鎖による韻文=「言語の線条」としての短歌(万葉集)から、仮名の連鎖による韻文=「仮名の線条」としての和歌、すなわち新ジャンルの「短歌形式の抒情詩」としてのやまとうた(みそひと文字)の形成(古今和歌集)へ、そして音節連鎖への回帰(新古今和歌集)という「雅の韻文史」なのですが、このうち、井筒豊子の和歌的言語構造論に関連すると思われるのは、古今和歌集の和歌の表現上の特徴、すなわち「歌の文字」(仮名)の連鎖・線条がもたらす「複線構造による多重表現」の説と、新古今和歌集に特徴的な表現上の特徴、すなわち「言いさし」表現や本歌取りの技法ががもたらす「非結晶」の美しさ(幽玄)をめぐる議論です。以下、その素材を拾います。
まず、複線構造による多重表現について。
いわく、上代の韻文は「借字」で記録されたから、清濁、たとえば「フ」(布)と「ブ」(夫)を重ね合わせる表現技法はありえなかった。ところが、平安初期の和歌は、上代のような言語の線条ではなく、清濁を書き分けない仮名の線条であったから、たとえば、「やまたかみ つねにあらしの ふくさとは にほひもあへす はなそちりける」(山高み、常に嵐の、吹く里は、匂ひもあへず、花ぞ散りける)の第二句から第三句にかけて「しのふくさ」(忍ぶ草)を埋め込む(複線化する)ことが可能であった。和歌の表現技巧は、聴覚よりも視覚が、音声よりも仮名が優先される。言語(音声)の線条は逆行(第五句まで読んで遡って先行句の意味を読み取ること)を許さないが、文字(仮名)の線条ならそれが可能である。
ここで、仮名の連鎖、文字の線条がもたらす「多重表現の極致とも言うべき和歌」としてとりあげられるのが、「おくやまに もみちふみわけ なくしかの こゑきくときそ あきはかなしき」(奥山に、紅葉踏み分け、鳴く鹿の、声聞くときぞ、秋は悲しき)で、著者によると、この三十一文字の仮名連鎖には、ひとつは「奥山に#紅葉踏み分け」て鹿が鳴き、ついで作者が「奥山に紅葉踏み分け#鳴く鹿の声聞く」という、二種の和歌が重層的に組み込まれている。「鹿は妻を恋うてしきりに鳴き、その声に触発されて、作者もまた、愛する女性が恋しくてたまらなくなる。作者も鹿も、同じ気持ちで紅葉を踏み分けながら、やるせない恋に悩む。秋が切なく感じられるのはそういうときだ、ということである。」
(著者によると、「古今和歌集の和歌表現は、平安末期以来、[定家や宣長を含めた]歴代の歌学者たちによる誤った注釈に覆い隠されてきた」。また、「仮名の線条に基づいた和歌を現代語に置き換えることは原理的に不可能」であり、「現代日本語を含めて、いかなる言語にも置き換えることができない」。)
ところで、こうした「言語の線条から仮名の線条への転換」は、(「修字法」もしくは「字韻」(石川九楊)とよばれるべき)新たな表現の可能性を生み出すと同時に、二つの構造的欠陥を抱え込んだ。「その一つは、韻文の生命ともいうべきリズム[万葉集の五七調]を喪失したことであり、もう一つは、三十一文字の仮名の線条だけで表現しきれない部分を、しばしば詞書に依存せざるをえなかったことである。」
これらの欠陥を克服したのが、新古今和歌集の和歌表現であった。まず、上の句(五七五)と下の句(七七)の二部構成を基本とする構文の操作によって、元と末の二つの中心をもつ「五#七五(本)+七七(末)」の七五調を導入して、韻文のリズムを回復した。「また、末尾に名詞を据える言いさし形式によって、表現の完結を第三者にゆだね、また、既成の和歌と融合させる〈本歌取り〉を導入して、非結晶化が図られている。それが、幽玄にほかならない。表現を完結させる必要がなくなったから、詞書への依存も解消した。」
後段の「非結晶」をめぐる話題を二つ、いずれも本歌取りの技法にかかわるものをとりあげる。
その一、「春の曙といふ心を詠み侍りける」の詞書をもつ藤原家隆の「霞立つ 末の松山 ほのぼのと 波に離るる 横雲の空」。詞書の「春の曙」が枕草子冒頭の一節「春はあけぼの。やうやう白くなりゆく山際、少しあかりて、紫だちたる雲の細くたなびきたる。」を喚起し、第五句の夜明けの空の「横雲」が高貴な紫色に彩られ、第二句の「末の松山」が古今集の「君をおきて、あだし心を、我がもたば、末の松山、波も越えなむ」と結び付く。
その二、俊成の「たれかまた 花橘に 思ひ出でむ 我も昔の 人となりせば」が、古今集の「五月待つ 花橘の 香をかげば 昔の人の 袖の香ぞする」を本歌として取っていることをめぐって。
非結晶という語は、「シンタックス」に対して「アソシエイション」が機能的優位性をもつ和歌にあって、統辞的側面は拡散する意味単位の連鎖連合をかろうして拘束する凝固剤の役割を果たしているにすぎず、その統辞的「結晶力」が緩和されるにつれて、個々の意味要素の遊動的連鎖連合が助長される、とする井筒豊子の議論に直結している。また、表現の完結を読者にゆだねることで、一首の和歌の意味や詩的表現が「鈴なり」に無限の広がりをもち、他の和歌と融合して「言語による茫漠たるホログラム」を形成するという叙述は、井筒俊彦の意味論に通じ、そして井筒豊子の「意識フィールド」論文へとつながる導管に接続している。
★プロフィール★
中原紀生(なかはら・のりお)1950年代生まれ。兵庫県在住。千年も昔に書かれた和歌の意味が理解できるのはすごいことだ。でも、本当に「理解」できているのか。そこに「意味」などあるのか。そもそも言葉を使って何かを伝達することそのものが不思議な現象だと思う。
Web評論誌「コーラ」21号(2013.12.15)
<哥とクオリア>第27章:言語・意識・認識(言語フィールド篇)(中原紀生)
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2013 All Rights Reserved.
|
| 表紙(目次)へ |