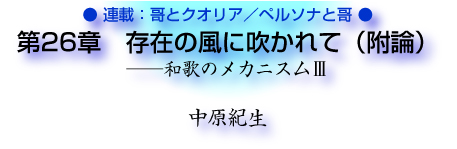|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「La Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
|
■アクチュアリティかリアリティか
前々章の最後の節に、歌を「読む」とは歌を「詠む」こと、すなわち、歌に潜むヴァーチュアルな意味(の種子)が読み手によってアクチュアルなかたち(花や実)となって「初めて」経験されることであるといった趣旨のことを論じた際、それは可能的な百ターレルが現実の百ターレルに転化するのと同じことなのだろうかと、疑問符をつけてそう書いた。
それはもちろん異なる次元に属する転換である。前者は「ヴァーチュアル/アクチュアル」の次元における転換に、後者は「イマジナリー/リアル」(本来は「イマジナリー・フィクショナル・ポッシブル・イデアル/リアル」と表記すべきところ、以下、煩雑を避けてこのように略記する)の次元における転換にかかわることだから。私はそう考えている。(そう考えたいと思っている。)しかし本当にそうなのかという疑問がつきまとう。どこかに概念の混乱もしくが誤用がありはしないだろうか。
私は、(リルケが「もの」の普遍的規定性は「ヴィルクリッヒカイト」(アクチュアリティ)の次元に成立し、「もの」の個的リアリティーは「レアリテート」(リアリティ)の次元に成立するとした、と『意識と本質』に書かれていたことに触発されて)、「ヴァーチュアル/アクチュアル」の軸を「マーヒーヤ」性(「本質」の普遍性)に、「イマジナリー/リアル」の軸を「フウィーヤ」性(「本質」の個体性)にそれぞれ関連づけて考えてきた。
そしてそこに中世スコラ哲学の二つの存在概念、すなわち「本質存在、エッセンティア」(前章で引いた『意識と本質』の文章中「本質」とよばれていたもの、少なくとも私はそのように理解してあの文章を読んだ)と「事実存在、エクシステンティア」(同様に「存在」)を重ね合わせて、「マーヒーヤ=ヴィルクリッヒカイト=アクチュアリティ=エッセンティア」と「フウィーヤ=レアリテート=リアリティ=エクシステンティア」という亜独英羅の四言語にまたがる二つの概念の系譜を思い描いていた。可能的もしくは現実的な百ターレル銀貨は前者「エッセンティア」の系譜ではなく、後者「エクシステンティア」の系譜に属するものと想定していた。
ところがハイデガー(『現象学の根本問題』『形而上学入門』、また木田元『反哲学史』『ハイデガー拾い読み』)によると、西洋の形而上学的思考はソクラテス以前の「フュシス」(生きた自然)が「エイドス、形相」あるいは「それが何であるかという存在」と「ヒュレー、質料」あるいは「それがある(かないか)という存在」に分岐したことに端を発し、これらの存在概念がそれぞれ「エッセンティア」と「エクシステンティア」に引き継がれていった。そしてこれらのうち「エッセンティア」の概念は「レアリタス」(『現象学の根本問題』によると、可能性を意味するライプニッツの「ポッシビリタス」やプラトンのイデアの概念と同じ意味)と等価であり、また「エクシステンティア」の概念は「アクトゥアリタス」(アリステレスの「エネルゲイア」のラテン語訳)と等価なものとされてきた。
ここから導きだされるのは、先ほどのものとは真逆の「アクチュアリティ=エクシステンティア」「リアリティ=エッセンティア」という系譜で、かの可能的もしくは現実的な百ターレルはここでは「エッセンティア」の系譜に属することになる。この「矛盾」を解消するためにはリルケの詩的直観とハイデガーの哲学史的考察を受け入れて、「マーヒーヤ=ヴィルクリッヒカイト=アクチュアリティ=エクシステンティア」「フウィーヤ=レアリテート=リアリティ=エッセンティア」の二系譜を確立すればよい。カントの議論は後段の「エッセンティア」の系譜に属することで決着する。
しかしそうなると今度は「マーヒーヤ=エクシステンティア」「フウィーヤ=エッセンティア」の等式に違和感を覚える。「普遍的本質、マーヒーヤ」が「事実存在、エクシステンティア」と同一視され、「個体的本質、フウィーヤ」が「本質存在、エッセンティア」に等値される。そこのところがどうしても腑に落ちない。語の表情(アスペクト)にそぐわない、というか語感として気持ちが悪いのである。
ここまで「病状」がすすんでしまうと、そもそも井筒俊彦がマーヒーヤを「本質」すなわち抽象的概念ではない「濃密な存在度をもったリアリティー」に関連づけ、フウィーヤを「存在」すなわち「この花」をただの「花」ではなく「この花」たらしめる「異次元のリアリティー」になぞらえたこと自体に「病因」があったのではないかと疑わざるを得なくなる。
もちろん井筒俊彦の議論を「マーヒーヤ=エッセンティア」「フウィーヤ=エクシステンティア」の主張として理解した私自身の読み方が間違いだった可能性はある。しかしそれでもやはり、いくら読み返してみてもそうした「誤読」は必然的だった(私にはそのようにしか読めない)と言わざるを得ないのである。(ひとつ「証拠」を挙げると、井筒自身が「本論全体を通じて、私は「本質」という語を、少くとも原則的には、一貫して西洋中世哲学の術語 quidditas(=essentia)に対応するものとして使う。」と書き、この「quidditas(あるいは essentia)、そして歴史的にその先輩にあたる」マーヒーヤが「字義的にはともに「(それは)何であるか、ということ」を意味し、その点でアリストテレスの「本質」概念に遡ることは明らかである」と書いている。それとも私の困惑は訳語がもたらす語感のミスマッチにすぎないもので、たとえば「エクシステンティア=外に出て立つこと」といった語源にまでさかのぼり考えていけば解消することなのだろうか。)
■普遍性と単独性、一般性と個別性
ひとつの「解決策」はマーヒーヤとフウィーヤ、「本質」と「存在」の関係を一義的なものと考えるのをやめることだ。マーヒーヤは「本質」であり「存在」でもある。エッセンティアと等値されることもあればエクシステンティアと等値されるのが適切な場合もある。そんなふうに(先に引いた文章中の「原則的には」という言葉を最大限に活用して、あるいは井筒俊彦自身が二つの本質、二つのリアリティに言及していることにならって)考えればいいのではないかということだ。
ここでひとつ、補助線を引く。柄谷行人が『トランスクリティーク──カントとマルクス』で導入した「普遍性─単独性」(異なるシステム=共同体間の交換=コミュニケーションにかかわる社会的で無媒介・直接的な回路)と「一般性─個別性」(同一の規則をもったシステム=共同体間の交換=コミュニケーションにかかわる被媒介的な回路)という二組の概念を借用して、「ヴァーチュアル/アクチュアル」の次元を「普遍性/単独性」の組み合わせで把握し、「イマジナリー/リアル」の次元を「一般性/個別性」の組み合わせで考えてみる(つまり「アクチュアリティ=エクシステンティア」の軸を共同体の「外に出て立つ」こととしてとらえる)。そうするとさきほどの違和感はかなり緩和されるように思う。
たとえば、井筒俊彦の次の文章。前章でも抜き書きしたものだが、先にのべた「誤読」の必然性についての決定的な「証拠」が潜んでいると思うので再度引く。
『意識と本質』の前後の文脈からは「この花」の「この」がフウィーヤ(リルケのいう「レアリテート」)に、そして一般者としての「ただの花」がマーヒーヤ(同じく「ヴィルクリッヒカイト」)に対応していることは間違いない。少なくともそのようにしか私には読めない。ところがこの文章はこの箇所で、少なくとも私に読みとれるかぎりでいえば、「即物的直視」の詩人リルケの側に、そして井筒俊彦がいうところの「存在」の側に肩入れした立場で書かれている。だから「本質」を抽象的一般的な概念的虚構物であるかのようにあつかっている。少なくともここでいわれる二つの「本質」のうちの最初のもの、「一般者、すなわち普遍的「本質」」と表現されているものについてはそうだ。
ここに先ほどの柄谷行人の二組の概念を導入してみる。そうすると「一般者、すなわち普遍的「本質」」という表現のなかで「一般=普遍」の等式によって規定される「本質」、それはすなわちマーヒーヤにほかならないのだが、この意味での「本質」それ自体のうちにも実は(「一般性」と「普遍性」という)二つの異なる相が重ね描かれていることがわかる。すなわち「一般性/個別性」の「抽象的概念」の相と「普遍性/単独性」の「濃密な存在度をもったリアリティー」の相。
井筒俊彦の文章をもうひとつ、再度引用する。
結論を言ってしまえば、「一般性/個別性」の相のもとで見られたマーヒーヤは「イマジナリー/リアル」の次元に「堕落」した形態のものであって、それはもはや「ヴァーチュアル/アクチュアル」の次元に帰属する本然の姿のマーヒーヤ、すなわち「普遍性/単独性」の相のもとで見られたマーヒーヤではない。したがって、本然の姿のマーヒーヤが「アクチュアリティ=エクシステンティア」の系譜に属するのに対して、堕落した形態のマーヒーヤが帰属するのは「リアリティ=エッセンティア」の系譜である。だから、井筒俊彦が「抽象的概念としてではなく、濃密な存在度をもったリアリティー」と書いていたのはやはり「アクチュアリティ」のことだったのだ。
(これに関連して、ハイデガーはたしか次のような趣旨のことを指摘していた。いわく、「ヴァーチュアル/アクチュアル」の軸の古層にしつらえられた「デュナミス/エネルゲイア」の概念には(「現われ出る」「おのずから発現する」を意味する「フュエスタイ」という動詞から派生した)「フュシス」をめぐるソクラテス以前の存在観が色濃く反映されていた。そして「イマジナリー/リアル」の軸はすでに「現われ出た」ものの「何であるか」を生成の外から、そして後から(制作されたものとして、フュシス=生きた自然ではなくイデア=永遠不死のものとして)眺める視線にもとづいている。
いまひとつ関連する議論を引く。木村敏は「リアリティとアクチュアリティ 離人症再論」で、離人症において失われるのは私的・主観的・一人称的なアクチュアリティであって公共的・客観的・三人称的な実在に関するリアリティではないとし、(アクチュアリティと対をなす)ヴァーチュアリティと(リアリティと対をなす)ポッシビリティとの違いを囲碁にたとえている。いわく、生身の棋士によって打たれる石はそれぞれに潜在的な働きあるいは勢いをもっている。「本来囲碁というゲームは、単なる碁石の計算可能な配列による勝負ではなく、この「勢い」の布置による勝負である」。しかしゲームが終了すると(ゲームの途中であっても、第三者が客観的に盤面を眺めたとき)碁盤の上には静止した多数の石の「リアル」な配列しか見えてこない。「そこではかつてのヴァーチュアリティが、こうも打てたであろう、という可能性に姿を変えている」。)
ここまでくると、「この花」をただの「花」ではなく「この花」たらしめるのもまた実は、文字通り「異次元のリアリティー」であるところの「アクチュアリティ」のはたらきだったのではないかと思えてくる。「何もないのではなく、何かがある」という「存在感覚」の根源には「ヴァーチュアル/アクチュアル」(「デュナミス/エネルゲイア」)の軸が、より精確に言えばその深層(潜勢態)における「力」の領域がしつらえられていて(「デュナミス」のラテン語訳「ヴィルトゥス」には「力」を意味する語[virtu,vis]が含まれている)、マーヒーヤにせよフウィーヤにせよ、エクシステンティアにせよエッセンティアにせよ、およそあらゆる存在概念はすべてその(「無」もしくは「空」とでも言うべき場所における)「力」の噴出による存在の風に吹かれて顕在化(現勢化)し、そしてそこから様々に分岐していったのだ、「この世界はそのような構造をしている」などと言ってみたくなる。
それと同時に、マーヒーヤと同様、フウィーヤにも本然の姿と堕落した形態があり得るのではないかと思えてくる。たとえばリルケが言う「レアリテート」には、堕落した形態のマーヒーヤが存在表層において折り重なる「イマジナリー/リアル」の軸の、その深層に住まいする「異次元のリアリティー」(すなわち「この花」を「この」花たらしめる本然の姿のフウィーヤ、いいかえると普遍的本質とは違う「もう一つ別の本質」)の実在に対する詩人の直観が潜んでいたのではないか。(貫之現象学に対する定家論理学の逆襲の起点として?)
※
以上で本論は終わり、以下、補遺と余録として、まず本然の姿のマーヒーヤ(アクチュアリティ)と堕落した形態のマーヒーヤ(リアリティ)の話題に関連して永井均の(最近の)議論を引き、さらに本然の姿のマーヒーヤの、より精確に言えは「ヴァーチュアル/アクチュアル」の軸の深層における「力」の領域の話題に関連して斎藤慶典の議論を引き、最後にリルケを起点とするもうひとつの存在論の世界を遠望する辻邦生の議論を引く。
■アクチュアリティかリアリティか、永井均の場合
可能的な百ターレルと現実的な百ターレルの話題は『純粋理性批判』の「神の現存在についての存在論的証明の不可能性について」と題された節のなかで、「存在はレアールな述語ではない」という高名な命題とともに登場する。(このカントが使った「レアール」という語の意味をめぐって、ハイデガーは『現象学の根本問題』で、カントの時代の「レアール」にはリルケがその語にこめた「実在的」の意味はなかったこと、レアールとは「もろもろの可能的事象一般の総体、つまり可能的な諸物のもろもろの事象内容、すなわち本質」を意味する語であるとした。)
永井均は、頭の中で考えているだけの「可能的な百ターレル」と現実に存在する「現実的な百ターレル」とのあいだの差異は、自己と他己(「私の私」と「他の私」)のあいだの差異と同種のものと扱うべきであると論じている(『哲学の密かな闘い』第2章「自己という概念に含まれている矛盾」)。いわく、私が二つに分裂するという思考実験において、分裂後になぜか私である人となぜか私でない人のあいだには、レアール(事象内容的)な差異はない。もし差異があったなら、同じ一つのものが二つに分裂して「同じ」ものが二つ存在していると言えなくなってしまうから。
かくして「他己」とはつねに「語られうる自己(レアリテートに回収されたアクトゥアリテート)」なのである。そして独在性の〈私〉もまた一般化する。〈私〉はそれが「何であるか」が語られてしまえば事象内容的にはそれとまったく同じものが他にも存在しうることになり、他者もまた事象内容的には〈私〉でありうることになって《私》が成立する。
いまひとつ、議論を引く。
ウィトゲンシュタインの『青色本』にチェスのキングの駒に紙の冠をかぶせる男の話がでてくる。「私はチェスがしたいのだが、ある人が白のキングに紙の冠をかぶせる。それによってその駒の使い方に何か変化が生じるわけではないのだが、彼は私にこう言う。その冠は自分にとって規則によっては表現できないある意味をそのゲームにおいて持っているのだ、と。私はこう言う。「それがその駒の使い方を変えないかぎり、それは私が意味と呼ぶものを持ってはいない。」」(永井均訳)
永井均は『ウィトゲンシュタインの誤診──『青色本』を掘り崩す』で、最初に大森荘蔵訳でこのチェスの駒にかぶせられた冠の比喩の個所を読んだとき、「身体が震えるほど興奮した」と書いている。ウィトゲンシュタインがここでチェスに喩えているのは言語で、かつ独我論の語りえなさを示している(批判している)のだが、私(永井)はそうは受け取らなかった。チェスは世界の比喩で冠は私の存在そのものの比喩と受け取り、かつこの比喩を新しい独我論の表現の仕方として受け取った。「冠はレアリテートにおいて表現されないアクトゥアリテートにおける差異をレアリテートの内部で表現しようとしたもの、ということになる」。
(王朝和歌を夢として読む。目を開けたまま集団で見る夢(映画)として、暗に独我論的な貫之現象学の世界を読み解く。それは「アクトゥアリテートを欠いたレアリテートの内部」における差異の表現として、あるいは「レアリテートからアクトゥアリテートへの超越」をめざす見果てぬ夢の表現として和歌を読む=詠むということなのだろうか。)
■アクチュアリティかヴァーチュアリティか、斎藤慶典の場合
永井均が語っている「アクトゥアリテート」は、木村敏が「自分であるとはどのようなことか」(『関係としての自己』)で、クオリアとは「個人と世界の界面現象」であり「個人と世界とのあいだにそのつど新たに成立するアクチュアリティ」である、また離人症患者において失われる「自己の実感」とは「世界がクオリアをおびて立ち現れている、いいかえれば私と世界のあいだにアクチュアリティが成立しているという行為的事実」にほかならないと書いている、その「アクチュアリティ」のとらえかたに通じている。
ここで私はふたたび混乱におちいる。というのも、私はクオリアを(ノエマ=事物事象=もの[res]にかかわる)リアリティの次元における「ありあり」感の問題として考えていたからだ。この「困惑」を解消する手がかりは、木村敏がクオリア=アクチュアリティを「私と世界のあいだ」に成立する界面現象であるとしている点にある。つまり、私的・主観的・一人称的なアクチュアリティが公共的・客観的・三人称的な実在に関するリアリティに先だち、そのアクチュアリティよりも先に「私」と「世界」(とおそらくは「他己」も)が立ちあがっている、そこを起点に考えてみてはどうかということだ。
このことに思いをめぐらせるうえで斎藤慶典が『フッサール 起源への哲学』の第四章3「私──アクチュアリティかヴァーチャリティか」で展開している議論が参考になると思うので、以下(私見をまじえず)その概要を記す。
「私」は世界が現象することの媒体である。世界が現象するというとき、それは他のどこにおいてでもなく〈いま・ここで・現に〉この「私」自身のもとででしかないのである。そうだとすれば、そのとき「私」のもとで現象した世界は「私」と切っても切れない性格を共有しているはずだが、その「のっぴきならない」性格のことをどのように名づけるのが適当か。
まず「リアリティ」という語について吟味してみよう。リアリティとは「現象するもの」が夢でも幻でも錯覚でもなく、もはや打ち消しがたいほどに確固として、「ありありと」現前しているさまを表現している。この「ありあり」感を私たちは「リアリティ」と呼ぶ。
だがこの言い方にはふたつの問題がある。第一に、「リアリティ」は「現象を見てとるもの」である「私」のそれ自身は現象しない半面(現象構成機能、いわば行為遂行的側面)に手が届いていない。第二に、夢や幻や錯覚、離人症のケースのように、「現象するもの」は必ずしもつねに「ありありと」しているとはかぎらない。したがって「リアリティ」という概念は、私のもとで現象している世界の「のっぴきならなさ」を捉えるのに十分なものではない。
それでは(ノエシス=行為=はたらき[actus]にかかわる)「アクチュアリティ」はどうか。木村敏によると「アクチュアリティ」とは現象を見てとる「私」の現象構成機能の作動のことであり、それが「生き生きと」はたらくことによって現象する当の世界の「ありありと」した存立が成立する(「アクチュアリティ」の作動不全によって、世界はいつも通り現前しているにもかかわらずそれらに「ありあり」感がまったく感じられなくなってしまうのが離人症)。したがって「リアリティ」概念の不十分さの第一の点は克服されている。
では第二の点はどうか。離人症が重篤化して人格の解体にまで進行したとしても、世界がもはやいかなる意味でも現象していないというわけではない。慣れない外国語で生活する場合を考えればわかるように、「アクチュアリティ」が「生き生きと」十全に作動するか否かは、現象するものを規定しているそのつどの特定の規則(言語の場合は「文法」)に「私」の身体がどれだけ順応・習熟しているかによって定まる。そして現象に立ち会うものの自己同一性が要求されるとすれば、それもある特定の社会組織の在り方(例:個人責任を重視する近代資本主義社会)と密接な関係をもっているはずである。
最後にアクチュアリティと対になる「ヴァ―チャリティ」が取りあげられる。この概念は、いまだ何も顕在化はしていないが顕在化へ向かう潜勢力(ポテンシャル)を内に孕んだ「潜在」性を意味し、アリストテレス形而上学での「潜在態、デュナミス」やアナクシマンドロスの「無限定なもの、ト・アペイロン」にまで遡る。
「ヴァーチャリティ」はいかなる「質(クオリティ)」でもない。「【それ】を指し示すのに「ありありと」であれ「生き生きと」であれ、何らかの「感じ」をもってすることはできない」。なぜなら「「感じ」とは、すでに何らかの規定がなされたところでしか発生しないからである」。
「ヴァ―チャリティ」はまったくの「無」でもない。というのも端的な「無」であれば、それにいくら規定を加えたところで、それがたちどころに「存在」へと転化することはないだろうから。それは「無」というよりはある種の「充実」なのである。世界に「実質」を与える「充満する空」。この「充満する空」と「現象するもの」=「存在」との接点にあって、前者から後者への〈いま・ここで・現に〉生じている移行を見届けているものが、この「私」なのである。
究極の問い。「私」が消滅しても世界は現象するのか。「世界がそこにおいて、そしてそこにおいてのみ「潜在態」から「顕在態」へ、「見えないもの」から「見えるもの」へと移行する[=「実質」を受け取る]「場所」である「私」の〈いま・ここで・現に〉」が消滅しても世界は現象するのか。
(斎藤慶典によると、「独我論」と訳されるラテン語 Solipsismus は「我」という意味の語を含んでおらず、この言葉は正確には「(何か分からぬその)それのみ(が存在する)」ということを言っている。「ここで現象学がみずからの基盤にして出発点と見定めた地点は、この言葉の本来の意味でのそれ、すなわち〈いま・ここで・現に〉という「現象」の直接性のみが存在するということ、簡略化して言えば〈いま・ここで・現に〉の独‘在’論なのである。」そして「驚くべきことに」(と斎藤は書いている)『省察』でのデカルトがその懐疑の極点(第二省察)ですでに「何か分からぬ私のそのそれ」と書き留めているのだ。
いま引いた文中の「独在論」という永井均から借用した表現についての注記。「氏が年来語ってきた〈私〉の「独在論」から私(斎藤)は多くの示唆を得ているのだが、私がフッサール現象学の内に見てとったものと氏が語っている事柄が重なるものなのか否か、いまだに判断がつきかねている。読者諸賢の判断に委ねると言いたいところだが、ひょっとするとこれは事柄の性質上、そもそも同じか否かを判定しうる類のものではない、と言った方がよいのかもしれない。何しろ【それ】は、何かとして規定できない以上、指示することもまたできないからである。指示の効かないもの同士を比べろ、というのは土台無茶な話だからである。」)
■余録、リルケの世界内面空間
リルケの「開かれた世界」もしくは「世界内面空間 Weltinnenraum」という概念が興味深い。(「充満する空」としてのヴァーチュアリティ。存在深層における(本然の姿の)フウィーヤとしての(リルケの)レアリテート。この二つの「本質」、二つのリアリティがかけあわされる空間。)
辻邦生著『薔薇の沈黙──リルケ論の試み』によると、「世界内面空間」は(天使的な)純粋意欲に対応して存在するものである。それは「存在と非存在を貫く存在形式」である。「生と死、内と外を貫く空間」であり、「過去も未来もない持続」である。また、「純粋意欲=欲求対象を決して所有しない、自己性を克服した純粋活動としての意欲」は、ニーチェの「力への意志」とほとんど同質の「生への意欲」といっていいものであった。
★プロフィール★
中原紀生(なかはら・のりお)1950年代生まれ。兵庫県在住。千年も昔に書かれた和歌の意味が理解できるのはすごいことだ。でも、本当に「理解」できているのか。そこに「意味」などあるのか。そもそも言葉を使って何かを伝達することそのものが不思議な現象だと思う。
Web評論誌「コーラ」20号(2013.08.15)
<哥とクオリア>第26章:存在の風に吹かれて(附論)──人和歌のメカニスムⅢ(中原紀生)
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2013 All Rights Reserved.
|
| 表紙(目次)へ |