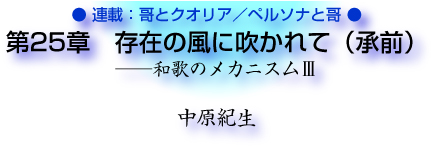|
|
|
Web評論誌「コーラ」 |
|
■創刊の辞 ■本誌の表紙(目次)へ ■本誌のバックナンバー ■読者の頁/ご意見・感想 ■投稿規定 ■関係者のWebサイト ■プライバシーポリシー |
|
<本誌の関連ページ> |
|
■「カルチャー・レヴュー」のバックナンバー ■評論紙「La Vue」の総目次 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
|
■二つの本質、二つのリアリティ
はじめに、『意識と本質』の議論を引きます。
井筒俊彦の思考のキーワード「存在感覚」のオリジナルな使用例を記録にとどめたくて、ついつい長く引用しました。ここで見ておきたいのは、「本質」には二つの類型がある(そして、私の直観がおぼろげに告げるところでは、一方が絶対者との霊的コミュニケーションや神としての文字体験に、他方が渾沌未形のイデア的実在に対する視覚的把捉(対象の視覚化)や共感覚的言語に、それぞれ関連づけることができるかもしれない)ということです。
『意識と本質』によると、その一は、イスラームのスコラ哲学が「マーヒーヤ」と呼ぶ「普遍的本質」(「人間の意識の分節機能によって普遍者化され一般者化され、さらには概念化された形でそれらの事物が提示する」ところの「ものの普遍的規定性」)、その二が、同じくイスラームにおいて「フウィーヤ」と名づけられた「個体的本質」(「生々躍動する現実のものの本源的リアリティー」としての「このもの性」)、で、「リルケの言葉を借りて言うなら」、前者「マーヒーヤ」は「ヴィルクリッヒカイト」の次元に、後者「フウィーヤ」は「レアリテート」の次元に成立する。
(「マーヒーヤ」=「ヴィルクリッヒカイト」=「アクチュアリティ」、「フウィーヤ」=「レアリテート」=「リアリティ」。かの哥の伝導体のモデルにひきよせるならば、「マーヒーヤ」は「ヴァーチュアル(空)/アクチュアル(現)」や「デュナミス(潜勢態)/エネルゲイア(現勢態)」の垂直方向もしくは縦軸の関係に、「フウィーヤ」は「イマジナリー・フィクショナル・ポッシブル・イデアル(虚)/リアル(実)」の水平方向もしくは横軸の関係に、それぞれかかわっている。)
■マラルメ・リルケ・芭蕉、そして王朝歌人
ところで、『意識と本質』には、これら二つのリアリティ(ユニークな個物の独自性を保持する異次元のリアリティと、抽象的概念ではなく濃密な存在度をもったリアリティ。ただし、後者は「アクチュアリティ」というべきではないかと私は考えている)を、存在の深層において体現する二人の詩人が登場します。リルケとマラルメ。井筒俊彦は、そこに芭蕉と王朝歌人をからませ、そして、その議論の最後のところで、新古今における「眺め」を通路に「現象界の彼方」を論じているのです。
以下、『意識と本質』のなかでもっともスリリングな(と私には思われる)論述の概要を記します。
◎マラルメは、「マーヒーヤをそのイデア的純粋性においてのみ直観しようとする詩人」であった。「この形而上的錬金術をなしとげる詩人(コトバの芸術家)マラルメの言語は、もはや日常の、人々が伝達[コミュニカシオン]に使用する言語(langage)ではなくて、事物を経験的存在の次元で殺害して永遠の現実性の次元に移し、そこでその物の「本質」を実在的に呼び出す「絶対言語」(le Verbe)なのである。」
◎一方、「即物的直視」を事とする詩人リルケは、「マーヒーヤ」を概念的虚構として退け、表層的意識(「……の意識」)ではなく意識の深部に存在者の実在的リアリティを、すなわち「フウィーヤ」を探ろうとした。「コトバの意味分節の力の及ばぬ「意識のピラミッド」の深層領域に開示されるもののフウィーヤを、詩人はあらためて言語化しなければならない。言いかえれば、フウィーヤを非分節的に分節し出さなければならない。(略)深層体験を表層言語によって表現するというこの悩みは、表層言語を内的に変質させることによってしか解消されない。ここに異様な実存的緊張に充ちた詩的言語、一種の高次言語が誕生する。」
◎もう一人の「即物的直視」の詩人芭蕉は、フウィーヤ追求の情熱のはげしさにおいて、いささかもリルケに劣らなかった。ただ一方で、「松の事は松に習へ、竹の事は竹に習へ」(服部土芳「赤冊子」)と教えた芭蕉は、事物の普遍的本質(マーヒーヤ)の実在を信じる人であった。芭蕉はそれを、連歌的伝統の術語を使って「本情」と呼んだ。「花は花、月は月という『古今』的本質のように、事物の感覚的表層にあらわに見える普遍者」ではなく、事物の「存在深層」に隠れひそむ本情。「しかし、この永遠不変の「本質」が、芭蕉的実存体験においては、突然、瞬間的に、生々しい感覚性に変成して現われるのだ。」
◎普遍的本質を普遍的実在のままではなく、個物の個的実在性として直観すること。すなわち、「不変不動のマーヒーヤの形而上的実在性を認めながら、それをそのまま存在の深層次元に探ろうとするかわりに、それが感性的表層に生起してフウィーヤに変成する、まさにその瞬間にそれを捉え、そうすることによって存在の真相をマーヒーヤ、フウィーヤの力動的な転換点に直観しようとする芭蕉」にとって、俳句とは、本質の「次元転換」の瞬間を、すなわち、「人と‘もの’との、ただ一回かぎりの、緊迫した実存的邂逅の場[フィールド]」のなかで、マーヒーヤ(本情)がフウィーヤ(生々しい感覚性)に転換・転成・変貌する瞬間を間髪を容れず詩的言語に結晶する「瞬間のポエジー」にほかならなかった。「物の見えたる光、いまだ心に消えざる中[うち]にいひとむべし」(「赤冊子」)。
◎本居宣長が「概念的普遍者を遠ざけて、ひたすら感動の深さのみによって「物の心」を追求しよう」としたのは、リルケのそれと類型的には同種の本質を探究しようとするものだった。ただ、そこには例外があった。ここでいう例外とは、フウィーヤでなくマーヒーヤを言語化するもうひとつの高次言語、詩的言語のことだ。
マラルメとリルケ、芭蕉と王朝歌人をめぐる井筒俊彦の議論は、実に興味深く、長い射程をもった洞察をふくむものだと思います。
マラルメとリルケは、井筒俊彦によって、主体客体の「認識的二極分裂以前の根源的存在次元」と定義される「存在深層」において、「マーヒーヤ」もしくは「フウィーヤ」を探究し、そして、それぞれの言語(絶対言語もしくは高次言語=詩的言語)をもって、それぞれの「本質」を(実在的喚起もしくは非分節的分節のかたちで)表現した。
これに対して、芭蕉と王朝歌人は、ともに「マーヒーヤ」を(存在深層において形而上的に実在するものであるか(芭蕉の場合)、存在表層において感覚的に顕現したものであるか(王朝歌人の場合)は別として)探究し、これを、もうひとつの「高次言語」において(深層のマーヒーヤから表層のフウィーヤへの次元転換の瞬間を結晶させるポエジーとして(芭蕉)、あるいはマーヒーヤの顕在的認知に基くコトバによって(王朝歌人))表現した。ただ、王朝歌人には前期、後期ともいうべき区別があって、普遍的「本質」世界の抽象性を(否定するのではなく)いわば「解毒」するために、それぞれに特有の詩的意識の構えをもってのぞんだ。
以下、先に引用した箇所につづく、井筒俊彦の文章を引きます。
■再論、和歌の感覚世界
前章で、万葉集の「見ゆ」から古今、新古今における「眺め」への変遷のうちに、とりわけ「見ゆ」の衰退のうちに暗示される、世界認識の土台を揺るがす変貌、あるいは「存在」への接近と対峙における大きな革命の特質についてふれました。ここではその後段、すなわち古今、新古今における「眺め」(以下、古今的な意識主体態度のもとでの眺めを「眺め1」、新古今的なそれのもとでの眺めを「眺め2」と表示します)の頻用のうちに暗示される認識論的変貌や存在論的革命とはいったいどのようなものであったかについて見ておきたいと思います。
以前、(第8章で)、共感覚をベースに、古典和歌における感覚の論理について考えをめぐらせました。そのときの「結論」部分を再掲します。
◎万葉集の感覚世界
見ることと触れること、匂いを嗅ぐことが等価であり、聴くことが見えないものを見ることであるような「異種感覚間連合」の根底に、そもそも個別の感覚がそこから分岐していく基盤となる原初の共感覚的な身体感覚が実在している。
この身体感覚は、非人格的な力がはたらく不可視の(潜在的な)領域に接触しつつ、森羅万象のリアルな事物事象とつながっていき、そこでは、物心一体、心身一如、主客合一の事態が成立している。
◎古今集の感覚世界
「見る」から「思ふ」へという第一の変化が生じる。
「見る」といっても、それは見るものと見られるものとが親密に結びつき、また身体感覚を介して自然の律動へとつながっていく共感覚的な視覚のこと。そうした視覚の内側に濃厚に息づく接触感覚、とりわけ「しみる」感覚や過ぎ去った時の記憶を一挙によみがえらせる嗅覚、あるいは不可視のものを可視化する聴覚が、和歌の世界においてしだいに重んじられるようになる。
その結果、確かに現前するものよりも遠くはるかなもの、非在、非有非無のものへの「思ひ」を詠む歌、あるいは遠方から到来する「よそのものの気配」に敏感な歌が好まれるようになっていく。
◎新古今集の感覚世界
「広がり」から「深み」へという第二の変化がもたらされる。
「広がり」は視覚だけでなく、遠くはるかなものを思いやる嗅覚や聴覚など、原初の身体感覚から独立し社交的に洗練されていった個別の感覚全般にかかわる。
「深み」とはそのような「広がり」を不可視の内部に繰り込んだもの。かつて「物」としてリアルに実在していた触覚=身体感覚が、無色のもの(言語)のなかに「心の色」を見る透視力を通じて(言語的に)再構築される。「深み」はそのような意味での「身体」にかかわる。
この新しい「身体」は端的に「心」と呼んでもさしつかえない。こうして、純触覚的な「身にしむ」感覚が、内触覚的な「心にしむ」認識に達していく。
こうやってあらためて眺めてみると、「見る」よりも「思ふ」こと、つまり、いま・ここに現前しないもの(たとえば他者の身体)への「もの思ひ」(淡い性欲的気分)にひたることが「眺め1」に、そして、そうした「思ひ」の方向が転じ、言語主体としての我が身、我が心の「深み」へとしみこんでいく意識態度が「眺め2」に相当するのではないかと、おぼろげながらそんなふうに思えてきます。
■「眺め」の世界、二つの現象学的還元
いま、私の脳髄にとびかっているのは、フッサールによる現象学的還元という「方法」のことです。
現象学の名がうかんだのは、そもそも前章冒頭で、二十世紀においてもっとも飛躍した学問の話題をとりあげた際、深層意識を組み入れた心理学(経験科学)と神学としての言語学との「間」に、二十世紀への「世紀の転換期に哲学において出現してきた新たな種類の記述的方法」であり、かつ「この方法から生じてくるアプリオリな学問」(フッサール「ブリタニカ第四草稿(最終稿)」、谷徹訳『ブリタニカ草稿』)であると、創設者みずから紹介している現象学を位置づけることができるのではないかと思いあたったことにはじまります。
(余談を挿む。フロイト(1856年)とソシュール(1857年)の「間」にフッサール(1859年)をおくと、同年生まれのベルクソン(1859年)の名がうかびあがる。この四人に、渡辺恒夫著『フッサール心理学宣言──他者の自明性がひび割れる時代に』がフッサールとフロイトの経歴上の「著しい類似」に言及し、そのひとつとして師に離反するアーリア系の弟子をもったことをあげ、もしハイデガーではなくウィトゲンシュタインがフッサールの助手になっていたらその後の現象学のありかたはまったく異なったものになっただろうと書いている、そのハイデガー(1889年)とウィトゲンシュタイン(1889年)の二人を加えるならば、そして萩原朔太郎(1886年)や折口信夫(1887年)や九鬼周造(1888年)や和辻哲郎(1889年)、さらにはベンヤミン(1892年)といった同時代人を配置すれば、(西田幾多郎(1870年)を起点のひとつとしてはじめたこの論考の着地点を探るための)、なにかしら見通しの良い系譜なり相関図を手に入れることができるのではないかと思う。)
そして、白川静の「見る」(や井筒俊彦の「読む」)、佐竹昭広の「見ゆ」をめぐる議論が、(とりわけ、非空間的なものを空間的なもので表現する「対象の視覚化」や、存在を「かたち」や「すがた」において描写的に把捉する「古代の心性」をめぐる議論が)、なによりも、若松氏によって、「井筒俊彦の意味論は遡源的に進む。すなわち、「コトバ」→意味→言葉→事象へと展開する。(略)井筒にとっての言語哲学とは、言葉に「意味」を探るというよりも、「意味」に「存在」へと回帰する道を見つける営みである」と規定された、井筒俊彦の哲学的意味論のプロセスもしくは「方法」が、私には、現象学的な「還元」(と「構成」)の実例もしくは異名と思えるようになっていったのです。
以下、私の思考野のうちにたちあらわれている(「私には……と思われる」)ことがらを、いっさいの論証や実証、説明や引用をぬきにして、ただ記録しておくことにします。
(最低限の出典を記しておくと、現象を構成する「はたらき(actus)」のアクチュアリティ=「生き生き」感、現象する「もの(res)」のリアリティ=「ありあり」感、といった語彙の組み合わせは、斎藤慶典著『フッサール 起源への哲学』第四章3節の議論を参考にした。また、自我体験(「私は私だ!」体験)によって出現する「我思う故に我ありの内的経験世界」と、独我論的体験を通じてみいだされる「私に固有なものの世界」という二つの「フッサール世界」のアイデアは、渡辺恒夫の前掲書による。)
◎古今集仮名序冒頭の一文「やまとうたはひとのこころをたねとしてよろづのことのはとぞなれりける」には、少なくとも三つの読み方がある。(以下の文中の「なった」は、凝固=結晶した、生長した、表現された、等々と文脈に応じて読み替えることができる。)
Ⅰ.「よろづ」(森羅万象、自然)が「ひとのこころ」を通して詞になったのが「やまとうた」である。
Ⅱ.「ひとつ」(壱)の心(「人の心」とはかぎらない)が「よろづ」(萬)の詞になったのが「やまとうた」である。
Ⅲ.「人の心」が様々な詞になったのが「やまとうた」である。
このうち「Ⅰ」は、「貫之が自然を詠む」ことと「自然が貫之を通して自己を詠む」こととが区別できない(あるいは、思いとその思いが実現すること、思いを言葉にすることとその言葉がそこにおいて立ち上がる世界そのものが出現すること、私が悲しいことと世界が悲しいこと、等々が区別できない)貫之現象学の(暗に独我論的な)世界の一端を、少なくともその後段の「自然が貫之を通して自己を詠む」ことの成立可能性を示す。
◎このような読み方、あるいは世界のとらえかたが可能になるためには、カミ(迦美)とヒトとの「生き生き」とした霊的(あるいはペルソナ的)な交流や、生きとし生けるものをはじめおよそ世にあるものと人の心との「ありあり」とした共感覚的(あるいは原クオリア的)な交響の経験が、それぞれ積み重ねられていなければならない。
このことを、(やや強引に)かの哥の伝導体のモデルにひきよせるならば、それぞれ「ヴァーチュアル(空)⇔アクチュアル(現)」の縦軸もしくは垂直方向の交流、「イマジナリー・フィクショナル・ポッシブル・イデアル(虚)⇔リアル(実)」の横軸もしくは水平方向の交響と定式化できる。そして、これら二つの流れが「空⇒現」かつ「虚=実」という一方向・単一の流れのうちに収斂されたとき、そこに出現するのが、「春は春、花は花、恋は恋」という、マーヒーヤを言語化するもうひとつの高次言語によって表現される「マンダラ的存在風景」である。
◎王朝歌人たちが、このような顕在化した「本質」の実在を否定するのではなく、事物の「本質」的規定性を弱め、朦朧化させるために駆使したのが、「眺め」という現象学的還元類似の方法にほかならない。そして、現象学的還元に超越論的還元あるいはエポケー(判断停止)と形相的還元あるいは本質直観の二つがあるように、「眺め」という「意識主体的態度」にも、古今的「眺め1」と新古今的「眺め2」という二つのものがある。
(斎藤慶典によると、超越論的還元と形相的還元の順序はいずれが先行してもよい。「いずれの途をとおっても、最終的に確保されたのは、すべての存在妥当を停止されて純粋に「私には~と思われる」という仕方で保持された「現象」が、その「何であるか」において明確な直観に与えられているという事態なのである。」(斎藤前掲書))
【眺め1】
形相的還元は、「リアル⇒イマジナリー・フィクショナル・ポッシブル・イデアル」と定式化できる。それと同様に、古今的「眺め1」は、「実⇒虚」もしくは「事物のありありとした描写⇒渾沌未形の状態にある可能性の領野」と表現することができる。(「空⇒現」もしくは「ヴァーチュアル⇒アクチュアル」という「生き生きとした実在」の世界をもたらす力の流れは否定されない。)
この「還元」を通じて、「私に固有なものの世界」(フッサール世界1)が区画され、仮名序冒頭文に関する解釈「Ⅱ」が可能となる。そこでは、「ひとのこころ」とは「私(独り)の心」のことであり、かつ「よろづの詞」が「私」であると言える事態が成立している。
【眺め2】
超越論的還元は、「アクチュアル⇒ヴァーチュアル」と規定することができる。同様に、新古今的「眺め2」は、「現⇒空」もしくは「生き生きとした実在⇒世界を成立させる実質(存在深層)」と表現することができる。(「眺め1」によってひらかれた渾沌未形の「虚」もしくは「イマジナリー・フィクショナル・ポッシブル・イデアル」な世界における深層領域へ。つまり、ヴァーチュアル・リアルならぬヴァーチュアル・イマジナリーな世界へ。)
この「還元」を通じて、「我思う故に我ありの内的経験世界」(フッサール世界2)が区画され、仮名序冒頭文に関する解釈「Ⅲ」が可能となる。そして、「心とはそもそも何ものかといふ疑惑」(唐木順三)がおこる。
いまだ仮説の域にも達しない思いつきでしかありません。早急にたちいった吟味を加え、破棄すべきは破棄しなければならないでしょう。(そもそも古今集の「マンダラ的存在風景」こそが現象学的還元によってもたらされた貫之現象学の原風景なのであって、「眺め1」と「眺め2」の手続きを介して構成されていくものが定家論理学の言語世界なのであるといった、まったく異なる立論が可能なのかもしれない。)
フッサールが「現象学的還元と形相的還元の二重操作を経て把握した「本質」は、窮極的にはマーヒーヤだったのだろうか、フウィーヤだったのだろうか」。井筒俊彦は『意識と本質』のなかでそのように書いていました。このことを考えるためにも、若松英輔氏が「日本古典文学における言語哲学的意味論という、実現されなかった夫俊彦の仕事の展開を類推させる論拠」と評した、井筒豊子の和歌論三部作(その最後の論考で、「ながめ」と「みわたし」をめぐる考察がなされている!)にあたらなければばなりません。
■補遺、和歌の感覚世界
万葉集の感覚世界から古今集のそれへと転じる際の、「見る」から「思ふ」への変化は、唐木順三が『日本人の心の歴史』で指摘した事柄だった。この書物のことは、第8章ではとりあげることができなかったので、ここに補遺もしくは思考素材として、その上巻冒頭三章の議論を適宜抜き書きしておく。
1.万葉集における「見れど飽かぬ」について
見れど飽かぬ吉野の河の常滑の絶ゆることなくまた還り見む(人麿)
「見る」対象は多くは自然であるが、単に空間でなく、過去や未来といった時間にかかわっている。「見れども飽かぬ」の中には、「見る」にさまざまな記憶、回想、歴史が入りこみ、飽かぬ「思ひ」をかきたてることがふくまれている。「思ひ、偲ぶことのなかに、初期万葉人たちは映像をともなつてゐた。思ひは見ることから離れてゐない。ヴィヴィットな思ひ、追憶である。眼で偲んでゐるといつてよい。そしてその見ることにおいて飽きず、飽きず思ひ見てゐる。「見れど飽かぬ」の中には、さういふ心情がある。」
後期になると、「見る」は恋、性、未練にかかわり、「見れど飽かぬ」の対象は一人の異性に集中するようになる。「盲目の「見る」といつてもよい。その「見る」において飽かないとみづから歌ふのはどこか野暮つたい。一途にすぎる。それが古今集以下において、この言ひ方が殆ど消失してしまつた理由の一つと考へられる。」自然を対象とする場合も時間、空間のひろがりがなくなり、「飽かぬ」は賞美になる。「観光客のありきたりの讃嘆語である。これもまた野暮といへば野暮である。」
うるはしみ吾が思[も]ふ君は石竹花[なでしこ]が花に比[なぞ]へて見れど飽かぬかも(家持)
「見れど飽かぬかも」の対象は「吾が思ふ君」なのか「石竹花」なのか。「しげしげと見入つてゐる対象は一つでなければならない。「比へて」と、かういふ風につかはれるにいたつて、この「飽かぬかも」といふ表現の仕方はその本来の意味を失つた。本来の具体性を失つた言葉はやがて消失するのが運命である。」
2.古今集における「思ふ」について、及び王朝末、中世初期に現はれた「心」への懐疑と否定
3.「思ふ」から「見る」への回帰、及び「見る」ことの深化
《「松の事は松に習へ、竹の事は竹に習へ」の「習へ」がどのやうな事であるかはよく読めばわかる。それは松や竹を対象として見たり写生したりすることではない。松が松を自若として其処に現成してゐる姿、竹がみづからをおのづからに表現してそこに立つてゐる姿を習へといふのである。芭蕉の言葉に「静にみれば物皆自得す」があるが、松、竹、各々自得してゐるところ、而今の山水が古仏の道を現成してゐるところへ参せよといふのである。いかにしてか山河大地を転じて自己に帰せしめんといつた弟子に、いかにしてか自己を転じて山河大地に帰せしめんといつた長沙景岑[けいしん]禅師のゐるところである。
古今集の序では和歌は「ひとのこころを種として」といはれてゐること、それが王朝時代を通じて歌人の通則となつてゐたことを既に我々は知つてゐる。その「心を種」とするのにひきかへて、芭蕉が、「乾坤の変は風雅のたね也」といつてゐることに注意すべきである。詩心を動かすものは、反つて自然の中、物の中にある。心の中で思ふのではなく、物を「見とめ」「聞とめ」よといふ。物の見えたるひかり、いまだ心に消えざる中に、いひとめよといふ。物からの語りかけに耳を傾けよといふ。これは先に引いた西田[幾多郎]先生の、「物となつて考へ、物となつて行ふ」や、「物来つて我を照す」を思ひださせる。》
(「「眼」にかはつて「心」が、「見る」にかはつて「思ふ」が」と言われるときの、その不可視の「心」や「思ひ」が「眺め1」の対象であり、「人間の計らひ、自己の計らひを超えるもの」、あるいは「詩心を動かすものは、反つて自然の中、物の中にある」というときの「物」、「物の見えたるひかり」や「物来つて我を照す」に言うところの「物」が「眺め2」の対象である。精確には、「眺め1」や「眺め2」によって志向され、構成される当のものである。)
★プロフィール★
中原紀生(なかはら・のりお)1950年代生まれ。兵庫県在住。千年も昔に書かれた和歌の意味が理解できるのはすごいことだ。でも、本当に「理解」できているのか。そこに「意味」などあるのか。そもそも言葉を使って何かを伝達することそのものが不思議な現象だと思う。
Web評論誌「コーラ」20号(2013.08.15)
<哥とクオリア>第25章:存在の風に吹かれて(承前)──人和歌のメカニスムⅢ(中原紀生)
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU 2013 All Rights Reserved.
|
| 表紙(目次)へ |