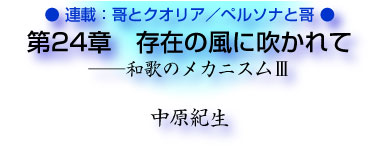|
|
|
Web昡榑帍乽僐乕儔乿 |
|
仭憂姧偺帿 仭杮帍偺昞巻乮栚師乯傊 仭杮帍偺僶僢僋僫儞僶乕 仭撉幰偺暸乛偛堄尒丒姶憐 仭搳峞婯掕 仭娭學幰偺Web僒僀僩 仭僾儔僀僶僔乕億儕僔乕 |
|
亙杮帍偺娭楢儁乕僕亜 |
|
仭乽僇儖僠儍乕丒儗償儏乕乿偺僶僢僋僫儞僶乕 仭昡榑巻乽俴倎 Vue乿偺憤栚師 |
Copyright (c)SOUGETUSYOBOU |
|
|
|
仭怺憌堄幆揑尵岅揘妛丄擇廫悽婭偺恄妛
丂
丂巌攏椛懢榊偲偺懳択偱堜摏弐旻偑岅偭偨丄屆崱丄怴屆崱偺巚憐揑峔憿偺堄枴榑揑尋媶偺榖戣傊偺暁慄丄偦偺堦丅
丂
丂庒徏塸曘挊亀堜摏弐旻劅劅塨抦偺揘妛亁偺側偐偱丄傕偭偲傕偡偖傟偨拝憐偱偁傝嬈愌偱偁傞乮偲巹偵偼巚傢傟傞乯丄敀愳惷偺暥帤妛偲堜摏弐旻偺乽怺憌堄幆揑尵岅揘妛乿偲偺斾妑榑傪偲傝偁偘偨偄偲巚偄傑偡丅
丂傑偢丄擇廫悽婭偺尵岅妛偵偮偄偰彂偐傟偨庒徏巵偺暥復傪擇偮丄偦偺尵奜偺奼偑傝傗枴傢偄傪娷傔偰娵偛偲敳偒彂偒偟傑偡丅
丂儊僞尵岅偺幚尰偼堜摏弐旻偺斶婅偱傕偁偭偨偑丄乽偨偩丄堜摏偑朷傓乽儊僞尵岅乿偼丄婛懚偺尵岅傪乽儊僞乿揑偵埖偆偺偱偼側偔丄暥帤捠傝尵岅傪 meta 偡傞乮挻偊傞乯幚嵼偱側偔偰偼側傜側偐偭偨乿丅庒徏巵偼偦偺傛偆偵彂偒丄偮偯偄偰丄僄僱儖僎僀傾乮弮悎尰惃懺乯偲偟偰偺乽弮悎帊乿傗丄儅儔儖儊偺乽愨懳尵岅乿偺榖戣傪偲傝偁偘丄偝傜偵丄侾俋俆俇擭姧峴偺塸暥挊嶌亀俴anguage and 俵agic亁偱堜摏弐旻偑榑媶偟偨丄magico-religious 側尵梩偺椡偺幚幙乮乽偦傟偼堄枴傪惗傓偩偗偱側偔丄幚懺傪寛掕偡傞乽懚嵼乿偺旈媀偱偁傞乿乯傊偲榖傪偮側偄偱偄偒傑偡丅敀愳惷偺柤偑搊応偡傞偺偼丄偦偆偟偨媍榑偺棳傟偑偄偒偮偔愭偱偡丅
丂
丂庒徏巵偼丄敀愳惷偺亀娍帤亁偐傜丄乽師偵暥帤偑偁偭偨丅暥帤偼恄偲偲傕偵偁傝丄暥帤偼恄偱偁偭偨乿偲偄偆堦愡傪堷偒丄偙傟傪丄堜摏栿偵傛傞儓僴僱暉壒彂朻摢偺堦愡丄乽懢巒偵僐僩僶偑偁偭偨丅僐僩僶偼恄偺傕偲偵偁偭偨丅偲偄偆傛傝丄僐僩僶偼恄偱偁偭偨偺偩丅偁傝偲偁傜備傞傕偺偑偙傟偵傛偭偰惉傝丄偍傛偦惉傝弌偱偨傕偺偺偆偪丄偨偩傂偲偮傕偙傟偵傛傜偢惉傝弌偱偨傕偺偼側偐偭偨乿偲傂偒偁傢偣傑偡丅
乮偙偺栿暥偼丄堜摏弐旻偑幍廫嵨偺擭丄崅栰嶳偱偍偙側偭偨島墘乽尵岅揘妛偲偟偰偺恀尵乿偺側偐偵弌偰偔傞丅偦偙偱丄堜摏弐旻偼丄乽懚嵼偼僐僩僶偱偁傞乿偲偄偆丄堜摏揘妛傪堦尵偱廂澥偝偣傞柦戣傪採帵偡傞偲偲傕偵丄拞妛惗偺崰丄嬼慠乽儓僴僱揱乿偺嵟弶偺堦暥偵憳嬾偟偨偲偒丄乽嬃偒偲傕姶寖偲傕偮偐偸丄幚偵堎條側婥暘偵埑搢偝傟乿丄偦偟偰丄乽堄枴晄柧偺傑傑偵丄偟偐傕壗偲側偔掙抦傟偸怺傒傪扻偊偨恄旈揑側尵昞偲偟偰丄偙偺堦暥偑丄偦偺屻傕塱偔徚偟擄偄梋塁傪巹偺怱偺墱偵巆偟偨乿偲岅偭偰偄傞丅庒徏巵偵傛傞偲丄偙偺懱尡偼丄惵擭婜偵偍偗傞僊儕僔傾揘妛偲偺弌夛偄偲偲傕偵丄堜摏弐旻偵偲偭偰偺乽孾帵揑弌棃帠乿偱偁傝丄偦偺乽幚懚揑宱尡乿偺妀怱傪側偡傕偺偱偁偭偨丅乯
丂敀愳惷偼暥帤丄堜摏弐旻偼尵岅偲丄偦傟偧傟偑榑偠傞幚懱偼堘偆偑丄偦傟偼昞憌堄幆偵塮偠偨嵎堎偵偡偓側偄丅庒徏巵偼偦偺傛偆偵弎傋丄堜摏帺恎偑亀堄幆偲杮幙亁乯偺側偐偱丄乽杮榑偱巹偑乽尵岅傾儔儎幆乿偲偄偆柤偺壓偵栤戣偵偟偰偒偨怺憌堄幆椞堟撪偱偺堄枴乽庬巕乿偺杮尮揑側僀儅乕僕儏姭婲嶌梡傪拞怱偵偡傞尵岅娤乿傪偦偺傑傑棟榑揑偵揥奐偡傟偽丄偦傟偼乽戝婯柾側尵岅揘妛乿傪丄偮傑傝乽変乆偑忢幆揑偵峫偊傞尵岅揘妛丄偡側傢偪昞憌堄幆偵偍偄偰棟惈偑嶌傝忋偘傞尵岅揘妛偲偼慡慠堎幙偺丄怺憌堄幆揑尵岅揘妛乿傪惗傓壜擻惈偑偁傞偲彂偒丄偦偺揟宆揑側働乕僗偲偟偰乽嬻奀偺垻帤恀尵丄僀僗儔乕儉偺暥帤恄旈庡媊丄摨偠偔僇僢僶乕儔乕暥帤恄旈庡媊側偳乿傪嫇偘偰偄傞偙偲傪帵偟傑偡丅
丂梋択偲偟偰丅偐偮偰嫗搒偱乽暥帤島榖乿偺戞堦夞傪挳島偟偨丅 抎忋偵棫偭偨乽帤惞乿乮摉帪敧廫嬨嵨乯偼丄 堦帪娫敿偵媦傇島墘偺娫丄挘傝偺偁傞椡嫮偄惡偱梽傒側偔丄嵟屻偵偼擬偔丄娍帤埲慜偺乽恾徾乿傊偺巚偄偲偦偺妛栤揑忣擬傪岅傝懕偗偨丅偦偙偵偼妋偐偵屆戙悽奅偑弌尰偟丄暥帤偑惗傑傟弌傞椪奅揰偺僄僱儖僊乕偑傢偒偨偭偰偄偨丅巹偼儊儌傕庢傟偢丄偨偩偦偺尵梩偵埑搢偝傟偨丅
丂偁傜偨傔偰敀愳惷偺尨揟偵偁偨傞嶌嬈傪偼偠傔偰偟傑偆偲摉暘婣娨偱偒側偔側傝偦偆側偺偱丄偙偙偱偼尰戙偺乽帤惞乿偺挊彂偐傜丄乽怺憌堄幆揑尵岅揘妛乿偁傞偄偼暥帤傪傔偖傞恄旈妛偵娭楢偡傞偲巚傢傟傞榑弎傪堷偔偙偲偵偡傞丅
丂愇愳嬨梜挊亀擔杮偺暥帤劅劅乽柍惡偺巚峫乿偺晻報傪夝偔亁偵丄堦壒懡帤丄惔壒昞婰傪摿挜偲偡傞乽彈庤乿乮傂傜偑側乯偲偲傕偵惗傑傟偨屆崱榓壧偺儗僩儕僢僋乮妡帉丄墢岅丄尒棫丄壧枍丄摍乆乯偼丄壒偵傛傞塁棩偱偼側偔暥帤亖彂帤偵傛傞塁棩丄偡側傢偪丄乽暥帤偵怗敪偝傟偨堄枴偺忋偱偺塁丄帤塁乿偺摉慠偺婣寢偩丄偲彂偐傟偰偄傞丅
丂偨偲偊偽丄乽攡偺崄傪懗偵偆偮偟偰偲傔偨傜偽弔偼夁偖偲傕宍尒側傜傑偟乿偺屆崱榓壧傪丄悺徏埩怓巻偼乽傓傔偺偐傪偦偰偵乛偆偮偟偰偲傔偨傜乛偼傞偼偡偔偲乛傕偐偨傒側傜傑乛偟乿偲丄屲峴偵偪傜偟偰彂偔丅廬棃偺夝庍偱偼丄戞擇峴枛偲戞嶰峴朻摢偺偁偄偩偺乽偼乿偼扙帤偲偝傟偰偒偨偑丄愇愳巵偼丄乽偆偮偟偰偲傔偨傜乪偼乫乿偲乽乪偼乫傞偼偡偔偲傕乿偲偄偆傆偆偵丄戞嶰峴朻摢偺乽偼乿偼擇廳偵撉傑傟傞傋偒偱偁偭偰丄偦偙偵乽妡帤乵偐偗偠乶乿偲偄偆乽帤塁乿偑嬱巊偝傟偰偄傞偲傒傞丅
丂偦偟偰丄偙偺妡帤偼丄乮乽偝乿偺嵟廔昅偲乽傜乿偺戞堦昅傪擇廳偵彂偔丄偁傞偄偼乽偪乿偺嵟廔夞揮晹暘偲乽偲乿偺彂偒巒傔偺戞堦昅偲偑擇廳壔偡傞丄側偳偺乯乽妡昅乵偐偗傂偮乶乿偺昞尰媄朄偵崻偞偟偰偄傞偲偡傞丅乽傂傜偑側偺壧乿偱偁傞榓壧偺嵟傕戙昞揑側儗僩儕僢僋偲偝傟偰偒偨枍帉偼妡帤偵巟偊傜傟丄偦偺妡帤偼妡昅偵巟偊傜傟偰偄傞丅
丂
仭乽尒傞乿偺悽奅丄幚懚揑宱尡
丂
丂偄傑傂偲偮丄敀愳惷傪傔偖傞媍榑傪堷偒傑偡丅
丂乽榓壧偵偍偗傞乽尒傞乿摥偒偵丄幚懚揑偲傕偄偊傞摿暿側堄巚傪崬傔偰榑偠偨偺偑丄敀愳惷偩偭偨丅乿庒徏巵偼偦偺傛偆偵彂偒丄敀愳惷偺亀弶婜枩梩榑亁偐傜丄乽帺慠偲偺岎徛偺嵟傕捈愙揑側曽朄偼丄偦傟傪懳徾偲偟偰乽尒傞乿偙偲偱偁偭偨丅慜婜枩梩偺壧偵懡偔傒傜傟傞乽尒傞乿偼丄傑偝偵偦偺傛偆側堄枴傪傕偮峴堊偱偁傞丅乿傪堷梡偟偨偆偊偱丄堜摏弐旻偺榓壧傊偺娭怱偲傂偒偁傢偣偰丄師偺傛偆偵岅偭偰偄傑偡丅
丂敀愳惷偺乽尒傞乿偑丄堜摏弐旻偵偲偭偰偺乽撉傓乿偵憡摉偡傞丅乽撉傓乿偙偲丄偡側傢偪僥僋僗僩偺乽巚憐揑峔憿偺堄枴榑揑尋媶乿丅娞怱側偙偲偼丄乽斵偑偳偆撉傫偩偐乿偱偼側偔偰丄乽斵偑側偤丄偁傞懳徾偵弌夛偄丄偦傟傪乽撉傓乿偙偲偑偱偒偨偺偐乿丄偁傞偄偼丄乽偦偺懳徾偑側偤丄斵偵偨偄偟偰帺傜傪岅傝巒傔偨偺偐乿偱偁傞丅庒徏巵偑偦偺傛偆偵尵偆偲偒丄幚偼偦偙偵丄傂偲偮偺儖乕僾偑惗偠偰偄傑偡丅乮偙偺儖乕僾偼丄夝庍妛揑弞娐側傜偸挻墇榑揑弞娐丄傕偟偔偼宍帶忋妛揑丄恄妛揑弞娐偲偱傕尵偆傋偒傕偺偩偲巚偆丅偁傞偄偼丄懚嵼榑揑嵎堎偺娭學偵偁傞椉崁偵傑偨偑傞懚嵼榑揑弞娐偲偱傕丅乯
丂偁傞屆揟揑僥僋僗僩丄偨偲偊偽屆崱榓壧廤傗怴屆崱榓壧廤傪乽撉傓乿偲偒丄偦偺僥僋僗僩偺堄枴傪撉夝偡傞曽朄傪廗摼偡傞偨傔偵偼丄偦傟偵愭棫偭偰丄傑偢偦偺僥僋僗僩偵弌夛偭偰偄側偗傟偽側傜側偄丅僥僋僗僩偺乽堄枴乿偵傛偭偰偁傜偐偠傔乽偮偐傑傟偰乿偄側偗傟偽丄偦傕偦傕僥僋僗僩傪乽撉傓乿偙偲側偳偱偒側偄丅乮弮悎帊偲偟偰偺榓壧傪乽撉傓乿偨傔偵偼丄偦偺摉偺壧傪帺嶌塺偲偟偰乽塺傓乿亖乽彂偔乿偺偱側偗傟偽側傜側偐偭偨傛偆偵丅乯
丂偙傟偼丄幚偼丄堜摏弐旻偺廔惗曄傢傜偸妛栤揑乽怣忦乿偵偮側偑偭偰偄傞帠暱偱傕偁傝傑偟偨丅庒徏巵偼丄偙偺偙偲傪師偺傛偆偵昞尰偟偰偄傑偡丅乽堜摏弐旻偑崻杮栤戣傪榑偠傞偲偒偼偄偮傕丄幚懚揑宱尡偑愭峴偡傞丅傓偟傠丄偦傟偩偗傪恀偵榑媶偡傋偒栤戣偲偟偨偲偙傠偵丄斵偺摿惈偑偁傞丅僾儔僩儞傪榑偠丄乽僀僨傾榑偼昁偢僀僨傾懱尡偵傛偭偰愭棫偨傟側偗傟偽側傜側偄乿乮亀恄旈揘妛亁乯偲偄偆尵梩偼丄偦偺傑傑斵帺恎偺怣忦傪昞尰偟偰偄傞偲尒偰傛偄丅乿
丂
乮僀僨傾榑偵愭棫偪懱尡偝傟傞傕偺傪乹僀僨傾乺偲昞婰偟偰傒傞丅堦斒偵丄偁傞崻杮栤戣偵愭峴偡傞幚懚揑宱尡丄偨偲偊偽乽巹乿偲偼壗偐偲偄偆栤偄偵愭偩偭偰宱尡偝傟傞傕偺傪乹巹乺偲昞婰偟偰傒傞丅偟偐偟丄偦傟傜偼尵岅埲慜偺宱尡偩偐傜丄杮棃丄乹僀僨傾乺傗乹巹乺側偳偲昞婰偡傞偙偲偼偱偒側偄丅尵岅婰崋傪傕偭偰昞婰偡傞偙偲偑偱偒傞偺偼丄乽僀僨傾乿傗乽巹乿側偳偺崻杮栤戣傪傔偖傞媍榑傪捠偠偰尵岅揑偵惛楤偝傟丄昞尰偝傟傞奣擮偱偁偭偰丄偦傟傪乻僀僨傾乼傗乻巹乼偲昞婰偟偰傒傞丅
丂巹偨偪偼丄偄傗丄偙偺巹偼丄乻巹乼傪傔偖傞媍榑偵愙偡傞偙偲偱丄傕偭偲嬶懱揑偵尵偊偽丄塱堜嬒巵偺撈嵼惈偺乹巹乺乮斾椶側偄巹丄偦傕偦傕懠恖偑懚嵼偟偊側偄巹乯傪傔偖傞榑弎傪扨撈惈偺乻巹乼乮懠恖偱偼偁傝偊側偄傎偐側傜偸偙偺巹乯丄偁傞偄偼挻墇榑揑庡娤惈偲偟偰偺乻巹乼傪傔偖傞媍榑偲偟偰撉傒丄棟夝偡傞偙偲傪捠偠偰丄偐偺乹巹乺傪傔偖傞幚嵼揑宱尡偺幚幙丄庤怗傝丄姶怗丄偁傞偄偼懚嵼姶妎偺傛偆側傕偺偑丄傎偐側傜偸偙偺巹帺恎偺幚懚揑宱尡偲偟偰丄偄傑丒偙偙偱丄尰偵丄偼偠傔偰乮偟偐傕丄偄傑丒偙偙偵愭棫偮懱尡偲偟偰斀暅揑偵乯偨偪偁偑傞偺傪宱尡偟偨丅
丂偦偺塱堜巵偑亀惣揷婔懡榊亁偱丄惣揷尰徾妛偺擇偮偺崻杮栤戣乮巹偺娭怱偵傂偒傛偣傟偽丄偦傟傜偼娧擵尰徾妛偵偍偗傞崻杮栤戣偵傎偐側傜側偄乯傪採帵偟偰偄偨丅偡側傢偪丄嘆乽尵岅偵塢偄尰偡偙偲偺偱偒側偄愒偺懱尡乿偺傛偆側丄尵梩偱岅傝偊偸傕偺偑偄偐偵偟偰尵梩偱岅傟傞傛偆偵側傞偺偐乮乹愒乺偼偄偐偵偟偰乻愒乼偲側傞偐丄偁傞偄偼丄乽傂偲偺偙偙傠乿傪庬偲偟偰乽傛傠偯亖僋僆儕傾偺塅拡乿偑乽偙偲偺偼亖帉乿傊偲惗挿偟偰偄偔僾儘僙僗偲偼偳偺傛偆側傕偺偐乯丄嘇捈愙偵寢崌偟偰偄側偄巹偲懠恖偑丄尵岅傗暥帤偲偄偭偨昞尰傪捠偠偰丄傑偨壒傗宍偲偄偭偨暔棟尰徾傪庤抜偲偟偰丄側偤憡棟夝偱偒傞偺偐乮乻愒乼偑偄偐偵偟偰乹愒乺偲側傞偐丄偁傞偄偼丄偦傕偦傕側偤乽帉乿偑懠偺儁儖僜僫偵揱傢傞偺偐乯丅
丂傑偨塱堜巵偼摨彂偱丄惣揷揘妛偵偍偗傞尰徾妛乮乹愒乺傗乹巹乺偺尰徾妛乯偲榑棟妛乮乻愒乼傗乻巹乼偺榑棟妛乯傪嬫暿偟丄師偺傛偆偵弎傋偰偄偨丅榑棟妛偵懳偡傞尰徾妛偺桪埵惈偑丄乽懱尡偼尵梩偲撈棫偵偦傟偩偗偱堄枴傪帩偪偆傞丅尵梩偺堄枴傕傑偨偦偆偄偆懱尡偵偡偓側偄偺偩乿偲偡傞惣揷揑妋怣斊偺摿幙偱偁傝丄堦曽丄乽尵梩偼懱尡偲撈棫偵偦傟偩偗偱堄枴傪帩偪偆傞丅乽懱尡乿傕傑偨偦偆偄偆尵梩偵偡偓側偄偺偩乿偲偡傞僂傿僩僎儞僔儏僞僀儞揑妋怣斊偑丄尰徾妛偵懳偡傞榑棟妛偺桪埵惈偲偄偆摿幙傪傕偭偰丄惣揷揑妋怣斊偲憡懳洺偟偰偄傞丅
丂埲忋偺偙偲偑傜偑丄堜摏弐旻偺尵岅揘妛揑堄枴榑傪傔偖傞彂暔傪撉傒偡偡傔側偑傜丄巹偺擼悜偵晜偐傫偱偼徚偊偰偄偭偨丅乽僀僨傾榑偼昁偢僀僨傾懱尡偵傛偭偰愭棫偨傟側偗傟偽側傜側偄乿偲弎傋傞偙偲偱丄堜摏弐旻偼惣揷亖娧擵尰徾妛偺懁偵梌偟偰偄傞丅乮堜摏弐旻偺庡挊亀堄幆偲杮幙亁偺偆偪偵丄巹偑偐偮偰尒偰偲傞偙偲偑偱偒偨偺偼乻巹乼偺榑棟妛側傜偸乻巹乼偺暘椶妛偺偛偲偒傕偺偱偁偭偰丄偦偙偵乹巹乺偺尰徾妛傪撉傒偲傞偙偲偼偱偒側偐偭偨丅偟偐偟崱夞偁傜偨傔偰捠撉偟偰婥偯偄偨偺偼丄亀堄幆偲杮幙亁偺偆偪偵乹巹乺偺尰徾妛偑娷傑傟偰偄傞偐偳偆偐偑栤戣偲側傞傛傝傕偝偒偵丄幚偼亀堄幆偲杮幙亁偦偺傕偺偑乹巹乺偱偁傞偲偄偆帠懺偑側傝偨偭偰偄偨偺偱偼側偄偐偲偄偆偙偲偩偭偨丅乯
丂巹偼丄弮悎帊偲偟偰偺榓壧偺儊僇僯僗儉偲偼丄僋僆儕傾偺尵岅昞尰乮乹愒乺佀乻愒乼乯偲丄懠偺儁儖僜僫傊偺偦偺揱払乮乻愒乼佀乹愒乺乯偲偄偆丄娧擵尰徾妛偺擇偮偺崻杮栤戣傪摨帪偵夝偔僾儘僙僗偺堎柤偱偁傝丄偐偮丄弮悎帊偲偟偰偺榓壧偵塺傑傟傞撪梕偲偼丄幚偼丄摉偺弮悎帊偲偟偰偺榓壧偺儊僇僯僗儉偦偺傕偺偱偁傞丄偲偄偭偨帠懺偑側傝偨偭偰偄傞偺偱偼側偄偐偲峫偊偰偄傞丅偦偟偰丄屆崱丄怴屆崱偺堄枴榑揑尋媶偺儊僇僯僗儉偙偦偑丄幚偼丄摉偺榓壧偺堄枴傪嶻弌偟偰偄傞偲偄偭偨帠懺偑側傝偨偭偰偄傞偺偱偼側偄偐丄傛傝抂揑偵尵偊偽丄堜摏堄枴榑偙偦偑榓壧偺儊僇僯僗儉側偺偱偼側偄偐丄偲峫偊偼偠傔偰偄傞偺偩偑丄偙傟偼愭憱偭偨媍榑偩丅乯
丂
仭乽尒備乿偺悽奅丄嫟姶妎揑尵岅
丂
丂屆崱丄怴屆崱偺巚憐揑峔憿偺堄枴榑揑尋媶偺榖戣傊偺暁慄丄偦偺擇丅
丂
丂扟愳寬堦偲偺懳択亀桍揷殸抝偲愜岥怣晇亁偱丄抮揷淺嶰榊偑丄乽杔偼斵乵堜摏弐旻乶偵嫟摨偱乽枩梩廤側傜枩梩廤偺壧偵怓傪揾偭偰傒側偄偐乿偲尵傢傟偰偄傞傫偱偡丅偨偲偊偽乽偁偐偹偝偡乿側傫偰偲偙傠偵偼埄怓傪揾偭偰乿塢乆丄偲岅偭偰偄傑偡丅庒徏巵偼丄慜宖彂偱偙偺偙偲偵傆傟丄乽榓壧偵怓傪揾傞栚揑偼丄屆戙恖偺怓嵤姶妎傗慛傗偐側暥壔晽搚傪抦傞偨傔乿偱偼側偔丄堜摏弐旻偼丄榓壧偵乽怓傪揾晍偡傞偙偲偱丄怓側傜偸傕偺傪丄敀愳惷偺偄偆乽偙偲偽偺堄枴偡傞幚懱偦偺傕偺乿傪晜偐傃忋偑傜偣偨偐偭偨偺偱偼側偐偭偨偐乿偲彂偄偰偄傑偡丅
丂偦偟偰丄儔儞儃乕乮乽俙偼崟丄俤偼敀乿乯傗儅儔儖儊乮乽惵偄屒撈乿乽惵偄崄傝乿乯丄攎徳傗儕僗僩偺嫟姶妎乮揑昞尰乯偵尵媦偟丄乽嫟姶妎揑尵岅偑偁傞偺偼丄斾歡昞尰偺敪払偵桼棃偡傞偺偱偼側偔丄帠徾偺幚嵼偑丄偦傕偦傕嫟姶妎揑側偺偱偼側偄偐乿偲丄斾歡昞尰偲嫟姶妎偲偺愭屻娭學傪傔偖傞僂僅乕僼偺愢傪徯夘偟偨偆偊偱丄師偺傛偆偵榑偠傑偡丅
丂偙偙偱庒徏巵偑偲傝偁偘傞偺偑丄乽偄偪憗偔擔杮屆揟暥妛偵偍偗傞嫟姶妎偵拲栚乿偟偨嵅抾徍峀偺丄乽亀尒備亁偺悽奅乿偲偄偆榑峫偱偡丅埲壓偵丄嵅抾榑暥偺奣梫傪丄嫟姶妎傕偟偔偼嫟姶妎揑怱惈丒昞尰丒塀歡偵娭偡傞慜抜偺媍榑偲丄屻抜偺枩梩廤偵偍偗傞乽尒備乿偺梡朄傪傔偖傞媍榑偲偵暘偗偰婰偟傑偡丅
丂
丂慜抜丅乽壒傪尒傞乿乽擋偄傪尒傞乿懱尡傪嫟姶妎偲偄偆丅巕嫙傗枹奐恖偵偍偄偰偒傢傔偰偄偪偠傞偟偄偑丄晛捠恖偺姶妎偺側偐偵傕丄屆偄嫟姶妎揑怱惈偼崱側偍巆棷偟偰偄傞丅偦偺撪晹峔憿偼昁偢偟傕堦掕偟偰偄側偄傛偆偩偑丄梌偊傜傟偨堦師姶妎偲悘敽偡傞擇師姶妎偲偺慻崌偣偺偆偪丄擇師姶妎偵帇妎偺惗偢傞帠椺乮乽柧傞偄壒乿乽埫偄嬁偒乿乽墿怓偄惡乿乯偑懡偄偲偄偆偙偲偼寛偟偰嬼慠偱偼偁傝偊側偄丅恖娫偺姶妎婍姱偵偍偗傞帇妎偺桪埵惈偑偙偙偵嫮偔敪尰偟偰偄傞偲峫偊傜傟傞偐傜偱偁傞丅傢傟傢傟偺抦妎偵偼丄偄偮傕帇妎婡擻偑嫤摨偟偰偄傞丅乽傕偲帇妎傪昞傢偟偨乽偵傎傆乿偲偄偆尵梩偑丄乽媖偺偵傎傊傞崄偐傕乿偺傛偆側梡朄傪宱偰丄傗偑偰歬妎傪昞傢偡岅傊偲揮偠偰偄偭偨堄枴曄壔傕丄擇師姶妎偵帇妎偑惗偠偨椺偲偟偰愢柧偟偆傞丅乿
丂屻抜丅漭梩廤傪傂傕偲偄偰捈偪偵婥偯偔偙偲偼丄乽尒備乿偲偄偆尵梩偺巊梡偑偒傢偩偭偰懡偄偲偄偆帠幚偱偁傞丅偨偩乽尒備乿偺巊梡椺偑懡偄偲偄偆偽偐傝偱偼側偔丄偦偺梡朄偵偍偄偰偒傢傔偰摿挜揑側偐偨偪傪偲偭偰偄傞丅偦傟偼丄乽揤棧乵偁傑偞偐乶傞缈偺挿摴備楒傂棃傟偽柧愇偺栧傛傝戝榓搰尒備乿偺傛偆偵丄廔巭宍乽尒備乿偱暥傪寢傇梡朄偱偁傞丅
丂屆崱廤偵擖傞偲丄偙偺梡朄偼偼傗偔傕巔傪徚偡丅怴愮嵹廤偵乽偨偯搉傞尒備乿偲偄偆漭梩帉傪梡偄偨椺偑偁傞偑丄偦偙偱偼乽搉傞乿偼摦帉偺楢懱宍偲偟偰堄幆偝傟偰偄偨丅偙傟偵懳偟偰丄屆戙偺乽尒備乿偼忋偺暥傪姰慡偵廔寢偝偣偨屻偱廔巭宍偲偟偰偺乽搉傞乿傪彸偗偰偄傞偺偱偁傞丅奜宍偼摨偠乽偨偯搉傞尒備乿偱傕丄屆戙偲暯埨埲屻偲偱偼暥朄揑偵戝偒側憡堘偑偁偭偨丅乽傢傟傢傟偼丄廔巭宍乽尒備乿偱暥傪寢傇偲偄偆丄屆戙榓壧偵偍偗傞摿挜揑側梡朄傪庤偑偐傝偵丄乽尒備乿偲偄偆岅偺攚屻偵偁偭偨屆戙偺堄枴偺悽奅傪扵傞偙偲偑偱偒傞乿丅
丂乽尒備乿偼乽暦備乿乽巚傎備乿偲偲傕偵丄乽尒乿乽暦偒乿乽巚傆乿庡懱偺敾抐偵娭偡傞岅偱偁傞偑備偊偵丄偦偺堄枴偼摦嶌揑偱側偔忬懺揑偱偁傞丅乽尒備乿偼乽尒傞乿偺庴恎偱偁傝乽尒偊傞乿堄傪偁傜傢偡偑丄偦傟偑堄枴偡傞偺偼乽尒偊偰棃傞乿嶌梡偱偼側偔乽尒偊傞乿偲偄偆忬懺側偺偱偁傞丅
丂庒徏巵偼丄偄傑敳偒彂偒偟偨暥復偐傜丄偦偺僴僀儔僀僩偲傕偄偆傋偒売強乮屆戙岅乽尒備乿偺攚屻偵嫮椡偵摥偔丄懚嵼傪帇妎偵傛偭偰僀僨傾亖乽偐偨偪乿偲偟偰攃懆偡傞屆戙揑巚峫偵尵媦偟偨偲偙傠乯傪堷梡偟丄乽乽尒備乿偲偼丄擏娽傪捠偠偨婡擻揑塩傒偱偁傞偩偗偱側偔丄姶妎摑崌揑側塩堊偩偭偨偙偲偵嵅抾偼拲堄傪懀偡丅乿偲弎傋丄榖戣傪堜摏弐旻偵揮偠傑偡丅偄傢偔丄乽嵅抾偑枩梩偵偍偗傞乽尒備乿偺悽奅傪榑偠偨傛偆偵丄堜摏偼怴屆崱偵偍偗傞乽挱傔乿傪捠楬偵尰徾奅偺斵曽傪榑偠偨偙偲偑偁傞丅乿
丂壚嫬偵擖偭偰偒傑偟偨丅
丂
仭尰徾奅偺斵曽丄巒尨揑嫬堟偐傜悂偔懚嵼偺晽
丂
丂巌攏椛懢榊偲偺懳択偱堜摏弐旻偑丄乽巹偼丄尦棃偼怴屆崱偑岲偒偱丄屆崱丄怴屆崱偺巚憐揑峔憿偺堄枴榑揑尋媶傪愱栧偵傗傠偆偲巚偭偨偙偲偝偊偁傞偔傜偄偱偡乿偲岅偭偨偙偲傪傔偖偭偰丄庒徏巵偼師偺傛偆偵彂偄偰偄傑偟偨丅慜復偱堷梡偟偨暥復偱偡偑丄廳偹偰堷偒傑偡丅
丂堜摏弐旻偵傛傞榓壧偺堄枴榑揑尋媶偺堦抂偲偼丄庒徏巵偑乽怴屆崱偵偍偗傞乽挱傔乿傪捠楬偵尰徾奅偺斵曽傪榑偠偨偙偲偑偁傞乿偲徯夘偟偰偄偨榑弎偺偙偲偱偡丅偙偺偙偲偑弎傋傜傟偨亀堄幆偲杮幙亁偺堦愡傪偲傝偁偘傞慜偵丄偙偙偱傆傟偰偍偒偨偄偙偲偼丄枩梩廤壧偺乽尒備乿偐傜屆崱壧丄怴屆崱壧偵偍偗傞乽挱傔乿傊偲偄偆丄榓壧偵梡偄傜傟偨岅渂偺曄慗偺偆偪偵埫帵偝傟傞丄乽悽奅擣幆偺搚戜傪梙傞偑偡傛偆側曄杄乿丄偁傞偄偼丄乽乽懚嵼乿傊偺愙嬤偲懳洺乿偵偍偗傞乽戝偒側妚柦乿偲偼丄偄偭偨偄偳偺傛偆側傕偺偱偁偭偨偐偲偄偆偙偲偱偡丅
丂庒徏巵偺媍榑傪傆傑偊偰丄偲偄偆傛傝丄敀愳惷偲嵅抾徍峀偺巇帠傪傔偖偭偰庒徏巵偑偔傝偩偟偨奣擮傗岅渂傪慺嵽偵偟偮偮丄乮偮偄偱偵尵偊偽丄乽擇廫悽婭傕偭偲傕旘桇偟偨乿擇偮偺妛栤偺榖戣偲偺娭楢傪傕擮摢偵偍偒側偑傜乯丄乽尒備乿偐傜乽挱傔乿傊偺揮姺丄偲傝傢偗乽尒備乿偺悐戅丄徚幐偺偆偪偵埫帵偝傟偨擣幆榑揑曄杄傗懚嵼榑揑妚柦偺摿幙傪丄恾幃揑偵惍棟偡傞側傜偽丄師偺傛偆偵側傞偱偟傚偆偐丅
丂傂偲偮偼丄愨懳揑幚嵼傕偟偔偼挻墇幰偲偟偰偺悽奅偲偺楈揑側乮偁傞偄偼丄乽惗偒惗偒偲乿偟偨乯岎傢傝偺婓敄壔偱偁傝丄偄傑傂偲偮偼丄熡撟枹宍偺忬懺偵偁傞僀僨傾揑幚嵼傪乽偐偨偪乿傗乽偡偑偨乿偵偍偄偰乽偁傝偁傝偲乿昤幨揑偵攃懆偡傞怱惈偺屻戅偱偁傞丅偙傟偲偍側偠偙偲傪丄僐僩僶偲偺娭學惈偵偍偄偰偄偄偐偊傞偲丄傂偲偮偼丄恄偲偟偰偺僐僩僶偲偺岎傢傝偺宱尡偺婓敄壔偱偁傝丄偄傑傂偲偮偼丄姶妎摑崌揑側僐僩僶偺摥偒丄偡側傢偪丄暋悢偺姶妎傪曪娷偟偮偮尰傟丄擣幆偝傟丄昞尰偝傟傞嫟姶妎尵岅乮偨偲偊偽丄屆戙偵偍偄偰偼乽傕偺傪挳偔偙偲偼栚偵尒偊側偄悽奅傪帇妎壔偡傞偙偲偱傕偁偭偨乿乮崅嫶尦梞亀擔杮恖偺姶忣亁乯偲巜揈偝傟傞丄偦偺傛偆側堄枴崌偄傪傕偭偨乽偙傦乿傗乽氵乿傗乽嬁偒乿乯偺屻戅偱偁傞丅
丂巹偼丄乮偐側傝嫮堷側偙偠偮偗偱偁傞偙偲偼廳乆帺妎偟偮偮傕乯丄偙偺椉幰偺娭學傪丄惣墷僗僐儔揘妛偵偍偗傞懚嵼榑偺婎慴奣擮偱偁傞乽杮幙乿乮杮幙懚嵼丄僄僢僙儞僥傿傾乯偲乽懚嵼乿乮帠幚懚嵼丄僄僋僔僗僥儞僥傿傾乯偺娭學偲偺傾僫儘僕乕偱峫偊傞偙偲偑偱偒傞偺偱偼側偄偐偲巚偆偺偱偡丅
丂埲壓丄師復傊丅
丂
仭曗堚丄榓壧偺堄枴榑揑尋媶丒彉愢
丂
仢榓壧偺巚憐揑峔憿偺堄枴榑揑尋媶丄傕偟偔偼榓壧偺堄枴榑揑夝庍妛偲偼側偵偐丅
丂妋擣偟偰偍偐偹偽側傜側偄偺偼丄偙偙偱偄偆榓壧偲偼乽偆偨傢傟偨壧乿偺偙偲偱偼側偔偰乽彂偐傟偨壧乿丄僷儘乕儖偲偟偰偺榓壧偱偼側偔僄僋儕僠儏乕儖偲偟偰偺榓壧乮榒帊乯偱偁偭偨偲偄偆偙偲丅僄僋儕僠儏乕儖偲偟偰偺榓壧丄彂偐傟偨榓壧偼乮暥帤偵怗敪偝傟偨堄枴忋偺塁偡側傢偪乽帤塁乿偑傕偨傜偡乯妡帉傗墢岅偦偺懠偺儗僩儕僢僋偺嬱巊偵傛傞懡憌亖懡憡惈丄廳憌亖廳憈惈傪摿挜偲偟丄傂偲偮偺帉偑懡廳側堄枴傪扴偄堎側傞暥柆傗暋悢偺忬嫷傪乽偄傑丒偙偙乿偵廂澥偝偣傞椡傪傕偭偰偄傞丅偙傟傪撉傒庤偺懁偐傜偄偊偽丄榓壧偼偄偐傛偆偵偱傕夝庍偟怺撉傒傪偡傞偙偲偑偱偒傞尵岅昞尰暔偱偁傞丅憂憿揑夝庍丄岆撉傪嫋偡偲尵偭偰傕偄偄丅
丂榓壧偺堄枴榑揑尋媶偼乮堜摏弐旻偑亀僐乕儔儞傪撉傓亁偱帋傒偨傛偆偵乯憂憿揑夝庍偲偼暿偺曽岦偱榓壧傪撉傓偙偲偐傜偼偠傑傞丅屆揟僥僉僗僩傪憂憿揑夝庍丒岆撉偲偼暿偺曽岦偱乽撉傓乿偲偼丄嬶懱揑側敪榖峴堊偺乽擹枾側忬嫷惈乿偵偍偄偰尵梩傪棟夝偟丄偝傜偵恑傫偱偦偺掙偵偼偨傜偄偰偄傞乽壓堄幆揑堄枴楛娭乿偵傑偱孈傝壓偘偰偄偭偰丄偦偺敪榖峴堊傪壓偐傜巟偊偰偄傞乽崻尮揑悽奅椆夝丄懚嵼姶妎丄婥暘揑悽奅憸乿傪扵媶偡傞偙偲丅乮偙傟偲摨條偺庯巪偺偙偲偑亀搶梞揘妛妎彂 堄幆偺宍帶忋妛劅劅亀戝忔婲怣榑亁偺揘妛亁偱偼乽屆偄僥僋僗僩傪怴偟偔撉傓乿偲昞尰偝傟偰偄傞丅乯
丂榓壧偺堄枴榑揑尋媶偺曽朄偼師偺嶰偮偺僾儘僙僗偵暘偗偰峫偊傞偙偲偑偱偒傞丅
丂
倎丏僄僋儕僠儏乕儖偲偟偰偺榓壧偺帉傪僷儘乕儖偲偟偰偺尵梩乮氵丄僇儈偺僊僼僩乯偑敪榖偝傟傞擹枾側忬嫷惈偵堷偒傕偳偡丅
倐丏偦偺掙偵摥偄偰偄傞壓堄幆揑堄枴楢娭乮偳傠偳傠偟偨棳摦懱丄敿堄枴丄堄枴偺壜擻懱丄尵岅傾儔儎幆乯偵傑偱孈傝壓偘傞丅
們丏偦偙偐傜榓壧偵摿桳側懚嵼姶妎乮擔杮揑楈惈偲偟偰偺僐僩僶偺偼偨傜偒丄傕偺偺偁偼傟傪抦傞偙偲乯傪晜偐傃忋偑傜偣傞丅
丂
丂庒徏巵偺媍榑傪墖梡偡傟偽丄帺慠揑懺搙傕偟偔偼捠忢偺尵岅妛偑乽帠徾仺尵梩乮倎'乯仺堄枴乮倐'乯仺拪徾揑側奣擮懱宯乮們'乯乿傊偲揥奐偡傞偺偵懳偟偰丄榓壧偺堄枴榑揑尋媶偼乽懚嵼亖僐僩僶乮們乯仺堄枴乮倐乯仺尵梩乮倎乯仺帠徾乿傊偲乮偁偨偐傕揹棳偲揹巕偺棳傟偑媡揮偡傞傛偆偵乯慿尮揑偵恑傓丅
丂
仢榓壧偺儊僇僯僗儉偲偼惣榚弴嶰榊偑乽挻尰幚庡媊帊榑乿偱榑偠偨弮悎寍弍偺儊僇僯僗儉丄偮傑傝乽宱尡堄幆偺悽奅懄偪儌傾乮moi乯偺悽奅乿傪徚柵偝偣丄塅拡偲偺崌懱偵傛偭偰柍尷偺宍懺傪偲傞偵偄偨偭偨帺変偡側傢偪乽弮悎堄幆乿傪婲偙偝偣傞儊僇僯僗儉偺偙偲丅乮弮悎堄幆偲偼丄偨偲偊偽尰徾妛揑娨尦偵傛偭偰傒偄偩偝傟傞挻墇榑揑庡娤惈丅偁傞偄偼尵岅偑柌尒偝偣傞堄幆丅塺傑傟偨榓壧偺悽奅偺側偐偵搊応偡傞儁儖僜僫亖塺傒偮偮偁傞怱丅乯
丂偙偺儊僇僯僗儉偼丄嘆憡堎側傞宱尡堄幆乮恄傗旤偺僾儔僗偺悽奅偲埆傗僌儘僥僗僋偺儅僀僫僗偺悽奅乯偺楢寢丄嘇惗偒傫偲偡傞椡亖旤傪媮傔傞椡丄偲偄偆擇偮偺梫慺偐傜峔惉偝傟丄偦傟帺恎偑幚偼弮悎寍弍偺昞尰懳徾偱傕偁傞丅
丂榓壧偺堄枴榑揑尋媶偺僾儘僙僗傪偙偺惣榚弴嶰榊偺乽寍弍亖婡夿愢乿偵偦偔偟偰峫偊偰傒傞丅偡傞偲丄堦偮偺夝庍偲偟偰師偺傛偆偵尵偆偙偲偑偱偒傞丅榓壧偺堄枴榑揑尋媶偺僾儘僙僗偲偼幚偼弮悎帊偲偟偰偺榓壧偺儊僇僯僗儉偦偺傕偺偱偁傝丄偟偨偑偭偰榓壧偵塺傑傟偨撪梕傕傑偨偙偺儊僇僯僗儉亖僾儘僙僗乮宍幃乯偦傟帺懱偱偁傞丅
丂徻愢偡傞偲丄榓壧偺堄枴榑揑尋媶偑乽帉仺倎仺倐仺們乿偲偄偆乮偳偙偐偟傜尰徾妛揑娨尦偺庤懕偒傪巚傢偣傞乯僾儘僙僗傪宱偰乽僐僩僶乮們乯仺堄枴乮倐乯仺尵梩乮倎乯仺帠徾乿偲掕幃壔偝傟傞悽奅偺幚憡傪柧傜偐偵偡傞偺偲摨偠傛偆偵丄榓壧偺儊僇僯僗儉偼乽憡堎側傞宱尡堄幆偺楢寢乮偵傛傞宱尡堄幆偺悽奅偺徚柵仺弮悎堄幆偺婲摦乯仺惗偒傫偲偡傞椡偺嬱摦乮偵傛傞弮悎堄幆偺柍尷壔仺塅拡偲偺崌懱乯乿偲偄偆乮摨條偵尰徾妛揑側娨尦偲峔惉偺庤懕偒傪巚傢偣傞乯僾儘僙僗傪宱偰乽弮悎堄幆偺婲摦仺偦偺柍尷壔仺塅拡偲偺崌懱乿偲掕幃壔偝傟傞弮悎帊偺撪梕乮弮悎堄幆偺悽奅乯傪傕偨傜偡丅
丂
仢榓壧傪乽撉傓乿偙偲丄榓壧傪堄枴榑揑偵尋媶乮夝庍乯偡傞偙偲丄偟偨偑偭偰奜懁偐傜榓壧偵偐偐傢偭偰偄偔僾儘僙僗偑丄幚偼夝庍偺懳徾偱偁傞摉偺榓壧偺撪梕丄幚幙偦偺傕偺偱偁傝丄偟偨偑偭偰撪懁偐傜榓壧偵偐偐傢偭偰偄偔偙偲偲摍偟偄丅榓壧傪乽撉傓乿乮堄枴榑揑偵夝庍偡傞乯偙偲偼榓壧傪乽塺傓乿乮僇儈偺僐僩僶傪乽東栿乿偡傞乯偙偲偱偁傞偲偄偆帠懺偑側傝偨偭偰偄傞丅
丂乽撉傓乿偼乽塺傓乿偱偁傞丅偮傑傝壧偺堄枴傪夝庍偡傞偙偲偑偦偺堄枴傪僐僩僶偵傛偭偰昞尰偡傞偙偲偲偮側偑偭偰偄傞丅偲偄偆偙偲偼丄壧傪乽撉傓乿偲偼壧偺堄枴傪夝庍偡傞偙偲傪捠偠偰偦偺壧偵塺傑傟偨乮偲夝庍偝傟傞偲偙傠偺乯堄枴傪帺傜偺傕偺偲偟偰弶傔偰宱尡偡傞偙偲偵傎偐側傜側偄丅偦傟偑乽東栿乿偱偁傞丅
丂偲偙傠偑堦斒偵壧傪乽塺傓乿偲偼丄壧偺塺弌偵愭棫偮宱尡傪尵梩偵傛偭偰昞尰偟揱払偡傞塩傒偩偲夝偝傟偰偄傞丅僆儕僕僫儖側宱尡偱側偔偰傕丄偁傜偐偠傔岞揑偵擣抦偝傟偨宱尡乮偦偺傛偆側忬嫷偺傕偲偱恖偼偦偺傛偆側巚傂傗姶忣傪偄偩偔偱偁傠偆丄偄偩偔傋偟偲悽偺懡偔偺恖偵傛偭偰丄偲傝傢偗壧恖偨偪偺嫟摨懱偵偍偄偰揱摑揑偵擣傔傜傟偨宱尡乯偲偄偆傕偺偺儕僗僩偑偁偭偰丄偦偺偄偢傟偐傪堷梡偟偰昞尰偡傞偙偲傕壧傪塺傓偙偲偺斖醗偵擖傟偰偝偟偮偐偊側偄偲峫偊傜傟偰偄傞丅
丂偦偆偩偲偡傞偲丄壧傪乽撉傓乿偙偲偼壧偵塺傑傟偨堄枴榑揑堄枴傪乽弶傔偰乿宱尡偡傞偙偲偩偲愭偵彂偄偨偺偼丄偄偭偨偄偳偺傛偆側帠懺傪尵偄昞偦偆偲偟偰偄傞偙偲偵側傞偺偐丅偦傟偼丄塺傑傟偨壧乮偲偄偆僼傿僋僔儑僫儖側峔偊偺傕偲偱彂偐傟偨壧丄偄傢偽暔偲偟偰偺壧乯偺偆偪偵償傽乕僠儏傾儖側偐偨偪偱搊榐偝傟偰偄傞堄枴亖宱尡亖巚傂偑丄壧傪撉傓偙偲傪捠偠偰傾僋僠儏傾儖側傕偺偲偟偰晜忋偟偰偒偨偲偄偆偙偲側偺偐丅乽僐僩僶乿偑尵梩偵側傞傛偆偵丅偦偟偰丄壜擻揑側昐僞乕儗儖乮嬧壿乯偑尰幚偺昐僞乕儗儖乮嬧壿乯偵揮壔偡傞傛偆偵丠
丂偁傞偄偼丄側偵偛偲偱偁傟捈偵宱尡偡傞偲偄偆偙偲偼丄偦偺偲偒偦偺恖偵摓棃偟偨堦夞偐偓傝丄慜戙枹暦丄嬻慜愨屻偺弌棃帠側偺偱偁偭偰丄偩偐傜丄壧傪乽撉傓乿偙偲偵傛偭偰壧偵塺傑傟偨堄枴榑揑堄枴傪宱尡偡傞偲偼丄偦偺偲偒偦偺撉傒庤偵摓棃偟偨乮偄傗丄偦偺偲偒偺偦偺撉傒庤偵偐偓傜偢丄偍傛偦偙偺悽奅偵懚嵼偟丄懚嵼偟偨丄懚嵼偡傞偱偁傠偆偡傋偰偺宱尡庡懱偺偡傋偰偺帪娫傪捠偠偰乯乽弶傔偰乿偺宱尡偵傎偐側傜側偄偺偩丅傕偟偐傝偵壧偺乽塺傒庤乿偑壧偺塺弌偵愭偩偭偰宱尡偟偨僆儕僕僫儖側堄枴亖巚傂偑偁偭偨偺偩偲偟偰傕丄偦傟偼偦偺壧偺乽撉傒庤乿偑弶傔偰宱尡偡傞堄枴榑揑堄枴偲摨偠傕偺偱偼側偄丅偦傫側尵偄曽偑偱偒傞偩傠偆偐丅
丂榓壧偺堄枴偼榓壧偺僐僩僶偺偆偪偵偟偐側偄丅榓壧偵奜晹偼懚嵼偟側偄丅榓壧偑壧偭偰偄傞偺偼丄榓壧傪夝庍偟棟夝偟娪徿偡傞塩傒傪捠偠偰偁偒傜偐偵側傞偲偙傠偺乽榓壧偑壧偭偰偄傞偙偲乿偦偺傕偺側偺偩丅榓壧偵偨偄偡傞堄枴榑揑尋媶傪偍偙側偆幰偑榓壧偺偆偪偵傒偄偩偡傕偺偲偼丄幚偼榓壧傪堄枴榑揑偵夝庍偟棟夝偟偰偄傞偍偺傟偺偦偺怱揑嶌嬈偦偺傕偺偱偁傞偲偄偆偙偲偩丅
丂惛妋偵偼丄乽傗傑偲偆偨乿乮僷儘乕儖偲偟偰偺乽榓壧乿偱偼側偔丄僄僋儕僠儏乕儖偲偟偰偺乽榒帊乿乯偑岅偭偰偄傞偺偼乽巚傂乿偑惡偲側偭偰壧傢傟傞丄偁傞偄偼乽傕偺乿偵傆傟偰乽偁偼傟乿偲摦偔怱乮姶忣乯偑尵梩偱傕偭偰乽昞尰偝傟傞乿偲偄偆帠懺偦偺傕偺側偺偩丅乻榓壧乼偺堄枴榑偼昁偢乹榓壧乺偺懱尡偵傛偭偰愭棫偨傟側偗傟偽側傜側偄丅
丂
仛僾儘僼傿乕儖仛
拞尨婭惗乮側偐偼傜丒偺傝偍乯1950擭戙惗傑傟丅暫屔導嵼廧丅愮擭傕愄偵彂偐傟偨榓壧偺堄枴偑棟夝偱偒傞偺偼偡偛偄偙偲偩丅偱傕丄杮摉偵乽棟夝乿偱偒偰偄傞偺偐丅偦偙偵乽堄枴乿側偳偁傞偺偐丅偦傕偦傕尵梩傪巊偭偰壗偐傪揱払偡傞偙偲偦偺傕偺偑晄巚媍側尰徾偩偲巚偆丅
Web昡榑帍乽僐乕儔乿20崋乮2013.08.15乯
亙欶偲僋僆儕傾亜戞24復丗懚嵼偺晽偵悂偐傟偰劅劅恖榓壧偺儊僇僯僗儉嘨乮拞尨婭惗乯
Copyright(c) SOUGETUSYOBOU丂2013 All Rights Reserved.
|
| 昞巻乮栚師乯傊 |